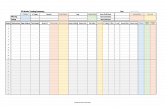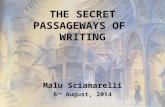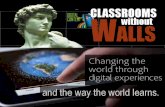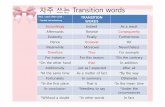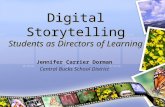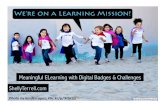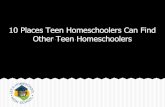Jep20171009sympmatsushima
-
Upload
hideaki-matsushima -
Category
Education
-
view
63 -
download
0
Transcript of Jep20171009sympmatsushima

UniversityofShigaprefecture.SchoolofHumanCulture
⼦どもの失敗についていく教育の相互的達成
松嶋 秀明(滋賀県⽴⼤学)
⽇本教育⼼理学会第59回⼤会⾃主シンポ『なせ⼦ともか⽴ち直ろうとするときに「問題」は顕在化するのたろうか ―「導かれた参加(guided participation)」の視点から「問題」を「発達の契機」へ―場所:名古屋国際会議場 2号館2階 会議室223⽇時:2017年10⽉ 9⽇ 13:00~15:00

分析の3次元モデル (Rogoff, 1995)
Personal Interpersonal Institution/community
図の出展:Rogoff,B. (2003). The Cultural Nature of Human Development. Oxford University Press
Participatoryappropliation(参加しつつの占有)
Guidedparticipation(導かれた参加)
Apprenticeship(徒弟制)

荒れた中学校のフィールドワークから
• ある「荒れ」た中学校への3年間の実践関与的観察。
– 都市部にある中学校。全校⽣徒、約700⼈で、この地域の⼤規模校にあたる。 ⽣活環境が厳しいなかで育つ⼦どもが多い地区を学区にもつ。
– 1年時、対教師暴⼒や授業妨害、授業エスケープなどがあり、騒然とした雰囲気。1年の後半から2年にかけて次第に落ち着いてきた。
• 当初から上記⾏動をおこしていたDの1年の経過を中⼼にとりあげる。
3

廊下4
Dらがたまっていたところ

「問題」か?発達の契機か?
• 場⾯1(1学期)–休み時間に起きたケンカをとめにはいっ
た担任に対し、そのケンカをとめさせまいとしてつかみあいになり、担任を殴った。→警察での継続補導
• 場⾯2(2学期後半)–授業中、Dはさんざん授業妨害をしたあ
げく、教師と⼝論になって激昂し、教室から出ていく。

1学期当初• 授業が成り⽴ちにくい状況。教師の促しにもか
かわらず、Dらは授業にでようとせずに騒いでいる。→ 「(私達を)教師と思ってない」
• でも実は、積極的に問題をおこさない⽣徒たちも騒いでいた(Dらだけが⽬⽴っていたわけではない)。
• ケンカをとめようとした担任は、⽌めさせまいとするDに殴られる。→被害届がだされ、Dは継続補導になる。

2学期後半の授業(4時間⽬の数学の時間。Dは散々授業妨害をしたあげく)
おもむろに「先⽣、俺2?」と問いかける。X先⽣は「それは最後にならないと…。今はわからない」と、答えない。Dは答えをひきだそうと⾷い下がるが、X先⽣は無視をつらぬく。・・・・ついにDは「俺が授業に出たってるんやゾ」「(授業に)出んでも良いのか?せっかくでてやってるのに」と毒づきはじめる。・・・X先⽣は「出るのは当たり前や。当然やろ」といい「クラスの迷惑になることはやめて!」と強い⼝調でいう。「ちゃんと授業に⼊ってるじゃん」と主張するDに、X先⽣はいい加減うんざりした様⼦で「今⽇はひどかった。みんなの邪魔をしてるっ」と叱る。「だったら出てる⽅がいいのか?」とくいさがるDにX先⽣は「邪魔するくらいだったら(授業から)出てるのと⼀緒だ」という。Dはこれを聞くなり「⼀緒やったら意味ない!」と憮然とした様⼦で教室からとび出ていく。
7

2学期後半に起きていたこと教師はDらを教室にいれることに挫折して1. 「⼀般⽣徒を育てる」ことにした。– その結果、便乗して騒いでいた⽣徒は少なくなった(Dが問題として⽬⽴つようになってきた)。
2. 場当たり的に廊下でDらの話をききはじめた。– その結果、Dらは彼らの⾟い境遇について語りはじ
めた– 教師らの「指導観」が更新され、⽣徒イメージも変
化した(ex.「Dは⽢えたい」)。 ▶(語り)

話をきくことで⾒えてくる(授業エスケープを許すことに)これを許していいのかなっていうのはやっぱりありますね。授業に⼊るべきと思ってるのに、授業に⼊らない、
( )でもやっぱりなんか、寄り添って話を聞くことで、そ
の⼦がやっぱり⾒えてきたところはあるので。この⼦は頭ごなしに⾔ったら、絶対もう⼊らないからとか。なんかDなんかはそのタイプですよね。もうなんか、⽗親的存在でガツンと、当然のことなんやけれどもガツンと⾔われると、あの⼦は絶対素直に聞き⼊れられないんですよ。その⾔葉だけで「なんやねんっ」てなってしまうんで(Dの2年次の担任)

「問題」か?発達の契機か?• いずれも表⾯的には問題だが・・・・・・
• 場⾯1– そもそも教師が「⾃分のしたいことを邪魔する⼈」
としかみられていない– 「逸脱」に親和的な雰囲気
• 場⾯2– ある意味で「⽣徒」になろうとしているともいえる。– 「逸脱」に違和的な雰囲気
=発達の契機?

1年の最後でのDの変化• Dに⽣徒としてのアイデンティティができる。
→廊下を歩きつつ、問わず語りに「俺も2年⽣になるんだなー」ともらす。
• (警察の継続補導を契機として)Dと教師との親密な関係ができる。→ 担任の⾞に何回のったかを覚えている。▶(語り)
帰りがけに「ありがとう」という。▶(語り)

うれしそうに...(⾞にのせると)「もう、これで◯◯の⾞に乗るのも4回⽬や」とかいうて⾔うとるんですよ、うれしそうに。…いろいろなところに謝りにいってるんでね。こっちとしては、乗せたくないんですけどね。全然、うれしいことではないんですけど。Dとしては、なんかうれしそうに「もう、何回⽬や。あそこにも謝りに⾏ったな」とかって⾔うとるんで。...それを世話になったと感じてるんじゃないかなと。そうであってほしいなと(Dの1年次の担任)
(警察署に送っていった際)学校送ってって、降ろしたら、「先⽣、今⽇はありがとう」って⾔ったんですわ。..(略)..おまえ、偉いな。そんなこと⾔えたら、こんなことせんでよかったのに、おまえ」って。ニタッて笑うてましたけどね。Dは、あんまり褒められるとかね、ほんまにそういう経験は少ないんでしょうね(⽣徒指導の教師)。

Dと学校の変化
1学期 2学期末 3学期から2年生
個⼈ 授業エスケープ教師への暴⼒
授業に⼊ることをめぐる衝突
⽣徒アイデンティティ感謝の⾔葉
相互作⽤(⼤⼈)
好き勝⼿するvs 枠にとどめる
なりゆきで対話Vs ⾃⼰開⽰
対話(=教師・⽣徒像の明確化)
(仲間) 混 乱 落ち着くvs⼊ろうとする
落ち着き、まとまる vs 孤⽴する
学校 通常の学校の「枠」
新たな「枠」の模索
拡張された学校の「枠」

⼦どもの失敗についていく関係の共同構築• 教師の指導によって⼀般⽣徒は落ち着いたが、そのことは
Dらの逸脱を際⽴たせた。
• 廊下での会話の増加は、Dらの変化(⽣徒アイデンティティ、感謝の⾔葉がいえる)につながった(=参加しての占有)。これは教師⾃⾝のDイメージ、指導観(=導かれた参加) の変化と、それを承認する学校のあり⽅(=徒弟制)の変化ともつながっている。
• 「被害届」は、⼀般的な「懲罰・排除」の道具から、「警察への送迎」「話をきいてやる」とあわせることで、思いがけず、「関わりの履歴」を共有する道具となった。