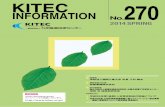米国反トラスト法における反競争的行為の正当化 …...( )97 米国反トラスト法における 反競争的行為の正当化 柳 武 史※ Ⅰ 序 Ⅱ 連邦裁判所の判例
アルカリシリカ反応を生じた構造物の 診断に対する技術者の...
Transcript of アルカリシリカ反応を生じた構造物の 診断に対する技術者の...

Vol. 50, No. 7, 2012. 7 593
1. は じ め に
我が国におけるアルカリシリカ反応(ASR)によるコンクリートの劣化現象は 1970~1980 年代に多く報告されたが,1986 年の旧建設省総合技術開発プロジェクト
(総プロ)による抑制対策以降,沈静化したものと考えられてきた。しかしながら,抑制対策を施したコンクリートを用いた構造物においても ASR により劣化した事例が国内外において専門家などにより近年報告され始めており,より適切な試験法および ASR 抑制対策の構築が望まれている。 合理的かつ効果的な試験法および抑制対策の確立のためには,現場における劣化事例の解析が必須である。しかしながら,構造物の劣化事例が報告されても,「抑制対策を行った構造物でなぜ ASR が発生したのか」という原因解明まで行われた事例は限定的である。現行の抑制対策下での ASR 劣化の原因が分からないので,新しい有効な対策を考えるのも容易ではない。このような状況の中,一部では独自に新しい抑制対策を講じている事業体もある。今後,より有効な抑制対策を構築するためには,現実の劣化状況と原因調査までを含めた包括的な診断(ASR 診断)を行うことが不可欠である。 このような背景の下,2011 年度より JCI-TC 115 FS
「ASR 診断の現状とあるべき姿研究委員会」が活動を開始した。本研究委員会では,ASR 診断に係る専門家により診断の現状とあるべき姿について議論し,岩石学的手法を含めた ASR 診断の実効的なフローを提示するこ
とを目的としている。初年度である 2011 年度は実務における ASR 診断の現状と ASR に携わる技術者の抑制対策および診断に関する認識について調査するため,アンケートを実施した。本稿では,現行の ASR 抑制対策の限界について,対策以降の劣化事例を含めて概説するとともに,ASR 診断の意義について述べる。また,実務における ASR 診断の現状と技術者の認識についてアンケート調査を行った結果について紹介する。なお,アンケートの内容や結果の詳細については本研究委員会のホームページ1)でもダウンロード可能である。こちらもご参照いただきたい。
2. ASR 抑制対策の技術的限界
1986 年の抑制対策以降,ASR による構造物の被害が少なくなったことは間違いない。一方,現行の抑制対策には限界があり,抑制対策の想定を超えた劣化事例が報告されている。ここでは,現行の抑制対策で十分に考慮されていない ASR に関連する現象と実構造物における劣化事例,また現行の抑制対策の問題点について述べる。2.1 ペシマム現象
ペシマム現象とは,反応性骨材単体で使用するよりも混合率が数~数十%で最も大きな膨張を示す現象である。オパールやクリストバライト,トリディマイトといった高反応性のシリカ鉱物を含む反応性骨材においてこのような現象が認められている。表-1に反応性鉱物の種類とペシマム混合率の関係を示す2)。ペシマムについては Katayama の論文2)に詳しいので参照されたい。 ペシマムは 1940 年代から知られている現象3)である。なぜ 70 年も前から知られている現象が現在でも発生しているのか4)~6)。これには,現行の試験方法および抑制対策のうち 2 つの限界が関係している。1 つ目は,現行
テクニカルレポート
アルカリシリカ反応を生じた構造物の 診断に対する技術者の意識調査
─ASR 診断の現状とあるべき姿研究委員会の活動─川端雄一郎*1・山田一夫*2・古賀裕久*3・久保善司*4
概 要 本稿は,ASR 診断の現状とあるべき姿研究委員会の活動内容を報告するものである。2011 年度には,ASR 抑制対策や診断の現状に対する技術者の認識や ASR 診断に関するアンケート調査を行った。調査結果から,構造物の重要度に応じて抑制対策を構築する必要性を訴える意見が半数以上を占めた。調査結果から,抑制対策は ASR 発生のリスクと抑制対策にかかるコストとのバランスを考慮して決定すべきであることを指摘した。 キーワード: アルカリシリカ反応(ASR),診断,意識調査,抑制対策
*1 かわばた・ゆういちろう/(独)港湾空港技術研究所 構造研究チーム(正会員)
*2 やまだ・かずお/㈱太平洋コンサルタント 営業推進部(正会員)*3 こが・ひろひさ/(独)土木研究所 基礎材料チーム(正会員)*4 くぼ・よしもり/金沢大学 理工学域環境デザイン学類(正会員)

コンクリート工学594
の JIS 規格の試験ではペシマムを生じる高反応性骨材のアルカリ反応性を検出するのが難しいことである。現行の JIS 規格には化学法とモルタルバー法があり,両試験法における判定結果が異なった場合,モルタルバー法の結果を優先することとなっている。化学法で骨材のアルカリ反応性を検出したとしても,対象の骨材を全量使用することを前提としたモルタルバー法ではペシマムを生じる骨材のアルカリ反応性を検出することが難しく,総合的な結果として「無害」と判定されてしまう場合がある。2 つ目は,高反応性骨材はアルカリ総量 3.0 kg/m3
以下でも ASR を生じることである。近年のセメントのアルカリ量は抑制対策制定当時に低アルカリ型セメントと認識されていたようなレベルにまで低減されており7),セメント量が約 400~500 kg とならない限りアルカリ総量が 3.0 kg/m3 を超えることはほとんどない。したがって現行の抑制対策から考えると,ASR は抑制されていると考えることができる。しかしながら,顕著なペシマム現象を生じる高反応性骨材が一定量含まれると,アルカリ総量が 3.0 kg/m3 以下でも反応する。また,近年ではコンクリートの収縮量を低減させるために石灰石粗骨材が使用される場合が多い。一般に石灰石骨材はアルカリの固定量が少ないため,空隙水に多くのアルカリが残存する。したがって,高反応性骨材が細骨材として含まれた場合,ASR を生じやすい条件となる。このような情勢も関連して,現在でもペシマムによる ASR が発生している。
では,どのような抑制対策が必要か。これは十分には分かっていない。試験室レベルでは,アルカリ総量 3.0 kg/m3 でも ASR が発生し,また小型の試験体を用いた実験ではアルカリ溶脱などの影響により実構造物の劣化と対応しないことが指摘されている8)。問題は,ペシマムによる劣化事例が現実にどの程度あり,また実構造物レベルにおいてどの程度のアルカリ総量であればペシマムによる ASR を抑制できるのかが不明な点である。実構造物の事例では,アルカリ総量 2.2 kg/m3,2.6 kg/m3
程度でもペシマムにより ASR を生じた事例が報告されている5),6)。また,近年の研究では高反応性骨材がペシマム混合率で含まれた場合,フライアッシュなどの混和材の抑制効果が極端に低下することも指摘されている9)。2.2 遅延膨張性骨材
安山岩のような急速膨張性骨材と異なり,典型的には数十年経過した後に問題となるような膨張が検出されるような骨材は遅延膨張性骨材と称される。遅延膨張性骨材は反応性鉱物として主に隠微晶質石英や微晶質石英を含んでおり,一般的な JIS の化学法やモルタルバー法では検出できない。また,近年ではこれまで区別されてきたアルカリシリケート反応,アルカリ炭酸塩反応も隠微晶質石英の ASR であると国際的に認識されている10),11)。海外では,温度 80℃の 1 mol/l NaOH 溶液に浸せきする試験方法が提案され,本試験法により検出できることが示されている12)。これは後のASTM C 1260の原型となった試験法であり,今や国際標準となっている。 遅延膨張性骨材については,国内においてまだ認知度が低い。したがって,現行の抑制対策が有効かどうかは明確になっていない。セメントの最小アルカリ量が 0.82~0.84%のコンクリートにおいて遅延膨張性 ASR が生じたという報告13)や,水溶性アルカリから算出したアルカリ総量 2.2 kg/m3 程度でも ASR が生じたとの報告14)
がある。また,亜熱帯性の気候の地域では 2.5 kg/m3 以下であっても ASR を生じるとの指摘もある15)。北米の暴露試験の結果では,1.9 kg/m3 でも遅延膨張性骨材のASR が確認されている16)。
An Attitude Survey of Concrete Engineers on Diagnosis of ASR-affected Concrete Structures ─First-year Activity of JCI-TC 115 FS “Technical Committee on Diagnosis
of ASR-affected Structures”─By Y. Kawabata, K. Yamada, H. Koga and Y. Kubo
Concrete Journal, Vol.50, No.7, pp.593~600, Jul. 2012
Synopsis This paper reports the first-year activity of JCI-TC 115 FS “Research Committee on Diagnosis of ASR-affected Structures”. An attitude survey was carried out in order to investigate the recognition of concrete engineers in regard to current preventive measures and diagnosis of ASR-affected structures. From the results, more than half of respondents recognized that it is required to establish the preventive measures appropriate for priority of the structure. The results also indicated that the preventive measures should be established by considering the balances between risk and cost. Keywords: alkali-silica reaction, diagnosis, attitude survey, preventive measures
表-1 反応性鉱物とペシマム量の関係2)
ペシマム量 化学法試験 主に含有される岩石
オパール 5 %以下 潜在的有害 珪質けつ岩,チャート,珪化岩(第三紀以降)
クリストバライト 10% 潜在的有害 安山岩,デイサイト,流紋岩(第三紀以降)
トリディマイト 10% 潜在的有害 安山岩,デイサイト,流紋岩(第三紀以降)
カルセドニー 20% 潜在的有害 チャート,凝灰岩,珪化岩隠微晶質石英 50%以上 有害 チャート,凝灰岩,珪化岩

Vol. 50, No. 7, 2012. 7 595
遅延膨張性骨材に関する問題は,国内での検証例が少ないために,遅延膨張性骨材に対する試験法や抑制対策についても十分には分かっていない。抑制対策の以前,以降にかかわらず ASR 劣化事例が遅延膨張性骨材を原因とするものであれば,現行の JIS の化学法とモルタルバー法では検出されない可能性が高く,岩石学的評価を含む ASR 診断を行わない限り,実態は明らかにならないと考えられる。2.3 セメント以外からのアルカリ供給
旧来 ASR はセメントから供給されるアルカリと骨材の反応とされてきたが,1990 年代から外部から供給される凍結防止剤や海水によって ASR が促進されることが指摘されてきた。また,近年では骨材からアルカリが供給されるという指摘もある。このようなセメント以外からのアルカリ供給が ASR の長期的な膨張挙動に影響を及ぼすと考えられている。ただし,そのセメント以外から供給されたアルカリの ASR に及ぼす影響度についてはまだ明らかになっておらず,国際的にも議論されている。委員会内においても,寒冷地の凍結防止剤によるASR 促進の可能性について話題となった。このような現象の存在から,初期のコンクリート配合でアルカリ総量3.0 kg/m3 以下を満足していたとしても,将来的には ASRが促進される可能性があると考えられている。国際的には飛行場で航空機に用いられるギ酸アルカリなどの凍結防止剤が著しい ASR 膨張の原因と考えられている17)。 セメント以外からアルカリが供給されることは事実である。しかしながら,このアルカリ供給が,セメント由来のものと比べてどの程度 ASR に影響を及ぼすのかは不明である。現行の抑制対策では,外部からアルカリが供給される場合には塩害防止も兼ねて塗装などの措置を行うことが望ましい,としている。したがって外部からのアルカリ供給については塗装を行えば ASR は促進されないかもしれない。一方,骨材からのアルカリ供給はコンクリート内部で生じるものであり,塗装などの対策では十分ではない可能性がある。実構造物の調査結果によると,骨材や凍結防止剤から 0.3~4.2 kg/m3 程度のアルカリ供給があると考えられている18),19)が,今後の検証が不可欠である。
3. 抑制対策と ASR 診断に関する議論
上述したとおり,現行の ASR 抑制対策は有効であるが,同時に限界もある。それでは,今後新しく試験法や抑制対策を導入すべきであろうか。新たな試験法を導入したり抑制対策を厳しくしたりすれば,ASR による被害は減ずるであろうが,当然コストアップは避けられない。一方,何も修正しないのであれば,ASR のリスクは避けられない。工学的判断のためには,どこで許容すべきなのか議論の余地が残る。また,新しく試験法や抑制対策を導入するのであれば,どのように修正すべきで
あろうか。 これらの議論を定量的に行うためには現状の劣化事例を的確に把握することが重要であり,そのためには岩石学的評価を含めた包括的な ASR 診断が必要である。しかしながら,その方法論の確立も容易ではなく,技術者が簡易に行うための基盤が整っていない。また,ASRに関連する診断技術は専門性が高く,また高額な費用と長い試験期間が求められる。このため様々な調査を行ったものの,得られた結果を十分に活用できず,誤った診断技術が適用されて診断結果そのものが間違えた場合もある。一方,研究レベルでは片山例えば,10)を筆頭として先進的な事例解析が行われている。調査に要するコストも考えながら,実務でどのような診断が最も合理的なのか,議論が必要である。 本研究委員会では,合理的な抑制対策を提示するためには,ASR 診断の理想像を追及するとともに,実務における合理的な診断フローを示すことが必要と考える。そのためには理想と現実のギャップを埋めるため,実務における ASR 診断の実態を把握する必要があると考え,次章に示すアンケートを実施した。
4. アンケートによる ASR 診断の現状と技術者の認識の調査
本研究委員会では,現状に対する技術者の認識を把握すべく,現行の試験法や抑制対策,また診断に用いる診断技術の有効性に対する技術者の認識についてアンケートにより調査を行った。あわせて,これまでの ASR 診断に関する経験や診断技術の実施経験についても調査することで,実務における ASR 診断の現状を明らかにすることとした。 アンケートでは,特に以下の 3 点に着目した設問を作成した。 (1)新設構造物の抑制対策に関する認識 (2)ASR に関連する診断技術に関する認識 (3)ASR により劣化した構造物の診断に関する経験 アンケートについては合計 361 件の回答を得た。表-2に回答者の職種内訳を示す。回答者は,構造物の管理者である官公庁職員,また実際の ASR 診断業務を請け負うコンサルタント会社員による回答が 6 割超であった。また,回答者 361 名のうち約半数がコンクリート診断士または技術士を有しており,83 名が技術士およびコンクリート診断士の両資格を有していた。 アンケート回答者の ASR に関する経験程度を図-1に示す。アンケート回答者の約 7 割は ASR 劣化が疑われた構造物に関わる業務に携わった経験を持っていた。また,ASR 診断に携わった業務回数について,約 2 割程度の回答者が 6 回以上経験していた。 アンケート結果を解釈する上で注意すべき点として,多くの経験を持つ技術者は,事例ごとに異なる結果を得

コンクリート工学596
ている可能性があるが,回答にあたっては典型的な一つの事例を念頭に回答することを依頼しているので,単一の技術者の回答であってもどのような場合にもあてはまる回答とはなっていないことがある。4.1 新設構造物の抑制対策に関する認識
アンケートでは,まず現行の ASR 抑制対策の有効性に対する認識について調査した。図-2に現行の ASR 抑制対策の有効性についての回答をまとめた。その結果,
「概ね有効である」との回答が最も多く,「有効である」と併せると全体の 64%を占めた。一方,「あまり有効でない」および「有効でない」との回答で,骨材の試験方法とアルカリ総量規制の有効性を疑問視する声が 12%あった。現行の抑制対策の有効性について「あまり有効でない」または「有効でない」とした回答者(n=43)に,ASR 抑制対策のうちどの部分を修正・変更すべきか問うた結果を図-3に示す(複数選択可)。修正・変更すべき点として骨材の試験方法が最も多く,回答者の半数以上から選択されていた。この理由としてコメント欄では,骨材試験で無害と判定された骨材が用いられているにもかかわらず ASR が生じた事例があること,現行の試験方法では遅延膨張性の骨材を適切に評価できないことなどが指摘されていた。次に多かったのは,アルカリ総量規制であり,その理由として,コメント欄でアルカリ総量規制を守っていても ASR を生じる場合があることが指摘されていた。また,地域による骨材の違いや,海からの飛来塩分の影響などを考慮してアルカリ総量の規制値を変更することが提案されていた。混和材の使用に関しては,他の対策と異なり,現行の規制内容そのものの課題は提起されておらず,適用を促進するための環境整備が求められていた。また,無害でない骨材を完全に排除することは困難であることから,結合材の選択や配合設計によって ASR を抑制すべきとの意見もあった。 抑制対策を行っていても ASR の発生リスクがあることについて,現行の抑制対策で良いか,もしくはより初期コストをかけても ASR の発生リスクを下げるべきか問うた。その結果を図-4に示す。「重要な構造物については,建設時により多くの初期費用がかかっても,より精緻な抑制対策を課すのがよい」が最も多く選択されていた。この中で,ASR 抑制対策として一律に厳しい基準を課すことは不経済となる可能性もあるため現状の劣化状況を把握したうえで,費用対効果の観点から検討をすべきとの意見が多かった。次に多かったのは「例外的なケースはやむを得ない。維持管理で対応」との選択が
表-2 各業種におけるアンケート回答者数
無回答 大学職員企業 1 企業 2
官公庁無回答 材料 設計 施工管理 研究関係 コンサルタント 無回答 道路 鉄道 電力
2 7 8 11 16 40 3 124 3 20 6 14 107
0 50 100 150 200
経験なし
経験あり(不明)
経験あり(1 ~ 5 )
経験あり(6 ~10)
経験あり(>11)
回答者数(人)
図-1 回答者のASR診断の経験数
有効, 37
概ね有効,193
あまり有効でない,
41
有効でない,2
わからない,88
図-2 現行抑制対策の有効性に関する認識
骨材の試験方法,
25
混和材の品質,置換率など,
12
わからない,1 その他,6
アルカリ総量の規制値,
14
図-3 現行抑制対策の変更・修正が望まれる箇所
例外的なケースはやむを得ない。維持管理で対応,
93
重要構造物にはより精緻な対策,
201
ほとんどの構造物により精緻な対策,
30
わからない,18 その他,16
図-4 ASRの発生リスクに対する考え方

Vol. 50, No. 7, 2012. 7 597
多かった。この理由として,精緻な対策を行ってもASR を完全に防ぐことは困難なので,これが現実的であるとするものが多かった。一方,「ほとんどの構造物について,建設時により多くの初期費用がかかっても,より精緻な抑制対策を課すのがよい」を選択した理由としては,その方がライフサイクルコストを低減できることのほかに,ひび割れの発生は社会に許容されないとの指摘もあった。なお,業種によって回答者を分類して比較してみたものの,受注者側と発注者側に顕著な違いは認められなかった。4.2 ASR に関連する診断技術に関する認識および実施経験
ここでは,まず技術者が ASR 診断の第一歩と考えられる外観観察に対してどのような認識をしているのか調査した。図-5に外観観察によるコンクリート構造物における ASR 劣化の判定に関する認識に関する回答集計結果を示す。図より,経験の少ない回答者では,外観観察による判定に対して「多くは困難」という回答が半数を占めている。一方,経験数が多い回答者の場合,外観観察による ASR 判定について「比較的容易」という回答が 70%程度であった。 次に,ASR に関連する各診断技術に対する有用性の認識度合いと実施経験について問うた。診断技術としては,図-6の判例に示すものを挙げた。ここで,比較のために各診断技術に対する有用性の認識や実施経験の回答を簡易に数値化した1)。具体的には,各診断技術に対する認識として,「有用」を 1 点,「場合によって有用」を 0 点,「有用でない」を-1 点とし,実施経験の回答についても同様に,「実施」を 1 点,「場合によって実施」を 0 点,「実施しない」を-1 点とした。したがって,+1 に近いほど有用な,もしくは実施される診断技術であることを表し,-1 に近いほど有用でない,もしくは実施されない診断技術であることを表す。 図-6 に異なる経験数の回答者の各診断技術への有用性の認識(役に立つと思うかどうか)と実施経験(実施
したことがあるかどうか)の関係を示す。全体傾向として,実施経験に関しては,診断技術によって差があり経験数によらず-0.8~0.8 程度の範囲にあった。一方,有用性に対する認識は経験数が少ない技術者の間では診断技術による違いが明確でなく,経験数が多いほど各診断技術に対する認識の差異が生じる傾向を示した。 それぞれの診断技術の分類として,大きく 4 つのグ
0 20 40 60 80 100
経験なし
経験あり(1 ~ 5 )
経験あり(6 ~10)
経験あり(>11)
割合 (%)
容易 概ね容易 多くは困難
非常に困難 無回答
図-5 外観観察によるASR劣化の判定の容易さに関する認識
-0.5
0.5
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
-1.0 -0.5 0.0 0.5 1.0
実施
しな
い←
→実
施
有用でない← →有用
周辺構造物調査モルタルバー法デンマーク法SEM による ASR ゲル確認構造物表面のゲル分析XRDコア観察アルカリ量測定
化学法JCI-DD 2カナダ法ASR ゲルの組成分析酢酸ウラニル静弾性係数コンクリート薄片
[経験数<6]
[経験数≧11]
実施
しな
い←
→実
施
有用でない← →有用
[6≦経験数<11]
‐実施
しな
い←
→実
施
有用でない← →有用
-1.0
‐
0.0
1.0
-0.5
0.5
-1.0
0.0
1.0
-0.5
0.5
-1.0
0.0
1.0
図-6 調査項目の有用性の認識と実施経験の関係

コンクリート工学598
ループに区分できる。1 つ目は,経験数にかかわらず,有用と認識され,かつ実施されている診断技術であり,これらは「周辺構造物調査」,「JCI-DD 2」,「静弾性係数」,「コア観察」の 4 項目であった。特に「コア観察」については,経験数が多いほど有用性を認識している。これは,経験数が多い技術者であるほどコア側面の観察から有益な情報を多く得ることができるためと考えられる。 2 つ目は,経験数によらず比較的有用とは認識されているものの,実施経験の値としては 0 に近く,場合により実施を行っていると考えられる診断技術であり,これらは「デンマーク法」,「カナダ法」,「SEM による ASR ゲル観察」,「ASR ゲルの組成分析」,「XRD」,「コンクリート薄片」,「アルカリ量測定」の 7 項目であった。このうち,「デンマーク法」,「ASR ゲルの組成分析」,「XRD」はいずれの経験数においても縦軸がマイナスとなっており,場合によって実施する割合が少ないものと判断される。 3 つ目は,経験数によらず有用性の値が 0 に近く,かつ実施されていない診断技術であり,これらは「構造物表面のゲル分析」と「酢酸ウラニル蛍光法」であった。これらの診断技術は技術的また制度的に様々な課題があるため,実施が難しいのが原因の一つとして挙げられる。 4 つ目は,経験数によって有用性に対する認識,また実施経験が変化する診断技術であり,これらは「化学法」と「モルタルバー法」であった。特に,経験数が 11 以上と多い回答では「化学法」と「モルタルバー法」について有用ではなく,また実施しないという結果となっている。化学法およびモルタルバー法はあくまでも骨材のアルカリシリカ反応性を判定するものであり,それ自体にも課題があるうえ,構造物の調査とするにはより多くの問題がある。経験数が少ない技術者は化学法,モルタルバー法の適用範囲を十分に認知しないまま,誤ってJIS 規格である化学法やモルタルバー法の判定基準を採用している恐れもある。したがって,今後はこれらの試験の技術的課題に対する認識を普及させる必要がある。 また,診断技術について記載された自由意見には,簡単に診断ができる技術の開発を要望する意見が多く寄せられた。また,基準などがないために診断技術の選定や結果の解釈などに苦慮しているとの意見も多く見られた。そのため,多くの診断事例の公開を要望する意見もあった。一方,微小領域の観察などを行うことでマクロな構造物全体の性能をどのように評価するのか,またどこまで診断に費用をかけるのか,といった点に問題を感じている技術者も多かった。4.3 ASR により劣化した構造物の診断に関する経験
最後に,実務における ASR 診断の現状を把握すべく,ASR により劣化した構造物の診断に携わったことのある回答者に対して,最初に ASR が疑われたきっかけについてアンケートを行った。回答結果を図-7に示す。日常点検と回答があったのは 10%程度であり,定期点
検が 30%程度,詳細点検が 15%程度であった。詳細点検の段階とした回答の多くはコンサルタントもしくは設計コンサルタントであった。これは,構造物に変状が生じて詳細点検を行う際に ASR が疑われたものと推察される。コンサルティング業務および技術相談とした回答の多くはコンサルタント業務に携わる技術者であった。 ASR と疑われた構造物に対して,最終的な劣化原因の判定の結果について問うた結果,ほぼ全てのケースでASR もしくは他の劣化との複合劣化と判断されていた。すなわち日常点検や定期点検で ASR を疑われた構造物のほとんどが最終的にも ASR が関与した劣化であると判定されている。ただし,本アンケートが ASR 診断に関わるものであり,典型的な ASR 劣化の事例について問うたものであるので,当然の結果といえるかもしれない。これらのことから,日常点検や定期点検といった外観観察によって ASR による変状をほぼ適切にスクリーニングできていると考えられる。 図-8に ASR と判定した根拠を示す。なお,ASR の診断においては各種調査結果から総合的に判断される場合が多いことを想定し,判定時の根拠については複数回答可能とした。ASR と判定した根拠としては「外観の特徴」だけでなく,「コアの膨張量測定結果」,「コア試料にASR ゲルを確認」といった調査を行っていた。この結果から,ASR が疑われた構造物の原因の判定について,外観の特徴に加えて,採取コア試験の結果などを用いることで判定しているケースが多かった。
0 20 40 60 80 100
その他
不明
技術相談
コンサルティング業務
第三者からの情報提供
詳細点検
定期点検
日常点検
回答者数(人)
図-7 ASRの発生の可能性を認識した段階
0 50 100 150 200 250
信頼できる専門家の意見に拠った
コンクリート薄片から推定
消去法同じコンクリートを用いた
構造物で ASRアルカリ量が3.0 kg/m3以上
骨材を改めて試験すると反応性あり
コア試料にASRゲルを確認
コアの膨張量測定結果
外観の特徴
回答者数(人)
図-8 ASRと判定した根拠

Vol. 50, No. 7, 2012. 7 599
外観の特徴を判定の根拠としながらも,他の調査データを併用する場合が多いことから,構造物の ASR の判定において,外観の特徴のみでは判定の理由として十分ではないというのが現状の認識であると考えられる。他方,外観の特徴を用いないケースは少ないことから,外観的な特徴を ASR の兆候あるいは可能性を判断する材料としており,それを確証するために詳細な調査などが行われているのが診断の実情であると考えられる。4.4 アンケート結果に対する考察
今回のアンケート結果から,現場技術者の多くがASR 劣化を生じた構造物の診断に苦慮していることが改めて分かった。このため,多くの回答から安価で簡易な診断技術を求める意見が多く寄せられた。現時点において,それぞれの診断技術はメリットとデメリットがあり,精度も異なる。これらが明確でないため,高額な費用で多くの調査を行ったとしても,場合によっては診断を行うにあたって有用とならない場合もあると想定できる。したがって,まずは状況に応じた診断技術の選定方法やその精度を明確にする必要がある。また,コストと目的に応じた診断技術の組合せ方法など,事例紹介も含めた実務的な診断フローの作成が必要と考える。一方,高額な費用を要しても詳細な ASR 診断が必要になるケースも存在すると想定される。このようなケースに対応する技術者への情報提供のためには,最先端の技術でどの程度の診断が可能か明示することが必要である。 また,現行の ASR 抑制対策は一般には有効であると同時に限界もある,という認識は徐々に実務技術者にも浸透してきた。ASR 抑制対策に対して,アンケート回答者の半数が「重要構造物には精緻な抑制対策が必要」と考えている。また,「例外的なケースはやむを得ないので,維持管理で対応」という意見も多かった。すなわち,一般構造物では ASR の発生を許容するという考えを多くの技術者がもっている。ただし,構造物においてどの程度の ASR の発生までを許容できるのかが不明であり,ASR 発生の許容値について議論する必要があると思われる。一方,重要構造物にはどの程度精緻な抑制対策が必要なのか。現時点では,新設時の抑制対策に要するコストと ASR の発生リスクの関係が明確になっておらず,技術者や専門家の中でもコンセンサスは得られていない。この点に関して,今後本研究委員会から情報発信を行い,活発に議論を行いたいと考えている。
5. まとめと今後の活動
JCI-TC 115 FS は,初年度として,現行の抑制対策で十分に考慮されていない ASR に関連する現象と実構造物における劣化事例,また現行の抑制対策の問題点についてまとめたうえで,ASR 診断の現状や技術者の認識に関するアンケート調査を行った。
1) ペシマム現象,遅延膨張性骨材,セメント以外か
らのアルカリ供給は,現行の抑制対策で十分には考慮されていない。
2) アンケート調査の結果,現行の抑制対策は概ね有効とする意見が半数であったが,骨材の試験方法とアルカリ総量規制の有効性を疑問視する声が 1 割強認められた。構造物の重要度に応じた抑制対策を講じることが必要と考える意見が半数以上を占めた。
3) ASR 診断は外観観察により可能性を検知し,より詳細な分析結果と総合してなされることが多い。
4) 新しい手法を導入することで ASR 抑制はできると考えられるが,抑制対策は ASR 発生のリスクと抑制対策にかかるコストとのバランスを考慮して決定すべきであり,この点について今後議論が必要であることを指摘した。
これらの結果を踏まえて,2012 年度以降の 2 年間では,以下の項目について検討する予定である。( 1 ) コストとリスクに関するシンポジウムの開催
ASR に関してアンケート調査を行ったが,さらにシンポジウムを開催し,一般市民,官庁,学識経験者,構造物管理者,施工者,材料業者などで,意見を交わしたい。( 2 ) 最新技術の収集および既存技術の再整理
2012 年 5 月に開催される ICAAR(アルカリ骨材反応の国際会議)のレビューなどを含め,最新の ASR 診断に関わる技術情報を収集する。また,それぞれの既存技術の適用範囲と得られる結果,解釈方法を解説する。( 3 ) ASR 診断フローの作成
上記項目を基礎として,ASR 診断フローを作成する。理想的なフローを充実させるとともに,技術者の理解に役立つよう解説などを多く盛り込むこととしたい。また,実務者の目的に応じた,目的別の診断フローもあわせて作成する。活動期間内中に可能であれば,実際に ASRを生じた構造物について,本研究委員会で提案するフローを用いた ASR 診断の実施例を示す。( 4 ) ASR 抑制対策の検討
ASR により劣化した実構造物の診断事例の収集,海外における ASR 抑制対策のレビューを行うことで現行の ASR 抑制対策の適用範囲を整理する。また,現行の抑制対策の適用範囲外の事例に対してどのような診断がなされることが抑制対策へのフィードバックに有効か整理する。これらを総括して,現時点で考え得る構造物の重要度を加味した ASR 抑制対策について検討する。
謝 辞 本報告は JCI-TC 115 FS「ASR 診断の現状とあるべき姿研究委員会」に参加いただいた各委員の,活動および話題提供いただいた方々の協力によるものです。また,本研究委員会のアンケートには非常に多くの皆様にご協力いただきました。ここに記して謝意を表します。

コンクリート工学600
参 考 文 献 1) http://www.jci-net.or.jp/˜tc115a/ 2) T. Katayama:Petrography of alkali-aggregate reactions in
concrete─reactive minerals and reaction products─, Supplemen- tary papers of East Asia Alkali-Aggregate Reaction Seminar, pp.45-59, 1997
3) T. E. Stanton:Expansion of concrete through reaction between cement and aggregate, Proceedings of ASCE, Vol.66, pp.1781-1811, 1940
4) 山田一夫・川端雄一郎・河野克哉・林 建佑・広野真一:岩石学的考察を含んだ ASR 診断の現実と重要性,コンクリート構造物の補修,補強,アップグレード論文報告集,Vol.7,pp.21~28,2007
5) 林 建佑・山田一夫・河野克哉・大庭光商:プレストレストコンクリート橋で生じた ASR の劣化診断,土木学会第 64 回年次学術講演会,pp.195~196,2009
6) 尾花祥隆・鳥居和之:プレストレストコンクリート・プレキャストコンクリートにおける ASR 劣化の事例検証,コンクリート工学年次論文集,Vol.30,No.1,pp.1065~1070,2008
7) 日本コンクリート工学協会:セメント系材料・骨材研究委員会報告書,2005
8) 井上祐一郎・佐川康貴・川端雄一郎・山田一夫:コンクリートのASR 促進膨張試験結果にアルカリ溶脱が及ぼす影響,土木学会第65 回年次学術講演会,pp.545~546,2010
9) 井上祐一郎・濱田秀則・川端雄一郎・山田一夫:ペシマム現象を生じる骨材を用いたモルタルのフライアッシュによる ASR 抑制効果,コンクリート工学年次論文集,Vol.32,No.1,pp.953~958,2010
10) T. Katayama:The so-called alkali-carbonate reaction(ACR)- Its mineralogical and geochemical details, with special reference to ASR, Cement and Concrete Research, Vol.40, pp.643-675, 2010
11) T. Katayama and T. Futagawa:Alkali-aggregate reaction in New Brunswick, Eastern Canada - Petrographic diagnosis of the deterioration, Proceedings of 8th International Conference on
Alkali-Aggregate Reaction, pp.531-536, 1989 12) R. E. Oberholster and G. Davies:An Accelerated Method for
Testing the Potential Alkali Reactivity of Siliceous Aggregates, Cement and Concrete Research, Vol.16, pp.181-189, 1986
13) T. Katayama, Y. Sarai, Y. Higashi and A. Honma:Late-expansive alkali-silica reaction in the Ohnyu and Furikusa headwork structures, Central Japan, Proceeding of the 12th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, pp.1086-1094, 2004
14) 西 政好・池田隆徳・佐川康貴・林 建佑:遅延膨張性骨材による ASR 劣化事例および骨材の ASR 反応性検出法の検証,コンクリート工学年次論文集,Vol.32,No.1,pp.935~940,2010
15) T. Katayama, T. Oshiro, Y. Sarai, K. Zaha and T. Yamato:Late-expansive ASR due to imported sand and local aggregates in Okinawa Island, southwestern Japan, Proceedings of the 13th International Conference on Alkali-Aggregate Reaction in Concrete, Trondheim, Norway, pp.862-873, 2008
16) D. Hooton, C. Rogers and T. Ramlochan:The Kingston Outdoor Exposure Site for ASR- After 14 Years What Have We Learned?, Proceedings of Marc-André Bérube symposium on Alkali-Aggregate Reactivity in Concrete, pp.171-193, 2006
17) P. R. Rangaraju et al.:Potential for Development of Alkali-Silica Reaction(ASR)in the Presence of Airfield Deicing Chemicals, Proceedings of the 8th International Conference on Concrete Pavements, pp.1269-1289, 2005
18) T. Katayama, M. Tagami, Y. Sarai, S. Izumi and T. Hira:Alkali-aggregate reaction under the influence of deicing salts in the Hokuriku district, Japan, Materials Characterization, Vol.53, pp.105-122, 2004
19) 野村昌弘・渡辺暁央・鳥居和之:砂のアルカリ溶出性状と構造物における骨材からのアルカリ溶出の検証,コンクリート工学年次論文集,Vol.29,pp.153~158,2007