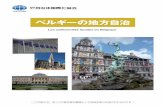ジョセブ・ナイの国際政治理論 -...
Transcript of ジョセブ・ナイの国際政治理論 -...

政治学研究論集
第21号 2005.2
ジョセブ・ナイの国際政治理論
一そのリアリズム性に関する一考察一
Joseph S. Nye, Jr.’s Theory of International Politics
An Examination of the Realistic Nature in His Theory
博士後期課程 政治学専攻 2004年度入学
水 沢 紀 元
MIZUSAWA, Norimoto
【論文要旨】
本論文は,ジョセブ・ナイが国防次官補就任時,いかなる思想で「ナイ・イニシアティブ」を推
進したのかを探るため,彼の理論がどのようなもので,いかなる所がリアリズム的で,どのような
リアリズムと見なすことができるか考察することを目的としたものである。
まず,今日言われているリアリズムの前提を6つ,類型を3つ提示し,ナ・イの理論がリアリズ
ムと呼ぶに値するのか,呼べるとすればどのようなリアリズムかを判断するための基準を設定し
た。本論は彼の理論を説明しながら,その都度基準に該当する箇所を指摘する形で展開される。彼
は国際政治には分析のための3つの基本要素があるとする。それに従い本論ではまず,国家,国
益,国力という視点から基本要素の説明をしている。次いで,その要素が作用する状況を相互依存
状況とナイがすることから,彼の相互依存論について,彼が指摘する状況と一般に彼とは相反する
思想的立場にいるとされるリアリストの指摘を対比しながら説明を試みている。そして,以上の整
理からリベラルのナイがリアリスト扱いをされたことについての理由,政策に反映された彼のリア
リズムの思想がどのように評価されうるかについて述べている。
【キーワード】 リベラリズム,6つのリアリズムの前提,人間性のリアリズム,防御的リアリズ
ム,攻撃的リアリズム
論文受付日 2004年10月1日 掲載決定日 2004年11月17日
一231一

1.はじめに
(1)問題の設定
本論文は,ジョセブ・ナイ(Joseph S. Nye, Jr.:現ハーバード大学ケネディー行政大学院教授)
が第1期クリントソ(William Jefferson Clinton)政権時,国防次官補として「ナイ・イニシアテ
ィブ」を推進した際,いかなる思想を抱いていたのか探ることを目的としている。
1990年代半ば,日米政府間で冷戦後に向けた安全保障の見直し作業が行われた。いわゆる「日
米安保再定義」である1。この「“再定義”への対話のプロセス」は,ナイの次官補転任を契機に活
発化した2。そのため「ナイ・イニシアティブ」と今日呼ばれている。
この再定義以前の日米関係は同盟が「漂流」したと形容される悪化した状態にあった。その状況
下で行われたこの対話プロセスは,同盟関係を「漂流」から再び強化・拡大へ方向づける役割を果
たしたとされている3。その役割を果たしたものの一つとして1995年2月28日に米国国防総省によ
り『東アジア戦略報告』(通称ナイ・レポート)4というものも出された。これは当時削減を続けて
いた米国の東アジアでの前方展開戦力を,10万人規模の兵力のまま維持することを明確にし,地
域安定への寄与を意図した内容が特徴とされる戦略レボートであった。これはその地域のほとんど
で広く歓迎された,と作成に関わったナイ自身も自画自賛している5。
こうした成果の一方,彼は時折,以下のような皮肉を言われたという。「脱国家的な相互依存の
概念に非常に近いと考えられる誰かがリアリストの思考にかなり依拠したレポート作成を手伝うな
んて驚きだ」6と。このように,通常,国際政治学の分野でナイはリアリズム(Realism)に属する
というよりも,脱国家的な現象や相互依存といった状況を重く見るリベラリズム(Liberalism)の
理論家と位置づけされる7。皮肉は彼の理論と実践には矛盾がある,あるいはナイ自身が従来の主
張の誤りを自身の行動で示したのだ,という意味の彼への非難とも解釈できよう。
この皮肉に,ナイは「私は自分のテキストUnderstanding lnternational Confiicts8でリアリズム
とリベラリズムはどちらも,環境に応じて政策決定者に教えるものを持つと述べている。1995年
の東アジアへ向けた米国の戦略は,リアリズムの健全な要素を必要としていた」と返答していると
いう9。まるで,自分は従来からリアリズムを否定しておらず,リアリストと呼ばれても構わない
かのような発言を彼はするのである。
これはどういうことか。「長い目で見れば,健全な安全保障政策は健全な理論研究に依存しなけ
ればならない」とナイはする10。加えて「理論は政策作成者が事実の理解と予測に役立ち,最もプ
ラグマティックな者でも,いくらかの理論概念を最後の拠り所にする」と言う11。理論家ナイが政
策作成者として政治過程に関われば,行動の拠り所にするのは自身の理論になることは想像に難く
ない。だが,欠陥のある理論では拠り所とはなるまい。自身の理論に欠陥があれば,批判者の皮肉
の如く,ナイはそれを捨て他人の理論を政策作成に援用することも余儀なくされよう。しかし,ナ
イは自著にも記した自身の理論体系と当時の自己の行動は一貫していたと主張する。しかも,それ
一232一

はリアリズムのアプローチでだと言う。ナイがイニシアティブに関わり活発化に寄与したのなら
ば,彼の理論とは一体どういうもので,「リアリズムの健全な要素」とは何なのか。これらの理解
が冷戦後の日本をとり巻く状況を知る上で,一つのヒントになるのではなかろうか。
② リアリズムとは
リアリズムとは,ロバート・ギルピソ(Robert G. Gilpin)の言葉を借りれば「本質的には哲学
的な立場」12であり,国際政治に対する思想の枠組みを指す。その枠組みの中で様々な思索をする
者がおり,リアリズムとは一枚岩なものでない13。それでも,一般に以下の6つの前提をリアリス
ト各々が共有し,学派が形成されると言う。①国家が中心である,②世界はアナーキーである,③
国家は安全,あるいは力の最大化を求める,④(力の分配など)国際システムが国際情勢における
国家行動のほとんどの原因となる,⑤力あるいは安全の追求の際,手段として国家は合理的な政策
を用いる,⑥軍事力を有用なものとする,である14。だが,全てのリアリストが確信の度合いをど
の前提にも等しく持つわけでなく15,枠組み内部で異なる主張が生じる。
それによりリアリズム内部の分類が様々なされているが,今日,3つに分けるのが主流になって
いる16。ジョン・ミアシャイマー(John J. Mearsheimer)は,(A)人間性のリアリズム(Human
Nature Realism),(B)防御的リアリズム(Defensive Realism),(C)攻撃的リアリズム(Offen-
sive Realism),との分類をする。(A)はハソス・モーゲンソー(Hans J. Morgenthau)を中心と
した古典的リアリズム(Classical Realism),(B)(C)は従来ネオ・リアリズム(Neorealism),
または構造的リアリズム(Structural Realism)と呼ばれていたが,近年,(B)はケネス・ウォル
ッ(Kenneth N. Waltz),(C)をミアシャイマーは自身を代表的論者と位置づけ分類をしている17。
そして,ミアシャイマーは(ア)なぜ国家は力を求めるか,(イ)どのくらいの力を国家は欲す
るのか,を基準としてリアリズムを3つに分ける。(A)における(ア)は国家に本来備わる権力
欲,(イ)をできうる全てを求め,覇権を究極の目標に相対的な力の最大化を図ろうとする。(B)
の(ア)はシステムの構造のため,(イ)は現状で所持する程度に過ぎず,国家は勢力均衡の維持
に集中する。(C)では(ア)をシステム構造,(イ)を(A)の場合同様,覇権を究極目標にでき
うる限り求め,相対的力の最大化を図ろうとする,という具合にである18。
今日,専ら(B)(C)のネオ・リアリストの間で論争が展開されている。(B)(C)の説明を補
足すると,ベソジャミン・フランケル(Benjamin Frankel)は,この論争をリアリズムの前提③
④の確信の程度の違いにより生じたものとする。(C)攻撃的リアリズムは国際システムは安全が
乏しく,そこは国家同士が互いの意図について確信を抱けない場所と見る。国家は不確かさから一
度の行動で安全を十分に成し得ると信じ緊張を緩めることはできず,相対的な力の最大化を常に求
めてゆくことになる。それゆえ,安全確保のための力獲得への激しく飽くなき競争がなされ,しば
しば戦争につながる攻撃的な戦略を国家は採用してしまう,とする。対する(B)防御的リアリズ
ムは(C)よりも戦争回避の可能性について楽観的で,安全は容易に得られるものとする。この立
一233一

場では国際システムは穏健で,注意深く,抑制された国家行動の動機のみを与える,となる19。こ
れはつまり,攻撃的行動は対抗と力の獲得の妨害,すなわちバラソシング行動を潜在的犠牲国にと
らせることになる。過度な力の獲得は他国を対抗同盟へと向かわせ自国に都合の良いことではな
い。ゆえに,国家は国際システムにおける地位の維持,すなわち自国の安全を目的に過度な力の獲
得に注意を払うことになる20,ということを述べている。(B)で国家が攻撃的で道理をわきまえな
い行動をとるのは,リーダーの誤算などを含む国内の病理のためとなる21。以上の議論をまとめる
と,下の表のようになる。
古典的リアリズム ネオ・リアリズム
(A)人間性のリアリズム (B)防御的リアリズム (C)攻撃的リアリズム
⑦力を求め@る理由
国家に本来備わる権力欲 システム構造 システム構造
(イ)力を欲す
@る程度できうる全て 究極目標は覇権 現状程度勢力均衡に集中 できうる全て 究極目標は覇権
補足O提③④ システム
@ と@国家行動
システムは国家に勢力均衡の心zをさせるが,構造的な拘束は二次的な国家行動の原因。生ま
黷ネがらの権力への意志が最高�≠゚させる*。
システムは穏健な動機を与え驕B敵による対抗を避けるた゚,過度な力の獲得に注意する。
システムは安全確保に激しい動@を与える。乏しい安全,相手フ意図が不明で,どこからが安Sなのか分からないため,過度ネほどの力の獲得を目指す。
*古典的リアリズムにとってのシステムからの拘束は二次的なものであり,本文中で補足としての論述をし
なかった。
古典的リアリズムの補足部分の内容に関してはMearheimer, The Tragedy OfGreatPowerPolitics, p,19,を参照。
本論文ではナイの理論の整理を通して,理論の「特徴」,「リアリズム性」と「いかなるリアリズ
ムか」見ることを目指す。そのため,彼の理論の特徴を論じながら,上記のリアリズム6つの前
提をナイの理論は踏まえているか,そして3つのリアリズムのどれと見ることができるかを述べ
る。まず,彼が国際政治分析の3つの基本要素(building blocks)と呼ぶものを整理する。彼は基
本要素を,主体,目標,力,とするが,これらを国家の属性として捉えている22。ゆえに,国家,
国益,国力,と本論では三要素を整理する。次に,その三要素の存在する状況として一般に彼をリ
ベラルと見る根拠にした相互依存の概念についてリアリストの主張と対比させながら整理する。
2.基本要素
(1)国 家
ナイは「領域国家は過去において,必ずしも継続して存在したわけではない。したがって,将来
それが存在する必要はない」23とする。およそ半世紀前にE.H.カー(E. H. Carr)が主権の概念
は将来において,より曖昧になる可能性がある24とした以上に,主権国家の衰退を確信する見方を
ナイはとる。
しかし,彼は今日,国家が主役の座から降りたと考えておらず,「領域国家及び領域国家の問題
は依然,世界政治の中心のままである」と言う。それは「人々は政治制度から,物理的安全,経済
一234一

福祉,共同体のアイデソティティの3つを欲する。確かに,国際的なプロセスの変化はゆっくり
とこれらの価値の位置づけを変えてきている。しかし,今までにネイショソ・ステイトは他のいか
なる政治制度よりも,3つ全てをより多く与えてきている」と彼が見るからである25。ナイは多く
の人々の手による国家を超える努力を認めてはいる26。だが,主権国家を主要な行為主体とする
「ウェストファリア体制を越えた秩序を実現するには,あと数十年,あるいは数百年の年月が必要
である」と言う27。
その一方で,スムーズに進んでいるわけでないが,国際政治は国家間関係のみならず各国民衆の
関係で規定されるリベラルな方向に徐々に向かいつつあることもナイは重視する28。国家を取り巻
く環境変化を以下のように彼は言う。従来,国家の対外関係での主要な関心事は物理的安全の確保
であった。全国民の生存は明らかに集団の利益ではある。だが今日,この伝統的安全保障の問題以
上に,社会・経済的問題への国家の関心が大きくなっている。社会・経済的問題の利益は広く共有
される性質でなく,国内受益者は全員ではない。ゆえに問題で各々利害を異にする集団・個人を生
む。これにより対外政策に向けた国内政治過程では異なる自己の利益擁護を主張する者が増え,利
益の複雑さをはらむ問題が重大さを増している。更に,国内の利害関係者には利益を共有する他国
の老と連絡を取り共に行動する者も現れ,国家間の枠を越える異なるタイプの世界政治を発達させ
ている29。ナイは以上のような現象を多国籍企業,政府間機関,非政府組織,エスニック・グルー
プ,ゲリラ,麻薬カルテル,マフィア,国際的宗教組織などの非国家的行為体が登場し生むものと
する30。
こうしたことで,国家を取り巻く状況の変容を軽視できないとし,「総じて国家は弱点の無いよ
うに見える。しかし,注意深く見ると,国家の各部分にはかなり脆弱なところもある。そうした部
分は脱国家的に作用し脆弱な状況を埋め合わせしている」31。加えて「性質的に脱国家主体は,何
世紀にも渡り役割を果たしてきているものである。だが,今日のその主体の量の変化は重大な変化
を示している」32と,国家が他の行為主体からの挑戦を受けているとナイはする。主要な行為主体
の国家を知るために,国家以外の行為主体を軽視せず見る必要があるというのが彼の国家観である
と言えよう。
彼は「常に国家は重要ではあるが」と前置きした上で「問題は国家と非国家グループのどちらが
重要かではない。新しく複雑な提携が,伝統的見方では暴き損ねてしまうやり方で,ある地域の政
治へ影響をいかに及ぼしているかが問題なのである。国家は現在の国際政治において主要な行為主
体ではあるが,国家だけが国際政治の舞台を独占はできない」と述べる33。対して,ロバート・ギ
ルピソは次のように述べる。「国家は国際システムの中で,今も昔もパワーを独占してきたとはリ
アリストは論じてきたわけでは決してなく,常に他の強力な行為主体と争ってきたことを認識して
いる。・その上で,国家は卓越し,最も重要な行為主体であると論じているのだ」34。このように,
現状で挑戦を受けながらも国家が主要な行為主体だとする点では両者の主張は共通していると言え
る。以上から,ナイの議論はリアリストの前提①国家が中心であること,を満たしているというこ
一235一

とになるだろう。
(2)国 益
国益とは国家の行動目標になるものであるとナイは捉え,通常,政府の形態がどうであれ「国家
は国益の範囲内で行動する」とする35。この見方は,ネオ・リアリストとされるクリストファー・
レイソ(Christpher Layne)36の「全ての国家が国益に基づいて行動するのは当然である」37との考
え方と大差はない。このように,国益に向けて行動するという点で国家は合理的政策を用いるとし
て,ナイはリアリストの前提⑤も踏まえていると言える。レインは国家のとるべき行動の「議論の
起点とすべきことは国益をどう定義するか」38という所に置くが,ナイも「国益を知るためにはそ
の定義の仕方を知る必要がある」39とし,国益を決める際の定義の仕方の重要性を説く。
その定義の仕方をネオ・リアリストが論じる場合,ケネス・ウォルツのように,適切な国家行動
は国家自身のいる状況に応じて計算されるものであり,効果的な選択には状況に応じた国家目標の
考察が必要である,とすることになる40。そして,ウォルッらは国家が置かれた国際政治の状況
は,高次の政府がない自助の状況という意味でアナーキーだとする41。ナイはこうしたリアリスト
のアナーキーに対する見方は,不安,武力,生き残りという要素をはらむ戦争状態という悲観的な
見方になるとする。その結果,国益の定義は少しも変えることができず,国家は国益を勢力均衡の
点から定義しなければ生き延びることができない,とリアリストは主張することになる。彼らの見
方は,国際システムにおける国家の立場が,どのように国益を定義するかを述べる。そして,リア
リストはアナーキーを常に戦争状態と捉え国益の定義を変えることはできないと考えるため,外交
政策を予測可能だと捉えているとナイはしている42。こうした悲観的な見方にナイ自身も,国際政
治がアナーキーである限り国家の究極の頼りとするのは自助であり,経済的目標が軍事的安全保障
の目標に完全に取って代わるわけではない,と同意する43。彼はリアリストの前提②世界はアナー
キーである,との前提で国益を考えると言えよう。
だが,ナイはアナーキーを常に戦争状態にあるとはしない。リベラルな見方で状況を捉え,国益
を定義する方が現実的となる場合もあるとする。彼はリベラルの見方のアナーキーを共有する主権
を欠くが人々は連携を発展させ契約を結ぶことができ,さほど脅威ではない状況,とする。そこか
ら導かれる国益は,国際システムでの国家の立場以外の多くの要素により定義づけられ,定義する
国家の国内社会のタイプに定義が依拠することになる。例えば,経済的福祉に価値を置き,貿易を
かなり重視する国内社会,または他の民主主義国と戦争することを不当とみなす社会である国家
は,国際システムで位置付けが同等な専制国と異なる国益の定義づけをするとナイは言う44。
こうしたようにリアリストの見方にとどまらず,リベラルな見方にまで視野をナイは広げ,その
上で2つの見方の間に実際の国益は存在し,状況によりこの範囲内で国益の定義は変わるとす
る。もしも国際的な状況が,隣人にすぐ殺されるかもしれない完全にアナーキーな状況であれば,
民主主義と通商を優先させようとする動機が対外政策に影響を与える機会は限られる。それゆえ,
-236一

生き残りが第1になるというのがリアリズムに近い国益の考え方。そして,それと対極のリベラ
ルの立場は,国内社会のような制度と平和への一貫した期待があり,システムを部分的にしかアナ
ーキーでない穏健な状態と見なし,相互不信から協調を阻害する囚人のディレソマを回避させ,国
内社会に関係するいくつかの他の要素がより大きな役割を果たし国益となるとする45。人権や民主
主義などの自らのアイデソティティに大切と思うものや通商などを安全保障と切り離し国益とする
ようになると言う。
以上のように,ナイの考える国益の概念はリアリストの見方も踏まえており,それを排除するも
のではない。しかし,彼がアナーキーと呼ぶ状況はリアリスト以上に質が変わるものと見る。それ
ゆえ,アナーキー下で国益の定義は変容し,国益と呼ぶ対象をリアリスト以上に幅広くナイは捉え
ている。上記のレインはリアリストであることから,湾岸戦争の際に米国がとった政策を勢力均衡
の視点から評価する。彼は「経済的生産活動における資源を投資することで他国を豊かにはする
が,米国は他国の国益を保護して死と衰退の危険を冒すことになる」46とし,他国との協調は自国
の疲弊につながるので利得を関係国との相対的なバランスで捉え行動すべきとした。対して,広い
定義をするナイは,湾岸戦争を反イラクの国際的連帯のとりまとめに成功し,協調行動を米国の国
益に適ったものと見た47。アナーキーの捉え方の違いが両者の国家行動に関する主張に差異をもた
らす結果にしている。
両者の主張の優劣はさておき,ナイの考える国益は「確かなことは,安全保障の問題は世界政治
のアナーキーな構造が消えない限り消えないだろう」48とリアリスト同様,前提④国際システムが
国家行動の原因となると安全保障に向けた行動を重視する。だが同時に,国際政治のアジェンダは
国家がより広大な領域の目標を追求するにつれ複雑化してきているとも言う49。国家が置かれる状
況が,リアリズムとリベラリズムのどちらの文脈に近いアナーキーになるかにより,国家の国益の
定義が変わってくるというのがナイの捉え方である50。国際システムが穏健な動機を与える可能性
も彼は示唆している。
(3)国 力
(a)基本的捉え方
ナイは力を「自らの目的,あるいは目標を達成するための能力」と定義する。これはロバート・
ダール(Robert A. Dahl)の定義「さもなくばしなかったことを他者に対してさせる能力」を踏ま
えたものである。こうした力は,相手の選好を知った上で行動の変化を見なければ判断できないも
のだとナイは指摘する51。彼は更に「態度・行動が醸し出す力」と「資源の保有に派生する力」と
いう2つに力の概念を類型化する。前者は「自分が望む結果を得る能力」,後者は「通常自ら望む
結果を得るという目的に沿った資源を所有していること」とする52。
この2種類の力のうち,政治指導者は「資源の保有に派生する力」の定義を用いる傾向にある
とナイは言う。理由は,力の判定で相手の選好を考慮する行動変化の分析は「過去の再構築に時間
一237一

をかける分析者と歴史家に有益であるが,実践的な政治家と指導者には時にとても変わりやすく儂
い」傾向となるからだと言う。つまり,「態度・行動」に比べ「資源の保有」の方が具体的,計測
可能,予測可能で,時間に制約のある指導者に便利な指標になるからである。加えて,他老を制御
する能力とは資源の所有としばしば関係あり,指導者は後者の定義を採用する。その資源をとりわ
け,人口,領土,天然資源,経済規模,軍事力,政治的安定,とナイは見なす53。
だが,行使される力は資源の保有に依拠したものだけでなく,「態度・行動が醸し出す力」も考
慮の必要があると彼は指摘する。それは,力は変換という作用により影響が相手に及ぶ,と見るか
らである54。実世界では,資源所有の少ない側が自身の「所有する資源」をパッタリも含む「態度
・行動が醸し出す力」で有効に「資源」を変換させ,相手の行動を制御し望む結果を得る事態も時
にある。資源からの派生のみでなく,派生を効率よく力に変換させて自らが望む結果は獲得できる
のである。「態度・行動が醸し出す力」が変換作用を増進させるので軽視できないと分析者のナイ
は重視する。
加えて,ナイは力を資源との関係で定義する際に,力の源泉の重要性は時代により変化するとい
うことに注意しなければならないとする55。それゆえ「どの資源が,いかなる特定の文脈の中で,
力への一番の基礎を提供できるかを判断すること」56が重要だとし,今日の文脈で重要な資源を見
る場合,力は以前に比べ代替が難しくなったと認識すべきとナイは言う57。特に「旧来の考えで
は,軍事力は力を誇示する上で最も有力な手段であった。しかし,武力は自分が全てという自助の
システムで力を具現する究極の形態として残るとしても,その行使は現代の大国に高くつくことに
なった」58と軍事力はなお大切だが,他の源泉の不足を補う代替性をなくしつつある,と彼は指摘
する。
こうした代替性の限界に関するナ・イの見解は,ウォルツの核兵器の見方と異なるものになる。ウ
ォルツは「核兵器は現状維持を良しとする国に,軍事力よりも経済力に関心を集中できる恩恵を与
える」や「核兵器により,経済生産力が世界を主導する国々の半分以下の力しかない国でも現状維
持政策と抑止戦略をとる場合,軍事的には世界を主導する国と容易に競合できる。逆に,経済生産
力で世界を主導する国でも,経済的優位を利用してライバル大国への軍事的支配を確立したり,戦
略的優位を得ることはできない」とする59。核兵器の今日の有用性,及びその国家維持の手段とし
ての代替的効果を強調する点で,核兵器を筋肉硬直で使えず高くつくものとするナイ60とウォルツ
は見解を異にする。
ナイは現状の自助の国際システムでは軍事力は必要だとして,リアリストの前提⑥軍事力の有用
性を認める立場ではある。しかし,ウォルッほどには彼のその評価は高いものではないとは言えよ
う。
一方,力の代替性低下を指摘するナイは,その低下が個々の力の領域に異なる権力者を生み,力
を拡散させる事態を生む。その結果,多くの争点で民間部門や小国の力が増し,大国は以前ほどに
は力を活用できない,とする。この拡散は,経済の相互依存,脱国家的な組織弱小国のナショナ
ー238一

リズム,技術の普及,政治上の争点の変化という5つの流れで拍車が掛かることになっていると
ナイは言う61。
以上のような代替性の低下,拡散という認識から,今日,力は「3次元のチェスゲーム」のよう
な構造の下,作用するとナ・イは述べる。1次元にあるのが軍事的領域。真ん中には経済領域。そし
て1番下の層は,政府の管理の外側にあり,国境を越えた流れをもつ脱国家的関係という構造に
なっているとナイは言う。そして,各層で力構造が分散した状態となり現在の政策決定は容易でな
く,軍事力が重要であっても違う層の領域でそれが効力を発揮するわけでなく,3つの層のチェス
ボードで同時にチェスを動かさねばならない権力ゲームになっているとしている62。
この考え方も,力の拡散に懐疑的なウォルツとは見解が異なる。彼は自助のシステムの下,国家
はそれぞれの源泉を結合させた力を行使させねばならず,個々の源泉を分けた考慮はできない,と
する63。そこから「ある問題領域を他の領域と分けたり,弱い国がいくつかの点で優位であること
を強調することは,不平等の意味を弱める」や「力は,弱い国には代替性はあまりないが,強い国
にとっては非常にあるものなのだ」とウォルッは主張している64。
(b) ソフト・パワー
ナイが提唱した力の概念に「力の第二の顔」65と彼が呼ぶ「ソフト・パワー」がある。これは上
記の「態度・行動が醸し出す力」に属し66,従来からある概念を「ハード・パワー」と呼んで分け
ている。ナイはハード・パワーを,それがなければ行わないような行動を行わせる能力で,その行
使は誘導と脅しといった「アメ」と「ムチ」という直接的あるいは命令的な手法に支えられるもの,
とする67。
そしてソフト・パワーは世界政治での課題設定や状況構築により,自身が欲するものを他者にも
欲するようにさせる力だとナイは言う。これはハード・パワーと異なり,間接的に力を行使する方
法,反対者などを吸収する力の行動であり,源泉には軍事力や経済力と対称的な文化,イデオロギ
ー,制度といった実態のないものがなる68。この源泉が,一国の持つ文化の普遍性と国際的活動領
域を取り仕切るルールや制度を有利に確立できる能力,または送り手が伝えようとする無料情報が
もつ説得力と結びつき醸し出される69。今日このソフト・パワーの重要性は増してきているとナイ
はする70。
こうしたソフト・パワーをサミュエル・ハンチントソ(Samuel P. Huntington)は「ソフト・
パワーはハード・パワーという基盤があって初めて,パワーになる。経済や軍事面でのハード・パ
ワーは,自国への自信を高め,傲慢さを助長し,自分達の文化,すなわちソフト・パワーが他の民
族のものに比べ優れているとの思いを強める。こうして,その文化は他民族に対しても魅力を増
す。経済的,軍事的な力が低下すれば自信はゆらぎ,アイデンティティの危機から人々は他文化の
中に経済的,軍事的,政治的成功の手がかりを求めようとするようになる」と評する71。彼はソフ
ト・パワーとはハード・パワーがあって持てる力で,後者から独立した力ではないとする。これは
「世論を支配する力」は軍事力と経済力に常に結びつき作用する,とするE・H・カーの見方に通じ
一239一

るものがあるだろう72。
このハンチントンの指摘に,ハード・パワー的側面の成功はソフト・パワーを上昇させ,逆に失
敗は低下を招くとする指摘は正しいが,ソフト・パワーがハード・パワーの基盤に完全に依存する
との指摘は間違いだとして,彼の見解をナイは退けている73。
この両者の意見の違いをどう捉えたらよいか。ナイはソフト・パワーを「力の第2の顔」とし,
ハード・パワー,すなわち「第1の顔」を上記のダールの「さもなくばしないであろうことを他
者にさせる能力」に相当するものと位置づけていた。他方,社会学者スティーブソ・ルークス
(Steven Lukes)は,ダールの定義をナイ同様「力の第1の顔」とした上で「第3の顔」まで力を
類型化している。彼はダールの権力観を「1次元的権力観」,ダールを批判し「権力の2面性」を
主張したピーター・バクラック(Peter Bachrach)とモートソ・バラッツ(Morton S. Baratz)の
権力観を「2次元的権力観」,そして自らが提唱した権力観を「3次元的権力観」とした74。このル
ークスの分類を基準に,ナイとハンチントンの言うソフト・パワーとハード・パワーを見てみる
と,両者の見方の違いが明確になる。
ルークスは「1次元的権力観」を争点を巡って決定が作成される際の行動に注視するものとする。
その行動は政治参加を通して示され,それゆえ明確な政策選好を捉えることができるという。こう
した(主観的)利害の観察可能な紛争に作用しているものとして彼はこの力を定義する75。
次いで,ルークスは「2次元的権力観」を「1次元的権力観」の政治争点と見なされるものの範
囲をある程度定義し直しているものとする。重要な争点は顕在的なものの他に潜在的なものがあ
る。それを「1次元的権力観」の顕在的争点へ決定作成の範囲を制限する「決定作成老の価値や利
害に対する隠然たる挑戦や公然たる挑戦を抑止または挫折しめる決定」すなわち「非決定作成」と
いう力が作用しているものとする76。利害対立の起こりうる争点を,一方が他方の行動を制御する
ことで対立を表面化させず,顕在化している対立に争点の幅を狭めた上で望む結果を得る能力とで
も言えよう。
彼は,この「2次元的権力観」を権力関係の分析の中に政治アジェンダの支配,潜在的争点が政
治過程から閉め出される手法の考慮という点で大きく「1次元的権力観」を踏み越えた概念としな
がらも,①集団や制度により潜在的争点が政治過程から排除される手法を的確に捉えていない77。
つまり,一方という主体からでなく,構造化されたバイアスのような間接的な形で客体に作用する
力を考慮していない。②実際の観察可能な紛争に結びつけて考えており,操縦や権威に価値を巡る
紛争の可能性が内包されている事を見落とし,日常ありふれた形態でなされる思考支配による紛争
の表面化阻止を見落とす形となっている78。すなわち,明確な意図を持つ一方と他方の存在を前提
とし,他方に不平不満を抱かせなくする思考支配の力を考慮せず,紛争の潜在性を忘却させてしま
う力が視野にない。③非決定の作成で行使される権力が争点として政治過程に入れなかった苦情の
存する所のみに現れることは,苦情の不在は真正の合意に等しいと,虚偽の合意が操作された可能
性を排除することになる79。換言すれば,思考支配により,本来,都合の悪い争点に他方が合意
一240 一

し,一方にのみ都合のよい状況に他方が不満を持たないことになる状況下での潜在的争点を視野に
入れていない。こうした点から,完全に「2次元的権力観」を「1次元的権力観」を超えた概念で
はないとルークスはする。
そこで,彼自身は①②③を踏まえて,「3次元的権力観」を「社会的諸力を制度上の慣行の操作
を通して,あるいは個々人の諸決定を通して潜在的争点が政治から排除される種々の手法について
考察することにより見られる力」と定義し主張している80。
以上のようなルークスの区分とナイとハンチソトンの考察を照合すると両者の違いが明確にな
る。「1次元的権力観」は顕在的な力を指す。ナイはもちろんハンチントンも,その行使には意図
を必要とする資源である軍事・経済的領域から醸し出される力を想定しておりハード・パワーに相
当する。
「2次元的権力観」は「1次元的権力観」と違い,潜在的争点の領域で作用するものだが,アジ
ェンダの支配や潜在的争点の政治過程からの締め出しに関するルークスの批判①②③をこの領域の
定義に考慮すれば,「1次元的権力観」すなわちハード・パワーの領域から完全に独立していない
領域となる。したがって,軍事,経済など行使に意図・意識が付随する力を基礎とし,その派生が
潜在的な争点の部分で相手を引きつけ従わせる作用となる特徴は,ハンチントンの言う「ソフト・
パワー」にあたると見ることはできる。しかし,ナイの主張する「ソフト・パワー」はハード・パ
ワーに完全には依存しないとすることから,この領域は基本的にナイが意図するソフト・パワーの
領域にならない81。
では「3次元的権力観」はどうか。ナイが意図したソフト・パワーの領域とは,実はこの領域に
位置する力である。ルークスはこの領域を「1次元的権力観」の影響の及ぼない領域とし,ハンチ
ントソの言う「ソフト・パワー」はこの領域を視野に入れた力ではないことになる。逆にナイの想
定する「ハード・パワー」は「1次元的権力観」の影響を受けた「2次元的権力観」までの領域を
指す。そして,ハンチントンの指摘も部分的に認め「2次元的権力観」の領域にいくらか及ぶが,
基本的に「1次元的権力観」の影響の及ぼない「3次元的権力観」の領域を「ソフト・パワー」と
ナイは捉えるのである。それぞれの権力観を図で表せば以下のようになるだろう。ナイが力と見な
すものの視野はハンチントン等の視野よりも広いと言うことができる。
ルークスの言う権力観
1次元的 2次元的 3次元的
ハード・
pワー
ソフト・
pワー
x崧蛛@践・ ”需塾 ・一
ハンチントンの権力観
ルークスの言う権力観
1次元的 2次元的 3次元的
バーiド・
ハワi一
ナイの権力観
ソフト・
ハワー
図 権力観の比較
一241一

加えて,ほぼ符合するとなれば,「3次元的権力観」の特徴はナイの「ソフト・パワー」に同様
に当てはまると見ることができよう。「2次元的権力観」同様「3次元的権力観」は,問題領域ご
とに権力者が複数存在すると見る「1次元的権力観」を批判したものである。前者2つの権力観は,
権力者が複数いるように見えて実はつながっており,結局は特定の権力者が一方的な権力行使をす
ると見る権力観である82。上記で今日の力は拡散した状況にあるとナイはするが,更に今後ソフト
パワーの重要性,影響力が増すことになれば,再び力は一元的に収敏される,しかし思考支配の
結果その状況に我々は気づかない,との事態を生む可能性もある。
ただし,そうした事態があるのかは本当にソフト・パワーなる力があるのかをまず証明しなけれ
ばならない。ルークスの概念への批判には,対立が抑圧されて顕在化しないというならば,そうし
たパワーは観察により確認できず,確認は実証的な裏付けの乏しい解釈や推論によらなければなら
ない,との類のものがある83。ソフト・パワーにも同様の批判ができよう。
批判の一方,スーザン・ストレンジ(Susan Strange)は力の概念を意図した結果または慎重に
追求された結果に限ることなく,そこに存在するだけで効果的に行使される対立の顕在化しない力
を認識することの重要性を説き,ナイの権力観を擁護する84。このように評価は現状では賛否が分
かれるが,いずれにせよ,ナイは権力状況の変容する可能性を広く視野に入れているとは言えるだ
ろう。
3.相互依存
これまで扱った,国家,国益,国力といった要素はナイの考える国際政治における分析の基本要
素であった。では,ナ・イはこれらの基本要素がどのような状況下で作用していると見なしているの
か。
ナイは,基本要素が存在する今日の世界の状況を相互依存の状況であるとする85。そして「簡単
に言えば,相互依存は互いに従属することを意味する」とし,「そのような状況はそれ自体良く
も悪くもなく,状況の中には多かれ少なかれ存在しうる」と言う。加えて「相互依存は分析的と同
様に・fデオロギー的にも用いられることが可能であり,イデオロギー的には統治者による支配を表
す言葉(Idepend;you depend;we depend;they rule.)として用い,分析的にはシステムの様々な
部分において行為主体と出来事が互いに影響を与える状況を言う」86とする。
こうした見方に対し,ケネス・ウォルッはこの用語を政治状況の分析に用いるべきでないと「ア
メリカ人が口にする“相互依存”という修辞的表現は,多分にイデオロギー的な装いを持っている。
“相互依存”なる表現は,国家間に存在する実力の不均衡を微妙な形で暖昧にするものであり,更
に,諸国は互恵的な相互依存関係を持っており,全ての国が同等の資格と能力において国際関係を
結んでいるかのような幻覚を与えるものである」87と述べる。彼は国内の政治と同様に国際政治の
多くは不平等についての政治であり,その用語が想起させる不平等さの曖昧な状況は現実にはほと
んどないとする。そして,ロバート・コヘイン(Robert O. Keohane)とジョセブ・ナイが「非対
一242一

称な相互依存」なる用語を国家間の従属と独立の関係の代わりに用いたことにより曖昧になった88
と「国家間の相互依存という神話」を作り出し広めた張本人としてナイを挙げている。
この文脈から判断できるウォルツのナイへの批判は,次の2点を指摘できよう。
①力の対称性について。力の箇所で述べたように,ウォルッは主体間の非対称な力関係が問題領
域ごとに異なるとするナイの見方を批判する立場にある89。彼にすれば,それが実力の不均衡を暖
床にしている,と相互依存を批判する要因になっている。
②国家が求める利得の性質について。相互依存という用語は互恵的関係を国家間にもたらすかの
幻想を与えるとウォルツは言う。アナーキーの下,国家は自助の行動をとる。そのため,国家の求
める利得は他国より相対的に高い利得で,相対性・不平等性を暖昧に他国との力関係を考慮しない
利得,絶対的利得ではない,と彼はするgo。更にそこから,相対的利得を度外視した他国の利益獲
得に貢献する協調行動を国家が選択することに懐疑的立場を彼はとる91。
ナイ自身は相互依存状況下で①②をどう捉えるのか。この点から彼の相互依存論を見ると,まず
①対称性の問題,で注意すべきは,ナイ自身「非対称性は相互依存の政治の中心に存在する」とす
る点である92。彼は「相互依存は言葉の上ではどこか美しい響きがあるが,調和を意味するわけで
はない。互いに依存し合っても釣り合いがうまくとれないことはよくある。こうした相互依存関係
では,依存度の低い側,または脆弱性の小さい側が相互依存を操作するという脅威を相手方に与
え,そこから力を引き出すことができる」とする93。必ずしもナイは相互依存状況から非対称とい
う見方を排除したのではなく,あくまで問題領域ごとに国家間の非対称な関係が異なると見る点が
ウォルッと違うのである94。この違いは,力の代替性が今日低下しているとナイがすることに由来
する95。これにより総合的国力で劣る国も,ある問題領域に強味があれば,時に強国にも優位に立
てるとした認識を彼は持つ。
そして,相互依存状況下の権力闘争は代替性に代わり,リンケージの形成あるいは分離という力
操作でトレード・オフされていく,と彼は捉える。これは自国の利益や立場により,問題を他の問
題と結びつけたり分離させたりする行動を通して優位に立つための闘争を諸国家が繰り広げるとい
うことである。そこでは,国家は自国が強い領域では相互依存の操作を試みるが,自らが弱い領域
では操作されることを防ぐ行動をとることになる,とナイは言う96。しかし,この見方であれば,
多くの問題領域で強さを誇る大国は「三次元のチェスゲーム」でのリンゲージ操作の機会を小国よ
りも多く持つことになり,各問題領域で優位に立つ可能性は高くなるだろう。弱小国も優位に立て
る機会は増えたとする分,ウォルッと程度は異なるが,現状の相互依存で大国優位の非対称となる
傾向に関してはナイもウォルッの意見と大きく違うものにはならないと筆者は考える97。
だが,ナイは相互依存状況下での権力闘争で必ずしもリンケージが強国優位に運ばず,小国優位
をもたらす状況もあるとして2つのケースを明示する。経済的相互依存による抑止,及び国際機
関と複雑な相互依存の網の目の作用,である。
経済的相互依存による抑止は核抑止に似た側面があり,小国であっても大国に勝つこともあるの
一243一

だとナ・イは言う98。双方に一定の恩恵をもたらす経済の相互依存状況は,関係を混乱させる威嚇が
なされると犠牲のかなり大きなものになりうる99。操作を試みる国も実際に紛争が起これば傷つく
ことになるが,1つの問題に強く集中し問題解決のための脅迫に高度の信愚性を持たせることがで
きれば,小国も相対的に脆弱な自らの地位に打ち勝つことができる事態を生む,とナイはす
る100。「態度・行動が醸し出す力」をいかに巧みに用いるかが望む結果を得る条件となる,と彼は
見ているのである。
国際機関はリンケージの操作で,各国が懸案の課題を自国優位に持ち込もうとする場でもある
が,問題領域を他の領域と切り離す働きもする場だとナイは言う。これはリソケージ操作ができな
くなることを意味し,圧倒的力を持つ国もある領域で強味を持つ弱小国に優位を与える状況を生
む。その際,他の領域で圧倒的な力を持つ強国はその力を武器に,自国に不都合な国際機関での取
り決めを無効にしようとする。ナイは相互依存状態の下では複雑な網の目がそうした行動を思いと
どまらせるよう働くとする。すなわち,強国内部で利害の異なる集団の政治参加増加により国際機
関の取り決めを支持する集団も現れ,弱小国との事実上の連合的行動で自国の行動を抑える働きが
生じる,と言う。単に軍事的優位のリンケージ戦略が強国に恩恵を与えることにならなくなってい
るとナ・fは見る101。
以上,①対称性の問題について,ナイはウォルッ同様,非対称性は大国優位に働く傾向にあると
見てはいる。だが,問題領域ごとに非対称関係は異なるとするため,時に小国も大国に対し優位に
立つ場合があるとする。小国優位となる状況を生むのは,態度・行動が醸し出す力をいかに巧みに
用いるかと優位の機会を与える国際機関等と国内社会の働きにかかっていると彼は見ていると言え
よう。
次にナイが考える②国家が求める利得の性質,であるが,利益の不平等に注目せず,相対的利得
の配分から生じる紛争に注目しない分析は相互依存の政治的側面を見失うことになる,と彼はす
る。そして「相互依存し合った国家同士に,共同利益があっても,誰がその利益の大きい方・小さ
い方を取るかを巡り紛争があるかもしれない」とまで言うユ02。それはかつて,リアリストとリベ
ラルの間の争点となった国家の求める利得の性質に関して,まるで国家は相対的利得を求め行動す
るとのリアリストの立場を支持するようでもある103。加えて,「リベラルな分析者の中には,世界
がより相互依存状況になると協調が競争に取って代わるようになる,と考え違いを犯す人々がい
る」とあくまで相互依存状況であっても権力闘争は存在すると彼はする104。
しかし,注意すべきは,ナイは協調が競争に「取って代わること」は否定するが,諸国家が協調
する状況を完全否定はしていないということである。彼は全ての当事国が安定を求めれば,勢力均
衡下でも共同利益を見出すことができるとする。加えて,相手国の経済成長が自国の好況につなが
れば,経済的相互依存の下,国家は他国との相対的利得同様に絶対的利得にも関心を持つとす
る105。ナイはウォルッの見方に大筋で同意はするが,国家は時として絶対的利得も追求し協力も
するとも考える106。
-244一

以上,ウォルッによる批判の観点から,ナイの相互依存を整理してきた。ウォルツはナイを批判
をするが,ナイの論じるかなりの部分はウォルツの主張する国際政治の状況と大差のないものであ
った。しかし,それでもこれまで述べた中で,次の2点は異なる要素として残る。①で述べた国
際機関の有効性107,②の国家が絶対的利得を求め協調する場合もある108,ということである。
では,この2点がネオ・リアリストの中心的人物とされるウォルツとナイの間の距離を学派を
隔てるまでのものにしているのか。していない,とするのが筆者の捉え方である。
①に関して,スティーブン・クラズナー(Stephen D. Krasner)は,力を持つ国がルールを作る
とするが,人,モノ,アイデア等が国境を越えて移動する傾向が増大したことが国際法的主権の重
要性をこれまでよりも更に高め,国家は自らの行動の自由度を制限しあうように,貿易に関する国
際的な取り決めに参加することにした,としている109。
②は,チャールズ・グレーサー(Charles L. Glaser)はウォルッのリアリズムの中心的仮説から
援用した独自理論を展開し,「相対的利得問題の論理により認識される問いに反して,協調が国家
の安全を高めるのであれば,敵の安全保障の増加は,防衛国の安全の増加に勝ろうがどちらの国に
とっても望ましい」110として,絶対的利得を求め,国家は協調を選択することもあるとの見方をと
る。
両老とも,ネオ・リアリストと呼ばれる論者であるが111,彼らの指摘はナイの主張と重なると
ころが見られる。その意味で,ナイとウォルッの主張の異なる箇所が,学派を分けるほどに大きく
異なる要素には必ずしもならない,と見ることもできよう。したがって,リアリズムの前提を全て
満たすのであれば,ナイをネオ・リアリストと見ることもできよう。最後に国家が求めるものを見
るリアリストの前提③だが,前述のように,アナーキーである限り安全保障は常に国家の目標・国
益となる点112,そして,国家は基本的に相対的利得獲得を目指すが,時に絶対的利得追求も不本
意としないとする上記の内容を考えると,ナイは国家は絶えず力の獲得の最大化を目指すわけでな
いが,安全は常に目指すはずだと考えているようである。③の条件を満たすと同時に,このことか
ら彼をネオ・リアリストで(B)防御的リアリストであると見ることもできるだろう113。
4. おわりに
以上,ナイの国際政治理論についての考察を行ってきた。
まず,彼が基本要素と位置づける,国家,国益,国力について概観した。国家は常に重要な行為
主体ではあるが,他の行為主体の存在も今日において軽視はできない。国益は国際政治がアナーキ
ーである限り,完全に軍事的安全保障が国家の目標・国益としてなくなることはないが,今日,よ
り広く多様なものを国益と見る状況になってきている。国力は軍事力は力を具現する究極の形態で
はあるが,源泉の重要性は変化し,代替性の低下,問題領域ごとに異なる力の拡散,ソフト・パワ
ーの重要性の増加,という変化を見せている。こうした彼の考えを貫くのは,継続と変容という広
い捉え方であると言えよう。そして,基本要素が存在する状況を相互依存状況としてナイは捉え
一245一

る。相互依存という概念はリアリストの指摘とは正反対な概念と見られがちである。しかし,基本
要素を広く捉えるナイではあるが,指摘する相互依存の現状はリアリストが述べるものと大きく違
っていなかった。そして,全体を通してナイの理論にリアリズムの6つの前提が含まれているの
かも見てきた。彼の議論の中には前提の①から⑥までが踏まえられていた。そして④でアナーキー
が穏健な動機を与える可能性を示唆し,③で,国家は力よりも安全を求めるとし,彼のリアリズム
は防御的リアリズムとすることができた。
ナ・イは基本的に自己をリベラリズムに属する理論家だと規定する114。彼のリベラリズムの根底
にある現状の見方は,概観したように,基本要素の継続と変容が同居した状態であると言える。彼
にとって,継続とはリアリズム,変容とはリベラリズムの捉え方を指す115。彼は従来,対立概念
であったこの2つの思想を自身が主張するネオ・リベラリズム(Neoliberalism)として統合を試
みたのである116。
その際,ナイは「国際システムを定義する際に構造の概念に過程のレベルを加えることは,元来
分裂していたリアリズムとリベラリズムをむしろ統合へと動かすネオ・リベラルなシステム理論を
発展させる機会を与える」とする117。この構造という主体間の能力の分配で,国家の行動の説明
を試みるのがネオ・リアリストの考え方で,リベラルは過程という主体の相互作用を重視するとナ
イは見る118。従来からリアリストが指摘する力の分配のみにより,国家は行動の選択に影響を受
けるのではなく,基本要素の変容から影響力を強めることとなる経済活動のレベルの変化,脱国家
的な相互作用,国際制度の変更などによっても,国家行動は影響を受ける119。こうしたことか
ら,国家の行動を分析する際に過程も視野に入れねばならないとして,ネオ・リベラリズムをナイ
は提唱した。
しかし,彼の理論は現状の説明においてリアリストの主張との違いをさほど生まない。そして,
論敵のウォルッ本人からも,相互依存の解釈は批判されながらも,ナイがコヘイソと共に主張した
概念の中核に自分の主張が反映されているとされた120。ナイは,こうした指摘を自身が目指した
リアリズムとリベラリズムの統合の成果と見たかもしれない。実務家としてイニシアティブを推進
した彼はリアリストのようだと言われた。ナイはそれを認め自身の思想に一貫した行動だとした。
これは彼自身がリベラルを自認しながら,リアリストの思想も視野に入れたリベラルであったから
だと筆者は考える。
冒頭で記したように,リアリズムは防御的リアリズムと攻撃的リアリズムの論者の間で今日論争
が繰り広げられている。論争の中で,ナイはクリストファー・レインにより防御的リアリストとし
て評されている121。本論文では,ナイ自身がリアリストであることをも否定しないことから,根
拠を提示して彼を防御的リアリストと評価することもできることを記してきた。
防御的リアリストは攻撃的リアリストに比べ,国際システムを楽観的に捉えるアプローチであ
る。ナイの考えが冷戦後の日米同盟及び東アジア地域に対する米国の姿勢に影響を与えているのだ
とすれば,楽観的で積極的な戦争回避を意図した考えが米国の姿勢に反映されているということに
一246一

なる122。それゆえ,今後暫く東アジア地域に大きな対立がなく安定が持続されるのであれば,政
策に援用された防御的リアリズムの思想が安定の大きな要因となっていると言える可能性も出てこ
よう。逆に,この思想に基づく政策を用いても同地域に権力闘争が生じたということになれば,攻
撃的リアリズムの方が優れた見識を有していた,として論争の評価を下す根拠となりうるものを提
供したことになるのかもしれない123。
注
1具体的な所産は1996年4月17日東京において,当時の首相,橋本龍太郎と米国大統領クリントソの間で発
表された「日米安全保障共同宣言(U.S.-Japan Joint Declaration on Security:Alliance for the 21st Century)」
を指す。これは,冷戦後の日米同盟の重要性を再確認し,日米防衛協力の指針見直しに駒を動かしたもので
あるとされている。土山實男「日米安全保障共同宣言」猪口孝,大澤真幸,岡沢憲芙,山本吉宣,スティー
ブソ・R・リード編「政治学事典」(弘文堂,2000年)840-841頁。
2国防次官補就任以前のナイは国家情報会議(National Intelligence CounciL NIC)議長というホワイトハウ
ス内の次官クラスの要職にあった。
3例えば土山實男「日米同盟の「漂流」一新たな存在証明を求めて」増田弘,土山實男編『日米同盟キーワ
ード』(有斐閣,2001年)86-87頁。
4 0缶ce of Internatinal Security Affairs, United States Security Strategy for the East Asia-Pacific Region,
U.S. Department of Defense, February 1995.邦訳は「米国防総省の第三次東アジア戦略構想①②③④」r世
界週報』①(1995年3月21日)64-68頁。②(1995年3月28日)62-70頁。③(1995年4月4日)60-65頁。
④(1995年4月11日)65-70頁。
5Joseph S. Nye, Jr,‘‘East Asian Security:The Case for Deep Engagement,”.Foreign Affairs, Vo1.74, No.4
(July/August 1995),p.94;Nye,‘‘The‘Nye Report’:six years later,”」haternational Relations of the Asia-Pa-
ci c, Vol.1,(2001),p.95.
6 Nye,‘‘The‘Nye Report’:six years later,”p.95.
7理論解説のテキストでは,ナイとロバート・コヘイン(Robert O. Keohane)との共著『力と相互依存』
(Keohane and Nye, Power and Interdependence’World Politics in Transition(Boston:Little, Brown, lsted
1977).)は,リベラリズムを代表する著書として紹介される。
なお,リベラリズムの定義としては,ミアシャイマーに従えば,リベラリズムには3つの前提があるとい
う。①国家が主要な行為主体である,②国家の内的性格がかなり変化し,その違いが国家行動に深く影響を
与える,③良い国家の行動を説明するのに力の計算をすることはほとんど重要でない,である。そして,彼
はこの前提を踏まえた3種類のリベラリズム,(A)国家間の相互依存の高い程度が互いに争うことを起こり
にくくさせる,(B)民主主義国間では戦争が起きない,(C)国際制度が国家間の協調の可能性を高め戦争の
可能性を減らす,があるとした。John J. Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics(New York:W.
W.Norton,2001),pp.15-17.
ナイはこれに(D)脱国家的な接触と提携が国家の態度と利益の定義について影響を与える,とする社会
学的リベラリズム(Sociological Liberalism)を加えている。 Nye,“Neorealism and Neoliberalism,”World
Politics, Vol.40, No.2(January 1988),p. 246.これを加えると,ミアシャイマーによる前提①の主要行為体に
国家以外の行為主体も加える必要がでてくる。他の文献を見ると,ナイの類型を含む4種類のリベラリズム
を提示しているものもあり(例えば,David A. Boldwin,“Neoliberalism, Neorealism, and Warld Politics,”in
Boldwin, ed.,Neorealism and IVeoliberalism:The Contempora7pU 1)ebate(New York:Columbia University Press,
1993),p.4.),本論文は,リベラリズムとはミアシャイマーの前提の主要行為主体に国家以外の主体も含め
ることにし,4種類に分類されるものとする。
8 Nye, Understanding lnternational Conflicts:An lntroduction to Theory and History(New York:Longman,3rd
ed.2000).
一247一

9 Nye,‘‘The‘Nye Report’:six years later,”p.95.
10@Nye,‘‘The Contribution of Strategic Studies:Future Challenges,” Adelphi Paper, Part I, No,235,(Spring
1989),p.22.
11 @1bid., p32.
12 @Robert G. Gilpin,“No One Loves a Political Realist,”in Benjamin Frankel, ed., Realism:Restatements and
Renewal(London:Frank Cass,1996),p.6.
13Benjamin Frankel,‘‘Restating the Realist Case:An lntroduction,” in Frankel, ed.,Realism, p. xiii;Sean M.
Lynn-Jones and Steven E. Miller,“Preface,”in Michael E. Brown, Lynn-Jones and Miller eds., Perils(ofAnar一
吻:Contemporai y Realism and lnternational Securdy(Cambridge, Mass.:The MIT Press,1995),p. ix.
14.Frankel,‘‘Restating the Realist Case,”pp. xiv-xviii;Lynn-Jones and Miller,“Preface,” pp. ix-x,
15Frankel,“Restating the Realist Case,”pp. xviii-xix;Lynn-Jones and Miller,‘‘Preface,” p. x.
16例えば,他にギデオン・ローズ(Gideon Rose)が提唱するネオ・クラシカル・リアリズム(Neoclassical
Realism)と呼ばれるものがあるが,ジェフリー・タリアフェロー(Jeffrey W. Taliaferro)はこのリアリズ
ムを防御的リアリズムと攻撃的リアリズムの対外政策理論として整理している。Rose,“Neoclassical Real・
ism and Theries of Foreign Policy,”World∫Politics, VoL 51, No。1(October 1998),pp.144-172;Taliaferro,
“Security Seeking Under Anarchy,”International Security, Vo1,25, No,3(Winter 2000/2001),pp.132-134,
17Mearsheimer, The Tragedy(of Great Power Politics, pp.17-22.
18 1bid., pp.18-22.
19 @Franke1,‘‘Restating the Realist Case,”pp. xv-xvi.
20Mearsheimer, The Tragedy(of Great、Power」Politics, pp.19-20.
21 @Frankel,‘‘Restating the Realist Case,”p. xvi.
22@Nye, Understanding lntemational Conflicts, pp.7-11.
23 1bid., p,208.
24E・H・カー(井上茂訳)『危機の20年一1919-1939』(岩波書店,1996年)416頁。25@Nye, Understanding lnternational Conflicts, p.210.
26①世界連邦主義(World Federalism)②機能主義(Functionalism)③地域主義(Reagionalism)④自然環
境主義(Ecologism)⑤サイバー封建主義(Cyber-fuedalism)という5つの主要な努力がなされたと,ナイ
は言う。Ibid., pp.208-210
27Nye,‘‘What New World Order?”、勘忽即4伽欝, Vol.71, No.2(Spring 1992),p.92.
28 1bid., p.84, p.93.
29@Nye, Understanding Jnternational Conflicts, pp.195-196.
30 1bid., pp.7-8.
31 @1bid., pp.196-197.
32 @1bid,, p.194.
33 @Nye, Understanding lnternational Conflicts, P.8.
34 @Gilpin,“No One Loves a Political Realist,”p.25.
35 1bid., p.46,
36例えばRandall LSchweller and David Priess, f‘A Tale of Two Realisms:Exapanding the lnstitutions De・
bate,’vMershon International Studies Review, No.41(1997),p。7.
37Christpher Layne, “American’s Role:What’s Built Up Must Come Down,” The VVashington post, November
14,1999.
38
39
40
41
42
Ibid.
Nye, Understanding International Co履ガicts, p.46.
Kenneth N. Waltz, Theoリノ(ゾInternationa~Politics(Reading, Mass:Addison-Wesley,1979),p.134.
Ibid., p.111.
Nye, Unders∫tanding ln temation(zl Conf7icts, p.46.
一248一

43
44
45
46
47
48
49
50
51
Nye,‘‘The Contribution of Strategic Studies,”p.24.
Nye,こlnderstanding lnternational Conflicts, p.46.
Ibid., p.46.
Nye and Layne,“The Galf War:An Exchange,”TI{E A TLAI>7YC, Vo1,268, Iss.1(July 1991),p.80.
Ibid., pp.54-81,
Nye,‘‘The Contribution of Strategic Studies,”p.22.
Nye,乙「nderstanding lnternational Co履ガicts, P.8.
Ibid., p,46.
Nye, Bound to lead:the changing nature(ゾノlmerican power(New York:BasicBooks,1990),p.26;Nye,
Understanding lnternational Co理ガicts, P.55.
52@Keohane and Nye,‘‘Power and Interdependence in the Information Age,”.Foreign Affairs, Vol.77, No.5
(September/Octorber 1998),p.86.
53
54
55
56
57
58
59
Nye,、Bound to lead, p.26;Nye,乙lnders tanding ln temαtional Con]7icts, p.55.
Nye, Bound to leαd, pp.26-27;Nye,乙lnderstanding lnternational Co履ガicts, p.56.
Nye,、Bound to lead, p.33;Nye,乙「nderstanding lnternationαl Co履ガicts, p.58.
Nye, Bound to lead, p.27;Nye,乙「nderstanding lntemational Co履ガicts, p.56.
Nye, Bound to leαd, p.189.
Ibid., p180.
Waltz,“The Emerging Structure of International Politics,”Internationat Secttrity, Vo1.18, No,2(Fal1
1993),pp,51-53.
60
6ユ
62
63
64
Nye,乙「nderstandin9 lnternational Copガicts, P.9.
Nye,、Bound to lead, p,182.
Nye,‘‘Redefilling the National Interest,”Foreign Affairs, Vo1.78, No.4(July/August 1999),p.24,
Waltz,丁舵oり,(ヅ砺6γ履競α1、Politics, p.131.
Waltz,“Structural Realism after the Cold War,”傭〃鰯競α1 Sθo纏砂, Vol,25, No,1(Summer 2000),p.
15.
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
Nye, Bound to lead, p.31, Nye, Understanding」lnternational Conflicts, p.57.
Keohane and Nye,“Power and Interdependence in the Information Age,「’p.86.
Nye, Bound to lead, p.31;Nye, Understanding lnternational Conflicts, p.57.
Nye, Bound右o lead, pp.31-32;Nye, Understanding lnternational Conflicts, p.57,
Keohane and Nye,‘‘Power and Interdependence in the Information Age,”p.86.
Nye, Bound to lead, p.33;Nye, Understanding International Conflicts, p.58.
サミュエル・P・ハソチントソ(鈴木主税訳)『文明の衝突』(集英社,1998年)132頁。
カー『危機の20年』207-208頁。
Keohane and Nye,‘‘Power and Interdependence in the Information Age,”pp.86-87.
スティーブソ・ルークス(中島吉弘訳)『現代権力論批判』(未来社,1995年)11頁。
同上,20-21頁。
同上,28-29頁。
同上,34-36頁。
同上,36-38頁。
同上,39-40頁。
同上,40頁。
ナイ自身はソフト・パワーをバクラック,パラヅッの概念を基礎に考え出したようであるが,
の本論文の考察からソフト・パワーを「2次元的権力観」に符合するものとは捉えない。Nye,
The Means to Success in World、Politics(New York:Public Affairs,2004),p.150.
82杉田敦『権力』(岩波書店,2000年)2頁。
筆者は以上
Soft P励9γ:
一249一

83例えば,伊藤光利,田中愛治,真淵勝著『政治過程論』(有斐閣,2000年)26頁。
enスーザソ・ストレソジ(桜井公人訳)『国家の退場一グローバル経済の新しい主役たち』(岩波書店,1998)
53頁。ただし,彼女はソフト・パワーはハード・パワーとの区分が正確に定義されてなく,国際政治経済学
でのパワーの一般理論へと発展したわけではない,ともしている。同上,41-42頁。
85ナイは,現実主義が前提に置く概念を一方の極に置き,同時にその対極に複合的相互依存(Complex In-
terdependence)という概念を並置し,その連続体(spectrum)の間に相互依存の状況はあるものとして概
念化を試みている。現状はこの両極の間にあり,両極の現実主義と複合的相互依存は現実の世界では存在し
ていないモデル化のための想像上の概念,理念型(ideal types)’としている。
彼は,現実主義の重要な仮説として次の三点,①国家が唯一の主要な行為体である,②軍事力が主要な手
段である,③安全保障が主要な目標である,を挙げる。そして,対極の複合的相互依存を①国境を越えて活
動する脱国家的な行為体も,また主要な行為体である,②経済の操作や国際制度の行使が主要な手段である,
③福祉が主要な目標である,とする。現実世界はこの両極の間にあり,諸国家間の特殊な関係がその範囲の
どこに位置するかで異なる政治と権力闘争の形態になるとナイは見なす。Nye, Understanding Internαtional
Con]7icts, pp.188-189.
この概念はPower and lnterdePendenceで示されたものである。ウォルッはこれに関して「コヘイソとナイ
は相互依存に関する本の中で,複合的相互依存は,時に現実主義以上に現実に近づく(lbid., p.23.)とする
際,明瞭な例示をするが,現実がどのようなものか判れば,理論は目的を果たさない」と,理論は現実を見
るためにあるのならば,現実で理論を見ようとする彼らの手法は本末転倒なものであると批判している。
Fred Halliday and Justin Rosenberg,‘‘lnterview with Ken Waltz,” Review(ofJnternational Studies, VoL 24, No.
3 (July 1998),p.386.
本論文はナイ個人が考える現状としての相互依存を考察することを目指す性質上,上記のコヘイソとの共
著書を参考にしつつも,ナイの単独の著書であるUnderstanding lnternational Conflicts,に記されている内
容を中心に,以下論じてゆく。
86@Nye, Unders tanding ln ternational Con]7icts, p.179.
87ケネス・N・ワルッ(和田和訳)「国家間の相互依存という神話」C.P.キンドルバーガー編(藤原武平太,
和田和訳)『多国籍企業 その理論と行動』(日本生産性本部,1971年)227頁。
88Waltz,“Structural Realism after the Cold War,”p,15.
89本論文,2.基本要素(3)国力(a)基本的捉え方,を参照のこと。
90Waltz,“Structural Reahsm after the Cold War,” p. 39.
91Waltz, Theory(of lnternational Politics, p.105.
92 Nye, Understanding lnternational Conflicts, p.184.
93@Nye, Bound to lead, p.180.
94ナイとコヘインは自著.Power and lnterdePendenceの改訂にあたり次のように述べている。「お互いに交際
をする際,行為体に最も影響力の源泉を与えそうなものは,我々が書いた非対称な相互依存であり,非対称
な相互依存が力の源泉であるというこの概念は,ケネス・ウォルツの論文「国家間の相互依存の神話(‘‘The
Myth of National Interdependence”)」,同様にアルバート・ハーシュマン(Albert Hirschman)の『国力と
対外貿易の構造(1>dtional Power and the Structure of Foreign Trade)』で明らかに見ることができる」。彼ら
はウォルツの見方と自身達の見方は共通しているとの認識があったようである。Keohane and Nye, Power
and lnterdependence(Reading, Mass:Addison-Wesley,2nded 1989),p. 247.
95本論文,2.基本要素(3)国力(a)基本的捉え方,を参照のこと。
96 Nye, Understandin8 lnternational Conflicts, p.185.
97Keohane and Nye, Power and lnterdependenCe,2nd, pp.30-32.において,リンケージ戦略は小国に優位にな
るとされているが,該当箇所で記されているのは複合的相互依存の状況下,ということである。理念型では
なく現状を記しているナイの単著Understanding lnternational Conflicts,の内容を判断すると,現状の相互
依存に対するナイの説明では大国優位の解釈ができると筆者は考える。
98 @Nye, Understanding lnternational Conflicts, p.186.
一250 一

99 Nye, Bound te leαd, pp.190-191.
100 Nye, Understanding lntemational Con]7icts, p.186.
101 1bid。, p.186.
102 1bid., p.181.
1031990年代前半のネオ・リアリストとネオ・リベラル制度主義者(Neo libera1 lnstitutionalist)の間で論争
を指す。詳しくはBoldwin, ed., Neorealism and IVeoliberalism,に記されている。日本語での解説は,河野勝
「対外政策」猪口邦子編『政治学のすすめ』(筑摩書房,1996年)148-159頁,石川卓「世紀末における国際
政治理論の状況」『外交時報』(1997年1月)83-86頁,などがある。
lo4 Nye, Understanding lnternational Conガicts, p.181.
105 1bid., pp,181-182.
106ナイは相互依存下において被る損失(costs)は短期的な敏感性(sensitivity)あるいは長期的な脆弱性
(vulnerability)に関係しうるものであるとする。
敏感性とは,依存の影響の程度と速さ,すなわちシステムの一部の変化がどれだけ速くシステムの他の部
分に変化をもたらすのかについてのことを言う。脆弱性は,相互依存のシステム構造を変えることによる相
対的な損失,つまりシステムから逃れたり,ゲームのルールを変える際に被るの損失を言い,社会が素早く
変化に対応できるか,代替案が有効か否か,多様な供給資源が存在するかなどに関わってくるものである。
システムの変化がその対応を迫ることになり,敏感性と脆弱性の高低は一致する場合もある。しかし,両
性質の程度の高低は必ずしも一致するわけではなく,例えば,状況の変更で損失が減る場合もあり,脆弱性
が高まると即断できない。したがって,両者は分けて考える必要がある。Ibid., pp.182-184.
本文中の利得とこのような損失から考察されるであろう,力の源泉の得失を巡り,国家は相互依存の状況
下で,政治行動をしてゆくことになる。
107ウォルツは,国際制度は強国により創設され,創設国の主要な利益に適う,または適うと考えられる限
り,当初の形態で存続し,強国の不利となる状況で制度が存続することはない,とする。すなわち,強国が
不利になる形で制度を運営する国際機関がその機能を果たし続けることに懐疑的な見方をしている。Waltz,
‘‘The Emerging Structure of International Politics,”p.26.
108ウォルッはダールの力の定義を否定する。彼は政治的に要を得るように,力を能力(capability)の分配の
観点から定義すべきとして,物質的なものから力を定義しようとする。しかし,能力を利用する際,AがB
に求めた服従を得るかどうかはAの能力と戦略,Bの能力とAへの対応の戦略とABが身近な状況から影
響を受ける要素の全てによる,とするように,定義はナイと異なるものの,戦略という態度が醸し出す要素
が相手の反応に与える影響自体をウォルツは否定しているわけではない。したがって,態度・行動が醸し出
す力に関する評価がナイとウォルツの異なる要素になるものとして筆者は取り上げることは控えた。Waltz,
Theo7 y Of lnternationαI Politics, p.191-192.
ウィリアム・ウォルフォース(William Curti Wohlforth)はウォルツの上記箇所を引用し,ダールの定義
を排除しリアリストは能力を力と見るとするが,スティーブソ・ウォルト(Stephen M. Walt)は脅威
(threat)という概念を用いる必要を説く。リアリストは必ずしも物質的側面からのみで力を捉えるわけでな
く,ナイの権力観がリアリストでないとする根拠にならないと筆者は考える。Wohlforth, Elusive Balance:
Power and Perception during the Cold War(lthaca:Cornell University Press,1993),pp.4-5. Walt, Tん6伽g勿s
of Alliances(Ithaca:Cornell University Press,1990),pp,21-26.
ウォルトがリアリストであることはTaliaferro,“Security Seeking Under Anarchy,”p.135,を参照。
109スティーブン・クラズナー(河野勝訳)「グローバリゼーショソ論批判一主権概念の再検討」渡辺昭夫,
土山實男編『グローバル・ガヴァナソスー政府なき秩序の模索』(2001年,東京大学出版会)45-68頁。
110 Charles L. Glaser,‘‘Realists as Optimists:Cooperation as Self-Help,”Intemational Seαnritノ, Vol.19, No。3
(Winter 1994/1995),p.76.
111例えば,クラズナーはBoldwin,“Neoliberalism, Neorealism, and World Politics,”in Boldwin, ed., Neoreal-
ism and IVeoliberalism, p.7,グレーサーはLynn-Jones and Miller,“Preface,”p. xi.などで,そのように紹介
されている。
一251一

112本論文,2,基本要素(2)国益,を参照のこと。
113 リアリズムの類型の定義は,本論文1.はじめに(2)リアリズムとは,を参照のこと。
114Nye,‘‘Neorealism and Neoliberalism,”pp.235-251,はそうした位置づけの上で書かれている。
115 Nye, Understanding ln ternational Con]7icts, P.6.
116 Nye,‘‘Neorealism and Neoliberalism,”p.251.
117 @1bid., p.251.
118 1bid., pp.249-251.
119 1bid., p.250.
120Waltz,“Structural Realism after the Cold War,”pp.24-25,
121@Christopher Layne,“From Preponderance to Offshore Blancing:Arnerica’s Future Grand Strategy,”ln te r-
national Security, Vol.22, No.1(Summer 1997),pp.92-95.
122ナイ・イニシアティブはナイの国防次官補就任以前から国防総省中堅幹部の間で始められていた(土山實
男『安全保障の国際政治学』(有斐閣,2004年)348頁。)が,ナイ・レポート作成に関わったマイケル・グ
リーン(Michael J. Green)防衛分析研究所研究員(当時)はレポート全体の枠組みは完全にナイのもので
あり,完全に彼がキーパーソソであったとしている。秋山昌廣『日米の戦略対話が始まった一安保再定義の
舞台裏』(亜紀書房,2002年)55-56頁。
123ナイは共有する安全保障の利益追求のために国際的提携を容易に米国は動員できると考える。彼は日本と
協力し,「封じ込め」と「取り込み(関与)(engagement)」に曖昧さを持たせた「建設的関与(constructive
engagement)」という手法で中国との関係をマネージメントすることを主張する。『朝日新聞』1996年3月
10日,Nye,“Conflicts after the Cold War,”The Washington(Quarterly, Vol.19, No.1,(1995),p. 20;Nye,
“China’s Re-emergence and the Asia-Pacific,” Suwival, Vol. 39, No.4(Winter 1997/1998),p75.
対する攻撃的リアリスト,例えばミアシャイマーはナイが支持したような中国を世界経済に組み入れ中国
経済の急速な発展を促す米国の政策を批判する。理由は,国家の生き残る可能性を最大にする方法は地域覇
権国になることであり,豊かな中国は現状維持国ではなく地域覇権国を目指すと考えるからである。彼は中
国の経済成長を遅らせる封じ込め政策を支持する。Mearsheimer, The Tragedy of Great Power Politics, pp.
402-403.
一252一