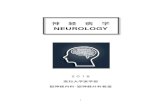文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 について ·...
Transcript of 文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 について ·...

文部科学省「脳科学研究戦略推進プログラム」 について
平成25年6月6日
文部科学省研究振興局ライフサイエンス課
資料3

脳科学研究戦略推進プログラムに関する経緯
脳科学研究戦略推進プログラム開始以前の動き
平成18年12月 脳科学研究の推進に関する懇談会(座長:金澤一郎先生)
報告書「脳科学研究ルネッサンス」を取りまとめる(平成19年 5月 )
脳科学研究戦略推進プログラム
平成 9年 5月 科学技術会議ライフサイエンス部会脳科学委員会(委員長:伊藤正男先生)(当時) 報告書「脳に関する研究開発についての長期的な考え方」を取りまとめる
平成18年 7月 研究計画・評価分科会 「10年が経過しようとしており、戦略的な研究推進方策を再検討する必要あり」
平成19年10月 文部科学大臣から科学技術・学術審議会に 「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について」を諮問
平成19年11月 脳科学委員会を設置
○脳科学に関する研究開発領域を「脳を知る」「脳を守る」「脳を創る」の3領域に分類
○科学技術振興調整費、戦略的創造研究推進事業(CREST)等を活用した政策課題対応型の脳科学総
合研究のプログラムやプロジェクトを推進
平成20年度 少子高齢化を迎える我が国の持続的な発展に資するため、脳科学研究を戦略的に推進
し成果を社会に還元することを目指し、本プログラムを開始。
○我が国における脳科学研究を戦略的に推進するため、その体制整備の在り方、人文・社会科学との融合、
さらには大学等における研究体制等を含めた長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策を
策定する。
2

脳科学研究戦略推進プログラム
概要 高齢化、多様化、複雑化が進む現代社会が直面する様々な課題の克服に向けて、脳科学に対する社会からの期待が高まっている。このような状況を踏まえ、『社会に貢献する脳科学』の実現を目指し、社会への応用を明確に見据えた脳科学研究を戦略的に推進するため、脳科学委員会における議論を踏まえ、重点的に推進すべき政策課題を設定し、その課題解決に向けて、研究開発拠点(中核となる代表機関と参画機関で構成)等を整備する。
①豊かな社会の実現に貢献するために
社会性障害(自閉症、統合失調症等)の解明・診断等に資する先導的研究
精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究
③安全・安心・快適な暮らしのために
BMI技術を用いた自立支援、精神・神経疾患等の克服に向けた研究
開発
基盤技術開発:疾患モデル動物
ニーズの高いモデル動物の開発・普及 精神・神経疾患の疾患モデルなど脳科学研究を推進する基盤として
遺伝子改変マーモセット等の普及体制の整備と共に、必要な技術開発を行う
②健やかな人生を
支えるために
精神・神経疾患の発生の仕組みを明らかにし、診断・治療・予防法の開発につなげる
社会的行動を支える脳基盤の計測・支援技術
の開発
脳の情報を計測から身体機能の回復・代替・補完や精神・神経疾患の革新的な予防・治療法の開発につなげる
複雑かつ多階層な脳機能を解明するために、脳の多種類・多階層情報を集約化・体系化した技術基盤を構築
基盤技術開発:神経情報基盤
平成25年度予算額 :3,488百万円 (平成24年度予算額 :3,487百万円)
(主査 : 金澤 一郎 日本学術会議会長(当時))
平成19年10月、文部科学大臣から科学技術・学術審議会に対し、「長期的展望に立つ脳科学研究の基本的構想及び推進方策について」を諮問
これを受け、同審議会の下に「脳科学委員会」を設置、平成21年6月23日に第1次の答申
本答申では、重点的に推進すべき研究領域等を設定し、社会への明確な応用を見据えて対応が急務とされる課題について、戦略的に研究を推進することを提言
重点的に推進すべき研究領域等
①脳と社会・教育(豊かな社会の実現に貢献する脳科学)
発達障害の予防と治療等への脳科学研究の確実な展開、脳
科学と人文社会科学との融合により社会へ貢献
②脳と心身の健康(健やかな人生を支える脳科学)
睡眠障害の予防、ストレスの適切な処理、生活習慣病等及
び精神・神経疾患の発症予防・早期診断などに資する研究
③脳と情報・産業(安全・安心・快適に役立つ脳科学)
脳型情報処理システムや脳型コンピューターの実現、脳内
情報機序の解明を通じた技術開発により社会へ貢献
○基盤技術開発 他の研究分野にも革新をもたらす基盤技術の開発により、
我が国における科学技術全体の共通財産を構築
脳 科 学 委 員 会 脳 科 学 研 究 戦 略 推 進 プ ロ グ ラ ム

BMI技術を用いた自立支援、精神・神経疾患等の克服に向けた研究開発
○概要:日本独自開発の低侵襲・非侵襲のBMI(ブレイン・マシン・インターフェース)技術を活用し、ロボットアームや歩行用外骨格ロボット等の機能代替・補完技術、リハビリテーション技術を開発し、身体障害や精神・神経疾患の克服を目指す。
脳表面の脳波を読み取り、 歩行機能をアシスト
「動け」という指令と「動いた」という感覚フィードバックの組合せにより、機能代償から機能回復へのシームレスなアシスト制御の実現・リハビリテーション効果を発揮。
皮質脳波を読み取り、腕の上げ下げ、掴む・握ることが可能
切断等の重症者に対しては、機能の代替を行うため、高度な動きを可能にする義手・義足等の開発。
脳活動の状態を訓練中に提示し、効率的なリハビリテーションの実施
脳の活動をリアルタイムで可視化することで、動かさないといけないという脳の緊張を解き、効率的で継続可能なリハビリテーションを実現。
事故による腕・脚
等の障害の場合
脳卒中等による
脳機能の障害の場合
脳卒中患者:
135万人
脳活動のリハビリテーションを応用することで、うつ病の意欲低下や、自閉症の社会性障害に対する機能回復を目指す。
筋萎縮性側索硬化症
(ALS)
患者:
8000人
脊椎損傷患者:
8万人
外骨格ロボット リアルタイム ロボットアーム制御
BMIリハビリテーション 精神疾患への応用
※BMI(Brain Machine Interface, ブレイン・マシン・インターフェース): 利用者が頭の中で考えた動作・意図を推定し、機械に伝える技術
4

霊長類モデル動物の普及体制の整備
○背景・概要: 精神・神経疾患の病態を解明するためには、げっ歯類であるマウス・ラットよりも、ヒトと比べて脳の構造・機能において近いマーモセットを使用することが有効であり、これまで疾患モデルマーモセットの作製に取り組んできたところ。 我が国では、世界に先がけ遺伝子改変マーモセットによる疾患モデル霊長類の作製に成功しており、これらはヒトに近い種であることや、長期間の疾病状況が観察できることから、脳科学研究のみならず、創薬研究を飛躍的に推進することができる。
この疾患モデル霊長類の国内研究者への供給体制の整備と、そのために必要となる技術等の高度化・効率化の開発を行う。なお、既に製薬会社等との共同研究について調整が行われている。
世界初
中核拠点 ・霊長類の発生工学等について技術開発
・疾患モデルマーモセットの作出・繁殖
遺伝子改変マーモセット
の作製・繁殖・供給
創薬等
研究者
技術
移転
遺伝子改変マーモセット
の作製・繁殖
実験場所の提供
日本マーモセット研究会
供給
製薬会社、研究コミュニティのニーズ調査を行い、 社会的要請の高い疾患モデルを優先的に作出
共同研究
製薬会社等
霊長類 げっ歯類
薬剤 代謝
ヒトに近い代謝のため、ヒトでの薬物残留時間等の予測ができる。
異なることが多く、げっ歯類で効果があった化合物が、ヒトでは標的臓器に届かないこともある。
病原体応答・感染症
免疫系が近縁のため、インフルエンザウイルス等の感染に対し、ヒトに近い感受性を持つ。
ヒトに重篤な感染症ほど、応答が異なる。新型インフルエンザは感染しない。
遺伝子 高次脳機能に関連する遺伝子がヒトと同じく働いている。
大脳皮質の発達が少なく、ヒトと同じ遺伝子がない場合もある。
疾患モデル
ヒトと同じような緩やかな病気の進行が再現でき、症状を改善する薬の開発ができる。(生活習慣病、認知症等)
寿命が短いこともあり、進行の早い急性病態モデルとしては有効。
【霊長類とげっ歯類との創薬開発における比較】
ヒト 霊長類 げっ歯類
高次脳機能をつかさどる大脳新皮質が霊長類以降で発達。げっ歯類では対応部位がない事もある。
5

Z
社会に貢献する脳科学の実現を目指す
H20年度 H21年度 H22年度 H23年度 H24年度 H25年度 H26年度 H27年度 H30年度~
課題C(モデル動物開発)<拠点>
課題D(社会脳) <拠点>
課題E(生涯健康脳)<拠点>
課題F(健康脳)<拠点>
課題G(神経情報基盤)<拠点>
課題A(情報脳)<拠点> 脳の情報を計測し、脳機能をサポートすることで、身体機能を回復・補完する機械を開発
複雑かつ多階層な脳機能を解明するために、脳の多種類、多階層情報を集約化・体系化した技術基盤を構築
遺伝子導入技術や発生工学的研究手法等を開発し、ヒトの脳研究等に必要な独創性の高いモデル動物の開発等を推進
社会性障害(自閉症、統合失調症等)の解明・診断等に資する先導的研究
心身の健康を支える脳の機能、健康の範囲を逸脱するメカニズム等を「分子基盤と環境因子の相互作用」という視点で解明する
精神・神経疾患の発生の仕組みを明らかにし、診断・治療・予防法の開発につなげる
課題B(情報脳)<個別>(18課題) 課題B(情報脳)<個別>
脳の情報を計測し、脳機能をサポートすることで、身体機能を回復・補完する機械を開発 (継続6課題)
脳科学研究戦略推進プログラム
H28年度 H29年度
【新規課題:BMI技術】<拠点> BMI技術を用いた身体機能の代替・補完、リハビリテーション等の自立支援、精神・神経疾患等の克服に向けた研究開発
【新規課題:霊長類モデル】<拠点> 精神・神経疾患モデル(遺伝子改変マーモセット)の普及・供給体制の整備と必要な技術等の高度化・効率化
6
中間評価実施時期 事後評価実施時期

脳科学研究戦略推進プログラム体制図
7
脳プロ運営委員会 科学技術振興機構
研究振興支援業務室
課題D・E・F
プログラムディレクター
津本 忠治
課題E 課題E・F
プログラムオフィサー
柚﨑 通介
課題E・F プログラムオフィサー 加藤 忠史
課題F
課題G プログラムディレクター 三品 昌美
課題G プログラムオフィサー 田邊 勉
生命倫理
プログラムオフィサー
赤澤 智宏
生命倫理 プログラムオフィサー 加藤 忠史(兼)
生命倫理
プログラムディレクター
津本 忠治(兼)
課題D
課題G
課題D
プログラムオフィサー
吉田 明
生命倫理
脳プロ事務局
文部科学省研究振興局
ライフサイエンス課
新規課題
(霊長類モデル)
新規課題
(BMI技術) 新規課題(BMI技術/霊長類モデル)
プログラムオフィサー
赤澤 智宏(兼)
新規課題(BMI技術/霊長類モデル) プログラムディレクター 三品 昌美(兼)
平成25年度
公募予定
平成25年度
公募予定

脳科学研究戦略推進プログラムの取組
脳は、人間が人間らしく生きるための根幹をなす「心」の基盤であり、その研究
は、人文・社会科学と融合した新しい人間の科学を創出し、これまでの科学の枠
組みを変える可能性を秘めている科学的意義の高い取組。
現在の脳科学研究は、脳の発達障害・老化の制御や、精神・神経疾患の病因解明、
予防・治療法の開発を可能にするとともに、失われた身体機能の回復・補完を可
能とする技術開発等をもたらすことから、医療・福祉の向上に最も貢献できる研
究分野の一つであるとともに、記憶・学習のメカニズムや脳の感受性期(臨界
期)の解明等により、教育等における活用も期待されるなど社会的意義も大変高
い取組。
このような状況を踏まえ、文部科学省では、少子高齢化を迎える我が国の持続的
な発展に向けて、脳科学研究を戦略的に推進し成果を社会に還元することを目指
して、平成20年度より本プログラムを開始している。
目 的
8

課題A(情報脳) ブレイン・マシン・インターフェース(BMI)の開発 6.0 5.7 5.2 6.0 5.3 - 28.2
課題B(情報脳) BMI個別研究事業(6課題) 4.0 3.7 2.8 1.2 0.9 - 12.6
課題C(モデル動物開発)※ 独創性の高いモデル動物の開発 5.7 6.6 5.3 5.6 5.3 - 28.5
課題D(社会脳) 社会的行動を支える脳基盤の計測・支援技術の開発
- 6.0 5.4 5.4 4.9 ※24.9 26.6
課題E(生涯健康脳) 心身の健康を維持する脳の分子基盤と環境因子
- - 4.6 4.8 4.2 3.9 17.5
課題F(健康脳) 精神・神経疾患の克服を目指す脳科学研究
- - - 8.1 8.0 8.8 24.9
課題G(神経情報基盤) 脳科学研究を支える集約的・体系的な情報基盤の構築
- - - 3.6 3.3 3.3 10.2
生命倫理等に関する課題の解決に関する研究 - - - 0.3 0.6 0.6 1.5
精神・神経疾患の克服のための研究基盤の整備に向けた課題の検討 - - - 0.2 0.2 - 0.4
新規課題 BMI技術を用いた自立支援、精神・神経疾患等の克服に向けた研究開発
- - - - - (公募予定) -
新規課題 霊長類モデル動物の普及体制の整備 - - - - - (公募予定) -
脳プロの運営事務(事務局) - - - - - 0.8 0.8
平成20年度 平成21年度 平成22年度 平成23年度 平成24年度 平成25年度
(4月当初) 合計
脳科学研究戦略推進プログラム (全体) 17.0 23.0 23.9 35.9 34.9 ※134.9 169.6
9
脳科学研究戦略推進プログラムの予算状況 (単位:億円)
※2 事務局経費を含む(~平成25年5月末)。 ※1 公募予定分があるため、合計しても全体額にはならない。




![脳科学研究科 一貫制博士課程 転入学 入学試験要項 …一貫制博士課程入学 Ó ð ± | þ ] ¢ B á Ë þ C ― ― 脳科学研究科 一貫制博士課程](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fe01c2b40f89343d1133f13/ecccc-eec-e-eeee-eec.jpg)