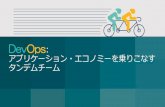エコノミー シリーズ - THK...21 エコノミーシリーズ Economy Series Model:VLAST 軽量スライダタイプ VLACT 軽量シリンダタイプ エアシリンダの置き換えに最適
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの 考え方に関する一 … ·...
Transcript of 交通分野におけるシェアリング・エコノミーの 考え方に関する一 … ·...

は じ め に
近年,カーシェアリングビジネスのUberや世界各地の民宿仲介サイトAirbnbに代表される
ように,「シェアリング・エコノミー」(SharingEconomy)と称するシェアリング・ビジネス
活動が急速に展開している。交通分野においては,自動車,船舶,自転車,倉庫,ターミナルを
利用したシェアリング・ビジネスモデルが数多く現れ,既存の交通輸送モードや関連施設の利用
率の向上を図ると同時に,CtoC(1)方式によるオンデマンドサービスの提供が可能となるなど,
交通分野における革新的なサービスの提供方法を提案している。
一方,公式的なシェアリング・エコノミー活動に関する定義はない。言葉通りに「共有経済」,
あるいは「共有型経済」と訳すが,これはあまりにも広くて曖昧である。現状では交通分野にお
けるシェアリング・エコノミーの概念整理を始め,サービスの実施対象や目的など,これまで公
式的に定義されていないまま,ビジネスモデルだけが先行している現状である。
本稿は,今後交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動のさらなる活発化により,新た
な価値創造及び交通関連資産の有効活用を実現することを認識し,より厳密的な定義付け及びカ
テゴリー別のビジネスモデルの現状及び特徴,課題などの整理を試みる。
1.先行研究について
交通分野のシェアリング・エコノミー活動について,ここ数年で注目度が高まったものの,国
内の活動実績が少ないため,関連する調査研究はまだ少ないが,これまで限られた活動事例に対
し,そのビジネスモデルの運営及び課題の研究が進められ,例えば高橋(2017)は過疎地におけ
49
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの
考え方に関する一考察
TheStudyonConceptDefinition
ofSharingEconomyinTransportation
町 田 一 兵
IppeiMachida
(1) 不特定多数の個人間の取引(CtoC:ConsumertoConsumer)

る交通機関の採算性と交通需要の対応の両立の可能性にシェアリング・エコノミー活動の代表の
一つであるUberアプリの活用を検討した。山内(2015)はグローバル規模でビジネスを展開し
たカーシェアリング企業の事例を研究したなど,個別事例を中心に研究が進めてきた。
一方,交通分野全般におけるシェアリング・エコノミー活動の研究について,寺前(2016)は
シェアリング・エコノミーの論議の方向性,複数の輸送モード及び関連施設の利用や複数の海外
事例,今後の方向性を検討した。しかし,交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動の範
疇やその定義付けには触れていない。
今後,シェアリング・エコノミー活動に対する認知度の向上及びIoT(2)のさらなる発展により,
国内交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動が本格的に展開すると認識し,まず交通分
野におけるシェアリング・エコノミー活動の発生と展開の背景,その範疇及び定義付け,カテゴ
リー別のビジネスモデル特徴並びに今後の課題を整理する。
2.交通分野における二つのパラダイム・シフト
交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動の発生及び展開は二つのパラダイム・シフト
によるものである。
一つは交通産業における規制緩和によるパラダイム・シフトである。交通産業は,従来広域に
わたるネットワークサービスを提供するため,サービスの均一性の維持と遂行を重要視してきた。
山内(2014)によれば,交通産業は基本的に規模の経済に端を発する自然独占的性格を備えなが
ら,ネットワーク産業として経済活動に必要不可欠なサービスを提供するため,長年に新規参入
の制限や独占・寡占の維持を行ってきた。一方,自然独占は市場の失敗を意味し,その失敗を修
正するための公的介入が必要とする。独占を形成する過程での無駄な競争を避けるために,長年
事業免許を課しながら,結果的に成立した独占体が横暴を働かないように,料金・運賃規制を課
す。事業者は独占が保証される代わりに,行動が縛られる。
このような固定したメカニズムは既得権益者に有利に働き,新規参入の制限や料金・運賃の規
制などで交通サービスの硬直化や新サービス創出の妨げとなり,経済活動の対応に遅れが生じる。
1980年代から欧米発の規制緩和は,この固定したメカニズムを見直すことから開始した。主
な実施策として,既存の国有企業の民営化及び事業の参入規制の緩和,運賃設定の自由化などが
挙げられる。
例えば1993年に実施したイギリスの国有鉄道の分割民営化の主旨は共に国営による赤字の脱
却と運営の効率化を目指したものである。このような考え方は現在日本の一部の地方空港の民営
化に受け継がれている(3)。つまり,交通インフラの所有権と運営権の分離による効率的な運営を
『明大商学論叢』第100巻第2号50 (146)
(2) InternetofThings,IT関連機器が接続されていたインターネットにそれ以外の様々なモノを接続し,
連動する仕組みである。
(3) 日本経済新聞2017年7月1日

目指すことである。
また,ほぼ同時期にアメリカ発世界を席巻した航空及び道路自動車輸送関連の規制緩和の目的
は,既存の硬直なサービス供給構造を変えるため,新規事業者の参入の促進及び運賃の自由化を
目指すものである。ただし,ほぼ30年近く経った現在,一巡した規制緩和策の実施結果と当初
期待した効果について,賛否両論が存在する。
本文は規制緩和の有効性については論じないが,1980年代に始まったグローバル範囲におけ
る交通分野の規制緩和は需給調整の廃止,新規参入の促進及び運賃の自由化の推進は間違いなく
従来の交通パラダイムを大きく変え,例えば自動車産業(最低車両保有台数の低減,営業区域の
廃止など),航空産業(新規参入の認可,運賃認可制から事前届出制など),内航輸送産業(需
給調整の撤廃など)など,交通産業における新規事業者の参入及び運賃設定の自由化を促進した。
さらに,規制緩和の流れは一部の交通分野における「構造分離」と「産業融合」を促進した。
堀(2015)によれば,構造分離とは「本来一体的に運営・管理されるべき事業構造,事業組織を,
その所有ないし支配関係を分離・分割して運営・管理すること」であり,産業融合とは「従来異
なる産業に分類されていた複数の産業が技術革新や規制緩和によって相互参入が容易となって双
方の産業が競争関係に立つ現象」である。
構造分離及び産業融合が進むことにつれ,サービスを同一主体による提供から,複数の主体に
よる水平分業的提供へと変わる(4)。例えば空港・港湾産業,ターミナル産業,倉庫産業,鉄道産
業などにおける一体的運営・管理から分離・分割が進み,同業他社あるいは異なる産業(5)によ
る運営や新規参入がみられた。
総じて,規制緩和より,大半の交通分野において,事業者の新規参入及び運賃設定の自由化が
促進され,今日の交通サービスにおけるシェアリング・エコノミー活動遂行のきっかけとなった。
もう一つのパラダイム・シフトは交通分野における情報の流れの役割の変化である。生田
(1981)によれば,交通の研究対象は古くから人の流れ,物の流れ,情報の流れで構成されてい
るが,それまで,交通関連の情報の流れは主に人の流れや物の流れに付随し,人流及び物流の円
滑化を果たすための補助的役割と認識してきた。
しかし,インターネットアクセスの一般化及び迅速化,IT機器の性能向上及び個人による情
報端末の普及により,情報の流れにpeertopeer方式が浸透し,情報の流れは人の流れ,物の
流れを主導するようになっている。それにより,交通サービスの提供はそれまで主にBtoB方式
から,BtoC,さらにCtoC方式まで対応できるようになり,シェアリング・エコノミー活動を
普及させる礎となる。
なお,本文では交通におけるBtoC方式について,事業者と個人の間におけるダイレクト―な
サービスの供給と消費と認識する。たとえば代理店経由の個人ないし団体の交通サービスの手配
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの考え方に関する一考察 51(147)
(4) 堀(2015)
(5) オリックスによる関西・伊丹,神戸空港の運営やダイワハウス工業による倉庫の整備・運営などが産
業融合の事例と考える。

や支払手続きをオンラインシステムの普及により,個人の直接予約や支払に切り替わったこと,
または宅配サービスのように,企業が個人に提供する物流サービスなど,BtoC方式の実現によっ
て可能となったのは個人単位での「オンデマンド交通」の提供である。
鈴木(2012)によれば,オンデマンド交通とは「利用者の要求(デマンド)を満たすようにフ
レキシブルに運行するシステム」つまり,利用者の異なる需要に合わせたサービス提供の仕組み
である。日本では過疎地におけるバス・タクシーなどの公共交通の運営維持に伴う業務の合理化
及び赤字の縮小に積極的に導入された事例が多くみられるが,中国では2017年にインターネッ
トで需要を募り,一定人数を達した場合には特別列車を出す「オンデマンドトレイン」(6)も運行
したなど,様々な輸送モードにおける個人単位の需要に基づくサービスの提供が現れる。
そして,近年のシェアリング・エコノミー活動の大きな特徴はCtoC方式の浸透である。ベー
スはpeertopeer情報プラットフォームであり,既存の交通インフラや関連施設はプラットフォー
ムの一部となって活用されつつ,新たな人・物の流れを創出する。
このような動きはIoT概念の浸透・強化によって,一層強まると認識し,かつての交通インフ
ラ/設備をベースとする交通サービスの提供から情報駆動型交通活動(Information-driven
TransportationActivity)による交通サービスの提供にシフトする。Uberによるカーシェア
リングビジネスモデルはシェアリング・エコノミー活動の代表例と言えよう。
情報流の発達が交通関連活動の主導的な役割を発揮するようになり,BtoB方式もさることな
がら,BtoC,CtoC方式による個人単位での「オンデマンド交通」サービスの提供が可能となり,
シェアリング・エコノミー活動の急拡大に繋がった。
3.シェアリング・エコノミー活動の定義付け
公式的なシェアリング・エコノミー活動に関する定義はない。言葉通りに「共有経済」,ある
いは「共有型経済」と訳すが,あまりにも広くて曖昧であるため,より厳密な定義が必要とする。
コトバンクは(7),シェアリング・エコノミー活動を「物・サービス・場所などを,多くの人
と共有・交換して利用する社会的な仕組み」とし,株式会社DeNAの原田氏は(8)「社会の中に
ある遊休資産,リソースを有効活用することで新しい価値を生むもの」と定義している。
また,PWCは(9),「個人および集団が,活用度の低い資産から収入を得られる仕組み。この方
法では,現物資産がサービスとして共有される」。根来(2017)は「使われていない資産や使わ
れていない能力・時間を一時的に市場化する『個人間の取引のマッチングサービス』」と定義し
ている。
『明大商学論叢』第100巻第2号52 (148)
(6) http://society.people.com.cn/n1/2017/1010/c1008-29577363.html,2017年10月13日取得
(7) https://kotobank.jp/word,2017年10月5日取得
(8) http://logmi.jp/82475,2017年10月5日取得
(9) PWCJapan,2017年10月5日取得

さらに,内閣官房情報通信技術(IT)総合戦略室は,「既存のリソース(遊休資産や個人の余っ
た時間等)を効率的に活用するためのIT利活用技術の発展成果であると同時に,従来型のサー
ビスのように本業として資本を投下した者が提供するサービス(BtoC)とは異なり,インター
ネット上のマッチングプラットフォームを通じた,不特定多数の個人間の取引(CtoC)や本業
として追加資本を投下していない者によるサービス提供を基本としたものである」と定義してい
る。
その他,アスペンインスティテュートは(10)シェアリング・エコノミー活動に関する公式定義
がないとした上,「テクノロジーによるプラットフォームをベースに,多様でダイナミックなセ
クターの集合を横断し,個々の間における品物,資材,サービスの機能的交換促進するもの」と
定義付けている。
上記諸々な定義はそれぞれの個人あるいは組織の立場やビジネスコンセプトによるシェアリン
グ・エコノミー活動に対する認識を描いた結果と言えよう。個々の記述にはかなり異なっている
ものの,共通する部分を抽出してみると,「シェアリング・エコノミー」という活動の特徴は以
下のキーワードによって描かれている。
「新たな価値創造」,「有効活用」,「開放型」,「社会的仕組み」,「テクノロジー」,「プラットフォー
ム」,「個人」,「集団」,「有償」,「品物」,「資材」,「サービス」,「共有・交換」「仕組み」
上記のキーワードをベースに,諸々の定義を参考したうえ,シェアリング・エコノミー活動を
定義付けると,シェアリング・エコノミー活動とは「所有を前提とせず,新たな価値創造及び資
産の有効活用を目的に,開放型社会的仕組みとして,テクノロジーによるプラットフォームをベー
スに,個人あるいは集団による提供及び利用を通じて,有償的に品物,資材,サービスを共有・
交換を行う生産活動あるいはそれを展開する仕組みである」。
その際,問題となるのはシェアリング・エコノミー活動の利用及び実施対象をCtoCに限定す
べきか否かである。確かに近年におけるUberやAirbnbなど,シェアリング・エコノミービジ
ネスの代表格ともいえる事業者はCtoC方式の展開で注目を浴びている。
しかし,改めてシェアリング・エコノミー活動の目的が「新たな価値創造及び資産の有効活用」
であることを考えた場合,事業者であっても,個人単位であっても,その目的に反することでは
ない。
したがって,上記定義における「集団」を「事業者」と解釈し,近年におけるシェアリング・
エコノミー活動の利用及び実施対象はCtoC方式を中心に取り上げているものの,本文がその活
動の目的を「新たな価値創造及び資産の有効活用」に注目し,当該活動の対象範囲をCtoCのみ
ならず,BtoB,BtoC方式も含むと認識する。
上記の定義に基づき,交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動の定義を置き換えてみ
ると,交通におけるシェアリング・エコノミー活動の定義は「各輸送モードや交通関連施設の所
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの考え方に関する一考察 53(149)
(10) https://assets.aspeninstitute.org,2017年10月5日取得

有を前提とせず,新たな交通分野における価値創造及び交通関連資産の有効活用を目的に,開放
型社会的仕組みとして,テクノロジーによるプラットフォームをベースに,個人あるいは事業者
による提供及び利用を通じて,有償的に各輸送モード及び関連交通施設の共有/利用を行う活動
あるいはそれを展開する仕組み」とする。
4.交通分野のシェアリング・エコノミー活動のビジネスモデル及び特徴
上記の交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動の定義を踏まえ,交通分野のカテゴリー
別に展開している事例を取り上げ,そのビジネスモデル及び特徴について検討する。なお,「民
宿」を交通分野のカテゴリーで取り上げることは一般的ではないが,シェアリング・エコノミー
活動で現在交通分野の研究対象である観光産業に大きく影響を与えているため,取り上げること
とする。
4�1 航空産業
航空産業は,高い産業集約度及び高度な専門技術,高い投資額が必要とし,しかも安全性の保
持を中心とする厳しい規制が敷かれていることを背景に,新規参入は難しく,シェアリング・エコ
ノミー活動が展開し難い分野と認識してきたが,CtoC分野において,米国企業「JetSmarter」(11)
はプライベートチャーター機の利用率の低さに注目し,定額制サービスの導入によるプライベー
トジェットの乗り放題というユニークなビジネスモデルを構築した。
特徴として,「JetSmarter」の専用アプリをダウンロードし,会員登録(12)を含むサービスの利
用はすべてネット上で完結するなど,従来の煩雑な手続きが不要となる。
また,サービスの提供において,自社によるジェット機を保有せず,3,000超のプライベート
ジェットと連携することで,ビジネスや観光旅行のハブであるニューヨーク,シカゴ,フォート
ローダーデール,ラスベガス,アトランタ,ロンドン,パリ,モスクワ,ドバイ,ミラノなど,
需要が高い50都市をベースに,煩雑な事前利用申請を省くうえ,通常の航空会社が飛ばない空
港に行くことも可能とし,早くて快適に移動できることで急成長している。
なお,JetSmarterはジェットを所有しない代わりに,自社でパイロットを雇い,ジェットの
オーナー,オペレーター,キャリアと共同でジェットの管理と整備を行うことで,規制の多い航
空業界のコンプライアンスに対応している。
一方,航空産業で情報プラットフォームによるBtoB,BtoC方式のシェアリング・エコノミー
のビジネスモデルはまだ見当たらない。
『明大商学論叢』第100巻第2号54 (150)
(11) https://japan.cnet.com/article/35081574/及びhttps://jetsmarter.com/を参照に。
(12)「コア・メンバーシップ」として初年度に1万5,000ドルを支払う必要がある。

4�2 鉄道産業
鉄道輸送はヒトとモノを一方向への大量輸送,しかも中長距離の輸送に長ける輸送モードであ
るため,CtoC方式の利用は難しい。BtoB方式についても,鉄道によるモノの輸送は一部の大
口荷主に限られるため,シェアリング・エコノミー方式による新規ニーズがあまり見込まれず,
ヒトの鉄道輸送も新規ニーズが期待し難い。
現状ではBtoC方式の試みとして,2017年10月,中国の国慶節に伴う長期休暇が終了後,鉄
道による帰省者の大量移動需要が高いと見込み,西安鉄道局がオンラインチケット販売システム
を通じて,特別列車編成の需要を募り,一定人数に達した後,運行ダイヤにない「オンデマンド
トレイン」を運行したことがそれにあたると認識する。
4�3 船舶産業
海運産業は,航空産業に劣らぬ高い専門技術及び投資額を必要とし,近年の技術進歩及び環境
規制の強化により,一隻当たりの積載容量が大きいため,BtoC方式による利用は難しい。
ただ,小型レジャーボートにおけるCtoC方式の利用はすでに行われている。プレジャーボー
トのシェアリング・ビジネスモデルを立ち上げたankaa社は(13),プレジャーボートを最も保有
する広島県を中心に,瀬戸内海における法人もしくは個人が保有するプレジャーボートを利用し
たいユーザーとマッチングさせるシェアリング・エコノミービジネスモデルを樹立した。
特徴として,ankaa社が運営するサイトに会員登録や船舶の登録を済ませた後,ユーザーが
自分の需要に合わせて船舶や利用日を決め,成立した場合,ユーザーがプラットフォーム手数料
やP2P保険料を一部負担し,ボートオーナーも利用料と操船補助費用等の一部を負担する仕組
みである。
また,ボート免許を持つユーザーと持たないユーザーに対し,操縦付きと船舶本体のみ両方の
利用メニューを提供し,ニーズに応じた手軽なレジャーボートの利用サービスを提供する。
なお,サービス品質の維持に関し,プラットフォームの運営会社として,Ankaa社は自社社
員による情報システムの開発及びメンテナンスを行う以外,登録された船舶の確認及び船舶査定,
船体,船内の写真撮影や装備品確認等の業務をボート操縦免許保有の専門家に外部委託で行って
いる。
なお,BtoB方式による利用は,従来複数の船会社による定期航路の共同運行やベトナムの
「IZIFIX」情報プラットフォーム上での船舶と貨物のマッチングビジネスがそれに属する(14)。
4�4 パイプライン産業
パイプライン産業には設置地域の制限もありながら,輸送する貨物はガス・石油など,ごく一
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの考え方に関する一考察 55(151)
(13) https://ankaa.jp/を参考にまとめた。
(14) https://vitalify.jp/app-lab/20170601-vietnam-sharing-economy/,2017年10月5日取得

部に限られるため,これまでシェアリング・エコノミー活動の事例はまだ見当たらない。
4�5 自動車産業
自動車産業で有名な事例はUberのカーシェアリングビジネスである。Uber社のビジネスの
成功により,CtoC方式によるシェアリング・エコノミー活動がグローバル的に注目されるよう
になったといっても過言ではない。
特徴として,Uber社のスマホアプリに車を所有する個人ドライバーと利用客が両方登録し,
利用する場合,登録した乗客が乗車場所と目的地を入力し,GPS機能によって近くにある車に
乗ることができ,しかもドライバーに目的地の指示や金銭授受が車内で発生しない。登録ドライ
バーは,空いている時間やお小遣い稼ぎによるメリットがある。
トラブル防止措置として,ドライバーの身分登録が必須,また,利用客とドライバーは乗車後
に相互評価する仕組みになっており,他の利用客はその相互評価をみて利用することが可能であ
る。
一方,BtoB方式による利用事例として,公益社団法人全日本トラック協会が開発し,日本貨
物運送協同組合連合会が運営しているWebKIT事業がある(15)。協会が運営している情報プラッ
トフォームにおいて,荷主の需要と中小トラック事業者の「帰り便の荷物の確保」や「融通配車」,
あるいは積載効率を高めるための「積合輸送」をマッチングする役割を果たす。なお,システム
を利用するには,有料会員となることを前提に,ビジネスの成立ごとに手数料及び月々のID利
用料が発生する。
また,BtoC方式の事例として,「オンデマンド交通」方式を取り入れた静岡県沼津市の乗合
タクシー事業を取り上げる。沼津市の委託より,集落から他の地区や沼津駅,市立病院まで繋ぐ
「生活の足」の確保として,地元の戸田交通株式会社が一日6回の頻度で一般タクシー車両によ
る運行ルートに予約があった便だけを運行するサービスを提供している。過疎地における交通サー
ビスを維持するための赤字削減及び効率化を両立するための方策である。
4�6 自転車産業
自転車によるシェアリング・エコノミー活動は世界で最も普及しているシェアリング・エコノ
ミー活動の一つと言えよう。一方,他の輸送モードにおけるビジネスモデルは主に資産の有効活
用を目的とするのに対し,そのビジネスモデルの狙いは主に交通分野における新たな価値創造で
ある。
かつて大都市や観光地において,レンタル・バイク・サービスが古くから存在する。しかし,
今日の大都市交通混雑の軽減及び環境の配慮,健康及びリクリエーションの視点から,自転車に
よるシェアリング・エコノミー活動はそれまでない価値を提供している。
『明大商学論叢』第100巻第2号56 (152)
(15) https://www.nikka-net.or.jp/business/webkit/によるまとめ。

これまで国を問わず,多くの都市で自転車によるシェアリング・エコノミー活動が検討・実施
されている。2017年6月に米国ハワイ州のホノルル市に導入された「BIKI」自転車シェアリン
グ・システムシステムがその代表例である。
ホノルル市にはハワイ州人口の7割弱(2015年)が集中し,狭いエリアに多くの政府機関や
商業施設など,高層ビルが林立し,しかも自家用車の発達と相まって,交通混雑が年々厳しくなっ
ている。現在州最大のショッピングモールを持つアラモアナ周辺の高層住宅群の建設が進められ,
完了した後,ホノルル市の交通混雑状況が一層悪化するに見込む。
そのため,2017年6月にホノルル市が最初の公共バイク・シェアリング・プログラム(Hono-
lulu・sfirstpublicbikeshareprogram)(16)として,シェアリング・バイク・システムの導入を
決定した。ハワイ州及びホノルル市,複数のファンドなどによる財政的支援(17)を受けながら,
非営利団体BikeshareHawaiiによって運営されている。
特徴は情報アプリの操作による24時間のサービス提供である。自転車の貸し返しはすべてア
プリとバイクステーションで利用者が行い,利用目的による多様な料金プラン(一回のみ利用,
FREESPIRIT(300分間を減算式),月利用(30/60分内の利用,回数制限なし))の提供,予
め登録したクレジットカードによる自動決済など,従来のレンタル・バイク・サービスとの違い
を打ち出している。
ホノルル市の中心街にバイクステーションを集中的に(100カ所)設置したことで利便性を向
上させ,観光客のみならず,現地のビジネス人のダウンタウンでの短距離移動の利用も狙う。
一方,自転車によるシェアリング・エコノミー活動は主に個人を対象にすることから,BtoB
方式による利用はあまり考えられず,それに対し,CtoC方式のバイクシェアリングシステムの
事例はあまり見当たらないが,一般的に個人及び家庭における自転車の普及状況及び自転車の潜
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの考え方に関する一考察 57(153)
図表1 レンタル・バイクとBIKIシステムとのビジネス特徴の違い
レンタル・バイク BIKI ビジネス特徴
○ ○ バイクの一時貸し出しサービス
× ○ アプリによるサービス供給,人による対応を最小限に
× ○ 異なる利用による多様な料金設定(一回限りの利用,定期パスによる利用など)
× ○ 繁華街だけに集中した拠点設置(BIKIの場合,ホノルル市の中心街のみ)
× ○ 高密度な設置(BIKIの場合100カ所)
× ○ すべての拠点でのバイクの貸し返しが可能
× ○ 予め登録したクレジットによる決済
× ○ 24時間利用可能
出所:筆者が新聞及びヒアリングによるまとめ
(16) https://www.bizjournals.com/pacific/news/2017/03/02/bikeshare-hawaii-names-secure-bike-
share-financing.htmlを参考にまとめた。
(17) 州政府による設備の設置費用の補助などは一回のみ,開業後の運営やメンテナンスには一切関与しない。

在的利用者の多さを考え,今後何らかのビジネスモデルによる展開は考える。
4�7 空港・港湾
各輸送モードの有効利用及び新しい価値の創造による移動の利便さの向上と違って,固定した
交通施設におけるシェアリング・エコノミー活動は主に土地あるいは空間の活用である。一方,
場所の利用は排他性があることから,シェアリング・エコノミー活動の目的は主に使いたいとき
に利用可能な空間を効率的に提供することである。
ただし,空港・港湾におけるCtoC方式の利用は現実的に難しい。また,空港・港湾のセキュ
リティの課題や構造上の問題から,他の方式によるシェアリング・エコノミー活動の展開も限定
的であると認識する。
4�8 倉庫・ターミナル/駅
それに対し,利用可能な空間を効率的に提供することを目的に,倉庫・ターミナル/駅におけ
るシェアリング・エコノミー活動の展開は多岐にわたる。
CtoC方式の一例は株式会社セームページがインバウンド観光客の手ぶら観光のために提供す
るユニークなサービスが挙げられる。サービス「Tebura」(18)と名付けられ,観光客などが一時
荷物預かり場所を探し,しかもスペースが予約できるサービスである。その場合,営業前のレス
トランや空き店舗など,あらゆる空スペースが対象となり,既存施設の「新しい価値創造」及び
「資産の有効活用」となる。
ほぼ同じコンセプトでmonooQ社(19)は使っていない倉庫,余ったクロークなどをトランクルー
ムとして,個人間取引で長期にモノを保管するトランクルームのシェアリングサービスを展開し
ている。
他方,BtoB,BtoC方式の利用について,倉庫情報ポータルサイト「e�sohko.com(イーソー
コドットコム)」(20)は,倉庫や物流施設を貸す側と借りる側(個人を含む)を結ぶビジネスモデ
ルが挙げられる。
4�9 民 宿
他の交通関連施設と違って,民宿におけるシェアリング・エコノミー活動は基本的にBtoC,
CtoC方式で行われる。そのビジネスモデルの樹立はシェアリング・エコノミー活動を普及した
きっかけの一つであり,当該分野で最も成功した事例の一つといえよう。その代表的なサービス
提供者は「Airbnb」である。
「Airbnb」はサンフランシスコに本社を置くAirbnb,Inc.によって運営される宿泊施設・民
『明大商学論叢』第100巻第2号58 (154)
(18) https://tebura.ninja/ja/home-jp/を参考にまとめた。
(19) http://jp.techcrunch.com/2017/03/03/cloak-sharing-monooq-launch/を参考にまとめた。
(20) http://jp.techcrunch.com/2017/03/03/cloak-sharing-monooq-launch/,2017年10月5日取得

宿を貸し出す人向けのウェブサイト,現在世界191ヶ国65,000以上の都市でサービスを提供し
ている(21)。
「Airbnb」のビジネスモデルは,ホストとゲストが共同で利用するプラットフォームを運営し,
そこで相互のニーズのマッチングを行い,さらに代金決済を行う方式である。その際,「Airbnb」
はホストとゲストから紹介手数料及びシステム利用手数料を徴収する手法を取っている。
綜合して,上記の交通分野におけるシェアリング・エコノミービジネス活動のビジネスモデル
から,従来の交通サービスと異なり,シェアリング・エコノミー活動が提供するサービスは以下
の特徴が取り上げられる。
1.情報プラットフォームによるサービスの利用
2.低コストでリアルタイムな需要マッチング及び代金決済
3.サービスを実施側/受ける側に対する評価の可視化
4.実施側/受ける側の情報公開による高いサービス信頼度
5.オンデマンドに基づくサービスの提供
5.交通分野のシェアリング・エコノミー活動の課題
上述のように,ビジネスモデルの樹立により,交通分野におけるシェアリング・エコノミー活
動は年々拡大する傾向にある。一方,カテゴリー別に活動展開の難易度が存在する。また,展開
する際に既存の法規制との調整,人流による利用と物流の違いなど,検討すべき課題は多く残る。
5�1 カテゴリー別のバラツキ
現状では交通各分野におけるシェアリング・エコノミー活動の展開にバラツキがある。カテゴ
リー別の産業特徴やサービス利用者側の状況を鑑み,それぞれのシェアリング・エコノミー活動
の展開を下表にまとめた。
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの考え方に関する一考察 59(155)
(21) https://www.airbnb.jp/about/about-usによる。2017年10月5日取得
図表2 カテゴリー別交通分野のシェアリング・エコノミー活動の特徴一覧表
カテゴリー
項目航空 鉄道 船舶
パイプ
ライン自動車 自転車 空港 港湾
倉庫・タ
ーミナル/駅民宿
産業的特徴
産業集約の度合 高 高 やや高 高 低 低 やや高 やや高 普通 低
ビジネスに必要な投資 高 高 やや高 高 やや低 低 高 高 やや高 低
高度な専門技術の必要性 高 高 やや高 やや高 やや低 低 高 高 普通 低
新規参入の難易度 高 高 やや高 高 低 低 高 高 普通 低
サービス
利用者側
サービス利用の条件 高 高 やや高 高 低 低 高 高 普通 低
一回当たりの利用コスト やや高 高 中 高 やや低 低 高 高 普通 低
CtoCビジネスモデル 有 無 有 無 有 有 無 無 有 有
法整備の課題 有 有 有 有 有 無 有 有 有 有
出所:筆者まとめ

また,一覧表に基づき,下記基準に基づく指数化を試みる。ただし,指数化の判断基準は筆者
の主観的な認識によるものである。
上記のシェアリング・エコノミー活動及び指数化一覧表により,カテゴリー別交通産業におけ
るシェアリング・エコノミー活動の展開は以下の特徴がみられる。
高い産業集約度/投資額/専門技術,難しい新規参入の交通産業であるほど,シェアリング・
エコノミーの展開は難しく,低いほど展開し易い。
また,サービス利用者側においても,「サービス利用条件」,「一回当たりの利用コスト」が高
い交通産業であるほど,シェアリング・エコノミーの展開は難しく,低いほど展開し易い。
同じく,シェアリング・エコノミー活動の特徴の一つであるCtoC方式の展開についても,下
表のように,カテゴリーごとに展開の難易度が存在し,交通産業全般における展開は難しい。
『明大商学論叢』第100巻第2号60 (156)
図表3 カテゴリー別交通分野のシェアリング・エコノミー活動の評価基準
評価
項目1 2 3 4 5
産業集約の度合 低 やや低 普通 やや高 高
ビジネスに必要な投資 低 やや低 普通 やや高 高
高度な専門技術の必要性 低 やや低 普通 やや高 高
サービス利用の条件 低 やや低 普通 やや高 高
一回当たりの利用コスト 低 やや低 普通 やや高 高
新規参入の難易度 低 やや低 普通 やや高 高
CtoCビジネスモデル 有 無
法整備の課題 無 有
出所:筆者まとめ
図表4 カテゴリー別交通分野のシェアリング・エコノミー活動の特徴の指数化一覧
カテゴリー
項目航空 鉄道 船舶
パイプ
ライン自動車 自転車 空港 港湾
倉庫・ター
ミナル/駅民宿
産業的特徴
産業集約の度合 5 5 4 5 1 1 4 4 3 1
ビジネスに必要な投資 5 5 4 5 2 1 5 5 4 1
高度な専門技術の必要性 5 5 4 4 2 1 5 5 3 1
新規参入の難易度 5 5 4 5 2 1 5 5 3 1
サービス
利用者側
サービス利用の条件 5 5 4 5 2 1 5 5 3 1
一回当たりの利用コスト 4 5 3 5 2 1 5 5 3 1
CtoCビジネスモデル 1 2 1 2 1 1 2 2 1 1
法整備の課題 2 2 2 2 2 1 2 2 2 2
合計指数 32 34 26 33 14 8 33 33 22 9
出所:筆者まとめ

5�2 法規制の課題
シェアリング・エコノミー活動に対応する法規制の枠組みの再検討を各交通分野で行われてい
るが,既存事業の反対,安全性の保持,責任所在の明確化などの未解決課題による利用制約が存
在する。国内外の事例を検討しながら,既存法規制との調整が重要となる。
5�3 人流と物流の相違
ヒトの利用を対象とするシェアリング・エコノミー活動はモノの利用を対象とする活動よりも
比較的に成立し易い。ヒトの利用を対象とする場合,主に空間(泊まる場所)と移動(輸送モー
ド)の要素が整えれば良いだが,モノを対象とするビジネスモデルは空間と移動以外,モノの搬
入/出作業・保管場所,温度・振度への対応など,より多くの課題を解決しなければならない。
ま と め
本文は交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動が本格的にスタートすることを念頭に,
交通分野におけるシェアリング・エコノミー活動定義付け,ビジネスモデルの特徴並びに課題を
整理した。
検討すべき課題がまだ多く残るものの,寺前(2016)は「新しいサービスの登場は,既存事業
者の新しいニーズへの対応ができていないことが背景にある」と指摘したように,交通領域にお
けるシェアリング・エコノミー活動は,各カテゴリーの交通産業に既存のサービスに対する見直
しを促進すると同時に,情報駆動型交通活動として,新たなサービスの提供による価値創造及び
交通関連資産の有効活用を模索する方策となる。
一方,本稿ではBtoB,BtoC方式によるシェアリング・エコノミー活動の展開を認識しつつも,
そのビジネスモデルの展開は更なる検討を行うべきと認識し,また,ベースとなる情報プラット
フォームの運営方法や属性についても,今後検討を重ねたいと認識する。
高橋愛典・野木秀康・酒井裕規(2017)「京丹後市の道路公共交通政策」近畿大学商経学叢第63巻第3号
伊達貴彦(2016)「新常態米国のシェアリング・エコノミー」三井物産戦略研究所レポート
交通分野におけるシェアリング・エコノミーの考え方に関する一考察 61(157)
参考文献
図表5 方式別にシェアリング・エコノミー活動の展開状況
カテゴリー
方式航空 鉄道 船舶
パイプ
ライン自動車 自転車 空港 港湾
倉庫・ター
ミナル/駅民宿
BtoB △ × ○ × ○ × △ △ ○ ×
BtoC △ △ △ × ○ ○ △ △ ○ ○
CtoC ○ × ○ × ○ ○ × × ○ ○
出所:筆者まとめ

山内昌斗(2015)「カーシェアリングビジネスにおける共通価値の創造」広島経済大学経済研究論集第38
巻第3号
寺前秀一(2016)「シェアリング・エコノミー論議の方向性 貸切と乗合の相対化 」横浜市立大学
論叢,人文科学系列第68巻第1号
庄司昌彦・川崎のぞみ(2016)「シェアリングエコノミー育成は「大都市のシェアリングティ化」から」
GLOCOMOPINIONPAPER.No7
根来龍之(2017)「シェアリングエコノミーの本質と成功原理」NextoomVol.302017Summer
鈴木文彦(2012)「地方におけるオンデマンド交通の可能性と課題」オペレーションズ・リサーチ第57巻
第3号
堀雅通(2015)「「構造分離」と「産業融合」に関する一考察」福岡大学商学論叢,No60(1�2)
大橋知佳(2016)「古くて新しい�シェアリング・エコノミー」日経研月報10月号
PWC(2016)「シェアリングエコノミー」コンシューマーインテリジェンスシリーズ
総務省(平成27年版)「情報通信白書」
山内弘隆(2014)「新しい社会的要請に応える交通事業」運輸と経済第74巻第4号
柳川隆,播磨谷浩三,吉野一郎(2008)「イギリス旅客鉄道における規制と効率性」神戸大学経済学研究』
第54巻
生田保夫(1981)「交通サービスの性質」流通經濟大學論集第15巻第3号
小倉昌男(1999)「小倉昌男経営学」,日経BP社
鈴木文彦(2012)「地方におけるオンデマンド交通の可能性と課題」オペレーションズ・リサーチ誌57巻
3号
KurtMatzler,ViktoriaVeider,WolfgangKathan,AdaptingtotheSharingEconomy,WINTER2015,
MITSloan,Managementreview.
TheAspenInstituteEconomicOpportunitiesProgram,TheFutureofWorkintheSharingEcon-
omy,December2,2014
『明大商学論叢』第100巻第2号62 (158)