歴史的にコンティンジェントな過程としての場所 - Osaka City ...―Paul Vidal de la Blache 歴史は人間のプロジェクトの成果を抜きにして理解でき
高等学校「日本史B」における 歴史資料の扱いについて€¦ ·...
Transcript of 高等学校「日本史B」における 歴史資料の扱いについて€¦ ·...

- 3 -
論文
高等学校「日本史B」における
歴史資料の扱いについて
―平成11(1999)年版高等学校学習指導要領地理歴史科
「日本史B」における「歴史と資料」の扱い―
児 玉 祥 一
(同志社大学免許資格課程センター准教授/
京都教育大学大学院教職実践研究科准教授)
Analyzing the contents of “History and Historical materials” in the
high school text of “Japanese history B”: Analyzed history textbooks
of “History and Historical materials” currently being used.
Shoichi Kodama
Summary
“History and Historical materials”, has been prescribed as the
high school course of study geography and history for senior high
school since 1999. After analyzing the contents of “History and
Historical materials” and also looking at the contents of all history
textbooks currently being used today, I found that there are three
major points that should be present in order for a history textbook
to be effective.
1. Is the alignment of historical events correct and appropriate for
an introductory text?
2. Does it reflect the trend of history?
3. Is the content easy enough for both students and teachers?
It turned out to be sufficient in 2, but insufficient in 1 and 3 as a
result. I put forward concrete ideas for the betterment of the
following. A textbook should expound the meaning and classification
of historical records and use a concrete example that history will be
described by records as an introduction. At the same time it should
include the description that draws students’ mind to something to
do with a textbook content.
In addition it should contain some questions so that students can
delve into the area.

- 4 -
1 はじめに
平成21(2009)年に新しい高等学校学習指導要領が告示された。地理歴史
科「日本史B」の「内容」において「歴史における資料の特性とその活用及
び文化財保護の意義について理解させる」ことを目的とし、かつ「日本史学
習に対する関心を高めるとともに、歴史の学習の基礎的な認識を深めること
をねらい」として、平成11(1999)年の学習指導要領より新しく加わった歴
史の学び方の学習ともいえる「歴史と資料」の項目が引き続き「日本史B」
学習の導入として実施することが位置づけられている。
「歴史」をイギリスの歴史家E.H.カーの言葉を借りて「現在と過去との
間の尽きることを知らぬ対話」と定義すると、過去との「対話」のための手
段が「資(史)料」であり、高等学校段階での歴史学習の導入で「資料」に
ついて、同時にその資料そのものの意味も含めて学ぶことは重要だと考える。
また、ドイツの元大統領であるR.K.F.ヴァイツゼッカーの「過去に目
を閉ざす者は、未来に対してもやはり盲目となる」という言葉を考えたとき
に、「社会認識」教育としての歴史教育の意義を歴史学習の導入で生徒に伝
えることも大切であり、新しい学習指導要領においても、平成11年版で示さ
れた「歴史と資料」の学習が引き続き採用されたことは大きな意味を持つと
言える。
筆者は平成11(1999)年の高等学校学習指導要領改訂にともなって編纂さ
れた地理歴史科「日本史B」(平成16年発行 実教出版)の教科書編集と執
筆にかかわった。また、平成21(2009)年版高等学校学習指導要領に対応し
て編纂された「日本史B」(実教出版)、そして新たに「日本史A」(実教出版)
の教科書編集と執筆にもかかわっている。
本稿では、平成11年版学習指導要領の「内容」の「(1)歴史の考察」の
項目としておかれた「ア 歴史と資料」について、学習指導要領での位置づ
けを確認し、その後、現行の教科書ではどのような取り扱いとなっているの
か考察していくこととする。
考察の視点として、①「歴史と資料」は日本史学習の導入として歴史の学
び方の学習となっているのか、また、②歴史学の成果をどのような資料を利
用して説明しているのか、そして、③それらは教師・生徒にとって学習しや

- 5 -
すい内容になっているのかを発行された教科書の記述などより比較・分析を
おこなう。同時に、筆者のかかわった教科書の事例について、上記の視点を
ふまえて説明する。そして最後に、その上で新しい学習指導要領に対応する
「歴史と資料」の教科書記述のあり方について考えていくこととしたい。
2 高等学校学習指導要領地理歴史科「日本史B」における「歴
史と資料」
平成元(1989)年の学習指導要領より、高等学校社会は公民科と地理歴史
科に改編された。いわゆる「社会科解体」である。この改編で、日本史は歴
史地理科の科目として、近現代史を中心に学習する「日本史A」(標準2単位)
と従前の「日本史」を継承し、日本史を総合的な観点から学習する「日本史
B」(標準4単位)に再編された。以来、平成11(1999)年の改訂を経て、
平成21(2009)年に告示された学習指導要領においても日本史教育の基本方
針・目標については大きく変わっていない。
本節では、平成11(1999)年の学習指導要領地理歴史科「日本史B」の「内
容」として、新しく加わった歴史の学び方の学習ともいえる「歴史と資料」
について検討していくこととする。
平成元(1989)年版「内容」
(1)日本文化の黎明
(2)古代国家と古代文化の形成
(3)中世社会の成立と文化の展開
(4)幕藩体制の推移と文化の動向
(5)近代日本の形成とアジア
(6)両世界大戦と日本
(7)現代の世界と日本
(8)地域社会の歴史と文化

- 6 -
平成11(1999)年版学習指導要領「日本史B」の目標をみると「我が国の
歴史の展開を諸資料に基づき地理的条件や世界の歴史と関連付けて総合的に
考察させ、我が国の伝統と文化の特色についての認識を深めさせることによっ
て、歴史的思考力を培い、国際社会に主体的に生きる日本国民としての自覚
と資質を養う」となっている。平成元(1989)年版学習指導要領の目標と比
べて大きな変更はない。平成元年版で「我が国の歴史の展開を世界史的な視
野に立って」とあった記述が、平成11年版では「我が国の歴史の展開を諸資
料に基づき地理的条件や世界の歴史と関連付けて」となり、「諸資料に基づき」
と「地理的条件」の語が加わって書き換えられた点以外は同様の記述となっ
平成21(2009)年版「内容」
(1)原始・古代の日本と東アジア
ア 歴史と資料
イ 日本文化の黎明と古代国家の形成
ウ 古代国家の推移と社会変化
(2)中世の社会・文化と東アジア
ア 歴史の解釈
イ 中世国家の形成
ウ 中世社会の展開
(3)近世の日本と世界
ア 歴史の説明
イ 近世国家の形成
ウ 産業経済の発展と幕藩体制の変容
(4)近代日本の形成と世界
ア 明治維新と立憲体制の成立
イ 国際関係の推移と立憲国家の展開
ウ 近代産業の発展と近代文化
(5)両世界大戦期の日本と世界
ア 政党政治の発展と大衆社会の形成
イ 第一次世界大戦と日本の経済・社会
ウ 第二次世界大戦と日本
(6)第二次世界大戦後の日本と世界
ア 現代日本の政治と国際社会
イ 経済の発展と国民生活の変化
ウ 歴史の論述
平成11(1999)年版「内容」
(1)歴史の考察
ア 歴史と資料
(ア)資料をよむ
(イ)資料にふれる
イ 歴史の追究
(ア)日本人の生活と信仰
(イ)日本列島の地域的差異
(ウ)技術や情報の発達と教育の普及
(エ)世界の中の日本
(オ)法制の変化と社会
ウ 地域社会の歴史と文化
(2)原始・古代の社会・文化と東アジア
(3)中世の社会・文化と東アジア
(4)近世の社会・文化と国際関係
(5)近代日本の形成とアジア
(6)両世界大戦期の日本と世界
(7)第二次世界大戦後の日本と世界

- 7 -
ている。「日本史B」においては、従来通り「我が国の伝統と文化の特色に
ついての認識を深めさせる」学習の方針について変更はないのである。
しかし、内容構成には変化があった。前記の表からわかるように、平成元
年版までの「日本史B」における「内容」は「我が国の歴史の展開を」を「総
合的」に学習するため、我が国の歴史の展開についての理解を図るいわゆる
通史的な学習内容に対応する項目が配置されている。紙面の関係で「内容の
取扱い」までは表示できなかったが、平成元年版では「歴史的思考力を深め
させるため」に「適切な主題」を設けて行う主題学習など、歴史的な見方・
考え方を培う学習に関する観点や方法については、「内容の取扱い」の項目
としておかれていた。しかし、平成11年版指導要領の改訂では、主題学習を
継承・発展させて「歴史の考察」という項目に再編し、従来までは「我が国
の歴史の展開」の学習内容でまとめられていた「内容」の中に加え、その最
初においたのである。
平成11年版の学習指導要領解説で確認すると、「歴史を考察する基本的な
方法を理解させるとともに、主題を設定して追究する学習、地域社会にかか
わる学習を通して、歴史への関心を高め、歴史的な見方や考え方を身に付け
させる」ために「内容」の最初に「(1)歴史の考察」が設けられたことが
わかる。この大項目の「歴史の考察」は「ア 歴史と資料」、「イ 歴史の追
究」、「ウ 地域社会の歴史と文化」から構成され、アとイは新しく加えられ
た項目である。アについては後述するとして、イについては、先にも述べた
が従来の主題学習を発展的に継承し主題を追究する学習として歴史の見方や
考え方を身に付けることが要求されている。ウに関しては従前よりあった項
目であるが(1)に移され、「地域社会にかかわる学習が、作業的・体験的
な学習活動を伴って実践されることが可能」とされ、生徒主体の学習活動を
重視することを明確に示した。
さて、(1)の「ア 歴史と資料」についてであるが、「歴史における資料
の特性とその活用及び文化財保護の意義について理解させる」ことを目的と
しており、さらに「様々な歴史的資料の特性に着目して、資料に基づいて歴
史が叙述されていることを理解させる」ための「(ア)資料をよむ」と「博
物館などの施設や地域の文化遺産についての関心を高め、文化財保護の重要
性について理解させる」ための「(イ)資料にふれる」の小項目に分けられた。

- 8 -
なかでも「(ア)資料をよむ」については、「日本史学習に対する関心を高め
るとともに、歴史の学習の基礎的な認識を深めることをねらいとして」、「日
本史B」学習の導入として実施することが位置づけられたのである。いわゆ
る歴史の学び方の学習を最初に行うことが要望されたのである。
この日本史学習の導入となる「(ア)資料をよむ」では「新聞・雑誌等も
含めた文献、絵画や地図、写真等の画像、景観、地名、習俗、伝承、言語な
ど様々なものが歴史的資料となり得ることに気付かせるとともに、それら資
料の有効性や限界等の基本的特性を踏まえた上で、それらから過去の出来事
や景観、生活、思想、社会などを考察させる学習を通じて、生徒の思考力を
高めることが期待される。そのために、資料を比較し、その比較から特色を
発見したり、また、変化を読みとって、その変化の要因を推理し、さらに多
様な資料を用いて多面的・多角的に考察し、総合的に論証する」、資料に関
する学習と歴史の学び方の学習が期待されている。また同時に、「中学校社
会科の学習との関連も視野に入れて、生徒の興味・関心から離れて細かな事
項の教え込みになることがないよう、抽象的ではなく、生徒の親しみやすい
具体的な資料を用いて作業的、体験的な学習を行うよう指導計画を作成する
必要がある」ことも示されていた。
次に、平成21(2009)年版学習指導要領について確認しておく。この改訂
された新学習指導要領による学習は、平成25(2013)年4月より学年進行で
行われる。この新しい指導要領でも「日本史B」の方針・目的には大きな変
更はないが、内容構成には新たな変化があらわれた。「2 内容とその取り
扱い」の中で、「我が国の歴史の展開」を6つの大項目にまとめなおし、そ
れぞれの時代の「社会や文化の特色について、国際関係と関連づけて考察さ
せる」となっている。従来の「理解させる」から「考察させる」学習への転
換が図られている。また、内容の取り扱いでも「資料を活用して歴史を考察
したり、その結果を表現したりする技能」の向上や、「様々な資料の特性に
着目させ複数の資料の活用を図って、資料に対する批判的な見方を養う」こ
とや「因果関係を考察させたり解釈の多様性に気付かせたりする」ことなど、
社会構成史的な内容項目をとり、資料などの活用を図り歴史を解釈する学習
を取り入れるなど、平成11年版指導要領よりさらに進めて内容理解の学習か
ら、歴史の学び方の学習を重視したものとなった。

- 9 -
なお、「2 内容とその取り扱い」の「(1)原始・古代の日本と東アジア」
の最初には「ア 歴史と資料」がおかれ、このアの項目は平成11年版と同様
に「資料に基づいて歴史が叙述されている」ことを理解させることをねらい、
「日本史B」学習の導入として位置づけられた。さらに、「歴史を考察し表
現するための学習」として「2 内容とその取り扱い」の(2)の最初に「ア
歴史の解釈」、(3)の最初に「ア 歴史の説明」をそれぞれ位置づけ、近
現代の最後には「ウ 歴史の論述」として、それぞれの大項目の中で歴史学
習の基本的な技能・方法を計画的・段階的に高めさせるような構成を取って
いる。
3 高等学校「日本史B」教科書における「歴史と資料」
(1)各教科書での「歴史と資料」に関する記述について
平成11年版学習指導要領に対応した「日本史B」の教科書は平成15(2003)
年から発行され、翌年には現行の教科書11冊がすべて刊行された。歴史の学
び方の学習となる「歴史と資料」、とくに導入の「資料をよむ」がどのよう
に記述され、どのような扱いになっているのかを次に比較していく。
①山川出版社『詳説日本史 改訂版』
最初に、最も発行部数が多く、大学受験用教科書として定評のある山川出
版社の『詳説日本史 改訂版』を確認していく。
「資料をよむ」に対応した内容は、口絵ととともに目次の前に配されてお
り、教科書本文(総ページ数408ページ)とは違う扱いとなっている。「資料
をよむ」に使われたページ数は4ページで「長屋王の変を探る」というテー
マがかかげられている。項目として1「文献資料をよみ解く」、2「史料の
背景に迫る」、3「史実に迫る」、4「歴史を掘り起こす」、5「木簡を読む」、
6「さまざまな資料を体験しよう」がおかれ、最初の項目1では「歴史は資
料に基づいて考察され、叙述される」と記し、文献資料・画像資料・遺跡・
遺物など様々な種類の史料をあげることからはじめている。そして、「長屋
王の変」をテーマとして扱い、最初に『続日本紀』の原文と読み下し文を並
列して並べ、『続日本紀』の史料としての価値にふれた上で、史料から事件
の概要を説明している。項目2で長屋王の人物像を説明し、項目3では長屋

- 10 -
王の変が藤原氏によって仕組まれたことを示す史料(同『続日本紀』)を使い、
教科書本文49ページの記述「729(天平元)年、策謀によって左大臣であっ
た長屋王を自殺させ(長屋王の変)」が生まれたことを解説している。さら
に4と5の項目で、長屋王邸宅跡から出土した木簡史料を解説し長屋王の生
活を説明している。最後の6の項目で近世の道祖神や石塔、寺社の境内にあ
る忠魂碑などを調べ、当時の人々の信仰や思いを考察するなどのテーマ学習
の必要にふれている。
この教科書での「歴史と資料」の位置づけは、本文の扱いとは完全に切り
離し、「長屋王の変」をコラム的に扱っている。歴史における「資料」の役
割についてふれてはいるが、生徒自ら資料を読み学習し歴史を探求する記述
にはなっていない。あくまでも教科書本文にある「長屋王の変」の補完的な
ものとなっており、教師の解説なしでは生徒の理解は難しい内容となってい
る。ただし、文献資料だけではなく、発見された考古資料から奈良時代の王
族の生活を探るなど社会史的な視点を入れ記述されていることは、歴史学の
研究成果が反映されており、教科書の本文との関連が書かれていることとと
もに評価できる。
②山川出版社『新日本史 改訂版』・同社『高校日本史 改訂版』
次に、同じく山川出版社の2冊の教科書についても確認していく。
『新日本史 改訂版』であるが、教科書本文のはじめに配されており、本
文全416ページの中で4ページが「資料をよむ」に割かれている。「木簡をよ
む」(2ページ)と「さまざまな資料から昔の人々の生活を読み解こう」の
項目を設け、木簡の項目では長屋王邸宅跡から出土した木簡史料を取り上げ、
ここに書かれた文字から当時の貴族の生活を解説している。また、大化の改
新の「郡評」論争についてもふれている。2つめの項目では、絵画資料『一
遍上人絵伝』と『洛中洛外図屏風』の図版をのせ、そこに描かれている人物
の姿に着目させ、男の烏帽子と髻、女の髪型の変化を比較する記述となって
いる。
『高校日本史 改訂版』でも「資料をよむ」は教科書本文のはじめに、本
文全319ページの中で4ページの枠で、『洛中洛外図屏風』をテーマとして記
述されている。1「洛中洛外屏風とは」、2「祇園祭をみてみよう」、3「商
業活動について調べてみよう」、4「同時代の文字記録とくらべ、資料の特

- 11 -
性についても考えてみよう」の4項目がおかれ、それぞれ絵図からの読み取
りと解説、さらに、インターネットの活用や図書館での調べ方を記載してい
る。また、同時期の文字資料として、宣教師ルイス・フロイスの残した『日
欧文化比較』の一部をあげ、当時の女性の姿を絵図と文字で比較させ、その
「相違点を資料の特性を考え話し合う」と記し、生徒の学習活動を促す記述
になっている。
2つの教科書を比べると、前者はコラム的な扱いとなっているのに対し、
後者は、生徒の学習活動の視点に立ち、資料の読み方や調べ方など、歴史の
学び方についても言及している。考古資料や図像学などを用いる新しい歴史
学の成果については両者とも取り入れられている。
③東京書籍『日本史B』・同社『新選日本史B』
東京書籍の2冊の教科書について確認する。
『日本史B』では、「資料をよむ」は教科書本文全426ページの最初の4ペー
ジの枠で扱われている。「絵画資料から歴史を読み解く」と「民衆に広まっ
た資料から歴史を読む」の2つのテーマが設定され、それぞれ2ページ中の
1ページを資料のページとして図版が大きく占められており、残りの1ペー
ジでそれぞれの資料を問いの部分とその解説として記述している。絵画資料
の項目では『一遍上人絵伝』の4つの場面を取り上げ、絵の読み取り作業(問
い)を提示し、その後問いに対する解説を加えており。民衆に広まった資料
の項目では黒船来航期の庶民に広がった瓦版や刷り物などの資料から当時の
世評を読み解く記述になっている。資料を提示し、その中で問いを与え、解
説していく記述は生徒が自ら歴史の学習をすすめることが期待できる。特に、
文字資料ではなく、図像資料を多く活用している点も日本史学習の導入とし
てはふさわしい。また、社会史の成果が大いに活用されている。
『新選日本史B』では、本文総ページ(312ページ)とは別に、口絵とし
て6ページ分の変形図版の体裁で「資料をよむ」の項目が作られている。図
像資料の『江戸図屏風』を大きく取り上げ、主題として「江戸時代の町の様
子や人々の暮らしは、どうなっていたのだろう。『江戸図屏風』を手がかり
に探ってみよう」が提示され、1「屏風全体をながめて」、2「江戸の町へ
タイムスリップ」、3「江戸の町づくり」、4「大名屋敷の配置・構造」、5「日
本橋周辺の人々」、6「人々の暮らしと環境」、7「関心のある主題で歴年代

- 12 -
を考察してみよう」の7項目が配され、それぞれのテーマに沿って解説され
ている。
最初に「歴史を考察する上で、その基本となるものは、さまざまな歴史的
資料である。歴史は資料をもとに叙述されているため、歴史を考察すること
は、多様な資料を通じて現代から過去を振り返ることにほかならない。そこ
で、まずはじめにこの考察方法を学んでいこう。それぞれの関心にもとづい
て主題を設定した上でその主題に主体的に向かい、それに関係する資料の特
性を考え的確に活用することで豊かな歴史認識を獲得することができる」と
記述した上で、先にあげた主題を示し、歴史の学び方、歴史学の成果として
の図像資料の読み方の説明がなされている。
④三省堂『日本史B 改訂版』
教科書の口絵としての扱いで教科書本文全402ページとは別に2ページの
枠で「文字史料を読む」がおかれている。「歴史を解明するためには資料は
不可欠である。歴史資料の解読をつうじて過去の歴史を復元するのが歴史学
である」と最初に記し、文字資料と考古資料、近年の歴史学の成果である図
像資料をあげたうえで、文字資料『大乗院寺社雑事記』の山城の国一揆を解
説している。最後に「当時の人々に関心をもち、興味をもったことをさらに
詳しく調べてみよう」とあるが、基本的にはコラム的な扱いとなっている。
⑤清水書院『高等学校日本史B 改訂版』
本文(総ページ264ページ)の中で「歴史の考察編」として「歴史と資料」、
「歴史の追求」、「地域社会の歴史と文化」の項目とをすべて合わせると、発
行されている全教科書の中で最大の分量となる27ページを割いている。
「資料をよむ」については織田信長を例として取り上げ、歴史の追究の方
法や歴史資料の見方などを解説している。「『若き日の信長』のイメージ」と
「同時代人の証言」の項目では太田牛一の『信長公記』とフロイスの『日本
史』の文字資料を使い、資料批判をふまえた上で信長の人物像を解説してい
る。さらに、「『史料』による歴史探究」の項目では、信長自身の書状や花押、
「『モノ資料』による歴史探究」では肖像画、「『考古資料』による歴史探究」
の項目では安土城趾を取り上げ、それぞれの資料の特性を説明しながら信長
像に迫っている。織田信長という誰でもが知っている歴史的人物を例にとり、
歴史の学び方をわかりやすく解説している。生徒にとって資料そして歴史の

- 13 -
学び方が十分に伝わる記述となっている。また、図像や考古資料など新しい
歴史学の成果も取り入れられている。
⑥桐原書店『新日本史B』
本文447ページの中4ページを「資料をよむ」にあて、「歴史の学び方と資
料の読み方」というテーマ設定を行い「歴史と資料」、「道具の変化を手がか
りにする」、「伝統行事から読み取る」、「文字資料で明らかになること」、「文
化財の保護」の項目をたて、最初の項目で「歴史とは、人間集団の過去から
現在にいたる活動の総体」と記し、「資料を相互に補完しあいながら、過去
の人間活動を復元し、過去と未来の人間のありかたを考えるのが、歴史を学
ぶことの目的」としている。続いての項目で弥生の木製農具の写真をあげ、
弥生時代の農耕の変化を解説し、さらに次に続く2つの項目では宇和島の伊
達と仙台の伊達に共通する伝統行事の「鹿踊り」の由来を文字資料を使い解
説している。そして最後に文化財保護の大切さを記している。歴史を学ぶこ
との意味と文化財保護の重要性にふれているが、全体的にはコラムとしての
扱いとなっている。民俗資料と文字資料の融合をはかっている点は新しい歴
史学の成果が取り入れられている。
⑦明成社『高等学校最新日本史』
本文280ページの中3ページが「資料をよむ」にあてられており、「多面的
な視点で見えてくる歴史像」の項目でペリー来航前後の日本人を吉田松陰の
『西遊日記』、『ペルリ提督日本遠征記』の文字資料とペリーの肖像画から解
説している。「出土品が語る歴史」の項目では「稲荷山古墳出土の鉄剣」の
写真と銘文をあげ、雄略天皇の国内勢力圏を解説し、さらに『宋書倭国伝』
や『高句麗好太王碑文』にふれ、東アジアと日本の関係を解説している。こ
の教科書では歴史を学ぶ意味について別の項目「日本の歴史を学ぶにあたっ
て」(2ページ)を立て「国民の物語」としての歴史を強調している。
⑧実教出版『高校日本史B 新訂版』
本文255ページの中6ページを「高校生の歴史探究」という項目で「資料
をよむ」と「資料にふれる」とを合わせて記述している。「縄文時代の犬は
なぜ埋葬されたのか」というテーマを設定し、加曽利貝塚で発掘された犬の
完全遺体の写真を手がかりに高校生が会話をしながら謎に迫るという形の記
述になっている。屈葬の人骨の写真、銅鐸に描かれた狩りの様子の絵、加曽

- 14 -
利貝塚の写真、調査報告の資料なども各ページに配され、会話の記述を補足
解説している。「資料にふれる」にあたる部分は、加曽利貝塚博物館を訪ね
た高校生と学芸員の会話文となり、「資料をよむ」での謎解きの答えを解説
している。さらにここでは加曽利貝塚の保存運動にもふれている。
高校生の視点に立ち、「歴史の謎」に対し複数の「解釈」をあげ、それぞ
れの解釈を「考察」していく、会話による記述は加藤公明実践をモデルとし
ており、「歴史の学び方」を学ぶ、日本史学習の導入として大きな効果をあ
げている。
(2)実教出版『日本史B』での「歴史と資料」の記述
筆者がかかわった実教出版『日本史B』について述べていく。教科書本文
415ページの中5ページを「資料をよむ」にあて、1「歴史は何にもとづい
て叙述されるのだろうか」、2「石像物に刻まれた『柳生の徳政碑文』をよ
んでみよう」、3「『絵巻物』から歴史をよんでみよう」、4「みずから資料
にあたり歴史を読み解く体験をしよう」の4つの項目を設定した。
最初の項目では「歴史を解き明かし叙述するということは、自然や人間な
どが残したさまざまなものを利用して、過去を再現することである。自然や

- 15 -
人間などが残した無数の痕跡のなかで、過去を再現するのに利用できるもの
を『歴史資料(史料)』」と記述し、歴史は資料にもとづいて叙述されること
を説明した。黒田日出男の資料分類を参考に、資料を次の5つに整理した。
①新聞・雑誌・文学などもふくめ、文字によって記録された文献資料
②絵画・写真・漫画・地図などの図像資料
③映画・ビデオ・録音などの映像・音声資料
④遺跡・遺物などの考古資料
⑤風俗・習慣・伝説・民話・歌謡・地名などもふくめ伝承された民俗資料。
次の項目では地蔵石に刻まれた『柳生の徳政碑文』と教科書本文中(146
ページ)の史料『大乗院寺社雑事記』の記述を比較して「正長の土一揆」に
ついて考察する解説を記した。石に刻まれた歴史、庶民の喜びと支配者の一
揆に対する驚きの両方を対峙させ、立場の違いにより同じ歴史的事実の評価
が異なることが理解できるように記述した。
3の項目では「絵巻物」の鑑賞の仕方や美術品としての価値ととともに、「絵
巻物」が持つ歴史資料としての意義について解説した。その後で、『一遍上
人絵伝』の「福岡の市」の場面とその中の4つの部分を拡大したページをお
き、次の4つの問いを立てた。「この絵巻の絵は何をしている場面でしょうか?」、
「絵にはどのような人々が登場していますか?」、「絵から気づいたことを記
してみましょう?」、「この絵巻物の時代は何時代だとおもいますか?」。絵
巻物がもつ歴史資料としての活用の仕方の一つを例示したのである。
続くページで「備前『福岡の市』から鎌倉時代の社会をよむ」というテー
マで、問いに対する解説を行った。そして最後の項目で、資料や情報の入手
方法、地域の遺跡や史跡などに訪れること、博物館や資料館の活用などにふ
れ、みずから調査を行う学習活動を示した。
なお、次に続く「資料にふれる」では2ページを使い「文化遺産との出会
い」をテーマに、博物館や資料館の意義をのべ、さらに世界遺産に登録され
た「原爆ドーム」を取り上げ、負の遺産ともなる「戦争遺跡」についても解
説した。

- 16 -
4 まとめ
平成11年版学習指導要領で加えられた「歴史と資料」について、2012年に
発行された教科書から分かったことを整理し、平成21年版学習指導要領の「歴
史と資料」の項目に対しての、教科書での扱い方と記述内容についてあらた
めて考えてみることでこの稿のまとめとしたい。
まず、扱い方についてであるが、すべての教科書で「内容」の(1)の「ア
歴史と資料」の小項目「(ア)資料をよむ」については、教科書の最初に
おかれ、指導要領の示す日本史学習の導入として扱われていることがわかる。
しかし、教科書本文とは別に、表紙裏の目次などの前に当たる口絵の部分に
配し、教科書の本論にあたる内容学習とは違うものとして扱う教科書も見ら
れる。本文とは違う扱いにして、口絵の部分に記載することは、受験を意識
する場合、教師も特に説明を行わず、生徒の自主的な学習にまかされること
となる。歴史の学び方の導入として位置づけるのであれば、教科書本文の内
容学習と同様の形で、最初に配するべきであると考える。
また、「資料にふれる」については「資料をよむ」の記述に含み、併せて
学習する体裁をとっている教科書が見られた。日本史学習の最初に歴史にお
ける「資料」のもつ意味を考えさせることは重要であり、平成21年版学習指
導要領ではこの項目が1つにまとめられたことは当然であると考える。
次に、記述内容についてであるが、各教科書とも歴史学にとっての「資料」
の意味と資料の分類については記しており、続けて資料を活用し、歴史的事
象や歴史的人物などを説明している。教科書本文の背景にあるものなど歴史
叙述の方法が理解できるようになっている。また、近年の歴史学の成果も多
く取り入れられており、資料に関しても文献資料だけではなく、考古資料、
民俗資料、図像資料などの活用がされており、内容も従来の政治事件史では
ない、社会史的なものが多い。しかし、多くの教科書での記述は生徒が自ら
学習できる内容のものは少なく、教師の説明が必要なコラム的なものとなっ
ている。
そこで、新しい学習指導要領に対応する「歴史と資料」の教科書記述のあ
り方について考えていくと、まずは、歴史における資料の意味と分類などを
解説し、次に、実際に歴史がさまざまな資料によって叙述されることを具体

- 17 -
的な例をあげて説明するとともに、教科書の本文との関係についても考察さ
せることが可能な記述がふさわしい。そして、最後に、歴史を叙述する方法
を理解した上で、生徒自らが今度は「歴史家」体験をすることができる、あ
るいは実際に「問い」などを設けて活動できる教科書記述となることが要求
されると考える。この歴史家体験をする学習活動は生徒の社会認識を培う上
でも重要なものとなるといえよう。
参考文献
E.H.カー『歴史とは何か』岩波新書 1962
R.K.F.ヴァイツゼッカー 永井清彦訳『荒れ野の40年―ウァイツゼッ
カー大統領演説全文 1985年5月8日』岩波ブックレット 1986
文部科学省編『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』実教出版 1999
文部科学省編『高等学校学習指導要領解説地理歴史編』教育出版 2010
森分孝治・片上宗二編『社会科重要用語300の基礎知識』明治図書
2000
星村平和編『歴史教科書を活用したわかる授業の創造』明治図書 1984
星村平和監修 金子邦秀編『新中学校社会科授業方略の理論と実践 歴
史編』清水書院 1992
土屋武志・下山忍編『学力を伸ばす 日本史授業デザイン 思考力・判
断力・表現力の育て方』明治図書 2011
黒田日出男『朝日百科日本の歴史・別冊歴史の読み方』朝日新聞社
1992
(2013年2月1日査読済)










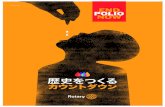



![Title II [最近文獻目錄] 中國 中國文學報 (1962), 17: 10-28 Issue … · 歴史劇是藝術,不是歴史 歴史評債與戯劇褒疑 歴史劇可以不根擦歴史鳴?](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fc1a2fc3ef0cd460a4b70df/title-ii-oeecceoe-oe-oe-1962-17-10-28-issue-eeioe.jpg)




