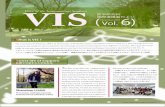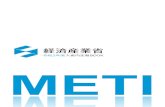大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ ·...
Transcript of 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ ·...
![Page 1: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/1.jpg)
2020
大学院法学研究科[修士課程]
GRADUATE SCHOOL OFLAW
大学院案内
![Page 2: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/2.jpg)
ごあいさつ
大 学院法学研究科は、他の研究科に先駆け、法学部を母体として1995年4月に開設された。本研究科
が地域社会に送り出してきた修了生は現時点で210名にのぼり、それぞれの分野で先導的な役割を果たしています。
本研究科では、社会において生起するさまざまな法的・政治的諸問題に対処するために、研究の中で獲得した専門的知識を健全な社会に役立てうる研究従事者及び高度専門職業人を養成することを目的として、法学部の人的資源を最大限に活用しつつ、実務家など外部の優秀な人材の応援も得て、多様なニーズに応えうる幅広いバランスのとれた科目編成を展開しています。
本研究科の特徴として第2に指摘しうる点は、特に税理士養成のための開講科目や支援体制が充実しています。本研究科を修了し、その後に税理士登録をした者は、開設以来、40名以上にのぼります。税理士養成に関しては東京以北で最大の実績を誇っています。
第3の特徴としては、地域社会マネジメント研究科と並んで、本研究科が日本ファイナンシャル・プランナーズ協会からCFP認定教育プログラムを実施する大学院として指定を受けています。これにより所定の科目の単位を修得すればCFPの受験資格を得ることができます。
第4は、仕事を持っている社会人院生への配慮として、2年分の学費で3年間ないし4年間在籍しうる「長期履修制度」と、特定科目について札幌都心にあるサテライト教室での授業を導入しています。
このような研究環境の下で本研究科は、①研究を通じて高度な専門的知識を身に付けたいと考える者、②行政や民間企業で法務に従事することを望む者、③税理士・司法書士・国税専門官などのいわゆる広義の準法曹を目指す者、④キャリア・アップを目指す有職者など、明確な目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない者の入学を多いに歓迎致します。
札幌学院大学大学院法学研究科長
石 井 和 平
大学院法学研究科の目的
大学院法学研究科の教育目標
大学院法学研究科は、国際社会及び地域社会において、当面する法的・政治的諸問題に対処するため、法律学・政治学との連携を図りながら、事象の歴史と理論を深く研究することによって、そこで得た知識を健全な社会の発展に役立てることのできる研究者及び高度の専門性を備えた職業人を養成することを目的とする。
⑴ 法学や政治学に関する高度な専門的素養を培い、将来、大学や研究所などで研究、教育に従事する能力を備える。
⑵ 現実の社会において有用な高度の理論と実務能力を備えることによって行政や民間企業の法務セクション・スタッフとして活躍しうる能力を身につける。
⑶ 納税者の人権擁護及び税制、税務行政の民主化に寄与しうる税法務分野の担い手としての資質を培う。
⑷ 投資家の投資行動に適合するポートフォリオを提案しうる創造的能力を涵養する。
⑸ 高度な教育資格を取得し、“心身ともに健康な国民の育成”という使命を担いうる能力を開発する。
さらなるキャリア・アップを目指して社会人にも開かれた札幌学院大学大学院法学研究科へ!!
2 GRADUATE SCHOOL OF LAW
![Page 3: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/3.jpg)
群 科 目 名 称 配当学年 単位数
公法科目
憲法特講AⅠ 憲法特講AⅡ 1・2 2刑法特講Ⅰ 刑法特講Ⅱ 1・2 2刑事訴訟法特講 1・2 2行政法特講Ⅰ 行政法特講Ⅱ 1・2 2地方自治法特講 1・2 2労働法特講Ⅰ 労働法特講Ⅱ 1・2 2社会保障法特講 1・2 2税法特講AⅠ 税法特講AⅡ 1・2 2税法特講BⅠ 税法特講BⅡ 1・2 2税法各論特講Ⅰ 1・2 2税法各論特講Ⅱ 1・2 2税法各論特講Ⅲ 1・2 2税法各論特講Ⅳ 1・2 2
民事法科目
民法特講AⅠ 民法特講AⅡ 1・2 2民法特講BⅠ 民法特講BⅡ 1・2 2民法特講CⅠ 民法特講CⅡ 1・2 2民事訴訟法特講Ⅰ 民事訴訟法特講Ⅱ 1・2 2商法特講AⅠ 商法特講AⅡ 1・2 2商法特講BⅠ 商法特講BⅡ 1・2 2国際私法特講 1・2 2不動産運用設計特講 1・2 2
政治・国際科目
政治学特講Ⅰ 政治学特講Ⅱ 1・2 2国際関係論特講Ⅰ 国際関係論特講Ⅱ 1・2 2行政学特講Ⅰ 行政学特講Ⅱ 1・2 2日本法制史特講Ⅰ 日本法制史特講Ⅱ 1・2 2国際法特講Ⅰ 国際法特講Ⅱ 1・2 2アフリカ法特講Ⅰ アフリカ法特講Ⅱ 1・2 2外国文献研究Ⅰ(英文) 外国文献研究Ⅱ(その他) 1・2 2
群 科 目 名 称 配当学年 単位数
演習科目
憲法演習AⅠ 1 2刑法演習Ⅰ 1 2行政法演習Ⅰ 1 2労働法演習Ⅰ 1 2税法演習AⅠ 1 2民法演習AⅠ 1 2民法演習BⅠ 1 2民法演習CⅠ 1 2民事訴訟法演習Ⅰ 1 2商法演習AⅠ 1 2商法演習BⅠ 1 2政治学演習Ⅰ 1 2行政学演習Ⅰ 1 2日本法制史演習Ⅰ 1 2国際関係論演習Ⅰ 1 2国際法演習Ⅰ 1 2アフリカ法演習Ⅰ※ 1 2
演習科目
憲法演習AⅡ 憲法演習AⅢ 2 2刑法演習Ⅱ 刑法演習Ⅲ 2 2行政法演習Ⅱ 行政法演習Ⅲ 2 2労働法演習Ⅱ 労働法演習Ⅲ 2 2税法演習AⅡ 税法演習AⅢ 2 2民法演習AⅡ 民法演習AⅢ 2 2民法演習BⅡ 民法演習BⅢ 2 2民法演習CⅡ 民法演習CⅢ 2 2民事訴訟法演習Ⅱ 民事訴訟法演習Ⅲ 2 2商法演習AⅡ 商法演習AⅢ 2 2商法演習BⅡ 商法演習BⅢ 2 2政治学演習Ⅱ 政治学演習Ⅲ 2 2行政学演習Ⅱ 行政学演習Ⅲ 2 2日本法制史演習Ⅱ 日本法制史演習Ⅲ 2 2国際関係論演習Ⅱ 国際関係論演習Ⅲ 2 2国際法演習Ⅱ 国際法演習Ⅲ 2 2アフリカ法演習Ⅱ※ アフリカ法演習Ⅲ※ 2 2
注:演習Ⅰは1年次後期に、演習Ⅱは2年次前期に、演習Ⅲは2年次後期に履修する。※2016年度以降開講しない。
「法学」の領域をトータルでとらえた科目構成で、あらゆる視点から問題に取り組みます。
カリキュラム
【税理士を目指す方へ】税理士試験と修士の学位による試験科目免除について①税理士試験は、税法に属する科目と会計学に属する科目について行われます。②税法に属する科目については、次の科目のうち受験者が選択する3科目(所得税法又は法人税法のいず
れかを含む)の合格(60点以上)が必要とされます。(1)所得税法、(2)法人税法、(3)相続税法、(4)消費税法又は酒税法のいずれか1科目、(5)国税徴収法、(6)地方税法のうちの道府県民税及び市町村民税に関する部分又は事業税に関する部分のいずれか1科目、(7)地方税法のうちの固定資産税に関する部分
③会計学に属する科目については、簿記論及び財務諸表論の2科目の合格(60点以上)が必要とされます。④本学大学院法学研究科で税法に属する科目等の研究により修士の学位を授与された者が税法に属す
る科目の試験免除を受けるには、自己の研究が税法に属する科目等に関するものであることについて、国税審議会の認定を受ける必要があります。この認定を受けることより、税法に属する科目のうちの2科目の免除を受けることができます。
【専修免許を目指す方へ】本大学院法学研究科では、「中学校専修免許状社会」、「高等学校専修免許状公民」の専修免許状の課程認定を有しています。これらの免許を取得するためには、当該免許教科の一種免許状を取得した後、基礎資格として修士の学位を取得し、「教科又は教職に関する科目」24単位を修得する必要があります。
【道内の大学院初】大学院CFP認定教育プログラムの指定について本学法学研究科並びに地域社会マネジメント研究科は、日本ファイナンシャル・プランナーズ協会(日本FP協会)からCFPⓇ認定教育プログラムを実施する大学院として、2007年4月に道内で初めて指定を受けました。CFPⓇ(Certified Financial Planner)は日本FP協会が認定するAFPの上位・国際資格で、近年、金融・保険などさまざまな業種でCFPⓇ資格が認められています。本学大学院で所定の科目の単位を取得すると、AFP(Affiliated Financial planner)資格(2002年から国家資格)を取得しなくても、直接CFPⓇ受験資格を得ることが出来ます。また、大学院で所定の課程を修了した者のうち、AFP認定研修の修了要件となっている「提案書課題の作成」を修了した者には、AFP資格の登録権利を付与します。(平成23年4月改定)
【社会人の方へ】働きながら大学院で学ぶために、以下のようなサポートをしています。○長期履修制度 ○サテライト教室(一部の科目)大学院(修士課程)の修業年限は通常2年間ですが、働きながら学ぶ人が勤務等の関係で計画的に修業年限を越えて(3~4年間)修得する長期履修制度があります。2年間の学費を「長期履修計画年数」に応じて分割納入できます。
■ 履修方法① 公法科目、民事法科目、政治・国際科目から、各2単位、計6単位及び演習科目(Ⅰ~Ⅲ)6単位以上を含む、合計30単位以上を修得しなければならない。② 上記の科目以外に、本学地域社会マネジメント研究科の開講科目のうち、「基本科目」並びに「展開科目」に属する科目を上限10単位ま
で修了要件単位として履修することができる。③ 研究指導は、演習Ⅰを1年次後期に、演習Ⅱを2年次前期に、演習Ⅲを2年次後期に開講する。④ 演習科目の担当者を指導教授とし、学位論文の作成その他研究一般について指導を受けなければならない。⑤ 修士の学位論文は、演習科目について提出するものとする。
SAPPORO GAKUIN UNIVERSITY 32 GRADUATE SCHOOL OF LAW
![Page 4: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/4.jpg)
講義内容
税法特講AⅠ・AⅡ担当/川股 修二 教授各2単位
税法特講AI及びAⅡは、税法各論特講の基礎学習を受けて、租税法原則の基本を習得し、租税法事件の司法判断を分析することで、租税法における思考能力を向上し、修士論文に関する問題意識を抽出する。
刑事訴訟法特講担当/岡田 久美子 教授2単位
刑事手続の基本構造・原則を理解し、判例を分析することによって、具体的事例にあたったときに何が問題であるかを抽出できるようにする。たとえば、近年の法改正が訴訟構造や憲法に反しうる点を指摘できるようにする。また、判例を分析して報告し、多角的に問題を捉え、自説の展開および議論ができるようにする。
憲法特講AⅠ・AⅡ担当/伊藤 雅康 教授各2単位
日本国憲法下での重要であり著名な判例について、その事案と判旨に関する基本事項について確認し、そのなかの主要な論点についての伝統的な理解を調べたうえで、現時点での学説の到達点を踏まえてそれぞれの判決の内容の読み取り方について議論することを通じて、重要判例の理解はもちろんのこと憲法学上の主要なテーマに関する論議についての学習を促進したいと思います。
憲法に関する主要な判例や学説についての十分な理解を得ることが第一の目標ですが、履修者に判例に関する報告を分担してもらうことで、判決の読み方、関連資料の調べ方、発表のしかた等の研究に関する技法についても習熟することが副次的な目標となります。
民法特講CⅠ・CⅡ担当/田處 博之 教授各2単位
開講当初に受講者の民法学習の経験および希望を聴いたうえで内容を決めたい。例年は初学者が多い。受講者からとくに希望がなければ、以下の内容を考えている。民法とは、おおざっぱにいえば、われわれのいわば私的な(公的ではない)日常生活で生じてくる紛争を法的に解決するための制度とかルールを定めたものである。この授業では、そうした制度とかルールとかのうちから特に重要なものを概説する。民法特講CⅠでは民法典の総則、物権にかかわる部分を、民法特講CⅡでは民法典の債権、家族にかかわる部分を中心に扱う。
民事訴訟法特講Ⅰ担当/横路 俊一 教授2単位
民事訴訟法に関連する判例及び当該判例に関する諸文献の調査及び報告を通じて民事訴訟法の理解を深めることをねらいとする。訴訟要件、処分権主義、弁論主義、証拠法、判決効といった民事訴訟法における諸原則、種々の規律及び判例を理解すること、また、法的調査及び報告の方法を身に着けることを目標とする。
政治学特講Ⅰ・Ⅱ担当/石井 和平 教授各2単位
政治学特講Ⅰ、政治学特講Ⅱを通じて、地域の組織、制度、歴史・文化、アイデンティティ等の分析・検討を行います。また、グローバル化した現代における地域戦略に関するケーススタディーを行い、実践的な問題解決力を養うことも本講座の目標です。学際的な知識と関心を必要とします。
行政学特講Ⅰ・Ⅱ担当/神谷 章生 教授各2単位
行政学、政治学等の専攻者は地方自治と行政学の基礎を、その他の専攻者は現代日本の政治と行政を学ぶ。授業内容は、ここのテーマを通じた討論をおこない、最後にレポートを提出する。昨年度は、戦争と行政をテーマにいろいろな角度から討論した。
国際関係論特講Ⅰ・Ⅱ担当/清水 敏行 教授各2単位
国際関係の一分野として現代韓国政治の理解を深める。演習と講義の二つの形式。講読する論文などは事前に配布します。韓国政治の文献を1冊購入してもらうこともあります(ただし安価な新書に限定)。また関連するビデオを見ます。国際関係論特講Ⅱでは、日本語文献で、韓国政治の理解を一層深める。
商法特講AⅠ・AⅡ担当/荻野 昭一 教授各2単位
会社法制についての最も基本的な法律である会社法と、会社法の特別法に位置付けられる金融商品取引法についての基本的な事例・判例の研究を行う。事例・判例の論点を的確に捉える能力を養成することを目的とする。
4 GRADUATE SCHOOL OF LAW
![Page 5: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/5.jpg)
日本法制史特講Ⅰ・Ⅱ担当/小澤 隆司 教授各2単位
この講義では毎年度、日本近現代法史に関する基本文献を検討しています。年間テーマは、受講者の希望をきいて決定します。開講後数回は担当教員から講義をおこない、その後は履修者全員が分担して個別報告をしてもらいます。
行政法特講Ⅰ・Ⅱ担当/小幡 宣和 准教授各2単位
本講義では、行政法の典型論点を押さえつつ、現代行政法論の特質(二面関係から三面関係へ、給付行政の増大、公私協働など)について探求する。各論を中心とした行政上の諸問題を素材とし、できる限り具体的な議論となるように話題を提供していく。また、受講者の興味関心や研究テーマに応じて、議論の素材も追加する。
民法演習CⅠ・CⅡ・CⅢ担当/田處 博之 教授各2単位
民法上の特定の領域に関するいわゆる論点を、専門論文や重要判例を素材に掘り下げて検討する。教員の講義によるのではなく、受講者による報告を基礎に授業を進める。したがって、受講者は、民法について一通りの学習をすでに済ませてあることが前提となる。特定の領域としてなにに取り組むかは、開講当初に受講者の意向をも踏まえつつ決定する。
行政学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ担当/神谷 章生 教授各2単位
地方自治、行政等現代の公権力にかかわる問題を扱う。とりわけ、公共事業にかかわる行政問題を検討する。演習Ⅰでは基本文献を渉猟し、テーマ設定をする。演習Ⅱでは上記を進めるとともに、必要な調査を行う。演習Ⅲでは修士論文にまとめる。必要に応じ、調査等も追加的に行う。
税法演習AⅠ・AⅡ・AⅢ担当/川股 修二 教授各2単位
演習Ⅰでは、修士論文のテーマ選定に向けて効率的な情報収集としてのリーガルリサーチ手法を習得し、選定予定の論文テーマの方向性及び妥当性について討論や質疑応答することで取組むべきテーマを絞り込む。演習Ⅱでは、選定されたテーマについて提示された期限を遵守し、論文骨子を作成する。各々のテーマを互いに検討することで、中間発表会に向けて論文の骨格を形成する。演習Ⅲは、論文最終報告会までの初稿論文の完成と提出期限までの論文完成を単位要件とする。
日本法制史演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ担当/小澤 隆司 教授各2単位
日本近代法制史上の重要なテーマについて学術的かつ実証的に究明する。演習Ⅰでは、各自が選んだ研究テーマに関する基本文献を収集、検討する。演習Ⅱでは、各自の研究テーマに関する基本史料を収集、検討する。演習Ⅲでは、演習Ⅰ・演習Ⅱをふまえて各自の調査・研究成果を学術論文にまとめる。
政治学演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ担当/石井 和平 教授各2単位
政治学・行政学の分野、特に比較政治や地域行政を中心に、履修者の知的関心に沿って研究を進めます。演習Ⅰ: 政治学・行政学に関する幅広い文献の中から履修者の関
心ある課題に基づいて選択したものを輪番で報告、討論を行います。
演習Ⅱ: 演習Ⅰの作業を通じてテーマを絞り込み、そのテーマに沿った文献を講読し、報告、討論を重ね、できるだけ早期に修士論文のテーマを最終確定することを目指します。
演習Ⅲ: 各自が修士論文の執筆に取り組みます。
憲法演習AⅠ・AⅡ・AⅢ担当/伊藤 雅康 教授各2単位
この演習では、憲法学の特定の領域のなかのごく限られた論点について、時間をかけて議論することによって、テーマを深く追究することを受講者に身につけてもらうことを最終的な目標とします。
演習Ⅰでは、受講者各自に憲法学のなかで関心のある領域を選んでもらい、当該領域での基本的な文献についての紹介と検討を行ってもらいます。演習Ⅱでは、演習Ⅰでの文献検討を踏まえ、選択した領域のなかで引き続き検討を行う論点を絞り込んだうえで、関連する文献についての紹介と検討を行ってもらいます。演習Ⅲでは、さらに検討した論点に関する判例、法律、制度などの具体的な素材についての紹介と検討を行ってもらいます。論点に関する調査を行った場合には、その結果の紹介と分析を行ってもらいます。
商法演習AⅠ・AⅡ・AⅢ担当/荻野 昭一 教授各2単位
会社法制についての最も基本的な法律である会社法と、会社法の特別法に位置付けられる金融商品取引法の重要な判例の研究を行う。重要判例の論点を的確に捉える能力の養成と多様な論理構成を理解することを目的とする。
SAPPORO GAKUIN UNIVERSITY 54 GRADUATE SCHOOL OF LAW
![Page 6: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/6.jpg)
2016(平成28)年度平和構築による紛争の封じ込め~国連平和維持軍とNATOの危機管理活動を通じて~給与所得者の源泉徴収制度における過誤納の是正に関する一考察法人税法における金銭債権に係る貸倒損失について譲渡所得における取得費及び譲渡費用についての一考察相続税の課税方式に関する一考察信託税制の課税要件の一考察所得税法における経費概念 ~事業所得の必要経費該当性~役員給与の損金性 ~法人税法34条の意義について~
主な修士論文テーマ
2017(平成29)年度消費税が抱える税転嫁の問題とインボイス方式について~インボイス方式による公正な仕組みの実現~働き方が多様化した納税者の所得区分についての一考察無償譲渡により取得した資産の取得費についての一考察 ~所得税法60条1項を中心に~法人税法22条4項についての一考察役員給与課税に関する一考察法人税法第22条2項における益金に関する一考察 ~無償取引の収益性を中心として~非営利法人課税に関する一考察 ~収益事業課税と租税回避を中心として~青色申告制度についての一考察 ~所得税法に規定する帳簿の記帳義務を中心として~
2018(平成30)年度加算税の免除要件に関する一考察
~「更正の予知」の検討を中心として~所得税と相続税の二重課税とその調整についての一考察
~長崎生保年金訴訟と土地譲渡二重課税訴訟を題材として~相続税法における課税方式に関する一考察
~遺産取得課税方式への移行の検討~租税法における「住所」に関する一考察
~居住の意思から考える「住所」とは~申告納税制度と租税行政手続についての一考察
~過納税額の是正手続~所得税法56条の一考察 ~現代の家族間取引にあった56条の射程範囲を探る~
2009(平成21)年度所得税法の納税義務者についての一考察 ~「住所」の意義を中心として~
繰越欠損金に関する一考察
法人税法における貸倒償却の取扱いに関する一考察 ~直接償却(貸倒損失)に重点を置いて~
同族会社等の行為又は計算の否認規定の比較法的考察 ~韓国の不当行為計算否認規定との関係を中心として~
消費税法における帳簿等の保存について ~租税法律主義から見た仕入税額控除を中心として~
租税法規の遡及立法についての一考察
所得の人的帰属の一考察
損害賠償請求権の収益計上時期についての一考察 ~役員や従業員等による横領や詐欺等の不法行為によるものを中心として~
法人税の納税義務者規定についての一考察
申告納税制度における青色申告の考察 ~青色申告承認取消しに係る問題を中心に~
北海道農業の現状と活性化
更正の請求の期間についての考察 ~減額更正の期間制限を中心として~
2010(平成22)年度法人税法22条における益金の認識について ~無償による役務の提供に係る収益を中心として~
所得税法における社会保険料控除についての租税法学的考察
所得税法第64条第2項についての一考察 ~「求償権行使不能の解釈」を中心として~
所得税法における公平性についての一考察
譲渡所得課税と財産分与についての一考察 ~夫婦財産の精算に伴う金銭以外の資産の譲渡を中心として~
株式の振替制度に関する一考察 ~振替制度における株主名簿閲覧謄写請求権を中心に~
給与所得と源泉徴収制度についての今日的考察
同族会社の行為計算否認規定による理由の差替えについての一考察
2011(平成23)年度推計課税と証拠能力との関係についての一考察
所得区分についての今日的考察 ~給与所得と退職所得を中心として~
損害賠償請求権の収益計上時期に関する一考察
役員給与損金不算入制度についての一考察
法人税法22条2項の無償取引についての一考察
源泉徴収義務の本質と制度上の課題に関する一考察
租税法における信義誠実の原則の適用要件に関する一考察 ~所得税法における司法判断を中心として~
第二次納税義務の一考察 ~納税義務の権利救済を中心として~
事実認定・私法上の法律構成による否認を巡る法解釈の一考察 ~所得税法における租税回避行為否認の検討~
離婚に伴う財産分与と譲渡所得課税に関する一考察
2013(平成25)年度地方公共団体の課税自主権に関する憲法学的考察
国内においての多様な事業形態の一つである組合に対する課税についての一考察
租税法律主義についての考察
法人税法第22条第2項における無償取引課税の一考察
租税立法における違憲審査基準に関する一考察
相続税法34条 連帯納付義務についての一考察
譲渡所得における取得費の一考察 ~遺産分割費用を中心として~
源泉徴収制度の法律関係に関する一考察
所得税法における不利益遡及適用に関する一考察~土地建物等の譲渡に関わる損益通算廃止規定の遡及適用に係る判例を通して~
税法における権利確定主義と管理支配基準についての一考察
所得税と相続税との関係の考察 ~長崎生保年金事件を素材として~
法人税法における貸倒損失
2014(平成26)年度馬券の払戻金に対する課税のあるべき姿についての一考察
法人税法における所得の年度帰属に関する研究
事業所得における必要経費についての一考察 ~家事費及び家事関連費を中心として~
法人税法における寄附金~固定概念とされる寄附金とその役割に関する一考察~
2015(平成27)年度株式会社の企業価値とコーポレート・ガバナンスに関する一考察ヘイトスピーチの法規制に対する検討課税単位と配偶者控除についての一考察 ~給付付き税額控除の導入の検討~収入金額の年度帰属に関する一考察 ~権利確定主義と管理支配基準の関係について~給与所得者と申告納税制度に関する一考察 ~特定支出控除制度を中心として~恒久的施設概念についての一考察 ~電子商取引における問題点を中心に~租税回避に対する否認規定の在り方 ~法人税を中心として~租税法における住所の意義の一考察
2012(平成24)年度消費税法第30条における保存と提示に関する一考察 ~租税法律主義の観点から~
給与所得課税制度の研究~申告納税制度のものでの源泉徴収・年末調整制度の選択を中心として~
所得税法第56条の現代的および将来的意義の考察 ~夫婦弁護士事件、夫弁護士・妻税理士事件を通じて~
法人事業税における外形標準課税に関する一考察
所得税法における遡及適用の合憲性に関する一考察
相続時精算課税制度の研究~シャウプ勧告における累積的取得税方式と現行相続時精算課税制度の比較において~
給与所得控除制度についての考察
所得税法60条に関する一考察 ~相続により移転する資産に係る譲渡所得課税の在り方~
役員給与課税に関する諸問題 ~法人税法34条1項2項の問題点を中心として~
所得税法64条2項についての一考察 ~「求償権行使不能」を中心として~
企業の整理・再建時における法人税法の課税上の諸問題
フリンジ・ベネフィット課税についての一考察
法人税法第22条第2項の無償取引についての一考察 ~現代的意義としての検討~
人間の発達と障がい児の教育権について
6 GRADUATE SCHOOL OF LAW
![Page 7: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/7.jpg)
2019 札幌学院大学 大学院法学研究科[修士課程]教員プロフィール� (2019年4月1日現在)
伊 藤 雅 康 (いとう まさやす)
最 終 学 歴 / 名古屋大学大学院法学研究科博士後期課程
学会等の活動 / 日本公法学会会員全国憲法研究会会員
担 当 科 目 / 憲法特講AⅠ·AⅡ同演習AⅠ·AⅡ·AⅢ
●研究テーマ
現代憲法の今後のあり様を考えるひとつの素材として、フランス憲法の労働者の経営参加権をめぐる制度の動態と理論を検討するとともに、日本における労働基本権の保障の内容について検討している。また、日本の平和主義や選挙制度にかかわる諸問題にも強く関心を持っている。
岡田久 美 子 (おかだ くみこ)
最 終 学 歴 / 一橋大学大学院法学研究科博士後期課程
学会等の活動 / 日本刑法学会日本法社会学会など
担 当 科 目 / 刑事訴訟法特講
●研究テーマ
性犯罪の構成要件および事実認定のあり方について、アメリカの証拠法などを参照しつつ検討している。
石井 和 平 (いしい わへい)
最 終 学 歴 / 小樽商科大学大学院商学研究科後期課程修了
〔博士(商学)〕
学会等の活動 / 北海道自治体学会
担 当 科 目 / 政治学特講Ⅰ・Ⅱ同演習Ⅰ
●研究テーマ
地域経営、住民自治、コミュニティ論
荻 野 昭一 (おぎの しょういち)
最 終 学 歴 / 早稲田大学大学院法学研究科修士課程修了
学会等の活動 / 上場会社顧問、特定NPO法人の金融経済教育監修
担 当 科 目 / 商法特講AⅠ・AⅡ同演習AⅠ・AⅡ・AⅢ
●研究テーマ
会社法と金融商品取引法の交錯分野の研究、金融商品取引法のエンフォースメントに関する研究
神 谷章 生 (かみたに あきお)
最 終 学 歴 / 大阪市立大学大学院法学研究科博士課程単位取得退学
学会等の活動 / 日本政治学会会員日本行政学会会員日本比較政治学会会員日本地方自治学会会員日本社会福祉学会会員
担 当 科 目 / 行政学特講Ⅰ・Ⅱ同演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●研究テーマ
グローバリゼーション下の福祉国家の行政システム比較福祉国家論
川股 修 二 (かわまた しゅうじ)
最 終 学 歴 / 北海道大学大学院法学研究科博士課程
〔博士(法学)〕
学会等の活動 / 日本税法学会会員租税訴訟学会理事日本相続学会理事など
担 当 科 目 / 税法特講AI・AⅡ同演習AI・AⅡ・AⅢ
●研究テーマ
研究者である側面と税理士(実務家)としての側面から租税法と信託法の交差するところを研究している。
清 水 敏 行 (しみず としゆき)
最 終 学 歴 / 北海道大学大学院法学研究科博士課程
〔博士(法学)〕
学会等の活動 / 日本政治学会、韓国政治学会など
担 当 科 目 / 国際関係論特講Ⅰ・Ⅱ同演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●研究テーマ
現代韓国政治を研究している。その中でも民主化以降の政治と市民社会について研究している。
横 路 俊 一 (よこみち しゅんいち)
最 終 学 歴 / 慶應義塾大学大学院法務研究科法務専攻修了
〔法務博士(専門職)〕
学会等の活動 / 日本民事訴訟法学会仲裁ADR法学会
担 当 科 目 / 民事訴訟法特講Ⅰ
●研究テーマ
民事調停法、民事訴訟法、倒産法。
田處 博 之 (たどころ ひろゆき)
最 終 学 歴 / 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程単位取得退学
担 当 科 目 / 民法特講CⅠ・CⅡ同演習CⅠ・CⅡ・CⅢ
●研究テーマ
損害賠償責任の契約による排除または制限に対しての諸国の判例・学説の対応をみることを通して契約自由のあり方を比較法的に検討している。
小 幡 宣 和 (おばた のぶやす)
最 終 学 歴 / 北海道大学大学院法学研究科博士後期課程
〔博士(法学)〕
学会等の活動 / 日本公法学会日本建築学会など
担 当 科 目 / 行政法特講Ⅰ・Ⅱ
●研究テーマ
行政法、環境法。特に歴史的環境保全の法制度を比較法的に研究している。
小 澤 隆司 (おざわ たかし)
最 終 学 歴 / 早稲田大学大学院法学研究科博士後期課程修了
〔博士(法学)〕
学会等の活動 / 法制史学会日本公法学会全国憲法研究会所属
担 当 科 目 / 日本法制史特講Ⅰ・Ⅱ同演習Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ
●研究テーマ
近代法学の言語はわれわれ自身の言葉になっているか。こうした問題意識の下に自由民権法学の代表者馬場辰猪の法学啓蒙の軌跡に日本近代法学の知的起源をたずねた。さらに近時は憲法史・刑法史・商法史等の諸領域を横断しながら日本近代法史学史の学問的反省を試みている。
SAPPORO GAKUIN UNIVERSITY 76 GRADUATE SCHOOL OF LAW
![Page 8: 大学院 法学研究科 [修士課程]€¦ · 目的をもちその実現に向けて努力することを惜しまない 者の入学を多いに歓迎致します。 札幌学院大学](https://reader034.fdocuments.net/reader034/viewer/2022052011/60279bcc16c8314f1c1bebfa/html5/thumbnails/8.jpg)
〒069-8555 北海道江別市文京台11番地TEL.(011)386-8111(代表)
http://www.sgu.ac.jp●
札幌学院大学大通サテライト〒060-0042 札幌市中央区大通西6丁目3-1
(札幌ルーテルセンター 5F)TEL.(011)280-1581
札幌学院大学大通サテライト(札幌ルーテルセンター 5F)
札幌学院大学までの交通機関
●JR札幌から〔普通・快速〕江別・岩見沢・滝川・旭川行に乗車大麻下車(普通15〜23分、快速12分)大麻駅南口より徒歩10分
●地下鉄(札幌市営 東西線)大通から新さっぽろ行に乗車新さっぽろ下車(20分)新さっぽろ駅からバスに乗り継ぎ10分
●バス(ジェイアール北海道バス)⑴新札幌バスターミナル北レーン10番乗り場から大麻11丁目・ゆめみ野東町・江別駅・情報大学前・野幌運動公園・(大麻駅南口先廻り)新札幌駅行に乗車北翔大・札学院大前下車(10分) 徒歩5分⑵新札幌バスターミナル北レーン10番乗り場から (学院大正門前先廻り)新札幌駅行に乗車学院大正門前下車(10分) 徒歩1分
●バス(夕鉄バス)⑴新札幌バスターミナル北レーン12番乗り場からあけぼの団地・南幌東町・栗山駅前・夕張南部行に乗車北翔大・札幌学院大下車(10分) 徒歩5分⑵新札幌バスターミナル北レーン12番乗り場から文京台南町・文教通西行に乗車学院大正門前下車(10分) 徒歩1分
札幌学院大学大通サテライトまでの交通機関
●地下鉄(札幌市営)大通駅(1番出口)より徒歩5分
大学院法学研究科のディプロマ・ポリシー(学位授与方針)
本研究科のカリキュラムに基づき、その成果を修士論文、又は特定課題研究論文としてまとめ、以下の観点からの評価に基づき審査に合格した者に修士(法学)の学位を授与します。
1�問題を的確に把握し、より賢い解決に導く能力を身につけていること。
2�法学や政治学に関する高度な専門的素養を修得していること。3�現実の社会において有用な高度の理論と実務能力を備えていること。
4�論文作成にあたって問題意識が明確であり、結論に至るまでの理論構成が一貫していること。
大学院法学研究科のカリキュラム・ポリシー(教育課程編成方針)
ディプロマ・ポリシーで掲げた目標を達成するための教育課程編成は次の通りである。
1�修士論文の執筆に向けて指導教授・院生間の双方向教育を重視するとともに、問題を的確に把握し、解決する能力を身につけさせるという教育の観点から、1年次後期から2年次前期・後期にかけて履修する演習科目6単位を必修とする。
2�高度な専門的な研究能力と実務的な実践能力を身につけさせるため、公法科目、民事法科目、政治・国際科目をバランスよく体系的に編成する。
3�税理士資格の取得を目指す税法専攻の院生の教育を強化するために、「税法特講」の開講に加えて、実務家教員による「税法各論特講」を配置する。
大学院法学研究科のアドミッション・ポリシー(入学者受入方針)
国際社会および地域社会の発展に貢献しようとする、以下のような方を求めます。
⑴�法学や政治学研究を通じて、大学や研究所等で研究・教育に従事したいと考える人。
⑵�実務に役立つ高度な理論および能力を通じて、行政や民間企業の法務セクション・スタッフとして従事したいと考える人。
⑶�税法務分野の担い手として、納税者の人権擁護および税制、税務行政の民主化に寄与したいと考える人。
⑷�高度な教育資格取得を通じて、教育の発展に寄与したいと考える人。