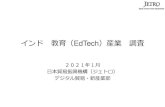日系海外現地法人の企業内貿易に関する実証分析(未定稿) 1...
Transcript of 日系海外現地法人の企業内貿易に関する実証分析(未定稿) 1...
-
(未定稿)
1
日系海外現地法人の企業内貿易に関する実証分析
大阪府立産業開発研究所
丸山 佐和子
1.はじめに
プラザ合意を契機とした円高を背景に,わが国企業は積極的な海外進出を行うようにな
った.海外進出の目的も貿易摩擦や為替差損を回避するための生産拠点の設立のほか,現
地市場向けの生産拠点や日本国内市場向けの生産拠点,あるいは海外販路開拓のための拠
点など,近年では多様になっている.
このような企業の海外事業展開に関する分析は,主に多国籍企業の行動に関する研究と
して行われてきた.海外事業の展開の背景には,多国籍化により海外の資源や生産要素を
活用し,生産コストが低下するメリットを享受できることが挙げられる.実際,バブル経
済崩壊後にもわが国企業の海外進出はこの目的の下に盛んに行われており,大企業のみな
らず中小企業においても海外展開がアジアを中心に進んでいる.わが国企業の海外進出に
は,海外現地法人と親会社のあいだでの工程間分業を伴うものが少なくない.その結果,
国際貿易では特に中間財貿易の活発化が観察される.
しかしながら,実際に海外進出を行っている企業の取引構造については依然分析の余地
が残されている.企業の海外取引の構造を把握できるようなデータが限られていること,
また得られるデータは集計データがほとんどで企業レベルでの動向を分析するには十分で
はないことがその理由として挙げられる.
そこで本論では,企業の海外取引に関するデータが収集されている『海外事業活動基本
調査』の個票データを用い,海外現地法人を有する企業の取引の構造について分析を行う.
海外現地法人はグループ企業とのあいだでどのような取引関係を構築し,どのような形で
親会社の活動に結びついているのかを明らかにすることが本論のねらいである.本論では
親会社・海外現地法人の取引に注目し,海外現地法人の行っている企業内貿易1についての
分析を行う.また,この現地法人企業の取引自体がどのような要因によって説明されるか
という点も,親会社との関係を考えるうえで重要である.
本論の構成は以下のとおりである.第2節では企業内貿易に関する先行研究のサーベイ
と,本論の分析で使用する統計について述べる.第3節では海外現地法人の販売・調達そ
れぞれについて,企業内貿易がどの程度を占めているかを分析する.第4節では海外現地
法人の企業内貿易を決定する要因についての回帰分析を行う.第5節では分析の含意と今
本論文は,近畿経済産業局の平成 18年度委託事業「近畿企業の国際化と生産性に関する実態調査」(大
阪府立産業開発研究所受託)として実施した研究に加筆・修正を施したものである. 1 なお,企業内貿易は一般に財が国際移動するケースを指すが,『海外事業活動基本調査』では同一企業
グループ内の現地での取引(すなわち貿易は発生しない)も調査対象としている.以下の分析では,「企
業内貿易」には現地でのグループ企業内の取引を含んでいる.
-
(未定稿)
2
後の課題を述べる.
2.先行研究と統計
2-1 企業内貿易の先行研究
2-1-1 理論的分析
企業の海外事業展開に関する分析は,主に多国籍企業の行動に関する研究として行われ
てきた.企業が多国籍化する背景を説明する代表的な理論に,Dunning(1977)による「O
LIパラダイム」もしくは「折衷理論」と呼ばれるものがある.企業が大きく3つの優位
性を持つとき,すなわち[1]その企業がもつ技術力やマーケティング能力,ノウハウと
いった経営資源の所有について他社に対し優位性があるとき(Ownership Advantage),[2]
相手国の市場規模や生産要素の賦存状況,インフラストラクチャーといった立地上の優位
性があるとき(Location Advantage),[3]海外に子会社を設立することで,(市場を通じ
て)グループ外の海外企業から調達を行うよりも低いコストでの取引が見込めるという,
企業組織の内部化による優位性があるとき(Internalization Advantage),その企業には
海外での事業活動を行うインセンティブが働く.
Dunning の折衷理論は実際には体系的な理論として構築されたものではなく,経験的に
得られた事実をまとめあげたものであるといえよう.より体系的なものとしては,貿易理
論からのアプローチが挙げられる.貿易理論では企業が海外に進出する動機として,関税
や輸入制限等の貿易障壁,為替レートの変動による交易条件の悪化などが存在することに
より,現地に子会社を設立し生産を行うほうがコストが低下するケースが考えられる .こ
の例としては,完成車に高関税を課されるために海外に生産工場を設け,現地で販売する
ことが多い自動車産業が挙げられる.また,1985 年のプラザ合意以降の円高を契機として
わが国企業でも海外に生産拠点を設ける動きが活発化したが,これは円高により日本から
の輸出がグローバルな経済環境の下で不利になったためである.
さらに従来の貿易理論に独占的競争を導入した新貿易理論では,規模の経済性の存在に
よる貿易の発生を説明し,そのなかで企業内貿易の発生のメカニズムについても述べてい
る(Helpman and Krugman, 1985).企業内貿易は同一の企業内で工程間の国際分業を行う
ことにより発生する,企業内部での貿易である.多国籍企業の活動が世界的に活発化する
なか,多国籍企業内部での財の流れは世界経済において重要な役割を果たしている.
2-1-2 実証的分析
実証分析を含むものとしては,例えば Braunerhjelm and Ekholm (ed.)(1998),Navaretti
and Venables (ed.)(2004),Markusen(2004)などが挙げられる.
近年ではわが国企業の事業活動についてもミクロベースのデータを用いた実証分析が行
われているが,経済産業省の承認統計『海外事業活動基本調査』は親会社および現地法人
-
(未定稿)
3
企業の国際取引を捉えているという点で,企業内貿易の分析に適した統計である.このデ
ータベースを用いた先行研究では,木村・安藤(2004),Ando and Kimura(2005)が機械
産業における国際生産ネットワーク形成の変化を分析している.このなかでは,日本企業
が東アジアにおいて,企業内貿易(intra-firm trade)と企業間貿易(arm’s length trade)
をうまく組み合わせた生産を行っているという結果が示されている.
海外現地法人の取引については,バックワード・リンケージに関する分析も行われている.
例えば,Kiyota et al.(2005)では同データベースを用い,現地調達に焦点を当てた分析
を行っている.この分析でも,現地調達率と企業特性・国特性との関係を分析している.
また,佐々波・河井(1998)では現地販売比率といった海外現地法人の取引を分析し,さら
に企業内での輸入が海外現地法人の効率性を高めるといった結果を示している.
このように企業内貿易の分析はいくつか行われているが,企業単位での企業内貿易の分
析は十分に行われているとは言い難い.また,現地調達の拡大がいくつかの研究で報告さ
れているが,企業内貿易についてもどのような変化をたどっているか分析する必要はある
だろう.
2-2 使用する統計
本論の分析には『海外事業活動基本調査』個票データを用いている.経済産業省の承認
統計である『海外事業活動基本調査』は海外現地法人を有するわが国企業とその海外現地
法人を対象とした統計調査で,親会社・現地法人の双方の情報を含んでいる.
同調査では,詳細な設問項目を盛り込んだ基本調査を3年ごとに実施している.基本調
査では企業内貿易の割合や技術取引の実施状況といった企業の事業活動が報告されている
が,経済産業省による報告書ではこれらの集計値のみが報告されており,企業ごとの動向
を知ることはできない.しかしながら,企業内貿易の実施の程度は企業ごとに異なると考
えられ,それを決定する要因を分析する上では企業ベースのデータが不可欠である.
この点に関しては,同調査の個票データを用いることで,親会社・現地法人企業のそれ
ぞれについてミクロレベルの分析を行うことが可能となる.本論の分析では個票データを
用いた独自の集計及び回帰分析を行っている.回帰分析には,同調査の現地法人企業のパ
ネルデータを用いる2.さらに各現地法人にそれぞれ振られている親会社の永久企業番号を
もとに,親会社データベースの情報を現地法人データベースに接続し,従業者規模といっ
た親会社の情報を現地法人の情報に加えている.
本論の分析では企業内貿易に関する設問の設けられている基本調査年1995年,1998年,
2001 年の三時点を対象とする.また,同調査の対象企業は膨大な数であることから,本論
では近畿に親会社本社が所在する海外現地法人のうち製造業に属する企業に分析対象を限
定している.
2 『海外事業活動基本調査』個票データを用いたパネルデータ作成については,松浦(2004),松浦・永
田(2006)を参照.
-
(未定稿)
4
3.海外現地法人における企業内貿易の実態
本節では海外現地法人で企業内貿易がどの程度行われているかを分析する.企業内貿易
の実施比率を企業ごとに算出し,その結果から実施比率階級別に企業の構成比を算出した.
表1は販売,表2は調達についての結果である3.
= 表1,表2を挿入 =
3-1 販売での企業内貿易
まず販売についてみると,販売全体(全地域)において企業内貿易を行っている企業(0%
超~100%の合計)は全体の5割超を占める.企業内貿易の実施の有無については,調査対
象年や現地法人の立地地域による違いはほとんどみられない.
違いがみられるのは取引地域を①現地向け,②日本向け,③第三国向けに分けた場合で
ある4.企業内貿易を実施する企業が最も多いのは②日本向けで,③第三国向けがそれに続
いている.輸出を伴うこれら2つのケースについては企業内貿易を実施する企業の割合は
大きい.①現地向けの販売で企業内貿易を実施しない企業が全体の7~8割と高いが,現
地販売が現地の顧客企業や消費者に向けたものが一般的であることを考えると,現地向け
でグループ内の取引がほとんど行われないのは当然であるといえよう.
企業内貿易の実施企業が最も多い②日本向けの販売については次のような2つの傾向が
ある.第一に,アジアに立地する現地法人では北米・ヨーロッパの現地法人に比べ企業内
貿易実施の程度は低い.売上高の 100%が企業内貿易であるような企業の割合はアジアが
最も低く,また企業内貿易を実施していない企業の割合もアジアが高い傾向にある.この
ことから,アジア現地法人ではグループ外の日本企業への輸出も盛んであることがうかが
われる.第二に,三時点を比較すると,売上高の 100%が企業内貿易であるような企業割
合の低下,企業内貿易を実施していない企業割合の拡大といった傾向がみられ,企業内貿
易の割合は低下傾向にあると考えられる.
③第三国向けの販売については,アジア現地法人で企業内貿易が拡大する傾向にある.
3-2 調達での企業内貿易
次に調達についてみると,企業内貿易を行わない企業の割合が1995年には全体の40.1%
を占めていたのが,2001 年には 47.9%に拡大している.また,調達のすべてを企業内貿易
3 なお,ここでの分析は販売もしくは調達(取引地域内訳については当該地域とのあいだの販売もしくは
調達)のある企業を分析対象としている.1995年,1998 年,2001 年の三時点について,売上高・仕入高
ともに回答のある各現地法人が取引のうち同一企業グループ内で行っている割合を算出した. 4 以下ではその取引地域との取引のある企業のみをみていく.
-
(未定稿)
5
でまかなうような企業の割合も縮小しており,全体としては企業外取引で調達を行う企業
が増加している.
調達全体(全地域)を現地法人の立地地域別にみると,北米およびヨーロッパで企業内
貿易が縮小傾向にあることがわかる.調達ではこのような変化が明確であることが販売と
の違いとして挙げられる.
調達先地域を①現地から,②日本から,③第三国からに分けると,販売と同様に③現地
からの調達ではグループ内の取引がない企業がほとんどを占めている.
企業内貿易がもっとも盛んである②日本からの調達についても,アジア現地法人では企
業外取引のみの企業割合が北米・ヨーロッパよりも高く,北米・ヨーロッパ現地法人につ
いては企業外取引が拡大する傾向にある,というように,立地地域別では販売とほぼ同様
の傾向が挙げられる.
③第三国からの調達についてはアジア現地法人で企業内貿易が拡大しているほか,北
米・ヨーロッパでも調達の 100%が企業内貿易であるような企業は増えている.
3-3 企業内貿易の傾向
以上の結果から,現地法人の企業内貿易の傾向として次の点が挙げられる.
第一に,1995 年,1998 年,2001 年の三時点を比較すると,全体として企業内貿易を実
施する企業割合が縮小し,企業外取引が拡大する傾向にある.
第二に,企業内貿易が最も盛んである取引地域は,販売・調達とも日本との間である.
企業内貿易が日本との取引で盛んであるという事実は,現地法人の事業活動において日本
の親会社とのつながりが重要であることを示唆している.
第三に,日本との間の取引においては,立地地域による差がみられる.企業内貿易の実
施はアジア現地法人で他の二地域よりも低い割合である.アジアは日本向けの販売・調達
を行う企業の割合が高い地域であるが,その取引はグループ外企業との間でも活発である
と考えられる.北米・ヨーロッパにおいてはアジアよりも企業内貿易実施の割合が高いも
のの,三時点を比較すると縮小傾向にある.
第四に,第三国との取引においては企業内貿易が拡大するようなケースもみられる.
4.企業内貿易の決定要因
海外現地法人の企業内貿易は立地地域により差異がみられるほか,企業外取引が拡大す
る傾向にあることが明らかになった.これらの特徴はどのような要因によるものだろうか.
本節では各海外現地法人の企業内貿易について,回帰分析によりその決定要因を検証する.
現地法人においては企業内貿易が生じるのは次のような場合である.まず,日本向けの
生産を行うような拠点では,日本の親会社から部材を調達して生産を行い,加工品を日本
-
(未定稿)
6
向けに輸出するような場合には,企業内貿易は双方向で生じうる.また,日本の親会社か
ら部材を調達して生産を行う場合であっても,現地での販売が主である場合には,企業内
貿易は調達の一方向のみでしか生じない.
実際,現地法人の調達先は現地で調達を行うケースや日本から行うケースなどさまざま
で,販売先地域も企業によってパターンが異なる.このため取引を同一グループ企業との
あいだで行うかは,現地法人設立の目的や設立国の状況,産業特性,企業特性など,さま
ざまな要因が影響すると考えられる.本節の分析では企業ごとの個票データを用いること
で,産業や進出先国による違いのみならず,各企業ごとの属性を要因として用いた実証分
析を行う.
4-1 分析のフレームワーク
従属変数である企業内貿易には,現地取引を含めた取引全体における企業内貿易[モデ
ル a]と海外との貿易取引に限定した(現地取引を除いた)企業内貿易[モデル b]の2つ
を設定する.さらに[モデル a],[モデル b]を①取引全体(販売および調達),②販売,
③調達の3つのパターンにそれぞれ分け,合計で6つのケースを設定する(表3).各ケー
スの企業ごとの取引比率を従属変数とし,独立変数には国特性としてグラヴィティ・モデ
ルの基本要因,現地法人企業の特性を表す要因,親会社特性の要因を用いた.
= 表3を挿入 =
4-1-1 グラヴィティ・モデルの基本要因
グラヴィティ・モデル(gravity model)は,経済規模や地理的距離などを基本要因とし
て二国間貿易の貿易量を説明するモデルである.グラヴィティ・モデルの特徴は,地理的
距離を取り入れることで,多くの貿易モデルでゼロと仮定されている輸送コストを扱って
いる点である.Tinbergen(1962)は貿易量を決定する基本要因として,距離のほかに経済
規模・市場規模を挙げている.経済規模が大きければ供給量はより大きくなり,また市場
規模が大きければより多くの販売が可能になるので,この2つの要因が大きいほど貿易量
は多くなる.一般に経済規模(あるいは供給規模)は輸出国のGDP,市場規模は輸入国
のGDPで表される.これらの3つの基本要因と貿易量の関係は,次のように表される.
(eq.1) 3210aij
aj
aiij DYYaE
ここでYは輸出国あるいは輸入国のGDP, ijD は地理的距離を含む貿易障壁を表す.
Linnemann(1966)は Tinbergen の基本モデルを拡張し,次式のように人口や貿易に対す
る優遇措置,関税などの貿易障壁を貿易の決定要因に加えている.
-
(未定稿)
7
(eq.2) 6543210aij
aij
aj
ai
aj
aiij DPNNYYaE
ここで N は輸出国あるいは輸入国の人口, ijP は貿易優遇措置を表す.
これらの国特性を表す要因として,地理的距離として二国間距離,輸出国・輸入国のG
DPもしくは1人あたりGDPを用いる.推定する従属変数が取引額ではなく割合である
ため,各要因に期待される符号条件は必ずしも明確ではないが,貿易に対して与える影響
は次のように考えられる.
二国間距離(DIST )は地理的・時間的コストを表し,貿易障壁であることから負の符号が期待される.
現地法人の輸出に対しては,輸入国である日本のGDP( JPRGDP )の拡大は輸出の増加をもたらすことから,正の符号条件が予想される.一方で輸出国である現地法人受入
国のGDP( HSRGDP )については,供給力を表す指標と捉えた場合には輸出の増大に結びつき正の影響が予想されるが,需要の大きさを表す指標と捉えた場合には現地販売が
増加し輸出比率が低下することから負の影響を与える可能性も考えられる.現地法人の輸
入についても,需要国である受入国のGDPは正の符号条件が予想され,供給国である日
本のGDPの符号条件は正と負の両方の可能性が考えられる.
1人あたりGDPは各国の所得水準を表すことから,労働コストの代理変数と捉えられ
る.生産の工程間分業に伴って発生する貿易の場合,受入国の労働コストの上昇は現地で
生産するインセンティブの低下を表し,受入国の1人あたりGDP(HSGDPPER )は貿易に対しても負の影響を与える.一方で日本の1人あたりGDP( JPGDPPER )の上昇は海外生産を促す一因であると考えられ,現地法人の輸出を拡大する正の符号が期待され
る.GDPと1人あたりGDPの間の相関が比較的高いことから,それぞれのモデルにつ
いてGDPのみを要因とした場合と1人あたりGDPのみを要因とした場合のそれぞれに
ついて回帰を行っている.
ここでは貿易に対して各要因が与えるであろう影響を述べたが,[モデル a]の従属変数
は取引全体を含むものであり貿易には限定されない.しかしながら企業内貿易は海外向け
が中心であることから,これらの要因が[モデル a]で与える影響については貿易のケー
スとほぼ同様であることが予想される.
4-1-2 企業特性
企業特性としては現地法人企業特性を表す要因,親会社特性の要因をそれぞれ用いてい
る.
現地法人企業の特性としては,操業年数(LCYEAR),日本側出資比率( JPCAP ),従業者数( LCEMP ),日本向け支払金額( PAYJPVL )もしくはロイヤルティ支払金額( ROYALTY)を用いる.現地法人企業特性は企業内貿易に対し次のような影響を与える
-
(未定稿)
8
と考えられる.
操業年数が長いほど取引相手企業,特に企業グループ外の取引が拡大することが予想さ
れる.このため操業年数についてはマイナスの符号が予想される.従業者数は企業の規模
を表し,規模が大きければ供給できる製品の量が増加し,また規模の経済性が期待できる
ことから,取引に対しては正の影響を与えると考えられる.日本側出資比率および日本向
け支払金額は,日本の親会社との関係を表す指標である.独資で設立された場合など,日
本側出資比率が高いほど親会社の結びつきが強く,企業内での取引も活発であることが期
待される.日本向け支払金額には配当金支払,知的財産権等のロイヤルティ支払などが含
まれる.ロイヤルティの支払は企業内での技術移転が行われることを示しており,それに
伴い生産拠点を日本から現地に移管するケースなどが考えられることから,企業内貿易も
増加すると予想される.
親会社の特性としては,従業者数( HQEMP ),売上高輸出比率( HQEXRT )を用いている.現地法人企業と同様,従業者数は企業の規模を表すことから,企業内取引におい
て正の影響を与えると予想される.
売上高輸出比率は海外販売の比率を表し,この比率が高いほど親会社の取引のグローバ
ル化が進んでいると考えられる.グローバル化の進展度と企業内貿易の程度の間の関係は
明らかではないが,次の二通りの可能性が考えられる.グローバルな展開を行なっている
企業においては企業グループ内部で取引を行うほうが取引費用が低くなる場合,それに伴
い財の取引が増加し,その結果企業内貿易の比重が大きくなることが考えられる.反対に,
海外よりも日本国内市場に向けた販売を主に行うような場合でも,途上国で安価な労働力
を利用して生産を行いその製品を日本に輸出するのであれば,企業内貿易の比重が大きく
なることも考えられる.
4-1-3 推定方法
回帰分析では非線形最小二乗法による推定を行う.従属変数に用いる各指標は比率であ
り0から1の間の値をとるため,関数形には次のようなロジスティック関数を仮定し,非
線形最小二乗法を用いた.
(eq.3) )exp(1
1x
E
ここで はパラメータ, x は独立変数のベクトルである.
4-1-4 データ
『海外事業活動基本調査』は毎年実施される統計調査であり,多くの項目が共通の設問
となっているためパネルデータの作成が可能である.ここでは企業内貿易に関して詳細な
設問項目が設けられる基本年(1995 年,1998 年,2001 年の3年)のデータを用いてパネ
-
(未定稿)
9
ルデータを作成した5.
従属変数・独立変数として用いたデータとその出所は表4,独立変数間の相関マトリッ
クスは表5の通りである.独立変数として用いている親会社特性,国特性については,同
一の親会社あるいは同一の国に立地する複数の現地法人の間で同一の値となるため,固定
効果・変量効果モデルによるパネル分析を行うことができない.このため,回帰分析では
作成したプールドデータとして非線形最小二乗法を用いて推定している.
= 表4,表5を挿入 =
4-2 推定結果
各企業内貿易の比率について非線形最小二乗法により回帰分析を行った結果,現地取引
を含めた場合[モデル a]については表6,現地取引を除いた場合[モデル b]については
表7の結果が得られた.
= 表6,表7を挿入 =
まず[モデル a]についてみると,①取引全体,②販売,③調達のいずれのケースにお
いても有意であったのは現地法人企業特性の日本側出資比率( JPCAP )で符号は正,操業年数( LCYEAR)で符号は負,国特性の二国間距離( DIST )で符号は負であった.一方で,ロイヤルティの支払(ROYALTY)についてはいずれのケースにおいても有意とならず,企業内貿易との間に強い関係を持たないと考えられる.また,親会社の特性につ
いては有意な結果はほとんど得られなかった.
①取引全体を②販売,③調達を分けた場合にはいくつかの要因が販売と調達で反対の影
響を与えるという結果が得られた.第一に,操業期間( LCYEAR )が長いほど販売に占める企業内貿易は縮小するが,調達に占める企業内貿易は拡大するという結果が得られた.
ここから販売においては,現地法人が操業を続けるなかで取引相手を企業グループ外に広
げていく傾向を読み取ることができる.第二に,現地法人の従業者規模(LCEMP )は販売に正,調達に負の影響を与える.このように正反対の方向に作用するため,取引全体で
みた場合には有意な結果が得られなかった.第三に,GDPに関連する国特性要因で有意
となったものについては,受入国GDP(HSRGDP )は販売のみに負の影響,日本GDP( JPRGDP )は調達のみに対し負の影響を与えている. [モデル b]の貿易に限定した場合には,①総貿易に占める企業内貿易の割合に対して
は,日本側出資比率,現地法人従業者数,親会社の売上高輸出比率,二国間距離の4つが
影響を与えるという結果が得られた.②輸出に限定した場合には,影響を与える要因は日
5 パネルデータの作成にあたり,同一企業であるにもかかわらず回答内容の異なる点については,最頻値
を用いて修正・統一した.主な修正項目は「設立・資本参加時期」「国分類」「業種分類」である.
-
(未定稿)
10
本側出資比率,親会社の売上高輸出比率,二国間距離,受入国の1人あたりGDPである.
③輸入に関しては,受入国・日本の1人あたりGDP以外のすべての要因が有意となって
いる.また,貿易に限定した場合でも,輸出と輸入では操業年数及び現地法人の従業者規
模が正負逆の影響を与えているという結果が得られた.
また,[モデル a]では有意でなかった親会社の売上高輸出比率(HQEXRT )が,①~③のいずれのケースでも負で有意となっている.グローバルな取引の実施状況を表す指標
である売上高輸出比率は企業内貿易との間でマイナスの関係があり,親会社が幅広く海外
展開を行っている場合には国境をまたがる企業内貿易は減少する傾向にある.企業の多国
籍的な展開により企業内貿易は促進されるとの予想とは異なる結果であるが,グローバル
化の進んだ親会社が現地法人を企業内貿易という形で活用するのではなく,現地法人自身
も独自にグローバルな活動を展開していると考えられる.この場合,グループ企業を通じ
た貿易よりも直接貿易を行うほうが貿易コストが小さくて済むならば,企業内貿易の割合
は低下する.
5.むすび
以上,本論では日本企業の設立した海外現地法人の企業内貿易の傾向を分析,そしてそ
の決定要因について回帰分析による検証を行った.
現地法人の企業内貿易の特徴としては,企業内貿易を実施する企業割合が全体としては
縮小し企業外取引が拡大する傾向にあること,企業内貿易が最も盛んなのは販売・調達と
も日本との取引においてであること,日本との間の企業内貿易の程度は立地地域による差
がみられることが挙げられる.
また,回帰分析の主な結果は次の四点である.
第一に,いずれのモデルにおいても日本側出資比率・二国間の地理的距離が企業内貿易
に影響を与えている.日本企業との間の資本関係は現地法人の取引と結びついており,出
資比率が高いほど取引も緊密化している.また,地理的距離が負の効果をもつという結果
から,現地法人のグループ企業との取引の可能性は立地地域にも左右されると考えられる.
第二に,販売と調達,あるいは輸出と輸入を分けた場合には,従属変数に対して相反す
る効果をもつ要因があることがわかった.そのひとつが操業年数で,現地法人が事業を続
けるなかで企業グループ外での販売(あるいは輸出)を拡大させ,結果としてグループ内
での取引の比重が低下している.反対に調達についてはグループ内での取引の比重が増し
ているという結果が得られた.
第三に,第一に挙げた点とは反対に,多国籍企業内の取引において重要な要因のひとつ
と考えられるロイヤルティについては,企業グループ内での取引に対しほとんど影響を与
えていない.この結果から,移転した技術は日本向けの生産よりもむしろ現地向けの生産
-
(未定稿)
11
に利用されている可能性が考えられる.
第四に,親会社との関係では,グローバル取引の多い親会社を持つ場合よりも,日本国
内向けの生産を行う親会社を持つ場合に,企業内貿易が拡大する傾向にある.この背景と
して,日本国内市場向けの製品を主とする親会社では海外の製造拠点を自社の生産に組み
込む傾向が強い一方で,グローバル化の進んだ親会社では現地法人での最適地生産もグロ
ーバルな取引を視野に入れたものとなり,グループ外企業との直接取引が増加することで
企業内貿易の比重が低下する可能性が考えられる.
本論の分析では新規設立企業の動向も含めるため,第3節の企業内貿易の動向の分析に
はパネルデータを用いなかった.今後の課題としては,企業ごとのパネルデータを用いて,
企業ごとに企業内貿易の傾向に変化があるかより詳細に確認することが挙げられる.
【参考文献】
Ando, M. and F. Kimura (2005) “Global Supply Chains in Machinery Trade and the
Sophisticated Nature of Production/Distribution Networks in East Asia”, KUMQRP
Discussion Paper Series, DP2005-015.
Braunerhjelm, P. and K. Ekholm (ed.) (1998) The Geography of Multinational Firms,
Boston: Kluwer Academic Publishers.
Dunning, J.H. (1977) “Trade, location of economic activities and the MNE: A search
for an eclectic approach”, In Ohlin B., P-O Hesselborn and P.M. Wijkman (ed.) The
international allocation of economic activity, London: MacMillan.
Helpman, E. and P.R. Krugman (1985) Market Structure and Foreign Trade ? Increasing
Returns, Imperfect Competition, and the International Economy, Cambridge: The MIT
Press.
Kiyota, K., T. Matsuura, S. Urata and Y. Wei (2005) “Reconsidering the Backward
Vertical Linkages of Foreign Affiliates: Evidence from Japanese Multinationals”,
RIETI Discussion Paper Series, 05-E-019.
Markusen, J.R. (2004) Multinational Firms and the Theory of International Trade ,
Cambridge: The MIT Press.
Navaretti, G.B. and A.J. Venables (ed.) (2004) Multinational Firms in the World
Economy, Princeton: Princeton University Press.
木村福成・安藤光代(2004)「東アジアの国際的生産・流通ネットワーク:日本企業のマイ
クロ・データを用いた統計的把握の試み」『経済統計研究』Vol.32 No.3 経済産業統計協
会.
佐々波楊子・河井啓希(1998)「欧州・アジア・北米における日本企業の海外事業展開」『三
-
(未定稿)
12
田学会雑誌』91 巻 2 号.
松浦寿幸(2005)「日系海外現地法人の経済活動規模,および販売・調達動向の推計~「海
外事業活動基本調査」による母集団推計の試み~」『経済統計研究』Vol.32 No.4 経済産
業統計協会.
松浦寿幸・永田洋介(2006)「日米海外現地法人の経済活動と国内雇用への影響-海外直接
投資データベースの作成による分析-」『経済統計研究』Vol.33 No.4 経済産業統計協会.
-
表1.現地法人の売上高総額に占める企業内貿易の割合ごとにみた企業の構成比 (単位:社,%)
販売先地域 販売全体(全地域) ①現地向け
子会社の立地地域 全体 北米 アジア ヨーロッパ 全体 北米 アジア ヨーロッパ
1995 年 100%の企業 72 (10.2) 9 (6.3) 54 (12.9) 6 (6.2) 46 (7.6) 9 (6.4) 22 (6.5) 13 (14.4)
50%以上 100%未満の企業 110 (15.5) 19 (13.2) 71 (16.9) 16 (16.5) 38 (6.2) 11 (7.9) 17 (5.1) 9 (10.0)
0%超 50%未満の企業 188 (26.6) 52 (36.2) 93 (22.2) 29 (29.9) 39 (6.4) 10 (7.1) 18 (5.4) 7 (7.7)
企業内貿易がない企業 338 (47.7) 64 (44.4) 201 (48.0) 46 (47.4) 485 (79.8) 110 (78.6) 279 (83.0) 61 (67.8)
合計 708 144 419 97 608 140 336 90
1998 年 100%の企業 96 (10.0) 11 (7.1) 72 (11.5) 8 (6.3) 82 (10.1) 13 (9.0) 47 (9.2) 18 (16.1)
50%以上 100%未満の企業 190 (19.8) 18 (11.6) 148 (23.6) 23 (18.1) 52 (6.4) 6 (4.2) 40 (7.8) 6 (5.4)
0%超 50%未満の企業 266 (27.7) 59 (37.8) 146 (23.3) 45 (35.4) 62 (7.7) 19 (13.2) 32 (6.2) 8 (7.2)
企業内貿易がない企業 407 (42.4) 68 (43.6) 260 (41.5) 51 (40.2) 617 (75.9) 106 (73.6) 394 (76.8) 80 (71.4)
合計 959 156 626 127 813 144 513 112
2001 年 100%の企業 117 (10.8) 14 (8.8) 83 (11.0) 12 (9.8) 69 (8.0) 8 (6.1) 47 (7.8) 11 (12.0)
50%以上 100%未満の企業 194 (17.8) 6 (3.8) 164 (21.8) 18 (14.7) 58 (6.7) 3 (2.3) 44 (7.4) 8 (8.7)
0%超 50%未満の企業 288 (26.4) 62 (38.8) 183 (24.3) 36 (29.3) 67 (7.7) 7 (5.3) 53 (8.8) 4 (4.4)
企業内貿易がない企業 489 (44.9) 78 (48.8) 324 (43.0) 57 (46.3) 672 (77.6) 114 (86.4) 455 (76.0) 69 (75.0)
合計 1088 160 754 123 866 132 599 92
販売先地域 ②日本向け ③第三国向け
子会社の立地地域 全体 北米 アジア ヨーロッパ 全体 北米 アジア ヨーロッパ
1995 年 100%の企業 235 (69.3) 53 (79.1) 154 (66.4) 21 (75.0) 88 (24.9) 25 (37.3) 43 (22.8) 13 (17.6)
50%以上 100%未満の企業 28 (8.2) 6 (9.0) 17 (7.4) 3 (10.7) 47 (13.3) 8 (12.0) 32 (16.9) 7 (9.5)
0%超 50%未満の企業 7 (2.1) 0 (0.0) 7 (3.0) 0 (0.0) 49 (13.8) 10 (14.9) 17 (9.0) 19 (25.7)
企業内貿易がない企業 69 (20.4) 8 (11.9) 54 (23.3) 4 (14.3) 170 (48.0) 24 (35.8) 97 (51.3) 35 (47.3)
合計 339 67 232 28 354 67 189 74
1998 年 100%の企業 380 (67.1) 66 (75.0) 269 (64.4) 41 (78.8) 136 (28.0) 19 (25.0) 92 (30.9) 12 (14.5)
50%以上 100%未満の企業 32 (5.6) 5 (5.7) 25 (6.0) 2 (3.8) 68 (14.0) 9 (11.8) 37 (12.4) 19 (22.9)
0%超 50%未満の企業 9 (1.6) 1 (1.1) 7 (1.6) 0 (0.0) 56 (11.5) 7 (9.2) 29 (9.8) 19 (22.9)
企業内貿易がない企業 145 (25.6) 16 (18.2) 117 (28.0) 9 (17.3) 226 (46.5) 41 (53.9) 140 (47.0) 33 (39.8)
合計 566 88 418 52 486 76 298 83
2001 年 100%の企業 374 (62.4) 53 (63.9) 287 (62.0) 27 (69.2) 202 (37.1) 23 (32.4) 154 (39.6) 16 (25.8)
50%以上 100%未満の企業 49 (8.1) 5 (6.0) 38 (8.2) 3 (7.7) 59 (10.9) 8 (11.3) 42 (10.8) 9 (14.6)
0%超 50%未満の企業 25 (4.1) 3 (3.6) 21 (4.5) 1 (2.6) 74 (13.6) 11 (15.5) 44 (11.3) 17 (27.4)
企業内貿易がない企業 151 (25.2) 22 (26.5) 117 (25.3) 8 (20.5) 209 (38.4) 29 (40.8) 149 (38.3) 20 (32.3)
合計 599 83 463 39 544 71 389 62
-
表2.現地法人の仕入高総額に占める企業内貿易の割合ごとにみた企業の構成比 (単位:社,%)
調達先地域 調達全体(全地域) ①現地から
子会社の立地地域 全体 北米 アジア ヨーロッパ 全体 北米 アジア ヨーロッパ
1995 年 100%の企業 82 (11.6) 15 (10.4) 48 (11.5) 14 (14.4) 24 (4.8) 3 (2.5) 14 (5.0) 4 (6.3)
50%以上 100%未満の企業 133 (18.7) 34 (23.6) 71 (16.9) 22 (22.7) 11 (2.2) 6 (5.0) 5 (1.8) 0 (0.0)
0%超 50%未満の企業 209 (29.5) 49 (34.0) 108 (25.8) 37 (38.1) 33 (6.6) 8 (6.7) 16 (5.7) 7 (11.0)
企業内貿易がない企業 284 (40.1) 46 (31.9) 192 (45.8) 24 (24.7) 435 (86.5) 102 (85.7) 247 (87.6) 53 (82.8)
合計 708 144 419 97 503 119 282 64
1998 年 100%の企業 87 (9.1) 14 (9.0) 56 (8.9) 14 (11.0) 27 (3.5) 4 (3.0) 21 (4.1) 2 (2.1)
50%以上 100%未満の企業 181 (18.9) 30 (19.2) 119 (19.0) 25 (19.6) 20 (2.6) 6 (4.6) 10 (2.0) 4 (4.3)
0%超 50%未満の企業 289 (30.1) 50 (32.0) 188 (30.0) 40 (31.5) 66 (8.5) 16 (12.1) 41 (8.1) 8 (8.5)
企業内貿易がない企業 402 (41.9) 62 (39.7) 263 (42.0) 48 (37.8) 662 (85.4) 106 (80.3) 437 (85.9) 80 (85.1)
合計 959 156 626 127 775 132 509 94
2001 年 100%の企業 92 (8.5) 14 (8.8) 59 (7.8) 14 (11.4) 33 (4.3) 8 (7.2) 23 (4.3) 1 (1.3)
50%以上 100%未満の企業 203 (18.7) 39 (24.4) 135 (17.9) 21 (17.1) 10 (1.3) 2 (1.8) 7 (1.3) 0 (0.0)
0%超 50%未満の企業 272 (25.0) 29 (18.1) 215 (28.5) 24 (19.5) 59 (7.7) 6 (5.4) 50 (9.3) 3 (3.9)
企業内貿易がない企業 521 (47.9) 78 (48.8) 345 (45.8) 64 (52.0) 658 (86.6) 95 (85.6) 459 (85.2) 73 (94.8)
合計 1088 160 754 123 760 111 539 77
調達先地域 ②日本から ③第三国から
子会社の立地地域 全体 北米 アジア ヨーロッパ 全体 北米 アジア ヨーロッパ
1995 年 100%の企業 308 (59.6) 80 (70.2) 158 (52.8) 54 (69.2) 80 (25.7) 25 (41.0) 33 (20.6) 13 (21.7)
50%以上 100%未満の企業 52 (10.1) 10 (8.7) 28 (9.4) 11 (14.1) 34 (11.0) 10 (16.4) 15 (9.4) 6 (10.0)
0%超 50%未満の企業 28 (5.4) 2 (1.8) 23 (7.7) 2 (2.6) 45 (14.4) 9 (14.8) 15 (9.4) 19 (31.6)
企業内貿易がない企業 129 (25.0) 22 (19.3) 90 (30.1) 11 (14.1) 152 (48.9) 17 (27.9) 97 (60.6) 22 (36.7)
合計 517 114 299 78 311 61 160 60
1998 年 100%の企業 397 (52.7) 77 (61.1) 239 (48.0) 66 (64.7) 119 (28.1) 30 (46.2) 62 (23.8) 16 (22.2)
50%以上 100%未満の企業 73 (9.7) 9 (7.1) 54 (10.8) 9 (8.9) 41 (9.7) 6 (9.2) 26 (9.9) 6 (8.3)
0%超 50%未満の企業 43 (5.7) 4 (3.2) 37 (7.4) 1 (1.0) 60 (14.2) 7 (10.8) 34 (13.0) 19 (26.4)
企業内貿易がない企業 240 (31.9) 36 (28.6) 168 (33.7) 26 (25.5) 204 (48.1) 22 (33.8) 139 (53.3) 31 (43.1)
合計 753 126 498 102 424 65 261 72
2001 年 100%の企業 376 (52.8) 55 (58.5) 260 (50.2) 49 (62.8) 168 (36.4) 26 (47.3) 109 (33.1) 25 (43.9)
50%以上 100%未満の企業 72 (10.1) 12 (12.7) 57 (11.0) 2 (2.6) 42 (9.2) 5 (9.1) 32 (9.8) 3 (5.3)
0%超 50%未満の企業 42 (5.9) 2 (2.1) 38 (7.3) 2 (2.6) 60 (13.0) 6 (10.9) 49 (14.9) 5 (8.8)
企業内貿易がない企業 222 (31.2) 25 (26.6) 163 (31.5) 25 (32.1) 191 (41.4) 18 (32.7) 139 (42.2) 24 (42.1)
合計 712 94 518 78 461 55 329 57
-
表3.各モデルに含まれる取引パターン
[モデル a] [モデル b]
①取引全体 ②販売 ③調達 ①総貿易 ②輸出 ③輸入
現地向けの販売 ○ ○ × × × ×
日本向けの販売 ○ ○ × ○ ○ ×
第三国向けの販売 ○ ○ × ○ ○ ×
現地での調達 ○ × ○ × × ×
日本からの調達 ○ × ○ ○ × ○
第三国からの調達 ○ × ○ ○ × ○
-
表4.変数リスト
[モデル a]
TRADEIF 取引全体に占める (取引全体に占める企業内取引の割合)
① 企業内取引の割合 =(売上高および仕入高うち同一グループ内)/(売上高総額+仕入高総額)
SALESIF 売上高に占める (売上高に占める企業内売上の割合)
② 企業内売上の割合 =(売上高うち同一グループ内)/(売上高総額)
PURCHIF 仕入高に占める (仕入高に占める企業内仕入の割合)
③ 企業内仕入の割合 =(仕入高うち同一グループ内)/(仕入高総額)
[モデル b]
TRIF 総貿易全体に占める企業内 (総貿易に占める企業内貿易の割合)=(日本向けおよび第三国向け輸出額うち
① 貿易の割合 同一グループ内+日本からおよび第三国からの輸入額うち同一グループ内)
/(日本向けおよび第三国向け輸出額+日本からおよび第三国からの輸入額)
EXIF 輸出に占める (輸出に占める企業内輸出の割合)=(日本向けおよび第三国向け輸出額うち同一
② 企業内輸出の割合 グループ内)/(日本向けおよび第三国向け輸出額)
IMIF 輸入に占める (輸入に占める企業内輸入の割合)=(日本からおよび第三国からの輸入額うち同一
③ 企業内輸入の割合 グループ内)/(日本からおよび第三国からの輸入額)
【独立変数】
LCYEAR 現地法人企業の操業年数 経済産業省『海外事業活動基本調査』より.
JPCAP 日本側出資比率 経済産業省『海外事業活動基本調査』より.
ROYALTY ロイヤルティ(対数) 経済産業省『海外事業活動基本調査』より.基本調査年次のみ.
LCEMP 現地法人企業の従業者数(対数) 経済産業省『海外事業活動基本調査』より.
HQEMP 親会社の従業者数(対数) 経済産業省『海外事業活動基本調査』より.
HQEXRT 親会社の売上高輸出比率 経済産業省『海外事業活動基本調査』より.(売上高輸出比率)=(輸出高)/(売上高)
DIST 二国間距離(対数) 首都間距離の直線距離を計測(米国は州都,中国は省都).以下の web
サイトおよび地図ソフト「FLand-Ale 日本/世界地図」を用いて計測.
How Far Is It? by Indo.cpm http://www.indo.com/distance/index.html
HSRGDP 現地法人立地国・地域の 国連統計「National Accounts」より.米ドル建て,1990 年基準.
実質 GDP(対数)
JPRGDP 日本の実質 GDP(対数) 国連統計「National Accounts」より.米ドル建て,1990 年基準.
HSGDPPER 現地法人立地国・地域の 国連統計「National Accounts」より.米ドル建て,1990 年基準.
一人あたり GDP(対数) (一人あたり GDP)=(実質 GDP)/(人口)
JPGDPPER 日本の一人あたり GDP 国連統計「National Accounts」より.米ドル建て,1990 年基準.
(対数) (一人あたり GDP)=(実質 GDP)/(人口)
-
表5.変数の相関マトリックス
LCYEAR JPCAP ROYALTY LCEMP HQEMP HQEXRT DIST HSRGDP JPRGDP HSGDPPER JPGDPPER
LCYEAR 1.000
JPCAP 0.060 1.000
ROYALTY 0.038 0.050 1.000
LCEMP 0.078 -0.090 0.478 1.000
HQEMP 0.086 0.041 0.497 0.501 1.000
HQEXRT -0.081 0.058 0.170 0.166 0.208 1.000
DIST 0.161 0.329 0.113 -0.066 0.112 0.047 1.000
HSRGDP -0.046 0.142 -0.023 -0.211 -0.010 -0.125 0.262 1.000
JPRGDP 0.254 0.076 0.052 0.044 -0.027 -0.157 0.001 0.054 1.000
HSGDPPER 0.262 0.393 0.014 -0.311 -0.032 -0.010 0.446 0.371 0.001 1.000
JPGDPPER -0.199 -0.082 -0.075 -0.043 0.024 0.172 -0.001 -0.040 -0.866 0.012 1.000
-
表6.[モデル a]従属変数:現地法人企業の取引に占める企業内貿易(現地取引を含む)の割合
① 取引全体(TRADEIF) ② 販売(SALESIF) ③ 調達(PURCHIF)
C -8.629 (-0.173) -0.397 (-0.108) -103.337 (-1.498) 5.923 (1.162) 106.214 (1.703) * -7.347 (-1.610)
LCYEAR -0.014 (-2.664) *** -0.011 (-2.055) ** -0.032 (-4.380) *** -0.027 (-3.615) *** 0.017 (2.588) *** 0.018 (2.647) ***
JPCAP 1.387 (6.118) *** 1.475 (6.037) *** 1.549 (5.117) *** 1.754 (5.293) *** 1.018 (3.721) *** 1.175 (4.056) ***
ROYALTY 0.018 (0.851) 0.022 (1.030) 0.033 (1.074) 0.038 (1.268) 0.001 (0.038) 0.007 (0.248)
LCEMP -0.036 (-0.955) -0.035 (-0.908) 0.164 (3.068) *** 0.170 (3.142) *** -0.318 (-6.180) *** -0.345 (-6.601) ***
HQEMP 0.042 (1.267) 0.034 (1.014) 0.091 (2.045) ** 0.069 (1.570) -0.012 (-0.279) -0.012 (-0.272)
HQEXRT -0.180 (-0.811) -0.154 (-0.696) -0.153 (-0.494) -0.017 (-0.054) -0.336 (-1.230) -0.402 (-1.469)
DIST -0.354 (-5.727) *** -0.356 (-5.548) *** -0.377 (-4.439) *** -0.409 (-4.675) *** -0.306 (-3.952) *** -0.261 (-3.327) ***
HSRGDP -0.052 (-1.794) * -0.143 (-3.426) *** 0.056 (1.495)
JPRGDP 0.375 (0.218) 3.724 (1.558) -3.700 (-1.713) *
HSGDPPER -0.040 (-1.003) -0.055 (-1.062) -0.056 (-1.112)
JPGDPPER 0.144 (0.410) -0.479 (-0.989) 0.807 (1.839) *
nob 1083 1083 1083 1083 1083 1083
F(22,1060) 8.971 8.860 9.445 8.747 11.339 11.304
表7.[モデル b]従属変数:現地法人企業の取引に占める企業内貿易(現地取引を除く)の割合
① 総貿易(TRIF) ② 輸出(EXIF) ③ 輸入(IMIF)
C 59.458 (0.971) -1.139 (-0.252) -78.570 (-1.158) 6.327 (1.252) 133.865 (1.944) * -4.787 (-0.963)
LCYEAR 0.000 (0.066) 0.002 (0.362) -0.005 (-0.759) -0.001 (-0.146) 0.025 (3.424) *** 0.021 (2.967) ***
JPCAP 0.689 (2.845) *** 0.836 (3.322) *** 0.900 (3.248) *** 1.051 (3.590) *** 0.810 (2.922) *** 0.869 (3.008) ***
ROYALTY 0.021 (0.792) 0.030 (1.122) 0.020 (0.686) 0.028 (0.933) 0.067 (2.308) ** 0.072 (2.442) **
LCEMP -0.114 (-2.332) ** -0.154 (-3.023) *** 0.097 (1.800) * 0.070 (1.276) -0.205 (-3.657) *** -0.244 (-4.240) ***
HQEMP -0.055 (-1.272) -0.052 (-1.214) 0.016 (0.350) 0.012 (0.256) -0.176 (-3.562) *** -0.148 (-3.108) ***
HQEXRT -0.801 (-2.802) *** -0.865 (-3.047) *** -1.300 (-3.907) *** -1.330 (-4.030) *** -0.742 (-2.370) ** -0.853 (-2.755) ***
DIST -0.236 (-3.039) *** -0.169 (-2.153) ** -0.404 (-4.735) *** -0.349 (-4.056) *** -0.259 (-3.032) *** -0.179 (-2.085) **
HSRGDP 0.057 (1.575) 0.020 (0.486) 0.134 (3.279) ***
JPRGDP -2.025 (-0.954) 2.780 (1.182) -4.685 (-1.963) **
HSGDPPER -0.087 (-1.835) * -0.096 (-1.821) * -0.029 (-0.533)
JPGDPPER 0.376 (0.875) -0.358 (-0.747) 0.640 (1.338)
nob 1083 1083 1083 1083 1083 1083
F(22,1060) 6.645 6.674 5.070 5.188 9.565 8.922