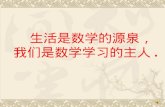新冠病毒传播的动力学模型与 数据分析 · 数据分析 程晋 复旦大学数学科学学院 ... 卫宁健康的App网站. 2020/4/1 52 . ... 于CCDC统计数据的随机时滞动力学模型,
主体的な学びを実現する 算数科学習指導法の研究...- 1 - Ⅰ 研究主題...
Transcript of 主体的な学びを実現する 算数科学習指導法の研究...- 1 - Ⅰ 研究主題...

平成29年度
福岡市小学校教科等研究委員会
算数科研究委員会
主体的な学びを実現する
算数科学習指導法の研究
~数学的な見方・考え方を働かせる
数学的活動の工夫を通して~
研 究 主 題


は じ め に
平成30年より新学習指導要領の32年完全実施に向けての移行期に入ります。そこに
は,小学校で授業時間を増やして英語に充てるなどのことと共に,従来の「何を学ぶか」
という学習内容に加え「主体的・対話的で深い学び」によって「どう学ぶか」「何ができ
るようになるか」といった視点で学びを考えていく必要があることがいわれています。つ
まり,習得すべき「知識・技能」に加え,それを土台に養成すべき「思考力・判断力・表
現力」「学びに向かう力・人間性」まで育成することが求められています。子どもたちが,
学ぶ喜びや大切さを感じながら自ら考え,表現していくことや対話を通しながら考えを組
み立てていくような協働する力を養っていくことが求められているものと捉えます。
本研究委員会では,平成26年度より「数学的な思考力・表現力を高める算数科学習指
導法の研究」を研究主題として掲げ,研究に取り組んできました。研究の方向性として
は,新学習指導要領改訂の方向とも合致するものであろうと捉えています。本年度は,
昨年度までの研究成果と課題を踏まえ,研究主題を「主体的な学びを実現する算数科学
習指導法の研究」,副主題を「数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を通し
て」としました。
研究を進めるにあたっては,次のような仮説を立て授業実践を行っていきました。
数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を,次のような点から行えば,
主体的な学びを実現する算数科学習指導法が明らかになるであろう。
(1)問題の解決に向けての見通しをもつことができる導入
(2)数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
(3)新たな問いを生み出すまとめ
仮説検証にあたっては,低・中・高学年の3部に分かれ各部に応じた学習活動を仕組
み,研究授業を行いました。その結果,主体的に自分の考えをつくり,その考えを表現
したり,言葉や式,図等を関連づけて説明しようとしたりする姿が見てとれました。交
流活動については,よりよい考えや多様な考えを見いだす姿が多く見られるようになっ
てきました。新たな問いを生み出すまとめということについては,まだまだ今後の研究
に追うところが大きいと考えます。さらに,研究を深めていきたいと考えます。
最後になりましたが,本研究委員会の推進にあたり,ご多用な中ご指導・ご助言をいた
だきました福岡市教育センター研修・研究課主任指導主事 井元 尚史様,授業会場校な
らびに研究委員をご推薦いただきました校長先生方に,心から厚くお礼申しあげます。
また,本研究主題の解明に向け努力していただいた研究委員の先生方の姿勢に敬意を表
するとともに,次年度に向けた実践を積み重ねられますようお願いいたします。
平成30年3月
小学校算数科研究委員会
委員長 原 卓也
(福岡市立筥松小学校長)

目 次
はじめに
目 次
研究の基本的な考え方
研究の成果と課題
……………1
……………6
各部の研究
◇ 低学年部の実践
第1学年 「たしざん」
◇ 中学年部の実践
第4学年 「面積のはかり方と表し方」
◇ 高学年部の実践
第5学年 「図形の角」
……………低1
……………中1
……………高1
終わりに

- 1 -
Ⅰ 研究主題
主体的な学びを実現する算数科学習指導法の研究
~数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を通して~
Ⅱ 主題設定の理由
1 福岡市小学校教科等研究委員会(第13期)の全体テーマから
福岡市小学校教科等研究委員会(第13期)の全体テーマは,以下のように設定されている。
学習指導要領を踏まえ,「新しいふくおかの教育計画」後期実施計画の具現化を図る学習指導の
あり方
「新しいふくおかの教育計画」後期実施計画(平成26~30年度)において,全国学力・学習状
況調査及び生活習慣・学習定着度調査により,児童の実態を把握し,学力向上の取り組みを明らかに
していくことが謳われている。後期実施計画は平成30年度が評価指標に基づく評価の年となってお
り,それに向けて本委員会でも学力向上の方途を明らかにし,成果を示していくことがとても重要で
ある。
2 算数科の動向から
平成28年8月の算数・数学ワーキンググループにおける審議の取りまとめでは,育成を目指す資
質・能力を,「主体的・対話的で深い学び」に向けた学習・指導の改善充実によって実現していくこと
が課題であることと述べられている。それぞれの学びについては,次のように述べられている。
○ 主体的な学びとは,児童生徒自らが,問題の解決に向けて見通しをもち,粘り強く取り組み,
問題解決の過程を振り返り,よりよく解決したり,新たな問いを見いだしたりするなどの学び
のこと
○ 対話的な学びとは,事象を数学的な表現を用いて論理的に説明したり,よりよい考えや事柄
の本質について話し合い,よりよい考えに高めたり事柄の本質を明らかにしたりするなどの学
びのこと
○ 深い学びとは,既習の数学に関わる事象や,日常生活や社会に関わる事象について,「数学
的な見方・考え方」を働かせ,数学的活動を通して,新しい概念を形成したり,よりよい方法
を見いだしたりするなど,新たな知識・技能を身に付け,知識の構造や思考,態度が変容する
学びのこと
これらの学びについては,平成29年6月に公表された小学校学習指導要領解説算数編においても,
「主体的・対話的で深い学び」の実現に向けた授業改善の推進として謳われている。
また,新学習指導要領では,算数科の目標が次のように示されている。
数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通して,数学的に考える資質・能力を次のとおり
育成することを目指す。
(1) 数量や図形などについての基礎的・基本的な概念や性質などを理解するとともに,日常の事象

- 2 -
を数理的に処理する技能を身に付けるようにする。 【知識・技能】
(2) 日常の事象を数理的に捉え見通しをもち筋道を立てて考察する力,基礎的・基本的な数量や図
形の性質などを見いだし統合的・発展的に考察する力,数学的な表現を用いて事象を簡潔・明瞭・
的確に表したり,目的に応じて柔軟に表したりする力を養う。 【思考力・判断力・表現力】
(3) 数学的な活動の楽しさや数学のよさに気付き,学習を振り返ってよりよく問題解決しようとす
る態度,算数で学んできたことを生活や学習に活用しようとする態度を養う。
【学びに向かう力・人間性等】
3 児童の実態から
「平成 29 年度第1回学力向上のための連絡会」において,福岡市教育委員会から本市の共通する課
題として,日々の学習における言語活動の充実が挙げられた。そのために,板書の構造化や「主体的・
対話的で深い学び」をめざす授業への転換をしていく必要性が示された。
また,本年度当初に研究委員に日々の算数の授業における課題を尋ねたところ,多くの研究委員が
次のような点を挙げており,子どもたちが主体的にのぞむことができるような算数科学習の実現に関
心をもっていることがうかがえる。
・ 子どもたちひとりひとりが意欲的に考えをつくれるようにすること
・ 一単位時間に複数の問題に取り組むような学習に取り組むこと
・ 児童のどのような姿を育成するか単元全体で考え,めりはりをつけていくこと
・ 学習のスタートから意欲的に取り組めるような学習を構想すること
・ 交流や学習形態の在り方について考えていくこと など
4 これまでの研究のあゆみから
本研究会における最近の研究のあゆみは次のとおりである。
○ 平成23~25年度(第11期)
研究主題「数理を確かなものにする算数科学習指導法の研究」
この研究で,演算決定や計算の意味や仕方を考える際に用いる数直線などの活用や,操作した
ことを図で表したり,関係性を表に表したりする,各領域に絞った研究を行った。
その成果として,各領域における表現内容や表現方法を明確にしたことで,何をどのように表
現したらよいかが分かり,考えをつくる際の表現方法を用いて自分の考えを整理して説明するこ
とができるようになってきた。
○ 平成26~28年度(第12期)
研究主題「数学的な思考力・表現力を高める算数科学習指導法の研究」
この研究で,「思考の道具」や「説明の道具」を活用する学習過程や活動の工夫の研究を行った。
その結果,2つの問題を位置付けた学習過程や「思考の道具」や「説明の道具」を活用する少人
数の交流活動,その有用性を価値付ける活動の有効性が明らかになった。

- 3 -
Ⅲ 主題の意味
1 「主体的な学び」とは
「主体的な学び」とは,問題の解決に向けて見通しをもち,粘り強く取り組み,問題解決の過程を
振り返り,よりよく解決したり,新たな問いを見いだしたりするなどの学びのことである。
2 目指す児童像
主体的な学びを実現している児童とは,次のような姿であると考える。
○ 日常生活で出会った場面を算数の問題としてとらえ,解決しようとする児童
○ 既習を活用し,見通しをもって問題解決しようとする児童
○ どうにか問題の糸口を探そうと問題場面を図などに整理している児童
○ 自分の考えを友達に伝えようと,言葉や数,式などを関連付けながら,表現している児童
○ 友達の説明に質問をしたり,よりわかりやすい表現をアドバイスしたりしている児童
○ 本時のまとめから新しい問いを生み出している児童
3 副主題について
平成29年6月に公表された小学校学習指導要領解説算数編において,数学的な見方・考え方につ
いて次のように述べられている。
算数科の学習における「数学的な見方・考え方」については「事象を数量や図形及びそれらの関係
などに着目して捉え,根拠を基に筋道を立てて考え,統合的・発展的に考えること」であると考えら
れる。
算数科の学習においては,「数学的な見方・考え方」を働かせながら,知識及び技能を習得したり,
習得した知識及び技能を活用して探究したりすることにより,生きて働く知識となり,技能の習熟・
熟達にもつながるとともに,より広い領域や複雑な事象について思考・判断・表現できる力が育成さ
れ,このような学習を通じて,「数学的な見方・考え方」が更に豊かで確かなものとなっていくと考
えられる。
また,算数科において育成を目指す「学びに向かう力,人間性等」についても,「数学的な見方・
考え方」を通して社会や世界にどのように関わっていくかが大きく作用しており,「数学的な見方・
考え方」は資質・能力の三つの柱である「知識及び技能」,「思考力,判断力,表現力等」,「学びに向
かう力,人間性等」の全てに働くものである。
また,算数科の学びの過程としての数学的活動の充実について次のように述べられている。
資質・能力を育成していくためには,学習過程の果たす役割が極めて重要である。中央教育審議
会答申では,算数科・数学科においては,「事象を数理的に捉え,数学の問題を見いだし,問題を自
立的,協働的に解決し,解決過程を振り返って概念を形成したり体系化したりする過程」といった
算数・数学の問題発見・解決の過程が重要であるとしている。
これらのことから,数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動を研究のよりどころとすることは
意義深いことであると考える。

- 4 -
本年度の研究は第13期の1年次である。3か年の研究の方向性(副主題)を次のように計画する。
数学的活動(学習過程) 研究の重点
1年次(平成29年度) つかむ・見通す ○ 問題の解決に向けて見通しをもつことが
できる導入
2年次(平成30年度) つくる ○ 数学的な見方・考え方を働かせる自力解
決・交流
3年次(平成31年度) まとめる ○ 新たな問いを生み出すまとめ
Ⅳ 研究の目標
主体的な学びを実現する算数科学習指導法を明らかにするために,数学的な見方・考え方を働かせ
る数学的活動の工夫のあり方を明らかにする。
Ⅴ 研究の仮説
数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を,次のような点から行えば,主体的な学びを
実現する算数科学習指導法が明らかになるであろう。
(1) 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
(2) 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
(3) 新たな問いを生み出すまとめ
Ⅵ 研究の内容
1 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
○ 問題設定・問題把握の仕方
2 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
○ 既習の数学的な見方・考え方をもとに自分の考えをつくる活動
○ 統合的に考え,数学的な見方・考え方に着目できる交流
○ 交流をもとに自分の考えに付加修正する活動
3 新たな問いを生み出すまとめ
○ 発展的に考え,本時のまとめをもとに,新たな問題をつくることができること
※ 本年度は第13期の1年次にあたる。さらに,学習指導要領が改訂され,その移行期間の直前の年
度にもあたるので,研究の内容は柔軟にとらえ,上記の例にとらわれず,各部で検討し,手立てを仕
組むことができるものとする。

- 5 -
Ⅶ 研究組織
研究委員長 原 卓也 校長(筥 松)
研究副委員長 白濱 雅道 教頭(青 葉)
研究推進部長 久連松 大輔(千 代)④
低学年部 中学年部 高学年部
推進委員【長田】 推進委員【仲尾】 推進委員【藤山】
長田 亜希(筥 松)① 秦 美幸(箱 崎)④ 川尻 周二(春住)⑤
岡 依梨子(原 西)② 荒木 愛子(香椎下原)④ 藤山 芳英(東花畑)⑥
丸田 文子(田 村)① 仲尾 卓(鶴 田)専科 髙倉 博美(野芥)⑤
百田 将夫(金 武)① 田口 小織(七 隈)④ 花木 賀啓(原北)⑤
川波 勇樹(西 都)① 濵地 佳那江(内浜)⑤
※ 丸付数字は所属校での担当学年
Ⅷ 研究計画
1 研究日程
月 日 曜 研究内容
5 22 月 小学校教科等研究委員会総会,組織作り,昨年度までの研究経過の説明
於:教育センター
6 26 月 研究の方向性検討,各部の主題・研究内容・授業者選出 於:筥松小 15:00~
7 24 月 研究の方向性検討,各部の主題・研究内容 於:筥松小 15:00~
7 27 木 低学年部会 於:教育センター
8 25 金 各部の研究内容検討,指導案審議,
中学年部全研オリエンテーション 於:筥松小 14:00~
9 28 木 低学年部全研・協議会,各部の指導案等審議 於:田村小
中学年部全研オリエンテーション
10 12 木 中学年部会 於:七隈小 18:30~
11 1 水 中学年部会 於:七隈小 18:30~
11 6 月 中学年部全研・協議会,各部の指導案等審議 於:七隈小
高学年部全研オリエンテーション
11 27 月 高学年部全研・協議会,於:原北小,研究のまとめに向けて
1 15 月 各部のまとめの作成と審議 於:筥松小 15:00~
2 5 月 各部のまとめの作成と審議 於:筥松小 15:00~
3 9 金 製本作業,次年度の研究の方向性検討 於:筥松小 15:00~

- 6 -
2 研究授業の日程
Ⅸ 研究の成果と課題
1 研究の成果
(1) 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
○ 問題設定・問題把握の仕方
・ フラッシュカードで既習を振り返る活動を仕組んだことは,本時に働かせる数学的な見方・
考え方を意識付け,それを活用して解決できるようにする上で有効であった。
・ 解決方法の見通しを交流したり,既習から類推して結果を予想したりしたことは,自力解決
の見通しをもちながら考えを主体的につくろうとする姿につながった。
(2) 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
○ 既習の数学的な見方・考え方をもとに自分の考えをつくる活動
・ 本時で働かせたい数学的な見方・考え方を明らかにしていたので,それをもとにどのように
解決させるか具体的にイメージをもちながら授業構想することができた。
○ 統合的に考え,数学的な見方・考え方に着目できる交流
・ ブロックや付箋を操作しながらペアや少人数の交流をするようにしたことで,自分の考えを
主体的に説明したり,考えのグルーピングをしたりする姿が見られた。また,共通点を明らか
にする全体交流を仕組んだことは,数学的な見方・考え方を強化したりその有用性を確認した
りする上で有効であったと考える。
(3) 新たな問いを生み出すまとめ
○ 発展的に考え,本時のまとめをもとに,新たな問題をつくることができること
・ 本時で扱った考えより複雑なものを提示したことは,数学的な見方・考え方を一般化する姿
につながった。
2 研究の課題
○ わかりやすく表現するために,数や式と図や言葉などを関連付けながら考えをつくる自力解決・
交流のあり方
○ 次時の学習課題を見いだしたり,問いを生み出したりするようなまとめのあり方
部 授業日時 学年 単 元 授業者 会 場
低 9月28日(木)14:10~ 1 たしざん 丸田 文子 田村小(早良区)
中 11月6日(月)14:35~ 4 面積のはかり方と表し方 田口 小織 七隈小(城南区)
高 11月27日(月)14:50~ 5 図形の角 花木 賀啓 原北小(早良区)

- 7 -
【本年度の実践から】
低学年 中学年 高学年
(既習のふり返り)
○ 10 の補数を答える問題
○ 長方形と正方形の求積公
式
○ 公式を使って長方形や正
方形を求積する問題
○ 長方形と正方形の内角の
和を答える問題
○ 三角形の内角の和を答え
る問題
○ 三角定規のある角の内角
の大きさを答える問題
つかむ・見通す
○ 実物(たまご)の提示
○ 教師による問題場面の
演示
○ 既習をまとめた掲示物
○ 被加数分解と加数分解と
いう見通しから,解決の方
法を加数分解にしぼる交流
○ 見通しの交流
・ 見通しを確実にもたせ
ること
○ 既習をまとめた掲示物
○ 長方形や正方形の内角の
和から類推し,結果を予想
する交流
○ 既習をまとめた掲示物
つくる
○ 式と図,言葉を結びつけ
た表現
○ ペアによるブロック操作
○ 共通点に帰着する交流
○ 少人数の交流
・ 役割分担
・ 付箋紙による考えのグ
ルーピング
○ 共通点に帰着する交流
○ 教師による別解の提示
○ 多様な見通しを整理し,
1つずつ解法を集団でつく
っていくよう導くこと
○ 共通点に帰着する交流
まとめる
○ まとめ
○ 適用問題
加数分解を使って答えを
求める加法計算の問題
○ 適用問題
本時で使った複合図形の
見方を使って,他の複合図
形の求積ができるか確かめ
る活動
○ まとめ
○ まとめ
○ 適用問題
3つの内角の大きさが示
されている四角形の,残さ
れた1つの内角の大きさを
求める問題
○ 数学的な見方の一般化を
促すような問題の提示
フラッシュカードで,既習を振り返る活動
学習問題を把握し,解決の見通しをもつ活動
考えをつくる活動
数理としてまとめる活動


低学年部の実践


- 低1-
第1学年4組 算数科学習指導案
指導者 福岡市立田村小学校
教諭 丸田 文子
単元名 「 たしざん 」
1 指導観
○ 本単元は,1位数どうしのくり上がりのある加算計算の仕方について学習する。くり上がりのあ
る計算に取り組むのは本単元が初めてで,次学年以降で学習する加法の筆算の基礎となる重要な内
容となる。数の構成,数に対する感覚,計算力を関連づけながら,くり上がりのある計算の仕方を
考え,習熟を図ることで,数と計算について理解を深めるものである。
児童は,第3単元「いくつといくつ」において,「10は8と2」と10を分解的にとらえたり,
「8と2で10」と10を合成的にとらえたりする学習をしている。第4単元「あわせていくつ ふ
えるといくつ」では,加法の意味とその計算について学習し,第6単元「10よりおおきいかず」
では,数の構成を和や差でとらえ,10+5などの計算ができるようになっている。また,第9単
元「3つのかずのけいさん」で学習した,9+1+3の計算のように第1項と第2項をたすと10
になる計算は,本単元の学習で10のまとまりをつくって計算すると考えるときに役立つものであ
る。
○ 本学級の子ども達は,第3単元「いくつといくつ」において,10までの数を合成や分解により
構成的にみることや第6単元「10よりおおきいかず」において,「十いくつ」を「10といくつ」
ととらえる学習をしてきている。本単元「たしざん」は,「10といくつ」の考え方に基づき,被加
数または加数に10の合成をしていく計算である。繰り上がりの足し算の計算の仕方を理解すると
ともに,確実にできるようになることが大切である。正確かつ速く答えを導き出せるように,被加
数と加数のどちらを10にするか,数の大きさに着目し,問題に応じて10の合成やその他の数の
分解をするということを意識づけたい。
学習活動の様子では,意欲をもって学習に取り組む子ども達がいる一方で,苦手としている子も
多い。これまでの学習を通して,「十いくつ」を「10といくつ」ととらえ,大きい数をいう場合は
10のまとまりをつくるとよいことは理解しており,計算においては挿絵や問題文から立式はでき
るものの,ブロック図をかいたり計算の順序を言葉で説明したりすることなどの表現の技能が身に
ついていない子どももいる。そこで,本単元では,そういう子どもたちの技能を高めていくために,
ブロック操作やブロック図,さくらんぼ計算を取り入れて,自分の考えや計算の手順が見えるよう
にする。さらに,解答までの過程を順序よく説明できるように,掲示物や交流活動の工夫をする。
○ 本単元の学習にあたっては,1位数どうしのくり上がりのある加法計算で,被加数,加数のいず
れかに着目し,着目した数の10に対する補数を瞬時にとらえることが大事である。その後,「1
0といくつで十いくつ」ととらえる必要がある。例えば,9+4は,10に近い被加数の9に着目
し,加数分解し,9+4=(9+1)+3=10+3=13と考えれば計算しやすい。3+9のよう
に,加数の9に着目した方が10に対する補数をとらえやすい場合がある。この場合,被加数分解
し,3+9=2+(1+9)=2+10=12と計算する。加数分解,被加数分解のどちらが考えや

- 低2-
すいかに関しては,個人により異なる。教科書では,最初に加数分解をしっかり学習できるように
し,次に被加数分解のアイディアが出やすい計算を取り上げ,一人ひとりの児童の実態に応じて扱
えるようにしている。
教科書では,計算の仕方をまとめる際に,第9単元で学習した3つの数の計算式は示していない。
それはより念頭操作に近いまとめにする意図があるためである。しかし,3つの数の計算式を用い
てまとめることを否定するものではないため,児童の実態に応じて,既習の3つの数の計算式と関
連づけてまとめてもよい。第4単元で学習した加法と比べ,本単元で拡張するのは数の範囲だけで
ある。数の範囲が拡張されても,演算の意味を同じようにとらえ,同じように立式して書き表せば
よいことをおさえていくことが大切である。
2 単元目標
○ 既習の加減計算や数の構成をもとに,1位数どうしの繰り上がりのある加法計算の仕方を考えよ
うとしている。 (関心・意欲・態度)
○ 1位数どうしの繰り上がりのある加法計算の仕方を考え,操作や言葉などを用いて表現したり工
夫したりすることができる。 (数学的な考え方)
○ 1位数どうしの繰り上がりのある加法計算が確実にできる。 (技能)
○ 10のまとまりに着目することで,繰り上がりのある加法計算ができることを理解する。
(知識・理解)
3 単元指導計画(全13時間)
時間 目 標 学習活動と数学的な見方・考え方 主な支援
1
◎ 1位数どうしの繰り
上がりのある加法計
算で,加法を分解して
計算する方法を理解
する。
・ 「あわせて何個」を求める場面
であることから,加法であること
を考え,立式する。
・ 9+4の計算の仕方を考える。
◆ 10のまとまりをつくろうと
する見方
・ ブロックを動かして計算
の仕方を考えるよう声を
かける。
・ 10のまとまりを意識で
きるよう,10個並べられ
るブロックケースを用い
る。
2
・ 加法分解による計算方法をまと
める。
・ 加数分解の方法で9+3の計算
をする。
◆ 10のまとまりをつくろうと
する考え方
・ ブロック操作をしなが
ら,計算の仕方を言うよう
にする。
・ 式に10のまとまりをつ
くることを書き込ませる。
3
◎ 1位数どうしの繰り
上がりのある加法計
算で,加法を分解して
計算する方法の理解
を確実にする。
・ 被加数が8の場合の計算の仕方
を考える。
・ 加数分解すると,10のまとま
りがつくりやすいことについて
まとめる。
・ 加数分解をして10のま
とまりをつくることがで
きるよう,「○はあと△で
10だから」と言って計算
するように声をかける。

- 低3-
4
・ 被加数が9,8の場合の計算練
習に取り組む。
・ 児童の実態に応じて,ブ
ロック操作をさせる。
5
・ 被加数が7の場合の計算の仕方
を考える。
・ 計算練習に取り組む。
・ 次時の学習につながるよ
う,10のまとまりをつく
って計算していることを
全体で確認する。
6(本時)
◎ 1位数どうしの繰り
上がりのある加法計
算で,被加数を分解し
て計算する方法があ
ることを知り,計算の
仕方の理解を深める。
・ 場面から加法であると判断し
て,立式する。
・ 3+9の計算の仕方を考える。
・ 被加数を分解した方が10のま
とまりをつくりやすい場合もあ
ることをまとめる。
◆ 被加数を分解して10のまと
まりをつくる考え方
・ 本時学習に必要な既習を
振り返る活動を取り入れ
る。
・ 見通しの段階で,被加数
の3を10にするのか,加
数の9を10にするのか
を考えることができるよ
う,具体物を操作してみせ
る。
・ 色々な考え方が理解でき
るよう,考えの共通点や相
違点について考えさせる。
7
◎ 1位数どうしの繰り
上がりのある加法計
算で,被加数を分解し
て計算する方法があ
ることを知り,計算の
仕方の理解を深める。
・ 計算練習に取り組む。
・ 文章題を解決する。
・ 式に10のまとまりをつ
くることを書き込ませる。
8~
◎ 加法の計算能力を伸
ばす。
・ 計算練習に取り組む。
・ 文章題を解決する。
◆ 被加数が同じ場合は,加数が1
増えるごとに和が1増えるとい
う見方
・ 板書上にカードを並べ
て,規則性に気付くことが
できるようにする。
◎ 学習内容の定着を確
認し,理解を確実にす
る。
・ 仕上げの問題計算練習に取り組
む。
・ 既習の掲示をしておく。
・ 発展的な問題を用意す
る。
4 本時目標
○ 1位数どうしの繰り上がりのある加法計算で,被加数を分解して計算する方法(被加数分解)があ
ることを知り,計算の仕方についての理解を深める。
1
2
1
3

- 低4-
5 本時指導の考え方
前時までに子どもたちは,1位数どうしの繰り上がりのあるたし算の仕方を,ブロック操作を行い
ながら,加数分解を使って,10のまとまりをつくれば,答えが求められることを学習してきた。
本時は,前時で学習してきたことを,加数の10に対する補数を考える被加数分解の方法を考え,計
算の仕方についての理解を深めることをねらいとしている。
つかむ段階では,本時学習につながる10のまとまりをつくることを意識させるために,フラッシュ
カードを使って10に対する補数を考える活動を設定する。そして,本時の学習問題を提示し,分かっ
ていることや尋ねられていることについて学習プリントに書き込ませ,問題場面を整理する。そして,
整理した問題場面から立式し,前時の問題と違うところを話し合い,本時学習のめあてをつかませる。
見通す段階では,まず結果の見通しをもたせる。次に既習から10のまとまりをつくれば,答えを求
められるという考え方を想起させる。さらに,既習のような被加数を10にする方法では手際が悪く時
間がかかるということに気づくことができるように,実物の卵を動かす場面を見せる。さらに,既習か
らブロック操作,サクランボ計算を用いて答えを出すという方法の見通しをもつ。
つくる段階では,図やサクランボ計算を使って自分の考えをつくらせる。自力解決ができない子ども
には,教師が一緒に操作をしたり,書き方を教えたりする。学習プリントに自分の考えを書いた子ども
には,説明の順序が書かれた掲示物を参考にしながら,順序よく言葉で説明ができるようにさせておく。
そして,自分の考えを隣の友達と交流する活動を行う。その際,説明する子どもは,算数ブロックを動
かしながら言葉で説明し,考えを聞いている子どもは,説明している子どもと同様に算数ブロックを動
かしながら考えを確認していくようにさせる。
まとめる段階では,まず,全体で考えを交流する。その際,加数分解も被加数分解も10のまとま
りをつくって計算しているという共通点に気づくように,板書で色分けをし,キーワードを黒板に書
き込んでいくようにする。その後,相違点についても考えさせ,どちらの方法でも計算できることを
確認し,自分のやりやすい方法で計算してよいことを本時学習のまとめでおさえる。最後に,適用問
題に取り組み,数が大きい方を10のまとまりにする方が考えやすいということを再度おさえる。
6 準備
教師:前時までの掲示物,教科書挿絵,具体物(卵),学習プリント
児童:算数ブロック
本時授業仮説
数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を,次のような点から行えば,主体的な学びを
実現するような児童を育むことができるであろう。
(1) 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
・ 本時学習につながる 10 のまとまりをつくることを意識させるために,フラッシュカードを使
って 10 に対する補数を考える活動を設定する。
・ 9を 10 にする見方(被加数分解)に気づくことができるように,見通し段階において,具体
物を使った操作活動を設定する。

- 低5-
7 学習展開(6/13)
配時 過程 学習活動 主な支援
3
7
10
10
つ
か
む
・
見
通
す
つ
く
る
1 フラッシュカードで10に対する補数
を考える活動を行う。
2 本時学習問題を知り,めあてをつかむ。
(1)立式する。
(2)前時との違いを見つけ,めあてをつか
む。
3 見通しをもち,解決する。
(1)結果の見通しをもつ。
○10より大きくなりそう。
(2)考え方の見通しをもつ。
◆10のまとまりを使うという見方
◆3を10にする考え方(加数分解)
◆9を10にする考え方(被加数分解)
(3)方法の見通しをもつ。
◆ブロック(図)を用いて答えを出すと
いう考え方
◆サクランボ計算を用いて答えを出す
という考え方
4 学習問題を解決し,交流する。
(1)被加数分解の方法で自力解決を行う。
○ 10に対する補数を考える活動を入れ
ることで,本時学習に思考がつながるよ
うにする。
○ 学習問題において,分かっていること
や尋ねられていることに印をつけさせ
る。
○ 前時と違い,被加数<加数になってい
ることに気づくよう,前時までの学習の
流れを掲示しておく。
○ 「10のまとまりをつくる」というア
イディアに着目できるように,既習内容
を掲示しておく。
○ 9を10にする見方(被加数分解)の
よさに気づくように,実物を使って10
のまとまりを作る活動を入れる。
○ 操作活動で戸惑っている子どもには,
一緒に操作してあげ,書き方を教える。
○ 表現方法で戸惑っている子どもには,
順序よく表現できるように,説明の順序
が書かれた掲示物を活用させる。
学習問題
たまごは あわせて なんこですか。
めあて
うしろのかずが大きいたしざんのしかたをかんがえよう。

- 低6-
10
5
ま
と
め
る
(2)二人組で考えを交流する。
・自分の考えを説明する。
・友達の考えに沿って追体験をする。
5 本時学習をまとめる。
(1)全体で考えを交流する。
・解き方,答えの確認をする。
・共通点を出す。
→どちらも10のまとまりをつくっ
ている。
◆10のまとまりをつくるという考え
方
(2)本時学習のまとめをする。
6 本時学習をふり返り,適用問題に取り組
む。
○ 自分の考えを確かにし,見直すことが
できるようにするために,二人組で交流
をする。このとき,相手の考えや操作の
手順がより理解できるように追体験を取
り入れる。
○ 共通点がはっきりするように,キーワ
ードを黒板に書き込んでいくようにす
る。
○ 本時学習と適用問題を通して,数が大
きい方を10のまとまりにする方が考え
やすいということをおさえる。
まとめ
うしろのかずが大きいときも,10のまとまりをつくるとけいさんできる。
【3を10にする】10
■■■ □□□□□□□□□
3
① 3はあと7で10。 ② 9を7と2にわける。 ③ 3に7をたして10。 ④ 10と2で12。
7 2
9
10
3+9=12
【9を10にする】 10
■■■ □□□□□□□□□
① 9はあと1で10。 ② 3を2と1にわける。 ③ 9に1をたして10。 ④ 10と2で12。
3 9 3+9=12
2 1 1 0

- 低7-
8 板書計画
たしざん
もんだい
10のまとまりをつくってけいさんしている。
たまごは あわせて
なんこですか。
めあて うしろのかずが大きいたしざんの
しかたをかんがえよう。
まとめ うしろのかずが大きいときも,10の
まとまりをつくると けいさんできる。
みとおし
・こたえは10より大き
くなる。
・10のまとまりを
つくってかんがえる。
・ブロックをつかう。
・ブロックずをつかう。
10
3+9=12
7 2 2 1 10
3+9=12
(れんしゅうもんだい)
①3+8 ②4+7
しき 3+9=12
こたえ 12こ
3 9
《かんがえ》 【9を10にする】 ■■■ □□□□□□□□□
10
3 9
【3を10にする】 ■■■ □□□□□□□□□
9
10
3

- 低8-
9 授業の実際と考察
(1) 授業の実際
時間 過程 学習活動と内容 主な発問と児童の反応
0
1 フラッシュカードで10に対する補
数を考える活動を行う。
2 本時学習問題を知り,めあてをつか
む。
(1)立式する。
(2)前時との違いを見つけ,めあてをつ
かむ。
T:それでは10をつくりましょう。(フラ
ッシュカード)
C:1はあと9で10。4はあと6で10。
T:今日の問題です。読みましょう。
C:たまごはあわせて何個ですか。
T:(卵の掲示写真を被加数から順に出し
て)たまごは何個かな。
C:3。…こっちは9だ!
T:プリントを見てください。卵の写真の
下に□があります。それぞれ数えて数
字を入れましょう。
T:発表してください。
C:3こです。9こです。
T:それでは大事な数字,お尋ね,大事な
言葉に印をつけて発表してください。
C:大事な数字は「3」と「9」です。
C:お尋ねは,「たまごはあわせてなんこで
すか」です。
C:大事な言葉は,「こ」です。
T:そうだね。では今日は何算になるか,
理由もいえる人?
C:あわせてだからたし算です。
T:みなさんたし算の木を見てください。
「あわせて」はたし算だったよね。
T:では,式を書いて発表しましょう。
C:3+9です。
T:今までの学習と違うところに気づきま
せんか。
C:今日は,小さい数字が前にきています。
T:そうだね。みんなできるかな?
C:できます。
T:今日はそれがめあてです。(めあて板書)
学習問題
たまごはあわせてなんこですか。
めあて
うしろのかずが大きいたしざんの
しかたをかんがえよう。
つかむ・見通す

- 低9-
12
15
20
3 見通しをもち,解決する。
(1)結果の見通しをもつ。
(2)考え方の見通しをもつ。
(3)方法の見通しをもつ。
4 学習問題を解決し,交流する。
(1)被加数分解のやり方で自力解決を行
う。
T:それでは見通しを考えましょう。答え
はどうなるかな。どんな考え方をした
らよいかな。プリントに書きましょう。
C:10より大きいから10のまとまりを
つくればよいと思います。
T:なんで10より大きくなりそう?
C:9+1が10だから。
T:じゃあみんな10のまとまりをどっち
につくる?
C:9かな…。3…。
T:先生,実は本物を持ってきましたよ。
C:われるやん!本物やん!
T:じゃあ先生が3を10にしてみるよ。
あぁドキドキする。
C:できた。
T:では,9を10にするよ。
C:はっや! 1秒で出来た。
T:はやかったね。では,今日は9を10
にするやり方でみんなでやっていきた
いと思います。
T:みんな,ブロックを出してください。
みんなもまねして置いてください。9
は右?左?
C:右です。
T:では,ブロックをどっちからどっちに
動かしたらいいの?
C:左から右です。
T:それではブロックでやった後は,みん
な何で答えを求めていたかな。
C:ブロック図とさくらんぼです。
T:そうでしたね。では,今日のさくらん
ぼは,こっちにできそうだね。(被加数
に茎を書く。)
T:では,はじめましょう。
C:(一人ひとりが声に出しながらブロック
操作をする。)
つくる

- 低10-
30
(2)二人組で考えを交流する。
5 本時学習をまとめる。
(1)全体で考えを交流する。
T:では,ブロックを元に戻します。お隣
とお話をしましょう。1回1回説明を
とめてあげてくださいね。
C:(一人が途中まで説明。もう一人は同じ
ところまで説明。)
T:それでは,発表してもらいます。
C:(代表児)9はあと1で10。ここまで
いいですか。
はじめに3を2と1にわける。次に9
を1にたして10。
後に2と10で12。だから答えは
12。どうですか。
T:○○さんが書いてくれたさくらんぼ計
算の方を見たいと思います。先生もさ
っきの説明と同じように言ってみる
よ。
(教師)9はあと1で10。ここまで
いいですか。
はじめに3を2と1にわける。次に9
を1にたして10。
後に2と10で12。だから答えは
12。どうですか。
T:(黒板と既習掲示物を指して)ここを見
てください。何か気づきませんか。
C:長丸の向きが違います。
T:今までの勉強でさくらんぼはどっちに
ありましたか?前の数字?後ろの数
字?
C:後ろです。
T:後ろさくらんぼでしたね。今日はどっ
ちについているかと言うと?
C:前。
T:そう,前さくらんぼになっていますね。
前さくらんぼでも答えが出せました
ね。では答えを書きましょう。答えを
みんなで言いましょう。
C:12こです。
T:今日は,みんな9を10にするやり方
まとめる

- 低11-
(2)本時学習のまとめをする。
6 本時学習を振り返り,適用問題に取り
組む。
でやってみましたね。でも3を10に
するやり方でも出来ましたね。先生さ
くらんぼ計算を書いてみるからみんな
で言ってください。
C:3はあと7で10。
はじめに9を7と2にわける。次に3
と7をたして10。
後に10と2で12。だから答えは
12。
T:今までのやり方,後ろさくらんぼでも
答えを求めることが出来たね。
T:次は比べてください。同じところはな
いでしょうか。
C:どちらも式が違うけど答えが同じです。
C:10が同じです。
T:何が一緒って言った?前さくらんぼで
も後ろさくらんぼでも一緒なのは?
C:10のまとまり。
T:ではめあてを振り返ります。みんなど
ういう考えで答えを出せましたか。
C:10のまとまり!
T:ではまとめを書きましょう。
C:後ろの数が大きいときも10のまとま
りをつくると計算できる。
T:では,練習問題をします。みなさん考
えてみてください。3+8はみんなど
っちのやり方でしてみますか。
C:8を10にする。
T:何で?そっちの方がすぐ?
C:10がつくれる。
T:じゃあ3をさくらんぼにしようね。で
は,そのやり方でやってみましょう。
C:練習問題(3+8・4+7)の発表。
T:今日のようにたしざんには,2つのや
り方がありましたね。みなさん自分で
どっちがやりやすいか考えながらさく
らんぼ計算をしてみてください。
まとめ
うしろのかずが大きいときも,1
0のまとまりをつくるとけいさん
できる。

- 低12-
(2) 考察
◎ 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
① フラッシュカードの活用
本時学習につながる10のまとまりをつくることを意識させるために,「つかむ・見通す」
の段階で,フラッシュカードを使って10に対する補数を考える活動を行った。児童に提示す
る際には,補数を答えやすいように,10に近い数字から提示していった。また,自力解決や
二人組の交流で使用する説明の言い方と同様になる様,「○はあと□で10」という言い方で
行った。児童は,1~9の数に対し,繰り返し補数を考える活動を本単元で行ってきていたた
め,本時もスムーズに答えることができていた。また,立式後の見通しの段階では,「10の
まとまりをつくる」ということや「9を10にする」「3を10にする」という考えが児童の
発言から出てきたことから,「つかむ・見通す」の段階で,フラッシュカードを使って10に
対する補数を考える活動を行ったことは,問題の解決に向けて見通しをもって自力解決するこ
とができる児童を育成する上で有効であると考えた。
② 具体物を使った操作活動
9を10にする見方(被加数分解)に気付くことができるように,見通し段階において,1
0個パックにそれぞれ3個と9個入った卵を用意し,実際に教師が,児童の前で卵を移動させ
て10のまとまりをつくる活動を行った。前時までの学習の流れに合わせ,被加数の3を10
にする操作を先に行い,その後加数の9を10にする操作を行った。児童は,卵ということで
慎重に扱わなければならないという意識があり,加数の9を10にした際,「こっちの方が速
い!」と発言していた。この操作活動によって,児童は被加数分解をした方が本時の式はより
簡単に答えを導き出せることに気付き,その後の自力解決にスムーズにつなげることができた。
このことから,具体物を使用し,生活場面に直結した操作活動を実際に行うことは,よりよい
解決方法を考え,見通しをもって問題の解決に向かう上で有効であった。
(3)課題
○ 具体物を使った操作活動の際,操作が見えづらい児童がいた。卵パック全体が見えるような角
度で教師が持ったり,操作を投影できる機器を用いたりすれば,全員がより理解を確かなものに
できたであろうと考える。また,教師による実演ではなく,児童に実際に操作をさせると,児童
が本時の問題の数に着目し,被加数分解のよさをより実感する活動になったと考える。
10 資料
○ 板書

- 低13-
○ 学習プリント
○ 掲示物
11 改善すべき点
○ 実際の卵を使ったことで移動の速さや簡単さを印象づけることができたが,被加数・加数分解両
方のさくらんぼ計算を行い,どちらがやりやすいか考える活動を行うことで,一人ひとりの考える
力をより高めていくと考えられる。
○ 本時の適応問題では,ブロックを使用せず,さくらんぼ計算を使い答えを求めた。実態に応じて,
ブロックを用いて考えることも手立てとすることも考えられる。
○ 適応問題において,加数と被加数のどちらが10にしやすいか考えさせるために,「9+3」や「3
+9」のように加数と被加数を入れ替えた問題を提示し,児童が大きいほうを10のまとまりにし
た方がいいことに気付けるような問題を用いると良いと考える。


中学年部の実践

- 中1-
第4学年4組 算数科学習指導案
指導者 福岡市立七隈小学校
教諭 田口 小織
単元名 「面積のはかり方と表し方」
1 指導観
○ 本単元は,面積について単位と測定の意味を理解し,長方形及び正方形の面積の求め方について
考え,それらを用いて面積を求めることができるようにすることをねらいとしている。
学習指導要領には,第4学年の数量関係の領域で「数量の関係を表す式について理解し,式を用
いることができるようにする。」とある。
量と測定については,第 1 学年では面積の比較などの活動を通して,面積の意味や測定すること
の意味を理解する上で基礎となる学習をしている。また,第 3 学年までに長さ,かさ,重さなどの
量について学習しており,「直接比較」「間接比較」「任意単位による測定」「普遍単位による測定」
という調べ方を段階的に学習してきている。そこで,第 4 学年の本単元ではこうした経験をふまえ
て,面積について,単位と測定の意味を理解し,長方形及び正方形の面積の求め方について考え,
面積を求める公式をもとにして,複合図形や大きな単位の面積の求め方を考えていく。
○ 本学級の児童は,算数の学習に意欲的に取り組んでいる。自力解決においては,見通しがもてれ
ば,自分なりの考えや方法で解決する事ができる。しかし,計算や作業する力の個人差が大きく,
理解に時間を要する児童もいる。また,自分の考えを上手に説明したり,他の児童が考えたことを,
自分なりに説明したりすることに,難しさを感じている児童もいる。そこで,グループでの交流を
通じて,説明を完成させたり,分かっていることを途中まででも話しながら完成させたりして説明
する機会を意図的に与えていきたい。
これまでに,長さ,かさ,重さなどの学習で,具体的に比べたり測ったりする操作や経験を重視
しながら,普遍単位の何こ分かで表すこと,計算を使って求めること,基本単位同士の関係を学ん
できた。「直接比較」「間接比較」「任意単位による測定」「普遍単位による測定」という測定の4段
階についても経験しているが,児童全員にこの考えが身に付いているわけではない。また,面積の
単位の基準となる長さについては,第3学年までに長さの単位「cm」「m」「km」と,その単位の関
係について学習してきたが,単位相互の関係についての理解がまだ十分でない児童もいる。これは,
面積の学習の際に単位ごとに面積の量感をつかみ,単位相互の関係を考える上で,大切な概念とな
る。
○ 本単元の指導にあたって,導入においては, 4 つの図形の広さ比べをする。直接比較をしたり,1
辺が1㎝の正方形に区切ってそれが何個並んでいるかを調べたりすることで,面積の意味とその単
位「平方センチメートル」を理解する。
展開においては,面積を求める活動から長方形や正方形の求積公式を導き,面積と一方の辺の長
さから,もう一方の辺の長さを求めることや,縦・横の長さ,面積,周りの長さの関係を整理する
こと,複合図形を長方形に分割して面積を求めることを通して公式の意味の理解を深めていく。

- 中2-
また,身の周りのいろいろなものの面積を,見当をつけてから調べる活動を通して,面積につい
ての理解を深める。
終末においては,「平方メートル」「平方キロメートル」などの単位とそれらの単位の相互関係を
知るとともに,必要に応じて使い分けられるようにする。
2 単元目標
○ 面積を数値化して表すことのよさや,計算によって求められることの便利さに気づき,身の周り
の面積を求めるなど生活に生かそうとする。 (関心・意欲・態度)
○ 面積について,量や乗法の学習を基に,単位の何こ分で数値化して表すことや,辺の長さを用い
て計算で求められることを考え,とらえることができる。 (数学的な考え方)
○ 長方形,正方形の面積を,公式を用いて求めることができる。 (技能)
○ 面積について,単位と測定の意味や,長方形や正方形の面積は計算によって求められることやそ
の求め方を理解し,面積についての量感を身につける。 (知識・理解)
3 単元指導計画(全11時間)
時間 目 標 学習活動と数学的な見方・考え方 主な支援
1
◎面積の比べ方をいろい
ろな方法で考え,面積を
比べることができる。
・ ますの数,カードを用いて重
ねる等,見通しを立てて考えが
もてるようにする。
・ ペアで考えを交流し,図をも
とに根拠をはっきりさせて説
明できるようにする。
◆ 広さを比べる活動を通して,
図形に着目する見方。
・ 陣地の広さを比べる際,
重ねたり切ったりして直
接比較もさせる。
・ 4種類のますの大きさ
(任意の単位)をもとに
して比較させる。
2 ◎面積の単位「平方センチ
メートル(c㎡)」を知り,
面積の意味について理
解する。
・ さまざまな形の面積を1㎠を
もとに求めることができ,同じ
面積でもさまざまな形がある
ことをとらえられるようにす
る。
◆ 1c㎡に着目し,いくつ分か
で面積を表し広さを比べるこ
とができる考え方。
・ 同じ大きさのますを用
いて数値化することで比
較しやすくなることを意
識させる。
・ 広さのことを面積とい
うこと,また,面積の基
本単位が1c㎡であるこ
とをおさえる。

- 中3-
3・4
◎長方形,正方形の面積を
計算で求める方法を理
解する。
◎面積を求める公式をつ
くることができる。
・ 長方形の面積も正方形の面積
も1㎠を何個敷き詰められる
かを考え,補助線を書き入れる
とよいことを知らせる。
・ 縦横の辺の長さと面積の関
係・周りの長さと面積の関係を
表にまとめることで,周りの長
さが等しくても面積が等しい
とは限らないことをとらえら
れるようにする。
◆ 面積と一方の辺の長さから,
もう一方の辺の長さを求める
ことができるという発展的な
考え方。
・ 面積は,1c㎡の正方
形の数で数値化して表わ
すことができることを確
認する。
・ 図形内に方眼を書かせ
方眼の数と辺の長さを結
びつかせる。
・ 周りの長さが等しくて
も面積が異なることをお
さえる。
5(本時)
◎既習の長方形や正方形
の面積を求める学習を
活用して,長方形を組み
合わせた図形の面積の
求め方を考え,面積を求
めることができる。
・ 長方形を組み合わせた図形の
面積を分割したり,補ったりす
るなどのいろいろな考えで求
める。
・ 図や式などで説明する。
◆ 長方形の面積の公式を使う
と複合図形の面積が求めるこ
とができるという帰納的な考
え方。
・ 既習事項を確認し,図
を分割,等積変形,大き
な長方形とみなして引く
といった考えを導きだし
ていく。
・ 長方形や正方形を基に
して考えるという点が共
通していることに気付か
せる。
6
◎面積の単位「平方メー
トル(㎡)」を知り,
辺の長さがmの場合も
長方形や正方形の面積
の公式が適応できるこ
とを理解することがで
きる。
・ 長方形の形をした教室と正方
形の形をした理科室の面積の
求め方を考える。
・ 面積の単位「平方メートル
(㎡)」を知る。
・ 辺の長さがmで表されていて
も,面積の公式が使えることを
確認する。
◆ 1辺が1mの正方形の面積
を単位にする類推的な考え方。
・ 1㎡がいくつ敷き詰め
られるかということか
ら,既習の面積の公式を
想起させる。
・ 大きな面積の単位の必
要性に気付かせる。

- 中4-
7
◎面積の単位㎡とc㎡の
関係を理解することが
できる。
・ 1㎡は何㎠になるか調べる。
・ 紙を使って,1㎡の正方形を
作り,面積の量感をつかむ活動
に取り組む。
◆ ㎡とc㎡を関連付ける統合
的な考え方。
・ 単位をそろえて面積を
求めさせる。
・ 1㎡=10000c㎡
という関係をおさえる。
・ 1㎡を作り量感を養う。
8
◎面積の単位「アール(a)」
「ヘクタール(ha)」「平
方キロメートル(k㎡)」
を知り,面積の単位の相
互関係を理解する。
・ 1辺の長さを 10mや 100mに
したときの面積を考え,面積の
単位「アール(a)」「ヘクター
ル(ha)」を知る。
◆ 「アール(a)」「ヘクター
ル(ha)」を関連付ける統合的
な考え方。
・ 1ha=10000㎡
1a=100㎡,
1ha=100aの関係を
表を掲示しておさえる。
9
◎学習問題を適用して,問
題を解決する。
◎算数的活動を通して学
習内容の理解を深め,面
積についての理解を広
げたり,面積の大きさに
ついての感覚を豊かに
したりする。
・ 町の面積を調べ,面積の単位
「平方キロメートル(㎢)」を知
る。
・ 1㎢は何㎡になるか調べる。
◆ 「アール(a)」「ヘクタール
(ha)」「平方キロメートル(㎢)」
を関連付ける統合的な考え方。
・ 辺の長さに着目し,1㎡
が1つの辺に何個並ぶか
考えさせる
・ 1㎢=1000000 ㎡の関係
や面積の単位の総合性を
表を使って説明させる。
10 ◎学習内容の定着を確認
し,理解を確実にする。
・ 「力をつけるもんだい」に取
り組む。
・ 「しあげ」に取り組む。
・ 既習内容を生かしなが
ら,問題を解決させる。
11
4 本時の目標
○ 既習の長方形や正方形の面積を求める学習を活用して,長方形や正方形を組み合わせた図形の面
積の求め方を考え,面積を求めることができる。
○ 図形の面積の求め方を説明したり,相違点を考えながら聞いたりすることができる。

- 中5-
5 本時指導の考え方
本時授業仮説
数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を,次のような点から行えば,主体的な学びを
実現する算数科学習指導法を明らかになるであろう。
(1) 問題解決に向けて見通しをもつことができる導入
複合図形のイメージを持たせるために,既習の長方形と正方形の公式や簡単な面積の立式
をフラッシュカードで確認後,問題を提示する。
(2) 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
複合図形を分割したり,補ったりして,既習の長方形に置き換えて考える。
全体交流の前にグループによる交流を行い,どの児童も自分の考えを説明する場を設ける
とともに,それぞれの考えの共通点・相違点に気付き全体交流につなぐ。
(3) 新たな問いを生み出すまとめ
適用問題を提示し,早く求積できる方法はどれかを考えさせるようにし,目的に応じた考
えの有用性に気付くことができるようにする。
本時は,長方形や正方形の面積の公式を用いれば,L字型の複合図形の面積も計算できるというこ
とを理解する場面である。その中で,図と式を結び付けていくことを通して表現力を,既習の公式が
使えるように複合図形を分割したり補充したりすることを通して思考力を高めていくようにしたい。
つかむ段階では,前時までの学習と本時までの学習との違いが意識させるため,面積の公式や簡単
な面積の立式を問う問題をフラッシュカードで確認したうえで,問題を提示する。今までの面積との
形の違いに目を向けさせ,めあてをつかむことができるようにする。
見通す段階では,どのようにすれば,長方形や正方形の面積の公式を使えそうか考えさせ,長方形
になおして面積を求めればよいことに気付かせる。
つくる段階では,まず,見通しにそって,図形に補助線を引き,面積を求める計算式を考えていく
よう指示する。次に,面積の求め方を言葉で書かせる。その際に,自分の考えを式や言葉で表現する
ことができるように,図形プリントを使うようにする。しかし,補助線を引いたり,計算式をつくっ
たりすることが困難な児童がいると予想される。そこで,ヒントカードを渡し,自分の考えを整理し
たり,見直したりすることができるようにする。そして,グループ交流では,どこを長方形と見て式
を立てれば面積が求められるか説明するようにする。その際,自分の考えを整理したり見直したり,
考えの相違点に気付いたりすることができるようする。さらに,全体交流の場面では,面積をどの方
法で求めたか伝える。黒板に必要な線や数値を書いた図形と計算式を書いた紙を掲示させ,考えを発
表させる。また,面積を分けて考えたり,大きな長方形と見立てて余分な部分をひいたり,切って合
わせたりという言葉を使って筋道だった説明ができるようにする。
まとめの段階では,交流の中で出てきた考え方はどれも長方形の公式をもとにして計算することが
できているということをおさえ,適用問題に取り組み,本時のまとめを行う。最後に,本時の学習を
振り返る。

- 中6-
6 準備
教師:既習内容の掲示物・フラッシュカード・問題提示用図形・ヒントカード・操作用図形
児童:図形プリント・交流シート
7 学習展開(5/11)
配時 過程 学習活動と数学的な見方・考え方 主な支援
4
3
7
つ
か
む
見
通
す
つ
く
る
1 本時問題を知り,めあてをつかむ。
(1)本時学習問題を知る。
(2)めあてをつかむ。
めあて
かいだんのような形の面積の求め方を考え
よう。
2 見通しをもつ。
○長方形や正方形(習った形)にする。
◆ 複合図形の図形を観察し,既習である長方形
に着目する見方。
◆ 長方形の求積方法と関連づける考え方。
3 自分の考えをつくり,交流する。
(1)自力解決をする。
〔考え①分けてたす〕
補助線で2つの長方形に分けて
たす。
式4×3+2×3=18 答え 18c㎡
〔考え②分けて動かす〕 図形を分けて,移動させ 1つの長方形にする。 式(2+4)×3=18 答え 18 c㎡
〔考え③あるとして見る〕
付け加えて大きな1つの長方形
にして余分な部分を引く。
式4×6-2×3=18 答え 18c㎡
○ 前時までに学習した長方形と正
方形の公式や簡単な面積の立式を
フラッシュカードで確認させる。
○ 複合図形の周りの長さが予測で
きるように,1㎝の方眼の上に図形
を置いた問題を提示する。
○ 前時との違いを明らかにして,め
あてをつかませる。
○ どのようにしたら公式が使える
か考えるように助言する。
○ 見通しにそって図形プリントに
書き込ませる。
○ 図形プリントに必要な数値など
を書き込んで式を立てるように指
示する。
○ 1つの考えができたら,他の方法
も考えさせる。
○ 考えをつくることが難しい児童
には,ヒントカードを用意する。
○ どこを長方形にして考えたか,自
分の考えを言葉で表現できるよう
に促す。
学習問題 次の形は何c㎡ですか。

- 中7-
8
15
5
3
ま
と
め
る
〔考え④2つ合わせて半分にする〕
2倍して1つの正方形にする。
式4×9÷2=18 答え 18 c㎡
(2)グループで交流する。
○どこを長方形にして考えたか,自分の考えを
説明する。
(3)全体で交流する。
○考えを発表する。
○①②③④の相違点を話し合う。
・長方形に分けて求める。
・全体を長方形にして求める。
・移動させて長方形にして求める。
○①②③④の共通点を話し合う。
・長方形や正方形を作って面積を求める。
◆ 長方形や正方形の面積の公式を使うと複合図
形の面積が求めることができるという帰納的な
考え方。
4 適用問題に取り組み,本時の学習のふり返り
まとめる。
(1) 適用問題をする。
(2) 学習のまとめをする。
○ 図形プリントと照らし合わせて
どこを長方形と見て式を立てたか
説明するようにする。
○ 図形と式を照らし合わせて,自分
の考えを言葉で表現できるように
促す。
○ 聞くときは自分の考えと比べな
がら聞くようにする。
○ 考え④が出ない場合は,教師が図
形を提示する。
○ どの考えを用いて解くのかを意
識させる。
○ 図形プリントに必要な数値など
を書き込んで式を立てるように指
示する。
○ どの考えも長方形や正方形の公
式を基にしていることをおさえる。
○ 学習して分かったことや既習を
活用することのよさにも気付くこ
とができるようにする。
まとめ
かいだんのような形の面積も,長方形や正
方形をもとに面積を求めることができる。

- 中8-
練習問題
8 板書計画
学習問題
次の形は何 c㎡ですか。
めあて
かいだんのような形の面積の
求め方を考えよう。
まとめ
かいだんのような形の面積も,
長方形や正方形をもとに面積を
求めることができる。
4×6-2×3=18
答え 18c ㎡
(2+4)×3=18
答え 18c ㎡
4×3+2×3=18
答え 18c ㎡
考え <分けてたす>
考え③ <付け加えて引く>
考え② <分けて動かす>
見通し
・長方形や正方形の
面積の公式
・長方形や正方形にす
る
考え④ <2つ合わせて半分>
4×9÷2=18
答え 18c ㎡
長方形や正方形をもとに面積を求めている

- 中9 -
学習問題 次のような形の面積を求めましょう。
9 授業の実際と考察
(1) 授業の実際
時間 過程 学習活動と数学的な見方・考え方 主な発問と児童の反応
00
02
03
05
つ
か
む
見
通
す
つ
く
る
1 本時問題を知り,めあてをつかむ。
(1) 本時学習問題を知る。
(2)めあてをつかむ。
2 見通しをもつ。
○長方形や正方形(習った形)にする。
◆ 複合図形の図形を観察し,既習である
長方形に着目する見方。
◆ 長方形の求積方法と関連づける考え
方。
3 自分の考えをつくり,交流する。
(1)自力解決をする。
〔考え① 分けてたす〕
補助線で2つの長方形に
分けてたす。
式4×3+2×3=18 答え18c㎡
T: 前の時間までのふり返りをしましょ
う。長方形の面積は(フラッシュカード
を提示。)
C:たて×よこ,よこ×たて
T:正方形の面積は
C:一辺×一辺
T:次の形は何 c㎡ですか。
C:35c㎡
T:次の形は何 c㎡ですか。
C:25c㎡
T:問題です。次の形は何 c㎡ですか。
T:何の形に見えますか。
C:くつです。
C:スケートぐつみたいです。
T:この形どうやったら求められそう。
C:長方形なら求められるから分ければ求
められます。
C:正方形も長方形も分かっているので付
加えればいいです。
T:どうして,長方形や正方形にしたら求
められそう?
C:公式が使えます。
T:自分で考える時間を7分とります。
(同時にプリントを配付)
T:はい,始めてください。
めあて
くつのような形の面積の求め方を考えよう。

- 中10 -
20
27
〔考え② 分けて動かす〕
図形を分けて,移動 させ1つの長方形に する。
式(2+4)×3=18 答え18 c㎡
〔考え③ あるとして見る〕
付け加えて大きな1つ
の長方形にして余分な
部分を引く。
式4×6-2×3=18 答え18c㎡
〔考え④ 2つ合わせて半分にする〕
2倍して1つの正方形
にする。
式4×9÷2=18 答え18 c㎡
(2)グループで交流する。
○どこを長方形にして考えたか,自分の
考えを説明する。
(3)全体で交流する。
○考えを発表する。
○①②③④の相違点を話し合う。
・長方形に分けて求める。
・全体を長方形にして求める。
・移動させて長方形にして求める。
T:今見たら,自分の考えが書けています
ので自分のグループの人と聞き合っ
てください。できたら,グループわけ
までしましょう。グループを作って。
T:では,グループでの考えをぜひ,発表し
たいというところ。
C:3班では3つの考えがでました。
① 分けてたす。
② 分けてたてに動かす。
③ 分けて横に動かす。
C:3班に付加えてあるとして考えるとい
う意見が出ました。

- 中11 -
34
37
ま
と
め
る
○①②③④の共通点を話し合う。
・長方形や正方形を作って求める。
◆ 長方形や正方形の面積の公式を使う
と複合図形の面積が求めることができ
るという帰納的な考え方。
4 適用問題に取り組み,本時の学習のふ
り返りまとめる。
(1)適用問題をする。
式
5×9+6×6=81
答え 81c㎡
T:では,3つの考えが出たので今から 3
人の人にどう計算したかについて発
表してもらうのでどの考えか考えな
がら聞いてください。
T:Aさんの考え方はどう考えましたか。
C:長方形を2つ作って計算しました。
C:分けてたすです。
C:式は4×3+2×3で答えは 18 c ㎡
T:では、Bさんをお願いします。
C:式は4×6-3×2で答えは 18 c ㎡
T:これは,どの考え
C:あるとして考えるです
T:Cさんの考え方はどう考えましたか。
C:たてに分けてここに持ってきました。
式は…
T:みんなからは出なかったのですが,ま
ずタイトルだけ。(考え④を提示)
T:何か気づいた人いる。
C:わぁ。
C:2でわれば…
C:すごい。
T:正方形なので式をいってください。
C:6×6=36,36÷2=18です。
T:他にも紹介したいものがあります。
C:すごい。
C:かしこい。
T:何でこういうことしたの。
T:なんで分けたの。
T:何か共通していることない。
C:長方形や正方形です。
T:共通点しているのは長方形や正方形を
もとにしているということですね。
T:じゃあ,本当に正方形や長方形にした
ら求められるのかもう一問用意して
います。
T:発表してくれる人。
C:よこに分けてたす考えでしました。
まず,上の長方形の面積を求めます。
式は5×9=45になりますよね。次

- 中12 -
42
45
(2)学習のまとめをする。
に下の正方形の面積を求めます…
T:他の考えで解いた人もいます。
T:たてに分けて考えた人。
C:長方形2つ。
T:あるとして考えた人。
C:はい。
T:今日のまとめをします。
T:くつのような形の面積も
C:長方形や正方形をもとにすれば
C:求めやすい
C:かんたん
C:求められる。
T:まとめを読みます。
T:「今日の学習で」振り返ってください。
T:最後に一人だけ発表してもらいます。
C:くつのような形の面積も長方形や正方
形にしたら求められることが分かっ
た。
T:習ったことを使えばできますね。これ
で終わります。
まとめ
くつのような形の面積も,長方形や正方形をもとにすれば求められる。

- 中13 -
(2) 考察
◎ 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
①フラッシュカードによる振り返り
フラッシュカードによる振り返りを行うことで,短時間で効果的に振り返りを行うことができ
た。児童はカードに対して意欲的に反応しており,楽しみながら振り返りをしている様子が伺え
た。その為,フラッシュカードを用いた振り返りは効率的であり児童の意欲付けといった点でも
効果的であったと考えられる。
②問題提示
問題提示では複合図形を様々な方向からすこしずつ見せるこ
とで,既習の長方形や正方形を基にしてできあがっているとい
うことに感覚的に気付かせることができたという点で効果的で
あったと考えられる。
◎ 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
①自力解決
自力解決においては,児童の考えを十分に書く時間を確保するため,複数の考えに取り組ませ
ず,1つの考えに絞って取り組ませた。そうして,時間を確保することにより,ほとんどの児童
が自分の考えを書くことができたと考えられる。
②少人数交流
少人数交流は,児童が自力解決で導き出した答えを
やり方別にグループ分けをさせるという意図をもって
行った。各グループに一つ,全員の考えを書いたプリン
トを貼り付ける大判のプリントを準備することで,一
目で全員の考えを見比べることができ,主体的で活発
な交流につながったと考えられる。
③全体交流
全体交流では,児童が発表したやり方とは違うやり方を教師が提示することにより,児童のプ
リントにはあるが,発表されることがなかったやり方も全員で共有することができていた。
◎ 新たな問いを生み出すまとめ
まとめの段階で行った適用問題は,問題に応じてより適したやり方を選択することが必要だとい
うことに気付かせるという意図をもって準備をすることができた。
(3) 課題
○ 複合図形をどのように分けたり,動かしたりするかということを説明することはできていたが,式
とつないで説明するまでにはいたらなかった点に課題が見られた。
○ 適用問題が教師の意図したような気づきを導くことができなかったので精選する必要があった。
○ 交流に多くの時間を使い主体的に解決することはできたが,適応問題を解いて発表する時間が短
くなってしまったので,時間配分を見直す必要がある。

- 中14 -
10 資料
○ 図形プリントを貼ったノート ○図形プリントを仲間分けした交流シート
○ 板書
11 改善すべき点
○ 自力解決は説明を書くことを重視し,一人一つの考えに絞って考えさせたが,説明の書き込み量を工
夫して複数の考え方を自力解決で考えさせることでより,交流に深まりが出たのではないかと考える。
○ 自力解決で書き込みをおこなった複合図形とその横に書かせた式を矢印等でつなぎ,図形のどの部
分をどの式が表しているかということを明確にすることで,より数学的な見方や考え方を深めること
ができたのではないかと考える。
○ 今回は適用問題を解いてからまとめをおこなったが,まとめてから適用問題を解くことでやるべき
ことがより明確になったのではないかと考える。


高学年部の実践

- 高1 -
第5学年2組 算数科学習指導案
指導者 福岡市立原北小学校
教諭 花木 賀啓
単元名 「図形の角」
1 指導観
○ 本単元は,三角形や四角形の内角の和について,図形の性質として見出し,それを用いて図形を
調べたり,構成したりすることができるようになることを主なねらいとしている。つまり,①筋道
立てて考えることのよさを認め,三角形の内角の和が180°であることを基に,四角形や他の図
形の性質を調べようとすること,②三角形の内角の和が180°になることを三角形の性質として
とらえ,それを基に,四角形の内角の和について演繹的に考え,四角形の性質としてとらえること
ができるようにすること,③三角形や四角形の内角の和を用いて,未知の角度を計算で求めること
ができるようにすること,④三角形の内角の和が180°であることや,四角形の内角の和は三角
形に分けることによって求められることを理解することなどである。
本単元で学習する三角形を基にした内角の和の求め方は,第5年生第14単元「正多角形と円周
の長さ」や第6学年1単元「対称な図形」へとつながっていく単元である。このため,三角形の内
角の求め方や四角形の内角の求め方を考える際には,対角線で分けたり,補助線で分けたりして既
習の図形に直して考えることの良さに気づかせる工夫が必要である。
○ 本学級の児童の子どもたちは,第6単元「合同な図形」では,合同の定義や合同な図形の性質,
合同な図形のかき方を学習してきている。合同な図形をかく際には,正三角形や正方形,長方形で
はない三角形や四角形の作図を通じて,様々な形の三角形や四角形に慣れ親しんでいる。また,学
習の導入では,合同な図形を実際に切り取って重ね合わせるというような操作活動も行なってきた。
学習活動の様子では,意欲をもって学習に取り組む子どもたちがいる一方で,算数が嫌い・苦手
とする児童も多い。塾等に通っている児童は全体の1割程度で,単元毎にする前提テストでも,未
習の問題を解けるのは1割前後である。既習を十分に想起させ,自ら考え,問題を解けたという実
感を持たせられるような学習展開をしたいと考えている。
既習を活用し,見通しを持って問題解決しようとしている児童は全体の半数程度いるものの,残
りの半数は,友だちの発表した見通しをノートに写すだけになってしまい,実際に自力解決をする
段階になって,見通しで出た内容と既習が一致せずに解決ができないことが多い。また,式と図を
関連付けて考えることは学級全体を通じて苦手としている。そこで,フラッシュカードによる既習
の振り返りと,問題の文章化・提示の工夫によって,児童が主体的に問題解決できるようなつかむ
段階の工夫を行ないたい。また,つくる段階では,四角形を三角形と見る見方に着目させ,多様な
解決方法を考えさせたい。
本学級の子どもたちの実態を把握するために,前提テストを行なった。結果は以下の通りである。
(8月第4週実施 男子21名 女子19名 計40名)
観点 問題 正答/正答率/誤答例
1 半回転,4直角の
角度
③半回転の角度=□度
④4直角=□度
③180度/86%/90度,無回答
④360度/86%/180度,無回答

- 高2 -
2 三角定規の角の合
成
下の図のように三角定規を組み
合わせました。あの角度は何度
ですか。
135°/75%/無回答
3 同位角,錯角に対
する理解
い,うの角度は,それぞれ何度
ですか。
い 120°/63%/40°,60°,無
回答
う 120°/63%/40°,60°,無
回答
【前提テストの結果の考察】
前提テストでは,図形の角の性質を正しく覚えている児童が全体の7割程度いるものの,残りの3
割程度の児童は,誤って覚えていたり,全く覚えていなかったりするため,かくことができない実態に
あることがわかった。そのため,既習の想起だけでなく,既習を繰り返し反復することで,既習を本単
元で定着させ,さらに本時で学ぶ内容も定着させることが必要であると感じた。
○ 本単元の学習にあたっては,三角形の内角の和,四角形の内角の和を形式的に覚えるのではなく,
既習をもとにすることで,様々な多角形の内角の和を求めることができることを理解できるように
したい。そこで次のような工夫を図る。
(1)フラッシュカードによる既習のふり返り
本時の解決にあたって必要となる既習内容(三角形の内角の和・四角形の名称・直角や一周など
の角の大きさなど)を,フラッシュカード形式でふり返る。
(2)図形の見方や考え方を深めるための段階的な見通しのもたせ方の工夫
・四角形の内角の和は三角形に分ければ求められるという考え方
・三角形に分けたときに四角形の内角ではない部分が生まれるという見方
・四角形の内角の和を求めるときは分けた三角形の全ての和から不要な部分を引くという考え方
2 単元目標
○ 筋道を立てて考えることのよさを認め,三角形の内角の和が180°であることを基に,四角形
や他の図形の性質を調べようとする。 (関心・意欲・態度)
○ 三角形の内角の和が180°になることを三角形の性質としてとらえ,それを基に,四角形の内
角の和について演繹的に考え,四角形の性質としてとらえることができる。 (数学的な考え方)
○ 三角形や四角形の内角の和を用いて,未知の角度を計算で求めることができる。 (技能)
○ 三角形の内角の和が180°であることや,四角形の内角の和は三角形に分けることによって求
められることを理解する。 (知識・理解)

- 高3 -
3 単元指導計画(全7時間)
時間 目標 学習活動と数学的な見方・考え方 主な支援
1
〇三角形の内角の和は1
80°であることを理
解し,計算で三角形の角
の大きさをもとめるこ
とができる。
・教科書の二等辺三角形を見て,気付いた
ことを話し合う。
・学習問題を読み,題意をとらえる。
・角の大きさを調べて,表にまとめる。
・三角形の角の大きさの和について課題意
識をもつ。
○二等辺三角形の2つ
の角の大きさが等し
いことをおさえてお
く。
2
〇三角形の内角の和は1
80°であることを理
解し,計算で三角形の角
の大きさをもとめるこ
とができる。
・二等辺三角形以外の三角形でも内角の和
が180°になることを調べる。
・ノートに書いた三角形の大きさを,分度
器を使って調べる。
・練習問題に取り組む。
◆三角形の内角の和を,三角定規の角の大
きさを調べたり,いろいろな三角の3つ
の角を1つの点に集めたりする見方
◆3つの角をたせば180°になる,3つ
の角を平角にすれば180°になるとい
う考え方
○三角形の3つの角の
違いが分かるように
それぞれ違う色をつ
け,区別できるよう
にする。
3(本時)
〇四角形の内角の和は3
60°であることを理
解し,計算で四角形の角
の大きさを求めること
ができる。
・学習問題を読み題意をとらえる。
・四角形の内角の和の求め方を考え,自分
の考えを書き表す。
・自分なりの考えをもとに交流活動を行う。
・本時のまとめをする。
・練習問題を解く。
◆三角形の内角の和を基にして,四角形の
内角の和の求め方を考える見方
◆四角形の内角の和を求める方法をいくつ
か考え,間違えなく360°になるだろ
うという考え方
○素早く既習を振り返
ることができるよう
に,フラッシュカー
ドを提示する。
○図形を操作しやすい
ように四角形を印刷
したカードを準備し
ておく。
4
〇「多角形」を知り,多角
形の内角の和の求め方
を考え,内角の和を求め
ることができる。
・学習問題を読み,題意をとらえる。
・五角形,六角形の内角の和を求め,表に
まとめる。
・本時のまとめをする。
・練習問題をする。
◆三角形の内角の和を基に,多角形の内角
の和を三角形に分ける見方
◆分けた三角形の内角の和をたせば求める
ことができるという考え方
○三角形に分けるため
には,1つの頂点か
ら対角線を引けばい
いことに気づかせ
る。

- 高4 -
5
〇基本図形の敷き詰めを
通して,図形に親しみ,
その美しさを感得する
とともに,論理的な思考
力を高めることができ
る。
・四角形(正方形,長方形,平行四辺形,
一般四角形)を掲示し,敷き詰められる
かを考える。
・学習問題を読み,題意をとらえる。
・敷き詰めた結果や気づいたことについて
交流活動を行う。
・本時のまとめをする。
◆形も大きさを同じ四角形が敷き詰められ
るという見方
◆形も大きさを同じ四角形を敷き詰めた時
に4つの角が360°になるからきれい
に敷き詰められるという考え方
○教科書p141にあ
る同じ大きさ・形の
図形を使わせる。
○正方形や平行四辺形
などこれまで学習し
てきた四角形の図形
も準備しておき必要
に応じて使えるよう
にする。
6
〇基本図形の敷き詰めを
通して,図形に親しみ,
その美しさを感得する
とともに,論理的な思考
力を高めることができ
る。
・学習問題を読み,題意をとらえる。
・平行四辺形の一部を変えて敷き詰めてい
る模様を見て,気付いたことについて交
流活動を行う。
・自分なりに平行四辺形の一部を変えた形
を作って,敷き詰める。
・自分が作った考えを発表する。
○方眼紙を準備しいろ
いろな模様にチャレ
ンジできるようにす
る。
○適当にならないよう
に,一部ずつ形を変
化させるようにす
る。
7
〇学習内容の定着を確認
し,理解を確実にする。
・学習内容の習熟と理解をする。
(しあげ)
○既習内容を生かしな
がら,問題を解決さ
せる。
4 本時の目標
○ 四角形の内角の和は360°であることを理解し,計算で四角形の角の大きさを求めることがで
きる。
5 本時指導の考え方
本時授業仮説
本時指導において,数学的な見方・考え方を働かせる数学的活動の工夫を,次のような点から行えば,
主体的な学びを実現するような児童を育むことができるであろう。
(1)フラッシュカードによる既習のふり返り
本時の解決にあたって必要となる既習内容(三角形の内角の和・四角形の名称・直角や一周な
どの角の大きさなど)を,フラッシュカード形式でふり返る。
(2)図形の見方や考え方を深めるための段階的な見通しのもたせ方の工夫
・四角形の内角の和は三角形に分ければ求められるという考え方
・三角形に分けたときに四角形の内角ではない部分が生まれるという見方
・四角形の内角の和を求めるときは分けた三角形の全ての和から不要な部分を引くという考え方

- 高5 -
前時までに子どもたちは,二等辺三角形の角の大きさを分度器で測ったり,三角形を切り合わせ
たりして,三角形の内角の和は180°であることを学習してきている。
本時は,前時で学習したことをつかって,四角形の内角の和は360°であることを計算によっ
て求める場面であり,四角形をいくつかの三角形に分けて,内角の和が180°であることをもと
に問題解決をはかっていくことをねらいとしている。
導入では既習をふり返る際に,素早く子どもが集中して取り組むことができるように,フラッシ
ュカードを使用する。カードは三角形の内角の和・四角形の名称・直角や一周などの角の大きさな
どの様々な内容を準備する。
つかむ段階では,問題提示で「四角形の4つの角の大きさの和は何度になりますか。」という文章
問題として提示する。求める方法の条件として,分度器を使わないこと,図形を切らないことの2
点を伝え,前時学習との違い(三角形ではなく,四角形であること)からめあて「四角形の角の大
きさの和を求める方法を考えよう。」を導く。
見通す段階では,答えの見当をつけるために正方形では内角の和が360°になることを確認し
た後に,問題の図を提示する。この際にどの角の大きさの和を求めればよいのかが視覚的に分かる
ように,4つの角に色をつけておく。考えを全体で交流して,四角形を三角形に分けるという見方,
四角形の内角の和は三角形に分ければ求められるということを確認する。他の解法である4つの三
角形に分ける考えを引き出すため,2つの三角形以外に分け方がないかと発問する。また答えは3
60°になることを押さえておくことで,自力解決の際,誤った答えが出た場合に考え直すことが
できるようにしておく。
つくる段階では,子どもが図と式を関連して説明できるように,図に数を書き入れたり,矢印で
繋げたりと表し方を工夫するように助言する。全体交流で,代表児が考えを発表し,三角形に分け
たときに四角形の内角ではない部分が生まれるという見方に気付かせるために,教師が三角形の図
形を合体させて見せる。そして不要な部分と式を関連させて理解を促していく。四角形の内角の和
を求めるときは分けた三角形の全ての和から不要な部分を引くという考え方をもとに,3つの三角
形にも分けられないかを考えさせる。
まとめる段階では,全ての考えの共通点である四角形の内角の和は三角形に分ければ求めること
ができること,四角形の内角の大きさの和は360°であることを共通理解して,本時学習をまと
める。その後適用問題に取り組み,最後に,5つの三角形に分けた四角形を提示し,見方を拡張し
ていく。
6 準備
教師:フラッシュカード,四角形の掲示物
児童:教科書,ノート,作業カード

- 高6 -
7 学習展開(3/7)
配時 過程 学習活動と数学的な見方・考え方 主な支援
5
10
つかむ・見通す
1.本時の学習問題を把握し,本時のめあ
てをつかむ。
(1)本時の学習問題を確認する。
○ 既習の四角形の内角の和から,本時
の図形を提示し,分度器はつかわない
ことと,図形を切らないことを条件提
示し,めあてをもたせる。
(2)本時のめあてをつかみ,見通しをも
つ。
○ 四角形を三角形に分けさせ,2つに
分けた児童に2つの分け方を説明させ
る。
<2つに分ける>
(式)180×2=360
答え 360°
○ 三角形 ACD と三角形 ABC を用意し,
2つの三角形をあわせると,切った角 A
と角 Cが合わさることを捉えさせる。
◆ 四角形を三角形に分けるという見方
◆ 四角形の内角の和は三角形に分ければ
求められるという考え方
○ 素早く既習をふり返ることができる
ように,フラッシュカードを提示する。
○前時との比較をするために,分度器を使
ったり,図形を切ったりして三角形の内
角の和を求めた掲示物を用意する。
○ どの角の大きさの和を求めればよい
のかが視覚的に分かるように,色をつけ
ておく。
○ <2つに分ける>考えを全体で交流
することで,考え方と答えの見通しをも
たせる。
めあて
四角形の角の大きさの和を求める方法を考えよう。
問題
四角形の4つの角の大きさの和は何
度になりますか。

- 高7 -
10
10
つくる
3 見通しをもとに追究し,発表する。
○ 他の分け方はないのかを問い,対角
線で分けた四角形の内角の和の求め方
を自力解決する。
(1)自力解決を行う。
<4つに分ける>
(式)180×4-360=360
答え 360°
◆ 三角形に分けたときに四角形の内角で
はない部分が生まれるという見方
◆ 四角形の内角の和を求めるときは分け
た三角形の全ての和から不要な部分を引
くという考え方
(2)考えを全体で交流する。
○ 三角形 ADE と三角形 CDE と三角形
ABE と三角形 BCE を用意し,四角形
ABCD に戻していくと,角 E は内角の
和には必要ない角度だということを捉
えさせる。
(3)三角形に分けたときには不要部分を
見つければ計算ができることを捉え
させ,3つに分けた三角形を自力解決
する。
<3つに分ける>
(式)180×3-180=360
答え 360°
(4)考えを全体で交流する。
○ 図形を操作しやすいように,四角形を
印刷したカードを児童に配布する。
○ 図と式を関連付けて説明できるよう
に,図に数値や矢印をかき入れ,表し方
を工夫するよう助言する。
○ 既習の角の大きさ(半周=180°,
1周=360°)などのフラッシュカー
ドを提示する。
○360度を引くという見方に思考をつ
なぐために,180×4は解けたが,そ
の後の式がわからない児童を指名し,途
中式を板書する。
○四角形を3つに分ける見方を育てるた
めに,教師が四角形に1本補助線を入
れ,その後児童に残りの1本を書かせ
る。

- 高8 -
8 板書計画
図形の角
2つに分ける 4つに分ける 3つに分ける 練習問題
3
7
まとめる
4 本時のまとめをする。
○ それぞれの考えに共通していること
と,他の3つに分ける四角形,4つに
分ける四角形の例から,本時をまとめ
る。
5 適用問題を解く。
○ 学習の最後に5つに分けた四角形を
提示し,見方を拡張して本時を終える
○ 前時の三角形,本時の四角形の内角の
大きさをふり返り,次時につなげる。
○ 机間指導をして,うまく問題解決でき
ていない子に助言する。
学習問題
四角形の4つの角の大きさ
の和は何度になりますか。
めあて
四角形の4つの角の大きさ
の和を求める方法を考えよう。
まとめ
四角形の4つの角の大きさの和は四角形を三角形
に分けて考えれば求められる。
四角形の4つの角の大きさの和は360°になる。
360°かもしれない
図形を切らない
分度器は使わない
式(A+B+C)+(A+C+D)
=?
180×2=360
式180×4=720
720-360=360
関係のない角の大きさをひく
A.360°
式180×3=540
540-360=360
A.360°
式360-(60+120+
100)=80
A.80°
60° あ
まとめ
四角形の4つの角の大きさの和は,四角形を三角形に分けて考えれば求められる。
四角形の4つの角の大きさの和は,360°になる。
120° 100°

- 高9 -
9 授業の実際と考察
(1) 授業の実際
時間 過程 学習活動と数学的な見方・考え方 主な発問と児童の反応
0
5
15
つ
か
む
・
見
通
す
1 フラッシュカードによるふり返りを
する。
2 本時学習問題を知り,めあてをつか
む。
(1) 学習問題を知る。
(2) 本時のめあてをつかみ,見通しをも
つ。
3 見通しをもとに追究し,発表する。
T: まずは,これまでの振り返りをしま
しょう。正方形の4直角の和は何度にな
りますか。
C:360°
T:では,長方形の4直角の和は何度にな
りますか。
T:どんな四角形を知っていますか。
C:正方形です。
C:長方形です。
C:平行四辺形です。
T:では今日の問題の四角形は何度になり
そうですか。
C:360°になりそうです。
T:では,どうすれば求められますか。
C:対角線で分けて,三角形にしたらいい
と思います。
C:四角形を2つの三角形にわけて考えた
らいいと思います。
C:三角形ABCの角の大きさの和は18
0度で,三角形ACDの角の大きさの和
は180°なので,あわせて360°で
す。
学習問題
四角形の4つの角の大きさの和は何度になりますか。
めあて
四角形の角の大きさの和を求める方法を考えよう。

- 高10 -
25
35
つ
く
る
(1)自力解決を行う。
(2)考えを全体で交流する。
(3) 三角形に分けたときには不要部分を
見つければ計算ができることを捉えさ
せ,3つに分けた三角形を自力解決す
る。
T:2つに分ける以外に,わけ方はありま
せんか。
C:4つに分ける方法があります。
T:三角形が2つの場合は180×2で求
めることができました。しかし,4つに
分けると式はどのようになりましたか。
C:180×4で720°になりました。
T:では,4つの三角形を組み合わせたあ
と,どのように計算すればいいのでしょ
う。
C:360°をひけばいいです。
T:ひく360°はどこにありますか。
C:(図を指して)ここに四角形の角の大
きさの和とは関係のない角が集まって
います。
T:2つ,4つと分けても求めることがで
きました。3つにわけても求めることが
できますか。
C:できます。
T:では,四角形を3つの三角形に分けて,
求めてください。

- 高11 -
38
45
ま
と
め
る
(4) 考えを全体で交流する。
4 本時のまとめをする。
5 適用問題を解く。
○ 学習の最後に5つに分けた四角形
を提示し,見方を拡張して本時を終え
る。
T:1つ目の式は何ですか。
C:180×3=540です。
T:2つ目の式は何ですか。
C:540-180=360です。
T:180というのはどこのことですか。
C:(図を指して)この角度のことです。
T:今日は四角形を3つの求め方で解きま
した。3つの求め方でわかったことは何
ですか。
C:四角形の角の大きさの和は360°に
なる。
C:どの方法も三角形に分けている。
C:四角形の角の大きさに関係のないとこ
ろはひいて考える。
まとめ
四角形の4つの角の大きさの和は,四角形を三角形に分けて考えれば求められる。
四角形の4つの角の大きさの和は,360°になる。

- 高12 -
(2) 考察
◎ 問題の解決に向けて見通しをもつことができる導入
① フラッシュカードによる既習のふり返り
本時の学習のねらいは,四角形の内角の和を三角形の内角の
和を用いて求めることと四角形をいくつかの三角形で分けた
ときに,四角形の内角でない部分をひくことの2つである。
そこで,授業の冒頭に本時の解決に必要となる既習内容(三
角形の内角の和・四角形の名称・直角や一周などの角の大
きさなど)を,フラッシュカードでふり返る活動を行った。子どもたちはフラッシュカードの答え
をスラスラと答えていた。フラッシュカードの中に解決に必要な要素を盛り込んでいたことが,
三角形の要素に気付いたり,四角形の内角でない360°や180°の部分に気付いたりする一
助となっていた。
② 図形の見方や考え方を深めるための段階的な見通しのもたせ方の工夫
今までの学習では,四角形の内角の和を三角形で分けて解く
という見通しをし,自力解決に取り組ませていた。しかし,こ
の流れでは,解ける子と解けない子に差が出てきていた。そこ
で,今回は,四角形を2つの三角形に分けて四角形の内角の和
を求める方法を全体で解き,共通理解した。次に4つの三角形
に分けて解く方法に取り組んだ。ここでは余分な角度を引くと
いうことを共通理解した。その後3つの三角形に分けて解く
方法に取り組んだ。この方法によって,図形を苦手としてい
た子どもたちも見通しをもちながら意欲的に学習に取り組む姿が見られた。このように,段階的
に問題を解いていくことで,子どもたちの考える視点を明確にし,見通しをもたせるという点で
有効であった。
◎ 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決・交流
求める角の大きさに色を付けることで必要な角度と不要な角度を見極めることにつながった。
また,四角形を2つ,3つ,4つの三角形に分けて解く方法の共通点を問いかけた。その結果,
①四角形の内角の和が360°である②構成する三角形の内角の和の合計から不要な角度を引く
③四角形の内角は三角形に分ければ求めることができることに気付くことができた。
◎ 新たな問いを生み出すまとめ
まとめの後に,四角形を5つの三角形で分けている図を提示し,
どのようにすれば解けるか尋ねた。すると,すべての三角形の角
をたし,不要な角を引けばよいという考えで解くことができそう
だという発言が出た。四角形をいくつの三角形で分けても,必要
な角と不要な角を見極めれば解けそうだということに気付かせる
ことができた。

- 高13 -
(3) 課題
○ 適用問題が授業の内容と異なるものになっていたので,段階的に見通してきた視点を生かして解
くことができなかった。
10 資料
○ 学習プリント (本時で使用したフラッシュカード)
○ 板書
11 改善すべき点
〇 3つの段階を仕組んだので,子どもたちに考えたり,発表したりする時間が十分取ることができ
なかった。なので,3つの三角形に分ける方法を適用問題にすると,子どもたちに考える時間を十
分に与えることができたと考えられる。また,授業のつながりを考えると5つの三角形に分ける方
法を適用問題にすることもよかったのではないかと考えられる。

終 わ り に
平成 29 年 6 月に小学校学習指導要領解説算数編が公表されました。今回の改訂では,
各教科等において育成すべき資質・能力の明確化がなされ,「主体的・対話的で深い学び」
の実現に向けた授業の質的改善の推進が求められています。
そして,小学校算数科においては,「数学的な見方・考え方を働かせ,数学的活動を通
して,数学的に考える資質・能力を育成すること」が目標とされています。
そこで,本研究委員会では,第 13 期(平成 29 年~平成 31 年)の研究主題を「主体的
な学びを実現する算数科学習指導法の研究」とし,『数学的な見方・考え方を働かせる数
学的活動の工夫』について研究してまいりました。
今年度の研究の成果としては,
○ 「つかむ・見通す」段階で,①フラッシュカードを使って既習の振り返りをすること
や②問題提示の仕方を工夫することは,問題の解決に向けて見通しをもって自力解決
することができる児童を育成する上で有効であったこと
○ 具体物を使用し,生活場面に直結した操作活動を実際に行うことは,よりよい解決方
法を考え,見通しをもって問題の解決に向かう上で有効であったこと
○ 自力解決においては,あえて1つの考え方に絞って考えをまとめさせることで児童一
人ひとりが自分の考えをしっかり書くことができたこと
○ 交流活動においては、グループ交流と全体交流のねらいを教師がはっきりさせて指導
にあたることで児童の数学的な見方・考え方の広がりや深まりが見られたこと
などがあげられます。
しかし,その一方で今後の課題として,
○ 数学的な見方・考え方を働かせる自力解決や交流活動において,操作活動や言葉によ
る説明はできていたが ,式や図などとつないで説明するまでにはいたらなかった点に課
題が見られたこと
○ 主要問題と適用問題の関連性によってどのような適用問題がよいのか,また,一単位
時間の中での自力解決・交流活動と適用問題の時間配分をどのようにすればよいかを考
える必要があること
などが残りました。これらの課題については,次年度以降,さらに研究を積み重ねていき
たいと考えています。
最後になりましたが,本研究委員会の推進にあたり,ご多用な中ご指導・ご助言をいた
だきました福岡市教育センター研修・研究課主任指導主事 井元 尚史様,授業会場校な
らびに研究委員をご推薦いただきました校長先生方に,心から厚くお礼申しあげます。
また,本研究主題の解明に向け努力していただいた研究委員の先生方の真摯な姿勢に
敬意を表するとともに,次年度に向けさらに実践を積み重ねられますことを祈念いたし
ます。そして,この研究集録が,福岡市の小学校の先生方の算数科の授業改善の一助と
なれば幸いに存じます。
平成30年3月
小学校算数科研究委員会
副委員長 白濱 雅道
(福岡市立青葉小学校教頭)