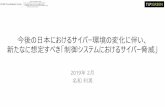3T MRI導入に伴う 安全規程の変更について - BAIC › reference › pdf ›...
Transcript of 3T MRI導入に伴う 安全規程の変更について - BAIC › reference › pdf ›...
現在の倫理・安全審査システム
ATR外の組織がfMRI,MEGを使う場合
各研究機関の倫理委員会(人権・被験者選定手続)
ATR-Promotions 安全委員会(安全)
倫理審査
安全審査
ATRによる審査代行は緊急避難的対応.
各研究機関における委員会設置を進めていただきたい.(協力いたします.)
現在の倫理・安全審査システム書式をダウンロードして記入後事務局に提出
http://www.baic.jp/user/shosiki.html
安全委員会への提出書式(改定予定)
3T MRI導入に伴い変更予定
現在の安全基準
第3条
fMRI装置・MEGシステムを利用する研究においては、 被験者の安全および実験装置の保全を考慮して計測条件 が決定されなければならない。特にfMRI装置を用いる実
験においては、以下の項目について、日本工業規格「磁気 共鳴画像診断装置 – 安全Z4951(JIS Z4951)」の
「通常操作モード」の範囲内で撮像パラメータが設定されな ければならない。撮像中は被験者の安全確保には細心の
注意を払うこととし、被験者が末梢神経刺激等の異常を感 知したと実験担当者に報告した場合には、撮像を中断する こととする。
静磁場強度
磁場強度変化率
比吸収率
騒音
2005年7月25日の
改正に合わせる
静磁場強度3Tは「通常操作モード」ではない
磁気共鳴画像診断装置 – 安全 JIS Z4951:2004
通常操作モード患者に生理的ストレスを引き起こす可能性のある値を一切出力しない
MR装置の操作モード
第一水準管理操作モード一つ又は複数の出力が患者に医療管理を必要とする生理学的ストレス
を引き起こす可能性のある値に達するMR操作モード.
安全基準改定案第3条
fMRI装置・MEGシステムを利用する研究においては、
被験者の安全および実験装置の保全を考慮して計測条件 が決定されなければならない。特にfMRI装置を用いる実験 においては、以下の項目について、日本工業規格
「磁気共鳴画像診断装置 – 安全 JIS Z4951:2004」で規程 された撮像条件で設定されなければならない.ただし
1.5TのMRIの場合は「通常操作モード」の範囲内、
3TのMRIの場合は「第一次水準管理操作モード」の範囲内 で撮像条件を決定する。撮像中は被験者の安全確保には
細心の注意を払うこととし、被験者が末梢神経刺激等の異 常を感知したと実験担当者に報告した場合には、撮像を中 断することとする。
□
静磁場強度
□
磁場強度変化率
□
比吸収率
□
騒音
磁気共鳴画像診断装置 – 安全 JIS Z4951:2004
静磁場
強度
磁場強度 変化率
(dB/dt)
比吸収率
(SAR)騒音
通常
操作モード
2T以下 PNS(*1) の80%
頭部は 3.2W/kg
(*2)
ピーク音圧 レベル(Lp)
140dB(A)
第一水準 管理
操作モード
2T超え
4T以下
PNS (*1) の100%
頭部は 3.2W/kg
(*2)
ピーク音圧 レベル(Lp)
140dB(A)
(*1) PNS=Peripheral Nerve Stimulation (抹消神経刺激が生じる磁場強度変化率)(*2) その他の部位はJIS Z4951:2004に従う(著作権の制限により掲載しません)
現行「安全審査」申請書6. 研究方法
・
実験の方法(前略:それぞれの実験方法についての説明)
fMRI装置の撮像条件について,下記の項目が「核磁気共鳴CT装置の承認申請に際して,臨
床試験の必要で無いものに関するガイドライン」(安全基準別表)の基準内にあるかどうか.
fMRIの撮像条件については,日本工業規格「磁気共鳴画像診断装置 - 安全Z4951(JIS Z4951)」の「通常操作モード」の範囲内であることを随時確認する.使用する島津Marconi製
MAGNEX ECLIPSE 1.5T PD250においては,「通常操作モード」を超える可能性がある場
合には,警告が発せられる.その場合には,撮像条件を吟味しなおして,「通常操作モード」の
撮像条件を満たすように変更する.なお,本実験で用いる可能性のある撮像条件において考
えられる下記のパラメータの最大値等は以下のとおり.
(1) 静磁場強度1.5T(メーカーによる表示に基づく)
(2) 磁場強度変化率軸方向の変化率が20 dB/dtをこえることが無いようにする.通常操作モードの範囲内である.
(3) 比吸収率(SAR)頭部SAR値は,通常操作モード範囲内である「任意の10分間において平均して3W/kg以下」の
条件を満たすようにする.
(4) 騒音測定不能.ただし,使用説明書によれば,「<90dBA(1日8時間平均),<105dBA(1時間平均),
<140dBA(ピーク値)」の厚生省による「核磁気共鳴CT装置の承認申請に際して,臨床試験の
必要で無いものに関するガイドライン(平成3年3月28日事務連絡)」を満たすとしている.耳栓
あるいは密閉型ヘッドホンにより騒音を軽減する措置を取る.
改訂版「安全審査」申請書(案)6. 研究方法
・
実験の方法(前略:それぞれの実験方法についての説明)
fMRI装置の撮像条件について,下記の項目が日本工業規格「磁気共鳴画像診断装置 – 安全 JIS Z4951:2004」
で規程された範囲内で設定されているかどうか.すなわち,
1.5TのMRIの場合は「通常操作モード」の範囲内、3TのMRIの場合は「第一次水準管理操作モード」の範囲内で撮像条件が設定されているか.
使用する1.5TのfMRIの撮像条件は,「JIS Z4951:2004」の「通常操作モード」の範囲内であることを随時確認する.
このモードを超える場合には, ,警告が発せられるので,撮像条件を吟味しなおして,「通常操作モード」の撮像条
件を満たすように変更する.なお,本実験で用いる可能性のある撮像条件において考えられる各項目の最大値等
は以下のとおりで条件を満たしている.
(1) 静磁場強度1.5T(メーカーによる表示に基づく)
(2) 磁場強度変化率平均PNS(Peripheral Nerve Stimulation:末梢神経刺激)しきい値の80%以下の通常操作モードの範囲内であり,
JIS Z4951:2004の図103のL01で表される曲線に相当する.
(3) 比吸収率(SAR)通常操作モード範囲内で以下のとおり.任意の6分間の平均で,全身2W/kg,頭部3.2W/kg以下.その他の身体
部位についてはJIS Z4951:2004の表105の指定に従う.また,局所(10g)では頭部・体幹部10W/kg,四肢20W/Kg 以下.
(4) 騒音140dBA(ピーク値)を超えない通常操作モードである.安全のため実験時は耳栓あるいは密閉型ヘッドホンにより
騒音を軽減する措置を取る.
1.5T MRIの場合
改訂版「安全審査」申請書(案)6. 研究方法
・
実験の方法(前略:それぞれの実験方法についての説明)
fMRI装置の撮像条件について,下記の項目が日本工業規格「磁気共鳴画像診断装置 – 安全 JIS Z4951:2004」で規程された範囲内で設定されているかどうか.すなわち,
1.5TのMRIの場合は「通常操作モード」の範囲内、3TのMRIの場合は「第一次水準管理操作モード」の範囲内で撮像条件が設定されているか.
使用する3TのfMRIの撮像条件は,「JIS Z4951:2004」の「第一水準管理操作モード」の範囲内であ
ることを随時確認する.このモードを超える場合には,警告が発せられるので,撮像条件を吟味しな
おして,「第一水準管理操作モード」の撮像条件を満たすように変更する.なお,本実験で用いる可能
性のある撮像条件において考えられる各項目の最大値等は以下のとおりで条件を満たしている.
(1) 静磁場強度3T(メーカーによる表示に基づく)
(2) 磁場強度変化率平均PNS(Peripheral Nerve Stimulation:末梢神経刺激)しきい値の100%以下の第一水準管理操作
モードの範囲内であり,JIS Z4951:2004の図103のL12で表される曲線に相当する.
(3) 比吸収率(SAR)第一水準管理操作モード範囲内で以下のとおり.任意の6分間の平均で,全身4W/kg,頭部3.2W/kg 以下.その他の身体部位についてはJIS Z4951:2004の表105の指定に従う.また,局所(10g)では
頭部・体幹部10W/kg,四肢20W/kg以下.
(4) 騒音140dBA(ピーク値)を超えない第一水準管理操作モードである.安全のため実験時は耳栓あるいは
密閉型ヘッドホンにより騒音を軽減する措置を取る.
3T MRIの場合