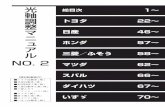日赤和歌山医療センター 整形外科専門研修プログラム · 2 年間の在籍中に整形外科では10 ¡以上が研修しています。整形外科は、これまで毎
国内電子書籍に関する状況整理 Jagat20131206
-
Upload
hiroki-kamata -
Category
Education
-
view
860 -
download
0
description
Transcript of 国内電子書籍に関する状況整理 Jagat20131206

©2013 Hiroki Kamata
本⽇のお話:状況認識
• 変化の本質• 変化への抵抗• ⽇本的エコシステムの解体• 出版の再⽣シナリオについて
2000年のアマゾンe-Bookのロゴ

©2013 Hiroki Kamata
マクロ認識:ITによる出版の再構築
• デジタル出版へのステップ:出版社は鈍感だった– 1990年代〜:⽣産(活字・ページの電⼦化) – 2000年代〜:流通・販売(インターネット)– 2010年代〜:読書(クラウドと端末)
• ⽣産・流通・読書がデジタルに再編=デジタル出版– 歴史上初めて出版が紙から独⽴。変化はこれから本格化– ITを使ったプロセスのコントロール(サービスの最適化)– 印刷本が消えることではない(フォーマットとして重要)
• コミュニケーション、メディアの再編の⼀部– メディアビジネスの主導権をめぐるレース– ⽇本の出版「業界」は変化に抵抗することで消耗・衰退

©2013 Hiroki Kamata
幻の「電⼦書籍」とデジタル出版前夜
• 「電⼦書籍」は勘違い– 書籍は実体。「電⼦書籍」は、ある環境の中にあってはじめて本となる。– 商業的にはオンラインストアと読書端末からなるクラウド環境。– オンライン・マーケティング(顧客データ)と⼀体。
• 読者が読みたいのは本であって、「電⼦…」ではない。– 本の形態:新書、古書、電書– 購⼊判断:話題性、内容、価格、⼊⼿性、装幀、スペース…– ニーズは多様で、選択肢は合理的範囲で多いほど良い。– 現実には市場は硬直している。書店離れが本離れを促す。
• 本が本であるためには、社会的な仕組みが前提となる。– 商業出版社の印刷本(本屋の集客⼒に依存)– 出版者のマーケティング、メディアの書評、書店の販促– 本/著者と読者との関係づけ
■デジタル革命第1期(2008~2013年)でわかったこと

©2013 Hiroki Kamata
⽇本的エコシステム崩壊の予感
出版社
印刷会社
取次
広告代理店
書店
KodanshaShogakukan
Dai NipponToppan
NippanTohan Maruzen
Kinokuniya
古書店
DentsuHakuhodo
著者 読者
図書館

©2013 Hiroki Kamata
変化への最後の抵抗• 「⽇本的電書」への挑戦
– 電⼦辞書、ガラケー出版:世界に先駆け商業ベースで成功– 書籍端末プロジェクト:業界+メーカー– 独⾃の「標準」フォーマット:ここから公的資⾦– さらに公的資⾦:デジ機構、緊デジ、クールジャパン…
• 海賊退治と電⼦出版権– 「版元」優位の法制化の試み– 「版⾯権」の再現:デジタル時代の法制として破綻– 著者、読者の版元離れを促進
• アマゾン課税?– これもグローバル時代の法制として破綻– 払うのはアマゾンではない– 消費者に⾒放され、権⼒にすがる業界に未来はない

©2013 Hiroki Kamata 7
⽇本的業界エコシステムの崩壊• 産業として空洞化
– 知識情報ビジネスとして成⽴・発展させる仕組みを喪失– 先⼈の遺産:商売、教育、冒険(ビジネスモデル)– 職業として:魅⼒がなければ出版ではない
• 出版不況という幻想– 「再販制」という思考停⽌– 読書離れ、本離れという幻想– 遠ざけているのは社会、何もしないのが出版社
• 市場の⽇本的衰退:横並び– ⽂明社会がある限り出版へのニーズは存在するが– 本に接する機会が減っている。去る本は⽇々に疎し

©2013 Hiroki Kamata 8
相互依存性の崩壊
• 誰も儲からない→⾚字のサプライチェーン– 著者⇔出版⇔印刷⇔取次⇔書店– ⽅向性なき膨張:DNP、凸版、楽天、東⽇販– メディアとしての消滅:広告主⇔代理店⇔クリエイター
• ⽀えきれない– マンガ・雑誌不振→書店減少→出版社減少– 現場:マンガ家、編集者、制作者、著者
• 崩落から離れて⽣き残る– ⾓川の独⾃エコシステム– ⾃主出版

©2013 Hiroki Kamata
出版の再⽣シナリオ:ヒント
• 崩壊=再建へのカウントダウンが始まった。– 衰退が⽌まらないと「メディア」として成⽴しなくなる。– ⼼理的には新聞+雑誌で1兆円だが底が⾒えないことには
• 2兆円市場復活へ別のアプローチが始まる。– マーケティング:著者・読者をオーガナイズする「ワールド」– オープンなデジタル・プラットフォームをベースとする。– モノ指向よりサービス指向:マーケティング主導– 雑誌+書籍の⼀体的展開:著者、読者、編集者を育てる– 広告、⾮商業出版との融合:ビジネスモデル主導– 版権ビジネスとグローバリゼーション