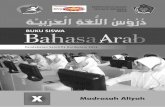- Å À C ß! ! |! V x!§! c Ö! ! !s!...- Å À C ß! ! |! V x! ! c Ö! ! !s! 2( q>/ %· p2¥7³ [...
Transcript of - Å À C ß! ! |! V x!§! c Ö! ! !s!...- Å À C ß! ! |! V x! ! c Ö! ! !s! 2( q>/ %· p2¥7³ [...

1
1.自転車の利用状況について
パーソントリップ調査は、子供や高齢者の移動を十分に考慮できていない点に留意する必要がある。
また、自転車の販売台数と利用実態に乖離があるように感じる。
→パーソントリップ調査の概要について補足説明。調査は、ある 1日を対象に、「どのような人が」、
「いつ」、「どこからどこへ」、「どのような目的で」、「どのような交通手段で」移動しているのか調
べている。トリップの総量に占める代表交通手段毎の割合のことを利用率という。代表交通手段と
は、1トリップの中で使用した交通手段において、予め設定した優先度が最も高い交通手段のこと
で、優先度は、鉄道、バス、自動車、二輪車、徒歩の順となる(例えば、自宅から勤務先まで、徒
歩→バス→鉄道→徒歩で移動した場合には、代表交通手段は鉄道となる)。
図1-1 トリップのイメージ
(第5回仙台都市圏パーソントリップ調査における調査結果の概要用語の説明より抜粋)
→自転車の利用率は、都心地域や一部の地下鉄沿線地域など平野部において高くなっている。
図1-2 自転車分担率(H29 平日_代表)(第 1 回仙台市交通政策推進協議会資料より抜粋)
前回委員会で出た主な意見への対応について
資料1

2
→短中距離帯で利用される主な代表交通手段(徒歩・自転車・バス)のうち、自転車の利用状況を移
動距離帯別にみると、通勤・通学では 1km 以上 3km 未満の移動距離帯で多く利用されているほか、
1km 未満、3km 以上 5km 未満も一定数利用されている。買い物・私事では 2km未満の利用が多い。
図1-3 短中距離で利用される主な代表交通手段(H29 平日_代表)(第 5回パーソントリップ調査より作成)
→国内自転車(新車)販売台数の推計数値と人口比から推計した、仙台市内の自転車(新車)販売台数
をみると、直近 5年では年間 6~7万台で推移している。5年間の新車販売台数の累計は約 32 万台で
あり、令和元年 10月 1日時点の市内人口(5~84歳)に対し約 3分の 1の数値となる。
図1-4 県内自転車(新車)販売台数の推移(推計)
表1-1 国内・県内の自転車(新車)販売台数の推移と全国・宮城県の人口推移
138.2
38.8
5.3
17.1
28.6
20.8
17.3
10.4
5.4
10.2
14.0
15.1
0.0 50.0 100.0 150.0 200.0
0~1km
1~2km
2~3km
3~5km
5km~
通勤・通学 発生集中交通量
徒歩 自転車 バス
(単位:千トリップエンド/日)
31.0
61.9
27.9
10.9
14.2
12.1
12.7
10.1
0.0 100.0 200.0 300.0
0~1km
1~2km
2~3km
3~5km
5km~
買い物・私事 発生集中交通量
徒歩 自転車 バス
300.0 400.0
296.0
(単位:千トリップエンド/日)
67 65
65
60 61
50
60
70
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
市内新車販売台数(推計)(千台)
平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年 5年間累計
国内新車販売台数(推計) (千台) 8,021 7,793 7,669 7,032 7,125 37,640
市内新車販売台数(推計) (千台) 67 65 65 60 61 317
(参考) 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年 令和元年
全国人口(5~84歳) (千人) 117,145 116,769 116,346 115,908 115,488
仙台市人口(5~84歳) (千人) 978 979 980 981 982
0.84% 0.84% 0.84% 0.85% 0.85%
項目
人口比
※国内新車販売台数 出典:一般財団法人自転車産業振興協会 ※全国人口・宮城県人口 各年 10 月 1 日時点、年齢階層毎千人単位の集計数値より計算
出典:政府統計の総合窓口(e-Stat)、仙台市 HP
※精度保証に満たない 2,800 未満の値はグラフに表示していない

3
2.市民の交通ルール遵守に関する状況について
自転車ルールの認知度と交通ルールを守らない理由が並べられているが、ルールを知りながら守ら
ない人がどの程度いるのか。
→令和元年度自転車に関する WEB アンケート調査より、「自転車ルールの認知度」と「自転車ルール
の遵守度」の相関を見ると、それぞれのルールを認知している場合には 6 割を超える割合でルー
ルが遵守されており、ルールを認知していない場合よりも遵守度が高かった。一方、ルールを認知
している場合でも、遵守していないとの回答が 1 割強から 3 割強の割合を占めている。ただし、
歩道通行時の指定場所については認知していないものでも約半数がルールに沿った乗り方をして
いるという結果が得られた。
図2 自転車基本ルールの認知度と遵守度(令和元年度 自転車に関する WEB アンケート調査より作成)
3.アンケートの手法について
「歩道通行時はすぐに止まれる速度で走行する」というルール自体が認知されていないように感じ
るが、アンケートではこのルールを認識しているものか問う内容になっているか。アンケートの際には
単に「ルールを知っているか」、「ルールを守っているか」を問うだけでなく、映像を呈示して危険性に
ついて考えてもらうなどして、乗車状況を振り返る等の工夫が重要である。
→令和2年度自転車に関する WEB アンケート調査実施の際に下図のとおり手法を検討する。
図3-1 令和元年度までのアンケート調査票 図3-2 令和2年度のアンケート調査票(案)
35.4
23.9
37.7
50.0
64.6
76.1
62.3
50.0
0% 20% 40% 60% 80% 100%
認知していない
73.9
65.6
64.3
83.6
26.1
34.4
35.7
16.4
0% 20% 40% 60% 80% 100%
車道走行時は左側端を通行
路側帯通行時は車道の左側を通行
歩道通行時は車道寄りを徐行
歩道通行時は指定場所を徐行
認知している
n=379
n=360
n=244
n=323
n=48
n=67
n=183
n=104
守っている 守っていない
イメージ
作成
Q〇:次の図の中から、交通ルールに違反していると思わ
れる自転車の番号をすべてチェックしてください
(交通ルールを守っていると思われる自転車の番号
はチェックしない)。

4
4.ヘルメットの着用率等について
ヘルメット着用に関する回答者の属性等を細かく分析することで、実際にどのような場面でヘルメ
ット着用が進んでいないのかという実情がわかり、対策の方向性が見いだせるのではないか。
→令和元年度自転車に関する WEB アンケート調査より、自転車に乗る際に、ヘルメットを「いつも着
用している」「時々着用している」と回答した人を性別・年代別の着用率を見た結果は下図のとお
り。各属性における傾向を掴むにはヘルメット着用者のサンプル数が少ないが、各年代において男
性の方が女性よりも着用率が高い状況が見られた。女性では 10 代、20 代と 70 代以上での着用者
はいなかった。
図4-1 自転車乗車時のヘルメット着用状況(令和元年度 自転車に関する WEB アンケート調査より作成)
→条例の認知度別のヘルメット着用率をみると、「条例を詳しく知っている」と回答した人の着用率
が 13%と最も高く、条例の認知度が下がるほど着用率も低くなる傾向がみられた。
図4-2 条例認知度別 自転車乗車時のヘルメット着用状況(令和元年度)
(令和元年度 自転車に関する WEB アンケート調査より作成)
6.6
2.7
3.8
0.9
1.9
2.6
92.5
95.4
93.5
0% 20% 40% 60% 80% 100%
令和元年度
平成30年度
平成29年度
いつも着用している ときどき着用している 着用していない
n=417
n=372
n=427
2
4
5
2
4
4
1
1
1
1
7
30
37
41
33
39
33
0 10 20 30 40 50
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代以上
いつも着用している 時々着用している 着用していない
n=9
n=34
n=42
n=44
n=38
n=44
n=34
1
2
1
2
1
14
24
25
44
29
29
10
0 10 20 30 40 50
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代以上
いつも着用している 時々着用している 着用していない
n=14
n=24
n=26
n=47
n=30
n=31
n=10
13.0%
10.5%
5.1%
2.7%
2.1%
87.0%
89.5%
94.9%
97.3%
97.9%
0% 20% 40% 60% 80% 100%
詳しく知っている
まあ知っている
条例の名前は聞いたことがある
あまりよく知らない
全く聞いたことがない
いつも・ときどき着用している 着用していない
n=46
n=181
n=79
n=73
n=48
男性 年代別 女性 年代別

5
49.5
27.1
34.4
24.3
21.6
17.9
3.2
32.0
37.8
32.0
29.7
30.2
15.7
8.1
0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 %
必要性を感じないから
移動距離が短いから
荷物になるから
恰好が悪いから
髪型が崩れるから
値段が高いから
その他
男性 女性
→令和元年度調査における「(自転車に乗るとき)ヘルメットを着用しない」と回答した人の、ヘル
メットを着用しない理由は「必要性を感じないから」が 41.5%と最も高く、「移動距離が短いから」
「荷物になるから」の順で高かった。過年度においても同様の傾向であるが、「必要性を感じない
から」と回答した割合は平成 30 年度と比べると約 10%下がっている。ヘルメット未着用の理由を
男女別にみると、男性では女性に比べ「必要性を感じないから」と回答した割合が高く、女性では
男性に比べ「移動距離が短いから」、「格好が悪いから」、「髪型が崩れるから」と回答した割合が高
かった。年代別に見ると、10代においては「荷物になるから」「格好が悪いから」と回答した割合
が高く、また、年代が若いほど「必要性を感じないから」と回答した割合が高い傾向が見られた。
年齢の高い世代ほど「移動距離が短いから」と回答した割合が高くなる傾向がみられた。
図4-3 ヘルメットを着用しない理由(複数回答)
(令和元年度 自転車に関する WEB アンケート調査より作成)
5.自転車の駐輪環境について
仙台市の託児施設で子育て中の母親に話を聞いたところ、多くの方から「市内のアーケード街近辺で
買い物をする際に自転車を停められる場所が欲しい」との意見が聞かれた。放置自転車は減少傾向にあ
るということだが、地域ニーズに合った駐輪場の整備を進めて欲しい。
41.5
31.9
33.4
26.3
25.6
17.0
5.3
51.9
33.4
32.3
25.7
23.5
14.9
2.8
54.4
33.3
24.9
18.2
15.4
9.0
5.4
0.0 20.0 40.0 60.0 80.0 100.0
必要性を感じないから
移動距離が短いから
荷物になるから
格好が悪いから
髪型が崩れるから
値段が高いから
その他
% % %%%%
■ 令和元年度集計データ(N=395)
■ 平成30年度集計データ (N=362)■ 平成29年度集計データ (N=390)
57.1
51.9
41.9
38.8
40.3
36.8
34.9
33.3
16.7
24.2
29.4
21.0
44.1
62.8
0.0 % 10.0 % 20.0 % 30.0 % 40.0 % 50.0 % 60.0 % 70.0 %
10代
20代
30代
40代
50代
60代
70代以上
必要性を感じないから 移動距離が短いから 荷物になるから
恰好が悪いから 髪型が崩れるから 値段が高いから
その他
ヘルメット未着用理由(年度別)
ヘルメット未着用理由(男女別) ヘルメット未着用理由(年代別)

6
→状況を確認。商店街によって状況は異なるが、ぶらんどーむ一番町等では、附置義務により設置し
ている民間の駐輪場は点在するが、必ずしも、わかりやすい看板が出ているとか、誰でも利用しや
すい状態になっている状態ではない状況が見受けられた。
→庁内関係課と連携し、必要な対応策について検討する。
6.施策に関する主な意見・取り組むべき施策の対応(一覧)について
第 1回委員会における施策に関する主な意見 取り組むべき施策例
※表中の項番は資料 2「仙台市自転車の安全な利活用推進計画
骨子案」における取組むべき施策例の番号に対応
環境や自転車利用の仕方に関して、将来の方向性がイメージできて、
市民・県民が共有できるようなものがあるとよい(例えば「CO2 削減」
を共通目標にするなど) 計画の趣旨の一つとして示す
(各施策案の検討においても留意)
10 年後、20 年後の将来を見据えた方向性も踏まえて実効性のある施
策を検討することが必要
市民の参加や活動を支え、後押しするような施策展開が必要(ドイツ
では市民が自分たちでアイデアを考えそれに補助金、助成金を出して
いる)
(9)自転車を活用したライフスタイルの提案
・自転車利用を推進する団体等との協働
ヘルメットの着用促進が必要(デザインや機能性に優れたヘルメット
の開発や、行政が率先してヘルメットを着用するなど)
(3)一人ひとりの自転車安全利用意識を高める普及啓
発活動の推進
・条例の周知に合わせ、保険加入・ヘルメット着用促
進に向けた取組みを実施 ヘルメットの被り方の周知が必要
自転車が路肩を安全に走行できるような路面清掃による小石の除去
等のハード以外の対策も必要 (4)自転車ネットワーク路線の設定・整備
・都心部ネットワーク路線の設定・整備
・補助幹線道路等の代替路活用したネットワーク
路線の拡充
・他エリアのネットワーク路線の追加
(5)安全・安心に通行できる自転車走行環境の整備
・あんしん通行路線等の整備
・道路標識・道路標示・信号機の適切な設置・運用
・自転車通行環境の適正な維持管理(路面清掃等)
・自転車走行環境のドライバーへの周知
路面表示等の整備は、自転車利用者の誤解を招かない整備実施が必要
歩行者最優先の道路ネットワーク形成が必要(自転車は本来車道に下
ろさなければならない)
地域の特性に応じた自転車利用の仕方や利用環境の整備推進が必要
自転車走行環境のドライバーへの周知が必要(国道 45 号では車道走
行する自転車に対するあおり運転についての苦情有り)
地域ニーズに合った駐輪場の整備が必要
(6)利便性の高い駐輪環境の整備・更新
・公共駐輪場の整備及び改修・改善
・民間駐輪場の活用促進
駅等の主要施設におけるコミュニティサイクルの案内標識の設置が
必要
(7)都心部におけるシェアサイクル等の利便性向上と
観光利用の促進
・「DATE BIKE」の案内看板の設置、インバウンド対
応(多言語化など)
・観光案内パンフレットを用いた外国人に対する自
転車利用方法の紹介
シェアサイクルの遠方からの出張サラリーマン等への浸透が必要
シェアサイクルのインバウンドへの対応が必要
外国人を対象とした交通安全対策が必要
観光案内のパンフレットに、イラスト等を用いて外国人にもわかりや
すい自転車利用の仕方を掲載するなど、啓発のための工夫が必要
シェアサイクルと自転車販売のバランスを考えることが必要(シェア
サイクルが居住者に普及しすぎると自転車販売業者の廃業が進み業
界に悪影響)
シェアサイクル利便性向上を図り、観光利用の促進を図
る方向で進める




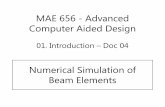
![( !4 Á#ë >á>Ü>ß>Ü>Ö>Ö>Ù>Ù - 内閣府防災担当È8 ' È Ý>Ì>Ý? è V >Ö >Ö >Ù >ß>Ü >Ý e ¿ ] ,¨ ]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fc948c504859a764d0c20d9/-4-oeoe-eoeec.jpg)



![¹ B>ß>Ü º>ß v ô'ì%· FÊ ¥ ö =FËH 4 ) H - KAWABE · ¹ B>ß>Ü º>ß v ô'ì%· FÊ ¥ ö =FËH 4 ) H ¹ B>ß>Ü º>á v>Ý>à ¥ V &k ¡ ]3¶ 4 ' &k V v , d ¾ GAG GW$](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5e7b7c08f1250763aa59d010/-boe-v-f-fh-4-h-kawabe-boe.jpg)
![- tauheed-sunnat.com Namaz (... · ÌÖ'Úıƒ´ Üônßuôƒ$ Ö ] àôÛF u߃$ Ö] äô×# Ö ] Üô −ß eô Üôm߃ôÓłÖß] äôÖôçß›ö–ło×F ´ł oß ×ôø™ł](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5e033a0ad9e2ea2f20425952/-tauheed-namaz-oe-oenu-f-u-.jpg)