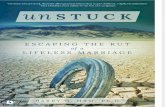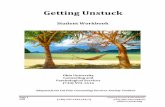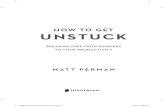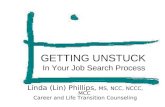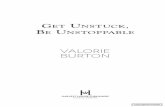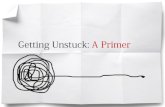Success story for your business Red Hat K.K....
-
Upload
vuongkhuong -
Category
Documents
-
view
219 -
download
4
Transcript of Success story for your business Red Hat K.K....
の度、Red Hatでは事例 PR誌「OPEN EYE」を創刊する運
びとなりました。これは文字通り事例を中心に最新の技術トレンドや当社プロダクトの最新情報など、みなさまのお役に立つ情報を発信するためのものです。ここにはオープンソースのリーディングカンパニーとしての自負が込められています。オープンソースとは単にプログラムのソースが公開されているだけにとどまらず、そこに参加する企業や個人が価値や問題意識を共有し、さらに新しい価値を生み出すことにあります。そのためには数多くのユーザーを抱えているベンダーである当社が積極的に情
報発信していく必要があると考えます。
化するIT業界の中でオープンソースの役割はより重要に
なっています。ハードウェアの物理的な制約に縛られて分散と統合を繰り返していた時代は終わりを告げ、仮想化による統合、さらにはSOAによるソフトウェアのコンポーネント化による再利用、クラウドコンピューティングによりシステムがサービス化される現在、オープンソースの活用度がビジネスの成否を分けるといっても過言ではありません。さらに、業務にフィットするシステムが求められる一方でシステムに
より業務プロセスを改革することも求められています。 このような時代に求められる情報とは何か?「OPEN EYE」では、この命題にチャレンジしていきたいと思います。オープンソースを普及させるにはIT部門だけでなく、業務部門、さらには社内のエンドユーザーへの理解を広める必要があります。例えばWindowsでExcelを使うといって反対の声があがるケースはほとんどありませんが、シンクライアントでOpen Officeを使うとなると社内の抵抗感を感じることもあります。そうした場合、他社のIT部門がどのように業務部門や社内ユーザーを説得したかが分かると、大きな力となるはずです。
そこで、「OPEN EYE」では、ソリューションの活用法や導入効果を伝えることはもちろん、IT部門と業務部門、現場で働く人たちとの関わりという面にも着目し、企画・設計から導入、運用、見直しというプロセス、システムのライフサイクルを意識した情報発信を目指していきます。
一回目の本号は巻頭特集として、昨年起ちあげられたユー
ザー会の会長である大和総研の鈴木専務執行役員、同理事であるNTTのオープンソースソフトウェアセンタの木ノ原センタ長に対談形式でお話を伺いました。異口同音に「ユー
ザーが増えることでオープンソースの価値を享受できる」と語るお二人のご意見は、オープンソースを活用する企業にとって大きな指針となるはずです。 また株式会社オージス総研の百年アーキテクチャ構想に基づく経営戦略、大阪ガスで推進されているオープン化の事例なども紹介。新たに発表されたばかりのRed Ha t Enterprise Virtual izat ionの製品情報とあわせ、仮想化環境の構築に役立つ情報が満載です。
去る2010年3月9日、米Red Hat社の仮想化事業を統括するRed Hat仮想化製品担当シニアディレクター Navin R. Thadani(ナヴィン・R・サダニ)が来日。新たな仮想化ソリューションについて会見を行いました。
こ進
第
事例には、
ユーザーの安心や
羅針盤となる応訴が
あると思います。
木ノ原
氏
オープンソースは、
ユーザーのニーズが
技術更改を
牽引するのが理想です。
鈴木
氏
○
>>>
○
最新の技術トレンドや最新の技術トレンドや当社プロダクトの最新情報を発信当社プロダクトの最新情報を発信創刊記念号創刊記念号
創刊特別対談
ユーザー会が果たす役割とは?オープンソースにおいて
三位一体となって、OSSを推進していきます。創刊のごあいさつ
創刊創刊特別対談特別対談
創刊創刊のごあいさつのごあいさつ
導入導入事例事例
Success Story
ユーザー会が果たす役割とは?が果たす役割とは?オープンソプンソースにおいてにおいて
オージス総研
百年アーキテクチャ構想百年アーキテクチャ構想のもと、確のもと、確かな経営基盤経営基盤とビジネとビジネス戦略実現ス戦略実現のため、のため、Red HatRed Hatによるオープン化を推進によるオープン化を推進
○ Red Hatリーディング・アイRed Hat Enterprise LinuxとJBossが示す、クラウドコンピューティングのあるべき姿とは?
○ 新製品レポート物理サーバと変わらないパフォーマンスと信頼性を低コストで実現する Red Hat Enterprise Virtualization
木ノ原 誠司氏大和総研専務執行役員
NTT OSSセンタセンタ長 鈴木 孝一氏
Seishi Kinohara Kohichi Suzuki
レッドハット株式会社 代表取締役社長 廣川 裕司廣川 裕司
Success story for your business Red Hat K.K. EDITORIAL 2010
OPEN EYE 01vol.2010 SPRING
オープンソースの新時代を築く、サクセスストーリーオープンソースの新時代を築く、サクセスストーリー
―この「OPEN EYE」は、事例を中心にオープンソースソフトウェアの活用に役立つ情報を広くユーザーに発信しようという目的で創刊されたものです。 鈴木さんはユーザー会のリーダを務められているわけですが、オープンソースの領域においてRed Hatが先進事例を紹介する意義をどう思われますか?
これまで、オープンシステムの技術更改はソフトウェアベンダーやハードウェアベンダーが主導してプロダクトをユーザー
に降ろす形で進められてきました。しかし本来OSS(オープンソースソフトウェア)は横の関係、つまりユーザーニーズにより技術更改を先導するのが理想です。その場合、ユーザー各社は他社のOSS活用状況を参
考にして、自社ニーズを明確にしていかねばならず、その意味で先進事例の紹介はOSSユーザーにとっても必須の情報であるといえるでしょう。 またOSSというと技術者の趣味的なアプローチのように誤解される面があります。実際はその逆でいかにITをビジネスに活かすかというアプローチを行った結果、ユーザーがOSSを選択してきたのです。 私が関わっている情報通信・金融分野では、さまざまな課題を解決するためにRed Hatの導入が、他の産業に比べ進んでいると思われます。そのひとつが東証次世代システムです。とはいえ規模の大きな製造業等ではまだ普及が進んでいないのが現状なのではないでしょうか。 今後、グローバル化がますます加速する市場において日本企業の競争力強化にはITの有効活用は不可欠であり、安全で安価なインフラを手に入れられる点でも、OSSによる標準化はもはや待ったなしの状況にあるのではないかと思い
ます。その点で最大手であるICTが事例を紹介する意義は大きいと思います。(鈴木氏)
―木ノ原さんはNTTグループにおいて、ICTソリューションでのオープンソースソフトウェア活用を促進されている立場だと思いますが、そうした活動をふまえて事例の意義をどう思われますか?
オープンソースは廉価での利用が可能な反面、サポート体制を初めとするサービスの貧弱さを不安視する人もいま
す。特に我が国のICT業界のように高い信頼性を要求される分野においてはなおさらなので、先行事例の多さは、顧客に対
する安心感や新技術導入のための羅針盤として重要な役割を果たすと思います。 さらに、こうした情報をオープンソースビジネス業界のキャリングビークルであるRed Hatから、開かれた形で発信することは、オープンイノベーションが進みつつあるICT業界の動きを加速すると同時に、豊富な人材チャネルを活かした、ICT利用技術という観点からのコミュニティ活動の更なる推進をはかる物になりうると思います。(木ノ原氏)
―ユーザーの立場から見て、われわれベンダーがどのような情報発信をするべきだと思いますか?
前述のようにオープンソース利用におけるユーザーの悩みの1つには、いかに簡単かつ安心して使えるかということがあげられます。先進的な導入事例もその解消に役立つわけですが、それ以外にもハードウェアを含めたバーティカルモデルの動作確認がプロプラ
去る2010年3月9日、米Red Hat社の仮想化事業を統括するRed Hat仮想化製品担当シニアディレクター Navin R. Thadani(ナヴィン・R・サダニ)が来日。新たな仮想化ソリューションについて会見を行いました。
Seishi Kinohara
事例には、
事例には、
ユーザーの安心や
ユーザーの安心や
羅針盤となる応訴が
羅針盤となる応訴が
あると思います
あると思います。
木ノ原
木ノ原 氏
「OPEN EYE」の創刊に当たり、「レッドハットエンタープライズユーザー会(Red Hat Enterprise User Group)の初代会長である鈴木 孝一氏(大和総研 専務執行役員)、木ノ原 誠司氏(日本電信電話株式会社 研究企画部門 NTTオープンソースソフトウェアセンタ センタ長)にお話を伺いました。先進ユーザーでもあるお二方が考えるオープンソース活用の極意、ベンダーに求める姿とは?
オープンソース活用の極意はユーザーとベンダーのコラボレーションにある。
オープンソースは、
ユーザーのニーズが
技術更改を
牽引するのが理想です。
鈴木
氏
○
>>>
○
最新の技術トレンドや当社プロダクトの最新情報を発信創刊記念号
創刊創刊特別対談特別対談
ユーザー会が果たす役割とは?が果たす役割とは?オープンソプンソースにおいてにおいて
三位一体となって、OSSを推進していきます。創刊のごあいさつ
創刊特別対談
創刊のごあいさつ
導入事例
ユーザー会が果たす役割とは?オープンソースにおいて
百年アーキテクチャ構想のもと、確かな経営基盤とビジネス戦略実現のため、Red Hatによるオープン化を推進
○
○
廣川 裕司
木ノ原 誠司氏大和総研専務執行役員
NTT OSSセンタセンタ長 鈴木 孝一氏
Seishi Kinohara Kohichi Suzuki
2 OPEN EYE
Success story for your business
オープンソースの新時代を築く、サクセスストーリー
イエンタリな製品に対抗する上での肝になると思います。 ICTの発展のスピード感についていくためには、ハードベンダー等も巻き込みながらコンフォーマンステスト等を行い、ユーザーにやさしい「オープンソースバーティカルモデル」の構築活動とそのフィードバック情報の共有が出来ればと思います。クリス・アンダーソン著の『FREE』を参考に、日本流の情報&技術の展開方法があるのではないかと期待しています。(木ノ原氏) 情報発信という意味では、まずオープンソースの技術そのものではなく、オープンソースの活用がコストダウンにどのように直結するのか、また現状のUNIXからの乗り換えのタイミングやその時のリスクや負荷などの情報を経営層に発信していくべきではないでしょうか。(鈴木氏) ―本誌の読者の多くはオープンソースソフトウェアを活用している、もしくは検討している企業だと思います。そういった方々に情報をどのように活用してほしいと思いますか?
先ほどもお話ししたように、事例情報は「新技術導入のための羅針盤」として重要な役割を果たすと思います。ユーザー会がそうであるように、志あるユーザーはこうした情報の共有をきっかけとして、新たな視点から「ユーザーコミュニティ」を構築していきます。 オープンイノベーションの中では経験やノウハウを共有しながら、いかにスピード感をもって技術を展開していくかが鍵となるのではないでしょうか。
この「OPEN EYE」から発信される情報がOSS利用者のチャレンジ精神創生と、行動力の源泉となることを期待しています。(木ノ原氏) ベンダー主導のシステム構築モデルが一般的であった時代に、高コストだと思いながらもシステム開発を続けてきた、あるいは続けざるをえなかった苦い経験を持つCEOは、「システム投資=高コストで低パフォーマンスの投資」という先入観を持っている可能性があります。開発コストの妥当性が判断しづらく、ビジネスのスピードについていけないという思いも強いでしょう。 抜本的なITコストの削減やビジネスニーズへの迅速な対応には、Red HatやLinux OSに代表されるオープンソース化による標準化が効果的だと考えているCIOやIT部門は多い一方で、決断できないでいる日本企業がほとんどだと思います。 今話題のクラウドコンピューティングを例にとると、多くのユーザー企業はグーグルやアマゾンを思い浮かべてしまい、顧客情報を抱える業務はクラウドへ移行できないと決めつけてしまうケースもあります。しかしそれは誤解なので、今一度、ユーザー企業にクラウドが持つ潜在力(標準化)をきちんと説明すべきだと思います。 実際、クラウドは何も一時に自社システムすべてを切り替える必要はないのです。リプレースのタイミングで、試行導入をして体験してみることがポイントだと思います。特殊な業務のための独自インフラは一旦そのままとしても構わないのですから、段階的に導入することも可能なはずです。
本誌は経営者向け情報誌として、クラウドをはじめ、仮想化やSOAなどに対するOSSへのアプローチ手順を分かりやすく発信してほしいと思います。(鈴木氏)
―今回お話をお聞きして、オープンソースソフトウェアの活用促進においてはユーザーと我々ベンダーが横並びの関係で双方向にコミュニケーションを行い、またコラボレーションしていくことが重要だと実感しました。この「OPEN EYE」も単なる情報発信にとどまらず、ユーザーのみなさまとのコンタクトハブとして機能するよう、今後ますます発展させていきたいと思います。本日はありがとうございました。
最近OSSに対する関心が高まっている一方、まだまだミッションクリティカルなシステムへの導入は進んでいません。それはOSSの信頼性への誤解や経営層への認知不足など、さまざまな要因が挙げられます。 しかしOSSの信頼性やパフォーマンスは飛躍的に向上しています。OSレイヤーに限らず、ミドルウェア、アプリケー
ションまで、企業のインフラを形成するピラミッドのすべてをOSSでまかなえるようになっています。 その中で私たちRed Hat社はニュートラルな立場を保ちながら、『Cost』『Innovation』『Agil i ty』の3つに集約される価値を提供しています。最近では仮想化が不可欠になっていますが、Red Hat Linuxでは既にOSレベルで仮想化
に対応し、物理環境と変わらぬ信頼性とパフォーマンスを提供。JBossを活用したシステムも数多く稼働しています。これにより企業は『徹底したTCO削減』と『革新的技術の導入』を『いち早く』実現できるのです。 私たちはこうした実績をパートナー企業およびユーザー企業のみなさまと共有し、三位一体となって情報や技術
を常にフィードバックして参ります。OPEN EYEもその活動の一環としてお客様にとって価値あるニュースを提供いたしますので、今後ともよろしくお願いいたします。
去る2010年3月9日、米Red Hat社の仮想化事業を統括するRed Hat仮想化製品担当シニアディレクター Navin R. Thadani(ナヴィン・R・サダニ)が来日。新たな仮想化ソリューションについて会見を行いました。
レッドハット株式会社代表取締役社長
廣川 裕司
Kohichi Suzuki
事例には、
ユーザーの安心や
羅針盤となる応訴が
あると思います。
木ノ原
氏
オープンソースは、
オープンソースは、
ユーザーのニーズが
ユーザーのニーズが
技術更改を
技術更改を
牽引するのが理想で
牽引するのが理想です。
鈴木鈴木
氏
○
>>>
○
最新の技術トレンドや当社プロダクトの最新情報を発信創刊記念号
創刊特別対談
ユーザー会が果たす役割とは?オープンソースにおいて
三位一体三位一体となってとなって、OSSを推進していきます。を推進していきます。創刊創刊のごあいさつのごあいさつ
創刊特別対談
創刊のごあいさつ
導入事例
ユーザー会が果たす役割とは?オープンソースにおいて
百年アーキテクチャ構想のもと、確かな経営基盤とビジネス戦略実現のため、Red Hatによるオープン化を推進
○
○
廣川 裕司
OPEN EYE 3
Red Hat K.K. EDITORIAL 2010
オープンソースの新時代を築く、サクセスストーリー
―百年アーキテクチャの出発点はどこにあったのでしょうか?
「きっかけは、持続可能な社会の実現です。地球温暖化やエネルギー、資源の枯渇が世界中で問題になっている中、ITの分野で貢献できるものはないかと思ったのです。
最近注目されているグリーンITは、IT機器の電力消費量=CO₂排出量を減らそうとするハードウェアからのアプローチが中心ですが、われわれソフトウェアの世界では何ができるかを模索しました。 実際、1946年に世界初のコンピュータENIACが開発されてから現在までの歴史の中で、ソフトウェアは『作っては壊し』
を繰り返してきました。これに関わっている人や労力、資金、時間は膨大なものです。そういうやり方を変えて、持続可能なシステム、再生可能なシステムを実現することは社会的にも大きな意義があるはずです。 そんな中『もしシステムを百年持続させなければならないとしたら、本質的に何が必要だろうか』というところから、百年アーキテクチャ構想が具体化しました」(平山氏)。
―ITの世界で百年というと途方もない数字のような印象も受けるのですが
「確かにドッグイヤーとかマウスイヤーとか言われる、変化の激しい ITの世界で本当に100年先を考えるのか?と思われる方も多いと思います。しかし何千万円あるいは何億円もかけて開発されているものは間違いなく5年後、10年後も使
用されるでしょう。30年後に存続しているシステムもゼロではないはずです。 実際に『2000年問題』が起こったとき、
1980年代あるいは1970年代のソフトウェア、中には1960年代に作られたソフトウェアの修正に苦労された方も多いのではないでしょうか? 今開発している大規模なビジネスシステムが『100年存続するかどうか』は別として、100年のスパンでシステムを考えることは、20年、30年持続するシステムをより真剣に考えるためのアプローチになるはずです」(平山氏)。
―では、百年アーキテクチャという視点で捉えたとき、本質的に必要とされるモノは何なのでしょうか?
「例えば住宅業界には『100年住宅』という考え方を打ち出している会社があります。これは百年間住宅をそのままの形で残すということではなく、しっかりとした躯体を作っておくことによって、家族変化やライフスタイルの変化に合わせてリフォームしながら快適に住み続ける、つまり『百年間変化し続ける』ということです。 これをソフトウェア業界に置き換えると、巨大なシステムが長期間持続かつ機能し続けるためには、まずビジネスにフィットしたしっかりとした設計の上で、時代の流れに耐える強くてシンプルな構造、ニーズや環境の変化に合わせて機能やインタフェースの追加・変更が容易な適応性が必要であ
るといえます」(平山氏)。
―ではビジネスにフィットし、時代の流れに耐える構造、ニーズに応じた追加・変更を容易にするために必要なテクノロジーは何なのでしょうか?
「第一に強い構造をつくるために必要な技術には、モデリングがあげられます。我々も古くからUMLなどのモデリング技術を活用していますが、ビジネスフィットしたシステムをつくるためにはビジネスプロセスを取り入れたBPMN(Business Process Modeling Notation)などを含め、モデリングが今後一層、重要になってきます。 第二に柔軟性を実現するには、部品を入れ替えたり追加したりといったことが簡単にできなければなりません。これはまさしくSOA(Service Oriented Architecture)の考え方そのものです。もちろん、SOAを効率的に実現するにはプラットフォームが仮想化されていることもひとつのカギとなります」(平山氏)。
―モデリング、SOA、仮想化という技術が核になるというお話ですが、その中でオープンソースソフトウェア(OSS)はどういう役割を担えるのでしょうか?
「モデリングとSOAの2つができていれば良いかというと、
株式会社オージス総研は、大阪ガスのITインフラを担う会社として誕生し、現在、関西を中心に日本の大手企業のシステム構築を手がける会社です。今、ITを取り巻く環境が技術的、経済的、社会的に激変する中、百年アーキテクチャを標榜して明確な戦略を打ち出しています。今回は代表取締役社長 平山 輝氏の話を中心に今後のオープンソースソフトウェア(OSS)活用のヒントを探ります。
百年アーキテクチャ構想百年アーキテクチャ構想のもと、のもと、オーオープンソプンソースを活用しースを活用してSOASOA、仮想化、クラウドを推進。仮想化、クラウドを推進。
JBossの活用により700万契約世帯向けサービスのID管理を低コスト、高信頼で実現。
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
JBoss+Red Hatを選んだ決め手は社内向けポータル構築の経験
JBossの活用により、コスト1/10で安定稼働を実現
700万契約世帯へのサービス提供を考えると
低コスト、高信頼のID管理が不可欠
ベンダー依存から脱却し、ビジネスにフィットするシステムを目指す大阪ガス
顧客サービスの充実のため、契約世帯向けのマイページを構築
テクニカルサポートの情報提供により、技術開発がスムーズに
JBossによりビジネスの継続対策を含めたシステム運用を効率化
JBossの適用範囲を拡げ、全社最適化からグループ最適化へ。Red Hatの仮想化環境の進化にも期待。
平山 輝 氏株式会社オージス総研 代表取締役社長
進化のカギは、オープン(OSS)、モデリング、SOA。そしてクラウド。
百年生き残るシステムは、百年進化し続けるシステム。
4 OPEN EYE
Success story for your business
導入事例導入事例Success Story
オージス総研トップインタビュー
導入事例
そうではありません。例えばパッケージソフトのバージョンアップ費用やサポートの問題があります。極端な話、ベンダー側の都合で来年サポートが打ち切られることもあり得ます。そういうことを考えるとOSSというのがひとつの方向性になります。 最近では、ソースコードが公開されているOSSが、OSからミドルウェア、データベース、アプリケーションやERPまで幅広く使用されてきており、エンタープライズシステムを構築するのに問題ないレベルまで品質が向上してきています。IT投資の削減や、より短期間での開発が求められる時代にOSSの採用は避けて通れないと思います」(平山氏)。
―最近ではクラウドコンピューティングが話題を集めています。これまでのお話を聞くとまさしくクラウドに向かっていると思われますが御社のクラウド戦略についてお聞かせください。
「確かにクラウドのように社外にあるシステムをサービスとして利用するケースが増えています。とはいえ、いきなりすべてがクラウドに移行できるわけではありません。例えば電力会社、ガス会社の料金システム、鉄道会社の運行管理システム、金融の勘定系などは絶対に雲の上に持っていかないですよね。少なくても現状は、ずっと地上のデータセンターにあると思います。 しかし、ERP、人事サービス、顧客向けのポータルなどはみな雲の上にもっていくかもしれません。そう考えると、将来の企業システムはクラウドと社内システムの融合体になるはずです。 これからは汎用のクラウドで運用できるサービスは何か、社内にずっと残しておくべき根幹の戦略的なシステムは何か、ということを選別することになるでしょう。 そのような場合、クラウドと
社内の他システムと連携させなければなりません。ですからそれらを結びつける E S B(Enterprise Service Bus)が必要になってきます。もっと言えば、『クラウドサービスバス』というものが必要なのではないでしょうか。ここでもやはりOSSがカギになります。我々は求められるサービスレベルに応じて社内システムと社外のクラウドを組み合わせる活用をクラウドインテグレーションと呼び、独自のサービスを展開しています。いろんなシステムが連携していても、それをユーザーに意識させずに利用できるようにするノウハウを持っていることが我々の強みだと思います」(平山氏)。 ―企業の中にはOSSについて不安を感じる、あるいはなかなか導入に踏み切れないというケースも多く見られます。 例えばOSSの活用について、大阪ガスでの反応はいかがでしょうか?
「大阪ガスを例にとると歴史的な必然性のようなものがあります。半世紀前から大型のメインフレームを中心にシステムを導入していましたが1990年代にオープン化がスタートし、2000年代に業務用のサーバを統合する動きがありました。数多くの場所に分散していたサーバをいくつかのデータセンターに集約したのです。ただ、単純にサーバの場所が移動しただけだと意味がないので同時に仮想化を進めていきました。その中でLinuxなどを導入し、大阪ガスも一緒に体験していますので、OSSへの理解は早かったと思います。 他のお客様でも、IT投資をより効率化したいという傾向が強くなっていますので、百年アーキテクチャやOSSに対する理解が増えています。 今まで保守的で手を出さなかった企業でも興味を示している印象です。何もかもLinuxにするのではなく、段階的に移行できるということが広まっ
ているのではないでしょうか」(平山氏)。
―OSSはその担い手となる人材も重要になると思います。最後に御社の育成方針やビジネスの展望をお聞かせください。
「もともとオージス総研はオブジェクト指向言語やモデリング技術に早くから取り組み、社外に公表する以前からOSSでフレームワークをつくっていた土壌もあります。人材育成については、社内の研修制度が職種にあわせてきめ細かく実施しています。OSSの活用という面でも、社内のサポート部門としてエンタープライズオープンセンターを設立しました。これは標準のスタックをつくり、検証できる環境を作り上げることでOSS 活用を促進するためです」(平山氏)。
―最後に、今後OSS普及のカギとなる部分、またRed Hatに期待することは何でしょうか?
「オープンソースの根源には、開発されたモノはお金を出した人だけのものでなく人類共通の財産という高い志があります。長い目で見るとその理想は広がると思いますが、一番の課題はビジネスモデル
の確立です。 例えば、パッケージソフトなら自社のソフトだけ分かっていれば良いのですが、オープンソースはそうはいきません。我々はOSS導入の標準化をつくりながら、そこにチャレンジしていきます。自分たちが全てを把握することができなくてもワンストップの窓口になりながら、例えばLinuxやJBossの部分はRed Hatに任せるなどのアライアンスを組んでオー
プンソースを広めていきたいと思います。OSS導入の標準化は既に大阪ガスのシステムにおいて実績を上げていますので、アライアンスが強化できれば適用範囲も広げられます」(平山氏)。
百年アーキテクチャ構想のもと、オープンソースを活用してSOA、仮想化、クラウドを推進。
JBossの活用により700万契約世帯向けサービスのID管理を低コスト、高信頼で実現。
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
JBoss+Red Hatを選んだ決め手は社内向けポータル構築の経験
JBossの活用により、コスト1/10で安定稼働を実現
700万契約世帯へのサービス提供を考えると
低コスト、高信頼のID管理が不可欠
ベンダー依存から脱却し、ビジネスにフィットするシステムを目指す大阪ガス
顧客サービスの充実のため、契約世帯向けのマイページを構築
テクニカルサポートの情報提供により、技術開発がスムーズに
JBossによりビジネスの継続対策を含めたシステム運用を効率化
JBossの適用範囲を拡げ、全社最適化からグループ最適化へ。Red Hatの仮想化環境の進化にも期待。
スタックの標準化と アライアンスでOSSの普及を推進。
企業システムはクラウドインテグレーションへ
IT環境の最適な組合せ
クラウドインテグレーション
クラウドを含めた統合認証
SOA・ESBによる連携
サービスレベル、セキュリティ上からオンプレミスグループIT最適化の視点からグループクラウドパブリッククラウドへ移行可能
・Amazon・Google・Salesforce.com
実現
パブリッククラウド
・E-mail、 ファイルサーバ・連結会計システム
大阪ガスグループ
社内データセンター
グループクラウド
・料金システム・顧客受付システム
オンプレミス
OPEN EYE 5
Red Hat K.K. EDITORIAL 2010
導入事例 導入事例
オージス総研と大阪ガスでは百年アーキテクチャ構想のもと、オープンソースソフトウェア(OSS)の導入を積極的に展開しています。その大きな理由はパッケージソフトウェアの場合、好む好まざるに関わらず、定期的にバージョンアップやパッチ処理が強いられ、いつサポートが切れるかどうか分からないというリスクがあります。さらにはライセンスコストやメンテナンスの工数が嵩みTCOの増大にもつながります。 とはいえOSSの導入および活用自体が本来の目的ではありません。大阪ガスのビジネスおよび時代の変化に対する対応力こそが重要なのです。現在、大阪ガスのシステムにおいては全社最適化からグループ最適化へ向かう段階であり、既存のシステムで使えるものは有効に活用しながら、新しくつくるシステムはOSSへと移行されています。
現在、家庭向け/企業向けを問わず、エネルギー産業は大きな変革期を迎えています。太陽光発電や燃料電池はもちろん、特定の地域で行われている風力発電などもふまえ、さまざまな形態が誕生してきています。 そんな中、大阪ガスではサービスの充実と顧客のロイヤリティ向上のために新たなポータルサイト『マイ大阪ガス』を構築するプランが持ち上がりました。
「マイ大阪ガスとは、大阪ガスが運営する家庭用ガス契約者を対象とした会員制サイトであり、お客さまひとり一人のガスの利用状況や嗜好にあわせ、常に最適な情報のご提供を目指すモノでした」(北村氏)。 「その内容は、ガス料金情報や大阪ガスのキャンペーンなどに関する情報はもちろんのこと、『献立カレンダー』や『健康』『グルメ』『映画』『気象』といった、暮らしに役立つさまざまなジャンルの生活情報を掲載することで、エネルギー利用の可視化とともにより身近に大阪ガスを感じてもらおうという意図がありました」(田村氏)。
ではマイ大阪ガスを構築するに当たり、オージス総研が直面したシステム要件とはどこにあったのでしょうか。 「大阪ガスは関西のインフラを担う企業ゆえに契約世帯数も700万を超えています。顧客向けサービスの構築にあたっては個人情報の保護が必要不可欠で、高いセキュリティを確保できる認証管理基盤が重要になります」(北村氏)。 「とりわけID管理は顧客の個人情報に関わることであり、より重要になります。従来はパッケージソフトのID管理システムを利用していた実績と経験があるのですが、その場合、1ユーザーあたりいくらというライセンス体系のため、コストが高くつくのです」(田村氏)。 「一方で、ライセンス料金を抑えられたとしても信頼性に問題のあるモノは使えません。そうした条件を
洗い出す中で最終的な候補として残ったのが、Red Hatが提供しているJBossのソリューションでした」(北村氏)。
オープンソース活用のプロセスはフリーのソースを活用して試用した後、ベンダーのサポートのもとで、より幅広い領域に適用するというケースが多く見られます。オージス総研においても同様のステップを踏み、今回の導入に踏み切られたようです。 「先ほどお話ししたシステム要件を満たすソリューションとしてJBossによるID管理を選択したのですが、その決め手となったのは大阪ガス社内のポータル構築での経験があったからこそだといえるかも知れません。 この社内ポータルの構築においてはパッケージソフトのサポート終了、カスタマイズの自由度などを考慮してOSSでシステムを構築しました。その中でさまざまなシステムの情報を連携させるミドルウェアとしてJBossを採用しており、そこでトラブルなく運用できたことが今回の大きなベンチマークとなったといえます」(北村氏)。
では、Red HatのJBossソリューションを導入したメリットはどこにあったのでしょうか? 「前述の社内システムではフリーで活用できるJBossを活用したのですが、マイ大阪ガスの構築では
株式会社オージス総研では前述の平山社長のコメントにもあるように、百年アーキテクチャ構想を軸にシステムの最適化、新規アプリケーションの導入を展開しています。今回はプラットフォームサービス本部 ソーシングビジネス部 運用業務第一チーム マネージャー 北村 裕司氏、プラットフォームサービス本部 IT基盤ソリューション第三部 基盤技術第一チーム マネージャー 田村 賢氏にRed Hatを活用した具体的なソリューション事例をお聞きしました。
大阪ガスとオージス総研の百年アーキテクチャ構想を加速するRed Hatのソリューション
百年アーキテクチャ構想のもと、オープンソースを活用してSOA、仮想化、クラウドを推進。
JBJBossの活用によりの活用により70700万契約世帯向けサービスの0万契約世帯向けサービスのID管理を低コスト、高信頼で実現。D管理を低コスト、高信頼で実現。
01ベンダー依存から脱却し、ビジネスにフィットするシステムを目指す大阪ガス
背景
システム構築のプロセス
・ 百年アーキテクチャ構想の実践・ パッケージソフトからの解放・ 部門最適から全体最適へ
02顧客サービスの充実のため、契約世帯向けのマイページを構築
ビジネス課題
・ 省エネのための利用量可視化・ お役立ち情報の提供・ 顧客のロイヤリティ向上
03700万契約世帯へのサービス提供を考えると低コスト、高信頼のID管理が不可欠
ビジネス課題を実現するためのシステム要件
・ 強固なセキュリティ・ 大規模システムへの対応・ ライセンス料の低減
04JBoss+Red Hatを選んだ決め手は社内向けポータル構築の経験
Red Hat(JBoss)を選んだ決め手
・ 導入と運用が低コスト・ OSSならではの柔軟性・ トラブルなしの運用実績
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
Red Hat(JBoss)を選んだ決め手JBoss+JBoss+Red Hatを選んだ決め手はRed Hatを選んだ決め手は社内向け社内向けポータルポータル構築の経験構築の経験
Red Hat(JBoss)のメリット 1JBossの活用により、JBossの活用により、
コストコスト1/10で安定稼働を実現1/10で安定稼働を実現
ビジネス課題を実現するためのシステム要件700700万契約世帯への万契約世帯へのサービス提供サービス提供を考えるとを考えると
低コスト、高信頼のID管理が不可欠低コスト、高信頼のID管理が不可欠
背景ベンダー依存から脱却しベンダー依存から脱却し、ビジネスにビジネスにフィットするシステムを目指す大阪ガスフィットするシステムを目指す大阪ガス
ビジネス課題顧客サービスの充実のため、顧客サービスの充実のため、
契約世帯向けのマイページを構築契約世帯向けのマイページを構築
テクニカルサポートの情報提供により、技術開発がスムーズに
JBossによりビジネスの継続対策を含めたシステム運用を効率化
JBossの適用範囲を拡げ、全社最適化からグループ最適化へ。Red Hatの仮想化環境の進化にも期待。
6 OPEN EYE
Success story for your business
導入事例 導入事例導入事例Success Story
オージス総研システム構築レポート
Red Hatのサポートが受けられるJBossソリューションを採用しました。それでもパッケージソフトに比べコストが1/10に抑えられ、安定した稼働を実現しています。実際にパッケージソフトを活用したID管理の場合、サーバなどのハードウェアリソースをより多く確保する必要がありますが、JBossを活用すれば限られたリソースで安定したパフォーマンスを発揮できるのです」(田村氏)。 「もちろんJBossには、コストやパフォーマンスに限らないオープンソースならではのメリットがあります。今回のマイページではメインフレームのデータなどもIDに紐づけなければなりません。JBossと同様にオープンソースのESBであるMuleと連携させることで、ユーザーにはシステムの違いを意識させることなく、すべてを一元化して情報提供できるようになったのです」(北村氏)。
「Red HatのJBossソリューションを活用したメリッ
トは、テクニカルサポートによる情報提供に他なりません。当社はそこから得られた情報をもとにトレーニングを行い、技術開発、システム構築をスムーズに行うことができました」(北村氏)。 オープンソースの魅力のひとつにはフリーで活用できるというメリットがある反面、問題が生じたときのサポートを受けられないという不安があります。Red Hatがそうした問題を解決する一助を担っているひとつの証明といえるのでないでしょうか。
オープンソース活用を積極的に推進しているオージス総研および大阪ガスにおいてJBossの利用は、単にマイ大阪ガスにとどまらないようです。 「大阪ガスのシステムにおいては、BCP(ビジネスの継続を実現するシステムプラン)としてRed HatのKVM(リナックスのカーネルベースでの仮想化技術)を活用したバックアップシステムを構築しています。バックアップシステムの管理のために人員を多く割く
のは効率的ではないので、システムの運用の省力、つまりより少ない人数で運用できることが重要となります。そうした展開もふまえ、このシステムにおいてもJBossを活用しています。社内ポータル、マイ大阪ガスを含めて効率的に運用できるトータルなシステムとしてJBossオペレーションネットワークが用意されているからです」(北村氏)。 「JBossオペレーションネットワークを活用した立場で言うと、今までコマンドで実施していたデプロイについてGUIとなり操作性が向上したのが一番の実感です。さらに、アプリケーションの処理明細が分かるようになり、設定値の管理を一元化できるようになり、しきい値を設定した監視による細かな運用が可能になりました」(田村氏)。
最後にオージス総研、大阪ガスの今後の展望についてお聞かせいただきました。 「当社では、大阪ガス本社の全社最適化のレベルを超え、グループ最適化を視野に入れた取り組みを行っています。現在は、JBossをベースにスケジュール管理システム(グループウェア)を独自に開発しようとしている段階です。 繰り返しになる部分もありますが、JBossオペレーションネットワークによる運用管理を導入したのも、こうした適用範囲の広がりをにらんだものです」(田村氏)。 「さらに、前述のBCPシステムにおいてRed HatのKVMを活用しているように今後も進化していくRed Hatの仮想化環境を積極的に活用したいと思っています。 そして社会に貢献するシステムインテグレータとして大阪ガス以外にもOSSを活用したソリューション提案を拡げていきたい。そのためのパートナーとしての役割をRed Hatに期待しています」(北村氏)。
大阪ガスの情報システム会社としてスタートするも、現在では関西のみならず日本有数のシステムインテグレータとして活躍のフィールドを広げています。他社に先駆けてモデリング技術、オープンソース活用、SOA構築、クラウドインテグレーションを手がけ、ユーザーの業務内容や規模に応じて最適なソリューションを提供しています。 事実、ビジネスプロセスを考慮したコンサルティング、モデリングのための組織から、それをシステムに実装するためのエンタープライズおよびオープンソースの技術検証センターまでトータルなソリューションを提供する組織を整備しています。特に自社内にクラウドを構築するプライベートクラウド、社外にシステムをアウトソースするパブリッククラウド、既存のオンプレミス(社内データセンター)を連携させるクラウドインテグレーションをいち早く打ち出し、先進的なノウハウを蓄積しています。
株式会社オージス総研とは?
田村 賢 氏
株式会社オージス総研プラットフォームサービス本部IT基盤ソリューション第三部
基盤技術第一チーム マネージャー
北村 裕司 氏
株式会社オージス総研プラットフォームサービス本部
ソーシングビジネス部運用業務第一チーム マネージャー
▼ ID管理システム構成図
百年アーキテクチャ構想のもと、オープンソースを活用してSOA、仮想化、クラウドを推進。
JBossの活用により700万契約世帯向けサービスのID管理を低コスト、高信頼で実現。
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
・ ・ ・
05JBossの活用により、コスト1/10で安定稼働を実現
Red Hat(JBoss)のメリット 1
・ パッケージに比較してコスト1/10・ 大規模運用に耐えられる安定性・ 既存システムとの柔軟な連携
06テクニカルサポートの情報提供により、技術開発がスムーズに
Red Hat(JBoss)のメリット 2
・ 経験に裏打ちされた情報提供・ 社内トレーニングへのフィードバック・ スムーズな開発
07JBossによりビジネスの継続対策を含めたシステム運用を効率化
Red Hat(JBoss)のメリット 3
・ JBossソリューションの統合管理・ BCPなどとの連携・ 一元管理によるトータルな省力化
08 今後の展望
・ グループ最適化におけるOSS活用・ KVMによる仮想化活用範囲の拡大・ 強固なパートナーシップの構築
JBoss+Red Hatを選んだ決め手は社内向けポータル構築の経験
JBossの活用により、コスト1/10で安定稼働を実現
700万契約世帯へのサービス提供を考えると
低コスト、高信頼のID管理が不可欠
ベンダー依存から脱却し、ビジネスにフィットするシステムを目指す大阪ガス
顧客サービスの充実のため、契約世帯向けのマイページを構築
Red Hat(JBoss)のメリット 2テクニカルサポートの情報提供により、テクニカルサポートの情報提供により、
技術開発がスムーズに技術開発がスムーズに
Red Hat(JBoss)のメリット 3JBossによりビジネスの継続対策をJBossによりビジネスの継続対策を含めたシステム運用を効率化含めたシステム運用を効率化
今後の展望JBossの適用範囲を拡げ、JBossの適用範囲を拡げ、
全社最適化からグループ最適化へ。全社最適化からグループ最適化へ。Red Hatの仮想化環境の進化にも期待。Red Hatの仮想化環境の進化にも期待。
JBossの適用範囲を拡げ、全社最適化からグループ最適化へ。Red Hatの仮想化環境の進化にも期待
アプリケーションサーバとアカウントマスタ及び動作パラメータを保存するDBサーバで構成。(OS、ミドルウェアともオープンソースを活用)
Red Hat Enterprise LinuxJBoss 4.x mule 2.1.1EE
Red Hat Enterprise LinuxMySQL 5.1
APサーバ DBサーバ
アカウントマスタDB
ESB Mule Based OGIS IdMエンドユーザーセルフサービス(パスワード変更、リマインダ)
http(s) LDAPv3
JDBC
一般ユーザー
アカウント情報の連携(プロビジョニング)
ディレクトリサーバアカウントの申請、承認
ワークフロー
監査ログのエクスポート
監査ログ
アカウントマスタDBのメンテナンス
アカウント情報の取込(ポーリングして、更新があれば取込)
大規模構成や可用性が要求される場合は、AP、DBともスケールアウトして対応する。
http(s)管理者
CSVファイル
RDBサーバ
OPEN EYE 7
Red Hat K.K. EDITORIAL 2010
導入事例 導入事例
Red Hat NEWS
去る2010年3月9日、米Red 去る2010年3月9日、米Red Hat社の仮想化事業を統括するHat社の仮想化事業を統括するRed Hat仮想化製品担当シニアRed Hat仮想化製品担当シニアディレクター ディレクター Navin R. ThadaniNavin R. Thadani(ナヴィン・R・サダニ)が来日。(ナヴィン・R・サダニ)が来日。新たな仮想化ソリューションに新たな仮想化ソリューションについて会見を行いました。ついて会見を行いました。
「新しいRed Hat Enterprise Virtualization for Servers(以下RHEV)は、KVMの仮想
化テクノロジーをベースにし、そのコア機能(Hypervisor)は既にRed Hat Enterprise Linux 5.4のカーネルに格納されています。これによりスケーラビリティ、セキュリティ、パフォーマンスなどの実証済のメリットがそのまま受け継がれ、L i n u x はもちろん、Windows OSなどを仮想環境上で稼働させ、一元管理できます。」(ナヴィン)。
まずナヴィンが強調したのはコスト的な優位性です。 「例えば2ソケット搭載の物理サーバ10台で仮想化環境を構築した場合、VMWareと比較して初年度のコストで最大約1/7、導入から3年間のコストで最大約1/3のコスト差になります。また分かりやすい
GUIインタフェースを備えており、まるでグーグルで検索するような感覚で仮想サーバやアプリケーションを管理できます。システム管理者の負担を軽減し、TCOの削減にも貢献します。」
RHEVはパフォーマンスにおいても物理環境と変わらないレベルを実現しています。 「KVMを核にすることにより、高いパフォーマンスを発揮できます。実際に物理サーバでの運用と比較してSAPにおいて最大95%、ORACLEで最大93%、LAMPのパフォーマンスにおいては最大139%パフォーマンスを発揮するという結果が出ています。さらに省電力機能でグリーンITにも対応し、カーネルに統合された
「SELinux」を使うことで、ホストとゲスト、あるいはゲスト同士を分離して高いセキュリティを確保できます。」
Red Hatでは仮想化環境においても物理環境と同等のサービスレベルと互換性を保証しています。 「物理サーバと仮想サーバの双方で同一アプリケーションの実行を保証します。万が一、仮想環境において障害が発生しても、我々はパートナーや顧客
企業と緊密に協力して問題解決に当たります。」 さらにRHEV 2.2ベータ版では、リモートデスクトッププロトコルにSP ICE(S imp l e Protocol for Independent Computing Environments)を採用した仮想デスクトップ環境を実装。デスクトップからサーバまでをトータルにコントロールできる仮 想 化ソリューションを実現します。今後も進化を続ける Red Hat Enterprise Virtualizationにご期待ください。
海外では社内のほとんどのシステムをクラウド上にアウトソースし、管理コストを大幅に削減した企業が多くあります。一方で利用を控える企業もあり、今後クラウドをさらに推進するには、技術の標準化が重要なトピックになってくるでしょう。例えば複数のクラウド間でデータのやり取りが行われるようになると、それぞれに異なる仕様ではポータビリティが確保できません。Red Hatはオープンソースの特性を活かし、仮想化に関してはKVM、メッセージングに関してはAMQP、クラウド間の共通のAPIとしてDeltacloudといったように各技術の標準化に取り組んでいます。 さらに、クラウドの利用が広まればソフトウェアのライセンスの考え方も変わってきます。あるクラウド環境で利用中のソフトウェアを別のクラウド環境に移して利用を継続するというケースも増えるかも知れません。Red Hatはグローバルに事業を展開するオープンソース・カンパニーとして、今後、そのような運用も視野に入れた製品体系をお客様に提供していく予定です。
Red Hat社はクラウドコンピューティングにおいてもリーダ的役割を担っており、KVMを活用したクラウドの構築に必要な全てのツールを提供しています。 その事例として最大のものはIBMの開発者向けクラウドでしょう。IBMのクラウドではKVMを利用して仮想化を行い、Red Hat Enterprise Virtualizationを利用することで管理をシンプルかつ効率化することも目指しています。 さらにクラウドコンピューティングにおけるRed Hatの最初のパートナー、Amazon EC2もテクノロジーおよびビジネスの両面で高い注目を集めています。両社は、Red Hat Enterprise LinuxとJBossの両方を使用したEC2のさらなる展開への期待に手応えを感じ、将来のクラウド技術について緊密な共同作業を続けています。日本国内でもNTTコミュニケーションズが提供予定のクラウドサービスにRed Hatが活用されており、日本発の日本企業向けクラウドとして期待されています。
レッドハット株式会社グローバルサービス本部プラットフォームソリューショングループソリューションアーキテクト 鶴野 龍一郎 氏
★KVM スタートアップサービス ◎仮想化技術KVMについてトレーニング◎導入と管理を行うために必要な技術的な基礎知識と操作1人 4万円/1日から
★仮想化技術ワークショップ ◎KVMまたはRHEVを検討しているお客様の検証をご支援◎コンサルタントがお客様環境にてパイロット導入をご支援80万円/4日間から
★仮想化技術導入支援サービス ◎KVMまたはRHEVの導入をご支援◎コンサルタントがお客様環境にて導入をご支援100万円/5日間から
★仮想化技術コンサルティング サービス 【詳細は、お問合わせください】
◎KVMまたはRHEVの適用、運用、移行等のコンサルティング◎お客様の環境にあわせた設計、運用、移行などのご支援
Red Hat Enterprise LinuxとJBossが示す、クラウドコンピューティングのあるべき姿とは?Amazon EC2で実績を積んだクラウドコンピューティングソリューションを日本のお客様に提供します。
Red Hat Enterprise Virtualization 仮想化サービスラインアップ NEW!★ 2010年4月から仮想化のための新サービスを提供開始しました。是非ご検討ください。
オープンソースの仮想化環境をリードするRed Hat
VMWareよりも初年度1/7、3年の運用で1/3の低コスト
物理サーバとの互換性をパートナーシップの下で保証
基幹DBでも物理サーバとほぼ変わらないパフォーマンス
物理サーバと変わらないパフォーマンスと信頼性を低コストで実現する
Red Hat Enterprise Virtualization
事例には、
ユーザーの安心や
羅針盤となる応訴が
あると思います。
木ノ原
氏
オープンソースは、
ユーザーのニーズが
技術更改を
牽引するのが理想です。
鈴木
氏
○ Red Hatリーディング・アイ
◎ レッドハットの製品、サービスに関するお問い合わせはこちらまで >>>>>> セールス オペレーションセンター ☎ 0120-266-086(携帯電話からは ☎ 03-5798-8510)〔受付時間/平日9:30~18:00〕 e-mail: [email protected]
○ 新製品レポート
最新の技術トレンドや当社プロダクトの最新情報を発信創刊記念号
創刊特別対談
ユーザー会が果たす役割とは?オープンソースにおいて
三位一体となって、OSSを推進していきます。創刊のごあいさつ
■ Amazon Web Services(AWS)■ Amazon Elastic Computing Cloud(EC2) ・仮想レンタルサーバ ・Amazon Machine Image(AMI) ・Amazon EC2 command-line Tool ・ElasticFox(Firefox Plugin)
■ Amazon Web Services(AWS)■ Amazon Elastic Computing Cloud(EC2) ・仮想レンタルサーバ ・Amazon Machine Image(AMI) ・Amazon EC2 command-line Tool ・ElasticFox(Firefox Plugin)
■ Amazon Simple Storage Service(S3) ・オンラインストレージ ・AMIも格納可能■ Amazon Simple Queuing Service(SQS)
■ Amazon Simple Storage Service(S3) ・オンラインストレージ ・AMIも格納可能■ Amazon Simple Queuing Service(SQS)
★Amazon EC2について
▼ Red Hat Enterprise Virtualizationの優位性
Red Hat
68,000円/ソケット/年
(RHEV for Servers)
47万円程度(含ゲスト)
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
96コア、1TBメモリ
16vCPU、64GBメモリ
VMWare
289,000円/CPU
(vSphere Advanced)
153万円程度
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
Yes
64コア、512GBメモリ
8vCPU、256GBメモリ
Microsoft
454,000円/CPU
(Enterprise)
193万円程度(含ゲスト)
Yes
Yes
48コア、1TBメモリ
4vCPU、64GBメモリ
ベンダー
単価
2サーバ構成、初年度費用概算
ライブ・マイグレーション
負荷分散機能
省電力機能
高可用性機能
イメージ・マネージャ
メモリ・オーバーコミット
メモリ・ページ・シェアリング
ホスト最大構成
ゲスト最大構成
製品比較 RHEV vSphere Hyper-V/System Center
創刊特別対談
創刊のごあいさつ
導入事例
ユーザー会が果たす役割とは?オープンソースにおいて
百年アーキテクチャ構想のもと、確かな経営基盤とビジネス戦略実現のため、Red Hatによるオープン化を推進
○
○
廣川 裕司
Success story for your business Red Hat K.K. EDITORIAL 2010
OPEN EYE Vol.012010年 5月 発行
発行:レッドハット株式会社東京都渋谷区恵比寿4-1-18tel:03(5798)8500
オープンソースの新時代を築く、サクセスストーリー