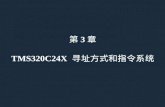当期純利益 令和元年(2019 12 月期-第 57 令和 …...2020/02/01 · 1 令和元年(2019)12月期-第57期- 決算ダイジェスト 令和2 年(2020)2月10
令和元年度 第2回 川口市文化財保護審議会 次 第令和元年度 第2回...
Transcript of 令和元年度 第2回 川口市文化財保護審議会 次 第令和元年度 第2回...
-
令和元年度
第2回 川口市文化財保護審議会
次 第
日 時 令和 2年 2月 18 日(火)
午前 10 時
場 所 川口市立文化財センター
3階 図書室
1 開 会
2 あ い さ つ
(1) 川口市文化財保護審議会 会長
(2) 川口市教育委員会 生涯学習部長
3 議事録署名委員の指名
4 議 事
(1) 指定候補文化財の審議について
ア 「木造薬師如来立像付旧厨子」
イ 「里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子」
(2) 旧田中家住宅保存活用計画(案)の策定について
5 報 告
令和元年度文化財保護事業報告について
(1) 文化財保護係の事業について
(2) 埋蔵文化財係の事業について
6 そ の 他
7 閉 会
-
令和元年度
第2回川口市文化財保護審議会
会 議 資 料
日 時 令和2年2月18日(火) 午前10時00分
場 所 川口市立文化財センター図書室
川口市教育委員会
-
川口市文化財保護審議会委員名簿
氏 名 担 当 備 考
有元 修一 有 形 会長・大学名誉教授
青木 義脩 埋 蔵 副会長・元県審議会委員
黒津 高行 有 形 大学教授
後藤 治 有 形 大学理事長
鈴木 淳 有 形 大学教授
鈴木 誠 記念物 大学教授
田村 均 有 形 大学教授
西沢 淳男 有 形 大学教授
林 宏一 有 形 公立博物館長
三田村 佳子 民 俗 元県職員
川口市教育委員会事務局
教 育 委 員 会 生 涯 学 習 部
埋蔵文化財係
管 理 係
文化財保護係
文 化 財 課
郷 土 資 料 館
-
4 議 事
(1)指定候補文化財の審議について
ア 「木造薬師如来立像付旧厨子」(別添資料 1 P1~12)
種 別
名 称
員 数
所 在 地
所 有 者
年 代
有形文化財 彫刻
木造薬師如来立像付旧厨子
一躯
川口市大字安行慈林954
宝厳院
室町時代後期
イ 「里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子」(別添資料 2 P13~20)
種 別
名 称
員 数
所 在 地
所 有 者
年 代
有形文化財 考古資料
里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子
一頭
川口市本町1丁目17番1号
川口市
室町時代
(2)旧田中家住宅保存活用計画の策定について(別添資料 3 P21)
―1―
-
5 報 告
令和元年度文化財保護事業報告について
(1)文化財保護係の事業についてア 指定文化財の保護・管理事業
(ア)国指定重要有形民俗文化財「木曽呂の富士塚」管理事業
樹木管理委託事業
擁壁改修工事に伴う健全度調査委託事業
(イ)赤山城跡保存整備事業
樹木管理委託事業
保存整備用地賃貸借事業
保存整備事業用地購入(大字赤山・赤芝新田 1887.02 ㎡)
(ウ)国指定重要文化財建造物「旧田中家住宅」管理事業
建物管理事業
庭園管理事業
各種修繕事業
ブロック塀・万年塀改修工事
(エ)指定文化財防火管理状況査察(消防局共催)
文化財防火デー協賛事業として実施(1 月 24 日(金))旧田中家住宅他 5 件
(オ)補助事業
市指定無形民俗文化財安行藤八の獅子舞公開用浴衣修繕事業
指定文化財管理維持費の交付
無形民俗文化財保存伝承活動事業補助金(5件)
イ 文化財調査・記録事業
(ア)指定候補文化財調査
木造薬師如来立像付旧厨子調査
里字屋敷添第 2 遺跡出土烏帽子調査植木業の文化的景観調査
赤山陣屋敷址調査
薬研屋・旧永瀬鉄工所跡調査
(イ)市内文化財現況調査(芝機織物見本帳他)
―2―
-
(ウ)民俗文化財調査事業
鋳物業関係資料及び民具資料の収集・調査・整理事業
ウ 文化財普及啓発事業
(ア)伊奈氏に関する交流イベント
「忠次と伊奈町・忠治と川口市―映像で伊奈氏を偲ぶ―」
【期 間】
映像解説・現地案内
令和元年11月24日(日)13:30~16:00
パネル展示・映像公開
令和元年11月19日(火)~12月15日(日)
【場 所】
歴史自然資料館
【内 容】
映像上映・解説
① 「伊奈忠次~関東の水を治めて泰平の世を築く~」
解説:伊奈町教育委員会 小杉 秀幸 伊奈町学芸員
② 「赤山陣屋に立つ~関東代官伊奈氏と赤山陣屋」
解説:川口市教育委員会 谷川 隼也 学芸員
現地見学会 赤山陣屋めぐり
【参加人数】
47名
(イ)文化財調査報告会の開催(予定)
日 時 令和 2 年 3 月 22 日(土)場 所 並木公民館視聴覚室
講 演 「慈林薬師のご本尊について」
林 宏一 氏(川口市文化財保護審議会委員)
「戦国川口の考古学」
浅井 希 学芸員
(ウ)歴史と文化を学ぶ体験教室 (資料 P1)
(エ)旧田中家住宅実施事業 (資料 P2)
(オ)郷土資料館実施事業 (資料 P2)
(カ)歴史自然資料館実施事業 (資料 P3)
―3―
-
(キ)文化財愛護団体育成事業
川口文化財サポーター魅がきたい育成事業(12 回実施)内 容 重要文化財旧田中家住宅の清掃 他
エ 古文書等文献資料の調査・記録・保存・普及活用事業
(ア) 古文書、古書籍、写真等の調査・収集・保存作業
① 元郷の倉田家資料の調査収集
年代:江戸期から明治・大正期
内容:主に江戸期は質物手形証文類他、明治・大正期の書類 57 件を寄贈。
② 戸塚の加藤家資料の調査収集
年代:明治期・大正・昭和 30 年代内容:主に江戸期は質物手形証文類他、明治・大正期の書類 57 件
を寄贈。
③ 西立野の早船家資料の調査収集
年代:江戸期・昭和期
内容:主に江戸期立野村年貢割付状他、昭和期の早船家の書類 19件寄贈。
④ 収蔵資料の記録整理作業
明治期資料の活用のための記録解読の作業を実施。
(イ)古文書講座の開催
① 夏休み子ども体験教室「この文字!探検隊!」&「旧田中家住
宅探検隊」
開催日 8 月 1 日(木)・2 日(金)2 日間場 所 旧田中家住宅1階日本間
講 師 古文書調査員2人
受講者 延 12 人内 容 江戸時代の寺子屋での読み書きを疑似体験する。また、
旧田中家住宅を見学する。
② 古文書初級講座「古文書ってなに?」
開催日 11 月 9 日(土)、10 日(日)、16 日(土)、17 日(日)4 日間場 所 川口市立文化財センター図書室
講 師 古文書調査員 2 人受講者 延 110 人内 容 江戸期の村方史料により、初歩的な古文書の読み方を
体験学習。
―4―
-
オ 協力事業
(ア)学校支援事業
① 歴史教室(小・中学生)
令和元年4月 11 日(木)~令和 2 年 1 月 30 日(木)来館コース 2 校、出前コース 45 校、資料貸出コース 1 校計 48 校、4,422 人
② 社会科見学・生活科町探検(小学校 2~6 年生)小学校 42 校、計 3,519 人
③ 「きらり川口 夢わーく体験事業」の支援
中学校 5 校、15 名
④ 学力向上支援事業「手づくり社会科マップコンテスト」への
協力
(古地図展示、土器展示、拓本体験、縄文土器文様付け体験等)
開催日 令和元年 11 月 15 日(金)、16 日(土)体験コーナー 拓本体験、縄文土器文様付け体験(16 日のみ
実施)
体験コーナー参加者数
拓本体験 50 名トレース体験 8 名川口検定 45 名
(イ)講演会・盛人大学等への専門職員の派遣
① 【生涯学習課主催】
「市民大学講座 南平の歴史と文化を考える」への協力
期間 令和元年6月26日(水)
14時~16時
内容 講師派遣 宇田 哲雄 学芸員
② 【新井宿駅と地域まちづくり協議会主催】
「2019年日光御成道鳩ヶ谷宿夏の陣」への協力
期間 令和元年6月30日(日)
11時~15時
内容 パネル貸出及び職員派遣 出野 雄也 学芸員
―5―
-
③ 【総務課主催】
「平和展 新しい時代へ伝える平和の大切さ」への協力
期間 令和元年7月20日(土)~7月24日(水)
内容 展示資料貸出
④ 【南鳩ケ谷公民館主催】
市民大学への協力
期間 令和元年11月9・16・23・30日
(いずれも土曜日)
13時30分~15時30分
内容 講師派遣 島村 邦男 学芸員
宇田 哲雄 学芸員
⑤ 【浦和郷土文化会主催】
定期講演会への協力
期間 令和元年10月4日(金)
13時30分~16時30分
内容 講師派遣 久保田 良男 学芸員
⑥ 【身近な歴史談話会主催】
芝川の舟運に関する講演会への協力
期間 令和元年10月17日(木)
10時~12時30分
内容 講師派遣 出野 雄也 学芸員
⑦ 【見沼田んぼ地域ガイドクラブ主催】
赤山街道に関する講演会への協力
期間 令和2年2月4日(火)
15時~16時
内容 講師派遣 出野 雄也 学芸員
⑧ 【新郷図書館主催】
歴史講座への協力
期間 令和2年3月15日(日)予定内容 講師派遣 島村 邦男 学芸員
―6―
-
(2)埋蔵文化財係の事業について
埋蔵文化財調査・記録事業(1月31日末現在)
ア 個人住宅建設、開発等に係る確認調査
問合せ 5,349 件、調査依頼 214 件、範囲確認調査 18 件
イ 遺跡発掘事業
発掘調査 2 件(内訳:公共 1 件、民間 1 件)小谷場貝塚遺跡 28 次、新郷貝塚遺跡 11 次
ウ 埋蔵文化財収蔵資料の整理
報告書作成 3 件(内訳:公共1件、民間1件、国庫1件)前田字前田第1遺跡4次、小谷場貝塚遺跡 24 次、平成 30 年度国庫市内遺跡発掘調査等
整理作業2件(内訳:公共2件)
小谷場貝塚遺跡 22 次、赤山曲輪遺跡3~7次
エ 川口市遺跡調査会への指導・助言
宮合貝塚遺跡 13・14 次、戸塚立山遺跡 6~47 次
―7―
-
資 料
-
歴史と文化を学ぶ体験教室№ 事 業 の 名 称 開 催 日 参加者数 備 考
1 夏休み自由研究サポート相談 7月26日(金)~8月23日(金) 47人 郷土の歴史・地理・文化財に関する調べ学習の支援。
2 夏休み子ども体験教室「勾玉をつくろう!」7月20日(土)・24日(水)・27日(土)・30日(火)
122人 川口の古代及び勾玉に関する学習及び勾玉作りを実施。
3夏休み子ども体験教室「この文字!探検隊!」&「旧田中家住宅探検隊」
8月1日(木)・2日(金) 12人 江戸時代の文字等に関する学習及び旧田中家住宅の見学を実施。
4夏休み子ども体験教室「縄文人になって縄文土器をつくろう!」
8月3日(土) 28人 川口の古代に関する学習及び粘土を使用した土器作りを実施。
5夏休み子ども体験教室「縄文ポシェットをつくろう!」
8月4日(日) 21人 川口の古代に関する学習及びクラフトバンドを使用したポシェット作りを実施。
―1―
-
旧田中家住宅実施事業№ 事 業 の 名 称 開 催 日 参加者数 備 考
1 旧田中家住宅の端午の節供 4月16日(火)~5月12日(日) 1,103人
文化財サポーター・魅がきたいの協力による五月人形の展示・解説。5月12日(日)には端午の茶会を開催(参加者85人)
2令和元年度 旧田中家住宅 文化イベント「演劇 かけくらべ」
7月6日(土)~7月7日(日) 174人劇団くすくすスパイスによる演劇を日本間で開催。7月6日に1回、7月7日に2回の全3回公演。(アプリュス共催)
3令和元年度 旧田中家住宅 文化イベント 美術展「A plus viewing 03 時の絲 」の開催
9月14日(土) 9月23日(月) 534人旧田中家住宅を会場に現代美術展を開催(アプリュス共催)
4第66回文化財保護強調週間協賛事業「旧田中家住宅で抹茶のひととき」
11月3日(日・文化の日) 130人旧田中家住宅において抹茶サービスを実施(川口茶道会共催)
5旧田中家住宅の桃の節供―雛人形の展示公開―
2月11日(火)~3月8日(日) 開催中文化財サポーター・魅がきたいの協力による雛人形の展示・解説。2月22日(土)には木目込み人形作り体験教室、3月1日(日)には箏演奏会を開催予定。
郷土資料館実施事業№ 事 業 の 名 称 開 催 日 参加者数 備 考
1企画展「川口味ものがたり ―水が育んだ味噌・ソース・酒―」
10月12日(土)~12月22日(日)
3,028人 企画展示室(本展示)、旧田中家住宅(サテライト展示)
2郷土資料館歴史講座①「ソース作り体験教室」
11月23日(土) 20人 ブルドックソース株式会社社員を講師としたソース作り
3文化財めぐりバスツアー「食べて埼玉!日本の醸造を探る旅!」
11月27日(水) 23人 企画展、神水ダム、ヤマキ醸造等の見学
4郷土資料館歴史講座②「味噌作り体験教室」
12月21日(土) 25人 NPO法人鳩ヶ谷協働研究所職員を講師とした麦味噌づくり体験教室
5企画展「今、思い出す。懐かしいあの頃のくらし。 ~昭和の遊び(おもちゃ)を中心に~」
1月21日(火)~3月27日(金) 開催中 企画展示室
―2―
-
歴史自然資料館実施事業№ 事 業 の 名 称 開 催 日 参加者数 備 考
1 自然を描いて ボックスアートをつくろう! 4月27日(土) 40人 イイナパーク周辺の思い出を描いた箱を制作するワークショップ
2 盆栽をつくろう! 5月26日(日) 8人 赤山盆栽の伝統技術について学ぶワークショップ
3 見えない形を掘り出そう! 6月2日(日) 19人 石膏を使った造形ワークショップ
4 ビー玉万華鏡を作ろう! 7月27日(土) 42人 手作り万華鏡のワークショップ
5 ライブペイントに挑戦しよう! 8月4日(日) 49人 大きなキャンバスを使って作品製作するワークショップ
6Wind of journey-光の遊ぶ庭-
9月10日(火)~9月23日(月) 2,070人 「自然」をテーマとしたアート作品群の美術展
7 石鹸でアート作品をつくろう! 9月21日(土) 30人 オリジナル石鹸を製作するワークショップ
8芸術の秋、親子に寄り添うファミリーコンサート
11月17日(日) 536人母子向けの演奏会のほか、楽器の演奏体験から、ソングライティング体験なども行う。
9 クリスマス飾りをつくろう! 12月7日(土) 25人 自然素材を活用したクリスマス飾りを製作するワークショップ。
10音和座「Vocative」呼び起される音~川口で鳴る世界の音楽家
1月19日(日) 90人 三味線とホルンによる演奏会。
11 縄文式土器をつくろう! 1月26日(日) 14人 縄文土器の製作するワークショップ。
12安行桜を知る- 植物の都・安行生まれの芸術品-
2月22日(土)予定 安行桜についての講演を行う。
13 (ワークショップ開催予定(内容未定)) 3月予定
―3―
-
令和元年5月1日現在
No. 種 別 指定等 名 称 所有(管理)者 所 在 地 等
1 重要文化財 建 造 物 国 旧田中家住宅 川口市 末広1-7-2
2 県 鶴ヶ丸八幡神社本殿付棟札一枚 宗教法人・八幡神社 大字芝6843
3 県 西福寺三重塔付元禄六年棟札一枚 宗教法人・西福寺 大字西立野420
4 市 前川神社内本殿 宗教法人・前川神社 前川町3-49-1
5 市 赤山山王権現社本殿付覆屋一棟・狛犬一対 宗教法人・日枝神社 大字赤山218
6 市 柳崎氷川神社本殿 宗教法人・氷川神社 柳崎5-20-1
7 市 宝厳院仁王門 宗教法人・宝厳院 大字安行慈林954
8 市 金剛寺山門 宗教法人・金剛寺 大字安行吉岡1361
9 市 羽盡神社本殿 宗教法人・羽盡神社 大字芝5379-1
10 市 八雲社社殿(旧金山権現社社殿) 宗教法人・川口神社 金山町6-15
11 県 龍派禅珠の頂相 宗教法人・長徳寺(県博寄託) さいたま市大宮区高鼻町4-219
12 県 中峰明本頂相 宗教法人・長徳寺(県博寄託) さいたま市大宮区高鼻町4-219
13 県 銅造クジャク文磬 宗教法人・宗信寺 上青木2-31-8
14 県 銅鐘 宗教法人・錫杖寺 本町2-4-37
15 県 太刀(銘長光) 個人蔵 飯塚
16 県 銅製秋草双雀鏡 宗教法人・羽盡神社 大字芝5379-1
17 市 安行吉岡氷川神社銅造懸仏 氷川神社(市寄託) 本町1-17-1
18 市 弘化二年銘鰐口 宗教法人・善光寺 舟戸町1-29
19 市 川口神社の神鏡 宗教法人・川口神社 金山町6-15
20 市 弘治二年銘鰐口 宗教法人・千手院(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
21 市 天保十年名銘天水鉢 川口市 本町1-17-1
22 市 明和三年銘半鐘 宗教法人・西光院 戸塚2-6-29
23 市 鉄製火鉢 明治三十五年一月喜道造ノ銘アリ 川口市 本町1-17-1
24 県 木造大日如来坐像(金剛界) 宗教法人・安楽寺 上青木2-18-30
25 県 木造阿弥陀如来坐像付胎内仏十字架 如意輪観音堂(県博寄託)さいたま市大宮区高鼻町4-219芝西1-19-17(複製)
26 県 金銅勢至菩薩立像 宗教法人・善光寺 舟戸町1-29
27 県木造僧形八幡坐像付紙本墨書造像願文等三十七点
宗教法人・峯ヶ岡八幡神社(付紙本墨書は県博寄託)
大字峯1304(さいたま市大宮区高鼻町4-219)
28 県 木造不動明王立像 宗教法人・地蔵院 桜町5-5-39
29 市 源長寺の阿弥陀如来坐像 宗教法人・源長寺 大字赤山1285
30 市 木造如意輪観音坐像及び像内納入物 宗教法人・西福寺 大字西立野420
31 市 木造釈迦如来坐像 宗教法人・興禅院 大字安行領家401
32 市 江戸袋氷川神社蔵仏像 宗教法人・氷川神社 江戸袋3-28-22
33 市 木造日蓮上人坐像 宗教法人・常住寺 辻700
34 県 寒松日記及び寒松稿 宗教法人・長徳寺(県博寄託) さいたま市大宮区高鼻町4-219
35 県 北潜日抄 個人蔵 東領家
36 県 小谷三志関係資料 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
37 市 安井息軒書翰及び同家奉公人請状 川口市 中青木2-20-31
38 市 増田家鋳造関係古文書 個人蔵(市寄託) 中青木2-20-31
39 市 高島秋帆褒状 個人蔵 本町
40 市 赤山陣屋敷絵図面 個人蔵 大字安行原
41 市 飯田家(地方)古文書 個人蔵 大字新堀
42 市 新光寺文書 宗教法人・新光寺(市寄託) 中青木2-20-31
43 市 早船家古文書 個人蔵(市寄託) 中青木2-20-31
44 市 羽盡神社朱印状 宗教法人・羽盡神社 大字芝5379-1
45 市 太閤秀吉の禁制 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
46 市 小谷三志関係資料 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
47 市 北条氏印判状 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
48 市 船津喜助家所蔵文書 個人蔵 里
49 市 小谷三志筆和歌 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
50 市富士講関係資料(小谷家文書・霜田家文書・折原家文書)
川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
51 市 黒田家富士講関係文書 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
52 市 戸塚精進場遺跡出土品 川口市 青木1-17-1
53 市 叺原遺跡出土蔵骨器(26点) 川口市 青木1-17-1
54 市 赤山縄文遺跡出土遺物付トチの実 川口市 青木1-17-1
55 市 浦寺遺跡出土石器付図面等関連資料一括 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
56 市里字屋敷添第4遺跡出土暦応二年銘板碑一基付出土板碑一括
川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
57 市前田字六反畑第1遺跡第1号井戸跡・井戸枠及び出土遺物一括
川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
58 市 三ツ和遺跡出土木簡付関連資料 川口市 青木1-17-1
59 市 伊奈家頌徳碑 宗教法人・源長寺 大字赤山1285
60 市 妙法蓮華経版木(全五十三枚) 宗教法人・新光寺 大字峯1319
61 市 元亨二年銘宝篋印塔 宗教法人・善光寺 舟戸町1-29
62 市 八幡宮石祠(伊奈忠順の碑文) 宗教法人・日枝神社 大字赤山218
63 市 大砲設計図 個人蔵 栄町
64 市 長徳寺三十六歌仙絵扁額 宗教法人・長徳寺 大字芝6303
65 市 福禄石炭ストーブコレクション及び関連資料株式会社 福禄川口工場川口市
幸町1-1-15本町1-17-1
66 市 文明三年銘庚申待供養板碑 宗教法人・実相寺 領家2-14-11
67 市 永正十五年銘二十一仏庚申待供養板碑 宗教法人・宝蔵寺 大字西新井宿355
68 市 道標(新四国八十八箇所札所五十九番標識) 宗教法人・地蔵院 桜町5-5-39
69 市 道標(庚申塔) 川口市 鳩ヶ谷緑町1-9
70 市 阿弥陀三尊図像月待供養板碑 個人蔵 里
71 市 元弘三年銘阿弥陀一尊板碑 宗教法人・実正寺 南鳩ヶ谷3-15-14
72 市建武五年銘阿弥陀一尊板碑及び貞和四年銘阿弥陀一尊板碑
宗教法人・源永寺 三ツ和2-19-8
73 市 享和四年銘算額 宗教法人・氷川神社 三ツ和3-22-2
74 市永仁四年銘釈迦一尊板碑及び嘉暦四年銘阿弥陀三尊板碑
個人蔵 鳩ケ谷緑町
75 市 蔵前橋の橋石 川口市 南鳩ヶ谷1-14
76 市 暦応三年銘阿弥陀一尊板碑 宗教法人・源永寺 三ツ和2-19-8
77 市 宿助成金御手形筐 個人蔵 里
78 市 日光御成道絵図 川口市 鳩ヶ谷本町2-1-22
79 市 五榜の高札(徒党強訴逃散禁制・切支丹禁制) 個人蔵(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
80 市 御宮地絵図面(鳩ヶ谷宿並絵図) 宗教法人・氷川神社(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
81 市 とんぼ橋の橋石 川口市 坂下町3-1-6
川口市指定文化財等一覧表
有形文化財 建 造 物
有形文化財 絵 画
有形文化財 工 芸 品
有形文化財 考 古 資 料
有形文化財 彫 刻
有形文化財 典籍 古文書
有形文化財 歴 史 資 料
―4―
-
令和元年5月1日現在
No. 種 別 指定等 名 称 所有(管理)者 所 在 地 等
82 市 五榜の高札(五倫の道遵守等) 個人蔵(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
83 市 弘安六年銘阿弥陀三尊板碑 個人蔵 桜町
84 市 道標(地蔵菩薩) 宗教法人・真乗院 大字石神1253
85 市 道標(庚申塔) 宗教法人・多宝院 大字新井宿157
86 市 「平剣」縞見本付関連資料 個人蔵 大字芝
87 市 「鍋平」商店鋳物問屋関係資料 川口市 青木1-17-1
88 重 要 有 形 民俗文化財 国 木曽呂の富士塚 川口市 大字東内野594他
89 市 だるま鞴(踏たたら) 川口市 青木1-17-1
90 市 長徳寺の獅子頭及び神楽面 宗教法人・長徳寺 大字芝6303
91 市 寛文五年銘阿弥陀庚申塔 宗教法人・実正寺 南鳩ヶ谷3-15-14
92 市 寛文四年銘地蔵庚申塔 台阿弥陀堂 南鳩ヶ谷2-8-3
93 市 須賀神社神輿 宗教法人・氷川神社 鳩ヶ谷本町1-6-2
94 市 曳き馬図絵馬 中居神明社(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
95 市 鎌倉権五郎矢抜き図絵馬 中居神明社(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
96 市 曳き馬図ガラス絵馬 宗教法人・八幡神社 八幡木1-25-2
97 市 八幡神社祭礼図絵馬 宗教法人・八幡神社 八幡木1-25-2
98 市 日光社参御小休所図絵馬 宗教法人・氷川神社 三ツ和3-22-2
99 市 川中島合戦図絵馬 宗教法人・氷川神社 三ツ和3-22-2
100 市 三条小鍛冶宗近図絵馬 上新田稲荷社 八幡木2-30-10
101 市 市神社 市神社保存会 鳩ヶ谷本町2-2-2
102 市 武者絵図絵馬 宗教法人・八幡神社 八幡木1-25-2
103 市 八幡木ばやしの神楽面・衣装・楽器 八幡木ばやし保存会(市寄託) 鳩ヶ谷本町2-1-22
104 市 景清の牢破り図絵馬 宗教法人・観福寺 前川4-30-13
105 市 浅間神社参拝図絵馬 宗教法人・東沼神社 差間2-15-45
106 市 伊勢太々神楽図絵馬 宗教法人・子日神社 大字新井宿155
107 市 日光東照宮参拝図絵馬 諏訪神社 東川口1-10-15
108 市 寛永二十年銘山王二十一仏庚申塔 宗教法人・西光院 戸塚2-6-29
109 市 寛文十一年銘地蔵庚申塔 宗教法人・法性寺 朝日2-28-9
110 市 安行藤八の獅子舞 安行藤八獅子舞保存会 大字安行藤八
111 市 江戸袋の獅子舞 江戸袋獅子舞保存会 江戸袋
112 市 安行原の蛇造り 安行原蛇造り保存会 大字安行原
113 市 領家の囃子と神楽 領家囃子と神楽保存会 領家
114 市 川口の木遣 川口鳶消防組木遣保存会 飯塚
115 市 八幡木ばやし 八幡木ばやし保存会 八幡木
116 国 見沼通船堀 川口市・さいたま市 大字東内野594他
117 県 新郷貝塚 川口市他 大字東貝塚25ほか
118 県 龍派禅珠の墓 宗教法人・長徳寺 大字芝6303
119 市 平柳蔵人居館跡 川口市 元郷4-12-6
120 市 代官熊沢家の墓 宗教法人・長徳寺 大字芝6303
121 市 金剛寺経塚付出土品 宗教法人・金剛寺 大字安行吉岡1361川口市 本町2丁目22-18他3筆宗教法人・川口神社 金山町6-15
123 市 良賢・英賢の墓 円明庵 八幡木2-8-10
124 市 垂井知等の墓 円明庵 八幡木2-8-10
125 市 小谷三志の墓 宗教法人・地蔵院 桜町5-5-39
126 市旧浦寺村の弁天池跡付元文元年・寛文九年銘の石碑2基
個人 桜町6-778-1
127 名 勝 市 旧鋳物問屋鍋平別邸庭園 川口市 金山町15-2
128 県 長徳寺のビャクシン 宗教法人・長徳寺 大字芝6303
129 市 真乗院のコウヤマキ 宗教法人・真乗院 大字石神1253
130 市 慈星院のカヤ 宗教法人・慈星院 大字芝5222
131 市 峯ヶ岡八幡神社の社叢 宗教法人・峯ヶ岡八幡神社 大字峯1304他
大字安行原2269-1 大字安行原2269-2・2270
133 市 地蔵院のタブノキ 宗教法人・地蔵院 桜町5-5-39
134 県 赤山城跡(赤山陣屋敷址) 川口市他 大字赤山766-2他
135 県 小谷場貝塚 個人 大字小谷場1002他
136 県 安行苗木開発の祖吉田権之丞の墓 宗教法人・金剛寺 大字安行吉岡1361
137 県 小谷三志居宅跡 個人 桜町1-1-12
138 国川口市母子福祉センター(旧鋳物問屋鍋平別邸)主屋
社会福祉法人川口市社会福祉事業団 金山町15-2
139 国川口市母子福祉センター(旧鋳物問屋鍋平別邸)離れ
社会福祉法人川口市社会福祉事業団 金山町15-2
140 国川口市母子福祉センター(旧鋳物問屋鍋平別邸)蔵
社会福祉法人川口市社会福祉事業団 金山町15-2
141 国 十一屋北西商店店舗 個人 鳩ヶ谷本町1-2-8
142 国 十一屋北西商店蔵 個人 鳩ヶ谷本町1-2-8
143 国 大泉家住宅洋館 個人 領家5-4-1
144 国 大泉家住宅和館 個人 領家5-4-1
145 国 永瀬昌文家住宅主屋 個人 本町1-8-6
146 国 永瀬孝男家住宅洋館 個人 本町1-5-12
147 国 永瀬孝男家住宅和館 個人 本町1-5-12
148 国 永瀬孝男家住宅土蔵 個人 本町1-5-12
149 国 永瀬孝男家住宅納屋 個人 本町1-5-12
150 国 永瀬孝男家住宅旧発電所 個人 本町1-5-12
151 国 永瀬孝男家住宅煉瓦蔵 個人 本町1-5-12
152 国 永瀬孝男家住宅表門及び煉瓦塀 個人 本町1-5-12
153 国 旧森龍織物主屋 個人 大字安行領根岸字台2219
154 国 旧森龍織物工場 個人 大字安行領根岸字台2219
155 県 宮合遺跡 西立野字宮合
156 県 猿貝貝塚安行字宮越990安行字大元790他
157 県 前野宿貝塚 東本郷字大塚1586他
158 県 江戸袋貝塚 江戸袋1-20-32
埼玉県川口市
市 凱旋橋跡付凱旋橋之碑
安行原イチリンソウ自生地132
122
選 定 重 要 遺 跡
天 然 記 念 物
旧 跡
無 形 民 俗 文 化 財
登録有形文化財(建造物)
市
史 跡
有 形 民 俗 文 化 財
有形文化財 歴 史 資 料
―5―
-
別表2 種別別一覧表別表1 指定主体別一覧表 重要文化財(建造物) 1国指定文化財 3 有形文化財(建造物) 9県指定文化財 23 有形文化財(絵画) 2市指定文化財 111 有形文化財(工芸品) 11国登録有形文化財 17 有形文化財(彫刻) 10選定重要遺跡 4 有形文化財(典籍 古文書) 18合計 158 有形文化財(考古資料) 7
有形文化財(歴史資料) 29重要有形民俗文化財 1有形民俗文化財 21無形民俗文化財 6史跡 11名勝 1天然記念物 6旧跡 4登録有形文化財(建造物) 17選定重要遺跡 4合計 158
―6―
-
木造薬師如来立像付旧厨子調査報告書
別 添 資 料 1
川口市文化財保護審議会
会長 有元 修一 様
写
川口市文化財保護審議会
委員 林 宏一
―1―
-
- 1 -
川口市宝厳院慈林薬師堂仏像調査報告書
平成二十八年十二月十六日・令和元年十二月十六日実査
一、木造薬師如来立像
一躯
[形状]螺髪切付、髪際一文字、白毫、耳朶環ならず。三道。裙を着け、右肩を覆肩衣で被い、衲衣
を左肩から右肩に廻して浅く掛け、右腋下を通して右脇腹で覆肩衣を挟んで再び左肩に深く掛ける。
両腕を屈臂し、左手に薬壺を持ち、右手に蓮華を執り、両足先を揃えて台座上に立つ。
光背はなし。台座は、蓮華に反花の二重蓮華座。
[品質・構造]寄木造(ヒノキ材)、彫眼、素地。
頭体幹部は耳後で前後二材矧ぎとし、内刳。後頭部は襟際で割首。左側面部は本体と共木。右側面
部は前面部のみ別材矧ぎ付け。両手先、両足先各々別材。持物薬壺は左手先材と共木。
台座は木製、蓮華と反花各々別材。
[保存状況]全身を火中した痕跡が認められる。平成十六年、京都の仏師により修理を受ける。本体
面部主要部及び三道彫り直し。右側面前面材、左大袖半ばより下及び両手先、両足先新補。台座蓮華
表面焼損。反花座新補。
[制作時期]室町時代後期
[法量]単位㎝
像
高
三四・一
髪際高
三一・九
頭頂〜顎
六・八
髪際〜顎
四・五
耳
張
五・〇
面
張
四・一
面
奥
五・〇
肩
張
八・〇
臂
張
一一・五
胸
奥
五・二
腹
奥
五・六
裾
奥
四・四
裾
張
九・五
袖
張
一二・〇
足先開
(
内)
二・二
(
外)
五・〇
台座高
七・八
台座幅
一七・〇
台座奥
一五・一
蓮肉径
一三・五
[備考]
(一)川口市安行慈林九五四番地所在の新義真言宗宝厳院慈林薬師堂本尊
縁起によれば、慈林薬師堂は天平十三年(七四一)聖武天皇の勅により行基によって草創されたと
云い、本尊薬師如来も行基の作と伝える。その後文徳天皇の御代に再興があり、清和帝の御代に寺領
を賜ったとされるが、詳しい寺歴は明らかでない。別に越谷野島浄山寺及び岩槻慈恩寺の縁起には、
東国巡錫中の慈覚大師円仁が貞観二年(八六〇)に慈恩寺を開創した際、霊木を得て手ずから材の根
の部分で観世音を彫り慈恩寺の本尊に据え、中程からは野島慈福寺(浄山寺)の地蔵尊、梢からは足
立郡慈林村(川口市)慈林寺の薬師如来と一木三躰の像を刻んで各々の地に安置し、慈覚大師の「慈」
を冠して寺とした、と云う異なる話を伝えている。
(二)中古火災に遭ったらしく焼損した痕跡が認められる。平成十六年の修理により整った形姿を見
せるが、表面の浚い直しや欠損箇所の新補部分が多く、当初の姿はかなり改変されているとみなされ
る。
(三)別に保管される旧厨子嵌板の文明十五年(
一四八三)
墨書銘に、「寺は応仁元年(
一四六七)
正月十
七日の火災により宮(?)許りを残して本尊以下灰燼に帰してしまった。文明三年(一四七一)七月
十穀阿吽上人が来山し柱立仮葺を遂げたが、その後天下大乱(享徳の乱、長尾景春の乱等を指すか)
ため修造事業は中絶した。同十五年(一四八三)五月南沼より慈覚大師御作の本尊が涌現し、また阿
―2―
-
- 2 -
吽上人も夢告を受けて沼から半分焼損した本尊の涌現を得、さらに柱立の際に別当権大僧都尊祐から
新仏の寄進があり再興が果たされた」との記述がある。
これによれば、応仁元年(
一四六七)
の回禄により宮許り残して灰燼に帰した慈林薬師は、四年後の文
明三年(一四七一)十穀阿吽上人の来山により堂宇の柱立仮葺復興に取りかかり、同十五年に伝慈覚
大師御作の本尊等の涌現を得て再興なったものと理解される。墨書銘は厨子嵌板のものであり、②の
銘文中に「宮殿造立時別当永賢僧都」の文字が見えることから、文明十五年(一四八三)は厨子のみ
の造立かとも受け取れるが、①を含めての記述内容からすると堂宇共々の再興と読み取るのが妥当で
あろう。これに従うなら、現本尊は、文明三年柱立の際に別当権大僧都尊祐から寄進された新仏に該
当するものとみなされる。
(四)様式技法的には鎌倉地方彫刻の特色を受け継ぐもので、卵形で秀麗な目鼻立ちの面貌や陰影の
強い衣文を刻む厚手の着衣の表現等にそれがよく表われている。戦国期から江戸初期頃の鎌倉仏師の
作風に共通するところがあり、作者はその系譜に連なる仏師が想定される。前出の文明十五年(
一四八
三)
旧厨子嵌板墨書銘に従うなら、文明三年(一四七一)堂再興(柱立)の時別当権大僧都尊祐法印が
寄進した新仏に該当する可能性が高い。
本像によく似た作風を見せる薬師如来像が、さいたま市桜区田島の薬王院に伝来している。同院薬
師堂の本尊像で、造像銘から文明三年(一四七一)十二月、鎌倉仏師民部の作であることが明らかに
される。薬王院像は坐像、本像は立像の違いがあり、法衣の服制や衣文表現にも多少の異同があるが、
頭部螺髪の目粗く大粒で葡萄珠のような表現や秀麗な目鼻立ちを刻んだ卵形で豊
長頤の面貌は本像
に共通した特色を備えている。特に側面からの頭部の輪郭線は瓜二つと云ってよいほどよく似ている。
同時期に近接した地域での造仏であることからすると、本像の作者は、鎌倉仏師民部もしくはその工
房の仏師であった可能性が高いと考えられる。
《本尊薬師如来立像》
―3―
-
- 3 -
二、《参考》
文明十五年旧厨子側板墨書銘
①当寺炎生応仁元年丁亥正月十七日
夜為本尊十二神始不残一塵皆焼失
畢宮計残後文明三辛卯七月一日十穀
阿吽上人来成造立次月潤七月十六日辰日
一天柱立所番匠来集事百余人仮葺
霜月廿四日畢其後赴天下大乱修造中絶也文明
十五年癸卯五月十一日巳剋自南沼本尊一躰涌現有是古
慈覚大師御作也又阿吽上時夢相之告自沼一躰涌現
是半分炎生也又新仏一躰柱立時別当権大僧都
尊祐法印天台真言両宗神仏旦那一躰三貫宛カ也
太陽寺中務少丞
カ
カ
②地頭長尾中務尉景広同代官岡部弾正益カ清
藤原直清
宮殿造立時別当永賢僧都同願主十穀永慶
妙祐禅尼
当奉行一乗房誓妙普賢坊賢永妙音坊常楽坊
常珍禅尼
祐実
印カ仲
犬子
大工武州新座左衛門次郎盛重子息右衛門三郎
孫太郎
小工三郎四郎五郎四郎
ミの□
木取始知覚叡宥永珍祐蔵永弁永祐盛円永資
ます子
祐舜祐海尊慶幸祐
承仕承西方円承東蓮カ
薬師子
と祢子
おくみ
カ
カ
カ
文明十五年
癸卯
八月十日
筆者如意輪坊誓慶律師
覚カ乗《
文明十五年銘旧厨子側板》
―4―
-
- 4 -
三、木造両脇侍像(木造日光・月光菩薩立像)
二躯
[形状]菩薩形。ともに宝髻を結い、天冠台(紐一条に列弁文)を付ける。頭髪毛筋彫り。鬢髪一条
耳にかかる。耳朶環ならず。白毫相、三道相を表す。鼻孔を彫る。条帛・天衣に裙を着け、腰布をあ
てる。
日光菩薩は、左腕屈臂し、右腕かるく伸べ、日輪を戴く蓮華を執り、わずかに右に腰をひねって左
足を前に出し、蓮台座上に立つ。
月光菩薩は、これとは逆に右腕屈臂し、左腕かるく伸べ、月輪を戴く蓮華を執り、わずかに左に腰
をひねって右足を前に出し、蓮台座上に立つ。
光背は輪光背。台座は、蓮華・敷茄子・受座・蘂・反花・岩座・框座の六重蓮華座。
[品質・構造]寄木造、玉眼、弁柄漆塗り。
表面の漆塗りが厚いため構造の詳細は不明。頭体幹部は耳後で前後二材矧ぎとし、内刳。三道下で
割首とするか。左右の腕は肩、肘、手首で別材矧ぎか。宝髻、足先は別材とみなされる。その他、左
右の臂後でループし、両側に垂れる天衣等は別材。
光背・台座及び持物は木製。本体と同じ弁柄漆塗り。
[保存状況]表面の弁柄漆塗り後補(戦後のものとみなされる)。臂後でループする天衣は江戸時代
の後補か。光背もその頃の後補か。持物・台座は当初のものとみられる。宝冠、胸飾り等の飾り金具
は江戸時代の後補。
[制作時期]室町時代後期
[法量]単位㎝
(日光菩薩立像)
像
高
一〇〇・〇
髪際高
八六・五
頭頂〜顎
二四・二
髪際〜顎
一一・七
耳
張
一二・七
面
張
一〇・二
面
奥
一三・七
肩
張
二一・五
臂
張
二九・二
胸
奥
一四・六
腹
奥
一五・四
裾
奥
一二・九
裾
張
二〇・七
足先開(
内)
六・〇
(
外)
一三・〇
足
(左)高四・〇×厚一・六×幅五・七
(右)高四・〇×厚一・四×幅六・〇
台座高
三七・五
台座幅
五五・三
台座奥
四〇・六
蓮肉径
二五・五
光背高
一〇〇・五
光背幅
三四・〇
(月光菩薩立像)
像
高
九八・四
髪際高
八四・六
頭頂〜顎
二三・七
髪際〜顎
一一・五
耳
張
一一・八
面
張
九・九
面
奥
一三・七
肩
張
一九・二
臂
張
三〇・〇
胸
奥
一五・一
腹
奥
一六・三
裾
奥
一四・三
裾
張
二一・二
足先開(
内)
六・六
(
外)
一三・六
足
(左)高四・二×厚一・六五×幅五・三
(右)高四・三×厚一・六×幅七・三
台座高
三七・九
台座幅
五五・五
台座奥
四〇・三
蓮肉径
二五・二
光背高
一〇〇・三五
光背幅
三四・〇
[備考]
(一)慈林薬師堂本尊両脇侍。秘仏本尊厨子の左右に安置される。本尊厨子内の小脇寺像とは別物。
(二)後世の厚塗りによる修理彩色のため、尊容や像の構造等の詳細を明らかにしない
―5―
-
- 5 -
形式化がめだち、彫技も硬いが、様式形制から見ると、後期宋風美術の影響を受けた鎌倉時代後期
頃の様式を受け継ぐもので、慶派系の鎌倉地方彫刻に近い作風が認められる。制作年代の判定は難し
いが、併せて安置される十二神将像ともども室町時代後期にさかのぼる可能性が考えられる。文明三
年(一四七一)頃の造立と推定される秘仏本尊像に遅れたころの製作か。作者は、鎌倉仏師とみなさ
れる。
《日光菩薩立像》
《月光菩薩立像》
―6―
-
- 6 -
四、木造十二神将立像
一二躯
[形状]ともに神将形。頭部は怒髪もしく着冑し、忿怒相。寛衣に袴・裙を着け革甲・手甲・脛当で
身を固め、沓を履き、様々な姿態で武器を執り、岩座上に立つ。前頭部に各々十二支の標識を表し、
金銅製透し彫りの宝冠を付ける。
子神
焔髪、両眼を見開き、開口、上歯を覗かせる。身体を右斜め前方に大きく傾け、両腕で三叉戟
を突き、両脚を踏ん張って立つ。
丑神
焔髪、両眼を見開き、閉口。やや左に身を傾け、腰前で左手に弓、右手に矢を執り、両脚を踏
ん張って立つ。
寅神
焔髪、瞋目、閉口。左手を額上にかざしてやや左斜め上方を睨み、右手に斧を持ち、身を前に
乗り出し、左脚を踏み出して岩座上に立つ。
卯神
焔髪、両眼を見開き、閉口。左手を腰に添え、右手で斧を振り上げ、右脚を小岩に踏み上げて
立つ。
辰神
着冑、両眼を見開いて眦を下げ、開口。左手臂をあげて弓を執り、右手腰脇で持物(箭か)を
執る構えをみせて、左脚を小岩に踏み上げて立つ。
巳神
着冑、両眼を見開き、閉口。左手腰前に構えて、右手臂を上げ独鈷杵を握り、左脚を木の切株
に踏み上げて立つ。
午神
焔髪、両眼を見開き、閉口。左手に法螺貝を捧げ、右手臂を上げ三鈷杵を握り、左脚を踏み出
して左斜めを睨んで立つ。
未神
着冑、瞋目、閉口。頭を左斜め前方に傾け、両腕で支えた箭柄の筋をたしかめ、両脚を踏ん張
って立つ。
申神
焔髪、両眼を見開き、開口。両手で宝棒を執り左斜め前方に構えて、両脚を踏ん張って立つ。
酉神
着冑、瞋目、閉口、上歯で唇を噛みしめる。左手を腰に置き、右手臂を上げて三叉戟を突き、
やや左に腰を捻って立つ。
戌神
焔髪、瞋目、閉口。両腕を胸前で構えて、左手宝剣を執り、右手刀印を結び、やや右に腰を捻
って立つ。
亥神
焔髪、瞋目、開口、上歯を覗かせる。大きく腰を左に捻り、左手を腰に置き、右手刀を振り上
げて、右脚を小岩に踏み上げる。
光背は、三方火炎付き輪宝光背。柄は短柄、背面中央に光背
受を設ける。台座は、岩座に框座。
[品質・構造]寄木造、玉眼、弁柄漆塗り。
表面の漆塗りが厚いため構造の詳細は不明。光背・台座及び持物は木製。本体と同じ弁柄漆塗り。
[保存状況]表面の弁柄漆塗り後補(戦後のものとみなされる)。光背・台座・金銅製透し彫りの宝
冠は江戸時代の後補とみなされる。持物は当初のものもまじるか(寅・巳・午神等)。
[制作時期]室町時代後期
[法量]単位㎝
像
高
髪際高
臂
張
腹
奥
光背高
台座高
子神
五八・七
五三・〇
二二・四
一一・九
三一・三
一二・二
丑神
六〇・四
五三・三
一三・八
一〇・二
三二・二
一〇・七
寅神
五九・四
五五・三
三八・八
一二・二
三一・〇
一二・三
―7―
-
- 7 -
卯神
六〇・一
五三・六
三九・〇
一二・一
三一・八
一六・六
像
高
髪際高
臂
張
腹
奥
光背高
台座高
辰神
五九・三
四三・四
二九・三
一〇・三
三一・〇
一七・0
巳神
五八・〇
五三・六
三七・二
一〇・三
三一・五
二〇・二
午神
六一・三
五六・三
三五・八
一〇・六
三一・三
一一・〇
未神
六一・五
五四・八
二一・八
一一・六
二九・五
一三・三
申神
六三・四
五八・〇
二三・七
一〇・八
三一・〇
一一・八
酉神
六七・六
五八・五
三五・八
一二・一
三〇・一
一二・〇
戌神
六四・〇
五七・四
二二・一
一一・六
三〇・一
一二・〇
亥神
六一・八
五四・二
三三・六
一一・一
三一・一
一九・六
[備考]
(一)慈林薬師堂本尊眷属十二神将像。秘仏本尊厨子の両脇に、向かって左から、子神を先頭に六体
ずつ安置される。
(二)後世の厚塗りによる修理彩色のため、尊容や像の構造等の詳細を明らかにしない。
十二躯一具の群像ながら、作風は大きく二つに分けられる。顔の肉付けや忿怒の表情の豊かさ、身
に着ける衣服や革甲の細部の彫りの丁寧さ、動きのある立体構成等において、子・寅・未・酉・戌・
亥神像は優れている。他の像は顔の表情や衣装の表現が陰影に乏しく、身のこなしも形式的となり、
どこか単調な表現となっており、造像に携わった仏師が違うことが知られる。
様式・形制から見ると、前の六躯の像等には応永年間鎌倉仏師朝
が造立した鎌倉・覚園寺の十二
神将像に似通うところがあり、同系の図像に倣ったものであることが窺える。日光・月光菩薩像と同
様、慶派系の鎌倉地方彫刻様式を受け継ぐ作例とみなしてよいであろう。制作年代の判定は難しいが、
日光・月光菩薩像と同じく室町時代後期にさかのぼるものと考えられる。文明三年(一四七一)頃の
造立と推定される秘仏本尊像に遅れるころの製作か。作者は、鎌倉仏師と想定される。
―8―
-
- 8 -
―9―
-
- 9 -
五、銅造薬師如来立像
一躯
[形状]螺髪鋳出、髪際一文字、白毫相、耳朶環ならず、三道を表わす。裙に覆肩衣、衲衣を着ける。
覆肩衣で右肩を被い、衲衣は左肩から右肩に浅く掛かり右腋下を抜けて覆肩衣を挟んで再び左肩に掛
かる。腹前で掌上にして左手下に両手先を重ね薬壺を持ち、両足先を揃えて立つ。
[品質・構造]鋳銅製。中型を設け、像底も含めて像全身を耳後で外型を前後に合わせて一鋳する。
外型の合せ目は、後頭部下方から斜め前に耳後に至り、側面に流れる。中型の土は除去されている。
[保存状況]正面を中心に土中、火中の痕跡が認められる。光背・台座はない。
[制作時期]室町時代
[法量]単位㎝
像
高
三五・六
髪際高
三一・六
頭頂〜顎
一〇・〇
髪際〜顎
五・六
耳
張
八・一
面
張
五・九
面
奥
九・四
肩
張
一〇・六
臂
張
一一・八
胸
奥
七・四
腹
奥
八・一
裾
奥
七・六
裾
張
一〇・三
袖
張
一一・五
足先開
(
内)
―・―
(
外)
六・三
[備考]
(一)藥師堂須弥壇上本尊厨子前に安置される。
(二)様式、作風から室町時代の制作と見なされる。大粒の螺髪、面高・丸顔で素朴な面貌、頭部過
大で猪首・短身の造型は鄙びており、地方作であることを示している。原型は土型、仏像の作者も鋳
物師も在地の職人と考えられる。
(三)伝来の詳細を明らかにしない。あるいは旧厨子銘に云う文明十五年(一四八三)
南沼より涌現した
尊像の一体に該当するか。
(四)本像と共に須弥壇上に保管される焼損磨滅した一木彫成像の残欠がある。バレーボール大のケ
ヤキ材の塊で、像のどの部分に当たるか不明だが、時代は古いものと判断される。縁起に説かれる草
創時の本尊像の残欠である可能性もある。
《銅造薬師如来立像》
―10―
-
- 10 -
※
木造脇侍像
二躯
[形状]共に如来形立像。焼損のため細部不詳ながら、螺髪切付、法衣は通肩(裙に覆肩衣、衲衣を
偏袒右肩にまとうか)、正面を向き、直立して二重蓮台上に立つ。台座は蓮華に反花座。
[品質・構造]共に一木造(材質不明)、彫眼、着衣部は黒漆地に漆箔。弁柄漆塗り。
頭体部及び台座蓮華部を含めて一材から彫出。反花座は別材。光背、台座は木製。
[保存状況]共に火中のため全身を炭化磨滅する。背面中央部と足元の一部に黒漆地、金箔が残る。
右脇侍像背面に銅釘留の銅板製光背支柱断片が残る。面部目鼻唇部を彫り直し、反花座を新補する。
平成十六年修理時の所為とみなされる。
[制作時期]室町時代
[法量]単位㎝
左脇侍
総
高一八・五
像
高一六・一
髪際高一五・〇
臂
張四・六
腹
奥二・六
台座高
三・七
台座幅七・二
台座奥
六・一
右脇侍
総
高一八・六
像
高一七・五
髪際高一六・四
臂
張四・七
腹
奥二・四
台座高
三・七
台座幅
七・二
台座奥
六・一
[備考]
(一)薬師堂本尊像の脇侍像として厨子内に安置される。
(二)いずれも像容、形制から千体仏の一つであったとみなされる。本来本尊薬師像の脇侍像ではな
く、後世脇侍として付け加えられたものと判断される。様式及び良質の黒漆地、金箔の材質から室町
時代に遡ると考えられる。
《右脇侍像》
《左脇侍像》
―11―
-
- 11 -
六、所見
木造薬師如来立像は、様式技法的には鎌倉地方彫刻の特色を受け継ぐもので、卵形で秀麗な目鼻立
ちの面貌や陰影の強い衣文を刻む厚手の着衣の表現等にそれがよく表われている。戦国期から江戸初
期頃の鎌倉仏師の作風に共通するところがあり、作者はその系譜に連なる仏師が想定される。前出の
文明十五年(
一四八三)
旧厨子側板墨書銘に従うなら、文明三年(一四七一)堂再興(柱立)の時別当権
大僧都尊祐法印が寄進した新仏に該当する可能性が高い。
また、本像によく似た作風を見せるさいたま市桜区田島の薬王院薬師堂の木造薬師如来坐像が、造
像銘から文明三年(一四七一)十二月の鎌倉仏師民部の作であることから、本像の作者は、鎌倉仏師
民部もしくはその工房の仏師であった可能性が高いと考えられる。
日光・月光の両菩薩像及び十二神将像は、後世の補修で漆の厚塗りが施されたため尊容が損なわれ
ているが、ともに中世後半代の鎌倉地方彫刻様式をみせる正統な仕上がりの像で、室町時代末頃の造
像とみなされる。作風から鎌倉仏師の手になるものと考えられ、十二神将像の造像には複数の仏師が
関わったことが認められる。
よって木造薬師如来立像は、鎌倉地方彫刻の特色と、戦国期頃の鎌倉仏師の作風を損なわず現在に
伝えていることから、今後市指定文化財として保護していくことが望ましい。日光・月光の両菩薩像
及び十二神将像も、文明三年(一四七一)頃の造立と推定される秘仏本尊像の脇侍と眷属神として一
具で造立されたものと考えられ、本尊とともに指定することが望ましい。また、寺院と像寄進の経緯
伝承の墨書銘が記されている文明十五年(
一四八三)
銘旧厨子側板についても、併せて付けたり指定す
ることが望ましい。
なお、銅像薬師如来立像についても、室町時代の在地の職人と鋳物師による製作と見なさすことが
でき、その様式・作風と薬師信仰の隆盛を伝えていることから、指定文化財として保護していくこと
が望ましい。
―12―
-
里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子調査報告書
別 添 資 料 2
川口市文化財保護審議会
会長 有元 修一 様
川口市文化財保護審議会
委員 青木 義脩
写
―13―
-
里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子指定候補文化財調査報告書
川口市文化財保護審議会
里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子 1頭
種別 有形文化財(考古資料)
所有者 川口市
管理者 川口市教育委員会
所在地 川口市本町1-17-1 川口市立文化財センター〔説明〕指定候補となる烏帽子は、里字屋敷添遺跡群に属する里字屋敷添第2遺跡(983
他地点)の発掘調査で出土した遺物である。里字屋敷添遺跡群は、旧入間川流路跡に
形成された自然堤防上に所在し、縄文時代中期から後期、古代、中世、近世に属する
遺構・遺物が出土する(第1・2図)。中心となるのは中世の遺構で、井戸跡・溝跡・
土坑のほか掘立柱建物跡や火葬跡などが確認される。大型の溝跡が多く、中には方形
に巡る 35m四方の区画溝があり、居館もしくは寺院の堀跡であったと考えられている。
烏帽子は長径 188cm、短径 185cm、深さ 142cm を測る井戸跡から出土した。(第3・4
図、写真図版1)。潰れた状態で検出されたため破損の危険があり、土ごと取り上げを
行った。そのため厚さの計測値は不明である。厚さ以外の計測値は高さ 14.0 ㎝、幅
23.9 ㎝である。全面が黒色を呈した漆塗製品であり、折り重なった状態であることか
ら折烏帽子であったと推定される(第5図)。
〔科学分析〕保存処理に伴いマイクロスコープと薄片作成による観察を行った(写真図版
2)。その結果、絹布に下地となる薄い漆を塗り、更に黒色物質を含む漆を重ね塗りし
ていることがわかった。黒色物質は炭粉とは明らかに異なるため、油煙や松煙などを
利用したと考えられる。
〔年代〕烏帽子の年代については土器などの年代を示す共伴遺物がないため詳細は不明で
ある。里字屋敷添遺跡群では、14 世紀頃には館跡もしくは寺院の区画溝と推定される
35m四方の堀跡が廻り、14 世紀中頃から 15 世紀代の紀年銘をもつ板碑が複数出土す
るなど、武士の活動を想起させる遺構・遺物が増加する。折烏帽子は別称を侍烏帽子
と呼ばれ、鎌倉時代以後はとくに武士が用いたものであり、室町時代には紙製黒漆塗
りのものに形式化される。折烏帽子の出土は里字屋敷添遺跡群での武士の活動と関連
するものであり、遺構・遺物が増加する 14 世紀から 15 世紀の所産であると推定され
る。
〔文化財的価値〕烏帽子は中世において成人男性が日常的に被っていたとされるが、伝世
品の数は少なく、材質や製作技法について不明な点が多い。発掘調査による烏帽子の
出土については 34 例の報告がある。しかし多くは部分的な破片であったり、著しく破
―14―
-
損し、出土状況や漆塗膜に残る布目痕から烏帽子と推定されているものが多い。完形
に近いものの出土は5例と少なく、ほぼ完形である里字屋敷添第2遺跡出土烏帽子は
全国的に見ても貴重な例であるといえる。なお、埼玉県内での出土例はない。当該烏
帽子は、地下水位の高い沖積地ゆえに、長期にわたり水分を含む状態であったため、
原形を留め保存された。烏帽子の風習は中世末期から衰退し、16 世紀には無帽が主流
となり近世へとつながっていく。中世における武士の装束を知るうえでも貴重な資料
である。また、里字屋敷添遺跡群の発掘調査成果と併せ、中世における川口の低地で
の武士団の活動を知るうえでも貴重な資料であり、市指定文化財に指定する価値のあ
るものと考える。
―15―
-
第1図 川口市鳩ヶ谷地区の地形分類と遺跡の分布
―16―
-
第2図 里字屋敷添遺跡群における発掘調査区
第3図 里字屋敷添第 2遺跡983番地他地点(第5次調査)全体測量図
―17―
-
写真図版2 烏帽子保存処理工程
烏帽子
第4図 SE11 平断面図
写真図版1 SE11完掘状況
第5図 烏帽子実測図
―18―
-
[補足資料]
―19―
-
表 烏帽子の出土事例
1 岩手県平泉町 柳之御所跡遺跡 3/4残存。12世紀代の立烏帽子。
2 栃木県下野市 下古館遺跡 遺存状態は良好。折烏帽子。 補足資料5
3 千葉県市原市 西野遺跡 布目の痕跡がある漆塗膜片。
4 千葉県市原市 白山遺跡 布目の痕跡がある漆塗膜片。
5 東京都府中市 武蔵国府関連遺跡 詳細な報告はなし。漆膜片。
6 神奈川県平塚市 坪ノ内遺跡 ほぼ完形。生地はイネ科の植物繊維。 補足資料4
7 神奈川県鎌倉市 今小路西遺跡 原形のわかる漆塗膜片。
8 愛知県松河戸町 松河戸遺跡 漆塗膜片のみ出土。
9 長野県千曲市 東條遺跡 漆塗膜片のみ出土。
10 新潟県村上市 西部遺跡 圭冠または烏帽子の漆膜破片。
11 新潟県新津市 沖ノ羽遺跡 麻と絹の布目の痕跡のある漆膜片。
12 新潟県新潟市 小坂居付遺跡 布圧痕が残る黒色漆膜片が出土。
13 新潟県村上市 大木戸遺跡 漆塗膜細片が出土。
14 富山県婦負郡婦中町 道場遺跡 原形のわかる漆塗膜片が出土。
15 富山県小矢部市 五社遺跡 圭冠または烏帽子の漆膜破片。
16 福井県福井市 石盛遺跡 原形のわかる漆塗膜。折烏帽子か。
17 石川県金沢市 大友 E遺跡 漆塗膜片のみ出土。
18 石川県白山市 北出遺跡 布目の痕跡がある漆塗膜片。
19 石川県白山市 宮保館跡 2枚重なった折烏帽子が―部残存。
20 京都府岩滝町 定山遺跡 漆塗膜片のみ出土。紙製か。
21 大阪府茨木市 栗栖山南墳墓群 遺存状態は良好。折烏帽子。 補足資料6
22 大阪府茨木市 総持寺遺跡 原形はわかるが破損が激しい。
23 大阪府泉佐野市 湊遺跡 漆塗膜片のみ出土。
24 大阪府守口市 梶遺跡 布目の痕跡がある漆塗膜片。
25 大阪府高槻市 田能北遺跡 漆塗膜片のみ出土。
26 兵庫県神戸市 出合遺跡 漆塗膜片のみ出土。
27 兵庫県神戸市 二葉町遺跡 繊維質が残存した薄い漆製品が出土。
28 岡山県岡山市 鹿田遺跡 潰れた漆膜片。生地は紙と布。
29 広島県福山市 草戸千軒町遺跡 多数の塗膜片が確認される。
30 山口県山口市 古大里遺跡 漆塗膜片のみ出土。
31 山口県山口市 東禅寺・黒山遺跡 漆塗膜片のみ出土。
32 山口県山口市 鋳銭司大歳 布目の痕跡がある漆塗膜細片。
33 山口県防府市 上り熊遺跡 漆塗膜片のみ出土。
34 福岡県福岡市 博多遺跡群 漆塗膜片のみ出土。
―20―
-
旧田中家住宅保存活用計画の策定について
1 目的 旧田中家住宅は、味噌醸造業と材木商で財を成した四代目田中德兵衞が大正 10年に上棟した煉 造り 3 階建ての洋館と昭和 9 年に増設した和館を中心とした和洋折衷の近代和風建築である。平成 17 年に川口市が取得し、平成 18 年に国登録有形文化財となった。その後、平成 30年 12 月に国重要文化財に指定されている。 平成 28 年度には市独自で耐震診断と構造調査を行ったが、国指定重要文化財となったことを踏まえ、耐震改修も含めた今後の保存活用方針を定めるため、旧田中家住宅保存活用計画を定めたもの。
2 組織 川口市文化財保護審議会委員及び川口市文化財保護審議会に設けることができる「専門調査員」により、策定を行った。 ・川口市文化財保護審議会委員 氏 名 専門 備 考 (職業等) 1 後 藤 治 建築 学理事 2 津 髙 行 建築 大学教授
・専門調査員 氏 名 専門 備 考 (職業等) 1 宇於﨑 勝 也 景観 大学理工学部教授/川口市景観形成委員 2 楠 浩 一 耐震 大学地震研究所教授 3 藤 田 香 織 耐震 大学院工学系研究科教授 4 太 田 勤 耐震 建築 学研究所所 5 小 林 稔 観光 川口市観光物産協会 専務理事
3 会議開催実績 令和元年 8月 5日(月) 第1回旧田中家住宅保存活用計画策定会議
10月 4日(月) 活用ワーキンググループ 10月21日(月) 第 2 回旧田中家住宅保存活用計画策定会議 11月 7日(木) 耐震ワーキンググループ 11月21日(木) 第 3 回旧田中家住宅保存活用計画策定会議 令和2年 2月17日(月) 第 4 回旧田中家住宅保存活用計画策定会議(最終)
4 会議結果報告 (令和2年2月17日開催 第 4回会議資料による)
別 添 資 料 3
―21―