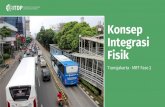道路交通から大量高速輸送機関(MRT)へのモーダ...
Transcript of 道路交通から大量高速輸送機関(MRT)へのモーダ...
Ⅱ-1
H24 二国間オフセット・クレジット制度の実現可能性調査 最終報告書(概要版)
「道路交通から大量高速輸送機関(MRT)へのモーダルシフトの促進」
(調査実施団体:株式会社三菱総合研究所)
調査協力
機関 丸紅株式会社、Transport Development and Strategy Institute a Vietnam(TDSI)、東京海洋大学兵藤教授
調査対象
国・地域 ベトナム、インドネシア
対象技術
分野 交通
事業・活
動の概要 バイク、自動車、バス等の道路交通機関に依存しているハノイ・ホーチミン、ジャカルタ
の 2 カ国 3 都市において、大量高速輸送システム(MRT)を導入し、モーダルシフトを促
進することにより、それまでの道路交通機関による GHG 排出量を削減する。 MRV 方
法論適用
の適格性
要件
・ 大量旅客輸送機関(MRT, BRT 等)を導入するプロジェクトであること ・ 当該輸送機関導入資金の一部又は全部に非民間外国資金を活用する(又は予定
である)こと
リ フ ァ レ
ンスシナ
リオ及び
バウンダ
リーの設
定
リファレンスシナリオは、MRT が導入されず既存の交通機関の利用が継続される。ただ
し、保守的に pkm当たりの排出量及び端末区間に相当する区間における移動距離を小
さく(95%信頼区間の下限値を)とり、かつ、既存交通機関の燃費が毎年1%ずつ改善
すると想定した。 また、バウンダリーには、①MRT区間(MRT乗車駅~MRT降車駅)、②端末区間(出発
地~MRT 乗車駅、MRT 降車駅~目的地)を含める。 算定方法
オプシ ョ
ン
下記2つの算定方法オプションがある。 オプション CO2 排出原単位 (リファレンスシナリオ) 端末区間
① デフォルト値 デフォルト値
② MRT 運行開始後アンケート MRT 運行開始後アンケート
① :MRT 駅間乗車人数及び電力消費のみモニタリングを要する、モニタリングが簡易
なオプション。ただし、排出削減量は②と比して小さい。 ② :正確に排出削減量を算定するオプション。MRT 運行開始後のアンケート調査が要
されるためモニタリング負荷は高いが、排出削減量も多くなる。 デフォル
ト値の設
定
設定した各デフォルト値/事業固有値、及び設定根拠を下表に示す。 デフォルト値/
事業固有値 設定パラメータ 設定根拠
デフォルト値 燃料 j の CO2 排出係数 IPCC Guideline 2006 等の公表値より設定
デフォルト値 燃費改善係数 燃費は様々な要因で増減するが、車両技術面では
改善が進むため技術改善に絞った設定とした。
デフォルト値 系統電力 CO2 排出係数 政府公表値より設定(送電端)
デフォルト値 送配電ロス World bank データより設定
事業固有値 MRT が無かった場合に MRT
乗客が利用していたであろう
交通機関の CO2 原単位(リフ
ァレンス)
∑(交通機関 i の移動距離÷燃料 j を使用する交通
機関 i の燃費÷交通機関 i の乗車人数×燃料 j の
CO2 排出係数)÷∑(交通機関 i の移動距離)
事業固有値 駅間距離帯 x の誘発率 MRT 沿線住民の MRT へ乗車するトリップ(転換トリッ
プ+誘発トリップ)に占める、誘発トリップの割合
事業固有値 端末区間において利用する交
通機関の CO2 原単位(プロジ
∑(端末区間の移動距離÷燃料 j を使用する交通機
関 i の燃費÷交通機関 i の乗車人数×燃料 j の CO2
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-2
ェクト) 排出係数)÷∑(端末区間の移動距離)
事業固有値 m 駅⇔n 駅間距離[km] MRT 1 号線、2 号線の路線計画
事業固有値 駅間距離帯xの乗客の端末区
間における駅間距離に対する
補正係数(リファレンス)[-]
MRT 沿線住民の日常的なトリップのうち、MRT 転換
前のトリップにおける仮想的な端末区間(MRT 転換
前トリップ距離と駅間距離の差)と駅間距離との比
事業固有値 駅間距離帯xの乗客の端末区
間における駅間距離に対する
補正係数(プロジェクト)[-]
MRT 沿線住民の日常的なトリップのうち、MRT 転換
後のトリップにおける端末区間と駅間距離との比
モニタ リ
ング手法 算定方法オプション①におけるモニタリング項目の、方法・頻度は以下の通り。
情報・データ モニタリング方法 モニタリング頻度
m 駅⇔n 駅間の乗車人数[人/y] IC カードの記録データ 継続(集計:年1回以上)
料金収入、各駅乗降客数より推計 継続(集計:年1回以上)
MRT に よ る 電 力 消 費 量
[MWh/y]
電力購入伝票 伝票取得毎(集計:年 1 回以上)
算定方法オプション②では、オプション①に加え、以下の項目について MRT 運行開始
後に MRT 乗客に対して年1回アンケート調査を実施する。 ・リファレンスシナリオ(MRT が無かった場合)における移動距離 ・リファレンスシナリオ(MRT が無かった場合)における交通手段の燃費 ・リファレンスシナリオ(MRT が無かった場合)における交通手段の乗車人数 ・MRT 利用時の出発地~目的地までの移動距離 ・MRT 利用時の端末区間の移動距離 ・MRT 利用時の端末区間の交通手段の燃費 ・MRT 利用時の端末区間の交通手段の乗車人数
GHG 排
出量及び
削減量
ハノイ 1 号線・2 号線、ホーチミン 1 号線、及びジャカルタ南北線における排出削減量の
算定結果は以下の通り。(単位:tCO2) オプション 路線 リファレンス排出量 プロジェクト排出量 排出削減量
Op.1 ハノイ 1 号線 92,466 54,199 38,267 ハノイ 2 号線 69,434 27,855 41,579
ホーチミン 1 号線 144,669 55,990 88,678 ジャカルタ南北線 88,973 68,565 20,408
第三者検
証の手法 オプション①における検証項目としては、1)各駅間距離(どの様な手法で測定した結果
かを確認)、2)各駅間乗車人数(IC カードの信頼性の証明)、3)MRT による電力消費
(不要な消費分が含まれてないか)である。オプション②では、オプション①に加え各乗客
の情報をアンケート結果から入力するため、アンケート原票と入力された値の整合をサン
プルチェックする必要がある。アンケート結果における異常値、アンケート手法等の問題
点は、方法論確定段階で手法を明確にすれば、プロジェクト毎の個別の対応手法の検
討は不要となる。 環境影響
等 建設に伴う煤煙・騒音やMRT運行に伴う振動等の影響が出る可能性はあるが、道路交
通機関の削減に伴う大気汚染物質の削減や持続可能な開発への寄与等も考慮すれば
効果的な事業と考えられる。 資金計画 本事業対象4路線はいずれも全投資総額の8割程度が円借款により拠出される予定で
ある。鉄道運営において収入源となる交通運賃については、JICA 殿がベトナム 3 事業
主体へ実施している技術協力において検討が行われている。 日本技術
の導入可
能性
本事業対象路線は本邦技術活用条件(STEP)での円借款供与が決定しているため、融
資対象総額の 30%以上が本邦資機材・役務とすることが定められており、製造技術や
運営ノウハウに優位性のある鉄道車両, E&M(信号、通信、電化等)(特に自動化料金収
受システム)への日本製品の導入が期待される。 ホスト国
における
持続可能
な開発へ
の寄与
対象 3 都市では公共交通機関が未発達であり、自動車交通への依存度が高く、また都
市人口も急増しているため、大気汚染対策、渋滞の低減等の観点で MRT が持続可能
な開発に寄与することが期待される。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-3
調査名:二国間オフセット・クレジット制度の実現可能性調査 「道路交通から大量高速輸送機関(MRT)へのモーダルシフトの促進」 団体名:株式会社三菱総合研究所 1.調査実施体制: 丸紅株式会社:主に事業の普及可能性及び経済性の調査及び現地関係者(関係省庁、
事業主体、現地コンサル会社)との調整を担当 Transport Development and Strategy Institute a Vietnam(TDSI):ベトナム運輸省(MOT)
管轄下の研究機関。ハノイでの現地実態調査を担当 東京海洋大学兵藤教授:モーダルシェア調査等現地実態調査に関する指導を担当 2.事業・活動の概要: (1)事業・活動の内容: 本事業は、バイク、自動車、バス等の道路交通機関に依存しているハノイ・ホーチミン、ジ
ャカルタの 2 カ国 3 都市において、大量高速輸送システム(MRT; Mass Rapid Transit System)を導入するものである。MRT へのモーダルシフトが促進されることにより、それまで
の道路交通機関による GHG 排出量が削減されると考えられる。
本事業対象 4 路線は、本邦技術活用条件にて円借款の供与が決定しており、事業実施
にあたり日本技術の導入が見込まれている。加えて、ベトナムでは、JICA の技術協力として、
O&M会社設立に向けた支援が実施されている。ハノイ 2号線事業主体であるMRBは 2012年度初旬に組織改編により従来のHRBより名前を変え、VNR, MAUR同様、正式に運営主
体設立に向けた検討機関としての役割を担うことが決まった。 (2)ホスト国の状況: ベトナムにおいては経済成長や都市部への人口集中に伴って交通量が増加しており、現
在では運輸部門のエネルギー消費量は国全体のエネルギー消費量の 30%、国全体の燃
料消費量の 60%を占める。これは過去十年間の平均で年間 10%増加している。中でも道
路交通は運輸部門の燃料消費量の68%を占めており、運輸部門で消費する燃料の90%が
ガソリンと軽油である。GHG 排出量でみても 2010 年には 2780 万 tCO2(IEEJ 及び TDSI 推計)に達する大きな排出源になっている。 このような背景から気候変動政策においても運輸部門は重要な位置を占めており、気候
変動の影響への対応と GHG 排出量の削減という2つの戦略を立てて対応している。前者に
対しては、MOTの気候変動への対応アクションプラン(2011-2015)に基づき、運輸部門への
気候変動の影響評価やそれに基づくアクションプランの作成、国際的なドナーからの支援
の獲得を研究している。また後者に関しては、気候変動に関する国家戦略(2011 年決定)に
おいて適切な交通計画の作成、公共交通機関の開発と都市部での私的交通増加の管理
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-4
等が定められている。 本調査で対象とする MRT の整備はこの国家戦略で位置づけられた公共交通機関の開
発に該当する。 なお、インドネシアにおいても経済成長や都市部への人口集中に伴って道路交通量は
増加し、運輸部門からの GHG 排出量の増加が問題となっており、改善策として公共交通機
関の導入が挙げられている。 (3)CDM の補完性:
CDM においては排出削減量に対する不確実性が大きいこと、1 プロジェクトで得られる排
出削減量が小さいこと、それに比べてモニタリング負荷が大きいこと等を背景に交通分野の
プロジェクトは概して少ない。特に単体対策ではない公共交通に関する方法論は 5 種類に
限定されており、これに対して登録されたプロジェクトも合計で 17 件にとどまっている。 本件に近い方法論は ACM0016 及び AM0031(うち MRT に適用可能なのは ACM0016)
となるが、これらの方法論では開業後の乗客に対するアンケート調査が必須となっており、
モニタリング費用が高くなるとともに、事前に削減量の見込みを立てにくくなっている。このた
めより多くのプロジェクトが形成されるためにはより簡便な方法論が必要であるが、これは多
くのプロジェクトの種類に適用できる原則に基づき、多くの国の同意が必要な CDM では実
現が困難である。このため、相手国の状況に応じた適格性要件やデフォルト値の設定が容
易な JCM/BOCM において実施する意義がある。 3. 調査の内容 (1)調査課題: ① 端末(出発地⇔MRT乗車駅、MRT降車駅⇔目的地)交通を、算定対象とすべきか否か
を、アンケート調査に基づく試算により判断する。 ② 端末交通を算定対象とする場合としない場合のそれぞれについて、排出削減量算定方
法を検討する。また、端末交通を算定対象としない場合については、リファレンスシナリ
オにおける移動距離の設定方法についても検討する。 ③ 排出削減量の算定に用いる、1)リファレンスシナリオにおけるモーダルシェア、2)各交
通機関の平均実燃費、3)各交通機関の平均乗車人数、について、デフォルト値設定方
法及びデフォルト値を、MRT 沿線住民等へのアンケート調査及びバス・タクシー会社へ
のインタビュー調査を実施することで検討・設定する。 ④ 上記検討及び調査の結果として得られた、排出削減量算定方法及びデフォルト値(案)
を用いて、対象路線の想定排出削減量の試算を行う。 ⑤ 適格性要件等、MRV 方法論に必要となる要素の検討も昨年度より継続して実施する。 ⑥ 現地 MRT 実施主体及び関係機関の JCM/BOCM に対する理解・協力促進に努める。 ⑦ ベトナム・ハノイにおける調査結果をもとに、ホーチミン、及び、ジャカルタへの MRV 方
法論適用可能性を検討する。 (2)調査内容: 上記(1)調査課題に対応した成果は、下記の通りである。 ① MRT 沿線住民への家庭調査の結果より、MRT が整備されたと仮定した場合の端末交
通(アクセスとイグレス)を無視できず、端末交通を考慮すべきとの結論を得た。 ② 端末交通やレファレンスシナリオにおけるモーダルシェアの把握方法により合計 2 通り
の算定方法のオプションを設定し算定方法を検討した(添付方法論参照)。また、レファ
レンスシナリオにおける移動距離についても検討した。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-5
③ MRT沿線住民への家庭調査(5,000人)及びタクシー運転手へのタクシー調査(460人)、
バス運行会社へのバス調査(10 社)結果より、1)モーダルシェア、2)平均実燃費、3)平均乗車人数の値を算出した(調査結果概要は、下表の通り)。またこれらの結果を用い
て算定に必要な各種のデフォルト値、事業固有値を設定した。 ④ 算定方法及び現地実態本調査結果を用いて、想定排出削減量の試算を行った。 ⑤ 対象 MRT 路線は円借款供与が決定しているため、JICA との議論を踏まえ、主に追加
性に係る適格性要件の再検討を行った。また、MRV 方法論のその他箇所についても、
全般的に検討を行った。 ⑥ 8 月 23 日ハノイにおいてキックオフセミナーを開催、また 11 月 9 日のハノイ・ホスト国委
員会に参加し、現地に対する理解・普及促進に貢献した。さらに 1 月 23 日にハノイにて
関係者会合を行い、方法論についての意見交換を行った。 ⑦ ハノイで適用する前提で方法論等の検討を実施し、結果を取りまとめた。それを受けて、
この方法論が他都市への適用可能かを検討し、適用上の課題を整理した。 本調査では現地実態を把握するため、ベトナム国ハノイ市で整備予定の MRT 1 号線、2
号線の沿線住民、タクシー運転手、バス運行会社を対象に対面式アンケートで現地実態調
査を実施した。現地実態本調査の調査内容と結果概要は下表のとおりである。
表 現地実態本調査の調査内容と結果概要 調査名 家庭調査 タクシー調査 バス調査
目的
・ MRT 転換前の利用交通手段(モーダル
シェア)を把握
・ 二輪車、乗用車の燃費、平均乗車人数を
把握
・ MRT の利用を仮定したときのアクセス・イ
グレス交通を把握
・ タクシーの燃費、平均乗
車人数を把握
・ バスの燃費、平
均乗車人数を把
握
対象者 MRT 1 号線、2 号線の沿線住民(5,000 人)
MRT 1 号線、2 号線の沿線
のタクシープールで待機し
ている運転手(460 人)
ハノイ市内を運行
しているバス会社
(10 社、79 台)
結果
・ モーダルシェア:
二輪車 73.9%、バス 14.7%
・平均実燃費:
二輪車は 30.84km/l
乗用車は 11.18 km/l
・平均乗車人数:
二輪車 1.17 人
乗用車(運転手含む)1.51 人
・平均実燃費(ガソリン):
12.75 km/l
・平均乗車人数:
2.30 人(運転手を含まな
い)
・平均実燃費(ディ
ー ゼ ル ) : 2.87
km/l
・平均乗車人数:
40.18 人(運転手
を含まない)
4. 二国間オフセット・クレジット制度の事業・活動についての調査結果 (1)事業・活動の実施による排出削減効果: GHG排出削減効果をもたらす理由・根拠 本事業は、都市交通をバイクや自動車、バス等の道路交通機関に依存しているハノイ、ホ
ーチミン、ジャカルタの 3 都市において、大量高速輸送機関(MRT)を導入するものである。
当該事業によって従来の道路交通機関から MRT へのモーダルシフトが生じ、従前の道路
交通機関(バイク、バス、自動車等)における温室効果ガス(GHG)排出量が削減される。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-6
MRV方法論の内容 モーダルシフトによる GHG 削減効果を定量評価するための MRV 方法論は、算定オプシ
ョンによって算定式が異なる。各オプションについては、(3)算定方法オプションを参照のこと。
なお、本方法論は、CDM の ACM0016(Mass rapid transit projects)を参考としている。 また、本方法論は MRT 以外にも BRT や LRT 等の大量輸送機関も対象としている。基本
的に算定式に相違は無いが、プロジェクト排出量は電気のみに限定している等、 MRTを想
定して検討を行ったため、表記も“MRT”に統一している。 排出削減量の算定式は、以下の通りである。リファレンス排出量は、MRT が導入されない
場合に利用される既存道路交通機関による排出量であり、「交通量(pkm)×排出係数
(tCO2/pkm)」で算定する。ただし、交通量には駅間距離だけでなく端末区間の移動距離相
当分も考慮して設定する。 また、プロジェクト排出量は、MRT 運行に伴う排出量「電力消費量(MWh)×排出係数
(tCO2/MWh)×(1-送配電ロス)」と端末区間での交通機関利用による排出量「交通量
(pkm)×排出係数(tCO2/km)」との合計である。
図 リファレンス排出量の算定方法
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-7
図 プロジェクト排出量の算定方法
(2)MRV 方法論適用の適格性要件: 適格性要件 大量旅客輸送機関(MRT, BRT 等)を導入するプロジェクトであること 当該輸送機関導入資金の一部又は全部に非民間外国資金を活用する(又は予定であ
る)こと 追加的な排出削減効果をもたらす根拠 大量旅客輸送機関の導入は、いかなる国においても当該国の交通マスタープランにおい
て長期間前より計画されている場合がほとんどである。しかし、実際に当該輸送機関が導入
されるか否かは、資金調達の可能性に依存する。自国資金や民間資金のみで導入可能で
ある場合には何ら問題なく導入されることとなろう。一方で、非民間外国資金を活用する場
合、融資されるか否かの決定が当該輸送機関の導入決定に大きく影響を及ぼすが、このよ
うな非民間外国資金のドナーが融資決定をする際には単なる経済性ではなくその融資の社
会的な意義を考慮して融資を行う。大量旅客輸送機関の導入において、温室効果ガスの削
減は主要な社会的意義の一つであり、導入決定の一要素となりうる。このため、非民間外国
資金を活用して導入する場合については、一定の障壁が認められることから追加的と認めら
れる。 (3)算定方法オプション: 本方法論における算定方法オプションとして、下記2つを設定する。 オプション①が簡易なオプションであるが、保守的なデフォルト値を設定するため排出削
減量はオプション②と比して相対的に小さくなる。一方、オプション②はMRT開業後にMRT乗客に対してアンケート調査の実施が必要であるためモニタリング負荷が大きいが、排出削
減量も大きくなる。モニタリング負荷と得られる排出削減量のバランスで、プロジェクト実施主
体が算定方法オプションを自由に選定する。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-8
表 算定方法オプション
オプション CO2 排出原単位
(リファレンスシナリオ) 端末区間
① デフォルト値 デフォルト値
② MRT 運行開始後アンケート MRT 運行開始後アンケート
図 算定方法オプションの選定フロー
(4)算定のための情報・データ: 算定に必要となる情報・データは次表の通りである。
表 算定に必要な情報・データ一覧 RE/PE*1,2 情報・データ M/S/D*3 整備状況 備考
RE(A) m駅⇔n駅間の乗車人数
[人/y]
M(Op.1/2) IC カードでの把握可能 IC カード導入は未だ正式に決定さ
れていない。導入される場合であ
っても、データ加工の対応有無に
ついて確認が必要。
料金収入、各駅乗降客数
より推計して把握
チケットシステムによって把握方法
は異なる。
RE(A) 駅間距離帯 x の誘発率 S(Op.1) 本 FS 調査で仮値を設定 MRT が空想上の存在に過ぎない
現時点での調査結果から固有値
を設定することは危険であるため、
MRT 運行開始直前に再度調査し
設定する必要がある。
RE(A) m 駅⇔n 駅間距離[km] S(Op.1/2) 路線計画あり -
RE(B) 駅間距離帯 x の乗客の
端末区間における駅間
距離に対する補正係数
(リファレンス)[-]
S(Op.1) 本 FS 調査で設定 95%信頼区間の下限値を採ること
で保守性を担保する
RE(A/B) CO2 原単位(リファレン
ス)[tCO2/pkm]
S(Op.1) 本 FS 調査で設定 95%信頼区間の下限値を採ること
で保守性を担保する
PE(B) CO2 原単位(プロジェク
ト)[tCO2/pkm]
S(Op.1) 本 FS 調査で設定 95%信頼区間の上限値を採ること
で保守性を担保する
RE(A/B) 燃費改善係数[-] D(Op.1) 本 FS 調査で設定 ACM0016 と同じ 1%/年とする
RE(A/B) MRT が無い場合に利用
される交通機関の燃料
の CO2 排出係数[tCO2/
固有単位]
D(Op. 2) 本 FS 調査で設定 毎年更新の必要あり
PE(B) 端末交通として利用され
る交通機関の燃料の
CO2 排出係数[tCO2/固
有単位]
D(Op. 2) 本 FS 調査で設定 毎年更新の必要あり
RE(A/B) MRT が無い場合に利用 M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ -
※ Y:YES,N:NO
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-9
される交通機関の燃費
[km/固有単位]
ート調査を実施して把握。
PE(B) 端末交通として利用され
る交通機関の燃費[km/
固有単位]
M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ
ート調査を実施して把握。
-
RE(A/B)
MRT が無い場合に利用
される交通機関の乗車
人数[人/台]
M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ
ート調査を実施して把握。
-
PE(B) 端末交通として利用され
る交通機関の乗車人数
[人/台]
M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ
ート調査を実施して把握。
-
RE(A/B) 駅間距離帯 x の乗客 i の
移動距離[km]
M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ
ート調査を実施して把握。
-
RE(B) 駅間距離帯 x の乗客 i の
端末区間に相当する区
間における移動距離
[km]
M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ
ート調査を実施して把握。
-
PE(B) 駅間距離帯 x の乗客 i の
端末区間における移動
距離[km]
M(Op.2) MRT 運行開始後にアンケ
ート調査を実施して把握。
-
PE(B) 駅間距離帯 x の乗客の
端末区間における駅間
距離に対する補正係数
(プロジェクト)[-]
S(Op.1) 本FS調査で設定 95%信頼区間の上限値を採ること
で保守性を担保する
PE(A) MRT による電力消費量
[MWh/y]
M(Op.1/2) 購入伝票の保有可能 MRT 運行による電力消費量
PE(A) 系統電力 CO2 排出係数
(送電端)[tCO2/MWh]
D(Op.1/2) 本 FS 調査で設定 毎年更新の必要あり
PE(A) 送配電ロス D(Op.1/2) 本 FS 調査で設定 毎年更新の必要あり
*1: RE:リファレンス排出量、PE:プロジェクト排出量 *2: A:MRT 区間、B:端末交通区間 *3: M:モニタリング、S:事業固有値、D:デフォルト値設定 (5)デフォルト値の設定: デフォルト値は、ベトナムで MRT を整備する際の CO2 排出削減量を算出する方法論とし
て共通に設定可能な項目とする。これらは、ハノイに限らずベトナム全土に適用可能とする。 本調査でデフォルト値を設定すべき項目を「算定に必要な情報・データ一覧」から抜粋す
ると、「燃料 j の CO2 排出係数」、「燃費改善係数」、「系統電力 CO2 排出係数(送電端)」、
「送配電ロス」の 4 項目である。 上記各項目についてデフォルト値を設定するための調査内容、デフォルト値、設定根拠、
当該デフォルト値が保守的な算定結果を導出する理由を記載した。 表 デフォルト値の設定
RE/PE 項目 調査内容 デフォルト値 設定根拠 保守的な算定結果を
導出する理由
RE
PE
燃料 jのCO2
排出係数
既存の公表値に
より把握する。
軽油:0.00279 tCO2/l
ガ ソ リ ン : 0.00240
tCO2/l
(毎年更新必要)
IPCC Guideline
2006 等の公表
値より算定
公表値による平均的な値で
あるため、保守的な設定は
不要である。
RE
PE
燃費改善係
数
既存の燃費改善
事例から類推す
る。
1%/年 燃費は様々な
要因で増減する
が、車両技術面
では改善が進む
ため技術改善に
絞った設定とし
た。
CDM 方法論 ACM0016 及び
AM0031 を参考に設定。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-10
PE 系 統 電 力
CO2 排出係
数(送電端)
既存の公表値に
より把握する。
0.5408 tCO2/MWh
(毎年更新必要)
MONRE による
公 表 値 よ り 設
定。
公表値による平均的な値で
あるため、保守的な設定は
不要である。
PE 送配電ロス 既存の公表値に
より把握する。
10.1%
(毎年更新必要)
世界銀行による
公 表 値 よ り 設
定。
公表値による平均的な値で
あるため、保守的な設定は
不要である。
事業固有値については、ハノイの MRT 1 号線、2 号線を整備する際に、固有に設定を行
う値である。従って、本調査で事業固有値を設定すべき項目を「算定に必要な情報・データ
一覧」から抜粋すると、「MRT が無かった場合に MRT 乗客が利用していたであろう交通機
関の CO2 原単位」、「駅間距離帯 x の誘発率」、「端末区間において利用する交通機関の
CO2 原単位」、「m 駅⇔n 駅間距離」、「m 駅⇔n 駅間の乗客の仮想端末区間における移動
距離の駅間距離に対する補正係数(リファレンス)」、「m 駅⇔n 駅間の乗客の端末区間にお
ける移動距離の駅間距離に対する補正係数(プロジェクト)」の 6 項目である。 上記各項目について事業固有値を設定するための調査内容、事業固有値、設定根拠、
当該事業固有値が保守的な算定結果を導出する理由を記載した。
表 事業固有値の設定
RE/PE 項目 調査内容 事業固有値 設定根拠 保守的な算定結果を
導出する理由
RE MRT が無
かった場合
に MRT 乗
客 が 利 用
していたで
あろう交通
機 関 の
CO2 原単
位
既存の公表値並び
に、MRT 沿線住民で
二輪車、乗用車等を
保有している人を対
象にアンケート調査
を実施すると共に、タ
クシー運転手、バス
会社へのインタビュ
ー調査を実施するこ
とで把握する。
駅間距離帯別に
4km以下:6.41×
10-5
tCO2/pkm
4~6km:6.88×
10-5 tCO2/pkm
6~8km:7.02×
10-5 tCO2/pkm
8km超:5.79×10-5 tCO2/pkm
∑(交通機関 i の移
動距離÷燃料 j を使
用する交通機関 i の
燃費÷交通機関 iの
乗車人数×燃料 jの
CO2排出係数)÷∑
(交通機関 i の移動
距離)
駅間距離帯別に、平均値の
95%信頼区間の下限値を用
いてデフォルト値を設定する
ことにより、統計誤差を踏ま
えて最小となる CO2 原単位
を設定することとなり、保守
的な設定が可能となる。
RE 駅 間 距 離
帯 xの誘発
率
MRT沿線住民を対象
にアンケート調査を
実施することで把握
する。
駅間距離帯別に
4km 以下:17.2%
4~6km:12.9%
6~8km:11.6%
8km 超:17.7%
誘発トリップの年間
人キロ/(誘発トリッ
プの年間人キロ+
転換トリップの年間
人キロ)
現在の回答結果には MRT
に乗車することが移動の目
的となっている人が含まれ
ており高めの数値になって
いる可能性がある。
PE 端 末 区 間
において利
用 す る 交
通 機 関 の
CO2 原単
位
既存の公表値並び
に、MRT 沿線住民で
二輪車、乗用車等を
保有している人を対
象にアンケート調査
を実施すると共に、タ
クシー運転手、バス
会社へのインタビュ
ー調査を実施するこ
とで把握する。
駅間距離帯別に
4km以下:1.39×
10-5
tCO2/pkm
4~6km:1.26×
10-5 tCO2/pkm
6~8km:1.91×
10-5 tCO2/pkm
8km超:2.69×10-5 tCO2/pkm
∑(端末区間の移動
距離÷燃料 j を使用
する交通機関 i の燃
費÷交通機関 iの乗
車人数×燃料 j の
CO2排出係数)÷∑
(端末区間の移動距
離)
駅間距離帯別に、平均値の
95%信頼区間の上限値を用
いてデフォルト値を設定する
ことにより、統計誤差を踏ま
えて最大となる CO2 原単位
を設定することとなり、保守
的な設定が可能となる。
RE m 駅⇔n 駅
間距離
[km]
MRT 1 号線、2 号線
の路線計画から把握
する。
駅間の路線延長
(具体的な数値
は多数あるため
割愛)
MRT 1 号線、2 号線
の路線計画
測量データ等から正確な値
を把握できるため、保守的
な設定は不要
RE
駅 間 距 離
帯 xの乗客
の 端 末 区
間における
MRT 沿線住民への
アンケート調査により
MRT へ転換するトリ
ップについて、MRT
駅間距離帯別に
4km 以下:0.68
4~6km:0.23
6~8km:0.22
MRT 沿線住民の日
常的なトリップのう
ち、MRT に代替する
トリップの転換前の
駅間距離帯別に、平均値の
95%信頼区間の下限値を用
いてデフォルト値を設定する
ことにより、統計誤差を踏ま
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-11
駅 間 距 離
に 対 す る
補 正 係 数
(リファレン
ス)[-]
転換前のトリップにお
ける仮想端末区間の
距離を把握し、駅間
距離との比を算出す
る。
8km 超:0.20 トリップにおける仮
想端末区間の距離
(転換前トリップ距離
と駅間距離の差)と
駅間距離の比
えて最小となる補正係数を
設定することとなり、保守的
な設定が可能となる。
PE 駅 間 距 離
帯 xの乗客
の 端 末 区
間における
駅 間 距 離
に 対 す る
補 正 係 数
(プロジェク
ト)[-]
MRT 沿線住民への
アンケート調査により
MRT へ転換するトリ
ップについて、MRT
転換後のトリップにお
ける端末区間の距離
を把握し、駅間距離
との比を算出する。
駅間距離帯別に
4km 以下:0.64
4~6km:0.42
6~8km:0.39
8km 超:0.36
MRT 沿線住民の日
常的なトリップのう
ち、MRT に代替する
トリップの端末区間
距離と駅間距離の
比
駅間距離帯別に、平均値の
95%信頼区間の上限値を用
いてデフォルト値を設定する
ことにより、統計誤差を踏ま
えて最小となる補正係数を
設定することとなり、保守的
な設定が可能となる。
(6)リファレンスシナリオ及びバウンダリーの設定: リファレンスシナリオ
MRT が導入されず、既存の交通機関の利用が継続される。 ただし、保守的に pkm 当たりの排出量及び端末区間に相当する区間における移動距離
を小さく(95%信頼区間の下限値を)とり、かつ、既存交通機関の燃費が毎年1%ずつ改善
すると想定した。 ハノイにおける実態調査において、MRT が導入された場合に MRT に転換すると回答さ
れた既存トリップに起因する CO2 排出量を調査した。これは現時点での BaU であり、これに
経年変化を考慮したものが、リファレンスシナリオと言い得る。経年変化予測は困難である点、
毎年調査するのは多大なコストがかかる点から、技術改善により燃費が毎年向上すると想定
して毎年1%(出典:ACM0016)を乗じることとした。 さらに、①CO2 排出原単位(tCO2/pkm)、②端末移動距離の補正係数、について、ハノイ
における実態調査結果の平均値ではなく、95%信頼区間の下限値を採ってデフォルト値と
することで、保守性を担保したリファレンスシナリオを設定することとした。 なお、MRT自体については、MRTの敷設自体が追加的である(「4.3 MRV方法論適用の
適格性要件」参照)ことから、MRT 未整備の状態をリファレンスシナリオとした。 現在ベトナム及びインドネシアでは都市鉄道は未だ導入されておらず、バイクや自動車な
どの私的交通に依存した交通体系であり、渋滞が深刻な状況にある。こうした状況を踏まえ、
運輸部門の気候変動対策として公共交通システムの開発が位置づけられているが、公共交
通機関は巨額の投資を伴うため実際に導入されるかは資金調達可能性に依存する。非民
間外国資金の活用が前提である場合、それがなければ当該公共交通機関は導入されない
と考えられる。このため、リファレンスシナリオは非民間外国資金による支援なしで実施され
るものであると考え、当該事業におけるリファレンスシナリオはMRTが導入されない状態と想
定する。 バウンダリー バウンダリーに含め得る排出活動の範囲として、下記3種類が想定される。 A) MRT 区間(MRT 乗車駅~MRT 降車駅) B) 端末区間(出発地~MRT 乗車駅、MRT 降車駅~目的地) C) 周辺道路(MRT 沿線) このうち、本方法論では A) MRT 区間、および、B) 端末区間をバウンダリーに含めること
とした。この考え方に基づく算定対象となる排出源及び GHG 種類は、次表の通り。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-12
表 算定対象となる排出源及び GHG 種類 RE/PE 排出源 GHG 種類
A) MRT RE MRT で代替される交通機関 CO2
PE MRT CO2
B) 端末 RE MRT で代替される交通機関 CO2
PE 出発地⇒MRT 乗車駅、MRT 降車駅⇒目的地で利用する交通機関 CO2
*1: RE:リファレンス排出量、PE:プロジェクト排出量
図 バウンダリー
なお、「(B)端末交通量に伴う排出」、「(C)周辺道路交通量への影響に伴う排出(リーケー
ジ排出)」の CDM 事例調査結果は下記の通りである。 表 CDM プロジェクトにおける端末・リーケージ排出の影響度
プロジェクト (適用方法論:ACM0016)
MRT /BRT
PDD/ MR※
(B)端末交通に伴う排出 (C)リーケージ排出量
tCO2/year 排出量
tCO2/year プロジェクト排
出に占める割合 BRT Lines 1-5 EDOMEX, Mexico BRT MR 10,858 46.4% 48 Metro Delhi, India MRT MR 72,658 29.4% 287 BRT Metrobus Insurgentes, Mexico
BRT PDD 51,397 74.6% 0
Mumbai Metro One, India MRT PDD 38,489 56.5% 0 Metro Line 12, Mexico City(未登
録) MRT PDD 125,871 93.4% 0
※MR:Monitoring Report 上記の結果、および、ハノイでの実態調査結果より、本調査におけるそれぞれの扱いは
以下の通りとする。 (B)端末交通に伴う排出:排出削減量への影響は一定程度あるためバウンダリー内。 (C)リーケージ排出:全ケースにおいてリーケージ排出量はゼロ,又は影響を無視できるほ
どの値である。よって、本調査においてリーケージ排出は考慮しないこととする。 (7)モニタリング手法: モニタリングすべきパラメータは次表の通りであり、モニタリング手法及び頻度を合わせて
示す。 表 モニタリングするパラメータと方法・頻度
RE/PE*1,2 情報・データ Op. *3 モニタリング方法 モニタリング頻度
RE(A) m 駅⇔n 駅間の乗車
人数[人/y]
Op.1/2 IC カードの記録データ 継続(集計:年1回以上)
料金収入、各駅乗降客数 継続(集計:年1回以上)
(A)MRT 交通 MRT で発生している交通量(CO2)
(B) 端末交通: 駅へ/駅からのアクセスで発生する交通量(端末需要) (CO2)
A 駅 B 駅 出発地
周辺道路 (C) 周辺道路における交通: 周辺道路交通量への影響(CO2)
目的地
バウンダリー
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-13
より推計
RE(A/B) MRT が無い場合に利
用される交通機関の
燃費[km/固有単位]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
PE(B) 端末交通として利用さ
れる交通機関の燃費
[km/固有単位]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
RE(A/B)
MRT が無い場合に利
用される交通機関の
乗車人数[人/台]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
PE(B) 端末交通として利用さ
れる交通機関の乗車
人数[人/台]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
RE(A/B) 駅間距離帯 x の乗客 i
の移動距離[km]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
RE(B) 駅間距離帯 x の乗客 i
の端末区間に相当す
る区間における移動
距離[km]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
PE(B) 駅間距離帯 x の乗客 i
の端末区間における
移動距離[km]
Op.2 MRT 運行開始後にアンケ
ート調査
年 1 回
PE(A) MRT による電力消費
量[MWh/y]
Op.1/2 電力購入伝票 伝票取得毎
(集計:年1回以上)
*1: RE:リファレンス排出量、PE:プロジェクト排出量 *2: A:MRT 区間、B:端末交通区間 *3: Op.:算定方法オプション アンケート調査を必要としないオプション①を選択する場合は、MRT 運営主体が通常の
鉄道経営の一環として把握するデータ(駅間乗車人数、電力消費量)のみのモニタリングを
要求している。このため、当該モニタリング手法の実施可能性は極めて高い。 一方で、アンケート調査を必須とするオプション②を選択する場合、実施可能性はオプシ
ョン①と比較して低くなる。CDM と同程度のモニタリングを求めており、排出削減量をより正
確に算定したい場合に自主的に選択するオプションである。 モニタリング体制は算定オプション毎に異なるが、基本的に MRT 運営主体のみでモニタ
リング可能である。ただし、アンケートを実施する場合(オプション②)、アンケート調査を外
部のコンサル等に委託して実施する可能性もある。想定しうる体制図を、次に示す。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-14
図 モニタリング体制
(8) 温室効果ガス排出量及び削減量: 本調査において入手したデータを用いて、ハノイ 1 号線・2 号線、ホーチミン 1 号線、及び
ジャカルタ南北線について、排出削減量の算出を行った。デフォルト値については、前述の
通りハノイにおける調査をベースとして設定した値であるが、本 FS の削減量試算について
は、ホーチミン及びジャカルタに対する排出削減量試算に関しても同値を使用することとす
る。 以下に、オプション 1 における排出削減量の算定結果を示す。
表 排出削減量算定結果 (単位 tCO2/年) オプション 路線 リファレンス排出量 プロジェクト排出量 排出削減量
Op.1 ハノイ 1 号線 92,466 54,199 38,267 ハノイ 2 号線 69,434 27,855 41,579
ホーチミン 1 号線 144,669 55,990 88,678 ジャカルタ南北線 88,973 68,565 20,408
なお、現在計画段階にあるベトナムにおける MRT 事業は、ハノイ 9 路線、ホーチミン 6 路
線(本調査の対象である1号線も含む)である。各路線の路線長等の詳細は未定だが、将来
的に全 MRT 路線が導入された場合で、かつハノイ 1 号線・2 号線と同程度の削減が期待さ
れると仮定すれば、排出削減ポテンシャルはオプション 1 で約 60 万[tCO2/年]となる。
(9)排出削減量の第三者検証: 本プロジェクトの場合、それぞれのオプションにおいて必要な検証は以下の通りである。
• オプション①:基本的にはデフォルト値を用いるため、入力項目は1)各駅間距離、2)
各駅間乗車人数、3)MRT による電力消費である。検証に際しては、1)はどの様な手
法で測定した結果かを確認する必要があり、2)は乗車人数を測定するための IC カー
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-15
ドの信頼性(国際規格/国内規格等の適合)をまずは証明する必要がある。また、欠落
等のエラーデータの除外もポイントとなる。3)は MRT による電力消費のみの値となっ
ているかがポイントとなり、その点も含めて消費量を伝票で確認する必要がある。 • オプション②:オプション①に加え、各乗客の情報(移動距離、MRT が無い場合の交
通機関、同交通機関の燃費、等)をアンケート結果から入力する。そのため、アンケー
ト原票と入力された値の整合をサンプルチェックする必要がある。なおアンケート結果
における異常値をどの様に外すか、あるいはそもそもアンケートがどの様な形式で行
われるべきかという問題もあるが、それらの点は方法論確定段階で手法を明確にすれ
ば、プロジェクトごとの個別の対応手法を検討することは不要である。 なおベトナム現地の検証機関としては、“Vietnam Certification Centre”、“Bureau Veritas
Certification Viet Nam”等が検証機関の候補として挙げられる。 (10)環境十全性の確保: 対象両国において環境影響評価は法制化されており、対象 4 路線に関する環境影響評
価(EIA)は既に実施済みであり、各国省庁又は地方政府より承認を受けている。本事業実
施により想定される環境への好影響は、道路交通機関の削減に伴う大気汚染物質(NOx、CO、HC、PM)の削減である。一方で、建設に伴う煤煙・騒音や MRT 運行に伴う振動等の
悪影響が出る可能性はあるが、環境への好影響や持続可能な開発への寄与等も考慮すれ
ば効果的な事業であると考えられる。 (11)利害関係者のコメント: 本調査は当該事業自体の実施可能性を検討するものではなく、MRT 導入による GHG 排
出削減量の測定方法を検討するものである。本調査の実施にあたっては、ホスト国関係省
庁、各路線事業主体及び資金供与を実施する JICA 殿が利害関係者にあたるものと思料す
る。調査過程において関係省庁、各路線事業主体等へは方法論検討状況につき数度の説
明を行うとともに、2013 年 1 月 23 日にはハノイにおいて、本調査の最終報告兼、方法論
への現地側意向聴取を目的とした会議を開催し、ベトナム天然資源環境省、運輸省、戦略
政策研究所やハノイ市都市鉄道 1 号線、2 号線の各事業主体であるベトナム鉄道総公社
(VNR)、ハノイ市都市鉄道管理委員会(MRB)等関係各機関出席の下、コメントを伺った。各
機関ともに本調査対象案件が JCM/BOCM の対象として調査実施されている点につき歓迎
しており、他路線についても対象となるよう期待している。
(12)事業・活動の実施体制: 当該事業の実施体制スキームは次図の通りである。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-16
一般的に、MRT の実施主体は地方自治体や自治体が設立した事業体が担う。また、
EPC 入札は「土木」「鉄道車両」「E&M(Electrical & Mechanical)」にスコープ分けされ、現
地・海外企業はそれぞれに優位性の発揮できる分野に対して企業コンソーシアムの形で参
加する。 (13)資金計画: いずれも全投資総額の 8 割程度が円借款により拠出される予定である。鉄道運営におい
て収入源となる交通運賃については、JICA 殿がベトナム 3 事業主体へ実施している技術協
力において検討が行われている。
(14)日本製技術の導入促進策:
MRT 建設では、一般的に(1)土木、(2)鉄道車両、(3)E&M(Electrical & Mechanical:信号、
通信、電化等) といったスコープに分けて入札が実施される。本事業対象路線は本邦技術
活用条件(STEP)での円借款供与が決定しているため、融資対象総額の 30%以上が本邦
資機材・役務とすることが定められており、製造技術や運営ノウハウに優位性のある(2),(3)への日本製品の導入が期待される。 特に(3)については自動化料金収受システム(Automatic Fare Collection/ AFC System)の
導入促進のため、国交省殿主導の下ベトナムでセミナーが開催されており、Type C (Felica System)及びそれに付随する本邦技術の導入が期待されている。ホーチミンでは Type C 導
入が確定しており、1 号線のみならず全路線共通で活用される予定である。
H24 JCM/BOCM FS 最終報告書(概要版)
Ⅱ-17
(15)今後の見込みと課題: べトナム、インドネシア両国における交通分野の GHG 排出抑制に対する意識は強く、同
分野への二国間オフセット・クレジット制度適用に対する期待は高い。 また、本調査対象の 4 案件はいずれも円借款供与が決まっており、それぞれ 2017~2020
年(予定)の運転開始と共に確実に実施が可能であるが、予定時期通りの運転開始のために
は事業性における課題(土地収用、予算確保、設計リスク、運営主体設立、複数路線のネッ
トワーク)や、JCM/BOCM 適用のための各種課題(合同委員会での方法論承認、方法論の
拡張、ホーチミン及びジャカルタへの適用、方法論適用に必要な再調査の実施、事業主体
にとってメリットのあるクレジットの制度設計、自動料金収受システムによるモニタリング可否)
が考えられる。
5. 持続可能な開発への貢献に関する調査結果 対象 3都市では公共交通機関が未発達であり、自動車交通への依存度が高く、また都市
人口も急増しており、現状の交通体系のままでは持続可能な開発を進めることは困難である。
このため都市部での MRT 整備による効率的輸送体系構築は不可欠であり、国の政策や都
市のマスタープランにも位置づけられている。 なお、ベトナムにおいては道路交通ヘの依存度が高いことから、GHG 削減のみならず大
気汚染対策としても MRT への期待が高いとのコメントをベトナム MOT よりいただいた。