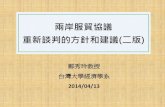経済財政運営と改革の基本方針 2020について 閣議 …...令和2年7月 17日 閣議決定 経済財政運営と改革の基本方針 2020を別紙のとおり定める
ISO/IEC 専門業務用指針 第1部 - IEC活動推進会議| … 専門業務用指針 第1 部...
Transcript of ISO/IEC 専門業務用指針 第1部 - IEC活動推進会議| … 専門業務用指針 第1 部...

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部
専門業務の手順
第6版 2008年

国際標準化機構 1,ch.de la Voie-Creuse Case postale 56 CH -1211 Geneva 20 電話: +41 22 749 0111 ファックス: +41 22 733 3430 E-mail: [email protected] ホームページ: http://www.iso.org
国際電気標準会議 3,rue de Varembé Case postale 131 CH -1211 Geneva 20 電話: +41 22 919 0211 ファックス: +41 22 919 0300 E-mail: [email protected] ホームページ: http://www.iec.ch
© ISO/IEC 2008 著作権 - ISO 及び IEC 文書の作成を目的とする場合に限り,この電子ファイルをダウンロードし,複
製・印刷することが認められています。これ以外の目的については,発行人の書面による許可なく,こ
のファイルまたはその一部をコピーしたり“他のパソコンに移す”ことはできません。
2

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
目次
まえがき ..................................................................................................................................................... 6 1. 専門業務に関する機関構成及び責任 ................................................................................................ 8
1.1 TMBの役割............................................................................................................................ 8 1.2 TMB諮問グループ ................................................................................................................. 8 1.3 合同専門業務......................................................................................................................... 9 1.4 事務総長の役割 ..................................................................................................................... 9 1.5 TCの設置................................................................................................................................. 9 1.6 SCの設置 .............................................................................................................................. 11 1.7 TC及びSC業務への参加........................................................................................................ 11 1.8 TC及びSC議長 ...................................................................................................................... 13 1.9 TC及びSC幹事国 .................................................................................................................. 13 1.10 編集委員会 ............................................................................................................................ 15 1.11 WG........................................................................................................................................ 15 1.12 PT.......................................................................................................................................... 17 1.13 委員会内の諮問機能をもつグループ..................................................................................... 17 1.14 アドホックグループ.............................................................................................................. 17 1.15 TC間のリエゾン.................................................................................................................... 18 1.16 ISOとIEC間のリエゾン......................................................................................................... 18 1.17 他の機関とのリエゾン .......................................................................................................... 18
2 ISの開発 ........................................................................................................................................... 20 2.1 プロジェクトへの取り組み ................................................................................................... 20 2.2 予備段階................................................................................................................................ 23 2.3 提案段階................................................................................................................................ 24 2.4 作成段階................................................................................................................................ 25 2.5 委員会段階 ............................................................................................................................ 26 2.6 照会段階................................................................................................................................ 27 2.7 承認段階................................................................................................................................ 29 2.8 発行段階................................................................................................................................ 30 2.9 規格のメンテナンス.............................................................................................................. 30 2.10 技術的正誤票及び追補 .......................................................................................................... 30 2.11 メンテナンス機関 ................................................................................................................. 31 2.12 登録機関................................................................................................................................ 31 2.13 著作権 ................................................................................................................................... 31 2.14 特許対象項目の扱い(附属書Iも参照のこと) ..................................................................... 31
3 その他の刊行物の開発...................................................................................................................... 32 3.1 TS.......................................................................................................................................... 32 3.2 PAS ....................................................................................................................................... 33 3.3 TR ......................................................................................................................................... 33
4 会議 .................................................................................................................................................. 34 4.1 一般 ...................................................................................................................................... .34 4.2 会議招集の手順 ..................................................................................................................... 34 4.3 会議での使用言語 ................................................................................................................. 35 4.4 会議の取消し......................................................................................................................... 35
5 異議申し立て .................................................................................................................................... 35 5.1 一般 ....................................................................................................................................... 35
3

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
5.2 SCの決議に対する異議申し立て .......................................................................................... 36 5.3 TCの決議に対する異議申し立て........................................................................................... 36 5.4 TMBの決議に対する異議申し立て........................................................................................ 37 5.5 異議申し立て期間中の業務の進行 ........................................................................................ 37
附属書A(規定)ガイド .......................................................................................................................... .38 A.1 序文 ....................................................................................................................................... 38 A.2 提案段階................................................................................................................................ 38 A.3 作成段階................................................................................................................................ 38 A.4 委員会段階 ............................................................................................................................ 38 A.5 照会段階................................................................................................................................ 38 A.6 発行段階................................................................................................................................ 39 A.7 ガイドの廃止......................................................................................................................... 39
附属書B(規定)リエゾン及び業務割当てに関するISO/IEC手順 ........................................................... 40 B.1 序文 ....................................................................................................................................... 40 B.2 一般概念................................................................................................................................ 40 B.3 新TCの設置 ........................................................................................................................... 40 B.4 ISO及びIECのTC間の調整及び業務割当て........................................................................... 41
附属書C(規定)規格制定提案の妥当性.................................................................................................. 44 C.1 一般 ....................................................................................................................................... 44 C.2 定義 ....................................................................................................................................... 44 C.3 一般原則................................................................................................................................ 44 C.4 専門活動の新分野(新委員会)提案に際して明確にすべき要素 ......................................... 45 C.5 新業務項目(新規格)提案に際して明確にすべき要素 ........................................................ 47 C.6 マトリックス......................................................................................................................... 47 C.7 専門活動の新分野提案例....................................................................................................... 48 C.8 新業務項目の提案例.............................................................................................................. 51 C.9 提案目的の確定のためのマトリックス ................................................................................. 52 C.10 専門活動の新分野提案の目的確定のためのマトリックス .................................................... 53 C.11 NPの目的確立のためのマトリックス例................................................................................ 54
附属書D(規定)幹事国の備えるべきリソース及び幹事の資格.............................................................. 55 D.1 定義 ..................................................................................................................................... 55 D.2 幹事国の備えるべきリソース ............................................................................................... 55 D.3 幹事への要求事項 ................................................................................................................. 56
附属書E(規定)言語の使用に関する一般方針 ....................................................................................... 57 E.1 国際の場における見解の表現及び伝達 ................................................................................. 57 E.2 専門業務における言語の使用 ............................................................................................... 57 E.3 IS........................................................................................................................................... 57 E.4 TCが開発するその他の出版物 .............................................................................................. 58 E.5 TC及びSC会議のための文書 ................................................................................................ 58 E.6 英語または仏語以外の言語で作成する文書.......................................................................... 58 E.7 専門会議................................................................................................................................ 59
附属書F(規定)プロジェクトの開発のための選択肢 ............................................................................ 61 F.1 選択のための簡易図式 .......................................................................................................... 61 F.2 “迅速法による手順” .......................................................................................................... 62
附属書G(規定)メンテナンス機関......................................................................................................... 63
4

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書H(規定)登録機関 ....................................................................................................................... 64 附属書I(規定)ITU-T/ITU-R/ISO/IECの共通特許方針の実施ガイドライン............................................ 65 対訳版への付録:略語集.......................................................................................................................... 77
5

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
まえがき
ISO/IEC専門業務用指針は,2部に分けて出版されている。 ・ 第1部: 専門業務の手順
・ 第2部: ISの構成及び原案作成の規則 ISO及びIECは上記に加え,両機関に共通でない手順を記載した補足指針をそれぞれ独自に発行してい
る。規格開発プロセスに関連するすべての書式は,ISO/IEC専門業務用指針のそれぞれの補足指針に掲
載している。 この第1部は,ISO及びIECが,専門委員会とその附属組織の活動を通じて、主にISの開発及びメンテナ
ンスを行うにあたって従うべき手順について定める。ISO/IEC JTC 1の手順は,ISO及びIECの他の委員
会に適用する手順とは異なっている。 ISO及びIECは,技術文書の作成に携わる人々のために,それぞれwebサイト(http://www.iso.ch/sdis 及び http://www.iec.ch)を設けて詳しい指針とツールを掲示している。 この第6版には,2004年の第5版発行以降にそれぞれのTMBが承認した変更事項を織り込んでいる。一
方の機関のみが採用した手順は,ISO/IEC専門業務用指針のISO補足指針またはIEC補足指針として,そ
れぞれ別冊で発行されている。補足指針は,この文書と併用すべきものである。 旧版に加えた主な変更事項は,次のとおりである。 a) JWGの手順を追加し(1.11.5参照),また,形態5-一体化したリエゾンでの規格開発の手順を追加
した(B.4.2.6参照)。
b) IECにおけるPASの取り扱いに関する条項を削除した。
c) ITU-T/ITU-R/ISO/IECの共通特許方針の実施ガイドラインを修正なくそのまま含めた(附属書I参照)。
ISO 及び IEC は,IS が広く認知され,一般的に適用されるとともに,経済的かつタイムリーに開発さ
れることが必要であるとの認識のもとに,これらの手順を定めた。これらの目標を達成するため,手順
は次のコンセプトに基づいている。 a) 近代的技術及びプログラムマネジメント これらの手順の枠内においては,新技術と近代的プログラムマネジメント手法を段階的に導入すること
で業務処理能率が向上するとともに,専門家及び幹事国のタスクが容易になることが期待される。 b) 合意 合意の形成は,本質的反対意見の解決が不可欠で,世界に受け入れられ広く使用される IS を作成する
ための手続上の基本的な原則であり,必要条件である。専門業務が迅速に進められることは必要なこと
ではあるが,重要な技術的見解の不一致については,承認段階に至る前に十分に時間を費やして審議し,
検討を行い,解決を図ることが必要である。
6

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
c) 規律 国代表組織は,長くはっきりしない“休止期間”を生じさせることがないように,期限と予定に関する
規律を守らなければならない。また同様に,審議の繰り返しを避けるため,国代表組織はその技術的見
解が自国の関係者すべての意見を確実に反映したものとする責任がある。その観点から 終(承認)段
階ではなく,業務の早い段階において,その技術的見解を明確にすることについての責任がある。さら
に,国代表組織は,本質的な意見を会議の場になって提出することが目的達成を妨げることを認識して
おかなければならない。なぜならば,他の代表たちが自国に戻って,そのために必要な協議を行うこと
ができないため,迅速な合意の達成が困難なものとなるからである。 d) 経済的効率性 これらの手順は,業務実施にあたっての総費用を考慮に入れている。“総費用”の概念には,国代表組
織の直接経費,ジュネーブ事務所の経費(主として国代表組織からの分担金の積み立てによる),国内
及び国際レベルの WG 及び委員会の専門家の旅費並びに時間的コストを含めている。 備考 1 簡略化のため,本書では ISO と IEC 内で類似の,または同一の概念を表わすために,適宜,次の用
語を使用している。
用語 ISO IEC
国代表組織 会員団体(MB) 国内委員会(NC)
技術管理評議会(TMB) 技術管理評議会(ISO/TMB) 標準管理評議会(SMB)
事務総長(CEO) 事務総長 事務総長
中央事務局 中央事務局(CS) 中央事務局(CO)
理事会 理事会 評議会(CB)
諮問グループ 専門諮問グループ(TAG) 諮問委員会
他の概念についてはISO/IEC Guide 2を参照。 備考2 本書では,次の略語を使用する。
JTAB ISO/IEC合同専門諮問評議会 JCG 合同調整グループ JWG 合同作業グループ TC 専門委員会 SC 分科委員会 WG 作業グループ PT プロジェクトチーム PWI 予備業務項目 NP 新業務項目提案 WD 作業原案 CD 委員会原案 DIS 国際規格案(ISO) CDV 投票用委員会原案(IEC) FDIS 終国際規格案 PAS 公開仕様書 TS 技術仕様書 TR 技術報告書
7

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1. 専門業務に関する機関構成及び責任 1.1 TMB の役割 ISO及びIECの各TMBは,専門業務のマネジメント全般,特に次の業務の責任を負う。 a) TCの設置
b) TC議長の任命
c) TC幹事国,及び場合によっては,SC幹事国の割当てまたは再割当て
d) TCのタイトル,業務範囲,作業計画の承認
e) TC が行う SC の設置及び解散の承認
f) 必要であれば,専門業務の特定項目の優先順位決定
g) 複数のTCが関係しているテーマに関する規格または共同開発が必要な規格を開発する際の責任の
割当てを含む専門業務の調整。このタスクを支援するものとして,TMBは関連分野の専門家で構成
される諮問グループを設置することがあり,この諮問グループは,基本的な調整,専門分野の調整,
分野間の調整,一貫性のある計画立案,並びに必要な新業務についてTMBに助言を行う。
h) 中央事務局の支援を得た専門業務の進捗状況の監視及び適切な措置
i) 新しい技術分野における業務の必要性及び計画の立案
j) ISO/IEC専門業務用指針及びその他の専門業務用規則のメンテナンス
k) 国代表組織から提起された原則的問題及び,NP,CD,照会原案またはFDISに関する決議に対する
異議申し立てについての検討 備考 NP,CD,照会原案及びFDISについての用語説明は,第2節で行う。 1.2 TMB 諮問グループ 1.2.1 1.1.g)でいう諮問機能を有するグループを,次のとおり設置できる。 a) どちらかのTMBだけで
b) 両方のTMBが合同で 備考 IECでは,このようなグループは諮問委員会と呼ばれている。 1.2.2 このようなグループ設置の提案には,効率的な運営を確保するために可能な限り少人数で行うと
同時に,影響を受ける関係者を十分に代表するという必要性を考慮して,業務事項とグループ構成に関
する勧告を含めなければならない。例えば,関係TCの議長と幹事だけをメンバーとすることができる。
いずれの場合も,TMBは適用すべき基準を定めて,メンバーを任命しなければならない。 業務事項,グループ構成,または該当する場合,作業方法に関するグループからの変更提案は,TMBに提出して承認を求めなければならない。 1.2.3 諮問グループへ割り当てるタスクには,出版物(特に,IS,TS,PAS及びTR)の原案作成また
は整合化に関する提案も含めてよいが,これらの文書の作成は,TMBの特別の承認がない限り,含めて
はならない。
8

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1.2.4 発行を目的として作成される文書は,附属書Aの手順の原則に従わなければならない。 1.2.5 諮問グループの成果は,勧告の形式でTMBに提出する。勧告には,出版物作成のためのWG(1.11参照)またはJWG(1.11.5参照)の設置提案を盛り込むことができる。これらのWGを設置する
場合は,関連TCの中で運営する。 1.2.6 諮問機能を持つグループの内部文書の配布はグループメンバーだけに限り,中央事務局にはコピ
ーを提出する。 1.2.7 諮問グループは,その特定の役目を完了するか,またはタスクが通常のリエゾンの仕組みで果た
せると決定した場合(1.16参照)には解散する。 1.3 合同専門業務 1.3.1 合同専門諮問評議会 JTABの任務は,ISOとIECの専門業務においてタスクの重複ないしその可能性を回避または排除するこ
とであり,両機関のいずれかが合同計画の必要性を認めた場合に開催する。 JTABは,現行の手順では
下部の組織間で解決困難な問題だけを取り扱う(附属書B参照)。このような場合には,専門業務の他に
計画及び手順上の問題を含めることができる。 JTABの決議は即時実施のために,両機関に伝達される。JTABの決議に対しては,少なくとも3年間,
異議申し立てを行うことができない。 1.3.2 合同専門委員会 合同専門委員会は,ISO/TMB及びIEC/SMBの共同決議,またはJTABの決議によって設置することがで
きる。 1.4 事務総長の役割 ISO,IEC両機関の事務総長は,特に,ISO/IEC専門業務用指針とその他の専門業務規則の施行に関する
責任をもつ。このために,中央事務局は,TC,理事会及びTMB間のすべての連絡調整を行う。 ISOまたはIECの事務総長の許可,もしくはJTABの許可なく,現行の文書に規定されている手順から逸
脱してはならない。 1.5 TC の設置 1.5.1 TCの設置及び解散は,TMBが行う。 1.5.2 TMBは,関係TCとの協議に基づいて,既存のSCを新TCとして改編することができる。 1.5.3 それぞれの機関において,新TCの設置が必要とみられる新しい専門業務分野に関する提案を行
うことができるのは、以下のものである。 ・ 国代表組織
・ TCまたはSC
・ 政策レベルの委員会
9

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
・ TMB
・ 事務総長
・ ISO,IECの後援を受けて運営されている認証システムの管理責任を担っている組織
・ 国代表組織が加入している他の国際機関 1.5.4 提案には適切な書式(ISO/IEC専門業務用指針の各補足指針を参照)を使用し,次の事項を記載
する。 a) 提案者
b) 提案のテーマ
c) 対象業務範囲及び初期業務計画案
d) 提案の妥当性
e) 該当する場合は,他の組織が行った類似業務に関する調査
f) 必要と思われる他の組織とのリエゾン 提案書は,中央事務局に提出される。 提案の妥当性に関する詳細については,C.4を参照。 1.5.5 事務総長は提案を受領した後,直ちに,TMB議長を含む関心を持つ人達と協議を行わなければ
ならない。必要であれば,提案内容の審査を行うためのアドホックグループを設置することができる。 協議を通じて事務総長がまとめたコメント及び勧告は,提案書に加えられなければならない。 1.5.6 中央事務局は,次の可否を問う質問を添えて,それぞれの機関(ISOまたはIEC)のすべての国
代表組織に提案を回付しなければならない。 a) 新TCの設置を支持するか
b) 新TCの業務に積極的に参加(1.7.1参照)する意思があるか 提案はまた,コメント及び同意を得るため,もう一方の機関(IECまたはISO)にも提出しなければな
らない(附属書B参照)。 提案に対する回答は,回付後3か月以内に適切な書式によって行われなければならない。 1.5.7 TMBは回答を評価し,次のいずれかを行わなければならない。 ・ 次の事項を条件として,新TCの設置を決議し,かつ幹事国を割当てる(1.9.1参照)
1) 投票した国代表組織の2/3以上が提案に賛成であり
2) 5か国以上の国代表組織が積極的に参加する意思を表明している
・ 上記の同じ受入基準に従って,その業務を既存のTCに割り当てる 1.5.8 TCには,その設置順に従って番号を付ける。TCが解散された場合,その番号を他のTCに割り当
ててはならない。 1.5.9 新TCの設置を決議した後は,できるだけ早く,必要なリエゾン体制を整えなければならない。
(1.15~1.17参照)
10

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1.5.10 新TCを設置した後は,できるだけ早く,望ましくは書面審議で,タイトル及び業務範囲につい
て合意しなければならない。業務範囲は,TCの業務の境界を正確に表現する記述である。 TCの業務範囲の定義は,“…の標準化”または“…の分野における標準化”という文言で始めるものと
し,またできるだけ簡潔に作成する。新TCの業務範囲は,国際標準化の一般的目的,またはすべての
専門委員会の業務に適用される原則を繰り返すものであってはならない。ある種の事項が当該TCの業
務範囲外であることを明示する必要のある場合は,これらの事項を業務範囲の末尾に列挙して,“除外
事項: … ”という文言で提示する。 業務範囲に関する推奨事項については,ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の第2節と附属書
A並びにISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の附属書SBを参照。 1.5.11 合意されたタイトルと業務範囲は,事務総長からTMBに提出され承認を得なければならない。 1.5.12 TMBまたはTCは,TCのタイトル及び/または業務範囲の修正を提案することができる。修正
文言はTCが作成して,TMBの承認を得なければならない。 1.6 SC の設置 1.6.1 SCは,TMBの承認を条件として,TCのPメンバーによる投票の2/3以上の多数決によって設置,
または解散される。SCは,ある国代表組織が幹事国を引き受ける用意のあることを表明すれば設置で
きる。 1.6.2 SCはその設置時に,SCの業務に積極的に参加(1.7.1参照)する意思を表明した5か国以上のTCのメンバーがいなければならない。 1.6.3 一つのTC内のSCは,その設置の順番で表示される。SCを解散した場合,それがTC全体の組織
再編の一環でない限り,その表示を他のSCに割り当ててはならない。 1.6.4 SCのタイトル及び業務範囲はTCによって定められるものとし,またそれは,TCの業務範囲内
のものでなければならない。 1.6.5 TCの幹事国は,SC設置に関する決議を適切な書式を使用して中央事務局に通知しなければなら
ない。中央事務局はその書式をTMBへ提出し,その決議の承認を求めなければならない。 1.6.6 新SCを設置するとの決議を承認後,できるだけ早く他の組織との必要なリエゾン体制を整えな
ければならない(1.15~1.17参照)。 1.7 TC 及び SC 業務への参加 1.7.1 すべての国代表組織は,TC及びSCの業務に参加する権利を有する。
も効率よく業務を運営し,必要な規律を確保するため,国代表組織は,各TCまたはSCに関して次の
意思を持つならば,これを中央事務局に明確に示さなければならない。
11

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
・ TCまたはSC内での票決のために正式に提出されるすべての案件,NP,照会原案及びFDISに対す
る投票の義務を負って,業務に積極的に参加し,また会議に貢献する(Pメンバー),もしくは,
・ オブザーバとして業務を行う。そのため委員会文書の配布を受け,またコメントの提出と会議への
出席の権利を持つ(Oメンバー)。 国代表組織は,どの委員会についてもPメンバーでもOメンバーでもない地位を選ぶことができるが,
この場合,これらの委員会業務に関しては,上述の義務も権利も持たない。しかしながら,すべての国
代表組織は,そのTCまたはSC内のこれらの地位にかかわりなく,照会原案(2.6参照)及びFDIS (2.7参照)投票の権利を有する。 国代表組織は,自国のすべての関係する利害を考慮して,効率的かつタイムリーな方法で自国の回答・
意見をとりまとめる義務を有する。 1.7.2 TCのPメンバー及びOメンバーはそのSCのメンバーになることができる。TCのOメンバーは,
TC内での地位を変えることなく,そのSCのPメンバーになることができる。 TCメンバーには,SCの設置に際して,そのPメンバーまたはOメンバーとなる意思を表明する機会が与
えられなければならない。 TCのメンバーであることは,必ずしも自動的にSCのメンバーであることを意味しない。SCメンバーに
なることを希望するTCメンバーは,その旨の通知を行う必要がある。 1.7.3 国代表組織は中央事務局と当該委員会幹事国に通知することで,いつでも,いかなるTCまたは
SCに関しても,メンバー資格の取得,返上,または地位の変更を行うことができる。 1.7.4 次の場合,当該のTCまたはSCの幹事国は,その旨を事務総長に通知しなければならない。 ・ TCまたはSCのPメンバーが継続的に不活動であり,連続して二回の会議に直接参加もしくは文書
による意見提出をせずに協力を怠った場合
・ または,TCまたはSCのPメンバーが,TCまたはSC内での票決のために正式に提出された案件に対
する投票を怠った場合(1.7.1参照) このような通告を受け取った場合,事務総長は,当該の国代表組織に対し,TCまたはSCの業務に積極
的に参加する義務を怠らぬよう注意を促さなければならない。この注意に対して満足すべき反応がない
場合,当該国代表組織は自動的にその地位をOメンバーに変更される。このような地位の変更を受けた
国代表組織は,12か月の期間を経た後,事務総長に対して委員会のPメンバーに復帰する希望を表明す
ることができ,その場合は復帰が認められる。 1.7.5 TCまたはSCのPメンバーが,それぞれの委員会が作成した照会原案またはFDISへの投票を怠っ
た場合,事務総長は,当該国代表組織に対し,投票の義務を怠らぬよう注意を促さなければならない。
この注意に対して満足すべき反応がない場合,国代表組織は自動的にその地位をOメンバーに変更され
る。このような地位の変更を受けた国代表組織は,12か月の期間を経た後,事務総長へ委員会のPメン
バーに復帰する意向を表明することができ,その場合は復帰が認められる。
12

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1.8 TC 及び SC 議長 1.8.1 任命 議長の任命については,ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の第3節及びISO/IEC専門業務用
指針2001年版ISO補足指針の1.8を参照のこと。 1.8.2 責任 TC議長は,SC及びWGを含むTCのマネジメント全般に関する責任をもつ。TC議長はTMBに対し,その
TCに関する重要事項をTC幹事国経由で通知しなければならない。そのため,TC議長は,SC幹事国経
由ですべてのSC議長からの報告を受けなければならない。
TCまたはSCの議長責任は,次のとおりとする。
a) 自国の見地から離れて,純粋に国際的な立場で行動する。それゆえ,議長は,自身の委員会で自国
代表組織の代表を兼務することはできない。
b) TCまたはSCの幹事の,職務遂行を指導する。
c) CDに関する合意を目的として会議を運営する(2.5参照)。
d) 会議において,出席者全員が確実にすべての意見を理解できるよう,適切に要約を行う。
e) 会議において,すべての決議事項が明確にまとめられ,また会議中に確認のために幹事によって文
書形式で提供できるようにする。
f) 照会段階(2.6参照)において,適切な決定を行う。 予期せず,議長が会議に出席できない場合,その会議の議長を出席者から選出することができる。 1.9 TC 及び SC 幹事国 1.9.1 割当て TC幹事国は,TMBが国代表組織に割り当てる。 SC幹事国は,TCが国代表組織に割り当てる。ただし,複数の国代表組織が同一のSC幹事国の引受けを
申し出た場合は,TMBがSC幹事国の割当てを決議しなければならない。 TC及びSCの双方について,幹事国の割当ては,次に該当する国代表組織を対象に行うものとする。
a) 当該のTCまたはSCの業務に積極的に参加する意思を表明しており
b) 幹事国としての責務を遂行することを了承し,幹事国業務を行うための適切なリソースを確保でき
る状態にある(D.2参照)。 TCまたはSCの幹事国が割り当てられた当該国代表組織は,適格な人物を幹事として任命しなければな
らない(D.1参照)。 1.9.2 責任 幹事国が割り当てられた国代表組織は,それぞれのTCまたはSCに対し,専門的及び管理的な任務を確
実に遂行しなければならない。
13

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
幹事国は,業務の進捗状況の監視,報告及び活発な業務進行に関する責任を負い,その業務が速やかに,
かつ,十分な結果を得られるように, 大限の努力を払わなければならない。このようなタスクは,で
きる限り書面審議によって行う。 幹事国は,ISO/IEC専門業務用指針及び理事会とTMBの決議を遵守して以下を確実に行う責任がある。 幹事国は,次のことを的確な時期に確実に行わなければならない。 a) CDの作成,その配布(ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の附属書D及びISO/IEC専門
業務用指針2001年版ISO補足指針の附属書SFを参照)の手配及び受領したコメントの処理
b) 次の点を含む会議の準備(第4節も参照)
・ 議題の設定及びその配布の手配
・ WGの報告書を含めた,議題に関するすべての文書配布の手配及びその他会議中に必要な審議
用資料の提示(E.5参照)
・ 議題の文書に対するコメント集の作成
c) 会議中に採択された決議の記録及びこれらの決議を会期中に確認できるようにするための文書化
(E.5参照)
d) 会議議事録の作成
e) TMB (TC幹事国の場合)または親委員会(SC幹事国の場合)に対する報告書の作成
f) 照会原案及びFDISの作成 TCまたはSC幹事国は,英語版と仏語版の同等性を確保する責任がある。この場合に必要であれば両言
語版の作成に関して責任を持てる能力と意思のある他の国代表組織の協力を得ることができる (1.10及びISO/IEC専門業務用指針の各補足指針も参照)。 いかなる場合においても,各幹事国は,そのTCまたはSC議長と緊密な連携をとりながら業務を進めな
ければならない。 幹事国は自国の見地から離れて,純粋に国際的な立場で活動しなければならない。 TC幹事国は,中央事務局及びその活動に関係するTCメンバー,さらにそのSC,WGメンバーを含め,
密接に連絡を保たなければならない。 SC幹事国は,TCの幹事国及び,必要に応じて中央事務局と密接に連絡を保たなければならない。SC幹
事国はまた,WGメンバーも含め,その活動に関係するSCメンバーとの連絡を保たなければならない。 TCまたはSC幹事国は,中央事務局と協力して,委員会メンバーの状況に関する記録を更新しておくと
ともに,ISOではそのWGメンバーの登録状況をメンテナンスしておかなければならない。 1.9.3 TC 幹事国の交代 国代表組織がTC幹事国をやめたいと望む場合は,直ちに事務総長にその旨を通知しなければならず,
その際, 低12か月の猶予期間をおかなければならない。他の国代表組織への幹事国の移行は,TMBが決議する。
14

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
TC幹事国がこれらの手順に定められた自らの責務の実行を継続して怠っている場合,事務総長または
国代表組織は,この問題をTMBに提起することができ,TMBは,TC幹事国を他の国代表組織に移すこ
とを念頭に置いて割当てを見直すことができる。 1.9.4 SC 幹事国の交代 国代表組織がSC幹事国をやめたいと望む場合は,直ちにTCの幹事国にその旨を通知しなければならず,
その際, 低12か月の猶予期間をおかなければならない。 SC幹事国がこれらの手順に定められた自らの責務の実行を継続して怠っている場合,事務総長または
国代表組織は,この問題をTCに提起でき,TCはPメンバーの多数決投票をもって,SC幹事国の再割り
当てを決議することができる。 上記のいずれの場合においても,TC幹事国はSCの他のPメンバーに対し,幹事国引受けの申し出がな
いか照会しなければならない。 同一SC内で複数の国代表組織が幹事国の引受けを申し出た場合,またはTCの構成上,幹事国の再割当
てがTC幹事国の再割当てにつながる場合は,TMBがSC幹事国の再割当てを決議する。引受けの申し出
が一件だけの場合に限り,TC自身がその任命を行う。 1.10 編集委員会 CD,照会原案及びFDISを更新し編集するため,並びにISO/IEC専門業務用指針第2部に適合させるため
に,一つまたは複数の編集委員会を設置することを推奨する(2.6.6も参照)。 編集委員会は,少なくとも次のメンバーで構成する。
・ 英語を母国語とし,仏語に十分な知識を有する技術専門家1名
・ 仏語を母国語とし,英語に十分な知識を有する技術専門家1名
・ プロジェクトリーダー(2.1.8参照)
プロジェクトリーダー及び/または幹事は,当該言語版の一つに対して直接責任を持っても良い。 IECの場合,要請があれば,中央事務局の代表は編集委員会の会議に出席する。 編集委員会は, TCまたはSC幹事国から要請された場合,書面審議で次の段階に進めることが承認され
た当該原案を更新し,編集するために会合を持たなければならない。(2.6.6も参照)。 編集委員会は,電子的に文書を処理し,機械読取り形式での 終文書を提出できる手段を備えていなけ
ればならない(2.6.6も参照)。 1.11 WG 1.11.1 TCまたはSCは,特定のタスクについてWGを設置することができる(2.4参照)。WGは,親委
員会が任命したコンビナを通して,TCまたはSCに報告しなければならない。
15

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
WGは,WGに割り当てられた特定のタスクを行うために招集され,親委員会のPメンバー,親委員会の
カテゴリーA及びDリエゾン機関からそれぞれ任命された限定された人数の専門家で構成される。専門
家は,彼らを任命したPメンバーまたはカテゴリーAもしくはDリエゾン機関(1.17参照)の公式代表と
してではなく,個人の立場で活動する。しかしながら、業務の進捗状況及びWG内のさまざまな意見を
できるだけ早い段階において報告するために,当該Pメンバーまたは機関と密接な連絡を保つことが推
奨される。 WGは,適切な人数に制限することを推奨する。そのため,TCまたはSCは,専門家の総数及び各Pメン
バーが任命する専門家の 大人数についても定めてよい。 WGを設置する決議が下されたら,専門家を任命するため,各Pメンバー並びにカテゴリーA及びDリエ
ゾン機関に正式に通知する。 WGには,その設置順に続き番号を付ける。 委員会がWGの設置を決議した場合,コンビナまたはコンビナ代理が直ちに任命され,3か月以内に第1回WG会議を開催するための準備を行う。委員会の会議後直ちに,この情報はその委員会のPメンバー
並びにカテゴリーA及びDリエゾン機関に,6週間以内の専門家任命要請を添付して,通知されなければ
ならない。 1.11.2 委員会幹事は,WGの構成名簿(氏名,住所,電話・FAX番号及び電子メールアドレス)を第1回WG会議前にWGコンビナが入手できるようにしなければならない。メンバーの氏名は,他のメンバ
ー及び親委員会のメンバーにも開示される。 1.11.3 タスクの完了― 通常は,照会段階(2.6参照)の終わり―に伴いWGは解散し,プロジェクト
リーダーは,発行段階(2.8参照)が完了するまでコンサルタントの地位に残る。 1.11.4 WGの内部文書及びその報告書は, ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の附属書D 及びISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の附属書SFに記述されている手順に従って配布され
なければならない。 1.11.5 特別な場合,複数のISO及び/またはIECのTCまたはSCが利害関係を持つ特定のタスクを引き受
けるために,JWGを設置してもよい。JWG設置の決定に際しては,以下の点で委員会相互が合意して
いなければならない。 ・ 委員会/機関がプロジェクトの管理責任を負うこと
・ JWGのコンビナ
・ JWGのメンバーシップ(例えば,親委員会のメンバーで利害関係を持つすべての専門家がメンバー
になれる,あるいは,それぞれの親委員会からの人数が同数になるよう参加制限を決めることがで
きるなど)
プロジェクトの管理責任を負う委員会/機関は,以下のことを行わなければならない。
・ 業務計画にプロジェクトを記録すること
・ プロジェクトのすべての段階におけるコメントと投票が適切に編集され,かつ処理されるよう保証
すること(2.5、2.6及び2.7参照)
・ 2.5,2.6及び2.7の手順に従って,委員会段階,照会段階及び承認段階の原案を作成すること
・ 出版のメンテナンスに責任を負うこと
16

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
終的な出版及びその後のメンテナンス,JWGのコンビナ及びメンバーシップをどちらの委員会/機関
が担当するかについての決定を含め,ISO/IECのJWGの設置提案は,TMBに提出しその承認を受ける
(B.4.2.11も参照)。 1.12 PT IECにおいては,新業務項目(2.3参照)を承認する過程において,業務項目を承認するPメンバーは,
プロジェクトの開発に参加できる専門家を指名することを求められる。IECにおいては,これらの専門
家がPTを形成し,プロジェクトリーダーの責任のもとで活動しなければならない。PTは,当該プロジ
ェクトに割り当てられたプロジェクト番号で指定する。プロジェクトが完了したら,PTは解散しなけ
ればならない。各PTは,通常,業務計画に一つのプロジェクトしか持たないことが望ましい。PTは,
グループ化してWGとすることも,親委員会の傘下に設置することもできる。 PTの業務に関する他の側面については,1.11,WGを参照のこと。 1.13 委員会内の諮問機能をもつグループ 1.13.1 TCまたはSCは,委員会業務の調整,計画,運営にかかわるタスク,もしくは諮問的性格の特
定のタスクについて,議長及び幹事国のタスクを支援するための諮問機能を持つグループを設置するこ
とができる。 1.13.2 このグループを設置する提案には,影響を受ける関係者を十分に代表することと,効率的な運
営のために人数を極力制限することの両方を念頭に置いた構成に関する勧告を含まなければならない。
諮問グループのメンバーは,国代表組織が指名する。 終的構成は,親委員会が承認しなければならな
い。 1.13.3 このグループに割り当てられるタスクには,出版物(特に,IS,TS,PAS及びTR)の原案作
成または整合化に関する提案の作成を含めてよいが,これらの文書の作成そのものを含めてはならない。 1.13.4 このグループの成果は,グループを設置した母体組織に勧告の形式で報告しなければならない。
この勧告の中に,出版物の作成のためのWG (1.11参照)またはJWG (1.11.5参照)の設置提案を含
めてもよい。 1.13.5 諮問機能を持つグループの内部文書は,そのメンバーだけに配布し,関係委員会の幹事国及び
中央事務局にはコピーを送る。 1.13.6 このグループは,指定されたタスクが完了次第,解散しなければならない。 1.14 アドホックグループ TCまたはSCは,アドホックグループを設置することができる。この目的は厳密に定義された問題を調
査し,親委員会に対しそれについての報告を,アドホックグループが設置されたのと同じ会議か,遅く
とも次の会議までに行うことである。 アドホックグループのメンバーは,親委員会に出席した代表者から選出され,必要であれば委員会で任
命された専門家により補強する。親委員会は,ラポータも任命しなければならない。 アドホックグループは,報告書を提出する会議において自動的に解散しなければならない。
17

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1.15 TC 間のリエゾン 1.15.1 ISO,IECのそれぞれの機関内にあって関連分野の業務を行っているTC及び/またはSCは,互
いにリエゾンを確立し,維持しなければならない。該当する場合は,標準化の基本的側面(例えば,専
門用語集,図記号)を担当しているTCともリエゾンを確立しなければならない。リエゾンにはNP及び
WDを含む基本文書の交換を含めなければならない。 1.15.2 このようなリエゾンを保つことは,それぞれのTC幹事国の責任であるが,TC幹事国はSC幹事
国にこのタスクを委任してもよい。 1.15.3 TCまたはSCは,リエゾン状態にある他のTCまたは一つ以上のその付属SCの業務に対処するた
めに1名以上のオブザーバを指名できる。オブザーバの指名は関連委員会の幹事国に通知され,この幹
事国は,このオブザーバ及び関連TCまたはSC幹事国にすべての関連文書を送付しなければならない。 任命されたオブザーバは,任命した幹事国に進捗報告をしなければならない。 1.15.4 オブザーバは,上記の業務を行うためにTCまたはSCの会議に出席する権利を有するが,投票
権はない。オブザーバは,その出席した会議において,自身の所属するTCの関連業務範囲内の事項に
ついて,文書によるコメント提出を含めて審議に協力することができる。オブザーバは,要求すれば,
TCまたはSCに所属するWGの会議にも出席することができる。 1.16 ISO と IEC 間のリエゾン 1.16.1 ISO及びIECのTCとSCの間には,適切なリエゾン関係を構築することが不可欠である。ISO及
びIECのTCとSCのリエゾンを確立するための連絡窓口は,両中央事務局である。新しいテーマの研究
に関する新規または改正業務計画がいずれか一方の機関において考えられており,他方の機関もそれに
ついて関心を持ちうる場合,両事務総長は業務が重複したり同じ努力を繰り返さずに業務が進捗するよ
うに,相互の意見の一致を求める(附属書Bも参照)。 1.16.2 ISOまたはIECによって指名されたオブザーバは,指名の対象となった業務に対処するために,
他方の機関のTCまたはSCの審議に参加する権利を有し,また文書によるコメントを提出できるが,投
票権はない。 1.17 他の機関とのリエゾン 1.17.1 リエゾンのカテゴリーすべてに適用可能な一般要求事項 リエゾンが効果的であるためには,適切な相互の働きかけによる双方向運営を行わなければならない。 リエゾンの望ましい形を業務の早い段階で考慮しなければならない。 リエゾン機関は,リエゾン機関が保有する場合であろうと他の機関が保有する場合であろうと,
ISO/IEC専門業務用指針に基づく著作権に関する方針(2.13参照)を受け入れなければならない。リエ
ゾン機関は,著作権の取扱い方針に関する声明文書を渡され,受け入れ可能な場合は明確な声明文書の
作成が求められる。協力機関は,提出された文書にいかなる変更も加える資格はない。 リエゾン機関は,IPRを含めて,ISO/IEC手順に同意しなければならない(2.13参照)。 リエゾン機関は,特許権に関する2.14の要求事項を受け入れなければならない。
18

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1.17.2 TC/SC レベルにおけるリエゾン 1.17.2.1 カテゴリーA リエゾン及び B リエゾン これらのリエゾンのカテゴリーは,次のとおり。
・カテゴリーA:TCまたはSCが取り扱う課題に関する業務について,そのTCまたはSCの業務に
効果的な貢献をする機関。これらの機関には,すべての関連文書へのアクセス権が与えられ,
会議への招請がなされる。これらの機関は,WG/PTに参加するための専門家を指名できる
(1.11.1及び1.12参照)。
・カテゴリーB:TCまたはSCの業務に関して,常に情報の提供を受けたいとの意向を表明した機
関。これらの機関には,TCまたはSCの業務に関する報告書へのアクセス権が与えられる。
1.17.2.2 受入基準 リエゾン機関は,類似もしくは関連分野で作業しているか,あるいはその分野に関心を持っている国際
機関,もしくは広範な基盤を持つ地域機関でなければならない。 TC及びSCは,リエゾンの資格を持つ機関が関係しているそれぞれの文書について,その機関の全面的
な,また可能なら公式な支持を求めなければならない。 1.17.2.3 リエゾンの確立 事務総長は,関係のTCまたはSCの幹事国と協議の上,リエゾンを確立する。リエゾンはまとめて記録
され,TMBに報告される。 1.17.2.4 リエゾンの見直し TC及びSCは,すべてのリエゾン状況を定期的に,少なくとも2年ごとに,またはすべての委員会会議
ごとに見直さなければならない。 1.17.3 WG/PT レベルでのリエゾン 1.17.3.1. カテゴリーDリエゾン1)
このリエゾンのカテゴリーは,次のとおり。
・カテゴリーD:WG,,MTまたはPTの業務に技術的貢献をし,かつ積極的に参加する機関。 1.17.3.2 受入基準 リエゾン機関には,工業会,販売団体,消費者グループ,専門家団体及び学会も含まれる。 リエゾン機関は,個人,法人または国の参加の下で,(その目的や規格開発活動において)多国籍でな
ければならないが,永続的なものであるか一時的なものであるかは問わない。 リエゾン機関は,ISOまたはIECに対して進んで適切に貢献しなければならない。 リエゾン機関は,関連する技術分野や産業分野の一部門(セクター)またはサブセクターの中で定義さ
れる能力領域に関し,セクターまたはサブセクターを代表し得る能力を有していなければならない。 1) カテゴリーCリエゾンはISO/IEC JTC1 で使用する。
19

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
1.17.3.3 リエゾンの運営 カテゴリーDリエゾンは,関連するWG/PT/MTを明らかにした上で,承認のために委員会幹事からTMBに提出されなければならない。提出に際しては,1.17.3.2に規定されている受入基準をその機関がいか
に満足しているかという点の明記のみならず,リエゾンを構築する理論的根拠を含めなければならない。
委員会幹事は,Dリエゾンの運営に責任を負う。 1.17.3.4 リエゾンの見直し TC及びSCは,すべてのリエゾン状況を定期的に,少なくとも2年ごとに,またはすべての委員会会議
ごとに見直さなければならない。 11.17.3.5 権利と義務 カテゴリーDリエゾン機関は,WG(1.11.1参照)またはPT(1.12参照)に完全なメンバーとして参加
する権利を有する。 カテゴリーDリエゾンの専門家は,彼らを指名した機関の正式な代表として活動する。
2 IS の開発 2.1 プロジェクトへの取り組み 2.1.1 一般 TCまたはSCの第一の任務は,ISの開発とメンテナンスである。しかしながら,委員会には同時に,第3節に述べる中間刊行物の出版を検討することが強く望まれる。 ISは,次に述べるプロジェクトへの取り組みに基づいて開発されなければならない。 2.1.2 戦略計画 各TCはそのTC独自の活動分野について,戦略計画を作成しなければならない。 a) 業務計画を進展させていくビジネス環境を考慮に入れる。
b) 業務計画の中の分野で拡大しつつあるもの,完了したもの,間もなく完了するかまたは着実に進展
しているもの,及び,進展がなく削除するのが望ましいものを示す(2.1.9も参照)。
c) 必要とされる改正作業を評価する(IEC/ISO専門業務用指針2008年版IEC補足指針の第4節及び
ISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の2.9も参照)。
d) 先端的ニーズについて見通しを示す。 戦略計画は正式にTCの合意を得た上で,TCの報告書に記載し,定期的にTMBによる見直しと承認を受
けなければならない。 2.1.3 プロジェクトの各段階 2.1.3.1 表1は専門業務が推進される間のプロジェクト段階の順序と各段階の関連文書名を示す。 TS, TR及び PASの開発については,第3節で説明する。
20

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
表1-プロジェクトの各段階と関連文書
関連文書 プロジェクトの段階
名称 略語
予備段階 提案段階 作成段階 委員会段階
照会段階
承認段階
発行段階
予備業務項目 新業務項目提案 作業原案1)
委員会原案1)
照会原案2)
終国際規格案3)
国際規格
PWI NP WD CD ISO/DIS IEC/CDV FDIS ISO,IECまたは ISO/IEC
1) これらの段階は,附属書Fに記載のとおり省略可能である。 2) ISOにおいてはDIS,IECにおいてはCDV。 3) 省略可能(2.6.4参照)。
2.1.3.2 F.1では,IS発行に至るまでの段階を示している。 2.1.3.3 ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の附属書F及び ISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の附属書SIは,プロジェクトの各段階をマトリックスで表現し,関連の副段階を一連番
号で表わしている。 2.1.4 プロジェクトの説明及び承認 プロジェクトとは,ISを新たに開発,追補または改正して発行することを目的として行われる業務のこ
とである。一つのプロジェクトは,さらに細分化することができる(2.1.5.4も参照)。 所定の手順に従って提案が承認された時,プロジェクトに着手する。(新業務項目の提案については2.3を参照,また,既存のISの見直し及びメンテナンスについては, ISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の2.9,及びISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の第4節を参照)。 2.1.5 業務計画 2.1.5.1 TCまたはSCの業務計画には,すでに出版されている規格のメンテナンス及びそのTCまたは
SCに割り当てられたすべてのプロジェクトを含める。
備考 これ以降の文章において,“TCまたはSC”という表現は,SCが存在し,また対象プロジェクトがその
SCに規定された業務範囲内のものである場合,すべてSCという意味である。 2.1.5.2 業務計画立案に当たり,各TCまたはSCは,他の機関,例えば,他のTC,TMBの諮問グループ,
政策レベル委員会,またはISO及びIEC以外の機関から出されたISへの要望とともに,分野ごとの計画
についての必要事項を検討しなければならない(2.1.2も参照)。 2.1.5.3 プロジェクトは,TCの合意された業務範囲内のものでなければならない。プロジェクトの選
定については,ISO及びIECの政策目標とリソースに基づいて綿密な調査を行わなければならない(附
属書Cも参照)。 2.1.5.4 業務計画の中の各プロジェクトには番号(ISO/IEC専門業務用指針の各補足指針を参照)を付
し,そのプロジェクトの業務が完了するかまたは廃止されるまで,その番号を保持しなければならない。
さらに,TCまたはSCは,プロジェクト自体の細分化が必要と思われる場合には,その番号も細分化す
21

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
ることができる。細分化した業務は,元のプロジェクトの業務範囲内に完全におさまるものでなければ
ならず,おさまらない場合は,新業務項目として提案しなければならない。 2.1.5.5 業務計画は,該当する場合,各プロジェクトが割り当てられたSC及び/またはWGまたはPTを示さなければならない。 2.1.5.6 新TCで合意された業務計画は,承認のためにTMBに提出されなければならない。 2.1.6 目標期日 TCまたはSCは,その業務計画の各プロジェクトについて,次の各段階完了の目標期日を設定しなけれ
ばならない。
・ 第1次作業原案の完了(NPの起草者から作業文書の概要のみが提出された場合-2.3参照)
・ 第1次CDの回付
・ 照会原案の回付
・ FDISの回付(中央事務局の同意のもとに)
・ ISの発行(中央事務局の同意のもとに) これらの目標期日は,ISを速やかに作成する必要性を考慮して,可能な 短の開発期間に設定するとと
もに,中央事務局に報告されなければならない。中央事務局は,その情報を国代表組織に配布する。目
標期日の設定については,ISO/IEC専門業務用指針の補足指針を参照のこと。 目標期日を設定するに当たっては,プロジェクト間の関係に配慮しなければならない。他のIS履行の基
準となるようなISを開発するためのプロジェクトは,優先的に進められなければならない。国際貿易に
重大な影響があり,またTMBがそのように認知したプロジェクトに対しては, 優先で実施しなければ
ならない。 (業務項目の承認に続き)目標期日を定める際の指針として,次の期限を用いることができる。 ・ 作業原案の提出期限(提案とともに提出されない場合):6か月
・ CDの提出期限:12か月
・ 照会原案の提出期限:24か月
・ 承認原案の提出期限:33か月
・ 発行規格の提出期限:36か月 TMBは,また,関係TCまたはSCの幹事国に対して,入手可能な 新の原案をTS(3.1参照)として発
行するため,中央事務局に提出するよう指示することができる。 すべての目標期日は継続的に見直しを行い,必要に応じて修正し,業務計画の中に明確に示さなければ
ならない。修正した目標期日は,TMBに通知しなければならない。業務計画の中に5年以上あって,承
認段階(2.7参照)に到達しない業務項目は,すべてTMBによって取り消される。
22

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
2.1.7 プロジェクトの運営 TCまたはSC幹事国は,合意された目標期日に対する進捗状況の監視も含め,そのTCまたはSCの業務
計画の中にあるすべてのプロジェクトの運営に責任をもつ。 目標期日(2.1.6参照)が守られない場合及び業務の支援が不十分な場合(すなわち,2.3.5に示す新業
務の受入れ要求事項をもはや満足していない場合),担当委員会はその業務項目を取りやめなければな
らない。 2.1.8 プロジェクトリーダー 各プロジェクトを推進するため,TCまたはSCは,NPの起草者(2.3.4参照)の指名を考慮して,プロ
ジェクトリーダー(WG/PTのコンビナ,指名された専門家または,該当する場合,幹事)を任命しな
ければならない。プロジェクトリーダーには,開発業務を遂行するための適切なリソースの活用が保証
されなければならない。プロジェクトリーダーは,自己の国家的な見地から離れて,純粋に国際的な立
場で活動しなければならない。プロジェクトリーダーは,提案段階から発行段階までに生ずる技術的問
題に関し,必要な場合,コンサルタントとして活動する用意をしておくことが望ましい(2.5~2.8参照)。PT(1.12参照)の場合は,プロジェクトリーダーは,担当委員会に報告を行う。 幹事国は中央事務局に対し,担当プロジェクトを明示してプロジェクトリーダーの氏名及び住所を,通
知しなければはならない。 2.1.9 進捗状況の管理 SC及びWGまたはPTは,そのTCに対して定期的に進捗状況を報告しなければならない(ISO/IEC専門
業務用指針2004年版IEC補足指針の附属書E及びISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の附属書
SLも参照)。関係幹事国間の打合せは進捗状況の管理の支援になる。 中央事務局はすべての業務の進捗状況を監視し,TMBに対して定期的に報告しなければならない。その
ため,中央事務局は,ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の附属書D及びISO/IEC専門業務用
指針2001年版ISO補足指針の附属書SFで指示されている文書のコピーを受け取らなければならない。 2.2 予備段階 2.2.1 TCまたはSCは,次の段階へ進めるには時期尚早の予備業務項目を(例えば,先端的な技術を扱
う問題に対応するため),Pメンバー投票の単純過半数を得たうえで業務計画に導入することができる。 これらの項目には,戦略計画に挙げられた項目,特に2.1.2 d)の先端的ニーズに対する見通しに示され
ているようなものを含むことができる。 2.2.2 予備段階は,目標期日を確定できない業務項目について適用する。 2.2.3 すべての予備業務項目は,委員会で定期的な見直しを行わなければならない。委員会は,それぞ
れの項目に必要なリソースを評価しなければならない。 2.2.4 この予備段階は,NPの推敲(2.3参照)及び初回原案の作成に用いることができる。 2.2.5 作成段階へ進む前に,これらすべての項目は,2.3の手順に従って承認されなければならない。
23

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
2.3 提案段階 2.3.1 NPとは,次に関する提案である。 ・ 新規格
・ 既存規格の新規のパート
・ ISOの場合は,既存規格またはパートの改正
・ ISOの場合は,既存規格またはパートの追補
・ TS(3.1参照),またはPAS(3.2参照)
2.3.2 それぞれの機関において,既存のTCまたはSCの業務範囲内のNPを提出できるのは、以下のも
のである。 ・ 国代表組織
・ 当該のTCまたはSC幹事国
・ 他のTCまたはSC
・ リエゾン機関
・ TMBまたはその諮問グループの一つ
・ 事務総長 2.3.3 ISOとIEC双方のTCが関係する場合,事務総長は必要な調整を行わなければならない(附属書Bも参照)。 2.3.4 NPは適切な書式を用いて提示されるものとし,十分な妥当性を示さなければならない(現行出
版物への追補を除くすべての新業務についてはC.5参照)。 NP の起草者は,次のことを行わなければならない。 ・ できるだけ審議用の第一次作業原案を提出するよう努力する。できない時は,同原案の概要を提示
する
・ プロジェクトリーダーを指名する 完成した書式のコピーは,投票のためにTCまたはSCのPメンバーに,及び参考のためにOメンバーに回
付される。 出版物の入手可能な予定期日を,書式に明記しなければならない。 NPに関する決議は,書面審議もしくはTCまたはSCの会議においてなされる。 NPに関する決議を会議で行う場合は,4.2.1に従って,その提案を議題に加えなければならない。 NP投票は,3か月以内になされるか決議が行われる会議でなされる。 業務への積極的参加に同意したPメンバーは,所定の書式によって専門家を指名しなければならない。 回答用書式に記入する際,国代表組織は附属書Cに示されている原則を検討することが望ましい。
24

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
2.3.5 承認要件は,次のとおりである。 a) プロジェクト開発への積極的な参加表明,すなわち,技術専門家を指名し,作業原案に対するコメ
ントを出すなど,作成段階で効果的な貢献を行うことを表明するPメンバー数について,
- IECの場合,Pメンバーの総数が16以下の委員会ではPメンバー4か国以上,Pメンバーの総数
が17以上の委員会ではPメンバー5か国以上(業務計画の中に業務項目を加えることを承認
[b)参照]しているPメンバーのみがカウントの対象)
- ISOの場合,業務項目を承認しているPメンバー5か国
個々の委員会は,この 低要求人数を引き上げてもよい。かつ,
b) TCまたはSCのPメンバー投票の単純過半数による業務項目の承認 2.3.6 承認されたNPは,適切な優先順位を付けて,新プロジェクトとして当該TCまたはSCの業務計
画に登録され,さらに中央事務局によって登録されなければならない。合意された目標期日(2.1.6参照)は,適切な書式に明示しなければならない。 2.3.7 プロジェクトが業務計画に加えられた時点で,提案段階は終了する。
2.4 作成段階 2.4.1 作成段階では,ISO/IEC専門業務用指針第2部に適合するWDの作成を行う。 2.4.2 新プロジェクトが認められた場合,プロジェクトリーダーは,承認手続き中にPメンバーが指名
した専門家と協力して作業を進める(2.3.5a参照)。 2.4.3 幹事国は,TCまたはSCに対し,会議または書面審議によってWGまたはPTの設置を提案するこ
とができる。通常WGまたはPTのコンビナがプロジェクトリーダーを務める。 WGまたはIECにおけるPTは,TCまたはSCが設置して,そのタスクを定義し,TCまたはSCに原案を提
出する目標期日を設定しなければならない(1.11も参照)。WGまたはPTのコンビナは,委任された作
業が投票で承認された業務項目の範囲内であることを確認しなければならない。 2.4.4 WGまたはIECにおけるPTの設置提案に対して積極的に参加することに同意したPメンバーは
(2.3.5a)参照),それぞれ技術専門家を出さなければならない。他のPメンバー,もしくはカテゴリー
AまたはDリエゾン機関も,専門家を指名することができる。 2.4.5 プロジェクトリーダーは,プロジェクトの推進に関して責任があり,通常,WGまたはPTのすべ
ての会議を召集して,議長を務める。プロジェクトリーダーはWGまたはPTの1人のメンバーに対して
幹事を務めるよう要請できる。 2.4.6 プロジェクト推進の後半の段階で遅れを生じさせないように,英仏両国語版の文書作成のために
あらゆる努力を払わなければならない。 三か国語(英語,仏語,ロシア語)の規格を作成する場合は,本項にロシア語版を含めるものとする。 2.4.7 本段階の期限については,2.1.6を参照のこと。
25

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
2.4.8 作成段階は,作業原案が,第1次CDとしてTCまたはSCのメンバーに対して回付可能になり,中
央事務局がこれを登録した時点で終了する。委員会は,特定の市場ニーズに対応するため, 終作業原
案をPAS (3.2参照)として発行することも決議できる。 2.5 委員会段階 2.5.1 委員会段階は,技術的内容について合意に達するよう,国代表組織からのコメントを検討する重
要な段階である。したがって国代表組織はCDを慎重に検討し,この段階で必要なすべてのコメントを
提出しなければならない。 2.5.2 CDの回付が可能になり次第,回答の 終提出期限を明記して,検討のためにTCまたはSCのす
べてのPメンバー及びOメンバーにCDを回付しなければならない。 国代表組織がコメントするために,3か月の期間を与えること。 コメントは,コメント集が作成できるよう,与えられた説明書に従って送付すること。 会議の前に,国代表組織は,その代表者に自国の立場について要点を伝えておかなければならない。 2.5.3 回答期限終了後,幹事国は4週間以内にコメント集を作成し,それをTCまたはSCのすべてのPメンバー及びOメンバーに回付するように手配しなければならない。コメント集の作成に際して,幹事国
はTCまたはSCの議長及び,必要であれば,プロジェクトリーダーと協議の上,プロジェクトの推進の
ために次のいずれかの提案を行わなければならない。 a) 次回の会議において,CD及びコメントについて審議する。または,
b) 検討のため,改正CDを回付する。または,
c) 照会段階へ進めるため,CDを登録する(2.6参照) b)およびc)の場合,幹事国は,受理された各コメントに対するアクションをコメント集に示さなければ
ならない,このアクションはすべてのPメンバーに利用可能でなければならず,必要に応じて改正コメ
ント集の回付を行うが,遅れないように,委員会検討用に改正CDを提出するのと並行(b)の場合),
または,照会段階への登録のためにCD 終版を中央事務局に提出するのと同時(c)の場合),に行う
ものとする。 回付後2か月以内に2人以上のPメンバーが幹事国提案のb) またはc) に反対した場合,そのCDは会議で
審議されなければならない(4.2.1.3参照)。 2.5.4 CDが会議で検討されても,そこで合意が得られない場合は,その会議での決議事項を取り入れ
たさらに別のCDを,3か月以内に検討のために回付しなければならない。その原案及びその後の版にコ
メントを可能にするために国代表組織には3か月の期間が与えられなければならない。 2.5.5 一連の原案の検討は,TCまたはSCのPメンバーの合意が得られるか,もしくはそのプロジェク
トを取りやめるか延期するかが決議されるまで継続しなければならない。 2.5.6 照会原案(2.6.1参照)を回付することの決議は,合意の原則に則って下さなければならない。
26

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
TCまたはSCの議長は,その委員会の幹事及び,必要であれば,プロジェクトリーダーとの協議の上,
ISO/IEC Guide 2:2004に示されている合意の定義を踏まえた上で,十分な支持があるかどうかを判断す
る責任を負う。
“合意:重要な利害関係者による実質的問題への一貫した反対がないこと,及びすべての関係当事
者の意見を考慮し,意見の不一致を調停させる努力の過程があることを特徴とする全体的合意
備考 合意は,必ずしも満場一致を意味しない。” ISOでは,合意について疑義のある場合,TCまたはSCのPメンバー投票の2/3以上の賛成があれば,CDは照会原案として登録することを承認されたと見なすことができる。しかし,反対票の解決のためのあ
らゆる努力を怠ってはならない。 CDを担当するTCまたはSC幹事国は,会議中のまたは書面審議による決議事項が照会原案に十分に反映
されるよう,確実を期さなければならない。 2.5.7 TCまたはSCで合意が得られた場合,幹事国は,その原案の 終版を,照会用(2.6.1)として国
代表組織に配布できるような電子形式で,中央事務局に(SCの場合はTC幹事国にコピーを)4か月以
内に提出しなければならない。 2.5.8 本段階の期限については,2.1.6を参照のこと。 2.5.9 すべての技術的問題が解決し,CDを照会原案として回付することが承認され,中央事務局によ
って登録された時点で,委員会段階は終了する。ISO/IEC専門業務用指針第2部に適合していない文書は,
修正用として登録前に幹事国へ返送される。 2.5.10 技術的問題が適切な期限内に解決できない場合,TC及びSCは,ISとして合意されるまでTS(3.1参照)の形式で中間刊行物を発行してもよい。 2.6 照会段階 2.6.1 照会段階では,中央事務局から4週間以内に,すべての国代表組織に照会原案(ISOではDIS,IECではCDV)が回付され,5か月投票にかけられなければならない。 言語の使用方針については,附属書Eを参照。 中央事務局は,国代表組織に記入済み投票用紙の中央事務局での受領期限を通知する。 投票期間が終了したら事後処理が迅速に行えるよう,事務総長は受け取ったコメントを添えて,4週間
以内に,TCまたはSCの議長及び幹事国に投票結果を送付しなければならない。 2.6.2 国代表組織が行う投票は,賛成,反対または棄権のいずれかとし,あいまいな点があってはなら
ない。 賛成投票には,編集上または技術的なコメントを添えることができるが,これらのコメントをどう取り
扱うかは,幹事がTCまたはSCの議長及びプロジェクトリーダーと協議して,決定する。
27

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
国代表組織は,照会原案に同意できないと思う場合は反対投票し,その技術的理由を述べなければなら
ない。特定の技術的事項の修正が受け入れられるなら反対票を賛成票に変えることがある旨を表記して
もよいが,修正の受入れを条件として賛成票を投じてはならない。 2.6.3 照会原案は次の場合に承認される。 a) TCまたはSCのPメンバーによる投票の2/3以上が賛成で,かつ
b) 反対が投票総数の1/4以下である。 棄権票は,技術的理由の添えられていない反対票と同様,投票数の集計から除外する。 規定の投票期間が過ぎた後に受け取ったコメントは,TCまたはSCの幹事国に提出されて,そのISの次
回見直しの時点で検討される。 2.6.4 投票結果及びコメントを受領したら,TCまたはSCの議長は,幹事国及びプロジェクトリーダー
と協力して,また中央事務局と協議の上,次ののいずれかの行動を取らなければならない。 a) 2.6.3の承認基準を満たしている場合は,照会原案を修正した形でFDISとして登録する。
b) 照会原案に反対票が投じられなかった場合は,直接,発行を進める。
c) 2.6.3の承認基準を満たしていない場合は,次による。
1) 投票のため,照会原案の改正版を回付する(2.6.1参照)。
備考 改正された照会原案が2か月間投票のために回付されるが,この投票期間は関連委員会の一つまたは複
数のPメンバーの要請によって,5か月まで延長できる。
2) コメント用に改正CDを回付する。 3) 次回の会議で,照会原案とコメントを審議する。
2.6.5 投票期間の終了後3か月以内に,TCまたはSC幹事国は詳細報告書を作成し,中央事務局はこれ
を国代表組織へ回付しなければならない。この報告書は,次のとおりとする。 a) 投票結果を示す
b) TCまたはSCの議長の決定を述べる
c) 受け取ったコメントを記載する
d) 提出されたコメントのそれぞれに,TCまたはSC幹事国の所見を含める 反対票の解決のため,あらゆる試みをしなければならない。 回付後2か月以内に,複数のPメンバーが2.6.4 c.1) またはc.2) にある議長決定に同意しない場合,当該
原案は会議で審議されなければならない(4.2.1.3参照)。 2.6.6 議長が承認段階(2.7参照)または発行段階(2.8参照)へ進める決定を下した場合,TCまたは
SC幹事国は,中央事務局がFDISを作成して回付できるように,投票期間終了後4か月以内に,編集委員
会の支援を得て 終原案を作成し,中央事務局へ送付しなければならない。
28

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
幹事国は,中央事務局に対し,書き換え可能で機械読取り可能な形式で,また書き換え可能な形式の妥
当性検証ができるフォーマットで,提出しなければならない。 ISO/IEC専門業務用指針第2部に適合していない案文は,訂正のため登録前に幹事国へ返送する。 2.6.7 本段階の期限については,2.1.6を参照のこと。 2.6.8 FDISとして原案を回付するため,または2.6.4 b) の場合においてISとして発行するために,中
央事務局が登録した時点で,照会段階は終了する。 2.7 承認段階 2.7.1 承認段階では,中央事務局は,3か月以内に,2か月投票のためにFDISをすべての国代表組織に
回付しなければならない。 中央事務局は,国代表組織に投票用紙の受領期限を通知する。 2.7.2 国代表組織が行う投票は,賛成,反対または棄権のいずれかとし,あいまいな点があってはなら
ない。 賛成票の場合,いかなるコメントも提出してはならない。 国代表組織がFDISに同意できないと思う場合は反対投票を行い,その技術的理由を述べなければなら
ない。修正の受入れを条件として,賛成票を投じてはならない。 2.7.3 次の場合,投票のため回付されたFDISは承認される。 a) TCまたはSCのPメンバーによる投票の2/3以上が賛成で,かつ
b) 反対が投票総数の1/4以下である。 棄権票は,技術的理由の添えられていない反対票と同様,投票数の集計から除外する。 反対投票の際の技術的理由は,そのISの次回の見直しの時点で検討するため,TCまたはSCの幹事国に
提出される。 2.7.4 投票期間終了までに,TCまたはSC幹事国は,これまでの原案作成作業中に生じた誤りについて,
中央事務局に知らせる責任がある。この段階では,それ以上の編集上及び技術的修正は認められない。 2.7.5 投票期間終了後2週間以内に,中央事務局は,投票結果及び国代表組織がIS発行を正式に承認し
たことを,またはFDISを正式に否決したことを示す投票報告書を,すべての国代表組織に回付しなけ
ればならない。 反対票の技術的理由は,単に情報として添付する。 2.7.6 2.7の条件に従ってFDISが承認された場合は,発行段階へ進む(2.8参照)。
29

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
2.7.7 2.7の条件に従ってFDISが承認されなかった場合は,反対票とともに提出された技術的理由を考
慮して再検討するため,その文書を当該TCまたはSCに差し戻さなければならない。 委員会は,次のことを決議できる。 ・ 修正原案を,CD,照会原案,またはISOにおいてはFDISとして再提出する
・ TSを発行する(3.1参照)
・ プロジェクトを取り消す 2.7.8 承認段階は,FDISをISとして発行することが承認されたことを記した投票報告書(2.7.5参照)
の回付,TSの発行(3.1.1.2参照),または文書が委員会に差し戻されたことをもって終了する。 2.8 発行段階 2.8.1 中央事務局は,TCまたはSC幹事国から指摘された誤りについて,ISOでは2か月以内,IECでは
1.5か月以内に修正し,ISを印刷し配布しなければならない。 2.8.2 発行段階は,ISが発行された時点で終了する。 2.9 規格のメンテナンス 規格のメンテナンスのための手順は,ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の第4節及び附属書
B 及びISO/IEC専門業務用指針2001年版ISO補足指針の2.9 に示してある。 2.10 技術的正誤票及び追補 2.10.1 一般 発行済みのISは,次のものを発行することで修正できる。 ・ 技術的正誤票 (または現行版の修正再刷版)
・ 追補 技術的正誤票及び追補は別文書として発行され,それらに対応するISはそのまま刊行が継続される。 2.10.2 技術的正誤票 技術的正誤票は,次のいずれかを修正するために発行される。 a) 原案作成または印刷において不注意から生じたもので,出版物の適用において誤りまたは危険を引
き起こす可能性がある,IS,TS,PASまたはTRの中の技術的な誤りまたはあいまいさ
b) 発行以後に陳腐化した情報で,ただし,修正によって当該規格の技術的規定要素に影響を及ぼさな
いもの(ISO/IEC専門業務用指針第2部2004年版の6.3参照) 備考 技術的正誤票は,例えば,軽微な印刷上の誤りのような,出版物の適用に影響を及ぼさないとみなせ
る誤りを修正するためには発行しない。 技術的な誤りと見なせるものまたは陳腐化した情報については,当該TCまたはSC幹事国に知らせねば
ならない。幹事国と議長は,必要に応じてTCまたはSCのプロジェクトリーダー及びPメンバーと協議
30

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
の上,それが誤りであると確認した場合は,幹事国は誤りを訂正する提案をその必要性の説明とともに,
中央事務局に提出しなければならない。 事務総長は,TCまたはSC幹事国と協議の上,機関に対する財務的影響及び出版物の利用者に対する利
益の双方を勘案して,技術的正誤表を発行するか,現行の出版物を修正または更新した改版を出すかど
うか決定しなければならない(2.10.4参照)。
2.10.3 追補 追補は,既存のISの中ですでに合意されている技術的規定について,変更及び/または追加するもので
ある。 追補の作成及び発行についての手順は,2.3(ISO)またはメンテナンス手順(IEC補足指針参照),及
び2.4から2.8の記述に従うこととする。 その承認段階(2.7)において,事務総長は,TCまたはSC幹事国と協議の上,機関に対する財務的影響
及びISの利用者に対する利益の双方を勘案して,追補を発行するか,その修正を入れたISの新版を出す
かどうか決定しなければならない(2.10.4も参照)。 備考 ISの条項について,頻繁に追加のあることが予想される場合は,これらの追加文を,一連のパートと
して作成するよう考慮することが推奨される(ISO/IEC専門業務用指針第2部参照)。
2.10.4 修正過多の回避 現行のISを修正するために,技術的正誤票または追補の形式で発行する別文書の数は,2点以内とする。
3点目となる場合は,ISの新版を出さなければならない。 2.11 メンテナンス機関 TCまたはSCが,頻繁な修正を必要とする規格を開発した場合はメンテナンス機関が必要であると決議
することができる。メンテナンス機関の指定に関する規則は附属書Gに示す。 2.12 登録機関 TCまたはSCが,登録に関する規定を含む規格を開発した場合は,登録機関が必要である。登録機関の
指定に関する規則は,附属書Hに示す。 2.13 著作権 すべての規格原案,IS及び他の出版物の著作権は,ISOまたはIEC(該当するいずれか)に所属し,中
央事務局が当事者となる。 2.14 特許対象項目の参照(附属書 I も参照) 2.14.1 例外的ではあるが,技術上の理由で妥当性があるなら,特許権 -特許,実用新案,その他の
発明に基づく法的権利として定義され,上記のいずれかに関する開示された出願を含む- の対象とな
る項目の使用を含む条件でISを開発することを,たとえ規格の条項として他に適用される代替手段がな
いような場合でも,原則として妨げるものではない。ISO/IEC専門業務用指針2004年版第2部の附属書Fで定めている規則及び次の項目を適用する。
31

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
2.14.2 技術的な理由から,特許権が適用される項目の使用を含む文書を作成することが妥当である場
合には,次の手順に従わなければならない。
a) 提案文書の起草者は,自らが認識し,提案の項目に関係があると考える特許権について,委員会の
注意を喚起しなければならない。文書の作成に携わる関係者は,文書の作成段階において気付いた
特許権について,委員会の注意を喚起しなければならない。
b) 技術的見地から提案が承認された場合,起草者は,a) に記載したように特定された特許権の所有
者に対して,所有者が合理的かつ非差別的条件に基づいて,全世界の申請者と,所有者の権利に基
づく世界的ライセンスの交渉を進んで行うとする声明書を求めなければならない。このような交渉
は関係者に任され,ISO及び/またはIECの外部で行われる。特許権の所有者の声明書は,適宜,
ISO中央事務局またはIEC中央事務局に登録され,当該文書の序文で引用される(ISO/IEC専門業務
用指針2004年版第2部,F.3参照)。権利の保有者がこのような声明を行わない場合,当該委員会は,
ISO理事会またはIEC評議会のしかるべき承諾なく,特許権の対象項目を規格文書に含めてはなら
ない。
c) 理事会が承認を与えない限り,特定された特許権所有者の声明文を受領するまで,文書を発行して
はならない。 2.14.3 ある文書の発行後に,その文書に記載されている項目に適用されると思われる特許権に基づく
ライセンスが,合理的かつ非差別的条件に基づいて獲得できないことが判明した場合,その文書は当該
委員会での検討のために差し戻される。
3 その他の刊行物の開発 3.1 TS 3.1.1 TSは,次の状況及び条件のもとで作成し,発行することができる。 3.1.1.1 対象のものがまだ開発中であるかまたは他の理由からISの発行に関する合意が将来的には可能
としても,直ちには得られないという場合,TCまたはSCは,2.3に定められている手順に従って,TSの発行が妥当であると決議することができる。このようなTSの作成手順は,2.4及び2.5に規定されてい
るものでなければならない。作成した文書をTSとして発行することを決議するには,TCまたはSCのPメンバー投票の2/3の賛成票を必要とする。TSのまえがきにはこれを発行する理由と国際規格への進展
可能性との関係について説明を記載しなければならない。 TSを“プリスタンダード用”で使用する場合には,適宜次の文章をまえがきに含める。
“この文書は,……の分野における特定の要請に応えるため,規格がどうあるべきかの指針に関
する緊急の必要性から,同分野で“暫定的に適用する規格の前段階のもの”として,(ISO/IEC専
門業務用指針第1部,3.1.1.1に従って)出版物のTSのシリーズで発行するものである。 この文書は,“IS”と見なされない。この文書は,実際の使用に基づく情報及び経験の収集を目的
として,暫定的適用のために提示するものである。この文書の内容に関するコメントは … [ISO中央事務局またはIEC中央事務局]…に送付されたい。
32

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
このTSの見直しは発行後3年以内に行い,さらに3年間延長するか,ISとするか,または廃止する
かが選択される。” IECの場合,TSには,IEC規格と同じメンテナンス手順が適用される。したがって,上記の文章の 後
の段落は,メンテナンスのための見直しの日付に関する適切な情報と置き換える必要がある(ISO/IEC専門業務用指針2008年版IEC補足指針の第4節及び附属書B参照)。 3.1.1.2 FDISが,承認段階(2.7参照)を通過するために必要な支持を得られなかった場合,または合
意について疑義がある場合,TCまたはSCは,Pメンバー投票の2/3の賛成票を得た上で,当該文書をTSの形式で発行するかどうか決議することができる。TSのまえがきには,必要な支持が得られなかった理
由を記載しなければならない。 3.1.2 TCまたはSCのPメンバーがTSの発行に合意した場合,TCまたはSC幹事国は,発行の4か月前ま
でに,機械読取り可能な形式で,仕様書原案を中央事務局に提出しなければならない。 3.1.3 TCまたはSCは,発行後3年以内にTSの見直しを行わなければならない。この見直しの目的は,
TSの発行に至った状況を再検討し,可能であれば,TSに代わるISの発行に必要な合意を得ることにあ
る。IECの場合,この見直しの期日はTSの発行に先立って合意されなければならない(メンテナンスの
ための見直し期日)。 3.2 PAS 3.2.1 PASは完全なISの開発に先立って発行される中間仕様書の場合と,IECの場合の,外部機関と共
同で発行される“二重ロゴ”出版物の場合とがある。これは規格としての要求事項を満たしていない文
書である。 3.2.2 AまたはDリエゾン機関(1.17.2及び1.17.3参照)またはTCまたはSCのPメンバーはPASの提出
を提案できる。 3.2.3 PASは,関連委員会が検証し,また現行ISと矛盾がないことを確認した上で当該委員会のPメン
バー投票の単純過半数で承認を得た後に発行される。 3.2.4 PASは,当初は 長3年間有効である。この有効期限は3年のみ延長でき、その後は改正されて
別のタイプの規範文書となるか,または廃止される。 3.3 技術報告書 3.3.1 TCまたはSCが,普通はISとして発行されるものとは異なる種類のデータ(例えば,国代表組織
で実施された調査データ,他の国際機関の作業に関するデータ,特定のテーマにおける国代表組織の規
格に関する“先端技術”のデータなどが含まれる)を収集した場合,TCまたはSCはPメンバー投票の
単純過半数を得た上で,これらのデータをTRの形式で発行するよう事務総長に要請する決議ができる。
この文書は,元々,全くの参考であり,これが規定であることを示すような内容を含んではならない。
この文書では,そのテーマに関するISで取り扱われるか,または取り扱われるであろうテーマの規定的
33

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
側面との関係を明確に説明しなければならない。事務総長は,必要に応じてTMBと協議の上,その文書
をTRとして発行するかどうかを決定する。 3.3.2 TCまたはSCのPメンバーがTRの発行に関して合意した場合,TCまたはSC幹事国は発行の4か月
前までに,報告書原案を機械読取り形式で事務総長に提出しなければならない。 3.3.3 TRは,担当委員会が定期的に見直して,常に有用性の存在を確認することが望ましい。TRの廃
止は担当TCまたはSCが決定する。
4 会議 4.1 一般 4.1.1 TC及びSCは,業務の遂行に当たって,可能な限り近代的な電子手段(e-mail,グループウェア
及び電話会議)を活用しなければならない。TCまたはSCの会議はCDまたは他の手段では解決ができな
いその他の実質的問題を審議する必要がある場合だけ招集することが望ましい。 4.1.2 TC幹事国は中央事務局と協議の上,業務計画を考慮した少なくとも向う2年間のTCとそのSC,
及び可能ならばWGの会議計画を立案・作成するため,将来の見通しを立てることが望ましい。 4.1.3 会議計画を立てるに当たっては,コミュニケーションを良くし,複数のTCまたはSCへの会議出
席者の負担を軽減させるため,関連テーマを取り扱うTCまたはSCの会議はなるべくグループ化して行
うよう配慮することが望ましい。 4.1.4 会議計画を立てるに当たっては,TCまたはSCの会議終了後直ちに編集委員会の会議を同じ場所
で開催するなどの原案の迅速な作成に利するような考慮が望まれる。 4.2 会議招集の手順 4.2.1 TC 及び SC 会議 4.2.1.1 会議の期日及び場所については当該TCまたはSCの議長及び幹事国,事務総長並びに主催する
国代表組織の間で合意しなければならない。SC会議の場合,SC幹事国は複数の会議の調整を確実に行
うため,まずTC幹事国と協議しなければならない(4.1.3も参照)。 4.2.1.2 特定の会議を主催することを希望する国代表組織は,事務総長及び当該TCまたはSC幹事国と
連絡をとらなければならない。 その国代表組織はまず 初に,TCまたはSCのPメンバーの代表が会議出席の目的でその国に入国する
ことについて,何らの制限も課せられないことを確認しなければならない。 4.2.1.3 幹事国は遅くとも会議の4か月前までに,議題が確実に配布されるよう手配しなければならな
い。IECにおいては,議題は中央事務局によって配布される。ISOにおいては,幹事国が議題を回付し,
コピーを中央事務局に送付する。議題以外のすべての基本文書,例えば,NPなどは,同じ期限内に配
布しなければならない。
34

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
コメント集が会議の6週間前までに配布されたCDのみが議題に取り上げられ,会議での審議対象となる。 会議で審議すべき原案に対するコメント集を含め,他のすべての作業文書は,会議の6週間前までに配
布されなければならない。 4.2.2 WG 会議 4.2.2.1 WGは,可能な限り,近代的な電子手段(例えば,e-mail,グループウェア及び電子会議)を
活用して作業を行わなければならない。会議の開催が必要な場合,WG会議のコンビナは,会議の6週間前までにWG会議の通知をWGメンバー及び親委員会幹事国に送付しなければならない。 会議の手配はコンビナ及び会議開催国のWGメンバーの間で行うものとする。後者は,すべての実務面
の準備に責任を負わなければならない。 4.2.2.2 WG会議が親委員会の会議に合わせて行われる場合,WGのコンビナは親委員会の幹事国と手
配の調整を行わなければならない。特に親委員会の会議に出席する代表者に対して送付される一般的な
会議に関する情報は,WGメンバーにもすべて確実に配布されなければならない。
4.3 会議での使用言語 会議で使用する言語は,英語,仏語及びロシア語とし,会議はこのうちの一言語,もしくは複数の言語
によって行われるものとする。 ロシア連邦の国代表組織はロシア語へのまたはロシア語からのすべての通訳または翻訳を提供する。 議長及び幹事国はISOまたはIECの一般規則に従って,適宜,参加者の同意が得られる方法で会議にお
ける使用言語の問題を処理する責任を負う(附属書Eも参照)。 4.4 会議の取消し 一旦招集された会議が取り消されたり延期されたりすることのないよう,あらゆる努力を払わなければ
ならない。それにもかかわらず,議題及び基本文書が4.2.1.3に定める期限内に間に合わない場合,事務
総長は会議を取り消す権利を有する。 5 異議申し立て 5.1 一般 5.1.1 国代表組織は次の異議申し立ての権利を有する。
a) SCの決議に対して,そのTCへの異議申し立て
b) TCの決議に対して,TMBへの異議申し立て
c) TMBの決議に対して,理事会への異議申し立て
この異議申し立ては対象となる決議が下された後,ISOでは3か月以内,IECでは2か月以内に行う。
いずれの異議申し立ても理事会の決議が 終である。
35

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
5.1.2 TCまたはSCのPメンバーは,TCまたはSCの活動または怠慢に対し,それらが次の場合にあて
はまると考えた場合には,異議申し立てを行うことができる。
a) 次に従っていない。
- 規約及び施行規則
- ISO/IEC専門業務用指針,または,
b) 国際貿易または,安全,健康,環境などの公共的要素にあまり寄与していない。 5.1.3 異議申し立ての対象となる問題は技術的性質のものでも管理的性質のものでもよい。 NP,CD,照会原案及びFDISに関する決議についての異議申し立ては,それが次の事項に当てはまる場
合だけ検討の対象となる。
・ 原則的な問題が含まれている。または
・ 原案の内容がISOまたはIECの評判を損ねる。 5.1.4 異議申し立ては,そのPメンバーの訴えを裏付けるために,すべて文書化しなければならない。 5.2 SC の決議に対する異議申し立て 5.2.1 Pメンバーは,文書化した異議申し立てをTC幹事国に提出し,同時に,そのコピーを事務総長に
送付しなければならない。 5.2.2 TC幹事国は,それを受領した後,すべてのPメンバーに異議申し立ての通知を行い,事務総長と
協議して,書面審議によってまたは会議によって,その異議申し立てを検討し決議するための迅速な処
置を行わなければならない。 5.2.3 TCがそのSCを支持する場合,異議申し立てを起こしたPメンバーは次のいずれかの行動を取る
ことができる。 ・ TCの決議を受諾する。または,
・ それに対し異議申し立てを行う。 5.3 TC の決議に対する異議申し立て 5.3.1 TCの決議に対する異議申し立てには,次の2種類がある。 ・ 上記5.2.3から生じた異議申し立て,または,
・ TCの決議から生じた異議申し立て 5.3.2 いずれの場合においても,文書化した異議申し立てはTCの議長及び幹事国へのコピーと共に事
務総長に提出しなければならない。 5.3.3 事務総長は適切と考える協議を行った上で,異議申し立ての受領後1か月以内に自らの意見とと
もにTMBに委ねなければならない。 5.3.4 TMBは異議申し立てに関し,処理すべきかどうか決議をしなければならない。処理継続の決議
がなされた場合,TMB議長は調停委員会を設置しなければならない。 調停委員会は3か月以内にこの異議申し立てを聴取し,できるだけ早く意見の相違の解決を図るものと
する。調停委員会は,3か月以内に 終報告書を作成しなければならない。意見の不一致を解決できな
36

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
かった場合,調停委員会はその問題解決のための勧告とともに,その旨を事務総長に報告する。 5.3.5 調停委員会の報告書を受け取った事務総長は,TMBにこれを通知するものとし,TMBは,それ
について決議する。 5.4 TMB の決議に対する異議申し立て TMBの決議に対する異議申し立ては,その件の全段階に関する文書をすべて添えて事務総長に提出しな
ければならない。 事務総長は異議申し立ての受領後1か月以内に,自らの意見とともに理事会メンバーに委ねなければな
らない。 理事会は3か月以内に決議しなければならない。 5.5 異議申し立て期間中の業務の進行 異議申し立てが進行中の業務に関する決議に対して行われた場合,その業務は承認段階まで続行されな
ければならない(2.7参照)。
37

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書A (規定)
ガイド
A.1 序文 TCが開発するIS,TS,PAS及びTRのほかに,ISO及びIECは国際標準化に関するガイドを発行する。ガ
イドは,ISO/IEC専門業務用指針第2部に従って原案が作成される。 TC及びSCはガイドを作成してはならない。ガイドを作成できるのはISO政策開発委員会,IEC諮問委員
会,ISO専門諮問グループまたはISO/IEC合同専門諮問グループである。以下,これらの組織を“プロ
ジェクト担当委員会またはグループ”と呼ぶ。 次に,ガイドの作成及び発行の手順について述べる。
A.2 提案段階 新業務項目を提案する方法及びそれらを承認する基準は,プロジェクト担当委員会またはグループが報
告する組織によって定められる。 プロジェクトが承認されたら,プロジェクト担当委員会またはグループの幹事国は,ISO及びIEC内の
適切な利害関係者に対する情報提供を確実に行わなければならない。
A.3 作成段階 プロジェクト担当委員会またはグループは,ISO及びIEC内の適切な利害関係者が作業原案の作成に代
表者を関与させることができるようにしなければならない。
A.4 委員会段階 作業原案が回付用CDとなり次第,プロジェクト担当委員会またはグループの幹事は,委員会またはグ
ループのメンバーのコメントを求めて回付するための手配を行わなければならない。 通常,回答期限は3か月とする。 プロジェクト担当委員会またはグループは受領したコメントを検討して,ガイドの改正案の作成に着手
しなければならない。
A.5 照会段階 A.5.1 中央事務局は 4 か月投票に付すため,改正ガイド案の英語版と仏語版の両方をすべての国代表
組織へ回付しなければならない。 A.5.2 ガイド案は、投票総数の内、反対票が 1/4 以下ならガイドとして発行が承認され,この場合,
棄権は投票数として数えない。
38

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
ISO/IEC ガイドの場合は原案を ISO 及び IEC の国代表組織に承認のために提出する。文書を ISO/IECガイドとして発行するためには,両機関の国代表組織の承認が必要である。 この条件が ISO または IEC のいずれか一方だけでしか満たされない場合,プロジェクト担当委員会ま
たはグループが A.5.3 に規定する手順を適用しない限り,このガイドは承認した機関のみの名前で発行
することができる。 A.5.3 ガイドが承認されないか,または合意を高めうるようなコメント付きで承認された場合,プロ
ジェクト担当委員会またはグループの議長は,修正案を提出して 2 か月投票に付すことができる。修正
案の承認条件は,A.5.2 と同じである。
A.6 発行段階 発行段階は,プロジェクト担当委員会またはグループが所属する機関の中央事務局が責任をもつ。 合同 ISO/IEC グループの場合の責任は,両機関の事務総長の合意によって決定されなければならない。
A.7 ガイドの廃止 当該ガイドの担当委員会またはグループは,ガイドを廃止するかどうかの決定について責任を負わなけ
ればならない。正式には,通常の手順に従って,TMBの承認によって廃止される。
39

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書B (規定)
リエゾン及び業務割当てに関するISO/IEC手順
B.1 序文 1976年のISO/IEC協定 (ISO/IEC Agreement of 19762))により,ISOとIECは全面的に国際標準化の協
調体制をとることとなった。この体制を効果的に運用させるため,両機関のTC,SC間における調整及
び業務割当てのための手順が次のとおり合意された。
B.2 一般概念 ISOとIECの間の業務割当ては,電気及び電子技術分野の国際標準化に関するすべての問題はIECが担当
し,その他の問題はすべてISOが担当するという合意原則に基づいており,さらに,電気及び非電気の
いずれの技術に関与するのかがにわかに判明しない場合の国際標準化の問題については,両機関の相互
の合意によって,その責任の割当てを定めることとなっている。 新たなISOまたはIECのTCが設置される場合や,または既存のTCが行っている活動の結果として調整及
び業務割当ての問題が生じてくることもある。 調整及び業務割当てに関しては,次のレベルが定められている。問題の解決に際しては,低いレベルか
ら始めて,あらゆる試みを尽くしてもうまくいかない場合にだけ,次の高いレベルに上げることが望ま
しい。 a) 正式リエゾン 通常の委員会間の協力として,ISOとIECの委員会間で行われる。
b) 機関間の協議 技術専門家及び事務総長代理を含めたもので,技術的調整が問題とされている点だけにとどまらず,
より広い範囲において将来の両機関の活動に影響を及ぼしうる場合に行われる。
c) 業務割当てについての決定 - TMBによるか,または必要なら - JTABによる
ISOとIECの双方に影響が及ぶ問題で,ISO/TMBとIEC/SMBの共同決議が得られることが明らかでない
ものについては,JTABに決定を委ねる(1.3.1参照)。
B.3 新 TC の設置 新TCの設置をISOまたはIECいずれかの国代表組織に提案する場合は,その提案は必ず,コメント及び
/または合意を得るために,もう一方の機関にも提出しなければならない。そこで行われる協議の結果
として次の二つの場合が生じうる。 a) その業務は,いずれか一方の機関が取り扱うのがよいとして意見が一致する。
b) 意見が別れる。
2) ISO決議 49/1976 及び 50/1976,及びIEC事務連絡文書 13/1977
40

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
a) の場合は,一致した意見に従い,新TCを設置するための正式な措置をとってよい。
b) の場合は,専門業務の割当てについて(すなわち機関レベルにおいて)満足のいく合意が得られる
よう,両事務総長の代理が出席する当該分野の専門家による会議が用意されることになる。このレベル
で合意に達すれば適切な機関によって実施のための正式な措置が取られる。 万一,これらの協議を経ても合意に達しない場合,いずれかの機関から,その問題の決定をJTABに委
ねることができる。
B.4 ISO 及び IEC の TC 間の調整及び業務割当て B.4.1 TC レベルにおける正式リエゾン ISOとIECの委員会間において生じる必要な調整のほとんどは,正式な技術的リエゾンの設定を通じて
円滑に進められる。こうしたリエゾンの設定は,一方の機関から出された要請に対し,もう一方の機関
の承認を得て行わなければならない。正式リエゾンの要請は,中央事務局によって統括される。リエゾ
ンを要請する機関は,リエゾンの形態を明示しなければならない。その形態は,次のようなものである。
a) 委員会文書のすべて,または抜粋の交換
b) リエゾン代表者の常時,または選択的な会議への出席
c) ISO または IEC の特定 TC に対する常設調整(運営)委員会への参加
d) JWG の設置 B.4.2 協定内容 B.4.2.1 作業領域をどちらかの機関に委任することでIECとISO間の重複分野を極力減らすための努力
を継続しなければならない。 このように委任された作業領域については,IEC及びISOは,それぞれ他方の機関の見解及び利益を十
分考慮するためにどうすべきかについて,JTABを通じて合意しなければならない。 B.4.2.2 共同作業については,五つの作業形態が制定されている。
形態1 –情報提供関係
ある特定の作業領域を一方の機関に完全に委託し,他方の機関はその進捗状況のすべてについて報
告を受ける。
形態2 – 貢献的な関係
一方の機関が作業を主導し,他方はその作業の進捗過程の適切と思われる場面で書面によって関与
する。すべての情報の交換も含まれる。
形態3 – 部分委託関係
特定された作業項目に関して,一方の機関に全作業が委託されるが,他方の機関の専門性により,
作業の一部が委託され,その責任下で行われる。その場合委託された作業の成果が計画の主要部分
に入れられるように必要な調整を行わなければならない。従って照会段階及び承認段階は,その標
準化タスクの主要作業を行う機関が担当する。
形態4 – 協力関係
一方の機関がその活動を主導するが,ワークセッション及び会議には,この機関との技術的リエゾ
ンを持つ他方の機関からの代表者をオブザーバとして迎える。このような代表者は,討議に参加す
41

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
る権利は有するが投票権は持たない。すべての情報提供は,このリエゾンを通じて行われる。
形態5 – 一体化したリエゾン
両機関のJWG及び合同専門委員会が,完全な平等参加の原則のもとに,規格実現に向けて協力し
て作業を行うための一体化した会議を開催する。
これら両機関の専門委員会によるJWGは1.11.5に従って作業を遂行しなければならない。 B.4.2.3 重複する可能性のある領域におけるIECとISOとの間の作業の分担は,関係者の合意を得て本
協定の追補として作られるスケジュールまたはプログラムの要求事項に従って設定される。 本協定によって,関係者は各々に有効な関連分野において,相手の関連規格の相互参照に同意する。 参照規格が更新されるとき,参照先の文書を適宜更新するのは,参照を行った組織の責任とする。 B.4.2.4 一方の機関が担当し,他方の機関に一部を委託するような作業がある場合は,その作業の目的
の決定に際して,委託された作業への参加者の利害関係が十分考慮されなければならない。 B.4.2.5 照会及び承認に必要な手順は,両機関のTMBがその他のやり方を承認しない限り,ある特定
の標準化タスクを委託された機関が行わなければならない。 B.4.2.6 形態5–一体化したリエゾンで開発される規格は,委員会段階、照会段階、承認段階がISOと
IECで並行して実行されなければならない。プロジェクトに運営責任をもつ委員会/機関は,回付日の2週間前に,他の機関にCD,照会原案,FDISを提出しなければならない。 B.4.2.7 照会原案が機関の一つで承認基準(2.6.3参照)を満たさなかったとき, ・ JWGに含まれる委員会の役員は2.6.4で与えられる選択肢の一つを選ぶことができる,または, ・ 例外的状況として,JWGに含まれるISO及びIECの委員会の役員と中央事務局が合意すれば,照会
原案が承認された機関のシングルロゴでプロジェクトを進めることができる。JWGは自動的に解散
となる。 B.4.2.8 もし,FDISが2.7.3の条件に従って承認されなかったとき, ・ IECでは第2次FDISの回付は認められていないこと及びTMBに適用除外を求めることに留意して,
JWGに含まれる委員会は2.7.7で与えられる選択肢の一つを選ぶことができる,または、 ・ 例外的状況として,JWGに含まれるISO及びIEC委員会の役員と中央事務局が合意すれば, FDIS
が承認された機関のシングルロゴでプロジェクトを進めることができる。JWGは自動的に解散とな
る。 B.4.2.9 ISOとIECのJWGを通じた形態5–一体化したリエゾンで開発される規格は,運営責任をもつ委
員会の機関により発行される。その機関は規格に参照番号を割り当て,著作権を所有する。規格には他
機関のロゴが付けられ,両機関で販売することができる。国際規格のまえがきで,開発に責任を負うす
べての委員会が特定される。運営責任をもつ委員会がIECの場合,規格のまえがきにISOの投票結果も
も記載される。ISOとIECで幾つかのパートに責任を持ち合うマルチパート規格の場合,80000シリーズ
番号が割り当てられる(例えばISO 80000-1,IEC 80000-2)
42

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
B.4.2.10 形態5–一体化したリエゾンで開発された規格のメンテナンスには,運営責任がある委員会を
もつ機関で現在適用されているメンテナンス手順が用いられる。 B.4.2.11 プロジェクトの進捗過程において,ある運用形態から別の形態へ変更する必要が生じたとき,
情報を与えるために,両組織の関連専門委員会は両TMBに勧告を行わなければならない。 B.4.3 幹事国間の協力 この協定の実施については,両機関のTC/SC幹事国は互いに協力しなければならない。規定の手順に従
って進捗中の作業に関する十分な情報交換及び必要な作業文書の相互利用を可能にしなければならない。
43

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書C (規定)
規格制定提案の妥当性
C.1 一般 C.1.1 標準化活動にはかなりの財源と人材がかかわりあい,また,それらをニーズによって割り当て
ていく必要性があるため,まずニーズを特定し,作成する規格のねらい,影響を受ける可能性のある利
害関係者を決定するところから始めることが重要である。そうすることにより,開発された規格が要求
された側面を適切な形で含むことが保証されるのである。したがって,新しい活動は合理的に妥当性を
評価されてから着手されなければならない。 C.1.2 本附属書に基づいてどのような結論が出されようとも,新業務を開始するには,十分な数の関
係者が必要な人材,資金を提供し,また作業へ積極的に参加する意志を明確に表明していることが必要
条件となっている。 C.1.3 本附属書は新業務の提案及び妥当性評価のための規則であり,関係する団体によって標準化の
ためのリソースが提供されて, も効果的に使われることを保証するため,提案の目的及び業務の範囲
について,できる限り明確な考えを他者に提供することを意図している。 C.1.4 本附属書は,ここに述べている指針の実施及び監視のための手続き規則も,そのために設置す
べき管理的機構も扱ってはいない。 C.1.5 本附属書は,主として,国際標準化の分野で使用されることを意図したものであるが,他の分
野においても使用することができる。 C.1.6 この附属書は,主として,これから着手されるあらゆる種類の新業務の提案者のために書かれ
たものであるが,それらの提案を分析したり,それに対してコメントする人たちや,また,それらの提
案について決議する組織がツールとして使用することもできる。
C.2 定義 C.2.1 新業務の提案 専門活動の新分野または新業務項目に関する提案 C.2.2 専門活動の新分野の提案 提案を受けたその機関の既存の委員会(専門委員会など)が網羅していない分野の規格作成の提案 C.2.3 NP 提案を受けたその機関の既存の委員会(専門委員会のような)が取り扱っている分野の規格または一連
の関連規格作成に関する提案
C.3 一般原則 C.3.1 すべての新業務の提案は,それが提出された機関の業務範囲内になければならない。
44

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
備考 例えば,ISOの目的はISO会則第2.1条に,IECの目的はIEC規約第2条に述べられている。 C.3.2 すべての新業務提案は,業務の必要性を評価し,正当化するため,(少なくとも)次の要素を含
めなければない。
・ タイトル
・ 適用範囲
・ 目的及び妥当性
・ 業務計画
・ 必要となるリソース
・ 関連文書
・ 協力及びリエゾン
C.3.3 C.3.2 に列記した要素は,専門活動の新分野(新委員会の提案)及び新業務項目(既存の委員会
における新規格提案)を扱う場合には,多少,解釈が異なる可能性がある。それらの内容については,
C.4 及び C.5 でさらに詳しく説明する。こうした提案の例については,C.7 及び C.8 に挙げた。(原則的
項目を例示するため,かなり詳しく記述している)。
C.4 専門活動の新分野(新委員会)提案のときに明確にしなければならない要素
C.4.1 タイトル
タイトルは,当該の提案が取り扱う専門活動の分野を,明確かつ簡潔に表すものでなければならない。
例:“工作機械”
C.4.2 業務範囲
C.4.2.1 業務範囲は,活動分野の限界を明確に示すものでなければならない。業務範囲は,当該機関の
業務の一般的目的及び原則を繰り返し述べるのではなく,関係する特定の分野を示すものでなければな
らない。 例:“金属,木材及びプラスチックの加工に用いる,材料の除去操作または圧力操作を行うすべての工作機械の標準化”
C.4.2.2 外見上同様のまたは関連の業務が一方の機関の他の委員会の業務範囲,または他方の機関にす
でにある場合,提案された業務範囲はその業務と他の業務との区別がつけられるものでなければならな
い。 C.4.2.3 提案者は,その提案を業務範囲を広げることによって既存の委員会で扱うのがいいのか,また
は新委員会を設置することによって扱うのがいいのかを示さなければならない。 C.4.3 目的及び妥当性
可能な限り,次の要素についての厳密な検討に基づいた詳細事項を示さなければならない。
a) 特に対象となる標準化の側面,解決しなければならない問題または克服しなければならない困難に
焦点を当てた,標準化活動の特定のねらい及び理由
b) 産業界,顧客,市場,政府,配送業者など,その活動から利益を受けるか,または影響を受ける主
な関係者
c) 活動実施の可能性:首尾よい規格の制定,または一般的な適用を妨げる要因はあるか?
45

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
例:一般的な使用のために単一のやり方を標準化する方がよいか,または二つ以上のやり方または水準を標準化する方が
実際的だと思われるか。
d) 開発する規格のタイミング:技術が適度に安定しているか。安定していないのなら,提案された規
格が技術の進歩によって時代遅れとなるまでにどのくらい時間があるのか。当該技術の今後の進展
の基盤になるものとして,その規格は必要とされているのか
e) 他の分野または機関でのニーズを検討した上での活動の緊急性はどうか
f) 提案された規格の実施によって得られる利益,または妥当な期間内に規格が制定されなかった場合
の損失または損害は何か。製品量または貿易額のようなデータが含まれ,数値が明示されていなれ
ばならない
g) その標準化活動が法規制の対象となるか,または既存の法規制との整合を必要とするか,もしくは
その可能性がある場合は,そのことを述べるのが望ましい
C.4.4 業務計画 C.4.4.1 業務計画の提案は,標準化活動のねらいに対応し,それを明確に反映しなければならず,した
がって提案されたテーマとの関係を示したものでなければならない。 C.4.4.2 業務計画の各項目は,規格化されるテーマと側面によって定義されなければならない(例えば,
製品の場合,項目は製品の種類,特性,他の要件,供給されるべきデータ,試験方法等となる)。 C.4.4.3 業務計画の特定の項目に,補足的な妥当性を組み込んでもよい。 C.4.4.4 提案する業務計画では,優先順位及び目標期日も述べなければならない。 C.4.5 関連文書 C.4.5.1 その出典にかかわらず,知る限りの関連文書(規格及び法規制など)を列挙しなければならな
い。 C.4.5.2 文書一覧にそれぞれの有意性を示すことができれば,有益となる場合が多い。 C.4.5.3 既存の定着した文書を(修正を加えて,または加えないで)規格として受け入れることができ
ると提案者が認めるきは,適切な妥当性と共にコピーを提案に添付して示さなければならない。 C.4.6 協力及びリエゾン C.4.6.1 協力及びリエゾン関係を持つことが望ましい関連機関または組織名を列挙しなければならない。 C.4.6.2 他の組織との競合するまたは重複する作業を回避するため,競合するまたは重複の可能性のあ
るすべての点を示すことが重要である。 C.4.6.3 他の利害関係組織とのすべての話し合いの結果も含まなければならない。 C.4.7 幹事国の責務 提案者は,自己の所属機関が,提案した新活動分野で必要な幹事国業務を引き受ける用意があるかどう
かについて示さなければならない。
46

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
C.5 新業務項目(新規格)の提案に際して明確にすべき要素
C.5.1 タイトル
タイトルは,提案する新規格のテーマを示すものでなければならない。 例:電子製品-環境試験の基本手順
C.5.2 適用範囲(及び適用分野) 適用範囲には,提案する新業務項目が取り扱う範囲を明示し,更に明確にする必要があれば,除外事項
を記述する。 例:この規格は,予想される使用条件における電子製品の性能を評価するための,一連の環境試験手順及びその厳しさの
程度について規定する。 この規格は,主として,このような適用を意図したものであるが,希望する場合は他の分野においても使用してよい。
個々のタイプの供試品に特有の他の環境試験は,関連仕様書に含めてもよい。
C.5.3 目的及び妥当性
C.5.3.1 C.4.3 で要求されているように,作成する規格の目的及び妥当性を提示して,規格に含めるべ
き各側面(特性など)の標準化のニーズの妥当性を示さなければならない。提案者は,自己の知る限り
では,提案のテーマを扱った他の作業がないという旨の記述を含めなければならない。 C.5.3.2 共通の目的及び妥当性を持つ一連の新業務項目が提案された場合は,明確にしなければならな
い要素を含め,それぞれの項目のタイトル及び適用範囲を列挙した共通提案を起草してもよい。 C.5.4 業務計画
目標期日を示し,また一連のシリーズ規格が提案されたときには優先順位を示さなければならない。
C.5.5 関連文書 C.4.5 参照
C.5.6 協力及びリエゾン
C.4.6 参照
C.5.7 作成作業
提案者は自らまたは自らが所属する機関が新業務項目に必要な作成作業を引き受ける用意があるかどう
かを示さなければならない。提案者は提案と一緒に完成した作業原案を提出するよう出来る限り尽力す
るか,または少なくとも,その概要を提出しなければならない。提案者は,同時にプロジェクトリーダ
ーを指名しなければならない。
C.6 マトリックス
C.6.1 提案者が考えを理解しやすい語句でまとめるために,C.9 にあるマトリックスは,提案の目的及
びそれに相応して対象とする側面を設定するのに役立つ。
47

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
提案者は,提案する新業務の主な目的を縦軸上で特定することが望ましい。 も関係のある側面は,適
切な目的の欄に特定されるようにする。 C.6.2 完成したマトリックスのコピーは,提案に添付することを推奨する。 各特性及び各試験方法は専用の欄が必要になる場合があり,C.9 のマトリックスは,あくまでもモデル
として考えることが望ましい。マトリックスは新業務の提案の評価に役立てることができる。 C.6.3 あるテーマについては,マトリックスを非常に早い段階で使用することができる。別のテーマ
については委員会の業務計画の設定と並行して,またあらゆる場面で適宜修正してもよい。その他の場
合(特に複合製品については)はマトリックスにある質問事項への回答が作業の進展を待たないと出て
こない可能性がある。そのような場合でも,できるだけ早いうちに適切なマトリックスを作成すると役
立つことがある。これは,そうしなければ気づかずにいたかもしれないギャップまたは矛盾が明るみに
でてくる可能性があるからである。 C.6.4 マトリックスの使用例を,C.10 及び C.11 に示す。
C.7 専門活動の新分野提案例
提案者:スロボビア国家規格協会(SNSI)- スロボビア3)のISO会員団体 タイトル:“工作機械” 業務範囲:
“金属,木材及びプラスチックの加工に用いる,材料除去または圧力で作動するすべての工作機械
の標準化。除外事項:工作機械に使用される電気機器の標準化(IEC/TC 44が担当)”
目的及び妥当性: ここに提案する標準化の目的は,工作機械そのもの及び関連工具,設備に関連する主な特性,イン
タフェース,互換性,操作要素,操作記号,安全装置,正確さ,試験,などについての国家仕様と
要求事項の整合化を促進することにある。 国際貿易においては,工作機械そのものだけではなく,半製品の部品に関しても,異なる国々で有
効とされている技術的要求事項の相違によって,とりわけ附属品の互換性とともに安全に関する要
求事項,試験の正確さに関する相違によって問題が生じている。 ここに提案する規格によって利益を得ると予測される主な関係者は,工作機械製造業者,工作機械
ユーザ,工具製造業者及び工作機械部品及び附属品の製造専業メーカである。また,工作機械を操
作する作業者も操作要素及び記号の統一によって利益を得ると思われる。 工作機械の国際貿易は急速に拡大し続けており,工業国はますます多くの機械を輸出している4)。
しかしながら,ときおり,異なる法規制要件が原因の貿易障壁に遭遇する産業も存在する。 いくつかの国における輸出量の減少の理由の一つは,これらの障壁であり,このような障壁は国際
標準化によって排除または削減できるものである。
3) 想像上の国を例とする。 4) この点を例証するため,提案者は表,グラフ,統計または他の補足資料を添付することが望ましい。
48

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
この活動の実現性は,上記の事実から明らかである。しかしながら,この国際標準化が遅れれば遅れる
ほど,国家仕様との整合化は困難になることだろう。この標準化を行っている国際機関は他になく,し
たがって,この作業は急を要する。 工作機械の設計及び技術は安定しているため,ここに提案する標準化はタイムリーなものである。それ
でも,新機種の生産や新制御システムなど今後の進展は速い。図からもわかるように世界中におけるこ
れら製品の需要は現在の世界的な供給能力よりも大きいのである。
工作機械の受注及び出荷(単位百万ドル)
出荷
受注
(百万ドル) 11月度予測 10月度実績 昨年11月度
継続受注,合計
切削
成形
出荷,合計
切削
成形
輸出
出荷
在庫,切削
成形
キャンセル,切削
成形 国内受注,3か月 移動平均
切削
成形 資料:全国工作機械製造者連合
図C.1-工作機械の受注及び出荷
49

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
得られる利益:標準化された部品及びユニットの専業生産及び経済的交易,国際協力と貿易,輸入業者
の安全要求事項への適合,簡易で安全な取扱いと操作。5)
業務計画案:
必要規格のリスト タスク完了ま
での 予定期間
年 1 工作機械 - 速度及び送り 2 工作機械試験コード 3 工作機械上に表示する記号 4 工作機械 - 制御装置の操作方向 5 工作機械 - 主軸端及び面板 - 互換性を得るためのサイズ – パート1:タイプA 6 工作機械 - 主軸端及び面板 - 互換性を得るためのサイズ – パート2:カム止めタイプ 7 工作機械 - 主軸端及び面板 - 互換性を得るためのサイズ – パート3:差込みタイプ 8 縦形研削といしスピンドル形及び角テーブル形平面研削盤の試験条件 - 精度の試験 9 水平研削といしスピンドル形及び角テーブル形平面研削盤の試験条件 - 精度の試験
3 3 4 5 5 5 5 6 6
備考 このリストは作業の進捗に応じて,適宜見直して補足することが望ましい。
関連文書: 入手可能な国家文書
・フランス NF E 60-101,-102,-105,-111,-112,-115,-116,-117,-121,-122,-123,-124,-131,-132
・日本 JIS B 6330-74,6331-74,6332-77,6333-77,6334-77
・チェコ共和国 CSN 20 0301,20 0312,20 0315,20 0316,20 0318
・ポーランド PN-M-55330,55331,55332,55340,55350,55351,55356
・アメリカ NAS 913,938,953,972,979,983,985 われわれは,NAS 979,均一切削試験。金属切削機器仕様を,ISO規格として採用できると考える。 協力及びリエゾン: 工作機械に使用される電気機器を扱うIEC/TC 44との間で,リエゾンが確立されることが望ましい。 幹事国の責務: スロボビア国家規格協会(SNSI)は,提案された委員会の幹事国業務を引き受ける用意がある。 1996年11月5日 D. Prath Director スロボビア国家規格協会
5) 世界の工作機械の生産及び貿易に関する補足資料を提示するのが望ましい。
50

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
C.8 新業務項目の提案例 提案者:スロボビア国家規格協会(SNSI)- スロボビア
6)のISO会員団体
タイトル:“工作機械-主軸端及び面板-互換性を得るためのサイズ” 適用範囲:
この規格は,工作機械の主軸端とそれに対応する面板に互換性を持たせるための寸法について規定するもの
であり,接続面の位置公差とともに寸法公差と形状公差を含む。 目的及び妥当性:
この規格の目的は,工具及び工具ホルダ用に対する工作機械の接続部品としての主軸端及び面板の標準化さ
れた選択法を規定することにある。 鋳造品及び鍛造品の半製品を扱うスロボビアの輸出入業者は,様々な国における主軸端の寸法の差異によっ
てかなりの困難に遭遇してきた。この提案した業務を行うことにより,これらの問題が減少することが予測
される。 ここに提案する規格によって利益を得ると予測される主な関係者は,工作機械製造業者,工作機械ユーザ,
工具製造業者及び工作機械の部品及び附属品の専業メーカである。 工作機械と工具の国際貿易は急速に増え続けている。主軸端及び面板が標準化されたことにより各種の機械
における標準工具の利用を促進することになると思われる。また機械操作がさらに柔軟性のあるものになる。 長年にわたる実績に基づき,いわゆる“Aタイプ”,“カム止めタイプ”,“差込みタイプ”の3種の型の使用は
一般的に受け入れられてきているので,ここに提案される規格の作成は実施可能でタイムリーである。これ
らの3種の型は,安定しており,性能も優れている。主軸端の管理された多様性を確立するために,これらの
型の標準化を提案する。必要であれば,規格は3つのパート構成で発行することもできる。 タスク完了までの期間:3年 得られる利益:さまざまな企業が出荷する工作機械の主軸端の統一は,工作機械ユーザに同じ標準化された
工具セットの異なる工作機械における使用を可能にする。 工具を生産する専門工場で,標準化された工具が生産できる可能性。工作機械及び工具の国際貿易。工具の
互換性。 関連文書:
入手可能な国家文書:
- イギリス: BS 4442 - アメリカ: ANSI b 5.9 - ドイツ: DIN 55021 協力及びリエゾン:
工具の標準化を扱うISO/TC 29との間で,リエゾンが確立されることが望ましい。 作成作業:
SNSIは,作成作業を引き受ける意思がある。 1996年11月20日 D.Prath Director スロボビア国家規格協会
6) 想像上の国を例とする。
51

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
C.9 提案目的の設定のためのマトリックス タイトル:
規格が対象とする側面
提案する新業務の目的
専門用語
,図記
号,信号
表示
特性
サンプリ
ング
試験,検
査
補足要求
事項
(ラベリ
ング,
パッケー
ジング,
貯蔵他
)
文書,例
えば製
品に添付
する
その他の
側面,
要求事項
相互理解及びコミュニケーション
安全,電磁両立性,健康,環境保護
互換性の達成,インタフェースまたは 両立性の規定
性能,機能,品質
エネルギー及び原材料の経済性
多様性の管理(合理化)
消費者保護
その他
52

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
C.10 専門活動の新分野提案の目的設定のためのマトリックス例 タイトル:工作機械
規格が対象とする側面
特性
(下記参
照)
提案する新業務の目的
専門用語
a) b) c)
精度試験
工作機械
上の図
記号
モジュラ
ーユニ
ット
潤滑油
相互理解及びコミュニケーション
安全,電磁両立性,健康,環境保護 X
X
X
互換性の達成,インタフェースまたは 両立性の規定
X
X
性能,機能,品質
X
X
エネルギー及び原材料の経済性
X
X
X
X
多様性の管理(合理化)
消費者保護
X
その他
諸元:
a) 内部全高
b) 速度及び送り
- シャンクのサイズ
- Tスロット及び対応ボルトのサイズ
- 研削といしのサイズ
- 主軸端のサイズ
- 施盤センタのサイズ
c) 研削といしの据付け
- 制御装置の操作方向
53

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
C.11 NP の目的設定のためのマトリックス例 タイトル:工作機械:主軸端及び面板 - 互換性を得るためのサイズ
規格が対象とする側面 提案する新業務の目的
専門用語
,図記
号,信
号、
表示
寸法,公
差,互
換性
サンプリ
ング
試験,検
査
補足要求
事項
(ラベリ
ング,
パッケー
ジング,
貯蔵他
)
文書,例
えば製
品に添付
する
その他の
側面,
要求事項
相互理解及びコミュニケーション
安全,電磁両立性,健康,環境保護
互換性の達成,インタフェースまたは 両立性の規定
X
X
性能,機能,品質
エネルギー及び原材料の経済性
多様性の管理(合理化)
X
消費者保護
その他
54

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書D (規定)
幹事国のリソース及び幹事の資格
D.1 定義 D.1.1 幹事国 相互の合意に基づき,TC または SC に対する技術的及び管理的責務を割り当てられた国代表組織 D.1.2 幹事 技術的及び管理的任務を運営するために幹事国によって任命された個人
D.2 幹事国のリソース 幹事国に指定された国代表組織は,必要な業務を行うためにその国内においてどのような方策を取ろう
とも, 終的に幹事国として適切に機能することの責任は,その組織自身にあるということを認識しな
ければならない。幹事国機能を引き受ける国代表組織は,適宜 ISO 役務協定または IEC 基本協定の当
事者となる。 そのため,幹事国は次のことが確実になされるための十分な管理的及び財政的手段またはその裏付けを
持たなければならない。 a) 機械読取り可能な文書の提供及び文書の複製のための英語及び/または仏語の文書作成機能
b) 適切な技術図面の作成
c) 公用語で受領した文書の,必要ならば翻訳をした上で,識別と使用
d) 委員会及びその附属組織の構成の更新と継続的管理
e) 通信と文書の受領及び迅速な発信
f) 電話,ファックス及び電子メールによる適切な通信機能
g) インターネットへのアクセス
h) 主催国代表組織との協力による必要に応じた会議中の翻訳,通訳及びその他の任務に関わる手配と
設備
i) TC及び/またはSC,編集委員会,WG会議を含む幹事の出席が必要とされるすべての会議への幹
事の出席及び必要ならば議長との協議
j) 基本IS(ISO/IEC専門業務用指針第2部の附属書B参照)及び検討中の分野におけるIS,国家規格及
び/または関連文書への幹事によるアクセス
k) 必要な場合,当該委員会の技術的問題についてのアドバイス能力を持つ専門家への幹事によるアク
セス
事務総長はTCの初回の会議,新幹事国によるTC会議及び問題解決のためにその出席が望ましいと思わ
れるTCまたはSC会議に,事務総長の代理を派遣する努力を行っているとはいっても,中央事務局は,
永続的または暫定的なベースで幹事国のための業務の遂行を引き受けることはできない。
55

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
D.3 幹事への要求事項 幹事に任命される個人は,次のとおりでなければならない。 a) 英語及び/または仏語の十分な知識があること。
b) 規約及び施行規則の該当する項目及びISO/IEC専門業務用指針に精通していること(ISO/IEC専門
業務用指針のIEC補足指針及びISO/IEC専門業務用指針のISO補足指針を参照)。
c) 手順または原案作成に関するあらゆる点について,必要ならば中央事務局と協議をして,委員会及
びすべての附属組織に対してアドバイスできる立場にあること。
d) TC全般及び特に本人が担当している委員会の活動に関する理事会またはTMBの決議に注意を払っ
ていること。
e) 委員会の業務を組織,運営するために,また委員会メンバー及びすべての附属組織への積極的な参
加を促進するために,優れたまとめ役であり,また技術的及び管理的業務の訓練を受け精通した能
力があること。
f) 中央事務局が発行した文書,特にISO e-Services Guide並びにIECにおける情報技術の利用に関す
るIECガイドに精通していること。 新たに任命されたTC幹事は,早い時期にジュネーブの中央事務局を訪問し,関係スタッフと手順及び
業務方法について協議することが望ましい。
56

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書E (規定)
言語の使用に関する一般方針
E.1 国際の場における意見の表現及び伝達 国際レベルでは,少なくとも二つの言語を使用することが一般的な慣習である。二つの言語を使用する
ことの利点は,次のように数多い。
・ ある概念を表現するのに文法と構文の異なる二つの言語を使用することによって,意味をより明快
かつ正確に表わすことができる。
・ 一つの言語だけで起草した文書に基づいて合意を得ると,その原文を他の言語に翻訳する際にいろ
いろな問題が生じる恐れがある。審議のやり直しを必要とする問題点がいくつも出てくるかもしれ
ず,それによって,本来合意を得ている原文を変更することになれば,遅れを招くことになる。す
でに第一言語で承認を受けた原文を後から第二言語に起草し直すことは,しばしば,軽微ながらも
様々な表現上の不具合を発生させるが,こうしたことは,もしも初めからその両方の言語で文書が
作成され,修正も同時に行われるならば防げるはずである。
・ 国際会議の効率を 大限に確保するため,達成された合意に全くあいまいさがないことが重要であ
り,また,言語上の誤解によって,これらの合意に疑問があるとして取り消されるようなリスクが
あってはならない。
・ 二つの言語グループから選択した二つの言語を使用すれば,会議への参加の指名を受ける代表予定
者が多くなる。
・ すでに二つの完全に一致した版があれば,他の言語でも適切に概念を表現することがより容易にな
る。
E.2 専門業務における言語の使用 使用言語は,英語,仏語及びロシア語とする。 TC業務及び通信には,このうちの一つまたは複数の言語が適用される。 上記の目的のために,ロシア連邦の国代表組織は,ロシア語へのまたはロシア語からのすべての通訳ま
たは翻訳を提供する。 E.3 IS ISO及びIECは,ISを英語及び仏語で発行する(また特に,用語の場合は,ロシア語及び他の言語を含
む多言語版で発行することがある,特に専門用語の場合はそうである)。一つのISに対する英・仏版は,
同等であり,それぞれが原語版であると見なされる。 原案作成手順の初めから,規格の技術的内容を英仏両国語で表記することには,その二つの版が同時に
審議,修正,採択され,常に言語上の同等性が保たれるという利点がある(ISO/IEC業務用指針2004年版第2部の4.5も参照)。 これは次のように行われる。
・ 幹事国,または幹事国の責任のもとで外部の援助,または,
・ 担当TCまたはSCの編集委員会,または,
・ 当該幹事国との合意の下で,自国語が英語または仏語である国代表組織
57

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
多言語によるIS(例えば,用語集)を発行することが決定された場合,ロシア連邦の国代表組織は,そ
の文中のロシア語の部分を担当する。同様に,公用語以外の言語による用語及び関連文書を含むISを発
行することが決定された場合,自国語がそれに関係している国代表組織は,用語の選定または文中のそ
の当該言語の部分を起草する責任を持つ。
E.4 TC が開発するその他の出版物 その他の出版物の発行は,一つの公用語だけでよい。 E.5 TC 及び SC 会議のための文書 E.5.1 会議に先立って作成,回付する文書 会議に先立って作成,回付する文書については,次のとおりとする。 a) 議題案
担当幹事国は,議題案をできる限り英仏両国語で作成し,複製の上,配布する。 b) 議題に取り上げられたCD
議題に取り上げられたCDは,会議用に英仏両国語版を用意することが望ましい。
照会原案は,英仏両国語版を用意しなければならない。どちらかの言語の文書が適切な時間内に用
意できない場合には,ISO理事会またはIEC/SMBのガイドラインを適用する。 議題に関する他の文書(種々の提案,コメントなど)は,一つの言語(英語または仏語)だけで作
成してもよい。 E.5.2 会議中に作成,回付する文書 会議中に作成,回付する文書については,次のとおりとする。 a) 会議中に採択された決議
各決議案は,幹事及び可能な限り英語及び/または仏語を母国語とする1人または複数の代表から
成り、会議の冒頭に構成されるアドホックの原案作成委員会が編集する。 b) 各セッションの後で作成されることのある要約議事録
この種の議事録を作成する場合は,必要であればアドホックの原案作成委員会と協力して,英語ま
たは仏語で,できれば両国語で起草する。 E5.3 会議後に作成し回付する文書 各TCまたはSC会議の後,当該幹事国は,会議の報告書を起草しなければならないが,報告書は一つの
言語(英語または仏語)だけでよく,また採択された決議の全文は,できれば両国語で,附属書として
含める。 E.6 英語または仏語以外の言語で作成する文書 自国語が英語でも仏語でもない国代表組織は,幹事国から回付された文書をその国の専門家が審議しや
すいように,またはTC及びSC会議への出席の指名を受けた代表を補助するために,自国語に翻訳して
もよい。
58

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
一つの言語が二つ以上の国代表組織の共通語である場合,その国代表組織のうちの一つが率先して,い
つでも専門文書をその言語に翻訳し,同じ言語グループの他の国代表組織にコピーを提供してもよい。 上記の二つの段落の条件は,幹事国が幹事国自身の必要に応じて適用してもよい。
E.7 専門会議 E.7.1 目的 専門会議の目的は,様々な議題項目について,できるだけ全体の合意を得ることであり,全代表が互い
に確実に理解し合えるように,あらゆる努力を払わなければならない。 E.7.2 討議の英語及び仏語への通訳 基本文書は英仏両言語で入手可能であるが,どちらかの言語で出された意見のもう一方の言語への通訳
を,次のいずれが行うか,その場に応じて臨機応変に決定しなければならない。
・ 代表の中の有志による
・ 幹事国または主催国代表組織のスタッフメンバーによる,または,
・ 適切な有資格の通訳
また,英語も仏語も母国語でない代表が,十分に会議を理解できるように配慮することが望ましい。 専門会議における討論を通訳する必要性に関して,規則を規定することは実際的でない。当然,全代表
がその審議を理解できることが重要ではあるが,それぞれの発表を逐語通訳することは,それ程重要で
はないだろう。 前述した点から,通訳をしなくてよい特別な場合を除いて,次の方法が適切であると考えられる。 a) 手順通りの決議が成されると予測される会議には,簡単な通訳を幹事国のメンバーまたは代表有志
が提供することができる。
b) WG会議は,WGのコンビナ主導の権限で,可能な限り,メンバー間で必要な通訳を手配すること
が望ましい。 通訳の手配が必要なときに会議担当幹事国がそれを手配できるように,会議出席の通知を受ける際に,
その代表出席者が使用できる言語と通訳のために出席者が何を提供できるかについての情報も,同時に
得ることが望ましい。 会議が主に一つの言語で行われる場合には,他方の言語の代表出席者を補助するため,実行可能な限り
次の方法を採用することが望ましい。 a) 一つのテーマについてなされた決議は,次のテーマへ移る前に両方の言語で発表する。
b) 既存の文書の変更が一方の言語版で承認された場合は,各代表出席者が,この変更が他方の言語版
に及ぼす影響について検討する時間をとる。
59

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
c) 代表出席者から要請があれば,発言の要約をもう一方の言語でも提示する。
E.7.3 他の言語で行われた発言の英語及び仏語への通訳 TCまたはSC会議において,例外的な状況として,英語または仏語以外の言語で話すことを希望する出
席者があるとき,会議の議長は,会期中,通訳の手段が確保されることを条件に,それを認める権利を
有する。 TC及びSC会議において,すべての専門家に等しくその意見を述べる機会が与えられるように,この規
定はできるだけ柔軟に適用することが望ましい。
60

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書F
(規定)
プロジェクト開発のための選択肢
F.1 選択のための簡易線図
プロジェクト
段階 通常の手順 提案とともに提
出された原案 迅速法による
手順1) TS2) TR3) PAS4)
提案段階 (2.3参照)
提案の受理 提案の受理 提案の受理 提案の受理
提案の受理
作成段階 (2.4参照)
作業原案の 作成
WGに よる調査5) 原案の作成
PAS原案の 承認
委員会段階 (2.5参照)
CDの作成 及び受理
CDの作成 及び受理5)
照会段階 (2.6参照)
照会原案の 作成
及び受理
照会原案の 作成
及び受理
照会原案の 受理
承認段階 (2.7参照)
FDISの 承認6)
FDISの 承認6)
FDISの 承認
6)
原案の受理
原案の受理
発行段階 (2.8参照)
ISの発行 ISの発行 ISの発行 TSの発行 TRの発行 PASの発行
点線で囲まれた円内のイタリック体の段階は省略してもよい。 1) F.2参照 2) 3.1参照 3) 3.3参照 4) 3.2参照 5) 新業務項目提案に関する投票結果に従って,作成段階と委員会段階をともに省略してもよい。 6) 照会原案が反対票なしで承認された場合は,省略してもよい。
61

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
F.2 “迅速法による手順” F.2.1 迅速法による手順適用の提案は次による。 F.2.1.1 関係TCのPメンバー及びカテゴリーAリエゾン機関は,その作成機関にかかわりなく既存の規
格を照会原案として投票に付すために提出することを提案できる。提案者は,提案に先立って,その規
格作成機関の同意を得なければならない。迅速法による手順に関して,既存規格の提案基準は各提案者
に委ねられる。 F.2.1.2 ISOまたはIECの理事会が認めた国際標準化組織は,その組織が作成した規格をFDISとして投
票に付すために提出することを提案できる。 F.2.1.3 ISOまたはIECとの間に正式な専門業務協定を結んだ機関は,当該TCまたはSCと合意の上で,
TCまたはSC内部において,同機関の作成した規格案を照会原案として投票に付すために提出すること
を提案できる。 F.2.2 提案は事務総長が受理するものとし,事務総長は次の措置をとらなければならない。 a) 提案文書の起草機関とともに著作権及び/または商標の問題を解決し,提案文書の複製と国代表組
織への配布が制限を受けずに自由に行えるようにする。
b) F.2.1.1及びF.2.1.3の場合,提案文書のテーマに適切な関連TCまたはSCの幹事国と協議の上,その
文書を評価する。当該文書のテーマを適切に取り扱うTCがない場合,事務総長はその提案をTMBへ委ねなければならない。TMBは,その文書の照会段階への提出及びその後で生じる問題処理のた
め,アドホックグループの設置を事務総長に要請できる。
c) 他のISと,明らかな矛盾のないことを確認する。
d) 提案文書は,2.6.1に従って照会原案(F.2.1.1及びF.2.1.3)として,または,2.7.1に従ってFDIS(F.2.1.2)として配布する。なお,照会原案の場合は,提案文書が属する分野のTC/SCを示すこと。
F.2.3 投票期間及び承認の条件は,照会原案の場合は2.6,FDISの場合は2.7のとおりとする。TCが関 与していない場合のFDIS承認の条件は,反対が投票総数の1/4以下であることである。 F.2.4 照会原案の場合,承認条件が満たされていれば,その規格案は承認段階(2.7)へ進めなければ
ならない。承認条件が満たされていない場合,その提案は却下となり,F.2.2 b) に従って,その文書が
帰属するTC/SCが何らかの事後措置を決議しなければならない。 FDISの場合,承認条件が満たされていれば,その文書は発行段階(2.8)へ進めなければならない。承
認条件が満たされていない場合,その提案は却下となり,F.2.2 b) に従って,その文書が帰属する
TC/SCが何らかの事後措置を決議しなければならない。TCが関与していない場合は,提案した機関と
中央事務局が協議の上,事後措置を決議しなければならない。 規格を発行する場合,その規格のメンテナンスは,F.2.2 b) に従って,その文書が帰属するTC/SCが担
当しなければならない。TCが関与していない場合は,提案した機関が規格を変更することが必要と判
断したときは,上記に定められた承認手順を繰り返さなければならない。
62

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書G (規定)
メンテナンス機関 G.1 TCまたはSCがメンテナンス機関を必要とするISを開発する場合は,ISの発行に先立ってISO/TMBまたはIEC/CBが決議を下せるように,早い時期にこの旨を事務総長に通知しなければならない。 G.2 ISO/TMBまたはIEC/CBは,当該TCの提案に基づくメンバーの指名も含め,ISに関するメンテナン
ス機関を指定する。 G.3 メンテナンス機関の幹事国は,当該ISを作成したTCまたはSCの幹事国であることが望ましい。 G.4 事務総長は,メンテナンス機関の業務と関連のある外部機関との連絡に責任を持たなければなら
ない。 G.5 メンテナンス機関の施行規則は,ISO/TMBまたはIEC/CBによる承認を得たものでなければならず,
さらに,ISの更新または追補の発行に関連して要請されるメンテナンス機関の代表派遣は,特に
ISO/TMBまたはIEC/CBの承認を受けなければならない。 G.6 メンテナンス機関から供与される役務の対価は,すべて理事会によって承認されなければならな
い。
63

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書H (規定)
登録機関 H.1 TCまたはSCが登録機関を必要とするISを開発する場合は,ISの発行に先立って事務総長が必要な
折衝をでき,またTMBが決議を下せるように,早い時期にこの旨を事務総長に通知しなければならない。 H.2 TMBは,当該TCの提案に基づいて,ISに関する登録機関を指定する。 H.3 登録機関は,有資格の,国際的にも承認された組織であることが望ましい。このような機関がな
い場合,上記のタスクは,TMB決議を得て中央事務局に委ねることができる。 H.4 登録機関は,その業務において,ISOまたはIECによって指定されていることを明確に示すことが
必要である(例えば,指定組織のレターヘッドに適切な文言を含める)。 H.5 登録機関は,関連ISの規定に従って行う登録業務について,ISO,IECまたはそのメンバーから金
銭的な寄付を受けてはならない。ただし,理事会が正式に承認したものである場合,登録機関が供与し
た役務の対価を支払っても良い。
64

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
附属書I (規定)
ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許方針の実施ガイドライン
(2007年3月1日)
第1部 – 共通ガイドライン .................................................................................................................... 66 1 目的..................................................................................................................................................... 66 2 用語の説明........................................................................................................................................... 66 3 特許開示................................................................................................................................. 67 4 特許声明書及び実施許諾宣言フォーム................................................................................................ 67
4.1 宣言フォームの目的............................................................................................. 67 4.2 連絡先......................................................................................................................... 68
5 会議の運営.................................................................................................................................... 68 6 特許情報データベース...................................................................................................................... 68 第2部 – 組織別の規定................................................................................................................... 69 ITU固有の規定....................................................................................................................................... 69
ITU-1 包括的特許声明及び実施許諾宣言フォーム.............................................................................. 69 ITU-2 通知................................................................................................................................ 69
ISO及びIEC固有の規定........................................................................................................................... 69 ISO/IEC-1 規格類原案に関する協議..................................................................................... 69 ISO/IEC-2 通知......................................................................................................................... 70
付録1 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許方針....................................................................................... 71 付録2 ITU-T/ITU-R勧告,ISO/IEC規格類に関する特許声明及び実施許諾宣言フォーム..................72 付録3 ITU-T/ITU-R勧告に関する包括的特許声明及び実施許諾宣言フォーム..........................................75
65

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
第1部‐共通ガイドライン
1 目的 ITUの電気通信標準化部門(ITU-T)と無線通信部門(ITU-R),ISO及びIECは,特許権問題が生じた場合に,
各技術委員会の参加者に対して分かり易い実践的なガイダンスを与えることを目的として,長年にわた
って特許方針を定めてきた。 一般に,技術専門家は特許法上の複雑な問題に不慣れであることを考慮し,ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通
特許方針(以後“特許方針”という)が運用に際してのチェックリストとして起草された。そこでは,
勧告,規格類が全面的もしくは部分的に特許の実施許諾を必要とした時に起こり得る三つの異なったケ
ースを取り扱っている。 ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許方針の実施ガイドライン(以後“ガイドライン”という)は,特許方針
の実施を明確化し,促進することを意図している。特許方針の写しはこの文書の付録1に添付されてお
り,ISO,IEC,ITUの各ウェブサイトにも公開されている。 特許方針は,開発中の勧告,規格類に関係する可能性のある特許について,早期開示と確認を促してい
る。それによって,規格開発の効率を向上させることが可能になり,潜在的な特許権問題を避けること
ができる。 ISO,IEC,ITUは,勧告,規格類について,特許の関連性や必須性の評価に関与せず,実施許諾の交渉
に介入したり,特許紛争の解決に関わったりもしない。それは,これまでと同様,関係者に委ねるべき
である。 ISO,IEC,ITUの各機関固有の規定がこの文書の第2部に記載されている。しかしながら,当然のこと
ではあるが,それらの機関固有の規定は特許方針ともガイドラインとも矛盾してはいない。 2 用語の説明 寄書(Contribution):技術委員会から検討用に提出されたあらゆる文書。 無償(Free of charge):“無償”という言葉は,特許権者が必須特許に関する権利のすべてを放棄する
ことを意味しない。“無償”は金銭的補償に関するものであり,特許権者は実施許諾の措置の一部とし
て金銭的補償(このような補償は,ロイヤルティ,一括実施許諾料などと呼ばれる)を求めないという
ことを意味する。しかし,この場合,特許権者が金銭を課さないと約束しても,特許権者は勧告,規格
類の実施者に対して,根拠法,使用分野,互恵主義,保証等に関する合理的な条件を含む実施許諾契約
の締結を要求する権利を保持している。 機関(Organizations):ITU,ISO,IEC 特許(Patents):必須特許または必須特許と類似の権利∗や実用新案及び発明に基づくその他の法的権
利であり,それらの出願を含む。 特許権者(Patent Holder):特許を所有し,管理し,及び/または実施許諾ができる個人または事業体。 互恵主義(Reciprocity):ここで使われている“互恵主義”という言葉は,ライセンシーとなる見込み
の者が,同一の勧告,規格類を実施するために,自己の所有する必須特許または特許請求事項を無償ま
たは合理的な条件で実施許諾すると約束する場合にのみ,特許権者はライセンシーとなる見込みの者に
∗ 訳者注:著作権を指す(2008 年 10 月のIEC TC/SC Officers WorkshopでのIEC中央事務局見解)
66

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
実施許諾することが求められるということを意味する。 勧告,規格類(Recommendations | Deliverables):ITU-T及びITU-Rの勧告を“勧告”,ISO規格類及び
IEC規格類を“規格類”という。付録2に添付された特許声明及び実施許諾宣言フォーム(以後“宣言フ
ォーム”という)では,様々なタイプの勧告,規格類を“文書タイプ”と呼ぶ。 技術委員会(Technical Bodies):ITU-T及びITU-Rの研究委員会,その傘下のグループ,その他のグルー
プ,並びに,ISO及びIECの専門委員会,分科委員会,作業グループ。 3 特許開示 特許方針の第1項で義務付けられているように,ITU,ISO,IECの業務への参加者は,当初から,自己
または他者の既知の特許もしくは判明している出願中の特許に注意を払うべきである。 ここでは,“当初から”の言葉は,勧告,規格類の開発のできるだけ早い時期にこの種の情報を開示す
ることが望ましいということを意味する。 初の原案が提出された時点では,まだ内容が漠然としてい
るかあるいは引き続き大きな修正が加えられる可能性があり,情報開示は難しいであろう。さらに,情
報は誠実かつ 善の努力をもって提供されることが望ましいが,特許検索を求めるものではない。 上記に加え,技術委員会に参加していない者は誰でも,自己のか第三者のかを問わず,既知の特許につ
いてITU,ISO,IECに注意を促すことができる。 自己の特許を開示する際,ガイドラインの第4節に記述されているように,特許権者は,特許声明及び
実施許諾宣言フォーム(“宣言フォーム”という)を用いなければならない。 第三者の特許に注意すべきとの連絡は,関係する機関(ITU,ISO,IEC)に書面で送付されることが望
ましい。潜在的な特許権者は,その後,宣言フォームを提出するよう関係機関から要請されることにな
る。 特許方針及びガイドラインは,勧告,規格類の承認後にITU,ISO,IECに開示または注意が促された特
許にも適用される。 特許の確認が勧告,規格類の承認の前後のどちらであろうと,特許方針の第2.1項または第2.2項に基づ
き実施許諾する意思が特許権者にない場合,ITU,ISO,IECは,影響される勧告,規格類を担当する技
術委員会に速やかに助言し,適切な措置がとれるようにする。その措置には,勧告,規格類またはその
原案を見直し,潜在的な抵触を回避し,あるいは抵触の原因である技術的事項を更に吟味し明確にする
ことが含まれる(これに限定されることはない)。 4 特許声明及び実施許諾宣言フォーム 4.1 宣言フォームの目的 ITU,ISO,IECそれぞれの特許情報データベースに明確な情報を提供するため、特許権者は宣言フォー
ムを使用しなければならない。宣言フォームは各機関のウェブサイトに掲載されている(参考のため,
宣言フォームは付録2に添付されている)。ITUの場合は電気通信標準化局(TSB)または無線通信局
(BR)の局長、ISO/IECの場合は事務総長宛でそれを機関に送付しなければならない。宣言フォームの
目的は,特許権者が各機関に提出する宣言書をもれなく定型化することと,さらに重要なのは,特許権
者が宣言フォームの選択肢1または2による実施許諾を行う意思がない場合(つまり、宣言フォームの選
択肢3を宣言する場合)に,補足情報と説明を求めていることである。補足情報と説明は,ITUの場合は
必須であり,ISOとIECの場合は強く望まれる。
67

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
個々の勧告,規格類の実施に必要な特許権に関し,実施許諾宣言を行うための手段を宣言フォームは特
許権者に提供している。特に,この宣言フォームの提出により,提出者は,自ら所有し,特定の勧告,
規格類を部分的または全面的に実施するために実施許諾が必要になると思われる特許に関し,実施許諾
の意思の有無を特許方針に従って宣言することになる。 宣言フォームに記載された声明は,明らかな誤りの場合などで差し替えられない限り,効力を維持する。 特許権者が幾つかの特許を特定し,それらの特許について宣言フォームで異なる選択肢を選ぶ場合,及
び/または,複雑な特許の異なる請求事項について,特許権者が宣言フォームで異なる選択肢を選ぶ場
合,複数の宣言フォームの使用が適切である。 4.2 連絡先 宣言フォームに記入する際,長期にわたって有効な連絡先を記載するよう配慮することが望ましい。可
能であれば,“氏名と部署”及びeメールアドレスは総称的なものであることが望ましい。また,可能で
あれば,当事者,特に多国籍企業は,提出するすべての宣言フォームに同一の連絡先を記入することが
望ましい。 ITU,ISO,IEC各機関の特許情報データベースの情報を 新に保つために,過去に提出された宣言フォ
ームの如何なる変更もしくは修正について,窓口担当者に関するものについては特に,機関に通知する
ことが求められる。 5 会議の運営 早期の特許開示は,勧告,規格類の開発プロセスの効率性を高める。したがって,提案された勧告,規
格類の開発過程で,各技術委員会は,提案された勧告,規格類に必須のあらゆる既知の特許について,
開示を要請することになろう。 技術委員会の議長は,適宜,各会議の適当な折に,検討中の勧告,規格類を実施する上で必要となる特
許を誰か知っているかどうか,尋ねるであろう。質問があったという事実は,あらゆる肯定的な回答と
ともに,会議の報告書に記録されなければならない。 特許方針の第2.3項を選択した旨の通知を関係機関(ITU,ISO,IEC)が特許権者から受けない限り,
関係機関のそれぞれの適切な規則に基づいて,勧告,規格類を承認することができる。勧告,規格類に
特許関連事項を取り込むことを技術委員会で検討することが期待されるが,技術委員会は,主張された
特許の必須性,適用範囲,有効性,特定の実施許諾条件に関し,何らかの立場をとることは許されない。 6 特許情報データベース 規格作成プロセス及び勧告,規格類の適用を促進するために,ITU,ISO,IEC各機関は,宣言フォーム
で連絡された情報から成る特許情報データベースを公開する。特許情報データベースには特定の特許に
関する情報を含めるか,あるいは,そのような情報は含めず、代わりに特定の勧告,規格類に対する特
許方針の遵守についての声明を含めることができる。 特許情報データベースは正確性及び完全性の保証がなく,ITU,ISO,IECに連絡された情報が反映され
ているに過ぎない。特定の勧告,規格類の使用または実施に際して特許の実施許諾を取得せねばならな
いかを判断するために,ITU,ISO,IECに宣言フォームを提出した事業体と連絡を取ろうとする利用者
に対し,特許情報データベースは注意を促すフラグを単に立てているとみなすこともできる。
68

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
第2部‐ITU,ISO,IEC固有の規定
ITU固有の規定 ITU-1 包括的特許声明及び実施許諾宣言フォーム 誰でも,ITU-T及びITU-Rのウェブサイトから入手可能な包括的特許声明及び実施許諾宣言フォームを提
出することができる(参考のためにフォームを付録3に添付する)。これは,特許権者のあらゆる寄書に
含まれる特許で保護された事項について,その特許権者が包括的な実施許諾宣言を行うというものであ
り,特許権者にこうした自発的な選択の機会を与えることがこのフォームの目的である。明確に言えば,
ITUに提出された寄書中の提案の一部またはすべてが勧告に含まれ,その含まれた部分が特許で保護さ
れるかもしくは特許出願中の事項を含み,勧告の実施には実施許諾が必要となる場合,このフォームを
提出することによって,提出者はその所有するすべての特許について実施許諾するという意思を表明す
るものである。 包括的特許声明及び実施許諾宣言フォームは,勧告毎に作成される“個別の”宣言フォーム(第1部の4節参照)に取って代わるものではないが,これにより,特許権者が特許方針を遵守して速やかな対応と
早期開示を行うことが期待される。 包括的特許声明及び実施許諾宣言フォームは,差し替えられない限り効力が維持されるが,同一の特許
権者からの特定の勧告に関する“個別の(勧告毎の)”宣言フォームによって,覆されることがあり得
る(これは稀にしか起きないことを期待する)。 ITUの特許情報データベースは包括的特許声明及び実施許諾宣言の記録も含む。 ITU-2 通知 すべての新版及び改訂版のITU-T・ITU-Rの勧告の表紙に,ITU特許情報データベースを調べるよう利用
者に促す定型文を,適宜追記しなければならない。それは次の文章である: “ITUは,この勧告の実施に権利主張された知的所有権の使用が含まれる可能性があることに注意を促
す。権利主張された知的所有権の証拠,有効性,適用性について,ITUメンバーまたは勧告開発プロセ
スに関与しない者の何れから主張されたかを問わず、ITUは何らの見解も示さない。 この勧告の承認日現在,この勧告の実施に必要となる,特許によって保護された知的財産に関する通知
をITUは受け[取った/取っていない]。しかしながら,実施者に対し,これが 新情報を示すとは限らな
いことを警告し,従って,ITU特許情報データベースを調べるよう強く促す。” ISO及びIEC固有の規定 ISO/IEC-1 規格類原案に関する協議 コメントのためのすべての原案には,表紙に次の文章を記載しなければならない:
“この原案の受領者が認識している関連特許権があれば,コメントを付けて通告書を提出すると
ともに,関係書類を提供するよう求める”
69

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
ISO/IEC-2 通知 作成段階において特許権が特定されなかった発行文書には,まえがきに次の注意書きを記載しなければ
ならない:
“この文書の一部の要素は,特許権の対象となる可能性があることに注意が必要である。ISO[及び/または]IECは,このような特許権の一部または全部を特定する責任を負うものでは
ない。” 作成中に特許権が特定された発行文書には,序文に次の注意書きを記載しなければならない:
“国際標準化機構(ISO)[及び/または]国際電気標準会議(IEC)は,この文書に準拠するこ
とが,、(…項番号…)に示されている(…テーマ…)に関する特許を使う必要がある点に注意
を喚起する。 ISO [及び/または] IECは,この特許権の証拠,有効性,適用範囲について関知するもので
はない。 この特許権者は,合理的で差別のない条件で,世界中の申請者と実施許諾について交渉する用
意があることをISO [及び/または] IECに確約している。これに関して,この特許権者の声
明は,ISO[及び/または]IECに登録されている。情報は,下記から得られる:
特許権者の氏名 … 住所 ...
この文書の要素には,上記で特定できた以外にも特許権の対象になる可能性があることに注意
が必要である。ISO[及び/または]IECは,このような特許権の一部または全部を特定する
責任を負うものではない。” ISO(www.iso.org/patents)及びIEC(http://www.iec.ch/tctools/patent_decl.htm)は,その規格に関
連する特許のオンラインデータベースを保持する。特許に関する 新の情報を得るため,この
データベースを閲覧するよう利用者に望む。
70

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
付録1
ITU-T/ITU-R/ISO/IEC共通特許方針
以下は,ITU-T勧告,ITU-R勧告,ISO規格類,IEC規格類の対象事項を様々な程度で扱っている特許に
関する“実施基準”である(本文書においては,ITU-T勧告及びITU-R勧告を“勧告”と称し、ISO規格
類及びIEC規格類を“規格類”という)。“実施基準”の規則は簡潔明瞭である。勧告,規格類は,特許
の専門家ではない技術的な専門家によって作成される。よって,彼らは,特許等の知的所有権に関する
複雑で国際的な法律の情勢には必ずしも精通していない。 勧告,規格類には拘束力がない。それらの目的は,世界的に技術とシステムの互換性を確保することで
ある。すべての参加者の共通利益であるこの目的を達成するために,勧告,規格類,その適用,使用等
は,誰にでも開かれていなければならない。 よって,勧告,規格類に全面的または部分的に組み込まれている特許は,過度の制約なしに誰でもが利
用可能でなければならない。この要求を総合的に満たすことが,この実施基準の唯一の目的である。特
許に絡む細かな取り決め(実施許諾、ロイヤルティなど)は,その都度対処法が異なると思われるので,
関係者に一任される。 この実施基準は以下のようにまとめられる: 1 ITU電気通信標準化局 (TSB),ITU無線通信局 (BR),ISO及びIECの中央事務局は,特許権または類似
の権利の証拠,有効性,適用範囲に関する権威あるまたは包括的な情報を提供する立場にはないが,可
能な限り 大限の情報開示がなされることが望まれる。よって,ITU,ISO,IECの作業に参加するあら
ゆる関係者は,組織の内外を問わず,あらゆる既知の特許または判明している特許出願について, 初
から,ITU-TSB局長、ITU-BR局長,ISOまたはIECの中央事務局に注意を促すことが望ましい。ただし,
ITU,ISO,IECはそのような情報の有効性を検証することはできない。 2 勧告,規格類が開発され,第1項に記載された情報が開示された場合,次の三つの異なる状況が起こ
り得る: 2.1 特許権者は,非差別的かつ合理的な条件で無償の実施許諾を他者と交渉する意思がある。そのよう
な交渉は関係者に委ねられ,ITU-T/ITU-R/ISO/IECの外部で行われる。 2.2 特許権者は,非差別的かつ合理的な条件で他者と実施許諾を交渉する意思がある。そのような交渉
は関係者に委ねられ,ITU-T/ITU-R/ISO/IECの外部で行われる。 2.3 特許権者は,第2.1項、第2.2項のいずれの規定にも従う意思がない。そのような場合は,その特許
に依存する条項を勧告,規格類に含めてはならない。 3 いずれの場合(第2.1項,第2.2項または第2.3項)でも,特許権者は,それぞれ所定の“特許声明書及
び実施許諾宣言”フォームを用いて,ITU-TSB,ITU-BR,ISOまたはIECの中央事務局に声明文書を提
出しなければならない。この文書には,このフォームに示されているそれぞれの場合に対応するチェッ
ク欄の内容を越えるような条項,条件,その他のあらゆる除外条項を追記してはならない。
71

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
付録2
ITU-T/ITU-R勧告,ISO/IEC規格類に関する特許声明及び実施許諾宣言フォーム
特許声明及び実施許諾宣言 ITU-T/ITU-R 勧告,ISO/IEC 規格類用
この宣言は、実際の実施許諾を意味しない
文書タイプ毎に,以下の指示に従って関係機関に返信してください。 Director Telecommunication Standardization Bureau International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Switzerland Fax: +41 22 730 5853 Email: [email protected]
Director Radiocommunication Bureau International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Switzerland Fax: +41 22 730 5785 Email: [email protected]
Secretary-General International Organization for Standardization 1 chemin de la Voie-Creuse CH-1211 Geneva 20 Switzerland Fax: +41 22 733 3430 Email: [email protected]
General Secretary International ElectrotechnicalCommission 3 rue de Varembé CH-1211 Geneva 20 Switzerland Fax: +41 22 919 0300 Email: [email protected]
特許権者:
法的名称 _________________________________________________________________
実施許諾申し込みのための連絡先:
氏名及び部署名 _________________________________________________________________
住所 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
電話 _________________________________________________________________
ファックス _________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
URL (任意) _________________________________________________________________
文書タイプ:
□ ITU-T 勧告 (*) □ ITU-R 勧告 (*) □ ISO 規格類 (*) □ IEC 規格類 (*)
(このフォームを関係機関に返信してください)
□ 共通規格またはツイン規格 (ITU-T 勧告 | ISO/IEC 規格類 (*)) (共通規格またはツイン規格につ
いては,ITU-T,ISO,IEC の三機関それぞれにこのフォームを返信してください)
□ ISO/IEC 規格類 (*) (ISO/IEC 規格類については,ISO と IEC の両方にこのフォームを返信してく
ださい) (*)番号 _________________________________________________________________
(*)名称 _________________________________________________________________
72

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
実施許諾宣言: 特許権者は,上記勧告,規格類を実施する上で必要な登録済及び/または出願中の特許を保有すると考
え,ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共通特許方針に従い,以下を宣言する(1つの欄のみに印をつけること):
□ 1. 特許権者は,人数に制約なく世界の申請者に対し,上記勧告,規格類を実施し,利用し,
実施物を販売するために,非差別的かつ合理的な条件で無償での実施許諾を認める用意がある。 交渉は関係者に委ねられ,ITU-T,ITU-R,ISO,IEC の外部で行われる。 特許権者が上記勧告,規格類への互恵主義を条件として実施許諾する意思がある場合は,ここ__にも印をつけること。
上記勧告・規格類を実施するために必要となる特許請求事項について,合理的な条件で
(無償ではなく)実施許諾するとの意思を申請者が表明する場合,その申請者に対しては,
合理的な条件で(無償ではなく)実施許諾する権利を特許権者が保持する場合は,ここ__に印をつけること。
□ 2. 特許権者は,人数に制約なく世界の申請者に対し,上記勧告,規格類を実施し,利用し,
実施物を販売するために、非差別的かつ合理的な条件で実施許諾を認める用意がある。 交渉は関係者に委ねられ,ITU-T,ITU-R,ISO,IEC の外部で行われる。
特許権者が上記勧告,規格類への互恵主義を条件として実施許諾する意思がある場合は,
ここ__にも印をつけること。
□ 3. 特許権者は,上記1,2 のいずれの条件でも実施許諾する意思がない。
この場合,この宣言の一部として,以下の情報をITUに提供しなければならない。ISO とIEC では情報の提供が強く求められる。 - 特許登録番号または特許出願番号(申請中の場合) - 上記勧告,規格類が影響を受ける部分の明示 - 上記勧告,規格類に関わる特許請求事項の記述
無償: “無償”という言葉は,特許権者が必須特許に関する権利のすべてを放棄することを意味しな
い。“無償”は金銭的補償に関するものであり,特許権者は実施許諾の措置の一部として金銭的補償
(このような補償は,ロイヤルティ,一括実施許諾料などと呼ばれる)を求めないということを意味す
る。しかし,この場合,特許権者が金銭を課さないと約束しても、特許権者は上記勧告,規格類の実施
者に対して,根拠法,使用分野,互恵主義,保証等に関する合理的な条件を含む実施許諾契約の締結を
要求する権利を保持している。 互恵主義(Reciprocity):ここで使われている“互恵主義”という言葉は,ライセンシーとなる見込み
の者が,同一の上記勧告,規格類を実施するために,自己の所有する必須特許または特許請求事項を無
償または合理的な条件で実施許諾すると約束する場合にのみ,特許権者はライセンシーとなる見込みの
者に実施許諾することが求められるということを意味する。 署名: 特許権者 ___________________________________________________________
権限を持つ人の名前 ___________________________________________________________
権限を持つ人の役職名 ___________________________________________________________
署名 ___________________________________________________________
場所,日付 ___________________________________________________________
フォーム: 2007 年3 月1 日
73

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
特許情報(選択肢1 と2 の場合,情報が要望されるが必須ではない;選択肢3の場合,ITUでは必須であ
る(注)) No. 状態
[登録済/申請中] 国 登録特許番号
または 出願番号
(申請中の場合)
表題
1
2
3
注: 選択肢3 の場合,上記選択肢3の欄に記載されている 低限の追加情報も記入すること。
74

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
付録3
ITU-T/ITU-R勧告に関する包括的特許声明及び実施許諾宣言フォーム
ITU
包括的特許声明及び実施許諾宣言 ITU-T/ITU-R 勧告用
この宣言は、実際の実施許諾を意味しない 関係部門に返信してください: Director Telecommunication Standardization Bureau International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Switzerland Fax: +41 22 730 5853 Email: [email protected]
Director Radiocommunication Bureau International Telecommunication Union Place des Nations CH-1211 Geneva 20, Switzerland Fax: +41 22 730 5785 Email: [email protected]
特許権者:
法的名称 _________________________________________________________________
実施許諾申し込みのための連絡先:
名義及び部署名 _________________________________________________________________
住所 _________________________________________________________________
_________________________________________________________________
電話 _________________________________________________________________
ファックス _________________________________________________________________
E-mail _________________________________________________________________
URL (任意) _________________________________________________________________
75

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
実施許諾宣言: 上記特許権者によって提出された寄書中の提案の一部またはすべてがITU-T/ITU-R 勧告に含まれ,その
含まれた部分が特許で保護されるかもしくは特許出願中の事項を含み,その使用がITU-T/ITU-R勧告の
実施に必要となる場合,ITU-T/ITU-R/ISO/IEC 共通特許方針に従い,上記特許権者は次のように宣言す
る(1つの欄のみに印をつけること):
□ 1. 特許権者は,人数に制約なく世界の申請者に対し,関係するITU-T/ITU-R 勧告を実施し,
利用し,実施物を販売するために,非差別的かつ合理的な条件で無償での実施許諾を認める用意
がある。
交渉は関係者に委ねられ,ITU-T/ITU-R の外部で行われる。
特許権者が上記勧告への互恵主義を条件として実施許諾する意思がある場合は,ここ__にも印を
つけること。
上記ITU-T/ITU-R勧告を実施するために必要となる特許請求事項について,合理的な条件
で(無償ではなく)実施許諾するとの意思を申請者が表明する場合,その申請者に対して
は,合理的な条件で(無償ではなく)実施許諾する権利を特許権者が保持する場合は,こ
こ__にも印をつけること。
□ 2. 特許権者は,人数に制約なく世界の申請者に対し,関係するITU-T/ITU-R勧告を実施し,
利用し,実施物を販売するために,非差別的かつ合理的な条件で実施許諾を認める用意がある。
交渉は関係者に委ねられ,ITU-T、ITU-R の外部で行われる。
特許権者が上記ITU-T/ITU-R勧告への互恵主義を条件として実施許諾する意思がある場合は,こ
こ__にも印をつけること。 無償: “無償”という言葉は,特許権者が必須特許に関する権利のすべてを放棄することを意味しな
い。“無償”は,金銭的補償に関するものであり,特許権者は実施許諾の措置の一部として金銭的補償
(このような補償は,ロイヤルティ,一括実施許諾料などと呼ばれる)を求めないということを意味す
る。しかし,この場合,特許権者が金銭を課さないと約束しても,特許権者は,ITU-T/ITU-R勧告の実
施者に対して,根拠法,使用分野,互恵主義,保証等に関する合理的な条件を含む実施許諾契約の締結
を要求する権利を保持している。 互恵主義(Reciprocity) :ここで使われている“互恵主義”という言葉は,ライセンシーとなる見込
みの者が,同一のITU-T/ITU-R勧告を実施するために,自己の所有する必須特許または特許請求事項を
無償または合理的な条件で実施許諾すると約束する場合にのみ,特許権者はライセンシーとなる見込み
の者に実施許諾することが求められるということを意味する。 署名: 特許権者 ___________________________________________________________
権限を持つ人の名前 ___________________________________________________________
権限を持つ人の役職名 ___________________________________________________________
署名 ___________________________________________________________
場所,日付 ___________________________________________________________
フォーム: 2007 年3 月1 日
76

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
翻訳版への付録
略語集
AC Administrative Circular 事務連絡文書
BIPM International Bureau of Weights and Measures 国際度量衝局
C Council 総会(IEC) CA Committee of Action 技術管理委員会(IEC) CAB Conformity Assessment Board 適合性評価評議会(IEC) CASCO Committee on Conformity Assessment 適合性評価委員会(ISO) CB Council Board 評議会(IEC) CB Certification Body 認証機関
CC Compilation of Comments on CD CD に対するコメント集
CD Committee Draft for Comments コメント用委員会原案
CD Committee draft 委員会原案
CDV Committee Draft for Vote 投票用委員会原案
CEO Chief Exective Officer 事務総長
CL Circular Letter 連絡文書
CO Central Office 中央事務局(IEC) CS Central Secretariat 中央事務局(ISO) DA Draft Agenda 議題案
DC Document for Comments コメント用審議文書
DIS Draft International Standard 国際規格案
DL Decision List 決議リスト
DTR Draft Technical Report 技術報告書案 DTS Draft Technical Specification 技術仕様書案 EDR Essential Differences in Requirements FDIS Final Draft International Standard 終国際規格案
IEC International Electrotechnical Commission 国際電気標準会議
IECEE IEC Systm for Conformity Testing to Standards for Safty of Electrical Equipment IEC 電気機器安全規格適合試験制度
IECEx IEC Scheme for Certification to Standards relating toEquipment for use in Explosive Atmospheres
IEC 防爆電気機器規格適合試験制度
IECQ IEC Quality Assessment System for ElectronicComponents
IEC 電子部品品質認証制度
IEV International Electrotechnical Vocabulary 国際電気標準用語集
INF Document for Information 参考文書
IS International Standards 国際規格
ISH Interpretation Sheet 解釈票
ISO International Organization for Standardization 国際標準化機構
ITA Industry Technical Agreement 産業技術協定 ITSIG Information Technology Strategies Implementation Group 情報技術戦略実施グループ(ISO) ITU International Telecommunication Union 国際電気通信連合
JCG Joint Coordination Group 合同調整グループ
JTAB Joint Technical Advisory Board ISO/IEC 合同専門諮問評議会
77

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
略語集(続き)
JTC1 ISO/IEC Joint Technical Committee for Information technology ISO/IEC 合同専門委員会 1
JWG Joint Working Group 合同作業グループ
MB Member Body 会員団体(ISO) MCR Maintenance Cycle Report メンテナンスサイクル報告書
MOD modified 修正
MT Maintenance Team メンテナンスチーム
MTG Meeting Document 会議用文書
NC National Committee 国内委員会(IEC) NCC National Committee Comment (C/SMB only) 国内委員会コメント(C/SMB のみ)
NCP National Committee Proposal 国内委員会の提案
NP New Work Item Proposal 新業務項目提案
PAS Publicly Available Specification 公開仕様書
PT Project Team プロジェクトチーム
PW Programme of Work 作業計画
PWI Preliminary Work Item 予備業務項目
Q Questionnaire 質問票
QP Question of Principle (SMB only) 原則的質問(SMB のみ)
R Report 報告
RM Report of Meeting 会議議事録
RQ Report on Questionnaire 質問票回答結果
RSMB Report to Standardization Management Board SMB への報告 RV Report of Voting (C/SMB only) 投票結果(C/SMB のみ)
RVC Report of Voting on CDV CDV 投票結果
RVD Report of Voting on FDIS FDIS 投票結果
RVN Report of Voting on NP NP 投票結果
SC Subcommittee 分科委員会
SMB Standardization Management Board 標準管理評議会
SPS Strategic Policy Statement 運営方針計画書(IEC) TA Technical Area テクニカル・エリア(IEC/TC100) TAG Technical Advisory Group 専門諮問グループ(ISO) TC Technical Committee 専門委員会
TMB Technical Management Board 技術管理評議会(共通&ISO)
TR Technical Report 技術報告書
TS Technical Specification 技術仕様書
VT Validation team 妥当性検証チーム
WG Working Group 作業グループ
78

ISO/IEC 専門業務用指針 第 1 部 2008 年版
略語集(続き)
プロジェクト段階の略称(個々の位置付けは補足指針の附属書 F を参照。日本語表現は確定されていない。)
1CD 1st Committee Draft (to 9th Committee Draft) A2CD Approved for 2nd Committee Draft (to 9th Committee Draft) ACDV Draft approved for Committee Draft with Vote ADIS Approved for FDIS circulation ADISSB FDIS manuscript subcontracted to CO AMW Approved Maintenance Work ANW Approved New Work APUB Draft approved for publication APUBSB PUB manuscript subcontracted to CO BPUB Publication being printed BWG Draft returned to Working Group CAN Draft cancelled CCDV Draft circulated as Committee Draft with Vote CDIS Draft circulated as FDIS CDM Committee Draft to be discussed at Meeting CDPAS Circulated Draft for Publicly Available Specification CDTR Circulated Draft Technical Report CDTS Circulated Draft Technical Specification CDVM Committee draft with vote for meeting DEC Draft at Editing Check DEL Deleted items DELPUB Deleted Publication DREJ Draft rejected MERGED Merged project NADIS FDIS not approved NCD CCDV not approved PNW Proposed New Work PPUB Publication issued PWI Preliminary new work item RDIS Text for FDIS received and registered SPE Special Handling SRP Publication under Systematic Review WPUB Withdrawn Publication
79