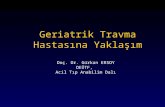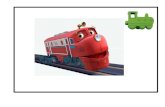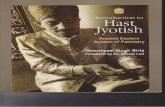HASTに よる加速劣化試験 - J-STAGE Home
Transcript of HASTに よる加速劣化試験 - J-STAGE Home

特集/実 装信頼性評価 ・設計の現状と動向
HASTに よる加速劣化試験
中村 和裕*
Evaluation of Accelerated Life Testing by HAST
Kazuhiro NAKAMURA*
*新 光電気工業株式会社基盤技術研究所(〒381-0103長 野県長野市若穂川田1457-1)
* Core Technology Research Laboratory , Shinko Electric Industries Co., Ltd.(1457-1 Wakaho Kawada, Nagano-shi, Nagano 381-0103)
1.は じめに
電子機器関連の加速性を伴 う耐湿性評価の1つ にHAST
(Highly Accelerated Temperature and Humidity Stress Test)
があり,よ く利用 されている。 これは,も ともと半導体デ
バイスの加速試験 と して開発 された試験法の1つ である。
しかし,プ リン ト配線板などでは,高 機能化 と環境保全 に
よる鉛フリーおよびハ ロゲンフリー化に伴い電子絶縁材料
のグレー ドアップが進み,比 較的低加速ス トレスの温湿度
定常試験(例 えば,85℃85%RHな ど)で は長期試験が必
要 とな り,そ の改善策 としてこの試験法がその後汎用的に
導入 された経緯がある。
しか し,意 外にもこの試験法は導入に先立 ち,事 前調査
確認が不十分な点が指摘 されてお り,当 学会 内に専門の調
査研究会を設置(主 査:津 久井 勤)し,試 験の妥当性を
調査検討されてきた。本報ではこの結果の要約 と,昨 年12
月 に開催 された公 開研究会の参加者か らの ア ンケー ト
(HAST試 験法,現 状抱えている問題点,実 際に携わって
いる方の意識など)結 果を中心に述べる。
2.HAST導 入経過
HASTを 含む加圧水蒸気試験の最初の導入は,1960年 代
にR.C.A.社 におけるソリッド抵抗器の試験であると言 われ
ている1)。その後,図1に 示すよ うに,当 初は加圧水蒸気
により半導体デバイスへの水分の浸透性を高め,ア ル ミ配
線の腐食性を短期間で評価するために導入された。
しか し,近 年では電子絶縁材料特性のグレー ドが上がり,
温湿度定常試験(85℃85%RHな ど)で は,故 障に至る前
の時間が数千時間以上かか り2),製 品開発に支障を来たす
ので,打 開策 として,こ の試験が電子機器全般 に至るまで
の幅広い分野で普及されてきた。
当初は飽和加圧水蒸気試験(PCT:Pressure Cooker Test)が
主流であったが,結 露の影響,市 場故障の再現性な どの問
題により3),4),HASTが 開発 され,今 日に至 っては広 く使わ
れるようになった。
図1.加 圧水蒸気試験法制定の経過
なお,PCTは 上記問題点などにより,EIAJ(現JEITA)
では1997年 に廃止され,現 在ではJEDECの みの規定となっ
ているが,飽 和加圧水蒸気による腐食性,樹 脂接合間の密
着性などの評価に優れていることか ら,今 なお半導体デバ
イスを中心に使われている。 しか し,後 で示す図3の よう
に,PCT条 件について3章 で述べるアンケー トを調査 した
結果,湿 度100%RHに 対 し,実 際は95~100%RHの 範囲で
試験されてお り,メ ーカにより湿度設定条件が異なってい
ることがわかった。 これは,環 境試験装置の槽内の雰囲気
が,飽 和タイプと不飽和タイプの2種 類の雰囲気が存在 し
ていることになる。そのため,今 後はPCTに おいて,こ れ
ら湿度の影響を改めて検討す る必要がある。
なお,HASTは 耐湿性試験法以外にも,信 頼性評価の分
野では,高 加速度ス トレス試験全般(HAST:Highly Acceler-
ated Stress Test)を意味する場合 もあるので,留 意 されたい。
3.ア ンケー ト調査か ら見たHASTの 実態 について
実際にHASTに 携わっている技術者が,ど のような意識
を持ち,ま たどのような問題点を抱えているのかな どを明
らかにするために,昨 年12月 に開催 した加速寿命試験法
検討研究会の公開研究会の参加者にアンケー ト調査を行 っ
540エ レ ク トロ ニ ク ス実 装 学 会 誌Vol.6No.7(2003)

図2.HASTに 関するア ンケー ト調査結果(そ の1)
た。主な内容を以下に報告する。
今 回のア ンケー ト回答率 は出席者(110名)の うち約
60%で,業 種別 にみると,機 器,部 品メーカが全体の約8
割近 く占めている。また,部 門別では研究開発部門が約6
割で,設 計開発時におけるHASTの 利用 に当たって,特 に
高い関心が持たれていると言える。
アンケー ト結果を図2,3に 示 したが,以 下に主な概要に
ついてまとめた。
(1) HASTの 導入 目的は,約50%が 試験時間の短縮 と相
対評価であ り,製 品開発の早期立ち上げが前提にある
と考える。 また,対 象 となる試料は,プ リント配線板,
デバイスPKGが 主流であった(図2(a)~(c))。
(2) HAST導 入 に当たり,事 前検討(条 件選定,故 障メ
カニズム,モ ー ドなど)が ほとんど実施 されておらず,
ユーザからの指定 とか,何 とな く導入 されているなど
の場合が多い(図2(d))。
(3) HASTの 有効性は,回 答の約5割 はあるとの ことだ
が,そ の うち約4割 は根拠が明確ではな く,感 覚的に
エ レク トロ ニ ク ス実 装 学 会 誌Vol.6No.7(2003)541

図3.HASTに 関する アンケ ー ト調査結果(そ の2)
判断 されている状況が伺える(図2(e),(f))。
(4)試験条件は,HASTで130℃/85%RH,120℃/85%RH
の順 に多 く,PCTで,121℃/100%RHが ほとんどであ
る(図3(g))。
以上のことよ り,HASTは 十分検討 した上で導入 されて
いるのではな く,ほ とんどは感覚的な判断であり,ユ ーザ
か らの要求に仕方な く導入 しているケースが多いようにも
判断される。 そのため,こ の試験法についての妥当性を見
極める検討を必要 とされていることを示 している。
4.HASTを 実施 するに当たって のチェックポイ ン ト
4.1関 連規格 と試験条件について
主なHAST規 格を表1に 示す。 ほとんどは半導体デバイ
ス等部品の適用規格である。一般にはJEDEC規 格が多 く使
われている。最近では2001年 に部品を対象 とした日本工業
規格(JIS)が,引 き続いてプリン ト配線板を対象に日本プリ
ント回路工業会(JPCA)がHAST規 格を制定 している。また,
一部産業会のロー ドマ ップでもHASTは 取 り上げ られてい
る5)。
現在,一 般に規格化 されているHASTの 温湿度条件は,
温度が110℃ と130℃ の2条 件,湿 度が85%RHの1条 件で
ある。HASTの 採用に当た っては,樹 脂材料ではガラス転
移温度を超える試験温度では,故 障メカニズムが通常とは
異なる可能性があり,そ の温度以上では使用 しないことが
指摘されている。また,試 験電圧値は,一 般には個別規格
で規定 されているが,JPCA規 格 の場合 は,DC5Vか ら
100Vの 範囲と定めている。参考 として,相 対比較の場合
には,比 較的高い電圧値(約DC30Vか ら100V)で,製 品
の信頼性評価の場合は,実 際に回路上の電源電圧値で設定
する場合が多い。試験条件の設定 に当たっては,絶 縁樹脂
材料の場合,硬 化プロセスの影響が顕著に現れるので,故
障モー ドが通常とは異なる恐れのないところで,試 験 目的,
材料特性,試 料の状態などに応 じた条件を設定す るのが望
ま しい。
最近のパーソナルコンピュータのデバイス動作電圧は,
現在約DC5Vか ら1.5Vと 低 くなる傾向にあ り,イ オンマ
イグレーションの発生 は抑えられるようには思われる。 し
か しなが ら,高 密度実装 に伴 って,フ ァインピッチ化 し,
逆 に電界強度は高 くなってきているので,今 後 とも留意は
必要である。
4.2環 境試験装置について
一般にHAST装 置 には,図4に 示すように一槽式(空 調
方式)と 二槽式の2タ イプがある6)。一槽式 は,水 蒸気発
生槽と試験槽が一体 となっており,水 蒸気が加熱 ヒータで
再加熱されファンによりか くはんされるタイプである。二
槽式は,水 蒸気発生槽 と試験槽が独立 してお り,別 の槽で
造 られた加湿雰囲気を試験槽へ送 るタイプである。
そこで,前 記研究会 において両装置の比較試験を行った
結果,同 一試料で両者 における故障時間の差異は特 に見 ら
表1.HAST規 格一覧表
542エ レ ク トロニ クス 実 装 学 会 誌Vol.6No.7(2003)

図4.HAST装 置 の構造
れなかったと報告 されている7)。
なお,留 意事項 として,環 境試験装置の制御 している温
湿度は,実 際に試料設置場所 とは異なるので,試 料周辺部
の温湿度 は事前に確認 してお くことが指摘 されている。
以下に国内におけるHAST装置 の主な仕様を示す。
温度105~160℃
湿度65~100%RH
圧力0.02~0.40MPa
参考までに,米 国製の試験装置には,圧 力が約0.6MPa
と非常に高い領域まで使用できるものがある。これは,高
ガラス転移温度(約150℃ 以上)の 樹脂封止パ ッケージな
どの評価 に使用 されているようである。
4.3計 測システムについて
耐湿性試験における絶縁劣化の計測方法 は,試 料を環境
試験装置より取 り出 して計測する方法(ス タティック測定)
と,試 料を環境試験装置に入れた状態で計測する方法(ダ
イナ ミック測定)が ある8)。後者の方法は,電 圧 印加中に
イオンマイグレーションで短絡 した場合に検出可能な利点
があり,現 在一般的に多 く使われている方法である。 また,
この方法 は,簡 易的な回路で電圧をモニターする電圧降下
法 と,リ ーク電流を連続的にモニターする方法とがあ り,
いずれも長所短所があ り,試 験精度,評 価 コス トなどを考
慮 し選択する方が良い。
絶縁抵抗値の判定基準は個別規格によるが,一 般的には
JPCA規 格で規定されているように,ス タティック測定で
107Ω以上,ダ イナミック測定で106Ω 以上が一般的である。
特にHASTの 絶縁劣化計測で留意する点は,判 定抵抗値
が試料の絶縁抵抗値の他,環 境試験装置(内 部引き回 し配
線抵抗,接 続端子など)や,計 測部を含めた抵抗値が加算
されるので,試 料の絶縁抵抗値より十分低 くするとともに,
誘導ノイズが入 らないようにすることが必要である。 また,
試料の導体間隙が狭い場合や,材 料系によっては,加 湿段
階ですでに判定抵抗値 まで擬似的に降下する場合があり,
劣化判定値と試験条件の設定 には事前に検討 してお く必要
がある(特 にプリン ト配線板の場合には,加 湿前より加湿
表2.耐 湿性 評価の加速モデル
後で絶縁抵抗値が3桁 以上低下する場合がある)。
5.耐 湿性評価試験の加速モデルにつ いて
一般にHASTを 含めた耐湿性評価試験では,温 度,湿
度,電 圧(電 界強度),水 蒸気圧などのス トレス因子 に対
する加速モデルがある。一般的によく使われている加速モ
デルを表2に 示す。 これは,加 速寿命試験法検討研究会の
プリン ト配線板におけるHASTの 加速性評価に使われた加
速モデルで,温 度の加速性はアレニウスモデルで,湿 度 と
電圧の加速性は,そ れぞれ湿度,電 圧ス トレスのべキ乗則
の加速モデルである。各加速モデルは,寿 命に対 してある
程度の加速性が認め られている。
ただ し,加 速モデルが成立つには,フ ィール ド条件 と加
速ス トレス条件において,故 障モー ドと故障メカニズムが
同じであることが前提である。
6.HASTの 評価状況 について
HASTの 評価事例 は,ほ とん どが樹脂封止半導体 デバイ
ス(ICパ ッケージ)に 関するもので,プ リント配線板など
は過去において報告 された事例が少ない。以下にHASTの
評価事例として樹脂封止半導体デバイスと,前 記研究会で
実施 されたプ リン ト配線板の評価事例について報告す る。
6.1樹 脂封止半導体デバイスの評価事例 について
樹脂封止半導体デバイスのHAST結 果については,過 去
に数多 くのデータを体系的にまとめたものがあるので図5
エ レ ク トロ ニ ク ス実 装 学 会 誌Vol.6No.7(2003)543

図5.85℃85%RHに 対する観測データ と計算データ と相関寿命
に紹介する9)。これは,エ ポキシ樹脂で封止されたパッケー
ジのアル ミ配線の腐食性を見た もので,試 験データによる
故障時間と,ア レニウスモデルにより計算 した故障時間を,
それぞれ85℃85%RHの 故障時間を1と してプロッ トした
ものである。 この図で,特 に150℃ の温度条件(� 印の個
所)で は故障時間のば らつきが大きい。 また,ガ ラス転移
温度が145℃ のエポキシ樹脂 について,試 験温度130℃ と
150℃ で評価 した結果(□ 印個所),130℃ 以下 の傾向 と
150℃ 以上 の傾向に大 きな違 いが見受け られることか ら,
エポキシの封止樹脂のガラス転移温度 となん らかの関連性
があると指摘 している。
6.2プ リン ト配線板の評価事例について
前述のように,当 初はプ リント配線板でHASTは 実施 さ
れていなかったが,半 導体デバイス評価 に影響 されて,頻
繁に導入 されるようにな った。 しかしなが ら,プ リント配
線板関連のHASTの 事例については,以 前か ら公開された
データが非常に少ないのが現状である。 そこで,当 学会で
は前記研究会を設置 し,プ リン ト配線板について,材 料の
グレー ド別に体系的な評価が行われた。以下に研究会で実
施された事例をもとに概要を報告す る7)。
この評価は,ガ ラスクロス強化基材 にソルダレジス トを
塗布 した単純な構造のNEMAグ レー ドに基づいた櫛形基板
でHASTを 行 ったものである。HAST条 件 は110℃85%RH,
130℃85%RHの2条 件 と,85℃85%RHの 低加速条件の計
3条 件について評価 された。 その結果,表3に 示す ように
表3.プ リ ン ト配 線 板(FR-4)のHASTに お け る加 速 係 数
加速モデルは,ア レニウスモデルを用いて解析 されており,
同一試料では,見 かけ上の活性化エネルギは一定で,加 速
性が得 られる結果 となった。85℃ を基準 として高温度側
130℃ における加速係数のFR-4基 板で基板 メーカの違いで
差が見 られたため,約160~490倍 と幅のある結果になって
いる。 このように同 じグレー ド内で も基板メーカの違いに
よりかな りの違いがあることを示 している。現在,低 温度
側(85℃85%RH)で の試験が継続 されており,こ の結果が出
るとHASTの 有効性についてさらに明確 になると予想され
る。
なお,プ リント配線板では,加 湿時の飽和時間(吸 湿特
性)と 材料の加水分解との関連性が指摘されてお り,故 障
判定時間の設定は,そ の時間を目安に設定すべきとの見解
もある10)。ただし,重 量を測定する場合,試 料の加湿終了
544エ レ ク トロニ クス 実 装 学 会 誌Vol.6No.7(2003)

時の冷却方法(急 冷 と徐冷)に よ り重量値が異なるので,
どの方法を選択するかは検討を要する11)。
7.HAST試 験 槽の取 り扱 いに関す る留意点について
HASTは 非常 に加速性 が高 いことが影響 し,コ ンデ ィ
ションの維持管理が難 しい試験 とも言える。そこで,HAST
特有とも言える主な環境試験装置取 り扱い上の問題点と留
意点を以下 にまとめた。
(1)電 子部品に使用されている樹脂の硬化状態により故
障時間(寿 命)が 異なるので,試 料作成時のプロセス
には十分な注意が必要である12)。
(2)環 境試験装置の耐用年数,環 境試験装置の槽内の汚
染状態,使 用水の水質などにより,試 料間での故障時
間,試 験所間での故障時間が異なる結果を もたらす要
因となるので,事 前の確認が必要である7)。
(3)環 境試験装置内の残留空気(酸 素濃度など)の 影響
で,プ リン ト配線板などの樹脂材料の硬化が促進(基
板の色調に変化)さ れ7),13),異なる故障モー ドが見 ら
れるので,環 境試験装置取 り扱 いについてきめ細かい
規定が必要である。
(4)環 境試験装置,試 料からアウ トガスが発生する。 こ
れは,試 験装置槽内の材質,試 料数,試 験時間,試 験
温度,材 料のガラス転移温度などの違いによって異な
るが14),試 験への影響が懸念されている。そのため,
槽内の洗浄などによってアウ トガスの発生を抑えるこ
とが必要である。
8.お わ りに
将来 における信頼性評価の理想像 は,現 状の試験に頼 る
評価ではな く,設 計段階での信頼度予測(机 上での予測)
に基づ く評価 と考え られる。そのためにHASTは その到達
点に近づ くために不可欠な手法であ り,現 状 も含め将来に
おける開発スタンスに非常に合致 した寿命加速試験法 と考
える。 しか し,そ の試験の有効性についてはいまだに賛否
両論があ り,特 に電子絶縁材料では,評 価データと故障物
理的な側面か らの解析が不十分であり結論が出るまでには
至 っていない状況 である。現状HASTは,プ レコンディ
ションの吸湿工程として,ま たCAFの 評価試験としても導
入 されている。
今後は多様化するニーズと使用環境の変化により標準化
が難 しくな りつつある中で,柔 軟性のある評価技術の確立
が必要 とされ,加 速寿命試験法とはどうあるべきかを問わ
れる時期が来ていると考える。
なお,当 学会の加速寿命試験法検討研究会にて,プ リン
ト配線板 におけるHAST研 究ができたことは,今 後の信頼
性評価のあ り方に一石を投 じた ものであ り,各 委員に深謝
する。
(2003.8.13-受理)
文 献
1) 三 根 久(編):“ プ レ ッシ ャー ・ク ッカー ・テ ス トに関 す
る文献 調査 報告 書”,関 西電 子工 業振 興 セ ンター,1983
2) J. E. Gunn and S. K. Malik:•gHighly Accelerated Temperature
and Humidity Stress Test Technique (HAST)•h, 19th Annual
Proceedings Reliability Physics, pp. 48-51, 1981
3) 戸 井 恵子,山 本敏 男,吉 田弘 之:“ プ レ ッシ ャー ク ッカー
試 験実 施 上の問題 点(1)”,第16回 日科技 連 信頼 性 。保 全性
シンポ ジウム,pp.405-408,1986
4) 余 田 浩 好,戸 井 恵 子,山 本 敏 男,吉 田 弘 之:“ プ レ ッ
シャー ク ッカー試験 実 施上 の 問題点(2)”,第17回 日科 技連
信 頼性 ・保 全性 シ ンポ ジウム,pp.179-!84,1987
5) “2001年度 版 日本 実装 技術 ロー ドマ ップ”,JEITA(社 団法
人 電子情 報技 術 産業 協会),2001
6) 高 久 清,他:“ デ バ イ ス ・部 品 の信 頼 性 試 験 ”,信 頼 性
110番 シ リーズ第2巻,日 科技 連 出版社,1999
7) “HASTに よ る加 速 劣化 試験結 果 とそ の課題 ”,エ レク トロ
ニ クス実 装 学会,加 速寿 命試験 法検 討 研究 会,2002
8) JPCA-ET01-2002,“ プ リ ン ト配 線 板 環 境 試 験 方 法-通 則
(2001の 改 訂版)”,日 本 プ リ ン ト回路 工 業会,2002
9) D. S. Peck:•gComprehensive Model for Humidity Testing
Correlation•h, 24th Annual Proceedings Reliability Physics, pp.
44-50,1986
10) 中村 和 裕,津 久井 勤:“HASTに よる プ リン ト配 線板 の 耐
湿 性評 価 につ いて”,第12回 マ イ クロエ レク トロニ クス シ
ンポ ジウ ム(MES2002)論 文 集,pp.339-402,2002
11) 細 谷 長貞,山 市 隆:“ 電 子部 品の 信頼 性 の た めの プ レ ッ
シ ャー ク ッカ適用 の一 考 察(そ の1)”,第18回 日科 技連 信
頼性 ・保 全性 シ ンポ ジウム,pp.233-238,1988
12) 中 村和 裕:“ プ リン ト配 線 板 の耐 湿性 評 価 に お け る加速 試
験 法 の課 題”,第16回 エ レク トロニ クス実 装 学術 講 演大 会
講演 論文 集,pp.119-120,2002
13) K. Toi, H. Yoshida, T. Yamamoto and M. Yamauchi:•gHAST
(Highly Accelerated Temperature & Humidity Stress Test)
under Air and Steam•h, 22th Symposium on Reliability and
Maintainability, pp. 130-135,1992
14) 川 由 信 行,他:“ 蒸 気 汚 染 が プ レ ッ シ ャ ・ ク ッ カ 試 験 に 及
ぼ す 影 響 ”,第19回 日科 技 連 信 頼 性 ・保 全 性 シ ンポ ジ ウ ム,
pp.291-296,1989
中村 和裕(な かむら かずひろ)
昭和33年 生まれ。昭和57年,千 葉工業大学電気
工学科卒業。現在,新 光電気工業株式会社基盤
技術研究所勤務。電子部品の加速劣化試験法に
おける信頼性評価技術の研究開発に従事。
エ レク トロ ニ ク ス実 装 学 会 誌Vol.6No.7(2003)545