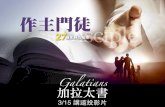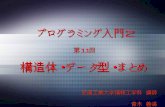H° H Ë - WordPress.com...淡路島 友ヶ島 ビャクシン イチョウ 重要文化財の本殿...
Transcript of H° H Ë - WordPress.com...淡路島 友ヶ島 ビャクシン イチョウ 重要文化財の本殿...

第一景
第三景
第五景
第七景
第二景
第四景
第六景
第八景

中ノ瀬戸
友ヶ島
❼ 第七景 紀淡海峡防備の要、友ヶ島・深山第一砲台(深山)ほか
❶ 第一景 南海加太駅(仲丁)❷ 第二景 常行寺のビャクシン(北丁)❸ 第三景 淡嶋神社と雛流し(新出)
加太浦八景加太浦八景
❻ 第六景 阿字ヶ峰行者堂(向丁)
❹ 第四景 加太春日神社(戎丁)とえび祭り
❽ 第八景 加太の漁業を守る大波止(新出)
沖ノ島
❺ 第五景 法然上人(円光大師)ゆかりの報恩講寺(大川)
南海加太線
住吉崎
城ケ崎
地ノ島
虎島
神島
紀淡海峡
田倉崎
休暇村紀州加太
加太加太
65
712
463
8
7
7
5
加太瀬戸
針祭り
第一景 南海加か
太だ
駅えき
(仲丁)
加太の交通奈良時代、平城京から紀伊(和歌山県)、淡路(兵庫県淡路
島)、阿波(徳島県)、讃岐(香川県)、伊予(愛媛県)、土佐(高
知県) 6国を結ぶ南海道の賀太駅(加太駅)が置かれた。万
葉人は「藻も
刈がり
舟沖漕ぎ来く
らし妹いも
が島(友ヶ島)形見(加太)の
浦に鶴たづ
翔ける見ゆ」「紀の国の飽あく
等ら
の浜の忘れ貝吾は忘れじ
年は経ぬとも」と加太の優れた景観に心を寄せた歌を残して
おり、田倉崎と城が崎に万葉歌碑が建つ。
江戸時代、廻かい
船せん
の拠点商港、淡路街道の起終点として交通
の要衝「左あわしま 右和歌山」などと刻まれた大きな道標
が残っている。
また、大川地区には紀州と泉州との境界を示す大川浦衆が
建立した「是より南紀伊国」と刻んだ国標や、江戸、京、丸亀な
どへ何里と刻む廻船関係の路程石標が残る。(第5景参照)
明治45年(1912)、加太軽便鉄道の開設により和歌山市
と直結された。駅舎や構内はその頃の建物として大切に保存
活用されている。
昭和31年には田倉崎燈台が点灯され、紀淡海峡から和歌
山港への航路安全を担った。
第二景 常じょう
行ぎょう
寺じ
のビャクシン(北丁)加太の天然記念物
ビャクシンはおもに温暖地の海岸線に生育する常緑樹。北
丁常行寺のビャクシンは高さ13m、幹回り4.7mを測り、およ
そ400年以上を経た県指定天然記念物の巨木である。
その他の天然記念物友ヶ島(沖ノ島)の深
しん
蛇じゃ
池いけ
には熱帯性のシダと寒地性のスゲな
どが混成する植物群落があり県天然記念物に指定されている。
また加太駅西方の山裾に高さ20m、幹回り3mを測るイチョ
ウの巨木があり、指定こそ受けていないが春の芽吹き、秋の
黄葉は住民だけでなく観光客の眼を楽しませている。
第三景 淡嶋神社と雛流し(新出)創建
神じん
功ぐう
皇こう
后ごう
が三さん
韓かん
出兵の帰路、紀伊水道で嵐に合った際神
に祈りを捧げたところ、友ヶ島(神島)に無事にたどり着き、少すくな
彦ひこ
名な
神しん
を祀まつ
る祠ほこら
に書物を奉幣した。
その後仁徳天皇が神かみ
島じま
から現在の地へ社を遷うつ
したとされ
ている。
ひな流しが有名で、3月3日が近くなると6千体の雛人形が
本殿に祀られる。婦人の守り神としても知られ、婦人病・安産・
子授けなどにご利益がある。そして境内には恋愛のパワース
ポットと呼ばれる一角があり、若い女性のお参りが絶えない。
例大祭2月8日の針
はり
祭り、3月3日のひな流し、4月3日の春の例
大祭、7月31日の夏祭り、10月3日の甘酒祭りなどがある。
第四景 加太春日神社(戎丁)とえび祭り加太地区の氏神
平安時代の初めころ作成された『紀伊国神名帳』に「正しょう
一いち
位い
春日大神」とみえるが創建は定かでない。
『向むかい
井け
家もん
文じょ
書』によれば鎌倉時代には住すみ
吉よし
神じん
社じゃ
とも呼ば
れ、室町時代には春か す が
日明みょう
神じん
と呼ばれていた。安土桃山時代に
現在地で再建された本殿は国指定の重要文化財である。
例大祭「えび祭り」伊勢えびを彫りこんだ本殿の蟇
かえる
股また
が象徴するように氏子は
初夏によく獲れる伊勢えびを神殿に供えたことに由来する。
渡と
御ぎょ
祭さい
は、もともと各丁から繰り出す「大漁のぼり」を御み
霊たま
代しろ
としていたが大正時代に神しん
輿よ
に替わり、現在では5月第
3土曜日に天狗、子供神輿、鬼舞、獅子舞、長なぎ
刀なた
振り、神輿、稚ち
児ご
行列など総勢500人が町内を巡行する。未指定ながら重
要な無形民俗文化財である。
大川 紀伊国碑
田倉崎 万葉歌碑
城ヶ崎 万葉歌碑
淡路島
友ヶ島
ビャクシン
イチョウ
重要文化財の本殿
2
加太浦八景 3
加太浦八景

観音堂
吾妻屋旧本館
加太漁業組合
北波止場
友ヶ島行発着所
万葉の碑淡嶋神社
阿字ヶ峰行者堂
淡嶋神社
淡嶋神社
N
S
E
ESWS
NW NE
W
❸
❻
❽
加太浦八景詳細マップ
鯛の一本釣(通年)
わかめの天日干し(2~4月)わかめの天日干し(2~4月)
JAわかやま加太支店
市役所加太支所
旧加太警察署庁舎
迎之坊(向井家)
加太中学校
観光案内所
加太小学校加太幼稚園
光源寺
稱念寺
阿弥陀寺郵便局
幸前家
堤川
大谷川
旧◯治醤油 消防署前の道しるべ
徳本上人の石碑
万葉の碑
道しるべ
推定樹齢200年、高さ20m、幹周3mの大きなイチョウの木
多目的広場
加太春日神社
南海加太駅
常行寺
ビャクシン
至 大川・大阪 休暇村紀州加太・報恩講寺
南海加太線
至 和歌山市駅
至 R26・和歌山市街
加太海水浴場
❷❹
❶
65
●休暇村紀州加太
バス停
至 加太
●オートキャンプ場
城ケ崎
至
報恩講寺
大阪
大阪府
至 休暇村紀州加太
柚ノ浜
65
報恩講寺
県境
大川八幡神社
嘉永橋
「是より南紀伊国」の碑
❺
❼
阿振川
65
65
7
❶第一景 南海加太駅
❷第二景 常行寺のビャクシン
❸第三景 淡嶋神社と雛流し
❹第四景 加太春日神社とえび祭り
❺第五景 法然上人ゆかりの報恩講寺
❻第六景 阿字ヶ峰行者堂
❼第七景 紀淡海峡整備の要、友ヶ島・深山第一砲台ほか
❽第八景 加太の漁業を守る大波止
わかめの天日干し(2~4月)
海水浴場
4
加太浦八景 5
加太浦八景

加太は古代以来交通のまた国防上の要衝として極めて重要な位置を占めてきたため、各時代の政治は加太におおいに関心を抱いてきた。とくに、江戸時代から明治時代にかけては国策として加太の社会基盤整備に力が注がれた。このた
め加太は和歌山県の西北端にもかかわらず漁業と商業が、また軍需経済も大いに発達してきた。その姿は加太浦八景としてだけでなく、「土蔵」を数多く残す古い町並みや、和歌山市合併前の加太警察署の貴重な遺構として国登録文化財となっている近代洋風建築「旧加太警察署庁舎(中村家住宅主屋」(仲丁)、また、同じく観光華やかなりし頃の伝統的な和風建築として「吾妻屋旧本館」(新出)などの諸施設のほか、町内のおいしいものの食べ歩きや和歌山藩の儒学者で「紀伊続風土記」編纂、和歌山藩の海防を建議した仁井田好古の光源寺墓所へも足を運んでほしいものである。
コラム
加太砲台跡
蓄養施設
大波止
大波止
天保年間の大波止
距離をきざんだ道標
大川八幡神社友ヶ島(休暇村より望む)
第七景 �紀淡海峡防備の要、友ヶ島・��深山第一砲台(深山)ほか
和歌山藩の海防施設江戸時代の終わり、欧米列強の国々は日本に鎖国を解くよ
う圧力をかけてきた。紀淡海峡は大阪湾の玄関口に当たりロ
シアの軍船などが大阪、神戸を目指した。
和歌山藩はこれらを警備するため、勝海舟など幕府の指導
を求め加太浦や友ヶ島の海岸線に砲台や番所を築いた。
明治の洋式要塞これを受け継いだ明治政府は淡路島の由
ゆ
良ら
、友ヶ島、加
太にコンクリート、レンガ積みの洋式近代要塞を明治22年
(1889)から同38年にかけて建設した。友ヶ島には5か所
の砲台(沖ノ島)と砲塁(虎島)、加太地区には深み
山やま
第一砲台
(休暇村紀州加太 地内)、加太砲台(加太少年自然の家 地
内)、田倉崎砲台(同前)と付属施設が建設された。これらの
砲台には28cm榴りゅう
弾だん
砲ほう
、27cmカノン砲などが配備された。
深山砲台の28㎝榴弾砲は日露戦争時には、遼東半島のロ
シア軍の旅順要塞203高地(現、中華人民共和国)の攻略に
出動している。
第八景 加太の漁業を守る大おお
波ば
止と
(新出)
築堤の歴史と規模大型廻船や漁船の安全を図る大波戸(止)は和歌山藩直
営事業として天保9年(1838)から3カ年をかけ128間(約
230m)が建設された。
さらに大正5年(1916)には大波止延長工事が実施され、
その後も延長、嵩上げなど大波止整備がすすめられてきた。
加太漁業の歴史紀淡海峡の早い潮流の恩恵を受け豊富な漁業資源をもつ
加太の漁業は、大谷で出土した弥生時代の釣り針が物語るよ
うに古くから連綿と受け継がれてきた。江戸時代には千葉県
沖へ鰯漁に出掛けていることを示す享保19年(1734)の史
料などが残っている。現在では鯛の一本釣りを中心に様々な
魚介類が水揚げされている。
蓄養施設と波止釣り大波止内側南端には漁師や仲買人の負担軽減を図る大規
模魚介類蓄養施設(約15㎡の水槽18基をもつ総床面積約
880㎡)が平成20年に整備され市場への出荷も今まで以上
に円滑化された。尚、隣接して魚介類の直売施設も設置され
ている。大波止ではメバル・アジ・グレ・ガシラのほか時には
マダイ・ハマチなど大物も釣れるので大人から子どもまで年
間25,000人の釣り客が訪れる人気スポットとなっている。
第五景 法ほう
然ねん
上しょう
人にん
(円えん
光こう
大たい
師し
)ゆかりの �報恩講寺(大川)浄土宗報恩講寺と徳本上人名号碑
専修念仏を説き旧仏教派の圧力で承しょう
元げん
元年(1201)に讃
岐国(香川県)へ配流されるが同年12月赦免された法然ゆか
りの名めい
刹さつ
。本尊阿弥陀如来座像は市指定美術工芸品である。
帰京の途次、遭難し村人に助けられた法然は大川を去るに
当たり谷深くに桜を見つけ自像を刻み堂に残したという。
日高郡出身で江戸時代後期の浄土宗高僧として諸大名か
らも崇敬を受けた徳とく
本ほん
上しょう
人にん
も本寺を訪れたのか、徳とく
本ほん
揮き
毫もう
に
なる「南無阿弥陀仏」名号碑があぶり坂の海岸に建っている。
大川浦の石造物大川浦を拠点とした廻船業者等は大川八幡神社、住吉神
社に宝暦8年(1758)、同13年、文化5年(1808)、文政9年
(1812)を刻んだ立派な灯とう
篭ろう
を奉納するとともに、文政4年
の国境碑、同8年には大川浦から江戸や丸亀など15か所まで
の距離を刻んだ標ひょう
柱ちゅう
、市指定建造物の嘉永7年(1854)架橋
の石橋、嘉か
永えい
橋ばし
を残している。
第六景 阿字ヶ峰行者堂(向丁)葛かつら
城ぎ
修しゅ
験げん
序じょ
品ほん
・一の宿役小角(えんのおづぬ、奈良時代の修験者)が開設したと
いう葛城修験二十八宿は友ヶ島(虎島)に始まり和泉山脈を
東へ金剛山、さらに金剛葛城山系を北へとり二上山を越え
大和川畔の亀が瀬にいたる山中に28か所の法華経経塚を営
んだ、現在も4月に京都聖護院の修験者が行に訪れる。修験
道の行ぎょう
場ば
となっている。
「迎之坊」と行者堂虎島には序品経塚のほか合わせて5か所の行場があり、拠
点となる加太には「迎之坊」(仲丁、向井家)、阿あ
字じ
ヶ峰みね
行者堂
などの諸施設があり今も活動が盛ん。
しかし、中世に一の宿と呼ばれた「鳩はと
留どめ
八はち
幡まん
」は北丁の東
の山裾にその跡を留め、同じく「加か
陀だ
寺でら
」も廃寺となり、加太
駅の北東がその跡といわれている。
旧加太警察署庁舎
吾妻屋旧本館
徳本上人名号碑
報恩講寺
田倉崎砲台跡
深山第一砲台跡深山第一砲台跡
6
加太浦八景 7
加太浦八景

加太地域の行事
開催日 開催行事 開催場所
和歌山市の加太っちゅう、海辺にある村でむかしにあった「タヌキの恩返し」ちゅう話でもしょうかえの。
この村にたんがい(たいへん、とても)仲のええとっしょり(年寄り)夫婦が住んでたんやいしょ。天気のええ日にゃ沖へ出て魚
いお
をば釣ってね、冬は山で柴をば刈って細々暮らしてたんやて。とっしょり夫婦の舟は、じきにアカ(海水)が浸み込んでくるよなやつで、そのたんびに手桶でかき出さんとあなんような、たんがい(たいへん)ごったい舟(ごったいせん=古い舟)やったんやいしょ。ほて、いつもとおんなじよに沖で釣ってたある日のこと、一匹のタヌキがパシャパシャ音をば立てて溺れてたんやいしょ。ほいで助けたったんやと。ほいだらどーよ(するとどうだろう)、そいつぁ、酔うた拍子に海に落ちてもて、淡路島から流れて来た柴右衛門タヌキやったんやいしょ。 あくる日、元気になったタヌキは夫婦が目ぇ覚ます前に、いてないよになってもたあったんやて。
その年の冬、夫婦はごうせに(一生懸命に)柴刈りをばしてたけども、ちったかい(少し)しかとれなんで売りに行くほどもなかったんやいしょ。ほいたら毎晩夫婦の家の表に、よーうさん(たくさん)柴が積まれるよになったんやて。その柴は火付きが良かったさけに、めっぽかいよーさん(びっくりするほどたくさん)売れたんやて。
だんだんぬくくなって春になってぇ、こなえだ(以前)助けた柴右衛門タヌキが来たんやいしょ。ほいで「春になったさけ柴はもうしまいやで。わしは淡路へ帰らよ。ほいでまいっこ(もうひとつ)、浜に新し舟をば繋いじゃあるさけ、明日からはそれ使いよしよ。」ちゅうて淡路へいんでもた(帰ってしまった)んやて。
それからとっしょり夫婦はその舟をばつうこて(使って)、魚をめっぽかい(びっくりするほど)とったんやと。
おしまい
淡路の柴し ば え も ん
右衛門タヌキが恩返しをする話
発行 平成25年2月 加太地域活性化協議会 まちづくりのPR活動グループお問い合せ先 TEL.073–459–0003
1月1日
1月9日〜11日
2月8日
2月中旬
3月上旬
3月3日
3月中旬
4月3日
4月28日
5月第3土曜日
6月末
7月7日
7月31日〜8月3日
7月31日
10月3日
10月中旬
11月上旬
11月22日〜24日
12月31日
歳旦祭
初戎祭
針祭(針供養)
紫陽花植樹祭
加太の桜鯛祭り
雛祭(ひな流し)
島開き
春の大祭
春会式
例大祭御渡祭(えび祭り)
浜開祭(海開き)
行者講夏祭り
夏祭(夏越しの祭)
大祓祭(芧の輪くぐり)
秋の大祭(甘酒祭り)
加太の竹燈夜
加太の紅葉鯛祭り
秋の大会式
除夜祭(庭火の神事・焼納祭)
淡嶋神社・加太春日神社・行者堂
加太春日神社
淡嶋神社
加太森林公園
新出駐車場
淡嶋神社
友ヶ島
淡嶋神社
報恩講寺
加太春日神社
加太海水浴場
行者堂
淡嶋神社
加太春日神社
淡嶋神社
多目的広場
新出駐車場
報恩講寺
加太春日神社
加太の民話加太の民話