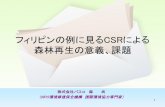MCMCアルゴリズムによるロジットモデルの ベイ …MCMCアルゴリズムによるロジットモデルの ベイズ推定に関する若干の考察 田島博和 1.はじめに
GISによる「地域の知」の活用に関する一考察harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hijiyama-u/file/12597/20190531111329/05谷川宮次.pdf ·...
Transcript of GISによる「地域の知」の活用に関する一考察harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hijiyama-u/file/12597/20190531111329/05谷川宮次.pdf ·...

43
比治山大学短期大学部紀要,第54号,2019Bul. Hijiyama Univ. Jun. Col., No.54, 2019
1.はじめに
今から 10 年前,日本学術会議(地域研究委員会)は「『地域の知』の蓄積と活用に向けて」という提言で,地域に内在する「地域の知」に注目し,これを蓄積,整理,活用,公開する制度改革,技術開発,さらにこれらの運営体制の整備が必要であるとした。「地域の知」とは,同会議によると,「地域の状況や人々の暮らし方などに関する地域に関わる情報,知識,そして知恵。行政組織や研究機関が蓄積してきた情報はもちろん,地域に生きる人々がもつ広く深い情報,知識,知恵も含まれる。地域の知は,単なる文字ないし数字などの記号だけでなく,画像,音声など様々な情報形態が想定される」[1]ということである。
地域に生きる人々がもつ広く深い情報,知識,知恵という「経験知」に限らずとも,その地域もしくは自治体の Web ページを閲覧しただけでも,地域に関する情報を得ることができる。また,日本でもオープンデータへの取り組みが進められており,各地域の情報については e-stat(政府統計ポータルサイト)の国勢調査データ,国土交通省国土政策局国土情報課の国土数値情報ダウンロードサービス等の各省庁による公開データをほぼ無料で得ることができる。さらには,「コンビニまっぷ」等のような民間企業団体が提供する地域関連データも得ることができる。
しかし,これらのデータは様々な所有者の Web ページ上に散在しており,しかも,必ずしも,パソコン等の情報機器に取り込み,直接的に他のデータと関連付けることができるようにはなっていない。このあたりの議論はオープンデータの進捗と関連するが,一部の先進的な地域・自治体・企業等を除いて,多くの地域・自治体・企業等は pdf ファイルを Web ページにリンクしたり,Web ページそれ自体にデータを書き込むことによって情報提供を行っているのが実状である。
本稿では,このような状況を前提として,特定の地域の地理空間をベースにして目的志向的な知識を得るために,オープンソースの GIS(Geographic Information Systems:地理情報システム)であるQGIS[2]を使い,必要なデータを層状に積み上げることによって関連付け,その成果を「地域の知」につながる情報として可視化することを試みる。
また,このような試みはすでに地理分野だけでなく,森林,都市計画,防災,マーケティング等の多くの分野でなされているが,本稿は,オープンソースとしての QGIS とオープンデータを含めた地域データの接続可能性を確認しながら進めることで研究ノートとしている(1)。
* 1 総合生活デザイン学科註 1 本稿では,QGIS の操作説明を行うことはない。それについては,参考文献[3][4][5]等の市販本や Web 上で詳細にかつ親切に記述されている。
GISによる「地域の知」の活用に関する一考察
―オープンソース・オープンデータの利用を含めて―
谷 川 宮 次* 1

谷 川 宮 次
44
2.QGIS と地域データ
2. 1.QGIS というオープンソース
高機能の GIS ソフトウェアは以前から複数存在するが,多くが非常に高額であるため,気軽に導入することは困難であった。それに対して,本稿で利用する QGIS は無償提供されるオープンソースであり,多種類のプラットフォーム(Windows, MacOSX, Linux, Android 等)で動作する。
QGIS は 2002 年から開発が開始されているが,バージョン 1.x では,日本語対応等に課題があった。しかし,2013 年にバージョン 2.0 以降にその課題も解決され,動作も安定していることから,GIS の入門的教育から各種業務まで,幅広く利用されるようになった。また,多くのプラグインによって様々な解析ツールが提供されており,オープンデータと合わせて使うと,業務の第一歩として最小限のコストから始めることができる。ちなみに本稿では,Windows 版 QGIS のバージョン 3.2.2 を使用している。
QGIS の画面は図 2-1 のとおりであり,グラフィカルなユーザイン夕フェースを持ち,多くの GIS に共通する機能を本体のコア機能と多くのプラグインで提供している[6]。
QGIS として必要な地理空間情報の作成,編集,可視化,解析の機能を使用することができ,商用システムと遜色ない多機能なシステムになっている。また,プラグインと呼ばれる後から追加機能をインストールできる仕組みもあり,ユーザの目的に応じて弾力的に表現できる。
2. 2.地域データの活用
GIS を使用する上でデータは当然不可欠である。あらかじめ GIS で直接的に使用可能なデータを入手できれば,GIS でデータを作成する労力を省くことができる。また,入手できるデータには,有償と無償があるが,有償のデータは GIS ですぐに使用できるよう加工および調整されていたり,精度が高い等の特徴がある。無償データについては,近年,オープンデータの整備が国・地方自治体等で進みつつ
図 2-1 QGIS の画面

GIS による「地域の知」の活用に関する一考察
45
ある。総務省[7]によると,オープンデータは「営利目的,非営利目的を問わず二次利用可能なルールが適
用されたもの」「機械判読に適したもの」「無償で利用できるもの」と定義されている。日本においては,2012 年 7 月の「電子行政オープンデータ戦略」の決定,2013 年の G8 サミットでの「オープンデータ憲章」を契機として,国,地方自治体等のオープンデータへの取り組みが活発になっている。オープンデータとして公開することで,より多くの人々に活用され,その潜在的な価値が引き出される。GIS でしばしば使われるオープンデータの例は表 2-1 のとおりである。
表 2-1 GIS で利用されるオープンデータの例サイト名 提供機関 主な提供データ データ形式等
基盤地図情報 国土交通省国土地理院 等高線,行政区画,道路縁,建物の外周線等
XML ドキュメント利用登録
国土数値情報 国土交通省国土政策局国土情報課
海岸線,小学校区,避難施設,観光資源,バスルート等
shape ファイル等
政府統計の総合窓口(e-Stat)
総務省統計局 国勢調査,経済センサス,学校基本調査等
shape ファイル,テキストデータ等
気象庁 国土交通省気象庁 気象データ,震源リスト等 テキストデータ等地理院地図 国土交通省国土地理院 標準地図,淡色地図,白地図,
航空写真閲覧方式
OpenStreetMap OSM 財団(運営に関与) 道路地図などの地理情報データ
「自由な地図」を「みんなの手」で作る世界規模のプロジェクト
これらの中で,地理空間情報に関連するデータ提供については,2007 年に策定された地理空間情報活用推進基本法を契機に国土地理院[8]の「基盤地図情報」が Web 上で無償公開されるようになり,さらに 2013 年に「地理院地図」に更新され利便性が高まった。オープンデータ化については,地図や空中写真などの「地理院タイル」が「国土地理院コンテンツ利用規約」にもとづき,二次利用可能になった。また,オープンデータは公共のデータに限らず民間主導で作成されたものも存在する。代表的なものとして OpenStreetMap[9]がある。これは,道路地図などの地理情報データを誰でも利用できるよう,フリーの地理情報データを作成することを目的としたプロジェクトである。
ただし,利用に関していえば,「地理院地図」にも,さらには一見して無料で自由に使えそうなGoogleMap にも利用規約がある。例えば,GoogleMap は Web 地図のスクリーンショットの使用は違反であり,動く埋め込み地図になっている必要がある。また,「地理院地図」は申請しなくても研究発表や研究論文には使えるが,Web ページへの貼り付けはサイズや枚数の制限を超えると申請する必要がある[10]。
現時点で申請せずに使える地図には,自分で作った地図以外は OpenStreetMap がある。この場合も出典を明示(「OpenStreetMap and contributors CC-BY-SA」または「背景地図には OpenStreetMap を利用しています。CC-BY-SA」等々)する必要がある。
しかし,地域データには,PDF ファイルとして編集されているもの,Web ページに表として貼り付けられたもの,Web ページに直接記述されている文字のように,単に閲覧のための文字列や数値も非常に多い。これらが GIS のデータとして必要な場合,一つ一つコピーするなどして csv ファイル等を作成することになる。

谷 川 宮 次
46
3.QGIS による主題図の作成
GIS を使って地理空間情報として目的志向的な知識を得るプロセスでは,まず,背景図をベースとして置き,その上に,主題図を作成するために,必要な情報(地域データ等)を積み重ねて描く。
背景図は,GIS においてはベースマップとも呼ばれ,当該の地域の地図の表示位置や周辺環境を視覚的に提供する役割を持ち,主題図全体の見やすさやわかりやすさにも大きな影響を与える。
主題図とは,背景図の上に目的志向的に任意の情報をレイヤ(層)として積み重ねて作成される情報である。地域の安全・安心マップ,ハザードマップ,観光マップ等も利用する人を想定し,利用シーンを考慮した目的を持った主題図ということができる。主題図作成の際は,その目的を明確にするとともに,利用する情報,データを検討し,情報を伝達する相手を意識して色彩や表現等を工夫することが求められる。
本稿では,地方の小規模都市である山口県柳井市の中心部を対象とした私流の「洪水避難マップ」づくりを,表 3-1 のようなプランをもとに,先ほど紹介した QGIS を使って地図表現の手順を示す(2)。
本稿では,表 3-2 のようなオープンデータ等を使用して,加工,表示,解説を進めていく。これらのデータは,そのまま GIS に読み込める形式で公開されているものもあれば,前処理が必要なものもある。まずは,日本全国を広範囲にカバーしているタイル形式の地図を背景図として読み込み,その上に,洪水避難マップに必要なデータをレイヤとして,それぞれ表示し重ねてみよう。洪水避難マップに至る可視化の作業フローは図 3-1 のとおりである。
表 3-1 主題図作成のプラン作成物 山口県柳井市中心部を対象とした私流洪水避難マップ
作成の背景 柳井市洪水避難地図(洪水ハザードマップ)[11][12]は,山口県が,柳井川,土穂石川,灸川について指定した浸水想定区域に基づいて,3 河川が大雨によって増水し,堤防が決壊したり,水があふれて洪水となる場合の浸水の深さや区域などの浸水情報,また避難場所や避難方法などの避難情報等を掲載した地図のことであり,すでに「柳井市洪水ハザードマップ【冊子】」「柳井市洪水ハザードマップ【地図】」が作成・公開されている。
作成方針 この柳井市洪水避難地図(洪水ハザードマップ)に倣って,私流に洪水避難マップを作成する。
使用するデータ 表 3-2 のとおりであり,主としてオープンデータを使用する。
ただし,本稿では QGIS[2]を使った関連データのレイヤの積み重ねとその成果の可視化を試みることが目的であり,また紙幅の都合もあり,使用するデータは限定される。
表 3-2 マップづくりに使用するオープンデータ公開元 取得範囲 データ種別 提供形式
地理院地図(国土地理院)[8] 全国 標準地図,写真 地理院タイル国土数値情報(国土交通省)[13] 山口県 浸水想定区域 shape ファイル防災情報(柳井市)[12] 柳井市 指定避難所 pdf ファイルコンビニまっぷ(株式会社アットステージ)
柳井市 店名,住所等 html ファイル
NAVITIME(ガソリンスタンド一覧)
柳井市 店名,所在地等 html ファイル
註 2 「私流」としているのは,本稿の意図が防災や災害の専門知識をもとにハザードマップを提供することでは なく,QGIS の利用可能性を探ることにあるからである。

GIS による「地域の知」の活用に関する一考察
47
図 3-1 洪水避難マップの作成作業フロー
図 3-2 山口県柳井市あたりの地域図(左)と柳井市の中心部(右)
(1)背景図:地理院地図
GIS の背景図として,本稿では国土地理院の地理院地図を利用する。地理院地図は,国土地理院がインターネットをとおして提供している地図サービスである。地理院地図で配信している地図や画像などのデータのことを「地理院タイル」という。この閲覧のために,「QGIS で地理院地図を追加する方法」[4]
を参考にして QGIS で「地理院タイル」を利用できるようにした。図 3-2 は「地理院タイル」の「標準地図」で描いた柳井市あたりの地域図(左)と柳井市の中心部(右)である。
(2)浸水想定区域:国土数値情報
ここから背景図上に目的志向的に地域データを積み重ねて主題図を作成する。

谷 川 宮 次
48
国土数値情報として公開されている柳井市及びその周辺の浸水想定区域をベースマップに重ね合わせる。国土数値情報は,地形,土地利用,公共施設,道路,鉄道など国土に関する地理的情報を数値化したものであり,国土交通省国土政策局の Web サイトから無料で提供されている(3)。
データ項目から山口県の浸水想定区域をタウンロード・解凍するとshape ファイルでの浸水想定区域データ(A31-12_35.shp)が得られるので,それを QGIS で読み込み,ポリゴンを融合し 50%透過して表示すると,図 3-3 のように背景図上に浸水想定区域が描かれる。本来は河川の氾濫は単なる特定地域の浸水だけでなく,土砂災害の危険も鑑みる必要があるが,本稿では河川の氾濫による浸水のみとしている。
(3)指定避難所
柳井市の Web ページに「柳井市洪水ハザードマップ」と「柳井市洪水ハザードマップ【地図】」がpdf ファイルで載せられている。本稿掲載時期には,柳井市洪水ハザードマップに記載されている避難場所の変更及び浸水想定区域内の要配慮者利用施設の追加があるということで,「洪水ハザードマップ変更点(指定緊急避難場所・指定避難所)」がやはり pdf ファイルで載せられている。本稿では,この変更を含めた避難場所(pdf ファイル)について,指定避難所の一覧(表 3-3)を利用する。このような情報をレイヤとして主題図に積み重ねるためには,座標データを含めた csv ファイルを必要とする(4)。
この表には住所としての位置情報はあるが,座標データはないので,住所あるいは施設・場所名から座標を導く必要がある。そのために,この表を利用して,表 3-4 のような Excel シートを作成する。
図 3-3 柳井市中心部の浸水想定区域
表 3-3 柳井市の指定避難所一覧(平成 30 年 8 月 31 日取得)
(以下略) 出典 http://www.city-yanai.jp/uploaded/attachment/6863.pdf
註 3 操作手順は参考文献[5]117 〜 119 頁に丁寧に記述されている。註 4 ここからの操作手順は参考文献[5]52 〜 61 頁に丁寧に記述されている。

GIS による「地域の知」の活用に関する一考察
49
表 3-4 Excel 形式の指定避難所一覧施設名 住所 想定収容人数
1 柳東小学校体育館 山口県柳井市柳井 964-1 3602 柳東文化会館 山口県柳井市柳井 1029 2503 柳井小学校体育館 山口県柳井市柳井 3680-4 6204 アクティブやない 山口県柳井市柳井 3718-16 320
(以下略)
(以下略)
ただし,想定収容人数の単位を外して計算可能にし,住所に「山口県柳井市」を加えた。また,本来なら「電話番号」等が必要であるが,説明を簡略化するために外した。
表 3-4 の Excel データを CSV形式に変換して,「CSV アドレスマッチングサービス(東京大学空間情報科学研究センター)[14]を利用して,住所から地図上の座標データを得ると,表 3-5 のような所在地情報が得られる。この中で,「fX」列は経度(東経),「fY」列は緯度(北緯)を表し,「iConf」列は変換の信頼度(3 〜 5 で 5 が高い)を表し,「iLvl」列は変換された住所の階層レベル(1 〜 7 で 7 が詳細)を表す。ただし,いくつかの施設の座標データ(fX, fY)が実際の位置とは少しずれていたので,Google Mapを使って,緯度と経度を検索して訂正している。この csv ファイルを GIS のレイヤとして重ねると図3-4 のようになる。
(4)コンビニエンスストアとガソリンスタンド
災害時に国の要請に応じて緊急支援を行う「指定公共機関」に,全国に店舗がある大手コンビニチェーンなど 7 社が平成 29 年 7 月 1 日付で追加指定されている。「指定公共機関」とは,災害対策基本法に基づいて指定されるもので,災害時に国の要請に応じて,ライフラインの復旧や支援物資の輸送などの緊急対応を行うこととしている。
ここでは,このコンビニエンスストアと,既に指定されているガソリンスタンドの位置情報をレイヤとして積み重ねる。
図 3-4 指定避難所の追加
表 3-5 座標データを追加した指定避難所一覧(csv ファイル)

谷 川 宮 次
50
表 3-6 と表 3-7 のようにこれらの情報はhtml ファイルに埋め込まれているので,一つ一つコピーして csv ファイルを作成する。そして,先述の CSV アドレスマッチングサービスと GoogleMap による若干の修正により,それぞれ表 3-8 と表 3-9 の csv ファイルを得る。
これらを QGIS にレイヤとして追加して積み重ねると,図 3-5 のような独自の洪水避難マップを描くことができる。
(以下略)
(以下略)
表 3-6 柳井市のコンビニマップ
(以下略) 出典 こんびにマップ https://cvs-map.jp/city/35212
表 3-8 座標データを追加したコンビニエンスストア情報
表 3-9 座標データを追加したガソリンスタンド情報
表 3-7 柳井市のガソリンスタンド
(以下略)出典 NAVITIME 柳井市のガソリンスタンド一覧https://www.navitime.co.jp/category/0801/35212/

GIS による「地域の知」の活用に関する一考察
51
(5)私流洪水避難マップ
さらに便利に,QGIS のバッファ作成機能を使用して,措定避難所から半径 1km 圏内を図示すると図 3-6 のようになる。つまり,指定避難所までの避難距離を直線で 1km として表しているので,任意の避難場所の包含エリアがわかる。また,縮尺を 1/25,000 図にし,スケールバー,北マーク,凡例を加えて,私流洪水避難マップとして完成させている。
図 3-5 コンビニエンスストアとガソリンスタンドの情報の追加
図 3-6 私流洪水避難マップの完成

谷 川 宮 次
52
4.まとめ
図 3-6 によって,目的とする主題図が完成したことになるが,QGIS はいろいろな情報を層状に重ねることによって,可視化された自分なりの新しい情報を表現することができる。また,この図に「経験値」が加わると,「あの避難所に行くためには,この道が近いが夜通ると危ないので,あのコンビニに寄ってあちら側を迂回する道を通ろう」などという経路設計ができる。
本稿では,特段の新規性があるわけではないが,地方の小規模都市を対象に GIS のオープンソースである QGIS とそれが扱うデータの活用について述べた。独自の洪水避難マップとして視覚的に把握できることで,「地域知」につながる情報の可視化を可能とした。
【参考文献】
[1]日本学術会議(地域研究部会),提言「『地域の知』の蓄積と活用に向けて」(平成 20 年(2008 年)7 月 24 日),http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-t60-2.pdf,2018 年 01 月 23 日取得.
[2]QGIS の Web サイト http://www.qgis.org,2018 年 01 月 23 日取得.[3]朝日孝輔・水谷貴行稿,地理空間情報入門:QGIS を使って,岩波データサイエンス(岩波データ
サイエンス刊行委員会編),Vol. 4, 5 〜 30 頁,岩波書店,2016 年.[4]chiakikun のブログ,QGIS で地理院地図を追加する方法,https://chiakikun.hatenadiary.com/
entry/2018/05/12/182139 2018. 08. 23 取得.[5]橋本雄一編,QGIS の基本と防災活用(二訂版),古今書院,2017 年.[6]QGIS ユーザガイド https://docs.qgis.org/2.14/ja/docs/user_manual/index.html,2018 年 08 月 23
日取得.[7]総務省,オープンデータとは,http://www.soumu.go.jp/menu_seisaku/ictseisaku/ictriyou/
opendata/index.html,2018 年 01 月 27 日取得.[8]国土交通省国土地理院,基盤地図情報サイト,http://www.gsi.go.jp/kiban/index.html,2018 年 02
月 03 日取得.[9]OpenStreetMap Japan,自由な地図をみんなの手で,https://openstreetmap.jp/,2018 年 01 月 27
日取得.[10]国土地理院,承認申請 Q & A,http://www.gsi.go.jp/LAW/2930-qa.html,2018 年 08 月 23 日取得.[11]柳井市洪水避難地図(洪水ハザードマップ),http://www.city-yanai.jp/soshiki/11/hazardmap.
html,2018 年 01 月 27 日取得.[12]柳井市「ご自宅等の防災地図情報をご確認ください」,http://www.city-yanai.jp/site/bousai/
chizu.html,2018 年 10 月 07 日取得.[13]国土交通省国土政策局国土情報課,国土数値情報ダウンロードサービス,http://nlftp.mlit.go.jp/
ksj/,2018 年 02 月 03 日取得.[14]東京大学空間情報科学研究センター,CSV アドレスマッチングサービス,http://newspat.csis.
u-tokyo.ac.jp/geocode/modules/addmatch/index.php?content_id = 1,2018 年 02 月 03 日取得.[15]伊藤裕之稿,地理空間情報のウェブ配信一オーブンデータ,オープンソース,そしてオープンイ
ノベーション-,行政&情報システム(行政情報システム研究所),49-54 頁,2016 年 4 月号.(受理 平成 30 年 10 月 31 日)

GIS による「地域の知」の活用に関する一考察
53
GISによる「地域の知」の活用に関する一考察
―オープンソース・オープンデータの利用を含めて―
谷 川 宮 次
要 旨
地域についての必要な情報は,その地域もしくは自治体が発信している Web ページ,国・地方自治体等によって提供されるオープンデータ,さらには民間企業団体が提供する地域関連データからも得ることができる。本稿では,オープンソースの GIS である QGIS を使い,これらのデータを層状に積み上げることによって関連付け,その成果を「地域の知」につながる情報として可視化することを試みる。
キーワード:地域の知,GIS(地理情報システム),オープンソース,QGIS,オープンデータ
A Study on Utilization of “Local Knowledge” by GIS - Including the Use of Open Source and Open Data -
(Received October 31, 2018)