環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要 …...- 1 - 環太平洋パートナーシップ協定(TPP協定)の概要 内閣官房TPP政府対策本部
パートナーシップがつくる 持続可能な自然共生社会Ÿº調講演... · •...
Transcript of パートナーシップがつくる 持続可能な自然共生社会Ÿº調講演... · •...

パートナーシップがつくる持続可能な自然共生社会
東京大学サステイナビリティ学連携研究機構長・特任教授
公益財団法人地球環境戦略研究機関理事長
武内和彦
生物多様性民間参画パートナーシップ 第7回会員会合
2018年2月19日(月)13:00~16:45
経団連ホール南(千代田区大手町)
1

持続可能な社会と自然共生社会
• 21世紀環境立国戦略(2007年閣議決定)で、低炭素社会、循環型社会、自然共生社会の統合による持続可能な社会を提唱
• 生物多様性条約第10回締約国会議(COP10) で採択された「愛知目標」の長期目標は「自然と共生する世界の実現」となる
• 東洋的自然観に立つ自然共生社会の概念には、先進国の批判もあったが、アフリカなど多くの開発途上国が積極的に支持
• COP10では環境省と国連大学が提唱したSATOYAMAイニシアティブが採択され、国際パートナーシップ(IPSI)が創設される
• SATOYAMAイニシアティブは、生物多様性条約の第二の目的である「生物資源の持続的利用」の理念を具体化するもの
2
SATOYAMAイニシアティブ国際パートナシップ第4回定例会合(IPSI-4) 2013年9月 於・福井県
↑越前市 白山コウノトリ米水田白山小学校 →

東日本大震災と自然共生社会
• 東日本大震災は、私たちに、改めてわが国の自然が豊かな恵みである一方、大きな脅威でもあることを再認識させた
• 里山里海の連環による地域再生の考え方は、とくに東北地方の沿岸部における震災復興に適用可能な概念
• 短期的・長期的な自然変動に対して しなやかに対応できる「レジリエントな社会」を構築していく必要がある
• 自然共生社会とは、それぞれの地域の自然資本を生かし、豊かな生態系サービスを保全しながら新たな価値創造を目指す社会
• 瓦礫の山や地盤沈下した低地を、積極的に自然再生を行うことで、地域に新たな価値を生みだす
(U.S. Navy Photo)
3

震災復興におけるレジリエントな社会の形成• 新たに台頭した課題は、突然の災害(e.g.津波、洪水)と長期的な変化(e.g.気候変動)の両方に対応する “レジリエントな社会” をどうやってつくるか
• 生産・人工資本とともに、自然資本、人的資本の蓄積による包括的富の増大が持続型社会構築のカギ
• かつて干潟を埋め立てた場所が、津波により再び干潟のような環境が出現(市の復興計画において、干潟に自然再生)
• 物的なレジリエンスと同様に、社会・生態的なレジリエンスを強化することもまた重要である(e.g.避難ルートの新設、減災訓練の取り組み)
• パートナーシップによる地域資源の活用とレジリエンスの強化
4
1948 20111977
気仙沼市大島の田中浜から高台のホテルへの避難路(環境省)
小友浦の自然再生事業(国土地理院による)

注目され始めた“パートナーシップ” と “地域”
共有する 広めていく 補いあう
個々の知恵や能力を最大限に引き出すパートナーシップ• 震災で発生した地域の課題に対して、政府、企業、NGO・NPO、被災者、支援者など様々な主体がパートナーシップを結び、復興への大きな原動力となった
• 今後の持続可能な社会づくりにおいて、パートナーシップは、人々の課題解決能力を高めるという点で大きな可能性を持つ
パートナーシップによるグリーン経済の推進• パートナーシップの取組の中から、新しいアイデアや仕組みが生まれ、被災者以外にも広く利益をもたらすことがあった
• 雇用を維持し、関係者の経済的な自立、地域の活性化へと繋がっている
• パートナーシップの構築が多くの関係者に利益をもたらすようになるという点に注目すべき
なぜ、パートナーシップなのか
地域の課題解決と活性化
• 単独では実現困難な復興という目標を達成できる
• 様々な主体とのパートナーシップにより、互いの持つ様々な情報を共有し、それぞれの知恵や資源、人材を出し合い、相互に補完しあいながら復興を進めている
5
活動をリード・サポートするキーパーソン
活動を支える資金 調達の仕組み
win-winのアイデア
新しいビジネスモデル

きっかけは東日本大震災での人と人との絆
People to People 人から人へ
アメリカから“トモダチ作戦”
スマトラ沖地震の被災地からの食糧支援
世界の子供たちからのメッセージ
世界各国からの支援
・24カ国/地域+5機関からの救助・専門家チーム
・63カ国からの救援物資
・93カ国からの寄付金(175億円以上)
・世界各国の NGOや企業、個人からの支援
後発途上国からの義援金
友好都市・姉妹都市からの支援の手
お隣の国・韓国からの大規模な救援隊 外務省ホームページ公表資料をもとに作成
• 日本国内では、これまで世界各地の自然災害からの復旧をサポートしてきた国際協力NGOや日本中の自治体、企業、市民、地域のNPOなどが、被災地支援のために結びつき、互いに助け合い、協力した
• 国際社会から国や地域、組織や個人も含めて様々な形で支援が寄せられた
米軍トモダチ作戦
(U.S. Navy Photo)
(U.S. Navy Photo)
6

Rio+20を契機としたステークホルダーのパートナーシップ• Rio+20は国連の会議としては約4万5千人という史上最大の参加があった
• 持続可能な社会の構築には多様な主体のパートナーシップによる取組の重要性が強調
• 日本では、9つのメジャーグループを招集し、Rio+20国内準備委員会を設置震災の経験を世界と共有する意義を認識
• 成果文書「The Future We Want(我々の望む未来)」が採択
• 持続可能な開発目標(SDGs)策定プロセスの開始に合意
• Rio+20のサイドイベントでは、自然共生社会の実現がグリーン経済に貢献することを主張
7
マルチステークホルダー会合 (C)iisd

新たなコモンズと新しいビジネスモデル• 里山里海では、伝統的に自然資源を共同管理する仕組みがあったが、里山ではそうした仕組みが崩壊
• 農林水産業従事者の減少、高齢化にともなって、適切な資源管理の仕組を維持していくことが困難になっている
• 農林水産業従事者に加え、企業、NPO、市
民などより広範なステークホルダーの参画により共同管理を行うのが「新たなコモンズ」の考え方
• 震災復興では、生物多様性・生態系と調和した高付加価値型の農林水産業を基軸とした地域複合産業の創造が重要
• グローバル化した現代の経済社会にも適合するような自然資本を活かした「新しいビジネスモデル」としての再生を目指す
8

三陸復興国立公園• 2013年3月中央環境審議会自然環境部会が「三陸復興国立公園」の指定を答申、5月に創設
• 自然の脅威と恵みに立脚し、森・里・川・海の連環の再生を大きなテーマに
• 里山・里海フィールドミュージアムや、総延長約700kmにおよぶ「みちのく潮風トレイル」を整備
• 三陸ジオパーク構想とも連携し、震災・津波の経験を次世代に引き継ぐことが重要
• 三陸の地域特性を踏まえた、生態系を活用したレジリアンスの高い防災をまちづくりの基礎とする活動も生まれている
• 地域のレジリアンスを高めるためには、地域コミュニティの活性化と、パートナーシップの強化が必要となる
• 東北の被災地では、今まさに、真の復興をめざし、自然と共に生きる地域の将来ビジョンを地域住民自身が考え始めている
種差海岸除幕式 平成25年5月25日
国立公園構想図
9

10
提供:環境省提供:環境省提供:環境省
提供:環境省

世界農業遺産(Globally Important Agricultural Heritage System)
• 2002年のヨハネスブルグサミットをきっかけに、国連食糧農業機関(FAO)が始めたイニシアティブ
• 持続可能な開発に貢献する伝統的な農業土地利用システムを認定する仕組み
• GIAHS(世界農業遺産)として、主に途上国の伝統的農業システムを認定
• 国連大学は、2002年のGIAHS発足当初からFAOに協力
し、中国、日本などアジア、アフリカ、南米地域などでGIAHSの候補地を提案し、その認定申請を支援
• 2011年5月、トキと共生する佐渡の里山と能登の里山里海が、先進国としては初めて世界農業遺産に認定される
• 2013年、阿蘇の草原維持と持続的農業と静岡の茶草場
農法とクヌギ林とため池がつなぐ国東半島・宇佐の農林水産循環も認定
11
日本佐渡での認証式 (2011年)
能登の揚げ浜式製塩法
佐渡島の水田とトキ

1981年:日本のトキが絶滅1999年:中国から譲り受けたトキの
ペアで初めて人工繁殖に成功2008年:トキの放鳥開始2017年5月:佐渡での飼育数 158羽
野生下での確認数 196羽過去最多の自然繁殖数 77羽
トキの野生復帰と認証米制度の意義
生きものを育む農法
江
ふゆみずたんぼ
魚道 ビオトープ
2008 2016 伸び
農家数(戸) 256 524 2.0倍
面積(ha) 427 1,278 3.0倍
佐渡(認証米)の価格は、新潟一般コシヒカリの2割高
企業・消費者の産地視察、体験、交流
トキの野生復帰
トキの野生復帰を通じて、環境に配慮した農法による認証米生産がトキの餌場を提供するとともに、経済効果を創出
農家、地域住民、消費者の生物多様性保全に対する意識も向上
餌場提供
付加価値向上
認証米農家が実施する年2回の生きもの調査に市民が参加
「朱鷺と暮らす郷づくり」認証米制度
生物多様性保全の意識向上
無農薬無化学肥料栽培
畦畔除草剤の不使用
生態系の再生
12

最高品質
高品質
並品質
バイオマス発電・熱供給
木材
合板・集成材
パルプ・チップ
森林資源
森林管理生態系保全
生態系サービスの増大
水質向上安定水資源
太陽光・熱 風力・水力・地熱等
電気・熱
熱・電気供給
佐渡島における自然共生社会実現のための産業振興
森・里・海の連携
森林資源を使うことにより、森林は管理され、木材の質・量も増大
農業を活性化することにより、農地は管理され、農産物・バイオマス量も増大
海洋資源の活用
水産業
食品産業 バイオマス
産業
6次産業
観光業
エネルギー
食品
自治体の本気の努力
電気・熱
13

佐渡島における自然共生社会実現のための産業連携
水産業
食品産業
林業
6次産業
観光業
農産物
水産物
林産物
自然資本
文化的サービス
調整サービス
景観
観光
祭事
花粉媒介
水浄化
炭素固定
治水
エネルギー産業
教育・人材育成
供給サービス
農業
バイオマス
飲料・加工品
14

地域パートナーシップにおける効果的手法
•大学や研究機関による科学的知見が議論に必要な定量的材料と情報共有手段となる多様な主体の参画はそれぞれの背景となる活動分野や知識量が異なっているため、議論が平行線になることも多い
•行政の下支えによる自由なつながりの創造行政が仕組みを作る役割を担っていたとしても、運用し活用するのは各主体である
• インフォーマルなつながりこそフォーマルな取組の土台となる常に繋がってはいないが、必要な時にすぐ繋がれるゆるやかなネットワークを構築
•継続性と新たな視点を持った専従コーディネーターによるネットワークの形成個人であることによる機動力と、行政の枠にとらわれない見方と柔軟な対応
•地域計画への反映や協定の締結による取組基盤の確立明確な将来ビジョンを提示することで、外部の企業や団体側からの信用を得られる
15

多様な主体が支える里海づくり
里海
漁師
農家林業者
潜水士旅行者
観光業者
旅館経営者
写真家マスコミ
企業
行政
消費者 スーパー経営者
料理研究家 飲食店経営者
研究者
NPO・NGO・国際機関
学生
IT技術者
地域住民
16

地域の役割と国際社会との関連付け
• 持続可能な社会の構築に向け、リアルな地域モデルを積み上げていくことは地域の役割であり、その成果を積極的に国際社会に発信していくことも重要である
• 地域にとって認定・認証といったラベリングが推進力となることがある
• 地域の取組を、既存の国際的な枠組みと関連付けていくことは、取組の動機付けや価値を見直すきっかけにもなり、結果的に地域での活動に還元されていく
17

ご清聴ありがとうございました
18


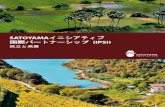










![zfjs.km.gov.cnTranslate this pagezfjs.km.gov.cn/upload/attachment/201406/20140626024059.doc2016-04-02 · ºhÇ %`%¢ ]ˆ¼1( òVQɈ ¬±ÿº •¬ ýiˆkGT`þ T2/½Ù€. Tõq.ì-uÜ_](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5b2aedda7f8b9a07778b5ad2/zfjskmgovcntranslate-this-ohc-1-ovqe-yo-yikgtb.jpg)





