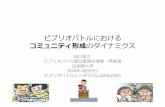「つくる」でつながる 新しいコミュニティ · 「つくる」でつながる 新しいコミュニティがあったら どんなことができるんだろう?
コミュニティ形成と住民意識 - shizuoka-eiwa.ac.jp ·...
Transcript of コミュニティ形成と住民意識 - shizuoka-eiwa.ac.jp ·...

コミュニティ形成と住民意識―掛川市の「生涯学習まちづくり」をもとに―
コミュニティ福祉学科 志 田 倫 子
1 はじめに
本稿は、これまで静岡県掛川市で行われてきた「生涯学習まちづくり」の取り組みを、コミュニ
ティ形成の観点から論ずることを目的とする。掛川市の取り組みは「生涯学習」と名付けられてい
るものの、1979年(昭和54年)からスタートした取り組みであり、1970年代のコミュニティブーム
と切り離して考えることは、できないであろう。
グローバル社会となった現在、都市においても便利な街並みがどこに行っても見られ、住民はそ
れに満足しているかに思われる。しかし、こうした時代だからこそ、身近な地域社会に心なごむと
ころがないだろうか。ところが、昔あったような村落共同体は崩壊しているが故、地域社会は自分
たちで作っていかなければいけないという「コミュニティ形成」の考え方が生まれる。私たちが住
むまち、地域社会はコミュニティとして「形成」していくという意識をもつことが必要とされる。
戦後、「ふるさとは、遠くにありて思うもの」といわれたように、実態としての地域社会は崩壊し、
便利になったが潤いの欠ける都会で日々すごし、故郷は懐かしい「ふるさと」として心のなかに想
い出として存在するものととらえられていた時期があった。何故そうなるのかといった理由を考え
るときに、地域社会の特徴というのは言葉にするのが難しい一体感のようなものが存在するところ
にあるからであろう。同じ景色をみて育ち、その地域独特の方言、同じ時代を生きた隣人に対する
一体感のようなもの、こうした言葉にならない「何か」を「感じる」ところに、懐かしさを覚える
ということである。
従って、時代が変わり、近代化や利便性の追求の中でまちが変化することで、人々は疎外された
ような気持ちをもつことになるといえよう。その結果、自分たちの「ふるさと」は想い出の中に存
在すると思うようになると考えられる。こうして考えると、時が経ち、社会が便利になっていくこ
とは避けられないわけであるが、歴史の積み重ねや地域性を無視した上で開拓をするのではなくて、
古いものを再生しながら再構築していくことが必要ではないだろうか。すなわち、住民も古くから
いる住民に新来住層や新生児が加わっていくと考えると、こうした古い時代のものを新しい世代に
伝えていくことが必要になっていくのではないかと思われる。
そこで、前述したように「地域社会」の特徴は言葉にならない「何か」を「感じる」ところにあ
ると言ったが、こうした「何か」を同じような環境設定のもとで、もう一度感じてもらうこと、あ
るいは、「言葉にならない何かを感じたということ」を、言葉や体験で伝えていくことで、地域住
民が感情を共有できるのではないかと考えられる。
- 107 -

冒頭で述べたように、掛川市は「生涯学習まちづくり」という形で、市民が行政に関わる形で住
民一体となってまちづくりをすすめてきた点で注目を集めてきた。その取り組みを幾つかとりあげ
ると、平成15年「生涯学習まちづくりモデル支援事業」の中で、「スローライフ」のまちづくりの
ための県内大学機関による調査研究を行い、その中で高齢者の考えるまちづくりを意識調査によっ
て調べる試みは筆者自身も携わった。そのほか、地元住民が掛川36景という名所を発掘し、それを
観光ルート化する取り組みなどが顕著であろう。
この掛川36景の中の具体的な名所をとりあげると、小夜の中山にある「夜泣き石」も含まれてい
る。住民が地元のことについて調べ、ふるさととして共有できるものを取り上げている。小夜の中
山にある夜泣き石、ふるさと伝承の昔話でとりあげられる石を見学にいくことで、ふるさと志向を
強めることができる。ただの石であったものが昔話で語られてきた「夜泣き石」であると意識が変
化することで、その石をみることで新しく「ふるさと意識」を根付かせていくこともできる訳であ
る。わが町にある「夜泣き石」は住民の心のふるさととなっていくことができる。
こうした地域社会のふるさと志向の産物は、住民だけのものではなく、観光ツアーの中に取り入
れることで、掛川を訪れた観光客にも知ってもらうことができるし、そのことで観光客とも感情を
共有することができることで新たな発展を期待できる。
すなわち、なつかしい「ふるさと」はこのように作っていくことができるし、言葉にできない感
情を言葉で説明することで、多くの人に共感してもらえると言えよう。こう考えていくと、地域社
会とのかかわりの度合いによって、思い入れは違うにせよ、地域社会というものは誰にとっても開
かれており、誰もが共有していくことができる魅力のある対象であるといえるであろう。
本稿では、コミュニティブームが生じるまでの流れと、コミュニティ形成の理論について概観し
た上で、掛川の生涯学習まちづくりの活動がコミュニティ形成の理論からみてどのように位置づけ
られるのか検討したい。その他、他の地域でみられた住民運動から発展した住民主導型のタイプな
どと比較しながら、掛川市の行政主導型のタイプを図によってあらわしたい。さらに、筆者自身が
行った意識調査の結果から、住民意識についても検討していきたい。
2 コミュニティ形成とは
本節では、コミュニティ形成の理論について整理しておきたい。高橋勇悦ほか編(1994)によると、
次のように要約することができる。高度経済成長期に経験した社会的変動はわが国に大衆社会的状
況をもたらしたという認識にたって、社会目標としてのコミュニティを打ち出したのが周知の1969
年に提出された国民生活審議会調査部会コミュニティ問題小委員会の報告書『コミュニティ―生活
の場における人間性の回復』である。「生活の場において、市民としての自主性と責任を自覚した
個人および家庭を構成主体として、地域性と各種の共通目標をもった、開放的でしかも構成員相互
の信頼感のある集団」と規定された。人びとの連帯感が薄れ、孤独感や無力感が強まる社会にあっ
て、人間性を回復する1つの方途としてコミュニティの形成が必要だと位置づけられたのである。
- 108 -

これを実現するために住民や行政がなすべきことは何か、報告書では具体的に検討されている。
とくに強調されるのは、行政と住民との関係であり、公聴と広報によって住民と行政のフィード
バック・システムを確立することが望まれている。
この他にも、自治体が採用した典型的な手法として次の3要件をみることができる。第1はゾー
ニングである。コミュニティとしてのまとまりを地区として設定する作業である。既存の地域集団
の累積状況や住民の面識的関係が維持可能な範域として小学校区ないし中学校区程度の広がりが考
えられた。コミュニティ地区とか住区などと呼ばれるものである。
第2は組織づくりである。ゾーニングによって設定された地区を単位として、コミュニティ形成
の主体となる地域住民を組織化するために、コミュニティ協議会などと呼ばれる住民組織を新たに
結成する自治体が多かった。「あらたに」といっても、既存の地域集団を母体とする場合や、既存
の地域集団の代表者が参加する協議会など形式は様々である。
第3には、施設づくりがあげられる。コミュニティ地区ごとにコミュニティ活動の拠点となる集
会機能をもった施設が自治体によって建設された。コミュニティ・センターとか地域センター、地
区会館などと呼ばれる。この施設は、住民組織に管理運営を委託されることがある。コミュニティ
施設の住民管理という方法である。
住民が自主的に施設を管理運営して、公営施設では行き届かない配慮のある利用が可能になり、
あわせて住民がルールづくりや利用方法などを共同して考えていく学習の場を通じたコミュニティ
形成をめざしたものであった。
このように、人間性回復のためには、生活の基盤である地域社会がよりどころとなること、その
ために地域社会はつくっていかなければならないこと、地域的範域であるゾーニングを行い、そこ
で人を組織化するために組織づくりが行われ、さらに集い、会合ができる施設をつくる。このよう
な環境設定をし直すことが必要だった訳である。
その後、コミュニティ形成は国の行政の各省庁にも広がり、また多くの地方自治体でコミュニ
ティづくりを目標に掲げて展開し、1970年代はコミュニティ・ブームといわれる時代となるのは周
知の通りである。
3 理論上の整理
(1)-① コミュニティ形成の理論
1970年代の初頭に、行政主導で展開してきたこのようなコミュニティ形成の全国的な潮流の中で、
コミュニティがどのようなものとして概念化されるか、行動体系と意識体系という2つの軸を基準
に、実証的研究の枠組みを構成し、考察を試みたのが奥田道大である。(1)
行動体系の軸は、「住民自
身に主体化された価値の創出」としての主体化、「体制とのかかわりにおいて対象化された客体化」
をそれぞれの極としている。
もう一方の軸である意識体系は、「特定のコミュニティが他のコミュニティと交流し、連帯しう
- 109 -
コミュニティ形成と住民意識

る価値を共有するという意味あい」でコミュニティの普遍主義的価値意識を一方の極とし、「地域
埋没的なぐるみ的連帯行動」や「排他的な地元郷土意識、郷土愛」を典型とする特殊主義的価値意
識をもう一方の極とする。
この両軸を交差させたところに、4つの地域社会類型が構成されるのである。4つの類型を簡単
に説明すると次のようになる。①地域共同体モデル・・・行動体系において主体的、価値意識にお
いて特殊的で、そのイメージは「村落の旧部落、都市の旧町内といった、共同体的(ムラ的)規制
の支配する、伝統的地域社会」である。②伝統型アノミー・モデル・・・行動体系において客体的、
価値意識において特殊的で、伝統型地域無関心層を住民とする大都市近郊農村地帯などの解体化地
域である。③個我モデル・・・行動体系において客体的、価値意識において普遍的で、シビル・ミ
ニマム的な権利意欲を自覚した住民、とくに新来住層、新中間層、高学歴層、若年齢層などで構成
された大規模団地地区などがイメージされる。④コミュニティ・モデル・・・行動体系において主
体的、価値意識において普遍的で、地域社会を生活基盤と考える住民が、連帯してこれを創り上げ
ていこうとする。コミュニティ・モデルはいわば目標であって、他の3モデルからコミュニティ・
モデルへの展開が構想されることになる。
図3-1 地域社会の分析枠組
- 110 -

わかりやすい
行政主導型
住民・行政協働型
弱 強 (住民の一体感)
住民主導型
わかりにくい
(わかりやすさ)
図3-2 まちづくりのタイプ
②
①
③
④
(1)-② まちづくりのタイプ
もう1つの指標として、「まちづくりのタイプ」によるモデル設定を試みたい。図3-2は、コ
ミュニティ形成の中でもとりわけ「まちづくり」に関する取り組みをタイプわけするときに用いる
ことができる。
縦軸は「わかりやすさ」、横軸は「住民の一体感」をあらわしている。縦軸の「わかりやすさ」
とは、「まちづくり」に関する取り組みが「オープンでわかりやすいもの」と、「閉鎖的・内輪的で
わかりにくいもの」が極となっている。横軸の「住民の一体感」とは、まちづくりへの取り組みに
かかわる住民の一体感が「強い」ものと、「弱い」ものが対極となっている。
この両軸を交差させたところに、4つのまちづくりの取り組みのタイプを見出すことができる。
①わかりやすく、住民の一体感が強いもの ②わかりにくく、住民の一体感が強いもの ③わかり
にくく、住民の一体感が弱いもの ④わかりやすく、住民の一体感が弱いものである。
まず、住民運動のような形で問題意識の強い住民が集まって、問題解決に当たるような場合、運
動にかかわる人々の一体感は強く盛り上がりをみせる。さらに、後に行政がサポートするような形
で取り組みをバックアップするような場合、運動の過程はわかりにくいが、その活動自体は後に公
表されるために「わかりやすい」といえよう。住民運動としてスタートしていることから、住民の
一体感は「強い」。従ってタイプ①といえよう。
一方、住民運動のような形で問題意識の強い住民が集まって問題解決に当たるが、行政の関与が
みられないような場合、運動にかかわる人々の一体感は強く盛り上がりはみせても、関心のない住
- 111 -
コミュニティ形成と住民意識

民は蚊帳の外であり何をやっているのか内容がわかりにくい。従って、タイプ②といえよう。
また、住民主導の運動でありながら、住民同士の士気があがらなかったり、途中で内部分裂する
ような場合、「わかりにくく、住民の一体感も弱い」タイプ③と言えよう。
最後に、行政主導で行政が市民に呼びかける中で行われるような取り組みは、インターネットや
広報などで情報が公開されやすく、取り組みの過程も同じように公開される傾向にあるので縦の軸
は「わかりやすい」と言える。しかし、住民が行政に引っ張られるようにして活動するような場合、
横の軸である住民同士の一体感は「弱い」。従ってタイプ④といえよう。
以上の観点からすると、「わかりやすさ」の軸は「わかりやすく」、「住民の一体感」からみると
強くも弱くもない中間型~強いタイプを理想とみることができる。
(2)コミュニティ形成の指標
近年、コミュニティ活動はますます多様化し、さまざまな展開の様相を呈している。
実際にコミュニティ活動を行うにあたって、とりわけ現代社会の課題に応えるコミュニティ、住
みよい地域社会の形成のためのテーマを例示してみたい。次のような8つの観点を考えてみた。
「住みよさ」の指標は、具体的には、利便性、健康性、安全性、快適性がこれまでにもよく指摘さ
れ、どれを採用するか、強調するかは、行政だけの選択ではなく、住民や市民全体の最大公約数的
な合意が必要となる。
現代社会では、コミュニティに多大な期待をよせているが、今日の多様な生活課題や地域課題に
対応する住民主体の地域活動への要請の高まりをうけて、当面次の8つの今日的課題を指摘してみ
たい。
① 青少年の地域健全育成―地域で育てる子どもたち―
② 余暇・生涯学習の推進―地域で学ぶ学習社会の実現―
③ 高齢化と地域福祉の展開―地域で支える高齢者の生活と福祉―
④ 地域産業の振興―地域(地元・地場)の産業に魅力と活力を―
⑤ 環境問題への取り組み
―地域の環境問題(環境美化・ゴミ処理等)への取り組みから地球環境問題へ―
⑥ 地域文化の創造と発信―ふるさと志向の高揚(自然・景観・歴史・伝統文化への憧れ)
と地域づくり―
⑦国際化・国際交流の促進―外国人と共生する地域社会の形成―
⑧防災・災害への地域の対応―安心できる安全な住民生活の確立―
(3)町並み保全のまちづくり、ふるさと志向
本稿では、前述した問題意識のもとで、コミュニティ形成における再生に強い期待がもたれ、そ
の意味の強い⑥「地域文化の創造と発信―ふるさと志向の高揚(自然・景観・歴史・伝統文化への
憧れ)と地域づくり―」に目を向けて、その展開の事例を考えていきたい。
- 112 -

「街並み保全のまちづくり」について、掛川市の生涯学習活動のなかから、城下町風の「町並み
保全のまちづくり」を取り上げ、さらに大阪府の2事例を加えて、これらの事例について「まちづ
くりのタイプ」と奥田道大の「コミュニティ・モデル」のそれぞれから分析を試みていきたい。さ
らに、掛川生涯学習で取り組んできた「掛川36景」の事例もまちづくりの観点からこれに加えて考
察していきたい。
4 町並み保全のまちづくり
本節では、掛川市の事例に加えて、大阪府の2つの事例の3事例を取り上げてこれらを比較検討
していきたい。大阪市の2事例は、鈴木広(1997)をもとに(2)
その経緯と展開を紹介したい。
(1)掛川市天守閣復元―行政主導型―
まずは、掛川市の取り組みについて、掛川市HPの「生涯学習」の内容を引用して簡単に紹介し
たい(3)。
『掛川市は、市町合併前の旧掛川市では、昭和54年全国に先駆けて生涯学習都市宣言を行い、「生
涯学習によるまちづくり」をすすめていました。合併後の平成19年12月には、この精神を引き継い
だ「生涯学習都市宣言」を再宣言しています。
ここでいう、掛川市における生涯学習とは、個人の学びを自己の充実のみならず、まちづくりに
生かしていこうという大きな特徴があります。それは、「生涯学習都市宣言」の「掛川市民は(中略)
お互いに何をなすべきか常に問いかけあいながら、一生涯学び続けていこう(中略)そしてゆった
りした豊かな生涯学習社会を構築していこう」に集約されています。
これには、市民一人ひとりが、お互いに問題・課題意識を共有しながら、常に地域社会や市政に
参加し行動すること、すなわち協働を前提とした学びを呼び掛けているものです。つまり、掛川市
の生涯学習によるまちづくりは、情報共有による相互理解や、参加と協働の概念を内包したまちづ
くりの推進運動といえます。』
1979年(昭和54年)に始まったこの掛川市の取り組みは、住民が地域のことについて考えている
こと、行政と市民とのフィードバックが行われていることなどを考えると、「コミュニティ形成」
を彷彿とさせるものの、「コミュニティ活動」というよりは、関心をもった市民が集まってくる「ア
ソシエーション」としての要素が強い。アソシエーションとして「コミュニティを考えていく」と
いった立場ではないか。
旧掛川市の生涯学習運動(資料編)を参考にすると、掛川城天守閣復元(平成6年4月開門、総
事業費10億8千万円)、「400年前の山内一豊公築城時の天守閣を、全国で初めて本格木造で復元」
「城下町風まちづくりの展開:掛川城公園、城下町風町並みづくり、駅天守ギャラリー」などが具
体的な取り組みとしてあげられている。
この取り組みは生涯学習運動の一環として行われて、性格的には行政が市民に声をかけ参加者が
集まる行政主導型の取り組みといえよう。
- 113 -
コミュニティ形成と住民意識

(2)大阪府宮田林市寺内町―住民・行政協働型―
宮田林市は、現在大阪市南部のベッドタウンの1つであるが、市制施行前は南河内郡の中心地を
なす町であった。この旧宮田林町は、1557(永禄二)年一向宗の興正寺という寺院を中心にして、
町人たちが今日いうところの「都市計画」をしてつくった寺内町に発する。この寺内町は堺や後述
の平野と同じく、周囲に土居をめぐらした「自治都市」の一つであった。そののち長く、付近の農
村地域を後背地にして、木綿や酒などの地場産業の中心地として栄えてきた。
戦後商店街は近鉄富田林駅の方に形成されて、旧町内から移動したため、旧町内は開発の影響を
あまり受けず、古い町の姿を残すことになった。ここには、江戸期に建てられた町家だけでも50棟
近くは残っている。それらがこの町の景観の主役であるが、そのいずれもがそろって大規模である
ことがほかの都市の歴史的町並みと比べてすぐれている点である。
富田林寺内町の歴史的意義を最初に公表したのは、1967年の日本建築学会での報告であったが、
その後は専門の研究者以外からは関心ももたれずに時がたった。1973年1月、その歴史的意義に気
づいた地元寺内町の住民有志が主体となって「富田林寺内会を守る会」が結成されて、町並み保存
の住民運動が始まった。
1975年に文化財保護法が改正されたが、同年には2つの動きがあった。つまり一つは住民の要望
を受けて、(財)観光資源保護財団が研究チームに調査を委託し、報告書『富田林寺内町の町並み
と町家』がまとめられたことである。
もう一つは、市もこの改正を受けて保存対策調査に取り組みはじめたことである。しかし、市が
実際の保存事業を実施するまでにはまだ時間がかかった。その間寺内町に大きな改造・再開発は加
えられなかったが、それには「富田林寺内町をまもる会」の果した役割が大きかった。
1983年に至って市は、寺内町で一番大きくて古い建築物である「旧杉山邸」を土地・建物ともに
買収したが、同邸は同時に国の重要文化財にも指定された。そして市が「寺内町歴史的町並み保全
要綱を制定し、本格的に町家と町並みの保存事業に乗り出したのが1987年4月からのことであった。
現在市は、「要綱」をもって修理・修景に対して技術協力や助成措置を行っているが、事業は順
調である。富田林寺内町の町並み保全は観光開発型ではなく、現に人びとのくらしがそこで営まれ
ている生活環境型である。だから、ある時代の様式にすべての建物を統一してしまう発想ではうま
くいかない。たとえば町家の外観、塀、二階建ての建物などについても、伝統的様式の細部にこだ
わらずに、現状に柔軟に対応した修理がなされている。また周辺の道路、公園、公共建物等につい
ても、町家と町並みに調和するように整備が進められている。
このタイプは、有志住民と専門家が先行して、あとで行政も参加するという形での「住民・行政
協働型」のまちづくりが展開しているところに特徴がある。
(3)大阪市平野区平野の事例―住民主導型―
平野地区は「平野卿」と呼ばれていた環濠集落地域で、戦国期には商人たちの「自治都市」をな
- 114 -

し、西隣の堺とともに栄えた歴史をもつ。江戸期には、長く近在の良質の河内木綿の加工地として
商工業の地方センターをなしていた。こうした経済力のうえに、1717(享保2)年には、わが国の
私学の魁ともいうべき町人による学問所「含翠堂」が当地の名望家の1人によって創設された。
この地区は第二次大戦の戦火を免れたが、戦後の大阪市の外延的発展により、その南部の住宅地
域として大都市のなかに埋没していった。この地区には、広大な境内をもつ大念仏寺をなじめ、江
戸初期以来の建造物をもつ19の寺院、1708(宝永5)年に建てられた全国的にもめずらしい「連歌
所」をもつ2つの神社、古い町割り、環濠集落の名残りを示す郷外から郷内への13の木戸口と、そ
こに建立された13の地蔵堂など、歴史を残す地域景観が多い。地区内には、主として平屋や二階建
ての低層住宅が建ち、それらは関西の住民諸階層の都市住宅の時代別変遷を示す「住宅博物館」的
景観を作り出している。
この地区で次々に失われていく地域景観の独自性を貴重だと思い、それを守ろうとする住民運動
のキッカケとなったのが1981年の南海電車平野線の廃止であった。廃止により、1914年以来住民に
「八角堂」として親しまれ、地区の歴史のシンボルの一つとなっていた駅舎が取り壊されることに
なった。住民の熱心な保存運動にもかかわらず、駅舎は取り壊されたが、現在廃線敷は、電車軌道
を追憶させる舗装と修景をもつ緑堂として残されている。
この運動を通じて、地域景観の保全が住民にとって生活のアメニティを高め、くらしを豊かにす
るのに不可欠だと認識されるようになった。こうして自らの住む住区を、主として若い次世代のた
めにかけがえのない「ふるさと」にしていこうとする、住民たちのまちづくりの努力が、たとえば
13の地蔵堂めぐりをしながら、その扉の鍵の形をあてる「パズル・オリエンテーリング」、「平野の
オモロイはなしめぐり」という民話オリエンテーリング、先賢の苦労を偲ぶ「含翠堂講座」、明治
初期まで続いてきた「平野連歌の会」の復活、大念仏寺での「たそがれジョイント・コンサート」
など、老・壮・青・幼をつなぐ各種のイベントとして展開されている。
この地区の最大の特徴は、江戸期以来の各時期の都市住宅の実物をワンセットとしてもつ「住宅
博物館」的地域景観が展開している点にあるが、この特徴は、住民の自覚と努力による保全だけで
なく、大都市行政によっても周到に保存されていく必要がある。
この事例は、行政によるかかわりの形がみえない。つまり、ここでは行政参加がないかあるいは
薄いという意味での「住民主導型」のまちづくりが進められていると思われる。
5 3事例の分析
(1)「まちづくりのタイプ」による分析
本節では、前節で例示した3つの事例を、タイプにあらわし考察してみたい。
前掲の図3-2にあらわしたように、縦の軸は「わかりやすさ」を、横の軸は「住民の一体感」
をあらわしている。まず、「(1)掛川市天守閣復元」のケースを分析したい。生涯学習運動の一環
として行われる「行政主導型」の取り組みと位置づけられる。この活動を図3-2の「まちづくり
- 115 -
コミュニティ形成と住民意識

のタイプ」にあてはめるとどうなるであろうか。
縦の「わかりやすさ」の軸をみると、広報やインターネットなどでまちづくりに携わる「学士」
を募集したり、その活動内容や決定事項を公開したりする大変「わかりやすい」活動であるといえ
よう。
一方、横の「住民の一体感」の軸をみると、生涯学習活動を共に行う者、「学士」同士の一体感
が生み出されるであろう。こうした感情は、同じ問題意識をもつ住民が団結する住民運動のような
激しい感情とは違うが、活動を継続することにより生じる穏やかな連帯感のようなものが生み出さ
れるであろう。したがって、「住民の一体感」といった面では強くも弱くもない中程度のものとい
えよう。
以上の結果から、この掛川のケースは図3-2の中で、タイプ①とタイプ④の境目に位置づけ、
「行政主導型」として表記した。
次に、「(2)大阪府宮田林市」のケースは、「住民・行政協働型」の取り組みといえよう。「富田
林寺内会を守る会」が結成されて、町並み保存の住民運動から始まった活動であるが、後に市が保
存対策調査に取り組んでいったことからわかるように行政が活動をバックアップしていくことにな
る。
したがって、「わかりやすさ」の軸からすると、活動の過程はわかりにくいが、行政が関与する
ことによって公に知れ渡るようになったため「ややわかりやすい」といえよう。「住民の一体感」は、
住民運動から始まり活動を継続していくことからも「強い」といえよう。
以上の結果から、この大阪府富田林市のケースは、図3-2のタイプ①の中に位置づけ、「住民・
行政協働型」として表記した。
最後に、「(3)大阪市平野区」のケースは、「住民主導型」の取り組みといえよう。南海鉄道平
野線の廃止と駅舎の取り壊しに反対する住民による保全運動からスタートして、その後の展開はみ
られるものの行政のかかわりの形がみられない。
したがって、「わかりやすさ」の軸からすると、運動に関わりのない市民にとって、特に活動の
過程はわかりにくいといえよう。しかし、保全運動としてスタートしたものが、まちづくりの活動
へと展開しながら継続していることからも「住民の一体感」は強いといえよう。
以上の結果から、この大阪市平野区のケースは図3-2のタイプ②の中に位置づけ「住民主導型」
と表記した。
(2)コミュニティ形成の観点からの考察
次に、3つの事例にみられるこれらの活動を「コミュニティ形成」の観点からみるとどうだろうか。
まず、「失われた人間性を回復するため、生活のよりどころとなる地域の問題を考える活動」と考
えた場合には、住民の一体感の強い「住民主導型」「住民・行政協働型」が理想的であるといえよう。
さらに、先に示した奥田道大のコミュニティ・モデルを用いると、住民の運動としてスタートした
活動が個我の満足で終わらせず、普遍的で主体的な住民の活動へと結びついているという点でも理
- 116 -

想的なタイプといえるのではないか。
では、掛川市の「行政主導型」の活動をコミュニティ形成の理論からどのようにみることができ
るであろうか。
(3)ネットワークとしてのコミュニティ形成
掛川市のケースは、行政主導であるがゆえに決定の過程がHPなどで公開され住民に広く知らし
めている。掛川城天守閣復元のようなハードな面でのまちづくりにも積極的に市民が参画している
ことも特徴であるし、掛川36景を取り上げると、コースは数多く作られており(A、B、C、Dコー
スなど)、それぞれのコースは、他のコースと関連があるため、市民自らが携わったコースの他の
地域のことにも興味がもちやすいといえよう。
すなわち、住民同士がゆるやかなネットワークでつながっている、新感覚タイプの活動であると
いえよう。
6 高齢者意識調査の結果から
本節では、こうした住民参加型のまちづくりに対して、とりわけ高齢者はどのように受けとめて
いるのか、まちづくりに対する高齢者の意識を高齢者の満足度の観点から考察してみた。
ここでは、2002年に行われた「掛川市における高齢化に対応した新しい地域社会構築に関する研
究」において実施してきた調査結果をもとに、まちづくりに対する高齢者の満足度を分析した。な
お、これと同時に静岡市においても同じ質問項目でまちづくりに対する高齢者の意識調査を行って
きた(4)
ので、掛川市と静岡市の高齢者の意識を比較し、考察してみた。
調査結果によると、掛川市は住民がまちづくりに参加するようなスタイルをとっている。これに
対して静岡市では、まちづくりに対してとりわけ特徴的な方策は取られていない。従って、掛川市
と静岡市に住む高齢者に対して行った「地域社会に関する意識調査」の結果を比較することによっ
て、掛川市のまちづくりへの取り組みが高齢者の暮らしや意識に効果があるのかどうかを知ること
ができよう。
表6-1(人)
掛川市 静岡市そう思う 18 4ややそう思う 21 18あまりそう思わない 19 31まったくそう思わない 4 6わからない 4 2合計 66 61
- 117 -
コミュニティ形成と住民意識

図6-1
「歴史的・伝統的な面影があるか」という質問に対しては、全体として掛川市の高齢者のほうが、
静岡市の高齢者よりも「そう思う」という割合が高い。これは、城下町としての掛川を守る形で
まちづくりが行われてきたことと関係があるだろう。
旧掛川市では、掛川城天守閣復元、「400年前の山内一豊公築城時の天守閣を、全国で初めて本格
木造で復元」「城下町風まちづくりの展開:掛川城皇有縁、城下町風町並みづくり、駅天主ギャラ
リー」などを行っているため、こうした活動が「歴史的・伝統的な面影」に結びついているといえよう。
さらに(5)全市36景独立採算型テーマパーク化「市内の名所・名園・各施設をミニテーマパー
クとし、民活独立採算を主力に形成」「その中から36箇所を選定して“掛川36景”とし、ネットワー
ク化・観光ルート化を目指す」という内容もある。
すなわち、実際に城下町風まちづくりをしているだけでなく、そのことが生涯学習運動と連動し
ていることで市民に広く知られることとなっていると考えられるであろう。さらに、「掛川36景」
とあるように、市内の名所について市民はよく把握している。この中には前述した「夜泣き石」な
ども入っており、歴史的な趣についての認知度が高いことも理由としてあげられるであろう。
これに対して、静岡市は駿府城跡は駿府公園となっており、歴史的な趣は皆無ではないものの、
駿府城としての名残はあまりみられず、さらに掛川市のように市民に認知される機会が少ないため
に、「あまりそうは思わない」と答える割合が半数以上を占める結果となっている。
そう思うややそう思
う
あまりそう
思わない
まったくそう
思わないわからない
掛川市 18 21 19 4 4
静岡市 4 18 31 6 2
05
101520253035歴史的・伝統的な面影があるか
- 118 -

(人)掛川市 静岡市
そう思う 18 4ややそう思う 21 18あまりそう思わない 19 31まったくそう思わない 4 6わからない 4 2合計 66 61表6-2
図6-2
では、「建物や町並みの望ましいあり方」をどのように考えるかについてであるが、静岡市の高
齢者は「歴史的・伝統的な面影があるかどうか」について、「あまりそう思わない」傾向にあるが、
決してそのことに満足しているわけではないことが分かる。
「昔ながらの風景を保存」「昔ながらの外観と近代化を並立」と答えた市民が、圧倒的に多数を
占めている。この数は、掛川市民よりも割合としては多く、近代化されることについての危機感を
感じることもできる。
以上の内容をまとめると、「歴史的・伝統的な面影があるか」という質問については、掛川市民
のほうが「そう思う」傾向にある。さらに、「建物や町並みの望ましいあり方」については、静岡
市民のほうが「昔ながらの風景を保存、昔ながらの外観と近代化を並立」すべきだと考えており近
代化に反対している。
従って、掛川市のほうが「歴史的・伝統的な面影」があり、「昔ながらの風景を保存、あるいは
昔ながらの外観と近代化を並立」できており、街並み保存が成功しているといえよう。そして、そ
のことを高齢者も自覚していることがわかる。
従って、掛川市の「行政主導型」の取り組みは、「わかりやすい」ものであり、高齢者にも行き
昔ながら
の風景を
保存
昔ながら
の外観と
近代化を
並立
近代化に
伴って変
わるべき
別になん
とも思わ
ない
その他わからな
い
掛川市 22 14 6 3 17 4
静岡市 24 18 3 4 9 3
05
1015202530
建物や町並みの望ましいあり方
- 119 -
コミュニティ形成と住民意識

渡るような「ゆるやかな一体感をもたらす」活動であることが、このアンケート調査の結果から証
明できるのではないだろうか。
7 コミュニティとのかかわりをもとめて
「コミュニティ形成」において考えられたまちづくりは、人間性の回復のために自分たちのまち
のことを自分たちで考えていくという取り組みであった。これに対して、掛川の取り組みは少し緩
やかな観点から地域社会をとらえていく、すなわち、本当に顔の見える範囲で自分達の問題を考え
ていくというよりは、アソシエーションのような広がりをもった形でも地域社会を考えていくこと
ができるのではないかと思われる。
すなわち、奥田道大の「コミュニティモデル」をさらに、「地域性」を限定しない形で実現する
スタイルと考えられるのではないか。コミュニティモデルにあるように、行動体系は主体的、価値
意識も普遍的である。そして、地域性を小学校区・中学校区程度に限定せずに、市内に住む関心の
ある住民程度の範域として考えていったらいいのではないか。
コミュニティ形成に関しても、コミュニティからネットワークへと変化することで、住民運動と
いった激しい感情を伴わなくとも、住民にとって気軽にかかわることのできる「わが町」へと変わっ
ているのではないだろうか。
こうした掛川市のまちづくりの取り組みは、今後ネットワーク型の地域形成としてその他の地域
でも導入していくことで、地域社会の活性化が望まれると考えられる。
(注)(1)高橋(1999)、P125~P126(2)鈴木(1997)、P110~P113(3)主に、前市長榛村純一氏のもとで行われてきた掛川市の生涯学習の取り組みは掛川市HP「生涯学習」の箇所に詳しく紹介されている。(4)掛川市の調査は、掛川市内の後期高齢者に対して、訪問面接方式の質問紙調査を行った。1件につき、1時間程度を費やした。実施機関は2002年(平成14年)10月~11月。 静岡市の調査は、静岡市内の高齢者に対して、掛川市と同じ質問紙を用いて、同じように訪問面接方式の社会調査を実施した。実施時期は2003年(平成15年)。
(主要参考文献)・奥田道大 1983『都市コミュニティの理論』東京大学出版会
・金子勇 2011『コミュニティの創造的探求』新曜社
・ 小沼肇、志田倫子ほか 2004「静岡市における高齢化に対応した新しい地域社会構築に関する研
究」『静岡英和学院大学紀要 第2号』
・J.C.ミッチェル編 1983 『社会的ネットワーク』国文社
・鈴木広ほか 1997 『まちを設計する―実践と思想―』九州大学出版会
- 120 -

・高橋勇悦ほか編著 1999 『今日の都市社会学(第三版)』学文社
・広井良典 2011 『コミュニティを問いなおす―つながり・都市・日本社会の未来』 ちくま新書
・本間義人 1994 『まちづくりの思想』有斐閣選書
・ 文部科学省委託事業『生涯学習まちづくりモデル支援事業―スローライフ研究報告書―』
2003 掛川市
- 121 -
コミュニティ形成と住民意識

- 122 -



![ZENworks 10 Configuration Managementコマンド …...zman [-options] [arguments] 通常は、zman コマンドには、短い形式と長い形式があります。長い形式は、category-action](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5f7282c15ea2ef6940549c18/zenworks-10-configuration-managementfff-zman-options-arguments.jpg)