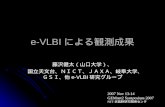小惑星4Vestaの 可視・近赤外同時観測による 表面反射特性 ......McCheyne et al....
Transcript of 小惑星4Vestaの 可視・近赤外同時観測による 表面反射特性 ......McCheyne et al....

小惑星4Vestaの可視・近赤外同時観測による表面反射特性マップの推定
野中秀紀(東大・JAXA/ISAS)長谷川直(JAXA/ISAS)中村良介(JAXA)十亀昭人(東海大)
石黒正晃(ハワイ大)
安部正真(JAXA/ISAS)藤原顕(JAXA/ISAS)
1

• 1807年発見
• 測光観測
• 多色測光観測
• 分光観測
• 2次元画像
• (探査機)
メインベルト、大きさ約500km
周期は5.34212時間
表面の非一様性
スペクトルがHED隕石に類似
アルベド分布、軸の向き、形状
(表面の詳細)
H. W. Olbers (1807)
C.B.Stephenson (1951) etc.
McCord et al. (1970)、McCheyne et al. (1985) etc.
Binzel et al. (1997)、Zellner et al.(1997)、etc
NASAのミッションDawn 2006打ち上げ2010到着予定
Feierberg et al. (1970)、M.J.Gaffey (1997) etc.
小惑星4Vestaの観測史

Vestaの特異性分化して層構造を持つ唯一の小惑星である
HED隕石の母天体と考えられる
S E
Vesta Ceres Pallas
・小惑星帯の中でCeresの半分、Pallasと同程度の直径を持つVestaのみが分化している ・
表面のアルベド・鉱物に局所的な違いがみられる
分化した隕石であるHED隕石とスペクトルが近く、他の候補天体が無いことなどから、HED隕石の母天体と考えられる
分化した石質隕石の多くを占める

1. Gaffey et al. (1997):それまでのVestaの地上観測をまとめて、表面の鉱物分布のマップを作成
2. Binzel et al. (1997):ハッブル宇宙望遠鏡を用いて、面光源として観測(北半球低緯度、4バンドのみ)
3. Zellner et al. (1997):ハッブルの写真から求めた詳細な形状
• 点光源の観測データでは半球の積分になる→シミュレータを用いて細かい分解能を
• 2次元画像が取得された北半球において鉱物推定に用いたデータ点が4点しかない→データ点を増やしてより詳細な議論を
•HSTの観測では北緯0-45°しか可視・近赤外のデータはとれていない →南半球に議論の余地
Vestaについての既知事項のまとめと問題点

Gaffey et al. (1997)による、それまでの地上観測をまとめたVesta表面の鉱物マップ
longitude
latit
ude
olivine
diogenite
howardite
Low Ca
eucrite
180 0 18090
問題点 : このマップ作成に用いた分光・測光データは、Vesta半球の積分から求めたもので、そもそも空間分解能は無い
Vestaについてわかっていること(I)

Grating
CCDスリット
分光観測において、星全体をスリットに入れて分光した場合、小惑星全体(半球分)の情報が含まれてしまう
図:分光の模式図
Vestaのように、表面構成物質が変化に富む場合、この方法は適さない!
空間分解能が無いことの補足説明

Binzel et al. (1997)より
4波長域でのアルベドマップ
4波長域の2次元画像による局所的なスペクトル
局所的な鉱物組成の推定
90°付近
150°付近
200°付近
270°付近290°付
近
0.439μm
Latit
ude
50
0
-50
180 90 0 270 180
Longitude
問題点 :データ点が4点では鉱物の推定は難しい
Vestaについてわかっていること(II)

Zellner et al. (1997) より誤差±3kmの形状データ
70°W20°N
270°W10°N
生画像
デジタル処理済
Vestaについてわかっていること(III)

本研究の目的: 小惑星4Vesta表面のアルベド分布・鉱物分布を求める
可視・近赤外6バンドの多色測光観測.(ライトカーブ作成)
ポリゴンモデルを用いたライトカーブシミュレーションにより、推定したアルベドマップと観測結果の整合性を確認.
観測結果を満たす最も尤もらしいアルベド分布・鉱物分布を求める
各波長のアルベドマップから経度ごとの離散スペクトルを導出.表面鉱物を推定.
ライトカーブをガウス関数の和で表し、ガウス関数とアルベドの関係から、各波長で経度ごとのアルベド(マップ)を推定.
研究の流れ:
2

可視・近赤外で鉱物の特徴を見る
1μm付近と、2μm付近に鉱物の吸収が見られる.
ECASフィルタ
V:544nmw:703nmx:858nmp:950nmz:1011nm
Hバンド:1650μm付近 }Vesta
可視・近赤外6バンドを観測し表面鉱物を推定.
KONIC
3

ISAS/JAXA(相模原)
(屋上)
東大
木曾観測所(屋上)
観測場所
6.1°V,W,X,P3/22
6.4°W,X,P3/21
13.9°Z2/28
14.3°W,P2/27
10cm屈折望遠鏡
CCD視野1.76°x2.64°
分解能6.2秒角
16.7°V2003/2/20
観測機器位相角バンド日時
位相角は変化しているが、Vesta上の緯度は約14°N
観測条件
5/21 H 木曾観測所 KONIC23.63°
4

1. ダーク処理 : CCDに元から含まれる暗電流(バイアス)と熱によるノイズを引くため、シャッタを閉じてVestaの画像と同じ時間だけ露光した画像を、全ての画像から引いた。
2. フラット処理 : CCD各ピクセルの感度ムラを補正するため、一様な光を当てた画像で、Vestaの画像を割った。
3. 星のカウントを求める : IRAFというソフトでCCD上の星のカウント値を求め、明るさを求めた。
4. ライトカーブ作成 : 横軸時刻、縦軸明るさ(フラックス)で明るさの時間変化を表した。さらに自転周期がわかっており、経度0°も定義されているので、横軸を経度に変換させた。
ライトカーブ作成の手順

V(0.544µm)
W(0.703µm)
X(0.858µm)
P(0.950µm)
Z(1.011µm)
バンド毎にライトカーブが異なる Vesta表面の非一様性がここから確認できる
観測結果
H(1.650µm)
5

小惑星の形状
軸の方向
光源と観測者の位置
表面の反射特性(Hapkeパラメータの内、wのみ可変)
入力パラメータ
ライトカーブ
出力
Zellner et al. (1997)
Thomas et al. (1997)
ライトカーブシミュレータ
ポリゴン各面からの反射光の和を小惑星の明るさとし、一周分の光度を求める.反射モデルとしてHapkeの散乱モデルを採用.
6

( ) ( )( ) ( ) ( ) ( ){ } ( )φµµξααµµ
µπ
α ,,1,,,14
,, 000
0 eiSHHphBBweir eeee
e −+++
=
i,eが入射角、出射角。rが散乱強度。
パラメータはw、ξ、B0、h、θの5つ。
w:シングルスキャッタリングアルベド
ξ:位相関数を決定するパラメータ
B0、h:オポジション効果の高さ・幅を表す
θ:表面のマクロなラフネスを表す
Verbiscer and Veverka(1995)より、w以外を固定
ξ=-0.25、B0=0.86、h=0.44、θ=20.0 として、wを様々に振った
Hapkeの散乱モデル

5°以外アルベド0
30°以外アルベド0
自由度は経度方向のみ
左のようなアルベド分布を与え、試しに計算した結果が右の赤いライン.
得られたライトカーブがガウス関数(緑)によく似ている.
ライトカーブはこれらの足し合わせであるから‥‥.
7

標準偏差(ガウス関数の幅に相当) σ
シングルスキャッタリングアルベド w
強度(ガウス関数の面積) S
アルベドに値を与える分布幅(経度(°)) x
ピーク中心(経度(°))
μ
観測時の位相角(°) α
ライトカーブ(ガウス関数) のパラメータ
入力パラメータ
( ) ( )
−−⋅= ∑ 2
2
2 2exp
2
1
i
i
iii
xSxGσ
µπσ
ライトカーブをガウス関数の足しあわせで表現
ガウス関数G:
8

アルベドのみによるライトカーブ
観測のライトカーブ
シミュレーションによる形状のみのライトカーブ
LongitudeIn
tens
ity
形状の効果

Longitude
Inte
nsity
ライトカーブをガウス関数の足しあわせで表現
ガウス関数を8つに固定し、ピーク中心を45°おきに設定.
ライトカーブから形状の効果を差し引いてから、ガウス関数の和でfittingした.
9

経験式の導出について
横軸: x (アルベドを持たせる経度分布幅)
縦軸:σ(ガウス関数で表したときの標準偏差)
σ(x、α)を導出
横軸:w(single scattering albedo)
縦軸:S(ガウス関数の強度(面積))
S(x、α、w)を導出
(S∝xは自明)

・中心値μ :Vestaの経度と1対1で対応
・強度S(w,α、x) :
・標準偏差σ(α,x) :w依存性は無い
( ) [ ( ) ( )( ) ( ) ( ) ]( )( )( )( ) 69763.8
674774.4505.1
121686.05
tan,,
51.1
57.1
2
+−=+−=
=+−=
×++⋅⋅=
αααα
ααα
ααααα
dcba
xwdwcwbaxwS
( ) ( ) ( )( )( ) 7.3802.0
000933.01079.8,
50.1
28
2
+−=+×=
+=−
αααα
ααασ
gf
gxfx
経験式

結果~Vバンドについて
今回の観測でのVバンドのアルベドマップ
Wの可視化(白:w=0.5、黒:w=0.4)
緯度 上:ガウス関数の面積から
経験式を用いてwに変換し、コンターをつけて表した図.
下:求めたアルベドマップをVestaの形状に当てはめ、実際にライトカーブシミュレータで計算させた結果.赤が観測を表し、緑の点線がシミュレーション. 観測結果をよく満たす結果が得られた.
基線がガタガタなのは形状の効果による
10

結果~Vバンドについて
過去の研究を合わせたアルベドマップ
McCheyne et al. (1983)(18°N)
Blanco et al. (1978)(16°S)
今回の観測(14°N)
HST画像Binzel et al. (1997)
これら3つをまとめると‥‥
北半球でHSTの画像と非常に近い結果→南半球も近いであろう. 11

多波長での観測から~結果
北緯14°のアルベドマップ
12経度
同様にして求めた各バンドでのアルベドマップ.
縦に切ると、経度ごとに各バンドのアルベドが見られる.
つまり経度ごとに、横軸に波長をとると離散スペクトルが得られる.

多波長での観測から~結果
経度ごとの離散スペクトル
13

多波長での観測から~考察
•315~135°の4つが同様の傾向。吸収が浅く幅が広い、またアルベドが低いことから、Olivineが存在していることがわかる。
•135~315°は変化に富んでいる。
•270~315°は幅が狭く強度が強い、またピークが長波長側にあることから、Olivineは無く、Diogeniteの傾向と一致する。
•135-180°は逆に幅広で短波長側にある。これらはEucriteの傾向と一致する。
180 90 0 270 180
olivine DE
wavelength(µm)
Nor
mal
ized
“w”
14

• 可視から近赤外6バンドの観測をし、ライトカーブを得た.
• ライトカーブをガウス関数の足し合わせで表現する手法を導入し、地上観測から表面のアルベドカップを作成した.
• 過去のデータと合わせることで、得られていない南半球のアルベドマップを作成した.
• 北半球のバンドの解析から、HSTの観測結果よりも詳細な議論が可能となり、270°付近の特徴的な地域についてOlivineの存在に否定的でDiogeniteに近いという結果を得た.
結論
15

以下Appendix

pバンドは常に他のバンドと同時に観測した
その中でpバンドが最もCCD感度が悪いので、焦点をpで合わせた
スカイ領域
オブジェクト(小惑星)
星が写っていない領域をスカイといい、この値に誤差が含まれる
この値をオブジェクト領域から引いて、星のカウントを求める
このとき星像が大きいほど誤差が大きくなる
Inte
nsity
pバンドの誤差が小さい理由

観測誤差がフラックスで最大2%
経験式を求めるときに、分布経度幅xを様々な値で振り、xを変えたときにライトカーブの差が2%以内になるのが⊿x<45°であった
従って、解像度として45°を採用し、8つのガウス関数でフィッティングした
従って、観測精度がよくなれば、より詳しく分布を求められると考える
ガウス関数を8つにした理由

用いたガウス関数は、分布幅45°に対応する標準偏差37.41°のみである。これをガウス関数でフィッティングしたときの、 強度Sの誤差が約0.3%
経験式により、Sからwに変換した時の誤差は最大で0.1%
観測誤差(ライトカーブの誤差)が最大2%(1σ)
以上はランダム誤差(確率密度関数は一定値)であり、種類の異なるランダム誤差の足し合わせで誤差は大きくなる。各波長での誤差は以下の通り。
V:1.91%
W:1.67%
X:1.99%
P:1.09%
Z:2.53%
H:1.69%
誤差について

1μm付近の吸収は、
•olivine、pyroxene比
•olivineの組成
•pyroxeneの組成
•粒径
•宇宙風化作用
に依存する
通常は2μmの吸収との比較で求められる。1μmのみでは、Adams (1974)より、olivineが増すと吸収の幅が広くなる
ともにFe成分が増すとピーク中心が長波長側にシフトする。PyroxeneにおいてはCaが増すと、長波長側にシフトし、吸収が浅く、スペクトルの傾きが大きくなる。宇宙風化作用に似ているが、pyroxeneにはほとんど効かないので区別できる。
Hiroi et al. (1994)より、粒径が細かくなるにつれて吸収が浅くなる。Vestaの平均スペクトルは非常に細かい(25μm以下)HED隕石に近い。
Olivineが宇宙空間に長期間暴露されていると吸収の減少、アルベド低下、スペクトルの傾きの増加がおこる。
さらに、Hiroi et al. (1995)のHED隕石の室内実験より、eucriteはdiogeniteに比べてピーク中心が長波長側、吸収の幅が狭い、吸収の強度が弱い、という特徴をもつ。HED隕石はpyroxeneとplagioclaseでできている。
1μmの吸収の一般論

以上をまとめると、
・ 強度が異なる場合、粒径による可能性がある。同時期に晶出したと考えると岩石中のmaficな成分量は同じと考えられるからである。また、olivineについては宇宙風化作用の可能性も合わせて考える必要がある。
・ バンド中心が長波長の場合、周囲と比較して、Feに富む、pyroxeneの組成がCa-richである、olivineが多い、という3点が考えられる。
・ 吸収の幅が広いほど、olivineの量が多いことを示す。
・ ただし、クレータ地形においてはmaficな成分量が違う可能性があるので、上の限りではない。
・ HED隕石との比較を考えると、eucrite(より表面でできたとかんがえられている)はピークが長波長側、幅広で、吸収の強度が小さい。
1μmの吸収の一般論(II)

最終的に再現したライトカーブ
W