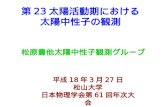太陽観測衛星 SOLAR-C...1 太陽観測衛星SOLAR-C ワーキンググループ設立提案 太陽が、今「ひので」で面白い 宇宙科学研究本部・宇宙理学委員会
名古屋大学太陽地球環境研究所 外部評価資料...3 部門と4...
Transcript of 名古屋大学太陽地球環境研究所 外部評価資料...3 部門と4...

名古屋大学太陽地球環境研究所 外部評価資料
自己評価書・将来計画(案)
2014 年3月
1

名古屋大学太陽地球環境研究所外部評価資料
目次
はじめに ....................................................................................................................................................... 4 1.自己評価書 ............................................................................................................................................ 5 2.将来計画(案) ................................................................................................................................... 19 資料編 ......................................................................................................................................................... 22 資料1:研究所全般 ................................................................................................................................... 23
A.概要 .................................................................................................................................................. 23 B.研究所の運営体制 ............................................................................................................................ 25 C. 予算状況 .......................................................................................................................................... 29 D.研究活動 .......................................................................................................................................... 30 E.国内及び国際共同研究 .................................................................................................................... 33 F.学会活動などへの貢献 .................................................................................................................... 41 G.学内他部局との連携(研究) ......................................................................................................... 44 H.教育活動 .......................................................................................................................................... 45 I. 一般社会への貢献 .......................................................................................................................... 48
資料2:各部門の活動 ............................................................................................................................... 52 大気圏環境部門 水野グループ(第 1 部門 1) ...................................................................................... 52 大気圏環境部門 松見グループ(第 1 部門 3) ...................................................................................... 56 電磁気圏環境部門(第2部門) ............................................................................................................. 60 太陽圏環境部門 太陽風グループ(第3部門1) .................................................................................. 67 太陽圏環境部門 宇宙線グループ(第3部門2) .................................................................................. 70 総合解析部門(第 4 部門) .................................................................................................................... 75 ジオスペース研究センター(学術的成果) ................................................................................................ 80 ジオスペース研究センター(運用・運営・貢献面) ................................................................................. 83
資料3:観測所 .......................................................................................................................................... 92 母子里観測所 .......................................................................................................................................... 92 陸別観測所 .............................................................................................................................................. 93 富士観測所 .............................................................................................................................................. 94 鹿児島観測所 .......................................................................................................................................... 95 観測所関連業績(論文・報告書・紀要、等)数 .................................................................................... 96
資料4:基盤設備 ....................................................................................................................................... 98 基盤設備名:IPS太陽風観測装置 .......................................................................................................... 98 基盤設備名:超高層大気イメージングシステム(OMTIs) ................................................................... 99
2

基盤設備名:太陽中性子望遠鏡ネットワーク ..................................................................................... 100 基盤設備名: 短波ドップラーレーダー装置 ......................................................................................... 101 基盤設備名:高層大気温度観測装置(ソディウムライダー) ............................................................ 103 基盤設備名:ミリ波大気放射分光観測装置 ......................................................................................... 104 基盤設備名:大気組成フーリエ赤外分光観測装置 .............................................................................. 105 基盤設備名:大気環境変動解析装置 .................................................................................................... 106 基盤設備名:STEL磁力計ネットワーク ............................................................................................... 107 基盤設備名:STEL VLF/ELF ネットワーク ............................................................................................ 109
資料5:領域横断的な重点共同研究プロジェクト ................................................................................... 111 プロジェクト1 ...................................................................................................................................... 111 プロジェクト2 ..................................................................................................................................... 112 プロジェクト3 ..................................................................................................................................... 114 プロジェクト4 ..................................................................................................................................... 116 1.年度別の参加研究者数 .................................................................................................................. 118 2.年度別の共同利用・共同研究数 .................................................................................................... 119 3.関連業績(学術論文)数 ............................................................................................................... 119
3

はじめに
名古屋大学太陽地球環境研究所は、関連学会(現地球電磁気・地球惑星圏学会等)の要望を基に、文部省
測地学審議会、日本学術会議などの決議を受けて、「太陽地球環境の構造とダイナミックな変動過程の研究」を
目的とした全国共同利用研究所として、1990 年 6 月に設立された。宇宙科学と地球科学双方にまたがる太陽地
球系科学全域をカバーする唯一の共同利用・共同研究拠点として、1)太陽地球系で生起する物理素過程及び
複合系の理解、2)太陽から放出されるエネルギーと物質が太陽地球系の構造と変動に与える影響の解明、3)陽
地球系科学の国際プロジェクト推進と実社会に役立つ成果の創出、4)太陽地球系研究における共同利用・共同
研究拠点の推進、を目的に掲げてきている。この目的のために国際水準の高度な研究を推進し、高度な学術研
究の成果をあげるための組織と環境を整備することにつとめ、国内外の研究者との共同利用・共同研究を進める
よう努力してきた。
設立から 5 年後の 1995 年 9 月に、研究所の活動状況について第 1 回目の外部評価を実施している。6 年後の
2001 年 2 月には、全国共同利用の附置研究所としての特色ある研究の将来計画案を対象に第 2 回外部評価を
実施した。さらに、大学の法人化から 3 年が過ぎた 2007 年 9 月から 2008 年 1月にかけて、第 3 回目の外部評価
を実施した。大学評価機構による第一期中期計画の中間評価に合わせて、評価対象事項を①研究所の水準、
②研究課題毎の成果と将来計画、そして③共同利用の水準の 3 項目とした。特に研究業績の評価は、2 段階の
評価方式を行った。第一段評価は国内 8 名、海外 41 名の匿名評価者により、発表論文の研究業績評価がなさ
れた。評価結果は、論文がおおむね優れており、とりわけ高い評価のものがあることが指摘されている。第二段評
価は、4 名の外部評価委員により行われた。その結果として研究所の現状はおおむね満足できるものであるが、
更なる発展に向けて、研究所が将来あるべき姿をロードマップとして提示すること、宇宙天気や学際的な研究の
推進、国際連携、若手育成についての提言を受けた。
前回の第三回外部評価以降の今日までの 5 年間、外部評価の提言を生かしつつ研究・教育活動や組織運営
を進めてきた。この間の研究所に係る主な出来事として、2009 年に行われた大学評価機構による第一期中期期
間中の研究所の評価では研究活動に関しては「期待される水準を上回る」と言う高い評価を受けた。また、2010
年からの第二期中期期間では、研究所は文部科学省より共同利用・共同研究拠点に認定されている。本年度
(2013年度)の拠点の中間評価で S,A,B,C評価で「A評価」をもらいその活動を良く評価された。さらに、教育活動
では、主として大学院教育において、グローバルCOEプログラム「宇宙基礎原理の探求」(2008-2012年度)、そ
して 2012 年度から始まったリーディング大学院「フロンティア宇宙開拓リーダー養成」で、本研究所の教員が中心
的な役割を果たしている。
前回の外部評価から 5 年が経ち、我々のこの間の活動と今後の計画に対して新たに外部評価を行うことにした。
毎年、年報の形で自己点検評価を行っているが、今回は外部の有識者の皆様に客観的な視点で評価・検討して
いただく。外部評価委員の 4 名の先生方には、お忙しい中で評価委員をお引き受けくださり感謝している。評価
委員会の先生方から頂くご意見を・ご提言を生かして、本研究所の今後の発展と社会への貢献に生かしていきた
いと考えている。
2014 年 3 月
名古屋大学太陽地球環境研究所
所長 松見 豊
4

1.自己評価書 (1)過去 5 年間の概要とその自己評価 太陽地球環境研究所では第 1 期中期計画(2005 年~2009 年)において、太陽-地球間の天気予
報図を世界に発信することを最大の目標として、「ジオスペースにおけるエネルギー輸送過程」に関
する特別研究教育経費を獲得し、全国共同研究を実施した。この計画においては、3 つのプロジェク
ト(資料 E)を立てるとともに、新たに大型装置を導入して太陽から地球に至る広大な範囲の中の
重要領域で観測を行い、モデリング・シミュレーションとリアルタイムで融合する研究を行った。
国際的には、SCOSTEP の CAWSES プログラムへの協力を行った。これにより、基盤設備の整備
が進み、地球大気、電磁気圏、太陽圏各領域の観測を発展させることができた。特に、IPS による
太陽風分布図(資料 4:IPS 太陽風観測装置)や太陽地球環境データ解析システム(GEDAS)によ
る電離圏電流分布図などがリアルタイムで配信されるようになり、当初の目標はほぼ達成したと考
えている。大学評価機構による第一期期間中の研究所評価においても、「研究の水準」に関しては「期
待される水準を上回る」と言う高い評価を受けている。 第 2 期中期計画(2010 年~2015 年)では、宇宙嵐にともなう粒子加速・輸送機構と、太陽活動
変動が地球大気に与える短期・長期的影響を明らかにすることを目標として、「太陽極大期における
宇宙嵐と大気変動に関する調査研究」を特別教育研究経費によって実施している。この中では 4 つ
のプロジェクト(資料 5)を推進し、新たな大型共同利用の導入やサイエンスセンターの整備をお
こなっている。国際的には SCOSTEP の国際プロジェクト CAWSES-II を主導している。プロジェ
クト 4 年目にあたる 2013 年度において、計画の最終目標である宇宙嵐にともなう粒子加速・輸送機
構と、太陽活動変動が地球大気に与える短期・長期的影響の解明には未だ至っていないと考えてい
るが、資料に示すようにそのための衛星や地上観測、モデリングに関する基盤整備は整いつつある。
文科省による共同利用・共同研究拠点の第二期中期の前半 3 年間(2010-1012 年)の評価では、「A」
評価をうけた。このことは、全国の研究者と連携した共同研究を着実に推進していることを意味し
ている。 (2)運営組織に関する自己評価 ・部門組織 太陽から地球までの領域に分けた部門制とその中の研究グループ内の教員が比較的まとまって研
究を進めており、多数の研究成果を上げている(資料)。また、2 部門・4 部門・ジオスペースセン
ターによる地球電磁気圏研究、1 部門・3 部門・4 部門による宇宙線による雲核生成に関する研究、
3 部門と 4 部門による太陽風観測データを基にした太陽地球系モデリング研究など、これまでに無
い部門間の協力研究が過去 5 年間で拡大している。これらは、本中期計画におけるプロジェクト研
究の成果でもある。こうした分野横断型研究をさらに発展させ、新たな成果に結びつけるためには
さらなる工夫が必要であるが、一定の発展性を見出すことができると考えている。 ・研究所の所内運営組織
5

教授会及び運営協議会の他に、助教も含めた全教員が同じ立場で参加する教員会議や教授のみか
らなる教授会議など多様な運営システムの基に、研究所の運営諸課題にについて所員の意見を反映
した適切な運営がなされていると考えている(概要:研究所の運営体制)。 ・共同利用運営組織 共同利用の運営に関しては、共同利用委員会及びその専門委員会を組織し、全国の関連する研究
者の参加の基に、最新の研究動向とニーズにマッチした共同利用・共同研究拠点の運営ができてい
ると考えている。ただし、特別経費を財源として共同利用委員会が所掌する共同利用と、ジオスペ
ース研究センターの運営経費を財源として同センターが所掌する共同利用が複雑にからみあった構
造となっているため、より分かりやすい運営体制の構築が課題となっている。ただし、毎年 160 件
余りの共同研究申請を適切に審査するためには相応の人数が必要であるが、これらの運営の負担を
如何に軽減するかも現在の課題となっている。 ・所内教員年齢構成及び人事交流 人材の流動性の向上のため教員個人評価システムを導入しているが、その実効性を高める為には
さらなる取り組みを必要すると考えている。 (3)基盤設備及び観測所に関する自己評価 ・第 1 期中期で導入された大型装置(概要参照)はすべて、定常観測が開始・継続されて、成果が
得られている。(資料 4:基盤装置) ・観測所については全般に定常的な成果を生み出しているが、一部その維持が困難になりつつある
ものがある。特に、母子里観測所では職員の定年退職などにより維持が難しくなっている。ただし、
維持が難しくなっている観測所でも、母子里観測所・鹿児島観測所の VLF 波動観測などは 1970 年
代から長期観測を続けており、長期変動に関する貴重なデータを供給している。現在、母子里観測
所では人件費 450 万円を負担しているが、豪雪地帯であるので、今後維持し続けるならばきちんと
した管理が要求される。早急に今後の方針を決める必要がある。 (4)予算に関する自己評価 ・研究所予算のうち外部資金は 2010 年以来、安定して取得されている。科研費の取得については、
他の類似研究機関に比べて、外部資金の獲得数・金額共に多いことから、平均的に高い水準を維持
している(資料:外部資金)。しかし、基盤 S や新学術領域研究などの大型予算が獲得できていない。
全国的な大型共同研究をさらに拡大するために、大型科研費の獲得は必要であり、今後さらに努力
を続けるべきと考えている。また。JST 等からの委託研究はそれほど多くないので、増やす必要が
ある。 ・特別経費などの概算要求予算については、安定して共同利用の拠点運営経費を受けており、安定
した共同研究を維持している。さらに、太陽地球システムの各領域の包括的な観測を目指して大型
装置の概算要求を毎年申請し、2012 年度補正予算によって北海道第 2 レーダーや IPS アンテナの大
型装置がの予算を獲得することができた。
6

・ただし、第 3 期に向けて新たな展開を検討する必要がある。このため、研究所の長期的な将来計
画の基本方針を策定すると共に、これに基づいたより実効性の高い新たな共同研究の形態やこれま
でに無い分野間連携を目指した研究計画を策定する予定である(将来計画(案)参照)。また、国際
協同研究 VarSITI、太陽活動の気候影響等の課題を中心に、組織改革を含めて新たな概算要求のプ
ロジェクト申請を出す準備を進めている。さらに、大学間連携による IUGONET は、2014 年度で
終了するが、その後のデータベース整備のため、新たな予算獲得の取り組みが必要であるため、現
在計画を策定しつつある。 (5)研究活動に関する自己評価 研究所全般 第 2 期中期の目標である太陽極大期の粒子加速・太陽活動の地球への影響に関連して、最近、太陽フ
レアの予測可能性の実証、過去の巨大フレアの発見、放射線帯粒子加速のプロセスの実証、などのめざ
ましい成果が上がっている。研究所の論文数に関しては、類似の他研究機関と比べて遜色ない成果が得
られている(資料)。共同利用が広がり、外部の研究者との共著論文が増えている。関連分野の共同研究
機関と比較するならば、「一人あたりの科研費受入金額」及び「一人あたりの論文数」共に、高い水準を
維持していることが分かる(資料)。さらに、論文あたりの年平均被引用数も関連機関に比べて遜色ない
値を示していることから、研究の質においても一定の水準を維持していると評価している。一方、研究
所の研究者による主著論文の数が少ないことと、100 件以上の citation を持つような革新的な成果論文が
少ない、という点が課題である。今後、インパクトの大きな研究成果を独自に創出するための取り組み
が必要と考える。 (6)教育活動に関する自己評価 ・環境学研究科や理学研究科との連携により 21 世紀 COE や GCOE プログラムを成功裏に終えて、リー
ディング大学院への採択に大きな貢献を行った。現在、リーディング大学院「フロンティア宇宙開拓リ
ーダー養成プログラム」では本研究所の教員がプログランコーディネーターを出すなど中心的役割を果
たしている。 ・豊川から名古屋への移転、GCOE プログラムの導入によって明らかに学生数が増加した(資料学生数)。
昨年 10 月からのリーディングプログラムによりさまざまな施策が実施されており、さらに今後学生数が
増加すると期待できる。 ・理学研究科は学部生の卒業研究を引き受けていないので、大学院生が入りにくくなっている。物理教
室との連携を深めることによって、名古屋大学の学生にSTE研の活動により興味を持ってもらえるよ
う努力する必要がある。 ・博士後期課程への進学率は約 30%程度であり、修了者は国際的な研究機関から民間企業まで広い分野
で活躍している(資料 進路調査)。現在、後期課程への進学を妨げるものは、PD 問題と博士後期課程
における生活費の問題が考えられる。企業で活躍できる人材を博士後期でより積極的に育成することや、
博士後期での生活費支援などを、新たに採択されたリーディングプログラムで進めることによってこれ
らの問題の解決に取り組んでいる。
7

(7)各部門の研究教育活動に関する自己評価 ・1 部門1(資料) この5年間は太陽極大期の昭和基地でのミリ波観測という明確な目標に向け、機器開発、観測、デー
タ解析がうまく連結し実施でき、高エネルギー電子の降りこみの効果に関する新たな知見などの成果が
出つつある。機器開発においては、これ以前の5年間で明らかになってきた問題点や課題を克服し、操
作が容易で安定性の高い実機を組み上げられた。国内で地上ミリ波観測を長期間安定に運用できている
のは我がグループのみであり、こうした技術を継承し更に発展させられる若い世代を育成しなければい
けない。その一方で、データ解析アルゴリズムの開発がやや遅れ気味で、今後人材を投入し、より効率
的で汎用性の高い解析プログラムのシステム化開発を進めていく必要がある。また、解析アルゴリズム
の開発の後には、衛星観測データとの比較、他の地上観測データとの比較、モデル計算との比較などを
きちんと押さえていく必要がある。衛星観測データとの比較のための環境作りは国立環境研のグループ
と、他の地上観測データとの比較については JICA-JST の国際協力(SATREPS)の枠組みの下でアルゼン
チンのライダー研究機関やチリのオゾンゾンデ研究機関とともに進みつつある。モデル計算についても
所外の研究者との議論は進めているが、自前でも WACCM 等のモデルを走らせる環境を整えていきたい。 また、ミリ波観測以外でも、光スペアナを用いた赤外線分光による温室効果ガス測定装置の開発や、
地球外の太陽系内天体の大気観測も少しずつではあるが着実に進み、成果につながりつつある。 1 部門3(資料) ・本研究グループに関しては、前回の外部評価では、「『大気圏環境研究−大気環境変動に与える人為活動
や太陽活動の影響の解明』においては、高精度かつ高感度の大気微量成分の計測技術の開発とそれを用
いた観測・実験研究が行われており、その内容は先導的であり、当該グループの定評ある大きな特徴と
なっている。」と評価された。この 5 年間で、それらの課題を発展させ、課題とされた「独自に開発した
装置のフィールド観測への応用」や「他の研究機関の研究者の連携」が着実に進んでいる。地球温暖化
に関連して二酸化炭素の動態を調べるため気球CO2観測装置の開発・計測同位体計測装置の開発・計測、
光吸収性エアロゾルの装置開発・計測等で研究成果を上げてきた。外部資金については、科学技術振興
機構(JST)の競争的資金:先端計測機器開発事業の光イオン化計測器(PI:松見)の 5 年で 2 億 2 千万円
の比較的大規模な予算を 2009 年 3 月に終了して、事後評価で A 評価をもらっている。その後も科研費
などを着実に獲得している。教育に関しては、この 5 年間で 11 名の修士号取得者を輩出している。 ・2 部門(資料) 光学観測機器・電磁場観測機器による地上多点観測ネットワーク、北海道レーダーによるサブオーロ
ラ帯の電離圏観測、大型ライダー・EISCAT レーダーによる北欧での拠点観測は、国内に広く共同研究
が広がるとともに国際的な共同研究も展開され、数多くの成果が上がっている。SCOSTEP に関連した
国際的なリーダーシップ活動や既存の観測の維持に時間をとられ、マンパワーが足りなくなりつつあり、
2011 年 11 月より欠員になっている 1 名の助教ポストの充足が強く望まれる。2011 年 4 月から新たに加
わった探査機搭載機器開発グループは、研究所の建物移転に伴って実験室が整備され、これから成果が
上がっていくと思われるが、大きなプロジェクトや長期の開発計画に関わっているため、成果創出の時
間スケールが長くなっている。教育においては、2008 年の名古屋移転後、工学部・工学研究科及び理学
研究科から毎年 5-10 名程度の学生が入るようになり、豊川時代に比べて学生数が大幅に増えたのは良い
ことである。
8

・3 部門1(資料) 太陽風は太陽から地球への重要なエネルギー輸送過程の一つであることから、その生成機構やダイナ
ミックスを独自の技術に基づいた観測から解明することを当部門の使命として研究活動を行ってきた。
前回の外部評価では、その取り組みが世界的にユニークなものとして高く評価され、「人材と資金の継続
的投資により、今後も継続発展すべき」との提言を得た。これを踏まえて、第Ⅰ期特別研究経費を使っ
て豊川新アンテナを開発し、さらに平成 24 年度補正予算・科研費などを使って富士・木曽アンテナの更
新を行っている。得られた観測データから特異な太陽活動に伴う太陽風の変動や宇宙天気予報、太陽圏
外圏域に関する研究が実施され、成果が得られつつある。特異な太陽活動や太陽圏外圏域の研究は今後、
さらに発展が見込まれ、当部門の観測研究の重要性は将来に向けて益々高まっている。現在、低周波帯
の電波天文観測には広い分野から注目されており、当部門の観測研究は我が国における数少ない実績と
なっている。よって、当部門の活動を今後も一層強力に推進すべきであり、その活動の中核となる人員
の確保が必要と考える。自前のデータに基づく研究を強化することは共同利用研の観点からも有意義で
ある。 ・3 部門2(資料) 第3部門2では、前回外部評価において受けた2つの提言に対してアクションを行った。ひとつめは
「理学研究科の宇宙実験経験者(X線・赤外線)との連携による宇宙への進出」であり、飛翔体による
宇宙ガンマ線実験への進展を図るため、田島教授、奥村助教を採用し、部門内に新たに宇宙ガンマ線研
究グループを形成した。田島教授は Astro-H 衛星軟ガンマ線検出器や次世代ガンマ線望遠鏡研究を推進
し、宇宙プラズマでの粒子加速研究を行う傍ら、超小型衛星 ChubuSat 計画の推進者として研究所に衛
星ハードウエア開発の芽を導入すると共に、理学研究科、工学航空宇宙工学専攻と共同で行っているリ
ーディング大学院「フロンティア宇宙」のプログラムコーディネーターとしても活躍している。 ふたつめは「太陽地球系科学の研究者と宇宙線研究者が同じ研究所に属する事実をメリットとして他
ではできない学際的研究にとりくむ」であり、第 1 部門松見グループ、第 4 部門草野教授らと共同で、
宇宙線による雲核生成実験を立ち上げ、放射線計測、大気物理、シミュレーション研究の3領域が複合
するユニークな研究を推進した。 部門内の研究は着実に進展し、多くの成果が上がっている。古木年輪中放射性炭素14の研究ではA
D775年の宇宙線上昇事象を発見、重力マイクロレンズ効果による系外惑星探査では浮遊惑星の証拠
を発見し、大きなインパクトを持つ業績となった。ここ数年間では、年間論文数は主著論文(学生主著
含む)約5本、共著論文約40本、平均引用数は30以上(2011 年以前の論文に対して)となっている。
共同研究が主となる実験的研究グループであるため共著論文数は多いが、研究所の visibility をあげるた
め、今後は教員主著論文の数や引用数も増やしていく必要がある。外部資金獲得状況については、ここ
数年は年間約10件、総額約6000万円に達しており、高い研究アクティビティを支えている。学生
の教育については、総学生数は平均25名前後、博士課程後期学生数も約5名程度と高いアクティビテ
ィを維持している。教員が理学研究科教育への積極的な貢献したり、GCOE、リーディング大学院な
どを中心となって推進してきた成果が現れている。 このように、研究、教育両面にわたって高いアクティビティを持ち、引用数の高い業績も多く創出し
ている反面、それらの成果の大半は必ずしも太陽地球系分野内にとどまらず、理学研究科で行うべき研
究トピックであるとの指摘もある。素粒子宇宙起源研究機構、南天観測センター等、所外の関連組織と
の連携で現在の研究アクティビティを維持したまま、今後は、衛星開発への貢献や太陽地球系分野によ
9

り直結した研究の推進などを戦略的に立ち上げていく必要がある。 ・4 部門(資料) 前回外部評価においては「データ解析とモデリング・シミュレーションを有機的に結びつける努力の
発展性に期待が持てる」との評価を受けた。その後、データ解析とシミュレーションの融合による本格
的な総合解析研究を発展させるため、草野教授、町田教授、今田助教を新たに迎え、太陽地球環境シス
テムを包括的に研究できる体制を整備すると共に、GEMSIS プロジェクトを着実に推進した。その結果、
太陽フレアの発生機構に関する研究、磁気圏サブストーム開始時における電磁流体力学的なネルギー収
支の定量解析、磁気嵐時における電場の赤道領域侵入過程の解析、放射線帯外帯の変動と太陽風大規模
構造の相関メカニズムに関する研究などについて多くの重要な成果をあげることができた。こうした成
果に基づいて宇宙天気予測へ貢献できる研究成果が生まれ始めていることは評価できる。さらに、国立
天文台及び宇宙科学研究所との連携を通して、太陽観測衛星ひのでサイエンスセンター及びジオスペー
ス探査計画 ERG サイエンスセンターそれぞれの設立・運営の主体として活動し、コミュニティーへ大
きな貢献を行ったことは特筆すべきである。こうした多様な活動を通して活発な共同研究を実施し、高
い論文出版数を維持している。ただし、教員数に対する主著論文出版数は十分ではなく、今後の努力が
必要である。また、引用数の特に多い論文の出版も十分といえない。インパクトのより大きな研究の創
出に向けた取り組みが必要と考えている。 教育活動やアウトリーチ活動も積極的に行っており、特に大学院教育においては過去数年で大きな改
善がみられている。過去 5 年間の学生数は 5 名、6 名、6 名、9 名、11 名、20 名(学部 4 年生を含む)
と急増した。本年度の大学院入試では理学系で 8 名の応募が全国の大学(名大、京大、大阪市立大、立
教大、明星大、島根大)からあった。平成 25 年度からは工学研究科担当の町田教授の赴任に伴い、理学
系学生と工学系学生が同じ研究室で研究する本格的な理工融合型教育を実施している。こうした取り組
みによって太陽地球系を包括的に捉える総合解析部門独自の教育活動が活性化しつつあると考えており、
太陽地球システムを包括的に捉えることができる世界的にもユニークな人材育成に今後とも努めたい。 ・ジオスペースセンター(資料) 流体モデルから運動論モデルに至る宇宙プラズマシミュレーションの開発と応用研究を多角的に実施
し、優れた成果を生み出すことができた。3次元 MHD コードを用いた研究については、評価期間にお
いて 11 名の学生が本研究課題に関わった。また、様々な計算機上での高速化チューニングが高く評価さ
れ、学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)研究課題として採択された。無衝突衝撃波の
研究については、評価期間において 2 名の学生が本研究課題に関わり、学生が第 2 著者の査読付き論文
を 6 編発表した。また、無衝突衝撃波の研究成果を含めた業績により大林奨励賞を受賞するとともに、
新学術領域の採択にも繋がった。ブラソフコードを用いた研究については、評価期間において 5 名の学
生が本研究課題に関わり、学生が第 2 著者の査読付き論文を 6 編発表した。また 1 名は電気系教室修士 1年生中間発表会において優秀発表賞及び、International Conference of Frontiers in Computational Science 2008 において Best Presentations Award を受賞した。また、ブラソフコードを用いた一連の成
果を含めた業績により大林奨励賞を受賞するとともに、HPCI「京」利用課題にも採択された。当分野・
当研究所のような HPCI 戦略分野に該当しないグループから HPCI「京」利用課題が採択されるのは名
誉なことであり、計算科学関連分野において認知度が徐々に上がってきていると言える。
10

限られた予算・人員の中で、所外の意見を取り入れつつ領域横断的な共同研究プロジェクトその他デ
ータベース作成共同研究、計算機利用共同研究等の事業を進める体制を整備しており、各事業の遂行に
おいて主導的な役割を果たしている。 (8)観測所に関する自己評価 母子里観測所(資料)
母子里観測所については同じ道内に陸別観測所があることから、研究所としてより効率的・効果的な
観測所運営を目指す必要がある。また、技術職員や研究支援推進員制度が利用できなくなっており、非
常勤の技術補佐員 2 名の雇用にかなりの費用がかかるようになっている。本研究所は、共同利用研究者
の地上観測を支援する責務があるが、効率的な支援を考えて、現地の雇用人件費を含めてかなり多額の
お金をかけているので、それに見合う重要度のデータが得られているかどうか、同じ金額を他の共同利
用に回した時との比較など、経営的感覚を持ちながら今後の検討をする必要がある。
陸別観測所(資料) 北海道陸別は低緯度オーロラやオゾン層破壊を観測する上で日本国内としてもユニークな場所に位置
し、長期にわたるモニターデータを粛々と蓄積し様々なデータベースとして関連研究者に利用されてい
る。また、北海道-陸別短波レーダーは中緯度の SuperDARN レーダーとして興味深いデータを学界に提供
している。観測室として町立天文台の2階部分を借り受けている陸別町ともパブリックアウトリーチ等
の社会貢献を通じて非常に良好な関係にある。成果もコンスタントに出ており、観測所としては順調に
運用がなされていると考えている。しかし、その一方で開所以来 10年以上を経過し、装置によっては最
初の導入から 20 年近く経過している観測装置もあり、老朽化にともなう故障や制御系計算機の OS のサ
ポート中止に伴い新たな更新や改良が難しくなっているなどの問題も出てきている。観測装置の管理や
データの一次処理を現地の派遣業者職員(1名)に依頼しているが、観測室内だけの作業だけでなく冬
季の雪かきや 15km離れたレーダーサイトまわりの管理などの付加的な作業もあり、自動化や遠隔モニタ
ーの充実を通して作業量を減らし省力化を図っていくことが課題である。
富士観測所(資料)
富士・木曽・豊川・菅平の4つの観測所で取得されている太陽風データは、貴重な研究資料として活用
されており、将来に向けて観測を継続してゆく必要がある。また、富士観測所はその地理的利点から所
外の研究者による利用が活発になっている。これらの観測所の維持・運営はこれまで経費を極力抑えつ
つ行ってきた。今後もその努力を継続しつつ、維持のための財源の拡充を行ってゆく必要がある。
鹿児島観測所(資料) 鹿児島観測所は日本の南部に位置し、1976 年からの長期にわたる VLF 波動観測と、1989 年の 210 度地
磁気チェーンの開始時からの地磁気観測のデータを長期にわたって連続的に提供している。特に VLF 波
動観測は、千葉大学と共同で電離圏 D 層高度の長期変動を明らかにするなど、世界に他に類を見ないデ
ータである。また、佐多観測点は、2004 年に世界で初めて中規模伝搬性電離圏擾乱の磁気共役性を明ら
11

かにするなど、オーストラリア・ダーウィン観測点の地磁気共役点というユニークな位置にある。今後
は、VLF・地磁気・大気光の長期観測をできるだけ継続し、地球の気候変動に伴う電磁気圏の変動を明ら
かにするための基礎データを取得していく必要があると思われる。
(9)基盤設備に関する自己評価 IPS 太陽風観測装置(資料) 太陽風加速機構の解明や宇宙天気への応用に加えて 特異な太陽活動の到来や太陽圏外圏域探査の新
展開の観点から、本装置による観測データの重要性は益々増してきている。当該期間において獲得した
大型予算により装置が更新され、IPS 観測が継続して実施できる環境が整ったことは大いに評価できる。
将来の太陽圏研究に向けて次世代の IPS 観測システムの開発研究が重要な課題となる。また、熟練した
技術職員の退職に伴い若手への技術継承も緊急の課題となっている。 超高層大気イメージングシステム(OMTIs) (資料) 本システムは世界に他に類を見ない多数の大気光カメラを保有し、他の分光機器と組み合わせて、中
間圏・熱圏・電離圏の新しい成果を創出してきた。また国際展開することにより、国内だけではなく世
界の関連研究者との共同研究が発展している。発展途上国では、現地の研究者の育成にも役立てられて
いる。大学院生を現地に派遣することで、学生のフィールドワークの訓練にもなっている。
一方で、機器数・観測点数が増えるにつれ、限られたマンパワーでの運営が限界に達しつつある。全
ての機器は自動化されているが、常にどこかは故障していることが多く、定常運用を続けるための予算
的・人的資源が必要とされる。それぞれの観測点はそれぞれ現地との関係が深く、容易に観測を停止す
ることは難しい。 今後は、特に発展途上国において、現地研究者の教育をすることにより、現地で成果の創出と機器の
メンテナンスを行えるようにしていくことが重要と思われる。 太陽中性子望遠鏡ネットワーク (資料) 太陽中性子のエネルギーと方向を測定できる唯一の検出器として、太陽フレアでの粒子加速の解明に
ユニークな貢献をしている。また乗鞍山頂および世界各国低緯度の 4000m 級高山6箇所に配置された 24時間観測ネットワークは、多国間にわたる国際共同研究体制を構築している。一方で、太陽中性子イベ
ントはレアな事象であり、20 年近い観測期間で得られた事象数は11例に過ぎない。さらなる発展のた
めに統計の飛躍的な増加が必要であり、新型望遠鏡の目指すような低S/N事象の検出や、ISS-SEDA で
行われているような宇宙空間での観測の検討が必要である。特記事項として、新型太陽中性子望遠鏡は、
最新の素粒子測定技術を研究所に導入する契機となっており、高エネルギー加速器研究機構測定器開発
室と本研究所技術部が連携して SiTCP 等最新技術によるデータ取得回路の開発が進行中である。 短波ドップラーレーダー装置 (資料) 本装置が属する SuperDARN ネットワークは世界 11 ヶ国から 33 基のレーダーが参加しており、南北
両半球の高緯度から中緯度にわたる観測を継続して実施しているが、本装置は磁気緯度約 36 度と最も低
12

緯度の場所に位置しており、この地理的特徴を生かして上記のような成果を出し続けている。また STE研が陸別観測所および極東ロシア観測点に設置した大気光CCVカメラ等と連携して観測を行うことによ
り、伝搬性電離圏擾乱に関する新しい成果も出している。当該レーダー装置を活用してデータ解析や現
地実習等で学生の育成も行っており、今までに修士論文 3 編、卒業論文 7 編が生まれている。 当該装置の成功を受けて、日本国外でも中緯度域に SuperDARN レーダーを建設する計画が進み、現
在アメリカで 8 基、ロシアで 1 基のレーダーが稼働しており、さらにアメリカで 2 基、ロシアで 3 基の
レーダーが建設中である。日本でも陸別町に二基目のレーダーシステムを建設中である。このように中
緯度の SuperDARN レーダーがネットワークしつつある中、他のレーダーと協力して地球的規模での電
離圏ダイナミクスを理解しようとする取り組みを進めるとともに、他のグループと競争していち早く新
しい科学的成果を追求していくことがより重要になると考えられる。このための取り組みとして、内部
磁気圏衛星 ERG や、宇宙ステーション大気光観測ユニット ISS-IMAP 等との共同研究を進めるつもり
である。 高層大気温度観測装置(ソディウムライダー)(資料) 開発期間3年によりライダーを製作し、トロムソに設置。さらに毎年システム改善を行い、非常に安
定したシステムを構築している。世界初の5方向観測を 2012 年シーズンから実施し、多くの大気温度・
風速データを蓄積している。今後これらのデータを用いた成果を出していく。共同利用的な観測は、毎
年10%程度を実施している。所内論文数3、所外論文数1。成果は順調に出だしているが、共同利用
的な観測が少なく、今後の課題である。なお、取得したデータは基本的にすべて共同利用に供している。 ミリ波大気放射分光観測装置 (資料) 北海道陸別を除くチリ、アルゼンチン、南極昭和基地の観測装置はミリ波観測網の空白域である南半
球の亜熱帯、中緯度帯、極域に位置し、ユニークな観測網を形成している。標高約 5,000m のチリ・アタ
カマ高地の観測条件は極めて良好で、他では取得できない微弱なスペクトルデータの観測を可能にした。
陸別は運用体制は安定していたが、装置自身に経年変化の問題あることが後になって判明した。現時点
では経年変化の影響を補正するための処方箋がほぼ確立しつつあるが、確度の高いデータにまで落とし
込むのに時間を要した。これらの経験をもとに設計・製作したのが南極昭和基地の観測装置であり、特
性も安定しており専門家でない越冬隊員でも容易に運用できるような完成度の高い観測システムとなっ
ている。現時点での課題は、データ解析処理の効率化である。プログラム開発の人員体制を強化して解
析アルゴリズムやプログラムの共通化・汎用化を進め、タイムリーにデータを提供できる環境を整える
ことにより、利用者を増やし、成果の数をあげていきたい。 大気組成フーリエ赤外分光観測装置 (資料) 本設備は陸別では 1995 年、母子里では 1996 年より 15 年近く継続して成層圏・対流圏の大気微量成
分を計測してきた。両地点の観測データを併せることで、季節によって気象条件が大きく異なる北海道
においても天候が相補的な特性を活かして年間を通して大気微量成分の季節変動や長期にわたる経年変
13

化が観測され、太陽活動の地球大気への影響等を長期の地球環境変動を研究する上で日本上空における
ユニークなデータベースとなっている。 また、近年の研究者のニーズに応えて温室効果ガスの定常観測を開始するなど、多様な研究ニーズに応
えた観測にも柔軟に対応してきた。一方で老朽化する測定装置を維持して定常観測を継続することに大
きなコストが必要となってきている。そのため、今後はデータの継続性を維持することを前提に、国立
環境研究所が陸別観測所に導入した温室効果ガス測定用の新型 FTIR によるデータの利用など、運用方
法の見直しを進める。 大気環境変動解析装置 (資料)
大気環境変動解析装置は、平成 21 年度に導入された後、装置の性能試験等を経て、大気エアロゾルの
生成過程や光学特性の観測および室内実験研究に利用されている。特に、本装置により、粒子が浮遊し
た状態でその光学特性を直接計測することで、エアロゾル粒子が気候変動に及ぼす影響の正確な推定に
つながる成果が得られつつある。本装置は、学内(環境学研究科)に加え、国立環境研究所、東京大学、
京都大学、海洋研究開発機構、千葉大学、茨城大学などとの共同研究として利用されており、共同研究
としての利用が 50%以上を占めている。 STEL 磁力計ネットワーク (資料)
本システムは特にサブオーロラ帯に ULF 波動を観測する誘導磁力計を経度方向に展開し、ERG 衛星による内
部磁気圏観測と相補的な観測になっている。国際展開することにより、国内だけではなく世界の関連研究者との
共同研究が発展している。磁力計は比較的簡単で安定した観測装置なので、発展途上国での観測にも活用され
ている。大学院生を現地に派遣することで、学生のフィールドワークの訓練にもなっている。
今後は、ERG 衛星の打ち上げに向けて、観測がなされていないロシア極東域やカナダ東海岸の L=4 付近のサ
ブオーロラ帯に磁力計を設置し、内部磁気圏の放射線帯粒子の加速・消失メカニズムの探査に対して、地上観
測からグローバルな情報を提供していきたい。
STEL VLF/ELF ネットワーク (資料)
本システムは母子里・鹿児島における 30 年以上の長期観測と、サブオーロラ帯での経度方向をカバーする多
点観測が特徴である。後者は ERG 衛星による内部磁気圏の直接観測と相補的である。国際展開することにより、
国内だけではなく世界の関連研究者との共同研究が発展している。大学院生を現地に派遣することで、学生のフ
ィールドワークの訓練にもなっている。
今後は、ERG 衛星の打ち上げに向けて、観測がなされていないロシア極東域やカナダ東海岸の L=4 付近のサ
ブオーロラ帯にループアンテナを設置し、内部磁気圏の放射線帯粒子の加速・消失メカニズムの探査に対して、
地上観測からグローバルな情報を提供していきたい。
(10)共同研究に関する自己評価 国内共同研究(資料)
14

・共同利用の数が年間 160 件以上あり、当研究所が広くコミュニティに共同利用されていると評価でき
る。特に、地方大学や公立・私立大学に優先的に共同利用の支援を行っており、この点は文部科学省に
も高く評価されている。ただし通常の共同研究(70 件程度)は配分額が 1 件あたり 5 万円程度と少額で
ある。一方、第 2 期中期で新たに導入した地上ネットワーク共同利用(上限 100 万円)には申請が年々
増えており、主に国際ネットワーク観測の展開に活用されている。今後、件数を減らしてより重点的な
支援をするか、現在のように少額の支援を広く行うか、議論が分かれており、最適な予算配分について
今後とも検討を続ける必要がある。 ・研究集会が多すぎるという批判があるが、件数を減らしてより大型化するという考え方と、小型でも
焦点を絞った研究集会を数多く支援するか、議論が分かれている。コミュニティ全体の意見を考慮しな
がら調整していきたい。 ・国立天文台及び宇宙科学研究所との連携を通してひのでサイエンスセンター及び宇宙科学連携拠点(E
RGサイエンスセンター)の活動を開始したことは特筆できる。NICTとも学術連携協定を結び共同
研究を積極的に開始しつつある。こうした活動をさらに活性化し、宇宙科学及び宇宙天気研究に関する
新たな拠点の形成につなげる必要がある。 領域横断的な重点共同プロジェクト ・第 2 期中期のプロジェクト(資料)を通して、外部の研究者が地上ネットワーク共同利用などの大き
な予算を使って、当研究所と連携して研究することができるようになった。これは新しい試みとして評
価できる。 ・今後は、適切な問題設定を行うと共に所外の研究者との連携をより強めて分野横断的なプロジェクト
の推進を行う。 ・各プロジェクトの自己評価 プロジェクト1 (第 1 期)CME の素過程の研究 (第 2 期)特異な太陽活動周期における太陽圏 3 次元構造の変遷と粒子加速の研究 第 1 期では、太陽風中における CME の 3 次元特性について宇宙線・IPS 観測データから新たな知見
が得られ、当初の目標は達成された。第 2 期においても、装置の拡充やデータの収集が順調に進んでお
り、期間内に目標とした成果が得られる見込みである。プロジェクト立ち上げ以来一貫して、観測装置
を独自に展開している所外の研究グループに対して重点的に支援を行ってきており、我が国発のデータ
発信に寄与してきた。また、本プロジェクトは我が国における大学院教育にも貢献しており、これまで
に共同研究を通じて所外の大学院生 3 名が博士号を取得している。今後も、この方針は維持して、我が
国の太陽圏研究を発展させてゆきたい。現在、特異な太陽ダイナモ活動が進行中であるとともに、Voyager, IBEX 等による太陽圏外圏域の研究で大きな展開が起こっている。将来には、Solar-C, Solar Probe, Solar Orbiter ミッションによる太陽圏研究の新展開も予想される。こういった研究の流れに対応し、独自のデ
ータをもって国際共同研究を推進できる体制を整備してゆくことが必要になっている。特に重要な課題
は、国内の太陽圏研究者、特に観測・実験グループの層を如何にして厚くするかであり、次期プロジェ
クトの立案にあたっても留意すべき点である。
15

プロジェクト2 (第 1 期)人工衛星ー地上共同観測によるジオスペース研究の新展開 (第 2 期)グローバル地上・衛星観測に基づく宇宙プラズマ-電離大気-中性大気結合の研究 領域横断型プロジェクトは、第 1 期中期計画、第 2 期中期計画ともに、共同利用・共同研究拠点の推
進のための特別経費の母体として立案・計画された。本プロジェクト2は、衛星観測と地上観測をつな
げることを目標にしている。このような努力はm熱圏、電離圏、磁気圏、太陽圏のどの分野でも継続的
に必要であり、本プロジェクトのような試みは、プロジェクト、というよりはセンターのような形でも、
継続すべきと思われる。 第 1 期中期計画のプロジェクトの開始時に、衛星観測、地上観測だけではなくモデリングとも融合して
いく計画であったが、関係教員の転出があり、その点があまり進展しなかったことは反省点である。 プロジェクト3 (第 1 期)太陽活動の地球環境への影響に関する研究 (第 2 期)太陽活動の地球環境への影響に関する研究
太陽活動の地球環境への影響をメカニズムから調べるための方法として,過去の太陽活動と気候の関
係を調べること,現在の太陽活動と地球気候の決定要素の関係を調べること,地球へ影響を与える反応
の素過程を調べることのために,各サブグループで研究を進めてきた。それぞれのサブグループではそ
れぞれ装置開発や学術的成果が得られつつある。今後は開発した装置を用いて実際の観測を行なう段階
になっている。過去の太陽活動の検証も試料作成の効率を上げることによりさらに飛躍的な結果を目指
すことができる。どのテーマもこれからがさらに発展すべき段階と考えられる。そして,それぞれのサ
ブグループが結果を出してくれば,これらを統合して太陽活動と地球気候の関係を解明する糸口にたど
り着くことができる。そのときに,毎年開催している「「太陽活動と気候変動の関係」に関する名古屋ワ
ークショップ」が重要な役割を果たすものと期待される。 プロジェクト4 (第 2 期のみ)実証型ジオスペース環境モデリングシステム(GEMSIS-phase II):宇宙嵐に伴う多圏
間相互作用と粒子加速の解明に向けて ジオスペース環境研究における世界的な研究拠点を目指して、GEMSIS 計画を立ち上げ、2007 年度か
ら実施。3つのサブグループに分かれてプロジェクトを推進してきた。一部当初の計画よりも遅れたも
のもあるが、ジオスペースの各要素モデルの開発など、世界的にもユニークなモデルの開発に専念する
など、野心的な計画を実施できた。また、磁気圏研究の手法を太陽研究に応用するなどの成果もあり、
研究所から人件費を負担していただき、ハードウェアは科研費等でとってくるという、人材を重要視す
る戦略はよかったと思う。今後は開発したモデルのユニークさを活かして、研究を発展させていくこと
が期待される。また、太陽サブグループと磁気圏サブグループの連携によって、期間内に複数の共著論
文を発表されている。さらに、太陽風、放射線帯のシミュレーションを結合させた SUSANOO と呼ばれ
るリアルタイム宇宙天気シミュレーターの実験を開始するなど、相互の専門を活かした研究が進められ
16

ている。今後さらに、サブグループ間の密接な連携においては、まだ改善の余地があると識別しており、
今後の課題と認識している。 • STE 研が科学コミュニティのサイエンスセンター機能を担うというコンセプトはまだ道半ばで
あり、ERG がテストベッドとしてその成否が問われている。大学の付置研レベルのリソースでどこまで
実現できるのか、諸外国のミッションと比して「サービス」として求められる質を提供できるのか、試
行錯誤しながら開発を進めてきたが、今年度の ISAS との連携拠点の設置で体制は整いつつある。国際的
なコミットメントと期待も増しつつあるが、現在道半ばであり、これからの数年間が正念場であり、次
の中期計画に向けて発展させたい。 • 世界的な研究の動向の一つとして、比較惑星研究へのニーズが高まっている。現に、コミュニ
ティからの惑星関係の共同利用申請件数も増えている。比較惑星研究は、名大 STE 研ではサイドワーク
として行っているのが現状であるが、BepiColombo, JUNO, MAVEN, ALMA、JUICE など、魅力的な
計画が今後10年間に実施予定であり、プロジェクト 4 の研究者も参画している。研究所が進めている
惑星軌道での太陽風環境の研究も含めて、研究所のプロジェクトとして立ち上げていく可能性を探りた
い。 国際共同研究 (資料) 数多く(主なもの 15 件)の国際共同研究を実施すると共に、20 件の国際学術協定を各国の研究機関
を結び発展させている。特に、国際組織 SCOSTEP(国際太陽地球物理学・科学委員会)の国際プロジ
ェクト CAWSES-II にほとんどの教員が参加し、太陽活動の気候変動への影響、気候変動に対するジオ
スペースの応答、太陽の短期変化がジオスペース環境に与える影響、下層大気からの入力に対するジオ
スペースの応答などに関する共同研究を実施している。また、アルゼンチン、チリ、インドネシア、ヨ
ーロッパ各国、ロシア、カナダ、メキシコ、アメリカ、ニュージーランド、中国など地理的にも幅広く
国際共同研究を推進している点に本研究所の特徴がある。国際共同研究を通して十分な成果を得ている
と評価している。 (11)学内他部局との連携(資料) グローバル COE「宇宙基礎原理の探求(2008-2012 年度)」及び博士課程教育リーディングプログラム
「フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム(2012 年度~)」では理学研究科・工学研究科と積極
的に協力し高度な大学院教育と学際的な研究活動の交流を共同で推進してきた。また、名古屋大学 HPC計算科学連携研究プロジェクトを名古屋大学情報基盤センター及び地球水循環研究センターと共同で実
施し、分野横断的な高度計算科学共同研究を全国の研究者の参加を得て展開している。さらに、素粒子
宇宙起源研究機構(KMI)及び理学研究科附属南半球宇宙観測研究センターにそれぞれ教員が参加し、
共同で研究活動を行っている。東山キャンパス移転後は学内他部局との連携の環境が整い、多角的な協
力活動を活動していると自己評価している。今後はこうした連携を太陽地球環境研研究の将来計画につ
なげる努力を継続して進める必要がある。
17

(12)学会への貢献 (資料) JAXA、国立天文台、NICT,国立極地研究所などの研究機関、地球電磁気・地球惑星圏学会、
日本物理学会、日本学術会議など学会及び学術機関で多くの教員が役割を担っている。また、本研究所
の教員は地球電磁気・地球惑星圏学会、太陽研究者連絡会、宇宙線研究者会議の中核メンバを担ってお
り、本研究所は各関連分野の将来構想の取りまとめに重要な役割を果たした。さらに、CAWSES-II シン
ポジウム、国際サブストーム会議 ICS-12、フェルミシンポジウムなど重要な国際会議の主催者としても、
国内外の学会活動の推進に本研究所は大きく貢献している。HPCI コンソーシアムのユーザーコミュニテ
ィ代表会員にも選ばれ、我が国の計算科学の推進にも参画している。上記の通り、学会活動には十分な
貢献を行っていると自己評価している。 (13)社会貢献 (資料) 研究成果を通した社会貢献 本研究所では、太陽から地球に至る宇宙での擾乱現象を事前に予測する宇宙天気の研究に取り組んで
おり、太陽面爆発、放射線環境、電離圏変動などの予測アルゴリズムの開発を通して社会に貢献するこ
とを目指している。その具体的な成果として太陽風と放射線帯の電子変動を予測する新たなアルゴリズ
ムの開発を行い、情報通信研究機構で宇宙天気予報として運用されている。また、当研究所で取得した
観測データをリアルタイムで解析することで地球に到来する太陽風の予報する研究を実施し、その成果
を韓国宇宙天気予報センターが予測業務に活かしている。この他、ガンマ線カメラの開発による福島原
発事故調査への貢献、南米大気環境リスク対応への貢献、PM2.5 など大気環境に影響する大気エアロゾ
ルの動態解明や温室効果期待の計測による社会貢献、中部地方の航空宇宙中小企業グループとの小型衛
星共同開発、地震の超高層大気に対する影響の解明や太陽活動の気候影響の解明を通した社会貢献を進
めている。 こうした研究を通した多角的な社会貢献の実現は本研究所の特徴の一つであり、高く評価できる。今
後はこうした特徴を生かすと共に関連機関とも連携することで、社会生活への貢献度を高めることが期
待できる。 アウトリーチ活動 本研究所は他機関ではあまり例の無い一般向けの解説書(12 種類)とコミック(9 種類)の作成と配
布を通して科学成果の発信と普及に積極的に務めている。また、研究所一般公開を毎年実施すると共に、
教員による公開講座、ラジオ公開講座、文化講演会などを年間平均約 20 回ほど開催し、毎年合計 1000人ほどの参加を得ている。陸別や鹿児島など地方の観測所を利用したイベントを自治体と協力して定期
的に開催しており、いずれも多くの市民の参加を得ている。2010 年度には研究所のホームページを改修
し、最新の成果や画像などを即座に公開する活動を組織的に実施している。特異な宇宙線イベントの発
見や太陽フレアの予測研究など、本研究所が生み出した最新の研究成果のいくつかはNHKなどの科学
番組でも取り上げられている。これらの活動によってアウトリーチ活動の平均以上の水準を維持してい
ると自己評価している。今後はさらにプレスリリースの回数を増やすなどして、研究成果の発信力を高
めることが期待できる。
18

2.将来計画(案) A.研究所の基本構想
1957 年に人類初の人工衛星が打ち上げられて以降、人類の宇宙進出は急速に進み、ついにボイジャー探査
機が太陽圏の外へ到達したことが確認された。また、多くの惑星探査が進行し、今や人類の活動範囲は太陽圏
全体に広がり、さらに拡大しつつある。同時に、現代社会は高度な情報通信機器に依存したこれまでにない精緻
な文明を形成している。この高度な情報化社会は強く宇宙インフラに依存すると同時に、その基盤となる電力・通
信・交通・エネルギー網は太陽活動と宇宙環境のダイナミクスから激しい影響を受け得ることが指摘されている。
一方、地球の長期的な環境変動も太陽と宇宙のダイナミクスから独立ではないことを示唆する多くの観測データ
が存在する。すなわち、現代文明は宇宙と地球を一体とする包括的なシステムにおいてはじめて成立しており、
未来の文明は太陽・地球・惑星を含んだ太陽圏全体をその活動の舞台として発展すると考えることができる。
太陽地球環境研究所はこうした基本思想のもと、太陽と地球を中心とした太陽圏とその周辺領域を我々の生存
の場である太陽地球環境と位置づけ、そこで発生する様々な複雑現象のダイナミクスとメカニズムを探ると共に、
社会生活に影響を与える太陽地球環境の変動を事前に予測するための知見を獲得することで、科学と社会の発
展に貢献することをその基本使命とする。太陽地球系科学に関する全国で唯一の共同利用・共同研究拠点とし
て、国内外の研究者と協力し、太陽地球環境研究を世界的にリードする役割を担う。
太陽地球環境研究所は 1990 年の設立以来、その使命と目的の実現のため、太陽地球系科学の探求を進め、
数多くの優れた成果をあげてきた。また、共同利用・共同研究拠点としての役割を積極的に果たしてきた。研究
所の設立から 20余年が経過したが、人類と宇宙のつながりは急速に深まっており、その設立理念と目的はますま
すその重要性を増している。こうした背景のもとに、太陽地球環境研究所は新たな発展を目指し、以下の基本計
画を推進する。
B.基本計画
1.太陽地球環境の理解に関する研究を継続的に進めると共に、太陽地球環境の変動予測につながる学際研究
及び関連する基礎研究を推進する。
2.関連研究機関との連携を進め、太陽地球環境を包括的に研究するための国際的な拠点を形成する。
3.地球環境分野をはじめとする関連分野との連携を深め、太陽活動の地球環境に対する長期的影響等に関す
る研究を推進する。
C.今後約 5 年間の主な研究計画
上記の基本計画を実現するため、以下の計画を今後 5 年程度の重点項目として推進する。
1.太陽地球系宇宙科学の大学における全国的な拠点としての役割を担うため、衛星データ・地上観測・モデリン
19

グを融合した研究を主導的に進める衛星サイエンスセンター(ひので、ERG、Solar-C など)の整備と拡充を
行う。これによって、国内外の研究者にデータや解析ツールの提供を行うと共に、宇宙環境の理解と予測の
ための研究を推進する。
2.質の高い衛星データを取得するため、衛星のハードウエア開発を進める。さらに新しい衛星提案に関わって
行く。また、ChubuSat 超小型衛星計画を積極的に推進する。
3.太陽活動が地球気候へ与える影響を解明する研究を、地球生命圏研究機構や地球水循環研究センターと協
力して推進する。
4.太陽地球環境の変動をグローバルかつ精密に把握するため、アジア・アフリカ・中南米など観測の空白が多い
地域や、北欧の EISCAT_3D サイトなど超高層大気研究の拠点となる地域に、独自の地上観測拠点を積極
的に拡充する。また現地の研究者・組織と連携を深める。
5.SCOSTEPが推進する国際協同研究計画「太陽活動変動とその地球への影響」VarSITI(2014-2018)において、
中核的な研究拠点の一つとして国際的に主導的な役割を果たす。
D.組織改組に関する計画
1.所内のジオスペース研究センターを新しい機能と課題に適合するように改編・改組する。
2.学内の理学研究科・工学研究科・環境学研究科・地球水循環研究センター・情報基盤センター・年代測定研
究センター・素粒子宇宙起源機構などと密接な連携をとって、プロジェクトや研究組織の維持・策定を進めて
行く。新たに太陽研を中心に始まったリーディング大学院「フロンティア宇宙開拓リーダー」(2012-2017 年)を
積極的に推進する。
3.第 3 期中期目標期間(2016-2021 年度)に向けて、研究所やセンターの再編の準備を進める。
4.宇宙科学研究所、国立天文台、国立極地研究所、東大宇宙線研究所などと協力し、人的交流、連携組織の
設立を通して、関連する研究課題に積極的に取り組む。
E. 各部門の計画(今後 5 年間) 第 1 部門 オゾン層破壊や地球温暖化、越境汚染などの大気環境問題に関して、大気微量成分のその場・リモート
計測の実施、大気計測機器開発、衛星観測支援などにより、環境変動メカニズムの解明および問題解決
への道筋の探求を行う。熱圏・中間圏との相互作用や高エネルギー粒子・宇宙線の大気環境に与える影
響を調べる。このため共同利用や JICA-JST などの国際協力を進める。さらに、地球外惑星大気や森林
生態・水循環の研究など、所外の組織と協力しつつ研究領域を広げて行く。 第 2 部門 地上からの多点ネットワーク観測と拠点観測を通じて、地球の電磁気圏における中性大気-プラズマ
結合やプラズマ粒子の加速・消失過程とそれらの宇宙利用への影響に関する観測的研究で世界をリード
20

する。また、地球惑星探査機に搭載する最新のイオン・中性粒子の観測機器の開発を独自に行うととも
に、これらの機器の地上較正実験環境を整備する。 第 3 部門
惑星間空間シンチレーション観測システムの改良を行いつつ、取得したデータから特異な第24太陽
サイクルの極大期から次極小期における太陽圏のグローバルな特性の変動を明らかにする。また、パル
サー観測から極小期の極域太陽風の密度測定を行う。これらの独自の観測データに基づき太陽圏や宇宙
天気予報に関する国際共同研究を推進する。 宇宙線観測により宇宙プラズマにおける粒子加速などの非熱的過程の解明を行う。また、宇宙線と大
気の相互作用を幅広いエネルギーに渡り詳細に理解し、粒子生成と地球環境へ影響を明らかにし、宇宙
線放射線核の測定から宇宙線による太陽地球史の解明を行う。さらに、理学研究科等との連携により太
陽系外惑星や宇宙素粒子などの素粒子宇宙的研究を推進する。 第 4 部門 太陽フレア・CMEの発生及び放射線帯変動を中心とした宇宙天気現象の機構解明と予測に関する研
究で世界をリードする。また、粒子加速、磁気リコネクション、ダイナモ、オーロラサブストーム、惑
星圏環境変動などに関する総合解析研究を継続して推進する。ひので・ERGサイエンスセンターにお
ける研究・開発を進め、共同利用環境整備に貢献する。 ジオスペース研究センター 共同研究、観測、計算機利用を推進し、データベースを整え観測データの効果的利用を図る。サイエ
ンスセンター群の運営を初め、所内外研究組織や国内外研究機関との連携・協力により、領域横断的共
同研究プロジェクトの立案・遂行を行う。具体的には、サイエンスセンターのより一層の充実をはかる。
また、大学間連携事業や大型共同研究等と協力することにより、データベース作成共同研究の拡充をは
かる。上記事業で観測・取得したデータのデータベース化・公開を進め、統合データベース構築を目指
す。さらに、これまで構築した太陽地球系科学における分野横断的データシステムを維持発展させる。
現在実施中の大学間連携 IUGONET では地上観測データを対象としていたが、今後も大学間連携などの
枠組みを活用し、衛星データとの横断利用を促進するシステム構築を目指す。 なお、本センターの将来的な位置付け・役割については、研究所全体の将来構想を考慮し早急に検討
を進める。
21

資料編
22

資料1:研究所全般 A.概要
太陽から地球に至る各領域で起きる基本的な物理・化学素過程を解明しつつ、それら全体を統合した複合系
としての理解を深めるため、3 つの領域(大気圏・電磁気圏・太陽圏)の研究部門と全領域を総合的に扱う総合解
析部門で研究を進めてきた。また、ジオスペース研究センターが領域横断的な研究プロジェクトを推進してきた。
国内外に数多くの観測拠点を展開し、独自の観測データに基づいて世界最先端の観測研究を実施し、さらに地
上・人工衛星データの総合解析と計算機シミュレーションによりモデリング研究を行い「宇宙天気」の研究を推進
した。
文部科学省の特別教育研究経費の拠点形成事業「ジオスペースにおけるエネルギー輸送過程」(2005-2009
年度)により、太陽風アンテナや短波レーダー、ミリ波装置、全天カメラ、ライダー装置などの大型設備を設置し、
太陽活動の極小期におけるジオスペースと大気変動の計測を行った。2010 年度からの第二期中期目標期間、
本研究所が共同利用・共同研究拠点として文部科学省から認定された。特別経費(拠点形成)「太陽極大期にお
ける宇宙嵐と大気変動に関する調査研究」(2010-2015 年度)により、それまでに整備された大型設備の観測を維
持・継続し、さらに最先端観測機器を増強しながら、太陽極大期における宇宙嵐と大気変動の総合的な観測研
究を行い、また「実証型ジオスペース環境モデリングシステム(GEMSIS)」プロジェクトの推進を行っている。極地
研、東北大、京都大など連携した大学間連携プロジェクト(2009-2014 年度)として、超高層大気の地上観測網で
これまでに蓄積された観測データのメタデータ・データベースである IUGONET を構築し、横断検索できるシステ
ムを整備している。また、2012 年度補正予算で宇宙環境電波観測システム事業(新たなHFレーダーと太陽風ア
ンテナ)が採択されており、その整備を進めている。
共同利用・共同研究拠点として、従来の4種類の共同利用形態(共同利用、共同研究集会、データベース共
同利用、計算機共同利用)に加えて、2010 年度より新たに大型共同研究枠を導入して、他大学と共同してジオス
ペースや大気変動の地上ネットワーク観測を展開している。2010-2013 年度はこれらを合計して毎年 160-170 件
の共同利用・共同研究を推進している。また、情報基盤センター、地球水循環研究センターと協力して名古屋大
学 HPCI 計算科学連携プロジェクトを 2011 年度より開始した。
SCOSTEPが推進する国際協同研究計画「太陽地球系の気候と天気」CAWSES-Ⅱ(2009-2013年)において中
核的な研究拠点の一つとして主導的な役割を果たしている。2011 年より国立天文台と連携して「ひので」サイエン
スセンタープロジェクトを立ち上げ、ひので衛星の太陽活動データをコミュニティーに提供している。さらに、宇宙
科学研究所と連携し、衛星観測・地上観測・数値モデリングの統合的な研究を推進する宇宙環境サイエンスセン
ターを 2013 年 4 月より設立して、ERG衛星のサイエンスセンター機能を果たそうとしている。文科省主導で 2012
年に作られたた日本のスパコンに関して将来計画を作成する組織であるHPCIコンソーシアムのユーザーコミュニ
ティ代表会員(全国で 15 機関)に選ばれている。
理学研究科及び工学研究科の協力講座として大学院教育を積極的に推進している。グローバル大学院「宇宙
基礎原理の探求」(2008-2012 年度)に参画するとともに、昨年からは本研究所が中心となって理学研究科・工学
研究科の教員と共に博士課程教育リーディングプログラム「フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム」(2012
-2017 年)を開始し、国際的リーダーとして活躍し、宇宙をはじめとする次世代の産業を開拓する能力を持つ人材
の育成を始めている。学内連携の継続的発展のため、理学研究科附属南半球宇宙観測研究センターと引き続き
23

連携し、また素粒子宇宙起源研究機構の創設にも参画している。
本研究所の新しい建物が 2013年 3月に完成し、文字通り一つの建物に全研究所が結集して、研究を進めるこ
とが可能となった。また、地球水循環研究センターも同じ建物に入り、連携がやり易くなった。 (4)大学評価・学位授与機構による評価の結果 大学評価・学位授与機構による第一期中期目標期間(2004-2009年度)の当研究所の評価結果は以下の
通りである。
*研究活動の状況:期待される水準を上回る
*研究成果の状況:期待される水準にある
*質の向上度 相応に改善、向上している
特に、研究活動の状況については、当初の 2008年における大学評価・学位授与機構による中間的な評
価判定は「期待される水準にある」であったが、2008-2009 年度の現況分析により著しい改善がみられ
たとされ 2010年の最終判定で「期待される水準を上回る」と高い評価へ変更された。
24

図1:太陽地球環境研究所の組織構成
B.研究所の運営体制
(1)運営組織 太陽地球環境研究所は第 1~4 部門及
び客員部門からなる研究部門、ジオスペ
ース研究センター、技術部、研究部事務
局より構成されている。その組織構成は
図 1 の通りである。 運営体制を図 2 に示す。学内外の関連
コミュニティから選出された委員から
なる運営協議会設け、年4回以上開催し、
研究所の運営方針や人事計画等の重要
事項について諮り、コミュニティの意見
を取り入れている。また、各専門委員会
及び総合観測委員会での議論をもとに、
共同利用・共同研究委員会を開き毎年の
共同研究についてコミュニティの意見
を取り入れながら実施している。 ジオスペース研究センターには同セン
ター運営委員会を設け、その運営に当た
っている。
図 2:太陽地球環境研究所の運営体制 25

(2)人員体制 所長 松見 豊(2009~) 副所長 荻野瀧樹(2008~2012)、草野完也(2012~)
部門 教授 准教授 助教 特任教員 大気圏環境 (第 1)部門
松見 豊(1997着任) 水野 亮(2003着任)
長濵智生(2004着任) 中山智喜(2007 着任) 中島 拓(2012 着任)
電磁気圏環境 (第 2)部門
塩川和夫(2008昇任) 平原聖文(2011 着任)
野澤悟德(2002昇任) 大塚雄一(2011 昇任)
大山伸一郎(2006 着
任) 鈴木 臣(特任助教) 下山 学(特任助教)
太陽圏環境 (第 3)部門
伊藤好孝(2004着任) 德丸宗利(2008昇任) 田島宏康(2010着任)
松原 豊(1992着任) 増田公明(1997着任)
﨏 隆志(2000 着任) 奥村 曉(2012 着任)
山岡和貴 (特任准教授) 注1
毛受弘彰 (特任助教)註 1
総合解析 (第 4)部門
草野完也(2009着任) 町田 忍(2013着任) *菊池 崇(2012退職)
関華奈子(2002着任) 増田 智(2002昇任)
家田章正(2003着任) 今田晋亮(2012 着任)
齊藤慎司 (特任准教授)註1
塩田大幸(特任助教) 宮下幸長(特任助教) 桂華邦裕(特任助教)
ジオスペース 研究センター
平原聖文(センター
長 2013~) *荻野瀧樹(センター
長、2013 退職)
阿部文雄(1995着任) 西谷 望(2005昇任) 三好由純(2012昇任)
藤木謙一(2004 着任) 梅田隆行(2006 着任)
堀 智昭(特任助教)
註 1:大学院理学研究科所属(リーディング大学院担当) (3)基盤設備及び観測所 基盤設備(資料)
1.IPS 太陽風観測装置
国内4地点(豊川、富士、木曽、菅平)に設置した高感度アンテナを用いて天体電波の惑星間空間シンチレ
ーション(IPS)現象を測定し、地上から太陽風をリモートセンシングする装置である。多地点 IPS 法による観測
は世界で他に類を見ないユニークなもので、飛翔体による測定が困難な領域を含む広い範囲の太陽風のダ
イナミックな 3 次元特性を高い精度で調べることができる。2012 年度の補正予算で装置の更新・改良が進めら
れている。
2.超高層大気イメージングシステム
高度80-300kmで発光している夜間大気光を観測することにより、超高層大気の密度変化の2次元分布、風速、
温度を同時に複数高度で計測する。同システムは、日本、ノルウェー、ロシア、インドネシア、タイ、オーストラリ
ア、カナダなどの観測点で、無人自動観測を定常的に行っている。このように数多くの大気光観測機器を各地
26

で運用しているシステムは世界で唯一である。
3.太陽中性子望遠鏡
太陽表面の爆発(フレア)に伴って大量に生成される高エネルギー中性子の検出装置で、発生機構を解明す
るために用いられる。太陽中性子は地球大気中で減衰するために高山に設置されている。日本の乗鞍、ボリ
ビア、ハワイ、チベットなど、世界 7 カ所に設置され、24 時間体制で観測を行っている。とくに現在、新型の太
陽中性子望遠鏡(SciCR)をメキシコのシエラネグラ山に設置を進めている。
4.HF ドップラーレーダーシステム
短波帯(9-16MHz)の電波を上空に発射して戻ってくるエコーを解析することにより、電離圏・熱圏・上部中間圏
における環境変動を観測する装置である。この装置を用いて、電離圏・熱圏領域におけるプラズマ速度およ
びプラズマ密度変動、中間圏界面の温度変化に伴う環境変動等を高時間分解能で計測することができる。陸
別観測所に設置され中緯度領域で重要なデータを提供している。現在、2012 年度の補正予算で 2 台目の装
置を製作中である。
5.高層大気温度観測装置(ソディウムライダー)
高出力なレーザー光を上空に打ち上げ、高層大気(高度 80 km -110km)の「ナトリウム層」から反射されてくる
光を受信することにより、高層大気の大気温度を導出する装置である。5受信機を用いることにより、鉛直方向
だけなく、空間構造も導出できる。ノルウェートロムソに設置し、2010 年 10 月から観測を開始している。太陽風
エネルギー注入に対する地球高層大気の変動や下層大気ー高層大気の大気間結合の解明を目指してい
る。
6.ミリ波大気放射分光観測装置
大気微量分子のミリ波放射スペクトルを測定し、その高度分布を計測する装置である。現在、チリ、アルゼンチ
ン、北海道陸別、南極昭和基地に装置が設置され、オゾン、一酸化塩素、窒素酸化物等の観測を行っている。
オゾン層破壊の状況を解明するとともに、太陽活動に伴う地球外高エネルギー粒子の地球大気への侵入の
影響など地球内外の環境変動が大気環境に与える影響解明を行っている。
7.太陽地球環境データ解析システム(GEDAS)
太陽地球環境モニタリング装置、太陽地球環境情報補正装置、太陽地球環境情報表示装置、太陽地球環境
情報ゲートウェイ装置、ネットワーク関連装置、2/3 次元モデル検証装置、大型表示装置から構成される。太陽
から地球までの大規模なエネルギーの流れ/変換過程を理解する。ひので衛星の太陽フレアデータベース、
磁気圏プラズマの 5 次元分布関数の時間発展を追跡可能な世界最先端の放射線帯・環電流モデル、世界で
も類をみない放射線帯確率予報などが開発され、組み込まれている。
8.大気組成フーリエ赤外分光観測装置
太陽赤外光を背景光源として大気中の微量分子による吸収スペクトルを測定し、それらの組成の高度分布を
計測する装置である。現在、北海道陸別町及び母子里に装置が設置され、モニタリング観測を継続している。
温室効果ガスやオゾン層破壊物質、対流圏大気汚染物質が観測可能であり、地球環境変動の原因物質の長
期変動を研究するための基礎データとして活用されている。
9.大気中二酸化炭素同位体リアルタイム分光計測装置
中赤外波長領域のレーザーを光源として多重反射セルで光吸収測定を行うことにより、大気 CO2 の直接的に
同位体比の計測を測定する装置である。これまでの同位体質量分析装置とは異なり、この装置では濃縮など
27

の前処理は不要で、リアルタイムで連続的に計測できる。植物の光合成の外部環境変動に対する応答などの
生物応用や、都市域の CO2 の変動要因の解明の共同研究などを進めている。
10.大気中窒素酸化物オゾン濃度測定装置
大気中の窒素酸化物およびオゾンの濃度を高精度・高感度で測定する装置である。窒素酸化物の濃度につ
いては自然起源のベースラインとなる濃度まで計測できるように pptv (10-12 体積比)レベルまで計測が可能で
ある。この性能は国内最高レベルである。
観測所(資料)
母子里観測所
北緯 44 度の北海道中央部に位置する母子里観測所は、冬季には最低気温が -30 度以下になる寒冷地で
あり、また、豪雪地域でもある。母子里観測所では、地上からの分光計測や気球による計測により成層圏及び
対流圏の微量化学成分の観測を行っており、人工衛星の検証データにも使用されている。中緯度の電磁気
圏環境を観測するための観測点として、地磁気や電波・オーロラ観測を行っている。
陸別観測所
北海道陸別町のりくべつ宇宙地球科学館内にあり、国立環境研究所と共同で運営している。赤外線や紫外
線の分光観測装置を用いたオゾン等の成層圏の大気微量成分の研究や、全天 CCD カメラ・掃天型分光計・
磁力計を用いたオーロラなどの地球電磁気現象の研究を総合的に進めている。また、HF ドップラーレーダー
システムをポントマム地区に設置し、観測を進めている。
富士観測所、豊川分室、菅平観測施設、木曽観測施設
これらの 4 地点に設置されたアンテナを用いて、惑星間空間シンチレーションを利用した地上からの太陽風観
測が定常的に行われている。離れて設置された複数のアンテナで観測することにより、太陽風の速度や密度
擾乱の強度の 3 次元構造を観測している。
鹿児島観測所
鹿児島観測所は、1974 年に垂水市本城に設置された。フラックスゲート磁力計、誘導磁力計、VLF 帯観測用
ループアンテナなどを設置して地球周辺の電磁環境を計測している。また約 70km南の佐多にもコンテナハウ
スがあり、大気光全天カメラ、分光温度フォトメータ、誘導磁力計が稼働している。
28

C. 予算状況
大学運営費交付金、特別経費など、外部資金以外の予算の状況(単位 円)
2012 年の部局配分運営費交付金は、移転経費・建物新営設備費\101,792,000 円を含む
部局配分運営費交付金には、常勤職員の給与は含まれていない。
外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度) 科学研究費等採択数及び金額(下段:単位百万円)
H16 年度
(2004)
H17 年度
(2005)
H18 年度
(2006)
H19 年度
(2007)
H20 年度
(2008)
H21 年度
(2009)
H22 年度
(2010)
H23 年度
(2011)
H24 年度
(2012)
採択数 17(1) 20(1) 28(1) 29(0) 30(0) 27(0) 25(0) 28(0) 29(0)
金 額 174 133 167 119 142 98 105 157 118
学振特別研究員奨励費を除く。採択数括弧内は特別推進等の大型科研費件数。
外部資金受入れ状況 件数及び金額(下段:単位百万円)
H16 年度
(2004)
H17 年度
(2005)
H18 年度
(2006)
H19 年度
(2007)
H20 年度
(2008)
H21 年度
(2009)
H22 年度
(2010)
H23 年度
(2011)
H24 年度
(2012)
受入件数 11 8 8 10 11 10 11 8 9
金 額 57 50 40 39 39 17 29 25 35
2008 年 2009 年 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年
部局配分運営費交付金 272,809,219 265,865,146 259,309,360 272,667,075 367,278,000 275,474,130
特別経費(拠点形成) 178,200,000 178,200,000 74,994,000 73,119,000 69,463,000 69,463,000
特別経費(大学間連携) 0 17,108,000 14,900,000 13,400,000 12,740,000 11,740,000
共同利用拠点運営経費 0 0 46,480,000 46,015,000 45,417,000 44,827,000
29

D.研究活動
(1)特筆すべき論文(6編)とその特筆すべき理由 1.Miyake, F., K. Nagaya, K. Masuda and T. Nakamura, A signature of cosmic-ray increase in AD 774-775 from
tree rings in Japan, Nature 486, 240-242, (doi:10.1038/nature11123) 2012.
屋久杉の単年輪の放射性炭素(炭素14)濃度を1年分解能で高精度に測定した結果,西暦775年に大気中の
炭素14濃度の急激な増加があったことを発見した。その原因は近傍の超新星爆発や太陽表面におけるスーパ
ーフレアなどが考えられ,その地球環境への影響の解明と関連する極めて重要な成果である。
2 . Kusano, K., Y. Bamba, T. T. Yamamoto, Y. Iida, S. Toriumi and A. Asai, Magnetic field structures triggering
solar flares and coronal mass ejections, Astrophys. J. 760, 31, (doi:10.1088/0004-637X/760/1/31) 2012.
太陽フレアやコロナ質量放出などの太陽面爆発を引き起こす磁場構造を、160通りを超す様々な3次元電磁流
体力学シミュレーションと「ひので」衛星観測との比較から特定した。本研究は太陽フレア発生の条件とメカニズ
ムを明確にしたものであり、フレアに起因する宇宙天気擾乱の予測にも貢献する重要な成果である。
3. Sumi, T., K. Kamiya, D. P. Bennett, I. A. Bond, F. Abe, C. S. Botzler, A. Fukui, K. Furusawa, J. B. Hearnshaw,
Y. Itow, K. Masuda, Y. Matsubara, et al., Unbound or distant planetary mass population detected by gravitational
microlensing, Nature, 349-352, (doi:10.1038/nature10092) 2011.
主星をまわる軌道を持たず、銀河内を単独で運動する「浮遊惑星」をMOAおよびOGLEグループは、木星程
度の質量を持つ浮遊惑星または大軌道惑星によると思われる事象10個を発見し、解析の結果こうした惑星が
通常の星の約2倍存在することを明らかにした。この様な多数の浮遊惑星を、惑星形成の標準理論で説明す
る事は困難であり、星惑星形成を理解する上で極めて重要な成果である。
4. Tokumaru, M., M. Kojima, and K. Fujiki, Solar cycle evolution of the solar wind speed distribution from
1985-2008, J. Geophys. Res., 115, A04102, (doi:1029/2009JA014628) 2010.
本研究は2太陽周期にわたる惑星間空間シンチレーション観測から、太陽風のグローバルな構造の時間変化
を初めて明らかにしたものである。特に、今太陽周期の太陽風速度分布が特異なものであることを初めて示す
ことにより世界的に注目された。
5. Nakayama, T., Y. Matsumi, K. Sato, T. Imamura, A. Yamazaki, A. Uchiyama, Laboratory studies on optical
properties of secondary organic aerosols generated during the photooxidation of toluene and the ozonolysis of
alpha-pinene, J. Geophys. Res., 115, D24204, (doi:10.1029/2010JD014387) 2010.
本研究は、大気中に放出された揮発性有機化合物が大気反応過程を経て粒子化する二次有機エアロゾル
の光吸収特性について、独自に開発した装置によって初めて示した成果である。有機エアロゾルの地球気候
に与える影響の重要なデータとなる。
6. Miyoshi, Y., K. Sakaguchi, K. Shiokawa, D. Evans, J. Albert, M. Conners, and V. Jordanova, Precipitation of
radiation belt electrons by EMIC waves, observed from ground and space, Geophys. Res. Lett., 35, L23101,
(doi:10.1029/2008GL035727) 2008.
理論的に予言されていた地球放射線帯における電磁イオンサイクロトロン波動と相対論的電子の共鳴過程を、世
界で初めて観測的に実証した。
30

(2) 出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年(西暦) 教員が筆頭著者
であるもの 特任教員・研究員が
筆頭著者であるもの 学生が筆頭著者
であるもの 所外の研究者が筆
頭著者であるもの 2013 10 4 7 53
2012 25 13 10 100
2011 19 9 13 105
2010 19 19 9 79
2009 18 8 6 92
2008 19 2 9 58
各教員別被引用数調査は各部門の活動概要に記述 (3) 学会での研究発表数 学会での研究発表の数
H16 年度
(2004) H17 年度
(2005) H18 年度
(2006) H19 年度
(2007) H20 年度
(2008)
参加 参加 参加 コンビーナ 参加 コンビーナ 参加 コンビーナ
国際研究集会 86 86 89 10 78 2 77 4
国内学会 105 64 61 8 71 3 62 7
国内研究会 156 120 111 22 61 11 69 7
H21 年度 (2009)
H22 年度 (2010)
H23 年度 (2011)
H24 年度
(2012)
参加 コンビーナ 参加 コンビーナ 参加 コンビーナ 参加 コンビーナ
国際研究集会 88 4 81 3 101 3 88 8
国内学会 55 10 72 11 68 8 68 10
国内研究会 104 11 101 18 80 11 86 39
招待講演の数
H16 年度
(2004)
H17 年度
(2005)
H18 年度
(2006)
H19 年度
(2007)
H20 年度
(2008)
H21 年度
(2009)
H22 年度
(2010)
H23 年度
(2011)
H24 年度
(2012)
国内 9 34 12 27 12 25 28 15 25
国際 12 23 28 17 13 24 34 36 34
31

(4) 主な受賞など 主な教員の受賞
藤井 良一 ノルウェー科学文学アカデミー会
員 2008 年 3 月
大塚 雄一 EPS Award 2008 2009 年 1 月
GPS detection of total electron content
variations over Indonesia and Thailand
following the 26 December 2004 earthquake
塩川 和夫 田中舘賞(地球電磁気・地球惑
星圏学会) 2009 年 5 月
光学観測機器を用いたオーロラと超高層大
気変動に関する研究
三好 由純 森田記念賞(東北大学泉萩会) 2009 年 10 月 地球放射線帯における粒子加速過程の研
究
関 華奈子 平成23年度文部科学大臣表彰
若手科学者賞 2011 年 4 月
惑星起源イオンのダイナミクスに着目した
太陽地球環境の研究
徳丸 宗利 田中舘賞 (地球電磁気・地球惑
星学会) 2011 年 5 月
惑星間空間シンチレーション観測による太
陽風の加速と擾乱伝搬ダイナミックスの研
究
上出 洋介 Axford Medal(アジアオセアニア
地球科学連合) 2012 年 8 月
太陽地球系物理学における顕著な業績と
国際的研究推進への長年にわたる貢献
梅田隆行 大林奨励賞(地球電磁気・地球
惑星圏学会) 2012 年 10 月
計算機シミュレーション手法の開発とその
宇宙プラズマ現象への応用
三好由純 平成25年度文部科学大臣表彰
若手科学者賞 2013 年 3 月
宇宙天気の基礎要素としての放射線帯電
子加速機構の研究
今田晋亮 大林奨励賞(地球電磁気・地球
惑星圏学会) 2013 年 6 月
磁気リコネクションによる粒子加速過程の研
究
指導する学生の受賞 2013 年度 名古屋大学学術奨励賞 三宅芙沙さん(理学研究科博士後期課程) [名古屋大学の博士後期課程院生(1 学年 500 余名)の中から年間 6 名が受賞] 他に学生の学会ポスター賞など多くある。
32

E.国内及び国際共同研究
(1)領域横断的な重点共同プロジェクト (資料5:領域横断的な重点共同研究プロジェクト報告書) 1.第 1 期(2005-2009) プロジェクト 1:CME の素過程の研究 プロジェクト 2:人工衛星-地上共同観測によるジオスペースの新展開 プロジェクト 3:太陽活動の地球環境への影響に関する研究 2.第2期(2010~2015)
プロジェクト 1:特異な太陽活動周期における太陽圏 3 次元構造の変遷と粒子加速の研究 プロジェクト 2:グローバル地上・衛星観測に基づく宇宙プラズマ-電離大気-中性大気結合の研究 プロジェクト 3:太陽活動の地球環境への影響の研究 プロジェクト 4:第 2 期実証型ジオスペース環境モデリングシステム(GEMSIS-phase II): 宇宙嵐に
伴う多圏間相互作用と粒子加速の解明に向け (2)国内共同研究の実施状況 共同利用・共同研究拠点として行った共同研究などの件数と参加人数
2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 2012 年度
件数
(延人数) 予算
件数
(延人数) 予算
件数
(延人数) 予算
件数
(延人数) 予算
件数
(延人数) 予算
共同研究 70
(206)
3,900 76
(227)
4,650 72
(299)
4,600 76
(295)
3,900 66
(247)
4,000
研究集会 31
(1485)
12,150 28
(1108)
10,350 39
(2314)
11,400 35
(1730)
10,900 37
(1670)
13,500
データベース 12
(52)
3,704 11
(49)
3,931 12
(47)
3,931 11
(49)
3,925 11
(53)
3,900
計算機 34
(73)
4,625 32
(81)
5,061 31
(90)
4,536 23
(81)
4,738 24
(75)
4,500
海外観測支援
10
(67)
6,090 10
(25)
6,600 (2010 年度から下欄に移行)
地上ネットワーク大型
研究 および
同(重点)
(2010 年度から開始)
16
1
12,020
4,980
19
1
12,030
4,970
21
1
12,000
5,000
名古屋大学 HPC プロ
ジェクト (2010 年度から開始)
10 3,000 11 4,000 11 4,000
合計 30,469 30,592 44,467 44,458 46,900
33

2012 年度の共同研究:主なもの 10 件のみを例示
課題名 概要
1
地上観測ネットワーク
のための、対流圏オゾ
ンリモートセンシングお
よびエアロゾルの研究
PI:北和之(茨城大理・教授)。近年、半球規模で対流圏オゾン濃度が増加傾向にあ
り、直接の人体や植物への悪影響、およびその温室効果による気候影響が懸念され
ている。オゾンは可視光のリモートセンシングでもカラム量の定量が可能である。オゾ
ンの可視域 Chappuis 帯での差分吸光フィッティングの精度が十分であるか確認する
ための太陽直達光観測および地表散乱光スペクトルの推定、さらにエアロゾル推定
による誤差推定を行った。
2
レーダーおよびライダ
ー観測と大気圏・電離
圏統合モデル・シミュレ
ーションによる極域熱
圏・電離圏変動の研究
PI:藤原均(成蹊大理工・教授)。本研究では、極域熱圏・電離圏へのエネルギー流
入量、及び極域熱圏・電離圏変動そのものをオーロラ帯(トロムソ)から極冠域(ロング
イアビン)に展開されている装置(EISCAT, ESR, MF レーダー、ナトリウムライダー等)
による観測から明らかにする。
3
SciBar 検出器を用いた
メキシコ・ミューオン計
の新設
PI:宗像一起(信州大理・教授)。宇宙線強度の汎世界的観測ネットワークを用いた宇
宙天気研究を展開し、高エネルギー銀河宇宙線の長大なリーチを活かして、0.1 天
文単位に及ぶ大規模な太陽磁場構造の変動の実態と、その中での宇宙線輸送過程
を解明することを目的とする。Mexico 高山に入射方向分解能の高い新宇宙線計を設
置する計画に着手した。本年度は測定器をメキシコに輸送し,メキシコ側研究機関の
建物内で検出器組上げて宇宙線ミューオンの予備観測を行った
4
北半球高緯度および
南半球高高度におけ
る大気中宇宙線生成
核種 Be-7 などの濃度
変動の観測研究
PI:櫻井敬久(山形大理・教授)。太陽活動の停滞期から上昇期、そして下降期にお
ける北半球高緯度、中緯度および南半球低緯度での大気中宇宙線生成核種の濃度
変動の観測を行い、地球規模での大気運動も含めた宇宙線生成核種の強度変動と
太陽活動の関係を調べた。
5
インドおよび日本の都
市大気エアロゾルの化
学的特徴および光学
特性
PI:持田陸広(名大院環境学・准教授)。大気中の微粒子(エアロゾル粒子)は、太陽
光を吸収・散乱するほか、雲凝結核として雲粒の生成をもたらすことにより、地球の放
射の収支に関与している。インドや日本の各都市でフィルタ上に採取された大気エア
ロゾル成分を溶媒を用いて抽出した後、その抽出物の化学的特徴、光学特性を調べ
る手法により、大気エアロゾル粒子を構成する有機物の化学的・光学的な特徴につ
いて新たな知見を得た。
6
太陽画像データに基
づく太陽紫外線放射
量の活動周期変動の
推定と、超高層大気へ
の影響
PI:浅井歩(京大宇宙総合学・特定助教)。太陽紫外線放射は、電離圏・プラズマ圏で
の化学反応や電磁エネルギー輸送を介して、超高層大気変動を引き起こす要因の
一つとなっている。人工衛星による太陽全面極端紫外線・紫外線撮像データを用い
ることでコロナホールや活動領域の明るさ/面積の長期変動を詳しく調べ、それらを
IUGONETのデータベース上の超高層大気データ群(主に Sq場の長期変動)などと比
較することで、超高層大気への影響を及ぼす要因が空間分解された太陽面構造の
中にあることを明らかにした。
7
ブラジル磁気異常帯に
おけるイメージングリオ
メータ・データの収集と
光学観測
PI:巻田和男(拓殖大工・教授)。地球磁場が異常に弱い南米大陸南部域には放射
線帯から高エネルギー粒子が多量に降り注いでいる。地球磁場の減少に伴い、如何
なる環境変動が起こるのかを明らかにする。磁気嵐時にこの地域で顕著な宇宙雑音
吸収(CNA)が見られることから、粒子の入射が起きていると推定された。
34

8
オーロラの高時間分解
能モニタリング
PI:片岡龍峰(東京工大理・特任助教)。ビデオフレームではぎりぎり分解できないよう
な現象も含めた今後の太陽極大期におけるオーロラの最先端モニタリング観測を行
った。NHK番組「宇宙の渚」と協力することによって、高い時間分解能を追求するキャ
ンペーン実験の成果をまとめた。その結果、脈動オーロラとよく似た動態だが、桁違
いに速い 50-60Hz で変化するオーロラを発見した。
9
国際協同太陽地上ネ
ットワーク観測データを
用いた太陽活動の地
球磁気圏への影響に
関する国際学術交流
PI:柴田一成(京大理・教授)。太陽フレア監視望遠鏡を世界的に配置することにより、
太陽面爆発やフィラメント噴出現象の速度場データ、彩層全面輝度分布データを漏
れなく継続的に取得できるようにするため、『CHAIN プロジェクト』という国際協同観測
プロジェクトを実施している。日本における国際共同データ解析ワークショップの開催
と論文の執筆、現地ネットワーク・計算機環境整備等を行なった。
10
高感度サーチコイル磁
力計を用いた VLF 帯
ホイスラモード波の地
上観測
PI:尾崎光紀(金沢大工・助教)。VLF 電磁波動の地上観測ネットワークの構築を妨げ
ている巨大なループアンテナ(ループ面積 100 m2 以上)の小型化を図るため、高感
度サーチコイル磁力計の新規開発を行った。試作したサーチコイルを用いて 2012 年
9 月末から約 3 週間、アサバスカ(カナダ)の観測所で実際のフィールド試験を実施し
た。
2012 年度の研究集会:主なもの 10 件を例示
期間 種類 国内 or
国際 集会名 概要 参加人数
H24.11.20-11.23 研究集
会 国際
電波観測に
よる太陽物
理学
太陽電波国際シンポジウム"Solar Physics
with Radio Observations - Twenty
Years of Nobeyama Radioheliograph"として
開催した。海外 10 か国から 32 名の参
加があり、太陽電波研究の現状と将来につ
いて議論した。
63
(内外国
人 32)
H25.3.21-3.23 研究集
会 国内
STE シミュレ
ーション研
究会:
太陽地球系科学・プラズマ科学に関するシ
ミュレーション全般、領域間/スケール間
結合モデル、宇宙天気シミュレーションなど
の最新の研究成果・展望を議論した。
116
H24.9.3-9.5 シンポジ
ウム 国内
シンポジウム
-太陽地球
環境研究の
現状と将来
変革期を迎えつつある太陽地球環境の研
究に携わっていこうとしている若手研究者
を中心として、これからの太陽地球環境の
研究に関して議論を行った。
81
H24.11.6-11.8 研究集
会 国内
大気化学討
論会
エアロゾル測定法、遠隔計測、OH ラジカ
ル、エアロゾル観測、大気―陸面物質交
換、同位体比の大気化学への応用、衛星
観測、東シナ海航空機観測、大気観測に
基づく発生源解析、モデル研究について
議論した。
109
H25.2.16 ワークシ 国内 「太陽活動と 気候の変動の未解明のプロセスのひとつ 100
35

ョップ 気候変動の
関係」ワーク
ショップ
が、太陽活動の影響に関与するプロセスで
ある。太陽活動と気候変動の関係について
の、さまざまな側面とプロセスについての現
状の理解と今後の課題について議論した。
H24.12.25-12.27 研究集
会 国内
GEMSIS 電
磁気圏ワー
クショップ:
ジオスペー
スにおける
多圏間相互
作用と粒子
加速機構
宇宙嵐時には、磁気圏-電離圏結合や領
域ごとに特色ある波動粒子相互作用など
が活発になることが指摘されており、衛星
観測と地上からのリモートセンシングによる
ジオスペースの面観測と数値モデリング/シ
ミュレーションをあわせた研究により、衛星
一点観測による限界を補うことがきわめて
大切であるが、そのための研究体制の構築
について議論した。
70
H25.3.6-3.8 研究集
会 国内
惑星大気
圏・電磁圏
研究の展開
惑星の観測・解析・数値シミュレーションに
関する研究成果の発表並びに、現在進行
している惑星探査計画の進捗と計画につ
いて報告と議論を行った。
61
H24.8.23-8.24 研究集
会 国内
中間圏・熱
圏・電離圏
研究会
中間圏・熱圏・電離圏領域の特徴を意識
し、この領域で生じている物理・化学過程
の理解を深めること、及び他の研究領域や
社会への応用を俯瞰的に捉えるための議
論を行った。
50
H24.9.7,
H24.10.1-2,
H25.3.6
ワークシ
ョップ 国内
STE 研究連
絡会現象報
告会および
現象解析ワ
ークショップ
2012 年 5 月 21 日(日本時間)に日本各地
で観測された金環食に伴う電離圏変動な
どの関連現象を取り上げた。主に地磁気嵐
に関連した現象を取り上げた。太陽活動の
極大期にあたり、CME による地磁気嵐の数
が増えているが、2012 年 11 月以降、あまり
大きな現象が発生していないことを議論し
た。
120
'H25.2.27-28 研究集
会 国内
ミリ-テラヘ
ルツ波受信
機技術に関
するワークシ
ョップ
国内のミリ-テラヘルツ波受信機開発に携
わる研究者およびこれを用いた観測的研
究を行う研究者が集い、高周波受信機の
関連技術や課題、応用等について、情報
交換の場である。
80
(3)国際共同研究の実施状況 国際プロジェクトの主なもの 15 件を記載
相手国名・研究機関名 研究プロジェクト等の概要 関係研究者名
ICS傘下の国際組織 SCOSTEP
(国際太陽地球系物理学・科学
委員会)
プロジェクト概要:ICS 傘下の国際組織 SCOSTEP が
2009-2013 年に推進する国際協同研究プロジェクト。
太陽活動の気候変動への影響、気候変動に対するジオ
塩川和夫、荻野達樹、
草野完也などほぼ教員
全員
36

プロジェクト名:太陽地球系の
気候と天気-II(CAWSES-II)
スペースの応答、太陽の短期変化がジオスペース環境
に与える影響、下層大気からの入力に対するジオスペ
ースの応答の 4 つのタスクグループに分かれて、国際的
なキャンペーン観測やデータ解析・モデリングを推進す
る。当研究所の教員はこのタスクのリーダーや学術会議
の SCOSTEP 小委員会の委員長を務めている。
規模・参加国等:米国、日本、カナダ、英、仏、独、伊、ノ
ルウェー、露、中国、オーストラリアなど 29 カ国が
SCOSTEP に加盟。
アルゼンチン・CEILAP
チリ・マゼラン大学
「パタゴニア南部地域におけるオゾン層および紫外線観
測能力強化と住民への伝達活動プロジェクト(JICA 広域
科学協力プロジェクト)」
ミリ波・ライダー・オゾンゾンデ・紫外線分光計等を用い
たオゾンホールおよび紫外線量の観測体制を構築し、
実態把握を行う。(参加国:日本、アルゼンチン、チリ)
水野亮、長濵智生、他
インドネシア・インドネシア航空
宇宙庁(LAPAN)
プロジェクト名:インドネシアにおける宇宙天気の体制構
築。プロジェクト概要:インドネシアと日本の超高層大気・
宇宙天気の研究者が協力して、インドネシアの宇宙天
気予報の体制を構築する。
参加国:日本、インドネシア
大塚雄一、塩川和夫、
他
EISCAT 科学協会
(ノルウェー、フィンランド、スウ
ェーデン、イギリス、中国)
プロジェクト名:EISCAT 国際協同研究
プロジェクト概要:国際共同により、北欧にて IS レーダー
を稼働し(年間計 約3000時間)、極域超高層大気の
研究を進める。
野澤悟徳、大山伸一
郎、藤井良一、他
カナダ・アサバスカ大学
カナダ・アサバスカ郊外の AUGO-I,-II 観測点において
複数の光学観測機器を用いてオーロラに関連したジオ
スペース変動の総合観測を行う。
参加国:カナダ、米国、日本
塩川和夫、大塚雄一、
三好由純、他
INFN(イタリア)・CERN(スイ
ス)・エコールポリテクニク(フラ
ンス)・ローレンスバークレー研
(アメリカ)
LHCf実験:CERNLHC にて宇宙線の超前方ハドロン
相互作用を検証するLHCf実験を行い、宇宙線シャワー
の精密理解を目指した研究を行う。
伊藤好孝、増田公明、
さこ隆志、他
UNAM(メキシコ)、INAOE
(メキシコ)
SciCRST実験:15000本シンチレーターアレイを用い
たフルアクティブ太陽中性子望遠鏡をメキシコ高山に設
置し太陽中性子の観測を行う。
伊藤好孝、松原豊、
さこ隆志、他
カンタベリー大、オークランド大
(ニュージーランド)、ノートルダ
ム大(アメリカ)
MOA実験:ニュージーランドに設置した1.8m広視野
望遠鏡を用いた重力マイクロレンズ観測を行い、太陽系
外惑星や暗黒物質の探索を行う。
阿部文雄、伊藤好孝、
松原豊、さこ隆志、他
SLAC(アメリカ)他 AstroHSGD:アストロH衛星に搭載される軟ガンマ線
カメラを用いた宇宙線加速の研究を行う 田島宏康、他
アメリカ Space Science FOXSI (Focusing Optics X-ray Solar Imager)m による太 田島宏康、他
37

Laboratory 陽の硬 X 線撮像分光観測
アメリカ(JHU/APL、バージニア
工科大学、アラスカ大学、ニュ
ーハンプシャー大学)、イギリス
(レスター大学、BAS)、フランス
(LPCE/CNRS)、他計 11 ヶ国
プロジェクト名: 短波レーダーによる極域・中緯度域電
磁気圏の研究。南・北半球の大型短波レーダー
(SuperDARN)を用いた国際共同研究を行い、太陽風変
動に伴う電離圏プラズマ対流の応答、プラズマ密度擾
乱の広域輸送などの過程を解明してきた。
西谷望
J.M. Ruohoniemi, M.
Lester, C. Hanuise, J.
Rash, J. Devlin, A.V.
Koustov, E. Amata, H.
Hu 他約 100 名程度
米国・NASA NASA の放射線観測衛星ミッションである Radiation
Belst Storm Probes への参加
三好由純
L. Lanzerotti, D.
Mitchell 等
米国、英国、ノルウェー、
NASA、ESA、他
ひので科学プロジェクト、太陽観測衛星「ひので」による
国際太陽研究プロジェクト
草野完也(プロジェクトサ
イエンティスト)、他
アメリカ合衆国・ニューハンプシ
ャー大学他 IMSA/SCOPE proposal at NASA
関華奈子
Lynn Kystler(UNH)他 20
名の国際チーム
国際学術協定 20 件中主なもの 10 件を記載
締結年月 終了予定年
月 相手国・機関名 協定名 分野
昭和 63 年5月 特に定めな
し
インドネシア国立宇宙
航空研究所
大気及び太陽地球系物理
学共同研究協定覚書
大気、太陽地球系物
理学分野
平成2年7月 特に定めな
し
アメリカ国アラスカ大学
地球物理研究所
アラスカ大学地球物理研究
所名古屋大学太陽地球環
境研究所学術交流覚書
大気科学、磁気圏科
学、太陽地球系科学
分野
平成2年 11 月 特に定めな
し
ノルウェー国オスロ大
学物理学教室
名古屋大学太陽地球環境
研究所オスロ大学物理学教
室学術交流協定
電離圏-磁気圏科
学、太陽地球系科
学、大気科学、太陽
圏科学分野
平成4年 12 月 特に定めな
し
アメリカ国海洋大気局
宇宙空間環境研究所
名古屋大学太陽地球環境
研究所と米国海洋大気局宇
宙空間環境研究所との学術
交流に関する覚書
大気圏科学、電磁気
圏物理学、太陽圏物
理学分野
平成6年 10 月 特に定めな
し
アメリカ国マサチューセ
ッツ工科大学ヘイスタ
ック研究所
名古屋大学太陽地球環境
研究所とマサチューセッツ
工科大学ヘイスタック研究
所との学術交流協定書
大気科学、電離圏物
理学、磁気圏物理学
分野
38

平成9年3月 5年ごとに更
新
ブラジル国立宇宙科学
研究所
名古屋大学太陽地球環境
研究所とブラジル国立宇宙
科学研究所との学術交流に
関する覚書
電離圏、磁気圏物理
学、宇宙天気、太陽・
地球系物理学分野
平成9年 12 月 5年ごとに更
新
アメリカ国カリフォルニ
ア大学サン・ディエゴ
校天体物理及び宇宙
科学研究センター
名古屋大学太陽地球環境
研究所とカリフォルニア大学
サン・ディエゴ校天体物理
及び宇宙科学研究センター
との学術交流に関する協定
書
特に定めなし
平成 10 年7月 5年ごとに自
動更新
ニュージーランド国カ
ンタベリー大学理学部
名古屋大学太陽地球環境
研究所とカンタベリー大学
理学部との学術交流に関す
る協定書
特に定めなし
平成 13 年2月 5年ごとに更
新
中国中国科学院高能
物理研究所
名古屋大学太陽地球環境
研究所と中国科学院高能物
理研究所との学術交流に関
する協定
宇宙線物理分野
平成 19年 4月 特に定めな
し
ロシア科学アカデミー
極東支部宇宙物理学・
電波伝搬研究所
名古屋大学太陽地球環境
研究所とロシア科学アカデミ
ー極東支部宇宙物理学及
び電波伝搬研究所との学術
交流協定書
太陽地球系科学、磁
気圏電離圏物理学、
大気科学分野
(4)国内の他機関との連携組織
宇宙科学研究所との宇宙科学拠点
本研究所は宇宙科学研究所との大学共同利用連携拠点として宇宙科学拠点を設置する協定を 2013 年 3 月に
締結した。共同利用・共同研究拠点である本研究所と宇宙科学研究所双方の大学共同利用の視点に基づいて、
双方の知見を活かして学術コミュニティに貢献することとされている。この連携拠点により、地上からの観測データ、
衛星からの観測データと数値モデリングを統合的に取り扱える仕組みを整備し、近地球宇宙空間環境総合科学
分野での共同利用機能を大きく強化することを目指す。ERG衛星のサイエンスセンター機能をこの拠点で遂行す
る。従来の衛星プロジェクトの所掌範囲外である地上観測・数値実験データもあわせて、ミッションの科学成果を
最大化するための効果的なデータベース・統合解析ツールを開発する。衛星による一点観測の欠点を地上から
の面的な観測で補い、両者を数値モデルでつなぐことで、その相乗効果により衛星単体では達成できない科学
成果が見込まれ、また、数値モデルと観測との密な連携により、宇宙環境モデル構築への貢献などが波及効果と
して期待される。この協定に基づき、両研究所の委員により構成される拠点運営協議会を設置し、教員人事を含
む大学共同利用連携拠点の運営にあたるなど、本拠点運営に相応しい機構も構築されている。2013年4月より 5
年計画でこの宇宙科学拠点を名古屋大学に設立する。本研究所からの教員および特任助教 2名の参加と共に、
宇宙科学研究所からの予算で名古屋大学に 2 名の特任教員を雇用する。
39

国立天文台との連携拠点の設立の動き
本研究所は、国立天文台および学内の理学研究科等と協力・連携して「太陽気候影響研究センター」を設立しよ
うとしている。太陽活動は気候変動に何らかの影響を与えると考えられているが、その実態とメカニズムは未だに
良く理解されていないが、本センターは地球環境を多角的な視点から理解し、気候変動に関する歴史的問題を
解決するため、太陽物理学、気象学、気候学、古気候学、地球電磁気学、海洋学、古地磁気学などの専門家が
従前の研究分野を超えて本格的な学際連携研究を行うための研究センターを整備するものである。自然起源の
気候変動メカニズムを広く理解し、環境変動予測に貢献することをその目標とする。太陽地球環境研究所はその
前身である空電研究所より国立天文台へ太陽電波部門を 6 名の教職員(教授1名、助教授 1 名、助手 2 名、一
般職員 2 名)と共に移管し、太陽電波観測所の設立に大きく貢献した。国立天文台はこうした人員を基に、野辺
山太陽電波観測所において電波ヘリオグラフを用いたユニークな太陽研究を継続してきた。しかし、国立天文台
は電波ヘリオグラフを近い将来停止することを計画している。このような歴史的な経緯を踏まえて、あらたに名古
屋大学にセンターを設立することを目指している。また、本センターは次世代太陽観測衛星 Solar-C 計画の実現
に役割を果たすと共に、その打ち上げ後に Solar-C 衛星の科学利用、特に宇宙天気・宇宙気候研究について国
際的に先導する役割を担う予定である。
国内組織との学術協力協定
国立極地研究所、統計数理研究所、情報通信研究機構電磁波計測研究所と学術協力協定を結んでい
る。
40

F.学会活動などへの貢献
2012 年度に本研究所の教員が委員等の委嘱を受けている学外委員会
機関・組織名 委員会・役職等の名称
宇宙航空研究開発機構 情報・計算工学センタースーパーコンピュータ運用・利用分科会委員
情報・システム研究機構/国立極地研
究所
非干渉散乱レーダ委員会委員/南極観測審議委員会宙空圏専門部会委
員/非干渉散乱レーダ委員会特別審査部会委員
情報通信研究機構 研究活動等に関する外部評価委員会 電磁場センシング基盤技術領域外
部評価委員会委員(副委員長)
自然科学研究機構/国立天文台 運営会議委員/太陽・天体プラズマ専門委員会委員/太陽天体プラズマ
専門委員会電波ヘリオグラフ科学運用小委員会委員/仕様策定委員会委
員/電波専門委員会電波天文周波数小委員会委員
高エネルギー加速器研究機構 素粒子原子核研究所運営会議委員
京都大学生存圏研究所 運営委員会委員/赤道大気レーダ (EAR) 全国・国際共同利用専門委員
会委員/MU レーダー全国・国際共同利用専門委員会委員/電波科学
計算機実験 (KDK) 全国・国際共同利用専門委員会/附属生存圏学際
萌芽研究センター運営会議委員
東京大学宇宙線研究所 運営委員会委員/共同利用研究運営委員会委員/将来計画検討委員会
委員/共同利用研究課題採択委員会委員
北海道大学低温科学研究所 共同利用・共同研究拠点運営委員会委員
日本原子力研究開発機構 平成 24 年度炉心プラズマ共同企画委員会専門委員理論シミュレ
ーション専門部会
地球電磁気・地球惑星圏学会 総務担当運営委員/大林奨励賞推薦委員会委員
日本物理学会 理事、Editorial Board, Progress of Theoreticaland Experimental Physics
サイエンティフィック・システム研究会 マルチコアクラスタ性能 WG 推進委員
日本学術会議 地球惑星科学委員会国際対応分科会 SCOSTEP 小委員会委員/地球
惑星科学委員会国際対応分科会 STPP 小委員会委員/環境学委員会・
地球惑星科学委員会合同 IGBP・WCRP・DIVERSITAS 合同分科会 IGAC
小委員会委員、URSI 分科会プラズマ波動小委員会委員
日本エアロゾル学会 日本エアロゾル学会編集委員
名古屋大学出版会 評議員
Committee on Space Research Chair of the COSPAR subcommission C1 (The Earth’s Upper Atmosphere
and Ionosphere), Vice Chair of Panel on Radiation Belt Environment
Modeling
EISCAT Scientific Association Council member
Super Dual Auroral Radar Network Executive Council
The Scientific World Journal Editorial Board
ASA Astronomy and Physics Research
and Analysis
Gamma-ray panel
La Trobe University PhD examiner
41

American Geophysical Union Associate Editor of Journal of Geophysical Research
この他に国内外の各種研究提案書のレフェリー、各種専門誌のレフェリーの委託を受けている。 [学会将来構想のとりまとめ] 太陽地球系科学における将来構想のとりまとめ(SGEPSS) STEL の学問分野を広く包含する地球電磁気・地球惑星圏学会(SGEPSS)は、その学問分野の将来構
想のとりまとめを平成24年度に1年間かけて行った。当研究所の教員(塩川)はこのとりまとを主査
として主導した。この将来構想のとりまとめにおいては、平成24年10月20~23日に札幌コンベ
ンションセンターで開催された同学会において、将来構想特別セッションを当研究所の教員が主催する
とともに、当研究所の共同研究集会として「地球電磁気・地球惑星圏研究の将来計画について」を平成
24年12月12~13日に名古屋大学で開催した。完成した将来構想の文書は http://www.sgepss.org/sgepss/ shorai/SGEPSS_syorai_Jan2013.pdf で公開している。 宇宙線物理学分野の将来計画のとりまとめ(CRC) 平成23年に CRC(宇宙線研究者会議)が取りまとめた宇宙線研究分野の将来計画「宇宙線分野の現状
と将来計画」の編纂に STE 研研究者(伊藤)が関わった。同冊子には STE 分野に関わりの深い宇宙線
研究計画も掲載されている。編纂母体は平成22年度 宇宙線研究者会議実行委員会における将来計画冊
子編集ワーキンググループであり、活動期間は平成22~23年、最終的な寄稿者数は 19 名であり、 http://www.icrr.u-tokyo.ac.jp/CRC/Symposium/2010-09/future20110630.pdf にて公開されている。 太陽研究者連絡会における将来計画のとりまとめ 太陽及び太陽圏分野の全国的な地上観測ネットワーク構想である「次世代太陽圏環境変動ネットワーク
観測計画」のとりまとめを、太陽研究者連絡会運営委員長でもある草野が行なった。本計画は平成 25 年
度に日本学術会議天文学・宇宙物理学分科会による「天文学・宇宙物理学中規模計画の展望」の一部と
しても公開される予定である。 [大きな国際学会等の運営] CAWSES-II シンポジウムの主催 ICSU 参加の国際組織 SCOSTEP(国際太陽地球系物理学・科学委員会)が平成21年-平成25年に推
進する5ケ年計画の国際協同研究である CAWSES-II (Climate And Weather of the Sun-Earth System-II、太陽地球系の気候と天気-II)では、その最終年度にあたる平成25年11月17-22日に、
総まとめの国際研究集会を名古屋大学で開催する。STEL はこの研究集会を事務局として主催することに
なっており、現在、さまざまな準備が進んでいる。この研究集会では、外国人研究者約100名を含む
200名以上の参加を見込んでいる。 ICS-12 の主催 国際サブストーム会議(International Substorm Conference - ICS)は、平成2年以降、およそ2年に1
42

回各国で開催されて地球磁気圏の主要な擾乱現象であるサブストームに関する世界の研究者が一堂に会
する国際研究集会である。STEL は平成10年に ICS-4(第4回)を浜名湖ロイヤルホテルで主催し、3
00名以上の参加者があった。平成26年10-11月に ICS-12(第12回)を再び STEL が主催する
ことが決定しており、準備が行われている。 フェルミシンポジウムの主催 宇宙線、宇宙プラズマ分野からの要請として、ガンマ線観測による宇宙線加速の解明をおこなっている
フェルミ衛星に関する国際シンポジウムの平成26年度の開催(10月)を引き受けることになった。 [コミュニティープロジェクト] ジオスペースの放射線帯は、主に太陽風と地球磁場に影響されて大きく変動し、宇宙機などの宇宙イン
フラに障害を及ぼすことが知られている。太陽地球環境所(STEL)では、将来の探査計画として、この放
射線帯におけるプラズマ粒子の加速・輸送・消失に関する物理過程を直接観測する人工衛星計画
「ERG(Energization and Radiation in Geospace)」を提案・推進してきた。ERG 計画は平成24年8
月に宇宙航空研究開発機構(JAXA)にて、JAXA・宇宙科学研究所(ISAS/JAXA)にて小型衛星計画 2 号機
として正式に承認され、衛星本体・搭載機器の開発が進んでいる。これまでに STEL では、磁力計・波
動アンテナ・全天カメラ・HF レーダー等の地上観測網を整備し、加えて、GEMSIS に代表される国内
外探査機用データベース・解析ツールの環境構築、シミュレーション・モデリングの実績などを有する
ため、衛星観測・地上観測・モデリングを統合した三位一体型計画としての ERG 計画においては、その
立案時より中核的役割を果たしてきた。現在、ERG 計画は NASA の VAP(ヴァンアレンプローブ)・THEMIS 衛星計画に比肩し得る国内計画であり、日本の太陽地球系物理学における唯一のコミュニティ
ーミッションとして推進されている。また、後述の通り、STEL と ISAS/JAXA との宇宙科学拠点として
協定が締結され設置された宇宙環境サイエンスセンターが、これまでの ERG サイエンスセンターを発展
させた総合的な機能を担うこととなり、STEL の各部門との協力体制の基、国内におけるジオスペース科
学の推進母体となりつつある。この機能は、ERG のみにならず、運用中・開発中・検討中の探査計画
(NASA:THEMIS・VAP・MMS、ESA・JAXA 共同:BepiColombo、ISAS/JAXA:SCOPE)において
も国内の基幹となるサイエンスセンターを実現する基礎となっている。 [社団法人 HPCI コンソーシアム] 計算機共同利用や太陽地球系科学のシュミレーション研究の成果が評価され、2012 年度作られた HPCIコンソーシアムのユーザーコミュニティ代表会員(全国で 15 機関)に選ばれている。HPCI コンソーシ
アムは文科省主導で作られ日本のスパコンに関して将来計画を作成する組織である。このコンソーシア
ムで関連するコミュニティーの研究者の意見を反映することができる。
43

G.学内他部局との連携(研究)
地球生命圏研究機構(SELIS)
本研究所が環境学研究科・地球水循環研究センターと共に推進した 21 世紀 COE プログラム「太陽・地球・生命
圏相互作用系の変動学」(SELIS-COE, 2003-2007 年度)では、地球システムを、人類活動をも包含した生命圏の
役割も含めて理解する、「シームレス地球学」の研究・教育を体系的に推進してきた。このような先導的な研究・教
育の枠組みを、生命農学研究科などの関連する組織教員の参加をも含め強化し、国内外の研究機関と密な連
携が可能な研究教育組織へ発展させるべく、学内バーチャル機構として 2008 年度より発足し、本研究所も 11 名
の教員が参加している。
素粒子宇宙起源研究機構(KMI) 小林・益川両博士の 2008 年ノーベル物理学賞受賞をはじめとする素粒子・宇宙研究の輝かしい伝統をさ
らに発展させるべく、理学研究科、多元数理科学研究科、太陽地球環境研究所に所属する素粒子理論・
実験分野、宇宙理論・観測分野、数理物理学分野、宇宙線研究分野の関連研究者を結集し、さらには素
粒子理論に計算物理学の手法も取り入れ、現在の標準理論をも越える現代物理学の新たな地平を開拓す
ることを目的とした学内組織である。本研究所からは、機構内の現象解析研究センターに 2 名の教員が
兼務で参加している。 理学研究科附属南半球宇宙観測研究センター 理学研究科は、南半球に設置した本学の先端的宇宙観測研究施設の円滑かつ効果的な 運用のために、2006 年より設置されている。NANTEN2 サブミリ波望遠鏡(理学研究科)と MOA-Ⅱ重
力レンズ探査望遠鏡(太陽地球環境研究所)を核とした南半球天文台である。さらに地球大気観測装置(太
陽地球環境研究所)は、南米アルゼンチン・南極昭和基地への測定器の展開をしている。4 名の教員が兼
務で参加している。 名古屋大学 HPC 計算科学連携研究プロジェクト 名古屋大学情報基盤センター,太陽地球環境研究所及び地球水循環研究センターが連携して予算を出し
合い、名古屋大学情報基盤センターのスーパーコンピュータを利用する HPC 計算科学研究プロジェク
トを学内外に公募し、共同研究を進めている。並列型スーパーコンピュータの要素技術の開発・評価,
いろいろな分野(流体,プラズマ,気象,環境,数理科学,計算科学)への応用とアプリケーションの
総合性能評価など, HPC 計算科学全般にわたる課題を進めている。
44

H.教育活動
最先端の研究を通じた教育により、理学・工学研究科の協力講座として、両研究科の人材育成に貢献し
ている。グローバル COE「宇宙基礎原理の探求(2008-2012 年度)」(中間評価で S 評価に認定)、「地球学
から基礎・臨床環境学への展開(2009‐2013 年度)」の活動により、横断的な宇宙−地球環境の教育研究
拠点を形成し、若手研究者を育成している。また、2012 年 10月に採択された博士課程教育リーディング
プログラム「フロンティア宇宙開拓リーダー養成プログラム」では、所内の教員がプログラムコーディ
ネーターとして中心的な役割を果たし、国際的リーダーとして活躍し次世代の産業を開拓する能力を持
つ人材を育成をすすめている。
グローバルCOE「宇宙基礎原理の探求」への参加状況
年度 2008 2009 2010 2011 2012
事業推進担当者 6 名 6 名 6 名 6 名 6 名
協力教員 14 名 13 名 13 名 13名 12 名
特任スタッフ 1 名 1 名 1 名 1 名 0 名
COE 研究員(PD) 2 名 2 名 2 名 3 名 2 名
COE 研究アシスタント(DC) 13 名 14 名 12 名 17 名 10 名
博士課程教育リーディングプログラム「フロンティア宇宙開拓
リーダー養成プログラム」への参加状況
年度 2012
プログラムコーディネータ 1 名
事業推進担当者 11 名
協力教員 28 名
特任スタッフ 0 名
研究アシスタント(MC,DC) 13 名
指導している学部・大学院生数(理学研究科、工学研究科の協力講座) 学 生 数
(人) 2013 年度 82 名(学部理 5、工 10/院前期理 31、工 15/院後期理 20、工 1) 2012 年度 76 名(学部理 6、工 12/院前期理 31、工 9/院後期理 17、工 1) 2011 年度 72 名(学部理 3、工 6/院前期理 35、工 9/院後期理 19、工 0) 2010 年度 65 名(学部理 6、工 4/院前期理 31、工 8/院後期理 16、工 0) 2009 年度 61 名(学部理 7、工 6/院前期理 21、工 8/院後期理 19、工 0) 2008 年度 55 名(学部理 6、工 5/院前期理 19、工 9/院後期理 16、工 0)
45

課程修了者・満了者の就職状況(理学+工学)
年度 2008 2009 2010 2011 2012
前期課程修了者 14 12 13 21 13
後期課程修了・満了者 4 4 3 8 2
就職者数 15 13 9 26 10
就
職
先
民間企業 11 10 5 21 8
公務員 0 0 0 1 0
教員 0 0 1 1 1
大学・研究所 2 0 3 3 1
日本学術振興会特別研究員の採用者数(理学+工学)
年度 2008 2009 2010 2011 2012
PD 1 4 2 2 2
DC 5 0 5 2 3
計 6 4 7 4 5
PD: 学位(博士)取得者 DC: 学位取得前の大学院在籍者 学位(博士)取得状況(理学+工学)
年度 2008 2009 2010 2011 2012
博士学位授与数 4 3 2 7 3
前期課程(過去7年間)の主な就職先・進路
(*が付いているのは工学研究科学生の就職先)
2006 年度
前期課程: べリングポイント,東芝,オークマ, ペンタックス, 富士通エフ・アイ・ピー, 三菱商事, ブラザー
工業, 全日本空輸, 日立ソフトウェアエンジニアリング,進学 7 名
2007 年度
前期課程: 富士通, キャノン,奈良県立大学附属病院, サクラクレパス, タマディック, 東海理化*など,
進学 4 名
2008 年度
前期課程: みずほフィナンシャルグループ, MU投資顧問, キャノン, 豊田市役所, セイコーインスツル, ソ
ニー, 東亜ディーケーケー, トヨタ*,ローム*,リコーエレメックス*,進学4名
46

2009 年度
前期課程: 富士重工, 富士通, 美濃窯業, トヨタテクニカルディベロップメント, CSK ホールディングス, 豊
田自動織機*,日本車輌*,NTT ドコモ*,パナソニック電工*,三菱電機*,進学 2 名
2010 年度
前期課程: (株)菱化システム, 長野県高等学校,愛三工業,日立システムアンドサービス,三菱 UFJ 信託銀行,
宇宙航空研究開発機構(JAXA),三菱電機*,高砂電機工業*,豊田自動織機*,京セラミタ*,進
学7名
2011 年度
前期課程: 愛知県高等学校,SCSK,関西電力*,KDDI*,クラウジット,コンサルティング・エムアンドエ
ス,中部日本放送,中央エンジニアリング,豊通ケミプラス,ナガセイテグレックス,富士通,
バッファロー,富士通*,文溪堂,三菱自動車,森精機製作所*,進学 4 名
2012 年度
前期課程: アクティオ,プロトコーポレーション,日本高圧電気,トリオシステムプランズ,ネクスウェイ,
ヤマハ,トヨタテクニカルディベロプメント,三菱東京 UFJ 銀行,パイオニア,川崎重工,関西
電力,パロマ,進学 5 名
博士後期課程修了者の進路
名古屋大学理学研究科 研究員、特任助教 京都大学生存圏研究所 研究員 和歌山大学宇宙教育研究所 研究員/特任助 国立天文台岡山観測所 研究員 独立行政法人 科学技術振興機構(JST) 常勤職員 独立行政法人 情報通信研究機構(NICT) 研究員 ドイツ・ブラウンシュバイク工科大学 フンボルト財団 研究員 フランス LATMOS/IPSL, CNRS 研究員 イタリア INFN PD 研究員 次世代宇宙システム技術研究組合 財団法人鉄道総合研究所 株式会社 トヨタテクニカルデベロップメント 会社員 株式会社 日立製作所 会社員 株式会社 川崎重工 会社員 株式会社 ISOWA
47

名古屋市立富田高校 教員 名古屋市工業研究所 研究員
I. 一般社会への貢献
社会に貢献する実用的な研究成果 1.宇宙天気予報に向けた基礎研究 通信・気象衛星や GPS など、私たちの生活は人工衛星などの宇宙インフラによって支えられている。し
かし、太陽面で爆発が起こると、地球のまわりの宇宙空間の放射線が急増することによって、衛星が故
障したり、電離圏が乱れることによって測位誤差が大きくなったり衛星電波が受信できなくなることが
ある。本研究所では、このような宇宙での擾乱現象を事前に予測する宇宙天気の研究に取り組んでおり、
その太陽面爆発、放射線環境、電離圏変動などの予測アルゴリズムを開発している。太陽での爆発現象
である太陽フレアは、宇宙環境擾乱の源であり、その規模と発生タイミングの予測は宇宙天気予報の基
礎となる。コンピュータシミュレーションと衛星観測の比較によって、太陽でフレアが発生するための
条件を明らかにすることによりフレア発生の数値予報が可能にしようとしている。さらに、放射線帯(ヴ
ァン・アレン帯)の高エネルギー電子が増加すると、人工衛星の 故障が起きやすくなる。データ同化技
術を用いて、放射線帯の電子変動をシミュレートし、放射線帯の数値予報の精度を向上させている。ま
た、情報通信研究機構と協力して、放射線帯変動予測の新たなアルゴリズムの開発を行い、情報通信研
究機構で宇宙天気予報として運用されている。これらの理論的な研究と並行して、当研究所で取得した
観測データをリアルタイムで解析することで地球に到来する太陽風の予報する研究を実施し、その成果
を韓国宇宙天気予報センターの業務に活かしている。 2.太陽活動の気候影響に関する研究 太陽活動の変動が地球気候に影響を与える可能性について古くから指摘されているが、その実態と原因
は未だに明らかではない。太陽地球環境研究所では過去の太陽活動を樹木年輪中の炭素同位体から明ら
かにする研究や、太陽活動によって変化する宇宙線が雲の形成に与える影響を室内実験やシミュレーシ
ョンで解明する研究を行っている。さらに、電波を通して現在の太陽風の構造と変動を探り続けている。
これらの研究成果は太陽活動の気候影響を理解し予測するために重要な貢献をするものである。 3.ChubuSat 小型衛星の開発 超小型衛星プロジェクト ChubuSat を中部地方の航空宇宙開通の中小企業グループ「MASTT」と共同開発
している。中部地方は自動車と並ぶ航空宇宙産業の集積地として知られており、小型衛星の製造技術を 確立すれば、自動車に次ぐ次世代の主要産業としてさらなる発展が期待できる。ChubuSat 第1号機は、
可視光・赤外線カメラを搭載し、二酸化炭素や地表温度を計測するとともに、宇宙ごみの観測を目指し
ており、今年度冬ごろに打ち上げ予定である。 4.地震の超高層大気に対する影響 巨大地震による地面の振動や津波によって励起された大気の波は、上方伝搬し、高度約 300km の超高層
48

大気に到達し、プラズマ密度の変動を引き起こした。GPS 受信機網や短波レーダーを用いて、このプラ
ズマ密度やプラズマ構造の変動を観測した。この成果は、従来考えられていたよりも地圏の影響が超高
層大気に及んでいることを表すものであり、電離圏観測によって津波の到来予測や地球内部構造の探査
を行うという新たな研究分野を開拓するものである。 5.ガンマ線カメラの開発 JST の先端計測分析技術・機器開発プログラムの支援の下、JAXA、三菱重工と共同で高感度・広視野の
半導体コンプトンカメラを開発した。宇宙からの微弱なガンマ線の観測で威力を発揮するのみならず、
セシウムなど放射性物質固有のガンマ線が識別でき、放射性物質の分布を広視野にわたり可視化できる
ことから、福島原発事故の影響調査などでも貢献が期待されている。 6.南米の大気環境リスク対応の貢献 南米パタゴニア地域におけるオゾンホール、火山灰等のエアロゾル対策に貢献するため、JST-JICA の地
球規模課題対応国際科学技術協力事業(SATREPS)の支援の下で、本研究所は国立環境研究所およびア
ルゼンチン・チリの関連省庁・研究機関等と連携して地上観測網の整備、情報伝達網の整備を進めてい
る。ミリ波分光放射計などの先端遠隔計測技術を活用し、オゾン層破壊とエアロゾルという2つの大き
な大気環境リスクに対応する社会システムをアルゼンチンとチリに構築することを目指している。 7.大陸からの PM2.5 など大気環境・気候に影響を与える大気エアロゾルの動態解明 大気中に存在する微粒子(エアロゾル)は、太陽光を吸収もしくは散乱することにより、大気を加熱も
しくは冷却し、大気の放射収支や気候変動に影響を及ぼす。また、呼吸により取り込まれ人間の健康に
影響与える可能性がある。JST 先端計測機器開発事業などによりレーザー分光法を用いた新しい計測装
置を開発して、都市域や大陸からの玄関口の五島列島で観測し、および室内実験によりこれらの環境影
響を解明している。 8.温室効果気体の計測と GOSAT 衛星の検証 地球温暖化をもたらす CO2 などの温室効果気体を、独自に開発した計測機器を搭載した気球観測や、母
子里・陸別観測所の地上リモート赤外分光計測装置で計測し、温室効果気体の動態解明を行うとともに、
温室効果気体観測衛星 GOSAT の検証試験のデータを提供している。また、CO2 の安定同位体をリアル
タイムで計測できる装置を応用し、都市や森林地帯での CO2 の放出・吸収・移流などを解明して地球温
暖化研究に貢献している。
49

研究成果の社会への広報活動
[一般向け冊子制作]
多くのテーマについて一般向け冊子「○○50のなぜ」をりくべつ宇宙地球科学館などと共同制作して
いる。2011 年度までに、オーロラ、オゾン、太陽・太陽風、惑星、宇宙線、地球温暖化、南極、地磁気、
放射線帯、電波、宇宙天気についての 12 種類の冊子を制作してきた。また、プロの科学漫画家はやのん
氏に依頼し、コミックシリーズ「××ってなんだ!?」も、地磁気、オーロラ、オゾン、太陽風、宇宙
線、地球温暖化、極地、超高層大気について 9種類を発行し、「宇宙天気ってなんだ!?」を制作中であ
る。これらのコミックは国際科学会議(ICSU)の太陽地球系物理学科学委員会 (SCOSTEP)を通して、英
語を含め様々な言語への翻訳が進められており、太陽地球系科学の社会還元と教育に世界的規模で大き
く貢献している。
[一般向け講演会]
毎年 6 月に研究所一般公開を行い、オーロラや南極などをテーマに一般講演会を開催している。また、
名古屋大学ホームカミングデイでは、毎年研究紹介ブースに出展し、研究成果の公開に努めている。こ
の他、研究所教員による公開講座、ラジオ公開講座、文化講演会などを開催したほか、名古屋市科学館
などと協力した一般講演会なども積極的に企画している。
公開講座、公開講演会等の実施状況
年度
シンポジウム・講演会 セミナー・公開講座 その他 合計
件数 参加人数 件数 参加人数 件数 参加人数 件数 参加人数
2010 2 150 12 600 3 220 17 970
2011 1 130 7 560 6 240 14 930
2012 1 120 21 740 6 240 28 1,100
[地方自治体との連携]
北海道から九州にわたって当研究所が保有する附属観測所のおかれている自治体の協力を得ながら、個
性豊かな自治体のニーズに答える努力をしている。特に北海道陸別町では当研究所が中心となってオー
ロラ、大気光、オゾン関連の観測を始めて以来、地元の宇宙/地球に対する熱心な活動に呼応して、講
演会、国際会議など数々の連携事業を行ってきた。地域振興プランの企画/運営を行うため、陸別町と
当研究所の間で発足させた「社会連携連絡協議会」を発展させて、全国の研究機関を含めた「陸別町社
会連携連絡協議会」を 2012 年度に新たに発足させた。また、鹿児島県垂水市が主催する子供向けの「科
学の祭典」イベントに鹿児島観測所としてブース展示を出展している。
[ニュースレターの発行]
毎年 3 回、14 ページ、カラー版のニュースレター等を編集し継続して発行している。読者層を非専門家
50

に設定し、研究の最前線を分かりやすい記事で説明することに心がけ、マスコミや出版社などへも広く
配布している。
[研究成果の活用の実績、ホームページの活用]
ホームページを活用し、最新の研究成果を速やかに広く発信した。研究所のホームページには毎年3百
万件程のアクセスがあり、ニュースレターのダウンロードも約3万件ある。また、テレビ・新聞を通し
た研究成果の発信にも積極的に取り組んでいる。2012 年度には 5 件の新聞報道と 3 件の放送協力を行っ
た
[施設等の一般公開の状況]
名大祭やオープンキャンパスの際に研究室の公開を実施している。また、ニュージーランドに設置した
1.8m望遠鏡を同国マスコミ関係者や一般希望者に随時公開し、研究活動について説明している。さらに、
毎年夏季の休日を利用した木曽観測施設の一般公開も実施している。
[スーパーサイエンスハイスクール(SSH)事業への協力、その他]
愛知県立岡崎高校、同豊田西高校のスーパーサイエンスハイスクール事業に協力し、特別科学活動研究
室体験研修を実施した(2010 年及び 2009 年)。さらに、全国の理系大学生を対象とした太陽研究最前線
ツアーを 2009年より毎年、関連研究機関と協力して実施している。
51

資料2:各部門の活動 大気圏環境部門 水野グループ(第 1 部門 1)
(1)部門の役割と目的(5 行) 太陽地球系の最も地球側に位置する中層大気(成層圏および中間圏)中の微量分子の観測を通し、オ
ゾン層破壊や気候変動等の地上の生態系に影響を与える大気環境変動の実態を把握しその要因を特に太
陽活動との関係という観点から解明することを目指すと同時に、微量分子の変動をプローブとして大気
ダイナミクスに関するあらたな知見を得ることを目指す。また、観測に用いる新たな観測手法の開拓や
観測装置の高精度化も併せて推進する。 (2)過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行) 太陽活動が極大期へと向かったこの5年間は、太陽活動の影響がより顕著に現れる領域でのミリ波分
光観測を実現させるべく、装置開発と南極昭和基地での観測にもっとも力を入れて研究を展開してきた。
加えてチリ・アタカマ高地におけるオゾン破壊過程で重要な一酸化塩素の昼夜変化の観測、オゾンホー
ルが到来する南米南端部でのオゾン観測、FTIR による温室効果ガスの観測、テラヘルツ帯受信機開発、
光スペアナを用いた赤外線での温室効果ガス分光器の開発なども推進してきた。装置開発面では南極の
限られた電力量の下で安定に動作する超伝導ミリ波分光システムを完成させ、昭和基地に設置し 2012 年
より観測を始めた。同装置を用いて磁気嵐に伴い降り込む放射線帯電子による NOx の通年変化や降下イ
ベント発生時の詳細な時間変動などが明らかになった。また、電波望遠鏡を用いた木星や海王星の分子
分光観測から巨大ガス惑星の大気化学進化に関する研究も進めている。 (3)組織 教授 水野亮 准教授 長濵智生 講師 助教 前澤裕之(2011 年 3 月異動)、中島拓(2012 年6月赴任) 特任教員 研究員 礒野靖子(2011 年 8 月赴任, 2013 年 3 月退職)、大山博史(2013 年 6 月赴任) 学 生 数
(人) 2013 年度 4 名(学部理 0、工 0/院前期理 2、工 0/院後期 2、工 0) 2012 年度 4 名(学部理 0、工 0/院前期理 1、工 0/院後期 3、工 0) 2011 年度 5 名(学部理 0、工 0/院前期理 3、工 0/院後期 2、工 0) 2010 年度 4 名(学部理 0、工 0/院前期理 2、工 0/院後期 2、工 0) 2009 年度 5 名(学部理 0、工 0/院前期理 3、工 0/院後期 2、工 0) 2008 年度 3 名(学部理 0、工 0/院前期理 2、工 0/院後期 1、工 0)
(4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行)
52

“Ground-based millimeter-wave observation of stratospheric ClO over Atacama, Chile in the mid-latitude Southern Hemisphere”, Kuwahara, T., Nagahama, T., Maezawa, H., Kojima, Y., Yamamoto, H., Okuda, T., Mizuno, N., Nakane, H., Fukui, Y., Mizuno, A., Atmospheric Measurement Techniques, Volume 5, Issue 11, .2601-2611, 2012 超伝導受信機とデジタル分光計を搭載したミリ波分光計を開発し、チリ・アタカマ高地における高感度
観測によりオゾン層破壊で重要な役割を果たす ClO の昼夜変化を、従来の 278GHz 帯とは異なり他のラ
インの混入のない 204GHz 帯での分光観測から明らかにした。 “Stability of a Quasi-Optical Superconducting NbTiN Hot-Electron Bolometer Mixer at 1.5 THz Frequency Band”, Maezawa, H., Yamakura, T., Shiino, T., Yamamoto, S., Shiba, S., Sakai, N., Irimajiri, Y., Jiang, L., Nakai, N., Seta, M., Mizuno, A., Nagahama, T., Fukui, Y., IEEE Transactions on Applied Superconductivity, vol. 21, issue 3, 640-644, 2011 次世代のテラヘルツ帯ヘテロダイン検出器として注目されるホットエレクトロンボロメタミクサにおい
て、従来型 NbN 細線を NbTiN 細線で構築することにより、安定動作点と高感度性能動作点を両立させ、
実用化に際して重要な特質を有していることを明らかにした。 “Column-averaged volume mixing ratio of CO2 measured with ground-based Fourier transform spectrometer at Tsukuba”, H. Ohyama, I. Morino, T. Nagahama, T. Machida, H. Suto, H. Oguma, Y. Sawa, H. Matsueda, N. Sugimoto, H. Nakane, K. Nakagawa, J. Geophysical Research, 114, D18303, doi:10.1029/2008JD011465, 2009. つくば市に設置した高分解能フーリエ変換型赤外分光器を用いて観測される近赤外領域の太陽光吸収ス
ペクトルデータから大気中の二酸化炭素のカラム平均混合比を 1%以下の精度で求めることが可能なこ
とを航空機観測との比較から実証し、その季節変化を得た。 (5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年 (西暦)
当該部門の
教員が筆頭
著者である
もの
当該部門の特任
教員・研究員が
筆頭著者である
もの
当該部門の学
生が筆頭著者
であるもの
所外の研究者
が筆頭著者で
あるもの
所内(他部門)
の研究者が筆
頭著者である
もの 2013 0 0 0 2 0 2012 0 0 1 3 0 2011 1 0 0 6 0 2010 0 0 0 9 0 2009 0 0 0 6 0 2008 0 0 1 5 0
53

(6)論文以外の特筆すべき成果(5 行) 省電力型(従来機の 1/3)のミリ波分光計を開発し、受信機雑音 80K(DSB)@250GHz を達成した。2012年昭和基地上空の中間圏・下部熱圏の NO の通年観測を行い、極渦の時期に増加する季節変動と磁気嵐
による放射線帯電子の降下にともなう数日スケールの変動を検出し、REP が NO に大きく影響している
ことを観測的に示した。FTIR に代わる可搬型光スペアナを用いた温室効果ガスの測定装置実用化の基本
開発を進めた。 (7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度) 総額 148,657 千円(間接経費含む) 研究期間 種別 研究者名
(代表・
分担)
研究題目 総額(百
万円、間
接 経 費
を含む)
2006-2009 科研基盤 B (一般)
水 野 亮
(代表) 準ミリ波水蒸気分光放射
計による中層大気水蒸
気・オゾンの観測的研究
4.42 総額 19.24百万円
の内の 2008年以降の額
2006-2009 科研基盤 B (海外)
水 野 亮
(代表) チリ共和国アタカマにお
ける成層圏・中間圏の水蒸
気同位体およびオゾンの
観測的研究
7.54 総額 18.85百万円
の内の 2008年以降の額
2008 民間等との共
同研究 (ULVAC)
水 野 亮
(代表) 小型冷凍機を用いた超伝
導電波分光計の電波強度
較正系の開発
3.077
2009 民間等との共
同研究 (ULVAC)
水 野 亮
(代表) 小型冷凍機を用いた超伝
導電波分光計の電波強度
較正系の実用化開発
3.077
2010 JST 企業研究
者活用型基礎
研究推進事業
水 野 亮
(代表) 省電力・可搬型の大気中オ
ゾン及びオゾン消滅分子
のミリ波測定装置の開発
4.373
2011-2012 JST-JICA 科学技術研究
員派遣事業
水 野 亮
(代表) 南半球大気質観測網によ
る同化の 実証的研究プロジェクト
5.56
2011-2014 科研基盤 B (一般)
水 野 亮
(代表) 太陽極大期の高エネルギ
ー粒子の降込みが極域中
間圏大気に及ぼす影響の
観測的研究
13.26 総額 15.73百万円
の内の 2013年以前の額
2012-2017 JST-JICA 地球規模課題
対応国際科学
技術協力
(SATREPS)
水 野 亮
(代表) 南米における大気環境リ
スク管理システムの開発 25.68 総額
130.2百万円
の内の 2013年以前の額
2007-2009 科研基盤 B (一般)
前澤裕之
(代表) 地球大気 OH・酸素原子リ
モート計測のためのテラ
10.4 総額 20.41百万円
54

ヘルツ波ヘテロダインセ
ンサーの開発 の内の 2008年以降の額
2010-2012 科研基盤 B (一般)
前澤裕之
(代表) NMA の単一鏡化と多周波
2SB 受信化による惑星中
層大気環境の変動起源の
観測的研究
13.0 総額 18.1 百万円
の内の在職
期間中(2010年以前)の額
2009-2014 科研基盤 S 前澤裕之
(分担) 多波長ラインサーベイに
よる星形成から惑星系形
成に至る化学進化の解明
2.34 在職期間中
(2010 年 以
前)の額
2010 国立天文台 共同開発研究
前澤裕之
(代表) 汎用デジタル FFT 分光計
の搭載による、NMA-F 号
機を利活用したミリ波惑
星大気観測の開発研究
5
2006-2008 科研基盤 B (一般)
長濵智生
(代表) 磁気圏加速電子との相互
作用による大気微量分子
の組成変動機構の観測的
研究
2.73
総額 16.51百万円
の内の 2008年以降の額
2008 国立環境研究
所 受託研究
長濵智生
(代表) 平成 20 年度デジタル分光
計による広帯域高分解能
ミリ波オゾンスペクトル
の高度分布解析法とその
精度評価に関する研究委
託業務
1.5
2008-2009 国立環境研究
所 受託研究
長濵智生
(代表) 高分解能フーリエ変換型
赤外分光器によるGOS
AT検証実験
6
2008-2012 科研基盤 B (海外)
長濵智生
(代表) 南米最南端でのオゾン層
破壊分子の総合観測によ
るオゾンホールの中緯度
帯への影響研究
17.16
2009 国立環境研究
所 受託研究
長濵智生
(代表) 平成 21 年度陸別ミリ波放
射計のオゾン高度分布解
析法とその長期精度の確
保・評価に関する研究委託
業務
1.5
2010 国立環境研究
所 受託研究
長濵智生
(代表) 平成 22 年度ミリ波分光放
射計によるオゾン高度分
布観測の長期安定運用に
関する研究委託業務
1.5
2011-2013 科研基盤 B (一般)
長濵智生
(代表) 近赤外光スペクトラムア
ナライザによる温室効果
ガスカラム濃度の高精度
計測手法の開発
20.54
55

大気圏環境部門 松見グループ(第 1 部門 3) (1)部門の役割と目的(5 行) 太陽-地球系の中で我々の生活・社会に最も密接に関連する大気圏環境では、数千年分の変動がわずか
に数十年の期間で人間活動によって引き起こされ、オゾン層破壊、地球温暖化、対流圏オゾンや PM2.5の越境汚染などの多くの問題が起こっている。大気環境部門は、大気環境を太陽地球システムの中でと
らえて、室内実験や大気観測を通じて、地球大気に存在する大気微量成分の特徴や時間変化を調べ、地
球環境問題の原因解明に貢献する。 (2)過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行) 二酸化炭素の高度分布の計測が可能な、気球搭載二酸化炭素計測装置を世界に先駆けて開発し、首都
圏から排出された二酸化炭素が輸送・拡散する様子を捉えるなどの成果を得た。レーザー分光法を用い、
二酸化炭素安定同位体の高時間分解能での連続観測を行い、都市や森林における二酸化炭素の放出・吸
収過程に関する知見を得た。また、気候変動や人類の健康への影響が注目されているエアロゾルの物理
化学特性について調べた。室内実験により、人為起源の有機エアロゾルが光吸収性を持つことを初めて
示すとともに、アジア大陸から飛来するエアロゾル中の重金属成分の起源を明らかにした。これらの成
果の多くは、前回「大気環境の実態把握と理解に重要な貢献をなす研究成果」と評価された課題を発展
させ、他の研究機関と共同で実施したものであり、課題とされた「独自に開発した装置のフィールド観
測への応用」や「他の研究機関の研究者の連携」が着実に進んでいる。 (3)組織 教授 松見豊 准教授 講師 助教 中山智喜 特任教員 研究員 ジュリーピアース(2009 年 9 月退職)、江波進一(2009 年 3 月退職)、和田龍
一(2009 年 4 月赴任、2011 年 3 月退職)、弓場彬江(2012 年 4 月赴任)秀森
丈寛(2012 年 7 月赴任)、上田紗也子(2013 年 4 月赴任) 学 生 数
(人) 2013 年度 4 名(学部理 00、工 00/院前期理 02、工 00/院後期 02、工 00) 2012 年度 7 名(学部理 00、工 00/院前期理 05、工 00/院後期 02、工 00) 2011 年度 7 名(学部理 00、工 00/院前期理 06、工 00/院後期 01、工 00) 2010 年度 6 名(学部理 00、工 00/院前期理 06、工 00/院後期 00、工 00) 2009 年度 5 名(学部理 00、工 00/院前期理 04、工 00/院後期 01、工 00) 2008 年度 6 名(学部理 00、工 00/院前期理 04、工 00/院後期 02、工 00)
(4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行)
56

1) Nakayama et al., Laboratory studies on optical properties of secondary organic aerosols generated during the photooxidation of toluene and the ozonolysis of α-pinene, J. Geophys. Res., 115, D24204, doi:10.1029/2010JD014387 (2010).
独自に開発した装置を用いた室内実験により、近紫外領域において、代表的な植物起源の二次有機エ
アロゾルは光吸収性を持たないのに対し、代表的な人為起源の二次有機エアロゾルは光吸収性を有す
ることを初めて明らかにした。 2) Wada et al., Observation of carbon and oxygen isotopic compositions of CO2 at an urban cite in
Nagoya using Mid-IR laser absorption spectroscopy, Atmos. Environ., 45, 1168-1174 (2011). 赤外レーザー吸収分光法を用いて、二酸化炭素の炭素および酸素安定同位体比を高い時間分解能で連
続的に測定し、生物呼吸・ガソリン燃焼・天然ガス燃焼などの排出源が、都市大気の二酸化炭素濃度
に及ぼす寄与が時々刻々と変化する様子を示した。 3) Nakayama et al., Wavelength and NOx dependent complex refractive index of SOAs generated
from the photooxidation of toluene, Atmos. Chem. Phys., 13, 531-545, (2013). 代表的な人為起源の揮発性有機化合物であるトルエンの光酸化反応により生成する二次有機エアロゾ
ルの光学特性の波長依存性や窒素酸化物濃度依存性を詳細に調べ、人為起源の有機エアロゾルが大気
の放射収支や光化学反応に影響を及ぼす可能性を示した。 (5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年 (西暦)
当該部門の
教員が筆頭
著者である
もの
当該部門の特任
教員・研究員が
筆頭著者である
もの
当該部門の学
生が筆頭著者
であるもの
所外の研究者
が筆頭著者で
あるもの
所内(他部門)
の研究者が筆
頭著者である
もの 2013 1 1 2012 2 2011 1 1 2 2010 4 1 2 2009 1 2 2008 1 1 4 2 (6)論文以外の特筆すべき成果(5 行) 二酸化炭素の高度分布を計測することで、気候変動の理解する上で、二酸化炭素の放出・吸収過程を
定量的に調べることが可能となる。従来、二酸化炭素の高度分布の計測には、航空機により観測が用い
られているが、世界中の様々な場所で、安価に測定を行うことは困難であった。我々は、企業と共同で、
世界初の気球搭載二酸化炭素計測装置の開発に成功し、国内外の研究者から注目されている。
57

(7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度)総額 173,500 千円(間接経費を含む) 研究期間 種別 研 究 者 名
(代表・分
担)
研究題目 総額(百万
円、間接経
費を含む)
備考
2004-2008年度
受託研究 (JST) 先端計測
松見豊 (代表)
光イオン化質量分析法による微
粒子・微量成分計測 38.0 総額
219 百万円
2007-2008年度
科研 若手 B
中山智喜 (代表)
赤外半導体レーザーを用いた安
定同位体のリアルタイム計測装
置の開発
1.7 総額 3.1 百万円
2007-2008年度
共同研究 ( 矢 崎 総
業)
松見豊 (代表)
大気中の微量成分の検出装置の
開発 1.0 総額
2.0 百万円
2007-2009年度
学振・ 特別研究員
松見豊 ( 受 入 研
究者)
レーザーイオン化個別粒子質量
分析の開発と大気エアロゾル解
析への応用
1.4
総額 2.3 百万円
2007-2008年度
学振・ 特別研究員
松見豊 ( 受 入 研
究者)
キャビティリングダウン法と質
量分析計を組み合わせた新しい
エアロゾル研究
1.1
総額 2.2 百万円
2008 年度 奨学寄附金 ( 三 菱 化
学)
中山智喜 (代表)
夜間の窒素酸化物の大気化学反
応過程の解明 1.0
2008-2010年度
科研・ 基盤 B
松見豊 (代表)
大気中の二酸化炭素の気球観測
器の開発 18.2
2008-2012年度
科研・ 新学術領域
松見豊 (分担)
健康影響が懸念される PM2.5 粒
子状物質のわが国風上域での動
態把握
24.0
2009-2010年度
受託研究 (JST) 先端計測
松見豊 (代表)
二酸化炭素モニタリング用超小
型計測装置 6.0
2009-2011年度
科研・ 若手 B
中山智喜 (代表)
光吸収性エアロゾルの光学特性
の湿度依存性の解明 4.4
2009-2010年度
受託研究 (環境省) 推進費若手
中山智喜 (代表)
エアロゾルの放射影響の定量化
のための二次有機エアロゾルの
光吸収特性に関する研究
15.0
2010-2012 科研・ 中山智喜 高精度エアロゾル光学特性測定 7.0
58

年度 基盤 B (分担) 法の開発と実証観測 2011 年度 受託研究
(JST) 先端計測
松見豊 (分担)
世界標準をめざした光学的二酸
化炭素自動測器の実用化開発 2.0
2011 年度
奨学寄附金 (TOTO)
松見豊 (代表)
大気圏環境部門における研究助
成 0.8
2011 年度
奨学寄附金 (鉄鋼環境
基金)
中山智喜 (代表)
産業起源の揮発性有機化合物か
ら生成する二次粒子の光学特性
の評価
1.0
2012-2014年度
科研・ 基盤 B
松見豊 (代表)
レーザー分光同位体計測計を用
いた大気環境の動態解明 15.3
2011-2015年度
受託研究 (文科省) GRENE
松見豊 (分担)
衛星データ等複合利用による東
アジアの二酸化炭素、メタン高濃
度発生源の特定解析
23.5
総額 45.5 百万円
2012 年度 奨学寄附金 (日本生命
財団)
中山智喜 (代表)
木材燃焼により発生した微粒子
が大気環境に与える影響の評価 1.0
2012-2013年度
奨学寄附金 (豊秋奨学
会)
中山智喜 (代表)
大気中ブラックカーボン粒子の
形状と混合状態が光学特性に及
ぼす影響の解明
0.8
2013-2016年度
科研・ 若手 A
中山智喜 (代表)
自動車排ガス起源の二次有機エ
アロゾルの光学特性の解明 10.3 総額
23 百万円
59

電磁気圏環境部門(第2部門) (1)部門の役割と目的(5 行) 太陽風から地球の磁気圏・電離圏に流入してくるプラズマと電磁エネルギーは、地球周辺の宇宙空間
でのプラズマダイナミクスを支配し、極域のオーロラ発光や超高層大気の擾乱を引き起こす。一方、下
層大気から伝搬してくる大気波動は超高層大気内でエネルギーと運動量を放出しながら熱圏・電離圏ま
で侵入し、中間圏・熱圏・電離圏の大気・プラズマダイナミクスを支配している。電磁気圏環境部門で
は、国内外における電波・光技術を用いた観測機器、および飛翔体搭載機器を基にしてこれらの変動現
象を研究する。 (2)過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行)
2007 年度に行われた前回の外部評価においては、課題2(磁気圏・電離圏・熱圏・中間圏のエネルギ
ー交換過程と物質の結合過程の解明)に関して、それまで地上観測の整備に力を入れてきたことが評価
され、今後、観測設備の維持・運用が研究活動に過度の負担とならないように配慮しつつ活動を続けて
ほしい、との指摘がなされている。これ以降、当部門では、それまでの自動観測を維持・継続すると共
に、2010 年にトロムソに大気温度と風速の観測が可能なナトリウムライダーを設置、2009-2010 年に 4台のファブリ・ペロー干渉計をノルウェー、タイ、インドネシア、オーストラリアに設置、2012 年にカ
ナダ・アサバスカに VLF 波動観測用ループアンテナを、ノルウェー・トロムソに GPS 三角観測点をそ
れぞれ設置、2013 年 3 月にはハワイに全天カメラを設置、また 2008 年 9 月に SuperDARN 北海道-陸別 HF レーダーに新たにデジタル受信機を設置するなど、さらに地上ネットワーク観測を拡充してきた。
これらの新たな観測とこれまでの観測点から得られるデータをデータベース化して、年間 15 件程度の共
同研究を国内の他の研究機関と行うなど、さまざまな成果を挙げてきた。2011 年 4 月には新たに平原聖
文教授が東京大学から赴任し、飛翔体搭載用粒子分析器の開発と共同利用としての室内較正装置(ビー
ムライン)の整備を開始している。1990 年代から第 2 部門はずっと豊川と東山に半々に別れていたが、
2008 年 6 月に豊川 2 部門が名古屋に移転して以降は、ようやく 1 つの部門として協力することができる
ようになった。移転後は学生数も増え、平成 25 年度は学部・大学院生を合わせて 26 名の学生が所属す
る大きな研究室になっている。一方、2011 年 12 月以降、1 つ空席になっている助教ポストが埋められて
おらず、教育研究の人員が不足している。 (3)組織 教授 小川忠彦(2008 年 3 月退職)、塩川和夫(2008 年 9 月昇任)、藤井良一(名古
屋大学理事・副総長と兼任)、平原聖文(2011 年 4 月赴任) 准教授 塩川和夫(2008 年 8 月まで)、野澤悟徳、大塚雄一(2011 年 11 月昇任) 講師 - 助教 大塚雄一(2011 年 10 月まで)、大山伸一郎 特任教員 鈴木臣(2010 年 8 月赴任)、下山学(2011 年 11 月赴任) 研究員 西岡未知(2010 年 4 月-2011 年 8 月)、津田卓雄(2012 年 3 月まで)
60

学 生 数
(人) 2013 年度 26 名(学部理 00、工 06/院前期理 04、工 12/院後期理 03、工 01) 2012 年度 19 名(学部理 00、工 06/院前期理 03、工 07/院後期理 02、工 01) 2011 年度 11 名(学部理 00、工 02/院前期理 03、工 04/院後期理 02、工 00) 2010 年度 10 名(学部理 00、工 02/院前期理 03、工 03/院後期理 02、工 00) 2009 年度 10 名(学部理 00、工 04/院前期理 01、工 03/院後期理 02、工 00) 2008 年度 9 名(学部理 00、工 01/院前期理 02、工 04/院後期理 02、工 00)
(4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行) Shiokawa, K., Y. Otsuka, and T. Ogawa, Propagation characteristics of nighttime mesospheric and thermospheric waves observed by optical mesosphere thermosphere imagers at middle and low latitudes, Earth, Planets, Space, 61, 479-491, 2009. 世界最大の夜間大気光イメージング観測ネットワークである超高層大気イメージングシステム(OMTIs)の成果をとりまとめてレビューした論文。高緯度から低緯度までの熱圏・中間圏の大気波動の伝搬特性
を総合的に明らかにした。 Otsuka, Y., K. Shiokawa, T. Ogawa, T. Yokoyama, and M. Yamamoto, Spatial relationship of nighttime medium-scale traveling ionospheric disturbances and F region field-aligned irregularities observed with two spaced all-sky airglow imagers and the middle and upper atmosphere radar, J. Geophys. Res., 114, A05302, doi:10.1029/2008JA013902, 2009. 中緯度における電離圏電子密度変動の一種である中規模伝搬性電離圏擾乱(MSTID)と沿磁力線不規則構
造(FAI)の空間構造を観測的に明らかにすることにより、MSTID に伴う分極電場が FAI の生成に重要な
役割を果たしていることを初めて明らかにした。 Kurihara, J., Y. Ogawa, S. Oyama, S. Nozawa , M. Tsutsumi , C. Hall , Y. Tomikawa , R. Fujii, Links between a stratospheric sudden warming and thermal structures and dynamics in the high-latitude mesosphere, lower thermosphere, and ionosphere, Geophys. Res. Lett., 37, L13806, doi:10.1029/2010GL043643, 2010. 2009 年1月に発生した成層圏突然昇温(SSW)の前後期間における極域中間圏・下部熱圏・電離圏の変動
を調べた。SSW が極域中間圏・熱圏・電離圏の温度構造および大気ダイナミクスに大きな影響を与えて
いることを示した。
61

(5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年 (西暦)
当該部門の
教員が筆頭
著者である
もの
当該部門の特任
教員・研究員が
筆頭著者である
もの
当該部門の学
生が筆頭著者
であるもの
所外の研究者
が筆頭著者で
あるもの
所内(他部門)
の研究者が筆
頭著者である
もの 2013 4 3 3 7 0 2012 8 2 3 19 1 2011 5 1 3 35 1 2010 3 2 2 8 3 2009 10 3 3 27 0 2008 4 0 2 19 2 (6)論文以外の特筆すべき成果(5 行)
当部門の教員は、地球電磁気・地球惑星圏学会の総務担当運営委員として、2012 年に同学会の将来構
想のとりまとめを行ったり、ICSU 参加の国際組織 SCOSTEP が 2009-2013 年に推進する CAWSES-II国際プログラムの 4 つのタスクグループの中で、中間圏・熱圏・電離圏を中心としたタスクグループの
リーダーを務めたりするなど、国内・海外においてリーダーシップをもって研究を推進している。また、
当部門の新しい共同利用装置として、ナトリウムライダーや衛星搭載機器の地上較正装置の整備・運用
を開始し、国内外への観測データ・機器開発環境を提供し始めた。 (7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度) 総額 265,670 千円(間接経費含む) 研究期間 種別 研究者名
(代表・
分担)
研究題目 総額(百万
円、間接経
費を含む)
備考
2013 年
度 ~
2015 年
度
JSPS研究
拠点形成
事業(B.
アジア・ア
フリカ学
術基盤形
成型)
塩 川 和
夫(代表) 東南アジア・西アフリカ赤
道域における電離圏総合観
測
7.81 (2013 年度
の額)
2013 年
度 ~
2017 年
度
科研費・
基盤研究
(A)
塩 川 和
夫(代表)、大塚雄一
(分担)
人工衛星-地上ネットワー
ク観測に基づく内部磁気圏
の粒子変動メカニズムの研
究
21.06 2013 年度
の額。 総 額 は
43.81 2010 年 科研費・ 塩 川 和 人工衛星-地上ネットワー 16.77 2010-2013
62

度 ~
2014 年
度
基盤研究
(B)(海外) *
夫(代表) クによるオーロラと電磁波
動の高時間分解能観測 年度の額。 総 額 は
19.89 2008 年
度 ~
2012 年
度
科研費・
基盤研究
(A)(一般)
塩 川 和
夫(代表)、大塚雄一
(分担)
高感度分光多点観測による
超高層大気変動の研究 47.84
2006 年
度 ~
2009 年
度
科研費・
基盤研究
(B)(海外)
塩 川 和
夫(代表)、大塚雄一
(分担)
シベリア域から日本におけ
るジオスペース環境変動の
衛星-地上共同観測
6.63 2008-2009年度の額。 総 額 は
16.84 2007 年
度 ~
2010 年
度
科研費・
基盤研究
(B)(一般)
小 川 忠
彦、塩川
和夫 、大
塚 雄 一 (分担)
カナダ北極域におけるオー
ロラの高時間分解能光学観
測
9.1 2008-2010年度の額。 総 額 は
16.51
2009 年
度 ~
2012 年
度
科研費・基
盤研究(A) 平原聖文
(代表) 波動-粒子相互作用・電磁
場による放射線帯・衝撃
波・極域磁気圏での宇宙プ
ラズマ加速
12.87 赴 任 後 の
2011 -2012年度の合計
( 総 額 :
44.46)
2008 年
度 ~
2010 年
度
科研費・
若手研究
(A)
大塚雄一
(代表) 低緯度電離圏不規則構造のレ
ーダー・イメージング観測 22.62
2010 年
度 ~
2012 年
度
科研費・
基盤研究
(B) (海外)
大塚雄一
(分担) インド・東南アジア・太平洋
の広域観測による赤道スプレ
ッド F 現象の日々変動の解明
0.91
2011 年
度 ~
2013 年
度
科研費・
基盤研究
(B)(海外)
大塚雄一
(代表) GPS シンチレーション観測に
よる極域電離圏イレギュラリ
ティの研究
20.02
2011 年
度 ~
科研費・
基盤研究
大塚雄一
(代表) 電離圏・熱圏の春・秋非対称
性 4.94
63

2013 年
度 (C)(一般)
2012 年
度 ~
2014 年
度(予定)
科研費・
基盤研究
(B)(海外)
大塚雄一
(分担) 異なる地域の対流圏活動が起
こす中間圏変動の地上と宇宙
からの同時観測
1.41
(2012 ~
2013 年度)
2013 年
度 ~
2015 年
度(予定)
科研費・
基盤研究
(B)
大塚雄一
(分担) 赤道大気レーダーと広域観測
網による赤道スプレッド F 現
象と電離圏構造の関連の解明
0.15
(2013 年
度)
2012 年
度 ~
2014 年
度(予定)
科研費・
基盤研究
(B)
大塚雄一
(分担) ロケット・地上連携観測によ
る中緯度電離圏波動の生成機
構の解明
0.64
(2012 ~
2013 年度)
2010 年
度 ~
2012 年
度
科学技術
戦略推進
費
大塚雄一
(分担) インドネシア宇宙天気研究の
推進と体制構築 7.43
2013 年
度 ~
2015 年
度
科研費・
基盤研究
(B)
野澤悟徳
(代表) 北極域拠点観測による大気上
下結合の研究 7.67 (2013 年
度)
2010 年
度 ~
2013 年
度
科研費・
基盤研究
(B)
藤井良一
(代表)、
野澤悟徳
(分担)
大山伸一
郎(分担)
EISCATレーダーを用い
たジオスペースに関する国際
協同研究
17.42
2011 年
度 ~
2013 年
度
科研費・
基盤研究
(B)
野澤悟徳
(分担) 電離圏嵐の数値予報:北極・
赤道域観測と連携したシミュ
レーション手法開発と実証
20.15
2012 年
度 ~
2014 年
度
科研費・
基盤研究
(B)
野澤悟徳
(分担) ナトリウムライダーの新規観
測モード:3次元観測への拡
張
8.97 2012 ~
2013年度
64

2008 年
度 ~
2010 年
度
科研費・
基盤研究
(C)
野澤悟徳
(分担) データ融合シミュレーション
による熱圏・電離圏変動の研
究
4.42
2007 年
度 ~
2010 年
度
科研費・
基盤研究
(C)
野澤悟徳
(分担) 流星エコー観測に基づく極域
中間圏界面領域の大気重力波
特性の研究
4.68
2008 ~
2010年度
2006 年
度 ~
2009 年
度
科研費・
基盤研究
(B)
藤井良一
(代表)、
野澤悟徳
(分担)
大山伸一
郎(分担)
EISCAT レーダーを主に用いた
磁気圏・電離圏・熱圏・中間
圏結合の総合的研究
9.23
2008 ~
2009年度
2005 年
度 ~
2008 年
度
科研費・
基盤研究
(B)
藤井良一
(代表)、
野澤悟徳
(分担)
大山伸一
郎(分担)
磁気圏-電離圏結合における
電離圏の能動的役割の研究 3.12 2008年度
2011 年
度 ~
2013 年
度
科研費・
若手研究
(B)
鈴 木 臣
(代表) 光学・電波観測を組み合わせ
た大気重力波の鉛直伝搬過程
の解明
3.64
2007 年
度 ~
2008 年
度
山田科学
振興財団 大山伸一
郎(代表)
EISCAT レーダー用信号処理装
置の開発と極域下部熱圏観測
への応用
2.00 2007-2008
年 度 の 合
計(年度ご
と の 分 類
無し)
2010 年
度 JSPS 特
定国派遣
研究者制
度
大山伸一
郎(代表)
ノルウェーに設置されたオー
ロラ観測装置の観測モード開
発
ノルウェ
ー(30日)
旅費相当
65

2010 年
度 JSPS 国
際学会派
遣事業
大山伸一
郎(代表)
Characteristics of the
mesospheric gravity wave
observed with an all-sky
camera at Tromso, Norway in
2009-2010
チェコ (7
日間 ) 旅
費相当
2010 年
度 中部科学
技術セン
ター 学
術奨励研
究助成金
大山伸一
郎(代表)
北極域の中間圏界面における
大気重力波の特性と大気大循
環への影響
0.30
2012 年
度 ~
2014 年
度
科 研 費
( 基 盤
C)
大山伸一
郎(代表)
脈動オーロラが起こす熱圏風
速変動の解明
3.87 2012-2013
年度
2012-2013 日本学術振
興会日露二
国間共同研
究事業
西谷 望
(代表)
日本北方・シベリア域における電離
圏擾乱研究手法の開発
5.000
(2008-2012)
5.000
(全期間)
2007-2010 科 研 基 盤
(B)
西谷 望
(代表)
大型短波レーダーによる中・高緯度
電離圏プラズマー超高層大気相互
作用の研究
12.090
(2008-2012)
17.550
(全期間)
66

太陽圏環境部門 太陽風グループ(第3部門1) (1)部門の役割と目的(5 行) 当該グループは、太陽から地球へのエネルギーを輸送する過程の一つである太陽風について、天体電波
源の“またたき”現象(惑星間空間シンチレーション、IPS)を用いた独自の観測から、その生成機構や
太陽活動に伴うダイナミックな変動を解明することを目指している。本観測研究を軸として国内外の研
究者と協同研究を推進し、太陽地球系物理や天文学の発展に寄与する。 (2)過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行) 当該グループの IPS 観測による太陽風研究は、前回の外部評価において、世界的にもユニークなものし
て「人材と資金の継続的投資により、今後も継続・発展すべき」との評価を得ている。その評価を受け
て我々がまず取り組んだのは、IPS 観測システムの更新である。2008 年夏からは豊川で高感度の大型ア
ンテナ(SWIFT)による観測を開始し、2010 年秋からは富士・木曽の IPS システムの更新により SWIFTとの同時観測が可能になった。さらに 2013 年からは富士・木曽アンテナの高感度化のため更なるシステ
ム更新を行っている。一方、取得した IPS 観測データからは、第 24 サイクルにおける特異な太陽活動に
伴って太陽風のグローバル分布に過去とは異なる特徴を発見した。これらの成果は、IBEX や Voyagerによる太陽圏外圏域探査に関する協同研究に発展している。また宇宙天気予報の協同研究を推進し、IPSデータの解析から CME 伝搬における加速・減速過程を明らかにした。 (3)組織 教授 徳丸宗利(2008 年 9 月~) 准教授 同 (~2008 年 8 月) 講師 助教 藤木謙一* 特任教員 研究員 学 生 数
(人) 2013 年度 1 名(大学院前期 理 0/後期 理 1) 2012 年度 1 名(大学院前期 理 0/後期 理 1) 2011 年度 3 名(大学院前期 理 2/後期 理 1) 2010 年度 4 名(大学院前期 理 2/後理 期 2) 2009 年度 2 名(大学院前期 理 1/後期 理 1) 2008 年度 2 名(大学院前期 理 1/後期 理 1)
*ジオスペース研究センター所属 (4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行) Tokumaru, M., M. Kojima, K. Fujiki, and K. Hayashi, Non-dipolar solar wind structure observed
in the cycle 23/24 minimum, Geophys. Res. Lett., 36, L09101, 2009 (doi:10.1029/2009GL037461). 67

サイクル 2/24 極小期において高速風が両極域のみならず赤道付近にも出現したことを、IPS 観測か
ら明らかにした。このような構造は過去の極小期には見られず、今期の太陽活動の特異性(弱い極
磁場)を反映している。 Tokumaru, M., M. Kojima, and K. Fujiki, Long-term evolution in the global distribution of solar
wind speed and density fluctuations for 1997-2009, J. Geophys. Res., Vol. 117, A06108, 2012 (doi:10.1029/2011ja017379). サイクル23~24における IPS観測から太陽風速度と密度揺らぎのグローバル分布の長期変動を IPS観測から決定したところ、太陽風密度揺らぎのレベルが全球的に徐々に低下していることが判明し
た。この事実は太陽圏全体の収縮を示唆する。
Iju, T., M. Tokumaru, and K. Fujiki, Radial speed evolution of interplanetary coronal mass ejections during solar cycle 23, Solar Physics, in press, 2013 (http://arxiv.org/abs/1303.5154). サイクル 23 における 39 の CME イベントについて IPS データを使って太陽から地球軌道までの速
度変化を明らかにした。その結果、高速の CME の伝搬は Stokes drag により支配されていることが
判明した。本成果は宇宙天気予報の精度改善に寄与する。 (5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年 (西暦)
当該部門の
教員が筆頭
著者である
もの
当該部門の特任
教員・研究員が
筆頭著者である
もの
当該部門の学
生が筆頭著者
であるもの
所外の研究者
が筆頭著者で
あるもの
所内(他部門)
の研究者が筆
頭著者である
もの 2013 2 0 3 4 0 2012 3 0 0 2 0 2011 1 0 0 6 1 2010 3 0 2 9 0 2009 2 0 0 4 0 2008 0 0 0 0 0 (6)論文以外の特筆すべき成果(5 行) UCSD との協同研究を通じて内部太陽圏の3次元構造と時間変動を復元する Time-dependent Tomography(TDT)の開発を行ってきた。このプログラムは現在 NASA Community Coordinated Modeling Center のサーバ上で広く利用可能になっており、名大 STE 研の IPS データが日々upload さ
れている。さらに TDT は韓国宇宙天気センターでも予報業務に用いられるようになった(2012 年、同
センターと STE 研は研究交流協定を締結)。
68

(7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度) 総額 62,100 千円(間接経費含む) 研究期間 種別 研究者名
(代表・
分担)
研究題目 総額(百
万円、間
接経費を
含む)
2008-2009 学術創成
研究費 藤木謙一
(分担) 宇宙天気予報の基礎研究 9.4
2009-2012 科研基盤
B 徳丸宗利
(代表) 第 24 太陽活動極小期における
特異太陽風構造の解明 18.1
2013-2017 科研基盤
A 徳丸宗利
(代表) 特異な太陽ダイナモ活動に伴
う太陽圏全体構造の変動の解
明
34.2 2013 年
度の額
2012 JSPS サ
マープロ
グラム
徳丸宗利
(受入) Numerical modeling of the heliosphere using interplanetary scintillation data/K. Tae (UAH)
0.1
2010-2012 科研基盤
B 徳丸宗利
(分担) NMA の単一鏡化と多周波
2SB 受信化による惑星中層大
気環境の変動起源の観測的研
究
0.3
69

太陽圏環境部門 宇宙線グループ(第3部門2)
太陽圏環境部門(第3部門2) (1) 部門の役割と目的(5 行) 太陽圏の内外から到来する高エネルギー粒子・宇宙線の研究を通じて、宇宙物理、太陽地球系物理、素
粒子物理にまたがる以下の研究を行う。 ・宇宙線をプローブとして太陽圏内外の電磁気的構造と宇宙線環境を明らかにする。 ・宇宙線の加速機構の解明を通じて宇宙プラズマの非熱的な素過程の理解を目指す。 ・宇宙線と地球大気との相互作用の詳細を解明し、宇宙線が地球に及ぼす影響を解明する。 ・素粒子実験の技術、手法を利用した新たな宇宙線観測装置、解析手法の開発。 (2) 過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行) ・年輪中炭素14濃度の測定と解析を進め、西暦774年の宇宙線異常増加イベントを発見した。今後
の定常的測定体制の確立に向けて検討進めている。 ・重力マイクロレンズ観測については浮遊惑星の発見という独自の成果を挙げた。大阪大、京都産業大
に連携を拡大して定常的な観測体制を維持し、データの利用による多くの成果が出ている。 ・太陽中性子観測に関して、エネルギー測定性能を飛躍的向上させる新型検出器をメキシコ観測サイト
へ設置し運用を開始した。 ・宇宙線と大気との相互作用を加速器実験で検証する LHCf 実験を素粒子宇宙起源研究機構と共同で遂
行し、これまで最も高いエネルギーでの宇宙線の反応を明らかにした。 ・「研究所の分野横断的人員の活用」との外部評価コメントに対して、第一部門と共同で「宇宙線による
雲核生成実験」を立ち上げた。 ・「理学研究科宇宙実験との連携による宇宙への進出」との外部評価コメントに対して、飛翔体ガンマ線
研究者(田島教授、奥村助教)を採用し、新たに宇宙ガンマ線研究のグループを立ち上げた。同教授は
超小型衛星 ChubuSat の責任者でもあり、本研究所の衛星アクティビティ強化にもつながっている。 ・フェルミ衛星の観測データを解析し、超新星残骸の衝撃波で宇宙線陽子が加速されていることを確立
した。 ・フェルミ衛星の観測データを解析し、素粒子暗黒物質が存在するとすれば、その質量が 30 GeV/c2以上
であることを明らかにした。 ・太陽硬 X 線観測ロケット FOXSI のための硬 X 線カメラを開発し、集光光学系を用いた太陽フレアの
硬 X 線分光撮像に初めて成功した。 (3)組織 教授 伊藤好孝、田島宏康(2010 年 9 月赴任) 准教授 増田公明、松原豊、(阿部文雄:ジオスペース研究センター) 講師
70

助教 さこ隆志、住貴宏(2011 年 3 月転出)、奥村曉(2012 年 9 月着任) 特任教員 研究員 三塚岳(GCOE研究員 2009 年着任、2013年転出)、内藤博之(GCOE研究員 2008
年着任,2012 年転出)、野田浩司(2010 年着任、2010 年転出)、奥村曉(学振PD 2011 年着任、2012 年転出)
学 生 数
(人) 2013 年度 27 名(学部理 5、工 0/院前期理 13、工 0/院後期 9、工 0) 2012 年度 26 名(学部理 6、工 0/院前期理 13、工 0/院後期 7、工 0) 2011 年度 28 名(学部理 3、工 0/院前期理 15、工 0/院後期 10、工 0) 2010 年度 28 名(学部理 6、工 0/院前期理 14、工 0/院後期 8、工 0) 2009 年度 25 名(学部理 7、工 0/院前期理 9、工 0/院後期 9、工 0) 2008 年度 21 名(学部理 6、工 0/院前期理 9、工 0/院後期 6、工 0)
(4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行) 1)” Measurement of zero degree single photon energy spectra for √s=7TeV proton-proton collisions at LHC ”, O.Adriani et al., Phys. Lett. B, 703, 128-134, 2011 「超高エネルギー宇宙線の空気シャワー発達に重要な超前方データをこれまでで最も高い衝突エネルギ
ーで測定し、宇宙線に使われるハドロン散乱モデルを検証した。引用数 17」 2) “Unbound or distant planetary mass population detected by gravitational microlensing”, T.Sumi et al., Nature, 473, 349-353, 2011, 「これまで理論的に予想されていた浮遊惑星の存在量を始めて明らかにした。重力マイクロレンズ効果
のみが可能なユニークな研究で、TV報道、海外誌などにも紹介され反響を呼んだ。引用数 75」 3)” A signature of cosmic-ray increase in AD 774–775 from tree rings in Japan”, F.Miyake et al., Nature, 486, 240-242, 2012 「年輪中放射性炭素14から過去に地球的規模で宇宙電離放射線が突発的増加事象の存在を立証。国内
外で多くの追随研究を生んだ。TV報道、海外誌などでも注目された。引用数 12」 (5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年(西暦) 教員が筆頭著者
であるもの 特任教員・研究員が
筆頭著者であるもの 学生が筆頭著者
であるもの 所外の研究者が筆
頭著者であるもの 2013 0 0 1 10
2012 0 4 5 31 2011 5 0 5 17 2010 1 0 1 11 2009 2 0 0 18 2008 3 0 0 12
71

(6)論文以外の特筆すべき成果(5 行) ・AstroH 搭載の軟ガンマ線カメラの原理を応用して、福島第一原発事故由来の放射性セシウムからのガ
ンマ線を可視化するカメラ(Astro-CAM)をJAXA,三菱重工と共同で開発した。除染などに役立つと期
待される。 (7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度) 総額 404,167 千円+?(間接経費含) 研究期間 種別 研究者名
(代表・
分担)
研究題目 総額(百万
円、間接経費
を含む)
2007-2008 科 研 萌
芽 伊藤好孝
(代表) LHCでの高エネルギー
ニュートリノ研究の検討 3.3 2008 年度の
み
2007-2008 科 研 特
定 領 域
研究
住 貴 宏
(代表) 重力マイクロレンズによ
る太陽系外惑星、浮遊惑
星の探索
1.7
2007-2008 科 研 特
定 領 域
公募
さこ隆志
(代表) LHCf2号機による最高
エネルギー宇宙線相互作
用モデルの高精度検証
1.8 2008 年度の
み
2008-2009 科 研 若
手B さこ隆志
(代表) LHC原子核衝突を利用
した宇宙線と地球大気相
互作用の解明
4.29
2008-2010 科 研 基
盤 B 海
外
伊藤好孝
(代表) 超高エネルギー宇宙線解
明のためのLHC陽子衝
突での超前方測定
16.5
2008 科 研 特
定 領 域
公募
さこ隆志
(代表) 光学赤外観測による南天
高赤方偏移 GRB の探索
1.2
2008-2009 科 研 若
手B 住 貴 宏
(代表) 惑星アラートシステムの
運用及びトランジット系
外惑星の探査
4.55
2009-2010 科 研 特
定 領 域
公募
さこ隆志
(代表) 南天ガンマ線バースト残
光探索による初期宇宙・
高エネルギー宇宙の研究
2.2
2010-2013 科 研 基
盤B 松 原 豊
(代表) 高感度宇宙放射線測定装
置による太陽中性子の観
測
19.63
72

2010-2012 科 研 基
盤B 増田公明
(代表) 放射性炭素測定による過
去の太陽活動の周期性及
び地球環境との関係の解
明
18.46
2010-2012 科 研 特
定 領 域
公募
さこ隆志
(代表) LHC最前方での放射線
環境測定とGSO輝度モ
ニタの実証
10.27
2011-2014 科 研 基
盤A 田島宏康
(代表) 大面積・半導体チェレン
コフ・カメラの開発研究
とその実証
34.32 2011-2013年度のみ
2011-2014 科 研 基
盤 A 伊藤好孝
(代表) LHC超前方測定による
宇宙線シャワーとハドロ
ン散乱の包括的解明
29.73 2011-2013年度のみ
2011-2014 科 研 基
盤B 住 貴 宏
(代表) 重力マイクロレンズによる
地球質量系外惑星、浮遊
惑星の探索
6.5 名 大 在 籍
2011 年度の
み
2011-2012 科 研 萌
芽 増田公明
(代表) 宇宙線による雲核生成と
気候への影響に関する検
証実験
3.51
2011-2012 科 研 若
手B 三 塚 岳
(代表) LHCf 実験における TeV領域での中性Kメソンの
観測、および中性 K/pi比の測定
4.03
2012-2013 科 研 新
学 術 公
募
さこ隆志
(代表) GSOシンチレータの放
射線損傷回復の理解とそ
の能動的回復の挑戦
9.1
2013-2015 科 研 萌
芽 伊藤好孝
(代表) 光読み出し型球形一相式
液体キセノンドリフトカ
ロリメーターの開発
1.95 2013 年度の
み
2013-2014 科 研 萌
芽 奥 村 曉
(代表) 世界最高の角度分解能を
持つ光学望遠鏡の実現 2.86 2013 年度の
み 2013-2016 科 研 基
盤B さこ隆志
(代表) LHC 軽原子核衝突超前
方測定にむけたシリコン
ピクセルカロリーメータ
の開発
4.18 2013 年度の
み
2013-2016 科 研 若 奥 村 曉 大気チェレンコフ光の収 5.2 2013 年度の
73

手A (代表) 集効率改善による次世代
ガンマ線望遠鏡 CTA の
高感度化
み
2011-2013 共 同 研
究 田島宏康
(代表) 50kg 級 小 型 衛 星
ChubuSat-1 の開発 5.478
2012-2013 受 託 研
究 田島宏康
(代表) 革新的超広角高感度ガン
マ線可視化装置の開発 24.375
2006-2009 科 研 基
盤(A) 阿部文雄
(代表) MOAⅡ1.8m望遠鏡に
よるマイクロレンズ事象
の探索
13.104 25.194
2008-2010 科 研 基
盤(B) 阿部文雄
(代表) マイクロレンズ追尾観測
網による太陽系外地球型
惑星の探索
9.100 9.100
2010-2012 科 研 基
盤(B) 阿部文雄
(代表) MOA II 1.8m望遠鏡によ
るマイクロレンズ事象の
探索
13.000 13.000
2011-2014 科 研 基
盤(B) 阿部文雄
(代表) マイクロレンズ追尾観測
網による太陽系外惑星の
探索
8.970 12.610
2011-2013 科 研 挑
戦 的 萌
芽
阿部文雄
(代表) ワームホールの観測的検
証 3.055 3.055
2013-2014 新 学 術
領域 阿部文雄
(代表) 広視野望遠鏡を利用した
重力波天体の光学観測 3.510 4.472
74

総合解析部門(第 4 部門) (1)部門の役割と目的(5 行) 総合解析部門は太陽地球環境をひとつのシステムと捉えその構造とダイナミクスを総合的に理解する
と共に、その変動予測のための科学研究を推進することを目的としている。このため、様々な観測デー
タの解析及びモデリング・シミュレーション研究を多角的に実施する。さらに、「実証型ジオスペース環
境モデリングシステム(GEMSIS)」プロジェクトの推進、太陽観測衛星・ジオスペース探査衛星サイエ
ンスセンターの運営を担当する。 (2)過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行) 前回外部評価においては「データ解析とモデリング・シミュレーションを有機的に結びつける努力の
発展性に期待が持てる」との評価を受けた。その後、データ解析とシミュレーションの融合による本格
的な総合解析研究を発展させるため、草野教授、町田教授、今田助教を新たに迎え、太陽地球環境シス
テムを包括的に研究できる体制を整備すると共に、GEMSIS プロジェクトを着実に推進した。その結果、
太陽フレアの発生機構に関する研究、磁気圏サブストーム開始時における電磁流体力学的なネルギー収
支の定量解析、磁気嵐時における電場の赤道領域侵入過程の解析、放射線帯外帯の変動と太陽風大規模
構造の相関メカニズムに関する研究などについて多くの重要な成果をあげることができた。さらに、太
陽観測衛星ひのでサイエンスセンター及びジオスペース探査計画 ERG サイエンスセンターそれぞれの
設立及び運営の主体となり、コミュニティーに大きな貢献を行った。 (3)組織 教授 菊池崇(2012 年 3 月退職)草野完也(2009 年 7 月赴任)、町田忍(2013 年 4
月赴任) 准教授 関華奈子、増田智、三好由純(2012 年 1 月着任) 講師 助教 家田章正、三好由純(2004 年 1 月~2011 年 12 月)、今田晋亮(2012 年 9 月) 特任教員 塩田大幸(2013 年 4 月赴任)、宮下幸長(2013 年 4 月着任)、桂華邦裕(2013
年 7 月赴任)、 研究員 松本洋介(2004 年 4 月~2011 年 3 月)
新堀淳樹(2006 年 4 月~2010 年 3 月) 堀 智昭(2007 年 4 月~2009 年 4 月) 天野孝伸 (2008 年 4 月~2009 年 3 月) 平木康隆(2008 年 4 月~2010 年 3 月) 簑島敬(2008 年 4 月~2010 年 3 月) 山本哲也(2008 年 4 月~2013 年 3 月) 齊藤慎司(2008 年 6 月~2010 年 3 月) 西村幸敏(2009 年 4 月~2011 年 9 月)
75

宮下幸長(2009 年 4 月~2013 年 3 月) 塩田大幸(2009 年 9 月~2010 年 3 月) 姚 堯(2009 年 1 月~5 月末)北村成寿(2012 年 4 月着任) 横山正樹(2010 年 4 月~4 月末) 中溝 葵(2010 年 4 月~2013 年 3 月) 長谷川実穂(2012 年 3 月~2013 年 3 月) 八木 学(2012 年 1 月~2012 年 5 月)
学 生 数
(人) 2013 年度 20 名(学部理 0、工 4/院前期理 10、工 3/院後期 3、工 0) 2012 年度 11 名(学部理 0、工 0/院前期理 9、工 0/院後期 2、工 0) 2011 年度 9 名(学部理 0、工 0/院前期理 6、工 0/院後期 3、工 0) 2010 年度 6 名(学部理 0、工 0/院前期理 4、工 0/院後期 2、工 0) 2009 年度 7 名(学部理 0、工 0/院前期理 3、工 0/院後期 4、工 0) 2008 年度 5 名(学部理 0、工 0/院前期理 1、工 0/院後期 4、工 0)
(4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行) Kusano, K.; Bamba, Y.; Yamamoto, T. T.; et al, Magnetic field structures triggering solar flares and coronal mass ejections, ASTROPHYSICAL JOURNAL, 760, 31, 2012, DOI: 10.1088/0004-637X/760/1/31 包括的な 3 次元電磁流体力学シミュレーションによって太陽フレアの発生原因となる磁場構造を特定し
た。さらに、その結果が実際のフレア発生と一致することをひので衛星データより実証し、磁場観測に
よってフレア予測が可能であること明らかにした。 Miyoshi, Y.; Kataoka, R., Solar cycle variations of outer radiation belt and its relationship to solar wind structure dependences, JOURNAL OF ATMOSPHERIC AND SOLAR-TERRESTRIAL PHYSICS, 73, 77-87, 2011, DOI: 10.1016/j.jastp.2010.09.031 放射線帯外帯が太陽活動期には地球側に太陽活動下降期には地球から遠ざかる方向に移動することを発
見した。その成果は宇宙天気研究の重要課題である放射線帯の長期変動予測に重要な指針を与えるもの
である。 Kikuchi, Takashi; Hashimoto, Kumiko K.; Nozaki, Kenro, Penetration of magnetospheric electric fields to the equator during a geomagnetic storm, JOURNAL OF GEOPHYSICAL RESEARCH-SPACE PHYSICS, 113, A06214, 2008, DOI: 10.1029/2007JA012628 磁気嵐時における赤道域の地上磁場変動が、惑星間空間磁場の変動に対応していることを明らかにした。
この結果から、電場が極域から赤道へ伝搬するモデルによって、地磁気変動が統一的に説明できること
を提唱した。
76

(5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年 (西暦)
当該部門の
教員が筆頭
著者である
もの
当該部門の特任
教員・研究員が
筆頭著者である
もの
当該部門の学
生が筆頭著者
であるもの
所外の研究者
が筆頭著者で
あるもの
所内(他部門)
の研究者が筆
頭著者である
もの 2013 1 0 0 19 3 2012 2 6 0 26 4 2011 2 5 2 28 3 2010 3 17 2 23 2 2009 2 3 2 21 3 2008 7 1 2 16 2 (6)論文以外の特筆すべき成果(5 行) 国立天文台と協力し「ひのでサイエンスセンター」を構築し(2011 年度)、ひのでデータの科学利用に貢
献している。また、JAXA 宇宙科学研究所と協力し宇宙科学連携拠点として ERG サイエンスセンターを
構築し、ERG 衛星科学利用のための研究環境の開発を本格的に開始した(2013 年度)。さらに、太陽風
モデルと放射線帯モデルを連結した宇宙天気自動予報システムを開発し、試運転を実施した。 (7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度)総額 209,200 千円(間接経費含む)
研究期間 種別 研究者名 (代表・ 分担)
研究題目
総額 (百
万円、間
接経費
を含む)
2007-2009 基盤研究(B) 草野完也 (代表)
連結階層シミュレーションで探る
マルチフィジックス・プラズマダ
イナミクス
3.7 2009 年度の額
2011-2015 基盤研究(B) 草野完也
(代表) 太陽フレア・トリガ機構の解明と
その発生予測 6.8 2013 年度まで
の額 2008-2011 基盤研究(B) 関華奈子
(代表) 実証型ジオスペースモデリングに
向けた内部磁気圏基本モデルの構
築による宇宙嵐の研究
18.1
2012-2016 基盤研究(B) 関華奈子
(代表) 新しい環電流モデルを用いたULF波動が放射線帯粒子加速に果たす
役割の実証的研究
12.0 2013 年度まで
の額
2008-2010 若手研究(B) 三好由純
(代表) 巨視的・微視的計算にもとづく内
部磁気圏ホイッスラー波動の励起
と粒子加速
5.1
2011-2014 基盤研究(B) 三好由純
(代表) 放射線帯マルチスケールシミュレ
ーションによる相対論的電子の輸
送加速過程の研究
21.7 2013 年度まで
の額
2013-2016 基盤研究 (B)(海外)
三好由純
(代表) 北米域での高時間分解能オーロラ
観測と電波観測を軸とした脈動オ
ーロラ変調機構の研究
5.7 2013 年度の額
2008-2011 基盤研究(C) 家田章正 地磁気逆計算法を用いたオーロラ 4.4
77

(代表) 電流系の解明 2012-2014 基盤研究(C) 家田章正
(代表) 衛星直接観測と地磁気逆計算法に
よるオーロラ電流系の解明 4.3 2013 年度まで
の額 2006-2008 特別研究員
奨励費 新堀淳樹
(代表) 磁気嵐に伴う磁気圏-電離圏内に
おけるプラズマ擾乱の発生と発達
過程の研究
1.1
2008-2010 特別研究員
奨励費 松本洋介
(代表) グローバル MHD モデルを用いた
乱流的磁気圏描像の再現 2.4
2009-2011 若手研究(B) 簑島 敬
(代表) 太陽フレアにおける電子加速・輸
送機構の研究 4.4 総合解析部門
には2009年度
までの額 2009-2011 若手研究(B) 齊藤慎司
(代表) ホイッスラー乱流の非線形発展お
よびプラズマ粒子へのエネルギー
変換過程
4.4 総合解析部門
には2009年度
までの額 2009-2011 特別研究員
奨励費 西村幸敏
(代表) 磁気嵐時の内部磁気圏-電離圏結
合系における対流電場の発達過程 7.2
2012-2014 若手研究(B) 今田晋亮
(代表) 電磁流体・電離非平衡計算コード
の開発 3.1 2013 年度まで
2010-2012 若手研究(B) 宮下幸長
(代表) 衛星多点観測に基づく地球磁気圏
のサブストーム開始に伴うエネル
ギー解放過程の解明
3.8
2012-2014 特別研究員
奨励費 北村成寿
(代表) 電離圏からのイオン流出過程と地
球起源イオンのリングカレントへ
の寄与に関する研究
3.6
2010-2011 特別研究員
奨励費 辻 裕司
(代表) 地上磁力計と衛星・レーダー観測
に基づく磁気嵐時の大規模電場の
形成過程に関する研究
1.4
2012-2013 特別研究員
奨励費 原 拓哉
(代表) 磁気異常帯に着目した太陽風変動
が火星大気流出に与える影響の研
究
1.8
2005-2009 学術創成研
究費 草野完也
(分担) 宇宙天気予報の基礎研究 29.0 2009 年異動後
の額 2010-2012 基盤研究(C) 菊池 崇
(分担) 磁気圏攪乱における中緯度電離圏
-内部磁気圏電磁結合の役割 0.8
2010-2012 基盤研究(B) 三好由純
(分担) サブストームトリガー・駆動機構
の完全解明に向けた先端研究 0.8
2010-2012 基盤研究(B) 宮下幸長
(分担) サブストームトリガー・駆動機構
の完全解明に向けた先端研究 0.8
2010-2012 基盤研究(B) 家田章正
(分担) サブストームトリガー・駆動機構
の完全解明に向けた先端研究 2.7
2011-2015 基盤研究(S) 三好由純
(分担) 波動粒子相互作用直接観測システ
ムの開発による相対論的電子加速
機構の研究
46.4 2013 年度まで
の額
2013-2015 基盤研究(B) 宮下幸長
(分担) 深内部磁気圏における高エネルギ
ーイオン生成・輸送機構とそのイ
オン種依存性の解明
0.8 2013 年度の額
2013-2014 挑戦的萌芽
研究 三好由純
(分担) 超広視野・超高精度オーロラ 3 次
元ステレオ計測 0.4 2013 年度の額
2013-2017 基盤研究(A) 草野完也
(分担) 大規模数値解析による乱流中の流
れ構造の動力学と異方性の解明 0.8 2013 年度の額
2013-2016 基盤研究(B) 草野完也
(分担) 過去 4 万年間の宇宙線強度変動・
太陽圏構造と地球環境変動 0.6 2013 年度の額
2007-2009 大川情報通 菊池 崇 伝送線理論を応用した宇宙天気予 2.0
78

信基金 報の研究 2007-2008 放送文化基
金 菊池 崇 放送衛星の放射線環境予測シミュ
レータの開発・研究 4.2
2008 交流協会 菊池 崇 台湾 ROCSAT/FORMOSAT 衛星
による宇宙天気研究 1.2
2011 受託事業等
直 接 経 費
二国間交流
事業 韓国
(NRF)
草野完也 日韓宇宙天気ワークショップ
2011: 宇宙天気モデリングと観測
研究の現状と展望
1.2
備考:間接経費は、直接経費(部門配分額)の 30%の額として算出。
79

ジオスペース研究センター(学術的成果)
以下では荻野・梅田に関連する項目を記す。平原・西谷、藤木・阿部、三好、及び、長濱・前澤に関連
する項目はそれぞれ 2 部門、3 部門、4 部門、及び 1 部門を参照のこと。 (1)部門の役割と目的 工学研究科電気工学専攻の協力講座(宇宙情報処理グループ)として、スーパーコンピュータを用いた
大規模シミュレーション及び、情報学的手法を用いて大量のシミュレーションデータを可視化・解析す
るにより、流体スケールから電子スケールまでの宇宙プラズマの諸現象及びスケール間結合・領域間結
合の理解を目指す。また、計算科学・情報科学関連分野のプロジェクトに参画する。 (2)過去 5 年間の研究活動の概要(前外部評価では評価対象外であった) ・世界的に高く評価されている 3 次元グローバル MHD コードを用いて、地球磁気圏のみならず、木星・
土星、さらには系外惑星の磁気圏構造について研究を行った。また、コードを地球電離圏や内部太陽
圏にも拡張した。 ・世界的にもユニークな衝撃波静止系粒子コードを開発し、従来の 10 分の 1 程度の計算領域での衝撃波
のシミュレーションを可能にした。これにより、全粒子シミュレーションにおいて衝撃波面のイオン
スケールの変動を含めた大規模計算が可能となり、波面におけるイオンスケールの波打ちが遷移層に
おける電子スケールの波動と結合して、無衝突衝撃波の発達が従来の 1 次元計算とは全く異なること
を明らかにした。 ・世界的にもほとんど実用の域に達していないブラソフシミュレーション技術について、既存の計算機
環境に適した新たな手法を構築し、磁気リコネクションやケルビンヘルムホルツ不安定性などのメソ
スケールの境界層不安定性現象のみならず、小天体などのグローバルスケールの問題に対しての適用
に世界に先駆けて成功した。 (3)組織 教授 荻野瀧樹(2013.3 退職) 准教授 講師 助教 梅田隆行 特任教員 研究員 学 生 数
(人) 2012 年度(学部工 04/院前期工 03/院後期工 00) 2011 年度(学部工 04/院前期工 05/院後期工 00) 2010 年度(学部工 02/院前期工 05/院後期工 00) 2009 年度(学部工 02/院前期工 05/院後期工 00)
80

2008 年度(学部工 04/院前期工 05/院後期工 00) ※三好、長濱、前澤の各教員が指導した人数を除く。 (4)特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行) Pogorelov, N. V., S. N. Borovikov, G. P. Zank, and T. Ogino, Three-dimensional features of the
outer heliosphere due to coupling between the interstellar and interplanetary magnetic fields.
III. The effects of solar rotation and activity cycle, The Astrophysical Journal, Vol.696, No.2,
1478-1490, 2009.
本論文は、太陽圏グローバル構造に関する長時間かつ大規模な 3次元 MHDシミュレーションの結果をま
とめたものであり、計算機利用共同研究の枠組みで行われた国際共同研究の成果である。(被引用数:
49)
Umeda, T., M. Yamao, and R. Yamazaki, Electron acceleration at a low-Mach-number perpendicular
collisionless shock, Astrophysical Journal, Vol.695, No.1, 574-579, 2009.
本論文では、衝撃波静止系粒子コードを用いた大規模シミュレーションを行い、遷移領域における電子
加速が衝撃波面のイオンスケールの波打ちによって強められることを示した。この論文の成果を含めた
業績により大林奨励賞を受賞した。
Umeda, T., A conservative and non-oscillatory scheme for Vlasov code simulations, Earth, Planets
and Space, Vol.60, No.7, pp.773-779, 2008.
宇宙プラズマ第一原理ブラソフコードの新手法として、正値性及び無振動性を保証したより高精度な保
存型解法を開発した。本論文は ESPの Highlight Papers に選出されており、またこの論文の成果を含め
た業績により大林奨励賞を受賞した。
(5)出版論文数(2013 年 6 月までの出版決定済を含む。) 年 (西暦)
当該部門の
教員が筆頭
著者である
もの
当該部門の特任
教員・研究員が
筆頭著者である
もの
当該部門の学
生が筆頭著者
であるもの
所外の研究者
が筆頭著者で
あるもの
所内(他部門)
の研究者が筆
頭著者である
もの
2013 1 1 2012 10 3 2011 4 1 6 1 2010 4 11 2009 2 1 6 2008 4 2
81

(6)論文以外の特筆すべき成果 ・情報基盤センター・スーパーコンピュータシステムの仕様策定と技術審査(2008) ・情報基盤センター・教育研究用高性能コンピュータシステムの仕様策定(2012) ・太陽地球環境情報処理システムの仕様策定(2010) ・学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN)の課題採択(2011~2013) ・HPCI「京」利用課題の採択(2012~2013) ・Best Presentations Award for International Conference of Frontiers in Computational Science 2008
Grant Prix, "Vlasov code simulation of GEM reconnection challenge" by K. Togano, T. Umeda, and T. Ogino(2008)
(7)外部資金獲得実績(2008 年度~2013 年度)
研究期間 種別 研究者名
(代表・分
担)
研究題目
当該年度
総額(百万
円、間接経
費を含む)
研究期間
総額(百万
円、間接経
費を含む)
2008-2010 科研基盤 A 荻野瀧樹
(分担)
地球惑星科学仮想データセンターの
構築と昨日の実証的研究
2.990 2.990
2005-2009 学術創成 荻野瀧樹
(分担)
宇宙天気予報の基礎研究 21.003 59.883
2008 国立情報学研
究所最先端学
術情報基礎の
構築推進委託
事業
荻野瀧樹
(代表)
ジオスペースバーチャル研究所/バ
ーチャルオーガニゼーション構築の
基礎研究
1.500 1.500
2009 国立情報学研
究所最先端学
術情報基礎の
構築推進委託
事業
荻野瀧樹
(代表)
ジオスペースバーチャル研究所/バ
ーチャルオーガニゼーション構築の
基礎研究
2.500 2.500
2010
国立情報学研
究所最先端学
術情報基礎の
構築推進委託
事業
荻野瀧樹
(代表)
ジオスペースバーチャル研究所/バ
ーチャルオーガニゼーション構築の
基礎研究
2.500 2.500
2007-2008 科研若手(スタ
ートアップ)*
梅田隆行
(代表)
革新的なブラソフシミュレーション
手法の研究
1.755 3.510
2009-2010 科研若手(B) 梅田隆行
(代表)
次世代スーパーコンピュータに向け
たブラソフシミュレーション手法の
研究
3.510 3.510
2009-2011 科研新学術(課
題提案型)
梅田隆行
(代表)
次世代第一原理粒子シミュレーショ
ンによる無衝突衝撃波の粒子加速機
構の解明
27.040 27.040
2011-2012 科研若手(B) 梅田隆行
(代表)
大規模ブラソフシミュレーションに
よる宇宙プラズマのスケール間結合
の研究
3.900 3.900
82

ジオスペース研究センター(運用・運営・貢献面)
(1)部門の役割と目的 国際共同研究・観測の企画と推進、及び、観測データの効果的利用を図るため、所内研究部門や国内外
研究機関・所外共同研究者と連携・協力し、領域横断的な共同研究プロジェクトの立案・遂行に中心的
役割を担う。そのため、サイエンスセンターを新機軸として、観測、データ解析、理論・シミュレーシ
ョンを統合したプロジェクト研究を、データベース作成、計算機利用に代表される各種共同利用・共同
研究の側面から支援・遂行する。また、日本各地の観測所の統括、HPC への参画、大学間連携の中心的
役割を果たす。 (2)過去 5 年間の活動の概要(前外部評価結果への回答を含む)(10 行)
本センター固有の研究支援・活動に関して、領域横断的な共同研究プロジェクト、観測所、データベ
ース作成共同研究、計算機利用共同研究、HPC 関連、大学間連携、WDC の報告資料を末尾に添付する。
特に領域横断的な共同研究プロジェクトにおいては 2010 年度の第二期の開始とともに地上ネットワー
ク大型共同研究の公募を開始し、本センターでは総合観測委員会等を通じてその立ち上げ・運用に重要
な役割を果たしている。その他の共同研究事業もジオスペース研究センター運営委員会等において所外
の意見を取り入れつつ推進した。 また最近では、探査機・地上観測網によるデータを統合的に集約・解析し、コミュニティーに一元的
に提供するためのサイエンスセンター群を構築・整備する中心的役割を果たしている。 (3)組織 教授 荻野瀧樹(2013.3 退職)、平原聖文(2013.4 センター長着任:兼任) 准教授 阿部文雄、西谷望、三好由純(2012.1 赴任) 講師 助教 梅田隆行、藤木謙一 特任教員 堀智昭(2009.4 赴任) 研究員 齊藤慎司(2010.4 赴任、2011.3 退職)、寺本万里子(2011.4 赴任-2013.3 退職) (4)運用面において特筆すべき論文(3 編)とその特筆すべき理由(各 3 行)
Hayashi, H., Y. Koyama, T. Hori, Y. Tanaka, S. Abe, A. Shinbori, M. Kagitani, T. Kouno, D. Yoshida, S. UeNo, N. Kaneda, M. Yoneda, N. Umemura, H. Tadokoro, T. Motoba & IUGONET project team (2013) Inter-university Upper Atmosphere Global Observation Network (IUGONET), Data Sci. J., 12, WDS179-184.
大学間連携 IUGONET プロジェクトの目的と、計画通り 2012 年度末にメタデータデータベースと解析
ソフトウェアを公開したこと等が開発員らにより記載されている。ICSU/WDSの査読付き論文誌であり、
83

IUGONET についての初期リファレンスとなった。
堀智昭,鍵谷将人,田中良昌,林寛生,上野悟,吉田大紀,阿部修司,小山幸伸,河野貴久,金田直樹,
新堀淳樹,田所裕康,米田瑞生, "IUGONET 共通メタデータフォーマットの策定とメタデータ登録管
理システムの開発", 宇宙科学情報解析論文誌, JAXA-RR-11-007 (ISSN 1349-1113), 105-111, 2012.
IUGONET プロジェクトでのメタデータ記述に用いられるメタデータ・フォーマットを策定・公開し、
さらにメタデータ編集の管理とデータベースへの登録を行うメタデータ登録管理システムを開発した。
ここで報告されたフォーマット及びシステムは現在も用いられている。
堀智昭 , 梅村宜生 , 阿部修司 , 小山幸伸 , 田中良昌 , 林寛生 , 上野悟 , 新堀淳樹 , 佐藤由佳 , 八木
学 , "IUGONET メタデータ登録・管理システムの処理性能評価", 宇宙科学情報解析論文誌 , JAXA-RR-12-006 (ISSN 1349-1113), 71-78, 2013.
IUGONET メタデータ・データベースへのメタデータ登録のために運用されているメタデータ登録・管
理システムの詳細な性能評価を行った。ここで報告された結果は登録・管理システムの改良や実際の運
用を最適化するためのチューニングに生かされた。 (5)運用面での特筆すべき成果(5 行) CAWSES-II 宇宙天気国際協同研究データベース (2009-2013) CAWSES-II Space Weather International Collaborative Research Database in Japan (2009-2013) Data Catalog・Reference Manual の作成・出版(2012) その他の参考資料
領域横断的な重点共同研究プロジェクト 1. 概要・意義・目的・状況
2004 年度のジオスペース研究センター設立における一つの重要な基軸として、複数部門にまたがる数
年程度の共同研究プロジェクトを立ち上げることが提案された。プロジェクトの意義は従来各分野・部
門で閉じる傾向にある太陽から地球大気までの研究領域を統一システムとして扱う、研究所本来の設立
目的を実施することにある。 第一期(2005-2009 年度)には「ジオスペースにおけるエネルギー輸送過程に関する調査研究」として、
ジオスペースの変動機構を解明するために太陽から地球大気までを統一システムとして扱い、その中で
のエネルギーや物質の輸送/変換プロセスを定量的に理解することを目的として、以下の 3 つの研究プ
ロジェクトが遂行された。 プロジェクト1: CMEの素過程の研究 プロジェクト2: 人工衛星-地上共同観測によるジオスペース研究の新展開 プロジェクト3: 太陽活動の地球環境への影響に関する研究 詳細については年報やホームページ等の資料を参照。 現在の第二期(2010-2015 年度)においては「太陽極大期における宇宙嵐と大気変動に関する調査研究」
84

として、宇宙天気予報に代表される安全・安心な宇宙利用の確保と、太陽活動に起因する地球環境変動
の解明を目指し、太陽活動極大期における宇宙嵐と大気変動に関する領域横断的な調査研究を実施して
おり、以下の 4 つの研究プロジェクトが遂行中である(各プロジェクト毎の詳細は別途記述)。 プロジェクト1: 特異な太陽活動周期における太陽圏 3 次元構造の変遷と粒子加速の研究 プロジェクト2: グローバル地上・衛星観測に基づく宇宙プラズマ-電離大気-中性大気結合の研究 プロジェクト3: 太陽活動の地球環境への影響の研究 プロジェクト4: 第 2 期実証型ジオスペース環境モデリングシステム(GEMSIS-phase II):宇宙嵐に伴
う多圏間相互作用と粒子加速の解明に向けて 2. プロジェクト遂行におけるジオスペース研究センターの貢献
第二期研究プロジェクトの遂行における目玉として地上ネットワーク観測大型共同研究・同研究(重点
研究)があり、前者は年間 100 万円、後者は年間 500 万円が最大予算規模である。いずれについても毎年
公募により所外の研究者が代表となる研究を募集し、ジオスペース研究センター運営委員会の下部組織
である総合観測委員会が大型共同研究(重点を含む)提案のとりまとめ、審査、選択及び選択された提案の
推進を行っている。 大型共同研究(重点を含む)の運用においては研究所外意見の集約を総合観測委員会等で行っており、出
された意見について議論した上で翌年度以降の公募要項に反映させている。例としては、予算のバラン
スやコミュニティに対する共同研究のあり方も考慮し、大きな研究機関等に予算が偏らないように配慮
する等が審査条件として取り入れられている。 3. 成果 領域横断的な重点共同研究プロジェクトの第一期、第二期とも多数の共同利用・共同研究が実施され、
成果も多数得られている(科学的成果の詳細は各プロジェクトの記述を参照)。 たとえば、2010 年度大型共同研究(重点研究)「全地球的宇宙線観測ネットワークによる宇宙嵐前兆現
象の精密観測」では、宇宙線強度の汎世界的観測ネットワーク(GMDN: Global Muon Detector Network)の装置の増強を進めるとともに、これを用いた宇宙天気研究を展開し、大規模な太陽磁場構造の変動の
実態と、その中での宇宙線輸送過程に関 する解明を進めた。 特に論文 Fushishita et al. (APJ, 2010)では GMDN を用いて、2006 年 12 月 14 日の磁気嵐に伴う Forbush 減少の予兆現象を捕らえることに成功
したことを報告している。 さらには領域横断的研究プロジェクトの装置として導入した短波ドップラーレーダー装置の研究成果
がある。同装置を使用した過遮蔽電場の観測・計算機実験による研究の成果(Ebihara et al., 2008 等)が2008 年外部評価の第二部門・第四部門の主な成果で報告され、高い評価を受けた。これは1つの部門に
特化していたら実現しなかったことである。また 2008 年以降も領域横断的研究の新たな成果(赤道環電
流とサブオーロラ帯電場の関連: Ebihara et al., 2009 等)が出ている。 4. 大型予算申請・採択について 領域横断的な重点共同研究プロジェクトの第一期(2005-2009 年度)には特別教育研究経費(1 年当たり
約 2 億円)の配分を受け、研究プロジェクトの遂行に不可欠な研究設備の導入を進めた。第二期(2010-2015年度)には特別経費として配分された金額(1 年当たり約 7000 万円)を活用し上記研究設備等を活用した共
同利用・共同研究を実施している。2012 年度には補正予算において宇宙環境電波計測システム(IPS+HF
85

レーダー、約 2 億円)の設置費用の配分を受けた。 5. 自己評価・今後の計画 プロジェクト全体の規模としては限られた予算・人員の中で、所外の意見を取り入れつつプロジェク
トを進める体制を整備しており、領域横断的な研究プロジェクトの遂行に大いに貢献している。また次
の段階を見越した予算獲得にも成功している。今後の課題としては、第三期以降(2015 年-)における体制
の整備をどうするかが挙げられる。これについては全所的議論が不可欠であり、第三期特別経費概算要
求と関連させるか、どういう新機軸を打ち出していくかについて時間をかけて議論していくことが必要
である。 各プロジェクトからの報告 別資料参照 大学間連携プロジェクト(IUGONET)
1. 概要・意義・目的・状況 2009 年度より 6 ヶ年計画で特別教育研究経費プロジェクト「超高層大気長期変動の全球地上ネットワー
ク観測・研究 (英語名: Inter-university Upper Atmosphere Global Observation NETwork, IUGONET)」
が発足した。このプロジェクトでは国立極地研究所、東北大学、名古屋大学(太陽地球環境研究所)、京
都大学(理学研究科及び生存圏研究所)、および九州大学(国際宇宙天気科学・教育センター)の 5 機関
が連携し、各研究機関がこれまで全地球上に展開してきた超高層大気観測網をさらに発展させるととも
に、連携機関および関連研究機関で観測データのメタ情報(観測所、観測機器、観測期間等)を共有できる
ようメタデータをデータベース化している。また統合データ解析ツールの開発・普及を行い、データの
流通・利用を促進している。これらにより超高層大気の長期変動過程の研究を推進するために不可欠な、
緊密な共同研究体制(超高層大気科学バーチャル情報拠点)を構築することを目指している。
2012 年度には、IUGONET に対し、欧米の超高層大気に関するデータベース作成グループとの連携・
共同研究の話が持ち上がり、今後の正式な国際共同体制を構築するため、IUGONET 実施機関内の協定書
を作成、6 組織の長により調印した(京大は上記 2 組織)。これにより、IUGONET 運営協議会が 2013 年
2 月 28 日に正式に発足し、議長に京都大学家森俊彦教授が選出された。このことにより翌年度(2013 年
6 月 18 日)、IUGONET とヨーロッパと類似する目的を有する ESPAS プロジェクトとの間で、共同研究の
協定書(MOU)が締結された。
ジオスペース研究センターでは、プロジェクト発足当初から専任の特任教員1名および技術補佐員1
名の計 2 名が本プロジェクトの開発チーム(バーチャル情報拠点構築)に参加している。開発チームに
おいて同特任教員は、NASA、 UCLA 等の研究者で構成される SPASE コンソーシアムと協同し、メタデ
ータを IUGONET 参画機関内で共通的に管理し国際展開をするためのデータフォーマットを、担当リー
ダーとして策定した。現在国際展開や他のデータベースとの相互検索を視野にいれた開発・運用を担当
している。同技術補佐員は、メタデータデータベースの初版を構築したほか、システム開発の専門家と
して IUGONET 全体のシステムの日常運用、改良等を担当している。
開発されたメタデータデータベースと統合データ解析ツールは、2011 年度末にインターネット上で公
86

開し、引き続き名古屋大学・九州大学がメタデータデータベースの運用の中心的な役割を担っている。
IUGONET による研究基盤は国内外の超高層大気研究に利用されており、プロジェクト実施機関の学生や
プロジェクト主催の講習会に参加した学生の学位論文研究に用いられるなど、研究と教育の両面で太陽
地球系科学コミュニティに貢献している。
ジオスペース研究センターでは、上記開発員らが名古屋大学太陽地球環境研究所の所持する地上観測
データの登録と、実データを統一的に解析描画するためのツール開発を行っており、宇宙線、電離圏、
磁気圏、対流圏エアロゾルデータなど多種多様なフォーマットの実データの解析効率の向上に貢献して
いる。このことで、太陽地球環境分野の分野横断的研究の促進に貢献している。また、IUGONET 予算に
より、当該研究所が展開する国内外の観測網のさらなる拡充が行われ、さらにアナログデータの電子化
など古いデータの救出も進みつつあり、太陽地球系科学の長期データの保存と公開に寄与するとともに、
超高層大気システムの長期変動の研究に貢献している。
2. 自己評価
・本プロジェクト特任教員を始めとするジオスペース研究センターのメンバーが所内でのプロジェク
ト推進を主導し,さらに IUGONET 全体においても中心的役割を担ってきた。これが可能となったのは、
各領域の研究とデータ及び最新の ICT 技術に精通した当該センターメンバーの相乗効果によるところが
大きい。
・年 2 回の事業報告会・研究会へ旅費を拠出し、そのうち 1 回を名大 STE 研が主催している。さらに
データベース・統合解析ツールの講習会にも積極的にコミットすることで、太陽地球環境分野でのデー
タ流通・利用を促進させ、またデータ処理・アーカイブの知識を持ついわゆるデータ専門家の育成やコ
ミュニティ形成に寄与することができた。
・開発員が所内の PI にコンタクトし,データ登録,処理を行うことは,STE 研内外の分野横断的研究
促進に貢献するものであるが,他の IUGONET 実施機関に比して,名大 STE 研は,扱うデータの種類,
対象,フォーマット等が多岐にわたり,学位を持つ研究者・技術者のみで限られた期間に対応するには
限度があった。
3. 将来性・発展性
・STE は古くから宇宙線の WDC (現 WDS メンバー)であり、IUGONET は、この WDC の他オーロ
ラ WDC(極地研)、地磁気 WDC(京大地磁気世界資料解析センター)を含んでいる。プロジェクト実施
期間中に日本の NICT が ICSU World Data System (WDS)の国際プログラムオフィスを引き受けることと
なったが、IUGONET は、WDS からも期待され、相互の研究集会等に人的交流を行っている。今後の日
本におけるデータ活動の一端を確実に担うものとしてその継続のため、この WDS-IPO や SCOSTEP(太
陽地球系科学委員会)、地球電磁気・地球惑星圏学会(SGEPSS)、国際地球電磁気・超高層大気物理学協
会(IAGA)等からサポートレターを頂戴している。
・IUGONET が開発したメタデータシステムは、福島の放射線データベースや震災時の気象データベー
スにも応用されようとしているなど、最終年度の計画(超高層大気以外の地球環境情報への拡大)も前
倒しで実施しており、今後の展開が期待される。
・IUGONET システムやメタデータフォーマットは、当初から国際的展開を想定している。その結果、
ヨーロッパの太陽地球系物理(STP)コミュニティのデータベース構築プロジェクトとの連携の話があり、
87

2013 年度研究協定(MOU)締結に結び付いた。引き続き、ヨーロッパ・アメリカの同コミュニティと連
携を促進し、国際会議のセッション共同開催も行っている。
・IUGONET がカバーするデータは全球に及ぶが、アジア・アフリカ地域は欧米のネットワークに比し
て日本の観測網が必須である。IUGONET は極域等も担当しているが、国際協力の点では、アジア・アフ
リカの観測展開の主導的立場であり、同地域への IUGONET キャパシティービルディング活動等を通じ
て、開発途上国にも IUGONET は普及しつつある。
4. 今後の課題
・IUGONET で開発・公開されたプロダクトは研究インフラとして多くの研究者・学生に利用されてい
る。プロジェクト第 1 期が終了する 2014 年度以降についてもこれらを持続的に発展させていくことは必
須であり、そのための予算獲得を目指しているが、一般経費化は不可となり、現時点では予算確保には
至っていない。上述のように、国際展開や分野横断的活用、他分野への転用がすすんでおり、予算的・
人的枠組の構築が今後の課題である。
・IUGONET に登録されたメタデータには、観測データ(実データ)の公開がされているものと、主研
究者(Principal Investigator、 PI)の判断により公開されていないものがある。IUGONET メタデータには、
コンタクトパーソンの情報が含まれるため、IUGONET メタデータデータベースユーザーは PI にコンタ
クトをすることが可能であるが、実データの利用が許可されるとは限らない。観測者、データ活動に携
わる者のプライオリティの確保や、彼らがリワードされる仕組みの構築も必要であるが、実データの公
開がなされることが本質的に重要であり,今後の大きな課題の1つとなっている。
観測所報告 別資料参照
データベース作成共同研究 STE および関連分野のデータベース構築を目的として、共同観測情報センター発足の平成8年度から、
センター運営費を使って毎年継続的に実施している。課題は、重点(20万円から100万円程度まで)
と一般(20万円以下)に分けて募集し、運営委員会で審査を行い採択・実施される。平成24年度か
らは、所内・所外に分けて公募している。センター運営費の予算減に伴い、本共同研究の予算も減少傾
向にあるが、平成20年度以降はほぼ390万円程度を確保している。 これまでに210度地磁気データベース、宇宙線 WDC、OMTI、MAGDAS、EISCAT、太陽黒点デー
タベース、HF レーダー、VLF のほか、最近では ERG・HINODE サイエンスセンターのデータベース
構築などにも利用されている。 これまでのところ将来の研究成果に向けたデータベース構築を中心に行っているが、すでに広く利用
され多くの研究成果をあげているものもある。平成22年には、第2回の成果報告書を作成した。しか
しながら、最近は所外からの応募が減少し、また予算が減少傾向にあるので、広報と予算の確保が課題
として挙げられる。
88

データベース作成共同研究採択数(上段)及び金額(下段:単位円)
H20 年度 (2008)
H21 年度 (2009)
H22 年度 (2010)
H23 年度 (2011)
H24 年度 (2012)
H25 年度 (2015)
採択数 12 11 12 11 11 11 金 額 3,913,000 3,931,000 3,925,000 3,925,840 3,925,000 3,925,000
計算機利用共同研究
平成8年の共同観測情報センター発足以来、継続して実施している。平成22年度までは、研究所と
しては共同利用・共同研究用の計算機ハードウェアを持たずに、名古屋大学情報基盤センターに利用負
担金を支払う形でスーパーコンピュータシステムを利用し、年間30件以上の共同研究が実施されてき
た。情報基盤センターのシステムを用いることにより、太陽地球惑星系科学関連分野の他の計算機共同
利用型プロジェクトに比べてより多くの計算リソースを使用することができ、国内の太陽地球惑星系科
学シミュレーション・モデリング研究を推進するとともに、数多くの若手シミュレーション・モデリン
グ研究者の育成に大きく貢献している。一方で、平成21年度に情報基盤センターのスーパーコンピュ
ータシステムが更新されて利用負担金の体系が変更されたこともあり、平成22年度までは予算不足に
よる準定常的に計算資源の枯渇が発生していた。この対策として、平成23年度以降は、新たに導入し
た「太陽地球環境情報処理システム」(太陽地球環境研究所のスーパーコンピュータ)に一部のユーザー
を移行した。また、文部科学省や計算科学分野が主導する他の共同利用・共同研究(後述)が開始され
たこともあり、平成23年度以降は申請件数が約20件/年程度となっている。これらにより、結果的
に計算機利用共同研究の準安定的な運用が維持できている。今後も計算機利用共同研究が維持できるか
は、情報基盤センター利用負担金の体系に大きく依存している。現在、継続的に情報基盤センターと交
渉を行っており、現在の予算での準安定的な運用が困難な場合は、現在と同様に次期太陽地球環境情報
処理システムを補助的に使用せざるを得ない。 計算機利用共同研究採択数(上段)及び金額(下段:単位円)
H20 年度 (2008)
H21 年度 (2009)
H22 年度 (2010)
H23 年度 (2011)
H24 年度 (2012)
H25 年度 (2015)
採択数 34 32 31 23 24 22 金 額 6,132,000 5,061,000 4,525,500 4,662,000 4,483,500 4,441,500 ※平成20年度及び21年度は、外部資金(科研費)により補てん
名古屋大学 HPC 計算科学連携研究プロジェクト 情報基盤センター・地球水循環研究センターと共に平成22年度より「名古屋大学 HPC 計算科学連携
プロジェクト」を発足し、公募により厳選された共同研究を年間10件程度推進している。採択課題の
6割以上に当研究所教員が共同研究者として参加している。本プロジェクトの狙いは、名古屋大学で数
少ない共同利用・共同研究拠点である情報基盤センターの共同研究の実績作りと名古屋大学として今後
もスーパーコンピュータを継続的に維持していくことにあり、名古屋大学の戦略としては非常に重要で
89

ある。3部局間の取り決めにより、今中期間は本プロジェクトを継続することが決定しているが、次期
中期については今後話し合いが必要である。 名古屋大学 HPC 計算科学連携研究プロジェクト採択数(上段)及び金額(下段:単位円)
H22 年度 (2010)
H23 年度 (2011)
H24 年度 (2012)
H25 年度 (2015)
採択数 10 11 11 12 金 額 3,000,000 4,000,000 4,000,000 4,000,000
学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点(JHPCN) 北海道大学、東北大学、東京大学、東京工業大学、名古屋大学、京都大学、大阪大学、九州大学にそ
れぞれ附置するスーパーコンピュータを持つ8つの施設を構成拠点とした、ネットワーク型共同利用・
共同研究拠点であり、平成22年度より公募によって厳選された共同研究を年間40件程度推進してい
る。平成24年度までは、当研究所の課題「次世代ジオスペースシミュレーション拠点の構築」(代表:
荻野瀧樹)が採択され、スーパーコンピュータの利用負担金の一部(3割程度)を負担して共同研究を行っ
てきた。平成25年度からは後述する HPCI システムを利用した共同研究(HPCI-JHPCN)として当研究
所の課題「第一原理プラズマ運動論シミュレーションによるスケール間結合の研究」(代表:梅田隆行)
が採択され、利用負担金が免除されるようになった。 学際大規模情報基盤共同利用・共同研究拠点計算機利用負担金額(下段:単位円)
H21 年度 (2009)
H22 年度 (2010)
H23 年度 (2011)
H24 年度 (2012)
H25 年度 (2015)
金 額 0 735,000 851,000 654,666 0 ※平成21年度は試行のため、25年度は HPCI-JHPCN に移行のために負担金無し
革新的ハイパフォーマンスインフラ(HPCI)、及び、「京」を中核とする HPCI システム利用研究 計算機共同利用や太陽地球系科学のシミュレーション研究の成果が評価され、平成24年度に発足し
た一般社団法人 HPCI コンソーシアムのユーザーコミュニティ代表会員(全国で 15 機関)に選ばれてい
る。HPCI コンソーシアムは文科省主導で作られ日本のスパコンに関して将来計画を作成する組織であり、
関連するコミュニティーの研究者の意見を反映することができる。会費として、年間20万円を支払っ
ているが、当研究所のような小さな大学附置研がユーザーコミュニティ代表会員に選ばれるのは名誉な
ことである。 また、理研計算科学研究機構「京」、JHPCN と筑波大学のスーパーコンピュータ及び、海洋研「地
球シミュレータ」で構成される HPCI システムを利用した研究課題の公募が平成24年度に行われ、当
研究所の HPCI システム利用研究課題としては、「次世代宇宙天気予測シミュレーション」(代表:草野
完也、条件付「京」一般利用)及び「弱磁化天体のグローバルブラソフシミュレーション」(代表:梅田
隆行、「京」若手人材育成利用)が採択されている。 90

WDC-CR
宇宙線世界資料センター(WDC for Cosmic Rays)は、国際地球観測年(IGY)を期に国際科学連盟
(ICSU)が設立した WDC システムの一環として、1957 年に理化学研究所に設置されたが、1991 年に
当研究所に移籍された。この WDC は、1953 年から現座までに世界各国の総計 135 ヶ所で得られた宇宙
線中性子入射量データ(1 時間値)を収集し、品質管理を行ったデータを研究者に提供することを目的と
しており、この分野の WDC としては、世界で唯一の存在である。宇宙線データの主な利用者は太陽地
球系科学や宇宙工学の研究者であるが、宇宙線が環境放射線源の主要な要素であることから、原子力工
学や放射線医学の研究における基礎データとしても利用されている。宇宙線入射量は太陽活動の長・短
期変動に従って増減することが知られているが(太陽活動が低下すると増加)、宇宙線が雲の形成を通じ
て地球環境変動に関わっている可能性があることから、大気環境科学の研究者によるデータ利用も増え
ている。この WDC では半世紀以上に及ぶ宇宙線データを保有しているが、このようなデータの長期保
全・提供の継続性を確保する態勢の構築が、現時点における最大の課題となっている。また ICSU の WDCシステムは、現在 World Data System (WDS) に移行しており、今後も「国際的な認証を受けたデータ
センター」としての評価を維持するとともに、データ利用者の拡大を図るため、WDS 加入に向けた準備
を始めている。また、当 WDC のデータが使用されている研究論文等において、データソースが無記述
であることが多い現状を改善するため、データベースへの DOI 付与を進める。 参考資料 データ公開ホームページ(http://center.stelab.nagoya-u.ac.jp/WDCCR/):年間アクセス数は約 1000 件 データ CD-R:概ね年 1 回発行、国内外の約 200 ヶ所に配布 論文、解説 T. Watanabe, WDC Activities in Japan 2008, Data Sci. J, Vol. 8, S102-S107, 2009 T. Watanabe, M. Hirahara. F. Abe, R. Kadowaki, Cosmic-Ray Neutron Data held by WDC for Cosmic Rays, in Proc. International Forum on Polar Data Activities in Global Data Systems, Tokyo, pp 91-93, 2013. 渡邉 堯、「ICSU 世界データシステム(WDS)について」、学術の動向、2012 年 6 月 学会関連活動:日本学術会議情報学委員会 WDS 小委員会委員長(2012-) ICSU-WDS 科学委員会委員(2009-2011)
91

資料3:観測所
母子里観測所
1.概要
北緯 44 度の北海道中央部に位置する母子里観測所は、冬季には最低気温が -30 度以下になる寒冷地
であり、また、豪雪地域でもある。1962 年に空電研究所の附属観測所として設置された。1979年に観測
所庁舎が更新され現在に至っている。母子里観測所では、大気圏環境と電磁気圏環境に関する観測研究
を行っている。
2.主要な観測活動と成果
母子里観測所は人口密集地域から離れているので、地域的な大気汚染の影響を受けることが比較的少
なく、大気のバックグランド観測に適している。また、平地部分が多いため山間地ではないので、広い
地表範囲での平均的な対流圏成分を計測する人工衛星の検証データを得るのに適している。地上からの
分光計測や気球による計測により成層圏及びならびに対流圏の微量化学成分の観測を行っている。1996
年以来、高い波数分解能を持つ大型のフーリエ変換型赤外分光器 (FTIR) を母子里観測所に設置しオゾ
ンの全量の他、オゾンの化学に直接関係した重要な成層圏化学成分を計測してきた。2009 年より地球温
暖化の主原因である二酸化炭素 (CO2) およびメタン (CH4) の連続観測に切り替えた。この測定データ
は、温室効果気体の世界的な分布の計測を行うために地球規模の CO2 地上ネットワーク観測網 (TCCON)
とも共同し、また温室効果ガス観測技術衛星「いぶき」(GOSAT) の検証に必要なデータとしても利用さ
れている。
磁気緯度が北緯 36度(L=1.5)の母子里観測所は磁気緯度が北緯 36度に位置し、中緯度の電磁気圏環境
を観測するための観測点として、地磁気や電波・オーロラ観測を通して全国の研究者によると共同利用・
共同研究がなされている。広大な観測用地を持つため、人工の電磁気雑音や光の干渉が少なく、電磁気
圏環境の観測に適している。特に誘導磁力計や ELF/VLF 波動の観測は、近年注目されている波動粒子相
互作用による内部磁気圏での放射線帯粒子の加速・消失機構の解明においても重要な意味をもっている。
母子里観測所における磁場観測は 1989 年から継続し、210 度磁気子午面に沿った磁場多点観測網の主要
観測点として、データをウェッブページで公開している。内部磁気圏の電磁環境を探査する目的で、観
測所近くの高さ 43 mの三角直交アンテナによる ELF/VLF電磁放射の観測を定常的に実施している。2011
年度には、これまでの母子里観測所・鹿児島観測所でのトウィーク空電の総合的な解析により、千葉大
学の研究者が名古屋大学大学院理学研究科の博士号 (論文博士) を取得した。これまで低緯度オーロラ
の観測に使用してきた庁舎裏側の鉄塔の上の小屋は、老朽化のため 2011 年度夏期に撤収した。それ以後
は、本庁舎の壁面に設置された 3 波長分光フォトメータのみにより、低緯度オーロラの定常観測を行っ
ている。また、駒澤大学と共同で、地球温暖化の指標の一つになる超高層大気の夜光雲の観測を、自動
カラーカメラを使って 2010年度より行っている。
3.関連業績(論文・報告書・紀要、等)数
別表参照
92

4.社会的活動等
特になし
陸別観測所
1.概要
陸別観測所は、1997 年 10月に北海道陸別町の「りくべつ宇宙地球科学館」の 2階の一部を国立環境研
究所と共同で借り受け、成層圏の大気微量成分観測とオーロラ・地磁気活動の観測を開始したのが始ま
りである。開設当初は観測所ではなく、格下の観測室としてスタートした。本研究所と国立環境研究所
の他に情報通信研究機構や東北工業大学、横浜国立大学、東北大学、北海道大学などが加わり、省庁や
大学の枠を超えてこれまでに 10 台を越える測定装置が広さ約 1200 平米の部屋に設置され、共同研究を
展開してきた。2003 年 4 月からは学内措置により陸別観測所に格上げされ、2006 年 12 月にはりくべつ
宇宙地球科学館から約 15 km北西のポントマム地区に新たに大型短波レーダー (北海道-陸別短波レーダ
ー)を設置し、中緯度帯における電離圏の観測を開始した。現在、大気微量成分については赤外線フーリ
エ分光器(FTIR), 可視分光計、ミリ波分光放射計、紫外線放射計・ブリューワ分光計(ともに国立環境
研究所が運用)、オーロラ・地磁気活動の観測では、高感度全天カメラ、掃天フォトメータ、分光温度フ
ォトメータ、フラックスゲート磁力計が稼働している。
2.主要な活動(観測成果、改善点、問題点、対応策等)
国立環境研究所と共同で進めてきた大気微量成分観測では、母子里観測所とともに世界的な観測ネッ
トワークである NDACC の拠点にもなっており、赤外線分光および可視分光の観測データが同ネットワー
クのデータベースに提供されている。また、オーロラ・地磁気活動観測では、23期太陽極大期に低緯
度オーロラが観測されユニークな成果を出す一方、フラックスゲート磁力計による地磁気観測データの
データベース化や大気光分光温度フォトメータによる中間圏温度の季節変動の観測を定常的に進めてい
る。また、北海道-陸別短波レーダーは世界で2番目の中緯度 SuperDARNレーダーとして、多くの共同利
用者にデータが活用され、伝搬性電離圏擾乱、特に 2011 年の東北太平洋沖地震に伴い発生した超高速の
伝搬性電離圏擾乱の検出をはじめとする成果が挙がっている。
問題点は大気微量成分観測における測定機器の老朽化にともなう故障が目立ってきたことがあげら
れる。一部のハードウェアが計算機と直結しており、現在でも MS-DOSや OS2などの旧態依然とした計算
機で制御がなされており、ネットワークを通した遠隔制御や遠隔モニターになじまないシステムのまま
である。また FTIRの太陽追尾装置も人力で開閉をしなければならないなど現地作業員の作業項目が多く、
15km離れたレーダー施設の保守管理を含め作業量過多となっている。
制御システムの更新を行い、遠隔制御、自動化を推進することが人件費も含めた運用経費削減のため
に必要不可欠である。FTIR に関しては国立環境研究所が新たに導入した温室効果ガス測定用の新型 FTIR
への乗り換え、また、国立環境研究所から運用が移管されたミリ波分光計に関しては分光計のデジタル
化と制御システムの Linux化を現在進めているところである。
また、24年度補正予算により2台めの短波レーダーの設置が認められ、現在設置の準備を進めている。
観測領域の拡大とともに新たな成果が期待される一方、法人化後の設置となるため1台めの短波レーダ
93

ーとともに維持費が措置されていない。安定した運用を継続するための維持運用経費をどのように捻出
していくかが課題である。
3.関連業績(論文・報告書・紀要、等)数
別表参照
4.社会的活動等
陸別町および陸別町立りくべつ宇宙地球科学館(通称 銀河の森天文台)と連携し、活発なパブリック
アウトリーチ活動を続けている。陸別町の小中学校での出前授業の開催、りくべつ宇宙地球科学館にお
ける展示資料の提供、オーロラウィークイベント、南極授業、SSHの出前講義等、陸別町とともに社会連
携連絡協議会を毎年開催し、地域社会の科学振興・啓蒙教育活動に貢献している。
富士観測所
1.概要
惑星間空間シンチレーション(IPS)による太陽風観測を実施するため富士観測所(1978 年~)、菅平
観測施設(1979 年~)、木曽観測施設(1993 年~)および豊川分室(2006 年~)の4地点に国内最大級
の UHF帯アンテナ(電波望遠鏡)が設置されている。これらの観測所の場所は、IPS観測に適した基線配
置と良好な電波環境から決定された。富士観測所および木曽観測施設は宿泊設備を有し、国内の研究者
との共同研究に利用されている。観測は、すべて自動化され LANを通じて遠隔操作可能になっている。
2.主要な活動(観測成果、改善点、問題点、対応策、等)
長期にわたって取得されている IPS 観測データから、特異なダイナモ活動に伴う太陽圏の応答、太陽
風加速機構、CME の伝搬機構に関する研究成果が得られている(基盤設備の項参照)。また、富士・木曽
アンテナを用いた木星電波の観測からは太陽風変動と木星磁気圏の相互作用について解析が行われた
(東北大との共同研究による)。さらに、富士観測所においては富士山頂における放射線環境のモニター
(放医研)や VLF 電波観測(Stanford 大学)が実施されている。観測所の IPS 観測システムは、特別研
究経費(2006 年度)や補正予算(2012 年度)により更新された(基板設備の項参照)。これに伴うデー
タ量の増加に対応するため、菅平を除く各観測点では光ファイバーによる高速回線の導入を行った。ま
た、富士・木曽について宿泊設備の更新を進めている。今後の課題としては、①観測所の点検を依頼し
ている人の確保、②光熱水料やガソリン代の高騰、高速通信回線の導入に対応した財源の確保、などが
挙げられる。
3.関連業績(論文・報告書・紀要、等)数
別表参照
4.社会的活動等
94

毎年8月に木曽観測施設において一般公開を実施している。2010 年の一般公開では東京大学木曽観測
所にて一般向け講演を行った。また、IPS観測データを韓国宇宙天気センターの業務に利用するための研
究が開始されている。
鹿児島観測所
1.概要
鹿児島観測所は、1974 年に垂水市本城に設置された。観測所は本城川沿いの観測所と 500m ほど南の台
地に上がった上の台地観測点に分かれ、総面積は 13,203 ㎡である。フラックスゲート磁力計、誘導磁力
計、VLF 帯波動観測用ループアンテナ、LF 帯標準電波観測用ループアンテナを設置して、地球周辺の電
磁環境を計測している。観測所には 2 名の非常勤職員が週3日、午前中のみ勤務しており、観測は全て
自動化されている。また、垂水から約 70km 南に位置する大隅半島の最南端の佐多にも 2003 年にコンテ
ナハウスを設置して、大気光撮像、中間圏温度と地磁気脈動の無人自動観測を行っている。
2.主要な活動(観測成果、改善点、問題点、対応策、等)
鹿児島観測所では、1976 年から現在までの長期間にわたって VLF 波動の観測を行っており、この貴重
な観測データを使って千葉大学と共同で、35 年の長期にわたる電離層 D 層高度の長期変化を明らかにす
るなどの成果が上がっている。地磁気観測は、九州大学と共同で、210度地磁気観測ネットワークの基幹
観測点のひとつとして、広くデータが利用されている。また佐多における大気光観測は、オーストラリ
ア・ダーウィンとの地磁気共役点観測として重要な観測を継続している。また、スタンフォード大学、
電気通信大学の ULF/VLF 波動観測機器が設置され、共同研究が進められている。また、内之浦から打ち
上げられるロケット観測とも必要に応じて連携観測がはかられている。
観測所の現在の問題点としては、雷の被害が多く、毎年のように雷害で機器が停止し、数年に 1 回は
大きな被害がある。また、上の台地観測点や観測所周辺の草刈りと桜島の火山灰除去に毎年大きな予算
が必要になっている。さらに、常駐していた技術職員が 2006 年に亡くなられてからは、2 名×週 9 時間
(月・水・金の午前中)の勤務態勢で、VLF長期観測データのアナログテープのディジタル化と観測所の
維持を行っているが、前者はセンターのデータベース経費に毎年申請して採択された予算で行っており、
非常勤職員の雇用が将来にわたって維持できるかどうかが不安定である。
3.関連業績(論文・報告書・紀要、等)数
2008-2012年の 5年間の査読付き論文数 8編、博士論文 2編、詳細は別表
4.社会的活動等
2012 年度からは、地元の垂水市が開催する小中学生向けの「科学の祭典」イベントに科学実験を行う
ブースを展示して、地元との連携を図っている。
95

観測所関連業績(論文・報告書・紀要、等)数
96

97

資料4:基盤設備
基盤設備名:IPS太陽風観測装置
概要:国内4地点(豊川、富士、菅平)に設置した高感度アンテナを用いて天体電波の惑星間空間シン
チレーション(IPS)現象を測定し、地上から太陽風のリモートセンシングする装置である。多地点 IPS
法による太陽風観測は世界で他に類を見ないユニークなもので、飛翔体による測定が困難な領域を含む
広い範囲の太陽風のダイナミックな3次元特性を高い精度で調べることができる。第1期の特別経費に
て豊川に高感度 IPS アンテナ「太陽圏イメージング装置(SWIFT, Tokumaru et al., 2011)」を開発し、
2008年夏より観測を開始した。また、平成 24年度補正予算及び科研費基盤 Aにより富士・木曽アンテナ
の改良を行っている。運用のための経費は、科研費基盤 B や 3-1 部門予算、富士観測所経費、所長リー
ダシップ経費からの支援から支出し、機器の破損についてはその都度、研究所の維持費予算から支援を
受けている。人員は 3-1部門の教員 2名の他、技術職員 2名が随時技術支援を行っている。
成果:太陽活動が著しく低下したサイクル 24 において、IPS 観測から低緯度における高速風の発達
(Tokumaru et al., 2009)や太陽風密度の全球的な低下(Janardhan et al., 2011; Tokumaru et al.,
2012)を発見した。また、長期にわたる IPS データの解析から、太陽風の構造と極磁場強度との密接な
関係やサイクル 24の特異性を明らかにしている(Tokumaru et al., 2010)。この他、宇宙天気予報にと
って重要な CMEの伝搬特性についても IPS データの解析からそのメカニズムが明らかにされている(Iju
et al., 2013、博士論文取得予定)。この他、本装置のデータは修士課程の研究に利用されている。本装
置の観測データは即時的に公開され、最近 NASA/CCMC から利用できるようになった。韓国宇宙天気セン
ターにおける業務に利用するための研究も始まっている。
主な査読付き論文
1. Tokumaru, M., Three-dimensional exploration of the solar wind using observations of
interplanetary scintillation, Proceedings of the Japan Academy Ser. B, Vol.89(2), pp.67-79,
2013.
2. Iju, T., M. Tokumaru, and K. Fujiki, Radial speed evolution of interplanetary coronal mass
ejections during solar cycle 23, Solar Physics, Vol. 286 (1), 331-353, 2013.
3. Tokumaru, M., M. Kojima, and K. Fujiki, Long-term evolution in the global distribution of
solar wind speed and density fluctuations for 1997-2009, J. Geophys. Res., Vol. 117, A06108,
2012 (doi:10.1029/2011ja017379).
4. Janardhan, P., S. K. Bisoi, S. Ananthakrishnan , M. Tokumaru , K. Fujiki, The prelude to the
deep minimum between solar cycles 23 and 24: interplanetary scintillation signatures in the
inner heliosphere, Geophysical Research Letters, Vol. 38, L20108, 2011
(doi:10.1029/2011GL049227).
5. Tokumaru, M., M. Kojima, K. Fujiki, M. Maruyama, Y. Maruyama, H. Ito, and T. Iju, A
98

newly-developed UHF radiotelescope for interplanetary scintillation observations; Solar Wind
Imaging Facility, Radio Science, 46, RS0F02, 2011 (doi:10.1029/2011RS004694).
6. Tokumaru, M., M. Kojima, and K. Fujiki, Solar cycle evolution of the solar wind speed
distribution from 1985 to 2008, J. Geophys. Res., Vol.115, A04102, 2010
(doi:1029/2009JA014628).
7. Tokumaru, M., M. Kojima, K. Fujiki, and K. Hayashi, Non-dipolar solar wind structure observed
in the cycle 23/24 minimum, Geophys. Res. Lett., 36, L09101, 2009 (doi:10.1029/2009GL037461).
基盤設備名:超高層大気イメージングシステム(OMTIs)
概要:高度 80-300kmで発光している夜間大気光を、高感度全天カメラ、ファブリ・ペロー干渉計、分光
温度計、掃天フォトメータで観測することにより、超高層大気の密度変化の2次元分布、風速、温度を
同時に複数高度で計測する。現在、日本、ノルウェー、ロシア、インドネシア、タイ、オーストラリア、
カナダ、ハワイの 13観測点で、無人自動観測を定常的に行っている。このように数多くの大気光観測機
器 を 各 地 で 運 用 し て い る シ ス テ ム は 世 界 で 唯 一 で あ る 。 デ ー タ プ ロ ッ ト は
http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/omti/index.htmlで公開されている。
人員・運営体制:第 2 部門の小川忠彦(2008 年定年退職)、塩川和夫、大塚雄一の 3 名の教員と、3-4
名の技術職員を中心としてこれまで運営がなされてきた。海外の各観測点では、それぞれ現地の大学や
研究機関と共同研究が行われている。また、国内では京都大学、電気通信大学、国立極地研究所、九州
大学、東北大学、NICTなどと共同研究が展開されている。
成果:中規模伝搬性電離圏擾乱の磁気共役性と電場振動の発見、中間圏大気波動のダクト伝搬の証拠の
発見など、これまでに査読付き論文が 94 編(2008年以降は 42編)、博士論文は江尻省(2002年)、鈴木
臣(2007 年)、坂口歌織(2009 年)、野村麗子(2012 年)の 4 編が出されている。2008 年以降に出版さ
れた代表論文 5編を以下に挙げる。
Hosokawa, K., J. P. St-Maurice, G. J. Sofko, K. Shiokawa, Y. Otsuka, T. Ogawa, Reorganization
of polar cap patches through shears in the background plasma convection, J. Geophys. Res.,
115, A01303, doi:10.1029/2009JA014599, 2010.
Otsuka, Y., K. Shiokawa, and T. Ogawa, Disappearance of equatorial plasma bubble after
interaction with mid-latitude medium-scale traveling ionospheric disturbance, Geophys.
Res. Lett., 39, L14105, doi:10.1029/2012GL052286, 2012.
Shiokawa, K., M. Mori, Y. Otsuka, S. Oyama, and S. Nozawa, Motion of high-latitude nighttime
medium-scale traveling ionospheric disturbances associated with auroral brightening, J.
Geophys. Res., 117, A10316, doi:10.1029/2012JA017928, 2012.
99

Shiokawa, K., Y. Otsuka, S. Oyama, S. Nozawa, M. Satoh, Y. Katoh, Y. Hamaguchi, Y. Yamamoto
and J. Meriwether, Development of low-cost sky-scanning Fabry-Perot interferometers for
airglow and auroral studies, Earth Planets Space, vol.64, no.11, 1033-1046, 2012.
Suzuki, S., K. Shiokawa, Y. Otsuka, S. Kawamura, and Y. Murayama, Evidence of gravity wave
ducting in the mesopause region from airglow network observations, Geophys. Res. Lett.,
40, 601-605, doi:10.1029/2012GL054605, 2013.
図1.超高層大気イメージングシステムの観測点。
基盤設備名:太陽中性子望遠鏡ネットワーク
概要:太陽中性子望遠鏡は、太陽フレアでの粒子加速機構の解明のため、中性子による反跳陽子を検出
して中性子の到来方向とエネルギーを測定する検出器である。乗鞍 64m2 太陽中性子望遠鏡を中心として
世界 7 箇所に展開された太陽中性子 24 時間観測網は、第 23 太陽活動期後半から継続して太陽中性子検
出のための観測を行っている。また、メキシコで新型の太陽中性子望遠鏡 SciCRTの稼動が始まっている。
運営体制:太陽中性子望遠鏡観測網は、第 3 部門松原・さこによって運用され、国内では信州大、海外
ではメキシコ自治大などとの国際共同研究として行われている。乗鞍 64m2望遠鏡は本研究所が東大宇宙
線研究所乗鞍観測所の共同利用として運用し、世界6箇所の各望遠鏡は現地共同研究者により運用され
100

ている。データは共同利用研究者のみに公開されている。新型太陽中性子望遠鏡 SciCRTの建設について
は第3部門伊藤も大きく関与している。
成果:これまでの 11イベントの太陽中性子イベントを観測し、得られた中性子のエネルギースペクトル
のべきは、平均的にショック加速から期待されるものよりソフトであることを見出している。またイオ
ン加速継続時間は、X線放射から期待される瞬間的な放射に比べ長いことを見出している。2005 年 9 月
7 日の太陽中性子イベント以降は、太陽中性子は観測されておらず、2010 年以降学術論文への成果掲載
はない。その後は観測状況や新型中性子望遠鏡の開発状況を宇宙線国際会議や CAWSES II 国際シンポジ
ウムで報告している。新型望遠鏡は太陽中性子検出以外に、多方向宇宙線変動のモニターもできるため、
宇宙線モジュレーショングループとの共同研究となっている。高度 2,150mでの宇宙線観測結果について
は Astroparticle physics に投稿されている。
論文リスト:5年間に査読付き学術誌は無いが、多くの会議録がある。
<既存の検出器による太陽中性子観測報告>
[1] J. F. Valdes-Galicia et al., Solar neutron events as a tool to study particle acceleration
at the Sun, Advance in Space Research, 43, 565-572, 2009.
[2] K. Watanabe, et al., Physics of ion acceleration in the solar flare on 2005
September 7 determines γ-ray and neutron production, Advance in Space Research 44,
789-793, 2009.
[3] Y. Matsubara et al., Status of the world-wide network of solar neutron telescopes in solar
cycle 24, Proc. 31st Int. Cosmic Ray Conf., Lodz, web 掲載、
http://icrc20009.uni.lodz.pl/proc/html, 2009.
[4] Y. Nagai et al., Search for solar neutrons during solar cycle 24, poster, International CAWSES
II Symposium, 2013.
[5] D. Lopez et al., Solar neutron monitoring at Mount Chacaltaya during solar cycle 24,
International CAWSES II Symposium, 2013.
基盤設備名: 短波ドップラーレーダー装置
概要:北海道足寄郡陸別町に設置された本装置は、短波帯の電波を斜め上方に発射し、電離圏等から戻って来
るエコーを観測することにより、中緯度から高緯度域にわたる電場変動や電離圏プラズマ変動を広域にわたり
高時間分解能で二次元観測することが可能である。本装置は世界的な短波レーダーのネットワークである
SuperDARN (Super Dual Auroral Radar Network)に参加している。教員 2 名、技術職員 3 名(他のプロジェク
トと兼任)が装置の運用・運営に関わっている。
成果:本装置を活用して現時点で計 22 編の論文が出版済みあるいは掲載許可となっている(2008-2012 年は各
101

年度毎に所内: 3編、1編、2編、1編、3 編、所外: 2 編、2編、2編、0編、2編)。主な論文の内容は以下の
通りである。
(1) 夕方サブオーロラ帯西向き高速流(SAPS)と地磁気擾乱との関連性
SAPSは地磁気擾乱時に出現することがよく知られているが、地磁気擾乱との詳細な対応は不明な部分が数多
く残されていた。本研究では北海道-陸別 HF レーダーで観測した SAPS と地磁気擾乱の関係を統計的に調べた
結果、SAPS の出現が赤道環電流指数(Dst)の現象と高い相関を持つことを確認した。またイベント解析と内部
磁気圏の数値実験結果の比較の結果、SAPS の生成のためには赤道環電流が(非一様性を持って)発達することが
必要であることを示した。
(2)夜側中規模伝搬性電離圏擾乱の研究
極域から中緯度へ 5,500 kmを超えて長距離伝搬する夜間の中規模伝搬性電離圏擾乱(MSTID)が、スポラディ
ック E層(Es)からの強いエコーと同時に観測されている現象に注目し、詳細に解析した結果、MSTIDと Esが磁
力線に沿って電気的に結合していることを初めて二次元の電場データを活用して確認した。また、HFレーダー
および大気光撮像カメラで観測した MSTID 現象の間に一対一の対応があることも示した。
(3) 巨大地震に伴う電離圏変動の研究
2011年東北太平洋沖地震後に観測された電離圏擾乱の詳細な解析を行い、地震後 10-20分後に 3.5-6.2 km/s
の速度で伝搬する、速度分散性を持つ変動が存在することを明らかにした。また、この伝搬速度は地震表面波
の伝搬速度にほぼ一致することを確認し、地震表面波による地表面の上下振動が音波を誘起してそれが大気中
を上方に伝搬し、電離圏プラズマ構造の上下振動を引き起こしていることで説明できることを示した。
2008-2012年度の代表的な論文 5編(全て査読有り)
Nishitani, N., T. Ogawa, Y. Otsuka, K. Hosokawa, and T. Hori, Propagation of large amplitude ionospheric
disturbances with velocity dispersion observed by the SuperDARN Hokkaido radar after the 2011 off
the Pacific coast of Tohoku Earthquake, Earth Planets Space, 63, 891-896, 2011.
Suzuki S., K. Hosokawa, Y. Otsuka, K. Shiokawa, T. Ogawa, N. Nishitani, T. F. Shibata, A. V. Koustov,
and B. M. Shevtsov, Coordinated observations of nighttime medium-scale traveling ionospheric
disturbances in 630-nm airglow and HF radar echoes at midlatitudes, J. Geophys. Res., 114, A07312,
doi:10.1029/2008JA013963, 2009.
Kataoka, R., K. Hosokawa, N. Nishitani, and Y. Miyoshi, SuperDARN Hokkaido radar observation of westward
flow enhancement in subauroral latitudes, Ann. Geophys., 27, 1695-1699, 2009.
Ogawa, T., N. Nishitani, Y. Otsuka, K. Shiokawa, T. Tsugawa, and K. Hosokawa, Medium-scale traveling
ionospheric disturbances observed with the SuperDARN Hokkaido radar, all-sky imager and GPS network,
and their relation to concurrent sporadic-E irregularities, J. Geophys. Res., 114, A03316,
doi:10.1029/2008JA013893, 2009.
Ebihara, Y., N. Nishitani, T. Kikuchi, T. Ogawa, K. Hosokawa, M. -C. Fok and M. F. Thomsen, Dynamical
property of storm-time subauroral rapid flows as a manifestation of complex structures of the plasma
pressure in the inner magnetosphere, J. Geophys. Res., 114, A01306, doi:10.1029/2008JA013614, 2009.
102

基盤設備名:高層大気温度観測装置(ソディウムライダー)
概要:北極域下部熱圏・中間圏における大気温度変動を解明するため、2010年3月に高層大気温度観測装
置をノルウェートロムソ(69.6°N, 19.2°E)に設置した。設置したEISCATトロムソ観測所では、EISCAT
レーダーをはじめ、MFレーダー、流星レーダー、FPI、オーロライメージャなどが稼働しており、本装置
導入により初めて大気温度導出が可能になった。これらの観測装置を用いた拠点観測により、オーロラ
加熱や大気重力波散逸現象などの観測的解明を目指している。
運営体制・人員:
運営体制(ライダー整備):技術職員の川端氏が主にサポート。理化学研究所および信州大学との共
同研究として実施しており、レーザー保守およびシステム保守には、教員2名が参加している。
運営体制(観測): オペレーションは、教員2名、大学院学生数名。2011年度までポスドク1
名。GCOEのフィールド観測体験で2名参加。
成果:2011年1編、2013年3編
(1) Tsuda, T. T., S. Nozawa, T. D. Kawahara, T. Kawabata, N. Saito, S. Wada, C. M. Hall, S. Oyama, Y. Ogawa,
S. Suzuki, T. Ogawa, T. Takahashi, H. Fujiwara, R. Fujii, N. Matuura, and A. Brekke, Fine structure of sporadic
sodium layer observed with a sodium lidar at Tromsoe, Norway, Geophys. Res. Lett., 38, L18102,
doi:10.1029/2011GL048685, 2011.
2011年1月に発生したスポラディックソディウムレイヤー(SSL)を高時間分解能による解析し、生成メカニズムを議論。
(2) Matuura, N., T. Tsuda, and S. Nozawa, Field-Aligned Current Loop Model on Formation of Sporadic Metal Layers,
JGR, 118, doi:10.1002/jgra.50414, 2013.
新しいSSL生成メカニズムのモデルを提唱。
(3) Tsuda, T.,S. Nozawa, T. D. Kawahara, T. Kawabata, N. Saito, S. Wada, Y. Ogawa, S. Oyama, C. M. Hall, M. Tsutsumi,
M. K. Ejiri, S. Suzuki, T. Takahashi, T. Nakamura, Decrease in sodium density observed during auroral particle
precipitation over Tromsoe Norway,GRL, 40, DOI: 10.1002/grl.50897, 2013.
オーロラ降下粒子によるナトリウム密度の現象を初めて観測データにより示した。
(4) Nozawa, S., T. D. Kawahara, N. Saito, C. M. Hall, T. T. Tsuda, T. Kawabata, S. Wada, A. Brekke, T. Takahashi,
H. Fujiwara, Y. Ogawa, and R. Fujii, Variations of the neutral temperature and sodium density between 80 and 107
km above Tromso during the winter of 2010-2011 by a new solid state sodium LIDAR, J. Geophys. Res., in press,
2013.
トロムソソディウムライダーによる2010年シーズンの観測結果を示し、ライダーの説明をするととも
に、ジュール加熱効果を定量的に議論。
データ公開:http://www.stelab.nagoya-u.ac.jp/~noz
103

基盤設備名:ミリ波大気放射分光観測装置
概要:大気微量分子のミリ波放射スペクトルを測定し、その高度分布を計測する装置である。現在、チ
リ、アルゼンチン、北海道陸別(当初は国立極地研の資産であったが2011年に太陽地球環境研究所に委
譲)、南極昭和基地(国立極地研の資産だが太陽地球環境研究所が技術供与)に装置が設置され、オゾ
ン、一酸化塩素、窒素酸化物等の観測を行っている。オゾン層破壊の状況を解明するとともに、太陽活
動に伴う地球外高エネルギー粒子の地球大気への侵入の影響など地球内外の環境変動が大気環境に与え
る影響解明を行っている。
運営体制・人員: チリは基本的に自動無人運転(トラブル発生時には同じ観測サイトで電波天文観測を
行っている名古屋大学理学研究科のスタッフまたは学生に対処を依頼することがある)。アルゼンチン
は現地の観測所研究者・技術者、陸別は常駐の派遣会社職員、南極昭和基地は国立極地研究所の越冬隊
員が観測を行っている。
成果: 自作の超伝導受信機を用いて高感度のミリ波分光を行い、成層圏から中間圏の微量分子の時間・
空間変動のデータを取得している。標高約5,000メートルのチリでは、水蒸気によるミリ波大気吸収が極
めて小さいため、平地では観測困難な強度が極めて弱い微量成分の分光を行い、183GHz帯のH2Oスペクト
ルの検出と同データによる高度分布の導出、オゾン層破壊で重要な役割を果たす一酸化塩素(ClO)分子の
南半球中緯度帯での日変化の報告等の成果が出ている。陸別では、成層圏オゾンに的を絞り、10年以上
の長期にわたるモニタリングを行っている。アルゼンチンと南極昭和基地の装置は2011年に設置された
もので、アルゼンチンは南米大陸南端部にまでしばしば及ぶオゾンホールの境界領域の鉛直分布の観測
と長期的なオゾンモニタリングを行っている。アルゼンチンに関してはモニタデータを蓄積している段
階でまだ顕著な成果は得られていない。南極昭和基地では太陽活動に伴う高エネルギー粒子の降りこみ
が中間圏および下部熱圏の大気組成に与える影響の観測的な解明を目的とし、昭和基地の磁気緯度帯で
は太陽陽子よりも磁気嵐に伴う放射線帯電子の影響が顕著であることを観測的に示した等の成果を得て
いる(投稿中)。博士論文は桑原利尚(名古屋大学、2012年)の1編。
2008
“Ground-based millimeter-wave observations of water vapor emission (183 GHz) at Atacama, Chile”,
Kuwahara, T., Mizuno, A., Nagahama, T., Maezawa, H., Morihira, A., Toriyama, N., Murayama, S.,
Matsuura, M., Sugimoto, T., Asayama, S., Mizuno, N., Onishi, T., and Fukui, Y., Advances in Space
Research, Volume 42, Issue 7, p. 1167-1171, DOI 10.1016/j.asr.2007.11.030. , 2008 (査読付き)
2011
“Millimeter wave radiometer installation in Río Gallegos, southern Argentina”, P. F. Orte, J.
Salvador, E. Wolfram, R. D’Elia, T. Nagahama, Y. Kojima, R. Tanada, T., Kuwahara, A. Morihira,
E. Quel, and A. Mizuno, in International Conference on Applications of Optics and Photonics. Edited
104

by Costa, Manuel F.; Tavares, Paulo; Correia, Helena; Correia, Helena. Proceedings of the SPIE,
Volume 8001, article id. 80013Q, 6 pp. 2011. (査読無し)
2012
“Ground-based millimeter-wave observation of stratospheric ClO over Atacama, Chile in the
mid-latitude Southern Hemisphere”, Kuwahara, T., Nagahama, T., Maezawa, H., Kojima, Y., Yamamoto,
H., Okuda, T., Mizuno, N., Nakane, H., Fukui, Y., Mizuno, A., Atmospheric Measurement Techniques,
Volume 5, Issue 11, .2601-2611, DOI 10.5194/amt-5-2601-2012, 2012 (査読付き)
基盤設備名:大気組成フーリエ赤外分光観測装置
概要: 太陽赤外光を背景光源として大気中の微量分子による吸収スペクトルを測定し、それらの組成
の高度分布を計測する装置である。現在、北海道陸別町及び母子里に装置が設置され、モニタリング観
測を継続している。温室効果ガスやオゾン層破壊物質、対流圏大気汚染物質が観測可能であり、地球環
境変動の原因物質の長期変動を研究するための基礎データとして活用されている。
運用経費: 基本的には陸別観測所、母子里観測所経費により運用。
運用時間: 晴天時昼間。
運営体制・人員: 現地常駐スタッフ(母子里は技術支援員2名、陸別は業務委託による派遣職員1名)
が天候の状態により、太陽追尾装置のカバーを外し、観測を開始・終了する。データ解析については、
成層圏オゾン化学に関連する大気微量分子に関しては、大気組成変化検出ネットワーク (NDACC) が提供
する標準的な解析手法により、オゾン(O3)、塩化水素(HCl)、硝酸塩素 (ClONO2)、硝酸 (HNO3)、フッ化水
素 (HF) のカラム全量解析及び成層圏での高度分布解析を行い、結果は NDACCデータベースを通じて研
究者に提供している。また対流圏の温室効果ガスや大気汚染物質については共同研究ベース開発された
解析手法によりの二酸化炭素(CO2)、メタン(CH4)、一酸化炭素 (CO)、エタン (C2H6)、シアン化水素 (HCN)
等のカラム全量・カラム混合比の解析を行っている。
成果:豪雪地帯の母子里では夏期の観測効率がよく冬期に悪い。道東の陸別では夏期は天候が悪く、冬
期に晴天率が高く観測効率がよい。この2地点の相補的な特性を活かし、年間を通して成層圏の大気微
量成分の季節変動や長期にわたる経年変化が観測されている。
データはNDACCにアーカイブし、広く関連研究者に活用されている。二酸化炭素やメタン等の温室効果
ガスの衛星観測データの検証や新たに開発している光スペアナを用いた温室効果ガス観測装置の検証に
活用されている。2008年から2012年の5年間には以下のような6編の論文が出版されている。博士論文
は長浜芳寛氏(横浜国立大学、2010年)の1編。
105

2009
“Hydrogen cyanide in the upper troposphere: GEM-AQ simulation and comparison with
ACE-FTS observations”,A. Lupu, et al., Atmos. Chem. Phys., 9, 4301-4313,
doi:10.5194/acp-9-4301-2009, 2009. (査読付き)
2010
“Analysis of temporal variations of stratospheric and tropospheric constituents”, Y. Nagahama
(横浜国大 学位論文)
“Remotely operable compact instruments for measuring atmospheric CO2 and CH4 column
densities at surface monitoring sites”, Kobayashi, N., et al., Atmos. Meas. Tech., 3, 1103-1112,
doi:10.5194/amt-3-1103-2010, 2010 (査読付き)
“Validation of five years (2003-2007) of SCIAMACHY CO total column measurements using
ground-based spectrometer observations”, de Laat, A. T. J. et al.,Atmos. Meas. Tech., 3, 1457-1471,
doi:10.5194/amt-3-1457-2010, 2010 (査読付き)
2012
“Effects of atmospheric light scattering on spectroscopic observations of greenhouse gases from
space: Validation of PPDF-based CO2 retrievals from GOSAT”, S. Oshchepkov, et al., J. Geophys.
Res., 117, D12305, doi:10.1029/2012JD017505, 2012. (査読付き)
“Aircraft measurements of carbon dioxide and methane for the calibration of ground-based
high-resolution Fourier Transform Spectrometers and a comparison to GOSAT data measured
over Tsukuba and Moshiri”, T. Tanaka, et al., Atmos. Meas. Tech., 5, 2003-2012,
doi:10.5194/amt-5-2003-2012, 2012. (査読付き)
基盤設備名:大気環境変動解析装置
概要: 太陽-地球システムの中で大気圏は、太陽活動の影響を受けるとともに、生物・人間活動によ
り大きく変動している。大気環境変動解析装置では、エアロゾル(大気浮遊微粒子)の粒径分布や光学
的特性、炭素質エアロゾルの化学的特性の測定を行うことができる。本装置を用いた観測および室内実
験研究により、自然および人為起源のエアロゾルの生成メカニズムや、大気エアロゾルの太陽入射光に
対する特性を調べ気候への影響を解明することを目指している。
運営体制・人員:教員 2名(松見・中山)および博士研究員・大学院学生数名で運営を行っている。
106

成果: 本装置を用い、これまでに大気中の二次有機エアロゾル(SOA)の生成・変質過程(3,5)や光
学特性(1,2,4)、自動車排ガス起源のエアロゾル粒子の光吸収特性(投稿中)を明らかにしてきた。特に、
植物起源の揮発性有機化合物(VOC)の大気酸化反応を経て生成するSOAは可視から短波長紫外領域で光吸
収性を持たないに対し、人為起源のVOCの大気酸化反応を経て生成するSOAは、有意な光吸収性を明らか
にした研究は、先駆的な研究成果として評価されており、気候変動に関する政府間パネル(IPCC)第5次報
告書でも、引用されている。
(査読有り)
(1)T. Nakayama, Y. Matsumi, K. Sato, T. Imamura, A. Yamazaki, A. Uchiyama, Laboratory studies
on optical properties of secondary organic aerosols generated during the photooxidation of
toluene and the ozonolysis of -pinene, J. Geophys. Res., 115, D24204,
doi:10.1029/2010JD014387 (2010).
(2)T. Nakayama, K. Sato, Y. Matsumi, T. Imamura, A. Yamasaki, A. Uchiyama, Wavelength dependence
of refractive index of secondary organic aerosols generated in during the ozonolysis and
photooxidation of -pinene, SOLA, 8, 119-123 (2012).
(3)T. Nakayama, Light absorption properties of organic aerosols, Earozoru Kenkyu, 27, 13-23 (2012).
(Japanese with English abstract)
(3) Y. Han, Y. Iwamoto, T. Nakayama, K. Kawamura, T. Hussein, M. Mochida, Observation of new
particle formation over a mid-latitude forest facing the North Pacific, Atmos. Environ., 64,
77-84 (2013).
(4) T. Nakayama, K. Sato, Y. Matsumi, T. Imamura, A. Yamasaki, and A. Uchiyama, Wavelength and
NOx dependent complex refractive index of SOAs generated from the photooxidation of toluene,
Atmos. Chem. Phys., 13, 531-545 (2013).
(5) Y. Han, Y. Iwamoto, T. Nakayama, K. Kawamura, M. Mochida, Formation and evolution of biogenic
secondary organic aerosol over a forest site in Japan, J. Geophys. Res. (in press)
(査読無し)
(1) 「レーザーを用いた大気微量成分のリアルタイムその場計測」
中山智喜、松見 豊、月刊オプトロニクス、29, 128-133 (2010).
(2) 「レーザー分光法を用いたエアロゾル光学特性の計測」
中山智喜、松見 豊、化学工学、77, 566-568 (2013).
基盤設備名:STEL磁力計ネットワーク
概要: 1Hz サンプルの 3 軸フラックスゲート磁力計と、64Hz サンプルの誘導磁力計から構成される
磁力計群。ロシア、カナダ、日本、インドネシア、ニュージーランドの 10 カ所で 2005 年より順次、定
107

常観測を行っている。アジア地域の誘導磁力計の広域観測としては唯一のネットワークである。ERG衛星
で探査される放射線帯粒子の加速・消失に影響するイオンサイクロトロン波動(EMIC 波動=Pc1 帯地磁
気 脈 動 ) を 中 心 と し て 、 Pc1-5 帯 の 地 磁 気 脈 動 を 観 測 し て い る 。 デ ー タ プ ロ ッ ト は
http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/magne/index.html で公開されている。フラックスゲート磁力計
は、1996 年に湯元清文教授が九州大学に転出後、210 度地磁気観測点などで使用していた部品の残りを
使って整備された。誘導磁力計は、2005 年頃から、主に科研費を使って作られ、順次整備されている。
現在は研究所の特別経費や科研費で維持のための予算が手当されている。
人員・運営体制: 第 2部門の塩川和夫、大塚雄一と 3-4名の技術職員を中心としてこれまで運営がな
されてきた。海外の各観測点では、それぞれ現地の大学や研究機関と共同研究が行われている。また、
ニュージーランドは大阪電気通信大学、インドネシアは京都大学と共同で運営がなされている。
成果:EMIC 波動と孤立プロトンオーロラの一対一対応の関係の発見など、これまでに査読付き論文が 13
編(2008 年以降は 12 編)、出版されている。リストは別紙の通り。博士論文は坂口歌織(2009 年)、野
村麗子(2012年)の 2編。2008 年以降に出版された代表論文 5編を以下に挙げる。
Sakaguchi, K., K. Shiokawa, Y. Miyoshi, Y. Otsuka, T. Ogawa, K. Asamura, and M. Connors,
Simultaneous appearance of isolated auroral arcs and Pc 1 geomagnetic pulsations at
subauroral latitudes, J. Geophys. Res., 113, A05201, doi:10.1029/2007JA012888, 2008.
Miyoshi, Y., K. Sakaguchi, K. Shiokawa, D. Evans, J. Albert, M. Connors, and V. Jordanova,
Precipitation of radiation belt electrons by EMIC waves, observed from ground and space,
Geophys. Res. Lett., 35, doi:10.1029/2008GL035727, 2008.
Watari, S., M. Kunitake, K. Kitamura, T. Hori, T. Kikuchi, K. Shiokawa, N. Nishitani, R. Kataoka,
Y. Kamide, T. Aso, Y. Watanabe, and Y. Tsuneta, Measurements of geomagnetically induced
current (GIC) in a power grid in Hokkaido, Japan, Space Weather, 7, S03002,
doi:10.1029/2008SW000417, 2009.
Shiokawa, K., R. Nomura, K. Sakaguchi, Y. Otsuka, Y. Hamaguchi, M. Satoh, Y. Katoh, Y. Yamamoto,
B. M. Shevtsov, S. Smirnov, I. Poddelsky, and M. Connors, The STEL induction magnetometer
network for observation of high-frequency geomagnetic pulsations, Earth Planets Space,
62, 517-524, 2010.
Nomura, R., K. Shiokawa, K. Sakaguchi, Y. Otsuka, and M. Connors, Polarization of Pc1/EMIC
waves and related proton auroras observed at subauroral latitudes, J. Geophys. Res., 117,
A02318, doi:10.1029/2011JA017241, 2012.
108

図1.STEL 磁力計ネットワークの観測点。
基盤設備名:STEL VLF/ELF ネットワーク
概要:20-100kHzサンプルの高時間分解能の VLF/ELF波動観測ネットワーク。母子里、鹿児島の 2観測点
では 1970 年代から 30 年以上にわたってアナログテープに記録され、2006 年にディジタル記録に更新さ
れた。この観測は、千葉大学と共同で、Tweek 空電を通して、電離圏 D層高度の変動の長期観測に使われ
ている。ERG衛星で探査される放射線帯粒子の加速・消失に影響する VLF/ELF帯のコーラス波動を観測す
るために、カナダのサブオーロラ帯に位置するアサバスカで 2012 年より新たに 100kHz サンプルの観測
を開始している。今後、同じくサブオーロラ帯のカナダ東海岸のフレデリクトン、ロシア極東域のジガ
ン ス ク に 同 様 の 観 測 ア ン テ ナ を 設 置 す る 予 定 で あ る 。 デ ー タ プ ロ ッ ト は
http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/vlf/index.html で公開されている。母子里・鹿児島のループアン
テナは 1970 年代から既存のものを、必要に応じて改修しながら使用している。新しいカナダ、ロシアの
観測は、科研費により推進されている。
人員・運営体制:第 2部門の塩川和夫・大塚雄一、第 4部門の三好由純と 3-4名の技術職員を中心とし
てこれまで運営がなされてきた。母子里、鹿児島の観測・データ解析は千葉大学と共同で行われている。
海外の各観測点では、それぞれ現地の大学や研究機関と共同研究が行われている。
成果:母子里・鹿児島では Tweek 空電を通して電離圏 D層高度の 30年以上の長期変動や日食に伴う D層
高度変動などが報告されている。アサバスカの観測ははじまったばかりであるが、さまざまな種類のコ
109

ーラス波動が観測されており、今後、衛星データを組み合わせて解析を行っていく予定である。これま
でに下記のように査読付き論文が 4 編出版されている。博士論文は大矢浩代(千葉大学、2012 年)の 1
編。
Ohya, H., K. Shiokawa, and Y. Miyoshi, Development of an automatic procedure to estimate the
reflection height of tweek atmospherics, Earth Planets Space, 60, 837-843, 2008.
Ohya, H., K. Shiokawa, and Y. Miyoshi, Long-term variations in the tweek reflection height in
the D- and lower E-region ionosphere, J. Geophys. Res., 116, A10322, doi:10.1029/2011JA016800,
2011.
Ohya, H., F. Tsuchiya, H. Nakata, K. Shiokawa, Y. Miyoshi, K. Yamashita, and Y. Takahashi,
Reflection height of daytime tweek atmospherics during the solar eclipse of 22 July 2009,
J. Geophys. Res., 117, A11310, doi:10.1029/2012ja018151, 2012.
Ozaki, M., S. Yagitani, K. Ishizaka, K. Shiokawa, Y. Miyoshi, A. Kadokura, H. Yamagishi, R. Kataoka,
A. Ieda, Y. Ebihara, N. Sato, and I. Nagano, Observed correlation between pulsating aurora
and chorus waves at Syowa Station in Antarctica: a case study, J. Geophys. Res., 117, A08211,
doi:10.1029/2011JA017478, 2012.
110

資料5:領域横断的な重点共同研究プロジェクト
プロジェクト1
第 1期中期(2005-2009)
CMEの素過程の研究
第 2期中期(2010-2015)
プロジェクト1:特異な太陽活動周期における太陽圏 3次元構造の変遷と粒子加速の研究
1. 意義・目的の概要
第1期(2005-2009年)において宇宙天気に大きな影響を与える CME に注目して「CME の素過程の
研究」を推進し、第 2 期(2010-2015 年)ではサイクル 24 における特異な太陽活動に注目して「特
異な太陽活動周期における太陽圏3次元構造の変遷と粒子加速の研究」を推進している。宇宙線モ
ジュレーションの地上ネットワーク観測からは太陽圏の大規模な磁場構造の情報が得られる。STE
研の IPS 観測が太陽風速度・密度の情報を与えるのに対して、この宇宙線データは相補的であり、
両者を融合することで太陽圏の大規模な特性(特に CMEや特異なダイナモ活動に伴う太陽圏の応答)
をより詳細に解明することが可能となる。本プロジェクトでは、国内外の研究者と共同して、宇宙
線観測網の整備などを行ってきた。これらの活動を通じて、我が国独自のデータをもって太陽圏に
関する国際的な共同研究に寄与することを目指している。
2.年度別の参加研究者数
別表参照
3.年度別の共同利用・共同研究数
別表参照
4.主要な成果
宇宙線モジュレーション観測から精度よく太陽圏の磁場(IMF)構造の情報を抽出するには、全球
的な観測ネットワークが不可欠である。信州大学のグループは、全球的なミューオン宇宙線観測網
GMDN の整備を行っており、本プロジェクトではその支援を行ってきた。第 1 期では、信州大学にお
ける FPGA 開発環境の整備や海外への運搬費、旅費の支援を実施し、名古屋・乗鞍-ホバート(豪)
-ブラジルにクェートを加えた観測網を完成させた。また、取得したデータをデータベース化して
配信するシステムも整備した(http://cosray.shinshu-u.ac.jp/crest/)。取得された GMDN のデー
タからは、CMEに伴って円柱状の IMF構造が決定されている。一方、IPS観測からは CMEに伴って太
陽風中を伝搬するループ状の密度増加構造が決定されている。両者を比較したところ円柱状磁場構
造とループ状密度構造は概ね一致していることが判明し、太陽風 in situ データの解析から求めら
れた磁気ロープの方向とも一致していることがわかった(Tokumaru et al., 2010)。これは、太陽
111

風中における CME の 3 次元構造を理解する上で重要な成果である。本プロジェクトの第 2 期では、
GMDN の拡充を目指してホバートの検出器の大型化や新型レコーダの設置、メキシコ高地に新しい検
出器の設置などを行っている(メキシコの検出器は、STE 研が開発している太陽中性子望遠鏡 SciCRT
にミューオン宇宙線の測定機能を付与することで実現)。これまでに取得した GMDN データの解析か
らは、宇宙線強度の異方性と太陽圏の大規模磁場構造の関係が明らかになっている(Okazaki et al.,
2008; Fushishita et al., 2010 など)。第1期後半からは、愛知工大・大阪市大のグループが推進
するインドの大型ミューオン計 GRAPES-3を用いた宇宙線モジュレーション観測研究の支援を行って
いる。さらに米国 UCSDのグループと共同研究を通じ NASA/CCMCから IPSデータの提供や韓国宇宙天
気センターとの共同研究の立ち上げ、台湾での宇宙天気ウィンタースクール開催が実現している。
5.関連業績(学術論文)数
別表参照
プロジェクト2
第 1期中期(2005-2009)
人工衛星ー地上共同観測によるジオスペース研究の新展開
第 2期中期(2010-2015)
プロジェクト2:グローバル地上・衛星観測に基づく宇宙プラズマ-電離大気-中性大気結合の研
究
1.意義・目的の概要
第 1 期中期:新しい人工衛星-地上共同観測と領域間をつないだ数値モデルを基に、ジオスペー
スを構成する磁気圏―電離圏-熱圏の間でのエネルギー変換・物質輸送過程を研究し、人類の活動
領域としても重要度を増すジオスペース環境変動の理解に貢献する。地上観測機器は、近年新たに
開発されてきた高感度の光学観測機器、EISCAT レーダー、流星レーダーを用いるとともに、別途予
算要求している中緯度短波レーダーとも密接に連携協力していく。人工衛星は、これまでの国内外
の人工衛星に加えて、地上とのネットワーク観測を意図して 2006 年に打ち上げられる米国 THEMIS
衛星と共同観測を行うとともに、近い将来の小型衛星によるジオスペース観測のための基盤整備を
行う。
第 2 期中期:太陽からやってくる宇宙プラズマと地球の電離大気・中性大気の間の相互作用は、地
球のまわりの身近な宇宙空間(ジオスペース)で発生する諸現象を作り出す。本プロジェクトでは、
地上観測を有機的に結合させてネットワーク化し、人工衛星観測と組み合わせることにより、地球
周辺の宇宙プラズマ-電離大気-中性大気間の結合過程とその間のエネルギー・物質のやりとりを
研究する。また、長期モニタリングが可能な地上観測の特性を生かして、極大期・極小期を包括す
る長期的な観測を行い、太陽活動が地球大気に与える影響を明らかにする。
112

2.年度別の参加研究者数
別表参照
3.年度別の共同利用・共同研究数
別表参照
4.主要な成果
第 1 期中期、第 2 期中期ともに、継続的に、人工衛星と地上観測を結びつける研究を熱圏、電離
圏、磁気圏の領域に対して行ってきた。特に、2015 年に日本で打ち上げられる ERG 衛星と連携する
ために、国内の各機関と連携して、ERGが観測する内部磁気圏に対応するサブオーロラ帯に VLF帯の
波動と ULF 帯の波動及びオーロラを観測する装置を設置している。この活動は ERG 連携地上観測班
として、ERG プロジェクトの中で位置づけられており、現在、15機関から 29名の研究者が参加して
いる。Table 1に参加機関とその観測項目をあげる。例えばカナダのアサバスカ観測点では、金沢大
学、東北大学と現地のアサバスカ大学と協力して 2012 年に VLF波動観測装置を設置し、良質なデー
タ が 得 ら れ る よ う に な っ て い る 。 こ れ ら の デ ー タ は ホ ー ム ペ ー ジ
(http://stdb2.stelab.nagoya-u.ac.jp/vlf/)を開設して公開している。また 2012 年度の冬期に
は、EMCCDカメラによる 100Hzの高時間分解能のオーロラ観測を、第 2部門、第 4部門や所外の研究
者が協力して実施した。また、北海道陸別短波レーダーの観測、北欧のトロムソにおけるナトリウ
ムライダーや多波長フォトメータによる極域下部熱圏・中間圏の観測、CAWSES-II TG4の推進もこの
プロジェクトの中で位置づけている。
Table 1. ERG 連携地上観測班の観測項目と関連研究機関
5.関連業績(学術論文)数
別表参照
物理量 測定機器 研究機関磁場ULF波動 フラックスゲート磁力計 九州大学、名古屋大学、極地研、NICTEMIC波動 誘導磁力計 名古屋大学、極地研VLFコーラス波動、MF帯波動 ループアンテナ 金沢大学、極地研、名古屋大学電場グローバルなプラズマ対流 SupeDARNレーダー 極地研、名古屋大学、NICT電離圏電場 FM-CWレーダー 九州大学、NICT電離圏電子密度・温度・電場 ISレーダー 名古屋大学、極地研電子密度電離圏電子密度 GPS受信器 NICT、名古屋大学、京都大学プラズマ圏電子密度 フラックスゲート磁力計 九州大学粒子降り込み>100keV粒子降り込み 北欧気球 京都大学100keV電子降り込み LF標準電波受信器 東北大学100keV電子降り込み VLFアンテナ-Tweek反射高度 千葉大学30keV電子降り込み リオメータ 名古屋大学1-10keV電子・イオン降り込みオーロラ 名古屋大学、極地研、東北大学熱的電子 大気光 名古屋大学
113

プロジェクト3
第 1期中期(2005-2009)
太陽活動の地球環境への影響に関する研究
第 2期中期(2010-2015)
プロジェクト3:太陽活動の地球環境への影響に関する研究
1.意義・目的の概要(10行程度)
太陽活動はさまざまな形で地球環境に影響を与えている。我々は太陽活動の変動がどのように地
球環境に影響を与えてきたのか,過去から現在にわたって検証し,その素過程を解明しようと考え
ている。STE研ではこのテーマに関連する研究者が異なる部門に属するため,領域横断的なプロジェ
クトのテーマとして組織した。実際には個々の研究者グループが独自の研究を続けるが,その中に
プロジェクトのテーマを意識した内容を盛り込むことと相互の関係を意識して結果を解釈すること
とした。サブテーマは,(1)宇宙線生成核種による過去の太陽活動と気候の関係の検証,(2)太陽活
動と気候の関係の観測と相関メカニズム(太陽粒子の影響),(3)太陽放射,特に紫外線の大気との反
応素過程の解明と気候変動要素のその場観測,そして第2期中期計画からは,(4)太陽活動によって
制御される宇宙線の気候への影響,を設定した。ある程度まではそれぞれ独立に技術開発や測定・
観測を進めた後,各サブテーマの内容を統合して結果をまとめることを目標とする。
2.年度別の参加研究者数
別表参照
3.年度別の共同利用・共同研究数
別表参照
4.主要な成果
プロジェクトの目的を達成するために,いくつかのサブグループにより研究を進めている。第1
期中期計画で装置の開発研究を行なって設備を整備し,第2期中期計画では観測・測定に重点を置い
ている。サブグループごとの成果は以下の通り。
(1) 過去の太陽活動とその地球環境への影響
太陽活動が制御する宇宙線が地球大気中で生成する放射性同位体(宇宙線生成核種)の濃度測定か
ら過去の太陽活動や核種の大気中での挙動を調べている。試料処理効率と操作の安定性を向上させ
た装置を用いて,過去 3,000年のうちの約 1,200年間について樹木年輪中の炭素 14濃度を 1年分解
能で年代測定総合研究センターの加速器質量分析計を用いて測定し,太陽活動のシュワーベ・サイ
クルの周期長(平均 11年)の変化を調べ,太陽活動が弱い時期に周期長が長くなることを見いだした。
また 1-2 年以下の短い期間に大量の宇宙線を放出する突発現象が 1,600 年間に少なくとも2回起き
ていたことを発見し,さらに地球環境への影響を調べている。
114

山形大学と共同で,宇宙線生成核種の一つであるベリリウム7の濃度を世界数ヶ所で1日単位の
測定を行い,その大気中での挙動と太陽活動に対する変化を調べている。北半球高緯度や南半球の
高山のデータとシミュレーションとの比較から,高緯度地域で生成された核種が中緯度地域へ移動
している可能性を見いだした。
(2) 大気中微量成分への太陽活動の影響
モニタリング観測を通して,大気組成の数年から十数年のタイムスケールでの変動から,太陽の
11 年周期に対応する変動を抽出し,太陽活動の大気組成変動に対する影響を調べるとともに高感度
ミリ波大気観測装置の開発を行っている。
チリ・アタカマ高地及びアルゼンチン・リオガジェゴスに移設したミリ波大気分子分光観測装置
によるオゾン,水蒸気同位体,ClOの連続観測データは,長期にわたる成層圏微量分子の組成変動お
よび経年変化の基礎データとなる。人為起源のフロン等を起源とした塩素や温暖化との関連が指摘
される水蒸気を起源とするHOX によるオゾン層破壊は,オゾン長期トレンドに大きな影響を与える要
因であり,太陽活動との関連を調べる上でも重要なファクターであり,今後も連続的に観測を継続
して,微量分子の高度分布と時間変動及びオゾン長期変動との関連を調べるための時系列データを
取得する。同時に,ブラジル磁気異常帯直下において,磁気嵐に伴う相対論的加速電子による解離・
電離で生じるHOX やNOx が引き起こす中間圏大気組成変動を連続的に観測することで,太陽活動に伴
う高エネルギー粒子の地球大気への影響を明らかにする。
小型冷凍機を利用したミリ波装置を開発したことにより,大気微量分子組成が高エネルギー粒子
の降下等の太陽活動の影響を最も受けやすい極域で連続観測を行い,中層大気の組成変動と太陽活
動との関連に関する新たな知見の獲得を目指す。
母子里観測所の高分解能FTIRを整備して温室効果気体のモニタリング観測を可能にした。今日の
地球温暖化の主たる原因物質である大気中のCO2及びCH4の長期変動データと,他の地上観測データ及
び「いぶき」衛星データとの組み合わせから,地域ごとの精度の高い温室効果気体の排出・消滅量
の推定を目指す。
(3) 太陽活動が大気微量成分の変動及び地球環境に与える影響の素過程の解明
太陽活動変動の顕著な現れである太陽紫外線の強度変動が大気組成に与える影響を解明し,なら
びに大気中の二酸化炭素 (CO2) の濃度,CO2 安定同位体比およびエアロゾルの光学特性を計測して,
地球環境に与える影響を解析する。
そのために,真空紫外レーザーを用いた分光装置を開発し,これを用いた室内実験により高層大
気中の光反応過程を調べた。また,大気中のエアロゾルの成分をリアルタイムで計測する装置を開
発し,エアロゾルの成分と光学特性を調べることにより気候への影響を調べた。さらに大気中の二
酸化炭素同位体の変動を速い応答でリアルタイム計測が可能なレーザー分光を用いた計測装置を開
発し,測定を行った。
(4) 宇宙線による雲生成の検証
平成 20 年度から JAMSTECとの共同研究として,太陽活動と地球気候の関係を調べるために,宇宙
線による雲生成仮説の検証実験を継続して進めている。放射線源による大気電離とエアロゾル生成
の関係を明らかにするために,容積 75Lの金属チェンバーを用いた実験を行なっている。その結果,
115

放射線や紫外線がエアロゾル形成に影響を与えることが確認されたが,一方でイオン密度が大きい
とエアロゾル生成が飽和する可能性が示された。異なる放射線源と模擬大気の組み合わせにより雲
核の元となるエアロゾルの生成率の変化を調べる実験を準備している。
5.関連業績(学術論文)数
別表参照
プロジェクト4
第 2期中期(2010-2015)のみ
第 2期実証型ジオスペース環境モデリングシステム(GEMSIS-phase II):宇宙嵐に伴う多圏間相互作
用と粒子加速の解明に向けて
1.意義・目的の概要
「実証型ジオスペース環境モデリングシステム」(Geospace Environment Modeling System for
Integrated Studies: GEMSIS)計画では、太陽、磁気圏、電離圏の3つのコアチームを中心に、ジオス
ペースにおける各領域での実証型モデルを構築し、宇宙嵐時に強く発動する多圏間相互作用と高エネル
ギー粒子生成・消滅をになう物理機構の解明を目指している。そのためには、地上観測と衛星観測を含
む多点観測で得られた多様な観測データを、数値モデルを介して結合する研究手法の確立が本質的とな
るため、GEMSIS計画では、地上観測、衛星観測、数値実験をつなぐ実証型モデルの構築とともに、異な
るデータを同じプラットフォームで効率的に解析可能な総合解析ツールを開発し、コミュニティに提供
することも計画している。研究計画の実行にあたっては、磁場・光学ネットワーク観測、北海道短波レ
ーダー等を含む関連する地上観測データを組み入れるとともに、コミュニティのニーズに応えて、太陽
観測衛星ひのでのサイエンスセンターのタスクの一部や、ジオスペース探査計画ERGのサイエンスセン
ターの中核部分を担当している。
2.年度別の参加研究者数
別表参照
3.年度別の共同利用・共同研究数
別表参照
4.主要な成果
フレアトリガー機構の理論的・観測的研究
太陽フレアは激しい宇宙天気擾乱の原因であることからその発生を予測する試みが古くから行われて
いる。しかし、突発現象であるフレアの発生原因は未だに十分理解されていないため、その予測性は低
いままである。我々はフレア発生条件を明らかにするため、200通り以上の異なる磁場構造に関して3次
116

元電磁流体シミュレーションを実施した。その結果、コロナ磁場を構成する2つの成分(ポテンシャル
磁場及びシア磁場)のどちらかに対して反転する磁束が太陽表面に現れることによってフレアに対応す
るエネルギー解放現象が発生することを見出した。この結果は太陽表面の精密な磁場観測に基づいてフ
レア発生を予測し得る可能性を意味するため、宇宙天気予報につながる成果として世界的に注目されて
いる [Kusano et al., 2012]。
可視光高速撮像観測による太陽フレア研究
2011 年度太陽地球環境研究所地上ネットワーク観測大型共同研究(重点研究)として、京都大学大学院
理学系研究科附属天文台と可視光高速撮像観測による太陽フレア共同研究を開始した。まず、フレア高
速撮像システムを製作し、京都大学飛騨天文台の SMART望遠鏡に設置した。これは Hα線と連続光を同時
に且つ 25 フレーム/秒という高いレートでフレアの撮像を行うものである。2012 年度も順調に観測を続
けており、白色光フレア高速観測による粒子加速研究、Hαカーネルの観測によるフレアトリガー研究な
どの共同研究を行っている[Ishii et al., 2013]。
GEMSIS-放射線帯モデルを軸としたマルチスケール放射線帯電子シミュレーションの開発
放射線帯を構成する相対論的エネルギー電子の振る舞いを正確に追跡するために、ドリフト近似を用
いた3次元相対論的粒子軌道計算コード(GEMSIS-RBモデル)の開発を行ってきた[Saito et al., 2010]。
このGEMSIS-RBモデルを軸に、様々な時空間スケールで起こる放射線帯の高エネルギー電子ダイナミクス
を明らかにするために、マルチスケール放射線帯電子シミュレーションの開発を行い、ホイッスラーモ
ード波動と電子との非線形波動粒子相互作用をグローバルに解くことに成功した。このコードはホイッ
スラーモード波動の非線形情報を保持しつつ、時空間に広いスケールにおいて計算が可能という特徴を
もっている。このコードを用いて、MeV電子とホイッスラーモード・コーラス波動との相互作用のシミュ
レーションを行った結果、マイクロバーストとして知られる1秒以下の時定数でのバースト的な降りこみ
現象を再現することに成功し、マイクロバーストの起源はコーラスによる非線形波動粒子相互作用であ
ることを実証した [Saito et al., JGR, 2012]。
ドリフト運動論近似に基づいたGEMSIS-環電流モデルの開発
ジオスペース環境に多大な影響をもたらす宇宙嵐現象の理解に向け、内部磁気圏の数値シミュレー
ションモデル (GEMSIS-RCモデル) の開発を行った。その結果、ドリフト近似した5次元の運動論的
(Vlasov)方程式とマックスウェル方程式を連立させた、電磁場とプラズマ粒子の運動を自己無撞着に解
き進める方程式系を新たに導出することに世界で初めて成功した。また、この方程式系に基づき数値コ
ードを開発し、内部磁気圏での電磁流体波動の伝搬や、粒子のドリフト軌道が場との結合によって変形
する様子など、従来の磁気圏モデルでは解くことのできなかった現象をシミュレートすることが可能と
なった [Amano et al., 2011]。
運用中の公開成果物
・宇宙天気予報システムSUSANOOの試験運用
http://st4a.stelab.nagoya-u.ac.jp/susanoo/
・「ひので」サイエンスセンター@名古屋からのフレアリストの公開
http://st4a.stelab.nagoya-u.ac.jp/hinode_flare/index.html
117

・大フレアを発生した太陽活動領域の3次元磁場データベース
http://st4a.stelab.nagoya-u.ac.jp/nlfff/
・ERGサイエンスセンターにおける統合解析ツールの提供
http://ergsc.stelab.nagoya-u.ac.jp/analysis/
5.関連業績(学術論文)数
別表参照
プロジェクト関連資料
1.年度別の参加研究者数
2.年度別の共同利用・共同研究数
3.関連業績(学術論文)数
1.年度別の参加研究者数
118

2.年度別の共同利用・共同研究数
3.関連業績(学術論文)数
119