思考力・判断力・表現力を育成する協同的な学習の工夫kiriken/26report-C.pdf ·...
Transcript of 思考力・判断力・表現力を育成する協同的な学習の工夫kiriken/26report-C.pdf ·...

- 学力C 1 -
思考力・判断力・表現力を育成する協同的な学習の工夫
-ジグソー学習を取り入れた授業を通して-
学力向上班C
桐生市立川内中学校 小倉 隼人 桐生市立清流中学校 加藤 絵美子
桐生市立梅田中学校 荻野 剛朗
あらまし
本研究では、群馬県の喫緊の課題である「知識・技能を活用する力」を伸ばすこと、桐生市
の重点とする「思考力・判断力・表現力」を伸ばすことをねらいとして、既習の知識や技能を
活用させる場面を意図的に設定する協同的な学習方法を追究した。その結果、生徒同士のかか
わりを深めるジグソー学習が効果的であり、ジグソー学習の有効性について授業実践を通して
明らかにした。
Ⅰ 主題設定の理由
現在、全国学力・学習状況調査(以下:全国学テ)のB問題に対応できるような「活用する力」
を伸ばす指導の工夫が、群馬県としても桐生市としても急務である。
平成25年度「ぐんまの子どもの基礎・基本習得状況調査」や「全国学テ」の結果から、群馬
県の児童生徒には、基礎的・基本的な知識や技能はおおむね身に付いているものの、既習事項と
結びつけて考える思考力や、考えたことを記述する表現力、いわゆる「活用する力」に課題があ
る。これは、桐生市の「全国学テ」の結果においても同様の傾向があり、特に「思考力・表現力」
を問うB問題に対して無回答率の高さが目立った。桐生市は、授業改善推進プランを実施し、今
年度の指導の重点とする学力に「思考力・判断力・表現力」を明記、学習過程を工夫するよう指
示している。
全国学テのB問題に対応できるような「活用する力」は、教師が一方的に説明し児童生徒が聞
くだけの授業や、単なる問題練習を行うだけの授業では伸ばすことができない。身に付けた知識
や技能を活用させる場面を意図的に設定し、児童生徒に目的意識をもたせ、既習事項と結び付け
て考えさせ判断させたり、考えたことを表現させたりする授業展開が必要である。これを展開す
る授業形態として小グループによる協同的な学習がある。
現在の学習指導要領に移行してから、小中学校の全ての教科において言語活動が推奨され、そ
れに伴ってグループでの学び合いや協同的な学習が数多く実践されるようになった。言語活動は、
考え方を共有したり視点の異なる考え方を学んだりすることができ、思考力を高めるために有効
な活動である。しかし、授業に言語活動を取り入れただけで教師が安心してしまっているケース
や、言語活動そのものを展開することに精一杯になり、ねらいがぶれてしまっているケースがあ
る。さらに、一般的な言語活動では、話合い活動をするときに一部の優れた児童生徒のみが活躍
することがある。その場合、その他の児童生徒も話合いにかかわりをもてれば一定の学習効果が
期待できるが、相互を高める効果としては限界があり、多くの課題がある。これらの課題を解決

- 学力C 2 -
するため「ジグソー学習」を取り入れ、実践することとした。
ジグソー学習は、1978 年、社会心理学者エリオット・アロンソン教授らが子ども同士の人種
間の緊張を解きほぐし、協同的な学びを実現するために考案した協同学習の一形態である。ジグ
ソー学習は、次の流れで学習が行われる。
①3~4人程度のホームグループに分かれ、与えられた複数の予備課題を分担する。
②同じ予備課題を追究する学習者同士が集まってエキスパートグループをつくり、予備課
題を追究して情報(手がかり)を得る。
③元のホームグループに戻って追究結果を報告し合い、得られた複数の情報(手かがり)
を総合して本課題を追究する。
この流れの中には、各個人が情報をもち寄って討論しなければ本課題を解決できないという仕
掛けがあり、必然的に各個人に役割と責任が生まれる。ジグソー学習は、言語活動の一つであり
学び合いの一つであるが、グループ環境だけ整えて学び合いを自然発生的に待つのではなく、学
び合いを意図的に引き起こすことに価値がある。
ジグソー学習をはじめとする協同的な学習は有効な言語活動であるが、グループで話し合う時
間を確保するために学習進度が遅くなることが課題として挙げられる。これに対応するためには、
年間指導計画や単元計画の中で、取り入れるタイミングを見計らうとともに、適した題材を精選
する必要がある。そこで、本研究においては理科・数学に限られてしまうものの適した題材を選
定し、実際にジグソー学習の実践を繰り返し行って事例を示すことで、桐生市の理科・数学を担
当する先生方の学習指導の一助になればと考える。
本研究では、理科・数学の授業において、自分の考え方や実験から得た結果を伝え合い、共有
化し、そこからさらに本課題を追究するジグソー学習を展開することで、生徒相互の思考力を高
め、主体的に表現する力を育成することができると考え、本主題を設定した。
ジグソー学習の展開例 理科 「4つの白い粉末の正体を調べよう」
①ホームグループ(生活班)の中で A班 B班 C班
予備課題となる複数の実験を分担 A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
する。
②エキスパートグループ(実験班) 実験1 実験2 実験3
に分かれ、予備課題を追究して、 A1 B1 C1 A2 B2 C2 A3 B3 C3
それぞれが実験結果を得る。 結晶の観察 水への溶け方 加熱後の変化
③ホームグループに戻り、得られた A班 B班 C班
複数の情報を総合して本課題につい A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3
て追究する。 複数情報を総合
※実験指導等においてサイエンスドクターを活用

- 学力C 3 -
Ⅱ 研究のねらい
理科・数学の特性に応じたジグソー学習を取り入れることを通して、生徒相互の思考力を高め
るとともに、主体的に判断し表現する力を育む。
さらに、理科・数学におけるジグソー学習を各学年、各分野、各単元において多くの事例を示
すことで、効果的な分野や単元を提案する。
Ⅲ 研究の見通し
課題解決的な学習場面において、意図的な言語活動を行う協同的なジグソー学習を取り入れ、
個々の生徒が役割を分担して課題解決する授業デザイン構想し実践する。意図的な言語活動を通
して生徒は、課題解決の仕方を科学的・数学的に説明する機会が増えることで、生徒相互の思考
力を高め、主体的に判断し、表現する力を高める。
Ⅳ 研究内容
1 研究計画
1学期 ○研究課題の確認
○研究主題・サブテーマの検討
○主題設定の理由・研究のねらい・研究計画の検討
○ジグソー学習についての文献研究
○主題検討会
2学期 ○中間検討会
○ジグソー学習を取り入れた授業の指導案の検討および作成
○授業実践
○授業検討会・草案検討会
○検証方法の検討(質問紙調査、インタビュー調査)
○調査結果からの分析
3学期 ○実践結果・成果と課題の検討
○紀要原稿の作成
○紀要原稿のまとめ
2 基本的な考え方
(1)ジグソー学習について
理科におけるジグソー学習は、学習内容から次の3つの類型に分類した。3つの類型は、①「実
験構成型」、②「実験反復型」、③「知識構成型」である。①「実験構成型」は、学習課題に対
し、複数の異なる実験を実施し、異なる結果をもとに知識を再構成し課題を解決する方法である。
また②「実験反復型」は、課題解決に対し、同じ実験を繰り返すことを通して、実験結果から法
則等を見いだす方法である。さらに③「知識構成型」は、学習課題に対して、調べた知識を発表
し合い、総合的に判断することを通して知識を再構成し課題を解決する方法である。本研究は、
3つの類型のうち生徒の実態に応じて一つを実践し学習効果を検証する。

- 学力C 4 -
数学におけるジグソー学習は、学習内容から次の3つの類型に分類した。3つの類型は、①「知
識結合型」、②「多思考型」、③「多思考・知識結合型」である。①「知識結合型」は、いくつ
かの知識を総合して学習課題を解決する(解を見いだす)方法である。また、②「多思考型」は、
学習課題に対し、多様な考え方を発散させ、収束させながら課題を解決する方法である。さらに
③「多思考・知識結合型」は、「知識結合型」と「多思考型」の2つを合わせた方法である。本
研究は、3つの類型のうち生徒の実態に応じて一つを実践し学習効果を検証する。
(2)思考力・判断力・表現力について
本研究における思考力・判断力・表現力は、次のように定義する。思考力は事象を筋道立てて
体系的に考える力、判断力は言葉や数、式、図、表、グラフなどの相互関連を理解し、それらを
適切に用いて問題を解決する力、表現力は思考・判断した課程や結果を、言語活動を通じて表現
する、である。さらに、思考力・判断力・表現力を育成する取り組みとして、コンセプトマップ
を活用する。
生徒が自らコンセプトマップを作成することは、新たな知識が既習事項に付加され、関連性や
広がりから、生徒の理解を促進させるのに役立つ。また、教師は、生徒が作成したコンセプトマ
ップから、生徒の学習状況とその程度を調べ、把握するために有効である。
(3)言語活動の充実
言語活動を充実させるため、ジグソー学習を取り入れ、意図的な言語活動を行う授業デザイン
を構想する。ジグソー学習における言語活動は、エキスパートグループで予備課題を追求するた
めの言語活動、ホームグループに戻り追求した知識を説明する言語活動、の2つの言語活動を意
図的に設定することができる。意図的な言語活動を行うことで、思考力・判断力・表現力への効
果を検証する。
3 検証方法
検証は、「ジグソー学習の効果」、「思考力・判断力・表現力の育成」、「言語活動の活性化」、
の3点について行う。具体的な方法として、「ジグソー学習の効果」は、学習後の生徒のインタ
ビュー調査、学習前と学習後に実施する質問紙調査により検証する。また、「思考力・判断力・
表現力の育成」は、生徒が作成したコンセプトマップのワードの数やつながり方より検証する。
さらに、「言語活動の活性化」は、他者との関わりについて、学習前と学習後に実施する質問紙
調査により検証する。
また、質問紙調査は、他者との関わりによる知識の再構成について問う質問項目を作成した。

- 学力C 5 -
Ⅴ 研究の実践
<実践例①> 中学校第1学年 数学科 桐生市立川内中学校 小倉 隼人
1 単元名 1次方程式
2 章の目標
(1)方程式を解くことを通して、式を形式的に操作して解を求めることができることのよさと
等式の性質が式変形の根拠になっていることを理解させる。
(2)文章題を通して、方程式の有用性を知らせ、方程式を用いることができるようにさせる。
3 学習計画(全 16 時間予定)
時 学習活動 指導上の留意点及び支援 評価項目【観点】(方法)
1 ・とびらの問題をもとに、ペットボトルの ・数量の関係を文字を用いた等 ○キャップの個数の求め
キャップの個数の求め方をいろいろと考え 式で表現できるようにする。 方を様々な視点から考え
る。 ・言葉の式で考えさせてから文 ている。【関心・意欲】
字式で表せるようにする。
2 ・方程式とその解、及び方程式を解くこと ・等号「=」を使った式は、左 ○方程式とその解につい
3 の意味を知る。 辺と右辺の相当関係を示してい て理解している。
・方程式の解を、文字にいろいろな値を代 ることを理解できるようにす 【知識・理解】
入して求める。 る。 ○等式の性質について理
・等式の性質を理解する。 ・方程式の文字に数を代入し 解している。
・等式の性質を使って、簡単な方程式を解 て、その数が解であるかどうか 【知識・理解】
く。 を考察できるようにする。
・等式の性質を利用した1元1
次方程式の解き方を理解できる
ようにする。
4 ・移項の意味を知り、その考え方を使って ・1元1次方程式の解き方を、 ○移項が等式の性質をも
5 方程式を解く。 等式の性質と関連付けて考察で とにしていることを理解
・基本的な方程式を解くときの手順を理解 きるようにする。 している。【知識・理解】
する。 ・移項によって形式的に解ける ○移項を使って、基本的
ことを理解できるようにする。 な方程式を解くことがで
きる。【表現・処理】
6 ・かっこを含む、小数係数、分数係数の方 ・等式の性質をもとに、複雑な ○いろいろな方程式を、
7 程式などの、いろいろな方程式を解く。 方程式の解き方を考察できるよ 手順に従って解くことが
・一般的な方程式の解き方の手順を確認す うにする。 できる。【表現・処理】
る。 ・間違えやすい箇所を確認しな
・一次方程式の意味を知る。 がら解き方を理解できるように

- 学力C 6 -
・解の値をもとに、方程式の係数を求める。 する。
8 ・基本の問題に取り組む。 ・T2と連携し、方程式の解き ○基本的な問題が解け
方を全員が理解できるようにす る。【表現・処理】
る。
9 ・数量の間の関係を、方程式で表すときの ・具体的な事象の中の数量の相 ○数量の関係から方程式
10 手順に従って、方程式をつくる。 等関係をとらえられるようにす をつくることができる。
11 ・具体的な問題を、方程式を利用して解決 る。 【数学的な見方・考え方】
する。 ・1元1次方程式を立式できる ○求めた解が題意に合っ
・求めた解が、題意に合っているかどうか よう言葉の式を立ててから文字 ているか考察することが
を考える。 を用いた式で表せるようにす できる。【見方・考え方】
・数量の間の関係を方程式であらわすとき る。
の手順をまとめる。 ・数量の相等関係を表や図を用
いて表せるようにする。
12 ・道のり・速さ・時間の問題に取り組む。 ・小グループを設定し、なぜ与 〇等式のχの意味を理解
本 えられた等式になるのかを全員 し、説明し伝え合う活動
時 が説明できるようにする。 を通して考察することが
・意図的な話し合いを通して、 できる。【見方や考え方】
問題を考察できるようにする。
13 ・基本の問題に取り組む。 ・問題を解く流れを確認しなが ○基本的な問題が解ける
ら進めていく。 【表現・処理】
14 ・比例式の意味とその性質を理解する。 ・既習の比例式と比較しなが ○比例の関係から比例式
15 ・比例式の性質を利用して、文字の値を求 ら、解き方を理解できるように をつくることができる。
める。 する。 【知識・理解】
・具体的な問題について、比例式の性質を ・方程式に帰着して考察できる ○数量の関係から比例式
利用して方程式をつくり、解決する。 ようにする。 をつくることができる。
・数量の相等関係を比例式で表 【見方・考え方】
せるよう、言葉の式と比較しな
がら考察できるようにする。
16 ・章の問題に取り組む。
4 本時
(1)ねらい
道のり・速さ・時間の問題について、いろいろな等式を用いて解くことを通して、等式の
χの意味を理解し、考え方を説明することができる。
(2)授業改善の視点
課題解決場面において、ジグソー学習を取り入れたことは、生徒相互の数学的な思考力や
表現力を伸ばすのに有効であったか。
(3)準備

- 学力C 7 -
◇等式のχの意味を理解し、それぞれ
の考え方を説明することができる 【見方・考え方】
ワークシート、ホワイトボード
(4)展開
学習活動 時間 指導形態 指導上の留意点及び支援・評価
◎努力を要する生徒への支援 ◇評価
1.導入 5 4名×7班
・本時の学習課題を確認する。
2.エキスパート学習 10 8~ 11 名 ◎1人では課題解決が不安だと思われる
・A、B、Cのどの式にするか ×3班 生徒には2人でエキスパート学習に参加
決め、各班のA、B、Cを解く するよう促す。
メンバーで集まる。 〇各エキスパート学習のなかで、何をχ
①3人が作った式がそれぞれ何 としているのかを明らかにさせ、考え方
をχとしているのか考える。 や理由を説明できるようにする。
②方程式を解く。 〇考え方をわかりやすく説明できるよう
③自分たちの考えをワークシー に書き出すよう促す。
トに記入する。 〇 T2 と連携し、各エキスパート班に必
A あきこさんが作った式 要に応じて支援をする。
60(x + 6)= 80x 〇方程式の解がどんな数量なのかを考え
B はやとさんが作った式 させることで、自分たちの考え方を深め
60x = 80(x - 6) たり、説明しやすくさせたりする。
C ともゆきさんが作った式 〇理解できた生徒は積極的に他の生徒に
x=x + 6 教えたり、自分たちの考え方を確認
60 80 し合ったりするよう促す。
3.ホーム学習 15 4名×7班 〇3つの考え方を交流し、それぞれの考
・エキスパート学習で得た考え え方を理解できるようにする。
を交流する。 〇他のメンバーの説明を理解できたか確
・以下の課題を解決する。 認するために、説明を聞いた生徒に説明
①「2人が学校に着いた時刻」 させる。
を求める。 ◎ T2 と連携し、うまく説明できない生
②「家から学校までの距離」を 徒には、順序立てて説明するよう促す。
求める。 〇速さを求める問題を出題することで、
③「母親の自転車の速さはどれ 今までの学習で得た情報を活用すれば解
くらいか」を求める。 決できることに気づけるようにする。
「み・は・じの問題をマスターしよう」

- 学力C 8 -
8073
512
事後
事前
4.クロストーク学習 15 4名×7班 〇ホーム学習で解いた結果を学級全体で
・ホーム学習で出た結果をホワ 共有することで、多様な思考を学び理解
イトボードに記入し、各班の結 を図れるようにする。
果と比較、考察する。
5.振り返り・まとめ 5 4名×7班 〇アンケートを用いて本時の学習を振
り返られるようにする。
(5)ジグソー学習の様子
<エキスパート学習の様子①> <エキスパート学習の様子②>
<ホーム学習の様子> <クロストーク学習の様子>
5 結果
(1)質問紙調査
ジグソー学習の事前と事後に、生徒に4件法での質問紙調査を行った。以下にその結果を
示す。(数値は人数の値である)
( あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない )
(1)グループの話し合いで、友達の意見と自分の意見を比べながら聞くようにしている。

- 学力C 9 -
7868
717
事後
事前
7565
1020
事後
事前
8073
512
事後
事前
6956
1629
事後
事前
6756
1829
事後
事前
(2)グループの話し合いをしているうちに、自分の考えがはっきりしてくることがある。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・自分の考えを友達に説明したら、考えをより明確にすることができた。
・友達の意見がとてもためになり、解くことができた。
(3)グループで話し合いをしていると、自分の考えがまとまることがある。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・最初はわからない問題でも、友達の意見を聞きわかるようになった。
・ひらめかなかったことも、話し合いの中で「そうだったのか」と納得できた。
(4)グループの話し合いで、友達の意見を聞いて自分の意見を考え直すことがある。
(5)グループの話し合いで、積極的に自分の意見を発表するようにしている。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・普段はできる人に任せていたけど、「やらなきゃ」と思った。
・積極的に意見交換ができた。わからなくてもみんなが助けてくれた。
・1人1人が自分の考えを言っていた。
(6)グループの話し合いで、相手にわかりやすく自分の考えを伝えるようにしている。

- 学力C 10 -
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・好き。いろんな考え方がわかるし、自分の考えも発表できて楽しい。
・みんなで意見を出し合わないと解けないから協力できる。
・図を使って説明してくれたのでわかりやすかった。
(2)コンセプトマップ
※「方程式」は新出ワードが少ないため、「比例と反比例」において作成した。
28 人中 ワードとワードをつなぎ、つながりの意味を付加できる。<十分満足> 17 人
28 人中 ワードとワードをつなぐことができる。<おおむね満足> 11 人
図1 ワードとワードをつないだマップ 図2 つながりの意味を付加したマップ
図3 発展的なマップ 図4 他分野でのマップ
6 成果と課題 ( ○成果 ●課題 )
(1)ジグソー学習の効果
生徒への質問紙調査の結果をもとに、肯定的な回答に変容した人数をみると、(1)は7人、
(2)、(3)は 10 人、(4)は7人、(5)は 13 人、(6)は 11 人の増加とすべての項目におい
て大きな変化が見られた。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(5)の結果から、「積極的に自分の意見を発表する」こ
とについて効果があった。ジグソー学習によるホーム学習において、生徒が異なる内容を説明
する場面を意図的に設定したことで、話し合い活動に積極性が増したと考えられる。

- 学力C 11 -
・変容した生徒の感想から、「普段はできる人に任せていたけど、やらなきゃと思った。」、「積
極的に意見交換ができた。わからなくてもみんなが助けてくれた。」があった。生徒一人一人
に責任感をもてるよう役割分担したことが、積極性の増加につながったと推察される。さらに、
問題の難易度をやや高めに設定し、協力して一つの問題を解くよう設定したことで、話し合い
活動が活性化され、積極性の増加の要因となったと考えられる。
○肯定的な回答への返答が顕著だった(6)の結果から、「相手に分かりやすく考えを伝える」
ことについて効果があった。ジグソー学習による意図的な話し合いは、相手を意識した活動と
なったと考えられる。
・変容した生徒の感想から、「好き。いろんな考え方がわかるし、自分の考えも発表できて楽し
い。」、「みんなで意見を出し合わないと解けないから協力できる。」、「図を使って説明してく
れたのでわかりやすかった。」があった。役割分担をした生徒が、自分の考えを相手に伝えな
くてはいけないという責任感から、わかりやすい言葉や伝わりやすい図を用いて説明したこと
が推察される。
●事前におけるホームグループの構成メンバーの工夫が必要である。
・数学は学力差の大きい教科であるため、ホームグループの学力に偏りがあるとホーム学習で話
し合いが深まらず、学習に支障をきたす恐れがある。学力が高いグループであるとすぐに問題
を解決し、逆に学力が低いグループは何も解けずに終わってしまうことがある。ジグソー学習
の話し合いを深めるうえで、ホームグループの能力差を均等にすることが必要である。
●ジグソー学習の形態だけにとらわれず、教師側がエキスパート学習、ホーム学習、クロストー
ク学習での目的を明らかにして取り組むことが必要である。
・ジグソー学習の形態だけを意識してしまうと、学習形態にこだわりすぎて、授業のねらいとず
れてしまうことがある。また、毎時間ジグソー学習を取り入れることは事前準備等に時間がか
かり難しい。生徒の実態や適切な単元を明らかにし、数学という教科の特性を生かした題材選
びが必要である。
(2)思考力・判断力・表現力の育成
○コンセプトマップを単元の終末に取り入れた。図1と図2を比較する。図2は、図1に比べ関
連するワードの数、また1つのワードから結ばれる線の数が多い。さらに、ワードとワードを
結ぶ線につながりの意味が付加されており、図2は、図1よりも思考の深まりが見られたと考
えられる。
○図3のように、キーワードを比例・反比例に分け、それぞれのつながりを考え、まとめる発展
的なマップを作成する生徒も見られた。二分したコンセプトマップをかくことで、生徒は、自
身の思考の深まりを実感できメタ認知につながったと考えられる。さらに、図4は、他分野の
ワードについても自主的にコンセプトマップを作成し考えをまとめる生徒もいた。生徒は、思
考の広がりを意識し、新しい知識を既習の知識に結びつきを見出したと考えられる。
●コンセプトマップにおいて、「おおむね満足」から「十分満足」と変容させるためには、振り

- 学力C 12 -
返りの時間を十分確保し、普段の授業から計算の仕方だけでなくワードの理解を定着させると
ともに、ワードとワードを比較・分類してつながりを意識しながら復習するよう促す必要があ
る。
●単元や分野によって新出するワードの数が大きく変化する。関数や図形の学習など、ワードが
たくさん新出する単元や分野においては有効である。しかし「式と計算」分野など、主に計算
の仕方を学ぶ場面においては、新出するワードが少ないため、あまり効果を得られない。適切
な単元や分野で取り入れていくことが望ましい。
(3)言語活動の活性化
○肯定的な回答への変容が顕著だった(2)の結果から、「自分の考えがはっきりしてくる」こ
とについて効果があった。ジグソー学習によるエキスパート学習やホーム学習における意図的
な話し合いが、生徒相互の考えをより明確にしたと考えられる。
・変容した生徒の感想から「自分の考えを友達に説明したら、考えをより明確にすることができ
た。」や「友達の意見がとてもためになり、解くことができた。」とあった。話し合い活動に
おいて、説明する側・聞く側の双方に有効であると考えられる。あいまいな自己の考えは、他
の生徒に説明できないため、自己の考えを再構成することにつながり、また、他の生徒の考え
を聞くことで、あいまいな自己の考えと照らし合わせ、自己の考えを再構成することにつなが
ったと推察される。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(3)の結果から、「自分の考えがまとまる」ことについ
て効果があった。ジグソー学習によるエキスパート学習やホーム学習で、他の生徒の説明を聞
くことで、新たな気付きを生み、自己の考えを発展させたと考えられる。
・変容した生徒の感想から「最初はわからない問題でも、友達の意見を聞きわかるようになった。」
や「ひらめかなかったことも、話し合いの中で「そうだったのか」と納得できた。」とあった。
意図的な話し合い活動において、自分の考えとは異なる新しい考えや類似している考えを判断
しながら自分の考えを再構築したと推察される。
●表や図を用いた数学的な説明する力を身に付けるため、普段の授業から意識して伸ばす必要が
ある。
・生徒の感想には「うまく伝えられなかった」、「説明するのが難しかった」とあった。言葉だ
けで自分の考えを伝えるのには多くの時間を要する。数学的な説明する力をつけるため、視覚
的に捉えやすい表や図を活用してわかりやすく伝えるための手段として効果的に用いることが
できるような場面を増やしていく必要がある。
●筋道立てて説明する力を身に付けるため、説明する場面を多く設定するなど、継続的な指導が
必要である。
・生徒にとって「○○だから▲▲」や「○○の根拠は▲▲だ」など筋道を立てて説明する力は、
身に付けることが困難であることが多い。エキスパート学習で備えた情報を、伝達するだけの
ホーム学習に陥りやすい。普段の授業の中で根拠となる事柄を問うよう発問を工夫したり、ヒ
ントカードを取り入れたりして説明する力を養っていく必要がある。

- 学力C 13 -
<実践例②> 中学校第1学年 理科 桐生市立清流中学校 加藤 絵美子
1 単元名 身のまわりの物質 ~第3章 水溶液の性質~
2 章の目標
物質が水に溶けるようすの観察を行い、水溶液の中では物質が均一に分散していることを見い
ださせ、その現象を粒子のモデルで説明できるようにするとともに、再結晶の実験を行い、水溶
液から溶質を取り出すことができることを溶解度と関連づけてとらえさせる。
3 学習計画(全7時間予定)
時 学習活動 指導上の留意点及び支援 評価項目【観点】(方法)
1 ・身の回りで水に溶けているも ・物質が水に溶ける様子や、 ・物質が水に溶ける様子
のにはどのようなものがあるか 溶けた後のゆくえについて考 を調べ、結果をわかりや
を話し合う。 えさせる。 すくまとめることができ
・物質が水にとけることについ る。
て確かめる実験を行う。 【技能】(ワークシート)
2 ・固体の物質が水に溶けていく ・物質が水に溶けている様子 ・固体の物質が水に溶け
ようすについてまとめる。 について、粒子のモデルを用 ていく様子を、粒子のモ
・コーヒーシュガーが水に溶け いて、考えさせる。 デルを用いて説明できる。
る様子について説明を聞く。 【思考・表現】(ワークシート)
3 ・水溶液とは何か、純粋な物質、・溶質、溶媒、溶液の定義を ・純粋な物質や混合物に
混合物についての説明を聞く。 押さえ、純粋な物質と混合物 ついて、例を挙げて説明
・溶液の濃度について説明を聞 を区別ができるようにする。 できる。
く。 【知識・理解】(観察)
4 ・溶液中の溶質の割合によって ・濃度に関する例題をいくつ ・質量パーセント濃度を
濃度を表すことができることを か挙げ、問題を解くことがで 計算し、水溶液の濃度を
確認する。 きるようにする。 求めることができる。
・示された課題について、「例 【技能】(ワークシート)
題」を確認しながら考える。
5 ・水溶液から溶質をとり出す実 ・水溶液から物質をとり出す ・実験結果から、水に溶
験を行う。 には、水を蒸発させる以外に、ける物質の量には、水の
どのような方法があるか考え 量や水の温度によって限
させる。 界があることを説明でき
る。
【思考・表現】(ワークシート)
6 ・結晶と再結晶、飽和水溶液と ・飽和水溶液や溶解度は、つ ・物質によって溶解度が
溶解度の説明を聞く。 まずきやすい内容なので、丁 異なることを理解してい
寧に説明する。 る。

- 学力C 14 -
・実験で行った再結晶が、溶解 ・溶解度、飽和水溶液、
度によって起きる現象である説 結晶、再結晶について理
明を聞く。 解している。
【知識・理解】(観察)
7 ・6つの水溶液の種類を調べる ・身近な水溶液を使い、水溶 ・実験結果をわかりやす
本 実験を行う。 液の種類を調べる方法を考え く説明し、水溶液の種類
時 させ、ジグソー学習を用いて を推測することができる。
分析する。 【思考・表現】
(ワークシート・発表)
4 本時
(1)ねらい
水溶液の性質を調べる実験を通して、水溶液の種類を推測することができる。
(2)授業改善の視点
課題解決の場面において、ジグソー学習を取り入れたことは、生徒相互の科学的な思考力
や表現力を伸ばすのに有効であったか。
(3)準備
実験道具・・水溶液(塩酸、アンモニア水、食塩水、砂糖水、炭酸水、水道水)、
BTB溶液、蒸発皿、ガスコンロ、金網、硝酸銀溶液、スポイト、ビーカー、
試験管、安全眼鏡、ゴム手袋
その他・・・ワークシート、ホワイトボード、マジック
(4)展開
学習活動 時間 指導形態 指導上の留意点及び支援・評価
1.導入 5 3名× 11 班 〇見通しを持って学習に向かえるよ
〇本時の学習課題を確認する。 うに、学習のめあて及び学習の流れ
「6つの水溶液の種類を当てよう」 を提示する。
〇本時の活動の流れを知る。
2.エキスパート学習 15 実験①・③ 〇わかりやすく結果を伝えるため
〇実験からわかることを確認しあ 4名×2班 に、机間指導の中でアドバイスを与
う。 3名×1班 える。
実験①:BTB溶液を加えたときの 実験② 〇サイエンスドクターと連携し、各
色の変化 11 名×1班 エキスパート班に必要に応じて支援
実験②:水を蒸発させたときの変化 をする。
実験③:硝酸銀溶液を加えたときの
変化
3.ホーム学習 15 3名× 11 班 〇相手が実験内容を理解しやすいよ
〇ホーム班に戻り、エキスパートで うに、必要に応じて実験結果を提示
得たことを説明し合い、ワークシー しながら説明するようアドバイスを

- 学力C 15 -
トに記入する。 する。
〇課題の解答を考え、ホワイトボー 〇サイエンスドクターと連携し、説
ドにまとめる。 得力のある説明をさせるために、机
間指導の中でアドバイスを与える
4.クロストーク学習 10 〇自分のグループの考えと比較する
〇各班で出した解答とそう考えた根 ために、共通点や相違点を意識しな
拠を説明し合う。 がら聞くように説明する。
5.振り返り・まとめ 5 〇学習した内容を確認するために本
〇自己評価と感想をワークシートに 時の学習を振り返って評価させる。
記入する。
(5)ジグソー学習の様子
<エキスパート学習・実験①の様子> <エキスパート学習・実験②の様子>
<エキスパート学習・実験③の様子> <クロストーク学習の様子>
評価
・実験結果をわかりやすく説明
し、水溶液の種類を推測すること
ができる。【科学的思考・表現】

- 学力C 16 -
5 結果
(1)質問用紙調査
ジグソー学習の事前と事後に、生徒に4件法での質問紙調査を行った。以下にその結果を
示す。(数値は人数の値である)
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・友達の意見と自分の考えが似ているところや、全く違うところがあって楽しかった。
・実験後、一人一人の意見をちゃんと聞いて、自分の考えと、いつもよりは比べられた。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・班に戻り、報告し合い、自分の知らなかったことがわかったりして楽しかった。
・他の班の人の意見も聞けて、とてもためになるし、自分の考えにもつながるので良いと思っ
た。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・みんなの意見を聞いて、自分の考えがまとまったのが良かった。

- 学力C 17 -
・他の班の人の意見は、みんな同じではないし、予想も違っているので、その理由から自分の
考えを変えたり、考えることができた。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・自分の考えだけでなく、他の子の意見も聞いて「確かにそうかも」と考え直すことができた。
・いつもと違うメンバーで実験し、他の子の意見が聞けたので、いつもと違う考え方ができた。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・班の中でその課題をやるのは、自分だけという責任感を持ってがんばれた。
・いつもは頭がいい人がいるので、自分の意見が言えなかったけど、自分の役割で色々と意見
を言うことができて良かった。
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・役割を決めて、自分の調べた結果や意見をわかりやすく言うのが少し難しかった。
・班に伝えるとき、見ていたのは自分だけなので、説明する力がつくと思った。

- 学力C 18 -
・グループの人に伝わりやすいように、言葉などを考えて発表した。
(2)コンセプトマップ
33 人中 ワードとワードをつなぎ、つながりの意味を付加できる。<十分満足> 12 人
28 人中 ワードとワードをつなぐことができる。<おおむね満足> 13 人
図1 ワードとワードをつないだマップ 図2 つながりの意味を付加したマップ
6 成果と課題 ( ○成果 ●課題 )
(1)ジグソー学習の効果
生徒への質問紙調査の結果をもとに、肯定的な回答に変容した人数を見ると、(1)は5人、
(4)は1人の増加と、あまり変化は見られなかった。また、(2)、(6)は7人の増加、(3)
は 11 人の増加、(5)は 12 人の増加と、大きな変化が見られた。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(5)の結果から、「積極的に自分の意見を発表する」こ
とについて効果があった。ジグソー学習によるホーム学習において、話す内容が生徒により異
なるよう意図的に話し合い活動をしたことで積極性が増したと考えられる。
・変容した生徒の感想から、「班の中でその課題をやるのは、自分だけという責任感を持ってが
んばれた。」、「いつもは頭がいい人がいるので、自分の意見が言えなかったけど、自分の役割
で色々と意見を言うことができて良かった。」があった。責任感をもてるよう役割分担したこ
とで、積極性の増加につながったと推察される。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(6)の結果から、「相手にわかりやすく考えを伝える」
ことについて効果があった。ジグソー学習による意図的な話し合いは、相手を意識した活動と
なったと考えられる。
・変容した生徒の感想から、「班に伝えるとき、見ていたのは自分だけなので、説明する力がつ
くと思った。」、「グループの人に伝わりやすいように、言葉などを考えて発表した。」があっ
た。役割分担した生徒は、相手に伝える必要性を感じ、わかりやすい表現や言葉を考えて交流
したことが推察される。
●ホーム学習の話し合い活動において、わかりやすく表現できない生徒への支援が必要である。
変容した生徒の感想から「役割を決めて、自分の調べた結果や意見をわかりやすく言うのが少

- 学力C 19 -
し難しかった。」があった。役割分担し、相手が知らない情報を伝えることで、負担と感じる
生徒がいた。伝える情報を視覚的にとらえられるよう画像等を用意したり、情報の内容を精選
したり、ペアで取り組ませるなど、丁寧な配慮が必要である。
●エキスパート学習における担当以外の情報や実験の扱いについての配慮が必要である。
質問紙調査より「自分が担当した実験も楽しかったが、他の実験もやってみたかった。」とい
う意見があった。相手が実験内容を理解しやすいように、必要に応じて実験結果を提示しなが
ら説明するよう指導したが、生徒にとっては実際に操作したり、体験したことを上手に伝えた
りすることは困難であった。さらに他の手立ても必要である。
(2)思考力・判断力・表現力の育成
○コンセプトマップを授業の終わりに毎時間活用することで、既習事項に新しい知識を付加して
いった。授業を振り返り、新しいワードを結びつけ、つないだ理由を記入していくかを考える
ことで、既習の知識に新しい知識が結びつき、メタ認知につながった。知識の結びつきを意識
し、授業を振り返ることで、思考力・判断力・表現力を高めていくことができたと考えられる。
●コンセプトマップにおいて、「おおむね満足」から「十分満足」と変容させるためには、振り
返る時間を十分確保し、ワードとワード、知識と知識のつながりを意識しながら復習するよう
促していかなければならない。また、ワードが少なく、つながりが広がらなかった生徒を「お
おむね満足」に変容させるには、机間指導の中で個別の細かな支援が必要である。
(3)言語活動の活性化
○肯定的な回答への変容が顕著だった(2)の結果から、「自分の考えがはっきりしてくる」、
ことについて効果があった。ジグソー学習によるホーム学習における意図的な話し合いが、役
割分担され、未知の情報を伝え合うことで自己の考えを明確化できたと考えられる。
・変容した生徒の感想から「班に戻り、報告し合い、自分の知らなかったことがわかったりして
楽しかった。」、「他の班の人の意見も聞けて、とてもためになるし、自分の考えにもつながる
ので良いと思った。」が述べられている。未知の情報を獲得し、情報を咀嚼し、自己の考えを
再構成していることが推察される。役割分担した言語活動は、生徒にとって情報の共有化を促
し、自己の考えを明確化することができたと考えられる。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(3)の結果から、「自分の考えがまとまる」、ことにつ
いて効果があった。ジグソー学習によるエキスパート学習において、他班の意見から自己の考
えを直したり、新しい考え方を発想したりすることで自己の考えを再構築できたと考えられる。
・変容した生徒の感想から、「他の班の人の意見は、みんな同じではないし、予想も違っている
ので、その理由から自分の考えを変えたり、考えることができた。」が述べられている。意図
的に他班との交流を通して、自己と異なる考えについて比較・検討し、判断しながら自己の考
えに新たな情報を加え、再構築できたと推察される。

- 学力C 20 -
<実践例③> 中学校第2学年 理科 桐生市立梅田中学校 荻野 剛朗
1 単元名 電気の世界 ~第2章 電流と磁界~
2 章の目標
磁石や電流による磁界の観察を行い、磁界を磁力線で表すことを理解して、コイルの周りに磁
界ができることを知る。また、磁石とコイルを用いた実験を行い、磁界中のコイルに電流を流す
と力がはたらくこと、及びコイルや磁石を動かすことによって電流が得られることを見いだすと
ともに、直流と交流のちがいを理解する。これらのことを日常生活と関連づけて科学的に考察し
ようとする意欲と態度を養う。
2 学習計画(全 12 時間予定)
時 学習活動 指導上の留意点及び支援 評価項目【観点】(方法)
1 ・小学校で学習したことを確認す ・磁力や磁界、磁界の向き ・電流と磁界の関係に関心
る。 についての用語を押さえ、 をもって学習している。
・電磁石のまわりの磁界について 意味を区別させる。 【関心・意欲】(観察)
調べる。
2 ○磁界のようす ・磁界の向きについて確認 ・磁界のようすを磁力線で
・鉄粉などを用いて、棒磁石と電 し、N→Sに向かってたど 表すことができる。
磁石のまわりの磁力線や磁界の向 らせる。磁界は立体的にと 【技能】(ノート)
きについて調べる。 らえさせる。
3 ○電流がつくる磁界 ・1 本の導線のまわりにで ・目的意識をもって、コイ
・コイルの周りにできる磁界を観 きる磁界をもとに、コイル ルのまわりの磁界を調べ、
察し、磁界の向きと電流の向きと の磁界を考えさせる。 結果をまとめられる。
の関係について、結果をまとめる。 【技能】(ワークシート)
4 ○磁界の中の電流が受ける力 ・予想させながら磁石の向 ・磁界の中で電流が受ける
・磁界の中に置いた導線に電流を き・電流の向きを変えるこ 力について、予想と実験の
流し、磁石の磁界の向きと、導線 とで、力の向きを変える要 結果を比べることができ
に流れる電流の大きさと向き、導 素になっていることに気づ る。
線の動き方との関係について、結 かせる。 【思考・表現】(観察)
果をまとめる。
5 ○フレミングの左手の法則 ・磁界、電流、力の3つの ・モーターが回転するしく
・磁界の向き、電流の大きさと向 向きを確認しながら規則性 み、逆回転するしくみを理
き、電流にはたらく力との関係に があることに気づかせる。 解できる。
ついて理解する。 【知識・理解】(ノート)
・モーターのしくみを理解する。
6 ○モーターを回転したときに発生 ・手回し発電機どうしをつ ・磁界の中でコイルを動か
する電流 ないで、一方を回すと他方 すことによって、電流がつ

- 学力C 21 -
・磁界の中でコイルを動かすと電 も回ることから、モーター くられることに関心をもっ
流がつくられることを理解する。 が発電機に成り得ることを て聞いている。
・発電機のしくみを理解する。 示す。 【関心・意欲】(観察)
7 ○コイルと磁石で電流をつくる ・コイルを動かすことと、 ・どのようにしたら電流を
・コイルに磁石を出し入れすると 磁石を動かすことは、相対 流し続けることができる
きの速さや向き、コイルの巻き数 的に同じ運動であることを か、その方法を見つけるこ
によって流れる電流がどうなるか 確認する。 とができる。
を調べる。 【技能】(ワークシート)
【思考・表現】(発表)
8 ○電磁誘導の条件 ・コイル内部の磁界の変化 ・電磁誘導が生じる条件、
・電磁誘導が生じる条件、誘導電 を打ち消す方向(安定方向)誘導電流の向きや大きさを
流の向きや大きさを決める条件に に誘導電流が流れることを 変える条件を、コイル内部
ついて理解する。 押さえる。 の磁界の変化と関連づけて
説明できる。
【知識・理解】(ノート)
9 ○電磁調理器のしくみ ・ジグソー学習を用いてヒ ・既習事項をもとに電磁調
本 ・既習事項をもとに、電磁調理器 ントを与え、クロストーク 理器(IH)のしくみを考え、
時 (IH)のしくみを解き明かす。 学習によって考察を練り上 理論立てて説明できる。
げさせる。 【思考・表現】(ワークシート)
10 ○直流と交流 ・乾電池・発電機のしくみ ・直流と交流のちがいを理
・乾電池とコンセントの電流のち のちがいをもとに、それぞ 解し、用途を区別すること
がいを理解する。 れ直流・交流電源になるこ ができる。
・発光ダイオードの点灯の仕方の とを説明する。 【知識・理解】(観察)
ちがいを観察する。
11 ○家庭に電気が届くしくみ ・変電所や変圧器を使うこ ・これまでの学習と家庭で
・国内に周波数の異なる地域があ とによって電圧を変えられ 使われている電気について
ること、交流の利点を理解する。 る交流の利点を紹介する。 関心をもって聞いている。
【関心・意欲】(観察)
12 ○クリップモーターをつくろう ・一人で一つのモーターを ・意欲的にモーター作りに
・桐工出前授業を受講し、自分で 作り上げて、達成感を味合 取り組んでいる。
モーターをつくる。 わせる。 【関心・意欲】(観察)
3 本時
(1)ねらい
電流と磁界が互いに及ぼしあう関係(既習事項)をもとに、電磁調理器上の豆電球が光る
しくみ(導線に電流が流れるしくみ)を説明することができる。
(2)授業改善の視点
課題解決の場面において、ジグソー学習を取り入れたことは、生徒相互の科学的な思考力

- 学力C 22 -
や表現力を伸ばすために有効であったか。
(3)準備
電磁調理器(IH:induction heating)、豆電球、導線、IH 内部写真、電磁誘導式懐中電灯、
コイル、手回し発電機、プロペラモーター、ホワイトボードセット、ワークシート
(4)展開(実験構成型ジグソー学習)
学習活動 時間 指導形態 教師の留意点及び支援・評価
1.導入 10 ホーム ○豆電球には一本の導線が輪になってつ
○電磁調理器(以下 IH)の上に置 グループ ながっているだけで、電源がついてない
いた導線付き豆電球が光る様子 ことを確認する。
を見る。 4~5人 ○豆電球と導線を卓上から浮かすこと
・IH から電流が流れてきている ×6班 で、電磁調理器から豆電球へ直接電流が
のかな 一斉指導 流れ込まないことに気づかせる。
・導線を IH の卓上から浮かし ○時間をかけないよう個人で予想させ、
ても豆電球が光っているぞ 口頭で発表させる。
○本時の目標を知り、その場で
自分なりの予想を考える。
2.エキスパート学習 10 エキスパート ○エキスパート学習が課題の手がかりに
A.電磁調理器の構造は? グループ なることを示唆する。
B.コイルがつくる磁界とは? ○サイエンスドクター(以下:SD)と
C.電磁誘導が起こるには? 6~7人 分担して支援する。
D.交流電流とは? ×4班 A班:SD B班:生徒のみ
C班:荻野 D班:荻野
○各班に手がかり書を用意し、各班への
課題を明確にする。
3.ホーム学習 15 ホーム ○ホームグループに持ち帰った情報は、
○エキスパート班で得た情報を グループ 単に資料を見せ合うのではなく、担当者
互いに説明し合う。 4~5人 が自分のワードで説明するよう指示す
○豆電球が光る原理を話し合い、 ×6班 る。
その説明をホワイトボードに書 ○ホワイトボードにコイルの模式図を挿
く。 入しておき、他の班へ説明するときに混
乱しないよう、電流を青、磁界を赤で書
き表すよう統一を指示する。
○ヒントとして、豆電球を持ち上げると
光が弱くなっていくことから、磁界の範
囲と影響を考えさせる。
なぜ電磁調理器上の豆電球は光りつづけるのか?

- 学力C 23 -
4.クロストーク学習 10 ○解明が難航している場合は、他の班と
○グループで考えた説明を発表 の意見交流を行うことで、気づきの機会
する。 を与える。
・二人組で巡回発表、または代 ○速やかに解明できた場合は、全体発表
表者が全体へ発表 を行う。同じ考え方のものをくくり、異
なる考え方ごとに発表させる。
5.まとめ 5 ○電熱線を例に、抵抗がある金属は発熱
○IHのしくみを確認する。 することを想起させる。電磁調理器では
誘導電流によって、金属の鍋自体が発熱
することを押さえる。
○次時で確認することを伝える。
※本時は1時間扱いで構成しているが、本課題の難易度が高いため1.5時間から2時間扱いでの展開が望ましい。
(5)ジグソー学習のようす
<エキスパート学習で予備課題を追求> <エキスパートA班に指導するSD>
5 結果
(1)質問紙調査
ジグソー学習の事前と事後に、生徒に4件法での質問紙調査を行った。以下にその結果を
示す。
22人
21人
2人
3人
事後
事前
(1)グループの話し合いで、友達の意見と自分の意見を比べながら聞くようにしている。あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない
評価【思考・表現】電流と磁界の関係に基づいて、
順序立てて説明している。(観察・ワークシート)

- 学力C 24 -
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・みんながそれぞれ学んだことを発表できたから良かった。
・みんながそれぞれ違う分野の考えをもってきているから(話しやすい)。
・その事を知っているのが班の中に自分しかいないから(がんばって伝えた)。
19人
20人
5人
4人
事後
事前
(2)グループで話し合いをしているうちに、自分の考えがはっきりしてくることがある。あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない
19人
20人
5人
4人
事後
事前
(3)グループで話し合いをしていると、自分の考えがまとまることがある。あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない
16人
12人
8人
12人
事後
事前
(5)グループの話し合いで、積極的に自分の意見を発表するようにしている。あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない
20人
18人
4人
6人
事後
事前
(4)グループの話し合いで、友達の意見を聞いて自分の意見を考え直すことがある。あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない

- 学力C 25 -
【肯定的な回答に変容した生徒の感想】
・自分的には、みんなにうまく伝えられたと思う。
・人に情報を素早く正確に伝えるのはとても難しいけど、やりがいがあったので良かった。
・正確に班の人に伝えなきゃならないから、間違ってたらみんなに怒られそうで緊張する。
・うまく伝えられなかった。分かりやすく伝えるのが難しい。
(2)コンセプトマップ
24 人中 ワードとワードをつなぎ、つながりの意味を付加できる <十分満足> 11 人
24 人中 ワードとワードをつなぐことができる <おおむね満足> 10 人
図1 ワードとワードをつないだマップ 図2 つながりの意味を付加したマップ
6 成果と課題 ( ○成果 ●課題 )
(1)ジグソー学習の効果
生徒への質問紙調査の結果をもとに、肯定的な回答に変容した人数を見ると、(1)~(3)
は1人の増減、(4)は2人の増加と、あまり変化は見られなかった。また、(5)は4人の増
加、(6)は5人の増加と、大きな変化が見られた。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(5)の結果から、「積極的に自分の意見を発表する」こ
とについて効果があった。ジグソー学習によるエキスパート学習やホーム学習において、話す
内容が生徒ごとに異なるよう意図的に話し合い活動をしたことで積極性が増したと考えられ
る。
・変容した生徒の感想から、「みんながそれぞれ違う分野の考えをもってきているから(話しや
21人
16人
3人
8人
事後
事前
(6)グループの話し合いで、相手に分かりやすく自分の考えを伝えるようにしている。あてはまる・ややあてはまる あまりあてはまらない・あてはまらない

- 学力C 26 -
すい)。」「その事を知っているのが班の中に自分しかいないから(がんばって伝えた)。」があ
った。発表する内容が生徒によりそれぞれ違うことは、生徒にとって担当を任されることとな
り、責任をもってエキスパート学習に取り組んだことが伺える。さらに責任感の増加にともな
って話し合いの積極性の増加につながったと推測される。また、「みんながそれぞれ学んだこ
とを発表できたから良かった。」と生徒の感想にあり、発表した達成感も感得できたことも積
極性の増加につながったと考えられる。
○肯定的な回答への変容が顕著だった(6)の結果から、「相手にわかりやすく考えを伝える」
ことについて効果があった。ジグソー学習による意図的な話し合い活動を2回取り入れたこと
で、わかりやすく伝えることを意識化できたと考えられる。
・変容した生徒の感想から「人に情報を素早く正確に伝えるのは難しいけど、やりがいがある」
とあり、生徒は自分のもってきた情報を班の友だちに「素早く・正確に」伝えようと努力し、
「やりがい」を感じている。ジグソー学習によるエキスパート学習での情報を、担当として友
だちに伝える責任感から正確に伝える必要性を感じさせたことで、わかりやすく伝えようと意
識化できたと推察される。一方で、「間違ってたらみんなに怒られそう」と感想にあり、一部
の生徒の中には、責任感が強すぎて「緊張」と感じたようである。緊張と感じた生徒は、前述
と反対に責任感がプレッシャーになってしまった例である。しかし、正確に伝えようとする意
識は非常に高まっているといえる。
●一人で授業を実施する場合、エキスパート学習における机間支援・指導においてティームティ
ーチングを採用するなど工夫する必要がある。
・エキスパート学習は複数の実験を同時に実施するため、一人で授業を実施する場合、事前準備
と実験中の支援・指導をきめ細かに行うことは困難が予想される。本実践例は、サイエンスド
クターの補助があり、支援・指導をきめ細かに行うことができた。可能な限りティームティー
チングを行える環境があると良い。
(2)思考力・判断力・表現力の育成
○コンセプトマップの完成度が<十分満足できる>生徒の感想から、ジグソー学習に対して「友
達の意見が聞けて楽しかった」「良かった」という肯定的意見が多かった。ジグソー学習を「楽
しい」と答えている生徒は、「自分と友達の意見を比べながら考えるのが楽しい」「自分とは
違う見方・考え方を知るのが楽しい」という理由を述べている。「楽しい」と回答した生徒は、
他者から受け取った情報を頭の中で整理し、どの情報を組み合わせるかを考えて、自分の考え
を再構築する(思考・判断)。次に、新しい自分の考えを班の友達に再提案する(表現)。こ
の繰り返しを無意識に行う習慣がついていると考えられる。この一連の「思考・判断・表現」
の過程を繰り返し発生させるジグソー学習は、思考力・判断力・表現力を育成するために適し
た学習方法といえる。
●コンセプトマップの完成度が<概ね満足できる>生徒の感想から、「班全員がしっかりしてい
ないといけない」「難しかった」という、否定的な意見が見られた。ジグソー学習を「難しか

- 学力C 27 -
った」と答えている生徒は、「班員の情報すべてを理解できなくて、本題を解くのが難しかっ
た」と理由を述べている。つまり、難しかったと感じるのは、受け取るすべての情報を理解し
きれなかったことに起因すると考えられる。聞き手生徒はよく聞いているが、これまでの学習
の理解不足のために話し手の内容が理解できずもどかしさを感じたり、逆に話し手の説明力が
不足しているために不満を感じたりしていることが推察される。コンセプトマップで、理解不
足の聞き手、説明力不足の話し手は、一つのワード(現象)の意味は分かっても、複数の他の
ワード(現象)とはつながらないことが多い。理解不足の聞き手、説明力不足の話し手が、ジ
グソー学習を繰り返し体験することで、複数の情報をつなげて思考・判断・表現する力を身に
付けることが必要であると考える。
(3)言語活動の活性化
○エキスパート学習やホーム学習における言語活動は、エキスパート学習からホーム学習へ持ち
帰る情報が全員違うことに起因し、次の3点の効果が見られた。①友だちの発表内容への関心
を高めること、②安心して発表できる環境が整えられること、③責任感をもち積極的な発言を
促すことに有効であった。
・質問紙調査(1)より、友だちの意見と自分の意見を比べながら聞くことについては、事前も
肯定的な回答が多いが、事後はさらに多い。また「いろいろな意見・考え方を聞けるのが良か
った」という感想が目立った。エキスパート学習からホーム学習へ持ち帰る情報が全員違うこ
とで、友達の発表内容への関心が高まり、交流の活性化につながったと考えられる。さらに、
「みんながそれぞれ違う分野の考えをもってきている」という感想から、周囲の聴く態勢が整
い、安心して発表することができたことも交流の活性化の一因となった可能性がある。また、
「その事を知っているのが班の中に自分しかいない」という感想から、発表する生徒の責任感
は、積極的な発言を促し、言語活動の活性化に役立っていると考えられる。
●「分かりやすく伝えることが難しい」という生徒への支援方法の工夫が必要である。
・ジグソー学習ではないグループ学習では、自分の意見を言うことはほとんどなく、周囲の生徒
の意見についていくだけの生徒が相当する。他者の意見に同調する生徒は、ジグソー学習では
責任という重圧と闘いながらも発表する。発表せざるを得ない状況で、「もっと伝えたい」、「う
まく伝えられるようになりたい」という気持ちを喚起させるため、写真やヒントカードを与え
たり、これだけは伝えてほしいキーワードを提示したりする支援の工夫や、一部ペア活動を取
り入れるような学習形態の改善をするなど、表現することに対しての抵抗感を軽減させること
が必要である。

- 学力C 28 -
Ⅵ 研究のまとめ ( ○成果 ●課題 )
1 ジグソー学習の効果
○話し合い活動において、積極的に自分の意見を発表すること、相手にわかりやすく伝えること
に効果がある。
・ジグソー学習では、役割分担をした生徒が、自分の考えを相手に伝えなくてはいけないという
責任感から、自分の考えや意見を積極的に表現しようとする意欲を高めることができた。また、
ジグソー学習による意図的な話し合いは、相手を意識した活動となり、正確に分かりやすく伝
えようとして表現の工夫を促すことができ、表現力を高めることができた。
●エキスパート学習における担当以外の情報や実験の扱いについて配慮が必要である。
一人の生徒が実際に行う実験は、複数のうちの一つしか行えないことは、ジグソー学習の構造
上避けられない。そのため、実験結果を残し、ホーム学習の時にあとから結果を確認にいける
ような工夫が必要である。
●エキスパート学習の際には、複数の課題や実験に同時に取り組むため、机間支援・指導におい
てティームティーチングを採用するなどの工夫をする必要がある。
2 思考力・判断力・表現力の育成
○コンセプトマップ作成は、知識の結びつきを意識した振り返りを行うことでジグソー学習を保
管することに有効であった。
・ジグソー学習における役割分担型の話し合いは、他者の情報を頭の中で整理し、情報の組み合
わせを考えて再構築(思考・判断)し、再構築した自己の考えを班の友達に再提案する(表現)
活動である。情報の再構築、再提案する活動の繰り返しを無意識に行うことで習慣化され、思
考力・判断力・表現力を高めることができた。
●コンセプトマップの活用は、適切な単元や分野で取り入れることが望ましい。
・単元や分野によって新出するワードの数が大きく変化する。特に数学では、関数や図形の学習
など、ワードがたくさん新出する単元や分野においては有効であるが、「式と計算」分野など、
主に計算の仕方を学ぶ場面においては、新出するワードが少ないため効果を得られないことが
あった。
3 言語活動の活性化
○役割分担型の話し合い活動において、自分の考えをはっきりさせ、自分の考えをまとめること
に効果がある。
・エキスパート学習からホーム学習へ持ち帰る情報が全員違うことによって、友達の説明に関心
を高めて聴くことにつながり、相手の情報と自分の情報とを比べながら考える態度が養われた。
また、ホーム学習においては、学習者は、友達の説明を聴き考えをまとめ、友達に説明をする
ことで自己の考えをまとめる活動となった。聞く側、話す側、双方にとって自己の考えを再構
成することにつながった。

- 学力C 29 -
○役割分担型の話し合い活動において、難易度を高めに設定することで話し合いを活性化させる
ことに効果がある。
・問題の難易度をやや高めに設定して、協力して一つの問題を解くように配慮することで、話し
合い活動に活性化が見られた。さらに、ホーム学習へ持ち帰る情報が異なることも、話し合い
を活性化した一因であった。
●役割分担し相手が知らない情報を伝えることを負担と感じる生徒への配慮が必要である。
伝える情報を視覚的にとらえられるよう画像等を用意したり、情報の内容を精選したり、ペア
で取り組ませるなど、きめ細かな手立てが必要である。
Ⅶ 資料
1 数学におけるジグソー学習題材
<数学におけるジグソー学習の類型>
①知識結合型・・・・・・・複数の情報を持ち寄ってはじめて答えが出るパターン。
②多思考型・・・・・・・・課題への多様な考え方を持ち寄るパターン。
③多思考・知識結合型・・・①・②を合わせたパターン。
(1)数学 1 年
型 本課題 エキスパート課題
② 2章 文字式 A 1+3χ
必要なマッチ棒の本数は? B 4χ-(χ-1)
C χ+(χ+1)+χ
③ 3章 方程式 A 等式の性質2を使う
白玉1個の重さは? B 等式の性質3を使う
C 実際に数を代入しながら見つける
③ 3章 方程式 A 兄が家を出発してから学校に着くまでの時間を
兄弟2人が学校に着いた時刻は何時何分? χとする
B 弟が家を出発してから学校に着くまでの時間を
χとする
C 道のりをχとする
② 3章 方程式 A 姉と妹の比を3:2として考える
姉の折り紙の枚数は? B 姉と全体の比を3:5として考える
C 全体を1とみて考える
③ 4章 比例と反比例 A 対応表を使って求める
コピー用紙全体の枚数を求めよう B 式を使って求める
C グラフを使って求める
① 4章 比例と反比例 A 給水口Aでの時間と水位の関係を表したグラフ

- 学力C 30 -
3つの給水口からプールに水を入れ始 め、B 給水口Bでの時間と水位の関係を表した対応表
何時間後にプールの水位が 150 ㎝になる C 給水口Cでの時間と水位の関係を表した式
か考えよう
③ 5章 平面図形 A 平行移動だけで動かせる位置を見つけ出す
2つの図形をぴったりと重ねるための図形 B 回転移動だけで動かせる位置を見つけ出す
の移動方法を考えよう C 対象移動だけで動かせる位置を見つけ出す
① 5章 平面図形 A 角の二等分線の作図
105 °を定規とコンパスを使って作図しよ B 垂線の作図
う C 正三角形を利用した 60 °の作図
② 7章 資料と活用 A ヒストグラムから値段を設定。理由も述べる
あなたはこの商品をいくらで売りますか? B 平均値から値段を設定。理由も述べる
C 中央値から値段を設定。理由も述べる
D 最頻値から値段を設定。理由も述べる
(2)数学2年
型 本題材 エキスパート課題
② 1章 式の計算 A 左上の数をnとおいて説明させる
カレンダーの秘密を探ろう B 中央の数をnとおいて説明させる
「9日間分の和は、囲んだ中央の数の9倍 C 9つの数の平均で考える
になる」
③ 3章 1次関数の利用 A 文章から式を作る
お客様におすすめのプランを紹介しよう B 文章から表を作る
C 文章からグラフを作る
② 4章 平行と合同 A 1つの頂点から三角形に分割して考える
多角形の内角の和の公式を導こう B 多角形の中央に点をうち、そこにできる三角形の
個数から考える
C 内角の増えていく様子の表やグラフから考える
① 4章 平行と合同 A 3組の辺、3組の角を調べる
2つの三角形が合同であることの条件は何 B 2組の辺と1組の角を調べる
か? C 1組の辺と2組の角を調べる
(3)数学3年
型 本題材 エキスパート課題
② 2章 平方根 A 近似値で調べる
2、 、 の大きさを比べよう B 2乗して調べる
C 面積図を使って調べる

- 学力C 31 -
② 3章 2次方程式 A 平方根の意味にもとづいて解く
2次方程式の解き方をつかもうどのような B 解の公式を使って解く
順で解いたらよいか C 因数分解を使って解く
② 3章 2次方程式 A 対戦表を使って考える
Χ人で握手をすると? B 多角形を使って考える
C 樹形図を使って考える
① 4章 y= ax2 A 変化の割合の公式
なぜ変化の割合は a(p+q)で求められる B 共通因数を含む因数分解
C 分数の約分を含んだ文字式の計算
2 理科におけるジグソー学習題材
<理科におけるジグソー学習の類型>
①実験構成型・・・複数の異なる実験の結果を総合して、課題を追究するパターン
②実験反復型・・・条件を変えた同様の実験を繰り返して、性質や法則を見いだすパターン
③知識構成型・・・得た知識や互いの価値観を総合して、新しい価値観を獲得するパターン
(1)理科1年
型 本課題 エキスパート課題
① 4つの白い粉の正体は何か A 粒の顕微鏡観察・手触り
B 水の溶け方
C 加熱
① プラスチックの正体は何か A 固さ・観察
B 水に浮くか
C 加熱
① 気体の正体は何か(塩素) A 水への溶け方
B 空気との重さ比較(密度)
C 硝酸銀溶液
① 水溶液の種類を当てよう A BTB溶液
B 蒸発
C 燃焼
② ばねののび方を調べよう(フックの法則) A ばねa
B ばねb
C ばねc
① 水蒸気を入れた缶を冷やすとどうなるか、 A 状態変化の体積変化実験
説明しよう。 B 空気の重さを測定
C 逆さ水入りコップ
② 岩石が含む有色鉱物の割合を調べよう。 A 花崗岩

- 学力C 32 -
B 閃緑岩
C 安山岩
(2)理科2年
型 本課題 エキスパート課題
① 火をつけたスチールウールに、酸素を入れ A 燃焼後のスチールウールの質量変化
た集気瓶をかぶせたときの変化を説明しよ B 大気圧の観察
う。 C 減圧と水面の変化(ストロー)
① 二酸化炭素中でマグネシウムが燃焼するの A 空気中でのマグネシウムの燃焼
はなぜか。 B 二酸化炭素中でのスチールウールの様子
C 加熱銅線を水素で還元
③ 体のつくりから進化の順番を考えよう。 A 魚類
B 両生類
C ハチュウ類
D 鳥類
E ホニュウ類
② 直列回路(または並列回路)に流れる電流 A 豆電球1つ
・電圧の関係を調べよう。 B 豆電球2つ
C 豆電球3つ
① 電磁調理器の上に、コイルにつないだ豆電 A 交流電流
球を置くと点灯するのはなぜか。 B 電流による磁界の発生
C 電磁誘導
① 大気圧の働き方を調べよう。(矢印で表す) A 加圧内での袋の変化
B 減圧内での袋の変化
C 紙のせ水コップを逆さまにすると
D 穴あきペットボトルから水を出して途中
でキャップを閉めると
③ 霧のでき方を説明しよう。(発展:川霧) A 地表の温まり方と冷え方
B 飽和水蒸気量と温度の関係
C 露点(凝結)の観察
③ 雲のでき方を説明しよう。 A 空気が上昇する原因
B 加圧と空気(風船)の収縮の関係
C 減圧と空気(風船)の膨張の関係
D 空気の膨張・収縮と温度の関係
② 季節と台風の進路の関係を調べよう。 A 6月の台風(中国大陸へ)
(台風のコースを OHP シートでトレース B 9月の台風(日本列島を縦断コース)
して重ねる) C 11 月の台風(太平洋へ)

- 学力C 33 -
(3)理科3年
型 本課題 エキスパート課題
② 塩酸に水酸化ナトリウムを加えていったと A 水素イオンの数のグラフを考える
きの、水溶液中のイオンの変化を説明しよ B 水酸化物イオンの数のグラフを考える
う。 C 塩化物イオンの数のグラフを考える
D ナトリウムイオンの数のグラフを考える
③ 遺伝子操作(やクローン技術)は、どこま A 絶滅危惧種保護への利用
で許されるか。 B 亡き我が子復活への利用
C 臓器再生医療への利用
D 予備パーツとしての利用
E 新人類創造への利用
② 斜面の傾きと分力の関係を調べよう。 A 緩い斜面
B 45 度の斜面
C 急な斜面
① 道具を使った仕事の大きさを比べよう。 A 定滑車
(仕事の原理) B 動滑車
C てこ
D 斜面
③ 月は自転をしているのか、いないのか説明 A 1ヶ月の月表面の模様比較
しよう。 B 1ヶ月の月の満ち欠け
C 1ヶ月の月の公転
② 地球上の場所による、太陽の見かけの動き A 日本での見え方を透明半球に記録
のちがいはなぜ起こるのか。(春分の日) B ニュージーランド
C 赤道
D 北極
③ 原子力発電は必要か。 A 原子力発電のしくみ調べ
B 原子力発電の長所
C 原子力発電の危険性
D 世界と日本のエネルギー事情調査
E 私達の暮らしと原子力発電の歴史




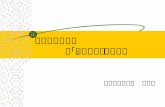










![[思考] 設計思考改變世界](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/55667400d8b42a3d3f8b54b5/-55667400d8b42a3d3f8b54b5.jpg)



