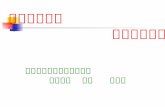視覚障害児童生徒のための 「「音訳教材音訳教材」」製作製作マ … · ヷ...
Transcript of 視覚障害児童生徒のための 「「音訳教材音訳教材」」製作製作マ … · ヷ...
視覚障害児童生徒のための視覚障害児童生徒のための視覚障害児童生徒のための視覚障害児童生徒のための
「「「「音訳教材音訳教材音訳教材音訳教材」」」」製作製作製作製作マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル
日本ライトハウス 発行
平成25年度文部科学省「民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業」
障害のある児童生徒のための教材普及推進事業
視覚障害児童生徒のための視覚障害児童生徒のための視覚障害児童生徒のための視覚障害児童生徒のための
「音訳教材」「音訳教材」「音訳教材」「音訳教材」製作製作製作製作マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル
はじめに 本誌は、視覚特別支援学校(盲学校)、特別支援学校、地域の学校で学ぶ視覚
障害児童生徒が、通常使用している点字・拡大教科書と併用することを目的と
した「音訳教材」の製作・提供方法をまとめたマニュアルです。
教材名になっている「音訳」とは、視覚障害者のための録音資料を製作する
ために生まれた言葉で、印刷物の情報を的確に、音声だけで伝えるための読み
の技術です。「音訳教材」とは、視覚障害児童生徒のために教科書等を音訳し、
デイジー編集したものを指します。
現在、点字・拡大教科書で学んでいる児童生徒の中には、
・発達障害や知的障害等の重複により、点字や墨字だけでは文章の理解が困難
・中途失明や視力低下による点字使用への移行途中のため、点字の触読が困難
・通学している地域の学校や特別支援学校において、視覚障害教育の専門知識
を持つ指導者が配置できないため、点字の読み書きの技能と学力が伸び悩ん
でいる
といったケースが少なくありません。こうした児童生徒の学習における理解を
助けるためのツールの一つが、適切な処理を施した肉声による「音訳教材」で
す。印刷された情報には、文字の装飾(太字、傍線等)や、図、表、グラフ、
写真、絵など、視覚でしか認識できないものが多く含まれます。単純な文字情
報ではないこれらの視覚的情報は、近年発達してきた合成音声では読み上げら
れない、もしくはコンピュータの単一的な読み上げでは理解しにくい情報です。
特に教科書の視覚的情報は、学年・教科の別、児童生徒のニーズによって、内
容の伝えかたに配慮が必要です。
社会福祉法人日本ライトハウスは、平成 25 年度に文部科学省「民間組織・
支援技術を活用した特別支援教育研究事業(障害のある児童生徒のための教材
普及推進事業)」を受託し、「視覚障害児童生徒のための『音訳教材』製作マニ
ュアル」(本誌)と、「デイジー編集された『音訳教材』を使うための取扱説明
書」を作成いたしました。全国の視覚特別支援学校(盲学校)、特別支援学校、
視覚障害者情報提供施設、音訳ボランティアグループなどに配布する他、当法
人のウェブサイトからも提供いたします。どうぞ、広くご活用ください。
なお、本誌に掲載している音訳例は一例に過ぎません。教科、学年、児童生
徒のニーズなどによって音訳方法(読みかた)は異なりますので、あくまでも
参考事例の一つとしてご覧ください。
平成 26 年 3 月 1 日
社会福祉法人日本ライトハウス
1
目次 はじめにはじめにはじめにはじめに・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・1111
音訳とは音訳とは音訳とは音訳とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4444
視覚障害児童生徒のための「音訳教材」とは視覚障害児童生徒のための「音訳教材」とは視覚障害児童生徒のための「音訳教材」とは視覚障害児童生徒のための「音訳教材」とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・5555
音訳教材を作る【音訳編】音訳教材を作る【音訳編】音訳教材を作る【音訳編】音訳教材を作る【音訳編】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7777
1.学年、ニーズに応じた配慮・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8888
(1)スピード・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8888
(2)用語、表現・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8888
(3)間ま
の取りかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8888
2.打ち合わせについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10101010
(1)コーディネーターの必要性・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・10101010
(2)音訳教材の依頼を受けた時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11111111
(3)担当教員との打ち合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11111111
(4)製作ボランティアとの打ち合わせ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12121212
(5)依頼、製作、納品の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12121212
3.見出しの読みかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・13131313
4.分野ごとの読みかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・11115555
(1)古典・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・15151515
(2)英語・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・22222222
(3)数式・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・26262626
(4)化学記号・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・28282828
5.注の読みかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29292929
6.記号などの読みかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・31313131
7.図、表、写真の読みかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32323232
(1)基本的な考えかた・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・32323232
(2)図を説明する時[グラフ、地図、見取り図、流れ図、系統樹]・・・・・・・・・・・32323232
(3)表を読む時・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・38383838
8.デイジーの凡例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39393939
(1)音訳教材の冒頭に入れる凡例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・39393939
(2)各章ごとに入れる凡例・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・40404040
音訳教材を作る【デイジー編集編】音訳教材を作る【デイジー編集編】音訳教材を作る【デイジー編集編】音訳教材を作る【デイジー編集編】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・41414141
1.セクション分割および見出しのレベル(階層)設定・・・・・・・・・・・・・・・・42424242
2.見出しの編集・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44444444
3.ページ付け・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・44444444
個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて個人情報の取扱いについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・45454545 1.児童生徒の個人情報保護・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46464646
2.使って喜ばれる音訳教材を作るために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・46464646
3.製作者の意識を高めるために・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・47474747
3
音訳お ん や く
とは 音訳とは、墨字の出版物を読むことが困難な視覚障害者のために、印刷され
ている情報を適切に音声に置き換えることです。日本全国の視覚障害者情報提
供施設、公共図書館、ボランティアグループなどで提供されている録音資料や
対面リーディングサービスなどに活用されており、視覚障害者への音声による
情報提供においてなくてはならない技術です。音訳をする人のことを音訳者おんやくしゃ
と
呼びます。
毎日、全国の音訳者(ボランティア)により製作されている視覚障害者のた
めの録音資料は、著作権を尊重しながら、録音資料としての一定の品質と機能
を定めた製作基準(※)に則って製作されています。そのため、音訳者は様々な技
術の習得が求められています。例えば、
・読みなどを調査する技術
・きれいに録音する技術
・発声、発音、滑舌などの技術
・目で見ればわかるが音に変えるとわからなくなる言葉(例えば同音異義語
など)を、意味が理解できるように読む技術
・読みあがったものが、原本の内容を正しく伝えているか校正する技術
などです。
(※)音訳技術の詳細、製作基準については、全国視覚障害者情報提供施設協会発行
『音訳マニュアル』シリーズを参照してください。
【参考】
全国視覚障害者情報提供施設協会 http://www.naiiv.net/
視覚障害者情報総合ネットワーク「サピエ」 https://www.sapie.or.jp/
※「サピエ」は全国視覚障害者情報提供施設協会が運営している視覚障
害者等への情報提供サイトです。会員は、「サピエ」の中の「サピエ図
書館」から、全国の視覚障害者情報提供施設やボランティア団体が製
作したデジタル録音資料(デイジー)をダウンロードして聞くことが
できます。
4
視覚障害児童生徒のための「音訳教材」とは 視覚障害児童生徒のために教科書等を音訳しデイジー編集したものです
(児童生徒の使用環境によっては、デイジー編集せずに MP3 の音源データと
して渡すことも考えられますが、本マニュアルでは、デイジー編集を行うこ
とを前提としてデイジー編集の際の注意点までを記載しています)。
「音訳教材」に求められる条件は、いくつかあります。
1.1.1.1.図、表、図、表、図、表、図、表、グラフ、グラフ、グラフ、グラフ、写真、絵写真、絵写真、絵写真、絵などなどなどなどの説明があることの説明があることの説明があることの説明があること
原則として、視覚的資料はすべて音訳します。
点字教科書は紙面に限りがあるため、墨字版の教科書に掲載されている図
や写真などが省略されていることがあります。省略されている情報を補足し
ている「音訳教材」は、児童生徒にとってかなり有用な教材と言えます。
2.学年、教科、2.学年、教科、2.学年、教科、2.学年、教科、ニーズニーズニーズニーズに応じた読みに応じた読みに応じた読みに応じた読みであることであることであることであること
学年や教科によって、読むスピードや視覚的資料を説明する時の用語・表
現は変わります。また、視覚障害児童生徒は一人ひとりニーズが異なります
ので、その「音訳教材」を使用する児童生徒に伝わるように読むことが大切
です。
3.3.3.3.教材教材教材教材..
であることであることであることであること
特に教科書を音訳した「音訳教材」は、視覚障害児童生徒が一人ですべて
理解することを目的としたものではなく、担当教員、保護者などの手助けを
得られることを前提としたものです。単に教科書を最初から最後まで秩序立
てて音訳するのではなく、学習の一助となるよう臨機応変に製作することが
重要です。担当教員が教科書をどのように活用するのかによって、「音訳教材」
の読みかた・作りかたが異なりますので、事前に児童生徒が「音訳教材」を
使用する状況を知っておくことが必要です。
注
・ 教科書は視覚的資料が多用されており、一つ一つの資料の説明が長いと
「音訳教材」を使用する児童生徒が疲れてしまいます。説明が簡潔かつ明
瞭であること、必要なことをはっきりと伝え、長い言い回しや不必要な比
喩表現は避けることが重要です。
・ 「音訳教材」の音訳者は、教科書の内容をある程度理解できる方が前提で
すが、複雑な式や図をどのように音声で表現したら良いのか迷った時は、
担当教員に授業の進めかたや読みかたを確認しながら製作してください。
5
1.学年、ニーズに応じた配慮
(1)スピード(1)スピード(1)スピード(1)スピード
読みのスピードは、原本の内容や、対象となる児童生徒の学年やニーズに合
わせて考えます。
デイジー再生機は、どれも再生スピードを調整することが可能です。例えば、
プレクストーク「PTN2」(シナノケンシ)では、-2から+8まで11段
階でスピードが調整でき、1段階の調整でスピードが0.25倍増減します。標
準の±0(1 倍速)を、-2にすると0.5倍速、+4では2倍速、+8では3
倍速まで変更できます。
ただし、再生スピードを遅くすると、音質が不自然に変わったり聞き取りに
くくなったりします。ほとんどのデイジー再生機は、音訳者の読みをスピード
を遅くして聞くよりも、スピードを速くして聞く方が聞きやすい傾向にありま
す。
特に、対象となる児童生徒が音訳教材を点字・拡大教科書と併用する場合は、
急がず丁寧に読むことが大切です。
(2)用語、表現(2)用語、表現(2)用語、表現(2)用語、表現
図の説明、漢字の補足などに使う用語や表現は、対象となる児童生徒の学年
に応じて慎重に選ぶことが大切です。小学校低学年の教科書では難しい熟語を
使わない、高学年の教科書では学年相応の言葉づかいや用語を用いるなど、児
童生徒が理解できる言葉での説明を心掛けてください。教科書の本文に使われ
ている言葉の意味を正しく理解することも重要です。
また、下の学年の教科書を使用している児童生徒の場合は、個々の発達や課
題に応じた用語、言い回しにも配慮してください。
((((3333))))間間間間ま
の取りかたの取りかたの取りかたの取りかた
音訳において、間は重要な役割を果たします。音声は、点字や墨字のように、
手軽に前に戻って読み返したり斜め読みをしたりすることができません。耳で
聞いた情報だけで正確に理解できるよう、正しい意味のまとまりを作って読む
ことが大切です。そのために間をうまく使います。間を使うというのは、入れ
る場所によって間の長さを変える、切ってはいけない箇所には絶対に間を入れ
ない、ということです。
8
間は、聞き手に意味のまとまりを伝えるのと同時に、聞いたことを理解させ
る時間でもあります。教科書に必ず出てくる注釈、表、リスト化された項目、
図の説明などは、間の取りかた一つで理解度が変わると言っても過言ではあり
ません。児童生徒が考える時間を作ることが大切です。特に、図や写真の説明
では、聞き手が図や写真を思い描く間を心掛けてください。
また、その音訳教材を通して聞いた時に、大きな項目、小さな項目、段落な
ど、意味のまとまりとして理解できるかどうかを確認することも必要です。
さらに、教科書の音訳では、児童生徒の特性や音訳教材の使いかたによって
は、読みの速度そのものを遅くしなければならない場合と、文と文、あるいは
文節と文節など、意味のまとまりごとの間を特別にゆっくり取らなければなら
ない場合があります。いずれにしても、適切な間を入れるためには、原本の内
容を理解した上で音訳することが重要です。
9
2.打ち合わせについて
(1)コーディネーターの必要性(1)コーディネーターの必要性(1)コーディネーターの必要性(1)コーディネーターの必要性
音訳教材の製作には、
・音訳教材を使用する児童生徒
・学校の担当教員(クラス担任、教科担任等)
・音訳教材製作者(ボランティアグループ等)
・(場合によっては)保護者、施設職員などの支援者
をつなぐためのコーディネーターが必要です。
コーディネーターは、
① 学校または教育委員会から、音訳教材の製作依頼を受ける。
② 音訳教材を使用する児童生徒の特長をふまえ、音訳教材の内容、音訳す
る原本の調達、納品方法、納期などを担当教員と打ち合わせる。
③ ②で打ち合わせた内容を元に、音訳教材を製作するボランティアグルー
プと読みかた、デイジーの構成(編集方法)、製作スケジュールを決める。
④ 完成した音訳教材をボランティアグループから受け取り、学校に納品す
る。
といった役割を担います。
※音訳教材の依頼者が保護者の場合は、上記①、②、④は保護者とのやり取
りになります。
コーディネーターがいないと、製作ボランティアグループが依頼者側(学
校・教育委員会、担当教員、児童生徒、保護者、支援者等)とすべてのやりと
りを行うことになります。原本の調達や納品といった事務的な作業も含め、す
べてのボランティアグループにこの役割を求めることはできません。音訳教材
を作るだけなら協力できるというボランティアグループも多いと思いますの
で、やはり、音訳教材を速やかに児童生徒の元に届けるためには全体を統括す
るコーディネーターが必須です。
このコーディネーター役は、点字図書館等の地域の視覚障害者情報提供施設
が担うのが理想的です。視覚障害者情報提供施設は各都道府県に必ず一つはあ
ります。ボランティアの協力を得ながら、日常的にデイジー資料を製作し、視
覚障害者への情報提供を行っていますので、依頼者、音訳教材の製作者の双方
の立場を理解し、調整することができます。
10
学校・教育委員会から、直接ボランティアグループに依頼があった時は、
グループ内でコーディネーター役を決めて作業を進めるのが良いでしょう。
((((2222)音訳教材の依頼を受けた時)音訳教材の依頼を受けた時)音訳教材の依頼を受けた時)音訳教材の依頼を受けた時
コーディネーターは、学校・教育委員会から音訳教材の製作依頼を受けたら、
まず下記のことを確認します。
・墨字教科書の教科書番号、タイトル、出版社
・音訳教材の製作に使用する墨字教科書を学校または教育委員会で用意でき
るかどうか
※製作に使用する墨字教科書は、裁断、書き込みが可能なものでなければなり
ません。また、音訳教材を次年度に使用する場合は、改訂の有無と、改訂が
ある場合は改訂された墨字教科書が手に入る時期を確認してください。
・児童生徒が音訳教材を使用する時期
内容を確認するための墨字教科書も、至急、学校・教育委員会から借りてく
ださい(この場合は改訂前のもので構いません)。墨字教科書が届いたら、ボ
ランティアグループに製作を依頼します。
((((3333)担当教員との打ち合わせ)担当教員との打ち合わせ)担当教員との打ち合わせ)担当教員との打ち合わせ
依頼者が希望する納期に、教科書1冊分の音訳教材を一括で納品できない場
合は、ゴールデンウィークまでに○ページまで、夏休みまでに○ページまで、
という具合に、授業の進行スケジュールを確認します。また、特に高等学校の
場合は、教科によっては「第一章→第二章→第三章…」と進むのではなく、「第
一章は使わずに第二章から使用」、あるいは「第二章→第一章→第三章…」と
いう進めかたをするものもありますので、あわせて確認してください。
図、表、グラフ、写真、絵などの資料の挿入場所、太字や記号の読みかた、
数式の読みかた、見出しの読みかたなどを確認します。教科によって確認する
内容は異なります。本誌 13 ページ以降を参照してください。
読みのスピード、デイジーのレベル、読みかたに関する細かい部分などを事
前の打ち合わせで決められない場合は、まずは数ページ分を音訳教材として納
品し、実際に使用してもらってから決めるのが良いでしょう。特に、「この部
分はどう読むか」といった内容に関する読みについては、作業中に何度か担当
教員に確認することになるはずです。
11
((((4444)製作ボランティアとの打ち合わせ)製作ボランティアとの打ち合わせ)製作ボランティアとの打ち合わせ)製作ボランティアとの打ち合わせ
具体的な読みかたについて、担当教員と打ち合わせたことを伝えます。この
時の打ち合わせには、音訳教材の製作にかかわる全員(音訳者、デイジー編集
者、校正者)が参加します。コーディネーターは、この時の打ち合わせで製作
者から出た質問を、再度、担当教員に問い合わせます。製作中も、担当教員へ
の質問はコーディネーターが窓口になって問い合わせてください。
分納する場合は、製作ボランティアからコーディネーターに納品するスケジ
ュールもたてておきます。
((((5555)依頼、製作、納品の流れ)依頼、製作、納品の流れ)依頼、製作、納品の流れ)依頼、製作、納品の流れ
コーディネーター
(視覚障害者情報提供施設)
担当教員 音訳教材を使用する
児童生徒
保護者
支援施設
製作ボランティア
(音訳者、デイジー編集者、校正者)
学校・
教育委員会
製作依頼
製作依頼
製作依頼
製作依頼
音訳教材納品
音訳教材納品
音訳教材納品
音訳教材納品
音訳教材音訳教材音訳教材音訳教材
回答回答回答回答
回答回答回答回答
12
製作依頼
製作依頼
製作依頼
製作依頼
製作製作製作製作にににに関関関関するするするする問問問問いいいい合合合合せせせせ
製作製作製作製作にににに関関関関するするするする問問問問いいいい合合合合せせせせ
製作製作製作製作、、、、納期納期納期納期にににに関関関関するするするする打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ
製作製作製作製作、、、、納期納期納期納期にににに関関関関するするするする
打打打打ちちちち合合合合わせわせわせわせ
音訳教材納品
音訳教材納品
音訳教材納品
音訳教材納品
3.見出しの読みかた
教科書を音訳する場合は、見出しに、『墨字教科書◇ページ』というアナウ
ンスを入れた方が使いやすくなります。
〔例〕墨字教科書の4ページから始まる「第一章 世界の中の日本」という見出し
の場合
音訳:『第一章 世界の中の日本
墨字教科書4ページ』
特に地域の学校に通う視覚障害児童生徒の場合、教師が使用する教科書は墨
字教科書であり、授業も「今日は4ページから始めます」といった具合に、墨
字教科書のページで進んでいきます。また、家族などが確認する教科書も墨字
の場合がほとんどだと思いますので、対象児童生徒の支援者への情報として、
墨字教科書のページを音声に入れておくことは有効です。
どの見出しで墨字教科書のページをアナウンスするかは、学年や教科により
ますが、少なくとも章、節くらいには入れた方が良いでしょう。項以降の見出
しに墨字教科書のページを入れるかどうかは、担当教員や児童生徒本人の希望
を確認してください。
【応用:音訳教材と併用する点字・拡大教科書のページが分かる場合は、次のような
読みかたもあります】
〔例1〕「第一章 世界の中の日本」という見出しが、墨字教科書は4ページから、
点字教科書は1巻の14ページから始まる場合
音訳例:『 第一章 世界の中の日本
点字教科書1巻14ページ
墨字教科書4ページ 』
拡大教科書には、拡大教科書としてのページ番号と、墨字教科書のページ番
号が付いています。例えば、ページの上の方に「6」とあり、下の方に「4-
1」、「4-2」などと付いている場合は、「6」というのが拡大教科書のペー
ジ番号で、「4-1」、「4-2」というのが墨字教科書のページ番号です。
恐らく、「4-1」、「4-2」という墨字教科書のページの方が目立つよう
13
に記載されていると思いますので、音訳する場合は「4-1」、「4-2」の方
を読むのが良いでしょう(拡大教科書のページ番号と墨字教科書のページ番号
のどちらを読むかは、まずは担当教員や本人の希望を聞いてください)。
〔例2〕「第一章 世界の中の日本」という見出しが、墨字教科書は4ページから、
拡大教科書は1巻の「4-1」ページから始まる場合
音訳例:『 第一章 世界の中の日本
拡大教科書1巻4-1ページ
墨字教科書4ページ 』
14
4.分野ごとの読みかた
(1)(1)(1)(1)古典古典古典古典
古文、漢文の音訳において最も悩ましいのは、注釈などの原文以外の情報の
読みかたです。基本的に古文も漢文も二回読み、一回目は古文なら原文を、漢
文なら読み下し文を読んだ後で、二回目に注釈を交えながら読みます。
【古文】
注釈が短かい場合や、原文の直後に注釈を入れられる場合は、『注』、『注、
終わり』のアナウンスは必ずしも入れる必要はありません。ただし、原文と注
釈のまとまりがわかるように読まなければなりません。
長い注釈の後や、注釈の後にそのまま原文の続きを読むと意味が分かりにく
くなる場合は、注釈を読んだ後に注釈の語句から読み返しても結構です。
本文が何ページにもわたる場合は、段落やページなどを目安に区切りながら
読むと良いでしょう。
次ページの音訳例は、あくまでも一例です。出版社や内容ごとに注釈の量は
異なりますので、担当教員と相談の上、工夫して音訳してください。
明朝体の文字列明朝体の文字列明朝体の文字列明朝体の文字列が注釈です。
15
注
ここに示した音訳例は、あくまでも一例です。学年、教科、担当教員
の授業の進めかた、生徒のニーズによって音訳の処理は異なりますの
で、担当教員と相談の上、読みかたを決めてください。
音訳音訳音訳音訳例例例例::::
児ちご
のそら寝ね
音訳者注。本文を、ある程度のまとまりごとに、2回読みます。1回目は原文で、
2回目は注釈入りです。なお、墨字教科書では、原文の左側に、理解を助ける
ために小さな文字で名詞や助詞が書いてある箇所があります。1回目に読む時
にカッコでくくって繰り返します。音訳者注、終わり。
出典:大修館書店「新編国語総合改訂版」(国総 035)馬淵和夫ほか
16
1回目。
今いま
は 昔むかし
、比叡ひ え
の山やま
に児ちご
ありけり。カッコ・児ちご
がありけり・閉と
じ。
僧そう
たち、カッコ・僧そう
たちが・閉と
じ、宵よい
のつれづれに、
いざ、かいもちいせん。カッコ・かいもちいをせん・閉じ。
と言い
いけるを、この児ちご
、カッコ・この児ちご
は・閉と
じ、 心こころ
寄よ
せに聞き
きけり。
(中略)
…出い
で来く
るを待ま
ちけるに、カッコ・ぼたもちが出い
で来く
るを待ま
ちけるに・閉と
じ…
(中略)
…ひしめき合あ
いたり。カッコ・僧そう
たちはひしめき合あ
いたり・閉と
じ。
2回目。
今いま
は 昔むかし
、
昔々。説話の語り出しに用いられるきまり文句。昔々。説話の語り出しに用いられるきまり文句。昔々。説話の語り出しに用いられるきまり文句。昔々。説話の語り出しに用いられるきまり文句。
比叡ひ え
の山やま
京都府と滋賀県との境にある比叡山の延暦寺京都府と滋賀県との境にある比叡山の延暦寺京都府と滋賀県との境にある比叡山の延暦寺京都府と滋賀県との境にある比叡山の延暦寺((((天台宗天台宗天台宗天台宗))))ををををささささす。す。す。す。
に 児ちご
寺に預けられた公家・武家などの少年。寺に預けられた公家・武家などの少年。寺に預けられた公家・武家などの少年。寺に預けられた公家・武家などの少年。
ありけり。
僧そう
たち、宵よい
、注注注注ちゅう
1111、の つれづれに、注注注注ちゅう
2222
注1、宵注1、宵注1、宵注1、宵 日没から夜中になるまでの時間帯。当時の日没から夜中になるまでの時間帯。当時の日没から夜中になるまでの時間帯。当時の日没から夜中になるまでの時間帯。当時の僧僧僧僧の…(中略)の…(中略)の…(中略)の…(中略)
…普通だった。…普通だった。…普通だった。…普通だった。
注2、つれづれに注2、つれづれに注2、つれづれに注2、つれづれに 手持ちぶさたなときに。手持ちぶさたなときに。手持ちぶさたなときに。手持ちぶさたなときに。
注、終わり。注、終わり。注、終わり。注、終わり。
いざ、かいもちいせん。
ぼたもち(おはぎ)を作ろう。ぼたもち(おはぎ)を作ろう。ぼたもち(おはぎ)を作ろう。ぼたもち(おはぎ)を作ろう。
と言い
いけるを、この児ちご
、 心こころ
寄よ
せに
期待して。期待して。期待して。期待して。
聞き
きけり。
17
さりとて、しいださんを
漢字漢字漢字漢字二二二二文字。行為・作為の文字。行為・作為の文字。行為・作為の文字。行為・作為の「「「「イイイイ」」」」とととと「「「「出す出す出す出す」」」」。。。。送りがな送りがな送りがな送りがな「「「「ださんをださんをださんをださんを」」」」。。。。
作り出すのを。作り出すのを。作り出すのを。作り出すのを。
(後略)
【漢詩】
1回目は読み下し文、2回目は注釈を交えて読みます。
漢詩の場合は、「五言律詩」、「七言絶句」等、詩の形式を伝えてから読み、
注釈は1行単位で挿入します。読み下し文と注釈の境目は間ま
で調整できるのが
ベストですが、読み下し文と注釈の切り替え箇所が分かりにくい場合は『注』、
『注、終わり』のアナウンスを入れても構いません。また、音訳では墨字教科
書と注の順序が変わる場合があります。生徒に分かるように工夫して読んでく
ださい。なお、下記の注 2「一〇二ページ参照」のような場合は、102 ペー
ジの該当箇所を読みます。
デイジー編集では、1 回目の読みで 1 行を 1 フレーズ化し、その旨を音訳
者注でアナウンスします。
出典:筑摩書房「精選国語総合古典編改訂版(国総 040)」安藤宏ほか
18
音訳例:音訳例:音訳例:音訳例:
王維お う い
に 留りゅう
別べつ
す
音訳者注。五言律詩です。この漢詩は、2回読んでいます。1回目は読み下し文
のみで1行ごとに1フレーズ化しています。2回目は一行ごとに注釈を入れな
がら読んでいます。音訳者注、終わり。
1回目。
王維お う い
に 留りゅう
別べつ
す
孟もう
浩然こうねん
寂寂せきせき
竟つい
に 何なに
をか 待ま
たん
朝 朝ちょうちょう
空むな
しく帰かえ
る
芳草ほうそう
を尋たず
ねて去さ
らんと欲ほっ
するも
惜お
しむらくは 故人こ じ ん
と違たが
うを
当路と う ろ
誰たれ
か 相あい
仮か
さん
知音ち い ん
世よ
の稀まれ
なる 所ところ
祇ただ
応まさ
に 寂寞せきばく
を守まも
り
還かえ
りて 故園こ え ん
の扉ひ
を 掩おお
うべし
2回目。
王維お う い
に 留りゅう
別べつ
す
王維王維王維王維お う い
七〇一年七〇一年七〇一年七〇一年・疑問符、・疑問符、・疑問符、・疑問符、から七六一年。盛唐の詩人。中央政府で活から七六一年。盛唐の詩人。中央政府で活から七六一年。盛唐の詩人。中央政府で活から七六一年。盛唐の詩人。中央政府で活
躍するかたわら、熱心な仏教信者として、また絵画の名手としても躍するかたわら、熱心な仏教信者として、また絵画の名手としても躍するかたわら、熱心な仏教信者として、また絵画の名手としても躍するかたわら、熱心な仏教信者として、また絵画の名手としても
知られた。知られた。知られた。知られた。
留別留別留別留別りゅうべつ
旅立つ人が残る人に贈る。旅立つ人が残る人に贈る。旅立つ人が残る人に贈る。旅立つ人が残る人に贈る。「「「「送別送別送別送別」」」」の逆。の逆。の逆。の逆。
孟もう
浩然こうねん
六六六六八八八八九年から七四〇年。盛唐の詩人。自然の風景を…(中略)九年から七四〇年。盛唐の詩人。自然の風景を…(中略)九年から七四〇年。盛唐の詩人。自然の風景を…(中略)九年から七四〇年。盛唐の詩人。自然の風景を…(中略)…と称…と称…と称…と称
された。された。された。された。
19
寂寂せきせき
竟つい
に 何なに
をか 待ま
たん
何何何何なに
をかをかをかをか待待待待ま
たんたんたんたん 何を期待できようか。何を期待できようか。何を期待できようか。何を期待できようか。
朝 朝ちょうちょう
空むな
しく帰かえ
る
朝 朝朝 朝朝 朝朝 朝ちょうちょう
毎日。毎日。毎日。毎日。
空空空空むな
しくしくしくしく 漢字二文字。空白のクウと、自分のジ。自分のジは、ここで漢字二文字。空白のクウと、自分のジ。自分のジは、ここで漢字二文字。空白のクウと、自分のジ。自分のジは、ここで漢字二文字。空白のクウと、自分のジ。自分のジは、ここで
は軽く添える字。は軽く添える字。は軽く添える字。は軽く添える字。
芳草ほうそう
を尋たず
ねて去さ
らんと欲ほっ
するも
芳草芳草芳草芳草ほうそう
故郷の春草。故郷の春草。故郷の春草。故郷の春草。
惜お
しむらくは 故人こ じ ん
と違たが
うを
故人故人故人故人こ じ ん
とととと違違違違たが
うをうをうをうを 親しい友人と遠く離れる。親しい友人と遠く離れる。親しい友人と遠く離れる。親しい友人と遠く離れる。
当路と う ろ
誰たれ
か 相あい
仮か
さん
当路当路当路当路と う ろ
要職にある人。大官。要職にある人。大官。要職にある人。大官。要職にある人。大官。
相相相相あい
仮仮仮仮か
さんさんさんさん 力を貸してくれる。引き立ててくれる。力を貸してくれる。引き立ててくれる。力を貸してくれる。引き立ててくれる。力を貸してくれる。引き立ててくれる。
知音ち い ん
世よ
の稀まれ
なる 所ところ
知音知音知音知音ち い ん
自分をよく理解してくれる人。自分をよく理解してくれる人。自分をよく理解してくれる人。自分をよく理解してくれる人。
祇ただ
応まさ
に 寂寞せきばく
を守まも
り
祇祇祇祇ただ
ただナニナニだけだ。ただナニナニだけだ。ただナニナニだけだ。ただナニナニだけだ。
還かえ
りて 故園こ え ん
の扉ひ
を 掩おお
うべし
故園故園故園故園こ え ん
故郷の我が家。故郷の我が家。故郷の我が家。故郷の我が家。
【漢文】
高校までの教科書であれば散文がほとんどだと思いますので、原則として古
文と同様に読みます。専門的な漢文(韻文など)を音訳する場合は、使用する
生徒や担当教員と相談の上、読みかたを決めてください。
20
視覚特別支援学校中学部 2 年の生徒。視覚と肢体の重複障害。小学校までは
地域の支援学級に通学。点字教科書を使用。上肢に障害がみられるが、両手
の人差し指を使って触読している。点字を読むスピードはあまり速くない。
■古文を音訳教材として製作。点字教科書では省略されている図の説明を音声化。
点字教科書と併用。
【本人の様子】
・標準のスピードでは点字を読む指が付いて行かなかったため、再生機でスピード
を 1 段階落として聞いた。音声を聞くことに慣れていないため、初めて聞く肉声
に戸惑っている様子だった。
� 再生機でスピードを落とすと、声質が不自然になったり言葉が不明瞭になっ
たりするので、点字を読むスピードが遅い児童生徒の場合は、ゆっくり音訳
することを心掛けてください。
・自分のスピードで点字を読みながら、一文ずつ、音声も聞きつつ古文を解釈して
いった。
・点字教科書の本文を読むだけではつかめていなかった建物の位置関係(※)が、音訳
教材で図の説明を聞いたことでわかり、本文を聞いていただけでは答えられなか
った教員からの質問に答えることができた。
(※)徒然草「仁和寺にある法師」で墨字教科書に掲載されていた極楽寺と石清水八
幡宮と高良神社の位置関係を表した図を音訳しました。
21
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
モニター
((((2222))))英語英語英語英語
ネイティブイングリッシュのように流暢に読む必要はありません。正しい英
語の発音で、一語一語を明瞭・明確に発音するよう心がけてください。
この項では、英文として読む箇所はイタリックイタリックイタリックイタリックで、スペル読みする箇所は
ゴシック体で表記します。
【アルファベットの読みかた】
日本語風の読みではなく、辞書の発音記号を元に正確に発音します。
〔例〕C:「シー」ではなく「スィー」
V:「ブイ」ではなく「ヴィー」
Z:「ゼット」ではなく「ズィー」
【スペルアウトが必要な場合】
スペルアウトするときは、単語のまとまりが分かるように間ま
を入れて読む
ことが大切です。原則として、最初に英文を読み、その後にスペルアウトし
ます。
小文字が基本なので、大文字の場合に「大文字」と言い添えます。また、
「コンマ」( , ) 「ピリオド」( . ) 「アポストロフィー」( ’ )
「クエスチョンマーク」( ? ) 「エクスクラメーションマーク」( ! )
「コーテーションマーク」( ‘ ’ )
なども必要であれば読み上げます。
〔例〕「Nice to meet you.」
音訳例1:『 NiceNiceNiceNice totototo meetmeetmeetmeet youyouyouyou....
大文字N、i大文字N、i大文字N、i大文字N、i、、、、cccc、、、、eeee
tttt、、、、oooo
m、e、e、tm、e、e、tm、e、e、tm、e、e、t
y、o、uy、o、uy、o、uy、o、u、ピリオド、ピリオド、ピリオド、ピリオド 』
注
下記の音訳例は一例です。担当教員と相談の上、生徒のニーズに応じた
読みかたに変更してください。
22
音訳例2:『 NiceNiceNiceNice totototo meetmeetmeetmeet youyouyouyou....
NiceNiceNiceNice 大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e
totototo t、ot、ot、ot、o
meetmeetmeetmeet m、e、e、tm、e、e、tm、e、e、tm、e、e、t
youyouyouyou.... y、o、u、ピリオドy、o、u、ピリオドy、o、u、ピリオドy、o、u、ピリオド 』
生徒の特性によっては、スペルアウト後に、再度英文を読むことも有効で
す。
音訳例3:『 NiceNiceNiceNice totototo meetmeetmeetmeet youyouyouyou....
大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e
t、ot、ot、ot、o
m、e、e、tm、e、e、tm、e、e、tm、e、e、t
y、o、u、ピリオドy、o、u、ピリオドy、o、u、ピリオドy、o、u、ピリオド
NiceNiceNiceNice totototo meetmeetmeetmeet youyouyouyou.... 』
音訳例4:『 NiceNiceNiceNice totototo meetmeetmeetmeet youyouyouyou....
NiceNiceNiceNice 大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e大文字N、i、c、e
totototo t、ot、ot、ot、o
meetmeetmeetmeet m、e、e、tm、e、e、tm、e、e、tm、e、e、t
youyouyouyou.... y、o、u、ピy、o、u、ピy、o、u、ピy、o、u、ピリオドリオドリオドリオド
NiceNiceNiceNice totototo meetmeetmeetmeet youyouyouyou.... 』
単語リストを読む時は、先にスペルを読んでから単語を読んでも良いでし
ょう。
〔例〕「nice」「meet」
音訳例:『nnnn、i、c、e、i、c、e、i、c、e、i、c、e nnnniceiceiceice 』
『m、e、e、tm、e、e、tm、e、e、tm、e、e、t meetmeetmeetmeet 』
23
【強く発音する部分を表す記号( 「●」「 ● 」「 ′」「▼」 )】
墨字教科書に示されている通りに強弱をつけて英文を読み、その後で、強
く発音する文字はどれかということを説明します。
〔例〕「T h i s i s m y b a l l.」
音訳例:『 ThThThThiiiissss isisisis mymymymy bbbbaaaa l ll ll ll l....
一番強く発音するのは bbbbaaaallllllllのaaaa、
二番目に強く発音するのは ThThThThiiiissssのiiii 』
【イントネーション(上がり下がり)を表す記号( 「 」「 」 )】
まず、「上がり調子の記号」、「下がり調子の記号」などの説明を入れながら、
イントネーションを付けずに読みます。その後に、上がり下がりのイントネ
ーションを付けて読みます。
〔例〕「Which live longer( ), elephants( ) or mice?( )」
音訳例:『 WhichWhichWhichWhich livelivelivelive longer longer longer longer 下がり調子の記号、カンマ
elephantselephantselephantselephants 上がり調子の記号
orororor micemicemicemice クエスチョンマーク、下がり調子の記号
WhichWhichWhichWhich livelivelivelive longer ,longer ,longer ,longer , elephantselephantselephantselephants orororor micemicemicemice???? 』
【構文(「 ~ ・・・」など)】
「~」や「・・・」にあたる部分を言葉に置き換えられない場合や、言葉に
置き換えると煩わしく感じる場合は、「A」、「B」などに置き換えても構いま
せん。
〔例〕「give ~ to ・・・ [・・・に~をもたらす。]」
音訳例1:『 givegivegivegive ナニナニ totototo テンテンテン
テンテンテンにナニナニをもたらす。 』
音訳例2:『 givegivegivegive Aエイ
totototo Bビー
Bビー
にAエイ
をもたらす。 』
●●
24
【発音記号】
発音記号を音声にするのは困難ですから、同じ発音を持つ簡単な単語を例
に出して説明します。
〔例〕「 」が出てきたときは、『catcatcatcat の、[アェ]』など。
特別支援学校中学部2年の生徒。小学校までは地域の支援学級に通学。視覚、知
的、肢体の重複障害。点字使用だが右手にマヒがあるため左手だけで読んでいる。
英語が好き。音声を併用することで、点字で英語のスペルや文法を覚えたい。
■中学1年の教科書を、23ページ『音訳例4』の方式で音訳し、点字教科書と併用。
本文はすべてスペルアウトしたが、会話文の最初の人名(「MIKA」、「Ms. Green」等)
や、コラムの見出し(「Tool Box」等)をスペルアウトしなかったため、点字を読む
指がそこで止まってしまった。
→人名、コラムの見出しなど、英語の文字列をすべてスペルアウトしたところ、良く
理解できるようになった。さらに、文章の場合は、単語単位でスペルアウトした後、
再度その単語を読んでから次の単語を読んだ。
� 本人の学力、点字の触読スキルを考慮し、英語学習の導入部分ということで行っ
た特別な配慮です。
〔例〕MIKA「Good Morning.」
音訳:『 MIKAMIKAMIKAMIKA 大文字M、大文字I、大文字K、大文字A MIKAMIKAMIKAMIKA
Good Morning.Good Morning.Good Morning.Good Morning.
GoodGoodGoodGood 大文字G、o、o、d GoodGoodGoodGood
Morning.Morning.Morning.Morning. 大文字M、o、r、n、i、n、g、ピリオド Morning.Morning.Morning.Morning.
Good Morning.Good Morning.Good Morning.Good Morning. 』
【本人の様子】
・最初は担当教員の補助を受けながら音声を追いかける形で点字をたどっていたが、
慣れてくると自力で点字を読んだ。
【担当教員の感想】
・すべての単語をスペルアウトしているのが良い。
・モニタリング前に点字教科書だけを読ませた時より、音訳教材を併用した時の方が
指がついてきている。音訳教材があれば、授業で担任の助けになるのではないか。
点字指導のできる教員がほとんどいない特別支援学校では、助けになる教材。
・英語の点字学習は難しいと思っていたが、音訳教材を併用しながらこのような形で
学習を積み重ねていけば、スペルや文法を覚えるのかもしれないという新しい発見
があった。
25
モニター
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
(3)数式(3)数式(3)数式(3)数式
【分数】
「a分のb+c」
この文章を数式に書いてみてください。
、
恐らく、上記のように2種類の数式が書かれると思います。音訳では、こ
のような状況になる読みかたは絶対に許されません。数式を読む場合には、
1つの式として特定できる読みが必要です。
① の場合
音訳例:『分数、a分のb、分数終わり、プラスc』
② の場合
音訳例:『分数、a分のbプラスc、分数終わり』
※ ②の式については、『a分の、カッコ、bプラスc、カッコトジ』という
読みかたも考えられますが、カッコ=( )は数式によく使われますので、
読みにカッコを使う際は注意が必要です。
【記号】
数式の読みかたは教師によって異なりますので、できるだけ担当教員が読
む読みかたで音訳することが望ましいです。音訳教材を使用する生徒のクラ
スでその数式の記号をどのように読むか、事前に担当教員に確認してくださ
い。
〔例1〕
音訳例:『 ルート、
分数、a分のb、分数終わり、
プラスc、
ルート終わり。』
26
aaaa
bbbb++++cccc
aaaa
bbbb++++ccccaaaa bbbb
++++cccc
aaaa bbbb
++++cccc
aaaabbbb
++++cccc
初めてその記号を使った式が出てきたときに、まず、音訳者注で数式の形
を説明し、その上で「以下、この記号の数式は○○のように読みます。」とア
ナウンスしてから読み進めます。「○○」の部分が、担当教員の読みかたにな
ります。
〔例2〕
音訳例:『 音訳者注
インテグラル、下付き文字a、上付き文字b
x、下付き文字n
d、x
の式です。以下、この記号の数式は、
インテグラルaからb、xn、dx、のように読みます。
音訳者注、終わり。』
〔例3〕
音訳例:『 音訳者注
シグマ、a、下付き文字p
シグマの下に、pイコールnプラス1、上に、プラス無限大
の式です。以下、この記号の数式は、
シグマap、pはnプラス1から無限大、のように読みます。
音訳者注、終わり。』
なお、その記号を初めて習う学年の教科書では、記号が出てきた最初に記
号の形そのものを説明することも有効です。
【カッコ】
複雑な数式には、複数の種類のカッコが使われています。それぞれのカッ
コの区別が必要な場合は、はっきり区別して読んでください。
(((( )))) :『カッコ』({ }〔 〕と混在している場合は『小カッコ』と読みます)
{ } :『中カッコ』
〔 〕 :『大カッコ』
+∞
∑∑∑∑p = n+1
a pppp
27
a
b
XXXX dddd n XXXX
(4)化学記号(4)化学記号(4)化学記号(4)化学記号
元素記号の右下に付いている数字は、英語読み、日本語読みのどちらでも
構いません。混乱することがなければ、英語と日本語の読みが混在しても構
いません。重要なのは、音訳教材を使用する生徒がすぐに理解できるような
読みかたを心掛けることです。担当教員にも読みかたを確認してください。
〔例〕 CO2 :『シーオーツー』
H2O :『エイチツーオー』
C6H6 :『シーロク・エイチロク』(シーシックス・エイチシックス)
元素記号は、H(水素)、O(酸素)のようにアルファベット一字で表され
るものと、Na(ナトリウム)、Cl(塩素)などのように二字で表されるも
のがあります。この場合は、1つの元素は必ずひとかたまりに読んでくださ
い。例えば、「NaCl(塩化ナトリウム)」の読みは、『N、aCl』ではな
く、『NaCl』(一続き)でなければなりません。
元素記号の右上に、+、-などの記号がついているのはイオン式と呼ばれ、
数字はイオンの価数を示します。右上にだけ数字や記号が付いている場合は
そのまま読んで構いませんが、下付き文字と上付き文字が付いている化学式
が混在している場合は、「~の」という言葉を加えて読みます。
〔例〕 H+ :『エイチプラス』 または 『エイチのプラス』
Na+ :『エヌエープラス』 または 『エヌエーのプラス』
Al3+ :『エーエル3プラス』 または 『エーエルの3プラス』
SO42- :『エスオー4の2マイナス』
元素記号の左上についている数字は質量数です。そのまま読みます。
〔例〕 12C :『シー12』 または 『シーの12』
13C :『シー13』 または 『シーの13』
28
5.注の読みかた
注は、原則として本文中に挿入しながら読み込んでいきます。どこに挿入す
るのが最も適切であるかは、本文と注をよく読み、その注が
・注番号が付いている言葉の意味が書かれているのであれば、その場ですぐ挿
入する。
・出典などであれば、適当な切れ目まで読んでから挿入する。
などのように判断してください。
注の挿入箇所は、教科や学年、対象となる児童生徒の特性によっても判断が
変わるところです。
本文中の注のついている言葉の後に[注]や[※]と記載されている時は、本文
を読む時にその場で『注』と読み込んでおきます。その上で、文の切れ目、段
落の切れ目などで注を読みます。その時は改めて『注、…(注釈)…。注、終
わり』とします。
〔例〕「ここ数年で、私たちが手に入れることができる情報[注]は、飛躍的に増大して
います。」
音訳例:『・・・手に入れることができる情報、注注注注、、、、は、飛躍的に増大してい
ます。
注、注、注、注、
手に入れることができる情報手に入れることができる情報手に入れることができる情報手に入れることができる情報 様々なメディア・リテラシー様々なメディア・リテラシー様々なメディア・リテラシー様々なメディア・リテラシー
の確立によって・・・(中略)・・・である。の確立によって・・・(中略)・・・である。の確立によって・・・(中略)・・・である。の確立によって・・・(中略)・・・である。
注、終わり。注、終わり。注、終わり。注、終わり。 』
文末に[注]と書かれている時には、ここに注がありますという意味の『注』
と、これから注を読みますという意味の『注』と、2回続けて読むことになり
ます。
〔例〕「インターネット検索におけるディレクトリー型サーチエンジン(※)。」
音訳例:『インターネット検索におけるディレクトリー型サーチエンジン、注注注注。。。。
注、注、注、注、
インターネット上にインターネット上にインターネット上にインターネット上に公開されているウェブサイトの中で・・・公開されているウェブサイトの中で・・・公開されているウェブサイトの中で・・・公開されているウェブサイトの中で・・・
(中略)・・・である。(中略)・・・である。(中略)・・・である。(中略)・・・である。
注、終わり。注、終わり。注、終わり。注、終わり。 』
29
本文中に書かれている注に、「注1」「注2」などと番号がついている時は
番号をつけて読みます。
■注をどこで読むかは注の長さにもよります。場所を決めたら、一度、注を含
んだ文の前後を少し長めに録音して聞いてみるなど、適切に処理されている
かを確認してください。
■注が後ろにまとめられている教科書は、本文中に注を挿入しながら読み、な
おかつ墨字教科書通りの場所に注を残しておく方法もあります。担当教員の
授業の進めかたや教科によっては、注がまとめられているのも便利かもしれ
ません。ただし、注が2回読まれることになります(1 回目は本文中、2 回
目は後ろにまとめられている所)ので、担当教員と相談して決めてください。
なお、この方法で音訳教材を製作した場合は、必ずデイジーの凡例(「この
音訳教材の使いかた」等)、または音訳者注でその旨をアナウンスしてくだ
さい。
※古典の教科書にはたくさんの注があります。本マニュアル 15~20 ページを参照
してください。
30
6.記号などの読みかた
教科書の中で使われている記号は、事前に担当教員が授業中にどのように読
むか、説明するかを確認し、その上で、教科書通りに読むか、あるいは省略で
きるものは省略するかをしっかり打ち合わせることが大切です。
以下は、記号を読む場合の音訳例です。
〔例〕 「太字の文字太字の文字太字の文字太字の文字」 :『太字、○○○、太字、終わり。』
(○○○) :『カッコ、○○○、閉じ』または『カッコ、○○○、
カッコ閉じ』
※文中のカッコの多くは補足の意味で使われており、数
式のカッコとは全く違うものです。数式では、『カッ
コ・・・カッコ閉じ』と読みます。数式の読みかたは
26、27 ページを参照してください。
(流れ図の)→→→→ :『矢印やじるし
』
※流れ図の中の「→」は、そのまま矢印と読むのが良い
でしょう。
「→ p102」 :『102ページ参照』
※参照先のページ番号を表している「→」は、言葉に置
き換えて読みます。この場合は、デイジーの凡例か音
訳者注で、『矢印は参照と読みます』と断って「○○ペ
ージ参照」と読む方法も考えられます。
その他、傍点、傍線、下線など、墨字教科書には、目で見てわかりやすくす
るための様々な記号が使われています。その都度、音訳者注で「どのような記
号をどう読むか」を断ってから読んでください。
言葉に置き換える記号が一つか二つであれば、デイジーの凡例(「この音訳
教材の使いかた」等)でアナウンスしても良いですが、記号の数が多い場合は、
その記号が出てきたところで音訳者注として挿入するのが良いでしょう。
31
7.図、表、写真の読みかた
(1)基本的な考え(1)基本的な考え(1)基本的な考え(1)基本的な考えかたかたかたかた
一つ一つの図、表、写真について、
・説明するのか、しないのか
・説明するとすれば、本文中のどこで説明するのか
・どの程度の説明をするのか
を判断します。本文をよく読み、そこにその図、表、写真がある意味を考えて
ください。
説明する時は、説明文を考えた上でそれを読みます。説明文は、
・主語、述語のはっきりした、できるだけ短い文であること
・用語が対象者に合っていること
が大切です。作文したら、必ず前後の本文と続けて読んでみてください。思い
がけない矛盾を発見することがあります。
説明しないときは、説明を省略する理由をアナウンスします。
(2)図を説明する(2)図を説明する(2)図を説明する(2)図を説明する時時時時 [[[[グラフ、地図、見取り図、流れ図グラフ、地図、見取り図、流れ図グラフ、地図、見取り図、流れ図グラフ、地図、見取り図、流れ図、、、、系統樹系統樹系統樹系統樹]]]]
① はじめに、図全体が何を表しているか説明します。
② 児童生徒が、頭の中で図の形を再現できるような説明が必要な場合もあ
りますが、形の説明にこだわるあまり内容が分かり難くなることもあり
ます。必要なポイントをしっかり掴んで説明してください。
③ あいまいな表現を使わず、事柄を特定できる言葉にします。ただし、不
確定なものを断定しないよう気をつけてください。
【グラフ】
数値が記入されている場合は、それを読みます。
数値が記入されていない場合は、目盛りの刻みかたを説明し、概数で読み上
げることを断ります。数値は物差し、分度器などを使って測ります。
また、グラフ上の直線、曲線、折線などの傾向を説明する場合、「急激な上
昇」や「なだらかな下降」といった表現は、比較対象がない時には使わないで
32
ください。目盛りの刻みかたが変われば、なだらかな上昇であっても急激な上
昇に見えるからです。
※以下の 2 つのグラフは、どちらも同じ内容です。
■点字教科書では、紙面が限られているため図やグラフが数ページ先のページ
に書かれていることがあります。その場合は、点字教科書では「△ページ参
照」と記載され、生徒はグラフを読むために参照先のページを開きます。参
照先でグラフを確認した後は、「△ページ参照」と書かれていた元のページ
に戻らなければなりません。グラフや図の多い教科の場合は、担当教員との
打ち合わせ時に、生徒が使用している点字教科書のレイアウトがどの程度墨
33
視覚特別支援学校高等部普通科1年生。点字使用者で、点字を読むスピード
は遅くないが、重複で発達障害があり、点字の教科書だけでは行単位で読み
飛ばしてしまう。数式やグラフが苦手。
■ 数学Ⅰの2次関数のグラフと数式の項を音訳。点字教科書と併用。モニタリング
前に自宅で音訳教材のみ何回も聞いて予習した。
【本人の様子】
・音声があることで、点字を読み飛ばすことなく指でたどっていける。
・音声によって数式の意味を理解すると同時に、点字の数式も読むことができた。
・2次関数のグラフの点図を、まず音訳者注で図の全体のイメージ(X軸とY軸の
交点Oオー
が示されている、頂点が下の放物線が描か
かれている、等)を説明。その後、
放物線のX軸・Y軸それぞれの交点を説明したところ、点図を触りながら4~5
回繰り返し聞くと、どのような図なのか理解できた。
モニター
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
字教科書と違うのか確認し、音訳教材ではどのような順番で読むのかを決め
られるとベストです。
例えば、点字教科書 10 ページの本文に「グラフ 1、13 ページ参照」と書
かれている場合は、音訳教材で下記のようにアナウンスすることも可能です。
音訳例:『音訳者注、
このグラフの点図は、点字教科書の13ページに書かれています。
13ページのグラフを読みます。
音訳者注、終わり。
点字教科書13ページ、グラフ1
音訳者注、
グラフの説明、X軸とY軸の・・・(中略)・・・グラフの説明、終わ
り。点字教科書10ページに戻ります。
音訳者注、終わり。
点字教科書10ページ、○○○○(←本文の音訳)・・・』
【地図】
全体の説明が必要な時には、
・北から南へ、あるいは東から西へ、順に説明する。
・一地点(例えば日本)を中心に、その東西南北を説明する。
などが考えられます。そこにその地図がある意味を考えて、必要な情報を掴
んだ説明をしてください。
特定の一部の地域の説明が必要な場合には、全体の説明を『日本地図です』
『○○県の地図です』など大まかにしてから、必要な部分だけ細かく説明しま
す。その場合、東西南北よりも上下左右で説明した方がわかりやすい地図もあ
ります。いずれにしても、その地図の目的を把握し、内容が伝わるよう工夫す
ることが大切です。
34
【見取り図】
全体の説明が必要な場合は、
・上から下に、左から右へ、順に説明する。
・何かポイントとなるものがあれば、それを中心に、その上下左右を説明す
る。
などが考えられます。
図の中の一部の説明が必要な場合には、「○○家の見取り図です」などと断
ってから必要な部分の説明をします。その図の意図を把握して説明してくださ
い。
■ 地理の音訳教材を点字教科書と併用。地図、地球の断面図などの点図の理解のため、
墨字の教科書ではなく点字教科書の点図を中心に音訳した(※点字教科書の確認を
しながら音訳を行った例です。ボランティアグループ内に点図を読める人がいない
場合は、点図の読める協力者が必要です)。
・本文の点字については音訳教材のスピードに問題なく指がついてくるが、絵や図に
なると、音声の説明を理解しながら点図を触るのにかなり時間がかかる。
・点図の全体把握が苦手な生徒なので、地図はできるだけ指を離さずにたどれるよう
地図の左上→右端→右下→左端の順に音訳(※すべての地図に有効な音訳方法では
ありません)。
・説明に使用する用語をできるだけ日常的な言葉にし、説明文も 1 文を短く、単純な
構造にした(例:「風に乗って宙を舞っている」ではなく「空を飛んでいる」等)。
・点字教科書で横書きの図が出てきたときは、音声でも『横書きの図』と案内をし、
その後に一時停止のための間ま
を挿入。地図の説明の合間にも一時停止のための間ま
を
入れた。
・点図では紙面が限られているため国名などが略して表記される(セルジューク朝は
「セル」、カイロは「カ」等)が、音声ではフルネームで読んだ。
【本人の様子】
・音訳教材を一時停止する間ま
があるので、落ち着いて教科書を横向きにできた。ただ、
説明の中の間ま
は、再生・停止をしながら聞く時はちょうど良かったが、通し聞きを
するときは滑らかに聞けない。
・触図に気を取られていると地図の前にあった凡例を忘れてしまうため、国名を省略
せずに音訳しているのがとても良かった。
・音訳教材を何回も繰り返し聞きながら点図を触っていると、少しずつ指が音声に先
行して動くようになった。
地域の学校に通う視覚単一障害の生徒。中学1年生。小学校から点字教科書を使
用しているが、点字学習のサポート体制が十分ではない面があり、点図の触読が
苦手。
35
モニター
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
【流れ図、系統樹】
書かれていることを順に読んでいくだけでは、内容が理解しにくい時もあり
ます。番号を付けるなど工夫してください。番号を付けた時は、何番まである
かを音訳者注で断ってから読みます。
音訳例:『音訳者注、1、2、3、・・・の番号は、音訳者が付けたものです。番号
は全部で14まであります。音訳者注、終わり』
系図などは、上から下へ順に読むのではなく、中心人物との関係を主に説明
する方法もあります。
※図、表、写真の処理は一つ一つ違います。全国視覚障害者情報提供施設協会発行
『音訳マニュアル』シリーズも参照してください。
視覚特別支援学校小学部 3 年の児童。視覚と発達の重複障害。拡大教科書を使
用。学年相当の学習をしているが、算数などは理解度が落ちてきている。音声
を聞くことに慣れていない。
■社会の副読本をマルチメディアデイジー化し、写真、イラストに説明を加えた音
訳教材として製作。弱視の児童なので、特に写真、イラストなどの資料を大きく
した。
モニタリングではパソコンとデイジー再生ソフトウェア「AMISア ミ
」を担当教員
が操作し、音訳教材(マルチメディアデイジー版)のみを使用した。
【本人の様子】
・音訳教材を聞きながら、担当教員が画面を指さして補足。児童もハイライトして
いる文字列を指さしてコメントをするなど、教員との活発なやり取りがあった。
・写真やイラストを見ながら音声を集中して聞き、教師が音声で説明していた箇所
について質問すると、ほぼ正しく答えられた。
・写真やイラストが、墨字教科書より大きく見えるのが良い。
【担当教員の感想】
・写真やイラストに説明が付いているのが分かりやすくて良い。
・家庭でも保護者に「AMIS」の操作を覚えてもらえれば活用できると思う。
36
モニター
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
視覚特別支援学校小学部 5 年の児童。視覚と知的の重複障害。基本は拡大教科書
を使用しているが、点字も導入し始めている。マルチメディアデイジー教科書を使
用したことがある。
■国語の教科書をマルチメディアデイジー化し、挿絵に説明を加えた音訳教材として
製作。弱視の児童なので、挿絵の画像を大きくした。モニタリングではパソコンと
デイジー再生ソフトウェア『AMIS』を担当教員が操作し、音訳教材(マルチメ
ディアデイジー版)のみを使用した。
・物語の雰囲気を壊さないため、挿絵の説明では『音訳者注』、『絵の説明』といった
言葉は入れず、本文とは違う音訳者が挿絵の説明をした。
・絵の説明は、簡単な言葉と文章で一文をできるだけ短くした。
� 音訳教材では、文学的な言い回しより、簡潔・単純で聞いていく傍から理解でき
る表現が求められます。
【生徒の様子】
・拡大教科書よりも文字を大きくして読んだ。
・挿絵の説明の所では、画面に顔を近づけて絵を見ながら音声を聞いた。声が変わる
ので、本文と絵の説明の違いが理解できた。
【担当教員の感想】
・絵に音声の説明がついているので、点字使用の児童も一緒に使える所が良い。
� 今回のモニタリングでは「AMIS」を使用しましたが、絵を大きくして見る場合は
「Easy Reader」(有料の再生ソフトウェア)や iPad の使用をおすすめします。
視覚特別支援学校小学部 4 年の児童。視覚とAD/HDの重複障害。下学年対応
の教科が多い。強度の弱視で点字使用だが本人は墨字への興味が強い。パソコン
や機械が好き。
■社会の副読本を音訳教材として製作。点字教科書と併用する予定だったが、再生
機でスピードを一番遅くしても点字の触読が追いつかなかったため、音訳教材の
みを標準スピードで使用した。
【生徒の様子】
・説明が長くなると落ち着きがなくなる。
・再生機に興味を示し、一度の説明でCDの挿入、再生、停止を覚えた。
・パソコンに興味を示したため、他の児童が使用したマルチメディアデイジー版の
音訳教材を見せたところ、イラストや写真が表示されると画面を見た。文字を大
きくすると、時々ハイライト部分を目で追った。
【担当教員の感想】
・機械が好きな児童なので、パソコンと音訳教材の組み合わせなら本人の興味が続
くかもしれない。
・マルチメディアデイジーに興味を持ったようなので、学校でも国語の教材から試
してみたい。
37
モニター
モニター
(3)表を読む時(3)表を読む時(3)表を読む時(3)表を読む時
縦に読むか横に読むかを、慎重に判断してください。場合によっては、縦に
読んでから横に読むというように、両方読んでも構いません。
空白の欄がある場合は、『空欄』『記載なし』などと読みます。
項目がたくさんある場合は、初めにその数を言ってから番号を付けて読みま
す。
音訳例:『音訳者注、この表の項目は、全部で8個あります。1、2、3、のよう
に、各項目に番号を付けて読みます。音訳者注、終わり』
「春・夏・秋・冬」、「縦・横・高さ」、など分かりやすい項目であれば、項
目名をいちいち読み上げる必要はありませんが、分かりにくい項目が並んでい
る場合は、項目名をその都度読んだ方が良いでしょう。
表に示されている必要な情報がきちんと伝わるかどうか確認しながら読む
ことが重要です。
視覚特別支援学校高等部1年。視覚単一障害の生徒 2 人。2 人とも音訳や
デイジー資料のことを知っている。
■生物基礎の音訳教材を製作。通常授業の中で点字教科書と併用した。
普段は担当教員がまず教科書を読み上げているが、その役割を音訳教材にさせた。
【生徒の感想】
・本文は、特に音声を併用する必要性は感じないが、表の音声があるのは良い。点
字の表の中の移動が楽にできる。ただし、点字教科書と同じ順序で音訳してほし
い。
・点字教科書で省略されている図や写真の説明が音声で入っているのが良い。
【担当教員の感想】
・視覚障害の児童生徒は、生徒ごとに症例やニーズが違うので、一概にデイジーが
あればOKとは言えないが、選択肢の一つとしていいのではないか。
・自宅学習用として製作するのなら、割り切って「実験をしてみましょう」などの
コーナーを飛ばし、本文を一つのストーリーとして音訳するのも良いかもしれな
い。本文があれば内容がわかる教科なら、図の部分は『図は点字教科書で確認』
などと飛ばすのも1つ。
・地域に通う単一の視覚障害児童生徒が、今後、より多くの本を読んでいくときに
音声デイジーを併用するのはとても有効だと思う。
38
モニター
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
8.デイジーの凡例
(1)音訳教材の冒頭に入れる凡例(1)音訳教材の冒頭に入れる凡例(1)音訳教材の冒頭に入れる凡例(1)音訳教材の冒頭に入れる凡例
タイトル(音訳教材の一番最初に読む見出し)のすぐ後に、その音訳教材全
体に関わる凡例を入れます。視覚障害者情報提供施設で製作されているデイジ
ー資料では、「デイジー図書凡例」という見出しで読まれていますが、音訳教
材の場合は「この音訳教材の使いかた」などの見出しで構いません。冒頭の凡
例では、
・見出し以外の箇所で細かくセクション分割している場合(42 ページ「1.
セクション分割および見出しのレベル(階層)設定」参照)
・拡大教科書に書かれている墨字教科書のページ番号で音訳教材にページ付
けをした場合(44 ページ「3.ページ付け」参照)
・太字、(参照の)「→」など、教材全体を通して同じ読みかたをする場合(31
ページ「6.記号などの読みかた」参照)
・音訳教材の中で出てくる音訳者注の意味
などをアナウンスします。各見出しのレベル設定を細かく行ったときは、各章
で必ずしもレベルと見出しの大きさ・種類が同じになるとは限りません。例え
ば、第一章ではレベル4だった「コラム」や「図表などの資料」が、第二章で
はレベル3になることもあります。
章ごとにレベル設定が異なっている場合は、レベルに関する凡例は各章の冒
頭でアナウンスした方が良いでしょう。
また、凡例は、児童生徒本人ではなく、音訳教材を操作する人(教員、保護
者等)が聞く場合もあります。凡例の用語・表現を、音訳教材を使用する児童
生徒の学年やニーズに応じて配慮する必要があるかどうかは、担当教員などに
確認してください。
音訳例1:『 この音訳教材の使いかた(←見出し)
この音訳教材は、レベル1のみです。すべての章、節、項、コラム
にあたる本文の見出しと、図、表、写真などの資料名をレベル1で区
切っています。
また、見出しや資料名以外に、本文の段落もレベル1で区切りまし
た。レベル1で区切られているところは、デイジー再生機の見出し移
動で前後に移動することができます。
39
墨字教科書の太字で書かれている文字は、「太字」、「太字終わり」
と読んでいます。
この音訳教材の使いかたは、以上です。』
音訳例2:『 この音訳教材の使いかた(←見出し)
この音訳教材は、レベル4まであります。レベルは章ごとに異なり
ますので、各章の冒頭でアナウンスします。
ページ番号は、拡大教科書に書かれている墨字教科書のページ番号に
沿って付けています。拡大教科書に書かれている番号には、「4 ―ハイフン
1」
「102 ―ハイフン
1」のようにハイフンが入っています。ハイフンを取り外した
数字を、この音訳教材のページ番号にしました。例えば、拡大教科書に
書かれている番号が「4 ―ハイフン
1」の場合は、この音訳教材では 41 ページ。
「102 ―ハイフン
1」の場合は、1021 ページになります。
この音訳教材の使いかたは、以上です。』
また、音訳では、読み手が入れる注釈を、墨字教科書の内容と区別するため
に『音訳者注』という表現で挿入します。児童生徒や保護者、担当教員が、音
訳された資料や教材を聞きなれていない場合は、音訳者注という言葉を初めて
聞くことになりますので、凡例で簡単に説明しておくと良いでしょう。音訳者
注の説明を凡例に入れるかどうかは、担当教員との打ち合わせで判断してくだ
さい。
音訳例:『 音訳教材の中に出てくる「音訳者注」という言葉は、教科書に書かれて
いないことをこれから読み手が説明します、ということです。』
(2)各章ごとに入れる凡例(2)各章ごとに入れる凡例(2)各章ごとに入れる凡例(2)各章ごとに入れる凡例
各章ごとに見出しのレベル(階層)が異なる時や、その章だけに出てくる処
理などについては、章ごとに凡例を入れるのが良いでしょう。
音訳例:『 第三章の使いかた(←見出し)
第三章は、レベル4まであります。レベル2とレベル3は、本文の見
出しです。レベル4は、図や写真などの資料名と、コラムです。
その他、注釈は一つ一つグループとしてまとめています。(←注釈をグル
ープにまとめた場合)
第三章の使いかた、終わり。』
40
デイジー(DAISY=Digital Accessible Information SYstem)は、視覚障
害者のためのデジタル録音資料を製作する規格として誕生しました。現在、全
国の視覚障害者情報提供施設(点字図書館等)から貸し出されている CD に入
った録音資料は、ほとんどがデイジー形式です。また、ウェブサイト「視覚障
害者情報総合ネットワーク『サピエ』」内の「サピエ図書館」で提供されている
録音資料も、デイジー形式です。
デイジーは、専用のデイジー再生機、またはパソコン用デイジー再生ソフト
ウェア、タブレット端末用のアプリを使って再生することができます。
大きな特徴は、
・ページ移動ができる
・見出し(項目)の前後移動ができる
・スピードや音量を簡単に変更できる
・複数箇所にしおりを付けることができる
などです。
デイジーの構造や編集方法そのものについては、全国視覚障害者情報提供施
設協会発行「音訳テキスト デイジー編集入門編」、「音訳マニュアル デイジー
編集事例集」を参照してください。
本マニュアルでは、音訳教材としてデイジー編集をする際のポイントを記載
します。一般的なデイジー資料の編集とは異なりますので、ご注意ください。
1.1.1.1.セクション分割セクション分割セクション分割セクション分割および見出しのレベルおよび見出しのレベルおよび見出しのレベルおよび見出しのレベル((((階層階層階層階層))))設設設設定定定定
児童生徒、教員、保護者など、音訳教材を実際に操作する人が、デイジー再
生機の扱いに慣れている場合は、一般的なレベル(階層)設定を行ってくださ
い。第一章はレベル 1、第一節はレベル2、第一項はレベル3・・・といった
具合です。この場合、セクション分割も見出し単位で行います。
音訳教材を操作する人がデイジー再生機の扱いに慣れていない場合は、でき
るだけ機器の操作を少なくするためのいくつかの工夫があります。例えば、
・見出し単位ではなく、段落単位、表の行または列単位、リスト化されている
箇所の項目単位、など、もっと細かい単位でセクション分割する。
・すべての見出しをレベル1に設定する。
といった構造にすると、見出し移動の操作だけで小さなまとまりで前後に移動
することができ、レベル(階層)の変更、巻き戻し・早送りなどの操作をしな
42
くて済みます。ただし、デイジーとしてはかなり異例の編集になりますので、
音訳教材を操作する人から操作についての相談があった場合にのみ提案してく
ださい。
地域の学校の弱視学級に通う小学 4 年生の児童。軽度知的障害の重複。点字
使用だが、手先を使うことが難しいため、点図の線をたどっていくことが苦手
で図形の認識が難しい。特に一箇所に複数の図形があると理解できない。
■担当教員が作成した算数の教材(A4用紙8ページ分)を音訳。音訳教材を聞きな
がら、立体模型→立体コピーの図→点図の順に触って学習。
【有効だった点】
・担当教員が、児童の手を持って図を触らせながら、音訳教材の再生、停止、巻き戻
しを繰り返すため、再生機の複雑な操作は無理。音訳教材のレベルは1のみで、ほ
ぼ一文単位でセクション分割を行った。
※ただし、一つ前の文に戻るときは便利だが、復習として前の見出しに戻るときは、
何回も見出し移動のボタンを押さなければならないので不便。再生機の使いかた
に慣れてきたら、見出しをレベル1、本文をレベル2で細かくセクション分割す
るなどの工夫ができる。
・同じフレーズを何回も繰り返し聞きながら理解していく上で、何度聞いても説明の
内容や声の調子が変わらないのが良い。
視覚特別支援学校中学部 3 年。点字教科書使用の生徒2人と拡大教科書使用
の生徒1人のクラス全員で音訳教材を併用した。
■科学の音訳教材を製作。ただし、この教科は点字教科書と拡大教科書(墨字教科
書と同じ内容)で内容が異なっており、音訳教材は点字教科書にあわせて製作し
たため、拡大教科書使用の生徒にとっては使いやすいものとは言えなかった(拡
大教科書使用の生徒には、教員が付いて指さし補助を行った)。
� 音訳教材を、点字使用と拡大使用の生徒が混在しているクラスで使用する場
合は、担当教員との打ち合わせ時に、点字教科書と拡大教科書がどの程度
違っているのか、どのように音訳するのかを決めておく必要があります。
【点字使用の生徒の様子】
・音訳教材の冒頭でページをアナウンスした時に、再生機を一時停止し、点字教科
書の該当ページを開くことができた。
・音声の説明通りに点図をたどっていけた。
・生徒:「授業で習った時にはどのような図か理解できるが、家に帰ると忘れてし
まうので、音訳教材は家庭学習で使いたい」
43
モニター
モニター
モニタリングよりモニタリングよりモニタリングよりモニタリングより
2.見出しの編集
音訳教材の場合は、見出しで『墨字教科書◇ページ』などのページ情報をア
ナウンスします。デイジー編集時は、ページ番号のアナウンスと見出しを1フ
レーズ化してください。
下記の例の場合、網掛け部分を見出しとして1フレーズ化します。
〔例〕墨字教科書の4ページから始まる「第一章 世界の中の日本」という見出し
の場合
音訳例:『第一章第一章第一章第一章 世界の中の日本世界の中の日本世界の中の日本世界の中の日本、墨字、墨字、墨字、墨字教科書4ページ教科書4ページ教科書4ページ教科書4ページ』
〔例〕「第一章 世界の中の日本」という見出しが、墨字教科書は4ページから、
点字教科書は1巻の14ページから始まる場合
音訳例:『第一章第一章第一章第一章 世界の中の日本世界の中の日本世界の中の日本世界の中の日本、、、、点字教科書1巻14ページ、墨字教科点字教科書1巻14ページ、墨字教科点字教科書1巻14ページ、墨字教科点字教科書1巻14ページ、墨字教科
書4ページ書4ページ書4ページ書4ページ』
〔例〕「第一章 世界の中の日本」という見出しが、墨字教科書は4ページから、
拡大教科書は1巻の「4-1」ページから始まる場合
音訳例:『第一章第一章第一章第一章 世界の中の日本世界の中の日本世界の中の日本世界の中の日本、、、、拡大教科書1巻4-1ページ、墨字教拡大教科書1巻4-1ページ、墨字教拡大教科書1巻4-1ページ、墨字教拡大教科書1巻4-1ページ、墨字教
科書4ページ科書4ページ科書4ページ科書4ページ』
3.ページ付け
原則として、墨字教科書通りのページ付けを行います。
拡大教科書と併用する音訳教材で、デイジー編集者の手元に拡大教科書があ
る場合は、拡大教科書に書かれている墨字教科書のページ情報(「4-1」「4-2」
等)に合わせたページ付けを行っても良いでしょう。
〔例〕 拡大教科書のページが「4-1」の場合:音訳教材のページは「41」
拡大教科書のページが「4-2」の場合:音訳教材のページは「42」
拡大教科書のページが「10-3」の場合:音訳教材のページは「103」
拡大教科書のページが「102-1」の場合:音訳教材のページは「1021」
44
注
この方法は一例です。どのようにページ付けをするかは音訳教材を操作する
人の意向を確認して決めてください。
1.児童生徒の個人情報保護1.児童生徒の個人情報保護1.児童生徒の個人情報保護1.児童生徒の個人情報保護
音訳教材の製作に関わる人は、個人の情報の有用性を大切にしつつ、同時に
個人の利益を守らなければいけません。
◆個人情報の有用性とは
教科書を音訳したり電子書籍化したりする場合、使用する児童生徒の視力、
視野、色覚などの情報を知ることで、その児童生徒にとって使いやすい音訳
教材等を製作することができます。
◆個人の利益を守るとは
個人の利益が損なわれないように配慮することです。例えば、音訳教材の
製作過程で氏名、学校名、学年などを知ることがあるでしょう。こうした情
報は個人の特定につながりやすく、それが個人のプライバシーを脅かすなど
の不利益をもたらす恐れがあります。第三者にその情報を伝えないようにし
ましょう。
※意図的でない情報の流出にも気をつけましょう。
音訳教材の製作にあたり知り得た児童生徒の情報は、家族を含め他の人に知
られないよう厳重に管理してください。例えば、「○○中学校の視覚障害の生
徒さんのために教科書を音訳している」、「今、教科書を音訳している生徒さん
は○○の障害がある」ということをうっかり口にしてしまうことがないように
注意してください。
2.使って喜ばれる音訳教材を2.使って喜ばれる音訳教材を2.使って喜ばれる音訳教材を2.使って喜ばれる音訳教材を作るために作るために作るために作るために
「おもてなし」という言葉があります。これは相手を思いやって行動するこ
とです。音訳教材作りにも「おもてなし」の気持ちが必要です。
そのためには、教材を製作する前に児童生徒、保護者、教師からよく話を聞
き、何が必要なのかを十分に確認することが大切です。場合によっては視覚障
害教育や音声教材・デジタル教材に詳しい専門家の意見を聞くのも良いでしょ
う。
また、製作した教材を利用した児童生徒、保護者、教師の感想を知ることも
46
大切です。視覚障害児童生徒のための教材作成技術は利用者の意見を聞くこと
で高められます。ですが、利用者の意見もプライベートな情報の一つです。個
人が特定できる形で外に出ることのないよう、取扱いに注意してください。
3333.製作者の意識を高めるために.製作者の意識を高めるために.製作者の意識を高めるために.製作者の意識を高めるために
ボランティアグループ内で、個人情報の取り扱いについてルールを決め、文
書化することをおすすめします。定期的にグループ内で個人情報の取り扱いに
関する勉強会などをするのも効果的です。
製作上、ボランティアグループ内で児童生徒の個人情報を共有する必要があ
る場合は、ボランティア一人ひとりが個人情報の取り扱いについて常に意識を
高く持って作業してください。
また、コーディネーターは、製作依頼をしたボランティアグループあるいは
ボランティア個人と個人情報の取り扱いに関する覚書を取り交わしておくな
ど、情報の流出を防ぐための工夫を行ってください。
47
平成25年度文部科学省「民間組織・支援技術を活用した特別支援教育研究事業」
障害のある児童生徒のための教材普及推進事業
視覚障害児童生徒のための「音訳教材」視覚障害児童生徒のための「音訳教材」視覚障害児童生徒のための「音訳教材」視覚障害児童生徒のための「音訳教材」製作製作製作製作マニュアルマニュアルマニュアルマニュアル
初版 2014年3月1日 発行
編集・発行 社会福祉法人日本ライトハウス
[連絡先] 〒550-0002 大阪市西区江戸堀 1-13-2
日本ライトハウス情報文化センター
TEL:06-6441-0015 FAX:06-6441-0095
http://www.iccb.jp/
原案執筆者(五十音順・敬称略)
久保 洋子(日本ライトハウス情報文化センター 音訳指導者)
山本 利和(大阪教育大学教育学部 教授)
本誌の無断転載・複製を禁じます。
本誌のPDFデータは日本ライトハウス情報文化センターの
ウェブサイトからダウンロードできます。
h t t p : / / w w w . i c c b . j p /