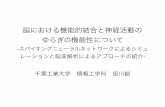行 内容 - health-net.or.jp活機能の維持・向上と生活の質の向上の観点から身体活動・運動 は非常に重要である。しかしながら,個人の意思や動機付けが出
高齢者生活機能評価マニュアル...- 5 -...
Transcript of 高齢者生活機能評価マニュアル...- 5 -...

- 1 -
高齢者生活機能評価マニュアル
高知県健康政策部健康づくり課 2010/03/08 ver3.00

- 2 -
目 次
生活機能評価の実施方法等について
1 生活機能評価とは・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
2 実施主体・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
3 対象者・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
4 生活機能チェック及び生活機能検査項目・・・・・・・・・・・・・・・・・・4
5 特定高齢者候補者選定の実施方法と基準・・・・・・・・・・・・・・・・・・5
6 生活機能評価の判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・6
7 特定高齢者の決定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・7
8(参考資料:厚生労働省作成) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・8
生活機能評価実施の流れと留意事項
1 生活機能評価の流れ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・12
2 基本チェックリストに関する留意事項・・・・・・・・・・・・・・・・・・・14
3 身長・体重・BMIについて・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・17
4 理学的検査について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・18
5 運動機能測定について・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・19
生活機能評価判定フローと医師の判断
1 特定高齢者の判定・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・23
2 介護予防事業の実施適否に関しての医師判断・・・・・・・・・・・・・・・・26
様式集(作成中)
1 健診結果通知・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
2 個人評価シート・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
3 結果一覧表・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27
4 健康診査用カルテ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・27

- 3 -
生活機能評価の実施方法等について

- 4 -
1.生活機能評価とは
生活機能評価とは、介護保険法に基づき実施される介護予防サービスの対象となる「特定高齢
者」を把握することを目的として、65歳以上の者の日常生活で必要となる機能(生活機能)の状
態を確認する健康診査をいう。
2.実施主体
市町村(一部事務組合、広域連合等を含む。)
3.対象者
当該市町村に居住地を有する 65歳以上の者(要支援、要介護認定者を除く介護保険第 1号被
保険者)。
4.生活機能チェックおよび生活機能検査項目
生活機能評価は、「特定高齢者の候補者」を選定する検査(「生活機能チェック(基本チェックリスト)」)と、受診者が「特定高齢者の候補者」に該当した場合に、介護予防サービスの実施の可否について判断するため実施する詳細な検査(「生活機能検査」)とで構成する。
(1) 生活機能チェック:「特定高齢者の候補者」の把握
ア 問診:既往歴、自覚症状、嗜好等
イ 生活機能に関する項目:基本チェックリストによるチェック(ただし、市町村が、
生活機能チェックを実施する前に、基本チェックリストを行い、特定高齢者の候補者
を選定している場合は、基本チェックリストは行わないものとする。)
ウ 身体計測:身長、体重
エ BMI(Body Mass Index:体格指数) 算出 =体重(kg)÷身長(m)÷身長(m)
オ 血圧測定(2回計測の場合は、各血圧値の平均値をとる)
カ 理学的検査(身体診察):視触診(歩行、関節も含む)、聴打診等
(2) 生活機能検査:基本チェックリストによるチェックで、特定高齢者の候補者に該当
する者に追加実施
ア 理学的検査:反復唾液嚥下テスト(RSST)、口腔衛生
イ 循環器検査:標準12誘導心電図
ウ 貧血検査:ヘマトクリット値、血色素量、赤血球数
エ 血液化学検査:血清アルブミン
オ 医師の判定

- 5 -
5.特定高齢者候補者選定の実施方法と基準
生活機能評価の実施の手順は、市町村が事前に生活機能チェック(基本チェックリストのみ)
を実施して候補者を選定し(この他、21 年度から要介護認定で非該当となった者も特定高齢者
の候補者となる)、後日健診実施機関がその他の検査等を実施する場合と、健診実施機関が生活
機能チェック等全部実施し、特定高齢者の候補者を選定する場合とに分け、下記の(1)及び
(2)により実施する。
(1) 市町村が独自に生活機能チェック(基本チェックリストのみ)を実施し、後日健診実施機関が検査等にて特定高齢者の候補者を選定する場合
ア 特定高齢者の候補者の選定
市町村は、第 1 号被保険者(要介護者及び要支援者を除く。)について、基本チェックリストを実施し、以下の基準に該当した者を特定高齢者の候補者として選定する。
(ア)設問1~20の計20問のうち、10問以上該当
(イ)設問6~10の計5問のうち、3問以上該当
(ウ)設問11~12の計2問のうち、2問該当
(エ)設問13~15の計3問のうち、2問以上該当
イ 生活機能チェックと生活機能検査の実施 健診実施機関は、市町村が選定した特定高齢者の候補者に対し、基本チェックリ
ストの内容(設問12 BMI値)の確認を行う。また、残りの生活機能チェックを行ない、特定高齢者候補者に該当する者には生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を医師が行う。
(2) 健診実施機関が生活機能チェック等全部実施し、特定高齢者の候補者を選定する場
合
ア 特定高齢者の候補者の選定する。 第 1 号被保険者について、生活機能チェックを実施し、基本チェックリストで以
下の基準に該当した者を特定高齢者の候補者として選定する。
(ア)設問1~20の計20問のうち、10問以上該当
(イ)設問6~10の計5問のうち、3問以上該当
(ウ)設問11~12の計2問のうち、2問該当
(エ)設問13~15の計3問のうち、2問以上該当
イ 生活機能検査の実施
特定高齢者の候補者に該当する者には生活機能検査を実施し、特定高齢者に該当する者であることの確認を医師が行う。

- 6 -
6.生活機能評価の判定
生活機能及び介護予防事業(「通所型介護予防事業」及び「訪問型介護予防事業」をいう。以
下同じ。)に関する評価については、基本チェックリスト、生活機能チェック及び生活機能検査
の結果を医師が総合的に判断するものとし、次のいずれかに区分する。
(1) 生活機能の低下あり
生活機能の低下があり、要支援・要介護状態となるおそれが高いと考えられる場
合で、地域支援事業実施要綱に定める「特定高齢者の候補者の基準」に該当し、か
つ地域支援事業実施要綱別添2の「特定高齢者の決定方法」に該当している場合
ア 介護予防事業の実施が望ましい
イ 医学的な理由により次の介護予防事業の利用は不適当
(ア) 運動器の機能向上に関するプログラム
(イ) 栄養改善に関するプログラム
(ウ) 口腔機能の向上に関するプログラム
(エ) その他のプログラム(閉じこもり、認知症、うつ病)
不適当とする理由の例:
生活機能の低下はあるが、心筋梗塞、骨折等の傷病を有しており、
・介護予防事業の利用により当該傷病の病状悪化のおそれがある
・介護予防事業の利用が当傷病の治療を行う上で支障を生ずるおそれがある
等の医学的な理由により、介護予防事業の利用は不適当であると判断される場合。
(2) 生活機能の低下なし
生活機能が比較的よく保たれ、要支援・要介護状態となるおそれが低いと考えら
れる場合で、特定高齢者の候補者の基準に該当しない場合又は特定高齢者の候補者
の基準に該当する場合であって「特定高齢者の決定」に至らなかった場合
(3) 各介護予防事業におけるサービスプログラムの提供について
平成20年度末現在、各事業実施主体が提供を考えているサービスプログラムの
提供予定は、下記の3つである。
ア 運動器の機能向上に関するプログラム
イ 栄養改善に関するプログラム
ウ 口腔機能の向上に関するプログラム
なお平成21年度現在、各事業実施主体における閉じこもり予防・認知症予防・う
つ病予防のサービスプログラムの提供については予定が無い。(個別対応をとる場
合はある)

- 7 -
7.特定高齢者の決定
基本チェックリストより「特定高齢者の候補者」として選定された者について、生活機能の評価結果
を踏まえて、(1)~(6)までの6カテゴリの該当基準により、特定高齢者を決定する。 ※ 特定高齢者候補者の選定(前述) 基本チェックリストによる「特定高齢者の候補者」としてのいずれかの選定基準4つ
(ア)設問1~20の計20問のうち、10問以上該当
(イ)設問6~10の計5問のうち、3問以上該当
(ウ)設問11~12の計2問のうち、2問該当
(エ)設問13~15の計3問のうち、2問以上該当
(1) 運動器の機能向上 <特定高齢者候補者が即、特定高齢者に決定となる>
基本チェックリスト設問6から設問10までの5項目のうち3項目以上に該当する者 (特定高齢者候補者の選定(イ)と同じ)
※ 運動機能測定について(任意検査項目)
<特定高齢者候補者が運動機能測定を実施し、特定高齢者の判断をする>
うつ予防・支援関係の項目を除く20 項目のうち10 項目以上該当し「特定高齢者候補者」と判定された者であって、基本チェックリスト設問6~設問10のうち3項目以上に該当していない者について、以下に示す運動機能測定を行った場合に3項目の測定の配点合計が5点以上となった場合についても、特定高齢者に該当する者とみなしてもよい。
運動機能測定項目 基準値 基準値に該当する場合の配点
男性 女性
握力(kg) <29 <19 2 開眼片足立時間(秒) <20 <10 2 10m歩行速度(秒) ≧8.8 ≧10.0 3 (5mの場合) (≧4.4) (≧5.0)
配点合計 0-4点・・・運動機能の著しい低下を認めず 5-7点・・・運動機能の著しい低下を認める
(2) 栄養改善
<特定高齢者候補者のうち、再度基本チェックリストから特定高齢者の判断をする>
基本チェックリスト設問11、設問12に該当する者 (特定高齢者候補者の選定(ウ)と同じ)
<特定高齢者候補者に生活機能検査を実施し、特定高齢者の判断をする>
血清アルブミン値が3.9g/dl未満 (3.8g/dl以下)

- 8 -
(3) 口腔機能の向上 <特定高齢者候補者のうち、再度基本チェックリストから特定高齢者の判断をする> 基本チェックリスト設問13から設問15までの3項目のうち2項目以上に該当する者 (特定高齢者候補者の選定(エ)と同じ)
<特定高齢者候補者に生活機能検査を実施し、特定高齢者の判断をする>
下記のうち1うでも該当する場合 ・医師の診察で、視診により口腔内の衛生状態に問題があることを確認 ・反復唾液嚥下テストが3回未満
(4) 閉じこもり予防・支援 <特定高齢者候補者のうち、再度基本チェックリストから特定高齢者の判断をする>
基本チェックリスト設問16に該当する者(設問17にも該当する場合は特に注意) (5) 認知症予防・支援 <特定高齢者候補者のうち、再度基本チェックリストから特定高齢者の判断をする>
基本チェックリスト設問18~設問20の計3問のうち、1問以上該当 (6) うつ予防・支援 <特定高齢者候補者のうち、再度基本チェックリストから特定高齢者の判断をする>
基本チェックリスト設問21~設問25の計5問のうち、2問以上該当 ※なお、認知症及びうつについては、特定高齢者に該当しない場合においても、可能な限り精神保健福祉対策の健康相談等によ
り、治療の必要性等についてアセスメントを実施し、適宜、受診勧奨や経過観察等を行うものとする。

- 9 -
参考

- 10 -

- 11 -
生活機能評価実施の流れと留意事項

- 12 -
1.生活機能評価の流れ
【生活機能チェック】
(1)問診
既往歴、自覚症状、嗜好等について聴取する。
(2)基本チェックリストの確認
既往歴等の問診(上記(1))とは別に、「基本チェックリスト」(様式2)により
生活機能に関するチェックを行う。
(3)身体計測
身長、体重の計測、BMIの計算を行う。
(4)血圧測定
できる限り自動血圧計を用いて(無い場合は水銀血圧計)、収縮期血圧、拡張期血
圧を測定する。収縮期 130mmHg 以上、または拡張期 85mmHg以上の場合は、受診者に
数回深呼吸をさせた後、もう一度測定する。測定記録は、1回目、2回目の両方の
結果を記入する。2回血圧測定した場合、判断に使う血圧値は2回の平均値とする。
握力検査は、採血検査がある場合は、採血前に実施するか、採血後15分以上って から行う。 ※ 受診者が収縮期血圧 180mmHg以上又は、拡張期血圧 110mmHg以上の場合には、過度の力を加える測定である握力検査を行わないこと(禁忌)。 よって、運動機能測定は必ず血圧測定の後に行うこと。
※ 収縮期血圧が 160mmHgまたは、拡張期血圧が 95mmHg以上の者については、握力
などの力を入れる測定は原則行わないが、保健師が受診者から日常の血圧状態を
聞き取り、日常においても収縮期血圧が 160mmHgまたは、拡張期血圧が 95mmHg以
上あると受診者が申告した者については、握力検査を行わないこと。そのとき保
健師が受診者から聞き取った血圧値を用紙余白メモしておくことが望ましい。
例外的に握力検査を含めた運動機能測定をする場合は、該当者の健康状態に留意
し、慎重に実施すること。
(5)診察(理学的検査)
聴打診、視診、触診等(歩行、関節も含む)の一般理学的検査を行う。
【生活機能検査】
(6)アルブミン検査
特定高齢者の候補者に該当した者に対し、血清アルブミン検査を実施する。特定
健康診査と同時実施する場合は、生化学検査用の採血において、アルブミン検査を
追加する。
(7)貧血検査
特定高齢者の候補者に該当した者に対し、貧血検査(ヘマトクリット値、血色素
量、赤血球数)及び反復唾液嚥下テスト)を実施する。

- 13 -
(8)心電図検査
特定高齢者の候補者に該当した者に対し、心電図検査を実施する。
(9)診察(理学的検査)
視診にて口腔内所見の確認、反復唾液嚥下テストを実施する。
明らかに素早く唾液を嚥下出来る者は、30秒間連続して続けなくてよい。
反復唾液嚥下テスト(RSST)
30秒間で唾液を3回以上飲み込めるかどうかのテストを行う。3回以上が正常と
みなされる。計測は、示指を舌骨相当部、中指を咽頭隆起に当て触診により回数を
カウントする。口腔乾燥がある場合は、尐量の水等で口腔内を潤してもかまわない。
(10)医師の判定
医師は、生活機能チェック及び生活機能検査(身体・口腔状況等)の結果から、
受診者の生活機能の低下有無について判断する。そして医師は、生活機能の低下あ
りと判定された者について、受診者の健診結果や受療状況を踏まえ、介護予防事業
プログラムの利用の適否について判断を行う。

- 14 -
2.基本チェックリストに関する留意事項 (1)基本チェックリストの構成
国が設定している基本チェックリストは全25項目の設問で構成される。質問の主旨は下
記カテゴリとなっている。全国統一設定のため、設問順番の変更や設問文字の変更は禁止である。 設問1~5 :手段的日常生活活動に関する質問 設問6~10 :運動器の機能向上に関する質問 設問11~12:栄養改善に関する質問 設問13~15:口腔機能の向上に関する質問 設問16~17:閉じこもり予防・支援に関する質問 設問18~20:認知症予防・支援に関する質問 設問21~25:うつ予防・支援に関する質問
特定高齢者の選定においては、回答の「0」又は「1」のうち、「1」と回答したものを「該当」とする。
日常生活
1 バスや電車で 1人で外出していますか 2 日用品の買物をしていますか 3 預貯金の出し入れをしていますか 4 友人の家を訪ねていますか 5 家族や友人の相談にのっていますか
0.はい 0.はい 0.はい 0.はい 0.はい
1.いいえ 1.いいえ 1.いいえ 1.いいえ 1.いいえ
運動機能
6 階段を手すりや壁をつたわらずに昇っていますか 7 椅子に座った状態から何もつかまらずに立ち上がっていますか 8 15分位続けて歩いていますか 9 この 1年間に転んだことがありますか 10 転倒に対する不安は大きいですか
0.はい 0.はい 0.はい 1.はい 1.はい
1.いいえ 1.いいえ 1.いいえ 0.いいえ 0.いいえ
栄養改善
11 6ヶ月間で 2~3kg以上の体重減尐がありましたか 1.はい 0.いいえ
12 身長・体重(BMI) 18.5未満なら該当 (注) 1.はい 0.いいえ
口腔機能
13 半年前に比べて固いものが食べにくくなりましたか 14 お茶や汁物等でむせることがありますか 15 口の渇きが気になりますか
1.はい 1.はい 1.はい
0.いいえ 0.いいえ 0.いいえ
閉じこもり
16 週に 1回以上は外出していますか 17 昨年と比べて外出の回数が減っていますか
0.はい 1.はい
1.いいえ 0.いいえ
認知症
18 周りの人から「いつも同じことを聞く」などの物忘れがあると言われますか
19 自分で電話番号を調べて、電話をかけることをしていますか 20 今日が何月何日かわからない時がありますか
1.はい 0.はい 1.はい
0.いいえ 1.いいえ 0.いいえ
うつ予防支援
21 (ここ 2週間)毎日の生活に充実感がない 22 (ここ 2週間)これまで楽しんでやれていたことが楽しめなく
なった 23 (ここ 2週間)以前は楽に出来ていたことが今ではおっくうに
感じられる 24 (ここ 2週間)自分が役に立つ人間だと思えない 25 (ここ 2週間)わけもなく疲れたような感じがする
1.はい 1.はい 1.はい 1.はい 1.はい
0.いいえ 0.いいえ 0.いいえ 0.いいえ 0.いいえ
(注)問 12 身長・体重(BMI)については、身体測定(身長・体重)より算出して該当・非
該当を判定する。

- 15 -
(2)基本チェックリストの考え方について
○基本チェックリストの設問は、原則、「している」か、「していない」かの「行動」を尋
ねる形式となっており、受診者は、普段の自身の行動について、ありのままを回答する。
○基本的には、受診者に自己記入してもらう。スタッフは、受診者が記入した基本チェッ
クリストを元に、各項目について回答の確認をする。
○基本チェックリストの目的は、特定高齢者の候補者の絞込みにあるため、本来、候補者
として把握される必要のある方が漏れてしまうことのないよう、受診者が判断に迷って
いる場合は拾い上げるような、柔軟な解釈をしてよい。
○回答は、「はい」または、「いいえ」の二者択一とするが、うつ項目等で受診者が判断
に迷っている場合は、どちらか「より受診者の思いに近い方」の回答を設問確認者が提
案する。
○OCRに転記する際は、基本チェックリストの番号が判定結果と連動しているため、番
号の並び替えはしないこと。
(3)各質問内容の解釈について
問1 行きたい場所へ、様々な手段を使って一人で外出しているかどうかの確認。必ずしも
バス、電車である必要はない。
問2 頻度や店までの距離には関係なく、日用品の購入をしているかどうかの確認。
(主に男性で、日用品の購入自体をしない習慣である場合「いいえ」とする)
問3 ATM・窓口での出し入れ、金銭管理をしているかのの確認。
(主に男性で、金銭管理自体をしない習慣である場合「いいえ」とする)
問4 社会活動性の確認。友人や近所への訪問の有無。“近所や友人の家は遠いから・・”
“友人は死んだから・・”等の回答の場合でも、訪ねることがなければ「いいえ」とす
る。
問5 社会活動性の確認。判断を伴う役割を果たしているかどうかを聞く質問。
“独居だから・・” “友達は死んだから・・”等の回答の場合でも相談にのる事がな
ければ「いいえ」とする。
問8 やすみやすみ歩くのは「いいえ」とする。
問9 自らの動作によって物につまづいたり、すべったりして、足の裏以外が地面に触れる
ことがあるかを確認する。歩行時のほか、自転車での転倒も含むが、交通事故は除外
する。
問10 日頃の行動で、常に足元に不安があって、行動に用心しているかどうかを確認する。
問13 咀嚼力低下のスクリーニング目的項目であるが、受診者が「半年前」と明確に比較す
ることは困難である。受診者の理解が難しい場合“最近、急に固い物が食べにくくな
ったか?”と問う。
問14 嚥下機能低下に関するスクリーニング目的項目であるため、その主旨を考えると1日
のうち、1回以上誤嚥・むせる程度(ほぼ毎日むせる)から該当とする。
問15 唾液分泌量低下のスクリーニング目的項目である。「常時、口の渇き」がある場合を
該当とする。日中も口渇が気になること。高齢者では睡眠中、口を開けて寝てる場合
(口呼吸、いびき)があるため、早朝口渇感を訴える者が多くみられる。

- 16 -
問16 外出は、介助されての外出も含む。外出とは、仕事、買い物、散歩、通院などで、庭
先のみやゴミだし程度は含まない。
問19 自分で電話番号を調べて(知人や番号案内に尋ねる、電話帳から調べるなどの手段を用
いて)電話をかけているかを確認。
問21~25 質問内容の補足や誘導は行わない。基本的には、文面どおりで、迷う場合はどち
らか近い方を回答とする。

- 17 -
3.身長・体重・BMIについて
設問12でBMIを計算で求めるにあたり、留意すべき点がある。
人による手計算と、後に電算による機械計算の検証が入り、安易に手計算で数値の四捨五入
などの「丸め」等を行うと設問12が“記入間違い”と判定され、生活機能検査の費用支払い
が出来ないトラブルが生じる恐れがある。
算出に係る基本数値は
身長は150.1cm というように整数3桁+小数1桁 (1m=100cm)
体重も100.3kg というように最大整数3桁+小数1桁
で入力されている。この小数点も含めた数値を計算式に当てはめて、算出されるBMI値が
18.5未満(18.49以下)かどうかが大変厳密に問われる。算出値は小数第2位(小数
2桁を四捨五入)まで用いて判断すること。
設問12は、18.5未満であれば「1.はい」となる。
例:身長180.0cm 体重が59.7kgの場合の BMI
59.8÷180.0÷180.0×100×100=18.42
18.42 の、小数第2位を四捨五入すれば 18.4 となり、「1.はい」となる。
例:身長180.0cm 体重が59.8kgの場合の BMI
59.8÷180.0÷180.0×100×100=18.45
18.45 の、小数第2位を四捨五入すれば 18.5 となり、「2.いいえ」となる。
BMI(Body Mass Index:体格指数)
算出式 =体重(kg)÷身長(cm)÷身長(cm)×100(mへ変換)×100(mへ変換)
(注)背中の曲がりがある受診者(円背)は、BMIが不正確になるのを考慮すること。

- 18 -
4.理学的検査について
生活機能チェックでは、一般的な診察に加えて下記(1)、(2)のチェックを行うこと。ま
た、特定高齢者の候補者に該当した場合は、(3)を追加して実施する。
(1)視診(口腔内)
・口腔内の衛生状態(歯垢・食物残渣の有無による清潔度や下苔の有無、あるいは口臭)のチェックを行う。
・口腔内の衛生状態に問題がある場合は「生活機能評価身体診査視診・触診」の「口腔所見」の枠にチェックをいれる。または、医師の診察所見部分に「500(口腔衛生の軽度不具合)」の所見コードを入力する。
(2)視診(歩行)、触診(関節)
身体的な不具合があり、介護予防事業(運動器の機能向上に関するプログラム)の実施に
は医学的観点から転倒、関節状態悪化等の恐れが強いかどうかの判断を行う。視触診では、
受診者が異常感を訴える局所や、有意な部分の性状を確認する。特に、関節の変形や関節
痛が強い・関節可動域の制限が強い・歩行が不安定かを調べる。
・介護予防事業実施に不適当な、医学的な関節異常所見があれば、「次の介護予防利用は不適
当(医師の判断)」の「運動機能向上」の枠にチェックをいれる。または、医師の診察所見
に「501(関節の軽度不具合)」の所見コードを入力する。
・介護予防事業実施に不適当な、医学的な歩行の不具合が認められる場合も、「次の介護予防
利用は不適当(医師の判断)」の「運動機能向上」の枠にチェックをいれる。または、医師
の診察所見に「502(歩行の軽度不具合)」所見コードを入力する。
所見コード 所見区分 対応コメント
501 軽度異常 関節の軽度不具合
502 軽度異常 歩行の軽度不具合
(3)反復唾液嚥下テスト
特定高齢者候補者のみに反復唾液嚥下テストを実施し、30秒間に2回以下の場合は「生活機能評価身体診査視診・触診」の「反復嚥下テスト該当」の枠にチェックをいれる。明らかに素早く唾液を嚥下出来る者は、30秒間連続して続けなくてよい。
所見コード 所見区分 対応コメント
500 軽度異常 口腔衛生の軽度不具合

- 19 -
5.運動機能測定について(任意検査)
生活機能評価では、うつ予防・支援関係の項目を除く設問1~20の計20問のうち、10
問以上該当し「特定高齢者の候補者」と判定された者であって、基本チェックリスト設問6~10の計5問のうち、3問以上に該当していない者については、下記の3項目の運動機能測定を行い、測定の配点合計が5点以上となった場合については、特定高齢者に該当する者とみなしてもよいこととなっている。
① 握力―上肢筋力の測定
② 開眼片足立時間―バランス能力の測定
③ 歩行時間―総合的基礎体力の測定
以下に各測定手順及び留意事項を示す。
(1)血圧測定
・血圧測定に関しては前述説明「生活機能評価の流れ」部分に実施手順および注意事項を
書いているので参照のこと。
(2)握力
ア 測定手順・留意点 ・血圧測定において高血圧状態の場合には注意すること。 ・握力検査は、採血検査がある場合は、採血前に実施するか、採血後15分以上たってか
ら行う。 ・握力計を使用して、効き手で 1回測定する。
・受診者ごとに握力計の「握り幅」を調節する。(人差し指の第二関節が直角になるように) ・測定姿位は両足を自然に開いて安定した直立姿勢とし、握力計の示針を外側にして体に
触れないようにして力一杯、握力計を握ってもらう。(図 1) ・測定の際は腕を自然に伸ばし、握力計を身体から離し、握る際に手を振らないように注
意する。(図 2) ・検者は受診者が力を入れるのにあわせて「掛け声」をかける。
図 1 握力の測定時の悪い例
握るときに手は振り上げない。 図 2

- 20 -
イ 使用器具・測定値記入の注意点
使用器具 スメドレー式握力計
受診者 1 人あたりに要する時間
約1分
記入の注意点
・測定値は小数点第一位まで記入する。 ・測定した側(左右)の欄に記入する。 ・測定不可は空白とする。 ・測定値を複数記入した場合は最高値で判定とする。
(3)開眼片足立ち
ア 測定手順・留意点 ・目を開けた状態で、片足だけでどのくらいの時間立っていられるかをストップウオッチを用いて測定する。測定は硬い床面で行う。(図 3)
・挙げる足は、好きな側でよい。足の挙げ方は最も安定する形でよいが、反対側の足に付けたり支えたりしてはならない。(図 4)
・測定は、片足を挙げたときから足が床に着くまでの時間を測定する。 ・軸足が動いたとき(ずれたとき)はその時点までの時間を測定する。 ・測定時間は 60秒までとし、60秒を経過した者はそこで打ち切る。 ・一回目で目標時間(60秒)に達しなければ、2回目の試行を行う。 ・受診者が倒れる可能性があるため、検者は細心の注意を払い、受診者がよろけたときは即座に保持できるようにする。
・目標時間に達せずに2回試行した場合は、大きい値の方を採用する。
イ 使用器具・測定値記入の注意点
使用器具 ストップウォッチ
受診者 1 人あたりに要する時間
約1~3分
記入の注意点
・片足で全く立てない(足が挙げられない)者は0秒、片足を一瞬しか挙げられない(1秒未満)者は1秒、ケガや障害などで測定が不能の場合や拒否をした場合は空白とする。
・読みとりは小数点第一位を四捨五入して整数で記入する。 (例:18秒)
利き腕で測定し成績を記入する。 複数記入の場合は最高値を採用して判定 測定不可は空白
片足立ち測定時の悪い例
挙げている足を反対側の足につけたり支えたりしない。
なお、挙げる足の左右、高さ、挙げ方はやり
やすい方法でよい。
図4 図 3

- 21 -
(4)歩行テスト【5m・(10m)歩行】通常歩行
ア 測定手順・留意点 ・検者は 1名とする。 ・受診者に、11(16)mの歩行路上を教示に従い歩いてもらう。
・教示は「いつも歩いている速さで歩いてください」に統一する。 検者は受診者の体幹の一部(腰または肩)が手前のテープ・3m地点を超えた地点から8(13)m地点のテープを身体の一部が超えるまでの所要時間をストップウォッチを用いて 0.1秒単位で測定する。(例:4.2(8.2)秒)
・受診者との間隔は、あまり遠すぎずかつ受診者の歩行の邪魔にならない程度で、転倒しそうになったらすぐに支えられる距離とする。(図 5,6)
・ただし、受診者より前を歩くことは、誘導することになるので避ける。 ・1回実施する。明らかに通常歩行速度よりも早すぎると判断される場合は、本人に確認した上で再度測定する。
・検者はテスト中における受診者の転倒に気をつける。歩行能力の低い者では補助員をつけるとなお好ましい。
イ 使用器具・測定値記入の注意点
使用器具 ストップウォッチ
受診者 1 人あたりに要する時間
約1~3分
記入の注意点 ・測定値は小数点第二位を四捨五入して小数点第一位まで記入する。
1回実施し成績を記入する。 複数記入の場合は最高値を採用して判定 全く挙上できない場合は0 一瞬挙上できた場合は1 ケガ等で測定不可は空白とする。
5m・10m歩行いずれか採用した方の成績を記入する。 測定不可は空白
歩行テストの測定風景
図 6 図 5
検者と受診者との距離は何かあった場合に対処できるよう遠すぎないようにする。

- 22 -
生活機能評価判定フローと医師の判断

- 23 -
1.特定高齢者の判定
(1) 生活機能評価の目的について
65才以上の高齢者のうち、介護保険サービス受給の対象者にはなってないが、日常生活
において各種の虚弱が見られることがある。生活機能評価の目的は、これらの虚弱者を見い
だし、介護予防事業のサービスを実施することで、当該虚弱からの改善を目指す。
(2) 特定高齢者の判定方法
特定高齢者の判定方法の主な流れは下記のとおりである。
ア 基本チェックリスト(設問25問)による特定高齢者候補者の選定
イ 特定高齢者候補者に生活機能検査の実施
ウ 基本チェックリストと生活機能検査の結果を踏まえ、特定高齢者の選定および虚弱の改
善に対して必要と思われる6つのサービスプログラムの選定
エ 診察医師による医学的観点からの介護予防事業のサービスの適否判断
(3) 各介護予防事業におけるサービスプログラムの提供について(再掲)
現在、各事業実施主体が提供を考えているサービスプログラムの提供の予定は、下記の3
つである
ア 運動器の機能向上に関するプログラム
イ 栄養改善に関するプログラム
ウ 口腔機能の向上に関するプログラム
なお各事業実施主体における閉じこもり予防、認知症予防、うつ病予防のサービスプログラ
ムの提供については現在、予定が無い。(個別対応をとる場合はある)

- 24 -
(4) 判定の流れ:6つの介護予防事業サービス適否の選定
(5) 判定の流れの補足
・ 基本チェックリスト設問12は身長・体重より算出されたBMI値で18.5未満の者が
該当者となる。(手計算は要注意。特定健康診査実施の場合は身長・体重測定値より自動的
に再計算・再判定される。)
・ 閉じこもり予防・支援対象者は、基本チェックリスト設問16に該当する者で、設問17
にも該当する者は、特に注意が必要な対象者となっている。
設問による特定高齢者候補者の選定基準
以下の①~④のいずれかに該当するか?① 設問1~20の計20問のうち、10問以上該当② 設問6~10の計5問のうち、3問以上該当③ 設問11~12の計2問のうち、2問該当④ 設問13~15の計3問のうち、2問以上該当
特定高齢者候補者に該当
生活機能検査の実施心電図・貧血検査・血清アルブミン検査追加診察所見:反復唾液嚥下テスト、口腔衛生
特定高齢者の決定基準
A 運動器の機能向上関係A-1 設問6~10の計5問のうち、3問以上該当A-2 設問1~20の計20問のうち、10問以上該当 かつ「運動機能測定」を行った結果が5点以上
B 栄養改善関係B-1 設問11~12の計2問のうち、2問該当B-2 血清アルブミン値が3.8g/dl以下
C 口腔機能の向上関係C-1 設問13~15の計3問のうち、2問以上該当C-2 診察結果にて口腔衛生の軽度不具合ありC-3 反復唾液嚥下テストが3回未満
D 閉じこもり予防・支援関係D-1 設問16が該当
E 認知症予防・支援関係E-1 設問18~20の計3問のうち、1問以上該当
F うつ病・支援関係F-1 設問21~25の計5問のうち、2問以上該当
「生活機能の低下あり」と判定 「生活機能の低下なし」と判定
医師の判断 医学的な理由により下記の介護予防事業A-Fのうち該当した介護予防事業について、医師が の実施は不適当と医師が判断医学的観点からみた介護予防事業利用の適否 A 運動器の機能向上に関するプログラム
B 栄養改善に関するプログラムC 口腔機能の向上に関するプログラムDEF その他(閉じこもり、認知症、うつ病)
A-Fのうち該当した介護予防事業の利用が望ましい 不適当とされた介護予防事業の利用は不可
いずれかに該当する
いずれにも該当しない
いずれかに該当する(特定高齢者に該当)
不適当な事業あり
全て適当
適当な事業のみ 不適当な事業
いずれにも該当しない

- 25 -
(6) 運動機能測定の判断基準と各測定項目の配点
運動機能測定項目 基準値 基準値に該当する場合の配点
男性 女性 握力(秒) <29 <19 2 開眼片足立時間(秒) <20 <10 2 10m歩行速度(秒) ≧8.8 ≧10.0 3 (5mの場合) ( ≧4.4) (≧5.0)
配点合計 ※0-4点・・・運動機能の著しい低下を認めず 5-7点・・・運動機能の著しい低下を認める
※ 生活機能の顕著な低下を認めずと判断されるが、今後も十分なフォローアップが必要である。
各測定項目の配点
配点
<29(Kg) 2点
≧29(Kg) 0点
<19(Kg) 2点
≧19(Kg) 0点
<20(秒) 2点
≧20(秒) 0点
<10(秒) 2点
≧10(秒) 0点
≧8.8(秒) 3点
<8.8(秒) 0点
≧10(秒) 3点
<10(秒) 0点
≧4.4(秒) 3点
<4.4(秒) 0点
≧5(秒) 3点
<5(秒) 0点
≧13.8(秒) 3点
≦13.7(秒) 0点
≧14.3(秒) 3点
≦14.2(秒) 0点
≧14.2(秒) 3点
≦14.3(秒) 0点
≧20.4(秒) 3点
≦20.3(秒) 0点
5m歩行速度
男 性
女 性
Up&Go(参考)
男性
65~79歳
80歳以上
女性
65~79歳
80歳以上
開眼片足立ち
男 性
女 性
10m歩行速度
男 性
女 性
運動機能測定項目
握 力
男 性
女 性

- 26 -
2.介護予防事業の実施適否に関しての医師判断 各介護予防事業に関しては、健診医師が事業実施にあたり適否判断をする。 (1) 医師の判断
医師が生活機能検査結果等から、介護予防事業実施にもっぱら不適当と判断する例。
この他にも、心筋梗塞または、骨折等の傷病を有しており、介護予防事業の利用により当該
傷病の病状悪化のおそれがある、または介護予防事業の利用が当傷病の治療を行う上で支障を
生ずるおそれがある場合は、プログラム実施は不適当と思われる場合がある。健診医師は、受
診者の現病歴、既往歴、自覚症状、診察所見を踏まえて、介護予防事業の一部または全部不適
当の最終判断を行う。
(2) 補足
健診医師は、生活機能評価および生活機能検査の結果だけからの判断である。もし、受療中の者で介護予防事業実施が不適当となった者のうち、主治医に当該介護予防事業参加にあたって、治療に支障がなしの判断を文面でもらった場合は、事業実施主体の責任で事業に参加させることが出来る。
検査項目 検査値および判定 下記の介護予防事業は不適当
貧血検査Hb75才未満男性:11.0g/dl未満またはHb75才以上男性:10.0g/dl未満またはHb女性 :10.0g/dl未満
運動器の機能向上に関するプログラム実施は不適当
その他その他の検査結果、医師の診察結果 医師が指摘したプログラムの実施
は不適当
診察所見関節の軽度不具合ありまたは歩行の軽度不具合あり
運動器の機能向上に関するプログラム実施は不適当
血圧測定収縮期血圧180mmHg以上または拡張期血圧110mmHg以上
運動器の機能向上に関するプログラム実施は不適当
心電図心臓判定で「要精密検査」または「要医療」
運動器の機能向上に関するプログラム実施は不適当

- 27 -

- 0 -
V1.00:08/08/29 初期修正版
V1.01:08/09/01 フロー修正
V2.00:09/02/20 特定健診用に修正
V2.10:09/02/23 修正
V2.11:09/02/26 選定フローの説明追加
V2.20:09/03/02 6つの介護予防事業等の修正
V2.21:09/03/05 血圧測定に関する文言の修正
V2.30:09/03/21 診察に関する流れの修正・医師による介護予防事業不適当の判断部分修正
V2.31:09/03/23 文面修正
V2.32:09/04/03 文面修正
V3.00:10/03/08 BMI判断修正、OCR記録方法修正
発行 高知県健康政策部健康づくり課
(医学記述:医師 杉本章二)
平成 22年 3月 8 日 〒780-8570 高知県高知市丸ノ内 1丁目 2番 20号 TEL088-823-9675 FAX088-873-9941 E-mail:[email protected]







![[AWS Summit 2012] 事例セッション #3 金融機関でのクラウド活用について -金融機関向けAWS対応セキュリティリファレンスの活用と事例-](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/558d2588d8b42a21638b45db/aws-summit-2012-3-aws-.jpg)