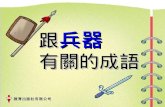兵庫県の気候変動適応の 取組についてkinki.env.go.jp/06_資料6_兵庫県取組資料.pdf兵庫県農政環境部環境管理局 温暖化対策課 兵庫県の気候変動適応の
非核兵器技術の開発と抑止との関係 極超音速兵器を …HTV-2...
Transcript of 非核兵器技術の開発と抑止との関係 極超音速兵器を …HTV-2...

非核兵器技術の開発と抑止との関係
23
非核兵器技術の開発と抑止との関係 ―極超音速兵器を中心に―
有江 浩一
〈要旨〉
冷戦後の抑止において、非核兵器の比重が高まりつつある。アメリカは、抑止政策の一環として非核極超音速兵器、レーザー兵器、電磁レールガン等の非核兵器技術の開発を積極的に進めている。これに対して中国は核・非核両面で抑止力の向上を図っており、ロシアは核抑止を重視する方向を示している。本稿では、極超音速兵器を中心とする新たな非核兵器技術の動向を概観し、これらの非核兵器技術が従来の核抑止といかなる関係性を持ち得るか検討した上で、非核兵器技術の開発に伴って抑止がどのように変化するのか、またアメリカの拡大抑止にどのような影響が及ぶのかを考察する。極超音速兵器技術の動向は未知数であるが、これを駆使した非核戦略兵器が実戦配備されるようになれば、アメリカの抑止政策は、核兵器による懲罰的抑止に依拠してきた従来の政策から、非核兵器による拒否的抑止を重視するものへと変化する可能性がある。これに伴い、わが国に対するアメリカの拡大抑止にも同様の影響が及ぶものと考えられる。
はじめに
冷戦後の抑止において、非核兵器の比重が高まりつつある。アメリカは、「通常兵器型即時全地球攻撃(Conventional Prompt Global Strike: CPGS)1」構想のもとで、非核兵器による戦略攻撃力を獲得することにより、抑止における核兵器の役割を低下させようとしている。CPGS構想において開発が進められている非核兵器技術の一つが極超音速兵器(hypersonic weapon)に関するものである。また、中国とロシアはアメリカの CPGS構想が核兵器国間の戦略的安定性を損なうと懸念を表明しつつも、核・非核両用の極超音速兵器の開発を進めており、インドもロシアと共同で極超音速兵器を開発中である。さらに、極超音速兵器の他にも様 な々非核兵器技術が開発されつつあり、既に米海軍はレーザー兵器や
1 CPGSの定訳はないが、ここでは次の文献から引用した。森本敏「米国のアジア重視政策と日米同盟」『国際問題』No. 609、2012年 3月、46頁注 (28)、http://www2.jiia.or.jp/kokusaimondai_archive/2010/2012-03_005.pdf?noprint. これを含め、以降のURLのアクセス日付は、記載されているものを除き全て2016年12月7日である。

24
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
電磁レールガンの試験に成功したとされている 2。これらの非核兵器技術と抑止との関係については、これまでに様 な々議論がなされてきた。それらの議論は、抑止における核兵器への依存を低減し得る可能性を論じたものが多く、中には技術革新によって非核兵器が核兵器に代わる抑止力となり得るといった極論もある 3。他方、非核兵器技術の向上に伴い、非核兵器において既に優位にあるアメリカに対抗して中国やロシアが核兵器の増強に乗り出す恐れがあることから、核抑止との関係性にのみ焦点を当てるべきではないとする議論がある 4。また、非核兵器技術を従来の核兵器システムとうまく組み合わせて抑止を強化すべきという意見がある一方で、そうすることにより核兵器と非核兵器の境界線が曖昧になって抑止が不安定化するとの指摘もある 5。以上の議論を踏まえつつ、本稿では、極超音速兵器を中心とする新たな非核兵器技術の動向を概観し、これらの非核兵器技術が従来の核抑止といかなる関係性を持ち得るか検討した上で、非核兵器技術の開発に伴って抑止がどのように変化するのか、またアメリカの拡大抑止にどのような影響が及ぶのかを考察する。
2 防衛省『平成 27年版 日本の防衛―防衛白書』(日経印刷、2015年)133頁。3 こうした議論は、冷戦後の早い時期にすでに行われていた。Gary L. Guertner, Deterrence and Conventional
Military Forces, Strategic Studies Institute, U.S. Army War College, May 20, 1992, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a251476.pdf. Seth Cropsey, “Life after Proliferation: The Only Credible Deterrent,” Foreign
Affairs, Vol. 73, No. 2, March/April 1994, pp. 14-20. また、カートライト(James E.Cartwright)元米戦略軍司令官は 2007年の議会公聴会で CPGS技術による核兵器の代替可能性を主張している。U.S. House of Representatives Armed Services Committee, Hearing on National Defense Authorization Act for Fiscal Year
2008 and Oversight of Previously Authorized Programs: Budget Request from the U.S. Strategic Command,
Northern Command, Transportation Command, and Southern Command, H.A.S.C. No. 110-40, 110th Congress, 1st session, March 21, 2007, p. 6, http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/CHRG-110hhrg37320/pdf/CHRG-110hhrg37320.pdf, accessed on October 15, 2015.
4 Andrew Futter and Benjamin Zala, “A Sustainable Approach to Nuclear Zero: Breaking the Nuclear-Conventional Link,” Oxford Research Group, October 25, 2013, http://www.oxfordresearchgroup.org.uk/sites/default/files/A%20Sustainable%20Approach%20to%20Nuclear%20Zero.pdf.
5 Michel Fortmann and Stéfanie von Hlatky, “The Revolution in Military Affairs: Impact of Emerging Technologies on Deterrence,” in T. V. Paul, Patrick M. Morgan, and James J. Wirtz, eds., Complex
Deterrence: Strategy in the Global Age (Chicago, IL: University of Chicago Press, 2009), pp. 312-315.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
25
1 非核兵器技術の動向
(1)極超音速兵器の開発状況①アメリカ極超音速兵器とは、一般にマッハ 5以上の極超音速で飛行する精密攻撃兵器を指す 6。米国防総省は、2003年 5月にCPGS構想を提起し、地球上のあらゆる目標を1時間以内に精密攻撃できる非核兵器の取得を目指すとした 7。CPGS構想では、全地球を射程に収め得る極超音速兵器技術が求められており、その有力な候補が「極超音速ブースト滑空(hypersonic
boost-glide: HBG)」と呼ばれる技術である。HBG技術は、飛翔体の空力学的揚力によって大気圏上層を跳躍・滑空させることで飛行距離を延伸するものである 8。HBG飛翔体は推進装置を持たず、揚力を得るための特殊な形状に加工されており、ロケットで大気圏外に打ち上げられた直後にロケットから切り離されて大気圏上層に再突入し、そこで跳躍と滑空を繰り返しつつ数千キロメートルに及ぶ長距離を極超音速で飛行して目標に着弾する 9。アメリカでは、CPGS構想のもとでHBG技術を用いた極超音速兵器の研究開発が行われているが、まだ兵器としての実用段階には至っていない。HBG技術が兵器として実用化されれば、HBG飛翔体はロケットによる打ち上げ後に通常の弾道ミサイルの軌道と異なる大気圏上層を飛行するため、ミサイル防衛(MD)を回避できると見られている 10。他方、その実用化にあたっては、飛翔体が大気圏に再突入した際に生じる摩擦熱に長時間晒される点や、飛翔体が大気のイオン化によるプラズマに覆われて外部との通信が遮断されるために精
6 Robert Farley, “A Mach 5 Arms Race? Welcome to Hypersonic Weapons 101,” The National
Interest, December 31, 2014, http://nationalinterest.org/feature/mach-5-arms-race-welcome-hypersonic-weapons-101-11935. Oxford Dictionaries, http://www.oxforddictionaries.com/definition/english/hypersonic.
7 James M. Acton, Silver Bullet? Asking the Right Questions About Conventional Prompt Global Strike (Washington, DC: Carnegie Endowment for International Peace, 2013), p. 1, http://carnegieendowment.org/files/cpgs.pdf.
8 HBG技術は、1930年代にオーストリアのロケット工学者ゼンガー(Eugen Sänger)が発案したとされる。ゼンガーは、特殊な形状をした有翼飛翔体を液体燃料ロケットエンジンでマッハ 24まで加速して大気圏外に突出させ、そこでエンジンを停止し大気圏に滑空接触させて揚力を得つつ大気圏上層を何回もスキップさせることにより、長距離の極超音速飛行が可能になると考えた。Maj. Kenneth F. Johnson, “The Need for Speed: Hypersonic Aircraft and the Transformation of Long Range Airpower,” School for Advanced Air and Space Studies, Air University, June 2005, xii-xiii, http://www.dtic.mil/dtic/tr/fulltext/u2/a477042.pdf. Roy F. Houchin II, US
Hypersonic Research and Development: The Rise and Fall of Dyna-Soar, 1944-1963 (London and New York: Routledge, 2006), p. 8.
9 Acton, Silver Bullet? p. 6.10 James Martin, Hyper-glide Delivery Systems and the Implications for Strategic Stability and Arms
Reductions, Reports, Calhoun: the Naval Postgraduate School Institutional Archive, April 2015, p. 3, http://calhoun.nps.edu/bitstream/handle/10945/45558/Hyperglide%20Final%20Report.pdf?sequence=1.

26
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
密誘導が困難になる点など、解決すべき課題が山積している 11。現在、CPGS構想のもとで兵器化を目指して開発が進められているHBG飛翔体としては、米空軍が米国防高等研究計画局(DARPA)と共同で開発中の「極超音速試験飛翔体(Hypersonic Test Vehicle
2: HTV-2)」と、米陸軍が開発中の「先進極超音速兵器(Advanced Hypersonic
Weapon: AHW)」がある。HTV-2は、HBG技術を用いてマッハ 20で全地球規模の長距離飛行を目指す非核極
超音速試験飛翔体である。HTV-2の飛行試験はミノタウロス IV(Minotaur IV)ロケットを使用してこれまでに 2回行われた。2010年の初試験では 9分間の極超音速飛行を達成したものの、2011年の試験では飛翔体が制御不能となり失敗に終わっている12。また、AHWは、HTV-2と同じくHBG技術を用いた非核極超音速飛翔体であるが、HTV-2よりも射程が短いため、米本土への配備ではなく前方展開して運用されると思われる。AHWは 2011年の初飛行試験では成功を収めたものの、2014年の第 2回目試験では打ち上げ直後に故障が見つかり試験中止となっている 13。これらの他に、CPGS構想の代替案となり得る極超音速兵器技術として、米空軍・
DARPA・NASAが共同開発中のX-51A(通称「ウェーブライダー」)、米海軍が開発中の「非核弾頭型トライデント(Conventional Trident Modification: CTM)」がある。X-51Aは、B52戦略爆撃機を母機とするスクラムジェットエンジン推進の非核極超音速巡航ミサイル試験機である。X-51A は 2010年の初飛行試験でマッハ 5を達成したものの飛行時間が短く、続く2011年と2012年の飛行試験も失敗に終わったが、4回目となる2013
年の試験ではマッハ 5で数分間の持続飛行に成功した 14。また、CTMは、トライデントII
潜水艦発射弾道ミサイル(SLBM)に非核弾頭を搭載する構想であるが、核弾頭装備のSLBMと誤認される恐れがあると指摘されている 15。
11 Johnson, “The Need for Speed,” pp. xxiii, 1-1iii.12 Amy F. Woolf, “Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles: Background and
Issues,” Congressional Research Service, R41464, February 24, 2016, pp. 17-19, https://fas.org/sgp/crs/nuke/R41464.pdf.
13 Ibid., pp. 19-20.14 “X-51A Waverider Achieves Goal on Final Flight,” Aviation Week, May 2, 2013, http://aviationweek.com/
defense/x-51a-waverider-achieves-goal-final-flight. なお、スクラムジェットエンジンとは、マッハ 4以上の超音速での動力飛行に使用されるエンジンとして研究が進められているものであり、超音速で吸い込まれた高温の空気をエンジン内部で圧縮・減速せず、そのままの速度で燃焼させる形式のラムジェットエンジンの一種である。ラムジェットは、回転式の圧縮機を使用せずに空気の勢いを利用して圧縮する形式のジェットエンジンで、エンジン内部の空気の通路を狭くすることで空気の流れを堰き止めて圧縮する形式である。ラムジェットでは、エンジン内部の空気の速度はマッハ1(亜音速)以下になるが、飛行速度が上がっていくにつれて吸い込んだ空気の温度や圧力が過大になり、性能が低下する。「スクラムジェットエンジン推力を従来の 3倍以上に増強」航空宇宙技術研究所(NAL)プレスリリース、2003年 2月 4日、http://www.jaxa.jp/press/nal/20030204_engine_j.html.
15 Woolf, “Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles,” pp. 10-11, 35-39.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
27
アクトン(James Acton)は、CPGSを運用するためには、極超音速兵器技術に加えて、C4ISRや戦闘損害評価などの様 な々機能(enabling capabilities)が必要になると指摘する。特に、多様な情報源から目標情報を収集・分析して意思決定者たる米大統領へ正確に伝達するシステムや、CPGSによる目標攻撃の成果を遠距離から評価・判定する仕組みが不可欠だという16。
②中国、ロシア、インド中国は、アメリカの非核極超音速兵器の開発状況を注視しつつ、それに懸念を表明する一方で、MDなどの対抗手段とともに同種の攻撃兵器の開発を進めている 17。2014年 1月には、中国による極超音速飛翔体Wu-14の初飛行試験が成功したと報じられた 18。同年 8
月の第 2回目の試験は失敗に終わったものの、それ以降の試験は全て成功したものと見なされている。Wu-14は、HBG技術を用いて軌道を急激に変更することによりMDを回避できる利点を持ち、2015年11月の第6回目試験では米国防総省によりDF-ZFと呼称されている。Wu-14(DF-ZF)の開発動向については、中国は米空軍のHTV-2のような全地球規模の長距離攻撃兵器としてではなく、当面はDF-21などの中距離弾道ミサイルをブースターとしたHBG技術開発を進めるとの見方もあるが 19、DF-41などの大陸間弾道ミサイル(ICBM)にも搭載可能であることから将来的には米本土を射程に収める戦略攻撃兵器の開発を目指すものと思われる20。また、非核極超音速兵器の開発を目指すアメリカのCPGS構想と異なり、中国は極超音速兵器に核・非核両方の弾頭を搭載するものと見られており、この点では次のロシアも同様である 21。ロシアは、旧ソ連時代からHBG技術に対する関心をもっていたとされる 22。旧ソ連時代に
16 Acton, Silver Bullet? pp. 88-90.17 Lora Saalman, “Prompt Global Strike: China and the Spear,” APCSS, April 2014, http://apcss.org/
wp-content/uploads/2014/04/APCSS_Saalman_PGS_China_Apr2014.pdf.18 Bill Gertz, “China Conducts First Test of New Ultra-High Speed Missile Vehicle,” Washington Free
Beacon, January 13, 2014, http://freebeacon.com/national-security/china-conducts-first-test-of-new-ultra-high-speed-missile-vehicle/.
19 Richard D. Fisher, Jr., “US Officials Confirm Sixth Chinese Hypersonic Manoeuvring Strike Vehicle Test,” Jane’s Defence Weekly, November 26, 2015, http://www.janes.com/article/56282/us-officials-confirm-sixth-chinese-hypersonic-manoeuvring-strike-vehicle-test, accessed on January 26, 2016.
20 “China, India and Russia have supersonic cruise missiles and are nearing hypersonic cruise missiles,” Nextbigfuture, March 22, 2015, http://www.nextbigfuture.com/2015/03/china-india-and-russia-have-supersonic.html.
21 Philip Ewing, “Arms race goes hypersonic,” Politico, August 11, 2015, http://www.politico.com/story/2015/08/russia-china-arms-race-goes-hypersonic-weapons-future-121230.
22 例えば、スターリン(Josef Stalin)はゼンガーのHBG研究に執心していた。Robert Godwin, ed., Dyna-Soar:
Hypersonic Strategic Weapons System (Burlington: Apogee Books, 2003), p. 7.

28
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
はラムジェットエンジンを用いたHBG技術研究が行われ、実験ではマッハ 5以上の極超音速飛行を達成したものの、ソ連崩壊によって研究は頓挫した 23。冷戦後、ロシアは 2009年に極超音速兵器技術の研究を再開したが、これは旧ソ連時代の研究成果に基づくものとされる 24。現在、ロシアはYu-71と呼ばれる極超音速兵器を開発中であり、2015年 2月に秘密裏の初飛行実験を行った。Yu-71を含むロシアの極超音速兵器開発は「4202計画(Project
4202)」の名の下で行われており、核弾頭を搭載した約 24基のYu-71ミサイルを2020年から2025年までの間に実戦配備するとの見方もある 25。また、こうしたロシアの極超音速兵器開発にフランスの企業が技術協力などで関与しているとの指摘もある 26。インドは、ロシアと共同で極超音速兵器の開発に取り組んでおり、その前段階としてマッハ約 3のブラモス(BrahMos)超音速対艦巡航ミサイル PJ-10を開発した。これに続いて、インドは最高速度マッハ 7の極超音速で飛行する「ブラモス 2(BrahMos-II)」の開発を計画している。ブラモス 2の射程は 290キロメートルと見られており、アメリカのCPGSのような長距離の戦略兵器ではなく短距離の戦術兵器と考えられる。ブラモス 2はスクラムジェットエンジン推進で、インドは 2017年までに飛行試験の準備を整えると見られている 27。なお、共同開発を担当しているブラモス・エアロスペース社は、スクラムジェット推進技術への繋ぎとして、PJ-10に使用されているラムジェット技術を向上させて低速域の極超音速飛行を達成することも検討している 28。
(2)その他の非核兵器技術の動向ここでは、レーザー兵器とレールガンの開発状況を概観する。レーザー兵器については、アメリカは 1960年代から技術開発を続けており29、その先鞭をつけたのは 1960年に合成ル
23 “Hypersonic weapon: New US bomb kills long before you hear it,” RT, November 18, 2011, https://www.rt.com/news/pentagon-new-bomb-681/.
24 “Russia pursues hypersonic weapon research,” Voice of Russia, May 12, 2013, http://sputniknews.com/voiceofrussia/2013_05_12/Russia-pursues-hypersonic-weapon-research/.
25 ただし、2015年 2月のYu-71の実験は失敗したとされていることから、これはかなり楽観的な見方である。“Will Russia Really Build 24 Hypersonic Nuclear Missiles by 2020?” The National Interest, June 30, 2015, http://nationalinterest.org/blog/the-buzz/will-russia-really-build-24-hypersonic-nuclear-missiles-by-13230.
26 Bill Gertz, “French Technology Helping Russian Hypersonic Missile,” Washington Free Beacon, December 10, 2015, http://freebeacon.com/national-security/french-technology-helping-russian-hypersonic-missile/.
27 “China, India and Russia have supersonic cruise missiles and are nearing hypersonic cruise missiles”. 塚本勝也「精密誘導兵器拡散の東アジアへの影響」『防衛研究所紀要』第 17巻第 1号、2014年 10月、12頁。
28 “BrahMos pushing hypersonic ramjet technology as scramjet stopgap,” FlightGlobal, August 27, 2015, https://www.flightglobal.com/news/articles/brahmos-pushing-hypersonic-ramjet-technology-as-scr-416119/.
29 Jason D. Ellis, Directed Energy Weapons: Promise and Prospects, Center for a New American Security, April 2015, pp. 24-31, http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/CNAS_Directed_Energy_Weapons_April-2015.pdf, accessed on December 8, 2015.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
29
ビーによるレーザー発生装置を開発したメイマン(Theodore Maiman)であった。それ以降、軍事技術としての高出力レーザーの研究が進み、1968年に 138キロワットの連続出力実験が成功し、さらに 1980年には中赤外線先進化学レーザーで 2メガワットの出力を達成した。レーザーの兵器化には数々の技術的困難を伴ったが、米空軍はボーイング 747改造機搭載の空中発射レーザー(Airborne Laser: ABL)により弾道ミサイルを発射直後のブースト段階で破壊するMDシステムの開発に着手した 30。その結果、ABLは 2010年にミサイル迎撃実験に成功した。これを受けて、現在、米国防総省は高高度無人機にレーザー発射装置を搭載する構想を検討している 31。
ABLに使用される化学レーザー(chemical oxygen iodine laser: COIL)はメガワット級の大出力を誇るものの、発射回数が増えれば化学燃料の再補給のために基地へ戻らねばならないという欠点を持っていた 32。また、ABLは射程が短いため、目標近くまで接近する必要があり、敵の対空砲火に晒される危険性もあった。米国防総省の無人機レーザー兵器構想を進めるにあたっては、射程を延伸するためにABLの20倍から30倍の出力を持つレーザーの開発が必要とされる 33。固体レーザー(solid state laser: SSL)の兵器化も進んでいる。米海軍は、中国などによ
る対艦巡航ミサイル(ASCM)及び対艦弾道ミサイル(ASBM)攻撃への対抗策の一環として、高出力の固体レーザーにより数キロメートル先の目標を迎撃する短射程の艦載レーザー兵器を開発中である。2014年 8月には、「レーザー兵器システム(Laser Weapon System:
LaWS)」を搭載したドック型輸送揚陸艦ポンセ(USS Ponce)のペルシャ湾での試験運用が開始された。ポンセに搭載されたLaWSは出力30キロワットで、1.6キロメートル先の小型ボートやドローンを無力化できる程度だが、1発当たりの単価が安く運用コストが低いという利点を持つ。米海軍はLaWSに続いて 100キロワット以上の高出力艦載レーザー兵器の開発計画に着手しており、これによってASCM及び ASBMを迎撃できる態勢を整えようとしている 34。
30 Jan Stupl and Götz Neuneck, “Assessment of Long Range Laser Weapon Engagements: The Case of the Airborne Laser,” Science and Global Security, 18, 2009, pp. 1-2, http://scienceandglobalsecurity.org/archive/sgs18stup.pdf, accessed on February 1, 2016.
31 “Pentagon Eyes Laser-Armed Drones to Shoot Down Ballistic Missiles,” Defense One, January 19, 2016, http://www.defenseone.com/technology/2016/01/pentagon-laser-drones-ballistic-missiles/125232/.
32 “Laser weapons at the crossroads,” Military & Aerospace Electronics, November 18, 2015, http://www.militaryaerospace.com/articles/print/volume-26/issue-11/special-report/laser-weapons-at-the-crossroads.html.
33 “Laser-Armed Drones is Pentagon’s Idea for Anti-Ballistic Missiles Defense,” Sputnik, January 22, 2016, http://sputniknews.com/military/20160122/1033522512/pentagon-equips-drones-lasers.html, accessed on February 1, 2016.
34 Ronald O’Rourke, “Navy Lasers, Railgun, and Hypervelocity Projectile: Background and Issues for Congress,” Congressional Research Service, R44175, November 6, 2015, pp. 2-7, http://fas.org/sgp/crs/weapons/R44175.pdf.

30
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
レールガンについては、米海軍が艦載用兵器として開発に注力している。レールガンは、従来の火薬の代わりに電磁気力によって弾丸を加速して撃ち出す兵器であり、その基本構造は砲身に相当する金属製のレール 2本と弾丸、及び電源からなる。レールガンの弾速はマッハ 5.9から7.4にも達し、ASCM及び ASBMの迎撃能力を持つと期待されている。米海軍は、開発中のレールガンのプロトタイプを統合高速輸送艦(Joint High Speed Vessel:
JHSV)に搭載して海上での試験運用を行う計画を公表しており、さらに 2020年代中頃を目途にズムウォルト級駆逐艦(DDG-1000)へのレールガンの実戦配備を検討中とされている 35。ただし、将来の長距離対艦攻撃用兵器としては、予想されるレールガンの射程が 370
キロメートルにとどまる一方で、ASCMの中には射程 550キロメートルに達するものもあることから、レールガンでは不十分との指摘がある 36。レーザー兵器やレールガンの開発に乗り出しているのはアメリカだけではない。中国によるレールガンの開発状況としては、砲身に相当するレールの摩耗を減らすための材料工学などの面で研究が進んでいる 37。また、レーザー兵器やレールガンに必須の電源として、中国の研究チームが大容量かつ軽量の「スーパーキャパシタ」を開発中とされている。これまでの技術では 1メガワットの出力を得るのに必要なキャパシタの重さが 10トンであるところ、理論上は 40キログラムのキャパシタで可能になるという38。ロシアでもレーザー兵器やレールガンの開発が進められているようであるが、詳細は明らかでない 39。旧ソ連時代には、衛星などのセンサーを無力化するレーザー兵器や、1980年代後半には航空機搭載のレーザー兵器の開発が行われていたが、これらの計画はソ連崩壊とともに頓挫している。この他、ドイツ、チェコ、インドでもレーザー兵器の開発が行われており、イスラエルはガザ地区から飛来する短射程のロケット弾を迎撃するための「アイアン・ビーム(Iron Beam)」レーザー兵器システムの開発を進めているという40。
35 Ibid., pp. 8-12.36 Vitaliy O. Pradun, “From Bottle Rockets to Lightning Bolts: China’s Missile Revolution and PLA Strategy
against U.S. Military Intervention,” Naval War College Review, Vol. 64, No. 2, Spring 2011, p. 30.37 Jeffrey Lin and P. W. Singer, “An Electromagnetic Arms Race Has Begun: China is Making Railguns too,”
Popular Science, November 23, 2015, http://www.popsci.com/an-electromagnetic-arms-race-has-begun-china-is-making-railguns-too.
38 “China moves to a big step closer to ‘Star Wars’ laser weapons,” South China Morning Post, December 22, 2015, http://www.scmp.com/news/china/diplomacy-defence/article/1893973/china-moves-big-step-closer-star-wars-laser-weapons.
39 Bill Gertz, “Intelligence Report Warns of Russian Naval Buildup,” Washington Free Beacon, December 29, 2015, http://freebeacon.com/national-security/intelligence-report-warns-of-russian-naval-buildup/.
40 Daniel Gouré, The Next U.S. Asymmetric Advantage: Maritime Lasers to Counter the A2/AD Challenge, Lexington Institute, March 2014, pp. 17-19, http://lexingtoninstitute.org/wp-content/uploads/2014/03/Maritime-Lasers1.pdf.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
31
2 非核兵器技術と核抑止との関係性
ここでは、前項で概観した新たな非核兵器技術が核抑止といかなる関係性を有するのかについて拒否的抑止及び懲罰的抑止の観点から検討する。なお、拒否的抑止とは、特定の攻撃的行動を物理的に阻止する能力に基づき、攻撃目標の達成可能性に関する敵の計算に働きかけて攻撃を断念させるものであり、懲罰的抑止とは、耐え難い打撃を加える威嚇に基づき、敵のコスト計算に働きかけて攻撃を断念させるものである 41。
(1)拒否的抑止拒否的抑止は、攻撃・防御両用での方法で敵の攻撃を阻止する能力に基づくものとされ
る 42。例えば、弾道ミサイル攻撃に対する拒否的抑止の能力には、損害限定を図るための防御手段(MD等)と弾道ミサイルを発射前に破壊し無力化する攻撃手段とが含まれる。拒否的抑止の思想は、懲罰的抑止に依拠してきた冷戦期の米ソ間核抑止においては説得力を欠いていたが、冷戦後に大量破壊兵器や弾道ミサイルの拡散が進むとMDの推進という形で注目を集めるようになった 43。さらに 2001年の米国同時多発テロ以降、核テロの脅威が焦眉の的になると、拒否的抑止の防御手段であるMDに加えて、テロ組織を無力化するための攻撃手段が求められるようになった。ブッシュ政権期には、CPGSは主として対テロ戦争の文脈において、核テロの実行を阻止するための拡散対抗(counterproliferation)の手段として、あるいはテロリストの集合地点を攻撃するための手段として考えられていた。また、CPGSは北朝鮮やイランなどの地域的敵対国(いわゆる rogue states)が軍事力を行使できないようにするための実行可能な先制攻撃オプションとしても期待されていた 44。さらに、これらの敵対国に拡散した核兵器能力がテロ組織と結び付いてアメリカで核テロを起こすことが懸念されており、例えばイランにいるアルカーイダのテロ集団が核弾頭やミサイルを窃取して数時間以内にアメリカを攻撃するといったことも想定されていた 45。当時は、テロ組織や地域的敵対国には懲罰的抑止に基づく従来の
41 防衛省『平成 22年版 日本の防衛―防衛白書』(ぎょうせい、2010年)263頁解説。42 柿原国治「日中間における安全保障上の課題と我が国の対応」『IIPS Policy Paper』295J、2003年 3月、12頁、
http://www.iips.org/research/data/bp295j.pdf.43 新井勉「米国の抑止戦略とミサイル防衛」『軍縮・不拡散問題シリーズ』No. 15、2001年 11月、4頁、http://
www.cpdnp.jp/pdf/003-02-015.pdf.44 Eleni Ekmektsioglou, “Hypersonic Weapons and Escalation Control in East Asia,” Strategic Studies
Quarterly, Summer 2014, p. 47.45 Maj. Jason E. Seyer, “Adding the Conventional Strike Missile to the US’s Deterrence Toolkit,” High
Frontier, Vol. 5, No. 2, February 2009, p. 28

32
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
核抑止が効かないと考えられており、これらの脅威主体による攻撃が予想されるなかで、先制攻撃によって相手の目標達成可能性を物理的に低下させるための拒否的抑止の手段としてCPGSが注目されていたといえよう。冷戦後のアメリカは、全世界に前方展開された在外米軍基地及び部隊を縮小する一方
で、予期しない地域において多様な脅威主体に対処することを余儀なくされるようになった。CPGS は、これらの「敵」に対して在外米軍基地や部隊に依存することなく運用し得る能力として期待されたのである 46。バン(M. Elaine Bunn)らは、核テロを阻止するためにCPGSを運用するシナリオの中で、某国内でテロリストが核物質を積んで走行中の列車などを攻撃することを挙げており、目標地点が欧州及びアジアに展開する米軍基地や部隊から遠く離れていて他に手段がない場合を想定している 47。近年もなお、テロ攻撃を抑止するためのオプションとしてCPGSに期待が寄せられており、例えば前米戦略軍司令官のケーラー(Robert Kehler)退役空軍大将はテロ組織に核抑止は効かないとしてCPGSの必要性を訴えている 48。また、核兵器開発の疑いのある地域的敵対国の攻撃を抑止するためのCPGSの運用も想定されている。2009年の米国防科学委員会の報告書は、約 10発の ICBMを保有するとみられる地域的敵対国がアメリカ又はその同盟国に対して核攻撃の脅しを発し、アメリカがCPGS(非核 SLBM及び空中発射巡航ミサイル)を含む「あらゆる手段」を用いてその脅しを止めさせるというシナリオを検討していた 49。ベネット(Bruce Bennett)は、こうした比較的小規模の核戦力に対しては、非核兵器による攻撃で目標の大部分を破壊できると指摘している。この際、例えば核兵器が貯蔵された地下施設(underground facilities: UGF)への入り口を非核兵器による攻撃で破壊して核兵器を閉じ込めてしまい、その後に核攻撃を行って確実に破壊するといった核・非核の「相乗攻撃(attack synergies)」も考えられるという50。さらに、CPGSが地球上のいかなる目標をも迅速に攻撃できる非核兵器システムを目指して
46 Woolf, “Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles,” p. 2.47 M. Elaine Bunn and Vincent A. Manzo, “Conventional Prompt Global Strike: Strategic Asset or Unusable
Liability?” INSS Strategic Forum, National Defense University, February 2011, p. 9, http://ndupress.ndu.edu/Portals/68/Documents/stratforum/SF-263.pdf.
48 “U.S. needs conventional ballistic missiles, former strike commander says,” AirForceTimes, December 12, 2015, http://www.airforcetimes.com/articles/us-needs-conventional-ballistic-missiles-former-strike-commander-says.
49 U.S. Department of Defense, Office of the Under Secretary of Defense for Acquisition, Technology and Logistics, Time Critical Conventional Strike from Strategic Standoff, Report of the Defense Science Board Task Force, March 2009, pp. 81-84, http://www.acq.osd.mil/dsb/reports/ADA498403.pdf.
50 Bruce W. Bennett, “On US Preparedness for Limited Nuclear War,” in Jeffrey A. Larsen and Kerry M. Kartchner, eds., On Limited Nuclear War in the 21st Century (Stanford, CA: Stanford University Press, 2014), pp. 225-226.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
33
いることを考えれば、目標はテロ組織や地域的敵対国に限らず、理論上は中国やロシアの戦略的アセットも含まれてくる。先の米国防科学委員会報告書には、十分な核・非核戦力を保有し、これらをさらに増強しつつある仮想敵国(near peer competitor: NPC)がアメリカの低軌道衛星を攻撃し、アメリカがNPCの対衛星兵器への反撃要領を検討するシナリオが提示されていた 51。また、現オバマ政権のもとで、CPGSの焦点がそれまでのテロ組織や地域的敵対国を目標とした運用から、A2AD環境を突破あるいは回避しつつ遠距離から戦力を投射し得る兵器としての運用に移りつつあるのではないかとの指摘もある 52。バウム(Seth Baum)は、仮にアメリカが将来 CPGSを大量に(数千発程度)配備し
た場合は、核使用に訴えることなく中国とロシアの核戦力の相当部分を無力化することが可能になると指摘する 53。中国とロシアは、当初はCPGSの能力が小規模だったとしても急速に拡張される可能性があり、それが自国に向けられない保証はないとして、アメリカによる「非核対兵力(conventional counterforce)」攻撃の可能性に警戒感を顕にしている 54。特に両国は、アメリカが非核極超音速兵器を用いて自国の核戦力や指揮中枢に対して先制攻撃を仕掛けた後、残存核戦力による対米報復攻撃をMDで阻止するというシナリオを懸念している 55。これに対し、中国とロシアが、非核兵器分野におけるアメリカの圧倒的優位を相殺するために核兵器の限定的使用を含む「オフセット・エスカレーション」を展開するとの見方がある。「オフセット・エスカレーション」とは、敵対国が紛争を核のレベルにエスカレートさせることによってアメリカの非核兵器における優越を相殺しようとすることである56。コルビー(Elbridge
Colby)は、「オフセット・エスカレーション」を抑止するには、アメリカが非核戦力とともに核戦力も運用し得る態勢を整備するとともに、必要であれば核使用も含む対応を行って事態を
51 このシナリオでは CPGS兵器の運用について明示されておらず、NPCの対衛星兵器の指揮統制・戦闘管理システムを無力化するために運用し得る手段の検討を行うこととされているU.S. Department of Defense, Time
Critical Conventional Strike from Strategic Standoff, Report of the Defense Science Board Task Force, pp. 65-68.
52 Ekmektsioglou, “Hypersonic Weapons and Escalation Control in East Asia,” pp. 44-45, 47-48.53 Seth D. Baum, “Winter-safe Deterrence: The Risk of Nuclear Winter and Its Challenge to Deterrence,”
Contemporary Security Policy, Vol. 36, No. 1, 2015, pp. 134-135.54 Acton, Silver Bullet? pp. 120-124.55 Richard Weitz, “Arms Racing in Strategic Technologies: Asia’s New Frontier,” Hudson Institute, May 3,
2015, http://www.hudson.org/research/11307-arms-racing-in-strategic-technologies-asia-s-new-frontier.56 Adam Mount, “Questioning the case for new nuclear weapons,” Bulletin of the Atomic Scientists, August
21, 2015, http://thebulletin.org/questioning-case-new-nuclear-weapons8671.

34
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
収束させることが望ましいとの見方を示している57。他方、マウント(Adam Mount)は、「オフセット・エスカレーション」を抑止するためにアメリカが限定的に核報復できる態勢を整備するのではなく、非核攻撃を行うとの威嚇(threat of conventional attack)に依拠すべきだと主張する 58。その他の非核兵器技術については、これらが対 A2ADの文脈で拒否的抑止を強化する
と考えられる反面、抑止を不安定化させるのではないかと懸念する意見もある。ゴア(Daniel
Gouré)は、A2AD環境において運用コストの低い艦載レーザー兵器が敵の飽和攻撃に対処する上で有効であるとの見方を示している 59。他方、トラファガン(John Traphagan)は、米海軍が開発中のレーザー兵器(LaWS)について、これを搭載した艦艇に接近することを敵に躊躇させるであろうとして拒否的抑止の効果を認めつつも、LaWSの運用コストが低いことから、使用する側は躊躇なくこれを使おうとするかもしれず、抑止が不安定化する恐れもあると警鐘を鳴らしている 60。
LaWSをはじめとするアメリカのレーザー兵器は現在のところ短距離の戦術兵器として開発が進められているが、将来メガワット級のレーザー兵器が開発された場合はMDなどにも適用されるであろう61。さらに、レーザー兵器が防御手段としてのみならず、攻撃手段として拒否的抑止を強化するようになることも考えられる。ただし、近年のレーザー兵器技術の急速な進展に鑑みても、メガワット級レーザー兵器の開発はなお「野心的な目標」とされている 62。レールガンも、レーザー兵器と同様にMDへの適用が可能になると考えられる 63。ビスワス
(Arka Biswas)は、レールガンで「ペレット」と呼ばれる無数の弾丸を極超音速で発射して一種の弾幕を構成することにより、中国の極超音速飛翔体Wu-14を破壊し得るとしている 64。こうしたレールガンによるMDが実戦配備されれば、高価な迎撃ミサイルを使用する現
57 Elbridge Colby, “Nuclear Weapons in the Third Offset Strategy: Avoiding a Nuclear Blind Spot in the Pentagon’s New Initiative,” Center for a New American Security, February 2015, p. 11, http://www.cnas.org/sites/default/files/publications-pdf/Nuclear%20Weapons%20in%20the%203rd%20Offset%20Strategy.pdf, accessed on February 12, 2016.
58 Mount, “Questioning the case for new nuclear weapons”.59 Gouré, The Next U.S. Asymmetric Advantage, p. 12.60 John W. Traphagan, “Is the US Navy’s New Ray Gun a Good Idea?” The Diplomat, December 12, 2014,
http://thediplomat.com/2014/12/is-the-us-navys-new-ray-gun-a-good-idea/.61 Ellis, Directed Energy Weapons, p. 39.62 O’Rourke, “Navy Lasers, Railgun, and Hypervelocity Projectile,” pp. 17-18, footnote 42.63 “Pentagon Decides to Release the Railgun on the Battlefield,” WatchingAmerica, November 19, 2015,
http://watchingamerica.com/WA/2015/11/19/pentagon-decides-to-release-the-railgun-on-the-battlefield/.64 Arka Biswas, “China’s WU-14 Nuclear Device: Impact on Deterrence Equation,” IndraStra, June 30, 2015,
http://www.indrastra.com/2015/06/Chinas-WU-14-Nuclear-Device-Impact-on-Deterrence-Equation-by-Arka-Biswas.html.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
35
在のMDと比べて運用コストが格段に低くなる 65。ただし、トラファガンがレーザー兵器について指摘しているように、レールガンの運用コストの低さが抑止を不安定化させる可能性にも留意する必要があろう。
(2)懲罰的抑止核抑止は、主として核兵器の懲罰的抑止力に依拠するものとされてきた 66。ミアシャイマー
(John Mearsheimer)は、通常の場合、拒否的抑止は非核兵器と、懲罰的抑止は核兵器と関連付けられると指摘した 67。他方、長射程の非核兵器によって被抑止国の戦略中枢や政府施設、都市などの目標を攻撃できるようになれば、理論上は非核兵器も懲罰的抑止の機能を果たし得る 68。特に、近年の極超音速兵器を中心とする非核兵器技術の進展に伴って、非核兵器による懲罰的抑止の可能性が検討されつつある。ガーソン(Michael Gerson)は、非核兵器による抑止(conventional deterrence)は一義的には拒否的抑止に基づく戦略であるものの、非核兵器の精密攻撃能力が向上していることを踏まえて、その懲罰的抑止への適用可能性も看過すべきではないという69。また、マーティネージ(Robert Martinage)は、中国のA2AD脅威を念頭に置いた「オフセット戦略」を展開する上で、新たな非核兵器による拒否的抑止とともに懲罰的抑止にも焦点を置くべきだと主張している。この際、非核兵器による懲罰的抑止は「非対称の報復攻撃(asymmetric
retaliatory attacks)」の脅しによって行うとし、このための新たな非核兵器の候補として極超音速兵器技術による潜水艦発射非核弾道ミサイルなどを挙げている70。ただし、マーティネージがこうした「非対称の報復攻撃」の例として、中国軍の水上及び潜水艦隊を撃沈することによって中国側に高いコストを強いると述べている点 71については、戦闘による艦船の喪失が中国にとって耐え難い打撃となり得るのか、また非核攻撃で中国を抑止できなかった場合は核抑止によるエスカレーション・コントロールが可能なのかについて慎重に考察する必要があろう。
65 Richard Weitz, “The Next Round of the Military Competition: Considering Non-nuclear Strategic Technologies,” Second Line of Defense, September 25, 2015, http://www.sldinfo.com/the-next-round-of-the-military-competition-considering-non-nuclear-strategic-technologies/.
66 Steven P. Lee, Morality, Prudence, and Nuclear Weapons (New York: Cambridge University Press, 1993), p. 29.
67 John J. Mearsheimer, Conventional Deterrence (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1983), p. 15.68 Toshi Yoshihara and James R. Holmes, eds., Strategy in the Second Nuclear Age: Power, Ambition, and the
Ultimate Weapon (Washington, D.C.: Georgetown University Press, 2012), pp. 82-83.69 Michael S. Gerson, “Conventional Deterrence in the Second Nuclear Age,” Parameters, Vol. 39, No. 3,
Autumn 2009, p. 37.70 Robert Martinage, Toward a New Offset Strategy: Exploiting U.S. Long-term Advantages to Restore U.S.
Global Power Projection Capability, Center for Strategic and Budgetary Assessments, 2014, pp. 46, 63-64.71 Ibid., p. 47.

36
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
また近年、非核兵器の破壊力が高まりつつあるとはいえ、その抑止効果は核兵器のそれに遠く及ばないことから、懲罰的抑止への適用に否定的な見解もある。デムス(Alyssa
Demus)は、大規模爆風爆弾(Massive Ordnance Air Blast: MOAB)がその破壊力による懲罰的抑止の機能を期待される一方で、MOABの爆発威力が TNT換算で 11トン程度であるのに対して、アメリカの保有する最小の核弾頭W76でも100キロトンに達することから、核兵器の抑止効果には敵うべくもないと指摘する 72。また、CPGSは攻撃速度が速いことから、核弾頭装備の ICBMに匹敵する抑止効果を期待されているが、実戦配備の目途もついていない段階でCPGSを核兵器に代わる抑止力と考えるのは時期尚早であり、また非核の大型貫通爆弾(Massive Ordnance Penetrator: MOP)についても強化コンクリート製の地下核施設に対する破壊効果は限定的であるという73。さらに、物理的な抑止効果に加えて、懲罰的抑止における相手の認識を決定付ける心理的な効果の面でも、非核兵器に対しては否定的な意見がある。例えば、米戦略軍司令官を務めたチルトン(Kevin Chilton)は、CPGSのような非核兵器では核攻撃の脅しに匹敵するほどの「恐怖(fear)」を相手の心のうちに生じさせ得ないと述べている 74。他方、将来メガワット級のレーザー兵器が実戦配備されれば、これを懲罰的抑止に適用
し得るとの見方もある。米空軍のスティーブンス(Michael J. Stephens)は、地上設置型の高出力レーザー発射機と宇宙配備のミラー衛星を組み合わせた戦略攻撃システムをアメリカが他国に先んじて構築することができれば、被抑止国に耐え難い打撃を与え得るとしている 75。これについてもCPGSの場合と同様に、そうした非核兵器システムの物理的・心理的な抑止効果を従来の核抑止に照らして慎重に検討する必要があろう。アメリカが CPGS構想に基づき極超音速兵器技術を非核兵器に適用する計画を進めているのに対して、先述したように中国とロシアも極超音速兵器技術による飛翔体の開発を進めているが、両国はこれに核弾頭を搭載する考えを持っている。カニンガム(Fiona
Cunningham)らは、中国が極超音速兵器技術を非核兵器としてではなく、自国の核抑止力を強化する手段として開発していることを挙げ、中国が極超音速兵器を実戦配備したとし
72 Alyssa Demus, Conventional Versus Nuclear: Assessing Comparative Deterrent Utilities, School of International Service, American University, August 25, 2012, pp. 10-12, https://www.american.edu/sis/usfp/upload/A-Demus-SRP-COPY-AU-Website-2-10-13.pdf.
73 Ibid., pp. 13-17.74 Woolf, “Conventional Prompt Global Strike and Long-Range Ballistic Missiles,” p. 8.75 Lt Col. Michael J. Stephens, “Harnessing Light: Laser/Satellite Relay Mirror Systems and Deterrence in
2035,” Air War College, Air University, February 16, 2010, pp. 18-19, http://www.au.af.mil/au/awc/awcgate/cst/bh2010_stephens.pdf.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
37
てもアメリカのように非核兵器に限定して運用するとは考え難いと分析している76。こうした考え方は中国とロシアに限らず、インドにおいても存在する。例えば、インドの戦略研究者ゴシャール(Debalina Ghoshal)は、インドに対するパキスタンや中国からの巡航ミサイル脅威に対し、インドはブラモス 2極超音速巡航ミサイルの開発を促進するととともに、ブラモス 2に核弾頭を搭載可能なようにして懲罰的抑止の態勢を検討すべきだと主張している 77。ソコフ(Nikolai N. Sokov)によれば、ロシアは優勢な非核戦力を持つアメリカに対して限定核攻撃により懲罰的抑止を図ろうとしている。アメリカが CPGSのような長射程の非核精密誘導兵器を使えるのであれば、ロシアは長射程の核兵器をもってその使用を抑止する構えであり、人口・経済中枢を目標とするのではなく、空軍基地や空母などの軍事目標に限定した核攻撃を考えているという78。さらに、ロシアが開発・建造中とされる核搭載無人潜水艇(コード名“Kanyon”)は、メガトン級の大型核弾頭をもってアメリカの港湾や潜水艦基地を破壊するとともに、沿岸都市に大規模な放射能汚染による耐え難い損害を与えることを狙いとしており、人口・経済中枢への付随的損害も考慮に入れている 79。このようなロシアの核戦力への傾倒は、冷戦後に西側(アメリカとNATO)が対ロ優位となった非核戦力を背景としてロシアの国益を脅かしつつあるとの認識から、これ以上の国益侵害が行われた場合は核攻撃による懲罰も辞さない姿勢を示すものと考えられる。ロジャンスキー(Matthew Rojansky)は、ロシアの死活的国益に係る「レッドライン」を越えないよう西側を説得するために、ロシアは核兵器の「十分な能力を保持して明確な抑止のメッセージを送ること」を重視しているのであって、冷戦期のような大規模な核戦力を持とうとしているのではないという。また、ロシアが懸念する西側の非核戦力についても、アメリカのMDや CPGS
はロシアの核攻撃を「鈍らせる(blunt)」程度の能力を潜在的に持つと思われるが、その全てを阻止し得るものではないとロジャンスキーは分析している 80。
76 Fiona S. Cunningham and M. Taylor Fravel, “Assuring Assured Retaliation: China’s Nuclear Posture and the U.S.-China Strategic Stability,” International Security, Vol. 40, No. 2, Fall 2015, pp. 29-30.
77 Debalina Ghoshal, “India: Defeating the Cruise Missile Threat,” The Diplomat, October 26, 2013, http://thediplomat.com/2013/10/india-defeating-the-cruise-missile-threat/.
78 Nikolai N. Sokov, “Why Russia calls a limited nuclear strike ‘de-escalation’,” Bulletin of the Atomic
Scientists, March 13, 2014, http://thebulletin.org/why-russia-calls-limited-nuclear-strike-de-escalation.79 Bill Gertz, “Russia Building Nuclear-Armed Drone Submarine,” Washington Free Beacon, September 8,
2015, http://freebeacon.com/national-security/russia-building-nuclear-armed-drone-submarine/.80 Matthew Rojansky, “Russia and Strategic Stability,” in Elbridge A. Colby and Michael S. Gerson, eds.,
Strategic Stability: Contending Interpretations, Carlisle Barracks, PA: U.S. Army War College Press, February 2013, pp. 311-312, http://www.strategicstudiesinstitute.army.mil/pdffiles/pub1144.pdf.

38
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
3 抑止に及ぼす影響
(1)非核兵器技術の導入による抑止の変化ここでは、極超音速兵器を中心とする非核兵器技術の導入に伴って、抑止がどのように変化するのかについて、モーガン(Patrick Morgan)の「一般抑止」概念を用いて考察する。モーガンによれば、「一般抑止(general deterrence)」とは、抑止国と被抑止国の少なくとも一方が他方に対して「機会があったら」軍事力の使用を考えている状況のことであり、国際政治において典型的に見られる状況であるという。「一般抑止」が不安定化すれば当事国間で軍事力の使用の蓋然性が高まり、「直接抑止(immediate deterrence)」状況が生起する 81。非核兵器技術の導入により、抑止における非核兵器の役割が増大していくと、抑止に係
る攻撃・防御バランス(offense-defense balance)に変化がもたらされ 82、その変化が軍事力の使用への誘因となって「一般抑止」が不安定化するリスクが高まると考えられる。まず、攻撃面では、核兵器による懲罰的抑止に依拠してきた従来の抑止から、極超音速兵器技術を駆使した非核攻撃兵器による拒否的抑止を重視するものへと変化する可能性がある。この傾向は、特にアメリカの抑止政策において顕著になると考えられるが、これに対してロシアは抑止において核兵器を重視する傾向をますます強めていくであろう。バエフ(Pavel
Baev)は、近年のロシアがしばしば核の脅しに訴えるのは、西側との戦略バランスがロシア側に不利に傾きつつある状況において、核戦力に対する巨額の投資から「何らかの政治的な配当(some political dividends)」を引き出そうとするロシアの苦境を表すものだと指摘している 83。今後、アメリカがCPGSなどの非核極超音速兵器の配備に乗り出せば、ロシアはさらなる核兵器の増強をもってこれに対抗しようとする可能性が高い。こうした状況は米ロ双方に先制攻撃の誘因を与えることになり、「一般抑止」の不安定化につながり得る。
81 Patrick M. Morgan, Deterrence Now (Cambridge: Cambridge University Press, 2003), pp. 80-81. なお、モーガンは 1977年の著作で general deterrence及び immediate deterrenceの概念を提唱している。Morgan,
Deterrence: A Conceptual Analysis (Beverly Hills, CA: Sage Publications, 1977), pp. 31-43. これらの用語に定訳はないが、ここでは次の文献から引用した。安藤次男「宥和(appeasement)と抑止(deterrence)―歴史学としての宥和研究から政治学としての宥和研究へ」『立命館国際研究』第 15巻第 3号、2003年 3月、235頁、http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/ir/college/bulletin/vol15-3/15-3ando.pdf.
82 攻撃・防御バランスと抑止との関係については、例えば次を参照。Karen Ruth Adams, “Attack or Conquer: International Anarchy and the Offense-Defense-Deterrence Balance,” International Security, Vol. 28, No. 3, Winter 2003/2004, pp. 45-83.
83 Pavel K. Baev, “Apocalypse a bit later: The meaning of Putin’s nuclear threats,” Brookings Institution, April 1, 2015, http://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2015/04/01/apocalypse-a-bit-later-the-meaning-of-putins-nuclear-threats/.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
39
また、防御面では、極超音速兵器が実戦配備されるに伴い、MDによる拒否的抑止の実効性が低下する可能性もある。既に述べたように、現在のところ極超音速兵器の研究開発に取り組んでいるのはアメリカ、中国、ロシア及びインドに限定されている。しかし、将来にわたって他の国々に極超音速兵器技術が拡散していけば、MDが無用の長物になり得るとの指摘がある。そうなると、これまで公式には北朝鮮やイランなどの地域的敵対国からの弾道ミサイル攻撃に対するものと説明されてきたアメリカのMDも、これらの敵対国が極超音速兵器を持つようになればその実効性が低下することになるのは否めない 84。ゴシャールも、極超音速巡航ミサイルをMDで迎撃するのはもはや非現実的と思われることから、MDによる拒否的抑止のみで極超音速兵器の脅威に対抗するのは不十分との見方を示している85。つまり、被抑止国が極超音速兵器を持つことによって抑止国のMDを回避しつつ攻撃を成功させ得ると認識する一方で、抑止国はMDだけではその攻撃を抑止できないと認識するため、対抗的に極超音速兵器を導入して抑止の回復を図ろうとする構図となる。これに関して、ブルストラン(Corentin Brustlein)は、現在のアメリカの非核抑止はMD
システムの開発と非核打撃オプションの多様化に向かっていると指摘する 86。また、米国防総省は、極超音速兵器による(非核)グローバル攻撃能力と積極防衛(MD)を組み合わせることによって抑止の相乗効果(synergistic effect)が生じるとしている 87。他方、そうした非核戦略兵器の組み合わせが他国の抑止政策に悪影響を与える可能性もある。例えば、フッター(Andrew Futter)らによれば、アメリカのCPGS能力がMD能力と相俟って中国の核抑止力の信頼性を脅かしており、その対抗策として中国が ICBMの多弾頭化、さらには衛星攻撃能力やサイバー戦能力の開発を進めているという88。また、ロバーツ(Brad Roberts)もアメリカのCPGS能力とMD能力の組み合わせによって戦略的安定性が脅かされているとの中国の認識に言及している 89。極超音速兵器技術は、CPGSのように将来のグローバルな安全保障環境に影響を及ぼす
だけでなく、地域安全保障にとっても深刻な課題となっていくであろう。ケンブリ(Kalyan M.
84 Zachary Keck, “Will Hypersonic Capabilities Render Missile Defense Obsolete?” The Diplomat, February 7, 2014, http://thediplomat.com/2014/02/will-hypersonic-capabilities-render-missile-defense-obsolete/.
85 Ghoshal, “India: Defeating the Cruise Missile Threat”.86 Corentin Brustlein, “Conventionalizing Deterrence? U.S. Prompt Strike Programs and Their Limits,”
Proliferation Papers, No. 52, January 2015, pp. 10-11, http://www.ifri.org/sites/default/files/atoms/files/pp52brustlein.pdf.
87 U.S. Department of Defense, Deterrence Operations Joint Operating Concept (version 2.0), December 2006, pp. 38-39, http://www.dtic.mil/doctrine/concepts/joint_concepts/joc_deterrence.pdf.
88 Futter and Zala, “A Sustainable Approach to Nuclear Zero,” pp. 4-6.89 Brad Roberts, “Extended Deterrence and Strategic Stability in Northeast Asia,” NIDS Visiting Scholar
Paper Series, No. 1, August 9, 2013, p. 30, http://www.nids.go.jp/english/publication/visiting/pdf/01.pdf.

40
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
Kemburi)は、アジアで極超音速巡航ミサイルが拡散した場合、主要国の攻撃目標間の距離が相互に近接していることから、発射後 10分足らずで目標に着弾する状況が生起すると指摘している 90。こうなると、極超音速巡航ミサイルの脅威に対する国際的・国内的な危機管理体制を整えない限り、各国政府は危機的状況下でそれぞれの判断を迫られるようになり、アジアの「一般抑止」が不安定化することは避けられなくなるであろう。抑止に係る攻撃・防御バランスを変化させ得る新たな非核兵器技術は、極超音速兵器に
とどまらない。例えば、レーザー兵器やレールガンの導入によって米海軍の艦船の防御力が高まると、中国のA2AD脅威を克服して抑止バランスをアメリカに有利に変化させることが予想される。ゴアは、レーザー兵器とレールガンが攻撃・防御バランスを劇的に変化させ得ると指摘している 91。
(2)非核兵器技術とアメリカの拡大抑止非核兵器技術の導入によって抑止に変化がもたらされると、アメリカの拡大抑止にどのよう
な影響が及ぶであろうか。これに関して、モーガンの「一般抑止」に基づいてフース(Paul
K. Huth)やローリグ(Terence Roehrig)が用いた「一般拡大抑止(extended general
deterrence)」の概念を用いて考察してみたい。拡大抑止のアクターには、抑止国と被抑止国の他に、抑止国から拡大抑止を供与される被供与国(protégé)が含まれる。フースは「一般拡大抑止」を、被抑止国が被供与国に対する軍事力の使用を積極的には考えておらず、戦争に発展するような深刻な対立も惹起していない状況における抑止国と被抑止国間の政治的・軍事的な競合関係と定義した。「一般拡大抑止」における両国間の競合関係は、具体的には軍備競争の進展、対抗同盟の形成、域内諸国に対する経済・軍事援助、外交・安全保障に関する一般的な宣言や政策声明として表徴される 92。また、米韓同盟の歴史を「一般拡大抑止」の観点から分析したローリグは、抑止国であるアメリカが韓国(被供与国)に対する防衛コミットメントの信頼性を示すために、安全保障条約の締結、対韓支援の宣言、経済・軍事援助、通常戦力(在韓米軍)のプレゼンスなどの様 な々方策を駆使してきたと指摘する。ローリグによれば、冷戦前
90 Kalyan M. Kemburi, “Diffusion of High-Speed Cruise Missiles in Asia: Strategic and Operational Implications,” S. Rajaratnam School of International Studies (RSIS) Policy Brief, December 2014, p. 8, https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/2014/12/PB141209_High-Speed_Cruise_Missiles.pdf.
91 Daniel Gouré, “U.S. Navy Pursuing Its Own Offset Strategy Led By The Rail Gun,” Lexington Institute, February 9, 2015, http://lexingtoninstitute.org/u-s-navy-pursuing-its-own-offset-strategy-led-by-the-rail-gun/.
92 Paul K. Huth, Extended Deterrence and the Prevention of War (New Haven: Yale University Press, 1988), pp. 16-17.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
41
期から1991年まで行われてきた韓国への戦術核兵器の配備も「一般拡大抑止」の方策であったという93。前項での考察に鑑みれば、今後アメリカの拡大抑止は核兵器による懲罰的抑止に依拠し
たものから、最新の非核兵器技術の導入による拒否的抑止を重視していくものと考えられる。サントロ(David Santoro)らは、北朝鮮の核・ミサイル脅威に対して同盟国(日本及び韓国)に拡大抑止を確保するために、アメリカはCPGSを含めた「非核兵器による先制攻撃態勢(a
conventional preemptive posture)」の確保に努めるべきだと主張する 94。しかし、これまで述べたように、アメリカがこのような態勢をとれば、中国とロシアが自国の核抑止力に対する脅威感を増大させるであろう。また、アメリカによるCPGSの開発が同盟国に対する拡大抑止の再保証(reassurance)にいかなる影響を及ぼすかも検討しなければならない。ブルストランは、CPGSが中国のA2AD能力による米軍の前方展開戦力への脅威を避けつつ、その射程外から攻撃するための兵器として開発されていると見なされた場合、アメリカによる再保証が弱化する恐れがあるとの見方を示している。それは、CPGSの開発がアメリカによるリスク許容度の減少、ひいては「デカップリングへの準備段階(a preliminary step toward decoupling)」と同盟国に受け取られた場合に起こり得るという95。アメリカによるCPGSの開発・配備が被抑止国にとって脅威の増大と認識され、また被供与国にデカップリングへの懸念を生じさせるものとなるならば、「一般拡大抑止」を不安定化させる一因となり得る。こうした事態を避けるためには、CPGSの導入によって拡大抑止をより好ましいものに変えていくことが必要である。グース(Kurt Guthe)らは、アメリカのCPGSが韓国への拡大抑止を強化する可能性について、朝鮮半島事態におけるCPGSの運用について米韓が共同作戦計画検討を行うことができれば同盟の一体感が醸成され、拡大抑止の再保証につながり得るとしている。また、CPGSがアメリカの戦略核戦力を発動させる「エスカレーション・リンク」の役割を果たし得ることから、韓国に対するアメリカの核保証(nuclear guarantee)の信憑性を高め得るとも示唆している 96。
93 Terence Roehrig, From Deterrence to Engagement: The U.S. Defense Commitment to South Korea, paperback ed. (Lanham, MD: Lexington Books, 2007), p. 231.
94 David Santoro and John K. Warden, “Assuring Japan and South Korea in the Second Nuclear Age,” The
Washington Quarterly, Vol. 38, No. 1, Spring 2015, pp. 157-158.95 Brustlein, “Conventionalizing Deterrence?” p. 47.96 Kurt Guthe and Thomas Scheber, “Assuring South Korea and Japan as the Role and Number of U.S. Nuclear
Weapons are Reduced,” Defense Threat Reduction Agency, Advanced Systems and Concepts Office ASCO 2011 003, January, 2011, p. 43, https://www.hsdl.org/?view&did=716179.

42
防衛研究所紀要第 19 巻第 1号(2016年 12月)
核・非核の戦略攻撃力とともに、MD及び米軍の前方展開戦力もアメリカの拡大抑止を構成する重要な要素である 97。マニング(Robert A. Manning)は、レーザー兵器やレールガンなどの先進的な非核兵器技術がMDの能力及び米軍のA2AD対処能力を向上させ、拡大抑止を変化させる「ゲーム・チェンジャー」としての潜在力をもつと指摘している 98。ただし、レーザー兵器とレールガンに関しては当面短距離の戦術兵器の域を出ないと考えられることから、例えば北朝鮮の核・ミサイルによる韓国への攻撃をアメリカが抑止するための広域防空には対応できないとの指摘もある 99。非核兵器技術の導入によってアメリカの能力を向上させるのみならず、拡大抑止の被供与国の能力を向上させることも検討の余地がある。フィッシャー(Richard Fisher)は、中国の台湾侵攻を抑止する方策として、台湾に地上配備型のレールガンを10基程度供与すれば、中国軍の侵攻部隊にとって「受け入れ難い脅威(an unacceptable threat)」を与え得るのではないかと示唆している 100。これについては、台湾へのレールガンの供与がアメリカの防衛コミットメントの信頼性を向上させ、台湾への安心供与となって「一般拡大抑止」の安定化に寄与し得る一方で、被抑止国である中国を刺激して「一般抑止」そのものが不安定化する可能性にも配意しなければならない。このように、非核兵器技術の導入には「一般拡大抑止」の安定化に寄与する側面と、その不安定化につながる側面がある。この二面性は、核抑止との関係性に照らして検討する必要がある。特に、米中ロの大国間関係においては、非核兵器であるCPGSの導入がMDと相俟ってアメリカの拒否的抑止を強化し、「一般拡大抑止」に裨益すると考えられる一方で、中国とロシアの核抑止力に対する脅威となり、抑止関係を不安定化させる要因ともなり得る。また、非核兵器技術によってアメリカの損害限定能力が向上したとしても、非核兵器による拒否的抑止態勢が被抑止国や被供与国の「認識」に与える力は、核戦力の持つ物理的・心理的なインパクトには及び難いとの指摘もある 101。拡大抑止については、アメリカ
97 M・エレーヌ・バン「オバマ政権の核政策と東アジア安全保障への影響」『平成 21年度安全保障国際シンポジウム―主要国の核政策と 21世紀の国際秩序』防衛省防衛研究所、2010年、48-49頁。
98 Robert A. Manning, The Future of US Extended Deterrence in Asia to 2025, Atlantic Council, October 2014, pp. 17-19, http://espas.eu/orbis/sites/default/files/generated/document/en/Future_US_Ext_Det_in_Asia.pdf, accessed on January 12, 2016.
99 Sydney J. Freedberg Jr., “Save Our Seoul: Can Lasers & Rail Guns Protect Korea?” Breaking Defense, May 7, 2015, http://breakingdefense.com/2015/05/save-our-seoul-can-lasers-rail-guns-protect-korea/.
100 Richard D. Fisher, Jr., “Will It Be Possible To Deter China Into The 2020s?” School of Strategic Studies conference on “China’s Military Capability and The Security Situation on the Taiwan Strait,” Tamkang University, April 26, 2014, pp. 13-14, http://www.strategycenter.net/docLib/20140724_Fisher_DeterChina_0723.pdf.
101 戸崎洋史「核軍縮と日米同盟―拡大抑止への影響」『核軍縮をめぐる新たな動向研究報告書』日本国際問題研究所、2009年 3月、61頁、http://www.cpdnp.jp/pdf/003-01-009-07.pdf.

非核兵器技術の開発と抑止との関係
43
の戦略核兵器による懲罰的抑止への過度の依存を避けつつ、非核兵器技術の導入による拒否的抑止の強化とのバランスをいかにとっていくかが今後の課題となろう。
おわりに
本稿は、冷戦後の抑止において非核兵器の比重が高まりつつある状況に鑑み、非核兵器技術と抑止との関係を考察したものである。抑止政策の一環として非核兵器技術の開発を積極的に進めているのはアメリカであり、これに対して中国は核・非核の両面で抑止力の向上を図っており、ロシアは核抑止を重視する傾向を強めている。極超音速兵器技術の動向は未知数であるが、これを駆使した非核戦略兵器が実戦配備されるようになれば、アメリカの抑止政策は、核兵器による懲罰的抑止に依拠してきた従来の政策から、非核兵器による拒否的抑止を重視するものへと変化する可能性がある。これに伴い、わが国を含む同盟国に対するアメリカの拡大抑止にも同様の影響が及ぶものと考えられる。次期米政権の抑止政策がどのようなものになるのかは予断を許さないが、アメリカは今後と
も抑止における非核兵器の比重を高めていくと思われる。その推進力となるのは、本稿で取り上げた極超音速兵器を中心とする非核兵器技術である。非核兵器は、核兵器の圧倒的な破壊力が持つ心理的なインパクトを欠く可能性がある 102。抑止における非核兵器の比重が高まることは、「一般抑止」に変化をもたらす要因となり得る。「一般抑止」が変化すれば、「一般拡大抑止」にも影響が及ぶのは避けられない。極超音速兵器を中心とする新たな非核兵器技術が「一般抑止」及び「一般拡大抑止」
の不安定化を招かないようにするとともに、これらの技術を、核兵器に過度に依存することなく戦争を確実に抑止する手段に転化するための知的努力を継続していかねばならない。このためには、新たな非核兵器技術の進展を見極めつつ、非核兵器技術と核抑止の関係性を起点とした冷静な分析が求められる。こうした分析は、わが国がますます複雑化する安全保障環境に対応した抑止政策を立案するための布石となるであろう。
(ありえこういち 2等陸佐 政治・法制研究室所員)
102 金子将史「米国の新しい核戦略と「核の傘」」『PHP Policy Review』PHP総合研究所、2010年 4月、10頁、http://research.php.co.jp/policyreview/pdf/policy_v4_n27.pdf.