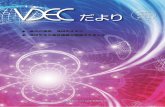英文学会通信 - Nihon...
Transcript of 英文学会通信 - Nihon...

─ ─
英文学会通信 第 100号
1
英 文 学 会 通 信英 文 学 会 通 信─日本大学英文学会─
2013年 11月
第100号
発行:日本大学英文学会
〒 156-8550 東京都世田谷区桜上水3-25-40 日本大学文理学部英文学研究室内 Tel.(03)5317-9709(直通) Fax(03)5317-9336 E-mail [email protected]
目 次
《ご挨拶》
会長挨拶 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本大学英文学会会長 深沢 俊雄 2
「英文学会通信」の歴史 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本大学英文学会副会長 高橋 利明 2
《「英文学会通信」第 100号記念企画》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 4
《エッセイ》
教員となって ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 埼玉県立川口北高等学校教諭 島田 雅史 6
島教育体験記~苦あれば楽あり、楽あれば苦あり~ ・・・・・・・・・・・ 東京都小学校教諭 志田 満瑠 6
《特集》
ゴールズワージィと「財産家」 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 元日本大学理工学部教授 桑山 泰助 7
《海外留学体験記》
アメリカ留学体験記 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本大学文理学部英文学科 4年 磯野 広大 8
留学を通して学んだ人生で大切なこと ・・・・・・・・・・・ 日本大学文理学部英文学科 4年 西村 雅裕 9
27歳からの海外留学 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本大学大学院博士後期課程 3年 小澤 賢司 10
《年次大会発表要旨》
Paradise Lostにおける「存在」の考察 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本大学文理学部助手A 野村 宗央 11
サマセット・モームの歴史小説Then and Now (1946)を読む・・・ 日本大学文理学部准教授 前島 洋平 11
可能性は無限大「お遊びに終わらない小学校英語教育」とは?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 日本大学文理学部講師 池田 和子(紅玉) 12
[最終講義]
ジョンソン博士に寄せるホーソーンの思いをめぐって ・・・・・・ 日本大学文理学部講師 當麻 一太郎 12
《年次大会プログラム》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
《月例会関連》
月例会報告・予定、その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 13
《新刊書案内》 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 14
《事務局・研究室だより》
卒業された同窓会員の皆様へ、その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 15

─ ─2
日本大学英文学会2013年 11月
会長挨拶
日本大学英文学会会長 深沢 俊雄
今年の夏は例年にない猛暑でしたが、9月になって暑さも少しずつ和らいでまいりました。日本大学英文学
会の皆様方はご健勝にてお過ごしのことと存じます。
前会長文理学部英文学科教授吉良文孝先生の後任と
して、本年(2013年)4月に会長に就任して以来、副会長の英文学科教授高橋利明先生と英文学科スタッフ
の皆様方に支えていただきながら早くも半年が過ぎま
した。この間、月例会では綿密で活気にあふれた研究
発表とカンザス大学名誉教授、東京大学大学院教授に
よる学術講演会等が執り行われてきました。会員の
方々や院生の皆様が多数参加してくださり、活発な研
究活動が行われてきました。
社会情勢としては、 7月に参院選が行われ、政治にも安定指向の兆しが見え始めるような報道がささやか
れるようになりました。是非とも社会が安定して、学
生の就職難が改善され、明るい兆しが見えるようにな
ることを願ってやみません。
一方、尖閣諸島や竹島等の問題で、隣国である中国
や韓国との関係がぎくしゃくしていますが、私用では
じめて、 8月中旬に上海に5日ほど行ってきました。上海の街並みを空と地上から見て、 100階建てのビルを含め、高層ビルの多さと道路の広さと街路樹の多さ
と街全体の緑の多さには、目を見張るものがありまし
た。建物の高さや色などにもけばけばしさがなく、調
和がとれて整然としていました。街には東京とは比較
にならないほど車が多く、日本車も少しは見かけまし
たが、ほとんどがヨーロッパ製の高級車でした。タク
シーもほとんどが 2000ccクラスのフォルクスワーゲンでした。 もちろん上海は国際都市として発展してきた街だという認識を持って訪れたものの、自分の目
で上海をつぶさに見て、その繁栄ぶりに圧倒させられ
ました。外気温は日中 38℃から 39℃ありましたが、人々は暑さにもめげずに活動し、活気にあふれていま
した。 現地で聞いたところでは、世界万博の頃に上海はかなり発展したのだそうです。地下鉄にも乗って
見ましたが、車内も大変きれいで、人々も整然として
乗車しているのが印象的でした。
さて日本大学英文学会は、長年歴代の会長と役員並
びに英文学科研究室のスタッフの皆様のご尽力によ
り、 すばらしい学会に築き上げられ発展してきました。 今回「英文学会通信」第 100号となる記念号を皆様のお手元にお届けする運びとなり、長年にわたり築
き上げてきた日本大学英文学会の重みを痛切に感じま
すとともに、喜びも一入です。
《ご挨拶》
「英文学会通信」の歴史
日本大学英文学会副会長 高橋 利明
今号で我らが「英文学会通信」は第 100号を迎えます。これを記念すべく過去の号の内容を少しだけ振り
返ってみたいと思います。R.W.EmersonはNature(1836)の Introduction 冒頭で、“Our age is retrospec-tive” と言い、過去に囚われない生き方を求めますが、「温故知新」の価値を等閑に付すこともできません。我
らが恩師たちの現役時代の奮闘こそが、今日に生きる
我々のための土台を作ってくれたことは確かなことで
す。日本大学英文学会の活動が今日まで途切れること
なく滔々と続いていることに感謝と喜びを感じます。
まずは「英文学会通信」の前身である「英文学会だ
より」について触れておく必要があるかと思います。
故大和資雄先生・故古谷専三先生・沢田城子様の文章
の見られるその第 1号は昭和 32年(1957年)6月に発行され、昭和 43年(1968年)7月発行の第 52号で途絶しております。1969年が全国的な学園紛争のピークであったことを考えれば、その中断は当然のことで
あったはずです。その第 52号では、渡辺敏郎先生(元本学経済学部教授)の「第 40回日本英文学会大会報告記」と壬生郁夫先生(元本学経済学部教授)の「学
園紛争経過報告」の二つが大きく目を引きます。渡辺
先生の「(日本英文学会)第 40回大会の第一日は、文理学部における本格的な学園紛争の第一日でもあった
のである」という言葉は、皮肉を超えて本当に重々し
く感じられます。37年の時を経て我ら英文学科が、第 77回の日本英文学会全国大会(平成 17年[2005年]5月 21・22日)を平和裏に無事にかつ有意義に終えられたことは本当にありがたいことだったと思います。
さて、本題に戻り以下では創刊第 1号から、と言いましても欠号となっておりますので第 2号から始めて、何号かを拾い上げながらその内容を簡単に紹介さ
せていただきたいと思います。また、全ての紹介は紙
面の都合上難しいので、恣意的な取り上げ方になるこ
とにはご寛恕下さい。なお、第 2号だけは紙上に再現させていただきます。
「英文学会通信」第 1号から第 11号のスパンで見ますと、 1・3・4・5号と欠号になっております。よって、残念ながらまず創刊第 1号の発行年月日が不明です。第 2号のそれが昭和 47年 7月 20日で、「月例会
今後とも会員の皆様の活発な研鑽活動によって、歴
史のある日本大学英文学会の月例会と年次大会がます
ます隆盛になるよう、副会長の高橋先生と共に微力な
がら努力させていただきたいと願っております。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●

─ ─
英文学会通信 第 100号
3
報告」として「昨年 12月に発足致しました月例会も回を重ねて、 9月には 7回目を迎えることになりました」とあり、その最初の 12月例会の開催日が昭和 46年 12月 18日となっています。いずれにしても第 1号の発行年月日の特定は大した問題ではないでしょう。
また、当初より発行は年 2回であったことは確かなようです。
話は準創刊号の第 2号に戻りますが、これはガリ版刷りの一枚仕立てです。月例会の司会者としてひっぱ
りだこなのは、恩師の故安田哲夫先生です。英語教育
をめぐる討論会が頻繁に開かれていることには、瞠目
します。英語教育が我々日本人にとって永遠のテーマ
なのだと改めて痛感します。またこの号には、研究発
表された方々として、当時院生であった高橋公雄先
生、泉琢磨先生、故岡田篤志先生、佐藤秀一先生、さ
らには助手であった故寺崎隆行先生と原良子先生のお
名前が見られます。そして、「人事異動」として目立
つのが、恩師の故阪田勝三先生の着任(昭和 47年 4月1日付)です。また、現存の第 6号と第 7号は、それぞれ昭和 48年 10月と 11月に発行されています。前者はその 11月 17日開催の研究発表会(現在の年次大会)の予告版で、会長・安田先生の開会の辞の後、阪田先生の司会
で當麻一太郎先生、佐藤三武朗先生の研究発表があ
り、恩師の故原田茂夫先生の司会で原公章先生、安田
先生の発表のあることが告げられています。そして、
後者は研究発表会報告版として各発表内容の梗概が載
せられています。第 8号(昭和 49年 7月 10日発行)では、前年の 9月から 6月まで、 3月を除いて通して例会が実施されていたことがわかり、当時の先生方や
院生方の熱気がよく伝わってきます。文学・語学の研
究発表と同時に、大学英語教育関連のシンポジウムが
毎月のように開かれていたことを思うと我々のその方
面での努力が少々足りないことに気づかされます。ま
た、昭和 49年 4月の月例会から毎月、故岡崎祥明先生が司会を担当されたことも驚嘆に値し、その意気込
みと熱情には感銘を受けます。そしてこの年は、英文
学科創設 50周年に当たり、11月 18日 (土 )に記念講演会・祝賀会等が開催されています。そしてその講演概
要などの内容は、第 9号で報告されており、講演会では、大橋健三郎東京大学教授が、『アメリカの小説―
「ノベル」と「ロマンス」について」を話され、大和資
雄本学名誉教授が、『ロマン派のコテリーズ』について
発表されています。また、祝賀会は学内から場所を移
して市ヶ谷の私学会館で行われたことがわかります。
この稿も第 10号(昭和 50年 4月 27日)と第 11号(昭和 50年 10月 20日)で筆を擱こうと思います。前者は、英文学科代表(現在の主任)に選ばれると同時
に規則上英文学会会長になられた恩師の中島邦男先生
の挨拶文から始まりますが、その中で昭和 49年末のロックアウトにより翌 4月までの月例会が途絶えたこ
とがわかります。因みに筆者は昭和 53年 4月入学ですが、その年の 12月 14日からのロックアウトを経験しました。改めて学生運動の余燼が長く尾を引いてい
たことを感じます。そして後者の号では、昭和 50年11月の研究発表会(大会)の予告として、恩師の故新倉龍一先生の司会で岡田篤志先生、當麻一太郎先生、
阪田先生の司会で関谷武史先生(当時、高知大学教
授)、岡崎先生のそれぞれの研究発表のあることが告
げられています。
「英文学会通信」の歴史、と銘打ったものの、草創期
の内容紹介で終わりますが、もっとその歴史や恩師の
ことを知りたいと思う方は是非とも英文学研究室をお
訪ねになって下さい。今回このように過去を振り返る
機会を持つことができたこと自体を、諸先生方たちに
感謝いたしたいと思います。抗うことのできない時間
のベクトルに従容として従いながらも、我々の英文学
会は、各時代の先生方、学生、そして研究室スタッフ
と共に培ってきた「学統的遺産」を継承し発展させてい
く使命を担っていると思います。そして皆さまと共に
その使命を生きる喜びにしていけたならば幸いです。
末筆ながら会員諸氏のますますのご活躍とご健勝を
心から祈念いたしております。

─ ─4
日本大学英文学会2013年 11月
「英文学会通信」の草創期のものとして、第 2号を掲載いたします。(残念ながら事務局には創刊号の保存はありませんでした。)昭和 47年の本学会の様子や、お世話になった先生方の当時のご活躍がうかがえます。
《「英文学会通信」第 100号記念企画》

─ ─
英文学会通信 第 100号
5

─ ─6
日本大学英文学会2013年 11月
教員となって
埼玉県立川口北高等学校教諭 島田 雅史
私は去年の埼玉県の教員採用試験に合格した新任の
教員です。まずは、僭越ではありますが、私の経歴と
教員になるまでの道のりを述べさせて頂きます。私は
大学 3年の秋に教員の道を目指し、英語力を向上させるために、学部の 4年時に交換留学でハワイ大学に一年間留学をしました。学部を卒業した後は、大学院に
「在籍」しながら、埼玉県の公立学校で 2年間非常勤講師をしていました。そして大学院の博士前期課程 2年時に埼玉県の教員採用試験合格し、今年の 4月から新任の教員として働いております。そして教員になる
までの道のりの中で、留学と大学院、非常勤講師が私
の中で大きく影響をしています。
留学時は、拙い英語でうまくコミュニケーションが
できなく、授業になかなかついていけず大変苦労した
思い出があります。しかし、厳しい時期もありました
が、英語の教員になりたいのなら力を付けるしかな
い、と思い日々一所懸命勉強をしていました。大学院
でも必死に授業についていき、英語力を伸ばし、学校
現場では非常勤講師として教壇に立ち教員の経験をさ
せて頂きました。二つの立場を両立するのはとても大
変でしたが、その時の経験が今現在も大変生きている
と感じています。
私は今現在、「文武両道」を掲げる学校に勤めてい
ます。多くの生徒たちが現役で国公立大学や有名私立
大学を目指し、実績も残しています。また、部活動も
盛んで、全国大会や関東大会に出場している部活が多
くあります。高いレベルでの文武両道を実践し、満足
度の高い進路希望の実現を行なっています。生徒たち
は礼儀正しく、向上心を持った生徒が多いです。その
中で、私も高いレベルでの文武両道を実現するため
に、部活動の指導と教材研究を行なっています。他に
も校務分掌の仕事もあり、瞬く間に一日一日が過ぎ
去っていきます。毎日毎日が大変ですが、生徒の成長
が実感できると大変嬉しく思います。非常勤講師の時
は、授業でしか生徒と接することはありませんでした
が、今では、一日の多くの時間を生徒と過ごしてい
て、非常勤講師の時は得ることが出来なかった多くの
経験をさせて頂いています。
しかし、同時に多くの点で失敗もしています。毎日
悩みや不安を抱えています。すべての生徒が将来、社
会に大きく貢献する可能性を持っています。そして、
課題発見や課題解決能力、コミュニケーション能力、
主体性や積極性、チームで働く力などが社会で求めら
れています。授業やあらゆる教育活動の場において、
社会で求められているこのような力を育成していかな
ければなりませんが、私は、生徒にこのような力を向
上させることが出来ているのかと常に自問自答をして
います。「初任の先生だから」という逃げ道を作るこ
とも可能なのかもしれませんが、生徒にとっては、そ
んなことは何も関係ありません。一教師として、真摯
に誠実に対応しなければならないと考えています。生
徒は学校で多くのことを毎日学んでいます。生徒だけ
でなく、私も多くのことを常に学び続け、驕らずに授
業力と人間力を高め成長していかなければならないと
感じています。
最後に、将来教師を目指している方は、常に学び続
けてほしいと思います。ありきたりな言葉かもしれま
せんが、教員生活は休みもなく大変なことが多くあり
ます、しかし、それ以上にやりがいがあります。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
島教育体験記~苦あれば楽あり、楽あれば苦あり~
東京都小学校教諭 志田 満瑠
私は今、東京都の教員として伊豆七島の小学校に勤
めている。今年で島の小学校での勤務は 3年目になるが、 1年生の担任として勤務している今年は子供への指導や、保護者対応など仕事の厳しさを痛感している。
そもそも小学校 1年生の担任は幼稚園、保育園から上がったばかりの子供達に小学校生活の「いろは」を
教えることが主となるので、入学したての1学期は特
に教えることが多かったり、子供たちの行動に神経を
使うことも多く、心身ともにヘトヘトになる。また、
学校であったことなど 1年生ではまだきちんと親に伝えられないため、連絡帳や電話を通じて親と連絡をと
ることも必要となる。
親とのかかわりが多い学年の担任となった私だが、
島ならではの厳しさも体験している。私のいる島のお
母さん方は女の先生を、「東京から来た若い女」とし
て見ている節がある。他学年の先生と同じことをして
いても自分のところだけにクレームの連絡帳が来た
り、ちょっとしたことで電話がかかってきたりする。
保護者対応にもエネルギーを要し、精神的にヘトヘト
になる。自分のエネルギーは保護者ではなく子供たち
への指導に使いたいものだ。
ここまで、つらいことばかりをつづってきたが、島
という土地で、今ここでしかできないこともたくさん
ある。海に囲まれた環境ゆえ、夏は勤務が終わってか
らそのまま海へ行き、魚と一緒に泳いだり、海で採っ
た貝を調理して夕飯にすることもできる。また、外を
《エッセイ》

─ ─
英文学会通信 第 100号
7
歩けば木の上を走るリスを眺めることができたり、キ
ジやサルなどの野生動物に遭遇することもある。夜は
空一面に星が輝き、星をじっくり見ることもできる。
休みの日にはこの土地で採れる食材を使って料理を作
り、友達や同僚とお家パーティーを楽しむことも。
仕事に疲れたら、自然の中に身を置いてバランスを
とることで、充実した島の生活を送っている。自然豊
かな土地で教育に携わりたいと希望してきた島の学
校。理想と現実のギャップに苦労することもあるが、
いい面でも悪い面でも貴重な体験をしていると感じ
る。島生活も残り半年。充実した 3年間になるよう、一日一日大切に生活していきたい。
ゴールズワージィと「財産家」
元日本大学理工学部教授 桑山 泰助
最近日本ではゴールズワージィの小説があまり読ま
れなくなったので、彼の代表作「フォーサイト家物
語」の第一巻「財産家」についてほんの少し紹介致し
ます。
ジョン・ゴールズワージィ(1867-1933)は後に「フォーサイト家物語」の第一巻となった「財産家」を
1906年に発表、作家としての地位を確立したが、この小説が核となって第二巻「裁判沙汰」、第三巻「貸
家」と続き、更に「現代喜劇」(第一巻「白い猿」、第二
巻「銀の匙」第三巻「白鳥の歌」)へと発展する。ゴー
ルズワージィが 1932年にノーベル文学賞を得たのもこの「財産家」が大きな影響をなしている。この小説
は、著者が序文で述べているように、ビクトリア朝時
代の繁栄と衰退を描いたものではなく、物欲と美を代
表する人達の相克を描き出したものである。
フォーサイト家の人々の生き方は当時の社会の支配
者達であるブルジョワジーの生き方を表したものであ
るが、著者自身も上層中産階級の出身である。彼の父
は弁護士で、会社社長を務める金持ちで、教養の高い
人であった。従って著者はパブリックスクールから
オックスフォード大学へと進み、大学を卒業すると父
の希望通り法律家になる予定であった。しかし大学を
卒業して法律家の修業はしたものの、実務につくのを
嫌って世界漫遊の旅に出てしまった。旅から帰ると従
兄弟の妻エイダがみじめな結婚生活をしているのに気
がつき、同情の末恋仲となり、彼女が離婚するまで彼
女を助け、後に二人は結婚する。彼が作家になったの
はエイダの助言によるものであった。
「財産家」には著者の一族がモデルになって登場す
る。例えば一族の首長的存在のジョリオン・フォーサ
イトは彼の父を、アン叔母は彼の叔母エイダ・ゴール
ズワージィ、ロジャーは伯父ロバート、ニコラスはエ
ドウィン叔父をそれぞれモデルにしている等である。
また一族ではないが女主人公アイリーニィのモデルは
彼の妻エイダである。従って「財産家」は上層中産階
級の代表的存在である著者の一族の生活や性格、感情
や行動を基にして描かれているといってよい。特に彼
の父をモデルにした老ジョリオンについては、より具
体的でビクトリア朝時代の紳士の生き方、考え方、感
情や行動が如実に描かれていて感銘が深い。著者は老
ジョリオンについては特に拘りをもっていて、第一巻
に続く挿話「あるフォーサイトの小春日和」の主人公
として老ジョリオンの最後の老年の生き方を描いてい
る。彼はフォーサイトの代表的存在だったソウムズの
《特集》

─ ─8
日本大学英文学会2013年 11月
叔父として描かれ、脇役だったにも拘わらず、ソウム
ズに劣らずその存在が強調されている。これは著者が
父ジョン・ゴールズワージィを深く尊敬していたから
である。
著者は自分の所属する上層中産階級の生き方を肯定
しているのではなく批判的に捕えていて、ビクトリア
朝時代の紳士の生き方に疑問をなげかけ、小説を通し
て当時の風潮を批判した。特に主人公はその典型的な
人物として描かれ、フォーサイトの生き方を如実に表
している。見るもの聞くものすべてを自己の利益に結
びつけ、所有欲を発揮する、物質的価値が彼の精神の
中心をなしていて、財産の獲得とその投資に余念がな
い。しかし常識的で、勤勉と節制のある日常生活、伝
統を重んじる態度は一族ばかりでなく顧客にも信用さ
れ、仕事の上でも有利となる。つまり世間一般からは
信頼できる人物と見られている。
しかし物質的生活は豊かであるものの、ソウムズの
妻アイリーニィはフォーサイトとは異質の性格で美的
感覚にすぐれ、ビクトリア朝の伝統よりは自由を尊重
しているので、夫とは性格的に合わない。彼女は夫が
邸宅の新築を依頼した若い建築家ボッシニィと考えが
一致して恋に落ちる。ソウムズは邸宅の建築が完了し
た後請負額の超過を理由に訴訟を起し、ボッシニィを
破産させる。ボッシニィはある日霧深いロンドンの街
頭で交通事故により死亡する。アイリーニィは絶望の
末ソウムズの家を出る。ソウムズはフォーサイト的考
えに捉われているため妻の考えていることを理解でき
ず遂に家庭は崩壊する。
著者はビクトリア朝時代の財産観念と所有欲に捕わ
れた上層中産階級の生き方にメスを入れ、反省を求め
たが、彼らの存在を否定してはいない。フォーサイト
の生き方はこの時代のイギリス紳士の生き方の一面を
表したものであるが、これは現代に通ずるものがあ
り、現代人にもこのような物質主義の世界に捕われた
生き方をしている人達がいることも否定できない。物
質的欲望に捕われた非人間的な一面を曝けだす人々が
いるのはどの社会にも見受けられるもので、この時代
に限られたものではないが、産業革命後のイギリスに
おいては特に顕著なものとなった。このように「財産
家」はビクトリア朝時代の社会的背景と紳士達の生き
方を知るだけでなく、人間のもつより根源的な人間性
を学ぶことができる。
アメリカ留学体験記
日本大学文理学部英文学科 4年 磯野 広大
私は 2012年 8月から 2013年 4月までの約 8ヶ月間、アメリカのミシガン州にあるWestern Michigan Universityに留学しました。大学に入る前から目指していた交換留学が実現でき、結果的にかけがいのない
時間をこの留学を通じて過ごすことが出来ました。
まず初めに授業には本当に苦労しました。短期語学
留学や英文学科で英語のみの授業を経験してきた私
は、アメリカの授業もなんとかなると高を括っていま
したがそれは初日に打ち砕かれました。先生は勿論生
徒もアメリカ人前提なので話すスピードは速いし、
しょっちゅう知らない単語が聞こえてきたりで何を
言っているのか良く分からず、これからの留学生活が
不安に感じました。しかしそんなときでもきちんと助
けを求めれば先生も生徒も優しく教えてくれ、 3ヶ月もすれば大体理解できるようになりました。私は留学
先では主に英文学と宗教学の授業を履修しました。ど
の授業も毎回必ず課題が出され、授業もその課題を
やったことを前提で行われます。テストも中間 2回に期末 1回と 1つの授業だけで 3回あり、そのほかにもレポートや毎授業行われるクイズなど常に勉強してい
ないとすぐに追いつけなくなります。テスト前やレ
ポート提出前は図書館に朝まで缶詰状態なんてことも
ありました。
平日は勉強に集中する分、週末は思い切り遊ぶこと
を心がけていました。といっても留学先であるWMUはKalamazooという田舎町にあるため、ダウンタウンに行っても特にレジャー施設はないので基本はキャン
パス内にあるジムでスポーツをしたり、友人宅でパー
ティーをすることが多かったです。また高校から続け
ているバドミントンを通じてキャンパス内だけでなく
様々な人とも出会うことができました。学校のジムで
知り合ったベトナム人の方に誘われ、カラマズーバド
ミントンクラブに入りました。ここでは老若男女・国
籍問わず様々な方がバドミントンをしており、週一回
ここにお邪魔させてもらっていました。またデトロイ
トで行われた大会に出場し、準優勝できたのもアメリ
カでの大切な思い出です。
私はこの留学を通じて自分が日本人であることを初
めて認識させられました。日本で生まれ育った生粋の
日本人であるはずなのに、周りにいる人も同じ日本人
であるせいか自分が日本人なのだと頭で分かっていて
も肌で感じることはありませんでした。しかし様々な
人種が集まるアメリカでの生活を通して、私が世界に
たくさんある地域の中のアジア人であること、その中
《海外留学体験記》

─ ─
英文学会通信 第 100号
9
でも日本人であることに気付かされました。日本への
帰属意識を感じると同時に日本人としての誇りも感じ
始めるようになりました。留学先の国柄に染まるのも
留学の 1つの目的ではあると思います。しかしただ染まりきるのではなく自国の精神も保ちつつその他の国
も理解できるようになること、これが真の留学する意
義なのではないかと私は思います。
私はこの留学を支えてくれた私の家族、日本と留学
先の友人、日本大学や FLEC(外国語教育センター)の方、同じWMUに留学された先輩方に心から感謝しています。ここで得た知識や経験、友人は一生物の宝
であり、これからの人生でも大切にしていきます。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
留学を通して学んだ人生で大切なこと
日本大学文理学部英文学科 4年 西村 雅裕
中学、高校、大学と何年も英語の勉強をしてきまし
たが、英語を話せるかどうかと言えば、答えはNoでした。英文学科に所属して、学部 2年までの間に、英文法の基本的な知識は詰め込んだつもりでしたが、実
際に外国人と英語で会話するとなると、まったく会話
が続きませんでした。そもそも疑問文が作れない。相
手が何を言っているのか分からない。自分の話す英語
に自信が持てず、下を向きながらもごもごと話してい
ました。
学部 1年の生活を終え、肝心の英語力は伸びたかというと、ほとんど伸びていませんでした。追い打ちを
かけるように、その頃受けたTOEICの結果を見て落胆しました。本当に、 1年を無駄に過ごしてしまったような気がしました。「このままじゃだめだ。他の人には
出来ない何かをしてやろう。」そう思い、留学について
調べ始めました。
本格的に留学について準備をスタートさせたのは、
学部 2年の 5月か 6月のことだったと思います。最初はTOEFLのスコアとの戦いでした。成績は伸びているものの、なかなか目標点としている 500点以上を取ることが出来ませんでした。授業の予習や復習、アル
バイトなどに時間を取られ、TOEFLを勉強するための時間はほとんどありませんでした。しかし、毎日コツ
コツ時間を作ってTOEFLの勉強をしました。そして、交換留学の申し込みまでTOEFLの試験回数が残り 2回を切った時に、初めて 500点を超えました。結局、そのスコアで交換留学を申し込み、試験に合格しました。
8月初旬、飛行機に乗って日本を発ち、初めて異国の地に降り立ちました。初めて来た異国の地は、日本
の夏のように暑かったのを覚えています。ただ、ジメ
ジメとはしておらず、心地よい風が吹いていました。
私が留学することになったのは、アメリカにあるアラ
バマ大学バーミングハム校(UAB)というところでした。UABには日本人の学生が私を含め、 5人しかいませんでした。そのうちの 2人は私と同じように日本大学からきた交換留学生と茨城大学から来た交換留学生
でした。UABから近くのスーパーまでは車で 20分、日本人は学内に数名、もちろん日本語は通じない。そ
んな環境の中で留学生活をスタートさせました。
一週間もすれば授業が始まり、キャンパスの中で生
活する機会が増えてきました。友達と一緒に図書館で
勉強をしたり、ジムで汗を流したり、夜は友達とご飯
を食べに行ったり、なかなか充実した生活を過ごして
いました。さて、本題の英会話ですが、 2カ月もすればだいたいの英語は聞き取れるようになりました。し
かし、私の言っていることはなかなか理解してもらえ
ませんでした。文法も発音もそこまで間違っているわ
けでもないのに通じない。そんな日が続いていました。
ある日、日本人の友人とアメリカ人の友人の 3人でフロリダまで遊びに行きました。その車中、また僕の
言った英語がアメリカ人に通用しませんでした。僕は
半ば自信を失いかけていました。その時、日本人の友
人が本当に滅茶苦茶な発音で、しかも文法なんか一切
気にしていない様子で英語を話し始めました。私は、
これは通じないだろうと内心思っていましたが、アメ
リカ人の友人は理解しています。なんと会話が成り
立っているのです。私はその場で驚き、思わずアメリ
カ人に聞きました。「なんで、彼の英語は分かるのに、
私の英語は通じないの?」そうすると、彼女はこう答
えてくれました。「あなたは話している時に下を向いて
いるし、自信がなさそうだから、分からないんだよ。」
その言葉を聞いてハッとしました。会話が続かなくな
るときはいつも、私が自信なさげに下を向いて話して
いたのです。アメリカ人の友人はこうも続けました。
「あなたの英語は間違っていないよ。だから自信を持っ
て、相手の目を見て話しなさい。」と。
私は旅行から帰ったあと、すぐにそれを実践しまし
た。すると今まで、続かなかった会話がだんだん続く
ようになりました。むしろ多少文法や発音を間違えた
としても、気にする人なんてほとんどいませんでした。
そう、私が犯していた最大のミスは、「自信なく話して
いたこと」だったのです。思い返してみれば、あの発
音も文法も無茶苦茶だった日本人の友人はいつも自信
満々で、笑顔で、相手の目を見て話していました。
それからの私は、間違いを恐れることなく、堂々と
英語を話すようになりました。そのせいか、だんだん
と英語も話せるようになっていきました。表情には笑
顔が増え、友達もどんどん増えていきました。
留学期間を終え、日本に帰ってきた今も、もちろん
英語は完璧ではありません。どんどん英語を間違えて
います。そして、その度に、英語母語話者の友人に英

─ ─10
日本大学英文学会2013年 11月
語を直してもらっています。私が留学生活の中で得た
ものは、「間違いを恐れない勇気」でした。これからの
人生、たくさん間違えることもあると思います。その
度に今回の教訓を思い出し、失敗を恐れず、また小さ
な間違いをしながら、先に進んで行こうと思います。
さて、末尾ながら、余談を少し。今回、「英文学会
通信」第 100号という節目にこのような形で執筆の機会を頂き、誠にありがとうございました。編集に携
わった皆さま、並びに先生方には、この場を借りて感
謝の意を申し上げたいと思います。加えて、私ごとで
はありますが、後期から FLECの英語圏留学アドバイザーに内定いたしました。留学について質問があれば、
お気軽に FLECにお越しください。また、私が留学中に書いた記事が日本大学のホームページに掲載されて
います。留学に興味があれば、そちらも参考にして頂
ければ幸いです。
さて、皆さまは「同窓会通信」の第 9号の吉良先生のお言葉を覚えていらっしゃいますでしょうか。吉良先
生は自身が大の革製品好きだということを例に「こだ
わり」を持つことの大切さを説いていらっしゃいまし
た。私も学部 2年の時、このままでいいのか、何も頑張らなくていいのか。そう思ったときに「こだわろう」
と思ったベクトルの先が留学でした。何も勉強が全て
ではありません。今、あなたが好きで、熱中出来るも
のに、他人に負けない「こだわり」を持ってみません
か。それがスポーツでもファッションでもアニメでも
何でも構いません。大学生活をより充実したものとす
るためには、何か熱中できるものが必要だと、この 3年半の生活を通して実感しました。残りの大学生活を
充実させるために、皆さまも他の人には負けない「こ
だわり」を持って大学生活を過ごしてみてはいかがで
しょうか。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
27歳からの海外留学日本大学大学院博士後期課程 3年 小澤 賢司
トロント大学へ留学しようと思った理由、それは世
界有数の大学であり、日本では得ることのできない経
験ができると思ったからです。また、英語の道を志そ
うと決めた中学の頃より、一度でもいいから留学をし
たいとずっと考えていました。それまでも行ける機会
は何度かありましたが、諸事情が重なり実現はしませ
んでした。しかし、 27歳を迎えた去年、学生のうちに行けるラストチャンスが訪れ、「今」しかないと思
いました。 よく言われることですが、最初の 1、 2か月は言葉
の壁や文化の違い、気の知れた友人もおらず、大学で
の授業レベルの高さなどに圧倒され、本当に厳しい状
況でした(住む場所を探すのが一番苦労し精神的にも
かなり堪えました。住む場所があることのすばらしさ
を身に染みて感じました)。しかしそれはある意味自
分が望んだ場所であり、その厳しさがあったからこ
そ、その後の楽しさも一ひと
入しお
だったと思います。語学力
の向上、もう一度一いち
から言語学を学びたいという思い
でトロントへ旅立ちましたが、生活をしていくうち
に、徐々にそれよりも重要なことに気づかされまし
た。それは、人との「出会い」です。詳しい統計的な
数字や割合は知りませんが、日本では道行く人ほとん
どが日本人です。しかしトロントはmulti-culturalと言われるほど人種のるつぼで、本当に様々な人たちが
います。カナダ人、というと白人をイメージする人も
多いかと思いますが、ことトロントに関してそれはあ
まり当てはまりません。移民の街とも言われており、
ヨーロッパ、南アメリカ、西アジア、東アジアからの
移民者がたくさんいます。一見アジア系の人にWhere are you from?と聞いても普通に I’m from here (Toronto, Canada). と返されることもありました。小さいころにカナダに来たり、親や祖父母の世代でカナダに移民
したりと、自分たちはすでにカナダ国籍を持ったカナ
ダ人なのです(一番仲良くなった友人も移民者でし
た)。このように様々な人種がいるせいか、いわゆる
人種差別ということは他と比べれば驚くほど少ないら
しいです。見た目は関係ない。こういった理由がさら
にも増して移民を増やす原因なのかもしれません。こ
れは単なる一例に過ぎませんが、語学・勉学だけでな
く、筆舌し尽しがたい有意義なことをトロントでの
(学生)生活を通して体験・経験することができたと
強く思います。 授業に関しては、(自分は単位を取る必要がないた
め)それほど多くの授業を履修していませんでした
が、それでも 1つ 1つの授業から多くのことを得られました。授業全てについていくのは難しかったです
が、出される課題、テキストや論文の読書(予習)、
少人数制クラスの tutorialでの質疑応答、 discussion等を通して総合的な力を身に付けることができたと実感
しています。また、トロント大学の学生・先生がたは
非常に熱意を持った人たちばかりでした。はっきり
言って、日本での学生生活では自分だけが勉強を頑
張っているという状況が度々ありましたが、トロント
大学ではむしろ自分の努力が少ないということがほと
んどでした。皆予習・復習をしっかりとこなしていた
し、授業前に学生同士で質問しあうということもしば
しばありました。授業もとても熱のこもったものが多
く、自分の分野がどれほど面白いものなのかを真剣に
伝えようとしていました。日本では残念ながら興味深
いとは言えなかった授業もこちらではなぜか楽しく思
える。決して日本の授業のレベルが低いと言っている

─ ─
英文学会通信 第 100号
11
のではありません。演者によってそれほど代わり映え
するということです。学生・先生ともに質の高い授業
をトロント大学では受けることができました。また、
日本では、いわゆる「理系」とは異なり、「文系」で大
学院に進学する人は少なく、自分のように研究者を目
指す人はさらに希少です。日本にいるときは互いに刺
激となるのは本当にごく一部の人でしたが、トロント
大学では研究者を志している学生も多く、そのような
出会いも自分にとって非常に良い刺激となりました。 トロントでの(学生)生活は本当に刺激の連続でし
た。留学の本当の意義とはこれなのかもしれません。
日本は非常に便利で豊かで平和な国です。だからこ
そ、その「ぬるま湯」に慣れてしまい、だんだんと刺
激がなくなってくる。刺激がなければ目標も曖昧にな
り、次第に消えてしまう。留学は良い意味での「人生
の劇薬」なのかもしれない、と今日本に帰ってきて一
番に思うことです。自分と同じように留学に興味が
あった人、そして今も興味ある人は、(少し、どころ
か半端じゃなく大変ですが)留学することを考えてみ
てもよいかもしれません(もう少し若い頃に行けばよ
かったとちょっぴり後悔しています)。 また、留学前から留学期間中、実に多くの人たちに
助けていただきました。そのすべての方々にこの場を
借りて感謝申し上げたいと思います。
Paradise Lostにおける「存在」の考察
日本大学文理学部助手A 野村 宗央
本発表では、 John Milton(1608-74)の Paradise Lost(1667)における「存在」について、 C. S. Lewis(1898-1963)による「善」と「悪」の観点からみた「存在」の定義付け、及び反乱の天使達の前では “self-begot, self-raised / By our own quickening power”(5. 860-1)と壮語する一方、“He [God] deserved no such return / From me, whom he created what I was / In that bright eminence, and with his good / Upbraided none; nor was his service hard.”(4. 42-5)と独り嘆く Satanの台詞をはじめとした、本作における「存在」にまつわる記述
を概観し、キリスト教詩人としてのMiltonの立場・考えを踏まえた上でなお、そこに新たな解釈を加える
ことが可能かどうかを考察する。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
サマセット・モームの歴史小説Then and Now(1946)を読む
日本大学文理学部准教授 前島 洋平
1946年に刊行されたThen and Now は、 16世紀初頭のイタリアを舞台に主人公のニッコロ・マキア
ヴェリが祖国フィレンツェ存亡の危機をかけて政治
の舞台裏で活躍する歴史小説であるが、作者モーム
には作家として駆け出しのころに歴史小説を書いて
大失敗に終わるという苦い経験があった。したがっ
て、このジャンルの作品に再び挑戦するには相当の
覚悟と準備を要したものと思われる。
こうしたモームの意気込みが実を結んだためか、
本作は出版直後にベストセラーとなった。しかし、
アメリカの批評家エドマンド・ウィルソンによる酷
評を機に、失敗作としての評価が定着した。ところ
が近年になって、日本では『昔も今も』の邦題で新訳
が出され、他方、マキアヴェリの交渉相手チェーザ
レ・ボルジアの父、教皇アレクサンデル 6世を主人公とする海外製作のドラマが好評を博す現象が起
こった。
本発表では、出版時の書評やその後の先行研究を
概観からすることからはじめ、モームの他の後期作
品との比較をとおして本作の特徴と意義を考察する。
《年次大会発表要旨》

─ ─12
日本大学英文学会2013年 11月
可能性は無限大「お遊びに終わらない小学校英語教育」とは?
日本大学文理学部講師 池田 和子(紅玉)
2011年度から公立小学校での外国語(英語)活動が必修となり、英語の教科化に関する記事やニュースを
目にすることも増えました。小学生時代に英検他のテ
ストを受験する生徒の数も年々増えています。
発表当日は「小学校英語教育」の目指しているもの
と可能性について話をし、「小学校英語教育」に対す
る賛成派、反対派の典型的な意見を私なりにまとめた
ものを発表します。また私が小学校で 2年間の研究授業を行った際の様子と成果をビデオでご紹介すること
で、幼い生徒の高い学習能力と可能性を感じとってい
ただき、ご一緒に「お遊びに終わらない小学校英語教
育とは何か」について考えたいと思っています。生徒
のやる気満々の笑顔と嬉々として英文を暗誦する姿に
ご期待ください。
● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
[最終講義]ジョンソン博士に寄せるホーソーンの思いをめぐって
日本大学文理学部講師 當麻 一太郎
ナサニエル・ホーソーンは、帰国後の 1863年、英国滞在記を基に纏め直した『われらが故国』を出版し
た。英国滞在中、出版者でもあり友人でもあった
ティックナーに宛てた手紙の中で「本当のことを書き
すぎたので、出版すると、かなり大勢の人たちの攻撃
を受けることになるだろう」と記したことがあった
が、それは、予想通り、出版されるとすぐに、英国文
壇の間で物議を醸すことになった。じっさいThe Timesや風刺雑誌 Punchなど多くの雑誌がホーソーン攻撃をしたのである。
英国人に対するホーソーンの辛辣な記述に反論する
雑誌の中で、「ホーソーンは英国人を単眼的人間であ
るとして非難している」とサミュエル・ジョンソンを
絡めて綴るThe Christian Remembrancerの筆致は、ジョンソンに対するホーソーンの感情を考える上で重
要な問題を提供しているように思われる。そこで、
ジョンソンに対するホーソーンの感情とそこから考え
られる『緋文字』における牧師の告白を考察してみた
いと思う。

日 時:12月 7日(土)13:30より場 所:日本大学文理学部
図書館 3階オーバル・ホール (学術研究発表会・総会) カフェテリア・チェリー(懇親会)
会長挨拶:深沢 俊雄(聖徳大学教授)
学術研究発表会
◆文学の部:13:35~14:55 [司 会] 安藤 重和(法学部教授) [発表者] 1. 野村 宗央(文理学部助手A) 2. 前島 洋平(文理学部准教授)
休憩:14:55~15:00(5分間)
◆語学の部:15:00~15:40 [司 会]中村 光宏(経済学部教授)
[発表者]池田 和子(紅玉)(文理学部講師)
休憩:15:40~15:50(10分間)
◆最終講義:15:50~16:50 [司 会]高橋 利明(文理学部教授)
[講 師]當麻 一太郎(文理学部講師)
休憩:16:50~17:00(10分間)
総 会:17:00~17:30 [司 会]飯田 啓治朗(文理学部准教授)
[会長挨拶]深沢 俊雄(聖徳大学教授)
[会務報告]一條 祐哉(文理学部助教)
[会計報告]堀切 大史(文理学部准教授)
その他
懇 親 会:17:40~19:40 懇親会費:研究会員 5,000円 学生会員・大学院生 2,000円 同窓会員 無料
日本大学英文学会 2013年度学術研究発表会・総会・懇親会
《年次大会プログラム》
─ ─
英文学会通信 第 100号
13
●月例会報告
2013年 6月以降の月例会・特別講演は以下の通り行われました。
6月 研究発表・特別講演(2013年 6月 22日)【研究発表】
[司 会]野呂 有子(文理学部教授)
[発表者]オセロ―の主体構築と国家
藤木 智子(文理学部講師)【特別講演】
[司 会]野呂 有子(文理学部教授)
[講演者]シェイクスピアと『サー・トマス・モア』
―もうひとつのプロット、もうひとつの夢 大橋 洋一(東京大学大学院教授)
9月 アメリカ文学シンポジウム(2013年 9月 28日) 「アメリカ文学作品にみる “humanity”」[司 会]深沢 俊雄(聖徳大学教授)
[発題者]
1. ロマンスの磁場 ― “The Snow-Image” の “humanity” について
高橋 利明(文理学部教授) 2. そのときアダムとイヴに何が起きたのか ―マーク・トウェインが描く ‘Humanity’ を探る
鈴木 孝 (理工学部准教授) 3. 『あの夕陽』(1931)―洗濯女ナンシーの周縁で 佐藤 秀一(佐野短期大学教授) 4. スタインベックの『二十日ねずみと人間』における humanity
深沢 俊雄(聖徳大学教授)
10月 英語学シンポジウム(2013年 10月 26日) 「テンスとアスペクトへの誘
いざな
い」
[司 会]佐藤 健児(文理学部講師)
[発題者]
1. 「自然の成り行き」を表すwill be -ing 構文をめぐって―テンス、アスペクト、モダリティの観
点から―
佐藤 健児(文理学部講師) 2. 英語の現在完了形はテンスかアスペクトか 山岡 洋(桜美林大学教授)
《月例会関連》

─ ─14
日本大学英文学会2013年 11月
3. 知覚動詞構文のアスペクト(再訪) 吉良 文孝(文理学部教授)
●月例会予定
2013年 11月以降の月例会の予定は以下の通りです。詳細が決まり次第、 e-mailと本学会ホームページでご案内いたします。
11月 研究発表(2013年 11月 16日)[司 会]鈴木 孝(理工学部准教授)
[発表者]
1. 推量を表す法助動詞と疑問文 小澤 賢司(博士後期課程 3年) 2. トニ・モリソンの描くパラダイスについての考察―Paradiseについて
茂木 健幸(文理学部講師)
12月 2013年度学術研究発表会・総会(2013年 12月 7日)
詳細は p.13の年次大会プログラムをご覧下さい。
1月 研究発表(2014年 1月 25日)[司 会]塚本 聡(文理学部教授)
[発表者]
1. 秋葉 倫史(文理学部講師) 2. 堀切 大史(文理学部准教授)
●研究発表者募集
当学会では、次年度の月例会・年次大会の発表者を
募集しています。申し込み希望者は、以下について事
務局までお知らせ下さい。なお、検討の結果、ご希望
に添えない場合がございます。
1. 氏名2. 住所3. 電話番号・メールアドレス4. 所属5. 発表希望年月6. 発表題目7. 要旨(日本語 400字以内、英語 200語以内)
本学会員による新刊書を下記の通りご報告します。
なお、学会員で研究書等を出版された方は事務局(英
文学科研究室)までお知らせください。新刊書案内と
して随時掲載いたします。
(1)藤井繁.『群青:トマス・ハーディ「世紀末への挽歌」』.東京:コプレス,2012年.
(2)―――.『逆光:D. H. ロレンスの詩―光と闇』.東京:コプレス,2013年.
(3)武井暁子、要田圭治、田中孝信編.『ヴィクトリア朝の都市化と放浪者たち』.東京:音羽書房鶴
見書店,2013年. (4)日本英語文化学会編.『英語文化研究』.東京:成
美堂,2013年. (掲載順は発行年月日による)
《新刊書案内》

─ ─
英文学会通信 第 100号
15
●寄贈図書について
本学会員の藤井繁先生(聖徳大学名誉教授)より、
以下 2冊のご著書を本学会宛に寄贈いただきましたので、ご報告いたします。なお、英文学科書庫にて配架
させて頂きます。
(1)『群青:トマス・ハーディ「世紀末への挽歌」』.東京:コプレス,2012年.
(2)『逆光:D. H. ロレンスの詩―光と闇』.東京:コプレス,2013年.
●全国学校図書館協議会選定図書について
本学会員の岡田善明先生(日本大学講師)による
『英語教育の精神と実践:コミュニケーションから英
米文学まで』が全国学校図書館協議会選定図書に選ば
れました。ご著書については「英文学会通信」(第 99号)の新刊書コーナーでご紹介しております。
●卒業された同窓会員の皆様へ
本学会の構成が同窓会員、研究会員、および学生会
員よりなっていることは、すでにご存じのことと思い
ます。これまで、英文学科入学時に学生会員としてご
入会頂き、 4年間の会費(年額 500円)を、また、卒業時には同窓会員として1年間の会費(年額 1,000円)を前納して頂いております。日本大学英文学会会則に
より、会員は 3年間会費未納の場合には、その資格を喪失します。研究会員への移行を望む方、または引き
続き同窓会員を希望される方は、振り込み用紙などを
使って年会費をお支払いください。もし 3年間を過ぎても会費が払われない場合は、その時点で自動的に退
会となります。
本学会では会員名簿を 1年に一度改訂し、出来上がり次第お送りしています。この会員名簿は英文学科卒
業生名簿としての役割もしていることにお気付きの方
も多いことでしょう。先に触れましたように、「英文
学会通信」や「会員名簿」につきましても、会員の資
格を失った場合には郵送されません。
しかしながら、英文学会では、全卒業生のその後の
消息を把握しておきたいと思います。そこで、住所変
更など、ぜひとも本学会ホームページ(http://www.chs.nihon-u.ac.jp/eng_dpt/esanu/index.htm)や e-mail([email protected])、もしくは「〒 156-8550 世田谷区桜上水 3-25-40 日本大学文理学部英文学研究室内 日本大学英文学会」宛てにご連絡くださるよう
にお願いいたします。送られてきました情報は、こち
らのコンピューターファイルに入れて、厳重に管理い
たします。
《事務局・研究室だより》 ●会費納入のお願い
2013年度学会費(研究会員 4,000円、同窓会員1,000円)を未納の方は、郵便振込で納入下さいますようお願いいたします。
口座番号:00140 - 3 - 27474 加入者名:日本大学英文学会

─ ─16
日本大学英文学会2013年 11月
『英文学論叢』 第 63巻 原稿募集について
日本大学英文学会機関誌『英文学論叢』第 63巻(2015年 3月発行予定)の原稿を募集いたします。
投稿希望の方は『英文学論叢』第 62巻(2014年 3月発行予定)巻末の投稿規定に従って下記にお送
り下さい。
締切日 2014年 9月 30日(火)(必着)
宛 先 〒 156-8550 東京都世田谷区桜上水 3-25-40
日本大学文理学部英文学研究室内 日本大学英文学会
Tel.: 03-5317-9709 Fax: 03-5317-9336
E-mail : [email protected]