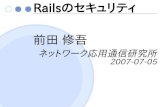技術研究所 研究所報 No...Title 技術研究所 研究所報 No.62 Author 技術研究所 企画部 Created Date 3/26/2007 8:48:16 PM
気になる会計用語 -...
Transcript of 気になる会計用語 -...
目 次 ねらい
基本編
内部留保
剰余金
自己資本利益率(ROE)
発行済株式数
債務超過
応用編
評価・換算差額等とその他の包括利益(OCI)
当期純利益と当期利益と純損益
IFRSと国際会計基準
probable(発生の可能性が高い)
ねらい
出席者は、経理関係のみならず、総務関係の実務に携わる方々
認識・測定を中心とした会計処理の論点よりも、しばしば使っている会計に関する用語を取り上げる方が適当ではないか
週刊 経営財務 [税務研究会] 毎週月曜刊行
<気になる論点>隔週 好評 連載中!
4月3日(No.3304) 第184回 業績予想の開示-決算短信の見直しにおいて
6月5日(No.3312) 第188回 権利確定条件付き有償新株予約権-なぜ費用計上されるか
7月17日(No.3318) 第191回 IASBの保険契約(1)-IFRS第15号の考え方との異同
3
内部留保(1)
財務大臣は福岡市で講演し、企業が利益を内部にため込んだ「内
部留保」が増え続けている現状を批判したうえで、経済を活性化さ
せるため、設備投資や賃上げなどに、より積極的に回すべきだとい
う考えを示しました。
(NHKニュース 2016年9月17日)
4
内部留保とは 上述の文脈前半において、「内部留保」は利益剰余金
上述の文脈後半では、企業が利用な可能な資金に近い現預金残高の問題を取り上げているのではないか
使い方が明確ではないことが、「内部留保」の有効利用という議論においても混乱を生じさせていないか(西山(2016))
内部留保=現預金残高? 余剰の現預金は、資本コスト以上で運用されないため、企業価値を下げる
企業価値の向上には、収益性のある投資か、株主還元へ
内部留保(2) 5
Topix1000のうち、金融を除く786社
1999年度 2007年度 2015年度
現預金 36兆円( 8%) 43兆円( 8%) 73兆円(11%)
利益剰余金 73兆円(17%) 137兆円(26%) 192兆円(28%)
* ( )内は、総資産に対する比率を示す
出所:西山(2016)
剰余金 6
個別財務諸表における純資産の部 Ⅰ 株主資本
1 資本金 2 資本剰余金 資本準備金 その他資本剰余金 3 利益剰余金 利益準備金 その他利益剰余金 4 自己株式
XXX XXX
XXX XXX
XXX
XXX
XXX △XXX
株主資本合計 XXX Ⅱ評価・換算差額等) XXX Ⅲ 新株予約権 XXX
純資産合計 XXX
会計/会社法 剰余金の意味
企業会計原則 注解(注19) 資本剰余金+利益剰余金
会社法446条、会社計算規則149条 その他資本剰余金+その他利益剰余金
自己資本利益率(ROE)の算定式
有価証券報告書における「主要な経営指標等の推移」において
決算短信のサマリー情報における「連結経営成績」において
自己資本利益率(ROE)(1) 7
自己資本利益率
= 親会社株主に帰属する当期純利益
純資産-新株予約権-非支配株主持分
自己資本 当期純利益率
= 親会社株主に帰属する当期純利益
× 100 (期首自己資本+期末自己資本)÷2
(*)自己資本 = 純資産合計-新株予約権-非支配株主持分
分母 2005年12月公表の企業会計基準第5号
「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
開示されているROEの分母は、改正前と、形式的な連続性はある
しかし、1999年公表の「金融商品に係る会計基準」により、その他有価証券評価差額金などを資本の部に直接計上することになったにも関わらず、それ以前と同様に、ROEを、「当期純利益/資本の合計額」で算定してきたこと自体が、実質的に連続性を失っていたのではないか
自己資本利益率(ROE)(2) 8
改正前 改正後
貸借対照表
①新株予約権 負債 純資産
②少数株主持分 負債と資本の中間 純資産
③評価・換算差額等 資本 純資産
ROEの分母 資本の合計額 純資産の合計額-①-②
<連結B/S>純資産の部 <連結損益及び包括利益計算書> Ⅰ 株主資本
1 資本金 2 資本剰余金 3 利益剰余金 4 自己株式
XXX XXX XXX XXX
売上高 XXX
・・・・ ・・・・ 当期純利益 1,000
株主資本合計 XXX 親会社株主に帰属 900 Ⅱその他の包括利益累計額
(AOCI) XXX
非支配株主に帰属 100
Ⅲ 新株予約権 XXX その他の包括利益 XXX Ⅳ 非支配株主持分(NCI) XXX (OCI)
純資産合計 XXX 包括利益 XXX
自己資本利益率(ROE)(3) 9
開示されているROE:分子と分母が見合っていない
分子:親会社株主に帰属する当期純利益(従来の当期純利益)
分母:純資産-新株予約権-非支配株主持分 (=株主資本+その他の包括利益累計額)
分子と分母が見合うROE
自己資本利益率(ROE)(4) 10
意味(*) 資本利益率
A 親会社株主に帰属する当期純利益
株主資本
A+B 親会社株主に係る包括利益
株主資本+親会社株主に係るその他の包括利益累計額
A+C 当期純利益
株主資本+非支配株主持分(その他の包括利益累計額分を除く)
A+B+C+D 包括利益
純資産
(*) A~Dは以下を意味する タイミング
範囲 投資のリスクから 解放されたもの
投資のリスクから 解放されていないもの
親会社株主 A B
非支配株主 C D
所有割合
事業報告の「上位10名の株主の状況」
大株主の議決権に着目し、自己株式を控除
有価証券報告書の「大株主の状況」
流通市場への情報提供等の観点から、自己株式を控除していない
2016年4月公表の金融庁 金融審議会DWG「ディスクロージャーワーキング・グループ報告-建設的な対話の促進に向けて-」
自己株式の数に係る情報は「議決権の状況」等でも開示されていることを考慮すると、有価証券報告書における「大株主の状況」においても、発行済株式から自己株式を控除することで事業報告との共通化を図ることが適当である
発行済株式数(1) 11
2002年9月公表
企業会計基準第2号 「1株当たり当期純利益に関する会計基準」
企業会計基準適用指針第4号 「1株当たり当期純利益に関する会計基準の適用指針」
発行済株式数(2)
1株当たり当期純利益
= 普通株式に係る当期純利益
普通株式の期中平均発行済株式数-期中平均自己株式数
1株当たり純資産額
= 普通株式に係る期末の純資産額
期末の普通株式の発行済株式数-期末の自己株式数
12
IFRS
IAS第1号「財務諸表の表示」における開示
授権株式(shares authorised)の数
Shares issuedの数
Shares outstandingの数の期中における変動内訳
IAS第33号「1株当たり利益」
わが国では、Shares outstanding(自己株式を除く発行済株式)に相当する用語はない
発行済株式数(3)
基本的1株当たり利益(Basic EPS)
= 親会社の普通株主に係る当期純利益
当期中における普通株式のShares outstandingの加重平均株式数
13
制定法
破産法の破産手続開始原因において(破産法第16条第1項)
債務超過は、債務者が、その債務につき、その財産をもって完済することができない状態
特別清算の開始原因において(会社法第510条第2号)
債務超過は、清算株式会社の財産が、その債務を完済するのに足りない状態
債務超過(1) 14
貸借対照表
資産 80 負債 100
純資産 ▲20
東京証券取引所の基準
指定替基準(有価証券上場規程第311条第1項第5号)
上場廃止基準(有価証券上場規程第601条第1項第5号)
債務超過の状態を判断するために算定される「純資産の額」
= 連結貸借対照表の純資産の部の合計額+所定の準備金等-新株予約権
-非支配株主持分(NCI)
債務超過(2) 15
貸借対照表
資産 110 負債 100
純資産
株主資本+AOCI ▲20
新株予約権+NCI 30
非支配株主持分(NCI)
2005年12月公表の企業会計基準第5号 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
子会社の資本のうち親会社に帰属していない部分であり、返済義務のある負債でもなく、また、連結財務諸表における親会社株主に帰属するものでもない
財務分析の観点
自己資本比率のような安全性:NCIも「資本」の一部
AOCIも「資本」の一部か?
資本利益率のような収益性: NCIは、どの利益に見合う「資本」か?
AOCIも、どの利益に見合う「資本」か?
債務超過(3) 16
改正前 改正後
非支配株主持分(NCI) 負債と資本の中間 純資産
その他の包括利益計上額(AOCI) 資本 純資産
評価・換算差額等とその他の包括利益(1)
評価・換算差額等
2005年12月公表の企業会計基準第5号 「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準」
評価・換算差額等は、払込資本ではなく、かつ、未だ当期純利益に含められていない ⇒株主資本とは区別し、株主資本以外の項目とする ストック情報
国際的な会計基準においては、その他包括利益累計額(AOCI)として区分
⇒2005年公表の過程では、包括利益が開示されていない中での表記は適当ではないため、その主な内容を示すよう「評価・換算差額等」として表記
評価・換算差額等の各項目は、株主資本に含めるべきという意見
⇒しかし、一般的に、資本取引を除く資本の変動と利益が一致するという関係は、会計情報の信頼性を高め、企業評価に役立つため、評価・換算差額等を株主資本とは区別
17
評価・換算差額等とその他の包括利益(2)
その他の包括利益(OCI)
2010年公表・2013年改正の企業会計基準第25号 「包括利益の表示に関する会計基準」
「その他の包括利益」(Other Comprehensive Income)とは
包括利益(*)のうち当期純利益に含まれない部分 フロー情報
(*)「包括利益」とは、ある企業の特定期間の財務諸表において認識された純資産の変動額のうち、当該企業の純資産に対する持分所有者との直接的な取引によらない部分
OCIを開示する意義
貸借対照表との連携(純資産と包括利益とのクリーン・サープラス関係)を明示することを通じて、財務諸表の理解可能性と比較可能性を高める
包括利益の表示の導入は、包括利益を企業活動に関する最も重要な指標として位置づけるものではなく、当期純利益と併用することにより、企業活動の成果についての情報の全体的な有用性を高めることを目的とする
18
評価・換算差額等とその他の包括利益(3)
フロー情報とストック情報
19
ストック情報 フロー情報
利益剰余金 ← 親会社株主に帰属する当期純利益
その他の包括利益累計額(AOCI) (=評価・換算差額等) ← その他の包括利益(OCI)
その他有価証券評価差額金 その他有価証券評価差額金
繰延ヘッジ損益 繰延ヘッジ損益
為替換算調整勘定 為替換算調整勘定
退職給付に係る調整累計額 退職給付に係る調整額
<連結B/S>純資産の部 <連結損益及び包括利益計算書> Ⅰ 株主資本
1 資本金 2 資本剰余金 3 利益剰余金 4 自己株式
XXX XXX XXX XXX
売上高 XXX
・・・・ ・・・・ 当期純利益 XXX
株主資本合計 XXX 親会社株主に帰属 XXX Ⅱその他の包括利益累計額
(AOCI) XXX
非支配株主に帰属 XXX
Ⅲ 新株予約権 XXX その他の包括利益 XXX Ⅳ 非支配株主持分(NCI) XXX (OCI)
純資産合計 XXX 包括利益 XXX
20 評価・換算差額等とその他の包括利益(4)
2つのクリーンサープラス関係を示すことができる
親会社株主に帰属する当期純利益と株主資本との間
包括利益と純資産との間
クリーンサープラス関係
ある期間における資本の増減(増資や配当などの資本取引を除く)が、その期間の利益の額と等しくなる関係
(利益の増加を伴わない余剰(surplus)が生じない)
この結果、資本の超過分は利益の累計分と一致し、資本が示される貸借対照表と利益が示される損益計算書との間での連繋(articulation)が保たれる
複式簿記を前提とした試算表の貸借は一致しており、それを単にB/SとP/Lに分解しているため、当然(企業会計上の前提)
閉じた体系になるため、財務諸表の数値に関する信頼性が高められる
企業評価モデルにおける残余利益モデル(RIM)・エンタープライズバリュー(EV)モデルにおいては、将来の利益に関してクリーンサープラス関係が前提
21 評価・換算差額等とその他の包括利益(5)
評価・換算差額等とその他の包括利益(6)
個別財務諸表における取扱い
企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」
当面の間、個別財務諸表には適用しない
包括利益は組替調整(リサイクリング)や利益概念と密接に関係するものであり、IFRS では当期純利益の内容が変質してきている可能性があるので、これらの点を整理することなく、個別財務諸表で包括利益を表示することは時期尚早であるなどの意見
リサイクリングと包括利益
22
リサイクリングする 借)その他有価証券評価
差額金(OCI) 10 貸)有価証券売却益 10
リサイクリングしない 借)その他有価証券評価
差額金(AOCI) 10 貸)利益剰余金 10
AOCIから、当期純利益を通さず、利益剰余金へ直接振り替えれば、ダーティーサープラスとなり、リサイクリングしないことと同じ
⇒リサイクリングの議論と包括利益の表示は、別問題
昭和49年修正前の「企業会計原則」における「当期純利益」
当期業績主義(1会計期間に属する経常的な損益を経営成績とする考え方)
1949年(昭和24年)の設定から、現在の経常利益を「当期純利益」とする当期
業績主義を採用
過年度損益修正項目や臨時的な損益項目は、利益剰余金計算書に計上
当期純利益と当期利益と純損益(1) 23
[損益計算書のイメージ]
(営業損益計算)
売上高 XXX
・・・ ・・・
営業利益 25
(純損益計算)
営業外収益 10
営業外費用 5
当期純利益 30
[利益剰余金計算書のイメージ]
前期未処分利益剰余金 100
前期剰余金処分額 10
前期繰越利益剰余金 90
繰越利益剰余金増減高
前期損益修正損 5
臨時損失 10 15
繰越利益剰余金期末残高 75
当期純利益 30
当期未処分利益剰余金 105
昭和49年修正の「企業会計原則」における「当期純利益」 「企業会計原則の一部修正について」 商法32条2項に「公正ナル会計慣行ヲ斟酌スベシ」を規定
大会社に対する公認会計士監査を実施
「企業会計原則」第二 損益計算書原則 一
当期純利益と当期利益と純損益(2) 24
公正なる会計慣行を要約した「企業会計原則」は、より重要に
改正前 改正後
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするため、一会計期間に発生したすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載し、当期純利益を表示しなければならない
損益計算書は、企業の経営成績を明らかにするために、一会計期間に属するすべての収益とこれに対応するすべての費用とを記載して経常利益を表示し、これに特別損益に属する項目を加減して当期純利益を表示しなければならない
商法に沿って包括主義に移行した(番場(1974))と考えられているが、特別損益は収益・費用に含まれておらず、当期業績主義の考え方を生かそうとしている(中村(1978))という見方もある
(参考) 特別損益の位置づけ 現在は収益・費用 (以前は収益・費用ではない) OCIの位置づけ IFRSでは収益・費用(わが国では収益・費用ではない)
概念フレームワークにおける取扱い IASB (現行および2015年ED)
ASBJ
A(資産)、L(負債) E(資本) クリーンサープラス関係は1つ(利益の一重開示)
I(収益)、E(費用)
(*) その他の包括利益(OCI)は、収益・費用に含まれる
A(資産)、L(負債) Net Assets(純資産)
クリーンサープラス関係は2つ(利益の二重開示)
CI(包括利益)
A(資産)、L(負債)、 OE(株主資本)
R&G(収益)、 E&L(費用)、 NI(純利益)
(資本取引を除く)資産・負債の増減 +投資のリスクからの解放(期待の事実への転化)
25 当期純利益と当期利益と純損益(3)
IASB (IAS第1号) 「包括利益」とは、資本取引以外の取引又は事象
による一期間における資本の変動をいう
「純利益」とは、収益から費用を控除し、OCIを除いたものをいう
「OCI」とは、他のIFRSが要求又は許容するところにより、純利益に認識されない収益及び費用をいう
26 当期純利益と当期利益と純損益(4)
包括利益
OCI 純利益
包括利益
純利益
OCI
ASBJ(企業会計基準第25号、討議資料「財務会計の概念フレームワーク」)
「包括利益」とは、当期の純資産の変動額のうち、資本取引によらない部分をいう。
「当期純利益」とは、特定期間の期末までの純資産の変動額であって、資本取引による部分を除いたうち、その期間中にリスクから解放された投資の成果であって、報告主体の所有者に帰属する部分をいう
「OCI」とは、包括利益のうち、当期純利益及び少数株主損益に含まれない部分をいう
昭和37年改正商法における特定引当金 昭和37年改正の商法第287条ノ2では、利益留保性の特定引当金を規定
特定引当金の繰入・取崩は、商法計算書類規則では、特別損益項目
当期純利益と当期利益と純損益(5) 27
[損益計算書の記載イメージ]
営業収益
売上高 XX
・・・ ・・・
経常利益 100
特別利益
固定資産売却益 5
特別償却準備金取崩額 15 20
特別損失
前期損益修正損 10
価格変動準備金繰入額 20 30
税引前当期利益 90
法人税等負担額 40
当期利益 50
昭和49年修正の「企業会計原則注解」注14 負債性引当金以外の引当金について
当期純利益と当期利益と純損益(6) 28
[損益計算書の記載イメージ]
売上高 XX
・・・ ・・・
経常利益 100
特別利益
固定資産売却益 5
特別損失
前期損益修正損 10
税引前当期純利益 95
特定利益
特別償却準備金取崩額 15
特定損失
価格変動準備金繰入額 20
税引前当期利益 90
法人税等負担額 40
当期利益 50
負債性引当金以外の引当金を計上するこ
とが法令によって認められているときは、当
該引当金の繰入額又は取崩額を税引前当
期純利益の次に特別の科目を設けて記載
し、税引前当期利益を表示する。
この場合には、当期の負担に属する法人
税額、住民税額等を税引前当期利益から
控除して当期利益を表示する。
なお、負債性引当金以外の引当金の残高
については、貸借対照表の負債の部に特
定引当金の部を設けて記載する。
昭和57年修正の「企業会計原則注解」 昭和56年の商法改正により、利益留保性の引当金の計上は排除
昭和57年修正の「企業会計原則注解」では、注14を削除
平成14年改正の商法施行規則 従前の「企業会計原則」上の「当期純利益」は、商法上の「経常利益」に対応
していたため、「当期純利益」という語を用いていなかった(弥永(2003))
平成15年の商法施行規則により、財務諸表等規則との一元化を図る ⇒商法上の長年の慣用語であった「当期利益」を「当期純利益」へ
最近の会計基準等にみられる「純損益」 IAS 第1号「財務諸表の表示」におけるprofit or lossの影響か
(IAS 第1号8項では、意味が明確である限り、合計を示すために「当期純利益」(net income)のような他の用語を使用することができるとしているが・・・)
当期純利益と当期利益と純損益(7) 29
IFRSと国際会計基準(1)
公表物 設定主体
会計基準 解釈指針
IASC(2001年まで) 国際会計基準(IAS)第×号 (*) SIC第×号 (*)
IASB(2001年から) 国際財務報告基準(IFRS)第×号 IFRIC第×号
(*) IASB(国際会計基準審議会)は、2001年の設立時点で、前身のIASC(国際会計基準委員会)の公表物(IAS、SIC))をそのまま採用
IFRS (International Financial Reporting Standards)は、直訳すれば「国際財務報告基準」
⇒しかし、連結財務諸表規則93条や金融庁告示では、「国際会計基準」としている
(なじみやすさから、従来同様、「国際会計基準」と表現しているのではないか)
IFRSは「国際財務報告基準」ではないのか
30
IFRSと国際会計基準(2)
IFRSは財務報告の基準ではないのか
IFRSは、財務報告の基準(FRS:Financial Reporting Standards)であり、会計基準(AS:Accounting Standards)とは異なるのではないか
2010年改正のIASBの概念フレームワークでは、財務報告を対象としているが、それまでは、IASCが1989年に承認した概念フレームワークを採用
2010年改正のIASBの概念フレームワークでは、財務諸表は、財務報告の中心であり、取り上げる論点の多くは財務諸表に関するものとしている
最近のIFRSの開発においても、明らかに「その他の財務報告」にあたるものは、「経営者による説明」(Management Commentary)のプロジェクトのみ
IFRSの性質は、従来と同様の会計基準ではないか
31
財務報告 それ以外の報告 財務諸表
その他の財務報告 本体 注記
Probable(発生の可能性が高い)(1) 32
probable
収益認識基準(IFRS第15号、Topic 606)
ステップ1(契約の識別)における回収可能性
いずれもprobableを使用
⇒コンバージェンスされないかもしれないが、両基準とも従前の収益認識でも要求していたため、それとの継続性を維持
(参考)ASBJの公開草案(2017年7月20日公表)16項(5):可能性が高い
ステップ3(取引価格の算定)における変動対価の見積りの制限
米国基準ではprobable、IFRSではhighly probableを使用 ⇒同じ意味とし、コンバージェンスさせた
(参考)ASBJの公開草案(2017年7月20日公表)51項:可能性が非常に高い
基準 意味
米国基準 発生する可能性が高い(likely to occur) ↑
IFRS 発生する可能性の方が高い(more likely than not) ↑
(参考)2015年12月開催の会計基準アドバイザリー・フォーラム(ASAF)会議におけるAASB/KASBのリサーチ
Probable(発生の可能性が高い)(2) 33
蓋然性の程度を表現する用語 該当するIFRS
Virtually certain
(ほぼ確実)
IAS第37号「引当金、偶発負債及び偶発資産」33項
Substantially all (ほとんどすべて) IFRS第9号「金融商品」B3.2.4項 IFRS第16号「リース」62項
Highly probable (可能性が非常に高い) IFRS第9号6.3.3項 IFRS第15号56項
Reasonably certain (合理的に確実) IAS第17号「リース」4項 IFRS第16号18項、19項
Reasonably assured
(合理的に保証) IAS第20号「政府補助金の会計処理及び政府援助の開示」7項
Probable (可能性が高い) IFRS第5号「売却目的で保有する非流動資産及び非継続事業」付録A IAS第37号23項
Probable(発生の可能性が高い)(3) 34
蓋然性の程度を表現する用語 該当するIFRS
Likely (見込みである) IAS第36号「資産の減損」12項(c) IFRS第9号B3.2.5項
Reasonably possible (合理的に可能性のある) IFRS第9号3.2.8項
Possible (可能性のある) IAS第37号10項
Unlikely (可能性が低い) IAS第37号74項
Highly unlikely (可能性が非常に低い) IFRS第9号B3.2.4項(c)
Extremely unlikely (可能性が極めて低い) IFRS第4号「保険契約」B23項
Remote (可能性がほとんどない) IAS第37号16項(b)
エッセンシャルIFRS[第5版] [中央経済社] 2016年12月刊行
IFRSの基本的な考え方に重点を置き、
その全体像を体系的に解説したテキスト
第1部では、抽象的なIASB概念フレーム
ワークの考え方をわかりやすく解説
第2部では、各IFRSを関連する活動や取
引等の観点から体系的に解説
コラムでは、現在議論されている論点の
本質・盲点などを、著者の豊富な経験を
随所に交えて解説
金融商品(改正IFRS9)や収益認識
(IFRS15)、リース(IFRS第16号)に加え、
概念フレームワークEDについても紹介
IFRSのみならず、企業会計を理解したい
実務家にも有益
35
参考文献 秋葉賢一(2010)「気になる論点(7) 財務報告基準と会計基準-IFRSは会計基準
ではないのか-」『経営財務』No. 2966 (2010年5月17日号)
――――(2013) 「包括利益と当期純利益の調整-IFRSにおけるリサイクリングの意味と意義―」『早稲田商学』434号
――――(2015)「気になる論点(125) ROEの算定-分子の利益と分母の資本の関係-」『経営財務』 No. 3198(2015年2月2日号)
――――(2016)「気になる論点(162) 発行済株式数-自己株式数の控除との関係-」『経営財務』 No. 3264(2016年6月13日号)
熊木純子(2016)「IFRS第0号「用語」 第2回 probable」『企業会計』68巻5号
番場嘉一郎(1974)「損益計算書の本質および区分」『企業会計』26巻11号
中村忠(1978)「損益計算書の任務と構成」『産業経理』38巻4号
西山賢吾(2016)『別冊商事法務 No.413 内部留保の実態調査-主要企業786社を対象に過去17年間の推移-』商事法務
弥永真生(2003)「証券取引法会計と商法会計の調整」『企業会計』55巻6号
36