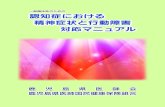認知症クイズ問題編(高学年用) - Chiba University...Title 認知症クイズ問題編(高学年用) Author 千葉市認知症疾患医療センター Created Date
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hirokoku-u/file/5519/...1.認知症ケア・支援に関する課題...
Transcript of 認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究harp.lib.hiroshima-u.ac.jp/hirokoku-u/file/5519/...1.認知症ケア・支援に関する課題...
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
一家族のサービスへの評価とストレス-
The Effective Cornrnunity-based support for Farnily
-Evaluation toward Day Care Service and Stress of Farnily Caregivers -
1.はじめに
1.認知症ケア・支援に関する課題
西村洋子
萎菊花
要介護認定者における認知症高齢者の将来推計 1) では、 2005年現在、何らかの介護・
支援を必要とする認知症である老人(認知症である老人の「自立度E以上J)が 169万人で
あるが、 2025年には 323万人に達すると予測される。また、平成 14年 9月末の要介護(要
支援)認定者は 314万人であり、そのうち認知症である老人の自立度E以上である人は 149
万人(47.4%)である。居宅で介護されている人が 210万人(66.9%)であり、そのうち認知
症である老人の「自立度E以上Jの人が 73万人(34.8%)である。
在宅で認知症の人を介護するということは、家族介護者にとっては、大きな負担であり、
精神的・身体的ストレスとなる。認知症の人は昼夜の生活が逆転したり、攻撃的になった
り、暴力的になることもあるので介護者はストレスがたまり、自分の感情を抑えることが
難しくなり、被介護者に嫌悪感をもち、精神的・身体的虐待を行うことがある。 E.メーリ
ンと R.B.オールセン 2)によれば、約 3'"'-'5%の認知症の人が何らかの形においての虐待
を受けていると推測している。その内容は、身体的に被害を与える虐待、強制的に認知症
の人から金銭を取り上げたり、住宅を遺産として親族に受け渡しをさせたりなどの経済的
虐待、介護を行う人聞が認知症の人に対して屈辱的な言葉の表現を使用したりする精神的
なものなどがあるとしている。日本の高齢者処遇研究会が平成 11年 11月に特別養護老人
ホームにおける虐待問題について調査を行った結果的、虐待の種類別では、心理的虐待が
最も多く、次いで、身体的虐待(うち身体抑制)、ネグレクトの順であった。虐待の被害者の
状況を認知症の有無別でみると、「認知症有り」が 62.9%を示しているとしている。また、
虐待がおきた状況では、「介護行為中」が全体の 71.1%となっているとしている。
家族介護者等による虐待を予防するための対策が必要であり、家族介護者の悩みや不安
83一
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
を解消するための相談・支援体制が強化されなければならない。さらに認知症の人が住み
なれた地域で家族、友人、知人等のなじみの人間関係の中で生活を継続するためには、地
域社会の人びとの認知症に対する理解と近隣の人びと、ボランティア、民間非営利団体等
の見守りのためのネットワーク等により、認知症の人及びその家族を支える地域ケアをす
すめることが必要である。
2. 先行研究の分析
杉山によると、認知症の人の介護について家族が抱えている諸問題は、認知症の症状を
理解することの難しさ、保健・医療・福祉制度等の社会サービスに関する知識の不足、周
囲の理解や支持不足からの孤立感、介護者の生活への制約や社会的・経済的条件等の様々
な問題であるとしている。そして、それらにより、家族の心理的負担も大きく、介護が困
難な状態となると述べている。すなわち、家族介護者の介護負担の状況を示している 4)。
滋賀県立成人病センターにおいて行った実践報告によると、行動障害(問題行動)のある
認知症の人を介護している家族介護者に対して、医師、心理判定員、看護師、ソーシャル
ワーカ一、作業療法士等の様々な専門職員の適切な支援、すなわち、介護指導やカウンセ
リング、社会サービスの紹介等をすることによって、家族介護者が感じる介護ストレスや
負担を軽減させることができるとしている。その結果、認知症の人の行動障害も改善した
事例があったことを明らかにしている 5)。
藤野によると、人間関係をソーシャル・サポートと考え、これが介護上のストレスフル
な出来事(介護ストレッサー)によってもたらされるストレス反応にどのように関係してい
るのかを調べた結果、同居家族、別居親族、友人・福祉医療行政職員の情緒的支援や情報
提供によって、ストレッサーが心理的・身体的ストレスまで至らないケースが多かったと
報告している 6)。
新名らによると、認知症老人の心身の症状(ADL、失禁の程度、痴呆の重症度、コミュ
ニケーション機能)が介護者に引き起こす負担感について検討した結果、家族介護者を心
理的に支える機能を持つソーシャル・サポート(相談の相手がし、ること、家族から情緒的
なサポートを受けていること)が将来の介護についての心配、人間関係の問題及び社会的
サーピスの不足等による負担感を緩衝する効果を持っていると報告している7)。
中谷によると、認知症の人を介護している家族に認知症の症状の特徴や対処方法に関す
る情報を提供することによって、介護知識や技術の欠如を補うことができるとしている。
また、介護者の立場に立ってニーズ予を把握するためにアセスメントをすることが重要であ
ると述べているへ
Joseph E, Gauglerらの研究によると、認、知症の介護の初期にホームヘルフ。サービスなど
の認知症に関する地域密着型長期サービスを利用することで、家族介護者は認知症の人を
ナーシングホームに入所させる時期を遅らせることができると述べ、地域密着型長期サー
ビスの早期利用は、家族介護者の費用効果及び介護ストレスの緩和に影響を及ぼしている
84
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
ことを示しているヘ
3. 本研究のねらい
認知症の人は記憶障害が進行していく一方、自尊感情やプライドは残っていることが多
く、介護者など周囲の人の対応によっては焦燥感や怒りなどを覚える。さらに、生活環境
の変化によって排佃やせん妄など行動障害を引き起こすことが多い。従って、認知症の人
のそれまでの生活や個性を尊重し、生活の継続性と日常の生活圏域を重視したケア・支援
をすることが必要である。また、一人ひとりの症状や進行の状況に応じたケア・支援を工
夫することにより、認知症の人の不安を取り除き、生活の安定を図ることができる。これ
らの認知症の人のケア・支援の基本は、保健・医療・福祉の専門職にとって、重要な課題
であるとともに、家族介護者及び認知症の人とかかわりのある周囲の人びとにも大切こと
である。
本研究では、在宅生活をしている認知症の人を介護している家族介護者の介護負担・介
護ストレスを軽減することにより、認知症の人ができるだけ長く在宅での生活を継続する
ことが可能であると考えた。その際、家族の介護負担、介護ストレスの軽減のためには、
様々な社会的サービスの利用も考えられるが、社会的サービスを提供している専門職員の
ケア・支援のあり方が大きく影響するのではなし、かと考えた。在宅で生活している認知症
の人は、社会的サービスのうち、デイケアやデイサービスを比較的多く利用しているので、
そのサービスに関与している職員の認知症の人及び家族介護者へのケア・支援の状況及び
家族介護のデイケア等社会的サービスの受けとめ方・評価について調査した。更に、家族
介護者のストレスに影響を及ぼす要因について分析した。これらの分析に基づき、家族介
護者へのサポートについて検討した。
1I.研究方法
1.調査対象と調査方法
(1)調査対象
認知症の人に対するデイケア及びデイサーピスを実施している施設の中から、協力の得
られた広島市と東広島市にある病院やクリニックに併設しているデイケア 5ヵ所(E、F、G、
T able 1 Subjects
E day-国間加 A 出 spital
F 曲y-servi田 in A t句S凶回l
G day-care in B Clinic
I由r園田 inC Cltnic
J day-回開加 oClinic
Other
TDtal
Subjects
Careejvers (0) Daycare Center staffs (叫
Distri加陶n Collection D隠 tribution Collection
19 13 7 7
23 11
25 24 15 15
39 10 24 11
23 16 20 7
3
t閣 66 89 57
85
I、J)とデイサービス 1ヵ所(H)に対し
てアンケート調査の協力を依頼した。
調査対象者は、利用者の家族 106人と
職員 89人である。回収されたのは利
用者の家族(家族介護者)66人(回収率
62.3 %)であり、すべてが有効回答で
あった。職員から回収されたのは 57
人(回収率 64.0%)であり、有効回答は
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
55人であった。
(2)調査方法
デイケア及びデイサービスを実施している施設の責任者に調査票を届け、協力の得られ
た家族介護者と職員に配布してもらい、各自記入してもらった。なお、認知症の人の基本
属性については、家族介護者に記入してもらった。
回収に際しては、家族介護者は各自回答した調査票を大学宛に郵送してもらった。また、
職員には、回答した調査票を封筒に入れ、封をして施設の責任者へ提出してもらった。な
お、この調査を行うに際しては、事前に家族介護者 1名と認知症の人のケアの経験のある 2
名にアンケートを記入してもらい、問題点を指摘してもらった。その結果に基づき、再検
討したものを今回の調査に用いた。回答者の個人情報保護の観点から個人のプライバシー
にかかわる情報については十分注意して取り扱うことを約束した。調査の期間は 2005年 7
月から 8月の 2か月間であった。
「痴呆性老人の日常生活自立度j については、平成 17年 8月末に出版された「国民の
福祉の動向 2005J において「認知症である老人の日常生活自立度(以後、認知症老人の
自立度と略す)Jと変更されたが、本研究においてアンケート調査の実施に当たっては「痴
呆性老人の日常生活自立度」を用いた。
2.調査の内容
次の(1)~ (3)の調査を行った。
(1)認知症の人に関する調査
認知症の人の基本属性、要介護度、認知症老人の自立度及び障害老人の日常生活自立度
(以後、障害老人の自立度と略す)、加入している保険等に関するものである。
(2)家族介護者に関する調査
家族介護者の基本属性、健康状態(自己評価)、認知症の理解(知識)と介護方法の工夫、
家族が認知症にかかったときの対応(相談相手、相談機関等)、医療機関の利用状況や医療
関係者からの支援状況、介護ストレッサーと心理的及び身体的ストレス 5) 10) 11)、社会的サ
ービスの利用と満足感、デイケアやデイサービスの職員からの支援内容等に関するのであ
る。
(3)職員に関する調査
職員の基本属性、健康状態(自己評価)、認知症の理解(知識)、アセスメントの内容、家
族介護者への支援、職員が実施したサービス及びケア、受診したときの支援、デイケア及
びデイサービスの利用時の対応など、認知症の人及び家族介護者への支援状況等に関する
ものである。
(4)介護ストレッサ一、心理的ストレス及び身体的ストレス尺度について
介護者が経験している様々なストレスの原因を客観的に評価するため、新名の作成した
介護ストレッサー尺度目)11)を修正した 18項目からなるスケールを用いた 5)。身体ストレ
-86
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年3月
ス症状は、身体的ストレス反応尺度(24項目版)10) 11)を 18項目に縮小したものを用いて測
定した 5)。
3. 分析方法
回収された調査票について、認知症の人(本人)、家族介護者、職員別に集計した。介護
ストレッサー、心理的ストレス、身体的ストレスについては点数化(1項目を 1点とした、 18
点満点)して、低いグ、ルーフ。(1点"-'4点)、中間グループ。(5点"-'8点)、高いグ、ルーフ。(9
点"-'18点)の 3分類した。点数が高いほどストレスの程度が強いことを意味している。
認知症に関する知識(理解)については、点数化(1項目を l点とした、 10点満点)して、
低いグループ(1点"-'3点)、中間グ、ループ(4点"-'7点)、高いグループ。(8点"-'1 0点)の 3
分類した。点数が高いほど認知症に関する知識があることを意味している。
家族介護者の介護ストレッサー、心理的ストレス及び身体的ストレスに影響を及ぼす要
因及びデイケアとデイサービスの利用時の満足に影響を及ぼす要因の分析に当たっては、
数量化 2類を用いて多変量解析を行った。また、点数化した介護ストレッサ一、心理的ス
トレス及び身体的ストレス、認知症に関する知識、アセスメントについては、平均値の差
の検定(t検定)を行った。これらの統計解析には EXCEL太閤 Ver.4.0のソフトを用いた。
III. 結果
1.基本属性
(1)認知症の人(本人)の基本属性(デイケア、デイサーどス利用者)
性別は「男性J24人(36.9%)、「女性J41人(63.1%)であり、女性が 6割以上を占めた。
Teble 2 Baseline Characteristics of Caregivers and Carere口問ents
V.r祖国e
c.陪陪d回en恒Ge間島r
D国 a担
Ma恒
Fe ... 也
Alzheimer Brain ce.-ebrovascular disease
Mean Age
Rank of the frail (8iggest Per田 ntage)
Dem宮武ia rank 日iuestpe rcentage) Frail rank (Blggest Pef"Centage)
Caregivers
G宮 司daer
Age
Male
Fema胎
40-49 50-59 60-69
R剖 ation ship to回 目 陪d匝entsSpou
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
人(7.6%)、「要支援J3人(4.5%)の順である。
認知症老人の自立度では、 rIIIJ23人(34.9%)が最も多く、次いで rIVJ21人(31.8%)、
r II J 18人(27.3%)、 rMJ、r1 Jの順となっている。認知症老人の自立度の II-----IVにつ
いて要介護度との関係をみると、 Eは要介護 1'"'-'3、Eは要介護 2'"'-'3、IVは要介護 3'"'-'4
に比較的多く分布している。各ランク(II'"'-' IV)とも要介護 2'"'-'3ランクに分布している。
認知症老人の自立度と要介護度の関係は Spearmanの順位相関係数r=0.99であり、有意性
(pく0.00を認めた。
T able 3 Relations between Rank of the Frail and Dementia Rank
ぶ?Aid 1 2 3 4 5 Total
n n n n n n n
ー
I 。 。 1 。 o o 1 L6 E 1 6 4 5 1 o 17 26.6
E 2 2 自 自 2 。 23 35.9 N 。 2 2 7 日 2 21 32.8 M o 。 o o 。 2 2 3.1
Total (‘〉 3 (4.7) 10 (15.6) 15
-
広島国際大学医療福祉学科紀要 第4号 2008年 3月
り、全体の 75.4%に値する。仕事の有無については「してなしリが 39人(59.1%)であっ
た。
最終学歴については、「高等学校卒(高卒)Jが 37人(57.8%)と最も多く、次いで、「中
学校卒(中卒)J 11人(17.2%)、「短期大学卒(短大卒)J7人00.9%)、「大学卒(大卒)J 9
人(14.1%)であった。健康状態については、「非常によしリ 3人(4.7%)、「まあまあよしリ 7
人(10.9%)、「普通Jが 30人(46.9%)、「悪しりと思っている介護者が 24人07.5%)であ
った。認知症の人を介護した期間は、 15年未満」が 39人(60.1%)で最も多く、 15年以上
'"'"'10年未満Jが 22人(33.8%)、 110年以上」が 4人(6.1%)であった。認知症の人への
介護の協力については、協力者が「し、るJと答えた人が 46人(70.8%)であった。その続
柄は、「配偶者」が 18人09.2%)で最も多く、次いで、「娘」、「兄弟」、「嫁J、「息子」の
順であった。
(3)職員の基本属性
性別については「男性J14人(25.5%)、「女性J41人(74.5%)である。年齢別にみると
120歳代J26人(47.3%)で最も多く、次いで 130歳代J12人(21.8%)、140歳代JlO人
(18.2 %)、 150歳代J7人(12.7%)であった。
職員の専門を職種別にみると、「介護職員J20人(36.4%)で最も多く、次いでは、「看護
師J15人(27.3%)、「介護福祉士J9人(16.4%)、「精神保健福祉士(PSW)J 6人(10.9%)、
「作業療法士J3人(5.5%)、「社会福祉士J2人0.6%)であった。
認知症のケアに従事してきた期間(以後、「ケア期間」とする)別にみると、 11年以上'"'"'3
年未満」が 20人(36.4%)で最も多く、次いで、 16年以上'"'"'10年未満J13人(23.6%)、 13
年以上'"'"'6年未満J12人(21.8%)、 11年未満Jと 110年以上」が各 5人(9.1%)であっ
た。健康状態、は「非常に良い」と「まあまあ良しリ 18人(32.7%)、「普通J28人(50.9%)、
「少し悪し、J9人06.1%)であり、「非常に良しリ、「まあまあ良しリ、「普通Jの状態のも
のが 92.7%であった。
2.認知症及び認知症の人へのケアについての家族介護者の理解の状況と対応
(1)認知症についての理解
家族介護者が最初に認知症と気づいた症状は、「同じことを何回も言ったり、聞いたり
するj が 42人(64.6%)、「置忘れやしまい忘れが目立ったj が 39人(60.0%)であり、両
項目とも、約 60%以上の家族介護者が気づいていたが、「期間や場所の感覚が不確かにな
った」、「病院からもらった薬の管理ができなしリ、「以前はあった関心や興味が失われた」、
「物の名前が出てこなくなった」等に気づいたものは約 40%で、あった。認知症の症状は
人によって違う症状が出る場合があるため、認知症について様々な症状が見られるという
ことを理解していないと、認知症の症状について気づくことができない。
家族介護者の認知症についての知識について調べたところ、「経験したすべてを忘れるJ
が 41人(68.3%)、「病気やケガ等によって進行速度は影響を受けるJ31人(51.7%)、「感
89
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
情の残像があるJ30人 (50.0%)、「記憶の逆行性喪失があるJ28人(46.7%)については約
半分以上の家族介護者が理解していた。その他についての理解は約 40%以下であった。
(Table 4)
認知症に関する知識を点数でみると、家族介護者の続柄間で平均点を比較した結果、「配
偶者J5.2 ::t 1.7点と「嫁J6.6 ::t 1.7点であり、両者間に統計的に有意差(p
-
広島国際大学医療福祉学科紀要 第4号 2008年 3月
次いで「精神科病院の医師J11人(21.2%)であった。「医師Jに相談したのが 52人(6l.9
%)で最も多く、次いで「ソーシャルワーカーJ15人07.9%)であった。ソーシヤルワー
カーは「一般病院」と「在宅介護支援センター」が多かった。一方、「相談・受診しなか
った」と答えた人の理由は「認知症とは思わなかった」と答えたのが 3人 (27.3%)、「年
のせいなので気にすることはないと思った」と「認知症についてよく知らなかった」と答
えたのが各 2人08.2%)で、あった。これは、認知症に関する理解がなかったためであると
考えられる。
医療機関受診の有無については、「受診したJ56人(87.5.(5))、「受診してなし、J8人02.5
%)であり、約 90%の者が受診していた。受診にいたるまでの時間については、 11年未
満」と答えた人が 44人(78.6%)、12年未満J6人(10.7%)、 12年以上J4人(7.1%)の順
であり、 1年経過するまでに約 80%の者が受診していた。
医療機関では、「訪問看護やデイケアの利用j について 81.1%が説明を受けているが、
「病気や症状への対応Jについては 50.9%と減少しており、さらに、「利用できる保健・
福祉サービスの紹介」については 34.0%と減少している O
(3)社会サービスの利用状況と満足感
社会サービスの利用状況をみると、最も多かったのは「デイケアJ52人(80.0%)であ
り、以下、「デイサービスJ39人(60.0%)、「ホームヘルフ。サービスJ20人(30.8%)、「精
神科病院JlO人(15.4%)で、あった。利用している社会的サービスのうち、満足している
のは、「デイケアJ44人(84.6%)、「デイサービスJ27人(69.2%)、「ホームヘルプサービ
スJ8人(40.0%)、「精神科病院J6人(60.0%)の順であった。以上のことから、「デイケ
アJの利用者が一番多く、また、満足していることがわかった。
(4)介護(ケア)の工夫
認知症の人が心地よく、安心して過ごせるようにするために、家族介護者が認知症の人
の過ごし方について工夫しているかを尋ねたところ、「工夫した」と答えたのが 49人
(76.7%)であり、その具体的な内容は、「清掃」が 44人(91.4%)で最も多く、次いで、「娯
楽J26人(54.2%)、「子供や動物の面倒をみてもらう JlO人(20.8%)の順となっていた。
その工夫による変化(効果)については「変化あり」が 32人(72.3%)、「変化なし」が 10
人(27.7%)であった。工夫した内容について家族介護者自身が考えたことは、認知症の人
が「元気な時家事をやっていたJ13人(36.1%)で最も多く、次いで、、「元気な時の趣味で
あったJll人(30.6%)であった。
家族介護者が、認知症の人が利用している施設の家族会及び催しへの参加・利用してい
たのは 54人(83.3%)であった。 8割以上の家族介護者がデイケア及びデイサーピスの家
族会や催しに参加しているが、ここでは「介護の工夫人「家族会への参加」、「ストレス解
消方の指導」等への支援を受けたものはいなかった。
3. 職員の認知症に関する理解と家族介護者への対応
91
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
(1)認知症についての理解(知識)
認知症についての理解(知識)を家族介護者に用いた質問 (Table4) と同じものを用いた。
認知症に関して正しく理解していたのは、「病気やケガ等によって進行速度は影響を受
けるJ35人(81.4%)、「行動障害には理由があるJ32人(74.4%)、「経験したすべてを忘
れるJ31人(72.1%)であった。「話をくり返すJ7人(16.3%)、「老化の速度には違いがあ
るJ6人(14.0%)であった。このことは家族介護者のみならず、認知症の人の支援やケア
に従事している職員も認知症に関して、更に正しい理解がなされることが必要である。認
知症に関しての理解を点数で家族介護者と職員を比較すると、家族介護者の平均点が 5.4
::t 2.4点、職員の平均点が 7.2::t 1.6点で、あった。職員の方が有意(pく0.00によく理解して
いることがわかった。
(3)職員の家族介護者への支援
デイケア及びデイサービスを提供している職員が家族介護者へ「支援している」が 38
人(73.1%)である。具体的な支援内容としては「行動障害やその対応の仕方を指導する」
が 18人(47.4%)で最も多く、次いで「在宅での介護で気をつけることを指導する」が 17
人(44.7%)、「認知症についてわかりやすく説明する」が 16人(42.1%)の順になっていた。
しかしながら「家族会への参加J7人(18.4%)、「ストレス解消方法の指導J5人(13.2%)
等についての支援は不十分であることがわかった。
Table 5 Staff given Services and Caregiver cognition to Services (Day care service)
Caregiver cognition Staff given service
Item to services
n % n %
1. A.sking symptom & situation. 28 45.2 2B 11.B
2. A.sking & advising difficulty of caring. 44 11.0 21 69.2
3. Keeping communication by the note. 55 BB.1 30 16.9
4. Evaluating caregiver menntal stress & . advising m巴thodof elimination
22 35.5 15 38.5
5. Evaluating caregiver burden & elimination. 21 33.9 19 4B.1
6. Researching their health condition & . advising to caregive r.
33 53.2 16 41.0
T口tal 62 39
Note; Multiple Answer
92
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
デイケア及びデイサービス利用者の家族介護者が職員から受けたと認識しているサービ
スの内容と職員が家族介護者へ実施したとするサービスの内容を比較した結果は、 Table5
のとおりである。「介護で困っていることを尋ね、相談にのる」、「デイケア及びデイサー
ビスでのことを連絡帳で知らせるJは職員の約 70%以上が実施しており、家族介護者も
約 70~ 80 %がそのサービスを受けたとしている O
「認知症の人の症状・状況を尋ねるJについては職員の 71.8%が実施したとしている
が、家族介護者は 45.2%しか認識していないので、このことについて十分理解している
とはいえない。その他「家族の精神的負担j、「介護負担」、「健康状態」については、職員
の約 40%しか対応していないことがわかった。
(4)過ごし方の工夫
認知症の人の生活について職員が「過ごし方の工夫をしている」と答えた者が 49人(92.5
%)であり、その工夫の内容としては、「音楽療法」が 35人(71.4%)で最も多く、次いで、
「園芸療法」が 26人(53.1%)、「グループワーク」が 20人(40.8%)の順であった。これ
らについて家族介護者が受けたと理解しているのは、「音楽療法J19人(32,8%)、「回想
法J13人(22.4%)、「園芸療法J8人(l3.8%)で、あった。このことから、職員は認知症の
人に対し、いろいろケアしているのにもかかわらず、家族介護者は、認知症の人が受けた
ケアとして理解しているものはわずかで、あった。それは医療機関及びデイケアで実施され
ているサービスの内容について職員が家族に十分知らせていないか、家族に関心がなかっ
たためかと推測される。過ごし方の工夫として主なものは「音楽療法」と「園芸療法」が
あったが、各利用者のニーズ、に基づ、き、様々な種類のサービスが実施されることが望まし
し、。
(5)職員によるアセスメント
認知症の人をアセスメントするとき、よく行われている項目は、認知症の人の「生活歴J
が 47人(92.2%)、「健康状態」が 46人(90.2%)、「既往歴Jが 45人(88.2%)の順であっ
た。しかしながら、「家族の認知症に関する知識の把握J24人(47.1%)、「協力者・相談
相手の有無の確認J24人(47.1%)、「介護するまでの主介護者と要介護者との関係J23人
(45.1 %)、「主介護者の決定権J21人(41.2%)であり、家族介護者、協力者等、利用者の
生活環境に関することのアセスメントが比較的軽視されている傾向がみられる。
4. 家族介護者の介護ストレッサーとストレス
(1)家族介護者の介護ストレッサー
①介護ストレッサ一
介護者が介護に当たって感じた介護ストレッサーとして、多かったものを 5つあげると、
「介護のために夜中に起きたことがある。 J36人(58.1%)、印、つもより神経を使うこと
があったJ35人(56.5%)、「やることがたくさんあって時間に追われたJ27人(43.5%)、
93
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
「どうしたらいいかわからなしリ 24人(38.7%)、「要介護者にどう対応したらいし、か迷う
Table 6 High Percentage Item of the Storessor and
Mean point
No Category %
1 Caring at midnight 58.1
2 More often g旦ttingne rvo us than usual 56.5
3 Being busy as a bee 43.5
4 Losing the way of Garing 3B.7
5 Getting lose hロw to GontaGt the GarereGipient 37.1
ことがあった1
23人(37.1%)
の順で、あった。
介護ストレツ
サーの得点に
ついて全体の
平均点をみる
Note; Mean Storessor's point
(Highest po int 1 B)
4.5士3-2 と、 4.5土 3.2
点であった C
平均点で統計的に有意義(p< 0.05)の認められたのは次の項目であった。介護期間のほ
年未満J(5.4::!:: 3.5 点)と r5 年以上~ 10年未満J(3.4士 2.6点)の問、健康状態の「普通」
(3.3 ::!:: 2.6点)と「少し悪しけ (5.7::!:: 3.4点)の間であった。要介護度については「要介護 lJ
(3.5 ::!:: 2.1点)と「要介護 3J (6.4土 3.3点)、「要介護 3J (6.4土 3.3点)と「要介護 5J (3.8
::!:: l.5)の問、認知症老人の自立度 rIIJ (6.1士 4.6点)と rMJ (3.5士 0.7点)、 rIVJ (6.0
土3.0点)と rMJ (3.5土0.7点)の聞に有意差があった。
以上のことから、介護期間 r5年未満」、健康状態「少し悪し、」、要介護度について「要
介護 3J、認知症老人の自立度 rII J、「皿」が家族介護者の介護ストレッサーを高めてい
ることがわかった。
②家族介護者の介護ストレッサーに影響を及ぼす要因(数量化 2類による解析)
数量化 2類の解析により「カテゴリースコア」が算出され、この「カテゴリースコア」
により影響を及ぼす要因の大きさと方向を知ることができる。カテゴリースコアがプラス
の方向に大きいカテゴリーを属性とする者は介護ストレッサーの点数が高いことを意味す
る。また、カテゴリースコアの絶対値を加算したものが「レンジJである。レンジの大き
いものほど偏相関比は大きくなる。偏相関比より偏相関検定がなされ統計的に有意差の有
無を確認する。
この度の目的変数には 3つのカテゴリーを用いているので、数量化 2類の解析結果、
l軸と 2軸の結果が示された。 1軸、 2軸それぞれの相関比(0.8~ l.0 :分析精度が非常に
良い、 0.5~ 0.8 :分析精度がやや良い、 0.5未満.分析精度が良くなし、)により、解析結果
の精度が決まる。
家族介護者の介護ストレッサーに影響を及ぼす要因について数量化 2類による分析結果
を Table7、Fig.1に示した。
目的変数には、介護ストレッサーの点数を 3 ランク、すなわち、低いグルーフ。は 1~4
点、中間グループは 5~8 点、高いグルーフ。は 9 ~ 18点を用いた。
説明変数には、「性別j、「仕事」、「健康状態」、「協力者の有無」、「介護期間」、「過ごし
-94
-
広島国際大学医療福祉学科紀要 第4号 2008年3月
方の工夫人「要介護度j、「認知症である老人の自立度」、「認知症に関する知識」を用いた。
各項目カテゴリーは Table7に示した通りである O なお、 l軸の相関比は 0.5390、2軸の
Table7 Number of Subjects by Categories and Category Score 相関比は 0.2998 であ
(Caregiverピs Storessors)
Fact口ritem CateJ!O刊 n CateJ!Orv Sc日 陪 (1stem)
Gender Male 13 -0.2578
Female 41 0.0818
Work Yes 25 0.1059
No 29 -0.0913
Perceived Health Very good 2 1.2923
G日日d 6 -0.7137
Standar叫 24 0.1353
8ad 17 0.0415
Wo陪 t 5 -0.4512
Co日開rator Yes 38 一0.0593No 16 0.1409
Period of ca陪 く 5Yea陪 33 一0.41535;:;;;~
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
Fig 1 Relationship胎tweenstoressors and Gen必r.Work. Perceived Health. Coo問問tor.Period of田 re.Device of Life. Fミankof the Frail. Dementia of Rank. Knowledge of Dementia (Category Score)and Partial Correlation
Gender Male Fe何回Ie
柚釦rk Yes 陥
Perceived Very good
Health Good Standard
Bad 柚曲目t
Cooperator Yes No
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
5.5 :::t 3.9点であった。
心理的ストレスの平均点で統計的に有意差(pく0.00が認められたのは、介護期間の r5
年未満J(6.9:::t 4.5点)と 15年以上'"10年未満J(3.7士 2.1点)、 15年未満J(6.9:::t 4.5
点)と IlO年以上J(2.7:::t 1.2点)の間であった。 (Tab1e8)
また、統計的に有意差 pく0.05が認められたのは、健康状態の「非常に良しリ (3.7:::t 1.5
点)と「少し悪いJ(7.0土 5.0点)、「普通J(4.1:::t 2.8点)と「少し悪いJ(7.0:::t 5.0点)の
間であり、要介護度については「要介護 3J (6.0:::t 4.4点)と「要介護 5J (2.8:::t 1.5点)、
「要介護 4J (5.3土 2.9点)と「要介護 5J (2.8:::t 1.5点)の問、認知症老人の自立度 IIIJ
(7.2 :::t 4.8点)と IMJ 0.5:::t 0.7点)、 lillJ (5.9:::t 3.8点)と IMJ 0.5:::t 0.7点)、 IWJ
(6.8 :::t 4.0点)と IMJ 0.5:::t 0.7点)の問で有意差が認められた。
以上のことから、介護期間 15年未満」、健康状態「少し悪しリ、要介護度について 13J、
14J、認知症老人の自立度 111J、「皿」、 IWJが家族介護者の心理的ストレスを高めてい
ることがわかった。
②家族介護者の心理的ストレスに影響を及ぼす要因(数量化 2類による解析)
家族介護者の心理的ストレスに影響を及ぼす要因について数量化 2類による解析結果を
Tab1e9、Fig.2に示した。
目的変数には、心理的ストレスの点数を 3ランク、すなわち、低いグ、ルーフ。は 1"'4点、
Table9 Number of Subiects Categories and Category Score
(Caregiver's Mental Stress)
Factor item Cate20rv r司 CateJ!Orv S回 re(1stem)
Gender Ma胎 12 0.2085 Female 41 0.0610
柄拘Drk Yes 24 。今E両日9
No 29 -0今0570
Perceived Health Very good 2 0.1579 Good 6 O.()(沼5
Standard 24 0.1115
Bad 16 0.0791
納h日目t 5 -0.3556
G日日開聖目tロ『 Yes 37 0.0149
No 16 -0.0345 Period of回 開 く 5Yea問 32 0.4201
5孟-
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
Fig. 2 Relationship between Mental Stress and Gender.Work.Perceived Health.
Coo回目tor.periodof care.Device of Life.Rank of the Frail.Dementia of Rank. Knowledge of Dementia (Category Score) and Partial Correlation
Gender Male Female
Work Yes
No Perceived Very good Health Good
Standard
Sad 納品目t
Coo匝 悶tor Yes
No Period of care < 5Yea目
5 豆 ~
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
Tablel0 High Percentage Item of The Physical Stress 身体的ストレスの平
and Mean凹 int 均点でが0.01で統計的
No Category
1 Fee ing languid
2 Having a stomachache and lum国 go
3 Sleeplessness
4 Eyestrain
4 Joleing heavily tired
N日te; Mean Physical Storess四 int2.5士2.5
(Highest point 18)
%
48
40
38
36
24
に有意差が認められた
のは介護期間の 15年
未満J(3.0::t 2.9点)と
110年以上J (0.7土 0.6
点)の間であり、健康
状態の「非常に良いj
(0.7 ::t 0.6点)と「少し悪しリ (3.5::t 2.7点)、「まあまあ良しり (0.9土 0.9点)と「少し悪
しリ(3.5 士 2.7点)の間で、あった。また、 p
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
ごし方の工夫」、「要介護度」、「認知症に関する知識jである。なお、 l軸の相関比は 0.5332、2
軸の相関比は 0.4598であったので、 l軸により要因を把握した。偏相関係数が大きく、偏
相関検定で、有意水準が pく0.01であった項目について、偏相関係数の大きい順にみると、 1
位・「要介護度」、 2位・「健康状態」であった、これらの項目についてカテゴリ一間の関
係をカテゴリースコアでみると次の通りである。
F唱.3 Relationship between Physical Stress and Gender.Work.Perceived Health. Coo回目tor.Periodof care.Device of Life. Rank of the FraiUくnowledgeof
Dementia (Categ口 町 Score)andPartial Correlation
Ger岨er
納品rk
Percei四 dHealth
Cooperator
Period of ca
Oevice of U
Rank of the Frail
Knowledge 0 Dementia
Male Female
Yes No
Very good Good
Standard Bad
V場。目t
Yes No
-
広島国際大学医療福祉学科紀要 第4号 2008年 3月
った。これらの項目についてカテゴリ一間の関係をカテゴリースコアでみると次の通りで
ある。
介護者の「健康状態」については、「少し悪し、」より「普通Jさらに「まあまあ良いj
の方が、医療機関及びデイケアで受けたケアのなか、「介護方法の指導Jを「受けなかっ
た」より「受けた」の方が、家族介護者のデイケアへの満足を高める要因であることがわ
かった。
(2)デイサービス利用者家族の満足に影響を及ぼす要因
目的変数には、デイサービスの利用に「満足するj と「満足しなしリの 2つのカテゴリ
ーを用いた。説明変数には「性別j、「仕事J、「健康状態」、「協力者J、「介護期間」、「医療
機関及びデイケアで受けたケア」を用いての解析(解析I)と「医療機関及びデイケアで桁
ケア」を「医療機関及びデイケア利用時の職員からの対応」に変更した解析(解析II)を実
施した。
数量化 2類により解析した結果、解析 Iの相関比は 0.4849であり、解析Eの相関比は
0.6208であったので、解析Eについて検討した。偏相関係数が大きく、偏相関検定で有意
水準が p
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
イケア・デイサービスで受けているケアのことを知ることが必要であり、それを考慮、して
継続できるような介護を在宅で行うことが望ましい。
(2)家族介護者の介護ストレッサーとストレス
介護ストレッサー、心理的・身体的ストレスにおいては、認知症の人の「要介護度」が
高く、また、認知症老人の「自立度」が低いほど介護ストレッサー、心理的・身体的スト
レスを強く感じる傾向がみられた。これは今回の調査でも明らかになったように、認知症
の人は比較的身体面で自立しているため、様々な行動障害をおこす可能性があるので家族
介護者にはそれがストレッサーとなっていると考えられる。一方、認知症老人の自立度の
判定が rMJになると身体面の衰えが生じてきて、寝たきり状態になる老人が多いため、
行動障害などをおこす可能性が低いので、家族介護者の介護ストレッサ一、心理的・身体
的ストレスとはなりにくい。
介護経験の r5年未満」の人は介護ストレッサ一、心理的・身体的ストレスを強く感じ
る傾向がみられた。それは認知症の人に対する介護経験がなく、ケアへの不安が原因とな
っていると考えられる。また、家族介護者における認知症及び認知症の人に対する理解と
知識がないことも原因になっているのではなし、かと考えられる。
(3)家族介護者のデイケア、デイサービスに関する評価
認知症の人が利用している社会的サービスのうち、デイケア及びデイサービスが比較的
に多かったので、それらのサービスに対して「満足」している場合について、その要因を
多変量解析により分析を行った。
その結果、デイケア利用者家族の満足を高める要因は、医療機関及びデイケアの関係者
から「介護方法の指導を受けた」ということ、家族介護者の健康状態が「普通」、「少し良
しリ場合であった。デイケアに関しては、サービス提供側の要因と家族介護者側の要因が
提示されており、両方の要因が満足感に影響している。デイサービスについては、家族介
護者の健康状態「少し悪しリ場合と介護者が「娘」、「息子j である場合、満足に影響を及
ぼす要因として提示されているが、これらはすべて家族介護者側の要因である。サービス
提供側の要因はみられなかった。
「満足」に影響を及ぼす要因については、サービス提供側の要因が比較的少なかった。
また、家族介護者の健康状態のカテゴリーに関してはデイケアとデイサービスでは異なる
結果となっており、この点に関してはさらに、今後継続して研究していく必要があると考
える。
2. 職員の家族介護者への支援に関する課題
(I)認知症に関する理解については、職員の平均点は 7.2::!:: 1.6点であり、家族介護は 5.4
::!:: 2.4点で、あった。職員の認知症についての知識については、 10項目のうち 5項目は約 60
%以上のものが正解であったが、残り 5項目は約 30'"10%の正解で、あった。このことか
ら、まず職員が認知症及びそのケアについての理解を深めると共に、家族介護者の理解を
102
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
深めるための指導・教育をしていくことが必要で、ある。特に、「認知症に関する理解(知識)
のなし、」ことが家族介護者のストレッサー及び心理的ストレスを高める要因になっていた
ので、家族介護者が認知症及びそのケアについて適切な理解をもっていることが重要で、あ
る。
(2)職員の家族介護者への支援を内容別にみると、「ストレス解消方法の指導」と「家族会
への参加j の項目については、職員の十分な支援や情報提供がなされているとはいえない
ので、家族への支援について理解し、家族介護者が感じるストレスを客観的に測定し、そ
のうえ、各自に合った「ストレス解消方法の指導Jを行うこと、また、「家族会への参加j
を進めていくことが望ましいと思われる。このことにより、家族介護者が感じる介護スト
レッサー及び心理的・身体的ストレスの軽減につながるのではなし、かと考える。
デイケア及びデイサービスの利用時の家族介護者が職員から受けたサービスの内容と職
員が家族介護者へ実施したサービスを比較した結果、「認知症の人の症状・状況を尋ねるj
ことについては、職員の 71.8%が実施したとしているが、家族介護者は約 50%しか認識
していない。このことを聞かれているということを家族介護者が十分理解しているとはい
えない。連絡帳によりデイケア・デイサービスでの認知症の人のことについて情報の交換
がなされていることについては、両者とも約 70%が認識しており、連絡帳は両者間での
情報交換の役割を責している。記載内容について家族介護者が十分理解していることが望
ましいが、実際はどうなのか不明である。十分理解できていたら、家族は、その内容を参
考にして家族の介護に役立てていくことが可能である。その他「家族の精神的負担」及び
「介護者の健康状態」については、職員の約 40%しか対応していないことがわかった。
利用者を送迎するときだけ、家族に接して会話がかわされるので、時間が十分あるとはい
えない。このような時間以外で、専門職による家族介護者への相談助言がなされることが
必要である。家族介護者の「介護負担」、「精神的負担」、「介護者の健康状態」について支
援がなされていれば、家族介護者の負担は軽減できるのではなし、かと考えられる。しかし
ながら、デイケア及びデイサービスの業務内容等の状況からして、それらを職員だけに期
待するのは無理があるので、訪問看護師や市町村保健センタ一保健師等、他機関の専門職
種の協力が必要となる。また、在宅認知症高齢者のケアに関係のある主治医、訪問看護師、
保健師、リハビリテーションセラピスト、ソーシヤルワーカ一、ホームヘルパー及びケア
マネジャー等によるチームケア及びネットワークが推進されることが必要で、ある lヘM. DuijnsteeとW.Rosによると、家族介護者の介護負担を専門職により軽減すること
の必要性を述べており、オランダにおいては保健師が家庭訪問して実施している 13)。
認知症の人が自分のライフスタイルを維持できることが必要であり、そのためには認知
症の人をできるだけ在宅(地域)でケアしていく体制を整えることが必要である。イギリス
では、訪問看護師によるサービスも存在するが、ホームヘルパーによる家事支援サービス
等だけでなく、認知症の人のニーズ、からして対人援助等のサービスの提供もできるように
ηo nu
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
してし、かなくてはならないとしている。そのためには、ホームヘルパーに対して認知症ケ
アに関する教育とサービス時間の改善をしてし、かなくてはならないと主張しているは)。日
本においても、在宅で介護保険サービスを利用している高齢者の 34.8%が認知症のある
老人(自立度E以上)であるので、訪問介護(ホームヘルプ)に当たるホームヘルパーに対し
ても認知症ケアに関する専門的教育が必要であると考えられる。
家族介護者の認知症の介護負担や介護ストレスを軽減するためには、介護方法に関し専
門職員が、具体的にアドバイスすることが必要であり、その際、家族介護者の介護ストレ
ッサー、心理的・身体的ストレスの程度を客観的に把握した上で行うカウンセリングは、
その効果を高めることができるとしている 5)。
有効な介護指導及び介護負担への助言、カウンセリングなどが得られる社会資源の一つ
は「認知症の人をかかえる家族の会jであると考えられ、介護指導及び介護負担への助言、
カウンセリングなどは専門職が行うよりは、同じような境遇にある介護者あるいは介護経
験のあるボランティアが行う方が有効な場合もあり、専門職よりも共感にもとづくよい指
導が可能である。介護者同士の相互援助を促すためには、家族会をつくることが有効であ
ることはよく知られているが、なかなか実行ができないのは介護に追われ、多忙の毎日を
送っている介護者がわざわざ家族会で出席することは困難であるためである。比較的可能
性があるのは、通所リハビリ、デイサービスへの参加の際、同じような境遇の介護者たち
がクリニック、デイケアやデイサービスの施設で会い、そこに介護者たちが話し合える場
所が提供されれば、職員が勉強会などを支援することで、自然発生的に家族会が結成され
ることもある。いわゆる「ついで、の家族会」である。このような家族会からスタートさせ
ることも社会的サポートとして必要である。
職員は、家族介護者間で有効な介護指導及び介護負担への助言、また、カウンセリング
などが行われるように指導すると同時に、家族会に関する情報を提供することも必要であ
る。また、家族介護者がどのようなことで悩んでいるかについて相談を通じて把握し、迅
速に相談にのれる体制を整備しておくことは重要であり、これが可能であれば、家族介護
者にとって心強いことであり、心の支えになることにつながると考えられる。
デイケア及びデイサービスにかかわっている職員は、認知症の人をアセスメントする際、
「主介護者の決定権」、「主介護者と要介護者との関係」、「家族の認知症に関する知識の把
握」、「協力者・相談相手の有無の確認」等については比較的軽視されている結果がみられ
た。すなわち、認知症の人(利用者)に関することのアセスメントは重視してなされている
が、家族介護者、協力者等、利用者等の生活環境に関することのアセスメントが軽視され
ている傾向がある。認知症の人とその家族が抱えている課題(ニーズ)を把握するために、
アセスメン卜することが必要で、あり、認知症の人のこれまでの人生、すなわち、子供から
大人に成長する様子、受けてきた教育、住んできた住宅、興味、家族との関係などに関し、
情報として収集しておくことがケアをするうえでも必要で、あるc アセスメントはケアマネ
104~
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年3月
ジャーだけが行えば良いというものではなく、全職員が関わっている利用者一人ひとりの
ニーズ、を把握しておき、ケアマネジャーと協議して適切なサービスの提供がなされること
が望ましい。
3. 家族介護者に対する社会的サポートのあり方
滋賀県立成人病センターの実践報告によると、介護者を支援するために、認知症は病気
であること、認知症の中核・周辺症状にかんする説明する等の「認知症の病態説明」、認
知症の中核・周辺症状への対応方法に関する「介護指導」、認知症の人が利用できる施設
やサービスの紹介及び相談等の「保健・福祉サービスの紹介J、カウンセリング外来及び
患者家族によるピアカウンセリング等の「カウンセリング紹介と導入J、「認知症リハビリ
及び軽症認知症リハビリの紹介」、「福祉機器や住宅改造の紹介」、認知症の人をかかえる
家族の会の紹介及び病院受診時の家族会への支援等の「患者家族会への紹介と支援」、介
護ストレッサー尺度、心理的ストレス反応尺度、身体的ストレス反応尺度、 CMI健康調
査票、 SDS うつスケール等による「介護状況チェック j、医療・保険・福祉の専門職と介
護者の合同「勉強会J等の介護者支援メニューを用いて、支援を行った結果、家族介護者
の介護ストレッサ一、心理的・身体的ストレス等の介護負担の軽減と認知症の人の行動障
害が軽減した事例もあったという報告をしている 5)。認知症の人及び家族介護者に適切な
社会的支援やサービスを提供することが大切で、あることを示唆していると考えられる。
本研究の結果から、心理的ストレスの程度について職員より、家族介護者の方が非常に
大きいことが判明した。従って、職員は家族介護者の心理的ストレスについて理解しにく
し、かもしれないので、家族介護者の心理的ストレスについてスケール等を用いて把握して
おくことが必要である。
E.メーリンと R.B.オールセンは認知症の人の行動障害(問題行動)をどのように受け入れ
るかによっては、家族介護者にとっても、認知症の人にとっても、お互いにいい影響を及
ぼし、認知症の人が自尊心を保つことができると、家族介護者は不必要に自分をすり減ら
すことを避けることができると述べている。
高齢化の急激な進行に伴い、高齢者個人のもつソーシャルネットワークに関する研究が
注目されている。それは、家族や地域社会との連帯が弱体化するにつれて、様々な人びと
を含んだソーシャルネットワークを高齢者の貴重な生活資源やサポート資源としてとらえ
ることの重要性が、社会的に強く認識されだしたわけで、ある。すなわち、高齢者が日常生
活の中でだれと付き合っているのか、付き合いのある人々とはどのくらいの頻度で接触し
ているのか、また、その人びとはどのように高齢者の暮らしに関わって(支援してあるい
は、阻害して)し、るのかなどである。
1981年、アントヌッチらによって提示されたコンボイモデル(convoymodeO 15) 16)は高齢
期のソーシヤルネットワーク全体の構造をはじめて統合的にとらえた。これは、援助をす
105-
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
る人びとをコンボイ(護送船団)にたとえて、高齢者はそれらを生活支援として活用するこ
とによって様々な危機的な状況などに対処していることに注目したものである。アントヌ
ッチらによれば、友人は選択的で任意の関係として認識されており、家族よりも容易に関
係を解消できることから、友人の存在自体が否定的な意味をもつことは少なく、精神的な
安定としての機能を果しているとしている。一方、友人や近隣とのつながりはネットワー
クの構造的には外周緑部に位置づけられているが、家族や親族よりも肯定的、情緒的な援
助を得やすい側面があることが、多くのアメリカの調査研究で共通して指摘されていると
ころであるとしている。このことから、ネットワークの構造上の外周緑部に位置している
専門職(職員)の方が家族や親族より肯定的、情緒的な援助を提供するであろうと考えられ
るので、デイケア及びデイサーピスの職員は、認知症の人及びその家族介護者の貴重な生
活資源として、サポートを期待することができる。
大牟田市は、すべての市民に認知症としづ病気や「人j の姿を正しく理解すること、認
知症に悩んでいる人やその家族に「ここに行けば安心J、認知症になっても安心して暮ら
せるまちづくりのために「支えあうことの大切さ」を伝えたいというねらいで、様々な社
会的サポートを行っている。認知症の人と家族介護者に対して大牟田市役所、かかりつけ
医、大牟田市社会福祉協議会、ケアマネジャー、地域認知症ケアサポートチーム、認知症
の人を抱える家族の会、地域のネットワーク、大牟田警察署生活安全課(高齢者 sosネットワーク)、民生委員、近所の人々との地域全体が認知症のケア、診断、治療、相談等に
関わり、地域に住民主体の見守りネットワークを形成している i九
認知症は認知症の人をその家族介護者だけでなく、社会的サポートを得て支え合うこと
により、できるだけ長く馴染みの環境で生活することが可能になり、幸せな人生を送るこ
とにもつながる。そのためには、本研究の結果にも示したように、まずは社会サービスに
かかわる職員は、家族介護者に対して、認知症のケアに関する理解を高めること、さらに、
家族介護者のデイケア・デイサービス利用への満足を高めるために、家族介護者の悩みに
耳を傾けることが望ましい。
本研究では認知症の人に関わる調査であったため、調査への協力を得ることが困難で、あ
ったので、多変量解析に用いた調査数(サンプル数)が少なくなった問題があり、今後とも
継続的に調査研究をする必要がある。また、面接調査などによる質的研究についても検討
して、実施することが必要であると考える。
v.おわりにデイケア及びデイサービスを利用している認知症の人(利用者)の家族介護者への職員の
対応、家族介護者のストレス等について調査し、社会的サポートについて検討した。
1.基本属性
(1)認知症の人は女性 63.1%であり、平均年齢は 80.7::!:: 8.3歳である。「アルツハイマー
106
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
型」、「要介護 3J、認知症老人の自立度は lillJ、障害老人自立度は IJJ と 1AJ が比較的
に多かった。「要介護度Jと「認知症老人の自立度j との有意の関係が認められた。
(2)家族介護者は、女性 72.7%であり、 150歳代J29.2 %、認知症の人との関係(続柄)は
「配偶者J33.3 %、仕事を持っているのは約 40%、最終学歴は「高等学校卒業Jが 57.8
%、健康状態(自己評価)は「普通J46.9 %、介護期間は 15年未満J60.l %で最も多かっ
た。
(3)職員(デイケア・デイサービス従事者)は女性 74.5%であり、 120歳代J47.3 %、「介護
職員J36.4 %、従事期間は 11年以上'"'"'3年未満J36.4 %、健康状態(自己評価)は「普通J50.9
%で最も多かった。
2. 認知症及びそのケア(介護)についての家族介護者の理解と対応
認知症の症状については 10項目のうち 2項目について約 60%に人が知っていたが、そ
の他の症状についてはよく理解していなかった。認知症に関する知識の平均点は 5.4::i: 2.4
点(10点満点)であった。知識に関しては学歴が高いほどよく理解していることがわかっ
た。認知症を疑ったときの家族の対応として、約 80%が、一般病院医師 44.2%、ソーシ
ヤルワーカー 17.9%に相談しており、医療機関受診を約 90%がしており、疑ってから受
診までの期間は 11年未満J約 80%であった。医療機関関係者から病気の説明を受けた
のは約 50%、訪問看護やデイケアの説明は約 80%であったが、その他保健・福祉サービ
スの説明 34.0%であり、家族は今後の介護に必要な情報を十分に得たとは言い難い。介
護について家族介護者が「工夫した」人は約 80%であり、その結果、認知症の人に変化(効
果)がみられたのは約 70%であった。このことにより家族がより良い介護について積極的
に工夫していることがわかった。
3. 職員の認知症に関する理解と家族介護者への対応
(1)認知症の知識の平均点は 7.2::i: 1.6であり、家族介護者の平均点と比較すると職員の方
が統計的に有意に高かったが、項目別にみると、職員の知識が十分あるとはいえない。ケ
アに関わる職員として認知症の人に関してアセスメントでは、利用者本人に関することは
よくなされているが、家族による介護環境等に関することについてはあまりなされていな
かった。
(2)職員の約 70%は家族介護者への支援をしているが、介護方法、認知症の説明、家族会
のことに関しては家族への説明、指導が十分なされているとはいえない。デイケアやデイ
サービス利用時における家族介護者への職員の対応についてみると、「介護で困っている
ことの相談」、 f連絡帳を活用」等は約 70%の職員が実施しており、家族介護者も約 70'"'"'80
%が認めている。その他、家族の「精神的負担」、「介護負担」、「介護者の健康状態」につ
いては職員の約 40%しか対応していない。
4. 家族介護者の介護ストレッサー・ストレス
家族介護者の介護ストレッサーとしては、「夜中に起こされる」、「し、つも神経を使う」、
円
inu
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
「どうしていし、かわからなし、」等をあげており、認知症の特異な症状に困っていることが
わかる。介護ストレッサーに影響を及ぼす要因について数量化 2類により解析した結果「要
介護度」、「介護期間j、「認知症老人の自立度j、「家族介護者の健康状態」、「認知症に関す
る知識」が家族介護者の介護ストレッサーを高める要因であることがわかった。
家族介護者の精神的ストレスとしては、「イライラ」、「気がめいるJ、「憂うつ」等を訴
えていた。家族介護者の心理的ストレスの平均点は 5.5::t 3.9点(18点満点)であり、職員
より有意に高いことがわかった。心理的ストレスに影響を及ぼす要因について数量化 2類
により解析した結果、「介護期間J、「要介護度J、「認知症に関する知識」が家族介護者の
心理的ストレスを高める要因であることがわかった。
家族介護者の身体的ストレスについては「体がだるし、」、「腰痛・胃の痛みがあるj、「眠
れなしリ、「目が疲れる」、「脱力感があるj 等をあげていた。身体的ストレスに影響を及ぼ
す要因について、数量化 2類解析した結果、「要介護度」、「健康状態」が身体的ストレス
を高める要因となっている。
5. 社会サービスの利用状況とデイケア・デイサービスの満足要因
社会的サービスの利用状況は「デイケアJ80.0 %、「デイサービスJ60.0 %、 fホームヘ
ルプサービスJ30.8 %、「精神科病~JtJ 15.4 %であり、これらのサービスに対して満足し
ていたのは fデイケアJ84.6 %、「デイサービスJ69.2 %、「ホームヘルプサービスJ40.0
%、「精神科病院J60.0 %であった。デイケア及びデイサーピスに関して「満足j に影響
を及ぼした要因について数量化2類により解析した結果は次の通りである。
(1)デイケアについては、「健康状態」、「介護方法の指導」が家族のデイケアに対する満足
に影響を及ぼしている要因であることがわかった。 (2)デイサービスについては、「健康状
態」、「続柄」が家族のデイサービスに対する満足に影響を及ぼしていることがわかった。
本研究の一部を TheGerontological Society of America 60th Anorual Seientific Meeting
(San Francisco, Ca)において発表した。
謝辞
本研究の調査にご協力頂いたデイケア及びデイサービス施設の関係者及び利用者家族の
皆様に心から感謝し、たします。また、東広島社会福祉協議会で開催されている「やすらぎ
会」の関係者から貴重なご指導いただきましたことを感謝申し上げます。
研究に際し、ご助言とご協力を頂いた広島国際大学大学院総合人間科学研究科医療福祉
専攻高尾文子教授、岡崎仁史教授、及び塩谷久子助教授に心から感謝申し上げます。また、
調査結果の集計について、ご指導いただいた元 IWAD環境福祉専門学校の二階庸光先生
に感謝申し上げます。
108
-
広島国際大学医療福祉学科紀要第4号 2008年 3月
文献
1)厚生統計協会「認知症高齢者の支援対策 要介護認定者の認知症である老人の自立度・
障害老人自立度に関する推計、要介護認定者における認知症高齢者の将来推計JW国民
の福祉の動向、厚生の指標臨時増刊:2005年、第 52巻 12号.ll145
2) E.メーリン.R.B.オールセン『デンマーク発痴呆介護ハンドブック 介護にユーモアと
ファンタジーを』ミネノレヴ、ア書房、 127,176、2004
3)田中荘司「施設高齢者の人権福祉対策JW図説高齢者白書 200U全国社会福祉協議会、
138-139、2001
4)杉山孝博『痴呆性老人の地域ケア』医学書院、 40-49、1995
5)藤本直規・小林由美子・丸岡寿美江ほか「痴呆患者の介護とその評価の実施JW別冊総
合ケア介護の展開とその評価.ll39-49、1995
6)藤野真子「在宅痴呆性老人の家族介護者のストレス反応に及ぼすソーシャルサポートの
効果JW老年精神医学雑誌.ll6、575-581、1995
7)新名理恵・矢冨直美・本間昭「痴呆性老人の在宅介護者の負担感に対するソーシャルサ
ポートの緩衝効果JW老年精神医学雑誌.ll2 (5)、655-663、1991
8)中谷陽明「痴呆性老人を介護する家族介護者を支えるためのソーシャルワーカーの役割J
『老年精神医学雑誌.ll10(2)、 819-823、1999
9) Joseph E. Gaugler,PhD、RobertL.Kane,MD、RosalieA.Kane,PhD、andRobert Newcomer,PhD
rEarly Community-Based Service Utilization and Its Effects on Institutionalizatuon in
Dementia CaregivingJ WThe Gerontologisd 45 (2)、177・185、2005
10)新名理恵「痴呆老人の家族介護者のストレス評価JW別冊総合ケア介護の展開とその評
価.ll33-38、1995
11)新名理恵「心理的検査JWCLINICAL NEUROSCIENCE.ll 12 (5)、54・57、1994
12)奥官暁子・後閑容子・酒田三允編「在宅福祉サービスの内容JW痴呆様症状のある人の
在宅ケア』中央法規、 100-102、2001
13) M. Duijnsee and W. Ros r Careing togethre for persons with dementiaJ WThe role of the
district nurse in home card Brunner-Routledge、334-341、2003
14) Noni Cobba rlmproving Domiciliary Care for People with dementia and their Carers : The
Raising the Standard ProjectJ WDementia and Sosial Inclusion.ll Jessica Kingsley Publishers、
50-66、2004
15)安達正詞「高齢者のソーシヤルネットワーク JW (社)日本家庭学会編 新版家庭学事典』
朝倉書居、 130-131、2004
16) Kahn, R.L., Antonucci, T.C. r Convoys over the life course : Attachment, roles and social
supportJ Baltes, P.B., Brim, O.G. eds. WLife-spandevelopment and Behavior, Vo1.3.ll
Academic, Press, 253-286、1980
109
-
認知症高齢者家族介護者への社会的サポートに関する研究
17)大谷るみ子「認知症ケアの基本と課題一デンマークの認知症ケアに学ぶ」第 3同山口
県介護福祉学研究会の講演資料
110