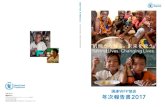教員免許制度の概要① - 文部科学省ホームページ2014/07/15 · 15 特別支援学校の教員は、特別支援学校と特別支援学校の各部(幼稚部・小学部・中学部・高等部)に
特別支援学校における「スクラッチ」を用いたプロ...
Transcript of 特別支援学校における「スクラッチ」を用いたプロ...

特別支援学校における「スクラッチ」を用いたプログラミング学習の実践
Programming Learning using "Scratch" in Special Needs Schools
中廣健治 下村勉 須曽野仁志
NAKAHIRO,Kenji SHIMOMURA,Tsutomu SUSONO,Hitoshi
特別支援学校東紀州くろしお学園 三重大学 三重大学
Higashikisyuu Kuroshio Gakuen Mie Univ. Mie Univ.
[要約]中学校卒業後に特別支援学校の高等部へ入学してくる生徒が増加している。その中には、企業
へ就職を希望する生徒もおり、問題解決に向けた主体的な取り組みや共同できる力を育むことが必要
になってきた。プログラミング学習は、試行錯誤や順序立てて問題を解決していく力が育まれると言
われている。しかし、知的障害を対象とする特別支援学校では、生徒にとって言語が難解であるため
プログラミング学習は困難であった。「スクラッチ」は、視覚的に理解しやすく、簡単に作成できるよ
う工夫されたプログラミング環境である。本実践では「スクラッチ」を用いて、就職を希望する高等
部生徒がそれぞれのテーマでアニメーション作成に取り組む授業を行い、生徒の学習の様子と作品か
ら共同する力や問題解決の意欲に着目して有効性を検討した。結果、試行錯誤や共同によって問題解
決をしようとする学習者の意欲を高める可能性が見出せた。
「キーワード」 スクラッチ 特別支援学校 知的障害 共同 プログラミング
試行錯誤 問題解決
1 はじめに
特別支援学校高等部には、小学部や中学部
から在籍する人と中学校を卒業後、入学して
くる人がいる。中学校卒業後に入学してくる
生徒には、高等学校か特別支援学校で進路選
択をしてきた人もいる。三重県でも、みえ
DataBox1)による生徒数の推移をみると、特
別支援学校の高等部生徒数が増加しているこ
とがわかる。
実践校である、くろしお学園おわせ分校は
知的障害と知的・肢体重複の児童生徒を対象
に三重県尾鷲市に設置された特別支援学校で
ある。知的障害を対象とする高等部生徒の中
には、障害の目安となる療育手帳を有してい
ない、または B判定の軽度に該当する生徒が
おり、卒業後は企業へ就職を希望する生徒も
いる。しかし、これら生徒の主体性が乏しい
と学校内外から指摘を受けることも多い。こ
れまで、重度の知的障害を有する生徒に対し
ては、生活支援を中心に教員の出すプロンプ
トに対応できるよう支援する授業が多く展開
されてきたが、企業への就労を目指す生徒に
は、問題を解決しようとする意欲やコミュニ
ケーション力の育成が重要である。問題を解
決していく力の育成において、プログラミン
グ学習は、試行錯誤や順序立てて問題を解決
していく姿勢が育まれるので有効だと言われ
ている。しかし、知的障害を対象にした特別
支援学校の生徒には、Javaや Cといった難解
な言語によるプログラミングの学習は困難で
あり、実践があまりみられない。「スクラッチ」
は、視覚的に理解しやすく、作成が簡単で小
学生でも取り組めるプログラミング環境であ
り、針本(2011)は小学校 5 年生を対象に実
践2)をしている。
本実践では「スクラッチ」を用いて、就職
を希望する高等部生徒がそれぞれのテーマで
アニメーション作成に取り組む授業を行った。
生徒の学習の様子と作品から共同する力や問
題解決の意欲に着目して有効性を検討する。
- 53 -

2 授業実践
2-1 スクラッチ(Scratch)とは
無料でダウンロードできる MIT(マサチュ
ーセッツ工科大学)メディアラボが開発した
プログラミング環境であり、日本語にも対応
している。本ツールは命令を表す「ブロック」
に「**歩動かす」「**度回す」といった内
容が記してあり、これらのブロックを積んで
いくことで、スプライトと呼ばれるイラスト
を動かすことができる(図 1)。
図 1 スクラッチ画面
2-2 授業対象生徒について
くろしお学園おわせ分校では、就職を希望
する生徒を対象に 2012年から「スクラッチ」
を使った実践に取り組んでいる。本稿では、
中廣が実践した 2012年度実施時、高等部 2
年生 2名(生徒 A・B)1年生 2名(生徒 C・D)
での考察を行う。
障害状況および学力の目安として、資料の
ある実践後から 2013年度末までに取得した
資格を以下に記す。
生徒 A 肢体不自由・ICTプロフィエンシー検
定(P検)2級・日本漢字能力検定 2級・乙種
第 4類危険物取扱者
生徒 B 療育手帳無・P検模試 4級合格・漢検
4級・丙種危険物取扱者
生徒 C 療育手帳 B・P検模試 3級合格
生徒 D 療育手帳 B・P検模試 4級不合格
2-3 授業時間と内容
自立活動の授業でパソコンスキルを訓練す
る時間(1校時を 45分として週 1回)の内、
合計 9校時を使った。授業の流れを図 2に示
し概要を順に記す。
図 2 授業の流れ
① 最初の授業では「スクラッチ」に用意さ
れている猫のスプライトを使い前進させ
るブロックの組み立て(図 3)を教員から
伝えた。生徒は入力数値を替え、移動距
離や速度変化を確認した。
図 3 ブロック組み立て例
② ブロックの意味調べでは「**と言う」
「**度回す」など、生徒が直感的に理
解しやすいものが、それぞれの生徒から
報告され、共有された(図 4)。
③ 理解できたブロックを使って20秒程度で
表現できるアニメーションストーリーを
それぞれの生徒で決定した。
④ 生徒たちが使いなれている描画ツール
「ペイント」を使用して、スプライトに
なるイラストを作成したが、こだわりも
あり多くの時間を要した。その後、ブロ
ックを組み立て、プログラムを作成した。
数値入力
部
- 54 -

生徒 A 生徒 B
生徒 C 生徒 D
⑤ 作成中にひらめいた動きについては、そ
れぞれの生徒が研究を行った。分岐処理
(図 5)についても教員への質問や組み立
て順を入れ替えるなどの試行錯誤により
獲得していった。また、得た知識を他の
生徒に伝える時間を設定した。
図 4 理解の共有がなされたブロック例
図 5 分岐処理ブロック組み立て例
2-4 完成作品
完成した作品は、それぞれ独創的なテーマ
であった(図 6)。作品の概要と完成時の作者
コメントを以下に記す。
生徒 A概要 車いすの人が移動中、壁にぶつ
かり「大丈夫?」と声をかけられる。
作者コメント「ぶつかったときの動きや言葉
を工夫しました。次回は、アニメーションの
時間を長くしたり、登場人物を増やし、迫力
のある作品を作りたいです。」
生徒 B概要 夕方、歩いて家に帰ってきた人
がドアを開け、家人と会話をしている様子を
セリフの吹き出しと人の動きで表現してある。
生徒コメント「夕方から夜に替わるところが
見所です。家に入ってからのコメントも面白
いと思います。動きはスペースキーを利用す
ることでうまく表せました。」
生徒 C概要 スクールバスでの登下校時のバ
スや生徒の動きと交わされる会話の吹き出し
で表現してある。
生徒コメント「バスの乗降と時計の針が進む
のが見所です。バスの名前を「ANKO」にする
と面白いと思いました。背景と人に力をいれ
ました。」
生徒 D概要 トラが昼寝をしていたシマウマ
を襲う場面をトラのセリフと襲われて立ち上
がるシマウマの動きで表現してある。
生徒コメント「トラ、しまうまの二つのスプ
ライトがうまく動くよう、頑張って作ったの
で、動きを見てください。」
図 6 作品画面
3 考察
① 作品と制作過程から
4 名の作品のプログラムを見ると、ブロッ
ク「**と言う」は生徒 Bが発見して、すべ
ての生徒が使っており「コスチュームを**
にする」は生徒 Cが発見して、生徒 Bも使っ
ているなど、それぞれの生徒が見つけ出した
ブロックの使用方法が波及している(図 7)。
色々な使い方を知ったことで、各作品の表現
内容が広がったと考える。イラストには、こ
だわりがあり多くの時間を要したので、スキ
ャナーやタブレット端末を利用して時間を短
縮できればよかった。
授業観察からは、スプライトの動くタイミ
ングや移動後の位置を自分のイメージしたも
のに近づけられるよう、何度もブロック内に
入力する数値を入れ替え調整したり、やり直
したり試行錯誤する姿勢がみられた。また、
これまでうまくいかないと、すぐ教員に答え
を求めていた生徒が、他の生徒と相談して共
同して問題解決を図る姿がみられた。
- 55 -

生徒 B から全体へ
生徒Cから生徒Bへ
生徒 D 生徒 C
生徒 B 生徒 A
感想に「面白そう」「次回の授業が待ち遠し
い」などの声が上がり、作成意欲の高まりが
みられたのは、アニメーションを自ら作成で
きることに高い価値を感じたことと、視覚的
に理解しやすく、作成が容易だったので、完
成への期待を膨らませたからだと考える。
完成後の作者コメント(2-4完成作品参照)
には「**が見所です」「面白いと思う」など
作品への思い入れと達成感を得ていることが
うかがえた。
図 7 プログラミング内容
② 授業後に確認できた効果
これまで生徒会活動や学級活動などで教員
に頼り、指示待ちで動く生徒たちであったが
自分たちで行動し始めている。また、危険物
などの資格試験にも挑戦して成果を出した。
これは、他教科での指導もあり、要因を一つ
に特定できないが、自分たちの力で完成させ
た達成感や生徒間で問題を解決する学習スキ
ルを身に付けたことが一因だと考えられる。
③ 学校側の効果
本実践では、生徒同士で問題を解決してい
くことを重視して、教員も生徒と一緒にプロ
グラム作成上の課題を共有し、取り組んでい
く授業形態をとった。また、授業の流れやス
クラッチの基礎的な知識は、次年度の担当教
員にも引き継ぎを行った。担当からは「生徒
が楽しく学んでいる。自分も楽しかった。」と
の感想が寄せられた。今後、様々な教員が授
業を担当することで、取り組みを継続してい
きたい。
4 結論
「スクラッチ」を利用してのアニメーショ
ン作成は、生徒のアニメーション作りに対す
る高い価値観と視覚的に理解を容易にしたプ
ログラミング環境が、作成意欲を高めた。ま
た、作品を完成させて達成感を持ったように
みえたほか、試行錯誤や共同して積極的に問
題解決に取り組む意欲がみられるようになっ
た。さらに、教員が持つ知識を生徒に注入す
るのではなく、生徒とともに考えていく内容
にすると、教員と生徒がともに楽しみ学習で
きるようになり、様々な教員が授業担当者に
なれる可能性が見出せた。スプライトの描画
に多くの時間を保障すると生徒の作品への感
情移入が深まり、作成意欲を高める効果があ
る反面、時間に制約があるためプログラミン
グ作成時間を圧迫するのでスキャナーやタブ
レット端末を利用した手書きでの作成などで
描画時間を短縮することなどが今後の課題で
ある。
参考文献
1)みえ DataBox
http://www.pref.mie.lg.jp/DATABOX/
2)針本佳織:児童の思考力・表現力育成の
ための教育用プログラミング環境「スクラッ
チ」の活用実践、三重大学大学院教育学研究
科学校教育専攻学校教育専修修士論文、2012
- 56 -

五心の逆の作図問題に関する GC/html5を用いた数学的探究について
Mathematical investigation using GC/html5 about centers of triangle
and its inverse construction problem
飯島康之 IIJIMA Yasuyuki
愛知教育大学 Aichi University of Education
[要約]3 点 A,B,C が決まれば,△ABC の五心が決まる。逆に, 3点が与えられたとき,それらを外
心, 重心, 内心とする三角形は作図可能か。本稿では, 作図ツール GC/html5 を使って,
筆者がこの問題や副問題を探究した様子を記述した。それを踏まえて作図による観察・検
証, 軌跡・領域など, 作図ツールが数学的探究を支援する点に関して明らかにするととも
に, 生徒が探究すべき問題とみなしたときの, この問題の特徴について考察した。
[キーワード]数学的探究,軌跡,領域,逆問題,作図,作図ツール
1.はじめに
GC などの作図ツールを使うと, 三角形
の五心に関わる探究できる。Euler 線のよ
うに, 五心の関係を調べたり, 頂点を動か
したときの軌跡などを調べることもできる。
三角形の 3頂点 A,B,C が決まれば,(3点
が一直線上にある場合をのぞいて)五心が
決まる。逆に, 3点を与えたとき, それらを
外心, 重心, 内心とするような三角形 ABC
を作図することはできないだろうか。本稿
ではこれを逆の作図問題と呼ぶことにする。
本稿では, この問題およびその副問題の
解決過程に関するケーススタディを行うこ
とにより,数学的探究への作図ツールの影
響やこの問題の教材としての特徴を明らか
にしたい。
2.研究方法
上記の逆の作図問題および副問題に関し
て, 筆者自身が取り組んだ様子に関して ,
その概略を記述し,作図ツールを利用する
ことによって, どのような数学的探究が可
能になったかについて考察する。また, こ
れらの問題は, 教材としてどのような特徴
を持ちうるかについて考察する。
3.結果
3-1 問題の理解と副問題の生成
まず, 問題を次のように定式化し, GCで
作図し, 問題の理解を進める。
逆の作図問題 三角形 ABC と, 3 点 O,G,I
がある。このとき, O,G,Iがそれぞれ, 三角
形 ABC の外心, 重心, 内心となるように,
A,B,Cの位置を定めよ。
図-1 GCによる試行錯誤と問題理解
最初は三角形と 3 点 O,G,I のみを与えられ
た図を使うのだが, GC利用では, それらの
A,B,C を基に,外心 O’, 重心 G’, 内心 I’を
作図し, OとO’, GとG’, Iと I’が重ねられる
かを, 試行錯誤した。3点を同時に重ねるの
は非常に難しいことを実感した。
- 57 -

そして, まず段階的に問題を解決するこ
とが不可欠であることを感じ, 次の 2 種類
の副問題を想定し, 取り組むことにした。
(1) A,B と 1 つの心を元に点 C を構成する
問題 (外心, 内心, 重心, 垂心の 4種類)
(2) A と 2 つの心を元に点 C を構成する問
題(6種類)
3-2 副問題(1) A,B,X→C 形式の問題
(1) A,B,G→C
三角形の重心 Gは, ABの中点Mと Cを
1:2に内分する点として構成される。そのた
め, 逆に A,B,Gが与えられていれば, MG
を3:2に外分する点としてCを構成できる。
実際, この図を構成して点 G を動かしてみ
ると, CはGの相似拡大になり, あらゆる位
置において点 Cを構成できることが分かる。
図-2 A,B,Gから Cを構成する
(2) A,B,H→C
三角形の垂心 H は, 3 つの頂点から対辺
に下ろした垂線の交点として構成される。
そのため, AHに対して垂直でBを通る直線
と, BHに対して垂直でAを通る直線の交点
として C を構成できる。実際, この図を構
成して, たとえばHを円上で動かすとCは
曲線にはなるが, その形状は楕円とも異な
っている。
図-3 A,B,Hから Cを構成する
(3) A,B,I→C
三角形の内心 Iは, ∠ABCと∠BACの二
等分線の交点として構成される。そのため,
AB,AI,BIを作図し, ABをAIに関して線対
称移動, BI に関して線対称移動した直線の
交点として点 C を構成できる。ところが,
図を構成して点 I を動かしてみると, 点 I
の位置によって, △ABC の内心になる場合
と, 傍心になる場合に分かれる。実際, ∠
AIB は 90 度よりも小さくならなければな
らないが,これを越える場合には, 2直線の
交点が AB の反対側に移り, ABC にとって
は傍心に変わる。(図 4右では傍心になって
しまったときの内心が一部描かれている)。
この場合も I を円上で動かすと点 C の軌跡
は曲線になるが二次曲線とは異なっている。
図-4 A,B,I から Cを構成する
(4) A,B,O→C
これまでの 3つの心(重心, 垂心, 内心)に
関しては, A,Bを加えた3点の位置は自由で
あった。そして, その 3点の位置に対してC
の位置は一意的に確定した。それに対して
外心の場合は様子が変わる。A,B の位置を
確定すれば, Oは線分ABの垂直二等分線に
限定される。そして O を中心とし, A,B を
通る円の上に Cの動きは制約されるものの,
一意的に決まるわけではない。あるいは, A
と O の位置をまず確定するならば, O を中
心としAを通る円の上にBの動きが限定さ
れ, C の動きもこの円上に制約されるもの
の一意的に決まるわけではない。
図-5 A,B,Oから Cを構成する
- 58 -

3-3 副問題(2) A,O,X→B,C 形式の問題
続いて, 2つの心とAの位置によってB,C
の位置を確定する問題に発展できる。外心
とそれ以外では大きな特徴の違いがあるの
で, まず, A,Oと他の 1つの心からCを構成
する場合について考察する。
(1) A,O,G → B,C
A と O によって, B は円上に動きが制限
される。そして, A,B,G によって C が構成
される。B を動かしたときの C の軌跡を調
べれば,その軌跡が円と交わる場所が, B, C
の存在しうる場所になる。
図-6 A,G,Oから B,Cを構成する
その場所を軌跡で調べると, 図 6 左のよ
うに円になることが推測され, B を元に C
がどう構成されているかを考えれば,図 6
右のようになり, 2 つの円の交点として,
B,Cが構成できる。
(2) A,O,H → B,C
上記の Gを Hに変えてみる。Bは円上に
動きが制限され, A,B,H によって構成され
る C に注目すると, B を円上に動かしたと
きのCの軌跡と円との交点としてB,Cが構
成される。このとき, Cの軌跡は次図のよう
になる。
図-7 A,O,Hから B,Cを構成する
Bが円上を動くときの Cの軌跡は図-7右の
ようになる。デカルトの正葉線のようにも
みえる。この曲線と円との交点の 2点が,
B,Cの候補になることが観察結果としてえ
られるが, GCにはこの曲線を作図する方法
がないので, 動的にこの交点を Cとして指
示することは難しい。これを扱えるソフト
があれば, 進展可能になる。
(3) A,O,I→ B,C
重心, 垂心の場合と同様に, Bが円上を動
くときの Cの軌跡について調べると次のよ
うになる。まず, Iが円の内部にあるときに
は, Cの軌跡は双曲線のようにみえる。そし
て, Iが円の外部にあるときには, Cの軌跡
は楕円のようにみえる。(Iが円上にあると
きには, 直線 OIになる。)
図-8 A,O,Iから B,Cを構成する
双曲線あるいは楕円になることを計算等
で証明したわけではないが, いろいろな場
合において, 二次曲線らしいものが観察さ
れることから, A以外の 2つの交点が B,C
として得られると推定される。ただし, GC
ではこれらの二次曲線を作図したり, 円と
の交点を作図することができないので, さ
らなる探究には別のソフトが必要だ。
3-4 副問題(3) A,X,Y→B,C 形式の問題
続いて, 外心以外の二つの心と Aを元に
B,Cを構成する問題について考えてみる。
(1) A,G,H→B,C
GとHが与えられているとすると, Euler
線の性質から, Oが確定する。そのため,
A,O,Gの場合に帰着されることになる。
一方, この性質に気づかずに取り組んだ
場合を想定してみた。AGを 3:1に外分する
点としてMをつくるとこれはBCの中点に
なる。AH⊥BCなので, AHに直交し, Mを
通る直線を引く(図-9左)。この直線と AH
の交点を Dとし, AHの中点をNとすると,
- 59 -

M,D,Nを通る円は, △ABCの九点円にな
る(図-9右)。AH=2AN なので, Hを中心に,
D,Nを 2倍拡大した点をD’,N’とし, A,D’,N’
を通る円を描くと, 図-10左のようになり,
この円と AHに直交し, Dを通る直線の交
点として, B,Cが構成できる(図-10-右)。
図-9 AGHから九点円を構成する
図-10 九点円から外接円を作り BCを構成
(2) A,G,I→B,C
A と G,I から B,C を構成する問題に取り
組もうとすると, これまでの問題とかなり
性質が異なることを実感した。これまでは
外心が関わっていたため, B,C の動きが円
上などに制限された。そのため, 他の条件
から Cの軌跡が曲線等によって表現される
なら, その曲線と円の交点として構成する
ことができた。特に軌跡が円になる場合は
GCの作図によって構成できた。しかし, G,I
に関しては, B,C の動きに関する制約がな
いので, 平面内を自由に動くことができる。
平面内に自由な点としての Bをとったとき,
A,B,Gによって構成されるC1とA,B,Iによ
って構成される C2 を作り,その二つの点
が重なる場合を試行錯誤で見つけようと思
っても,なかなか見つからない。Bを直線,
円上を動かしたとき, 図 11右のように, C1
の動きは直線・円になるが, C2の動きは扱
えそうもない曲線になってしまう。
図-11 Bを直線・円上を動かしたときの
C1と C2の軌跡
これでは扱えそうもないので, 図の構成
の仕方を変えた。B に対して, AGを 3:1に
外分する点が BC の中点M になるので, 点
Cを構成できる。この ABCの内心 I’を構成
し, Iと重なるのはどういうときかを調べた。
しかし, なかなか重ならないことがある。
そこで B を動かしたときの I’の軌跡につい
て調べた。B を直線上で動かしたときの I’
の軌跡が図-12左である。かなり限られた領
域しか動かない。B をほぼ平面内を動かし
たときの軌跡が図-12右である。
図-12 Bを直線・平面内で動かしたときの I’
の軌跡
A,G が与えられたとき, 内心がとりうる
領域は平面内のごく一部にしかならないこ
とが推測される。一方, これまでの問題で
は, 内心は, 傍心と合わせた挙動をするこ
とが多いので, △ABCの 3つの傍心も加え
て同じように軌跡の領域を調べてみた。
図-13 Bを平面内で動かしたときの内心・
傍心の動く領域
- 60 -

図-14 A を M に関して左右に 90 度回転し
た点を中心とし, Mを通る円を追加した図
上記の結果は単なる観察結果であって,
証明はしていないが, 上記の結果からは,
内心・傍心は, ある明確な領域の中にはと
り得ないことが推察できる。作図可能な場
合の作図の仕方を見つけるという意味での
解決には至っていないが,元の問題に対し
て想定外の事実が見つかったといえる。
(3) A,H,I→B,C
(2)の問題と同様に, A,H の他に自由に動
く点 B を取り, B の動かし方に対して, △
ABC の内心 I’をとって, その軌跡を調べて
みた。AHを y軸に平行にとり, Bを x軸に
平行に動かしたときの I’の軌跡は図-15 左
のように, そして B を平面内を動かしたと
きの B がとりうる領域の様子が図-15 右の
ようになった。
図-15 Bを動かしたときの内心 I’の様子
つまり, この結果を踏まえると, 少なく
とも A,H,I の位置関係によっては, 解が存
在しないこともありうることが推測される。
3-5 逆の作図問題 O,G,I→A,B,C
上記の結果を踏まえて, 当初の問題, つ
まり, 3点 O, G, Iを自由に与えられたとき
に, それらを外心, 重心, 内心とするよう
な△ABC はどのように構成できるのかと
いう問題に取り組んだ。
まず, O,G が与えられると Euler 線によ
り, Hが得られる。点 Aを追加し, A,O,Gに
よって構成される B,C および△ABC の内
心を I’として, Aを動かしたときの I’の軌跡
について調べると, 図-16左のように, Aが
直線上を動いたときの I’の軌跡は何らかの
曲線(の一部)になることや, AをOを中心と
する円上を動くと楕円のような曲線になる
ことが分かった。
図-16 Aを動かしたときの I’の軌跡
さらに A を平面全体を動かしたときに I’
が動く領域を調べてみると, 図-17 左のよ
うに, 平面の一部に限定され, 観察結果か
らは, HGを直径とする円の内部からOHの
中点(M)を除外した領域に限定されること
が推測された。
図-17 Aを動かしたとき I’のとりうる領域
曲線の特徴等は把握しきれず, 領域の内
部にあるときに, A,B,C をどのように構成
できるかという本来の解決は, 今回はでき
なかった。しかし, 与えられた O,G,I に対
してそれらが外心, 重心, 内心となるよう
- 61 -

な△ABC は常に構成可能というわけでな
く, GHを直径とする円の内部からOHの中
点を除外した位置に I がある場合に限られ
ることが推測できた。
4.考察
当初, 一定の努力で逆の作図方法が見つ
かると安易に考えていたが,逆の作図問題
は(ここでは未解決の)難問だった。しかし作
図ツールを使うことで部分的な解決には到
達できた。その数学的探究の特徴について,
まずまとめておきたい。
(1) 与えられた心の位置に対して, ABC
から構成できる心と比較することができる。
当初の問題理解の段階などが該当する。
また, 手続きや予想される領域を作図し,検
討することなども該当するといえる。
(2) 動点を一定の動かし方(直線・円)をし
たときに注目する点の軌跡を調べる。
軌跡が直線・円になる場合は実際に交点
等も作図可能になるが, 2次曲線・正葉曲線
などの場合も観察に基づく推測はできるし,
自分の力では扱えそうもない曲線かどうか
も推測できる。
(3) 動点を平面の限られた領域で動かす
ことによっても, 注目する点がとりうる領
域について推測することができる。
今回のケースでも, Iがとりうる領域の推
測は, かなり妥当性あるものが得られたと
いえる。このようにコンピュータを使った
場合に, 数学的には証明できていないが ,
実験的に推測されることが見つかることは
多々あると考えられる。
(4) 数学的探究を進めるための選択肢
一定の成果は得られたものの不完全な段
階にとどまっているとき, 少なくとも次の
ような選択肢がありうる。
A. (さまざまな曲線を扱えるような)より
強力なソフトを使う。
B. 推測に関して数学的証明を行う。
C. 暫定的な結論と次に取り組むべき課
題をまとめる。
今回の探究の中でも, 元の問題のままで
取り組むのか, 副問題を作りそこから取り
組むのかという意思決定の場面があった。
また, 作図をするのか, (直線や曲線に対応
する)軌跡の明確化を求めるのか, (平面全体
について調べて)領域を調べるのか等の選
択の切り換えという判断が関与したが, そ
のような意思決定が関わるものとして, 数
学的探究全体を扱っていくべきであろう。
次に,今回扱った五心の逆の作図問題に
関して, 作図ツールなどを使って探究する
教材としての可能性について考察する。
第一に, 出発点となる問題は作図手続き
の「逆」を考えるという意味で, 数学的に
は自然な問題であろう。すぐには解けない
ことを実感し, 段階的に解決するために,さ
まざまな副問題を生成可能な問題といえる。
第二に, そこで生まれた副問題には難易
度の違いや, 扱い方の違いがあり, 意外性
が内包されている問題といえる。
第三に, ソフトを使いこなす上でも, 作
図・軌跡・領域などのとの機能を使うかと
いう判断や, そこで得られた結果に基づい
て次に何に取り組むかを考えるという意味
で,様々な意思決定が関わる問題といえる。
これらの点は, 仲間と分担・協力しなが
らコンピュータを使って取り組むべき問題
例の一つとして, 今回の問題が適している
といえるのではないだろうか。
今後,作図ツールを使った数学的探究の
全体像を明らかにしつつ, 高校生等でもチ
ャレンジ可能な問題例・探究例を蓄積して
いきたい。
リソース
GC/html5
http://www.auemath.aichi-edu.ac.jp/teach
er/iijima/gc_html5/
- 62 -

正多角形描画のためのプログラミング用コンテンツ開発と授業実践
-正三角形・正方形描画と,プロシージャ作成-
LOGO programming contents for learning of the regular polygon and lesson study
杉野裕子
Sugino Yuko
皇學館大学
Kogakkan University
[要約]正多角形描画のためのプログラミング用教材コンテンツを開発し,学習指導要領に準拠
した学校での授業を設計し,授業実践を行った。この一連のサイクルによって,コンテンツお
よび授業について,改良の具体的な方向性を得る。特に,授業のプロトコル分析により,プロ
グラミングが,意欲,メタ認知を働かせ,自力解決場面での教え合いと自然発話を誘発し,さ
らに,図形概念形成における言語の意識化とイメージ形成などを促すことが分かった。
[キーワード]プログラミング,LOGO,算数,教材開発,正多角形
1.はじめに
算数・数学学習では,定規とコンパスで行
っていた作図や,筆算はじめ複雑な計算を,
コンピュータにやらせることが可能である。
ツールとしてコンピュータを活用し,素早い
処理の恩恵として,帰納的に数多くの場合に
ついて調べてみることは有用である。また,
頭の中で考えていたことが,コンピュータ上
でどのように表出されるのかについて,実験
的に確かめてみることを通して,思考を進め
たり概念理解へつなげたりする活用方法も模
索されている。
このようなツール型のコンピュータ活用の
ひとつとして,子どもによるプログラミング
がある。コンピュータは,人類が初めて手に
した,言語で動かせる道具である。道具が言
葉で動く楽しさと,「子供は数学を生きた言語
として学ぶ」(Papert1980)ことは,数学言語・
記号や用語の作用を実感しながらの学習が可
能であることを意味する。本研究では,プロ
グラミングのための教材コンテンツを開発し,
学習指導要領に準拠した学校での授業を設計
し,授業実践を行う。この一連のサイクルに
よって,コンテンツおよび授業について,改
良の具体的な方向性を得,プログラミング活
用の有効性を検証する研究の基礎部分とする。
2.これまでの研究の経緯
1)図形概念形成でのプログラミング活用
数学の表現体系には,現実的表現・操作的
表現・図的表現・言語的表現・記号的表現と
いった,抽象度の異なる5つの表現様式があ
り,それぞれが有機的なつながりを持ってい
る(中原 1995)。この,表現様式間の移行は,
算数・数学学習には欠かせない。授業を行う
教師には,移行を手助けするべく,教材・学
習指導法・子ども理解と外化の促進・評価に
ついて,的確性に配慮した多方面からの支援
が求められる。しかしながら,この表現様式
間の移行は,最終的には学習者の頭の中で行
われる。
Vinner(1991)は,図形概念は,言語的に表
現される「概念定義」と,イメージ的表象で
ある「概念イメージ」の2面からなることを
示した。川嵜(2005)は,Vinnnerの研究を,
授業における図形の認識過程に融合し,図形
概念の理解の様相モデルを示した。様相Ⅰ~
Ⅴの各レベルにおける,図形の「イメージ」
- 63 -

と「言語」の状態を明らかにした。
プログラミング活用では,様相ⅡからⅣに
おいて,図形を「言語」面から意識させ,さ
らに,「言語」と「イメージ」の関係性につ
いて考えさせる。両者の不整合を小さくし,
レベルの引き上げに役立てる(杉野 2013c)。
2)教材コンテンツ開発の理念
プログラミング言語は,日本語 LOGO(1)を
使用する。単元や学習目標ごとに,プログラ
ミング教材をコンテンツ化する方法で開発
を行ってきた(杉野 2013a,杉野 2013b)。
プログラミング言語の汎用性は,授業目標
に合った教材作成という点では有利に働く。
算数・数学学習では,理解・獲得された概念
は,新しい「用語」で表現される。LOGO言語
では,学年や学習段階に合わせて獲得してい
く「用語」を,プログラミングに使う言語と
して置くことができる。
各コンテンツには,子どもが使用する数個
の命令を,キーボード入力の負担を減らすた
め,画面でのボタン入力で配する。また,言
語で入力していることの意識化および,画面
の図形と言語の関係性の理解のために,入力
した言語コードを逐次表示させる機能を持た
せた(図1)。また,LOGOのタートル幾何と,
小・中学校カリキュラムのユークリッド幾何
との相違については,タートルの視点を図形
の外に置くために,「辺は」・「角度は」という
2つの命令を開発している(杉野 1988)。
3.研究の目的と方法
研究の目的は,小学校5年「正多角形」の
単元において,プログラミング(2)を活用し
た授業の実際を示し,その可能性と有効性を
検証することである。本稿では,この研究の
前半として,プログラミング未習の児童にプ
ログラミングを教えながらの授業が成立する
こととを示す。また,既習の正三角形と正方
形をプログラミングする過程を通して,図形
概念についての再確認および理解の深化が起
きることを示す。また,続く,担任教諭によ
る「正多角形」の授業へ向け,コンテンツの
改良と,授業改良の視点を得る。
方法としては,まず,この単元に適したプ
ログラミング用コンテンツを開発した。次に
授業を実践し,そのプロトコルから分析した。
4.開発コンテンツ
多角形描画のためのコンテンツには,「辺
は」,「角度は」という基本命令ボタンがある。
クリックすると,下のコマンドセンターに「辺
は」という文字が表示され,続いて辺の長さ
の数値のみ,数字キーで入力する。図 1 は,
「辺は 3」,「角度は 90」,「辺は 」までの
入力である。ユークリッド幾何に対応できる
ように,「辺は 3」と命令すると,3 に相当
する軌跡をかいた後,タートルは進行方向を
180°変える(ひっくり返る)。「角度は 90」
では,タートルは,ゆっくり内角で 90°回転
する。タートルの進行速度や回転速度も,画
面からのアフォーダンスに配慮し,子どもの
年齢や学習状況に合わせて変える。
図 1
この他に,補助命令として,「前に」,「右に」,
「左に」がある。また,「けす」によって画面
が全て消され,タートルが左下に位置する。
位置に関する命令と色を変える命令は,右側
に配した。このコンテンツは,角度学習をす
る小学校4年から使うことができる。
5.実践授業と分析
- 64 -

1)授業の概要
日時:2014年 2月 21日 5限目,6限目
対象:豊田市立小学校 5年児童 25名
場所:コンピュータ室(児童ひとり1台のコ
ンピュータ,教師用コンピュータとプロジェ
クター)
授業者は,担任教諭ではなく,筆者自身で
ある。授業設計に基づき,学習指導案を作成
した。5限目の目標は,「画面上のボタンを使
って,正方形や正三角形をかくための技能を
修得すること」と,「正方形や正三角形の性質
および,いろいろな大きさがあることを復習
する」ことである。6限目の目標は,「正方形
や正三角形のプロシージャを作成し,これら
を用いて,『家』をかくプロシージャを作成す
ること」と,「図形の傾きに対する感覚を養う
こと」である。本稿では,5限を中心にみる。
2)授業のプロトコルと分析
①児童の興味と集中
“かめ”に対する親しみが見られる。やっ
てみたい,やらせてもらえるという保障から,
プログラミング方法の説明を集中して聞いた。
T画面に何が出てきましたか?
Cかめ。かめ。
Tかめは,タートルといいます。(板書)
C知ってる。英語,習ってる。
Tこのかめ,結構いうこときいてくれます。
Cまじ?
T どういう風にするかというと,先生がやっ
てみるから,ちょっと見ていて下さい。
C面白そう。
T 先生は,皆がやりやすいように,ここにボ
タンを作ってきました。「辺は」「角度は」,
この2つで,タートルがどんな動きをする
か画面を見てみましょう。
…「辺は 3」,「角度は 90」を,説明しな
がらやって見せる(図1)…
Tピョッと進んだ。ちょっと変わりましたね。
Cあー。
②予測によるイメージ化と,完成への見通し
いきなり課題を与えないで,何をかこうと
しているか予測させることで,結果の図形の
イメージを持たせた。また,自分でやれそう
という見通しを持たせた。
T つぎ,先生はどんな命令を,何の図形をか
くと思いますか。
C正方形。長方形。
T 実は,長方形にしようかなと思ったけど,
今日は正方形をとりあげようと思います。
Tどんな命令をするといいですか。
C辺は3。
T続きかけそう?
(児童がやりたそうな様子を確認して,)
T 今からやります。辺の長さは 3 じゃなくて
もいいです。残念ながら 10だとはみ出す。
10より小さい数でかいてみてください。
(「けす」ボタンの説明をする。)
Tはい。始め。
③“かめ”にやらせる効果とメタ認知
児童の発話の表出
自分が定規・コンパスで作図する場合とは
異なり,言語命令でかめにやらせることで(本
当は自分の考え),メタ認知が働く。普段の授
業には出にくい,出来たとき・出来なかった
とき,また活動過程での発話が見られた。
…各自,プログラミングで正方形をかく。
教師は机間指導をする。…
(以下,Cは,自力解決時のつぶやき)
Cおー。すげー。
T分かんない子はきいて下さいね。
Cかめさん,いけー!
Cきゅうー!
C角度 90度。
Cおもかじいっぱーい。
C出来たよ。出来た。
C 9かけた。すごくでっかいの。
C全速,前進。
Cわーっ!
Cかめちゃん。変な…。
- 65 -

Tもう出来ちゃったっていう人?
Cはーい。(挙手 多数)
④教師と,教師のタートルへも教える
自分の画面で成功しているため,他者へ教
えようとする。自力解決場面でも,自然発生
的な教えあい・学び合いが起きていた。
T先生も続きをかきたいから教えて。
(スクリーンの正方形の続きの命令を,児童
が言ったとおりに入力する。)
T これでおしまい?にした人。タートルを最
初と同じ向きにしてね。「角度は 90」と入
れましょう。
Tはい。こんなふうにかけましたか?
図 2
⑤お互いにかけた正方形を観察しあうことに
よる,多面的なイメージの獲得
自分がかいた正方形以外の,いろいろな辺
の長さの正方形を見ることによって,正方形
のイメージを広げる。川嵜の様相Ⅲへの移行。
Tじゃあね。どの辺の長さでかいたか教えて。
T 9でやった人手を挙げて。(挙手 数名)
T 8でやった人。 いないの!
T 7,6,5,4,3,2,1(各数名。5は多数。)
T全員立ちましょう。時計と同じ向きで,ぐ
るぐるっと回りましょう。(グループの,他
の児童が書いた画面を見させる。)
Cなんだこりゃ。ちっちゃい!
T席に座ってください。
Tいま,友達の作ったの見て,自分のの比べ
て,どんなことに気づいた?
Cみんなでかかった。
Tみんなでかかったね。君,小さかったの?
いくつ?
C 5。
T 5。5で小さかったの?
C 1の正方形。かわいいの出来てた。
C みんな超でかかった。
⑥ 言語面での気づき
プログラムを見ることで,図形の性質へ目
を向けさせる。川嵜の様相ⅢからⅣへの移行。
T他にも気がついたひと。じゃね,皆形の方
ばっかり見ていたけど,言葉の方で何か気
がついた人。
C自分のだったら,「辺は 9」と「角度は 90」
で交互になっている。
T交互になっている?自分のちょっと見てみ
て。交互になっている?
Cなっている。
T先生のもそうですね。(スクリーンを指す)
T言葉の方を見て,まだ気がついたことがあ
った人。交互になっているだけかな?
Cぼくのは,9,90,9,90と繰り返されてい
る。
C正方形の角度が 90°だから,全員角度が 90。
Tもっと簡単なことでもいいから,気がつい
たことがあったひと。(挙手なし)
…正三角形のプログラム作成へ…
⑦図形の性質の確認と,既習事項がどこで使
われ得るかの気づき
言語を見ることで,その中に使われ得る既
習事項に目が向く。
図3
Cそこのさ。あのやつを見てもさ。角度は 60°
ってのが 3つあるからさ。それを全部あわ
- 66 -

せたら 180°になる。
C三角形の和は全て 180°
Tおー。角度の和は。もう勉強しているもん
ね。だから,60°が3つで,60+60+60で
C 60×3
T賢い。60×3って。180って。なってるなー
って確認ができたそうです。
Tこれ,さっきの正方形のプログラムの時に
はどうなってた?ちょっと違う。あれは?
C 90×4。360。
Tうん。四角形 360でよかったっけ?
Cはい。
⑧異なるプログラム同士の言語の比較
正方形と正三角形のプログラムの比較を通
して,改めてそれぞれの図形の特徴に気づく。
T他にも何か気が付いたことがある人。簡単
なことでいいよ。さっきの正方形かいたプ
ログラムちょっと消えちゃったけど,あれ
思い出して。どこが一緒? どこが違う?
Tないの?先生言っちゃおうかな。「辺は」っ
ていう言葉の数は何回出てくる?
C 3回。
Tさっきは?
C 4回。
T何で?
C辺が3つと4つ。
Tそう。四角形は 4辺。三角形だと?
C3辺。
T角度は? 続き言えるひと。
C三角形は角度が3つ。で,四角形が4つ。
Tだから,辺と角がいくつあるかということ
で,「辺は」という言葉と,「角度は」って
いる言葉の数も決まってきます。
T今からちょっと難しいことやるからね。
C五角形。
Tそれはね,月曜日に倉田先生が,三角形や
四角形じゃないことをタートルを使ってや
ってもらいますので,楽しみにしていてね。
⑨プロシージャを作成し,実行したときの,
児童の驚き
図形をかく一連の命令をプロシージャにし,
新しい「言葉(言語)」を“タートル”に教え
る。このことは,活動の一連が一語で表現さ
れるとともに,その中身の理解を意味する。
児童からは,「全自動」という言葉が出た。ま
さしく,コンピュータによる全自動化である。
T今からね。このタートルをもっと賢くする
ために,タートルの脳みそ。ここです。(ス
クリーンの手順エリアを指す。)右側の縦長
の四角の中。これがタートルの脳にあたり
ます。ここの中に覚えさせます。そうする
と,このタートル,すごく賢くなります。
T覚えさすにはね。言葉を入れないといけな
い。左側に三角形のプログラム(こういう
のプログラムっていう)出てますから,三
角形からかいていきましょう。
Tまだ打たないでね。画面を見ていて下さい。
T脳みその中に最初に書く言葉があります。
それはね。「てじゅんは」と書きます。(板
書する)てじゅん という言葉知ってる
人?
…以下,正三角形の命令を,コピー&ペー
ストで入力させる。…
Tでは,だいたい出来たと思います。じゃ,
本当に今,タートルが賢くなったかどうか,
確かめます。それはね。下のさっき命令し
たところからやってみますが,最初にじゃ
あ,「けす」で画面を消しておきましょう。
T下の命令のところに,さっきみたいに,何
個も命令を打たなくても,新しい言葉。「正
三角形」っていう言葉をいま覚えたから,
「正三角形」ってだけ打てば大丈夫ですね。
なので「正三角形」って打って下さい。コ
ピーしてもいいです。
T入れたら,リターンキーを押して確かめて
みましょう。
Cお。すげー。
C全自動!
…6限目では,「正方形」と,「家」のプロシ
ージャを作成する…
- 67 -

6.プロトコルから分かったことのまとめ
プロブラミング活用の授業では,定規とコ
ンパスの作図とは異なり,言語でタートルに
やらせたいという意欲がわく。授業感想では,
「楽しかった」,「またやってみたい」と多く
の児童が書いていた。タートルにやらせるこ
とで,自分の考えの結果について,図や言語
から観察でき,メタ認知が働きやすくなる。
プロシージャ作成では,それまで一語一語命
令していた手順全部を,たった一語の命令で
実行させる体験をした。「全自動」という言葉
に象徴されるように,自動化されることは,
人間の学習過程でも起きることである。
プログラミング活用の特徴か,ICT 活用の
特徴かは,今後明らかにする必要があるが,
自力解決場面での教え合いが自然発生してい
た。さらに,つぶやきとしての自然発話が多
く出るのも特徴的である。
図形概念形成における利点としては,まず,
画面にかこうとする形をイメージさせるとい
う特徴がある。教科書などでは,図が先にか
かれていて,それについて調べることが多い。
また,コンピュータでは,多様な数多い描画
が可能であり,より多面的なイメージ形成の
機会を得ることとなる。言語面からは,図形
の性質へ目を向けさせたり,既習事項が使わ
れていることの再確認をさせるきっかけとな
る。さらに,図とプログラミング言語を見比
べることで,イメージと言語との関係性に気
づき,各様相での両者の不整合を小さくする。
7.改良の視点
・プロシージャ作成での,コピー&ペースト
によらない,入力軽減コンテンツ作成
・教師用コンピュータやスクリーンの配置
・スクリーン,黒板,自分のコンピュータ画
面のどれを見るか,視線の移動と学習内容
に配慮した授業設計
・お互いの画面を見たり,意見を交換したり
する場面を適切に設けた授業設計
・プログラム同士を比較することのできる,
板書や画面の工夫
注
(1)LOGO言語は,FCマネジメント発売の,
「Micro Worlds EX」を使用。
(2)本研究においては,1単語であっても,
プロシージャ作成であっても,言語で命令
した場合は,プログラミングとする。
引用及び参考文献
Seymour Papert,マインドストーム,未来社,
1980,(奥村喜世子訳,1982)
川嵜道広,直感的側面に着目した図形指導過
程の研究,第 38回数学教育論文発表会論文
集,pp.379-384,2005
杉野裕子,算数・数学の授業におけるコンピ
ュータプログラミングの役割,日本数学教
育学会 第 21 回数学教育論文発表会,
pp.133-138,1988
杉野裕子,算数学習におけるコンピュータプ
ログラミング活用 -長方形概念形成のた
めの LOGO教材開発-,科教研報.27.5,
pp.43-48,2013a
杉野裕子,低学年算数のための「1単語-ボ
タン入力」による LOGOプログラミング教材,
日本科学教育学会年会論文集 37,
pp.363-364, 2013b
杉野裕子,図形概念のイメージを育て,言語
的表現とつなげるプログラミング活用コン
テンツの開発,日本数学教育学会,第 46
回秋期研究大会発表集録,pp.383-386,
2013c
杉野裕子,数学概念形成のための LOGOプログ
ラミングコンテンツの開発 -図形概念の
イメージ化と言語化を促すために-,『教科
開発学論集第 2号』愛知教育大学大学院・
静岡大学大学院共同教科開発学専攻,
pp.95-106, 2014a
中原忠男,『算数・数学教育における構成的ア
プローチの研究』,聖文社, 1995
- 68 -