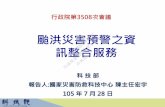幹線道路沿いの土砂災害対策 - mext.go.jp · 災害前 災害後 土砂崩れ 土砂堆積 災害前の詳細な地形をaw3dで把握。災害後の地形をヘリコプターから
世界の自然災害の発生件数(1980 -2017) 洪⽔災害 …2019/12/6 1 Ministry of Land,...
Transcript of 世界の自然災害の発生件数(1980 -2017) 洪⽔災害 …2019/12/6 1 Ministry of Land,...

2019/12/6
1
Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism
洪⽔災害多発時代に求められる河川情報のあり⽅
洪⽔災害多発時代に求められる河川情報のあり⽅
令和元年12⽉6⽇
⽔管理・国⼟保全局 河川計画課河川情報企画室⻑ 平⼭⼤輔
令和元年度 河川情報シンポジウム 世界の自然災害の発生件数(1980 - 2017)
○ 世界の自然災害の発生件数は、水・気象関連の自然災害は割合が大きく、かつ、増加傾向。○ 2017年は、水関連の自然災害(洪水・土砂災害等)の発生件数が47%を占め、1980 – 2017年の平均
でも約40%を占めている。
種別(2017比率)
災害例
水関連(47%)
洪水、土砂災害、雪崩、沿岸洪水
気象(35%)
熱波、寒波、落雷、竜巻、高潮
気候(11%)
旱魃、氷河湖決壊、山火事
地球物理
(7%)地震、津波、火山
【出典】 Munich Re website https://www.munichre.com/topics‐online/en/2018/01/2017‐year‐in‐figures#furtherinformation
全災害計
※1人以上死者が出た災害 及び 一定規模の被害額(国により異なる)で出た災害をカウント
1
気温
降雨
世界の平均地上気温は1850~1900年と2003~2012年を比較して0.78℃上昇
気候システムの温暖化につい
ては疑う余地がない
21世紀末までに、世界平均気
温が更に 0.3~4.8℃上昇
短時間強雨の発生件数が約30年
前の約1.4倍に増加
2012年以降、全国の約3割の地点で、1時間当たりの降雨量が観測史上 大を更新
1時間降雨量50mm以上の
発生回数が2倍以上に増加
1時間降雨量50mm以上の年間発生回数(アメダス1,000地点あたり)
※1 【出典】気候変動に関する政府間パネル(IPCC):第5次評価報告書、2013
※2 【出典】気象庁:地球温暖化予測情報 第9巻、2017
気候変動の影響と今後の予測
○ 気候変動に関する政府間パネル(IPCC)の第5次評価報告書によると、気候システムの温暖化については疑う余地がなく、21世紀末までに、世界平均気温が更に0.3~4.8℃上昇するとされている。
○ また、気象庁によると、このまま温室効果ガスの排出が続いた場合、短時間強雨の発生件数が現現在の2倍以上に増加する可能性があるとされている。
○ さらに、今後、降雨強度の更なる増加と、降雨パターンの変化が見込まれている。
既に発生していること 今後、予測されること
2
※1
※2
台風
平成28年8月に、統計開始以来初めて、 北海道へ3つの台風が上陸
平成25年11月に、中心気圧895hPa、 大瞬間風速90m/sのスーパー台風により、フィリピンで甚大な被害が発生
日本の南海上において、猛烈
な台風の出現頻度が増加※
台風の通過経路が北上する
台風が大型化する平成28年8月北海道に上陸した台風の経路
【台風 7号経路】
【台風 9号経路】
【台風11号経路】
渚滑
川
湧別川
網走川
釧路川
十勝川
沙
流川
鵡川
天塩川
留萌川
石狩川
尻別川
高瀬川
馬淵川
岩木川
米代川
※1 【出典】気象庁気象研究所:記者発表資料「地球温暖化で猛烈な熱帯低気圧(台風)の頻度が日本の南海上で高まる」、2017
既に発生していること 今後、予測されること
前線
局所豪雨
短時間豪雨の発生回数と降水
量がともに増加
停滞する大気のパターンは、増
加する兆候は見られない
流入水蒸気量の増加により、総
降雨量が増加
平成30年7月豪雨で発生した前線
平成30年7月豪雨では、梅雨前線が停滞し、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨が発生
特に長時間の降水量について多くの観測地点で観測史上1位を更新
時間雨量50mmを超える短時間強雨の発生件数が約30年前の約1.4倍に増加
平成29年7月九州北部豪雨では、朝倉市から日田市北部において観測史上 大の雨量を記録
平成29年7月筑後川右岸流域における12時間 大雨量
筑後川右岸流域
気候変動の影響と今後の予測
3
※1
4
日本を来襲した台風 (1851-2006年)
○ 日本は非常に多くの、かつ、カテゴリーの高い台風の経路上に位置している。
【出典】NASAホームページ https://www.earthobservatory.nasa.gov/images/7079/historic‐tropical‐cyclone‐tracks
年に平均20-30個の台風が発生
年に平均10-15個のハリケーンが発生
分 類(シンプソンスケール)
風速m/s
トロピカルディプレッション - 17
トロピカルストーム 18 - 32
カテゴリー1 33 - 42
カテゴリー2 43 - 49
カテゴリー3 50 - 58
カテゴリー4 58 - 70
カテゴリー5 70 -
氾濫危険水位を超過した河川が増加
2417
3746
62
0
20
40
60
80
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
氾濫危険水位を超過した河川数
(国管理河川)
※都道府県管理河川は国土交通省発表 災害情報(国土交通省ウェブサイト掲載)による。
59142
331409 412
0
100
200
300
400
500
平成26年 平成27年 平成28年 平成29年 平成30年
(都道府県管理河川)
○ 気候変動等による豪雨の増加により、相対的に安全度が低下しているおそれがある。○ ダムや遊水地、河道掘削等により、河川水位を低下させる対策を計画的に実施しているものの、氾濫危険水位
(河川が氾濫する恐れのある水位)を超過した洪水の発生地点数は、増加傾向となっている。
(河川数)
(河川数)
5

2019/12/6
2
水害の特徴
平成27年9月 関東・東北豪雨
平成29年7月九州北部豪雨
再度災害防災対策(被災地)
○鬼怒川緊急治水対策プロジェクト
○北海道緊急治水対策プロジェクト
○九州北部緊急治水対策プロジェクト
課題を踏まえた対応(全国)
・「住民目線のソフト対策」へ転換・「洪水氾濫を未然に防ぐ対策」・「危機管理型ハード対策」を導入
・土砂・流木による被害の危険性⇒透過型砂防堰堤等の整備
・再度の氾濫発生の危険性⇒河道掘削・堤防整備
・洪水時の水位監視の必要性⇒危機管理型水位計の設置
・ 常総市の1/3、約40km2の区域が浸水・約8,900戸が浸水、約4,300人が救助・ 浸水解消までに約10日間を要した
・死者40人、行方不明者2人・全壊338棟、半壊1,100棟、
一部損壊75棟、家屋浸水1,806棟
○水防災意識社会 再構築ビジョン
○中小河川緊急治水対策プロジェクト
小林川(十勝川水系)高齢者グループホー
ム 介護老人保健施設
グループホームの被災状況(小本川)
平成28年8月北海道・東北豪雨
直轄堤防の決壊に伴い広範囲で長時間浸水
北海道に3つの台風が上陸。県管理の中小河川で甚大な被害
山間部において土砂・流木を伴う洪水氾濫
「大規模氾濫に対する減災のための治水対策のあり方について」答申
「中小河川等における水防災意識社会の再構築のあり方について」答申
6
近年大規模水害が多発
7
平成30年7月豪雨
○ 6月28日以降、梅雨前線が日本付近に停滞し、また29日には台風第7号が南海上に発生・北上して日本付 近に暖かく非常に湿った空気が供給され続け、台風第7号や梅雨前線の影響によって大雨となりやすい状況 が続いた。
○ このため、西日本を中心に全国的に広い範囲で記録的な大雨となり、6月28日~7月8日までの総降水量が 四国地方で1,800mm、東海地方で1,200mm、九州北部地方で900mm、近畿地方で600mm、中国地方で 500mmを超えるところがあるなど、7月の月降水量が平年値の4倍となる大雨となったところがあった。
○ 特に長時間の降水量について多くの観測地点で観測史上1位を更新し、24時間降水量は76地点、48時間降 水量は124地点、72時間降雨量は122地点で観測史上1位を更新した。
8
平成30年7月豪雨
○ 平成30年台風第7号及び前線等による大雨(平成30年7月豪雨)により、西日本を中心に、広域的かつ同時多 発的に、河川の氾濫、がけ崩れ等が発生。
○ これにより、死者223名、行方不明者8名、家屋の全半壊等20,663棟、家屋浸水29,766棟の極めて甚大な被害が広範囲で発生。
○ 避難指示(緊急)は 大で915,849世帯・2,007,849名に発令され、その際の避難勧告の発令は985,555世帯・ 2,304,296名に上った。
○ 断水が 大262,322戸発生するなど、ライフラインにも甚大な被害が発生。(H30.9.10時点)
9
平成30年7月豪雨
○ 国管理河川では、26水系50河川で氾濫危険水位を超過。○ このうち、23水系46河川は記録的な大雨となった西日本に集中。
高梁川水系小田川(岡山県倉敷市)左岸及び複数の支川の決壊、右岸の越水により、多数の家屋等浸水(約1,200ha、約4,100戸)(7/7)
肱川水系肱川(愛媛県大洲市)全ての暫定堤防箇所や、東大洲地区の二線堤か らの越水等により、大洲市全域で浸水家屋数 3,114棟(8/30)
※発生件数及び人的・人家被害については、確認中であるため、今後数値等が変わる可能性があります。
○台風や前線性豪雨により、全国各地で甚大な水害や土砂災害が発生。○令和元年台風第19号では河川の堤防が各地で決壊し、甚大な被害が発生。
①:令和元年台風19号
死 者 50名※住家浸水 14,131棟※
長野県長野市 千曲川の浸水状況
④:令和元年台風15号
③:令和元年8月前線に伴う大雨
②:6月30日からの大雨
福島県須賀川市 阿武隈川の浸水状況
佐賀県大町町 六角川の浸水状況
千葉県山武市 電柱の倒壊状況
鹿児島県 大里川の応急復旧状況
①
①
①
④
②
③
埼玉県東松山市荒川水系越辺川の浸水状況
※消防庁「令和元年台風第19号による被害及び消防機関等の対応状況(第12報) 」(令和元年10月16日14:30現在)
10
今年発生した主な災害
11
令和元年10月台風第19号の特徴(降雨) 速報版(R1.10.17時点)
※気象庁ウェブサイトより作成;2019年10月10日~2019年10月13日(令和元年台風第19号による大雨と暴風 )※数値は速報値であり、今後変更となる場合がある。
53
72
103
120
89
40
9
0 50 100 150
72時間降水量
48時間降水量
24時間降水量
12時間降水量
6時間降水量
3時間降水量
1時間降水量
観測史上1位の更新地点数(時間降水量別)
○ 10 月6 日に南鳥島近海で発生した台風第19 号は、12 日 19 時前に大型で強い勢力で伊豆半島に上陸した。その後、関東地方を通過し、13 日12 時に日本の東で温帯低気圧に変わった。
○ 台風第19 号の接近・通過に伴い、広い範囲で大雨、暴風、高波、高潮となった。○ 雨については、10 日から13 日までの総降水量が、神奈川県箱根で1000 ミリに達 し、東日本を中心に
17 地点で500 ミリを超えた。特に静岡県や新潟県、関東甲信地方、東北地方の多くの地点で3、6、12、24時間降水量の観測史上1 位の値を更新するなど記録的な大雨となった。
○ 降水量について、6時間降水量は89地点、12時間降水量は120地点、24時間降水量は103地点、48時間降水量は72地点で観測史上1位を更新した。 (全国の気象観測地点は約1300地点)

2019/12/6
3
12
台風第19号による国管理河川の状況(水位) 速報版(R1.10.21時点)
○ 国管理河川の阿武隈川水系阿武隈川、鳴瀬川水系吉田川、信濃川水系千曲川、久慈川水系久慈川(3カ所)、那珂川水系那珂川(3カ所)、荒川水系越辺川(2カ所)・都幾川では堤防が決壊。
○ これらの河川では、観測水位が既往 高水位を超過又は迫る水位となった区間がある。
: 国管理河川決壊箇所
: 都道府県管理河川決壊箇所
: 国管理河川
8.88 8.4402468
既往 高 今回洪水
鳴瀬川水系吉田
川(落合)
44.29
42.72
20
30
40
既往 高 今回洪水
久慈川(山方)
27.27
28.24
20
25
30
既往 高 今回洪水
那珂川(野口)
11.13
12.46
5
7
9
11
13
既往 高 今回洪水
千曲川(立ヶ花)
16.71 18.2
10
15
20
既往 高 今回洪水
相模川(相模大橋)
6.46 6.220
2
4
6
既往 高 今回洪水
多摩川水系浅川
(石原)
14.44
16.51
10
12
14
16
既往 高 今回洪水
荒川水系入間川
(菅間)
11.33
12.78
5
7
9
11
13
15
既往 高 今回洪水
荒川(治水橋)
※決壊箇所は、令和元年10月21日 7:00時点 判明情報※□は、国管理区間で決壊がなかった河川※数値は速報値であり、今後変更となる場合がある。
21.04
20.68
10
15
20
既往 高 今回洪水
利根川(栗橋)
5.9 6.434
5
6
7
既往 高 今回洪水
阿武隈川(福島)
7.41m
6.56m
5.40m
44.15m
29.32m
26.26m
20.97m
19.97m22.38m
18.1m
5.94m
4.90m
16.55m
15.91m
14.37m
12.37m
10.75m
9.6m
-:計画高水位-:氾濫危険水位
7.30m
13
令和元年台風第19号における一般被害
令和元年台風第19号の豪雨により、極めて広範囲にわたり、河川の氾濫やがけ崩れ等が発生。これにより、死者90名、行方不明者9名、住家の全半壊等4,008棟、住家浸水70,341棟の極めて甚大な被害が
広範囲で発生。
北陸新幹線⾞両基地
破堤点(千曲川左岸58.0k付近)
信濃川水系千曲川(長野県長野市)
荒川水系越辺川(埼玉県東松山市他)
阿武隈川系阿武隈川(福島県須賀川市他)
破堤点(久慈川左岸25.5k付近)
久慈川水系久慈川(茨城県常陸市他)
※消防庁「令和元年台風第19号による被害及び消防機関等の対応状況(第32報) 」(令和元年10月28日)
14
台風19号の影響による河川の決壊発生箇所
: 国管理河川決壊箇所
: 都道府県管理河川決壊箇所
: 国管理河川
国 12箇所県 128箇所計 140箇所
利根川水系秋山川(佐野市)【2箇所】
阿武隈川水系広瀬川(伊達市)
鳴瀬川水系吉田川(大郷町)
信濃川水系三念沢(長野市)
荒川水系都幾川(東松山市)
宇多川水系宇多川(相馬市)【3箇所】小泉川水系小泉川(相馬市)
那珂川水系那珂川(常陸大宮市)【2箇所】
荒川水系越辺川(川越市)
久慈川水系久慈川(常陸大宮市)【3箇所】
荒川水系越辺川(東松山市)
関川水系矢代川(上越市)
利根川水系黒川(壬生町)【3箇所】
利根川水系三杉川(栃木市)
那珂川水系蛇尾川(大田原市)
利根川水系思川(鹿沼市)【3箇所】
利根川水系出流川(足利市)
砂押川水系砂押川(利府町)
鳴瀬川水系渋井川(大崎市)
荒川水系新江川(東松山市)
那珂川水系那珂川(那珂市)
荒川水系都幾川(東松山市)
那珂川水系藤井川(水戸市)【2箇所】
阿武隈川水系阿武隈川(須賀川市)
阿武隈川水系阿武隈川(矢吹町)【3箇所】
阿武隈川水系濁川(福島市)
阿武隈川水系滝川(伊達市)
阿武隈川水系安達太良川(本宮市)
阿武隈川水系社川(白河市)【5箇所】
阿賀野川水系藤川(会津美里町)
三滝川水系三滝川(新地町)
太田川水系太田川(南相馬市)
小高川水系小高川(南相馬市)【2箇所】
北上川水系照越川(栗原市)【2箇所】
小高川水系川房川(南相馬市)
夏井川水系夏井川(いわき市)【5箇所】
北上川水系荒川(栗原市) 北上川水系石貝川(登米市)
久慈川水系久慈川(常陸大宮市)
久慈川水系浅川(常陸太田市)
久慈川水系里川(常陸太田市)【2箇所】
阿武隈川水系社川(棚倉町)【3箇所】
信濃川水系魚野川(南魚沼市)
阿武隈川水系斎川(白石市)
阿武隈川水系新川(丸森町)【4箇所】阿武隈川水系内川(丸森町)【10箇所】
阿武隈川水系五福谷川(丸森町)【4箇所】
阿武隈川水系半田川(角田市)阿武隈川水系高倉川(角田市)
鳴瀬川水系身洗川(大和町)
鳴瀬川水系小西川(大和町)
鳴瀬川水系名蓋川(大崎市)【2箇所】
北上川水系熊谷川(栗原市)
利根川水系荒井川(鹿沼市)
阿武隈川水系阿武隈川(鏡石町)【2箇所】阿武隈川水系阿武隈川(玉川村)
北上川水系富士川(石巻市)北上川水系水沼川(石巻市)
真野川水系上真野川(南相馬市)
新田川水系水無川(南相馬市)
信濃川水系麻績川(麻績村)【2箇所】
利根川水系永野川(栃木市)【6箇所】
那珂川水系荒川(那須烏山市)【3箇所】
阿武隈川水系藤田川(郡山市)
北上川水系瀬峰川(栗原市)
阿武隈川水系鈴川(鏡石町)【2箇所】鮫川水系鮫川(いわき市)
阿武隈川水系谷田川(郡山市)【2箇所】
鳴瀬川水系名蓋川(加美町)
阿武隈川水系佐久間川(桑折町)
阿武隈川水系社川(石川町)阿武隈川水系社川(浅川町)【3箇所】
阿武隈川水系藤野川(白河市)
夏井川水系好間川(いわき市)
信濃川水系皿川(飯山市)
那珂川水中川(矢板市)【3箇所】
那珂川水系内川(さくら市)
那珂川水系百村川(大田原市)
利根川水系新川(下野市)
信濃川水系千曲川(長野市)
信濃川水系志賀川(佐久市)
信濃川水系滑津川(佐久市)
速報版(R1.11.13時点)
15
埼玉県、群馬県、茨城県、栃木県内で 初に大雨特別警報を発表した時刻からすべての大雨特別警報を解除した時刻まで
10/1215:30
10/132:20
※各観測所の水位の状況に応じて、洪水予報を発表
大河川における降雨の流出・流量の伝播(利根川の例)
○降雨が河川に流出するまでには時間がかかるため、大河川では台風が過ぎ去った以降も警戒が必要。
○今回の台風19号においても、利根川では、中上流部での大の降雨を記録してから、下流部の河川流量が 大になって も危険になるまでに、約1日程度かかっている。
181.45k130.39k
85.3k 40.08k
0
10
20
30
10/11 1時
10/11 4時
10/11 7時
10/11 10
時
10/11 13
時
10/11 16
時
10/11 19
時
10/11 22
時
10/12 1時
10/12 4時
10/12 7時
10/12 10
時
10/12 13
時
10/12 16
時
10/12 19
時
10/12 22
時
10/13 1時
10/13 4時
10/13 7時
10/13 10
時
10/13 13
時
10/13 16
時
10/13 19
時
雨量(八斗島)
15
16
速報版(R1.10.24時点)
○各地方整備局等TEC-FORCEが、東北、関東、北陸地方の被災地で活動中【TEC-FORCE】 743人を派遣 (リエゾン、先遣班、応急対策班、被災状況調査班、防災ヘリ、航空測量、高度技術指導班 等)
【災害対策用機械】 403台を出動 (排水ポンプ車、照明車、衛星通信車、散水車、路面清掃車 等)
10月23日 長野県長野市におけるドローンによる被災状況調査【北陸地整・砂防班】
10月23日 報道向けブリーフィングにて道路啓開状況の説明【東北地整・災害対策室】
10月23日 宮城県大崎市の道路啓開状況の確認・指導【中国地整・高度技術指導班】
10月23日 神奈川県真鶴町における道路施設の被災状況調査【四国地整・道路班】
【派遣人数 のべ 8,810人・日派遣】
10月23日 宮城県丸森町における散水車による路面清掃【近畿地整・道路清掃班】
10月23日 宮城県丸森町における給水支援の状況【北海道開発局・応急対策班】
TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の活動状況
17
TEC-FORCE(緊急災害対策派遣隊)の活動状況
○創設以来106の災害に、のべ約10万人・日を越える隊員を派遣。(令和元年11月)

2019/12/6
4
18
河川情報(水文観測)
レーダ雨量観測所中継局
河川事務所
警報表示板
気象台
地上雨量観測所
水位・流量観測所
災害対策本部
19
河川における水文観測の状況
所轄雨量
観測所水位
観測所
水管理・国土保全局 2,315 1,970
気象庁 1,299 -
都道府県及び水機構 5,154 4,782
合計 8,768 6,752
川の防災情報において情報配信している観測所数と観測頻度(2019.3時点)
観測種目 観測頻度
地上雨量観測
・10分間隔※都道府県の観測所及び国の一部観測所は
通常1時間毎、降雨があった場合に10分間隔
レーダ雨量観測・常時観測
観測結果をXRAINとして1分周期で配信
水位観測・10分間隔※都道府県の観測所及び国の一部観測所は
通常1時間毎、水位が閾値を超えた場合に10分間隔
流量観測・低水観測:年間36回以上・高水観測:年間10洪水程度
観測種目 観測施設の配置
地上雨量観測・均一の降雨状況を示す地域に1観測所・おおむね50km2に1観測所
レーダ雨量観測・Cバンド:半径120kmが定量観測範囲・Xバンド:半径60kmが定量観測範囲
水位観測流量観測
・河川整備計画、水資源開発計画のための基準点として、永続観測が必要な地点・洪水予報や水防警報等のために必要な地点・河川の流出特性を把握する上で重要な地点
観測施設の配置
水位計のほとんどない中小河川で人的被害が多く発生。■ 2016.8台風10号 小本川(岩手県岩泉町) 21名
⾼齢者グループホーム
岩泉町役場
⽔位観測所
⽔位計設置箇所より上流遺体発⾒現場
⾼齢者グループホーム
20
頻発する中小河川の水害
○初期コストの低減(洪⽔時のみの⽔位観測により、機器の⼩型化や電池及び通信機器等の技術開発によるコスト低減)(機器設置費⽤は、100万円/台以下)○⻑期間メンテナンスフリー(無給電で5年以上稼働)○維持管理コストの低減(洪⽔時のみに特化した⽔位観測によりデータ量を低減し、IoT技術とあわせ通信コストを縮減)○省スペース(⼩型化)(橋梁等へ容易に設置が可能)
⼩野川(⼤分県⽇⽥市)
危機管理型⽔位計
桂川(京都市伏⾒区)
従来型の⽔位計 危機管理型⽔位計
21
危機管理型水位計
②リアルタイムの河川⽔位に対応して表⽰の⾊が変化し、危険度がわかります。
③河川カメラのアイコンを選択することで河川の状況が簡単にみられます。
①危機管理型⽔位計に加え、通常⽔位計や河川カメラが同⼀画⾯に表⽰されます。
(イメージ)
水位情報は、河川カメラ情報と一体的に「川の水位情報」サイトで情報を提供。また、水位情報は、危険度に応じて変化。
https://k.river.go.jp/ (パソコン・スマートフォン共通)
■3つの特徴的な機能
(イメージ)
危機管理型⽔位計
通常⽔位計
河川カメラ氾濫危険⽔位
避難判断⽔位
22
水位情報の提供
開発スケジュール
フェーズ2︓開発チーム結成・事業計画書作成
(2018年6⽉)
フェーズ3︓機器開発・フィールド提供(2018年8⽉)
フェーズ4︓現場実証(2018年9⽉〜11⽉)
フェーズ5︓実装化(現場への導⼊等)
フェーズ1︓ピッチイベント(2018年5⽉)
近年の豪雨災害の課題として、洪水の危険性が十分に伝わらず、的確な避難行動につながっていない。
機能を限定した低コストな簡易カメラで多くの地点で洪水状況を確認
これまでの河川監視カメラ・ ⾼画質映像(FHD画質)・ 夜間監視にも対応(超⾼感度撮影等)・ ズーム・⾸振り機能、ワイパー搭載・ 事務所等で常時監視可能 等・ カメラ本体350万円程度
イメージ
簡易型河川監視カメラ(無線式)電源・通信が確保できない箇所でも設置可能なカメラ
【主な特徴】・ 商⽤電源がない場所でも太陽電池等で稼働
・ 無線通信により、連続的な静⽌画を伝送・ 夜間でも撮影可能(⽉明かり程度)・ 定点撮影(ズーム、⾸振り機能なし)・ インターネット経由で閲覧可能・ カメラ本体30万円以下
23
簡易型河川監視カメラの開発

2019/12/6
5
■背景
電波流速計測法
■流量観測の無人化・自動化技術開発
■今後のスケジュール令和元年7月~ 現場実証開始令和3年度以降 現場実装予定
画像処理型流速計測法
現在、洪水時の流量観測は、浮子観測を基本としているが、近年、洪水が激甚化する中で、観測員が待避を余儀なくされ観測が困難となる事案が頻発。また、観測が昼夜、長時間に及ぶため、人員確保も課題。このため、洪水時の流量観測の無人化、自動化の技術開発を推進。
現在の浮子を用いた流量観測( 低5人程度の観測員が必要)
渡月橋浮子投下位置
溢水
溢水
浮子観測では、作業が長期化した場合、交代要員が必要。
2013年台風18号では、桂川の氾濫により観測員が退避。
24
洪水時の流量観測の無人化・自動化
ステージ
観 測 河道形状
洪水予測
巡視 点検
雨量 水位 流量 平常時 災害時 平常時 災害時
0 普通観測
普通観測
浮子観測
横断測量
(1次元)
洪水予報河川
巡視車 巡視車 徒歩(経験値)
徒歩(経験値)
1 Cバンドレーダー
自動水位計
(テレ)
自動観測(有人)
航空測量
(2次元)
水害リスクライン(1級国)
ドローン(有人)
ドローン(有人)
徒歩(基準化)
徒歩(基準化)
2 Xバンドレーダー
・CバンドMP化
危機管理型水位計
自動観測(無人)
ドローン等
(3次元)
水害リスクライン(1級県)
ドローン(自動化)
ドローン(自動化)
ドローン(有人)
ドローン(有人)
3 衛星+水位・流量機器統合
衛星 水害リスクライン(2級県)
衛星 ドローン(自動化)
・衛星
面
点
到達点 開発中・見込み
革新P
革新P 革新P研究開発公募
研究開発公募
25
河川情報の充実イメージ
【出典】情報通信白書令和元年版(総務省)
26
情報通信環境の急速な発展
1G 2G 3G 4G
音声通話 +メール +カメラ+インターネット +動画+ブラウジング
5G
27
ビッグデータと人工知能(AI)による超スマート社会
【出典】令和元年版情報通信白書(総務省)
AIが自ら学び、考えて判断する「深層学習」
【出典】令和元年版 国土交通白書(国土交通省)
計算機処理速度の高速化とAI技術
クラウドコンピューティングとビッグデータ
世界全体で撮影された写真の枚数の推移
世界中の人が情報を発信
13,000億枚/年(2017年)
河川の特徴
H18.8撮影
H19.5撮影
○河川は自然公物⇒時に急激に変化する長大な河川を日々管理○従来の「熟練技術者の目」による管理+ICT,IoT技術を活用しデータを重視した河川管理○革新的河川技術プロジェクトを通じて、河川管理においてSociety5.0を具現化
縦横断測量(5年に1回、200mピッチ)
平常時巡視・点検(週2〜3回)
河川維持管理DB
⽔⽂観測
従来の管理⼿法■閉塞する河道
約1年で⼤きく変化
⾰新的河川技術プロジェクト 等
三次元点群データ(三次元測量)
危機管理型⽔位計(センサー網の増強)
タブレット端末で巡視結果や点検内容を記録しデータベース化
グリーンレーザーを搭載したドローンでの測量(数百点/㎡)
IoT技術を活⽤した洪⽔時の計測に特化した低コスト(従来の1/10)な⽔位計による⽔位観測
出⽔時現場状況確認
豊富な経験をもつ熟練技術者が実施
時間的、空間的な密度は⾼くない
出⽔時に実施する⾼⽔観測は危険を伴う
強⾵時はヘリは⾶べない。H23紀伊半島豪⾬では2⽇間⾶べず。
全天候型ドローン
台⾵通過後、天候の回復を待たずに強⾵下でも状況把握が可能
出典:河川情報センター
ノウハウの蓄積
可視化
ビッグデータ化
迅速化
<河川管理においてSociety5.0を具現化>
ICT、IoT技術を活用した新たな河川管理へ 河川巡視の高度化
29
巡視方法:パトロール車による目視巡視記 録: 現地で作業員が記録し、事務所等でデータを整理異常発見: 職員が経験により判断そ の 他:河岸や車の進入が困難な箇所は徒歩や船で巡視
河川巡視(目視) ドローンを活用した河川巡視(画像AI)
巡視方法:搭載したカメラによる監視記 録:監視から記録までを自動化異常発見:画像解析、AI技術により自動抽出そ の 他:堤防を含む河道空間をドローンによる巡視を実施
ドローン計測をもとに異常・変状箇所の把握までを自動化
洪水前 洪水後
<期待される効果>
監視・記録、異常発見までを自動化し、河川巡視の高度化、効率化が可能。
○洪水による河道の変化を定量的に把握
○日々の巡視では変化を捉えにくい土砂移動や樹木の変化を定量的に把握
○施設の損傷等の経年的変化を定量的に把握
○人が近づきにくい部分や危険箇所の状況を容易かつ安全に把握

2019/12/6
6
30
住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト
本プロジェクトでは、情報を発信する行政と情報を伝えるマスメディア、ネットメディアの関係者等が「水防災意識社会」を構成する一員として、それぞれが有する特性を活かした対応策、連携策を検討し、住民自らの行動に結びつく情報の提供・共有方法を充実させる6つの連携プロジェクトをとりまとめ実行する。
〇プロジェクト参加団体
<マスメディア>日本放送協会(NHK)、一般社団法人日本民間放送連盟一般社団法人日本ケーブルテレビ連盟NPO法人気象キャスターネットワークエフエム東京全国地方新聞社連合会
一般財団法人道路交通情報通信システムセンター(VICS)
<ネットメディア>LINE株式会社、Twitter Japan株式会社グーグル合同会社、ヤフー株式会社NTTドコモ株式会社、KDDI株式会社ソフトバンク株式会社
<行政関連団体>一般財団法人マルチメディア振興センター(Lアラート)
<市町村関係者>新潟県見附市
<地域の防災活動を支援する団体>常総市防災士連絡協議会
<行政>国土交通省水管理・国土保全局、道路局気象庁
A:災害情報単純化プロジェクト ~災害情報の一元化・単純化による分かりやすさの追求~
水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成、情報の「ワンフレーズマルチキャスト」の推進、気象キャスター等との連携による災害情報用語・表現改善点検
課題1 より分かりやすい情報提供のあり方は
課題3 情報弱者に水害・土砂災害情報を伝える方法とは
課題2 住民に切迫感を伝えるために何ができるか
〇住民自らの行動に結びつける新たな6つの連携プロジェクト~受け身の個人から行動する個人へ~
上記課題を具体化させるために
第1回全体会議(平成30年10月4日)
F:地域コミュニティー避難促進プロジェクト~地域コミュニティーの防災力の強化と情報弱者へのアプローチ~登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援「ふるさとプッシュ」の提供、「避難インフルエンサー(災害時避難行動リーダー)」への情報提供支援
E:災害情報メディア連携プロジェクト~災害情報の入手を容易にするためのメディア連携の促進~テレビ・ラジオ・新聞からのネットへの誘導(二次元コード等)、ハッシュタグの共通使用、公式アカウントのSNSを活用した情報拡散
B:災害情報我がことプロジェクト~災害情報のローカライズの促進と個人カスタマイズ化の実現~
地域防災コラボチャンネル(CATV☓ローカルFM)、新聞からのハザードマップへの誘導、マイ・ページ機能の導入、テレビ、ラジオ、ネットメディア等が連携した「マイ・タイムライン」普及
C:災害リアリティー伝達プロジェクト~画像情報の活用や専門家からの情報発信など切迫感とリアリティーの追求~河川監視カメラ画像の積極的な配信、専門家による災害情報の解説、
ETC2.0やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化
D:災害時の意識転換プロジェクト~災害モードへの個々の意識を切り替えさせるトリガー情報の発信~住民自らの避難行動のためのトリガー情報の明確化、緊急速報メールの配信文例の統一化
受け身の個人行動する個人
へ
避難決断
誘導(二次元コード、共通
ハッシュタグ等)
個人カスタマイズ
ブロードキャスト型
従来 強化
公式アカウントで情報発信
気象・水害・土砂災害情報A:災害情報単純化プロジェクト 水害・土砂災害情報統合ポータルサイト、情報の「ワンフレーズ・マルチキャスト」の推進等
緊急速報メール 等
(緊急速報メールの配信文例の統一化 等)
ネット情報
プル型
避難インフルエンサー
E:災害情報メディア連携プロジェクト
F:地域コミュニティ避難促進プロジェクト
C:災害リアリティー伝達プロジェクト
専門家の解説切迫したカメラ映像
防災コラボチャンネル(CATV☓ローカルFM)
新聞(ハザードマップ掲載等)
B:災害情報我がことプロジェクト
D:災害時の意識転換プロジェクト プッシュ型(気付き)
TV・ラジオ・CATV等
防災マイ・ページマイ・タイムライン等
B:災害情報我がことプロジェクト
31
住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト
住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト
マイ・ページ ~一人一人が必要とする情報の提供へ~
一人一人が必要な地域防災情報を一覧表示できる「マイ・ページ」機能を導入し、災害発生時の速やかな行動に結びつける。
これまで情報発信者がそれぞれ提供してきた災害情報をひとまとめで確認できるよう、気象情報、水害・土砂災害情報および災害発生情報等を一元的に集約したポータルサイトを作成
水害・土砂災害情報統合ポータルサイトの作成
各リンク先
リスク情報
河川情報 気象情報
被害情報 ライブ情報
避難情報
ダム情報土砂災害情報
コミュニティーFM等のラジオ放送からの音声放送や国土交通省の河川監視カメラ映像とのコラボレーション放送により、より身近な地域の防災情報を住民に届ける。
地域防災コラボチャンネルの普及促進
ケーブルテレビ局はLアラート等
を用い情報配信
国交省からの河川監視カメラ
映像配信
音声放送
二次元コード ・水災害について豊富な知見を有する専門家
・マイ・タイムラインの進め方をサポートする人材(マイ・タイムラインリーダー等)
避難行動に必要な情報の例
「マイ・タイムライン」
○ 避難行動を判断する時に
有効な情報
・台風・降雨・河川・避難情報等
○ 情報を知る手段
・テレビ、ラジオ、Webサイト、
スマートフォン
○ 地区の特性
○ 過去の水害
○ 地形の特徴
○ 最近の雨の降り方と傾向
○ 浸水想定
テレビ、ラジオ、ネットメディアと連携
・検討の手引き・作成支援ツール
等を共有
知る
気づく
考える
○マイ・タイムラインの作成方法
取組・支援
テレビ、ラジオ、ネットメディア等と連携した「マイ・タイムライン」の普及促進
32
住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト
33
スマートフォン、PCによる閲覧
テレビ放送(データ放送含む)
河川監視カメラ(増強)河川監視カメラ(既設)
浸水想定区域
インターネットライブチャンネル等を活用した河川監視カメラ画像配信
エリアメール配信文基本構造
・水害・土砂災害に関する情報発信についての文例を整理し、統一化・簡素化を図る
発信者によって配信内容や表現が統一されてなく、分かりにくい
配信文の統一化・簡素化
・文章が長く、真に必要な情報が伝わりにくい・緊急性が低い情報を配信している例がある 等
・文章を簡潔・明瞭化
件名:河川氾濫のおそれ
本文:○○川の○○(○○市○○)付近で水位が上昇し、避難勧告等の目安となる「氾濫危険水位」に到達しました。堤防が壊れるなどにより浸水のおそれがあります。防災無線、テレビ等で自治体の情報を確認し、各自安全確保を図るなど、適切な防災行動をとってください。本通知は、○○地方整備局より浸水のおそれのある市町村に配信しており、対象地域周辺においても受信する場合があります。
a.ヘッダー情報(レベル表示)
b.発信者
c.発令内容
d.理由
1.発令情報
2.発令時間
3.対象地域
1.何が
1.いつ
2.誰が
3.何を
4.どこで
5.どのように
e.行動要請
f.その他
河川監視カメラ画像の提供によるリアリティーのある災害情報の積極的な配信
○ETC2.0による更なる防災情報提供 (一般道における拡充)・画像情報、アンダーパス冠水情報
○VICSによる更なる防災情報提供の検討(走行時に注意するエリアの地図上表示)
○車両プローブ情報を活用した官民連携による通れるマップ情報の強化○道の駅や交通結節点における情報提供の強化○路上変圧器を活用したデジタルサイネージによる情報提供 など
ナビによる
大雨エリアの提供
広島市・呉市周辺
通れるマップ
道の駅「たけはら」
(広島県竹原市)
デジタルサイネージ
設置イメージ
情報提供
イメージ
○km先 冠水通行止め
など
ETC2.0やデジタルサイネージ等を活用した道路利用者への情報提供の強化
国土交通省職員など普段現場で災害対応に当たっている専門家がリアルタイムの状況をテレビやラジオなどのメディアで解説し、状況の切迫性を直接住民に伝える。
水害・土砂災害情報を適切に伝えるため専門家による解説を充実
緊急速報メールの配信文例の統一
国土交通省職員による解説
住民自らの行動に結びつく水害・土砂災害ハザード・リスク情報共有プロジェクト
34
二次元コードをテレビ画面等に掲載し、住民が容易にネット上の災害情報ページにアクセスして必要な情報をシームレスに取得できる環境を構築
テレビ等に二次元コードを掲載し、ハザードマップなどの詳細ページへ誘導
ハザードマップサイト
ポータルサイト
河川水位や河川カメラ情報
誘導
二次元コード
登録型のプッシュ型メール配信システム
▼対象者・親・祖父母・叔父叔母 等
▼対象者の住所
▼防災情報選択・避難判断水位・氾濫危険水位・避難指示 等
ふるさとプッシュ!
子へのメール
自分が生まれたときの母親との写真等も登録可
発災時
子 登録
・あなたの親が住む地域の○○川の水位が避難判断水位に達しました。(参考)ハザードマップでは、あなたの親の住む地域の浸水深は約5mです。
親
避難の声かけ電話
避難へテレフォン・ネットAI
サービスの活用
マイ・
タイムラインの確認
登録情報
一人暮らしの親等が住む地域の水位情報や浸水リスクを、離れて暮らす子供等親族に通知する「逃げなきゃコール」を推進
テレビ等のブロードキャストメディアからネットメディアへの誘導 登録型のプッシュ型メールシステムによる高齢者避難支援「逃げなきゃコール」
(例)小学校での水防災学習等の推進⇒水防災教育で学習した児童が家庭内や将来の「避難インフルエンサー」候補となることを期待
・災害や避難に関する情報への理解を促すため、「避難インフルエンサー」に対して勉強会を実施
・「避難インフルエンサー」と自治体が連携し、災害時における地域の円滑な避難に向けた意見交換会や避難訓練等を実施
○「避難インフルエンサー」育成・支援策
平常時
・「避難インフルエンサー」からの情報、地域の連携・協働による円滑な避難
災害時
※「避難インフルエンサー(災害時避難行動リーダー)」とは、災害情報を正しく理解し、発信できる人・信頼される人で、災害時にはリーダーとなって高齢者を含む周囲の人たちに情報を拡散させることで、避難に対して大きな影響を与える人。
○地域の大人や児童、関係機関による避難訓練
国、都道府県、市町村、メディア
避難インフルエンサー
連携・協働し、避難
○ダム下流住民及び関係機関への説明
災害情報伝達
個人
個人
個人
個人
情報拡散・行動
支援
「避難インフルエンサー※」となる人づくり
行政機関によるSNS公式アカウントを通じた情報発信の強化
SNS上の公式アカウントを積極的に活用した情報発信により信頼性の高い災害情報を利用者にリアルタイムで提供SNSメディアとの連携により行政職員に対する研修等を実施し、より効果的な公式アカウントの運営を促進
研修会の実施Twitterアカウント
LINEアカウント
“気象”ד水害・土砂災害”情報マルチモニタ
〇気象情報、水害・土砂災害情報および災害発生情報等をパソコンやスマートフォンで一覧閲覧が可能。
リアルタイムの川の画像 リアルタイムの川の水位
パソコン、スマートフォン:https://www.river.go.jp/portal/
二次元コード 洪水予報の発表地域 放流しているダムの状況洪水警報の
危険度分布状況
気象警報・注意報の
発表状況
リアルタイムの
レーダ雨量の状況
浸水の危険性が
高まっている河川
土砂災害の危険度分布状況
地域選択が可能・全国・北海道・東北・関東・北陸・中部・近畿・中国・四国・九州・沖縄
35

2019/12/6
7
川の防災情報【英語版(試行版)】サイト
近年急増する外国人観光客や在日外国人などを含めた洪水被害からの逃げ遅れゼロを目指すため、河川の水位情報やリアルタイムのカメラ画像などから洪水の危険性を把握できる「川の防災情報 英語版【試行版】」を配信。https://www.river.go.jp/e/
川の現況に関する情報
【河川横断図】川の⽔位とまち側の地盤の⾼低差を断⾯図で表⽰
【ハイドログラフ】
川の⽔位の時間的な
変化をグラフで表⽰
【河川状況カメラ画像】河川の状況が把握可能なライブ映像を表⽰
川の⽔位に関する情報
【XRAIN】現在の⾬域を表⽰
【浸⽔想定区域図】場所の浸⽔深を表⽰
ベースマップ(表⽰切替)
洪⽔リスクをプッシュで通知︕
【平時の表⽰】
現在地(GPS機能が動いている場合)やタップした場所(画⾯中央)から、2Km以内に避難判断⽔位を超過している観測所があれば、ポップアップで通知します。
近隣の⽔位計で
避難判断⽔位を超過 アクセスはこちらから
https://www.river.go.jp/e/(パソコン・スマートフォン共通)
36 37
水害リスクライン
水位観測所
7月1日2時50分
氾濫の切迫性に応じて、左右岸別、上下流連続的に色分けして表示
6時間先まで水位予測(市町村向け)
〇レーダ雨量計による面的な降雨量と観測所地点の実測水位をもとに、河川の上下流連続的な水位をリアルタイムで計算
〇計算水位と堤防の高さとを比較し、危険度を色で表示する「水害リスクライン」により、災害の切迫感をわかりやすく伝える取組を推進
災害時の情報収集の迅速化
ドローンやウエアブルカメラにより、被害状況等をリアルタイムで把握し、応急対応の迅速化を図る。
38
洪水災害多発時代に求められる河川情報のあり方
39
〇 気候変動の影響により洪水災害が激甚化・頻発化〇 情報通信技術の目覚ましい進歩による産業構造、生活スタイルの変化〇 人口減少・高齢化による社会構造の変化
〇 気候変動を見据えた治水計画の見直しと減災対策の検討・激甚化する洪水にも対応した水文観測の高度化・水文データと気象データ等に基づく将来気候変動予測の向上・流域全体での水災害リスク評価
〇 河川整備による事前防災の促進と、既存の河道と施設の 大限活用・河川、施設のモニタリングの高度化・省力化・洪水時の河道、堤防等のリアルタイム監視と安全度評価・施設操作の 適化・自動化
〇 住民の命を守るための真の避難行動につながる情報発信・洪水の危険度をわかりやすく伝える表現手法等の向上・災害時における確実な情報伝達手段の確保・早期避難のためのリアルタイム洪水予測、浸水予測手法の向上・水害発生時の情報収集や応急対応の迅速化
洪水災害多発時代
河川情報のあり方