量子暗号通信システムに関する 世界的な動向調査報 …2005情財第0689号 2007年4月 量子暗号通信システムに関する 世界的な動向調査報告書
世界の農林水産 2010年冬号 (通巻821号) · 2017-11-28 ·...
Transcript of 世界の農林水産 2010年冬号 (通巻821号) · 2017-11-28 ·...

Winter2010
World’s Agriculture, Forestry And FisheriesFAO News No.821
特 集
長引く危機に直面する国々――22ヵ国に重点的な取り組みが必要
R e p o r t 1
食品安全のためのEMPRES――FAOの緊急予防システム
R e p o r t 2
飢餓に対して結束する

2010年10月16日 世界食料デー
飢餓に対して結束する
www.fao.org
LOJ/10.09/200
WWW. BILLIONHUNGRY.ORG/JP飢餓を終焉させる申し立てに署名を 国際連合食糧農業機関(FAO)
398-009-312.indd 1 10/09/24 16:51

長引く危機に直面する国々
特 集
――22ヵ国に重点的な取り組みが必要
今年10月、FAOは最新の世界の飢餓人口を9億2,500万人と発表した。現在、特にアフリカを中心とする22ヵ国で、危機が長期化している。
干ばつに見舞われたケニアで、栄養不足の子どもを抱える女性。©FAO / Ami Vitale
Countries in
Protracted Crises
03
WIN
TE
R 2
01
0

1996年の世界食料サミットで、当時8億人とされた世界の飢餓人口を半減させる目標が掲げられたにもかかわらず、FAOが2010年に発表した世界の飢餓人口は9億2,500万人にのぼる。食料価格高騰や世界経済危機の影響を受けた昨年と比べると若干減っているものの、この数字が依然として受け入れがたい水準であることに変わりはない。こうしたなか、FAOは現在特に22ヵ国が「長引く危機」に直面しているとし、飢餓に関する年次報告書「世界の食料不安の現状 (SOFI)20
10」の中で、こうした国々の特徴と対策を論じている。本稿では、その一部を紹介する。
長引く危機にある国々の共通点長引く危機にある国に関する単純な定義はない。長引く危機そのものは、「国民のかなりの割合が、長期にわたり、死や疾病、生計の崩壊に対して非常に脆弱な状態にある環境。対応能力や、国民に対する脅威を緩和する、あるいは適切な水準の保護を提供する能力が制限されている国では、こうした環境の統治は、概して非常に脆弱である」と定義されている。食料不安は、長引く危機の最も一般的な兆候である。
■
長引く危機の状況は一様ではないが、次のような特徴のいくつか(必ずしもすべてではない)が共通していることがある。■ 持続時間/期間:例えばアフガニスタン、 ソマリア、スーダンの各国では、1980年 代以降、30年近くにわたって何らかの危 機が続いている。■ 紛争:紛争は一般的な特徴であるが、紛 争のみが長引く危機を生み出すわけではな い。長引く危機にある国のなかには、明白 な軍事紛争が主要な要因とはなっていな
い、もしくは要因となっているのが国の一 部にとどまる国もある(エチオピアやウガ ン
ダなど)。■ 脆弱な統治/脆弱な行政:これは単に抗
し難い制約に対するキャパシティが不足し ている可能性もあるが、市民の権利を守る 政治的意思の欠如を反映している可能性 もある。■ 持続的でない生活方式・食料安全保障の 乏しい成果:これらは、栄養不足や高い 死亡率の一因となる。一時的であれ慢性 的であれ、食料不安は長引く危機を増大 させる傾向がある。しかし、持続的でない 生活方式は長引く危機の兆候であるだけ
ではない。生活方式の持続性の悪化は、
紛争を招く要因にもなりえ、それがひいて は長引く危機をもたらす可能性もある。■ 地域の機構・制度の破綻:これは国家の 脆弱性によって悪化することが多い。比較 的持続的な従来の機構・制度が、しばし ば長引く危機の下で悪化することがあるが、 国が運営する代替案がそれを補完すること はまれである。
長引く危機にある国々の定義上記のことから、長引く危機の定義がいくらか流動的であることは明らかである。長引く危機を特定する単独の特徴はなく、前述した特徴の1つあるいは複数が欠けているからといって、必ずしもある国/地域が長引く危機にないということを意味するわけではない。
SOFI2010では、ある国が長引く危機にあるかどうかを確定するために、下記の測定可能な3つの基準を用いる。■ 危機の期間:危機の持続期間に関する基 準は、ある国が、対外援助を必要とする
危機(自然災害、人的危機/災害、あるいは 双方の併発)を報告した年数に基づいてい る。この情報はFAOの世界食料農業情報 早期警報システム(GIEWS)を通じ国連の 全加盟国に対して毎年照合される。この
GIEWSのリストに2001年から2010年の 間に8年以上(最新の危機を把握するため)、 もしくは1996年から2010年の間に12年 以上掲載された国は、長引く危機にあると
SOFI2010の発表記者会見。©FAO / Giulio Napolitano
高温と干ばつの被害を受けたトウモロコシの苗(エチオピア、20
10年6月)。©FAO / Giulio Napolitano
04
WIN
TE
R 2
01
0

みなされる。■ 援助の流れ:第2の基準は、その国が受 けている人道支援額の総支援額に対する 割合である。2000年以降に、政府開発 援助(ODA)の10%以上を人道支援が占 める場合、その国は長引く危機にあるとみ なされる。■ 経済状態・食料安全保障の状況:第3の 基準は、FAOの低所得食料不足国(LIFDC)
リストに掲載されていることである。現在、合計22ヵ国がこれら3つの基準をすべて満たしている(表1)。これらの国はすべて、何らかの人的緊急事態(紛争や政治的危機など)が発生した国である。このうち16ヵ国は、ある時期に単独、もしくは人的緊急事態を伴う自然災害を経験した。また15ヵ国が、少なくとも1度、自然災害と人的緊急事態の併発を経験した。
■
長引く危機の状況には、ある国の特定の地
理的領域に限定され、国民全体に影響を及ぼさないものもある。例えばウガンダは長引く危機リストに掲載されているが、この危機は同国の北部と北東部に限定されている。ヨルダン川西岸やガザ地区のような地域も、長引く危機にあるとみなすことができる。長引く危機にあると思われるものの、リストに掲載されていない国の事例もある。例えばスリランカは、島北部の大部分に打撃を与え、国民の多くを退去させた長期にわたる内戦から脱しつつある。しかし、同国がGIEWSのリストに掲載されたのは過去10年間のうち7
年間のみで、対象基準からわずかに外れている。このように、危機対応能力を含め、長引く危機にある国々にはかなりのばらつきがある。政府が機能している諸国もあれば、現在、国家が脆弱あるいは破綻したとみなされている国もある。援助の流れから見ると、長引く危機にある
2003年の洪水で被害を受けた井戸から泥を取り除く農民(スーダン)。©FAO / Antonello Proto
アフガニスタン 5 10 15 20
アンゴラ 1 11 12 30
ブルンジ 14 1 15 32
中央アフリカ 8 8 13
チャド 2 4 3 9 23
コンゴ共和国 13 13 22
コートジボワール 9 9 15
北朝鮮 6 3 6 15 47
コンゴ民主共和国 15 15 27
エリトリア 2 3 10 15 30
エチオピア 2 2 11 15 21
ギニア 10 10 16
ハイチ 11 1 3 15 11
イラク 4 11 15 14
ケニア 9 3 12 14
リベリア 14 1 15 33
シエラレオネ 15 15 19
ソマリア 15 15 64
スーダン 5 10 15 62
タジキスタン 3 8 11 13
ウガンダ 4 10 14 10
ジンバブエ 2 3 5 10 31
国
自然災害のみ 人的災害のみ 自然災害と人的災害の併発
災害数計
1996-2010
ODA合計に対する人道支援の割合2000-2008年
%年数
表1―長引く危機にある国々:危機の類型(1996-2010年)および人道支援の割合(2000-2008年)
出典:FAO GIEWSおよびDevelopment Initiatives
Countries in
Protracted Crises
長引く危機に直面する国々特 集
05
WIN
TE
R 2
01
0

国々の特徴は、開発支援よりも人道支援の方が支援全体において比較的高い割合を占めていることである。世界的にはODA全体の約10%が人道支援となっているが、長引く危機にある国々においては通常、その割合はかなり高く、ソマリアやスーダンなどでは全体の3分の2にのぼる。人道支援の1人当たりの受給金額も、長引く危機にある22ヵ国ではすべて、開発途上国の平均を上回っている。
食料不安:長引く危機にある国々は特別な事例なのか長引く危機にある国々では、一般的に食料不安が非常に深刻である(表2)。これらの国々における2005年から2007年にかけての栄養不足人口の割合は、最も低いコートジボワールが14%、最も高いコンゴ民主共和国が69%となっている。栄養不足、低体
重人口、5歳未満の死亡率に関する複合データを基に算出された世界飢餓指数は、下はコートジボワールの14.5%(「深刻な飢餓問
題」)から、上はコンゴ民主共和国の39.1%
(「きわめて憂慮すべき飢餓問題」)まで、程度はさまざまである。表2は、長引く危機にある国々では栄養不足人口の割合が平均して他の開発途上国(長引く危機にある国々、中国、インドを除いた場合)に比べて3倍近いことを示している。とはいえ、長引く危機にある国々のすべてにおいて栄養不足の水準が非常に高いわけではなく、危機が特定の地域あるいは地方に限定されている国もある。長引く危機にある国々における栄養不足人口は、約1億6,600万人である。これは世界の栄養不足人口の約20%、中国とインドを除いて計算すると世界合計の3分の1以上を占める。長引く危機にある国々の食料安全保障は、
紛争が終結した地域で、漁業を再開した帰還兵の男性(コンゴ民主共和国)。©FAO / Giulio Napolitano
アフガニスタン na na na 32.8 25.7 na 59.3 8.6
アンゴラ 17.1 7.1 41 14.2 15.8 25.3 50.8 8.6
ブルンジ 7.6 4.7 62 35.0 18.0 38.7 63.1 8.2
中央アフリカ 4.2 1.7 40 24.0 17.2 28.1 44.6 10.5
チャド 10.3 3.8 37 33.9 20.9 31.3 44.8 16.1
コンゴ共和国 3.5 0.5 15 11.8 12.5 15.4 31.2 8.0
コートジボワール 19.7 2.8 14 16.7 12.7 14.5 40.1 8.6
北朝鮮 23.6 7.8 33 17.8 5.5 18.4 44.7 8.7
コンゴ民主共和国 60.8 41.9 69 25.1 16.1 39.1 45.8 14.0
エリトリア 4.6 3.0 64 34.5 7.0 36.5 43.7 14.9
エチオピア 76.6 31.6 41 34.6 11.9 30.8 50.7 12.3
ギニア 9.4 1.6 17 22.5 15.0 18.2 39.3 10.8
ハイチ 9.6 5.5 57 18.9 7.6 28.2 29.7 10.3
イラク na na na 7.1 4.4 na 27.5 5.8
ケニア 36.8 11.2 31 16.5 12.1 20.2 35.8 6.2
リベリア 3.5 1.2 33 20.4 13.3 24.6 39.4 7.8
シエラレオネ 5.3 1.8 35 28.3 26.2 33.8 46.9 10.2
ソマリア na na na 32.8 14.2 na 42.1 13.2
スーダン 39.6 8.8 22 27.0 10.9 19.6 37.9 21.0
タジキスタン 6.6 2.0 30 14.9 6.7 18.5 33.1 8.7
ウガンダ 29.7 6.1 21 16.4 13.0 14.8 38.7 6.3
ジンバブエ 12.5 3.7 30 14.0 9.0 21.0 35.8 7.3
国
平均体重に対する低体重の5歳未満の人口
2002-07
栄養不足人口の割合
2005-07
栄養不足人口
2005-07
総人口
2005-07
5歳未満の死亡率
2007
世界飢餓指数
2009
発育不良※1
2000-07
衰弱※2
1996-07年
%100万人
表2―長引く危機にある国々では食料不安が非常に深刻である
注 na=データなし ※1 身長年齢比の割合 < -2SD(標準偏差) ※2 体重身長費の割合 < -2SD(標準偏差) 出典:FAO、IFPRI、WHO
06
WIN
TE
R 2
01
0

他の開発途上諸国に比べると、6つの重要な食料安全保障指標のうち4つにおいて著しく劣っている。この4つの指標とは、栄養不足人口の割合(FAO)、発育不良人口の割合、5歳未満の子供の死亡率、世界飢餓指数( IF
PRI)である(表3)。■
長引く危機と食料安全保障の成果の関係に
関するさらに詳しい分析では、収入の変化、統治の有効性、汚職抑制、危機にある年数が、栄養不足人口の割合に大きく関連していることが判明した(表4)。これらの要因のほか、教育も、その国の世界飢餓指数に有意に関連している。さらに重要なことは、長引く危機が存在するか否かだけではなく、その国が危機にある年数も肝要であるという点である。
FAOから配布された引換券を持って「種子フェア」に参加する人々。2005年の干ばつとキャッサバモザイク病の被害を受けた農民や、紛争の被害者を対象に行われた(ブルンジ)。©FAO / Giulio Napolitano
栄養不足人口の割合 18.8 31.4 -12.6 1.0-69.0
低体重人口の割合 17.9 19.9 -2.0 1.6-44.6
発育不良人口の割合 35.1 40.2 -5.1 3.7-63.1
衰弱人口の割合 8.2 9.3 -1.1 1.0-22.9
5歳未満の死亡率(%) 7.8 11.9 -4.1 0.7-26.2
世界飢餓指数 16.5 22.3 -5.8 5.2-39.1
従属変数T-検定
長引く危機長引く危機ではない危機
差 範囲
表3―長引く危機にある国々の食料安全保障は、その他の後発開発途上国に比べて著しく劣っている
出典:FAO、IFPRI、WHO注 2005-2007年のデータ* 長引く危機にある国 と々長引く危機にない国 と々の著しい差異 P <0.05(95%)** 長引く危機にある国 と々長引く危機にない国 と々の著しい差異 P <0.01(99%)
**
**
**
*
Countries in
Protracted Crises
長引く危機に直面する国々特 集

ある国が危機にある年数が長ければ長いほど、栄養不足は著しく増加する。
長引く危機への関与:制約と機会長引く危機にある国々の特性は、国際社会の関与を困難にすることがある。これは次の2つの重要な問題と関連している。①開発コミュニティが、長引く危機や、危機と開発プロセスとの関係を認識する方法と、②長引く危機に対する支援の方法(支援構造)である。第1の点に関しては、「開発」は生活の質の段階的改善として捉えられることがある。災害もしくは緊急事態は、この段階を(一時的に)中断するが、危機が終結すれば「正常」な上昇段階に戻ることが期待される(図)。したがって、「災害」「回復」「持続可能な開発」
という用語、原則、関与は互いに関連している。しかし、長引く危機においては、この段階の移行は長期にわたり予測不可能になると思われる。緊急事態の場合のように必ずしも急激に低下するわけではないが、少なくとも長期間にわたって上向きになることもない。
■
第2の問題は第1の問題と密接にかかわっているのだが、長引く危機への関与構造が、ある程度の長期的な改善につながる短期的危機に対する関与構造と、概して似かよっているという点である。しかしながら、大半の長引く危機的状況の性質には明らかに適していない。脆弱な国家状況における取り組みに関する経済協力開発機構(OECD)の最新原則の一部でさえ、長引く危機への関与においては適切であるようには見えない。この結果、長引く危機への関与、特に国際的関与は、直面する問題に十分に適合しておらず、用いられるアプローチは、柔軟性に乏しく、現状変化へ適応することができない。多くの場合、困窮する国の国家機構は長引く危機によって弱体化し、機構の隔絶と、関与の優先事項に関する長引く問題を残している。
The State of Food Insecurity in the World(SOFI) 2010世界の食料不安の現状 2010年報告
世界の飢餓の現状をモニタリングするFAOの年次報告書。20
10年版は、危機が長期化している国々に焦点を当て、その原因と対策を論じます。原文(英語ほか)は下記URLからダウンロードできるほか、FAO寄託図書館(p.32参照)で閲覧が可能です。www.fao.org/docrep/013/
i1683e/i1683e00.htm
FAO 2010年10月発行12ページ A4判 英語ほかISBN:978-92-5-106610-2
出典:P. Walker. 2009. How to think about the future: history, climate change and conflict. Presentation to the Harvard Humanitarian Summit, Cambridge, September 2009.
図─長引く危機は、緊急災害モデルとは 根本的に異なる
時間
生活の質
持続的な危機
開発
災害
Countries in
Protracted Crises
長引く危機に直面する国々特 集
出典:「The State of Food Insecurity in the World 2010」FAO, 2010(pp.12-17より抜粋)
関連ウェブサイト:FAO Hunger:www.fao.org/hunger
収入※1 -0.76 -2.85 収入※1 -0.72 -4.58
教育※2 0.32 1.21 教育※2 -0.36 -2.36
統治の有効性※3 -1.45 -3.63 統治の有効性※3 -0.65 -2.84
汚職抑制※4 1.05 2.79 汚職抑制※4 0.48 2.14
危機にある年数※5 0.38 4.29 危機にある年数※5 0.16 3.14
自由度調整済み決定係数 0.52 自由度調整済み決定係数 0.72(OLS)※6 (OLS)※6
従属変数:栄養不足人口(%) 従属変数:世界飢餓指数
Z(特徴)弾性要因 要因 弾性 Z(特徴)
表4―回帰結果:食料安全保障、人間開発指数、世界ガバナンス指標、長引く危機
出典:FAO、IFPRI、WHO* P <0.05 ** P <0.01※1 人間開発指数(UNDP) ※2 人間開発指数(UNDP)※3 世界ガバナンス指標(世界銀行研究所) ※4 世界ガバナンス指標(世界銀行研究所)※5 FAOのGIEWSの対外人道支援を必要とする国リストに掲載された年数 ※6 最小二乗法
** **
** **
** **
*
** **
** *
08
WIN
TE
R 2
01
0

World’s Agriculture, Forestry And FisheriesFAO News No.821
Winter2010
03 特 集
長引く危機に直面する国々 ――22ヵ国に重点的な取り組みが必要
10 R e p o r t 1
食品安全のためのEMPRES ――FAOの緊急予防システム
16 Report 2
飢餓に対して結束する
20 インターン報告記 大きな視野で捉えて小さなことを積み重ねる重要さ 明治学院大学 法学部政治学科3年 小林 理恵
21 Crop Prospects and Food Situation 穀物見通しと食料事情 2010.9
世界の穀物需給概況/食料危機最新情報
26 FAO水産養殖局とは? 第3回 FAO水産委員会について FAO水産養殖局 上席水産専門官 渡辺 浩幹
30 Food for All FAOの活動にご協力いただいている団体 国際学としてなぜ食を作り、学ぶのか。 作るまでは自然科学で、分配は社会科学で 明治学院大学 国際学部 教授/国際平和研究所 元所長 勝俣 誠
32 FAO寄託図書館のご案内
33 PHOTO JOURNAL 西アフリカの農村部女性への支援 ――National Allianceの活動現場を訪問して FAO日本事務所 企画官 三原 香恵
36 FAOで活躍する日本人 No.22
中近東ってどんなところ? FAO中近東地域事務所 自然資源(水資源)開発/管理担当官 阿部 信也
38 FAO MAP 世界の栄養不足人口 ――ハンガーマップ2010
世界の農林水産FAO News Winter 2010
通巻821号
平成22年12月1日発行(年4回発行)
発行(社)国際農林業協働協会(JAICAF)〒107-0052
東京都港区赤坂8-10-39
赤坂KSAビル3F
Tel:03-5772-7880
Fax:03-5772-7680
E-mail:fao@jaicaf.or.jp
www.jaicaf.or.jp
共同編集国際連合食糧農業機関(FAO)日本事務所www.fao.or.jp
編集:宮道 りか、リンダ・ヤオ(社)国際農林業協働協会編集:森 麻衣子、今井 ちづる
デザイン:岩本 美奈子
本誌と月刊ニュースレター「FAO Newsletter」は、JAICAFの会員にお届けしています。詳しくはJAICAFウェブサイトをご覧ください。
古紙パルプ配合率100%再生紙を使用
09
WIN
TE
R 2
01
0

食品安全のためのEMPRES ――FAOの緊急予防システム
R e p o r t 1
農産物や食品の国境を越えた取引きが増加し、フードチェーンが複雑化するなか、食品安全性を国際的に確保する重要性がますます高まっています。こうした背景のもとにFAOが立ち上げた「食品安全のための緊急予防システム」を紹介します。
スーパーマーケットの肉売り場(ハンガリー)。©FAO / Balint Porneczi
10
WIN
TE
R 2
01
0

世界的な食品安全食料供給が地球規模となりフードチェーンが一層複雑化していることで、食品安全――特に国境を越えて取引きされる食品の安全性――に対する国民の関心が高まっています。汚染された食品が人の健康や農業・食品産業の経済的安定にもたらす影響への意識は、いまや公的機関、食品安全機関の間でも高まっています。
■
最近生じた食品のメラミン汚染による世界的危機では、少なくとも6人が死亡し、30万人が罹患しました。約115種類の食品がメラミンに汚染されました。この危機は人の疾病と死亡、さらに貿易の混乱と関係者の経済的損失という結果をもたらしたのです。
近年の食品安全上の事件メラミン危機は特異なものでありません。世界に衝撃を与えた食品汚染事件は、下記のように近年頻発しています。開発途上国では食品安全上の脅威が非常に大きな課題となっているにもかかわらず、食品安全に関するインフラは多くの場合、構築過程にあり、強力な食品管理システムを有する先進国にも大きな影響を与えています。
■
サルモネラ中毒2009年、米国でピーナッツから発生し、死亡者9人、患者2万2,000人以上と見積もられています。何百種もの産品が影響を受けました。ダイオキシン2008年、ダイオキシンに汚染されたアイルランド豚肉によって、安全許容水準の80-
200倍のレベルの毒性に消費者がさらされました。経済的損失は10億USドル以上と見積もられています。
A型肝炎A型肝炎ウイルスに汚染されたメキシコ産青
ネギによって、2003年、米国内に3名の死者と600人以上の患者が発生し、メキシコ産農産物の市場が閉鎖されました。
緊急事態に対応するフードチェーン・アプローチ国境を越える動物の疾病や植物の病虫害、食品安全緊急事態が近年増加したことで、人の健康だけでなく、生計、食料安全保障、国民経済および世界市場に及ぼす潜在的な影響に対する一般国民の関心が高まりました。こうした問題の発生によって、フードチェーン全体に向けた総合的なアプローチを通じて脅威を取り扱う必要性があるという認識が高まりました。
■
農業生態学的条件の変化や食料生産システムの集約化、そしてこれらのシステムがもたらした世界貿易の拡大によって、動植物の疾病や害虫の発生が、以前と比べさらに遠方かつ急速に発生・拡大し、安全性の損なわれた食品が遠隔地市場の大勢の消費者にまで届く可能性が高まりました。
■
このような状況を背景に、フードチェーンに沿った危機防止と危機管理を目的とした統合的、協働的、合理的なプロセスをFAOの中に構築する計画が進められました。
■
その目的とするところは、越境性の動物疾病、植物害虫および食品安全上の脅威から生じる大規模緊急事態の一層の巨大化・頻発化から生じる問題に対処すること、そして加盟国に緊急事態の防止・対策に対する組織的かつタイムリーな援助を提供することです。こうしたFAOのフードチェーン緊急事態の枠組みのひとつが、すでにある動物衛生と植物衛生のためのEMPRES(緊急予防システム)を補完する「食品安全のためのEMPRES」を構築することでした。
バンコクの屋台(タイ)。©FAO / Dan White
EMPRES
Food Safety
食品安全のためのEMPRESR e p o r t 1
11
WIN
TE
R 2
01
0

食品安全のためのEMPRES食品安全のためのEMPRESの主目的は、食品安全危機を防除することです。その柱となるものは、世界・地域・地方レベルでの食品安全緊急事態に対する早期発見、早期警報と迅速対応です。第1の目標はFAOの持つ比較優位性を活用し、新たに生じる食品安全上の危険を見極める予測的監視(ホライズン・スキャニング)を可能とする国際的プログラムを確立し、加盟国に対して「何を監視し、いかにして新たに生じる食品安全危機を防止し、タイムリーに対応しうる体制整備を整えるか」についての助言を提供することです。
■
食品安全のためのEMPRESは、FAOの栄養・消費者保護部に設置され、以下を主な業務としています。■ 食品供給の安全性と健全性に関わる、人 の健康への潜在的かつ切迫した脅威の源
を特定し、その発生の可能性と結果を評 価する。■ 評価過程で特定されたリスクのうち、行動
が必要とされるリスクを決定し、確実に制 圧するために必要とされる具体的な行動に ついて助言する。■ 利害関係者間の話し合いをサポートし、
効果的な緊急対応への支援に必要とされ る総合的な情報を提供する。■ リスク緩和、現場評価および介入措置(国 家レベル、地域レベルでの防除と封じ込め、検
出と診断、対応体制整備と緊急時対策)の戦 略的分析のための戦略を策定し実行する こと。■ 標準的参照機関ならびに地域の支援単位 およびネットワークとの連携関係を構築・ 維持する。特にFAO / WHO国際食品安 全当局ネットワーク( INFOSAN)と連携する。
EMPRES
Food Safety
食品安全のためのEMPRESR e p o r t 1
トウモロコシを日干しする少女(ハイチ)。©FAO / Giulio Napolitano
食品安全のためのEMPRES長期戦略計画の構成要素
出典:FAO
早期警報 緊急事態予防緊急事態予防 迅速対応
要素1
要素3
要素8
要素2
要素7
早期警報の発令 差し迫った脅威の深刻化を防止すること
迅速な対応処理
ホライズン・スキャニング(予測的監視)の実施
食品安全性上の脅威に関わる早期警報を発するため、
INFOSAN(国際食品安全当局ネットワーク)を連動させる。
短期的、迅速措置によって、食品安全への差し迫った脅威の発生、深刻化、または再発を防止する。
特定された食品安全上の緊急事態への
適時な対応措置の実施。
目立たない兆候や指標の食品安全的視点からの分析的情報収集によって、食品安全への脅威を予測する。
対応体制整備のための手段、助言、業務の提供
すべての活動実施のための広範囲な枠組み
FAOの標準的な食品安全対策事業
キャパシティビルディング・
科学的助言
要素4
要素5
要素6
食品安全上の各種脅威の優先順位付け
不足している知識の充足
予防計画の策定と準備
12
WIN
TE
R 2
01
0

FAOの特別な立場世界の食品供給の安全性を高めるため、また食品安全上の脅威によって生じる社会・経済的損失を最小限に抑えるために、フードチェーン上に存在する脆弱性を早期に特定して、効果的な防止システムを実行に移すことは、世界の食料供給安全保障にとって不可欠です。
■
フードチェーンと食品安全に対する脅威が、性質として世界的規模に広がる場合が非常に多い昨今、FAOは、生産から消費に至るこうした脆弱性を評価し、潜在的な脅威に対する助言と対策を提供する特別な立場にあります。同時に、すべての脅威を予測できるわけではないため、どの国においても、食品安全危機に迅速かつ組織的に対応する適切なメカニズムを持つことが、同様にきわめて重要です。
■
FAOは食品安全関係のプログラムを効果的に実施するに当たり豊富な経験を有しています。本部であれ現場であれ、食品安全問題については世界保健機構(WHO)と強い連携関係を結んでいます。FAOとWHOはともに、食品安全上の危機と脅威に立ち向かうため、国レベルで農業部門と保健部門が協調的に行動できるよう努めています。
■
改善された世界規模の食品安全モニタリング、地域的・制度的連携と調整、強化した国家食品管理システムならびにあらゆる国際的、地域的、国家的レベルでの緊急事態対応体制と対応措置のプランニングはすべて、世界規模の食品安全システムを支え、強力なものとする重要な柱となっています。
出典:「EMPRES Food Safety」FAO, 2010関連ウェブサイト:www.fao.org/agn/agns
EMPRES Food SafetyStrategic Plan食品安全のためのEMPRES長期戦略計画
本稿で紹介した「食品安全のためのEMPRES」の長期戦略計画をさらに具体的に解説した冊子。原文(英語ほか)がFA
O本部のウェブサイトに公開されているほか、JAICAFのウェブサイトで日本語版をご覧いただけます。英語版:www.fao.org/ag/
agn/agns/files/FAO-empres
ENG_reduced.pdf日本語版:www.jaicaf.or.jp/
fao/publication/shoseki_20
10_2.pdf
FAO 2010年7月発行40ページ 18×18cm 英語ほか
FAO本部で行われた第2回世界種子会議の様子。 ©FAO / Giulio Napolitano
13
WIN
TE
R 2
01
0

飢餓に対して結束するR e p o r t 2
2010年10月16日、世界食料デーは30周年を迎えました。この日はFAO設立記念日の65周年にも当たります。今年は、世界の飢餓に対する国・地域そして国際レべルでの闘いにおける取り組みについて認識を高めるため、「飢餓に対して結束する」が世界食料デーのテーマに選ばれました。
ベネズエラの都市農業協同組合の農民。かんがい用のホースを調整する男性(前方)と、レタスの苗代のために土壌の通気を行う男性(後方)。©FAO / Giuseppe Bizzarri
14
WIN
TE
R 2
01
0

「飢餓に対する結束」の動き飢餓に対する結束は、政府や市民社会、民間セクターが、あらゆるレべルで飢餓や極度の貧困、栄養不足を克服するために協働する時に実現されるものです。この協働にあたり、ローマに本部を置く国連機関――FAO、国際農業開発基金( IFAD)、世界食糧計画(WFP)――は、2015年までに飢餓人口を半減させることを求める国連ミレニアム開発目標(MDGs)の第1目標――極度の貧困と飢餓をなくす――の達成に国際的な努力を向ける鍵となる、戦略的な役割を担っています。
■
国連システムとさまざまなプレイヤーが、
FAOの世界食料安全保障委員会(CFS)
に参加しています。CFSは最近改革が行われ、FAOの加盟国だけでなく、IFA
DやWFP、国連事務総長主宰の「世界の食料危機に関するハイレベル・タスクフォース(HLTF)」といった国連機関、さらには食料安全保障や栄養の分野で活動する他の機関が参加しています。
CFSは、市民社会やNGO、そして食料不安の影響を受けるすべての人々の代表、また国際的な農業研究機関、世界銀行、国際通貨基金( IMF)、地域開発銀行、世界貿易機関(WTO)を含んでいるだけでなく、民間企業や慈善団体にも門戸を開こうとしています。CFS
はまた、迅速で情報に基づいた決定を下すことができるよう、現在、食料安全保障と栄養に関する専門家によるハイレベル・パネルから助言を受けています。
■
約30ヵ国において、市民社会組織(CS
O)と政府機関で構成される国内の連帯が積極的に協力し合い、アドボカシーと意識啓発活動に取り組んでいます。先の2010年6月にFAO本部で開催され
た国際的な専門家との協議を受けて、この国内連帯の参加はさらに強化されました。各国の国内連帯は、食料と栄養の安全保障を強化するために拡大されたCFSやHLTFといった国際的な機構に積極的に参加しています。
■
世界食料安全保障サミット(飢餓に関するサミット)が2009年11月に開かれ、地球上から飢えを永遠になくすという1996年の世界食料サミットでの確約を再確認する宣言を採択しました。この宣言は、国レベル・国際レベルでの農業投資の拡大や、農村セクターへの新規投資、公共セクター・民間セクターの関係者と協力して国際的な食料問題への対応を改善すること、そして気候変動が食料安全保障に及ぼす脅威に対応した行動の強化も呼びかけています。
未来を養う農業革命2050年に90億となる人口を養うためには、農業生産を70%増加させる必要があります。土地が希少になっていくなかで、農民は、農地を拡大するのではなく、すでに耕作されている土地からさらに多くの収穫を得ることを求められるのです。しかし、集約的な食料生産はこれまで、農薬と肥料への依存の拡大、水の過剰使用を意味し、その結果、土壌や水資源を劣化させる恐れがありました。そうであってはならない、とFAOは主張します。
■
「飢餓に対して結束する」ことと、「新たな緑の革命」を開始する必要性を結びつけるのはなぜでしょうか? それは、これほど膨大な量の食料を増産するという任務、そしてすべての人がその食料にアクセスできなければならないという目標は、単独の機関やセクターだけでで
きる仕事ではないからです。民間セクターだけでは、その取り組みを行うことができません。政府や農民も同様です。しかし、政府、研究機関、大学、農民組合、圧力団体、国連機関、市民社会、そして民間セクターが協働して取り組めば、可能となるのです。
■
こうした状況の中で飢餓に対して結束することは、社会正義と貧しい人々のためのより優れた社会的セーフティネットを推し進めるために結束することを意味しています。市民社会、学校、エンターテインメントとスポーツ、NGOなど、さまざまなセクターの活動主体が連携すれば、一人も飢えることがないように社会が特別な注意を払うべきだ、というメッセージを強化することができるでしょう。例えばFAOは、プロ・スポーツのスターたちと連携してきました。欧州プロサッカーリーグをはじめとするサッカーリーグ所属の選手や経営陣、そしてファンたちと一緒に、イべントやキャンペーンを通して飢えの問題への注目を高めています。
新たな食料増産に向けてこれらの新たな食料を、誰が生産するのでしょうか? 小規模農家とその家族は約25億人にのぼり、世界人口の3分の1以上を占めています。こうした人々が食料増産に貢献できるという点を、F
AOは強調します。■
小規模農家の大多数にとっては、農業でさえも収入の主要な創出源にはなりません。小規模農家の多くは女性で、臨時の仕事や送金から現金収入を得ています。これらの人々は家庭菜園や都市農園で多少は作物を生産していますが、総体として多くが食料購入者であり、1
15
WIN
TE
R 2
01
0

成長過程の適切な時期に適切な量だけ注意深く使用することなのです。このような原則に基づく実践は「生態系アプローチ」と呼ばれ、自然が可能にするさまざまな「生態系サービス」に基づいています。現在、農業投入財は多くの場合、必ずしも最大限の効率で利用されているわけではありません。こうした投入財の使用を最適化することで、他の投入財の潜在力を全面的に発現させることができます。例えば、90億人を養う食料は、無機肥料がなくては生産できません。しかし、生産コストを削減し環境問題を軽減するためには、これらをうまく利用しなければなりません。肥料は、作物が必要とする栄養分と生育期間中の土壌の肥沃度とをうまく調和させ、肥料の放出時期の管理や深部埋め込みといった改良技術に切り替えることで、効率的な使用が可能となります。こうした
日を2USドル以下で暮らしています。世界で栄養不良に苦しむ人々の多くは、このような人々なのです。
■
私たちは、彼らの将来の食料生産への寄与を促進することができ、そうすることで、彼らが貧困と栄養不良から抜け出ることを支援することもできます。これは農業を可能としている環境を破壊せずとも実行が可能です。適切な政策と、自然を補完する適切な技術とアプローチを活用することで、作物生産を持続可能な方法で向上させることができるのです。自然の贈与物には、植物に大切な栄養分が届くように促す土壌微生物や、水分を保持したまま地下水を再補充する土壌構造、受粉、害虫を制御する自然の天敵などがあります。言い換えれば、持続可能な形で作物を増産させることは、比較的安全な外部投入財を、
技術によって、作物は、必要とする時期、必要とする場所で、肥料を確実に取り込むことができるようになります。
■
総合的病虫害管理( IPM)は、生産拡大、コスト削減、水使用および土壌汚染の減少のために、病虫害に強い品種や生物的病虫害管理技術、耕作方法、農薬の適切な利用を組み合わせたものです。このアプローチの主な特徴は、生態系の効用でもある天敵の活用を基本に置いていることです。農薬使用の最適化は明らかに環境と人間の健康に良いだけでなく、農民の資金節約にもつながり、その資金を農地に再投資したり家族のために栄養ある食料の購入に当てることができます。
■
保全型農業は、生態系サービスに基つく生態系アプローチのもう1つの方法で
16
WIN
TE
R 2
01
0

す。土壌中の有機物の増加が土壌の保水力を向上させ、かんがいの必要性を減少させたり、もしくはその必要性をなくしてしまいます。
■
1965年から2000年の間に達成された世界の作物生産増収の50%は、植物遺伝学の発展によるものであり、残りの50%は水供給や肥料、農作物管理実践の改善の組み合わせによるものでした。
■
生態系サービスは生命の多様性に依拠しています。家畜品種、微生物、作物品種……これらの多様性すべてが、それらが提供するサービスにとって不可欠です。実際、ある時期には不必要に思える種子が、気候やその他の変化が起きた時に重要となる可能性もあります。生物多様性は生態系サービスの未来に対するセーフガードとなっているのです。
政府の役割食料生産は、将来の需要に対応するのに十分な規模で拡大しなければなりません。
■
国民国家は、政府を通して、法律や規則、規制、プログラムを施行しています。国家はさまざまなレべルで、環境に責任を持つ農法を促進する権限を持っています。例えば国家は、農民が土地に関して安心し、天然資源の保護を含む長期的な見通しを持って、必要とされる食料を生産する農法を採用できるよう、土地保有を安定させる法律を制定することができます。また、使用される製品の品質をチェックし、それらが正しいラべルを貼られ、市場に出され、危険性を最小限にとどめていることを保証することができます。
■
United Against
Hunger
飢餓に対して結束するR e p o r t 2
左ページ:稲の生育状況を調べる農民(セネガル)。©FAO / Olivier Asselin
右ページ:農民と話し合うFA
Oの総合的生産・病害虫管理( IPPM)地域コーディネーター。©FAO / Olivier Asselin
17
WIN
TE
R 2
01
0

各国政府は、公共政策と立法によって生態系アプローチを促進しなければなりません。言い換えれば、国家は、農業が持続可能な方法で拡大することのできる環境を作っていくのに有益な媒体なのです。
■
また、各国は一致団結して持続可能な食料生産と食料安全保障を支援するために活動しなければなりません。例えば、2009年、イタリアのラクイラで、G8
諸国が、他の国々およびさまざまな機関とともに食料安全保障を広げていくため、「総合的なアプローチを活用する」「国家主導の計画に投資する」「戦略的協調を強化する」「多国間機関の利点を活用する」そして「持続的で明確な誓約を完遂する」という基本行動指針を採択しました。このラクイラ食料安全保障イニシアティブは、幅広い合意形成を促進し、CFSの改革を前進させました。
■
カナダのムスコカで開かれた2010年の
G8会合では、各国が、国境を超えた投資と開発の関係、そして政府開発援助(ODA)だけでは世界食料安全保障を実現するのに不十分であるという事実に注意を促しました。各国は、途上国において責任ある持続的な方法で国際的な投資を拡大することの重要性を強調しました。
■
意志と勇気、粘り強さを持ち、多くの活動主体が協働しまた互いに助け合えば、さらに多くの食料が、より持続可能な形で生産され、そしてそれが最も必要としている人々の口にもたらされるはずです。
United Against Hunger飢餓に対して結束する
世界食料デー2010を紹介するパンフレット。FAOのウェブサイト(関連ウェブサイト参照)では、本パンフレットの全文に加え、過去の食料デーの関連資料もご覧いただけます。FAO 2010年9月発行4ページ A4判 英語ほか
2009年、食料価格高騰と金融危機が要因の一部となって、世界の飢餓人口が10
億人という臨界点に達しました。2009年11月の「飢餓に関するサミット」に先立って、FAOはこの状況に対する良心の憤りを示す申し立てへの署名を呼びかけるプロジェクト「The 1billionhungry project
(10億人飢餓プロジェクト)」を開始しました。その後、価格高騰の緩和や途上国の経済成長などが要因となって、2010年の推定飢餓人口は9億2,500万人となりましたが、この数字は依然として容認できない水準であることに変わりはありません。
2010年11月現在、世界中から300万件を超える署名が集まっています。
10億人飢餓プロジェクト
The 1billionhungry project(10億人飢餓プロジェクト)
www.1billionhungry.org/jp
10億人飢餓プロジェクトを呼びかけるFAOローマ本部のイベント。 United Against
Hunger
飢餓に対して結束するR e p o r t 2
出典:「United against Hunger」FAO,2010
関連ウェブサイト:World Food Day:www.fao.org/getinvolved/worldfoodday
18
WIN
TE
R 2
01
0

www.fao.org/giews/english/cpfs
FAOの 「Crop Prospects and Food Situation」は、世界の穀物需給の短期見通しと世界の食料事情を包括的に報告するレポートです。地域別の食料事情や付属統計など、全文(英語)はウェブサイトでご覧ください。
Crop Prospects andFood Situation
穀物見通しと食料事情
2010.9
穀物CIS諸国では生産が急減したものの2010年の世界の穀物生産は史上3番目の記録(9月1日に発表された)2010年の世界の穀物生産予想は、前回の予想を若干上回り、22億3,900万トンに改訂された(精米換算のコメを含む)。2010年の世界の穀物生産は、2009年をちょうど1%下回り史上3番目の記録の水準となる。独立国家共同体(CIS)諸国での小麦と大麦の大幅な生産減が、減産が懸念される主な要因である。国際価格が高く、飼料用需要の伸びが緩慢と予想されることから、2010 / 11
年の世界の穀物利用はわずかな拡大に
とどまり22億4,800万トンと予想されるが、それでも今年の世界の穀物利用を900万トン上回る。しかし、比較的大きな穀物在庫があることから供給は順調で、穀物利用に占める在庫率はわずかに1%縮小の23%と予想され、2
007 / 08年に記録された19.6%という30年来の低水準を十分に上回る。多くの穀物の国際価格は最近数週間で急激に上昇した。FAOの穀物価格指数は、8月に182と、2009年6月以降の最高値に達した。特に小麦とトウモロコシ価格が上昇を続けていることから9月には指数はさらに上昇するものとみられる。2010 / 11年の世界の穀物貿易は、主として小麦の出荷減少により若干(1%)
縮小し、2億6,200万トンになると予想される。世界貿易が少し減少するにもかかわらず、穀物価格上昇のため、2010
/ 11年の国際穀物輸入勘定は、2009
/ 10年よりも12%高い770億USドルに増加すると予想されるが、最高であった2007 / 08年よりも28%低い。
小麦オーストラリアでの豊作予想により小麦の供給見通しが向上世界の小麦生産は、この数週間オーストラリアで好天が続き小麦の収穫予想が増加したことから、現時点で、前回の予想よりも400万トン多い6億5,00
0万トン近くになると予想されている。しかし、主要なCIS諸国の小麦生産国、特に干ばつによる生産急減がみられるロシア、さらにEUと北米での生産減少が主な要因となって、世界の小麦生産予想は、なおも2009年から4.7%の減少と予想される。2010 / 11年の世界の小麦利用の見通しは、6億6,600万トンへと若干上方修正された。食用利用の増加は、平均人口の伸びと足並みを揃えており、食用消費は合計4億6,700万トンに達するとみられる。しかし、小麦の飼料用利用は2年続きで伸びず、1億2,300万トン前後にとどまると予想される。最新の生産と利用見通しに基づき、20
11年の小麦の期末在庫は、前回予想を300万トン上回るが、8年来最高だった期首在庫を9%下回る約1億8,40
0万トンに修正された。今月の予想が高くなったのは、第1にオーストラリアでの在庫増予想によるものである。2010
/ 11年の小麦利用に対する在庫率は現時点では27.7%と算出されており、前期比2.5%減だが30年来の低水準を記録した2007 / 08年よりも5.5%高い。今季、5つの主要輸出国の供給状況が比較的良好であることから、期末在庫の全消失(国内利用および輸出の総計)に対する割合は、現在、18.6%と予想されている。これは、前期比でほぼ3
世界の穀物需給概況
穀物の利用に対する在庫率※1
出典:FAO
% %
※1 期末在庫と次期の利用を比較※2 2010 / 11年度の利用は 1990 / 2000年度から 2009 / 2010年度にかけての推定に基づいた傾向値
10
14
18
22
26
30
10
14
18
22
26
30
10 / 11年予測※2
09 / 10推定
08 / 0907/ 0806 / 07
コメ小麦
穀物計
粗粒穀物
21
WIN
TE
R 2
01
0

Cr op P r ospects and Food S i tua t ion穀物見通しと食料事情
%の減少だが、2007 / 08年の12%
以下に比して7%の増加となる。2010 / 11年の世界小麦貿易(小麦粉を含む)の予想は、9月に100万トン増加し、2009 / 10年を5%下回る1億2,000
万トンになった。前回報告からの増加は、オーストラリアからの輸出増予想を反映している。従来からの主要輸出5ヵ国からの小麦出荷は、急増し、ロシアおよび他の主要なCIS諸国の輸出国からの輸出急減を埋め合わせると予想される。輸出増加の大部分は米国(7月/ 6月の年度で前
期から800万トンの増)とオーストラリアで予想されるものである。輸入側では、アジア諸国の総輸入量が前期から800
万トン減少すると予想されるが、これは主としてイランでの豊作と最近発表された(いくつかの他の食料商品と並んだ)小麦輸入禁止決定によるものである。小麦価格上昇により、韓国が飼料用小麦の輸入を減らすことも、輸入総量の減少に寄与するだろう。これに対し、アフリカでは輸入増が予想され、モロッコ、チュニジアなど北アフリカの国々で今年の小麦生産が昨年の平年並の水準を下回るものだったことから、北アフリカの輸入が最も大きくなると予想される。
粗粒穀物供給は順調だが需要は弱い世界の粗粒穀物生産は、前回報告を約300万トン下回り、前年の水準より若干低い12億2,200万トンになると予想される。最新予想での減少はすべて、米国のトウモロコシ生産予想がわずかに減少し3億3,430万トンになったこと
によるものである。この減少があっても、米国では史上最高の生産を記録することになる。世界のトウモロコシ生産は8
億4,200万トンに達すると予想されるが、これは史上最高値で、前年より2.5%
増になる。米国に次ぐ世界第2のトウモロコシ生産国である中国も、今年、史上最高の生産が予想される。これに対し、世界の大麦生産は、今年14%近く急減して、1億3,000万トンにとどまり、40年来の低水準になるとみられる。これは、主としてCISとEUの主要な生産国が天候に恵まれず生産が急減したことによる。2010 / 11年の世界の粗粒穀物利用は、11億2,200万トンと前年からほとんど変わらず、また今年の生産予想にほぼ見合うと予想される。飼料向け利用については、トウモロコシは4億6,800万トンと増減がないものの、大麦の飼料向け利用(多くがロシアで利用されている)が約6%減少し9,300万トンになることから、全体として1.4%縮小し6億2,
600万トンになると予想される。粗粒穀物の食用利用は約2%増加して1億9,
500万トンになると予想されるが、その大部分はサハラ以南アフリカ地域での生産増予想によるものだ。粗粒穀物の工業用利用もさらに拡大すると予想されるが、米国でのトウモロコシ・ベースのエタノール生産の減速予想が主な要因となって、ここ2-3年よりも緩慢なペースになるだろう。世界の粗粒穀物の2011年期末在庫は、比較的高かった期首水準から3%減少し、2億800万トンと予想される。20
10 / 11年、粗粒穀物の世界利用に対する在庫率は2009 / 10年より1%減、
2006 / 07年の最低水準より約3%増の、18%を下回る程度へ減少すると予想される。しかし、供給が緊迫しつつある兆候として、主要輸出国の全消失に対する在庫率はさらに低下し、わずか10%と予想される。2009 / 10年は12.
5%、最近で最も低かった2006 / 07
年と2007 / 08年は12%であった。比率減少の主要な要因は、米国におけるトウモロコシ在庫が2004年以降最低水準に急減し、またEUにおけるトウモロコシ、大麦在庫が急減したことである。2010 / 11年の粗粒穀物の世界貿易は、前期比4%増の1億1,300万トンに達すると予想される。大麦の十分な輸出供給がないことでトウモロコシ需要が急増したことが、この増加の主要な要因とみられる。世界のトウモロコシ貿易は、2009 / 10年(編注:原文は2010 / 11年)
から800万トン近く増加し、史上2番目の記録となる9,000万トンに近づくと予想される。米国からの粗粒穀物輸出は少なくとも200万トン増の5,000万トン以上と予想される。アルゼンチンからの出荷も増加するとみられ、予想される
CIS諸国およびEUの輸出国からの大麦とトウモロコシの販売減少を十分に埋め合わせる。予想される輸入増の多くは、数ヵ国が高値の飼料用小麦に代わって粗粒穀物を購入するとの予想によるものである。また、北アフリカ諸国、特にエジプトとチュニジア、および中米(特にメキシコ)でも輸入増が予想される。
コメ2010年の生産は史上最高を予想されるが、貿易は若干減少9月以降、北半球の主要な生産国では、
22
WIN
TE
R 2
01
0

2010年の一期作の収穫が進んでいくとみられるが、これは例年、今期の収量の大部分を占める。この2-3ヵ月以上、主要国のうち数ヵ国は、収穫されるコメの収量や品質に悪影響を及ぼす干ばつとそれに続く洪水といった問題に直面した。その結果、FAOは2010年の世界のコメ生産予想を約500万トン下方修正し、精米換算で4億6,700万トンとしたが、それでも2009年より3%増の史上最高を記録することになる。2010
年の世界のコメ生産予想を大きく引き下げたのは、パキスタンにおける2大生産地のパンジャブ州とシンディ州で、洪水による大きな被害が発生したことである。中国も、南部のいくつかの省で天候不順のため早生米の収量が昨年比6
%減となり、2010年の生産予想を引き下げた。現在の予想では、モンスーンの雨に恵まれて生産を立て直し史上最高の生産が予想されるインドの回復に支えられ、アジアでのコメの収量は3%以上回復し、もみ米換算で6億3,400万トンとなっている。同様に、2009年に収量減であった日本、ネパール、フィリピンも、今期を通して続いた不足の大部分を回復すると予想され、また、バングラデシュ、インドネシア、イラン、スリランカ、そして限られた量ではあるがベトナムも、昨年に引き続き収量増となるだろう。昨季に比してごくわずかの増加ではあるが、最新の予想では、中国も史上最高の生産が予想されている。それに対し、カンボジア、北朝鮮、韓国、ラオス、ミャンマー、パキスタンでは、主として天候不順のために減産が予想されている。パキスタンの場合、広範囲に及ぶ洪水
のため、現時点で240万トンのコメが失われ、今季の収量は精米換算で500
万トンにとどまると測定されている。他の地域では、西アフリカおよび東アフリカ諸国の生産予想はおおむね好調で、多くの国で豊作となるだろう。しかし、政府の水使用制限により作付けを縮小したエジプトでは、生産が縮小すると予想される。今季の収穫の大部分が終わった南部アフリカ諸国に関しては、マダガスカルでは史上最高の生産と予想されるが、生産期を通して干ばつの問題があったモザンビークでは生産減となる。降雨の遅れとそれに続く大雨に見舞われた南米、特にボリビア、ブラジル、ウルグアイも生産減となった。残る地域では、オーストラリアは豊作で収穫を終えると予想され、EU、ロシア、特に米国
では記録的な生産になると予想される。2011年のコメの世界貿易は、2010年の予想量よりも100万トンすなわち3.3
%減の2900万トンに縮小するとみられる。これは主として、アジア諸国、特にバングラデシュ、中国、インドネシア、フィリピンで2010年が豊作になり輸入が減少するとの予想を反映している。国際価格の上昇もあって、この地域へのコメの流れは、2010年の1,380万トンから1,310万トンへと減少すると予想される。アフリカでは、輸入は980
万トン程度の水準を保つと予想される。主要な輸入国のうち、ナイジェリアとコートジボワールは購入量に変化がなく、南アフリカ、ケニア、セネガルは量を増やし、一方でマダガスカルとモザンビークは量を減らすと予想される。ラテンア
生産※1
世界 2285.3 2261.0 2237.7 2238.6 -1.0開発途上国 1239.9 1237.4 1267.5 1270.0 2.6先進国 1045.3 1023.5 970.2 968.6 -5.4
貿易※2
世界 281.5 264.8 261.1 262.2 -1.0開発途上国 72.0 66.3 73.7 74 12.2先進国 209.5 198.6 187.4 187.7 -5.5
利用世界 2182.3 2236.5 2247.9 2248.1 0.5開発途上国 1333.1 1358.0 1386.1 1386.6 2.1先進国 849.2 878.5 861.8 861.4 -1.91人当たり食用利用(kg /年) 152.2 152.1 152.7 152.6 0.3
在庫※3
世界 518.1 540.6 527.1 524.5 -3開発途上国 349.8 370.1 378.8 380.9 2.9先進国 168.4 170.5 148.3 143.6 -15.8利用に対する在庫率 23.2 24.0 23.1 23.0 -4.2
2009 / 10年に対する2010 / 11年の変化(%)
2008 / 09 2009 / 10推定
2010 / 11予測
20109 / 24
20109 / 1
世界の穀物状況(100万トン、精米換算)
注 合計は四捨五入されていないデータから算出した※1 記載されている2ヵ年のうち初年度のデータを示す※2 小麦と粗粒穀物の貿易は、7月/ 6月市場年度に基づいた輸出を示す。コメの貿易は、記載されている2ヵ年のうち後者の輸出を示す※3 国ごとの作物年度末時点での在庫の合計を示し、いかなる時点での世界の在庫レベルを示すものではない
23
WIN
TE
R 2
01
0

Cr op P r ospects and Food S i tua t ion穀物見通しと食料事情
メリカおよびカリブ海諸国では、現在の予想によれば、ブラジルとベネズエラへの搬入量は減少するが、地域の他の国々には変化がないだろう。EUの輸入量は、現時点では、2010年の110万トンから増えて120万トンになると予想される。予想される世界の2011年の輸出減少は、供給困難に直面するとみられるカンボジア、ベトナム、そして特にパキスタンからの出荷減予想を反映している。これに対し、ブラジル、インド、タイは販売を拡大する可能性がある。インドの場合、政府が現行の非バスマティ米の輸出制限を撤廃すると、現在の予想以上に輸出が拡大する可能性がある。米国からの出荷は、公式の予想では360
万トンと、2010年の予想量をわずかに上回る。現在の増加基調の2010 / 11年収穫予想に従えば、世界生産は世界のコメ消費を460万トンほど上回り、世界の在庫が2010年の1億2,500万トンから2
011年には1億3,300万トンへ増加すると予想される。在庫の多くは、伝統的な輸出国、特に2010年に記録的な豊作が予想される中国とインドに集中すると予想される。インドでは、7月1日、政府の大量購入により公的在庫が2,4
30万トンとなり、その時点で緊急用保管米として定められた980万トンを大きく超えたことが報じられた。生産増による在庫増は米国でも予想される。一方、エジプト、ミャンマー、パキスタン、タイ、ベトナムといったいくつかの主要な輸出国では、コメ在庫が縮小すると予想される。輸入国の全在庫は前年比で安定を保つとみられる。
価格国際穀物価格は9月にさらに上昇国際小麦価格は上昇を続けている。8月、ロシアの小麦輸出禁止が8月中旬から年末まで続くことに、市場が反応した。9月2日、輸出禁止措置が2011年の収穫期まで続く可能性があるとの発表により、国際価格上昇にさらに弾みがついた。9月最初の3週間の米国産小麦(No.2 硬質赤色冬小麦、湾岸出荷)の平均価格は、昨年9月の平均より55
%高い309USドル/トンであった。それでも小麦価格は(名目価格が)史上最高であった2008年3月より36%低い。ヨーロッパ産小麦の輸出価格の大幅な上昇はさらに顕著となり、黒海地域での輸入用購入がEU産(主としてフランス、ドイツ産)小麦へ急に移行したことから、80%を超える上昇となっている。最新の報告がオーストラリアの生産を前回よりも増加して予測したことが一時的に価格を軟化させたが、全体的な供給切迫の予想と最近のトウモロコシ価格上昇が小麦市場を下支えし、堅調な価格を保っている。9月第3週の、2010年12
月引き渡しCBOT小麦先物は、264US
ドル/トンに近づいている。これは8月初めにロシアが輸出禁止を発表した際の23ヵ月ぶりの高値より12%低いが、1
年前の同時期よりも50%近く高い。粗粒穀物価格も今期初めからかなり上昇した。大麦価格が最も急騰し、特に黒海地域での供給がこれまでになく厳しく、またEUでの不足が確認された7月から8月にかけて上昇がみられた。1トン当たり250USドル以上となった(飼料用)大麦価格は、昨年からほぼ倍増した。
トウモロコシ価格は、特に米国の生産予想が下方修正された8月後半から9
月にかけて上昇が加速した。9月最初の3週間の米国産トウモロコシ(No.2
黄色、湾岸)価格は1トン当たり204US
ドルと、2008年9月以降の最高値をつけたが、2008年6月の史上最高値に比べると27%低い。先物市場での価格も急上昇し、9月第3週の2010年12月引き渡しCBOTトウモロコシ先物価格は1トン当たり199USドルと、今期初めより30%上昇している。数ヵ月の比較的安定した時期を経て、コメ価格は2010年6月から9月にかけて上昇した。特に9月には、8月に217
であったFAOの価格指標平均が9月には232に高騰した。9月には、2009年には米国と並んで世界で3番目の国際的なコメ供給国になったパキスタンが洪水被害を受けたことから、国際コメ価格上昇の圧力が高まった。小麦をめぐる国際的な見積もりの上昇がコメの輸入へのシフトを促したことも、コメ価格を下支えした。例えば、7月に466US
ドル/トンだったタイ白米100%Bのベンチマークは、8月に472ドル、9月最初の3週間には496ドルへと上昇した。バングラデシュとイラクで政府の輸入入札が始まったことで、さらに低品質のインディカ米も上昇し、7月に325USドル/
トンだったベトナム米(25%の破砕米を
含む)の価格が9月最初の3週間に415
ドルへと急騰した。ジャポニカ米および香り米も、記録的な価格になった。
出典:「Crop Prospects and Food Situation,
September 2010」FAO, 2010(pp.2-9より抜粋)
翻訳:斉藤 龍一郎
24
WIN
TE
R 2
01
0

※ 「外部支援を必要としている国」とは、伝えられる食料不安の危機的問題に対処する資源が欠如していると予想される国である。食料危機は、ほとんど常に複数の要因が組み合わさったものであるが、その対応においては、食料危機の特質が、主として食料入手可能性の欠如に関連しているものなのか、食料へのアクセスが限られているものなのか、あるいは、厳しい状況ではあるが局地的な問題であるのか、といったことを確認することが重要である。したがって、外部支援を必要とする国のリストは、概略的ではあるが相互に他を排除するものではない次の3つのカテゴリーに区分される。●凶作、自然災害、輸入の途絶、流通の混乱、収穫後の甚大な損耗、その他の供給阻害要因によって、総体的な食料の生産/供給における異常な不足に直面している国。●きわめて低い所得、異常な高食料価格、あるいは当該国内において食料が流通しないといったことが原因で、人口の大多数が地方市場から食料を調達できないというような、広範な食料へのアクセス欠如が見受けられる国。●難民の流入、国内避難民の集中、あるいは凶作と極貧が組み合わさった地域など、厳しい局地的な食料不安に直面している国
食料危機最新情報
アフリカ(21ヵ国)食料生産/供給の異常な不足モーリタニア ■
ニジェール ■
ジンバブエ ■
広範囲なアクセスの不足エリトリア ▲
リベリア ■
シエラレオネ ■
ソマリア ▲
厳しい局地的食料不安ブルンジ ▲
中央アフリカ ■
チャド ■
コンゴ共和国 ■
コートジボワール ■
コンゴ民主共和国 ■
エチオピア ▲
ギニア ■
ケニア ▲
マダガスカル ▲
マラウイ +
モザンビーク +
スーダン ■
ウガンダ ▲
アジア(8ヵ国)食料生産/供給の異常な不足イラク ■
広範囲なアクセスの不足北朝鮮 ▼
モンゴル ▼
厳しい局地的食料不安アフガニスタン ▲
キルギスタン +
ネパール ▲
パキスタン ▼
イエメン ■
ラテンアメリカ・カリブ海諸国(1ヵ国)ハイチ ▲
外部からの支援を必要としている国※(30ヵ国)
食料不安の性質国名 主な理由 変化(2010年5月の前報告から ■変化なし ▲好転中 ▼悪化中 +新規)
数年来の干ばつ/2009年食料生産の急減/37万人に食料援助が必要2009年の穀物生産の急減および牧畜の不振により、約710万人(人口の48%)に食料援助が必要農村部・都市部の推定168万人に食料援助が必要/経済危機によって通常の食料へのアクセスが困難
経済危機と多くの国内避難民に起因する厳しい食料危機が続く/最近の降雨により干ばつに苦しんでいた牧畜地帯で牧草/水利用が回復戦争被害から回復の遅れ/不十分な社会サービスとインフラストラクチャー、市場アクセスの困難戦争被害から回復の遅れ/通貨安に伴うインフレーションの昂進により購買力が低下し食料安全保障が悪化現在も続く内戦により約200万人に食料援助が必要/20 09 / 10年小雨季「デイル」および2010年大雨季「グ」の穀物生産好調によって状況は改善
キャッサバ生産の減少をはじめとする複数の要因が重なり北部では慢性的な食料危機が続く社会不安により農地利用が困難であることに加え、食料価格の上昇や変動が食料へのアクセスを困難に多数の難民(スーダンより約27万人、中央アフリカより約8万2,000人)が南部と東部に避難/最近の洪水による作物被害
2009年末以降の10万人を超える難民流入が限られた食料資源をさらに圧迫戦争被害/国内の一部(主に北部のいくつかの地域)では支援の欠如により近年農業が大きな損害社会不安/国内避難民/帰還民/食料価格の高止まり2009年の「メーアー」雨季が不作だった地域で約520万人が食料援助を必要とし、慢性的な栄養不良に苦しむ/2010年の「ベルグ」雨季の豊作により食料安全保障の諸条件が改善食料の高価格とインフレが食料へのアクセスにマイナスの影響主として北西部の牧畜地帯・半農半牧地帯および南東部と海岸部の低地において推定160万人が食料不安に/20 09 / 10年の小雨季の豊作により食料安全保障の状況は改善穀物生産の不作のため南部の複数の自治体で慢性的な食料危機が続いているが、国産米の豊作により市場への供給が改善降雨不足により南部のいくつかの地区はこれまでにない不作/推定106万人に食料援助が必要南部および中央部地域で穀物生産の不作により約45万人に食料援助が必要紛争(ダルフール)、社会不安(南部スーダン)、2009年大雨季の穀物生産の減少、さらに食料の高価格をはじめとする複数の要因が重なり、約640万人に食料援助が必要主に2009年大雨季の不作と社会不安により、北部とカラモジャ地域で推定61万人に食料援助が必要
深刻な社会不安
経済的混乱と農業投入財不足が続き、食料生産の不足と食料危機の悪化をもたらしている2009 / 10年冬の厳しい寒さ(ズッド)により4,400万頭の家畜のうち600万頭近くが死亡、約50万人の生計に影響
紛争と社会不安/中央部と北東部の食料不安が緩和社会不安、最近の民族紛争、国内避難民の影響市場アクセスと輸送の制約により食料が不足し価格が不安定大洪水の影響で2,060万人の住居、インフラおよび収穫に被害最近の戦闘の影響/国内避難民(約33万人が現在も避難キャンプに滞在)/難民
食料消費は改善したものの、大地震前に比べ食料危機のレベルは高い
25
WIN
TE
R 2
01
0

国際平和研究所での国際シンポジウム「グローバリゼーションと『南』の農民」。左側はブラジル土地なし農民の運動リーダー。中央は地球環境学者、故原後雄太(はらご
ゆうた)さん(2005年)。
平和研による平和学のブックレット「南を考える」(2010年)。
私たちの南北問題研究ゼミの特色は、もう20年以上にわたり、演習の一環として、食べ物を自分たちで作ってみる体験が組み込まれていることです。そのせいか、よく外部の方から、おたくの学部は農学部系ですかと聞かれます。体験必修の理由は、国際学( international studies)
という世界を幅広く読み、よりよく生きるというリベラルアーツの理念と食料生産とは密接な関係があるからです。
■
人間社会は、一人一人が安心して食べ物を口にしないと、自由な考え方や生き方ができなくなり、ともすれば、争いの原因となります。平和というコトバも、「平」は万人
に対して平等で、「和」は穀物を指す禾と口からなっていて、万人が平等に食べ物を口にできる状態を意味することだと聞い
たことがあります。実際、FAOのロゴもよく見ると、小麦の下に、「FIAT PA-
NIS」というラテン語が記されています。FIATは「充たす」でPANISは「パン」です。これは第二次大戦後復興で、一日も早く万人が食べられる農業を促進する使命を意味しています。とはいっても、自然科学系ではないので、命の再生産に関わる諸問題の国際政治経済学からの分析と考察が中心です。食料生産体験は、初めは近くの市民農園地を借りて、サツマイモを作ったり、隣接する市立公園の田んぼで有機米を栽培したりしましたが、今では、秩父の山村で麦、イモなどに取り組んでいます。ゼミでよく言うのは、作るまでは自然科学の法則、収穫物の処分・分配は、社会科学の領域ということです。実際、収穫物は
Food for All
国際学としてなぜ食を作り、学ぶのか。作るまでは自然科学で、分配は社会科学で
明治学院大学国際学部 教授/国際平和研究所 元所長
勝俣 誠
FAOの使命は「人類の飢餓からの解放と世界経済の発展に貢献すること」です。そのために「FOOD for ALL(すべての人に食料を)」というスローガンを掲げてテレフード・キャンペーンを行っています。
FAOの活動にご協力いただいている団体
30
WIN
TE
R 2
01
0

人々の購買力でなく、人権をベースとした政治決定です。FAO
もこのスタンスから、世界人権宣言の「食料への権利」と、そこから政策的に導き出される「食料主権」の実現を強く訴えてきています。第2は、「南」が「北」の生活・生産水準に急速に近づくにつれて、激化している資源争奪をどう避けるかをこの生命財から考えたいからです。今や自国民の胃を充たすためには、資金力によって他国の農地を取得する動きも広がっています。この争いが地球環境の破壊と生物多様性の危機に行き着かないようにするには、持続可能なもうひとつの地球住民の食生活のあり方、ひいては、文明のあり方を考える知的作業が不可欠です。これをゼミではより少なく消費し、よりよく生きる文明を探る、自然をこれ以上商品にしない脱経済成長のシナリオが求められています。その問いを深く考えるには、デジタル世界から時々脱出して、自ら身体労働を基本とする農の体験が不可欠です。アフリカなどの「南」の地域での実習では、必ず農村体験を入れているのもそのためです。関連ウェブサイト:明治学院大学国際学部:www.meijigakuin.ac.jp/~kokusai2/明治学院大学国際平和研究所:www.meijigakuin.ac.jp/~prime/
有機米の稲架組みを指導する筆者(1993年)。
自分たちでは全部消費せず、お裾分けという自発的再分配をしています。
FAOとの関係では、ゼミ生が自分たちでFAO日本事務所から貸し出された途上国の食料問題のパネル展を学生食堂で実施したり、共催でイベントを行ったりするほか、横浜市国際交流協会(YOKE)と明治学院大学が共催する「国際機関実務体験プログラム」を通じて、FAO日本事務所にインターンを派遣してきています。
■
では、なぜ今、国際政治経済学系のゼミで、食というテーマにこだわるのか、次の2点を挙げておきたいと思います。第1は、グローバル市場化が進み、私たちの食べ物が、単なる商品となってしまい、人類が各地域の多様性を生かして形成してきた食生活、生産の地域の自立システムが崩壊し、しばしば食料難を起こすからです。これは市場の原理の当然の帰結で、その危険を唯一回避する手段は、食べ物は単なる商品でなく、万人に人権によって確保させる生命財であるという認識です。これは優れて、
自らの農具改良を説明するセネガルの農民。
31
WIN
TE
R 2
01
0

■ 所在地神奈川県横浜市西区みなとみらい1-1-1パシフィコ横浜 横浜国際協力センター5F FAO日本事務所内
■ 利用予約および問い合わせ
Tel:045-226-3148 Fax:045-222-1103E-mail:fao-librar [email protected]
■ 開館時間平日10 : 00 ~12 : 30 13 : 30 ~17 : 00
■ サービス内容
FAO資料の閲覧(館内のみ)インターネット蔵書検索(ウェブサイトより)レファレンスサービス(電話、E-mail でも受け付けています)
複写サービス(有料)
■ ウェブサイトwww.jaicaf.or.jp/fao/librar y.htm
FAOは「食料・農林水産業に関する世界最大のデータバンク」と言われており、加盟国や他の国際機関、衛星データ等からさまざまな情報を収集・分析・管理し、インターネットや多くの刊行資料を通じて世界中に情報を提供しています。FAO寄託図書館は、日本国内においてこれらの情報を多くの人が自由に利用できるよう、各種サービスを行っています。お気軽にご利用ください。
F A O寄託図書館のご案内F A O D e p o s i t o r y L i b r a r y i n J a p a n
みなとみらい駅
展示ホール
パシフィコ横浜国立大ホール
至横浜 至関内
2F クイーンズスクエア
インターコンチネンタルホテル
会議センター
ランドマークタワー
エスカレーター動く歩道
FAO寄託図書館横浜国際協力センター5FFAO日本事務所内
JR桜木町駅
Pu
bl
ic
at
io
ns
N E W
FAO寄託図書館は(社)国際農林業協働協会(JAICAF)が運営しています。
アクセス
みなとみらい線みなとみらい駅クイーンズスクエア連絡口徒歩3分
JR・横浜市営地下鉄桜木町駅徒歩12分
いずれの場合も、インターコンチネンタルホテルを目指してお出でください。1階または2階(連絡橋)のホテル正面入り口に向かって左側にあるエレベーターより5階へお越しください。
The Second Report on the State of The World ’s Plant Genetic Resources for Food and Agriculture食料・農業のための植物遺伝資源白書第2回報告
食料・農業のための植物遺伝資源(PGRFA)に関する世界の現状をまとめた報告書。第1
回報告から12年ぶりの発行となります。113ヵ国の国別報告データの分析結果や、食料安全保障と持続的な農業開発に対するPGRFAの貢献を論じます。www.fao.org/docrep/013/
i1500e/i1500e00.htm
FAO 2010年10月発行370ページ 25.5×18cm 英語ほかISBN:978-92-5-106534-1
The Wealth of Waste 資源としての廃水
都市化や気候変動などによって水資源への圧力が世界的に高まるなか、農業における廃水の再生利用が注目されています。本書は、再生水利用を経済的側面から考察するとともに、スペインやメキシコの成功例を紹介します。www.fao.org/docrep/012/
i1629e/i1629e00.htm
FAO 2010年9月発行129ページ A4判 英語ISBN:978-92-5-106578-5
N E W
32
WIN
TE
R 2
01
0

資源の制約から、地下水に頼っている国 も々多いのですが、著しい量の水が、ほぼ補充のされない化石地下水と呼ばれるものから汲み上げられており、持続可能性への問題を抱えています。一方で、地域の国 に々おけるかんがいの水利用効率は改善の余地が大きく、一滴の水を大切にする更なる努力が必要です。さらに、気温上昇、降水量低下、異常気象、海水面上昇といった気候変動の予測は、地域の水資源欠乏の悪化や農
イランにて、かんがいスキーム改善ミッションの集合写真(後段右から4人目が筆者)。
中近東地域は、広大な乾燥地帯を有しており、世界で最も水資源の乏しい地域のひとつです。地域の平均年間降水量は135mmで、日本の10分の1にも及びません。また、この地域の国 は々食料輸入への依存率が高く、国 の々大半は少なくともカロリーの半分を輸入でまかなっているのが現状です。農業が、この地域における水資源利用の主要セクターですが、乏しい水資源が地域の食料生産増加
の先天的、構造的な制約要因のひとつとなっています。地域の穀類の生産予測は、需要をはるかに下回る傾向を示しています。地域の人口増加率は世界平均のおよそ倍であり、国 は々生産と需要のギャップを輸入にてまかなわざるを得ませんが、それは世界の農産物市場変動に対して脆弱であることを意味しています。
■
また、この地域では、地表を流れる水
F
A
O
で
活躍する
日本人
国連で働く、とは?
No. 22FAO中近東地域事務所 自然資源(水資源)開発/管理担当官
阿部 信也
36
WIN
TE
R 2
01
0

した。また、大学院や仕事先でも素 晴らしい方 に々巡り合うことができ、多 くを学び、助けていただきました。現 在の上司も大変素晴らしい方です。 お世話になった方 に々は、連絡を絶や さずに、大切な宝を失わないことを心 掛けています。■ キャリア戦略:開発業界への門は狭く、 キャリア形成も容易ではありません。入 るための窓口、クリアすべきハードル、 その後のキャリア展開も含め、ウェブサ イトやポストの必要要件を分析すること などにより、キャリア形成戦略を立てる ことを心掛けてきました。私はロジック ツリーを使って考えるようにしています。■ 家族:留学や仕事において、妻は慣 れない場所での生活をすることになり、 大変感謝をしています。今後も仕事 上、家族とともに途上国で生活すること、 または単身での海外勤務となることが 考えられます。仕事と家庭の両立の 大切さを肌で感じ、今は一緒に来てく れている家族を大切にできるよう、日々 努力をしています。
業生産性への影響を示しています。■
私は現在、東はイランから西はモーリタニアにわたる18ヵ国をカバーするFAO中近東地域事務所(所在地:カイロ、エジプト)において、水資源と気候変動分野に関する技術部署に所属しています。仕事を通じ、この地域における食料安全、水資源、気候変動分野に対するFAOの重要性を大いに感じています。日本では8月に「世界食料デー月間2010」シリーズのセミナー※において、この地域の食料問題について水資源の現状と気候変動への課題の観点から発表をさせていただく機会を賜りました。当日は、大変暑い中、70名もの方 に々参加をしていただきまして、ここに厚く御礼を申し上げます。
■
FAOに入るまでの経歴は、私の場合、比較的長い時間を経ています。大学で農業を学び、民間企業での食料輸入業務、留学を経る間に、序 に々途上国開発支援に目を向けていきました。その後、開発コンサルティング会社勤務を経て、米国の大学院で農業における水資源開発・管理を研究し、その後、国際協力銀行( JBIC、現 JICA)勤務期間中に、外務省によるアソシエートエクスパート等派遣制度( JPO制度)に合格し、2009年より現職に就いています。
■
最後にFAOや国際協力の仕事を目指す方々へのメッセージとして、私が大切と感じていることを述べさせて頂ければと思います。■ 人との巡り合い:開発業界に入った初 期に、幾度かの国際協力メーリングリ ストのオフ会を通じて、貴重な人脈を 築くことができ、キャリア形成のアドバ イスをいただいたり、国連でのキャリア 形成小勉強会へ参加することができま
中近東って、
どんなところ?
“”
エジプトにて、かんがいスキーム改善ミッションにおける現地視察。
オフィスでの会議の様子。なお、職員の出身国で日本から一番近い国はインド。
※ FAO日本事務所主催、JAICAF共催
関連ウェブサイトFAO Regional Office for the Near East:www.fao.org/world/Regional/RNE
37
WIN
TE
R 2
01
0

マリ
コートジボワール
ブルキナファソ
ワガドゥグー
ニジェール
ベナン
トーゴガーナ
食料安全保障と飢餓・栄養不良人口の削減を目的として、約30の国や地域で国内連帯(National Alliance)や地域連帯(Regional
Alliance)がアドボカシーや啓発活動、農村住民への支援などに取り組んでいます。これらの国のアライアンスとのネットワーキングの可能性を検討するために、2010年9月、比較的活動の活発なガーナとブルキナファソを訪問しました※1。
■
2003年のローマの国際機関※2によるInter-
national Alliance Against Hunger ( IAAH、
2010年10月にAlliance Against Hunger and
Malnutrition, AAHMと名称を変更)の設立を受けて、ブルキナファソでは同年よりAlli-
ance Nationale Contre la Faim(ACF、飢
餓に対する国内連帯)という名称でアライアンスの活動を行っています。
ブルキナファソの9月は雨季に当たるが、雨の合間を縫って女性たちへのインタビューを行った。
FAO日本事務所 企画官 三原 香恵
西アフリカの農村部女性への支援 ――National Allianceの活動現場を訪問して
P h o t o J o u r n a l
33
WIN
TE
R 2
01
0

販売が行われています。シアバターは保湿力が高く、肌へのうるおい補給ということで、フランスの某有名ブランドでもシアシリーズの製品を展開しているほどです(筆者も同シリーズのクリームを愛用)。ASSANAのブティックに並べられた製品も負けず劣らず、日本人の目から見てもシンプルでお洒落なパッケージが女性にうけるのではないかと思いました。
■
ASSANAに続き、2番目に訪れたのはACF
のメンバーAMIFOB(Amicale des Forestiè-
res du Burkina)による女性グループ支援の現場です。同グループでは野菜栽培活動を
ACFのメンバーのうち、女性の社会経済面での向上を目的に活動する女性グループ、A
FD / Buayaba(Association Féminine pour le
Développement)の活動を訪問しました。AF
D / Buayabaは3,200人から成る47の女性組合をメンバーとする大規模なNGOであり、主要プロジェクト「ASSANA」では、女性グループの小規模社会事業の支援が行われています。ASSANAとはグルマンチェ語(同国の主要言語の一つ)で「シアバター」という意味で、女性たちの手により、文字どおりシアの木の実から抽出されるシアバターを原料とした石鹸やクリームなどの美容製品の加工と
石鹸製作過程。シアの木の実から抽出されるシアバターに香料と化成ソーダを混ぜて十分にこねる。AFD / Buayaba代表のAntoinette Ouédraogoさん(右端)も作業に加わった。
上:AFD / Buayabaの事務所。ASSANAのブティックも併設。 中:ASSANAのブティックの様子。石鹸、ポマード、クリームなどを販売している。石鹸は、1つあたり100CFAフラン(655C FAフラン=固定レートで1
Euro)。 下:ASSANAではシアバター抽出のためにシアの木の実を購入。女性によれば、訪問時の値段は2.5kgで350
CFAフラン(2010年9月時点)。価格が安い時期に多めに購入しているとのこと。
左:シアの木の下で。左から2番目が著者、左から3番目がAFD / Buayabaの代表のAntoinette Ouédraogoさん。西アフリカの逞しい女性を象徴するようなパワフルな女性。右から3番目がNGO「緑のサヘル」(Action for Greening Sahel,
AGS.JAPON)事務局長の菅川氏。 下:ACFブルキナファソの代表(左)と元代表(右)。西アフリカで最初に設立されたNational Allianceとしての自負心を持っていると筆者に語ったのが印象的。活動の一環として、ブルキナファソ政府の食料政策への働きかけも行っている。
34
WIN
TE
R 2
01
0

行っており、AMIFOBの支援のもと、メンバーから徴収した会費を井戸の維持管理やガードマンへの支払いなどの経費に当てています。女性たちとの簡単なディスカッションを行ったところ、2008年に野菜栽培の活動を始めて以来、「野菜取得による栄養改善を通じた健康面での向上を実感した」「野菜販売による収益で子どもの衣服を購入できるようになった」などの声が聞かれました。
■
ブルキナファソの農村部の女性の約95%は生計のために農業に従事しています
※3。日本
でもNGO / NPO、民間企業、関係機関等P h o t o J o u r n a l
Burk ina Faso
切り分けたオクラを並べる女性たち。オクラは乾燥させて保存食として販売される。
と連携してNational Allianceを設立予定ですが、アフリカのアライアンスとの連携を行うことで、食料安全保障への支援のみならず、アフリカの農村部女性のエンパワーメントやジェンダー平等の達成への貢献につながることを期待しています。
※1 誌面のスペースの都合上、本ジャーナルでは主にブルキナファソについて記載。※2 FAO、世界食糧計画(WFP)、国際農業開発基金( IFAD)、Bioversity Internationalの4機関。※3 FAO Gender and Land Rights DATABASE, Full Coun-
try Report, Burkina Faso.:www.fao.org/gender/land
rights/report/
左:AMIFOBはブルキナファソ国の環境・生活環境省の女性森林技官により設立されており、女性グループの野菜栽培活動などの支援を行っている。 右:AMIFOBの支援する女性グループのメンバーたち。プロソフィスの苗木の他、ピーマン、キャベツ、ナス、にがうり、セロリ、ニンジン、オニオンなどを栽培。メンバーのキャパシティにより栽培エリアを配分している。
石鹸作りの作業場でオクラを処理する女性たち。
35
WIN
TE
R 2
01
0

世界の栄養不足人口―― ハンガーマップ2010Prevalence of undernourishment in developing countries:Hunger Map 2010
■ FAO MAP
高い(25-34%)
非常に低い(5%未満)
データなし/データ不足
非常に高い(35%以上)
やや高い(15-24%)
やや低い(5-14%)
開発途上国における栄養不足人口の割合(2005-2007年)
38
WIN
TE
R 2
01
0

出典:FAO
2010年現在、世界では9億2,500万人が栄養不足に苦しんでいます。このうち、特にアフリカを中心とする22ヵ国では、紛争などの人為的要因や自然災害、もしくはそれらの併発によって、食料不安や飢餓などを主な特徴とする危機が8年以上続いています。こうした「長
引く危機」にある国々において食料安全保障を着実に高めていくためには、現地制度の枠組みを利用した長期的な支援活動の構築や、食料支援物資を現地で調達することによって現地の市場を活性化させるなどの取り組みが必要です。FAOは、これらの国々への重点的
な取り組みが必要であるとして、世界食糧計画(WFP)や他の国連機関と連携しながら、支援を強化しています。
関連ウェブサイト:FAO Hunger:www.fao.org/hunger
39
WIN
TE
R 2
01
0

FAO
New
s Winter 2010
通巻
821号
平成
22年
12 月1 日発行(年
4 回発行)
ISSN :0387
-4338
発行:社団法人
国際農林業協働協会(
JAIC
AF )
共同編集:国際連合食糧農業機関(
FAO)日本事務所
表紙写真:洪水防止のため、FAOとEUの支援で堤防が設けられたエチオピア(アムハラ州)の川(2010年)。アムハラ州をはじめとするエチオピアの各地域では、度重なる洪水に悩まされており、2007年にはアムハラ州だけで13万人以上が被災、約3万4,000haに及ぶ作物が被害を受けた。©FAO / Giulio Napolitano









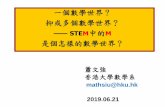





![フレッシャーズ特別号 世界スタンダード STM32Fマ …...NUCLEO F401RE [提供]STマイクロエレクトロニクス 世界スタンダード!STM32Fマイコン教科書](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fdeec4f7165f27299501e34/ffffffc-coeffff-stm32ff-nucleo-f401re.jpg)



