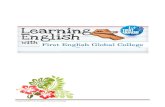留学成果報告書 - econ.tohoku.ac.jpynishide/files/studyingabroadreport.pdf2010年9月9日...
Transcript of 留学成果報告書 - econ.tohoku.ac.jpynishide/files/studyingabroadreport.pdf2010年9月9日...
2010年 9月 9日
東北大学経済学部経営学科 3年
小林 主茂
留学成果報告書
University of California Education Abroad Program 2009 - 2010
カリフォルニア大学デイヴィス校 Davis, CA, U.S.A.
Managerial Economics/ EAP Fall 2009/ Winter 2010
カリフォルニア大学デイヴィス校 ワシントンDCセンター Washington, DC, U.S.A.
Managerial Economics/ EAP-UC Davis Washington Program Spring 2010
インターナショナルレスキューコミッティー Washington, DC, U.S.A.
Asia Advocacy Intern/ Washington Program Internship March – June 2010
コロンビア大学国際公共政策大学院 人権問題研究所 New York, U.S.A.
Research and Program Intern/ EAP-Optional Training Program June – September 2010
CONTENTS
Ⅰ.学術科目面での成果
Ⅱ.研究能力面での成果
Ⅲ.実践知識面での成果
Ⅳ.言語運用面での成果
Ⅴ.交換留学課程とキャリアへの応用
Ⅵ.総括
Ⅰ.学術科目面での成果
留学中の修業期間を通しては、コミュニティー開発、地域紛争解決といったミクロレベルでの
計画能力と国際関係、外交力学などのマクロレベルでの分析能力がバランスよく養えるよう科
目選択を行った。さらに、これらの講義を通して得られた俯瞰的視点が国際開発学と開発経済
学の各分野にどのように応用されているかを学ぶため、秋季・冬季に開講されている経済開発
の授業を続けて履修し、専攻以外の分野に関する見識を深めると同時に、より実践的な知識を
獲得することができた。
国際政治学
-International Relations-
-リアリスト、リベラル、イデアリス
トの3政治力学分析視点
-国際紛争と平和構築理論
-国際機構と地球規模の問題
国際経済学
-International Economic Relations-
-国際貿易モデル分析
-貿易障壁の効果と影響
-国際収支と国際為替メカニズム
-国際マクロ・ミクロ経済理論
コミュニティー開発学
-Community Development-
-NPO/NGOと地域発展
-地域問題解決アプローチ
-ケーススタディ
国際開発学/開発経済学
-Economics of Development A&B-
エリア分析
貧困削減、人口管理、開発教育、国際保健、貿易開発、
農業開発、環境問題、MDGs、持続可能な開発
開発ツール
経済成長モデル、開発指標・評価、開発計画論、財政政
策、投資誘致、国際協力援助、対外債務削減、開発学史
リサーチトピック
“International Politics
of the United Nations
and NGOs”
リサーチトピック
“The Vanishing Era of “Simple is the
Best” in Community Development: A
Lesson from the Success of Common
Ground Community”
リサーチトピック
“Desertification in Northern Nigeria:
Visible Natural Disaster and
Invisible Human Disaster”
Ⅱ.研究能力面での成果
国際開発機関・NGOで働くにあたって、リサーチ能力は欠かせないスキルの一つである。アメ
リカの大学では特定の分野に特化した計量分析から、大学院進学を見越した総合的な研究能力
を養うためのコースも開講されているので、留学期間中は経済学と人権開発を主軸としてより
実用的な研究が行える知識を身につけることを目標の一つとした。
特に首都のワシントン DC で開講されたデイビス校独自のリサーチセミナーでは、文献収集、
論理展開、題目選定といった基本的な部分から学術プレゼンテーションと専門家インタビュー
等の応用的な手法までが包括的にカバーされ、最終的には25枚の研究論文と題目について説
明するプレゼンテーションを行うことが要求された。
さらに、本キャンパスで履修した紛争科学分析の講義では、国際紛争に関する統計分析とデー
タ解析を通して、計量的な手法を用いながら研究を展開するための基礎を学んだ。また、民族
対立、経済指標、人口動態、反政府勢力等の個別的要素がいかに紛争のダイナミックスに影響
するのか、相関関係を分析するための方法論もケーススタディを交えながら講義された。
リサーチ手法
研究計画、題目選
定、文献検索、デー
タ解析、統計分析、
ケーススタディ
応用リサーチ
学術プレゼンテー
ション、会議上のマ
ナー、専門家インタ
ビユー、インタビュ
ー理論
アドバイジング
個別アドバイス
クラス討論
研究監修・補正
研究計画書の改善
リサーチトピック
“Emerging Giant in the Southern Economy”
Does the South American monetary union satisfy the Optimum
Currency Area criteria?
新興南アメリカ諸国連合は効果的経済統合政策を実施するための基
盤を有しているか?また、地域内での各国経済・ビジネスサイクルに
は通貨統合を行えるだけの循環同期が存在するか?
紛争解決学
-Scientific Study of Civil Wars-
-紛争要素分析
-統計的重要性診断・相関解析
-応用ゲーム理論
ケーススタディ
難民流入、民族対立、反乱ダイ
ナミックス、内戦確率、国際介
入、経済指標、人口動態、医療
開発
Ⅲ.実践知識面での成果
首都 DC で開講された UC デイヴィスワシントンプログラムでは、国際人道援助分野のパイオ
ニアであり、世界的な信頼と評価を得ている International Rescue Committee の政務本部・ア
ドボカシーオフィスにて 3ヶ月間実務経験を積むことができた。未だ体験型のインターンシッ
プが多い日本企業とは一線を画し、初日から Director の代理として関連シンクタンクへ派遣さ
れ国際会議の報告書を提出するよう求められるなど、人道援助アドボカシーの最前線で実践的
な経験を積み将来のキャリアへの礎を築く貴重な機会となった。
インターンから帰宅した後の夜間コースでは政治学実務ライティングのコースを履修し、政治
スピーチ、官公庁広報、政策提言ペーパー等多岐に渡るスタイルのライティングスキルを磨く
ことができた。担当教授が前スピーチライターということもあり、ホワイトハウスにてオバマ
現大統領のチーフ・スピーチライターから課外授業を受けることができた他、ブッシュ、クリ
ントン前大統領・現職閣僚などの補佐官を招いてのゲスト講義も充実し、現代政治学を内面的
視点から学ぶ最高の機会が得られた。
実務インターンシッププログラム
-Internship in Washington DC-
International Rescue Committee
Department of Advocacy & Government Relations アドボカシー政務部
配属:アジアアドボカシー・インターン
勤務:09:00-17:00 火-金 2010 年3月-6月
関連機関での会議・連邦上院下院公聴会ヒアリング、政策メモ・現状報
告書作成、大使館へのコンサルティング、戦略ミーティングへの随行、
フランス語ドキュメンテーションの管理、上院へ送付する手紙の編集
管轄地域
アフガニスタン、パキスタ
ン、ブルマ、タイ、コンゴ
民主共和国、ウガンダ、中
央アフリカ共和国、スーダ
ン etc.
管轄分野
難民支援、人道援助、人権
保護、紛争中停、戦後復興、
国際開発、国際保健、ジェ
ンダー暴力、アメリカ外交
政策、国際援助監視、反乱
軍制圧オペレーション
etc.
主要派遣先
合衆国上院外交委員会、合衆国下院外
交委員会、国務省、InterAction、アメ
リカ平和研究所、国際戦略問題研究
所、ウッドロー・ウィルソン国際学術
センター、ジョンホプキンス大学、そ
の他提携国際 NGO etc.
政治学実務ライティング
-Speech Writing in DC-
-政治学と言論
-政治文書の作成
-主要なスピーチの特徴と秀逸点
-実務経験者特別講義
International Rescue Committeeで得た経験と知識を基に、6月から9月までの3ヶ月間はコロ
ンビア大学国際公共政策大学院(SIPA)人権問題研究所にインターンとして勤務した。SIPA
はハーバード大学ケネディ公共政策大学院等と並び世界を代表する国際関係論・国際管理論の
雄で、勤務中には著名な法学者や現代国際関係理論の最前線に立つ学者との交流を持つことが
できた。特に人権問題研究所は世界中の NGO ワーカーに対するトレーニングプログラムに重
点を置いているため、新規プログラム設立のためのリサーチや人権問題を扱った国際会議の報
告書編集など多様な仕事を経験することができ、学術的かつ実用的な視点を養うには最高の環
境であった。
また、ニューヨークという街を肌で体験した3ヶ月間は個性を磨き世界を知る上で非常な貴重
な時間となった。以前はニューヨークというとアメリカ版の東京というイメージが強かったが、
自由を愛する雰囲気の中に息づいた、差異を尊重する都市文化はどの街にも見られない独特の
もので、自分の性格に合っていると感じた。滞在中には国連本部や日本政府国連代表部で開催
されたセミナーにも参加できたほか、International Rescue Committeeの本部にも招待していた
だき、個人的な対談を通して人道支援プログラムを統括する上での障害や世界の人権問題の現
状について学ぶことができた。
留学課程付属学術トレーニングプログラム
-Optional Training Program-
The Institute for the Study of Human Rights
School of International and Public Affairs, Columbia University コロンビア大学国際公共政策大学院
配属:リサーチ・プログラム・インターン
勤務:10:00-17:00 月-金 2010 年6月-9月
宗教対立と人権侵害に関する所長の研究のサポート、副所長の研究補佐、人権保護・人道支援に関する
国際会議報告書の編集、人権トレーニングプログラムに関するリサーチ報告・提言書の作成、サマース
クール参加者向けの学術イベント管理
人権教育プログラムアーカイブ化プロジェクトの主導 外部セミナー
国際連合
-国際連合競争試験ブリーフィング
国際連合日本政府代表部
-日本の社会起業の現在と未来
国際公共政策大学院
-人権トレーニングガイダンス
ヒューマン・ライツ・ウォッチ
-人権保護フィルムスクリーニング
etc.
主導プロジェクト
世界各地の大学院・メディカルスクール・ロースクール・研究機
関が提供している人権教育に関するプログラムやトレーニングの
アーカイブ化。専攻・機関単位で約 800 のプログラムを精査・研
究し、比較ができる状態に整理・統合。研究結果に基づいて新規
プログラム立ち上げに有用な提言書・報告書を作成・提出。
Ⅳ.言語運用面での成果
交換留学と語学留学は異なる目的を有しているとの認識のもと、今回の留学を英語を学ぶため
の留学ではなく英語で学ぶための留学と位置づけ、渡航以前から語学面に関しては全く問題が
ないよう継続的な学習を行った。一年次後半より大学で講義を受ける際にはノートを全て英語
で取り、教科書・参考書も英語版のみを用いるようにしていたため、留学しても特に学習状況
が変わることがなく、カリフォルニア大学での講義を理解する際にも全く障害がなかった。
しかしながら、大学院専門課程で学び国際 IGO等で働くためには分野別の専門知識と用語を習
得する必要があるため、授業の参考書以外にも関連分野の文献や書籍を積極的に読むように心
がけた。
秋季にはより明確な言語を駆使して専門的研究が行えるよう、主に大学院生向けに開講されて
いる ESLのコースを受講し、大量かつ多様なスタイルのライティングをこなすことにより表現
能力に幅をつけることができた。特にこのコースは論理展開や全体構成を俯瞰して文章を構成
できる能力を養成することを目標としていたが、その達成はワシントン DC で報告書を作成し
ている際に実感することができた。リスニング、スピーキングに関しては留学当初から特段の
進歩がなく、教授やオフィスの上司とコミュニケーションを取る上で困ることは全くなかった。
ただ、ワシントンでの経験を通じては国連職員、外交官、政治家、NGOワーカーと立場の違う
相手によって異なる言語ニュアンスを用いて話せるようになったことが成果としてあげられる。
英語以外の言語に関しても、より多くの文献が読めるようスペイン語の授業を受講し、リサー
チや文書作成上の包括性と広範性を高めることができた。ワシントン DC では短期間ではある
が文書統合と整理のためにフランス語で仕事をすることがあったが、より専門的語彙を習得す
る必要性を実感した。そのため現在は、国連機関等が発行する多言語報告書を用いながらスペ
イン語・フランス語を中心として語学力の強化に努めており、卒業までに英語、フランス語、
スペイン語の三言語でリサーチができるようになることをひとつのマイルストーンとして設定
している。
語学履修コース
国際大学院生 ESLコース –International Graduate Students ESL-
ライティングを中心としたより高度な語学力を習得するための特別コース。学術プレゼンテー
ション、論文要約など研究に直結する英語能力を練成するためのカリキュラムが組まれている。
初級スペイン語 -Elementary Spanish-
平日月曜日から金曜日まで、3 ヶ月間開講される集中的な入門コース。中級レベルまでの進歩
を目標とし、日常コミュニケーションに問題がない程度までの語学力達成が期待される。
Ⅳ.交換留学課程とキャリアへの応用
前ページまでの学術知識、研究能力、実務経験、語学能力と分野別に達成された成果を踏まえ、
今回の留学経験はキャリア形成のために努力・改善が必要な点を浮き彫りにするための絶好の
機会となった。さらに、ワシントン DC で構築したネットワークを基にしながら、目標に到達
していくための具体的ルートについてもある程度の構想を得ることができ、最終的にはどのよ
うにして知識と経験を両得していくかが今後の課題であると位置づけるに至った。
大学院進学と国際 NGOへの就職
留学以前から国際機関への就職を目指し主要な国際公共政策大学院のリストアップ等を行って
いたが、ワシントンでインターン中に多くの上司からアドバイスを頂き、学部卒業後すぐに専
門職大学院へと進学するというのは賢明な選択しではないと理解するようになった。多くのプ
ログラムが実践的なコースを提供しているため具体的な職務経験や実績がなければ授業に対す
る貢献度が相対的に低くなる上、2 年間という貴重な期間で得るインパクトを最大化すること
も困難であるからである。
「修士というのはただ単に受け取るだけの学位ではなく、その学術コミュニティーに自分が何
を与えられるのかが問われる試練。」
自身も国際公共政策の修士課程で学んだ直属の上司からの経験に基づいたアドバイスは、卒業
後の方向性を転換するのに十分な説得力があった。
一方、ニューヨーク市内で教授や専門家と意見を交換する中では、「上に進む準備ができている
者はあえて機会を待つ必要はない」という意見が多数を占めた。特にコロンビア大学国際公共
政策大学院の卒業者・教授陣からは、学部課程で土台となるような教育を修了し、豊富なイン
ターン経験を積んだ者は学部から直接大学院課程へと応募する準備ができているのではないか
という意見をいただいた。
そのため、現在は多くの専門職大学院が推奨する「最低2年」という実務経験が積めるよう、
東京にリエゾンオフィスを持っている国際 NGO やワシントン DC のネットワークに就職する
機会を模索する傍ら、大学院進学のための準備も並行して進めている。2010 年の夏季・冬季、
2011年の夏季・冬季とさらに多くのインターンシップ・ボランティアをこなし、大学院教育を
追求する上で即戦力となりうる十分な実力を養うことが当面の目標となる。
また応募する修士プログラム選定にあたっても、主にワシントン DC で働いている国際 NGO
ワーカーの声を参考にすることができた。留学以前から調べていた大学院はアメリカ・イギリ
スを含めて 50 校程度であったが、現在は自分の専門分野での進路と強化が必要な点を総合的
に判断し、コロンビア大学国際公共政策大学院やハーヴァード大学ケネディ行政大学院等の 10
プログラムに絞るに至った。特に人権教育プログラムのアーカイブ化を進める中では何百もの
プログラムを詳細に研究する機会を得、ほぼ飽和状態に到るまで情報量を拡大することができ
たのは非常に有益であった。
さらに、以前は優れたプログラムさえそろっていれば大学の立地などは特に重要でないと考え
ていたが、大学院課程で学びながら高度なインターンシップ経験が積めるワシントン DC・ニ
ューヨークは知識と経験を両立させるのに非常に適した場所であると実感した。現在は複数の
キャンパスでユニークなプログラムを追求できるという面を鑑みて、ダブルディグリーも視野
に入れている。立地の面では多数の国際機関が本部を置くスイスのジュネーブも魅力的である
ため、今後はヨーロッパの大学院課程のリサーチ・アメリカとの比較を通してより最適なプロ
グラムを選定していきたい。
キャリア形成の観点から見た分野別改善点
1.学術科目
ワシントンでの勤務経験を通しては、国際法分野の知識の欠如を改めて認識した。特に人権保
護・人道援助機関ではプロジェクト遂行に関連した法律のみでなく、条約や議定書等について
の見識も必要とされる。そのため、人権問題研究所にてインターン中は会議やミーティング、
リサーチの補佐を通して国際法の知識が重点的に習得できるよう努力した。今後は主要な文献
を読むのはもちろんのこと、より現実的な問題を反映したケーススタディーを通して、国際開
発・経済学の知識に加え応用のきく法務知識を身につけていきたい。
その他の重点分野としては非営利組織管理、マーケティングとメディアコミュニケーション、
プロジェクト評価が挙げられる。
2.データ収集と研究能力
統計分析の基礎はデイヴィス校で身につけることができたが、実践ではフィールドでのデータ
収集能力が問われる。今後の重点としては、途上国内の限られた人材資材を活用していかに正
確かつ効率的な情報収集を行うか、またそれをいかにバイアスがないよう報告書に統合してア
ドボカシーに役立てていくか、など主にデータ収集の分野を集中的にに補強していきたい。
3.開発管理の専門知識
留学中に行った2つのインターンは双方とも人道支援・人権保護の分野であったため、経済開
発の視点は副次的なものとして扱われることが多かった。今後のインターンではより途上国と
のインタラクションが多く、国際開発を通した人間の安全保障拡大に焦点があてられているよ
うなポジションを経験し、より専門的かつ包括的な活動が行える基盤を構築していくことが課
題となる。
4.スペイン語・フランス語の語学能力強化
ワシントン DC でもコロンビア大学のインターン先でも、職場の同僚はインターンを含めてほ
ぼ全員が多言語話者であり、3 ヶ国語以上を流暢に話すものがほとんど、中には 7 ヶ国語で仕
事をしている人もいた。自分の第二・第三言語はまだネイティブレベルの作業ができる水準で
はないので、今後スペイン語を第一重点強化言語、フランス語を第二重点強化言語として設定
し、卒業までには最低 3ヶ国語で職務が遂行できるレベルまでまで改善していきたい。
5.途上国・紛争影響下にある地域での経験
国際開発・人道支援のキャリアを追求する上で、途上国やフィールドでの経験がない全くない
というのは完全に致命的である。残りの在学期間はアジア・アフリカ・ラテンアメリカなどで
の短期ボランティアプログラムを通して現場に根ざした視点を形成できるよう、広範な活動を
行っていきたい。
Ⅵ.総括
今回の交換留学では多くの学術的成果を残すことができ、卒業に向けて大きな弾みとなった 13
ヶ月間だった。
留学体験を通して世界の見方が変わるというのはよく聞く話であるが、自分は高校時代に一度
イタリアに留学した経験があったため、当初それ程大きな視点の変化は予期していなかった。
しかし、この一年を通して自分の考え方・人との接し方は自分でも驚くほど大きく変わったと
感じる。
一番大切だと思うようになったのは、私たち人間は本当に根本的な部分ではみんな同じである
という認識。人種や国籍、思想や信条を超えて、正義や愛情、困っている人に手を差し伸べよ
うとするすなおなきもちは人と人とをつなぐことができると学んだ。
以前は個人の考え方や主義を曲げて国際的な協力を打ち立てるのは不可能に近いと思っていた
が、国際人道援助に携わる中で発見したのは、共通の課題を前に宗教も政治的立場もないとい
うこと。道端で死にかけているこどもを見かけたなら、たとえ通りすがったのが資本主義者で
あろうと共産主義者であろうと、キリスト教徒であろうとイスラム信者であろうと、その子を
救うためにみんな必死の努力をするに違いない。そんな事実がある一方で、国際政治や国際経
済の舞台では私たちはまるで違った世界に住んでいる異なった生き物であるかのように語られ
る。見かけの違いやことばといった目に見える差異は常に強調されてしまうが、世界中の誰も
が共有するこどもを思う心や次の世代をよりよくしようという決意といった、目に見えない共
通点はその陰で霞んでしまっていると感じた。
さらにインターンシップでの経験を通しては、国家という枠組みの限界と非人間性を実感した。
多様な国からやってきた難民の話を聞いたり、上院下院で必死に援助の必要性を叫ぶアドボケ
イトの演説に耳を傾けたりするなかで、国とは人間が勝手に創りだした想像上の共同体に過ぎ
ず、私たちが見つめるべき唯一の現実は人々そのものだという価値観が深化した。そのため、
以前にも増して日本・外国という単純な区別や日本人・外国人という無意味で乱暴な線引きに
対する抵抗が高まった。国連の課題やミレニアム開発目標を引き合いに出しては、多くの学者
や外交官が金融危機、テロ、文化の差異といった面からその達成がいかに困難かを論じている。
しかし、私たちが現実に直面しているチャレンジは金融危機でもなければアルカイダでもなく、
多様化した国家の国益でもなければ文化的差異の中でのコミュニケーションでもなく、世界を
分裂したカテゴリーの集まりとして捉える思考方法そのものである。だからこそ、今後国境の
ないキャリアを追求する中では、人々を眼の中心に据えた正義と、人間を見つめるまっすぐな
視線を世界へと広げていけるよう、さらなる学術的研鑽と実務能力の獲得に努めていきたい。