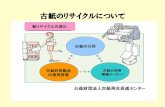廃プラスチックのガス化リサイクルとその評価 - …廃プラスチックのガス化リサイクルとその評価 -15- 中でも,容器包装リサイクル法における廃プラスチックのリサイクルは2000年4月よりペットボトル
紙おむつのリサイクル が進まない要因とその 解決策の考察 · 2017-05-24 ·...
Transcript of 紙おむつのリサイクル が進まない要因とその 解決策の考察 · 2017-05-24 ·...

紙おむつのリサイクル
が進まない要因とその
解決策の考察
東京都市大学 環境学部 環境マネジメント学科 枝廣淳子研究室 4 年
1362027 緒方峻
2017/01/30

1
目次
目次…P1
謝辞…P1
序論…P2
本論…P4~70
第 1 章:「紙おむつの構造と環境負荷とはどのようなものが考えられるのか?」…P4
第 2 章:「メーカー毎の環境配慮の取り組みの現状とは?」…P5
第 3 章:「企業はどのような取り組みをしているのか?」…P7
第 4 章:「自治体での取り組みの現状、取り組みの例」…P9
第 5 章:「紙おむつリサイクルが推進しない原因・問題点」…P21
第 6 章:「実際に行われているリサイクルの実例、その際の課題とは?」…P21
第 7 章:「インタビュー調査:公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター・
トータルケア・システム(株)、紙おむつリサイクルを推進する独立行政法人・
リサイクル会社の意見とその考察」…P26
第 8 章:「インタビュー調査:福岡県大木町、紙おむつリサイクルを既に実施している
自治体の意見とその考察」…P33
第 9 章:「インタビュー調査:紙おむつ製造企業(ユニ・チャーム株式会社)、メーカー
の紙おむつリサイクルへの考え方とその考察」…P39
第 10 章:「インタビュー調査:環境省、中央省庁の考えとその考察」…P51
第 11 章:「全インタビュー調査の振り返りと、見えてきた問題点の考察」…P62
第 12 章:「本研究を通じて見えてきた紙おむつリサイクルの発展のための提案」…P65
結論…P72
文献表…P75
謝辞
今回、この卒業研究を卒業論文として形にすることが出来たのは、指導教授として担当し
て頂いた枝廣淳子教授の熱心なご指導やトータルケア・システム株式会社の代表取締役で
ある長武志様、同営業企画課長の嘉福人文様、公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業
化センターのプロジェクト推進班企画主幹(班長)の松尾成宏様、同研究開発課コーディネー
ターの松村洋史様、同プロジェクト推進班技術主査の寺本洋子様、福岡県福岡県三潴郡大木
町の環境課課長である益田富啓様、環境省の担当者様、ユニ・チャーム株式会社の担当者様、
アンケート調査にご協力頂いた各自治体の担当者様が貴重な時間を割いてインタビュー・
アンケート調査に協力していただいたおかげです。
協力していただいた皆様へ、心から感謝の気持ちと御礼を申し上げます。

2
序論
日本において高齢者(65 歳以上)の数は現在増加傾向にあり、総務省統計局の報告書では
平成 25 年度の高齢者人口は 3186 万人で過去最多となっている。(文献表出典1)これによ
って総人口に占める割合は 25.0%で過去最高となり、4人に1人が高齢者の計算になって
いる。今後団塊世代が高齢者となっていくにつれて、さらに増加すると見られ、平成 47 年
には 65 歳以上の高齢者の人数は 3741 万人となっているとされている。(文献表出典 1)
このような状況において高齢者介護の機会は増加することが必至であると考えることが
出来、それにより杖・車いす・紙おむつ等の介護福祉用品の需要も増加が見込まれている。
実際に大手メーカーのユニ・チャーム(株)の調べでは、大人用紙おむつと子供用紙おむつの
市場規模は 2012 年に逆転し、大人用紙おむつの市場規模は子供用と比較して約 200 億円程
度大きいことが分かっている。(文献表出典 2)
特に現在中国や東南アジアで日本製の紙おむつの需要が高まっていることも影響して、
各メーカー・材料供給会社の両者ともに増産体制に移っている。その理由として、品質が高
く・安全であるという日本製の持つイメージや、新興国における紙おむつの利用が普及して
きたということも影響している。(文献表出典 3)
また子供用の紙おむつも、使用する子供の高年齢化・紙おむつの高性能化等によって使用
量も増加しているとの意見も存在していることがインタビュー調査によって判明した。
このように紙おむつの面では高齢者用の介護用紙おむつのみならず、子供用紙おむつに
至るまで需要の増加と、それに伴う消費が大きくなっているのが分かる。また上記の通り、
現在少子高齢社会が日本では進行しており、今後特に高齢者が使用する介護用紙おむつの
使用量は増大するのは確実であると見られている。
その場合、紙おむつ等の介護福祉製品の製造量・廃棄量は今後ますます増大すると考えら
れ、廃棄物問題等の環境負荷、資源の枯渇等、紙おむつの使用量・廃棄量の増加によって、
今までは問題にはならなかった環境負荷・資源面等の問題が新たに発生する可能性が危惧
される。
問題の 1 つである廃棄物問題では、可燃ごみにおける紙おむつの比重がより高まってく
るのではないかと見られている。福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会報告
書によると焼却ごみは今後減少傾向にあるとされている。特に 2012 年から 2060 年までに
約 1,000 万トンの可燃ごみが減少すると見積もられている。(文献表出典 5)
しかしそのような状況においても、使用済み紙おむつの量はほとんど変化が無いと見ら
れている。2012 年において焼却ごみに含まれる使用済み紙おむつの割合は全国平均で 7%
を超える結果となっている。そして、今後その割合は増えていくと見られている。実際に現
在ユニ・チャーム(株)が使用済み紙おむつからパルプを再生する再資源化技術を活用した実
証試験を実施している鹿児島県志布志市においては、埋め立てごみに占めるおむつの割合
は 20%に上っている自治体が存在するなど既に問題となっている自治体も存在する。1
1 文献表出典 4

3
そのような今までは問題視されていなかった程度の問題が、今後多くの自治体において
表面化していくのではないかと考えられる。
図:焼却ごみに占める使用済み紙おむつの割合(全国):(文献表出典 5)
だが日本において紙おむつの環境配慮、特にリサイクルに取り組んでいる事例は決して
多くは無い。その為取り組みや認識が不足していると言わざるを得ないのが現状である。
その為本論文では、介護製品の中でも消耗品であり国内外において市場規模が拡大して
いる紙おむつに注目し、「紙おむつのリサイクルが進まない要因とその解決策に関する考察」
というテーマに基づき考察を行う。なお本論内では 13 の章に分けて考察を行う。
第 1 章では紙おむつの構造と環境負荷とはどのようなものが考えられるのか、第 2 章で
はメーカー毎の環境配慮の取り組みはどのようなものがあるか、第 3 章ではメーカー毎の
環境配慮の取り組みはどのようなものがあるか、第 4 章では自治体での取り組みの現状、
取り組みの例、第 5 章では紙おむつリサイクルが推進しない原因・問題点について考察を
行う。
また第 6 章では実際に行われているリサイクルの実例、その際の課題、第 7 章は紙おむ
つリサイクルを推進している(公財)福岡県リサイクル総合研究事業化センター・トータルケ
ア・システム(株)へのインタビュー調査、第 8 章では既に紙おむつリサイクルを実施してい
る大木町の環境課へのインタビュー調査、第 9 章では紙おむつメーカーの中で既にリサイ
クルに取り組んでいるユニ・チャーム(株)へのインタビュー調査、そして第 10 章において
中央省庁の 1 つで環境に関して取り組んでいる環境省廃棄物・リサイクル対策部企画課循
環型社会推進室へのインタビュー、第 11 章において今回行ってきた全インタビュー調査の
振り返りと問題点の考察、第 12 章にて研究から見えてきた紙おむつリサイクルの発展のた

4
めの提案を行う。そして最後に総括の結論を記載する。
本論
第 1 章:「紙おむつの構造と環境負荷とはどのようなものが考えられるのか?」
現在、製造・使用されている主流のおむつは、その名前にも入っている“紙”を使用した
紙おむつである。紙おむつに使用されている“紙”とは紙パルプのことである。主に使用さ
れている紙パルプは、“吸水性と保水性”に優れる、繊維が太くて長い北米の針葉樹晒パル
プ(NBKP…針葉樹晒クラフトパルプ)に限られているという。
しかし紙パルプの使用量は決して多くは無い。紙おむつの多くの部分では、紙パルプ以外
の石油由来の素材が多く使用されているのが現状となっている。
衛生材料企業の業界団体である、一般社団法人日本衛生材料工業連合会のホームページ
によると、一般的な紙おむつの構造は以下の通りであると紹介されている。
図:おむつの構造:日本衛生材料工業連合会 紙おむつの構造より引用(文献表出典 6)
おむつは主に表面材・吸水材・防水材・漏れ防止の立体ギャザー・テープ等の 5 つに分け
る事が出来る。そのうち、実際に紙パルプが使用されているのは給水材のみである。それ以
外の表面材・防水材・漏れ防止の立体ギャザー・テープ等にはそれぞれ、ポリエチレン・ポ
リプロピレン・ポリウレタン等、各石油由来の材料が使用されている。その石油由来の材料
であり、紙おむつに使用されているプラスチック類の中で、ポリエチレンに次いで多く使用
されているのは、ポリプロピレンである。また吸水材として高分子吸水材=SAP(ポリアク
リル酸ソーダ)と呼ばれる石油起源の材料も使用されている。
紙おむつの構造と構成材料は以上のとおりである。そのような特性の存在も紙おむつリ
サイクルを阻んでいるが、現状の紙おむつの処分方法にも環境負荷が高まる要因があると
考えられる。
現在行われている処分方法は、現在製造されている紙おむつが紙を原料とするパルプ以
外に複数の石油由来の素材から構成されていること、衛生面を考えると使用後の紙おむつ

5
から安心して使える素材として取り出せない等の理由から、リサイクルは行われずに、ほと
んどの自治体において焼却・埋め立て処分が行われている。
以上を踏まえ、紙おむつには以下の 3 つのような環境負荷が考えられる。
1 つ目は紙おむつの使い捨て・焼却処分によって発生する廃棄物の問題。
2 つ目は紙おむつに使用されるパルプ等の木材由来資源のみならず石油由来資源を多く
使用することに関してのライフサイクル全体での環境影響の問題。
そして 3 つ目は本来再生利用することが出来る資源を無駄に捨ててしまい、資源を適正
に活用することが出来ない問題。
これら上記の 3 点が現状では存在し、その他に今後発生が予測されている資源枯渇の可
能性もある。
第 2章:「メーカー毎の環境配慮の取り組みの現状とは?」
今回、調査を行う紙おむつを製造しているメーカーを選定するにあたり、衛生材料企業の
業界団体である、一般社団法人日本衛生材料工業連合会、全国紙製衛生材料工業会の紙おむ
つ部会に所属している 27 社を、本調査の対象として選定した。
その理由として、衛生材料製造業者・輸入販売業者が連絡を強固にし、衛生材料の品質の
向上、斯業の発展を図り、国民保健の向上に寄与するという目的の元において、日本衛生材
料工業連合会が組織されており、その全国紙製衛生材料工業会の紙おむつ部会には、名だた
る国内の紙おむつの主要メーカーが所属している事が挙げられるからである。
以上のことから日本衛生材料工業連合会、全国紙製衛生材料工業会の紙おむつ部会に所
属している企業に関して調査を実施すれば、紙おむつ業界におけるリサイクルの取り組み
の全体像が分かるのではないかと考えたためである。
今回実施した調査方法としては、日本衛生材料工業連合会、全国紙製衛生材料工業会の紙
おむつ部会に所属している 27 社の会社ホームページをそれぞれ閲覧・評価することによっ
て調査を実施した。そしてどのような取り組みが、どの程度各社で行われているか、またそ
の情報が情報開示されているのか、調査を行った。また表においては、上方に紙おむつを製
造している大手企業 8 社を掲載し、その下にその他の紙おむつメーカーや材料の供給企業
を掲載した。
企業名 紙おむつに関して HP に環
境への取り組みの記載の有
無
具体的な目標の有無 目標に具体的な数字の記載の
有無
ユニ・チャーム株式会社 〇(エコチャーミングマ
ーク)・その他※₅-₆ △(全体で記載有) ✖
株式会社リブドゥコーポレ
ーション
○(紙おむつリサイクル
システム)※₇ ✖ ✖
P&G 株式会社 ✖ ✖ ✖

6
白十字株式会社 ✖ ✖ ✖
日本製紙クレシア株式会社 △(会社全体の取り組み
で記載有)※₃
△(会社全体の取り組み
で記載有)※₃
△(会社全体の取り組みで
記載有)※₃
大王製紙株式会社 △(会社全体の取り組み
で記載有)※₂
△(会社全体の取り組み
で記載有)※₂
△(会社全体の取り組みで
記載有)※₂
花王株式会社 ✖ ✖ ✖
王子ネピア株式会社 ✖ ✖ ✖
アイム株式会社 ✖ ✖ ✖
池田紙業株式会社 ※₁ ✖ ✖ ✖
伊野紙株式会社 ✖(HP 無し) ✖(HP 無し) ✖(HP 無し)
イワツキ株式会社 ✖ ✖ ✖
川本産業株式会社 ✖ ✖ ✖
クー・メディカル・ジャパ
ン株式会社 ✖ ✖ ✖
株式会社コーチョー ✖ ✖ ✖
株式会社光洋 ✖ ✖ ✖
株式会社サノテック ✖ ✖ ✖
第一衛材株式会社 ✖ ✖ ✖
大三株式会社 ✖ ✖ ✖
株式会社近澤製紙所 ✖ ✖ ✖
株式会社トーヨ ✖ ✖ ✖
東陽特紙株式会社 ✖ ✖ ✖
特種メーテル株式会社 ✖ ✖ ✖
ピジョン株式会社 △(会社全体の取り組み
で記載有)※₄ ✖ ✖
株式会社ララ ✖ ✖ ✖
ワンダフル日本株式会社 ✖ ✖ ✖
※1…池田紙業株式会社は不織布の生産会社
※2… 文献表出典 7 ※3… 文献表出典 8 ※4…文献表出典 9 ※5…文献表出典 10
※6…文献表出典 11 ※7…文献表出典 12
調査結果は上記の表から分かるように、紙おむつの環境への配慮はほぼ進んでいないの
が現状である。さらに配慮を実施している企業は一部の大手企業に止まっている。また、王
子ネピア株式会社等の会社では、テッシュペーパー等の他の製品において FSC 活動などを
行っていたが、その対象商品に紙おむつは含まれてはいなかった。

7
このように企業全体において、省資源・自然資源の保護を行っている企業はあるものの、
その取り組みが紙おむつにまで波及していると明記されている企業はごく少数であった。
以上の理由から、紙おむつ関連企業のリサイクルの取り組みは浸透・普及しているとは言
い難いのが現状であると考えられる。
第 3章:「企業はどのような取り組みをしているのか?」
前述の第 2 章では日本衛生材料工業連合会、全国紙製衛生材料工業会の紙おむつ部会に
所属している 27 社の紙おむつに関する環境への配慮に関して、実際にどのような取り組み
を行っているのか、調査を行った。
この章では第 2 章の調査を踏まえ、ホームページにおいて何らかの取り組みが確認され
た全 5 社(大王製紙株式会社・日本製紙クレシア株式会社・ピジョン株式会社・ユニ・チャ
ーム株式会社・株式会社リブドゥコーポレーション)の環境への配慮の取り組み・紙おむつ
へのリサイクルの実施の度合い等を調査していく。
1. 大王製紙株式会社
大王製紙株式会社では“森のリサイクル”と呼ばれる FSC 森林認証・PEFC 森林認証を
得た世界的な植林活動を行っている。また古紙のリサイクルの推進・グリーン購入法に対応
するための方針の設定などの全社を挙げた取り組みを推進している。
それ以外にも大木町の紙おむつ回収ボックスに広告出稿の形で他の紙おむつメーカー4
社と共同で一部費用負担をした。(文献表出典 7)
2. 日本製紙クレシア株式会社
日本製紙クレシア株式会社では、日本製紙グループ行動計画、環境行動計画「グリーンア
クションプラン 2015」の中で森林資源の保護育成を掲げている。その中で持続可能な資源
調達のため海外植林事業「Tree Farm 構想」を推進し、海外植林面積 20 万 ha を目指す、
国内外全ての自社林において森林認証を維持継続する、輸入広葉樹チップの全てを、PEFC
または FSC 材とする、トレーサビリティを充実させ、持続可能な森林資源調達を推進する、
といった取り組みが述べられている。また日本製紙クレシア行動計画の中においても、森林
資源の保護育成・環境に配慮した技術・製品の開発といった内容の取り組みを述べている。
(文献表出典 8)
それ以外にも大木町の紙おむつ回収ボックスに広告出稿の形で他の紙おむつメーカー4
社と共同で一部費用負担をした。
3. ピジョン株式会社
ピジョン株式会社では ISO14001 環境マネジメントシステムの認証・環境配慮製品の制
作が行われている。また生産されている環境配慮製品は、乳幼児用おむつではあるが、おし

8
っこ吸収ライナーと呼ばれる吸水材をパンツ型紙おむつにセットして使用することで、お
むつの使用枚数は約半分に減らすことができ、ゴミの削減につながることが出来るなどの
特徴がある。(文献表出典 9)
4. ユニ・チャーム株式会社
ユニ・チャーム株式会社では「環境負荷低減」と「商品価値向上」の両方の厳しい基準を
クリアした環境対応型商品に、ユニ・チャーム社独自のエコラベル「エコチャーミングマー
ク」を表示している。2008 年から開始したこの制度は、現在 25 品目の商品に適用されてい
る。運用においては、ファクター(商品の環境負荷と価値(機能など)を定量化し、新旧商
品の比較を行い、評価する環境指標のひとつ)の考え方に基づき、独自に作成したエコラベ
ルガイドラインに沿って判断しているという記載があった。そしてエコチャーミング商品
の一例の中には介護用紙おむつ・リハビリおむつ等の商品が確認できる。
ハード面では 2009 年に自立支援を可能とする排泄ケアを目的に、尿吸引ロボ「ヒューマ
ニー」を発売した。この機械は専用の尿吸引パッドに内蔵されているセンサーが尿を感知し、
瞬時に尿を自動的に吸引し、タンクに尿を溜める。これにより夜間のおむつ交換が不要とな
り、1 日 1 枚のパッドの交換で過ごせるので排泄ケアの負担を軽減、紙おむつの使用枚数が
減り、ゴミの量を重量比で 90%減らした。さらに CO2 の排出量も 80kg となり、紙おむつ
と比べて大きく削減しているとの説明がなされていた。また生物多様性の面での取り組み
は、2014 年度の活動の中で当社製品の吸収材に使用するパルプは管理された森林から採取
した木材パルプで、持続可能な資源利用に努めている。(文献表出典 10・11)
また同社では、リサイクル事業者であるトータルケア・システム株式会社(福岡県福岡市)
へ資本参加を行っており、大木町の紙おむつ回収ボックスに広告出稿の形で他の紙おむつ
メーカー4社と共同で一部費用負担をすることも行っている。
5. 株式会社リブドゥコーポレーション
株式会社リブドゥコーポレーションではリサイクル事業者であるトータルケア・システ
ム株式会社(福岡県福岡市)へ資本参加を行っているという。
また大木町の紙おむつ回収ボックスに、広告出稿の形で他の紙おむつメーカー4社と共
同で一部費用負担をした。
トータルケア・システム株式会社が行っている、水溶化処理システムの考案の際には、当
時元大手 SAP(高吸水性ポリマー)メーカーの技術者が在籍しており、その技術者が SAP
リサイクルについてのアドバイスを提供した事実が存在しているという。
以上が、会社としての環境への配慮に対して、実際に取り組みが確認できた全 5 社(大王
製紙株式会社・日本製紙クレシア株式会社・ピジョン株式会社・ユニ・チャーム株式会社・
株式会社リブドゥコーポレーション)の取り組みの内容である。取り組みの傾向としては、

9
多くの企業としては森林の保護に重きを置いているという事であるのが挙げられる。また、
現状では難しい紙おむつのリサイクルを目指して研究中の企業は、昨年から「オゾン水」を
使った「紙おむつの水溶化マテリアルリサイクル」の実験を行っているユニ・チャーム社 1
社に止まった。
しかしこのユニ・チャーム社の取り組みは、一部マスコミではすでに成功したかのような
報道がなされているが、いまだ課題は山積であり、研究中の技術となっているため、即座に
大々的な事業として実現する可能性は低い。さらに、紙おむつの多くを占める石油由来の材
料に関して、取り組んでいるような言及は一社も無かった。たしかに紙おむつのパルプは、
紙おむつ全体の重量の 70%程度に及んで、使用されているという報告書も存在する。2
しかしだからといって、同じく有限である石油資源を少しでも削減しようとする意識が
無いのは、大きな問題であると筆者は考える。それ以外でも、古紙パルプを紙おむつに利用
すると明記しているメーカーは、本調査では確認できなかった。
古紙パルプを紙おむつに使用していない理由は、肌触り・品質等の問題によるものではな
いという。紙おむつに使用する紙パルプに求められている機能が「吸水性と保水性」なので、
全ての木材パルプが紙おむつ用に該当する訳ではなく、繊維が太くて長い「北米の針葉樹晒
パルプ」に限られているためである。この北米産針葉樹晒パルプが使われる主な用途は、紙
おむつ用を除けば、いわゆる「和紙(障子紙・襖紙・奉書紙等)」や、百貨店・専門店等の手
提げ袋や、工業用大型紙袋の外側等の厚くて白い頑丈な紙用に限られており、古紙として回
収されてマーケットにでるものはごくわずかでしかない。さらに分別もされていないため、
メーカーが針葉樹晒パルプ紙の古紙利用を検討しようとしても、必要量を安定的に入手す
ることが困難であるのが現実であり、一般的に古紙利用はされていないという。このような
事情があるため、環境への対策としては十分であるとは言えないと考えられる。
以上を踏まえて、調査結果としては紙おむつの製造企業において、環境への配慮を行って
いる事は確認出来たものの、主に森林資源の保護に止まっており、偏りがあった。さらに内
容的には不十分である印象を受け、また紙おむつリサイクルの取り組みを行っている企業
は一社に止まり、その成果等の記載も無かった。
第 4章:「自治体での取り組みの現状、取り組みの例」
第 2 章・第 3 章では、主に企業を中心に取り組みの事例の調査を行った。そこでこの第 4
章では視点を変えて日本全国の自治体の調査を行った。その理由としては、現状では紙おむ
つの排出の多くが家庭から出ているからである。
現在、国内で年間約 300 万トン以上の使用済み紙おむつが排出されている。その内訳で
は、約 30%が病院や老健施設等の事業者から、残りの約 70%が家庭から出されている。そ
の家庭から出るごみは一般廃棄物(家庭系一般廃棄物)とみなされる。そして廃棄物の処理及
び清掃に関する法律の 6 条において、一般廃棄物の収集・運搬および処分は、市町村に処理
2 (文献表出典 14)

10
責任があり、市町村自らが行うのが原則であると定められている。そのため、自治体の力の
入れ具合によって、紙おむつのリサイクルの実施には大きな差が出てくるのではないかと
考えられる。
自治体の取り組みを調べるにあたり、その中でも今回は、各自治体がどのように紙おむつ
を回収しているのかを調査した。その理由としては、紙おむつの回収は、既存のごみ回収シ
ステムを活用することが大切であると考えたためである。
新しく回収システムを検討するのでは、費用や時間が掛かりすぎるうえ、回収担当者の選
定等をする必要があり多くの労力が必要となるなど、多くの問題が予想される。そのため回
収に関しては、既存の各自治体が実施しているごみ回収システムを活用して、適宜修正して
いく方が、効率的であり現実的であると、筆者が判断したためである。
以上から、紙おむつリサイクルの実現には、各自治体による使用済み紙おむつであると区
別出来る形で回収を円滑に行うことが出来れば、より実現に近づくのではない考えている。
今回調査を行ったのは、自治体における紙おむつの回収方法の実態である。調査対象は、
日本全国 47 都道府県に存在する全自治体である。対象の自治体の総数は 1,901 市町村であ
り、各自治体のホームページ(Web ページ)を閲覧して回収方法・内容の情報収集・調査を行
った。また、北海道に存在する現在ロシア連邦が実効支配している北方領土(択捉島、国後
島、色丹島、歯舞群島の島々)に存在する 6 村(色丹村・泊村・留夜別村・留別村・紗那村・
蘂取村)は、確認不能として本調査では処理した。
図:1901 自治体の紙おむつ回収の実態
本調査の結果は、上記のグラフから分かるように、紙おむつのみの回収はほとんど行われ
ておらず、他の可燃ごみと一斉に回収している自治体が、ほとんどであるということが分か

11
った。内訳としては、「可燃ごみと一斉回収を行っている自治体」は全体の 8 割(83%)を超
える 1528 であった。逆に「他の可燃ごみと完全に分けて回収している(専用袋の使用・袋に
紙おむつが入っている旨の記載・透明で中身の確認ができる自治体)」は、全体の 2%の 38
自治体に止まった。それ以外の「一斉回収ではないが、他のゴミ袋と明確に見分けが難しい
(他のゴミ袋と同じ方法で出すので間違える可能性がある等)自治体」は、全体の 1%にも満
たない 4 自治体、「他のゴミ袋と明確に区別出来ない可能性がある(使用済み紙おむつを排出
する際に、可燃ごみのゴミ袋と紙おむつ専用袋の両方が使用できる等)の自治体」は、全体
の 1%にあたる 20 自治体、「紙おむつの回収方法に関して未記載の自治体」は、全体の 10%
にあたる 182 自治体、「自治体の HP やゴミ回収に関する Web ページが無い自治体」は全
体の 4%にあたる 75 自治体という結果に終わった。
今回の調査ではある共通点が浮かび上がった。1 つは「他の可燃ごみと完全に分けて回収
している」38 自治体はその所在地において一定の偏りがあるということである。この 38 自
治体の内訳は以下の通りであるが、その中で他の可燃ごみと完全に分けて回収している自
治体が集まっており、その割合が突出しているのは東京都である。
図:紙おむつを明確に分かる形で、分別回収している 38 自治体の都道府県別の内訳
上記の表のとおり、東京都は全体の 4 割近くの 15 の自治体で、他の可燃ごみと完全に分
けて回収していることが分かった。またこの 15 の自治体はいずれも東京 23 区外の自治体
となっている。
筆者はさらに、この 38 自治体に関して財政面でも調査を行った。その調査の際に用いた
指標は、総務省が公表している「財政力指数」である。財政力指数とは、自治体の財政力を

12
示す指標である。基準となる収入額を支出額で割り算(÷)した数値を表したものである。
その数値が 1.0 であれば、収支バランスがとれていることを示しており、1.0 を上回れば基
本的に地方交付税交付金が支給されないというものである。
筆者は財政面の調査をする前に、財政の収支バランスが取れているということが、紙おむ
つを別途に回収するために専用のごみ袋を用意する等、通常の回収方法よりも費用が掛か
る回収方法を実施するためには必要となっているのではないかという仮説を考え、以上の
仮説を元に財政面の調査を企画した。
今回の調査の結果、38 自治体の内、全体の 76%に当たる 29 自治体においてその自治体
が所属している都道府県よりも財政力指数が高いという結果になった。特に区別回収をし
ている自治体が最も多く存在する東京都では、実に 15 自治体の内、87%(13 自治体)で東京
都そのものより、財政力指数が高い結果となった。
図:38 市町村の所属都道府県との財政力指数の比較
以上の調査から紙おむつの回収では、財政的な面が大きく関係してくる可能性があるの
ではないかと考えられる。さらにその財政基盤の強固さが重要なのは都道府県ではなく、一
般廃棄物の処理義務が課されている、それぞれの地方自治体の可能性があるのではないか
とも筆者は考えた。
また筆者は本調査を異なる視点から考察する為に、この 38 自治体における紙おむつを使
用していると思われる乳幼児(0 歳~3 歳まで)と高齢者(65 歳以上)の割合を調査した。
総務省統計局のデータでは全国平均では両者合計の割合が、全体の 29%となっている。
(文献表出典 1) 本調査では、母数の 38 自治体の内、各自治体役所のホームページ(Web)内
に記載があり、調査が可能であった自治体は 31 であった。その他の 7 自治体では情報を確
認することが出来なかった。
調査の結果、記録が閲覧できる 31 自治体の中では、紙おむつを使用していると思われる

13
乳幼児(0 歳~3 歳まで)と高齢者(65 歳以上)の割合が全国平均である、29%を超えている自
治体は全体の 5 割に満たない 45%となっていた。特に全体の 4 割近くの 15 の自治体を有
している東京都に至っては、高齢者と乳幼児の割合が全国平均を超えている自治体はわず
かに 3 自治体しかなく、2 割に止まっている。
そのため、紙おむつの使用が多いことが予測される高齢者と乳幼児の割合が多い自治体
において、紙おむつの区別出来る回収を行なっているわけではない可能性があることが分
かった。
つまり、紙おむつを使用が想定される人間の総数の多少が、区別出来る回収方法を実施し
ているという関係性を、本調査では実証することが出来なかった。
図:31 市町村(調査可能)の乳幼児・高齢者の全国平均の比較
前述のとおり、自治体の財政力を示す指標である財政力指数を用いての調査の結果、38
自治体の内、全体の 76%に当たる 29 自治体において、その自治体が所属している都道府県
よりも財政力指数が高いという結果になった。特に区別回収をしている自治体が最も多く
存在する東京都では、実に 15 自治体の内、87%の 13 自治体で東京都そのものよりも財政
力指数が高い結果となるなど、紙おむつの区別回収の実施において、財政面が影響している
可能性が考えられる結果となった。
以上から、紙おむつを他の可燃ごみと区別して回収する取り組みを行うには、財政基盤が
整っている自治体が行いやすいという可能性が考えられるのではないか。また、東京都にお
いて多く実施している自治体が見られたのは、東京都が日本全国 47 都道府県の中で、人口
増加率が最も高いためではないかと考えられる。
紙おむつはその製品特性上、減量が難しい特性が存在する。その為人口の増加が紙おむつ
を使用する人間の増加に繋がり、結果的に紙おむつの区別出来る方法での回収を求める声

14
が、経済的な側面から市民によって大きくなってきたのではないであろうか。後に紹介する
インタビューからも明らかなように、多くの自治体で市民への経済的等の支援で紙おむつ
の区別出来る回収を実施しているのも、この仮説を裏付けることに繋がるのではないか。
特に自然増加率に関しては、特に東京都では 2014 年より自然増加の 4 県の増加率は、前
年に比べ低下している中、東京都は唯一増加に転じるという点も大きな要因となっている
可能性も考えられる。また社会増減率においても東京都が最も大きくなっている。(文献表
出典 1)
以上から紙おむつを必要とする乳幼児や高齢者、またその家族や保護者等の多くの人々
の増加や転入によって増加している可能性があることが、紙おむつの区別回収の実施に大
きく影響が生じる可能性があるのではないかと考えられる。
上記の調査をしたうえで、筆者はこの 38 自治体(うち 1 つはインタビュー時に調査)にア
ンケート調査を行った。調査方法は該当自治体へ問い合わせフォームやメール等で質問票
を送り、回答して頂く形をとった。37 自治体中調査に協力して頂けた自治体は、全体の 73%
にあたる 28 自治体であった。本調査においては以下の 5 つの設問に回答して頂いた。
① なぜ紙おむつを他の可燃ごみと区別できるように回収をしているか
回答して頂いた 28の自治体における紙おむつを他の可燃ごみと分けて分別している理由
は、最も多くの約 7 割に上る 20 自治体において、「住民への経済的等の支援」を目的に分
別回収に取り組んでいることが分かった。2 番目に多い理由としては、4 自治体において「紙
おむつという製品特性上、個人の努力では減量が難しいことから」、他の可燃ごみと分けて
回収しているという結果となった。
またリサイクルを目的として、紙おむつを分別して回収していると回答している自治体
は 1 つに止まっている。
以上から、現状では環境配慮を目的としている自治体は少なく、住民に対する経済的・福
祉的支援の観点が、自治体の取り組みを行う動機であるということが見受けられる。
② 今後紙おむつのリサイクルを行う予定があるか、既に行っているか
調査を行った 28 自治体の中で、既に紙おむつリサイクルを行っているのは 1 自治体のみ
であり、今後紙おむつリサイクルを行うことを予定している自治体も 1 つに留まっている。
その他の自治体においては現在のところ紙おむつリサイクルを行う予定や検討は行って
いないとの回答が得られた。
③ 紙おむつリサイクルを実施・検討している、していない理由とは
上記のとおり、調査を行った中で紙おむつリサイクルを現在検討している自治体は 1 つ
に留まっており、その他は行う予定や検討もなされてはいない。唯一の紙おむつリサイクル
を行うことを検討している自治体はその方法として、剪定枝と混合してペレット燃料を製

15
造し、処理施設内のボイラー燃料に利用することを検討しているということである。その理
由としては、本来埋め立てるものをリサイクルすることによって、埋め立て処分場の延命化
を図る・エネルギー地産地消システム化のために紙おむつを有効利用する・燃料費の削減と
いうことを目指していると回答した。
その他の検討・予定していない自治体の回答は以下のとおりである。
調査の結果、最も多くの理由として挙がったのは、「紙おむつリサイクルシステムが未確
立である」という理由であり、全体の 44%に当たる 12 の自治体が回答した。その次に同数
で「リサイクル業者が近隣にない」・「衛生面で問題がある」という理由がそれぞれ 5 つの自
治体から回答があった。それ以外には「財政面」・「焼却処分のため」などがそれぞれ回答さ
れた。
図:紙おむつリサイクルを検討・実施しない理由
今回の調査結果は筆者にとって意外なものであった。当初筆者は自治体が紙おむつリサ
イクルを検討・実施しない理由として最も大きいものは、衛生面や財政面に問題があるから
ではないかと考えていた。その理由としては使用後の紙おむつには、必ず排泄物として尿や
便が付着してしまっている。そのため使用済紙おむつから作られた再生材料にも、衛生面で
問題があるのではないかという懸念が存在すると考えられる。また実際には清潔であった
としても、消費者等に不潔である可能性があるというイメージがついてしまう可能性もあ
る。さらに紙おむつリサイクルをする際には、燃料化・堆肥化する際にも追加で費用が発生
する。その為、その問題が解決されない限りは、自治体においては紙おむつリサイクルを検
討・実施することを、前向きに推進出来ないのではないかと筆者は考えていた。
調査結果は、筆者が考察した検討・実施しない理由である衛生面や財政面は確かに自治体

16
が気にしている条件ではあった。しかし実際はより自治体が紙おむつリサイクルを検討・実
施することをためらっている理由として挙げられたのは、紙おむつリサイクルシステムが
未確立であるということであった。
そのため、紙おむつリサイクルを普及させるために、まずは様々な方法で行われている紙
おむつリサイクルシステムの確定または制度化、また全国や地域ごとにおける企業・自治体
等を巻き込んだリサイクルシステム網を構築することが、紙おむつリサイクルの実施に対
して二の足を踏んでいる自治体に紙おむつリサイクルの検討・実施に踏み出せる起爆剤に
なるのではないかと考える。
④ 紙おむつを他の可燃ごみと区別して回収を行う際に苦労したこと
調査を行った 28 自治体において、紙おむつの他の可燃ごみとの区別回収を行う際に苦労
したこととして最も多いものは、「広報面」であり、全回答の 20%を占める結果となった。
2 番目に多かったのは 17%の「衛生面」、次いで「プライバシー保護」の 15%という結果
となり、上記の 3 項目で、全体の半分以上を占める結果となった。また大きな特徴としては
「苦労したことは特に無し」という回答も、第 4 位の 12%と一定数ある結果となった。
図:各自治体における紙おむつ回収時に苦労したこと
今回の調査では紙おむつの区別回収の際に自治体側が対応に苦労することは、主に広報
面・衛生面・プライバシー保護が大きな割合を占めているということが分かった。この結果
の中で特徴的であるのは、プライバシー保護が第 3 位に入っているということである。
この結果からは、周囲の人間に自らの家庭において、紙おむつを使用していることを知ら

17
れたくないと考える住民が一定数存在することの表れではないかと考えられる。今回調査
を行った東京都の武蔵野市等、一部の自治体からは集合住宅などでは周囲に紙おむつを使
用していることを知られたくない住民が、紙おむつを専用袋又は区別出来る形で排出せず、
一般の可燃ごみに混ぜて排出してしまうので対応に苦労しているとの回答も寄せられてい
る。
しかし、多くを占めるのではないかと考えていた費用に関しては、回答した自治体が少な
い結果となった。さらに特に苦労したことがないと答える自治体も一定する存在した。その
理由として筆者は元々紙おむつを使用する人口が多く、その負担軽減を住民が自治体側に
求めていた場合も多いのではないかと考える。
例えば実際に、神奈川県藤崎市では「もともと紙おむつの区別回収(専用袋を使用しての
無料回収)は住民要望も高かったため特に課題はない」との回答もあった。
今回調査を行った中で、紙おむつを使用すると考えられる年齢(0 歳~3 歳までの乳幼児と
65 歳以上の高齢者)の割合が全国平均より高い自治体は、データが存在する 24 自治体の中
では、全体の半数にあたる 12 に上った。このこともこの調査結果に影響している可能性が
あるのではないかと考えられる。
⑤ 紙おむつを他の可燃ごみと区別して回収を行う際に注意していること
調査を行った 28自治体においての紙おむつの他の可燃ごみとの区別回収を行う際に注意
したこととして最も多いものは、「衛生面」であり全回答の 22%を占める結果となった。
2 番目に多かったのは 19%の「広報面」、その後に「住民への理解を得る」(17%)・「規則
違反の発見・防止」(11%)のとなっており、この 4 つの項目で全体の約 7 割以上を占める結
果となった。
また苦労したことと同様に「注意していることは特に無し」という回答も全体の 11%と
第 4 位と同率となっている。さらにプライバシー保護に関しては、前述の苦労しているこ
とよりも低い結果となっている。
衛生面が最も高い理由としては、住民の協力が不可欠なこの取り組みにおいて、家庭で排
出する際や回収する際に如何に衛生的であるかが、取り組みが受け入れられるかどうかに
懸かっているのではないかと考える。如何に負担を軽減するためとはいっても衛生的でな
い排出・回収方法、その実施による環境被害が起こったのでは取り組みに賛同する住民は少
なくなってしまうのではないかと筆者は考察する。
そして特にプライバシー保護が苦労したことに比較して少ない理由は、各家庭において
既に家庭独自でプライバシー保護を行っているため、行政側が改めて注意する必要性が少
ない、または注意に神経を使わないで済む状況である為ではないかと考える。

18
図:各自治体における紙おむつ回収時に注意していること
上記には、調査に回答して頂いた 28 自治体の調査結果を記した。
筆者はその調査と同時に、紙おむつを使用するとみられる年齢(0 歳~3 歳までの乳幼児と
65歳以上の高齢者)の割合が、全国平均より高い12自治体に絞っての集計も実施してみた。
その結果として、紙おむつを他の可燃ごみと区別出来るように回収している理由は「経済
的等の支援」が全体の 8 割と最も多く、28 自治体対象のアンケートと結果は同様であった。
また紙おむつリサイクルを検討・実施しない理由は、「システムの未確立」・「業者が近隣に
ない」が双方とも 4 割を超える結果となり、衛生面と財政面のその両方を合わせた結果も 2
割に行かない等、28 自治体の結果よりも両者の差が如実に表れた結果となった。
紙おむつを他の可燃ごみと区別出来るようにして回収を行う際に苦労したことに関して
は、上位 3 つの「広報面」・「プライバシー保護」・「衛生面」は変わらず、その割合を伸ばし
ていた。また「住民への理解を得る」・「費用」・「特に無し」の項目は無くなったことが印象
的であった。
このことは元々紙おむつの利用者が多く存在するために住民側の要請や希望が一致して
おり、費用的な負担を住民に求める(紙おむつの区別回収を導入する)等の、自治体が回収費
用に対して出費することに関して市民の理解が得られやすく、納得しやすい可能性がある
ことがこの結果をもたらしたのではないかと思われる。そのため、その苦労は住民の理解を
得ていることで他の自治体よりも少なくなったのが、この結果に反映されているという可
能性を考えることが出来るのではないか。

19
図:紙おむつ利用者が多いと思われる 12 自治体における紙おむつ回収の際に苦労したこと
紙おむつを他の可燃ごみと区別できるようにして回収の際に注意することの上位 4 つは
「広報面(31%)」・「衛生面(15%)」・「プライバシー保護(15%)」・「規則違反の発見・防止(15%)」
となっていた。この結果は 28 自治体対象のアンケートと比較すると、1 位の「衛生面」が
低下し、2 位の「広報面」上昇してそれぞれの順位が入れ替わり、3 位の「住民への理解を
得る」が無くなり、その代わりに 5 位であったプライバシー保護が上昇して 3 位になった。
また 4 位の「規則違反の発見・防止」に関しては順位の変動はなかった。またそれ以外の下
位では「費用面」・「ルールの周知」に関する項目も無くなったことが変化した点である。
この結果は、紙おむつを使用する人が多く、元々住民が経済的支援に繋がるこの政策を求
めていたことから住民への理解を得ることが容易になり、それと同時に日頃から紙おむつ
を使用するため衛生面・費用面・ルール周知の面も同様に受け入れやすくなったためではな
いであろうか。また同様の理由で取り組みに対し、様々な価値観を持ち、それぞれ理解をし
ていると思われている住民に対して正しく目的や理由を伝えるためにも、広報面に力を入
れ、紙おむつ利用者が増加しているため、彼らが気にしているプライバシー保護に自治体は
重点を置いたのではないだろうか。

20
図:紙おむつ利用者が多いと思われる 12 自治体における紙おむつ回収の際に注意すること
以上の調査から分かったことは以下の通りである。
まず紙おむつを他の可燃ごみと区別出来るように回収している自治体は、全国の全自治
体の 2%ほどしか存在せず、ほとんどの自治体が他の可燃ごみと混在処分していると分かっ
た。また区別出来る回収方法を行っている 38 の自治体でも、その理由は「住民への経済的
等の支援」が大半を占めており、環境配慮を目的としたものではなかった。さらに紙おむつ
リサイクルを検討・実施しない理由として、自治体が挙げたものは「リサイクルシステムが
確立していない」というものが最多であり、当初筆者が予想していた、「財政・衛生面」よ
りも数値が高くなった。
このように、自治体における紙おむつの区別回収の際に苦労することは、「広報面」・「衛
生面」・「プライバシー保護」となっており、注意していることは「衛生面」・「広報面」・「住
民に理解を得ること」・「規則違反の発見・防止」であった。
ところが、苦労・注意したことの 2 つの結果は、紙おむつを利用すると思われる年齢層の
人口が多い地域においては、異なり順位が大きく入れ替わることが本調査において判明し
た。このことから紙おむつリサイクルの普及・促進に関しては、費用面・衛生面の問題より
も、まずは紙おむつリサイクルシステムの確立が、自治体の紙おむつリサイクルの検討・実
施に深く関わっている可能性がある。
さらにそれぞれの地域における、各年齢層の人口等の地域独自の特性を理解したうえで、
臨機応変な対応やアプローチを行い、各自治体の解決するべき問題点を見つけ、対応策を変
更することが必要であると考えられる。

21
第 5章:「紙おむつリサイクルが進まない原因・問題点」
第 2 章・3 章で述べた通り、紙おむつの環境配慮への取り組みは大手メーカーでしか見ら
れず、また紙おむつのリサイクルは一部では取り組みが行われているが、メーカー・自治体
等でも全国的にはまだ、リサイクルは推進されてはおらず、焼却処分が大半を占めるのが現
状である。そのような現状に紙おむつリサイクルは置かれており、紙おむつのリサイクル・
また再生材料の紙おむつへの使用等の、取り組みが推進しない要因はどのようなものが挙
げられるのか、本章では調査を行う。
紙おむつリサイクルは現状において、衛生面で多くの問題点があるとされ、紙おむつへの
リサイクル・再生材料の使用を妨げている。特に使用済み紙おむつは、一度し尿が付着した
ために、単に紙おむつを素材別に分離するだけでなく、薬剤を用いた消毒・滅菌等の処理工
程が必要になる。そのため専用の機材・設備が必要となってくる為、新たな設備投資や費用
が掛かってくるという問題点が存在する。
また紙おむつメーカー側も、紙おむつのリサイクル品ということでし尿の付着が気になる
等の不衛生であるという消費者・使用者のイメージが現状においてあり衛生面を重視する
為、なかなか利用が進めることが出来ないという側面も存在するとされている。
他にも廃パルプを堆肥化して、肥料を作る技術も研究されているが、法規制のため実現不
可能に近いものとなっている。
昭和 45 年に制定され、平成 27 年 7 月に最終改定された「廃棄物の処理及び清掃に関す
る法律」では、同法 17 条において「ふん尿の使用方法の制限」として「ふん尿は、環境省
令で定める基準に適合した方法によるのでなければ、肥料として使用してはならない。」と
定めている。そのため、人糞の肥料としての使用には加熱や化学的処理や長期熟成等の方法
で殺菌し、かつ寄生虫の発生を防ぐ等の法的規制が存在するので、ほぼ実現不可能となって
いるという意見がある。
以上のように現状においては紙おむつをリサイクルするためには、多くの新たなエネル
ギーを消費することや、衛生面・製品性能等・需要や環境面・法律面などを考慮すると、現
時点では有効な手段であると考えることは、難しくなっている。
第 6章:「実際に行われているリサイクルの実例、その際の課題とは?」
第 5 章では紙おむつのリサイクルを行う際の問題点を取り上げた。しかしこのような状
況下において、福岡県で、官民共同の紙おむつのリサイクルを行う実証実験が行われたとい
う興味深い事例が存在している。本章では福岡県で行われた実証実験を元に、リサイクル方
法の可能性・問題点を調査した。
福岡県環境部循環型社会推進課と、(公財)福岡県リサイクル総合研究事業化センターは、
平成 25 年 7 月に、学識経験者、排出事業者団体、関係各機関及び福岡都市圏の 17 市町
(福岡市、筑紫野市、春日市、大野城市、宗像市、太宰府市、古賀市、福津市、糸島市、那
珂川町、宇美町、篠栗町、志免町、須惠町、新宮町、久山町及び粕屋町)で構成する福岡都

22
市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会(委員長=北九州市立大学国際環境工学部 伊
藤洋教授)を立ち上げ、福岡都市圏での紙おむつリサイクル新プラント建設を目指して、3
年間各種実証実験と協議検討を実施した。
紙おむつは通常パルプ、プラスチック及びポリマーの複合材料で構成されており、(公財)
福岡県リサイクル総合研究事業化センターが 2015 年に調査した際には、未使用の場合重量
は大人用で約 60g なるが、そのうちパルプが 70%程度使用されているということが分かっ
た。さらに紙おむつを使用した場合、し尿を吸収して重量が約 3.5 倍に増加しており、同セ
ンターの調査でも使用済み紙おむつに含まれるし尿の割合は、全体の約 70%に上ることが
分かるなど、紙おむつ内に多くの水分が含まれることになる事が分かった。そのため、紙お
むつは燃えにくくなり、燃焼させるためには助燃材の投入が必要不可欠となってくる。
以上のように紙おむつの排出量が増加した場合、助燃材の費用負担等の要因から焼却コ
ストの増加が懸念される。現状においては使用済み紙おむつのほとんどが、可燃ごみとして
各自治体の焼却施設等で処理されている。一部で熱回収を目的とした“サーマルリサイクル”
は行われているものの、製品として再利用する“マテリアルリサイクル”は全国でもほとん
ど実施されてはいないのが現状である。リサイクル(特にマテリアルリサイクル)が浸透しな
い理由としては、使用済み紙おむつについては、使い捨てという用途上の問題や衛生面への
配慮等から、主に適正処分としての焼却処理が行われているというものは存在する。
しかし、リサイクルを実施することによって、針葉樹パルプの使用量削減(=森林資源の
保護)・焼却ごみの低減(=焼却施設の延命とごみ処理費用の低減)・リサイクル処理による
CO2 の排出抑制=温暖化防止などの大きなメリットが生まれるという利点が存在する。
その結果、福岡県では水溶化処理システムを確立することが出来た。この処理システムの
導入により、パルプとポリマーの分離技術によって、使用済紙おむつからパルプ・プラスチ
ック及び汚泥を取り出し、精製した再生パルプを建築資材へ、プラスチック及び吸水性ポリ
マーを RPF(紙・プラスチック由来燃料)へ、汚泥(微生物を利用した排水浄化施設から発生
する微生物残渣)を土壌改良剤へと、リサイクルシステムを確立することに成功した。
以上のリサイクルシステムの実施の為、平成 17 年にトータルケア・システム社が大牟田
エコタウン内に大牟田プラントを設置し、世界で初となる紙おむつのマテリアルリサイク
ル事業(水溶化処理システム)が行われた。この世界初となる紙おむつのマテリアルリサイク
ルでは、「水溶化処理システム」と呼ばれる方法を用いてリサイクルを行っている。
手順としては、一般家庭、病院・福祉施設等から回収してきた使用済み紙おむつを、リサ
イクルプラントに運ぶことが第 1 工程となっている。次に使用済み紙おむつを水と分離剤
の入った分離槽へ投入し、破砕して攪拌(かくはん)する。それによりそれぞれの比重を利用
して、パルプ・プラスチック・汚泥に分離して回収される。その後洗浄工程を経て回収され
た不純物がない上質なパルプはその後成形され主に建築資材の原料として建材メーカーに
販売される。不純物の混じった低質パルプは土壌改良材等、プラスチックはRPE(固形燃料)、
汚泥は堆肥の原料として再利用されている。

23
また、トータルケア社の処理プラントであり、大牟田エコタウン内に存在する“ラブフォ
レスト大牟田”では 1 日の処理能力は 20 トン、紙おむつ 10 万枚を誇り、パルプ回収率も
80%と高い水準である。(文献表出典 13 より引用)
上記の実証実験では、様々な問題点が浮上した結果となった。まず、消費者の意識の面で
の取り組みへの参加する際への問題点が明らかとなった。福岡市が調査を行った、紙おむつ
をリサイクルしたくない理由(複数回答有)では、圧倒的に「衛生面での問題が気になる」
というものが 63%とその他の項目を抑えて、最上位を占める結果となっている。
図:紙おむつをリサイクルしたくない理由:福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討
委員会報告書(案) より引用(文献表出典 14)
トータルケア・システム株式会社へのインタビューの際に担当者が強く語って強調して
いたのは、自社において水溶化処理システムを使用して再生した再生パルプの清潔さや安
全性であった。処理の過程では再生パルプ・廃 SAP を精製する過程では、洗浄滅菌層を通
して滅菌を行う。また使用する水の 80%を再生利用する際にも汚染処理システムを使用し
て処理を行うという処理方法を行っており、十分に清潔さ・安全性を確保している。
広報面では紙おむつリサイクルに興味を持った自治体職員・一般人などには積極的に広
報を行っている。しかし予算不足などの面から、紙おむつリサイクルを知らない、その他不
特定多数の一般人への大規模な広報活動は行えていないことが課題であると同社の嘉副営

24
業課長はインタビューの際に話していた。
そのため、紙おむつリサイクルに関しての取り組み、特に衛生面での取り組みや一般人・
消費者が気になる項目等の実際の数値などを包み隠さず公表して消費者・再生材料を使用
するメーカーサイドへの情報提供を強化し、紙おむつリサイクル・再生材料を使用した紙お
むつへの理解を得ることが重要であると考えられる。
それ以外にも紙おむつリサイクルの取り組みの公表など、広報活動を推進する際には、今
後将来的に紙おむつを使用していく子供等の若年層や中年層の大人等、これからの社会の
基盤となっていく、もしくは現在基盤となっている層に対して積極的かつ多岐に渡っての
広報を行っていくことが必要なのではないかと考える。
その他に現行の紙おむつリサイクル制度における問題点としては、福岡市が行った紙おむ
つリサイクルの推進条件を尋ねたアンケート(複数回答有)では、大きく分けて 3 つの推進条
件が浮き彫りとなる結果となった。
まず紙おむつのリサイクルを推進する際の条件として挙げられるのは、以下の 3 点である。
1 つ目は「リサイクルに係る料金がごみ処理料金と同等かそれ以下であること(68.9%、
2 つ目は「定期的に回収してもらえること(66.1%)」、3 つ目は「分別・前処理(大便等の
除去)に手間がかからないこと(62.6%)」であった。なお各項目ではそれぞれ 60%を超え
ている。以上のように現状では、コストや分別の手間といった実務的な条件が紙おむつリサ
イクルを推進するうえで課題となることが分かった。
図:紙おむつリサイクルの推進条件:福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会
報告書(案) より引用(文献表出典 14)

25
ただし上記の 3 条件の内、3 つ目の条件である「分別・前処理(大便等の除去)に手間が
かからないこと」に関しては、比較的簡単に条件のクリアが出来るのではないかと考えられ
る。そもそも紙おむつは廃棄する際に排泄物をトイレに捨てることが求められているとは
いえ、全ての排泄物は除去できず、微量の排泄物は付着したままになってしまう。そのため
放置しておくと、異臭が発生するという製品の特性上の問題がある。そのためほとんどの消
費者は、他の可燃ごみと紙おむつを分別して保管して匂いの発生・拡散を防ぐ取り組みをし
ていると思われる。また上記のように既存の紙おむつの廃棄方法でも事前に排泄物はトイ
レに流すと定めている自治体がほとんどとなっているのも事実である。
以上から紙おむつ専用袋で回収をする場合でも、比較的簡単に受け入れられるのではな
いかと考えられる。そのため紙おむつリサイクルの推進条件として難しいと筆者が考える
ものは、「経済面」・「回収の確実性」の 2 つであるのではないかと考えられえる。
上記のように、様々な問題が紙おむつリサイクルの推進を実現するために存在する。その
中でも経済面で考えてみた場合、使用済み紙おむつのリサイクル処理料金を現在のごみ処
理料金よりも安価に設定することができれば、経済原理により焼却処理からリサイクル処
理に自然と変更される可能性が高い。
しかし、逆に紙おむつのリサイクル料金が現在のごみ処理料金よりも高い場合は、経済原
理のみではリサイクルは進まない可能性が高い。
この場合、紙おむつのリサイクルを推進するためには、何らかの行政施策が必要となる。
考えられる行政施策としては以下の通りであると考えられる。
紙おむつリサイクルの推進のための行政施策
1. 事業系一般廃棄物の処理料金の値上げ
2. ごみ処理料金の徴収方法を有料指定袋制から従量制に変更
3. 事業系紙おむつに係る処理料金の設定
4. 事業系紙おむつの受入禁止措置
しかし、上記に記載した施策は、排出事業者の理解を得られる説明をすることが困難であ
り、いずれも排出事業者の経済的負担の増加となること等から、ほとんどの自治体において、
どの行政施策も実際に実施することは困難であるとされている。さらに紙おむつリサイク
ルの普及のためには、市民への分別の啓蒙、紙おむつ回収量の確保、自治他の枠を越えた広
域的な収集運搬体制、排出事業者の協力、自治体の支援等の実現が必要となってくると思わ
れている。

26
第 7章:「インタビュー調査:公益財団法人福岡県リサイクル総合研究事業化センター・
トータルケア・システム(株)、紙おむつリサイクルを推進する独立行政法
人・リサイクル会社の意見とその考察」
上記のように筆者は、紙おむつの現状・環境負荷、紙おむつリサイクルの推進のための問
題点・課題、またそれに付随する自治体・企業等の取り組みなどの実態の調査を行ってきた。
しかし、今までの調査では、主に書籍・アンケート・Web ページの閲覧などに止まってお
り、実際に紙おむつリサイクルに携わっている方々の声や意見を直接聞く機会もなかった。
また使用済み紙おむつの環境配慮を目的として、研究を行っている先行研究も存在せず、市
町村等の自治体等の現場において、紙おむつリサイクルに実際に関わっている方の主張や、
現状の取り組みの問題点や改善点を知ることが本研究において必要不可欠となっていた。
そのため筆者は、調査の一環として、福岡県においてリサイクルシステムを社会に定着さ
せることを目的に組織され、紙おむつリサイクルにも積極的に参画している“公益財団法人
福岡県リサイクル総合研究事業化センター”(以下リ総研)、福岡都市圏紙おむつリサイクル
システム検討委員会においてオブザーバーを務め、日本初の紙おむつの水溶化処理システ
ムを運用している“トータルケア・システム株式会社”(以下トータルケア社)の 2 団体に対
してインタビューを実施した。その際にお答え頂いた方は、トータルケア社からは、長代表
取締役・嘉副営業企画課長の 2 名、リ総研側からは松尾企画主幹(班長)・松村コーディネー
ター・寺本技術主査の 3 名、合計 5 名にインタビューをすることが出来た。
本第 7 章では、紙おむつリサイクルを推進し、実際にリサイクルを請け負っている事業
者という立場で以下 5 項目を回答して頂いた。
1. 実験を踏まえての現状の紙おむつリサイクルの問題点・改善点
リ総研・トータルケア社の現状の紙おむつリサイクルの問題点・改善点として両者が一致
して認識していることがあった。それは処理の際、請求されるリサイクル料金とゴミ処理に
実際にかかる費用に、大きな乖離が存在しているということである。
インタビューの際にリ総研の松尾企画主幹より横浜市のデータを見せて頂いた。それに
よると横浜市の HP においては、一般廃棄物である事業系ごみは横浜市の工場・処分地へ搬
入する際に処理費用として1㎏当たり 13 円を支払うことを定めているというものだ。
しかし松尾企画主幹はこの料金は安すぎると指摘する。本来であれば処理費用は 40 円以
上必要であるというが、実際に事業者に請求される金額とは大きくかけ離れているという
ことである。つまり一般廃棄物の焼却処理費用は安い理由は、税金をつぎ込んで安くしてい
るという理由となっている。このような例は日本全国において多く見られるという。
そのため生じる問題として挙げられるのは、行政が許可を出している業者の処理料金が
相対的に高額になるということである。そのため意識が高い事業者以外は、利益を追求して
これらは使用せず、費用の安い焼却処理を選択しがちになってしまう。産業廃棄物では民間
の業者一本なので再生利用実施率は高いという。しかし、一般廃棄物(事業系も含む)では市

27
町村の焼却やリサイクル、民間のリサイクル等の多くの選択肢があるため、どうしても処理
料金が安い焼却処分の方に流れてしまい割高なリサイクルには踏み出しにくいというのが
現状となっているという。
トータルケア社の長代表取締役からは、行政が中心で進めてしまうと、結果的に高い安い
か(経済的な比較)・現状の処理料金との比較で判断されてしまうため、ゴミ処理費用を安く
公表しているので本当の料金を出すことが必要であるという。そうしなければ完結型で行
う際に、入口の料金を下げないと出口の料金を下げることは出来ないと話しており、行政が
どこまで紙おむつリサイクルに対して腹を据えているのかが重要であると強く述べていた。
また紙おむつリサイクル事業は、誰がリサイクル事業をしようと発生するコストは変わ
らない。そのため付加価値を付けることが重要で、生活関連インフラ事業という形でインフ
ラ整備の 1 つとして紙おむつのリサイクルをやってみる視点も必要であるという、事業者
の視点でこの問題を話してくれていた。
上記のような、実際の処理料金と収集料金の乖離に関しては環境省も問題視をしている。
紙おむつではないが、食品循環資源の再生利用等の促進を進めるために環境省は、再生利用
の促進が進まない理由は、市町村に責任があるとして、民間の再生利用料金が公共サービス
の市町村の処理費用よりも“結果として”(実質ではなく、税金をつぎ込んで安くしている
から)割高になっているので進まないとしている旨の見解を示した。そのため、市町村にお
ける一般廃棄物の処理料金は再生利用の観点を踏まえ、廃棄物処理費用に関わるコストの
透明化(本当にその値段なのか、もっとかかっているのではないか明らかにすること)を促進
してほしいとの通知を出した。
トータルケア社の独自の意見としては、現状では本来の処理費用とは別に余分な処理費
用が発生するということである。現在水溶化処理システムにおいて、回収出来るものは再生
プラスチック・再生パルプ・廃 SAP・脱水汚泥である。現在紙おむつリサイクルで行われ
ている方法としては、水溶化処理等のマテリアルリサイクル、焼却の際に発生する熱エネル
ギーを回収・利用するサーマルリサイクルの 2 つが存在する。特にサーマルリサイクルの
場合、燃料として紙おむつをそのまま燃やすのではなく、紙おむつから作り出す燃料を燃や
す仕組みとなっている。その際に必要となってくる燃料は廃プラスチック・廃 SAP から作
り出す RPF 固形燃料である。
しかしながら RPF 固形燃料を加工する際には専門業者に委託する必要があり、その際に
処理費用がかかる。また脱水汚泥からコンポストを作成する場合にも、同様に専門業者に委
託する必要があるため処理費用が掛かってしまう。
さらに行政が中心で進めてしまうと、結果的に高い安いか(経済的な比較)・現状の処理料
金との比較で判断されてしまうという。高いか安いかの前に、行政が実施するという前提で
話し合いや検討を続けていけば、高い安いの議論は出てこないはずだとの意見も聞かれた。
リ総研側の独自の意見としては、“福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会報
告書”において、上記のリサイクルの処理料金以外には、紙おむつの回収量の確保・紙おむ

28
つの広域的な収集運搬・排出事業者の協力・自治体の責務及び協力という面において、現状
の紙おむつリサイクルは問題を抱えていると報告している。
筆者は以上から、ごみ処理費用の透明化は紙おむつリサイクルやその他多くのリサイク
ルにとって必要不可欠な措置であると強く感じることが出来た。またトータルケア社から
はリサイクル会社独自の視点からリサイクルに関する問題点を見出しているのではないか
と考えられる。
特に私が気になった点は、実際のゴミ処理料金と徴収する金額がなぜ乖離しているのか
についてである。一般廃棄物の処理責任を負っているのは自治体であり、全ての自治体にお
いて財政的に余裕があるという訳ではない。ならば適正な価格を徴収していこうとするの
が当然の考えではないであろうか。
そこで実際のゴミ処理料金と徴収する金額が乖離している答えとして筆者は、自治体が
処理責任を持っているからこそ、価格は安くせざるを得ないのではないかという事を考え
た。ごみ処理は、公衆衛生の観点から重要な柱とされている廃棄物政策であり、執行によっ
て地域住民の健康や環境保全の維持を行うことが求められる。しかし自治体が相応の料金
の下、回収を始めると料金を負担出来ない排出者は増えてくるのではないかと考えられる。
ごみ処理料金を値上げした場合に想定されることは、不法投棄の横行・未認可処理業者の発
生など行政の監督出来ないところでごみ処理が行われてしまう可能性である。そのため、住
民の生活を支えるためには安易に値上げをすることが難しく、税金を投入して処理を行っ
ているので差が広がっていくのではないかと思われる。
このことに関しては環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課が平成 25 年
4 月に発行した“一般廃棄物処理有料化の手引き”の手数料の料金水準の項目において住民
の受容性の考慮に関して、住民の受容性を無視した手数料の料金水準では不法投棄や不適
正排出を誘発する懸念もある。そのような観点から有料化の制度を円滑かつ効果的に運営
するために、住民の受容性に配慮することが適切である」という記載もなされており、筆者
の考察内容を裏付けているものであると考えられる。(文献表出典 15)
以上が実際のゴミ処理料金と徴収する金額が乖離している理由であると筆者は考察する。
2.将来的に再生材料を紙おむつに使用することを考えているのか、その際の問題点は
リ総研・トータルケア社の両者の回答において、再生材料を紙おむつに使用する際の問題
点として共通している個所は確認できなかった。
リ総研の回答としては、現状の紙おむつリサイクルに回す回収量が少ないことが問題で
あるという意見が出た。リ総研の松村コーディネーターが強調していたのは、紙おむつリサ
イクルを行うメーカーは民間企業であるということである。民間企業はその性質上、採算が
とれるか否かで取り組みは変わってくる。現状において行っている紙おむつリサイクルを
する際には水溶化処理等の別途処理を行う必要がある。そのためリサイクルに必要な設備
投資を行わなくてはならないという。

29
ただし現状においては使用済み紙おむつの回収量はあまり多くなく、十分な量の再生パ
ルプを生産できていない。そのため新たに設備投資をして紙おむつリサイクルを行い、その
再生材料を使用して採算がとれるようになるには、現在の再生パルプの生産量では全く足
りない。そのような背景から、現状では従来のバージンパルプを使用したほうがコストを抑
えることが出来てしまう。だから各紙おむつメーカーでは再生材料の使用を行おうとは思
わないのではないかと考えられていると話した。
民間企業が紙おむつリサイクルを行うための設備に対して、投資するためには一定程度
の物量が必要となってくる。そのためには物量を増加させる事が大切であるが、物量を増加
させる際に、同時並行で紙おむつリサイクルの取り組みを広範囲に広げていくことが必要
となってくるという。その理由は取り組みを広げることが紙おむつリサイクルに慎重で引
け腰となっている現状の意識も変化してくるためには必要であるからだ。
実際にペットボトルのマテリアルリサイクルも以前は反対が多かったが、取り組みの拡
大、回収されるペットボトルの増加で物量が増加した今では当たり前になった等の例が存
在している。そのような前例に倣い、現状の意識を変えていく為には、生産ラインに乗せる
だけの十分な量が必要であり、それさえあればもっと紙おむつのリサイクルを広げること
が可能であるとしている。
トータルケア社の回答としては、主に 3 つ存在する。1 つは紙おむつのリサイクルは大人
用・子供用によってその意識の違いがあるということである。トータルケア社の長代表取締
役は再生材料を使用した紙おむつをどの年齢層が使用するかによってリサイクルに感じる
抵抗感が変化するという。使用済み紙おむつからの再生材料を大人用の紙おむつに再利用
する場合は、大きな批判は起きないであろうという見解を示した。しかし、子供用の紙おむ
つに再生利用する場合には親が難色を示して反対する可能性が高いと業界では予想されて
いるという。
2 つ目は白=清潔という錯覚がどうしてもあるので、業界を含めて全体として問題点を捉
え、あるべき姿を訴え、ちゃんとした説明をして理解を深めていく必要があるというもので
ある。現状において紙おむつを再生利用した材料を使用して再度紙おむつにすることは試
作品のレベルまでは出来ているという。また衛生面でもクリア出来ているが後は意識の面
で理解が出来るかポイントであるとしている。長代表取締役は、紙おむつリサイクルには女
性で高齢な人ほど理解があるという。その理由として彼女らは布おむつが一般的な時代で
育っており、再利用をしていた人であるからと説明された。
3 つ目はリサイクルの必要性はメーカーも認識しているということである。以前と違うの
はメーカーサイドが環境問題を口にするようになってきた。また紙おむつから紙おむつと
いうものも話題にするようになってきたとのことである。
以上から、必ずしもメーカー側は乗り気ではないという訳ではないという。

30
筆者は以上から、リサイクルシステムの確立こそが最も必要なのではないかと推測出来
る。リ総研の意見から絶対量の確保が必要となってきていると考えられる。また自治体への
アンケートでは紙おむつリサイクルの検討・実施を行わない理由として「リサイクルシステ
ムの未確立」が最も多くを占めていた。つまりシステムの確立が、二の足を踏んでいる自治
体が紙おむつリサイクルを実施するための起爆剤となる可能性があり、メーカーや自治体
などの各機関が共同での取り組みを行う重要性を再認識した。
また消費者に対して説明することにも限界があるのではないかという事も感じた。現在
行われている紙おむつリサイクルに関しても衛生面での安全性に関しては学会発表等で科
学的に立証されているという。しかし、それでも一定以上の衛生面での懸念が、一般消費者
の間にあるのも事実である。
そのような情勢の中では取り組みにも限界があるため、一般消費者以外に啓発のポイン
トを移していくことも検討すべきではないかという意見を持った。
3.紙おむつのリサイクルを推進するために紙おむつメーカーに求めたい事
リ総研・トータルケア社の、現状の紙おむつリサイクルを推進するために、紙おむつを生
産するメーカー側に求めたい事として両者が一致して認識していることは、リサイクルを
しやすい商品を作って欲しいということである。リ総研の松村コーディネーターは、現状の
紙おむつには無駄遣いが多く素材の複雑化が進んでいると指摘する。例えば防水シートに
は主材料のポリエステル以外にもスチレンという物質も使用している。またパンツ部分に
はアクリルやゴムも使用されており、紙おむつには現状においてたくさんの素材が紙おむ
つに使用されている。
このように、紙おむつに使用されている素材の多さが、紙おむつリサイクルには材料の選
別をする際に障害となっていると話す。そのため、開発によってパルプや局部以外のポリマ
ーの使用量を減らす、また技術的に可能な部分は素材を単純化することによってリサイク
ルをしやすいような商品開発を行ってほしいと訴えていた。
その一方で松村コーディネーターはメーカー側に再生材料である再生パルプを紙おむつ
に使用を求めるためには、再生パルプの絶対量が必要であると話す。特に紙おむつ業界では、
主に紙おむつを生産している大手メーカーは、5~6 社なので再生パルプの絶対量が増えれ
ば、紙おむつに再生材料を使用してもらうことも可能なのではないかと話す。
筆者は以上から、メーカーの協力を取り付けるために世間・消費者の意識変化を促してい
くことが必要なのではないかと感じた。リ総研の松尾企画主幹は、住民は決して紙おむつリ
サイクルに反対ではないと話している。このことは、平成 21 年に特定非営利活動法人地域
循環研究所が福岡県大木町の行政に区加入している 4,256 世帯に対して行った調査におい
て、「紙おむつを分別収集・リサイクルすることについてどのように考えているか教えてく
ださい。」という項目に対して「賛成」・「条件付き賛成」が合わせて約 6 割となり、「反対」

31
が約 7%程度である調査結果が出ており、その発言を裏付けられていると考える事が出来る。
(文献表出典 16)
しかし、消費者にとって紙おむつに本来求められている快適性・利便性や、価格等を損ね
てまで紙おむつリサイクルを求めるとは考えにくいのが現状である。そのためメーカーも
なかなか踏み込むことが難しいのではないか。
紙おむつを生産するメーカーに対して、紙おむつリサイクルをしやすい製品を作ること
を求めることも大切だが外堀を埋め、メーカー側が取り組みをしやすくするためにも、同時
並行で世間・消費者の意識変化を促していくことが、リサイクルを推進する団体として必要
なのではないかという意見を持った。
4.紙おむつのリサイクルを推進するために市民・排出業者・政府等に求めたい事
リ総研・トータルケア社の両者において、紙おむつリサイクルを推進するために市民・排
出業者・政府等に求めたいこととして共通している回答個所は、確認できなかった。
リ総研の回答としては自治体及び排出業者に求めたい意見が 2 つ出た。
1 つは自治体に対し、住民の負担を少しでも安くするように制度を整備して、住民を実施
に誘導することである。つまり、紙おむつを回収する費用や袋代を他のゴミよりも安くとい
うことである。住民は決して元々リサイクルに反対的ではないとリ総研の松尾企画主幹は
話す。その為、リサイクルや専用袋の使用には快く賛同するという。
しかし、専用袋を他の袋よりも高価にする、有料にするなど新たに負担金額が増えること
が分かると途端にリサイクルには慎重になってしまうという側面が存在する。そのような
現象を防ぐためにも、自治体には住民への経済的負担がかからないように、安く誘導する必
要があるという。
2 つ目は排出業者に対し、料金の面で何と比較しているかを考えてもらい、自治体の処理
料金(焼却処分)は、税金が使用されている“ために”安いのである、ということを知っても
らいたいとのことであった。そのため今後は、その啓発を行うことも検討しているという。
トータルケア社の回答としては、自治体及び住民に求めたい意見が 3 つ出た。そのうち 2
つは自治体に対してであった。
1 つは取り組みを推進するにあたり、自治体には広報や協力体制をとり住民に対してしっ
かり説明をするということである。
2 つ目は紙おむつリサイクルの実施を街づくりの一環として取り組むことである。福岡県
大木町では、シルバー人材センターによる 65 歳以上のみの高齢者世帯を対象とした“ゴミ
出しサポート事業”を行った。これは希望があった高齢者の自宅に男女ペアで訪問し、ゴミ
回収や会話等のコミュニケーションを行う事業である。このような取り組みを他の自治体
においても実施することが出来れば、高齢者の雇用等の事業を行うことが出来るのではな
いか。さらに、紙おむつリサイクルを街づくり政策の一環として取り組みやすく、紙おむつ
リサイクルの存在価値が上昇するのではないかと考えている。

32
一方、3 つ目の住民に対して求めたいこととして挙げられたのは、取り組みの意義や方法
などを理解してもらうということであった。その理由として、紙おむつリサイクルの要点は
分別であるので、排出者である住民・事業者の協力がなくてはリサイクルをすることが困難
であると長代表取締役は話す。
筆者は以上からそれぞれ共通していることは、如何に住民や排出事業者を紙おむつリサ
イクルに参加させていくかが重要であると考えており、そのことに関して、自治体等に施策
の実施を求めているという考えであると感じた。それに関してトータルケア社の街づくり
の一環として行うという考え方は非常に斬新である。
しかし、東京のような大都市においては近所付き合いなどが希薄になっていることも問
題視されているので、大木町のような取り組みが実行できるのかは疑問である。そのため都
市部で行う際には、どのように街づくりや問題解決の為に落とし込んでいくのか、各自治体
の事情や規模に応じて、それぞれで検討する必要性を強く感じた。
5.どのような啓発活動で普及させていくのか
リ総研・トータルケア社の今後紙おむつリサイクルを普及させていくために、どのような
啓発活動を行うかについては、それぞれの特徴を生かした方法を検討・実施していた。リ総
研では、産学官民の共同研究を推進するという特性を生かし、紙おむつリサイクル検討委員
会の内容を冊子にしたものをホームページで紹介するだけではなく、全都道府県庁・福岡県
内の全自治体に送っている。さらに自治体や企業・市民の問い合わせや相談にも、積極的に、
逐次回答を行っており、そのような啓発活動を行っているという。
トータルケア社においては、まずは紙おむつのリサイクルということを、広く知ってもら
い、高齢化社会対応や町づくりという観点から、紙おむつリサイクルを知ってもらうことを
目的に、啓発活動を実施している。そのための特徴的な取り組みとして、自社の保有する大
牟田市にある紙おむつリサイクル工場の見学の受け付けを実施している。工場見学は、現状
としては小中学生や自治体・企業等の見学希望者に対しての実施が多い。特に小中学生の工
場見学は紙おむつのリサイクルの土台を作り、将来へ向けてリサイクルを当たり前の認識
にするために重要であると考えているという方針の下、トータルケア社では力を入れてい
るとのことである。その他に長代表取締役自らの講演会・展示会への出展等を行っている。
上記のような取り組みを行っている両者ではあるが、両者において共通している問題点
は、情報発信不足であった。その原因として挙げられるには予算・資金不足であるという。
トータルケア社の嘉福営業企画課長は現在、主に情報発信・啓発活動を行っている対象は
小中学生、企業・自治体関係者、紙おむつリサイクルに興味を持っている市民・市民団体な
ど、傾向としては既に紙おむつリサイクルに対して一定の関心がある対象であり、彼らのみ
に啓発活動の実施が限られているのが現状であるという。
また行っている啓発活動も、工場見学・講演会・展示会への出展等、受け身の形になって

33
しまっている。さらに紙おむつリサイクルの事を知らない・関心を持っていない一般家庭等
への啓発活動は予算の関係で難しいという理由で実施されてはいないのが現状であると説
明した。
筆者は、以上の両者の取り組みから、将来を見据えた取り組みを行っているという現状を
見る事が出来たのではないかと感じた。特に工場を所有しているリサイクル会社のアドバ
ンテージを活かした啓発の取り組みは自らの目で処理工程を見ることが出来るので見学者
の印象に残りやすいのではないかと考えられ、今後より大切なのではないかと考えられる。
しかし紙おむつを主に使用している高齢者や育児をしている保護者には、様々な問題か
ら啓発活動を行っていないとのことであった。そこで、再生材料から作られた紙おむつが生
産出来るようになった場合には、自治体とタイアップを行い、経済支援として無償提供す
る・工場見学に招く等の取り組みを行い、現在紙おむつを使用している子育て・介護世帯等
を対象に、アプローチをかけるべきではないかとも考えられる。
それ以外にも、現在はそれぞれの団体で別々に行っている取り組みを両者が得意とする
分野で分担しながらも、共同で行うことも重要なのではないかという意見を持った。
第 8章:「インタビュー調査:福岡県大木町、紙おむつリサイクルを既に実施している
自治体の意見とその考察」
第 7 章では紙おむつリサイクルを推進しているリサイクル会社・公益財団法人に対して
インタビューを実施した。本第 8 章においては実際に紙おむつリサイクルを自治体として
取り組んでいる自治体に対してインタビューを実施した。
調査対象は福岡県三潴郡大木町(以下大木町)であり、日本で唯一(執筆時)紙おむつリサイ
クルを実施しており、トータルケアに使用済み紙おむつを搬入してリサイクルを実施して
いる。本インタビュー調査では益田富啓大木町環境課長にインタビューをお願いした。
本第 8 章では紙おむつリサイクルを推進し、実際にリサイクルを行っている自治体とい
う立場で以下 8 項目について回答して頂いた。
1. どのような呼びかけ方法が最も地域住民の協力を得られやすいのか
現在大木町では、様々な手段を用いて、全ての分別のルールを広報している。それにより
認知度上昇を目指しているという。例えば、町の広報誌において現在のゴミ問題や分別状況
の問題・現状等の情報を繰り返し載せていき、町の方針を示して協力を要請した。益田課長
は繰り返しが重要であると話す。また大木町の Web サイトにおいて転入者向けのゴミの出
し方を動画にして掲載している。
その他に大木町の各地域において、行政と地域住民のパイプ役を果たしてもらうため、行
政区単位で“ゴミゼロ推進員”を選出しており、年2回の研修会を通して地域のゴミ問題・
課題を挙げてもらい、改善に努めているという。また、分別状況に応じて表彰を行い分別意

34
識の高揚を図っている。特に 4 月には地元役員の改選などでゴミ出しが乱れるので、職員
を派遣して実地研修に力を入れている。この際に希望があれば地域に出向き、分別の説明会
も随時実施しているという。
インタビュー調査の際に、益田課長が強調していたのは、「広報や回覧で一回のみでは伝
えきれない」ということであった。そのため大木町においては様々な媒体を通して紙おむつ
リサイクルへの理解・ルールの周知を行っている。
このように、自分たちの分別活動が町づくりにどのように反映されているのかが分かる
ことようにする事で、意識を高めていくことに繋げるのが大切であるとして、周知活動を行
っているという。
筆者は以上から、表彰の実施や HP での情報公開等、自らの分別活動がどのように反映さ
れるかを見える化していることは大きな意義があるのではないかと考えられる。見える化
が行われなければ、現状のごみ問題点やリサイクルの重要性は理解しにくいはずであり、そ
れらを自覚させやすくする施策は大きな効果が出るのではないかという意見を持った。
また広報に関しても、様々な媒体を通じて何度も繰り返し発信を行うということも、労力
はかかるが、制度を知ってもらい理解を得るには、近道であるのではないかと考えられる。
特に動画形式での制度説明に関しては、見やすさや伝わりやすさの点で画期的であり、その
他の自治体では取り組み例が少ないものでもあるため、紙おむつリサイクルに限らず様々
な施策の実施の際には必要なのではないかと思われる。
2.どのような紙おむつリサイクルであれば消費者に受け入れられるか
益田課長は第一に、紙おむつリサイクルが消費者に受け入れられるためには、紙おむつを
処分する際に分別が面倒ではなく、どのように再資源化・再生利用が出来ているのかのプロ
セスを住民や排出事業者に対して“見える化”されることによって当事者の理解は得られる
と思われるのではないかと話す。
ただし紙おむつという製品性質上、長期保管の際には匂いの発生があるため家庭内でも
他のゴミと分別し保管する人が多いので、分別面では抵抗無く出来ている。そのため最初か
ら他の可燃ごみとの分別での回収は集まったのではないかと考えられる。
また紙おむつを回収する際に発生する回収料金も大きな問題となっている。理由として
は、紙おむつリサイクルを実施する際の、別途個別回収した際に料金が発生してしまうと負
担が増えるためである。大木町では以前から、業者に委託して全てのゴミを回収しているが、
週二回紙おむつを回収し大牟田市の処理プラントに運ぶようになった際の運搬費について
は、業務内容の見直しにより据え置いてもらっているのが現状である。
筆者は以上から、1 つ目の項目と同様に見える化のような自分たちの行動で状況が変化す
ることを消費者や排出事業者に理解してもらうような施策の実施が、必要になっているの
ではないかと考える。そのうえで処理料金の重要性も感じる事が出来た。

35
どんなに有用な取り組みであっても負担が大幅に増大しては消費者や排出事業者は実施
することは出来ないであろう。如何に費用の増額を抑えるか、リサイクルシステムの見直し
や業者との間での交渉・協力を求めて、活動し歩み寄ることが必要であるという意見を筆者
は持った。
3.紙おむつリサイクル推進のために紙おむつメーカーに求めたい事
実際に紙おむつリサイクルを実施している大木町環境課の益田課長は、既に紙おむつリ
サイクルを取り組んでいる自治体として紙おむつメーカーに求めたいことは、3 つ存在する
という。
1 つはリサイクルしやすい素材を使用して製品を作ってもらうことである。つまり、ゴミ
としてではなく資源として使いまわしができることを前提とした製品開発を行うことが必
要であると考え、メーカー側に求めて行きたいという。
2 つ目は拡大生産者責任の考えを取り入れて、自分たちの製品がゴミ処理・資源として再
利用するための費用をあらかじめ製品に付加して業者には作って欲しいということである。
つまり、現在行われている自動車・家電などは再資源化の責任がメーカーにあるので、その
ような、メーカー側にもリサイクルの責任を負わせる制度を、紙おむつにも取り入れて欲し
いということである。
現在は、住民から排出される一般廃棄物の処理責任は自治体にあり、その費用も自治体の
税金の中から捻出されている。しかし、現行の制度では紙おむつを実際に製造している企業
側の排出責任が明確になっておらず、作ったら作りっぱなしであるということが問題であ
る。紙おむつ使用によって処理にかかる費用を自覚すれば、環境への取り組みは当たり前に
なるので、メーカーと消費者の双方の理解が必要であると益田課長は話す。
3 つ目は今のリサイクル技術(水溶化処理)はベストか分からないので、引き続き処理責任
はメーカーにも考えてもらい、そのうえで参画して欲しいということである。それによって
リサイクルしやすい製品が開発され、リサイクルそのものにもメーカーが関わっていく事
が必要だという。
筆者は以上から、自治体としては一層のメーカーへの責任の負担を求めているというこ
とを強く感じた。特にリサイクルに関しての費用負担の義務化・紙おむつリサイクルをしや
すい製品づくりを自治体側は求めている。
確かに紙おむつを設計・生産しているのはまぎれもなくメーカーであり、責任は重大であ
る。さらに、メーカーサイドが取り組まなければ、リサイクルが発展しないことは目に見え
ているのも確かである。
しかし、メーカーは民間企業であることを忘れてはいけないのではないか。現在の日本に
おける、紙おむつリサイクルという取り組みは、一部の先進的なメーカーやリサイクル会
社・自治体のみでしか、研究・実施がなされていない取り組みである。その中で取り組んで

36
いないメーカーに対して、新たに紙おむつリサイクルのために費用を出させることを認め
させるのは難しいのではないかと考える。
また紙おむつの利用者にとって紙おむつに求めているものは環境配慮よりも、衛生面・利
便性を重要としているのが現状である。そのため、利用者の求める衛生面・利便性を損ねて
まで、メーカー側が環境配慮をするとはまだ考えにくいのではないか。
以上から私はメーカーに対して負担や取り組みを求めるのも重要だが、まずは「リサイク
ルの土台を作る」、「利用者の理解を得ること」が最も重要なのではないかという意見を持っ
た。
4.紙おむつリサイクル推進のために市民・排出事業者に求めたい事
大木町において、市民・排出事業者に求めて行きたいことは、自治体が定めた資源化のた
めの分別ルールをしっかりと理解し、協力してもらいたいということの一点のみとなって
いた。
筆者は以上から、紙おむつリサイクルにおいて分別の徹底化の重要性を改めて感じた。し
かしその一方で使用済紙おむつを再生利用した商品の購入など、再生利用した商品の利用
を促すといったものは無かった。その要因として現在ではまだ市民の使用する物資におい
て再生材料を利用した商品が作られていないということもあるのではないかと考えた。
今後は紙おむつの再生材料を利用した商品の開発・普及ということを推し進めていって
もいいのではないかという意見を持った。
5.紙おむつリサイクル推進のために政府・都道府県に求めたい事
大木町において、紙おむつリサイクルを推進するために政府・都道府県に求めたいことは、
主に 3 つ存在した。
1 つは法制度の制定である。特に紙おむつに限ったことではないが、製造側にきちんと生
産する段階でリサイクルを行う責任があることを定めた法律を作ることを求めたいという。
現状においてそのような法律は環境省においては個別リサイクル法として自動車リサイ
クル法・家電リサイクル法等の法規制が整備されておりメーカーに対してもリサイクルを
行う際の義務を課すことが行われている。このような法制度の整備を紙おむつで実現する
ことを大木町としては求めているようだ。
2 つ目は「ごみ処理」から「資源管理」への考え方の転換が必要であるという。紙おむつ
を適切な処理を行うことが出来れば、再生パルプ・廃 SAP・廃プラスチック等様々な再生
材料に生まれ変わることが出来る。そしてそれらは十分に資源として使用が可能となって
いる。そのためごみ処理から資源管理という考え方への転換が、紙おむつリサイクルという
新しい取り組みを理解してもらうためには必要であるのではないかと感じた。
3 つ目は紙おむつの商品自体に処理費用を上乗せするようなデポジット等を行いリサイ
クルの促進を全国で図るべきであるというものであった。特にこの 3 点目は、小さなとこ

37
ろでは実施が難しいので政府・都道府県に対して取り組んでほしいとのことだった。
筆者は以上から、都道府県・政府には法律・条令等の諸制度の整備など強制力をもって取
り組むことに関しての期待、そしてリーダーシップをとる形になっている両者に「資源管理」
という考え方に転換して欲しいという、自治体側としての期待を感じる事が出来た。特にイ
ンタビューの際には政府や都道府県には法律などの制定を求める声が強かったのではない
かと感じた。この結果から、現在紙おむつリサイクルに関して法律面で制定はされてはおら
ず、そのことによって、足並みが揃わない原因であるのではないかとの見方もする事が出来
る。
以上から他の個別リサイクル法等の強制力のある法律の制定、現在多くの自治体で見ら
れるという処理の際、請求される処理料金とゴミ処理の際に実際にかかる費用に大きな乖
離の是正等、公権力の投入の必要性があるものは多く存在するとみられている。だからこそ、
環境省等の政府機関・中央省庁への各種法制の整備に向けての働きかけ、啓発活動の実施や
意義を理解してもらうなどの、従来の「ごみ処理」という考えをシフトさせていくことが大
切になってきているのではないかという意見を持った。
6.住民との意見交換を行う機会はあったのか
大木町における、紙おむつリサイクルを行う際に、住民との意見交換を行う機会は説明会
を除いて別途設けなかったという。またリサイクルに関するアンケート調査の中で、取り組
んでいる人の意見を集めたくらいであるという。
その他に実施していることは、ゴミゼロ推進員等の地域のパイプ役の人との研修を通じ
ての紙おむつ推進の意見交換は行っており、その内容は逐次政策に反映するようにしてい
るということである。特に新たな分別品目が増えるときには、説明会を実施しているという
ことである。それ以外の住民の意思表示の方法としては、町長への手紙という形で、要望は
随時受け付けているという。
筆者は以上から、随時住民の意見を取り入れることができる体制づくりの重要性を改め
て感じた。住民の協力が紙おむつリサイクルを行う上で重要であるのは言うまでもない。そ
の住民の意見を正確に聞き取ることが、制度の改善等に大きな役割を成すのではないか。
しかし、ただ聞くだけでは不十分である。その住民から寄せられた意見を適切に処理し、
制度に反映させる必要がある。自らの意見が反映されないと分かれば住民が意見発信の意
欲を削いでしまうことに繋がるのではないか。
以上のように、意見の汲み取りも重要ではあるということは理解出来ると考える。しかし、
出された意見を確実に処理しているということを住民にアピールする「見える化」を行うこ
とが、意見交換の場において今後ますます必要になってくるのではないかという意見を持
った。

38
7.なぜ紙おむつのリサイクルを推進しようとしたか。
大木町において、紙おむつリサイクルを推進する理由としては、現在大木町では平成 20
年に掲げたゼロ・ウェイスト宣言の元、全てのゴミの削減に取り組んでいるからである。大
木町では 2016 年(平成 28 年)度までに、ごみの焼却・埋立て処分をしない町を目指して
いる。益田課長は紙おむつリサイクルもこの取り組みの一環であるとしており、特別に紙お
むつに対してリサイクルを取り組んでいるという訳ではないと話す。
一般廃棄物は各自治体において処理責任があるため、何を優先するのかは自治体の判断
となってしまう。ただ、今後高齢化社会が進むに従って紙おむつは使用量が増える傾向にあ
ると考え、取り組む事にしたという説明を受けた。
筆者は以上から、紙おむつリサイクルの推進には自治体の判断が必要であるがその判断
を後押しする要素として、高齢者の割合等が大きく関係しているのではないかと考える。
紙おむつはその製品特性上、減量が難しいという側面が存在する。そのため高齢者人口が
増えるのであろう地区に関しては、紙おむつリサイクルに関する関心が他の自治体に比べ
て高いのではないだろうか。第 7 章にも記載したとおり、高齢者では自らが子供の時には
紙おむつではなく布おむつを使用してきたことから、再利用等の実施に対してそれほど不
快感を持たないのではないかというトータルケア社の長代表取締役の話もある。そのよう
な自治体において紙おむつリサイクルの推進を働きかけていくことも、一つの手段として
必要なのではないかという意見を持った。
8.自治体における紙おむつリサイクルの導入の条件やその問題点
益田課長は基本的に紙おむつのリサイクルは民間ベースで進めるほうが良いと話す。公
的機関だと、処理費用が高くなる傾向があり問題が多いという。
また一般廃棄物焼却施設は施設規模が比較的大きいので、税金で賄う必要があるが、リサ
イクル施設は民間の技術を活かし、柔軟に対応した方がいいと考えているという。そのため
には民間での事業採算性が問題となるが、行政との役割分担で解決できることは大きいと
思うと語った。
筆者は以上から、民間で進めることの意義はあるとは思うが、その前に多くの自治体で見
られるという処理の際請求される処理料金とゴミ処理に実際にかかる費用の間に大きな乖
離があり、その是正を自治体側が行わなければならないという考えを持った。このことは、
第 7 章に記載したリ総研・トータルケア社へのインタビューの際に大きな問題であるとさ
れたものが前述の料金の実態の乖離である。
現状においては、自治体がしているリサイクル会社の処理費用と自治体が行う焼却処分
の費用には大きなずれが存在している。その為リサイクル費用が相対的に高額となってい
る実態があるとされている。その理由として、リ総研・トータルケア社へのインタビューの

39
際に両者の担当者からは、処理料金の不足分を、税金を投入して補完している実態が存在す
るという見解を示している。
益田課長の民間の柔軟な対応が出来る点は非常に重要である。しかし現状の処理料金と
実際に処理にかかる費用が乖離しており、不足分に税金が投入されいるため、リサイクル料
金が相対的に高くなっている現状を変える事が出来なければ、いくら柔軟な対応が出来る
民間企業であろうとも対応の限界があるのではなかろうか。
現状の料金の乖離が進み、その中でリサイクルを推進しようとするなら、リサイクル会社
は料金を下げざるを得ない。そのような事態になってしまってはリサイクル会社の選択肢
の減少を招くことも予想される。
民間企業の力を借りる場合には、そのようなことも考慮しつつ、自らの自治体の制度・慣
習を見直していくことが必須になってくるのではないかという意見を持った。
第 9章:「インタビュー調査:紙おむつ製造企業(ユニ・チャーム株式会社)、メーカー
の紙おむつリサイクルへの考え方とその考察」
第 7 章では、紙おむつリサイクルを推進しているリサイクル会社・公益財団法人に対し
て、そして第 8 章においては、実際に紙おむつリサイクルに取り組んでいる自治体に対し
てインタビューを実施した。本第 9 章では、紙おむつを生産しているメーカーに対してイ
ンタビュー調査を実施した。
調査対象としたのは、「ユニ・チャーム株式会社」(以下ユニ・チャーム社)である。選定理
由は紙おむつの製造会社の中で最も紙おむつの環境配慮に取り組んでおり、オゾン処理を
活用した、紙おむつ水溶化マテリアルリサイクルの研究開発を実施しているなど紙おむつ
リサイクルに関して先進的に取り組んでいるためである。そのためどのような考え方・理
念・取り組みで紙おむつの環境配慮を行っているのかの調査を行った。
また今回は担当者の実名公開が認められなかったので「CSR 本部の担当者」(以下担当者)
という表記方法を行う。本第 9 章では紙おむつリサイクルを推進し、実際にリサイクルを
請け負っている事業者という立場で以下 2 つの大問、13 項目を回答して頂いた。
1.御社における紙おむつの環境配慮について
① 御社が考える、現在行われている紙おむつリサイクルの問題点・改善点は何か。
ユニ・チャーム社の担当者が、現在全国で行われている紙おむつリサイクルの問題点・そ
の改善点として認識しているものは、現状では紙おむつを処理した際に再度紙おむつに戻
せない、つまり循環の輪が出来ていない事が問題であるということである。
紙おむつリサイクルをするうえで重要であるのは、出口の確保であると担当者は見解を
示した。実際にリサイクルの技術が出来、再生材料を使用したモノも出来た場合でも、使い
道・売り先がなければ成り立たないと指摘する。また、担当者は既存のリサイクルシステム
にも言及していた。鳥取では現在、使用済み紙おむつをリサイクルしたものを用いて、燃料

40
として使用するサーマルリサイクルを行っている自治体が存在する。
しかし、サーマルリサイクルは燃やしてしまうために、紙おむつの資源化の面ではいかが
なものかと思うという意見を述べた。また福岡県で行われているトータルケア社の取り組
みも、紙おむつに戻せるような上質パルプには至ってないと指摘し、そこをつなげていきた
いと話した。
担当者が既存のリサイクルシステムを上記のように評価した理由は、今後海外における
紙おむつ需要が増大するという情勢からである。現在海外では新興国が発展している状態
であり、その中でも衛生環境の整備によって、紙おむつの使用率が上がってくるはずである
と担当者は言う。そのために木材資源の不足リスクが目に見えているという見解を示して
いる。そのリスクに対応するためにも、再度紙おむつにする循環の輪が必要となってくる。
そのために紙おむつを処理した後に、再度紙おむつに戻すことが必要であると考えてい
る。
筆者は以上から、紙おむつリサイクルを推進する団体の間での認識に、大きな差異がある
のではないかと感じた。第 7 章において、リ総研・トータルケア社における紙おむつリサイ
クルの問題点として挙がったものは、「回収料金の乖離・余計な処理費用・協力や運搬等」
であった。しかしユニ・チャーム社では、「循環の輪が出来ていないこと」であると考えて
いる。
ここに両者が目指す、紙おむつリサイクルの方向性の差異が見いだせるのではないか。リ
総研・トータルケア社とユニ・チャーム社とも、最終目標は「紙おむつから紙おむつを生産
すること」であるとしていた。そのうえでこの差異は興味深いものだと言える。
リ総研・トータルケア社の意見からは、紙おむつリサイクルにおける、循環の輪が出来て
いないことへの危機感はあまり感じることが出来なかった。現在トータルケア社では使用
済紙おむつを処理して住宅用建材の生産販売を行っている。だからこそ、再生材料を使用し
た製品を販売し、なおかつその買い手が存在することで循環の輪が出来ていると考えてい
るのではないか。そのような状況だからこそ、「循環の輪が出来ていないこと」をそれほど
問題視してはおらず、回収料金や処理費用といった、紙おむつリサイクルがさらに普及する
ための障害となっているものに問題意識が行くのではないか。
以上のような団体における取り組みの現状によって、同様の質問にも大きな差異が生ま
れる可能性があることが判明した。
そのため筆者は、同じリサイクルに取り組み、同じ最終目標を持つ者同士でも、取り組み
の現状を考慮して、取り組み方法・改善策を提案することが大切であるという意見を持った。
また企業ならではの視点で、循環の輪を作ることの重要性を訴えているが、最終目標は紙お
むつを処理した際に再度紙おむつにするということを目指す必要はある。
しかし今後様々な活用方法が生まれるはずである。そのような場合に備えて柔軟な発想
を出来るように備えることが求められているのではないかと考える。

41
② 御社が研究している紙おむつ水溶化マテリアルリサイクルにおける課題・改善点は
何か。
現在ユニ・チャーム社が研究しているのは、紙おむつ水溶化マテリアルリサイクルという
ものである。そのリサイクル方法における課題・問題点として挙げられるのは、研究開発段
階に留まっているということであると担当者は語った。
現在研究している紙おむつ水溶化マテリアルリサイクルは、研究室内の規模を超えた程
度で「研究開発段階」となっており、まだ実証実験の段階までも行ってはいない状態である
という。そのため小さくやっていた研究開発段階のものが、本当に大きなプラントになって
も大丈夫なのかが未知数であり、このことが現在の一番の問題点となっているという。
また現在ネックとなっているのは処理費用であると担当者は語った。処理費用に関して
は焼却処分よりも同等以下の値段でなくては受け入れられないと担当者は語っている。そ
の処理費用に関しては技術的には焼却にかかっている費用と同等以下で出来ており、試算
の段階でも成り立っている。
しかし大規模な実験は実施していないため、本当にできるかは実証がないという。そのた
め今後は、費用面が試算通りになるのかに関して、取り組む必要があるとしている。
筆者は以上から、研究開発には自治体の協力が必要不可欠であると感じた。大規模な実証
実験に関しては製造会社のみでは行うことは難しいのではないか。特に住民の理解を得る
ためには自治体の協力が必要となってくるはずである。実証実験等の協力を得やすくする
ためには、お互いの求める点に関して隠さず、腹を割って話し合える関係作りが必要となっ
ているのではないか、という意見を筆者は持った。
また今までの紙おむつリサイクルを行っている先行事例を踏まえての実施も行うべきだ。
前述のとおり、福岡県環境部循環型社会推進課と(公財)福岡県リサイクル総合研究事業化セ
ンターは、平成 25 年 7 月に、学識経験者、排出事業者団体、関係各機関及び福岡都市圏
の 17 市町で構成する福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会を立ち上げ、福
岡都市圏での紙おむつリサイクル新プラント建設を目指して、3年間各種実証実験と協議
検討を実施した。また現在大木町においては、紙おむつリサイクルをトータルケア社に委託
する形で実施している。
その取り組みや他のリサイクルを行っている自治体の実証実験のデータを有効活用する
べきだ。特にユニ・チャーム社は、大木町の紙おむつリサイクルに関しても大木町の紙おむ
つ回収ボックスに広告出稿の形で、他の紙おむつメーカー4社と共同で一部費用負担をし
た繋がりがあり、またトータルケア社にも出資を行っている。そのような繋がりを活かして、
オブザーバーとして参加を要請することも検討してみてはどうかという意見を筆者は持っ
た。

42
③ 御社が目指す(推進する)紙おむつリサイクルの完成形はどのようなものか。
その際に必要となる条件・解決すべき課題は何か。
ユニ・チャーム社が目指す、紙おむつリサイクルの完成形として担当者が回答したものは
“使用済紙おむつから出てくるものをすべて使用する”というものであった。具体例として、
糞便は堆肥化する(研究所において尿に含まれるリンを使用することを研究)、パルプ・フィ
ルム・SAP に関しては元に戻す等、燃やし捨てるものを無くして資源不足に備えることを
目指している。かつては布おむつのようにおむつは再利用をしていた。理想としてはそのよ
うな形態を目指すと担当者は回答した。
以上のようにユニ・チャーム社では、紙おむつリサイクルの完成形を設定している。その
達成のために解決すべき課題として、ユニ・チャーム社担当者は「如何に SAP を水溶化さ
せて取り除くか」ということであるという。現在生産されている紙おむつには、尿を吸うた
めに高分子吸収ポリマー(SAP)を使用している。SAP 使用されている部分の関係上はパル
プの中に入っているものである。紙おむつには、SAP 以外にもフィルムやパルプが使用さ
れているが、それらにおいては比較的容易に分離が出来る。しかし、セルロースの中に含ま
れている SAP は、普通では取り除くことは難しいという。処理の際に SAP がパルプ内に
存在すると、処理の際に使用する水を吸収してしまうので詰まりの発生や不純物になって
しまい商品として使えなくなる問題点がある。
その為「如何に SAP を水溶化させて取り除くか」がネックとなっているという。現在ユ
ニ・チャーム社においては SAP を水溶化させるための方法として、オゾン処理を用いて、
条件を工夫してやることで SAP を水溶化させることが実験室の段階では出来ている。
そのため前述のとおり、現在大規模な実験を実施しており、人口 3 万人規模の地方自治
体(鹿児島県志布志市)において 2016 年 12 月から実験を始めて、2020 年位にはその自治体
の全ての紙おむつを回収して、そしてそれを分離していきたいという見通しを示した。
筆者は以上から、利用者・消費者がおむつの再利用にどれだけ歩み寄れるように誘導する
のか、そして、歩み寄りそして出口を作ること必要性を改めて感じた。ユニ・チャーム社が
進める「使用済紙おむつから出てくるものをすべて使用する」という考えも、もし利用者・
消費者の理解が得る事が出来ず、再生材料を使用した商品に買い手がつかなければメーカ
ー側も製造する事が出来ない。このことに関してはメーカーのみならず、自治体・政府等の
協力も必要となってくるのではないか。
また紙おむつメーカーのみならず、他の材料を生産するメーカーにも紙おむつリサイク
ル推進を呼びかけていくことが大切なのではないかと考えられる。現在多くの紙おむつメ
ーカーが SAP を外注している状態となっている。そのため SAP 製造のメーカーとの共同
によって、SAP の水溶化処理の普及等を推し進めることが可能になるのではないかという
意見を持った。

43
④ 今後再生材料を紙おむつに使用する際に解決しなければならないことは何か。
ユニ・チャーム社では前述のとおり「使用済紙おむつから出てくるものをすべて使用する」
という目標の元、使用済紙おむつから再生した素材で再度、紙おむつを製造する循環の輪を
作ることを目指している。そのため再生材料を紙おむつに使用する際に解決しなければな
らないことは何かという問いに対し、「衛生面・安全性であり特にパルプにおいて大切だ」
と担当者は回答した。
衛生面・安全性の確保のため、ユニ・チャーム社ではオゾン処理の工程を採用している。
またこのオゾン処理によって、殺菌・漂白・匂いも分解可能であると担当者は紹介した。し
かし、使用済紙おむつを処理して取り出した再生材料を、再び紙おむつに使用するためには、
バージンパルプと同じ品質でなければ使用できないという制約が存在する。そのためにど
のように仕上げるかは、ミニプラントの実験では出来ているという。今後はより大規模なと
ころで出来るか、確認する必要があると担当者は話した。
筆者は以上から、再生材料を紙おむつに使用する際に解決しなければならないことで一
番ネックになっているのは、衛生面ではないかと改めて感じた。前述のとおり、ユニ・チャ
ーム社の担当者は、衛生面・安全性と説明しており、リ総研・トータルケア社の担当者の回
答も、衛生面を重要視しているのではないかと考えられる。特にトータルケア社の回答にあ
る、「子供用の紙おむつに再生利用する場合には親が難色を示して反対する可能性が高い」
並びに、「白=清潔という錯覚がどうしてもある」という意見はともに衛生面を重視してい
るとみられる。
つまり、子供用に使用するのには衛生面で課題があり、白くなければ不衛生であるという
様に、再生材料を紙おむつに使用することに関して使用者・消費者は、衛生面に関して疑問
視していることを表している。その為現状において、各々の取り組みへの理解が進んでいる
とは言い難い。このことは、リサイクルを推進する団体・メーカーの両者で一致しているも
のであり、非常に興味深い。
但し、この主張の細部では異なっているもの現状である。リ総研側は再生パルプの絶対量
が無いと、再生材料を紙おむつに使用することは難しいという姿勢を崩さなかった。
そのことに関して、この質問の際にはユニ・チャーム社の担当者からは、絶対量の必要性
に関しての回答は得られなかった。このリサイクルの取り組みは、様々な団体が協力するこ
とが重要であり、同様の問題点を認識していても、その解決策等が異なるのではシステムの
確立・循環の輪を構築することは難しいのではないか。
以上から両者の意見を共有して意見の隔たりが現れる理由を見つけることが必要である
という意見を持った。

44
⑤ 紙おむつリサイクルの認知度をどのような啓発活動で上昇させていくのか。
残念ながら現時点において紙おむつリサイクルは多くの人に認知されておらず、啓発活
動を行うことが必要でないかと筆者は考える。しかし、ユニ・チャーム社において認知度向
上を目的とした啓発活動は重要ではない、と考えていると担当者は話した。
消費者においては、ごみを出す時に紙おむつをしっかりと他のごみと分別してもらうこ
とは重要であると考えている。しかし、消費者に対しての紙おむつリサイクルへの認知度の
向上は、重要であるとは考えていないという。特に安全性の面に関しては、衛生学会等での
論文発表を行っているためその他の発表・啓発活動を行う予定はないという。
また自治体に対しては、エコプロ展やニュースリリースを行って問い合わせを頂いてい
るが、敢えて啓発活動は実施してはいなく、また必要としていないと考えているという。
担当者はその理由として、今までの自治体は紙おむつリサイクルに対して興味はあった
が技術はなかった。そのため、規模の小さな自治体でリサイクルが実施可能ということを実
証すれば、おのずと広がっていくのではないかと考えていると予測していた。
筆者は以上から、自治体における紙おむつリサイクルの広がりに対して疑問を抱いた。第
4 章において筆者は、全国の自治体に対して Web ページの閲覧と、紙おむつを他の可燃ご
みと区別できる状態で回収している 38 自治体に対してアンケートを実施して調査を行っ
た。その調査実施の際に電話を掛け、担当者に調査の趣旨の説明を行うことがあった。その
説明時に、ユニ・チャーム社が紙おむつリサイクルを行っている、また紙おむつリサイクル
そのものを知らないという担当者は少なくはなかった。
以上からも、自治体は紙おむつリサイクルに対して決して関心が高いわけではないので
あろう。その場合啓発を行わなければ、一部の意識の高い自治体のみに紙おむつリサイクル
は止まってしまい、紙おむつリサイクルは浸透しないのではないであろうか。
そのことから、少なくとも都道府県レベルの地方公共団体には、制度理解や円滑な協力体
制の構築のためにも、今後情報公開を含む積極的な啓発活動を行うべくではないのかとい
う意見を持った。
⑥ 御社における紙おむつリサイクルは、衛生面でどのような配慮をしているのか。
前述のとおり、紙おむつリサイクルを実施する中で、再生材料を紙おむつに使用する場合
に解決しなければならないことは衛生面・安全性の確保である。ユニ・チャーム社では、オ
ゾン処理を用いて衛生面を確保しているという。ユニ・チャーム社が現在研究している紙お
むつ水溶化マテリアルリサイクルでは、使用済紙おむつから低質パルプを取り出した後、製
品に使えるレベルである上質パルプにするために、大型の洗濯機で消毒洗浄を行う。その際
に、不織布・フィルム等は、再処理の時点で高温になるので衛生面に関して問題視していな
い。
しかし、パルプはその後の処理工程では熱がかからないため熱殺菌が行えないという問

45
題点が存在する。そのためパルプの中に含まれている SAP の分解も兼ねて、短時間オゾン
水の中に入れるという工程を設けている。担当者はそれによって殺菌・パルプ内に含まれて
いるタンパク質の分解・漂白を行っていると語る。実際に衛生安全性の評価では、オゾン処
理後のパルプからは排泄物に含まれる細菌(主に大腸菌)は検出されず、ヒト由来の汚れ指
標としたタンパク質濃度も、測定下限以下となるとされている。3
筆者は以上から、メーカーにおける日々の処理技術向上の必要性を感じた。今回の調査に
おいて、ユニ・チャーム社やトータルケア社においてそれぞれ独自の衛生面での配慮や処理
を行っていることを知る事が出来た。
筆者は技術者ではなく専門的な知識を有してはいない。だが現在研究している処理方法
は絶対的なものではないはずだ。特に技術は日進月歩の勢いで発展しており、その流れに追
随することが必要なのではないであろうか。現在の研究で開発されたシステムを運用する
にしても同時に更なる性能向上を目指し技術開発を邁進する必要があるという意見を持っ
た。
⑦ どのような紙おむつリサイクルであれば、消費者に受け入れられると思うか。
これまでの調査から、紙おむつを使用する消費者に対して、衛生面等から現時点では受け
入れられにくいのではないかと筆者は考えおり、最も紙おむつリサイクルを熱心に研究し
ているユニ・チャーム社において、どのような紙おむつリサイクルであれば、消費者に受け
入れられると考えているかを担当者に聞いた。
その結果、ユニ・チャーム社では、現時点では不特定多数の消費者に紙おむつリサイクル
を受け入れてもらうことは難しいのではないかと考えているという。前述のとおり、衛生面
等において、科学的にはバージンパルプと品質は変わらないことは証明されている。
しかし、消費者に対して、いくら学会で品質が変わらないということを証明されていると
説明しても、根本的になかなか理解してもらうことは難しいのではないかと考えていると
いう。そこでユニ・チャーム社では、紙おむつを使用する人の中でも、子供の保護者以外に
多くの割合を占めている、高齢者等のお世話をする医療・介護従事者に対象を絞っていると
いう。担当者は医療・介護従事者ならば科学的知識を持っている人が多い。そのため高齢者
にかかわる人に使用を促していき、介護施設を中心に安心して使えるようなものを作って
いけば、自ずと市民も安心して広がっていくのではないかと考えると説明した。
そのような戦略があるため、現在は高齢者中心にした紙おむつリサイクルを考えている
という。その理由としては、高齢者にとっては自らが再利用する布おむつを使用している経
験があるので、使い捨ての紙おむつのみしか使用してこなかった人に比較すると、再利用す
ることに抵抗感が少ないからであると考えていると、担当者から説明がなされた。
以上から、再生材料を使用した紙おむつを、高齢者施設を中心に導入していけたら良いと
3 (文献表出典 17)

46
考えており、医療・介護従事者への普及が、紙おむつリサイクルの第一歩としている。
筆者は以上から、敢えて一般消費者に対して理解を求めるのではなく、専門知識を持って
いる医療・介護従事者に対して、使用を促していくという発想の転換は、非常に重要であり
興味深いという考えを持った。
そのうえでよりよい成果を得るためには、先行事例を基にした取り組みの実施と、どのよ
うに医療・介護従事者に対して使用を促していくのかを考えていく必要があるのではない
か。特に医療・介護従事者は生命を扱う仕事であり、衛生面では神経をとがらせているはず
でありその対策を取らなければ納得はしてもらえないのではないか。
だが、啓発対象を医療・介護従事者に絞ったのは素晴らしい発想ではないかと考えた。そ
のうえで彼らに対して、どのような方法で処理をしているのか等の実演を含めた、見学会等
の取り組みを実施して、受け入れられるように努力を行う必要があるのではないかという
意見を持った。
⑧ リサイクルシステムの確立に向けてどのようなことを考え、取り組んでいるか。
筆者が行った第 4 章の調査において、自治体が紙おむつリサイクルを検討・実施しない
理由で最も多かったものは「紙おむつリサイクルシステムが確立していない」というもので、
財政面・衛生面を上回った結果となった。そのため、紙おむつリサイクルにおいては、その
リサイクルシステム確立が重要であると考えられる。それに対してユニ・チャーム社ではど
のように考えており、取り組んでいるのか聞いた。
その結果、ユニ・チャーム社では、実際に実証実験として実施可能ということを示すこと
でリサイクルシステム確立に取り組んでいこうとしているという。今までの紙おむつリサ
イクルの研究は実験プラントで行ってきたものであった。だが、今年(2016 年)から人口 3 万
人の自治体で小規模なプラントを作り、2020 年にはそこで処理が出来るように回収・住民
の方に理解を得るということを考えているという。
この実証実験の目標は、採算がとれるかを目指しており、その完遂が我々の取り組んでい
ることであると担当者は語った。そのため回収がしやすく、優秀な処理業者がいるところを
選んで今年から始めたという。
また筆者の紙おむつリサイクルに関するメーカー同士のつながりの有無に関して尋ねた
ところ、リサイクルに関するメーカー同士の連合体や、部会の設置に関しては、他社のメー
カーが全く取り組んでいないので行われてはいないという。ただし海外のメーカーでは一
部リサイクルを行っているという。
それ以外にリサイクルを推進する自治体などに対して行う資金出資に関しては今後、プ
ラントの建設などの際にはあるかもしれないのが、現状では未定であるという。担当者は自
治体がリサイクルに踏み切れない問題としては、財政面というよりは「安心して行えるのか」
というシステムが仕上がってないという様に、現状では自治体は考えているのではないか

47
と説明した。
筆者は以上から、実証実験を行うことで、実際に実施可能なのかを証明することの重要性
を改めて感じる事が出来た。そのうえで実証実験の結果を様々な規模の自治体に落とし込
める形にすべきである。そのようにすることで全ての自治体において、実施される実証実験
を自らの自治体に当てはめて検討出来るようになるはずであるのではないか。
そのような配慮を行うことによって、小規模な自治体のみならず大都市などを含めて多
くの自治体が検討する事が出来るはずであり、必要であるという意見を持った。
2.今まで私が行ったインタビュー・調査を踏まえた質問(企業への要望など)
①リサイクル会社はリサイクルが容易な製品(素材の単純化・パルプ、ポリマーの使用
量を減らす等)の製作を求めているが、どのように考え、取り組んでいるか。
今まで筆者が行ったインタビューでは、リ総研・トータルケア社からは「リサイクルが容
易な製品の制作(素材の単純化・材料使用量減)」ということを紙おむつメーカーに対して求
めているということが分かった。この要望に関してユニ・チャーム社はどのように考えてお
り、取り組んでいるのか聞いた。
この質問に対してユニ・チャーム社の担当者は、現状ではリサイクルを優先した商品開発
は行ってはいないという。しかし担当者は最終的にはリサイクルをしやすい紙おむつを作
りたいと思っていると語っていた。
取り組んでいない理由として、紙おむつリサイクルのシステム全体が仕上がってない段
階で我々だけが舵を取るわけにはいかないからだという。また今は快適性が一番であるの
で、そちらを優先しているため、再生材料を使用することは考えていないとしている。
将来的にリサイクルシステムが進んだ段階で、どこを簡略化すればリサイクルをしやす
いかを見出すつもりであるという。その際には紙おむつリサイクルの方向に進んでいくと
担当者は見通しを持っていた。
以上のように企業としての理念・消費者のニーズを反映させると現時点で、リサイクル材
料を使用した製品を開発するのは、紙おむつリサイクルが現在初期の段階という理由から
考えてはおらず、使用者の使いやすさ・利便性の実現をリサイクルよりも優先している。
つまりユニ・チャーム社の基本方針では、リサイクルを実施するために消費者が求めてい
る快適性・利便性を損ねることは本末転倒となっているのが現状であり、それを損ねてまで
リサイクルをするのは難しいということである。
その際に他の紙おむつメーカーの取り組みがどうこうではないと担当者は話していたの
が印象的であった。
筆者は以上から、メーカーとしては紙おむつリサイクルシステムの確立・消費者の意識変
化により紙おむつの環境配慮を求めるようにならなければ実施が難しいという意見を本調

48
査によって得た。そのうえで筆者は紙おむつリサイクルシステムの確立こそが最も必要と
なっているのではないかと考えられる。
しかしユニ・チャーム社の意見の中にある、消費者のニーズという面ではその変化を促す
ことは商品特性上困難であると思われる。そのため、紙おむつリサイクルシステムを確立さ
せることが自治体・企業に見通しを立てやすくなるのではないか。またそのリサイクルは再
生材料の使用を紙おむつのみに限ってでなく、住宅用建材等も含め、その活用方法を柔軟に
検討することが大切なのではないかと考えられる。
②既にリサイクルに取り組んでいる自治体は、資源として使いまわしが出来ることを
前提とした商品開発や、自動車等のような拡大生産者責任に基づく製品への処理費
用の付加を求めているが、どのように考えているか。
今まで筆者が行ったインタビューでは大木町からは、「資源として使いまわしが出来るこ
とを前提とした商品開発や、自動車等のような拡大生産者責任に基づく製品への処理費用
の付加すること」を紙おむつメーカーに対して求めているということが分かった。この要望
に関してユニ・チャーム社がどのように考えており、取り組んでいるのか聞いた。
この質問に対してユニ・チャーム社の担当者は、資源として使いまわしが出来るようにす
るために、パルプ・フィルムを元の状態に戻すようにしており、現在技術開発を通じて使い
まわしが出来るようにしていると説明した。
しかしそのうえで、紙おむつに対して拡大生産者責任(EPR)を適用する事には、難色を示
した。担当者がまず語ったのは EPR に関して、自動車等の産業の規模が違うという。また
環境省に聞いても、一般消費財にまでそのようなことを求めれば、その他の様々なもの全て
にも付与する必要が出ると言われたと話し、世界的にもそのような考えはあまり無いので
はないかとされていると話した。また現状では、個別リサイクル法として包装容器リサイク
ル法などが代表的であるが、その法律の下、リサイクルするために集めようとしたものはほ
とんどが燃やされているのが現状であるという。そのため現状では再使用できるものも焼
却されており、それにも処理費用が掛かることとなっている。
以上のように、本来燃やさなくてもいいものを燃やしているのが現状であると言い、それ
に対ししっかりと有効活用されるようにならなければ、EPR 導入に反対であるというのが
ユニ・チャーム社の立場であると述べていた。
さらにメーカーに対して、EPR を求める動きはゼロではないが、あんまり無い動きであ
るとも語っていた。また先進国は、自治体が廃棄物処理に関して自分たちの問題として行政
はとらえてやっているという。自治体の中にも焼却にお金がかかるので、その分お金をリサ
イクルに投入してもいいという自治体と、現在リサイクルを行おうと取り組んでいるとい
う。
特に担当者は、EPR はいわばメーカーに非を唱えるものであり、なおかつお金を単純に
かけたからリサイクル出来るという訳ではない、と強調していたように感じる事が出来た。

49
筆者は以上から、自治体とメーカーとの間の現状認識に大きい隔たりがあるのではない
かと考えた。現状では、一般廃棄物に関してはその処理責任を各自治体が負っている。また
リサイクルをする際にもその処理を行う際に発生する費用負担は、各自治体が負うことに
なっている。そのため製品を作っているメーカーにも費用負担を求めて行きたいと考えて
いるのは自治体側として、至極真っ当な考えであると考える。
しかし、メーカーとしては業界規模の違いや個別リサイクル法の下でリサイクルが進ん
でいない現状、そして単純にお金を投入するだけでリサイクルを進めることは出来ないと
いう考えから、リサイクルに先進的であるユニ・チャーム社でさえも反対をしているのが現
状となっている。メーカーや所属業界の対応能力、現状のリサイクルシステムの問題点、各
自治体に課せられている一般廃棄物の処理責任等、様々な要素を今一度見つめなおしてみ
て、現実的な施策かどうか再検討を行うことが重要ではないか。
そしてその認識を共有し、共通認識とすることで、出来ることを一つずつ実施することが、
大切なのではないかという意見を持った。
③紙おむつリサイクル推進のために市民・排出事業者に求めたいこと。
ユニ・チャーム社における、紙おむつリサイクル推進のために市民・排出事業者に対して
求めたいことという質問に対して、ユニ・チャーム社の担当者が回答したものは、しっかり
と分別をして異物を入れないというものだけであった。それ以外に求めたいものは特にな
いということであった。
④紙おむつリサイクル推進のために政府・都道府県・自治体等に求めたいこと。
今までの調査から、紙おむつリサイクルシステムの推進するためにはメーカーだけでな
く様々な団体の協力が不可欠となっていると考えられる。特に公権力を有しており、一般廃
棄物の処理義務を負っている自治体、また都道府県・政府の協力や参画が必要不可欠となっ
ていると思われる。そこで、紙おむつリサイクルシステムを現在研究しているユニ・チャー
ム社において、紙おむつリサイクルシステム推進のため、政府・都道府県・自治体等に求め
たいことを聞いた。
その結果、ユニ・チャーム社の担当者は、現状のリサイクルの実態を改善することを求め
ているようであった。現状ではごみを燃やすために大量の税金が使用されている。それを再
資源化・再利用できるように資源・資金を回して欲しいと担当者は訴えていた。また前述の
とおり、その動きに賛同する自治体と紙おむつリサイクルの実績を作ろうとしているとい
う。さらに環境省に対しても、元々は資源の循環に重きを置いている方針であるので取り組
んでほしいと語っていた。
筆者は以上から、リサイクルシステムの確立・推進のために、より企業が活動しやすい環
境を整えることの必要性を改めて感じた。現状ではリサイクルが推進しやすい状況とは言

50
うことは難しいと思われる。前述のとおり焼却処理費用が税金を投入されていることで、結
果的にリサイクル料金よりも低くなっているという側面等の存在があり、そのことが、リサ
イクルが進まない要因ではないかとのリ総研・トータルケア社の意見が、これに当てはまる
のではないであろうか。
そのためには、中央省庁・都道府県・自治体に対して方針変更やその重要性を訴えていく、
また、紙おむつリサイクルに対して興味を持っている自治体とのマッチングを支援すると
いうことも必要となっているのではないかという意見を持った。
【他】紙おむつメーカーが再生材料を使ってもらうためには、再生材料(パルプ等)の
絶対量が必要であるとしているがどの程度あれば使用に傾くのか。
第 7 章においてリ総研の松村コーディネーターは「メーカー側に再生材料である再生パ
ルプを紙おむつに使用を求めるためには、再生パルプの絶対量が必要である」と話していた。
その為、どの程度メーカーにおいて再生パルプの絶対量があれば、使用に傾くのかを聞いた。
その結果、ユニ・チャーム社の担当者は、再生パルプを紙おむつに使用をするための条件
として絶対量が必要であるという訳ではないと回答した。現在はまだ実証実験を行ってい
ない状態であるため、実証実験を元に今後活用方法を検討していくという。また、地域の特
性に応じてそれぞれ使い道があるとも話していた。
その他に再生パルプを使う場合でもテッシュペーパー・段ボール等の様々な用途がある。
そのような量に応じて多くの選択肢が存在しているため、再生パルプの絶対量が必要であ
るとはあまり考えられることはないと担当者は語っていた。
筆者は以上から、リサイクルを推進する団体とメーカーとの間での、方針の相違がこのよ
うな結果となって現れたのではないかと考えられる。今回インタビュー調査を行ったリサ
イクルを推進する団体とメーカー側は、その双方で最終的に紙おむつに再生材料を使用す
ることを目標としている。このような結果になったのは、メーカー側が再生パルプ等の利用
方法を、柔軟に考えているのではないであろうか。このことはユニ・チャーム社の担当者が、
地域特性や多くの選択肢の存在を理由に、絶対量の必要性を否定していたことがこのこと
を裏付けているのではないであろうか。
またそれ以外の要因として意見の隔たりの理由は、実験や事業の進行状況の違いが影響
しているのではないか、と考えられることが出来ると筆者は考察する。
既に実証実験やリサイクルを行っており、実績が存在するリ総研・トータルケア社と 2016
年 12 月より実証実験を行うユニ・チャーム社においてでは、経験・認識に基づいた意見に
隔たりがあるのも当然ではないのか。そのような状況であるために、この紙おむつリサイク
ル問題の解決・推進には、それぞれの意見交換を推進していく必要性を筆者は強く感じた。

51
第 10章:「インタビュー調査:環境省、中央省庁の考えとその考察」
第 7 章から 9 章にわたって紙おむつリサイクルを実施し、推進している様々な団体にイ
ンタビュー調査を実施して、現状の紙おむつリサイクルの問題点等を質問した。その際にイ
ンタビューを実施して話を聞いた担当者等から、政府や環境省に対して、対策や活動を求め
る声を多く聞くことが出来た。そのため日本の中央省庁の 1 つであり、持続可能な現代社
会を目指し廃棄物の排出の抑制及び適正な処理を主任務の 1 つとしている環境省の担当者
に、環境省の見解を聞くためにインタビュー調査を実施した。
今回調査にご協力頂いたのは、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部企画課循環型社
会推進室である。環境省は紙おむつリサイクルに関してどのように考え、また想定される状
況になった場合、どのような支援を行う事が出来るのか、またメーカー・自治体・リサイク
ル業者が求める対策をどの程度実施する事が出来るのか、調査を行った。
なお今回は担当者の実名公開が認められなかったので「環境省の担当者」(以下担当者)と
いう表記方法を行う。
本第 10 章では環境政策を担当する中央省庁の立場で以下9項目を回答して頂いた。
① 紙おむつの環境配慮(リサイクルを含む)についてどうお考えですか?
担当者はこの質問に対して、望ましいと考えているとの考えを示した。また福岡県大木町
や、鹿児島県志布志市における水溶化リサイクル、鳥取県伯耆町におけるサーマルリサイク
ルの取り組み等に注目しているとも答えた。
以上から筆者は、環境省としても紙おむつリサイクルの重要性に関しては、一応の認識が
あることが明らかになったのではないかと考えられる。
② 紙おむつの環境配慮(リサイクルを含む)を行う際にどのような支援を行うことが可能
ですか?(メーカー・自治体等に対して)
環境省の担当者は、様々な支援制度を用意していると説明をした。筆者が取材を行った、
大木町を含む福岡県南筑後地域のプラスチック等の循環圏形成計画づくりは、“地域循環圏
形成モデル事業”という環境省の請負事業の1つとして採択した。
ただ大木町に関しては様々なリサイクルを実施しており、その中の 1 つに紙おむつがあ
ったというものである。そのような計画づくりの支援は現在も行っており、今年度からは
「低炭素型廃棄物処理支援事業(地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業)」という補助
金の交付事業を実施している。
しかし、それも環境省としては紙おむつに限定しているわけではなく「地域でいろいろな
資源を循環させるような取組について行っている」自治体等を対象にしたものであるとい
う。また、その選定は国が行う支援のスキームがあると公募をかけ、取組をやっていると自
治体等が手を挙げて申請を行い、その中において先進的であるとして選ばれれば、支援を重

52
点的に実施しているという形となっているという説明を行った。またこれらの支援も予算
を確保出来れば、引き続きやっていきたいと考えている。その中で紙おむつの先進的な取組
が上がってくれば支援の対象となってくるとは思うと話す。
しかしその際には、他に普及の可能性があるものや、参考になるようなものという条件が
あるという。
企業への支援に関しては、基本的に自治体が実施する取り組み(特に資源循環に関して)は、
企業(リサイクル企業等)が連携していないと出来ないので、枠組みの中には企業も入ってい
るという。地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業への応募は、自治体・民間団体等のど
ちらでも可能だ。しかしその際には、官(自治体)・産(事業者)・学(大学等)・金(地域
の金融機関)・民(NPO、地域の住民等)の少なくとも3者以上が参画する会議体を設置
し、同会議体による検討・評価により進める事業であることを条件の1つとしているとのこ
とである。また、これ以外にも環境省には様々な支援スキームがあるので、そこに乗ってく
れば支援の対象となると思われるという見解を示した。
筆者は以上から、環境省の用意している様々な支援スキームの適用を受けるためには、
“循環型社会を作るための方策”であり、なおかつ“他に普及の可能性があるものや参考に
なるような事業”であり、また“官・産・学・金・民の少なくとも3者以上が参画する会議
体を設置し、さらに同会議体による検討・評価により進める事業”であることという条件が
本調査で分かった。また企業の参加は、「基本的に自治体が実施する取組(特に資源循環に関
して)は企業(リサイクル企業等)が連携していないとできない」という見解を示しており、そ
の重要性を環境省としても認識していると考えられるのではないか。
そのため多くの団体で助成金を得るようになるため、必要不可欠な企業とその他の団体
を繋ぐためにも、関係団体が協議を行う場の設置、またそれぞれを結び付ける事が出来るよ
うなマッチングの機会を設けることの重要性を再認識することが出来た。
③ 紙おむつリサイクルを進めるうえでリサイクルシステムの確立は大変重要となってい
るが、どのような支援を行うことが可能ですか?
前述の通り、筆者が行った第 4 章の調査において、自治体が紙おむつリサイクルを検討・
実施しない理由で最も多かったものは、「紙おむつリサイクルシステムが確立していない」
というものであり、財政面・衛生面を上回った結果となった。そのため紙おむつリサイクル
においてはそのリサイクルシステム確立が重要であると考えられる。それに対して環境省
としてどのような支援を出来るのか担当者に聞いた。
それに対して担当者は前述のとおりに、支援するスキームは存在するという。質問②のと
おり、地域循環圏・エコタウン低炭素化促進事業で、循環の仕組みづくりを関係者が集まっ
て協議・調査検討をする場を支援するスキームの予算はあるという。しかし、この場合にお
いても、「紙おむつのリサイクルシステムに限って」実施しているわけではないという。そ

53
のため、筆者の調査で、紙おむつの区別可能な回収方法を実施しているという 38 市町村や
その他の自治体で、もし紙おむつリサイクルシステムを推進したいということで応募して
くれば、支援対象となる可能性は十分あると話す。
だが今のところ、紙おむつに関しての応募は大木町のみに止まっているのが現状であり、
主に応募で多いのは食品リサイクルに関してとなっているという。以上のように、支援スキ
ームはあるが、「紙おむつリサイクルに限定して」の支援スキームは存在しないというもの
が回答であった。
筆者は、以上から質問②での筆者の意見を再度強く主張したい。しかし回答にあった紙お
むつに関しての応募が大木町のみに止まっているという現状に対して、違和感を覚えた。
現状でもあまり多くはないが、紙おむつリサイクルに取り組んでいる場所は存在する。し
かし大木町以外の自治体・団体が応募をしないことには、どのような理由があるのか。これ
に関して筆者は紙おむつリサイクルを実施できる企業が少ないという要因があるのではな
いかと考えられる。
実際に現在紙おむつリサイクルの実証実験を行っている、ユニ・チャーム社に対して行っ
たインタビュー調査において、質問⑧で、実証実験を行う際には「回収がやりやすく、優秀
な処理業者がいるところを選んで始めた」という発言があった。このように、紙おむつリサ
イクルを実施する際の 1 つの条件として、紙おむつリサイクルを行える優秀な処理業者の
存在が必要不可欠となっていると考えられる。
紙おむつリサイクルの歴史は浅く、現状では未発達の技術であり、その他のリサイクル技
術と比較しても確立されていないことは確かである。そのため多くの処理業者では、その紙
おむつリサイクルのノウハウや実施するための設備が不足しているために、受け入れるこ
とが出来ないのではないか。処理業者が存在しなければリサイクルシステムは確立される
可能性は低くなる。その結果、自治体は導入に二の足を踏んでしまうという状況が出来上が
ってしまっているのだと筆者は推察する。
以上のように、膠着状態の打破を行い、今後予測される環境負荷削減のためにも、既存の
紙おむつリサイクルを実施している企業の情報公開の推進、また情報公開を行った団体に
利益を付与出来る仕組み作り、企業同士のマッチング支援、財政支援等の踏み込んだ施策等
の対策を、環境省として進める必要性を強く感じた。
④ なぜ自治体が徴収するごみ処理料金と実際に処理にかかる費用に差があるのか。また
環境省としては考えている理由とそれに対する改善の取り組みはどのようなことを行
っていますか(考えていますか)?
担当者はこの質問に対し、一般廃棄物の処理に関しては市町村の自治事務であり、自区域
内の一般廃棄物について処理責任を有しており、また、市町村が一般廃棄物の処理において、
住民や事業者に対するサービスの一環として、どの程度実施するかは各市町村の判断とな

54
っていると説明した。そのため自治体ごとにごみ処理にかかる費用は異なっているという。
ごみ処理に関しては税金を活用しながら処理をしており、処理費用において税金を使用
せず市民負担とした場合、当然費用は高くなってしまう。その場合に、処理費用の全額を市
民負担とすると、住民・事業者への負担が大きくなり、日常生活や事業活動にも支障をきた
す可能性があること、また適正処理されずに不法投棄されるようになってしまう可能性が
あると税金を投入しない場合に想定される弊害があることを筆者に説明した。
環境省では、3R や排出抑制の観点からごみ処理の有料化(一部市民負担)の取り組みを
市町村に対して促しているという。その目的は、ごみ処理の有料化によって、その一部を住
民に負担してもらい、全員でごみの排出削減に努めていこうというものである。
ただし、今まで有料化を行ってはいなかった自治体にて有料化を実施する場合、住民への
理解等を得られるように丁寧な説明が必要であるとしている。これに対する環境省の支援
としては、「一般廃棄物処理有料化の手引き 4」というものを出しているという。これは有
料化の実施に向けた計画・実行・点検・見直しの段階ごとに、推奨する考え方や手順、全国
の市町村の事例等の情報を取りまとめているものだという。
また、環境省では、ごみ処理に関する「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール 5 」
を提供している。これはごみ処理に関する人件費や実際に掛かった経費などを評価するも
ので、他の市町村の状況や自分の自治体の実情を見える化することにより、自らの市町村に
おける一般廃棄物処理システムの改善点の抽出等に活用されることを考えているという。
なお、本来国がやるべき仕事を自治体に「法定受託事務」という形で行ってもらっている仕
事に関しては、国の関与はある程度存在するとした。
一方で、一般廃棄物処理に関する行政は自治体がそもそもやるべき仕事である「自治事務」
に相当するため、“どのように処理するのか、どのくらい税金を投入するのか”は自治体の
予算内で責任をもって決めているという見解を示した。筆者が質問したごみ処理料金に税
金を投入しない代わりに補助を行うなどの支援の可能性に関しては、そこに国の予算が入
ることは基本的にはないという立場を主張した。しかし、廃棄物処理施設の整備等に対して
の交付金というものはあるとのことであった。
以上から筆者は、担当者は明言こそしてはいないが、自治体が徴収するごみ処理料金と実
際に処理にかかる費用に差があるという認識はあるのではないかと感じた。また様々な支
援として一般廃棄物処理有料化の手引きや、市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツー
ルを提供するなど、実施・システムの改善等に尽力をしているがそれでも不十分ではないか
と考えられる。
その理由として、紙おむつ関係のものではないが、平成 28 年 5 月 17 日付けで各都道府
県・市町村廃棄物行政主管部(局)長に宛てた「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法
4 (文献表出典 18) 5 (文献表出典 19)

55
律に基づく取組等の更なる促進について」6 という通知の中で「食品流通の川下の再生利用
が進んでいない理由として、(中略)民間の再生利用料金が公共サービスである市町村の処理
料金よりも結果として割高になっていること」としている。さらに以上を踏まえ、各都道府
県・市町村廃棄物行政主管部(局)長に対して、「市町村における一般廃棄物の処理料金につ
いては、環境保全を前提としつつ地域の実情に応じて市町村が決定していることではある
が、その際には、(中略)再使用及び再生利用(3R)を進めるため、廃棄物処理に係るコストの
透明化等を一層推進することとしている」という、コストの透明化を図る必要があると、環
境省側が通知を出す事例が存在する。(文献表出典 20)
この状況は、紙おむつリサイクルに関しても同じことが言えるのではないであろうか。以
上のような通知が出されていることからも、自治体のみの力で、民間の再生利用料金と公共
サービスの市町村の焼却処理料金の透明化・その格差を埋め、リサイクルを促しやすい環境
を整備するのは、市町村の抱える財政問題等の面から困難であると思われる。実際、紙おむ
つリサイクルよりも進んでいると思われる食品循環資源の再生利用に関して、このような
結果となっているのであれば、紙おむつリサイクルに関してはより深刻な状況であるので
はなかろうか。
そのため、一般廃棄物処理に関する行政は、各自治体が行う自治事務であるとして、税金
を使用しての援助等が必要である。その部分に関しての介入は出来ないと環境省の担当者
は回答していたが、評価支援ツール等の提供に止まらず、リサイクルを促しやすくし、将来
的な環境・社会問題の発生を無くすためにも、資金援助等の政策・法規制の制定が求められ
ているのではないかと考えられる。
⑤ 紙おむつのリサイクルに取り組んでいる自治体からは紙おむつにも「拡大生産者責任」
に基づいて費用の負担を求める声があるが、実施は可能であるのか。また考えられる
問題点等はどのようなものがありますか?
担当者はこの質問に対して、現時点ではそのようなリサイクル制度を検討してはいない
と答えた。紙おむつリサイクルに関しては基本的にはいくつかの自治体で技術的な仕組み
を試行されているという事例がチラホラ出てきている段階であるという。それ以外の自治
体は基本的には可燃物として焼却処理をしており、紙おむつリサイクルの実態をまずは把
握をするということが必要であると感じていると語った。まず個別リサイクル法を作ると
なった場合では、色々な知見を集めて評価することが必要となる。本当に法整備が必要とな
っているのかという必要性の根拠を示すことが必要となっていると話す。
だが、現状では必要かどうかも環境省では把握してはおらず、環境省循環型社会推進室で
もそのような要望は受けていないという。よって、まず色々な知見を集めるところから始ま
り、そもそも必要なのか、仮に必要性があったとした場合にも、技術的にどこまで可能なの
か、焼却処理をしている自治体が困っていることがあるのかなどを考える必要が出てくる
6 (文献表出典 20)

56
という見解を示した。
また紙おむつには汚物が付着しているのでリサイクルも大切であるが、適正処理が大前
提である。その為、リサイクルするに当たって生活環境に支障を与えないことも重要になっ
てくるという条件があるという。
さらに現在行われている家電や自動車の個別リサイクル法では法整備がなされる前には、
不法投棄が横行していたので自治体が困っているケースが多くあった。その状況を改善す
ることを目的として、そのような状況の中で家電や自動車の個別リサイクル法が作ってい
ったものであるという、経緯がこれらの個別リサイクル法にはあると説明してくれた。
筆者は以上から環境省内における紙おむつリサイクルの認知度の低さが浮き彫りになり、
また紙おむつの個別リサイクル法が出来る糸口が出来たのではないかと考えられる。今回
実際にインタビュー調査を行った際に、担当者は筆者が説明する調査結果に対して時折メ
モを取っており、今回のインタビューを受けた理由について「紙おむつリサイクルに関して
情報収集の段階であるので、情報収集の一環という経緯がある」と筆者に対して説明する等、
中央省庁である環境省でもその必要性の認識したのは最近なのではないのか。そのような
状態では拡大生産者責任等の個別リサイクル法の整備などは行うことは困難である。
しかしここで、担当者は拡大生産者責任等の個別リサイクル法の整備のためには、その必
要性を示すことが重要であるとの認識を示した。現在行われている家電や自動車の個別リ
サイクル法では法整備がなされる前には、不法投棄が横行していたので自治体が困ってい
るケースが多くあり、その対応を迫られたために個別リサイクル法が整備されたという。で
は紙おむつリサイクルに関しても同じことが言えるのではなかろうか。
調査を進めるにあたって、様々な自治体・団体から、紙おむつリサイクルの必要性を感じ
ているとの意見が聞かれた。ならば自治体・その他団体が、紙おむつリサイクルが必要であ
り、紙おむつの処分で困っているという声を積極的に挙げることが必要であると考える。
拡大生産者責任等を定める個別リサイクル法の整備の可能性が低い現状では、現状変更
のためにも、その必要性を訴えるための情報発信こそが個別リサイクル法の整備に向けて
何よりも大切になっているのではないか。
また情報収集の段階である、環境省に対しても紙おむつリサイクルの現状等の説明を行
って理解を求めて行く必要もあり、声を上げるのと、同時進行で行うことが重要ではないか
と考えられる。だがユニ・チャーム社へのインタビューの際には、紙おむつに対して拡大生
産者責任(EPR)を適用する事には難色を示した。その理由は前述のとおり、他の産業の規模
が違い、現状では個別リサイクル法の下で、リサイクルするために集めようとしたものは、
ほとんどが燃やされており、それに対してしっかりと有効活用されるようにならなければ、
EPR 導入に反対であるという見解を示している。特にユニ・チャーム社の担当者は、EPR
はいわばメーカーに非を唱えるものであり、なおかつお金を単純にかけたからリサイクル
出来るという訳ではないと強調していたように感じる事が出来た。このようにメーカーサ

57
イドでは拡大生産者責任等の個別リサイクル法に対して反対の立場である。
しかし前述のとおり「基本的に自治体が実施する取り組み(特に資源循環に関して)は企業
(メーカー・リサイクル企業等)が連携していないとできない」との環境省担当者の見解もあ
る。そのような状況であるので、メーカーも納得するような拡大生産者責任等の個別リサイ
クル法の検討が必要なのではないか。
⑥ 紙おむつのリサイクルに取り組んでいるリサイクル会社・自治体からは「製造側にき
ちんと生産する段階でリサイクルを行う責任があることを定めた法律を作ることを求
めたい」との意見が出ましたが、国として取り組むことは可能か、また実現する際の問
題点はどのようなものですか?
担当者は、製造側にきちんと生産する段階でリサイクルを行う責任があることを定めた
法律を定めてほしいという要望があるという質問に対して、その質問に該当する法律とし
て、「循環型社会形成推進基本法第 11 条」の存在を筆者に説明した。
担当者は、同法 11 条の「事業者の責務」において、「事業者は、基本原則にのっとり、そ
の事業活動を行うに際しては、原材料等がその事業活動において廃棄物等となることを抑
制するために必要な措置を講ずるとともに、原材料等がその事業活動において循環資源と
なった場合には、これについて自ら適正に循環的な利用を行い、若しくはこれについて適正
に循環的な利用が行われるために必要な措置を講じ、又は循環的な利用が行われない循環
資源について自らの責任において適正に処分する責務を有する。」と定めていると説明を行
った。
この法律では、事業者の方で循環的な利用に資するように、廃棄物等となることを抑制す
るような設計等を考えるなどの措置を講ずる責務を有する等と定めており、この法律の存
在が、製造事業者に廃棄段階で何の責任もないわけではないと、担当者は筆者に説明した。
しかし個別の法規制は現在存在しないという。もし紙おむつに限定した法規制を作ると
なった場合は、必要性があるのかどうかを調査しなければならない。また、多くが焼却処分
されている現状を精査して、需要を調べなくてはならないと担当者は語る。特にリサイクル
の実施によって費用は上昇しないか、CO₂の排出量が増えないか、使用するエネルギーなど
の資源を今以上に多く使用しないかなどの問題を回避しなくてはいけない。その為、その辺
りのデータをもっと集めなくては紙おむつリサイクルの法規制を作ることは出来ないと担
当者は法規制の制定までの課題を語った。
また、メーカー側の動向も見極めて総合的に判断する必要があるという。例えば紙おむつ
メーカー1 社だけが紙おむつリサイクルに乗り気であったとしても難しいという。さらに法
律であれば日本全国で影響してくるので社会情勢を考慮して行う必要もあるという。
筆者は以上から既存の法規制の形骸化を認めざるを得ないのではないかと感じた。確か
に循環型社会形成推進基本法第 11 条の「事業者の責務」において、一応事業者に対して適

58
正に循環的な利用が行われるために、必要な措置を講じる責務を有すると定めており、この
法規制に則れば、各メーカーはリサイクル等の再生利用の対策を取らなければならなくな
る。
しかし、現状では各メーカーにおけるリサイクル等の環境配慮の実施例は少ない。その要
因として個別法規制の存在が無いということが挙げられると考えられる。循環型社会形成
推進基本法第 11 条は、事業者に対して事業者に対して適正に循環的な利用が行われるため
に必要な措置を講じる責務を有すると定めている。しかし、その責務を実行しない場合の罰
則に関しての記載内容は存在してはいない。
企業は当然営利団体であり、日々コスト削減に努めている。そのような団体がリサイクル
等の環境配慮を自主的に行うために資金を捻出するには、よほど環境配慮に先進的な経営
者の考え方や、経営戦略が無ければ実施しないのではないか。その証拠に、現時点で紙おむ
つリサイクルを実施しているメーカーは極めて少ない。そのような企業に対してリサイク
ル実施を強力に促していくためには、個別法による具体的な事項・規制の策定並びに罰則等
の規定も必要になっているのではないか。またメーカーにおいてはリサイクルの責任を自
らが負っているということをあまり感じていないのではないかと考えられる。
環境省の担当者はインタビューの中で、「事業者側に適正に循環的な利用が行われるため
に、必要な措置を講じる責務を有すると定めており、事業者に廃棄段階で何の責任も負って
いない訳でない」と述べていた。
しかしメーカー側ユニ・チャーム社の担当者は、インタビューの際に、あくまで自治体が
廃棄物責任を負っており、メーカー側に拡大生産者責任を求めることはあまりないという
発言を行っており、先進的な紙おむつリサイクルを開発しているメーカー側でも、環境省が
説明し、法律で明文化されている「企業によるリサイクル等の資源循環の適正化の責任」を
あまり感じていなく、またそれを実現するための一つの手段である、拡大生産者責任の適用
には難色を示しているように筆者はインタビューを通じて感じる事が出来た。この意識の
違いこそ、紙おむつリサイクル推進の障害になっているのではないか。
以上から筆者は各団体間における現状認識や法律等の理解を進めるための連絡会等の場
を設ける必要があるのではないか。
⑦ 紙おむつメーカーからは「拡大生産者責任に関しては各種リサイクル法で回収された
まだ使用できるものも燃やすために税金を投入している現状では賛成出来ず、再資源
化・再利用のための資源・資金を回して有効活用して欲しい」という意見が出ている
が、環境省・国としてどのように考えていますか?
環境省の担当者は以上の紙おむつメーカーの質問に対して、この質問・意見の趣旨が良く
分からないため、答えようがないという回答をした。また、税金の投入については、環境省
では予算として再資源化や再利用に関する事業を実施しており、自治体が焼却をする際に
必要となる処理施設等にも交付金を交付する予算を持っている等、様々な段階における一

59
定の予算を持っているという。
しかし、紙おむつメーカーが何に賛成できないと言っているのか、よくわからないという
意見を述べていた。
以上から前述のとおり質問②での筆者の意見を再度強く主張したい。今回も紙おむつメ
ーカーと環境省の間で意見・現状の相違がこの質問から分かったのではないだろうか。この
解決のためにも関係団体が協議を行う場の設置、またそれぞれを結び付ける事が出来るよ
うなマッチングの機会を設けることが必要であり、その重要性を認識することが出来るの
ではないか。
⑧ 紙おむつメーカーと意見交換する場はあるのか?
環境省の担当者は以上の質問に対して、紙おむつメーカーとの意見交換の場は、かしこま
ったものは設けていないと説明する。しかしそれ以外で様々な機会があるという。例えばユ
ニ・チャーム社の場合では、エコプロで紙おむつのリサイクルについての話を伺ったという。
それ以外でもシンポジウムなどで話を聞く等、環境に関して先進的な企業であるといろい
ろな機会で話を聞くことも出来るという。
また業界としての繋がりでは、環境省はおむつ業界とは交流会を持っているというわけ
ではないと説明された。より密接な関係を構築しているのは、法律が存在する業界(自動車・
家電)、廃棄物が多い業界でありそれらの業界とは、より密接な関係を持っているという。
以上から筆者は現状における環境省の情報交換の機会は不十分なのではないかという考
えを持った。確かに説明を聞く限りでは様々な意見を聞く機会は存在する。しかしそれは、
一部の環境に先進的なメーカーに限られているのではないか。その他の大多数を占めると
思われる、環境に関してあまり関心がないメーカーに関しての情報収集・意見交換の機会が
不足していることは、明らかになっているのではないか。
また、意見交換を行うにしても、かしこまった正式の場を設けないで行うのは、記録面や・
説明を受けた人の主観等が入り込んでしまう可能性があるため、事実・考え方等を正確かつ
十分に理解することが出来ないのではないであろうか。
どのような形式において情報交換を行っているのかは、今回の調査では明らかにならな
かった。しかし少なくとも会議室を設け集中できる環境を用意や、議事録の作成、記録のた
めに録音をしての意見交換を行っているという印象を、今回の環境省のインタビューから
は窺うことは出来なかった。情報交換の機会が無ければ、正しく環境省の意図・考え方等を
伝えることは出来ず、なおかつキーパーソンであるメーカーの意見や抱える問題点等が見
えてこないのは確実である。これでは如何に優れた・充実した補助金などの制度を作ったと
しても意味は無くなってしまう。
以上から、上記の問題を解決するためにも、正式に紙おむつリサイクルを推進している・

60
していないに拘らず、様々なメーカー側との意見交換の場を持つこと必要性を感じた。
⑨ 紙おむつメーカーからは「製品を作ってもその出口の確保が出来ておらず、使い道・売
り先がないので循環の輪が出来ない」と現行の紙おむつリサイクルの問題点が挙げら
れた。その事に関して環境省・国としてどのように考えているか・支援は出来ますか?
環境省の担当者は上記の質問に対し、よく聞く話であり、重要なことであると話す。まず
リサイクルを行う際には、リサイクル製品をどこに売るのか・どのように使うのかを用意し
てもらうというのが大切であり、そこに関しては基本的にはリサイクルの仕組みを作り、実
施する自治体側で探してマッチングの仕組みを作り上げないと成功しないと考えていると
いう意見を示した。環境省ではその為に、地域循環圏モデル事業の成果の実例については、
セミナー等で情報提供を行っている。
ただし、取組をしている自治体とリサイクル製品の売り先との橋渡し・マッチングを国が
個別に実施することはないと説明する。その理由は、環境省でそれぞれの自治体でどのよう
な事業者がいるのかは把握してはいないので、基本的に事業者を探すなどは市町村の方で
やってもらう必要があるからだという。また行わない理由に、人員不足も関係しているとい
う。現在地方には、8 つぐらい地方環境事務所はあるが、そこにいる廃棄物担当者は各 5~10
人程度しかいないので、個々のマッチングを行うのは難しいという。さらに基本的にはごみ
行政は地方の自治事務なので、市町村で「このような仕組みを作りたい」というのは自分た
ちで探してもらわないと継続ができないという見解を示している。また、マッチングを実施
することは国の仕事ではないと思っているという環境省の立場を説明してもらった。
ただ、その時のノウハウや先進的な自治体があると勉強できるように手伝いはしている
とのことだ。またそのような先進的なところに関してモデルとなるようなところには、予算
も限られてはいるが、いくつか環境省の予算を入れて育てるという。そして育てたモデルに
関しては、「このような事例があるので自治体の方で取り組まれてはどうか」という風なセ
ミナーを開くという支援を行っているという。
つまり、「マッチングは自治体の仕事であり、予算を投入してノウハウ育成・ノウハウ提
供のためにセミナーを開いて情報提供をするということが国・環境省の仕事」であるという
スタンスを環境省としては持っているとのことである。
以上から筆者は今後、環境省の業務内容等の拡大が必要になってきているのではないか
と考えられる。確かに現状において事例紹介のセミナーの実施や自治体と中央省庁の業務
管轄の違い・人員の制限等の問題も確かに存在しており、活動を増やすことは難しいと考え
られる。
だが、それを踏またうえで改めて、環境省の業務内容拡大の必要性を筆者は考える。例え
ば、筆者の紙おむつを他のごみと区別できる回収方法を実施している 38 市町村対象に実施
した調査の中では、紙おむつリサイクルを実施・検討しない理由として全体の 2 割の自治

61
体で「リサイクル業者が近隣にいない」という回答がなされた。この回答のとおり、本当に
近隣に紙おむつリサイクルを担当できるリサイクル業者は存在しないのかもしれない。
しかし、「紙おむつリサイクルを実行する技術・アイデアはあっても、パートナーとなる
自治体が見つからないので事業が成り立たないので実施しない」という業者も存在する可
能性があるのではないであろうか。事実、全国の自治体の中で紙おむつリサイクルを行うこ
との計画等を Web ページ等で公表・告知している自治体は、既にリサイクルを行っている・
検討している自治体以外では筆者が調査した限り存在してはいない。そのような状況下で、
適切に自治体と業者が独自でマッチングすることを期待することは難しく、現状で、自治体
のみにマッチングを行わせるのでは紙おむつリサイクルの普及・進展を促す際には困難な
のではないか。前述のとおり環境省は様々な場面において、資源循環の取り組みを支援する
スキームの予算はある。しかし、環境省の担当者は今のところ紙おむつに関しての応募は大
木町のみに止まっているのが現状であると説明をした。
このように応募が行われないのも、リサイクルシステム確立に必要不可欠となっている
リサイクルを行える企業の存在を自治体側が認識していない可能性があり、そのことが応
募の無い理由の一つとして考えられるのではないであろうか。だが現状においては、自治体
と企業がお互いに紙おむつリサイクルに興味があるのか、また実行可能な技術力・資金力を
有するのか等の、情報を取得し見定めるのは困難である。
特に筆者が今回調査を行い、最も多くの人が見やすいであろう各団体の Web ページにお
いて情報は掲載されておらず、そのような状況下にある現状では、困難であるのは間違いな
い。そのような状況下であるからこそ、様々な情報が集まる中央省庁の環境省だからこそ出
来ることがあるのではないか。以上の問題を解決するためにも、環境省はどこの自治体と企
業が紙おむつリサイクルに興味を持ち、資金・技術力があるか等の情報等を、Web ページ
等の使用によりデータベース化の実施や広報・セミナー・相談会等の各種メディアを使用し
ての発信を実施する必要があると考えられる。
また企業・自治体からの問い合わせの際にはデータベースの中から付近の対応が可能な
企業や関心がある自治体をそれぞれ紹介するなど、マッチング支援を行う必要があると考
えられる。しかし現状において自治体・メーカー・リサイクル団体等、各団体の主張や考え
方等が一致していない。その為、それぞれに合致するようなマッチング支援の方法を模索す
ることの必要性が今後はより出てくるのではないかと考えられる。
そしてこの業務に対応するためにも環境省における事業内容拡大や人員の拡充等の取り
組み、関係者各位からの意見交換を、より柔軟に推し進める必要があると筆者は考える。

62
⑩ 現在ユニ・チャーム株式会社ではオゾン処理を使用した「紙おむつ水溶化マテリアル
リサイクル」を現在研究開発中ではありますが、環境省としてその方法にどのような
見解を持っていますか。
環境省の担当者は同社の取組はエコプロなどで知っていたが、詳細に関しては把握して
いないという。また技術的に面白くは思うが、どこまでコスト面や CO₂等他の観点から見
ても有望なものなのか分かっていないとも話した。今後事業者と話をする機会はあるので、
そのようなときに内容を伺いたいと考えていると話した。
以上から筆者は環境省側の紙おむつリサイクルに関する理解度の現状を知り、その上で
環境省の情報交換の機会は不十分なのではないかという考えを持った。そのうえで正確な
情報を環境省側が得る事が出来るのであれば、紙おむつリサイクルの必要性やコスト面・環
境負荷等の観点から評価をすることが出来、担当者が語る紙おむつリサイクルに向けての
情報収集が出来るのではないか。
第 11章:「全インタビュー調査の振り返りと、見えてきた問題点の考察」
今回の卒業論文の執筆にあたり筆者は第 7 章から第 10章の全 4 章に亘って紙おむつリサ
イクルに関係があるのではないかと考えられる各団体に対してインタビュー調査を行った。
対象は実際に紙おむつをリサイクルしている自治体・リサイクルを推進しているリサイ
クル会社・県の独立行政法人・紙おむつメーカー・環境省であり、紙おむつリサイクルに関
わっている団体・日本における環境行政を取り仕切っている中央省庁の合計 5 者にそれぞ
れインタビューを実施して回答を得た。そのインタビューを通じて判明した紙おむつリサ
イクルに関する現状の問題点・考える必要があることは、2 点あるのではないかと筆者は考
える。
・問題点1:「各団体間で意見・認識の食い違いが多数ある点」
1 つは各団体間で意見・認識の食い違いが多数あるということである。
例えば「現状における紙おむつリサイクルの問題点は何か」という質問に関して、リ
総研・トータルケア社からは「回収料金の乖離・余計な処理費用・協力や運搬等」と
いう回答が得られた。しかしメーカー側のユニ・チャーム社はこの質問に対して「循
環の輪が出来ていないこと」という回答を筆者に対して行った。
さらに「再生材料を紙おむつに使用する際の問題点」としてリ総研の担当者は、「現在の
再生パルプの生産量では全く足りない。その絶対量が確保出来なければメーカー側は費用
の観点から再生パルプを使用する事が出来ず、絶対量が確保出来ればメーカーも使用に踏
み切るのではないか」と説明をしていた。だが、その質問をユニ・チャーム社にしたところ、
担当者は「再生パルプを紙おむつに使用するための条件として、再生パルプの絶対量が必要
な訳ではない」と真っ向から否定していた。

63
それ以外にもメーカー側のリサイクル責任の考え方の食い違いもあった。環境省は、事業
者の方で、循環的な利用に資するように、廃棄物等となることを抑制するような、設計等を
考える等の措置を講ずるなどの責務を事業者は有すると定めており、あくまでも製造事業
者に廃棄段階で何の責任もないわけではないと話した。しかしメーカー側のユニ・チャーム
社はあくまで自治体が、廃棄物処理義務を背負っているとして、メーカーに課せられたリサ
イクル等の資源循環の適正化の責任を認識していないように感じられ、その一つの手段で
ある拡大生産者責任(EPR)の導入に関して難色を示した。
以上のように多くの項目で、各団体間で意見や認識の食い違いが明らかになった。このよ
うな状況になった理由として筆者は、各団体間における進行状況の差がこのような差を生
んだと考える。例えばリ総研・トータルケア社・大木町は既に紙おむつリサイクルを実施し
ており、トータルケア社の使用済み紙おむつを使用した再生パルプは、平成 19 年から建材
用として 3 社に販売され続けている。その品質が耐火ボード用や外壁材用のパルプとして
充分なものであることと、コストパフォーマンス(ヴァージン品の約 70%の販売価格)に
より、平成 19 年から平成 27 年までに、再生パルプは約 5000 トンの販売量を記録している
等、実績を出している。しかしユニ・チャーム社は、今年の 12 月より鹿児島県志布志市に
おいて大規模な実証実験を開始したばかりであり、現在報道がなされている技術は全て実
験室段階であると担当者から説明があった。
そして環境省は現在、情報収集の段階であり、紙おむつリサイクルに関して詳しい情報や
意見を聞いているというわけではないという。
また現状において、各団体間における、情報共有の機会が十分にあるという訳ではない。
前述のとおり、環境省は紙おむつメーカーとの意見交換の場はかしこまったものは設けて
はいない。例えばユニ・チャーム社の場合では、エコプロで紙おむつのリサイクルについて
聞く機会があったという。それ以外でもシンポジウムなどで聞く等、環境に関して先進的な
企業であるといろいろな機会で話を聞くことも出来るという。だがそれは環境に対して先
進的なメーカーのみであり、その他のメーカーはこの限りでないはずだ。またどのような形
式でユニ・チャーム社の説明を聞いたのかは分からないが、もしエコプロのような騒がしい
会場で聞いたのならどこまで正確に、客観的に理解が出来、その他の職員に情報共有を行っ
たのか疑問が残る。
さらに、環境省はおむつ業界とは交流会を持っているというわけではないと説明された。
以上のように紙おむつリサイクルにおいて様々な段階で取り組んでいる各団体だからこ
そ、このような差が生まれたのではないであろうか。また各団体間の情報共有の機会が不十
分であるという点もこの問題に拍車をかけているのではないか。
・問題点 2:「各団体間でリサイクルを行う上で、今後の方針や足並みが揃っていない点」
2 つ目は各団体間において、紙おむつリサイクルに関する取り組みに関して今後の方針・
足並みが揃わない実態があるということだ。

64
この紙おむつリサイクルという取り組みは自治体・リサイクル企業・紙おむつメーカー・
中央省庁等の様々な団体が結束して 1 つの目標に向けて取り組まなくては、達成すること
が非常に難しいと考えられる。そのため実施の際にはお互いの息を合わせるためにも、足並
みを揃えて取り組みを行うことが大切だが、現実では足並みは揃っていないのではないか。
例えば「紙おむつリサイクルの啓発活動の実施」に関してはリ総研・トータルケア社は専
門家以外にも、工場見学等を通じて消費者・市民にも啓発の対象を広げている。しかしユニ・
チャーム社は消費者を対象にしておらず、高齢者等のお世話をしている医療・介護従事者を
対象に絞って働きかけていき、使用を促していくという。
さらに、現在行われている・以前行われた実証実験においても協力は限定的なものに止ま
っていると筆者は考えた。例えば、ユニ・チャーム社は現在鹿児島県志布志市において紙お
むつリサイクルの実証実験を実施している。しかしその実証実験には既に紙おむつリサイ
クルを行っているリ総研・トータルケア社はオブザーバーやその他提案を行う事が出来る
立場では参加していないという。実際にエコプロ 2016 のユニ・チャーム社のブースでお話
を聞いた際に、説明をしてくれた担当者はその事を否定していた。また、リ総研の担当者か
らもユニ・チャーム社へは、依頼に応じる形でリ総研もトータルケア社も昨年来情報提供を
しているが、この実証実験には今のところ関わってはいないと回答した。但し、今後何らか
の協力要請があれば、その都度検討して対応するつもりであるという方針であるという。
既に紙おむつリサイクルを実施しており、再生材料に関しても順調に販売を行っている
等の豊富なノウハウを蓄積しているリ総研・トータルケア社の意見を取り入れる事が出来
れば相互に大きな利益となり、紙おむつリサイクルの振興に一役買うのではないか。
そしてそのような共同事業を行う事が出来れば、各団体間における意見・認識の食い違い
を軽減する事が出来るようになるのではないかと考えられる。実際にリ総研・トータルケア
社・大木町・環境省とユニ・チャーム社は様々な場面において意見・認識を対立させており、
如何に広報戦略であるとしてもその差は大きい。その意見・認識の差を埋めることが今後の
紙おむつリサイクルを進めていく上で必要になってくるのではないか。
今後、その差を埋めていくことが出来れば、前述のよう各団体間における進行状況の差を
踏まえての共同歩調をとることが実現できると考えられる。
例えば、現在ユニ・チャーム社が予定している医療・介護従事者への再生材料を使用した
紙おむつの使用を促す活動も、今後再生材料を使用した紙おむつを製作出来た際に、既に紙
おむつリサイクルを実施しているリ総研・トータルケア社・大木町等で取り組む事が出来れ
ば、医療・介護従事者への再生材料を使用した紙おむつを普及させる為の有効なサンプルと
して活用が出来るのではないか。
また同様にユニ・チャーム社が進める実証実験でも、現在消費者・市民に対して啓発を行
っているリ総研・トータルケア社のノウハウやデータを活用することが出来れば、より効率
的に普及を進めることが出来るのではないかと筆者は考える。

65
以上が、今回筆者がインタビュー調査を行った中で見えてきたことである。今後紙おむつ
リサイクルを推進する上では以上のようなことを念頭に考慮を行いながら、進める必要が
あるのではないかと筆者は考えられる。
第 12章:「本研究を通じて見えてきた紙おむつリサイクルの発展のための考察」
今回の卒業論文の執筆を通じて、様々な調査やインタビューを通じた研究を行うことが
出来た。その研究を進める中で今後、様々な自治体やリサイクル会社、紙おむつメーカーが
紙おむつリサイクルを取り組み、新たな資源の循環を実現するためにどのようにすれば良
いのか、筆者なりの提案・提言の施策を以下の 8 項目にまとめた。
・提案 1:「認識共有や相互協力推進の為、各団体横断の会議体を設置する」
今回の研究で紙おむつリサイクルの障害となっているものの 1 つは前述のとおり、各団
体における意見が一致しておらず、また各団体間において紙おむつリサイクルに関する認
識等の十分な共有が出来ていないことである。
その為、各団体間の認識の共有不足に対応するために筆者は、少なくとも現在、紙おむつ
リサイクルを行っているリサイクル団体・紙おむつメーカー・自治体・環境省が参画する各
団体の垣根を超えた横断的な会議体を設置することが必要になってくるのではないかと考
える。
この会議体はあくまでも情報交換・相互の技術支援を目的に存在し、現状で不十分である
各団体の意見の共有・認識を深めることを目的とし、それに止めるようにすべきである。
その目的は、1 つのリサイクル方法のみに画一化するようになってしまっては、その方法に
対応出来ない場合、紙おむつリサイクルを推進することが出来なくなってしまうので、その
ような状況を防ぐにも様々な方法が選択肢として考えられるようにする必要があるためだ
からである。
また技術協力に関しては、現在報道されている本田技研工業株式会社とヤマハ発動機株
式会社の提携のように、今までライバルで切磋琢磨してきた企業同士が効率化・市場の活性
化を図ることを目的とした枠組み作りを紙おむつリサイクルの分野でも行うことが今後に
おいて重要になってくると思われる。
なおかつ、この会議体に参加の各団体はそれぞれの得意分野・地域性(産業・認識・年齢
層)・土地勘を活かしてリサイクル活動を行い、それぞれの紙おむつリサイクルシステムの
形(例えば A 町モデル・B 市モデル等)を作ることを実践する。その各モデルは、内容を会議
体が統括してデータベース化を行うことにより、より多くの人に見てもらえるようにする
必要がある。紙おむつリサイクルを検討している各自治体・企業には、そのデータベースを
見てもらい、どのモデルが自らの自治体において実施可能なのか落とし込めてもらう。
それによって紙おむつリサイクルを検討している各自治体・企業は、それぞれの地場産業
と協同してその地域の特性に合った独自の紙おむつリサイクルを創ってもらい進めること

66
を促していきたいと考えている。
これにより、紙おむつリサイクルの推進と地場産業の発展を、同時に推進することが出来
るのではないか。またそのような過程で生まれた紙おむつリサイクルのモデルに関しては
将来的に海外にシステムを輸出することを目的にすることも検討してみては良いのではな
いか。現在紙おむつが普及しているのは先進国が中心であり、新興国では今後広がっていく
のではないかと考えられる。その場合、将来的に新興国やその他の先進国でも同様の廃棄物
問題や資源問題が発生することも予測される。その際に日本のモデルを世界に輸出するこ
とが出来れば新たなビジネスチャンスに繋がり、また世界中において環境や資源における
配慮が進むのではないか。
さらに上記の会議体は最終的には、官(自治体)・産(事業者)・学(大学等)・金(地域
の金融機関)・民(NPO、地域の住民等)・環境省が参画する、より広範囲にわたって協力体
制が取れる会議体にすべきである。このようにすることによって、様々な意見を取り入れる
事が出来るものにすべきではないかと考える。
・提案 2:「啓発活動は介護支援専門員を中心とした医療・介護従事者に行う」
提案 1 で述べた以外の紙おむつリサイクルの障害となっているのは、現状において不衛
生でありそうという、使用済紙おむつを利用した再生材料に対して消費者が抱いている印
象が悪いということである。今回インタビュー調査を行ったトータルケア社・ユニ・チャー
ム社においても衛生面では特に気を使っており、人体に害がないように努めているが一般
の消費者への啓発は困難であるのが現状だ。そのためユニ・チャーム社では対応が難しい一
般人に啓発活動を行うのではなく、医療・介護従事者に対して啓発を行う方針であり、その
方針に筆者も賛成する。
そこで筆者は、啓発活動においては、特に筆者は医療・介護従事者の中でも「介護支援専
門員(ケアマネジャー)」に対して行うべきであると提案をする。
介護支援専門員(ケアマネジャー)とは、厚生労働省によると「要介護者や要支援者の人の
相談や心身の状況に応じるとともに、サービス(訪問介護、デイサービスなど)を受けられ
るようにケアプラン(介護サービス等の提供についての計画)の作成や市町村・サービス事
業者・施設等との連絡調整を行う者。また、要介護者や要支援者の人が自立した日常生活を
営むのに必要な援助に関する専門的知識・技術を有するものとして介護支援専門員証の交
付を受けた者。」7 という位置づけになっている。
介護支援専門員はその業務の性格上、要介護者・要支援者の相談に応じる・アドバイスを
する等を行うことで支援し、その家族がいる場合にはその家族とも関わる機会が多く、その
他の医療・介護従事者よりも、その機会は多いのではないかと筆者は考える。実際に筆者に
も要介護認定を受けている家族がおり、様々な面において介護支援専門員にはアドバイス
をしてもらい、その専門知識は大いに介護の際に参考になっている。
7 (文献表出典 21)

67
前述のとおり、使用済み紙おむつは、国内で年間約 300 万トン以上排出されており、約
30%が病院や老健施設等の事業者から、残りの約 70%が家庭から出されている。その 70%
を占める家庭において、介護を行う人たちのサポートを行う介護支援専門員と、その介護支
援専門員が所属する事業所に対して、再生材料を使用した紙おむつに関して安全性・意義等
を理解してもらい、介護担当者に薦めてもらうことが出来るのであれば、要介護者や要支援
者を抱える各家庭やその他の消費者への普及・理解等も進んでいくのではないであろうか。
・提案 3:「再生材料を使用した紙おむつを自治体等の子育て・介護支援に活用する」
提案 2 では主に高齢者への啓発を進めるための施策となっている。しかしそれと同時並
行で乳幼児の子育て世代等に対しても普及活動を行わなければならないと筆者は考える。
そこで筆者が提案する 3 つ目の施策は、乳幼児の子育て世代等に対する普及活動のため
に、再生材料を使用した紙おむつが製作されたようになった場合には、自治体等の子育て・
介護支援に活用するということである。
現時点において日本全国の様々な自治体では子育て・介護の経済的支援のために、ごみ袋
の購入量を抑えるため、紙おむつ専用のごみ袋を無料配布しているところが存在するが、同
様に紙おむつ自体を無料配布して、購入代金を補助している自治体が多く存在する。
その自治体において配布する紙おむつを、再生材料を使用した紙おむつに変える事が出
来れば住民の意識の変革・自治体内の啓発の両方を行う事が出来るのではないであろうか。
また、そのようなシステムが確立されれば再生材料を使用した紙おむつに一定の需要が出
来ることは間違いなく、循環の輪を構築することも可能となるはずである。
しかし、その際には再生材料を使用した紙おむつの清潔さ・安全性に関してしっかりと住
民に対して説明を行い、理解を得ていく必要はあると考えられる。
以上の再生材料を使用した紙おむつの普及に関して、双方で重要となってくるのは「住民
の負担を安くするように取り組みを誘導する」ことである。最終的に使用を決定するのは消
費者であるので、消費者の追加負担を如何に抑えていくかに関しては、再生材料を使用した
紙おむつ普及のためにもメーカー・自治体・リサイクル団体等の連携した取り組みが重要と
なっていると筆者は考える。
・提案 4:「紙おむつリサイクルを街づくり・雇用創出の手段として考える」
筆者が提案する 4 つ目の施策として、紙おむつリサイクルを環境対策のみで考えるので
はなく、トータルケア社の長代表取締役が提案していた、街づくりや雇用創出という新たな
見方で行っていくことも重要なのではないか。
実際に大木町では前述のとおり、住民のゴミ出しの支援のためシルバー人材センターに
よる 65 歳以上のみの高齢者世帯を対象とした“ゴミ出しサポート事業”を行った。
この事業は希望があった高齢者の自宅に男女ペアで訪問し、ゴミ回収や会話等のコミュ
ニケーションを行う事業である。これによって回収率に大きな変化はなかったが、大木町で

68
お年寄りがゴミを自宅内に溜め込むことは無くなり、高齢者の見守り対策は向上している。
このような制度は孤独死が増加している都市部などでは、問題解決の 1 つの手段となる可
能性があるのではないか。
このような見方を変えて取り組みを行うことも重要になっていると筆者は考える。
・提案 5:「メーカー同士等で積極的な情報開示・共同運営等を検討する」
紙おむつリサイクルは現状では一部の団体・企業が取り組んでいるに過ぎない。最も大事
なことは、業界全体で紙おむつリサイクルに傾かなければならないことである。
つまり業界全体で取り組まなければ、紙おむつリサイクルの普及はもちろんのこと、リサ
イクル実施を後押しするために必要となってくる法制度の整備も行うことは困難になって
くると考えられる。そもそも紙おむつリサイクルが普及しなければ紙おむつリサイクルに
取り組んでいない他の会社や消費者意識は変わらないはずである。
以上を解決するために、筆者は 5 つ目の提案として、業界全体でリサイクルの流れが起
こらないという問題を回避するためにも、既存の紙おむつリサイクルを実施している企業
等による、積極的な情報開示・共同運営等に及ぶ、踏み込んだ取り組みを行わなければなら
ないのではないかと考え、その実施を検討することを提案する。
実際に日本経済新聞によると、自動車業界ではトヨタ自動車株式会社が、2015 年 1 月に
同社が保有している燃料電池車(FCV)に関連する特許の実施権を無償で提供するという発
表がなされた。その対象となるのは、同社が単独で保有している世界で約 5680 件の特許(審
査継続中を含む)であり、FCV の開発・生産の根幹となる燃料電池システム関連の特許が
中心になる。これらの特許を使用して FCV の製造・販売をする場合、2020 年末までを期限
として特許実施権を無償とする 8 というものだ。
トヨタ自動車はこの対応に関して自社の Web ページ内にて、「FCV 導入初期段階において
は普及を優先し、開発・市場導入を進める自動車メーカーや水素ステーション整備を進める
エネルギー会社などと協調した取り組みが重要であるとの考えに基づくものである。9 」と
している。つまり、FCV 導入初期段階においては普及を優先し、開発・市場導入を進める
自動車メーカーや水素ステーション整備を進めるエネルギー会社などと協調した取り組み
が重要であるとの考えに基づくものであるということである。
この事例は自動車業界におけるもので、業界規模に関しては大きく異なっている。しかし
このような普及を促進させるための方策の実施することによって、紙おむつリサイクルの
普及を促進するようなことも必要となっており、検討する必要もあるのではないか。特にト
ヨタ自動車のような特許の無償提供では、特許を提供された企業において、その技術を踏み
台に新たな技術が開発されるようなことも、期待できる可能性がある。
しかしその場合には技術を提供する側の企業や団体は、自らが研究していた技術を不特
8 (文献表出典 22) 9 (文献表出典 23)

69
定多数に提供してしまうことになる。そのようなことが行われる場合には、決して技術提供
側が不利益を被らないような仕組みを整備することも必要である。さもなければ技術提供
側は渋ってしまい効率的に制度の研究開発が行えなくなってしまう。
トヨタ自動車の事例では、特許実施に際して、トヨタ自動車に申し込み、「具体的な実施
条件などについて個別協議の上で契約書を締結する」予定であるという。そのような技術提
供側がチェック出来るような体制づくり等を通じて、技術提供側が不利益を被らないよう
な対策・仕組みを整備する事が必要であると筆者は考える。
・提案 6:「紙おむつリサイクルの検討を行うべき自治体について」
6 つ目の提案として、筆者が研究を行う中で、紙おむつリサイクルを検討することを促し
ていきたいのは焼却炉の老朽化などの問題を抱えている自治体であり、それらを中心に取
り組むことが出来るのではないかと考えた。
紙おむつはその製品特性から使用済みの場合、内部の多くの水分を含んでいる。そのため
非常に燃えにくいので助燃材を投入して燃やすことが必要となってきている。そのような
特徴があるため、紙おむつの排出量が増加した場合、助燃材による費用負担増等の要因から
焼却コストの増加が懸念される。
また紙おむつには多くの石油由来の材料が使用されているために、その焼却によって炉
を傷めてしまうことがあるという。さらにその現象は現在老朽化が進んでいる焼却炉にお
いてよく見られるという。
以上が当てはまる自治体においては、処分費用の削減・焼却炉の高寿命化のためにも紙お
むつリサイクルという新たな施策を検討してみてもいいのではないか。
・提案 7:「紙おむつの区別回収を実施する際の注意点について」
7 つ目の提案は、紙おむつの区別回収を実施する際の注意点である。紙おむつリサイクル
を行う際には、処理の効率化を進めるためにも、他のごみと紙おむつが混在しないようにす
る必要がある。その為に、紙おむつを他のごみと区別出来るような状態で分別回収すること
が紙おむつリサイクルを実施する第一段階である。また今後、この区別回収こそが、紙おむ
つリサイクルを行うことを検討する場合において、重要になってくるのではないかと筆者
は考える。紙おむつの区別回収を実施する場合には、住民に対しての様々な配慮を行わなけ
ればならず、行わない場合はこの回収は実施出来ない。
実施の際に留意する必要があることは、「衛生面」・「広報面」・「住民への理解を得る」・「規
則違反の発見、防止」である。この 4 項目は、現在紙おむつを他のごみと区別できる回収方
法を実施している 38 自治体で、回収を実施する際に注意していることである。特に広報面
に関しては、その他の 3 項目の周知をしっかりと行うためにも最重要となってくる。イン
タビュー調査を行った大木町環境課の益田課長は広報において最も重要なことは「繰り返
し」であるとしている。広報誌・Web ページ等、様々な方法を用いて繰り返し広報を行い、

70
如何にその意義を関係する人々に理解してもらうかにかかっているという。
また行う際には、自分たちの分別活動が町づくりにどのように反映されているのかが分
かることで意識を高めていくことに繋げるのが大切であると語った。実際に、意識高揚のた
めに大木町で導入されているような、表彰制度等を活用する等、排出者が楽しみながら参加
出来る仕組み作りも、大切となっているのではないかと考える。
現在紙おむつの区別回収を行っている自治体でその対応に苦労することは、主に「広報
面」・「衛生面」・「プライバシー保護」が大きな割合を占めている。紙おむつの区別回収を実
施した際にはこのような注意点を元に取り組みを行うことが求められている。特にプライ
バシー保護に関しては、自らが紙おむつを使用していることを周囲に知られたくない住民
も多く存在する。その為特定の日にのみ限って排出する方法ではこの要望に応えることは
難しい。この要望に応えるためには、「回収」を実施する曜日“のみ”固定にして、24 時間
365 日いつでも排出することが出来る大木町のような取り組みが必要になってくるのでは
ないか。
なお都市部においては高層マンション等の高層建築物があり、そこに居住している場合
は排出する際に、同じ場所に住む住民と接触する場合も多々あると考えられる。そこに配慮
するためにも、別途プライバシー保護を念頭に置いた対策が求められる。
だが、以上に記載した苦労・注意していることに関しては自治体内の年齢構成によって異
なることも本調査で判明している。乳幼児・高齢者の人数が全国平均よりも高い自治体にお
いては、特にプライバシー保護の割合が上昇し、住民の理解を得る項目は無くなった。
このように、自治体内の住民の年齢構成によってどのようなことに気を配るのかは大き
く変わってくるので、定期的に調査を行いニーズの把握をしておく必要がある。
・提案 8:「法規制を整備すべきである」
8 つ目に提案する施策として法規制を整備すべきであると筆者は提案する。しかし、現状
において紙おむつに関係した法規制の制定は容易ではない。実際にその法規制を検討する
のは環境省となっている。しかし、紙おむつに限定した法規制を作るとなった場合は、必要
性があるのかどうかを調査しなければならないと環境省の担当者は話した。
また、紙おむつの多くが焼却処分されている現状を精査して、需要を調べなくてはならな
いという。特にリサイクルの実施によって、費用は上昇しないか、CO₂の排出量が増えない
か、使用するエネルギーなどの資源を今以上に多く使用しないかなど、多くの問題を回避し
なくてはいけないので、その辺りのデータをもっと集めなくてはいけないという見解も示
している。
しかし現状において、循環型社会形成推進基本法第 11 条「事業者の責務」の項目がある
にも関わらず、多くの紙おむつメーカー側はリサイクルへの取り組みや環境配慮に関して
も取り組みが無いのが現状である。この現状を変更し、業界全体で紙おむつリサイクルの制
度作り・技術開発を強力に推し進めていく為にも個別リサイクル法等の法規制の整備は必

71
要不可欠なのではないかと筆者は考える。
以上 8 項目が、筆者が本研究を行った際に今後様々な自治体やリサイクル会社、紙おむ
つメーカーが紙おむつリサイクルを取り組み、新たな資源の循環を実現するためにどのよ
うにすれば良いのか、筆者なりに考えられる施策と注意点である。
また上記以外に、筆者が本調査を通じて今一度考えるべきものがあると感じた。
それは紙おむつメーカーやリサイクル会社等が“民間企業”であるということだ。現在行
われている紙おむつリサイクルや、将来的に環境省や国が主導をして紙おむつリサイクル
を行うようになった場合のどちらであったとしても、紙おむつを生産しているメーカーや
リサイクル会社・回収の際に業務委託をされている業者、使用済紙おむつを排出する排出者
等、実施主体の中に民間企業が全く入らないということは無いと考えられる。
実際に環境省の担当者も「基本的に自治体が実施する取り組み(特に資源循環に関して)は、
企業(メーカー・リサイクル企業等)が連携していないと出来ない」という風に見解を示し、
さらに個別の法規制に関しても、メーカー1 社のみでなく、業界全体の動向も見極めて総合
的に判断する必要があるという考えを示している。
以上のことから民間企業の重要性は非常に大きなものであることが分かるのではないか。
民間企業や団体は自らの存続や従業員への給料の支払い等の履行の為に、利益を上げな
くてはならない。利益を上げなくては業務の選択肢が狭まるばかりか、最悪の場合は事業そ
のものが成り立たなくなってしまう。そのことを意識して方策を提案しなければ、民間企
業・団体はどんなに素晴らしいリサイクル計画であっても受け入れ・実施は困難であろう。
さらに民間の考えを排除して考えてしまった場合には、議論をいくら行ったとしても平
行線を辿ってしまい、リサイクル実施は困難である。
だが逆に民間の原理を理解する、または協議を通じて理解をして、それに対応可能な方策
を創出することが出来れば、民間とその他の団体のそれぞれが実施可能な方策を創ること
が可能であると考えられる。
筆者は、民間企業の独自の戦略があるので、リサイクルが進まないのは仕方ないという意
見を持っているのではない。紙おむつは今後の環境への影響や資源の枯渇等を考えると実
施することが大前提であると考える。
しかし現状のように双方の意見が嚙み合わず、足並みが揃っていない状態では、紙おむつ
リサイクルが進展することは難しいのではないか。ゆくゆくは全ての団体が協力出来るよ
うにするためには民間企業、特に紙おむつメーカーの戦略・思考・それを考えるに至った背
景等を理解していかなければならない。そして最終的には相互理解に繋げていかなければ
ならないと考える。
この紙おむつリサイクルは多くの団体・消費者が参加する性質のものである。その全てに
協力をしてもらうことが大切となっているため、民間の視点で考えられるような広い視野
を持ち、考えを理解することが必要となってくるはずである。

72
以上から筆者は民間企業の視点で考える大切さを学んだ。しかしこのような施策も結局
は紙おむつリサイクルに関わる全ての主体が協力しなければ成しえないものである。繰り
返しになるがまずは、それぞれ持っている認識・意見を共有し、共通認識を持つことが最も
重要なことであると筆者は考える。
結論
本研究ではまず初めに、文献調査・Web ページ調査を行い、紙おむつリサイクルの現状、
紙おむつの回収の現状を知る事が出来た。その調査後、情報を元に、紙おむつリサイクルに
取り組んでいる・関係している 5 団体に対してインタビュー調査を行い、様々な紙おむつ
リサイクルに取り組む人々の貴重な意見を聞くことで前述のとおり、現在紙おむつリサイ
クルが抱える様々な問題や参加している各団体の課題も発見する事が出来た。
筆者は研究を行うなかで当初、紙おむつリサイクルの問題点は、多くの企業や自治体が紙
おむつリサイクルの取り組みを実施しておらず、さらに広義的に環境配慮に取り組んでい
たとしても、その取り組みに偏りがあることが問題ではないかと考えていた。
その根拠として、そもそも紙おむつの環境配慮やリサイクルはほとんど行われておらず、
また行われている環境配慮の取り組みも主に森林資源の保護を多く実施しているという偏
りがある点。さらに現行の紙おむつで多く使用されている石油起源の材料で作られている
フィルム・不織布・高吸水性ポリマー等のリサイクルへの取り組みは、一部の企業を除いて
実施されていないという問題点が、筆者が考えていたものである。
だが研究を進めるうえで、福岡県の研究機関では数年前から紙おむつ由来のプラスチッ
ク及びポリマーのリサイクルの研究が進められており、実用化にあと一歩と言うところま
で来ていることも知ることが出来た。また先進的な紙おむつメーカーでは紙おむつリサイ
クルに取り組んでおり、特にユニ・チャーム社では今まで実験室レベルだったリサイクルを、
本論文を執筆中の 2016 年 12 月から大規模な実証実験を鹿児島県志布志市において実施す
るまでに至った。
このように紙おむつリサイクルは少しずつではあるが、取り組み例も増加しており、技術
的にも前進していることが分かった。しかし、インタビュー・アンケート調査等の研究を行
うにつれて、「紙おむつリサイクルに関係する各団体間の情報共有・協力・法整備が不十分
であること」、さらに「消費者の意識」、「紙おむつリサイクル制度が未確立である」等の、
当初見えていなかった問題点が紙おむつリサイクルには存在しているのではないかと筆者
は考えるようになった。特に筆者が一番問題であると感じた「各団体間の認識等のずれ」は
紙おむつリサイクルを行うにあたって、制度確立等の場面において大きな障害となってく
るはずであり、この問題解決の重要性を筆者は強く感じた。
以上のように取り組みが現在進んでいないことよりも団体間の認識等のずれ等の“目に
見えない部分の問題”が現在の紙おむつリサイクルの真の問題点であると、本研究から確信
する事が出来た。

73
現状としては、紙おむつ業界において紙おむつリサイクルはまだ始まったばかりである。
ほとんどの紙おむつ関連の企業においてリサイクルはもちろんのこと、環境配慮も行って
はいない。また行っている場合でも、その進行度は各団体によって異なっている。そして、
重要な自治体における紙おむつの区別回収実施率も、全自治体の 2%に止まっている等の問
題や、企業戦略等の複雑思惑が絡むなど、課題が多くあるのが現状である。
このように紙おむつリサイクルという制度自体新しいものであり、またそれぞれの進行
度の差異も大きなものがある。また、それぞれの戦略等の考え方もあるので意見や認識も揃
わないのも仕方のないことなのかもしれない。しかし、使用量の増加によって廃棄物問題・
資源の枯渇等避けられない問題が迫っており、その影響を受ける可能性は極めて大である。
その問題の影響を最小限にするためにリサイクルに取り組む場合、現状の問題点となっ
ている“団体間における情報共有・協力の仕組み作り”は実施すべきである。そのうえで一
致団結して円滑に取り組むためには、認識のずれを可能な限り無くさなくてはいけない。ま
た、認識のずれを無くすためにも、それと同時に紙おむつリサイクルに関する知識・経験・
認識等を、現在紙おむつリサイクルに取り組んでいる団体のみでなく、現在は取り組んでい
ない、さらに多くの企業・団体・消費者等に共有し、拡散する必要があると筆者は考える。
特に、現状で紙おむつリサイクルを行っていない紙おむつメーカー等の団体への意識啓発
や技術支援は、今後可及的速やかに行うことが求められているのでないか。
前述のとおり、環境省の担当者に対して、「紙おむつメーカー側に生産段階でリサイクル
を行う責任があることを定めた法律を実現する際の問題点」ということで尋ねた際に「メー
カー側の動向も見極めて総合的に判断する必要があるという見解を示した。その中では、例
えば紙おむつメーカー1 社だけが紙おむつリサイクルに乗り気であったとしても難しく、さ
らに法律であったら日本全国で影響してくるので社会情勢を考慮して行う必要もある。」と
いう意見も聞かれた。
このような条件を満たすために問題となってくるのは情報共有の場が少ないということ
である。特に紙おむつリサイクルを行う団体同士や、様々な支援制度を用意している環境省
との交流が無い事は、お互いの考えを理解するために大切となってくる交流の場が無い事
を示しており、その取り組みが行われていないことは大きな問題であると筆者は考察する。
以上の問題点を解決するためにも、筆者は交流の場を増やすために各団体の垣根を超え
た横断的な会議体の設置、一般に関する啓発に関しては、医療・介護従事者、特に介護支援
専門員に対して啓発活動の実施をすべきだ等の 8 項目を提案した。
また現在紙おむつリサイクルを行っていない企業や団体にリサイクルの輪を広げるため
にも、民間企業の視点で考えることの重要性・積極的な情報開示の必要性を改めて感じた。
最後に、紙おむつリサイクルは始まったばかりの制度であり認知度は決して高くない。ま
たそれゆえに多くの誤解や団体間での意見の食い違い等も多く存在しており、リサイクル
を阻んでいる。その中で進めていくには各団体や関係者への意見交換や協議の場において

74
時間をかけて差異を無くしていくことが必要となっているのは間違いない。
本研究が、そのような各団体間の認識の差異を無くす一助となり、多くの人々に紙おむつ
リサイクルに関して興味を持ってもらい、検討するきっかけとなれば幸いである。
以上が「紙おむつのリサイクルが進まない要因とその解決策の考察」という今回のテーマ
に関しての研究結果である。
東京都市大学 環境学部 環境マネジメント学科 枝廣淳子研究室 4 年
学籍番号:1362027 緒方峻

75
文献表
1.総務省統計局,2015,「人口の動向」総務省統計局ホームページ, (2016 年 10 月 12 日に
取得,http://www.stat.go.jp/data/jinsui/2013np/pdf/gaiyou3.pdf)
2.東洋経済オンライン,大野 和幸,2013 年「大人用おむつが、バカ売れするワケ」(2016 年
11 月 25 日に取得,http://toyokeizai.net/articles/-/26424)
3.日本経済新聞電子版,2016,「三井化学、紙おむつ用不織布2割増産を発表」(2016 年 11 月
25 日に取得, http://www.nikkei.com/article/DGXLZO04311170Q6A630C1TI5000/)
4. ユニ・チャーム株式会社,2016,「世界初「使用済み紙おむつ再資源化技術」
鹿児島県志布志市と実証試験開始」,ユニ・チャーム株式会社ホームページ,(2016 年 12
月 27 日に取得,http://www.unicharm.co.jp/company/news/2016/1205007_3942.html)
5. 福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会,福岡都市圏紙おむつリサイクルシ
ステム検討委員会報告書(案)P9,福岡県庁ホームページ,(2016 年 12 月 27 日に取得,
http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/185068_51399827_misc.pdf)
6. 一般社団法人 日本衛生材料工業連合会,2008,日本衛生材料工業連合会ホームページ,
(2015年 11月 19日に取得,http://www.jhpia.or.jp/product/diaper/data/structure.html)
7. 大王製紙株式会社,大王製紙株式会社ホームページ,
(2015 年 11 月 19 日に取得,http://www.daio-paper.co.jp/csr/paper/index.html)…P6
8.日本製紙クレシア株式会社,2015「日本製紙グループ環境憲章」,日本製紙クレシア株
式会社ホームページ,(2015 年 11 月 19 日に取得,
http://www.crecia.co.jp/environment/index.html)
9.ピジョン株式会社,「地球環境保全のために(環境)」,ピジョン株式会社ホームページ,
(2015 年 11 月 19 日に取得,http://www.pigeon.co.jp/csr/environment.html)
10.ユニ・チャーム株式会社,2015,「特集 3 地球環境に配慮したモノづくり」,ユニ・チ
ャーム株式会社ホームページ,(2015 年 11 月 19 日に取得,
http://www.unicharm.co.jp/csr-eco/special03/index.html)

76
11.ユニ・チャーム株式会社,2015,「生物多様性の取り組み」,ユニ・チャーム株式会社
ホームページ,(2015 年 11 月 19 日に取得,http://www.unicharm.co.jp/csr-
eco/environment/biodiversity/index.html)
12.株式会社リブドゥコーポレーション,2015,「紙おむつ リサイクルシステムへの取り
組み」,株式会社リブドゥコーポレーションホームページ,(2015 年 11 月 19 日に取
得,http://www.livedo.jp/company/csr/flow.html)
13.トータルケア・システム株式会社,紙おむつリサイクル《水溶化処理システム》P3,(平成
28 年 8 月 23 日取得)
14.福岡都市圏紙おむつリサイクルシステム検討委員会,福岡都市圏紙おむつリサイクルシ
ステム検討委員会報告書(案)P22・23,福岡県庁ホームページ,(2015 年 12 月 3 日に取
得,http://www.pref.fukuoka.lg.jp/uploaded/life/185068_51399827_misc.pdf)
15.環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課,一般廃棄物処理有料化の手引き
P16,環境省ホームページ,(2016 年 12 月 7 日に取得
https://www.env.go.jp/recycle/waste/tool_gwd3r/ps/ps.pdf)…P27
16.特定非営利活動法人地域循環研究所,紙おむつリサイクルに関する全世帯アンケート調
査結果 P21,(2016 年 8 月 23 日取得)…P31
17. ユニ・チャーム株式会社,2016, CSR 活動報告 2016 特集 3 地球環境に配慮したモノづ
くり(2017 年 1 月 13 日取得 http://www.unicharm.co.jp/csr-
eco/report/uccsr2016_all.pdf)
18.環境省, 一般廃棄物処理有料化の手引き,環境省ホームページ,(2017 年 1 月 13 日取得
http://www.env.go.jp/recycle/waste/tool_gwd3r/ps/)
19.環境省,「市町村一般廃棄物処理システム評価支援ツール」について,環境省ホームペー
ジ,(2017 年 1 月 13 日取得 https://www.env.go.jp/recycle/waste/tool_gwd3r/gl-
mcs/index.html)
20.環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部廃棄物対策課, 食品循環資源の再生利用等の
促進に関する法律に基づく取組等の更なる促進について(通知)P9,環境省ホームペー
ジ,(2016 年 12 月 28 日に取得

77
http://www.env.go.jp/recycle/food/160517_suisin.pdf)…P54
21.厚生労働省, 介護職員・介護支援専門員 2.介護支援専門員概要,厚生労働省ホームペー
ジ,(2017 年 1 月 5 日に取得 http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-12300000-
Roukenkyoku/0000114687.pdf)
22.日本経済新聞,久米 秀尚,2015 年「トヨタが燃料電池車の特許を無償開放へ」(2017 年 1
月12日に取得, http://www.nikkei.com/article/DGXMZO81616520W5A100C1000000/)
23.トヨタ自動車株式会社,2015,「トヨタ自動車、燃料電池関連の特許実施権を無償で提
供」,トヨタグローバルニュースルームホームページ,(2017 年 1 月 12 日に取得,
http://newsroom.toyota.co.jp/en/detail/4663446)