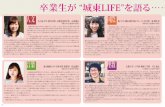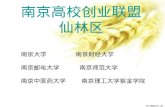四天王寺大学・大学院 四天王寺大学短期大学部...Contents Ⅰ.基礎情報 1.四天王寺大学、四天王寺大学大学院、四天王寺大学短期大学部沿革・・・
美術科における作品評価の客観性について - Hiroshima...
Transcript of 美術科における作品評価の客観性について - Hiroshima...
-
比治山大学短期大学部紀要,第40号, 2∞5 Bul. Hijiyama Univ. Jun. Col., No.40, 2α)5
73
美術科における作品評価の客観性について
斉藤克幸*
1 .はじめに
正解・不正解がはっきりする種類の試験とは違い,
小論文や美術作品の評価は,絶対的点数化が難しく,
時に採点者の主観や噌好に左右されかねない危険性
を苧んでいる。美術教育に携わり,常に学生作品を
評価しなければならない立場にある者にとって,こ
れは大きな問題である。例えば美術公募展の審査に
おいて,審査員によって評価が割れることも珍しい
ことではないだろう。審査員が一人か,または一人
に強い権限が与えられている場合は,個性的な審査
結果が期待できるし 思いもよらぬ才能が発掘され
る可能性が高い。一方 複数の審査員が持ち点方式
で投票する場合は,一部に秀でた個性的な作品より
も,平均的な作品が上位に来る可能性が高くなり,
平凡ではあっても概ね順当な結果が期待できるだろ
う。それぞれ一長一短で,どちらが優れているとは
断言できないし,出品者は結果に納得がいかなくと
も受け入れる他ない。公募展の場合,審査員によっ
て異なる結果が生じても,それは公募展の個性と解
釈することもできる。しかし成績評価という公的責
任をともなう行為において,評価基準が暖昧で,単
に主観や晴好や気分だけで評価されているとしたら,
それはやはり問題である。
しかし美術作品の客観的評価とは甚だ難しいこと
であると言わざるを得ない。時代や流行によって社
会の芸術概念が大きく変化し,その価値が180度変わ
ってしまうこともあれば,作家が生存中は認められ
ず,死後に評価されることも珍しくない。前衛的で
難解な作品なら,なおさら困難な評価を強いられる。
だからこそ評論という分野が確立し,豊富な知識や
経験に裏打ちされた,言わば「最も深く正しい作品
鑑賞jとでもいうべき概念を生み出そうと苦心して
*美術科
いるのだろう。しかし皮肉にも評論そのものが難解
な言葉となり,平易な解説や説明にならず「分かっ
ている者だけが分かっている」というジレンマに陥
るが,それもやむを得ない面もある。なぜなら,作
品を「よく鑑賞Jするためには,どうしても,その
分野における「豊富な鑑賞経験や制作経験また問題
意識と教養Jなどが不可欠で,それなしには,どう
しても表面的な鑑賞に終わってしまう可能性が高く
なるからである。しかしどんなに豊富な経験に裏打
ちされた評価であっても,経験の浅い者から見ると,
まるで評価者の主観や晴好や気分で勝手に判断して
いる,というふうに見えてしまう場合がある。さら
に評価する者の経験も様々で,理解の深さも異なり,
その上どうしても噌好は入り込み,説明能力の問題
もあるから一概に素人判断と切り捨てることもでき
ない。そのような複合的状況の中で評価しているか
ら余計に誤解を招き,時には間違いをも犯す。また,
そもそも晴好は決して悪いことではなく,美術作品
を鑑賞する際に最も大切な感情で,本来そこから出
発するべきことであるとも言える。したがって評価
者によって評価結果が異なるのは「当然のことであ
り,それが個性的で面白いことで多様な表現の価値
観を認めることであるJとも言えるが,できないこ
とを正当化しているにすぎないとも言えるし,美術
評論家の評価と,学校教育における評価とでは立場
も異なる。いずれにせよ,評価する側は豊富な経験
と責任感に基き公明正大な評価をすべきだが,評価
とは裁く行為であるから,知らずに騒りが生じ,つ
い散慢になってはいないだろうか。成績評価という
公的な責任に対して,単なる噌好の範障で評価判断
するなどということはあってはならないが,少しで
もそういう疑念を抱かせてしまったとしたら,それ
だけでも問題である。そこで実際に,十数点のサン
-
74 斉藤克幸
プル作品を,数名の美術科教員に評価してもらい,そ
の結果がどの程度一致するか否かの調査を実施した。
2.調査方法
2004年度美術科一年次前期必修科目「デザイン」
(講議概要は図 1のとおり)にて制作された学生作品
15点をサンプル(図 2)として選択し 8人の本学美
術科教員に評価してもらう。サンプル作品は,あらか
じめ斉藤が採点したものの中から,色々なタイプの作
品を選択しておいた。なお評価を依頼する各教員は,
互いの評価結果を事前に知らされず,評価は一人で行
い他者と相談しないこととする。各教員は調査用シー
ト(図3)に評価を記入する。調査を依頼したのはデ
ザイン・日本画・洋画・彫刻コースから各2名で,以
下の図中で「デA・デB.日A.日B.洋A.洋B.
彫A ・彫BJ と省略している。なお調査は2∞4年8月2 日~1O日に, 03202教室にて実施した。
科 目 デザイン (2単位、 1年次、前期)
担 当 斉藤克幸
太田川の河原で採集した石ころをモチーフ
に、色彩平面構成を制作します。財産的に
は無価値な石ころだが、それを造形として
認識し、観察してみよう。そこには今まで
概 要 気付かなかった美や魅力や面白さがあるは
ずで、つまりこれは、石ころにある造形的
魅力は何なのかを自問自答し見つけ出す行
為でもあるのです。また、ポスターカラー
の扱い方についても練習します。
0石ころの造形的魅力を発見し、それを表現できているか。 O色彩を表現としてコントロ
到達目標 ールできているか。 0全体として美しく仕上っているか。 Oじゅうぶんなスケッチ・エスキースが行われているか。
評価方法 提出作品の採点によって評価します。
図1 講議概要
3.評価方法
課題の主旨・評価基準に基き作品を相対的に序列化
し,その上で「秀・優・良・可jを判定する。また微
妙な判断を迫られる点数化はせず, I不可」はっけな
い。かつ「秀・優・良・可Jのいずれかが,必ず存在
するようにし,各作品の評価理由を自らが明確にし,
言葉にして記入する。なお,作者は同等に出席良好で
あるとし,また25意的判断が入り込む余地を無くすた
め制作者名は伏せておく。
4.調査結果
各教員の採点結果一覧を図4に,順位別一覧を図 5
に示す。なお,順位は,高い評価の多い順に配列して
ある。
さて,残念ながら予想に反し,評価はかなり割れて
しまった。 9人の教員の評価がほぼ一致したのは,作
品3・5・8・9・10の5点のみで,残りの2/3は評価
が割れた。中でも, I秀jから「良」までの範囲で評
価が割れたのが,作品 1・4・6・11・13・15の6点で,
評価として一応はプラス側にあるとはいえ聞きが大き
すぎる。その上,作品2・7・12は「優jから「可J,作品14に至っては「秀Jから「可」と,全く正反対に評価が割れているのだから問題であると言わざるを得
ない。また全体として,順位が上位と下位に位置する
作品の評価は一致しやすく,中間に位置する作品に,
見解の相違が表面化し評価が割れやすい傾向にあるこ
とも見て取れる O 以下に順位毎の評価結果と分析を示
す。なお,彫刻教員Bは「可jをつけなかった。
図4 採点結果一覧
-
圃・・・・・
美術科における作品評価の客観性について 75
作品 l 作品 2 作品3 作品4
作品 5 作品 6 作品 7 作品8
~
作品 9 作品10 作品11 作品12
作品13 作品14 作品15
図2 サンプル作品
-
-76 斉藤克幸
評価調査用シート
以下の作品について評価していただきますようお願いします。
科 目デザインJ(1年次前期必修2単位)
課 題:色彩平面構成「石ころの面白い造形と、直線5本を組み合わせて構成し、ポスターカラーで着彩せよ。J
制作条件 :B2パネルにケント紙水張りの上制作。画面サイズ縦60センチ横40センチとする。石ころは何個使用し
てもかまわない。直諌は画面の辺から辺に必ず到達すること。無彩色の使用禁止。
ポイント:財産的には無価値の石ころだが、造形(形と色)的観点から見れば、実に美しく・面白いものである。
その魅力を、色彩平面構成という方法で表現すること。
評価基準デザインjのための課題であることを前提とする。(従って、単にユニークさや元気さ力強さだけで判
断すべきではない。)
石ころの造形に対する感動が表現されているか。
画面構成の面白さ、巧みさ、バランスが良いか。
色彩表現の美しさ、色彩を意図的にコントロールできているか。
作品としての完成度が高いか。
丁寧に制作されているか。
評価方法:各作品の優劣を判断し、相対的に序列化する。
作品番号
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
評価は秀・優・良・可の4段階とし育、数化はしない、また不可はっけないこととする。
秀・優・良・可のいずれかが、必ず存在するように評価する。
各作品の評価理由を明確にし、記入する。
評価は課題の主旨・評価基準に基づいて行い、それ以外の観点による評価をしないこと。
制作者は同等に出席良好であるものとする。(制作者名は伏せておく。)
評価記入欄
評価 評価理由
1∞-90:秀 (S)、89-80:優 (A)、79-70:良 (B)、69-60:可 (C)図3 評価調査用シート
-
美術科における作品評価の客観性について 77
順
位
図 5 順位別一覧
5.各作品の評価結果と分析
( 1) 作品 3は「秀J4名, r優J5名と評価がほぼー致した。旧評価段階ならば,全員が「優」の評価
をしたことになる。最終的な決断が,色彩面の欠
点を重く見たか,全体の完成度を高く評価したか
で分かれている。確かにやや,意図的に過ぎる配
色だが,自分のやろうとしていることが明快で,
またそれを実行する力を持っており,かつ全力で
制作にあたっている。
(2) 作品 5は「秀J3名 「優J6名と評価がほぼ一致した。旧評価段階ならば,全員が「優Jの評価をしたことになる。シンメトリーの構図を単調で
面白くないとした場合と,安定感がありバランス
が良いとした場合とが対立し また色彩が弱いと
した場合と,調和がとれて落ち着いてバランスが
良いとした場合とが対立している。確かに面白味
には欠けるが,独特の色調が美しく,やはり全力
で制イ乍にあたっている。
作品3の評価と評価理由
直線を意図的に石の造形表現に利用。明暗の
斉コントラストに頼り過ぎて色彩感に欠ける
藤秀 が、その分徹底しており、暗調の中に表現さ
れた静かな空間が魅力。仕事は丁寧。完成度
が高い。
ア秀
動きのある構成で、作者の狙いが明快。丁寧
A な仕事ぶり。
ア優 色は重いが、石の形は見える。
B
日秀 色彩も良い、全体の構成力もある。
A
日優
構成は良いが、やや色バランスの配慮、に欠け
B る。「良jに近い。
洋秀
完成度 4点、丁寧さ 3点、動機3点、色彩4
A 点、構成4点、計18点。
洋優
石の組み合わせ・画面構成は良くできている
B が、色の配置に工夫がほしい。
周タ優
構成も観察もかなり良いのだが、色彩計画で
A 少し失敗してバランスがくずれている。
周5優
テーマに対してそれを理解しての表現。少し
B 暗い。
作品 5の評価と評価理由
石をしっかり観察している。動き・変化の無
斉 い構図は安定しているが退屈でもある。スモ優
ーキーな調子の色彩は美しいが、背景の石の藤配色が上手くいっていない。仕事は丁寧。
ア秀
調和のとれた構成と落ち着いた調子の、安定
A 感のある作品。
ア秀
石の形と直線の構成が良い。色もまとまって
B いる。
日優 仕事も丁寧でバランスも良い。
A
日秀
構成はやや単調だが、色バランスが良く効果
B 的である。
洋優
完成度3点、丁寧さ 3点、動機3点、色彩3
A 点、構成2点、計14点。
洋優 シンメトリーな構成で少し単調。
B
彫シンメトリックな構成にやや難点があるが、
優 構成・色彩・テーマとも明快。(,秀」になっA
てもおかしくない。)
周5優
色のインパクトが少し弱いが、表現しようと
B している。一」
-
78 斉藤克幸
(3) 作品11は「秀J3名, r優J4名, r良J2名と評価が割れた。「優」以上が7票であることを考え
れば,少数派の「良Jが行き過ぎな評価であったと考えられる。特に彫刻教員Bの評価理由は生理的な
もので,評価基準にはない観点である。また洋画教
員Aのこの作品に対する完成度と色彩の評価は低す
ぎると考えざるを得ない。また彫刻教員Aや日本画
教員A.Bが「凄みやリアルな描写表現がどれだけ
許容されるかJなどと指摘し,そのことを問題とし
て「秀」ではなく「優」と判断した様子がうかがえ
る。しかし作者は,濠み表現など果敢にチャレンジ
し,課題を存分に楽しんでいる。
作品11の評価と評価理由
石の質感的造形表現と色面のコントラストが斉 効果的。色相配色の魅力に欠けるが明暗のコ
藤秀
ントラストが快い。石の造形に対する素直な
感動。仕事は丁寧。完成度も高い。
デ優 議みを利用した石の表情が魅力的。
A
ア秀 独特な色の使い方だが、使い所を心得ている。
B
日優
絵画的であるが、石の持つ面白さが十分表現さ
A れている。
日優
作品性が強いが、表現力がある。色的には物
B 足りない。
洋良
完成度2点、丁寧さ 3点、動機3点、色彩2
A 点、構成3点、計13点。
洋秀
石の存在感が強く感じられ、画面構成の工夫
B も伺える。
彫優
問題作で意見の分れるところだろう。議みや
A リアルな描写表現がどれだけ許容されるか。
彫良 少し気持ち悪い。
B
(4) 作品10は「秀J2名 「優J7名と評価がほぼー
致した。旧評価段階ならば,全員が「優Jの評価をしたことになる。この作品は一見して派手で強い作
品である。仕事も丁寧で確実。石ころの表面に見え
る文様の造形化が,やや装飾的になってしまったが,
確信をもって制作している。ただ,配色が強烈では
あるが美しくないことと,構成が配置しただけに終
わっていて面白くないのが欠点であろう。奇しくも
彫刻教員 2名だけが「秀Jの評価をしている。しか
もこの 2名は 1点ずつしか「秀jをつけていなしEか
ら,なおさら興味深い。彫刻を専門とする者にとっ
て,配色の欠点を度外視しても,この作品の,ゴツ
ゴツとした造形感や手触り感が魅力的に映り,高く
評価したのだろう。
作品10の評価と評価理由
配色がうるさく汚い感じ。石の造形が観察に斉 よるのではなく、やや観念に陥っているよう
藤優
に見えるがしっかり自覚的に制作している。
仕事は丁寧。
デ優 明快な構成で石の模様が印象的。
A
デ優 石の表情は良いが、直線の構成に工夫が欲しい。
B
日優 丁寧に仕事をしている。
A
日優
配色・構成が十分に考えられている。あとは
B センス。
洋優
完成度3点、丁寧さ 3点、動機3点、色彩2
A 点、構成3点、計14点。
洋優 石からの発想に対して直線がやや単調。
B
彫秀
放射状の直線の入り方に難があるが、構成
A 力・色彩のバランスが美しい。
彫秀 仕事は丁寧で一般的には良い成績であろう。
B
以上4点については,たとえ専門分野が異なっても
「優れている」と評価する作品に大差がなく,概ね一
致した評価ができるという事実を示している。ただし
図 5によれば「秀Jの評価を得た作品は合計10点,
「優jの評価を得た作品に至っては合計13点にも及ん
でいることも事実だ。さすがに「良jの評価が過半数
を超えている作品に対する「秀・優Jの評価は,行き
過ぎであると考えざるを得ない。また「秀Jか「優」
かを差別化する判断においては,評価者の主観や曙好
が表面化することも見て取れる。サンプル15点中の
「秀・優・良・可」の割合は教員によって異なり「秀Jの数も l点から 4点までの聞きがある。サンプル15点
の範囲で考えると「秀J1 -2点が妥当で, 3 -4点はやや多すぎる。しかしサンプル15点に限って評価を
実施すると,どうしてもその範囲の中で変化を意識し
てしまうから「秀j が 3~4 点になるのも致し方ない。
ちなみに斉藤は,このサンプル15点を加えた計77点を
評価しており,その内 6点に「秀Jをつけているが,
サンプル中には3点の「秀jを選んでいる。
-
美術科における作品評価の客観性について 79
(5) 作品 lは「秀J2名, r優J3名, r良J4名と評価が割れた。多数決で考えれば「良Jになるが,それでも過半数を超えず, r優j以上の評価と措抗している。「秀Jの評価で,作品としてではなく色
そのものを理由にあげているが,それは配色を評
価していることにならない。確かにそれぞれの色
相内において,幅広い色彩を試みているが,色相
配色の魅力や心地良さが生まれているとは考えら
れず,ただ原色の羅列に終わっている。つまり各
色相がそれぞれにブロック分けされていて,互い
に絡み合い高め合う効果を生み出していない。デ
ザイン教員 Bや日本画教員 Bは,色彩そのものが
出せることを評価する傾向にあるようだ。一方
「良jの評価では「退屈・暖昧・平凡・オーソドッ
クスJなどの言葉が見られるように,構成の単純さ,色面の羅列に終わっていて意図的な方向性が示さ
れていないことなどを指摘している。また,石こ
ろの造形化が,じゅうぶんな観察によるのではな
く,手の運動だけで機械的に行われていて美しく
なくマンネリズムに陥っている点も見逃せない。
作品 1の評価と評価理由
石の造形化が観念的であるため形の魅力感に斉 乏しい。構成に変化が無く単調。色相をプロ
良藤 ツク毎に区分けしすぎているため、鮮やかで
あっても退屈。仕事はまあ丁寧。
ア優 構成はおとなしいが石の観察・彩色が丁寧。
A
ア秀
たくさんの色が生まれている。直諌の構成も
B 良い。
日良 オーソドックス。色をもう少し考えるべき。
A
日秀 色・面構成ともバランスが良い。
B
洋優
完成度3点、丁寧さ 3点、動機2点、色彩4
A 点、構成2点、計14点。
洋優
仕事は丁寧だが、画面構成・配色のバランス
B に欠ける。
彫良
構成も色彩感も悪くないが、統一感が不足し
A ているため暖昧な画面になった。
彫良 平凡である。
B
(6) 作品13は「秀J2名, r優J2名, r良J5名と評価が割れた。多数決で考えれば「良」になるが,
「優J以上の評価と括抗している。「秀Jの評価で
は,透明感や光を感じさせる配色の美しさを理由
にあげている。一方「良Jの評価では,構成が十
分でない点を指摘し,配色についても不足を感じ
ている。確かに部分的には色彩の魅力が生まれて
いるし意図的にコントロールしようとする努力が
見える。しかし日本画教員Aが「構成力に疑問 ?J
と指摘している通り,意図的にシンプルな表現を
狙ったものではなく,構成力の未熟さによる結果
と見るべきだろう。
作品13の評価と評価理由
直棋が石の造形表現に効果をあげていて、右斉 下のオレンジ色町石の表現には魅力を感凡|
藤良
配色も悪く無いが背景の色が不適当。構成力
が未熟で全体に未完成な感じ。仕事は丁寧。
デ良
丁寧な仕事ぷりだが、やや散満な構成。密度
A のある所が必要。
ア良 もう少し色幅があってもよいのでは。
B
日良 構成力に疑問?。色彩は良い。
A
日秀
シンプルな構成ながら透明感があり分かりや
B すい。
洋優
完成度4点、丁寧さ2点、動機2点、色彩3点、
A 構成3点、計14点。
洋秀
シンプルだが石の形の組み合わせが良く考え
B られ、光を感じさせる構成となっている。
彫良
透明感のある色彩は美しいが、画面構成が間
A 延びして緊張感に乏しいのが弱点。
彫優 ステキな要素を感じるが、乱れがほしい。
B
(7) 作品 6は「秀J1名, r優J5名.r良J3名と評価が割れた。多数決で考えれば「優jが過半数
となる。作品 5よりも高く評価したのは斉藤だけ
で,他8教員は,作品 5と同じかむしろ低く評価
している。また「良jの評価をした 3教員は,作
品6・8を同等に評価しているが,その他 6教員
は作品 6の方を高く評価し差をつけており,ここ
に見解の相違が見られる。デザイン教員Aや日本
画教員Aは,石ころらしさの表情が不足している
点を問題視している。確かに作品 5は,石の観察
がしっかりしており,色調も悪く無い。ただ,も
う一歩未完成で,シンメトリーの構図も変化に乏
しく,一個の作品としての方向性や明快さに弱い。
一方斉藤は作品 6の配色を高く評価したのだが,
-
80 斉藤克幸
他 8教員はそれを逆に減点対象と考えている。石の
観察不足と,それに起因する造形化の弱さがあるこ
とも確かだ。しかし洋画教員Bも指摘している通り
「石=水面=波紋=緑+青系の色彩j というような
全体としての明快な完成イメージを持ち,そのため
に立体の表現を無視してでも敢えてグラフイツクな
平面表現に徹し,全体の色調を意図的にコントロー
ルしている点を高く評価すべきであると考える。な
ぜなら,抑制的にコントロールしながら配色するこ
とが,この課題において最も難しいことで,むしろ
作品 lのように原色を順番に羅列することの方が容
易であるからだ。
作品 6の評価と評価理由
抑制的に用いられた緑色町語調が魅力。童図 l
斉的に石の立体的フォルムを無視し色面の重層
秀 的表現に徹している。やや観察不足と、中央藤 部分のピンクに違和感を感じる。仕事は優れ
て丁寧。完成度が高い。
ア良
丁寧な仕事ぶり。石の表情にもう少し変化が
A ほしし、。
ア優 もう少し色数が欲しいように思う。
B
日良
石の造形がテーマであるのに、別の物にも見
A える。
日優
やや暗く鈍い色調だが、構成力や丁寧さに好
B 感が持てる。
洋優
完成度4点、丁寧さ 3点、動機3点、色彩3A 点、構成2点、計15点。
洋優
石から波紋を連想させるイメージの発展が面
B 白い。
彫良
それなりに工夫はしているし色感にも良さを
A 感じるが、インパクトのある中心が無い。
彫優 造形的な部分と詩的な部分のバランスを感じる。
B
(8) 作品14は「秀J1名, I優J5名, I良J2名,「可J1名と評価が割れた。多数決で考えれば「優jが過半数となるが, I秀」から「可jまでの聞きは
大きい。ただ図 5から考えても,飛び地の「可Jは
行き過ぎで「秀」もまたそうであると考えられる。
「可Jの評価をした彫刻教員Aは,全体としてガツチリとした大きな石ころの存在感やざらつき感が表
現されている作品を高く評価する傾向にあるよう
だ。また「良」の評価をした彫刻教員Bの評価理由
は作品11の場合と同様,生理的なものである。さ
らに「秀」の評価をした日本画教員Bは,作品 1・
5・13・14を「秀Jとしているが,どちらかと言えば色彩感を強調したタイプの作品を高く評価する傾
向にあるようだ。日本画教員Bと彫刻教員Aの相反
する評価は,それぞれの専門分野や作品の傾向を反
映していて興味深い。確かに評価の難しい作品で,
努力は認められるものの,あまり美しく仕上ってお
らず,完成度も中途半端である。しかしギリギリの
ところで踏み止まって課題意図を汲んでいるし,自
分なりの個性的な方法を なんとか試みようと悩み
ながらも模索している。
作品14の評価と評価理由
石の造形表現の追求が中途半端で、色彩も濁
って汚さカf出てしまった。だカf迷いなカまらも斉 なんとか意図したことを表現しようと努力し
優藤 ている。汚いながらも、色相や明暗のコント
ラストが画面にリズムを与えている。下1/3はエネルギー不足。仕事はまあ丁寧。
ア優
淡彩による色の面白さがある。石の観察不足
A を感じるがリズミカルでポイントもある構成。
ア優 たくさんの石はいいが、少し色面が小さい。
B
日
A 優 構成・色彩が良い。
日秀
少し色バランスに問題があるが、よく練られ
B ており表現力が豊か。
洋良
完成度2点、丁寧さ 2点、動機3点、色彩3A 点、構成2点、計12点。
洋優
ごちゃごちゃしてデザイン的に良くないが、
B 石への想いが強く感じられる。
彫可
構成を複雑にし過ぎて画面がバラバラになっ
A てしまった。努力は認めるが。
周5良 11番と同じく無気味である。日本画的。
B
以上4点については,少なくとも「優」か「良」で
評価判断が揺れていると考えられる。このように順位
が中位に位置する作品の評価は大きく割れ,見解の相
違が表面化しやすいことが見て取れる。サンプル作品
15点を 9名の教員が評価して,計135の評価が下され
たわけだが,その内「秀jが20,I優」が46,I良jが
49, I可」が20となっておりバランスは悪くない。む
しろ「良jがもう少し多くてもよいくらいであるが,
特に「秀」と「優Jが広く分散してしまったことが,この調査の難しさを物語っている。
-
美術科における作品評価の客観性について 81
(9) 作品 4は「秀J1名, r優J3名, r良J5名と評価が割れた。多数決で考えれば「良jが過半数
となるが, r優」以上の評価と括抗している。洋画教員 Aが完成度・色彩・構成で満点として「秀Jの評価をしているが作品 4 ・5の評価で作品 4
の方を高く評価したのは洋画教員Aだけで,他教
員は同じか逆の評価となっていることからしても,
行き過ぎと考えられる。確かに一見して強い作品
で,決断力があり,はっきりとした方向性を感じ
させ,努力して制作している。しかし配色が美し
くないのと,全体としてたどたどしく,大雑把な
面は否定できない。やや見切り発車的に制作され
ていることは,日本画教員 Bの「全体的に思慮に
欠けているj という指摘からもうかがえる。作品
としての強さとは見掛けのそれではなく,例えば
落ち着いた色調の作品 5の方が,強い作品である
ということができる。
作品4の評価と評価理由
斉右上がりのベクトルを感じさせる手法や直線
良 を生かした構成は明快で楽しい。配色もコント藤 ラストがよく効いているが単純。仕事は丁寧。
デ良
丁寧な仕事で好感持てるが構成にもう-1A 工夫あると良い。
ア優 石の表情が少し単調か。
B
日優 丁寧に、また考えて仕事をしている。
A
日良 努力は感じるが、全体的に思慮に欠けている。
B
洋秀
完成度4点、丁寧さ 2点、動機3点、色彩4
A 点、構成4点、計17点。
洋良 構成の工夫があまり感じられない。
B
彫優
対角線状の構成が画面をダイナミックにして
A いるが、抜けるような空聞が無くて多少窮屈。
彫良 「優Jに近いのであろうが、少しパラついている。
B
(制作品15は「秀J1名, r優J2名, r良J6名と評価が割れた。多数決で考えれば「良」が過半数と
なる。洋画教員Aが完成度・色彩・構成で満点と
して「秀jの評価をしているが,作品11・15の評価
で作品15の方を高く評価したのが洋画教員Aだけ
で,他教員は同じか逆の評価となっていることか
らしても,行き過ぎと考えられる。石ころの造形
化が義務的に行われていてマンネリズムに陥って
いて美しくないことや,強いコントラストの配色で
はあるが,作為が過ぎて機械的な彩色に創作の喜
びが感じられないことなどを重くみるべきだろう。
作品15の評価と評価理由
石の造形表現が、観察によるのでなく観念で斉 なされていて、造形に対する感動や喜びに乏 l
藤良
しい。配色のコントラストも作為が過ぎて面
白味に欠ける。仕事はまあ丁寧。
ア優
大胆でコントラストのある構成が印象的。彩
A 色を丁寧にすると良い。
ア優 直線で区切られた形の中に、もっと色が欲しい。
B
日良 構成をもう少し考えるべき。
A
日良
努力としては「優jに近い。色の構成力が十
B 分ではない。
洋秀
完成度4点、丁寧さ2点、動機2点、色彩4点、
A 構成4点、計16点。
洋良 意図的な構成があまり感じられない。
B
周5良 色彩感は悪くないが、構成力が弱い。
A
彫良 石のテーマを感じないが、インパクトあり。
B
一
以上 2点については「良Jが過半数ではあるが,f優j以上の評価と対立していて,やはり中位に位置
する作品評価の難しさを物語っている。
(凶作品 7は「優J2名, r良J3名, r可J4名と評価が割れた。多数決で考えれば「可j となるが,
それでも過半数を超えず 「良」以上の評価と括抗
している。しかし,複数名が「可」と評価したの
が,作品 2. 7・9だけであることは見逃せない
事実だ。一方,斉藤や彫刻教員 Bは「優Jと評価しており,順位からすれば行き過ぎと考えられる。
「可Jや「良jの評価では,石ころの表情(文様的造形)の不足を指摘している。しかしこの課題に
おいて,石ころの表面の細かな文様を描くことだ
けが,表現ではないはずで,マッスとかボリュー
ムとかフォルムなどの量感・塊として捉えること
は,一つの正しい方法だと考える。しかもこの作
品は,そのフォルムをじゅうぶん美しく,かつユ
ーモラスに捉えているし,構成も面白く,慎重な
-
82 斉藤克幸
仕事をしている。斉藤もまた「優Jと「良Jで判断を迷ったのであるが,作者がよく石ころと対話し見
つめていて,単純な観察作業による表面模写に終わ
らず,そこに造形としての貴重な何かを発見し,か
っそのことをある程度は表現できていると評価し
て,配色面での弱点はあるものの「優jとした。作
品3・5は優等生的回答だが,この作品には,模範
囲答にはない可能性が見えるのだが,彫刻教員Bも
同様のことを感じているのではないだろうか。彫刻
教員Aは「石の表情にリアリティーが無いj と指摘
しているが,むしろ作品 1・15に当てはまる言葉で
あると考える。
作品 7の評価と評価理由
デイティールではなく、「ゴロリJとした石
斉のフォルムに着目し、その楽しさが表現され
優 ている。単純だがその造形化はしっかりして藤 いる。配色も悪く無いが、やや鈍い。仕事は
まあ丁寧。一応の完成度をもっている。
ア良
配色はきれいである。石の観察をし、表情を
A 盛り込む必要がある。
ア良 石の形や表情をもう少ししっかり見ること。
B
日可 構成をもう少し考えるべき。
A
日可
テーマに対する構成が十分に練り込まれてい
B ない。
洋可
完成度2点、丁寧さ 1点、動機 1点、色彩2A 点、構成2点、計8点。
洋良 画面構成・色彩に工夫が欠ける。
B
彫可
色彩感に面白味を少し感じられるが、石の表
A 情にリアリティーが無い。
彫優
何だか少し気になる要素を持っている。今後
B の展開を見たい。
(凶作品12は「優J1名, I良J7名, I可J1名と評価が割れた。多数決で考えれば「良」が過半数と
なる。少数派であるデザイン教員Bの「優J,彫刻教員Aの「可jは行き過ぎと考えられる。これは作
品7に近いアプローチで,石ころの表面の文様では
なく柔らかなフォルムに着目した作品である。その
上で,石ころの「ごろんjとした立体としてのボリ
ューム感よりも,影絵のように重なり合う色面の面
白さや美しさに着目し,それを表現しようと試みて
いる。作品 7同様,斉藤は「優Jと「良Jで迷って
いる。作者は実に慎重に制作していて,配色も途中
まではしっかりとコントロールされていた。だが後
半にそのルールが崩れてしまい,配色面での減点が
大きくなった。テーマが失われ石ころらしい形が見
えないという日本画教員A.B,彫刻教員A.Bの指摘は,作品 6に対するものと同種と考えられる。
4人もの教員が,偶然にも同じ「テーマ」という用
語を用いて指摘しているのは,これではこの作品に
対する石ころの存在意義がないということで, I優Jの評価をしたデザイン教員Bでさえデイティール不
足を指摘している。しかし制作現場を見ていなしEか
ら致し方無いことなのだが作者はじゅうぶんなス
ケッチを行っていて,石ころとじっくり対峠してい
たことを付け加えておく。
作品12の評価と評価理由
デイティールではなく石のフォルムの美しさ斉 に着目している。ただ配色が十分にコントロ
藤良
ールしきれず、そのため意図が散漫になって
しまった。仕事は丁寧。
デ良
丁寧な仕事ぶり。色面分割の変化と、石の表
A 情があると良い。
ア優
面白い形を出しているが、石の表情に違いが
B 出ればもっと良い。
日良
石というテーマからは少し別の物だが、この
A 構成であればデザインできる。
日良
色彩の発色効果は良く感じられる。残念なが
B らテーマを配慮できていない。
洋良
完成度3点、丁寧さ2点、動機1点、色彩3点、
A 構成1点、計10点。
洋良 意図的な構成があまり感じられない。
B
彫可
色彩に少し良い点もみられるが、形に具体性
A が感じられずテーマ性が弱い。
彫良 色の発色は良いが、テーマの石を感じない。
B
以上2点については「優Jから「可」にまで評価が
割れていて,やはり中位に位置する作品評価の難しさ
を物語っている。
(凶作品 2は「優J1名, I良J3名, I可J5名と評価が割れた。多数決で考えれば「可」が過半数と
なるが「良j以上の評価と括抗している。日本画教
員Bのみが「優jの評価をして,行き過ぎと考えら
れるが,その理由はじゅうぶん理解できるものだ。
-
美術科における作品評価の客観性について 83
実は作品 2は評価が割れるだろうことを予想して,
敢えてサンプルに加えたものである。「優Jの評価
では,その作品性を高く評価している。また「良j
の評価では,絵画的面白さとデザインらしさの欠
除の間で判断を迷っており,一方「可jの評価で
は,ユニークさに魅力を感じつつも,デザイン的
計画性や正確性の欠除を問題視している。ただし
どの教員も,この作品に対して,一定の面白さや
魅力があることを認めている。
しかしこの課題で要求している学修目標は,そ
ういう結果的面白さではない。ただ面白いだけで
作品を評価してしまっては,それぞれの科目にお
ける学修目標が失われてしまうことになる。もし
この科目が「絵画BJで,同様の課題設定であったならば「良jや「可jをつけた他の教員も,心
置きなく「優Jの評価をしたのではあるまいか。
ではなぜ「デザイン」では,力任せに大雑把に自
由奔放に描いてはだめで,きちんと凡帳面にきれ
いに制作し仕上げなければならないのだろうか?。
仮に結果的に面白い作品が生まれたとしても,大
事なことは,本人がどれだけその作品を自覚して
制作し,その面白さを認識しているのか,という
ことだからである O その上,教員から見たその面
白さも,じゅうぶん完成されたものではなく,あ
くまでも萌芽的な,面白さの可能性であるにすぎ
ないならば,尚更その面白さだけで過大評価する
のは危険であると考えられる。美術表現について
それなりに知識や経験のある教員から見て面白い
とする判断は,時に学生の実力以上に過大評価し
てしまう危険性がある。技術的に未熟な学生作品
の表面的面白さは,場合によっては,幼児期の子
供の絵に対して感じる面白さと同義で,学生本人
が意図的にそう描いたのでなければ,それは単な
る偶然的な産物であり,結果的にいくら面白くと
も,それだけで高く評価してしまうのは危険で,
学生が制作行為や方向性を誤解してしまう懸念が
ある。特に本学の場合 実力的に十分で、はない学
生が多く入学してくるから,このことは重要な点
であり,教育的見地からも,その面白さを本人が
本当に面白いと感じられるだけの,実力や深く幅
広い知識を育てることが必要である。
つまりこの授業「デザインjにおいて,何を学
生に要求し,何を学生に学ばせ・修得させたいと
考えているかが問題になってくる。講議概要には,
「財産的には無価値な石ころだが,それを造形とし
て認識し,観察してみよう。そこには今まで気付
かなかった美や魅力や面白さがあるはずで,つま
りこれは,石ころにある造形的魅力は何なのかを
自問自答し見つけ出す行為でもあるのです。j とあ
り,どちらかといえば,面白さの追求を強調して
いる。これだけを読むならば作品 2の評価は, r優jが適当であると感じる。しかし一方で到達目標で
は,仕事の完成度や色彩のコントロールなど抑制
的な面を強調している。すると概要と目標が矛盾
していることになるが,このことは,この課題を
設定している斉藤自身が,その両面で悩み揺らい
でいることを示すものでもある。なお講議概要に
ついては,後述にて改良版を検討している。
作品2の評価と評価理由
個性的で面白いが、主観的なイメージ優先で、
斉構成・配色を意図的に見せるデザイン的計画
可 性が無い。仕事は一生懸命だが美しく仕上げ藤 る技術が伴っておらず汚い。コンスタントに
こういう作風が出来るかどうかが問題。
デ可
石の観察が不足。彩色をより丁寧にする必要
A カまある。
デ良 色になっていない。
B
日可 筆のタッチを残しすぎると汚くみえる。
A
日優
デザイン的配慮に欠けるが、作品性がありユ
B ーモラスである。
洋可
完成度 1点、丁寧さ 1点、動機 1点、色彩3
A 点、構成2点、計8点。
洋可 絵画的に見ると面白いが、仕事が雑。
B 」
彫良
絵画として面白く見えてしまう。しかしデザ
A インの課題には沿っていない。
周5良
デザインとして考えれば良か可であろうが、
B 絵画的要素は好ましい。
(凶作品 8は「良J8名, r可J1名と評価がほぼー致した。斉藤のみが「可」の評価をして,行き過
ぎであったということができる。だが,この作品
に対して,真面目さは認めるものの,構図にも配
色にも意図的に作り上げていくイメージが無く,
機械的に色塗り作業を繰り返しているにすぎない
点を重く見ている。一方その他全教員が「良Jの
評価をしたわけだが,積極的に「良」であるとい
うよりも,真面目に努力していることを良心的に
評価してのものと考えられる。また作品 9との比
-
84 斉藤克幸
作品 8の評価と評価理由
作ろうとするもののイメージが明快でないま
斉ま終わってしまった。だから配色にも意図が
可 感じられず、構図に工夫が無く寂しい感じ。藤 仕事は真面目だが美しく仕上げる技術が伴っ
ておらず汚い。
ア良
無難にまとまっている。色面分割と色の調子
A にもうー工夫あると良い。
ア良 なんとなく残った空聞が退屈だ。
B
日良 構成・色彩をもう少し考えるべき。
A
日良 色・面構成が単調で、制作意識が少々弱い。
B
洋良
完成度3点、丁寧さ2点、動機1点、色彩3点、
A 構成2点、計11点。
洋良 配色と仕事の丁寧さに欠ける。
B
彫良
上半分は面白いが、下半分が形も色彩も凡庸。
A 全体として迫力が無い。
周院良 色はインパクトがあり素敵なのだが雑である。
B
作品 9の評価と評価理由
作ろうとするもののイメージが明快でないま
ま終わってしまった。努力しているのだが、 l
斉構成も色彩もデザイン的観点からの完成度が
可 低いo 仕事は真面目だが美しく仕上げる技荷|藤 が伴っておらず汚い。水張りもひどく失敗し
ている。ただ、夜配色的世界に魅力を感じな
いこともない。
ア可 石の観察が不足している。配色に強弱がほしい。
A
ア可 色彩の広がりに欠ける。
B
日可
ケント紙の水張りが良く無い。色彩はとても
A 良い。構成をもう少し考えては。
日可
特徴的な配色とも感じられるが、テーマと構
B 成を理解できていない。
洋可
完成度2点、丁寧さ 1点、動機1点、色彩2A 点、構成2点、計8点。
洋可 課題の内容が理解できていない。
B
彫可
色彩にメリハリが乏しく、構成もバランスが
A 悪い。モチーフ(石)をあまり感じさせない。
彫良
絵本的なもので個性を持っている。仕事が雑
B なのが残念。
較において,差別化を図ったためとも考えられる。
しかし作品だけを見つめた時,プラスとなる要素が
少ないと判断せざるを得ないと考える。
(15) 作品 9は「良J1名, r可J8名と評価がほぼー致した。ただ,日本画教員Aや彫刻教員Bが指摘し
ている通り,ある種の魅力があることは間違いなく,
それは作品 2の場合と同質のものである。しかしそ
れも,本人が意図的に計画し完成させていったもの
ではなく,結果としてである点は注意すべきことだ。
ただし作品2・9とも,作者は乱暴に制作したわけ
ではなく,大いに努力していたことは間違いない。
以上3点については, r良Jと「可Jで評価が割れているものの,概ね下位に位置すると考えられる。
斉藤はこの授業において 最初の練習課題から一貫
して,丁寧な仕事で美しく仕上げることが重要な目的
の一つであることを強調し指導している。しかしどう
しても丁寧で凡帳面な仕事が難しい学生には,ある段
階からは,その学生の長所を生かすため,無理な強制
をしないことにしている。なぜならこの授業は,日本
画・洋画・彫刻・デザイン各コースに分かれる前で,
どうしても不得意な学生が存在することを了解した上
であるからだ。しかしそれは科目の目的を放棄し,出
来ない事を正当化しているとも考えられるが,無理な
強制は学生の就学意欲を削いでしまいかねず,本人に
とっての授業の楽しさを損なわない程度に止めている
のが現状である。これは幅広い実力や意識の学生を受
け入れている我々にとって深刻な問題である。未熟だ
からこそ学ぶのであるし,可能性を引き出すのが我々
の責務である。力がある者の実力を伸ばすことは楽し
い行為だが,本学のように実力がじゅうぶんではない学
生を受け入れている場合は,そのための工夫が強く要
求されている。この点については今後の課題としたい。
6.評価結果分析のまとめ
教員によって評価が割れてしまったという事実は,
重く受け止めなければならない。たとえ専門分野が異
なっても,美術教育に携わってきた者の造形について
の最低限の共通認識があって,さほど評価結果に違い
が出ないであろうことを期待していたから,なおさら
予想外であった。評価が割れたということは,評価者
によって評価基準が異なっていたということで,つま
り結果として評価者の晴好が表面化してしまったとい
うことである。具体的に原因を探ってみると,
-
美術科における作品評価の客観性について 85
-評価基準が「面白さ,構成,配色,完成度,丁寧
さJと多岐に渡るため,評価者によって着目し重きを置く観点が異なり,結局は自分の専門分野の
考え方(自己流)に則って評価せざるを得なかっ
たため,晴好が表面化しやすかった。
「デザインj という科目が漠然としていて,また
それについて日頃から深く考察する必要がなく,
各教員によって認議や理解に差があること,教育
目的が明確でないこと,などから結局は自分の専
門分野の考え方(自己流)に則って評価せざるを
得なかったため,噌好が表面化しやすかった。
-今回の評価が,それを依頼した各教員の本当の成
績評価ではないため切迫した責任がなく,厳密に
ニュートラルな立場でいる必要がないから,比較
的自由な気分で評価することができ,そのため噌
好が表面化しやすかった。
「デザイン」という科目におもねった評価で,本
心とは違う結果を下し,二重にズレが生じた。な
ど考えられる。
斉藤の評価結果は概ね多数派に入っているが,い
くつかの作品で少数派となっている。「秀」と「優」
は,旧評価段階ならば共通の「優」と考えられ,そ
の違いを無視すれば,大勢と合致したのは12点。一
方,少数派に入ったのは,作品 1・7・8の3点と
なり,さらに作品 7・8については極めて少数派と
なっている。ただし斉藤は,サンプル作品の作者を
知っているから,授業態度や欠席状況や制作過程,
また学生がどれだけのスケッチやアイデアスケッチ
を重ね,どれだけ熱心に,どういう考えをもって制
作しているのかなどを知っており,それについて指
導やアドバイスをしている。したがって,どうして
も他8教員とは条件が異る。また斉藤はサンプル作
品目点を含む計77点を採点しており,全体の中でサン
プル作品がどういう位置付けにあるかを惰敵しなが
ら評価している。さらに,斉藤は 1年次生基礎実習
「デザインJに携わって長年の経験を有しており,この課題は改良を加えながら 6年連続実施しているか
ら,その授業法や考え方も熟成され,一日の長があ
ると考えたい。一方,採点を依頼した他 8教員は,
この課題に不馴れで,たとえ同じ美術系ではあって
も,考え方や評価すべきポイントが異なり,その上
課題を出した者とそうでない者の聞には,どんなに
評価基準を明確にしようとも超えられない,知何と
もし難い隔たりが存在することを痛感した。
7.評価方法の改良
調査のため実施した評価方法には,一応の評価基
準が示してあったが,最終的には,各教員の主観や
曙好に左右された総合的判断となってしまった。例
えば日本画教員 Bは,作品 2に対して「優jの評価
をしているが,これはこの作品の,結果的面白さを
評価してのことだが,既出の評価基準を遵守するな
らば「優」の評価はできないはずである。しかし,
どうしても捨て切れない魅力を感じた日本画教員 B
の「優jをつけざるを得なかった心情はじゅうぶん
理解できる。つまり,これに似たようなことが事の
大小にかかわらず存在し それが主観的判断として
振れを生じせしめ,結果を左右しているのではなか
ろうか。
そこで,なるべく主観の入り込まない評価方法を
検討した。これは今回の評価依頼に際して,洋画教
員Aが採用した方法を参考にしたものである O 洋画
教員Aは今回,自らで立てた 5項目の評価基準に4段
階評価で合計20点満点の点数化を試みている。その方
法は, r完成度・丁寧さ・制作動機・色彩・構成」を各4点で計20点満点で採点し, 16点以上を「秀j,14点
以上を「優j,10点以上を「良j,10点未満を「可」と
するものである。この方法ならば,完全とは言えな
いまでも,大きく主観や晴好に左右されることはな
いはずで,もとより評価基準に存在しない観点の入
る余地がなくなるから 部分的に突出した魅力だけ
を高く評価することがなくなるのではないだろうか。
そのような判断から,洋画教員Aもこの方法を採用
したのであろう。そこで考案したものが図 6に示す
改良版評価調査用シートである。ここでは五つの評
価基準を設け,それぞれ4段階で評価する O 評価基
準Aは構成を,評価基準Bは配色を,評価基準Cは
石ころの造形表現を,評価基準Dは仕事の丁寧さ・
完成度を,評価基準Eは作品全体のイメージだけを,
それぞれ単独で評価判断し,合計点数で評価を決め
る。「秀・優・良・可」のボーダーラインは,あらか
じめ斉藤がこの方法で採点してみた結果を,斉藤の
1回目の結果と合致するところでヲ!いた。したがっ
て斉藤の 2度の評価結果に一切の変化が無いのはこ
のためだが,それは作為ではなく偶然の結果であっ
たことを付け加えておく。その結果, 18点以上を
「秀j,16点以上を「優j,11点以上を「良j,11点未満
を「可」とした。「秀jは19点以上でも構わなかった
のだが,やや厳しすぎる懸念を感じたため, 18点以
上とした。
-
86 斉藤克幸
図 6:改良版評価調査用シート
改良版評価調査用シート
以下の作品について評価していただきますようお願いします。
科 目デザインJ(1年次前期必修2単位)
課 題:色彩平面構成「石ころの面白い造形と、直線5本を組み合わせて構成し、ポスターカラーで着彩せよ。j
制作条件 :B2パネルにケント紙水張りの上制作。画面サイズ縦60センチ横40センチとする。石ころは何個使用し
てもかまわない。直線は画面の辺から辺に必ず到達すること。無彩色の使用禁止。
ポイント:財産的には無価値の石ころだが、造形(形と色)的観点から見れば、実に美しく・面白いものである。
その魅力を、色彩平面構成という方法で表現すること。
評価基準:以下のA.B.C・D.E。
評価方法:以下の五つの評価基準について4段階で評価する。
4点:そう評価できる
3点:どちらかと言えばそう評価できる
2点:どちらかと言えばそう評価できない
I点:そう評価できない
評価基準A:構成が、変化・リズム・バランスなどを工夫して意図的に考えられている。
評価基準B:配色が、色相・明度・彩度・対比・調和などを工夫して意図的に考えられている。
評価基準C:石ころをよく観察し、その造形美をうまく抽出し造形化して構成に生かしている。
評価基準D:彩色の仕事が丁寧で完成度が高く美しく仕上げてあり、余白まで神経の行き届いた制作をしている。
評価基準E:作品のイメージが明快で、それをしっかり自覚して制作しており、作品としての魅力がある。
評価記入欄
作品番号 評価基準A 評価基準B 評価基準C 評価基準D 評価基準E 計
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
合計点18点以上:秀、 16点以上:優、 11点以上:良、 11点未満:可(ただし合計点を意識せず、それぞれの評価基準について評価すること。なお、制作者は同等に出席良好であるものとする。制作者名は伏せておく。)
-
美術科における作品評価の客観性について 87
図7 再調査による採点結果比較
8.再調査結果
日本画教員 Bと彫刻教員Aに再調査を依頼した。
その結果をまとめたものを図 7・8に示す。注目す
べきは 2回目の調査結果が回目の行き過ぎと
考えられる評価が減少し,概ね大勢の評価結果に沿
う方向へ変化している点である。なお,再調査を依
頼した 2教員は回目の他教員の調査結果は知ら
されていない。再調査による評価結果によると,
・順位 1の作品3の「優」が「秀jに変化した0
・順位 2の作品 5の「優jが「秀」に変化した。
-順位 3の作品11は変化なし。なおこの作品に対す
る「良Jの評価は,斉藤及びこの 2教員によるも
のではない。
-順位4の作品10の「優Jが「秀jに変化した。-順位 5の作品 Iは変化なし。この作品に対する評
価は 2教員間で「秀j と「良Jで大きく割れたままである。一回目の調査で「秀jをつけた日本画
教員Bは 2回目の評価でも20点満点中18点の高得
点、をつけている。なかでも評価基準Eが,斉藤や
彫刻教員Aが2点とネガテイプな判断を下してい
比較のため順位は前回のままとしている。
図8 再調査結果を加えた順位別一覧
るのと対照的で,ここにどうしても避け得ない日
本画教員Bの噌好が現れていると考えられる。
・順位 6の作品13の「秀Jが「良Jに変化し,順位 7
の作品 6の「優」が「秀」に, r良Jが「優」に変化したことによって,順位 5・6・7が逆転して
いる。
-順位8の作品14の「秀jが「優」に変化した。しか
し,この作品に対する行き過ぎと考えられる「可j
の評価は変化しなかった。
-順位 9・10の作品 4・15は変化なしだが,この 2作
品に対する「秀Jの評価は,斉藤及びこの 2教員によるものではない。
-順位11の作品 7の「可jが「良」に変化した。
-順位12の作品12は「良jが「可jに, r可」が「良Jに変化して,結果的にそのままとなっている。
・順位13の作品 2の「優Jが「良Jに, r良」が「可Jに変化した。一回目の評価で唯一「優」の評価を
与えていた日本画教員 Bが「良」に変化したこと
は大きな意味を持つ。なぜならこの作品は,一見
してとても面白いから,どうしても高く評価した
-
88 斉 藤克幸
いという衝動にかられるのだが,それは課題の目的
や評価基準を見誤ることになりかねない。そういう
影響を防ぐ意味からも,今回の評価方法が功を奏し
たと考えられる。ただ,それでも日本画教員 Bは,
評価基準B.Eに3点をつけてプラス側に評価して
いる。
-順位14の作品 8は変化なし。
-順位15の作品 9は「可Jが「良」に変化して,大勢とは逆に動いている。
この 2回目の調査は,斉藤を含め3名の教員でしか
実施していないため,ただちに前回の結果と比較する
には不十分かもしれないが,ある程度は,評価者の主
観や晴好に左右されない なるべく評価基準に沿った
評価ができたと判断してよかろう。また各作品の評価
基準ごとの点数分布など,見るべきものがあるのだが,
ここでは割愛する。
9. rデザインjという科目の目的と講議概要この科目は 1年次前期の必修科目であり,絵画A.
絵画B・彫刻とともに基礎実習と称して年次で最
初に取り組む最も重要な科目と位置付けられている。
本学美術科は,入試の時点では専門的に学修する分野
を決めずに受験し,入学後この基礎実習を経て,各学
生の適性や好みに合わせて専門的に学ぶコースを選択
していく方法を採用している。つまり,この基礎実習
の時期に,それぞれのコースの専門分野の特徴を端的
に示すことも要求されていると考える。したがって,
「デザインj という科目において大切なのは,自由な
造形表現の発露ではなく,他の科目にはないデザイン
的計画性や整理整頓していく考え方・慎重で丁寧な仕
事の体験であると考える。その意味で作品 2は魅力作
ではあるけれど,低い評価としなければならない。そ
うでなければ, rデザインjという科目の意味が失われてしまうからだ。しかし現在の講議概要では,むし
ろ表現としての面白さを肯定しているようにも読め,
到達目標とも矛盾している。そこで,改めて講議概要
を考え直してみた。改良版講議概要では,概要で授業
の全体像を伝えると共に,必要以上に表現の面白さを
肯定するような説明をやめ,計画的に全体を作り上げ
ていくことに重きを置いていることを強調する説明と
した。また到達目標に,改良版評価方法の 5項目の評
価基準をそのまま載せている。ただし評価方法に敢え
て「総合的に判断jという言葉を加えている。なぜな
らば,改良版評価方法のように部分的に評価する方法
を極端に徹底し過ぎると,作品全体で作り上げようと
している意図やイメージが見失われてしまう危険性を
苧んでいるからだ。このことは,洋画教員Aの評価結
果に,ややイレギュラーと考えられるケースが目立っ
たことからも裏付けられる。また,平均的な作品ばか
りが高く評価されることになってしまい,一部に秀で
た作品や実験的作品や可能性を感じさせる作品が,あ
まりに過小評価されてしまうことなども懸念されるた
めでもある。
科 目 デザイン (2単位、 1年次、前期)
担 当 斉藤克幸
まず、ポスターカラーの扱いに慣れるため
の練習課題で画材の特性を理解し、美しく
仕上げるコツを掴んでください。次にそれ
を発展させた色彩平面構成を制作します。
モチーフの石ころの造形的魅力を理解し抽
概 要 出するため、じゅうぶんなスケッチを重ね
ます。やがて、ただの石ころに、様々な造
形的面白さや美を発見できるでしょう。そ
れを基に構成・配色・全体のイメージを作
っていき、一個の作品として美しく丁寧に
仕上げて完成させます。
0構成が、変化・リズム・バランスなどを工夫して意図的に考えられているか。 O配色が、色相・明度・彩度・対比・調和など
を工夫して意図的に考えられているか。 O石ころをよく観察し、その造形美をうまく
到達目標 抽出し造形化して構成に生かしているか。
0彩色の仕事が丁寧で完成度が高く美しく仕上げてあり、余白まで神経の行き届いた
制作をしているか。 O作品表現として、しっかり自覚して制作し明快なイメージをも
っているか。
評価方法上記 5つの到達目標を評価基準とし、総合
的に判断して採点します。
図9 改良版講議概要
おわりに
学生の中には「作品評価は しょせん先生の趣味で
なされているのではないか。」と公言して樺らない者
がいる。そんな時「決してそのようなことはなく,責
任と経験と信念に基づいて公明正大に行っており,全
国どこで誰が評価しても概ね共通な結果となる。Jと
強調するが,内心いささか不安になることもあった。
日頃,学生に対し講評会において,可能な限りの言葉
を尽くして作品の講評を分かりやすく説明することに
努めているが,一体どの程度を学生が理解してくれて
いるか心許ないところではある。また講評会において
-
美術科における作品評価の客観性について 89
は直接,評価結果には触れず,できるだけ良い所を
見つけて誉めるスタンスでいるため,必ずしも評価
結果の理由説明とはならない。学生によっては,ず
いぶんナイープに評価結果に一喜一憂するから,慎
重な言葉使いにも努めている。しかし,果たして本
当に作品評価とは,教員の主観や晴好でなされてい
るのではなく,誰が評価しても変わらないものであ
るのだろうか。そのことを検証するための調査であ
ったのだが,思わぬ結果となった。調査方法が完全
ではないにせよ,個人が単独で評価した場合,どう
しても曙好が表面化してしまうことが避けられない
という事実が浮かび上がったのである。本来美術と
は,採点・評価という方法が馴染まない分野である
のは言うまでもない。しかし我々には,それを実施
しなければならない公的な責任がある。したがって,
今後はよりいっそう慎重に評価すべきだろう。ある
いは複数で合議しながら評価する方法もある。この
方法ならば,個人が見落とした点を補完できる可能
性があるし,異なる見解が視野を広げてくれ,判断
に迷う時は頼りになる。それどころか講評会におい
て,学生の目前で教員が喧々喜々やるところを抜露
すること自体が教育的な意味あることでもあるだろ
う。ただ,そのためには講評会や評価に,これまで
以上の時間と労力をかける必要が生まれ,しかもそ
れを継続し続けなければならない。長いスパンの課
題設定だと効果的だが,短大の美術教育のように
短期に多くの課題を課す方法では,それが頻繁にな
ってしまうから逆効果となってしまう可能性もある。
場合によっては全科目ではなく主要な科目に対して
だけ,前後期一回ずつ,そういう方法を採用するの
も一つの手で,今後の課題としたい。
なお,今回の研究のため多忙にもかかわらず,快
く調査に御協力いただいた美術科教員の皆様と,サ
ンプルとして作品を提供してくれた学生諸君に,心
より感謝するしだいであります。
(受理平成16年10月31日)
Absb百ct
About the Objectivity of the Work Evaluation in the Department of Fine Arts
Katsuyuki SAITO本
1 am engaged in fine-arts education in the junior college. Therefore, 1 am in a position to evaluate
students' works. 1 feel, however, the evaluation is very difficult task. Because when we evaluate the art
works, there is a possibility to be aftected by the subjectivity and the preference. Still, we have the
responsibiliり, of objectively evaluating students' works. Can the same result be expected when two or
more teachers evaluate the same work? 1 conducted an investigation in order to verify the question. That
is nine teachers evaluate 15 students' works, analyzing the result, searching for various problems and
making use of the results for future evaluation.
(Received October 31,2004)
* Department of Fine Arts





![大学院文学研究科 シラバス - Osaka City University大学院文学研究科 シラバス 平成 29年度[2017年度] 大阪市立大学大学院 文学研究科 大学院文学研究科](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/60090529cb17293a5f086695/eccc-ff-osaka-city-university-eccc.jpg)