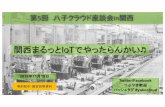平成28年司法試験出題趣旨分析会 解説レジュメ...1 平成28年度 司法試験・出題の趣旨分析会 今回の無料公開講座では平成28年度司法試験の出題の趣旨をみていくことにします。120
研究助成発表会 講演要旨集...(第35回) 公益財団法人 篷庵社...
Transcript of 研究助成発表会 講演要旨集...(第35回) 公益財団法人 篷庵社...

(第 35 回)
公益財団法人 篷庵社
研究助成発表会
講演要旨集
平成 28 年 7 月 29 日(金)
於 塩野義製薬株式会社 医薬研究センター

プ ロ グ ラ ム
日 時 :平成 28 年 7 月 29 日(金) 13 時 00 分から 17 時 20 分まで
場 所 :塩野義 製薬株式会社医薬研究センター オーディトリアム
*所 属 は講 演 当 時 のもの
13:00-13:05 ご挨拶 公益財団法人篷庵社 理事長 武田 禮二
演題および演者(講演 25 分、討論 15 分) 座 長
13:05-13:45
1. 立体化学的に不安定なキラルカルバニオンの合成化学への
展開
佐々木 道子 先生
(広島大学大学院医歯薬保健学研究院 基礎生命科学部門薬学分野)
(篷庵社評議員)
大和田 智彦 先生
13:45-14:25
2. 光制御可能な NO・活性酸素ドナー化合物の開発
中川 秀彦 先生
(名古屋市立大学大学院薬学研究科 薬化学分野)
(篷庵社理事)
廣部 雅昭 先生
14:25-15:05
3. 糖尿病性神経障害の治癒をめざす TNF-αの分子標的療法
小島 秀人 先生
(滋賀医科大学 生化学・分子生物学講座)
(篷庵社評議員)
岩尾 洋 先生
15:05-15:20 休 憩
15:20-16:00
4. 酸化コレステロール secosterol の生物活性機構解析
三好 規之 先生
(静岡県立大学 食品栄養科学部)
(篷庵社評議員)
伊勢村 護 先生
16:00-16:40
5. 新たな薬効評価系の確立に向けて
泉 康雄 先生
(大阪市立大学大学院医学研究科 分子病態薬理学)
(篷庵社理事)
宮﨑 瑞夫 先生
代理
岡村 富夫 先生
16:40-17:20
6.《特別研究助成》
メチル化 DNA 可視化マウスを用いた病態評価法の確立
山縣 一夫 先生
(近畿大学生物理工学部 遺伝子工学科)
(塩野義製薬㈱
創薬疾患研究所)
六嶋 正知 氏

目 次
1. 佐々木 道子
「立体化学的に不安定なキラルカルバニオンの合成化学への展開」
1
2. 中川 秀彦
「光制御可能な NO・活性酸素ドナー化合物の開発」
2
3. 小島 秀人
「糖尿病性神経障害の治癒をめざす TNF-αの分子標的療法」
12
4. 三好 規之
「酸化コレステロール secosterol の生物活性機構解析」
22
5. 泉 康雄
「新たな薬効評価系の確立に向けて」
32
6. 山縣 一夫
「メチル化 DNA 可視化マウスを用いた病態評価法の確立」
42

立体化学的に不安定なキラルカルバニオンの合成化学への展開
広島大学大学院医歯薬保健学研究院 佐々木 道子
1

光制御可能な NO・活性酸素ドナー化合物の開発
名古屋市立大学大学院薬学研究科
中川 秀彦
1. はじめに
一酸化窒素(nitric oxide, NO)は、生体内で NO 合成酵素(NO synthase, NOS)により産生
されて様々な生理作用を担う細胞情報伝達因子の1つである 1)。例えば、血管弛緩による血
圧調節作用、神経伝達の調節作用、生体防御作用、などが知られている 2-4)。常温常圧下では
ガス状態であるため、ガス状細胞情報伝達分子(ガス状メディエーター)と呼ばれている。
現在では、このようなガス状細胞情報伝達因子として、一酸化炭素(CO)や硫化水素(H2S)
も知られるようになっている 5)。NO は、分子量が非常に小さい上に、酸化されやすいなど反
応性が高く、さらにガス状の性質のため、生物実験において定量や投与が行いにくく、非常
に取り扱いにくい性質を有する。このため、NO の生物作用を検討する際には、実験系中で
NO を放出する試薬(NO 放出剤、あるいは NO ドナー)が用いられている。NO ドナーの中
でも、光照射により NO の放出を制御できる化合物、すなわち光制御 NO ドナー(ケージド
NO(caged NO)とも呼ばれる)は、系内で NO の投与場所、投与タイミングを任意に調節す
ることが可能である。これにより、生体内での NOS からの NO 産生を模倣したり、特定の部
位・時間での NO の作用を検討したり、といった実験が可能となり有用な研究ツールである。
これまでに、いくつかの光制御 NO ドナーが開発されているが、我々も独自の光制御 NO ド
ナーを開発し、実際に培養細胞系、組織、生体に応用して、その効果をデモンストレーショ
ンすることに成功している。また、NO に関連する他の低分子量細胞情報伝達因子についても、
光制御ドナーの開発に挑戦し、NO 関連活性種である、HNO、ONOO–については、我々が世
界に先駆けて開発を行ってきた。以下に、我々の開発した光制御 NO ドナーおよび関連活性
種の光制御ドナーの最近の進展について述べる。
2. 光制御 NO ドナー
2-1. ジメチルニトロベンゼン構造を有する光制御 NO ドナー
NO の生理作用が着目され、NO ドナー
の開発が始まった初期から、ケージド
NO の有用性は着目され、先駆的な研究
により二種類の光制御可能 NO ドナーが
開発されている。一つは、Roger Y Tsien
らによるケージド NONOate であり 6)、二
つ目は、筑波大学の藤森教授らによって
開発された BNN 類である 7)(図1)。そ
図1 初期の光制御 NO ドナー類の構造 a) ケージド NONOate の1つである CNO-4(カリウム塩)の構造(自発的に分解する NO ドナーである DEA NONOate を光解除性保護基で保護したもの)、b) 光照射により NO を直接生じる光制御 NO ドナーである BNN5 ナトリウム塩。
2

の後、生物応用に適した可視光領域の光で制御可能な NO 放出剤として金属ニトロシル錯体
も報告されている 8-10)。これらは主に鉄ニトロシル錯体やルテニウムニトロシル錯体である。
これらのドナーは実際には生体応用に用いられた例はほとんどない。我々は、上記の NO ド
ナーとは異なる光反応の仕組みによって光制御 NO ドナーの開発を行ってきた。1つは、2,6-
ジメチルニトロベンゼン(DNB)構造のニトロ基の光転位反応を利用したものであり、代表
的な化合物が Flu-DNB である 11)(図2)。
ニトロベンゼンに代表される芳香族ニトロ化合物では、アリール基の光吸収によってニト
ロ基の転位反応が起こり亜硝酸アリールエステルとなる 12)(図3)。Flu-DNB は UVA 光
(330-380 nm)によって NO 放出
を起こすことが示されたが、さら
に培養細胞に添加した場合にも
光制御 NO ドナーとして作用する
ことが示された。13)(図4)。そこ
で我々は、二光子励起による光反
応の誘起を行った。UVA 域の紫外線を吸収する化合物は、その約二倍の波長の光によって二
光子励起を起こすと考えられる。既に Flu-DNB が二光子励起により近赤外光照射で NO 放出
を起こすことを我々は証明していたが 11)、近赤外光が生体透過性の高い光であることを利用
して、in vivo にも応用可能であると予想し、培養細胞および、麻酔下のマウス脳内に Flu-DNB
を投与して動物実験を行った。まず、細胞内に投与した Flu-DNB に、近赤外域(720-780 nm)
のフェムト秒パルスレーザーを備えた二光子顕微鏡下で光照射を行うと、照射位置のみで NO
の生成がおこることが確かめられた 13)。NO 検出には NO 蛍光プローブである DAR 4M AM
を用いた(図5)。さらに、麻酔下のマウス脳内に Flu-DNB を投与して脳の血管に近赤外パ
ルスレーザー照射を行うと、照射した部分でのみ、光照射に応じた血管の拡張が観察された13)(図6)。近赤外パルスレーザーのみ、あるいは NO 放出部を除いた構造である fluorescein
では血管の応答はみられなかった。これにより、Flu-DNB と近赤外パルスレーザーを組み合
わせることで in vivo 生物応答を制御できることを初めて示した。パルスレーザーによる二光
子励起を利用した光制御 NO ドナーによる NO 投与は神経作用や炎症などの研究において有
効になると考えられる。
図2 開発した光制御 NO ドナーの構造
図3 ニトロベンゼンの光異性化反応の模式図 光吸収によりニトロ基が転位し、亜硝酸エステルとなった後、窒素—酸素結合がホモリシスすることで NO が生成する。
3

図4 Flu-DNB 投与細胞への UVA 照射による細胞内での NO 放出 培養細胞(HCT116 細胞)に Flu-DNB(25 µM)(a, b)または DMSO(c, d)を蛍光 NOプローブ DAR 4M AM(10 µM)とともに投与した後、UVA(330-380 nm)の光を照射した。Flu-DNB 投与細胞に光照射を行った場合(b)のみ NO 生成が検出された。Adapted with permission from ACS Chem. Biol., 8, 2493-2500 (2013). Copyright (2015) American Chemical Society.
図5 Flu-DNB 投与細胞への近赤外パルスレーザー照射による細胞内 NO 生成 培養細胞(HCT116 細胞)に Flu-DNB(25 µM)(a, b)または DMSO(c, d)を蛍光 NO プローブDAR 4M AM(10 µM)とともに投与した後、735 nm の近赤外フェムト秒パルスレーザーを点線で囲んだ1細胞にのみ照射した。Flu-DNB 投与した照射細胞でのみ NO 放出を示す蛍光上昇が観察された。Adapted in part with permission from ACS Chem. Biol., 8, 2493-2500 (2013). Copyright (2015)American Chemical Society.
4

図8 共焦点顕微鏡アルゴンレーザーを用いた NOBL-1 からの位置特異的な NO 投与 HEK293 細胞に NOBL-1 と NO 蛍光プローブ DAR 4M AM を投与し、一部(円内)に 488 nmアルゴンレーザーを照射したところ、NO 放出を示す蛍光プローブ(DAR 4M AM)の赤色蛍光上昇が観察された。(a) 照射前、(b) 円内に光照射後。Adapted with permission from J. Am. Chem.Soc., 136, 7085-7091 (2014). Copyright (2015) American Chemical Society.
図6 Flu-DNB 投与したマウス脳へのパルスレーザー照射による血管弛緩反応の観察 麻酔下にマウス頭蓋骨に小孔をあけ Flu-DNB(100 µM)を 60 分間浸透させた後、二光子蛍光顕微鏡でマウス脳を観察した。マウス脳血管の一部(矢印付近)に 735 nm フェムト秒パルスレーザー照射を行ったところ照射位置で光照射に依存した血管系の拡張が観察された。バーは元の血管径、矢印で示した部分で血管径が拡大した。Flu-DNB(25 µM)(a, b)または DMSO(c, d)を蛍光 NO プローブ DAR 4M AM(10µM)とともに投与した。Adapted in part with permission from ACS Chem. Biol., 8, 2493-2500 (2013). Copyright(2015) American Chemical Society.
5

2-2. 光誘起電子移動反応を利用する光制御 NO ドナー
二光子励起による NO 放出制御は非常に高い空間分解能を実現でき、位置選択的な NO 投
与に適しているが、フェムト秒パルスレーザー装置は、非常に高価であり、汎用性に課題が
ある。一光子励起(通常の励起)によって NO 放出反応を引き起こす光制御 NO ドナーで、
可視光や近赤外光が利用できれば、生体応用の観点で有用性が高まる。我々は、BNN5(図1)
に含まれる N-ニトロソ結合が、不安定ラジカル中間体を介して分解する機構に着目し、分子
内光誘起電子移動反応によって、分子内電荷分離状態である不安定ラジカル中間体を形成さ
せることを考えた。可視光域に吸収を持つ色素(BODIPY)と N-ニトロソアミノフェノール
構造を連結し、N-ニトロシル型の光制御NOドナーであるNOBL-1を開発した(図2)。NOBL-1
は、450-520 nm 付近に BODIPY 部に由来する吸収をもち、500 nm 付近の青色光を照射すると
NO 放出を起こすことが ESR スピントラッピング法および蛍光プローブ検出により確認され
た 14)。BNN5 では、一方の N-ニトロシル結合が光反応でホモリシス開裂した後、不安定ラジ
カル中間体が生成し、2つ目の N-ニトロシル結合が開裂することで安定なキノイミン体とな
る。NOBL-1 では、分子内色素である BODIPY 部が光吸収し励起した後、電子豊富な N-ニト
ロシルアミノフェノール部から1電子移動反応がおこり、不安定な電荷分離状態になると考
えられる。ラジカルカチオン構造となった N-ニトロソアミノフェノール部から水素イオンと
ともに NO が遊離し NO 生成につながったと考えられた(図7)。
NOBL-1 は一般的な光源で NO 放出を行うことができるため、キセノン光源(470-500 nm
のバンドバスフィルター使用)や蛍光顕微鏡のアルゴンレーザー(488 nm)を用いて NO 放
出を誘起できることが分かった(図8)。さらに、ラット大動脈切片を用いたマグヌス試験(ex
vivo 実験)においても、NOBL-1 を血管片組織に投与して青色光照射することで、血管張力
の変化、すなわち血管弛緩作用を誘起することに成功した(図9)。この作用は ODQ(可溶
図7 N-ニトロシル型の可視光ケージド NO である NOBL-1 の構造と推定反応機構 青色光吸収により色素が励起した後 N-ニトロソアミノフェノール部から1電子移動が起こり、NO と水素イオンを遊離した後、不均化がおこると考えられる。
6

性グアニル酸シクラーゼ阻害剤)の投与
により完全に消失したことから、生理的
なNOシグナル伝達系を介して血管張力
を制御した結果と考えられた。
2-3. 光制御 NO ドナーの長波長化
NOBL-1 では、N-ニトロシル構造を
NO 放出部として用いて青色光制御可能
なNOドナーの開発とデモンストレーシ
ョンに成功した。光を用いた治療法に光
線力学療法があるが、一般的な光線力学
療法で用いられる光源は 600 nm 以上の
黄色〜近赤外域の光を用いるものが多
い。そこで、我々の光制御 NO ドナーに
おいても、将来的な治療応用を視野に入
れ、更なる長波長化を試みた。DNB タ
イプの光制御NOドナーFlu-DNBを基に、
NO 放出部として働く DNB 部と可視光
吸収部であるキサンテン環部がより近
づくように分子設計した Rol-DNB を開
発した(図2)。Rol-DNB は、DNB 部と
緑黄色光(500-560 nm 付近)吸収色素で
蛍光分子でもある Rhodamine が連結し
た構造を有する。興味深いことに、Rol-DNB に Rhodamine 部が吸収する緑黄色光を照射した
ところ、NO 生成が観察され、培養細胞系での緑黄色光による NO 放出制御に成功した 15)(図
10)。NO 生成の反応機構は現在検証中であるが、キサンテン環部分の励起エネルギーがニ
トロ基の異性化に利用されたと考えられる。
3. 光制御 ONOO–ドナー
NO は生体内で酸化還元反応や他の小分子との反応を経て、多様な化学種に変換されると考
えられている。それらの化学種も生物活性を有する可能性があり、一部の化合物は広義の活
性酸素に含まれる。NO に関連し生体内で生じうる重要な活性酸素として、ONOO–(パーオ
キシナイトライト)がある。ONOO–は、NO とスーパーオキシド(O2•−)が拡散律速で化学反
応し生成する化学種である。パーオキシナイトライトには求核的な反応性があり、また生理
的条件下で高い酸化活性を示すことが知られている。このため、化学的反応性としては二重
結合やカルボニルへの付加反応と引き続く酸化反応などが起こる。また、生体分子に対して
図9 ラット大動脈切片のマグヌス試験におけるNOBL-1 からの NO の作用 ラット大動脈切片をマヌグス試験の条件で灌流し、NOBL-1 を灌流液を通じて投与した後、青色光を照射した(a)。光照射時のみ照射時間に応じて血管弛緩作用が観察された。ODQ をあらかじめ共存させた場合、光照射時の効果は抑制された(b)。Adapted with permission from J. Am. Chem. Soc., 136, 7085-7091 (2014). Copyright (2015) American Chemical Society.
7

は生体分子の酸化修飾に起因する酸化
ストレスによる細胞障害性が注目され
てきた。一方で、近年では生体内の酸化
ストレス状態の調整機能や、タンパク質
修飾を介した細胞応答の誘導など、活性
酸素シグナルに関わる機能も着目され
ている。光制御によって ONOO–を生成す
るドナー化合物はほとんど報告がない。
我々は、N-ニトロソタイプの化合物から NO が生成した後に生じると考えられるセミキノイ
ミンラジカルに着目し、NO 放出した後引き続いて酸素を1電子還元してスーパーオキシドを
生成するタンデム化学反応を起こす化合物 P-NAP を開発した(図11)。N-ニトロソアニリ
ン構造のパラ位に水酸基を導入することで、NO 放出後のラジカル化合物はセミキノンラジカ
ルと同様の電子構造となる。セミキノンラジカルは酸素を還元してスーパーオキシドを産生
することが知られている。実際には、効率よくスーパーオキシドを生成させるために、二段
階目の酸素の還元反応の効率を上昇させ、かつ、酸素還元後に副生するキノン自身は再還元
されない工夫が必要であった。そこで、芳香環電子密度を高め同時に反応点を塞ぐ目的で4
つのメチル基を導入し、効率よいタンデム反応を実現した。P-NAP に UVA 光照射すると、
NO とスーパーオキシドが連続して生成するため、両者は拡散律速で反応しパーオキシナイト
ライトが形成される。本化合物を培養細胞系に投与し、パーオキシナイトライト特異的蛍光
プローブである HKGreen-3 AM 16)を用いて検証したところ、光照射依存的に細胞内でのパー
図11 光制御型 ONOO–産生化合物(P-NAP)および
光制御型 HNO ドナー(NiP-DAC-DC)
図10 Rol-DNB 投与細胞への緑黄色光照射による細胞内 NO 投与 HCT116 細胞に Rol-DNB および DAF-FM DA を投与し、指定の円内にのみ緑黄色(562nm ダイオードレーザー光)を照射した。A, Rol-DNB 投与細胞;B, コントロール(ブランク)細胞。Adapted with permission from ACS Chem. Biol., 11, 1271-1278 (2016).Copyright (2016) American Chemical Society, with modification.
8

オキシナイトライト生成が上昇することが分かった(図12)生細胞に適用可能なものとし
ては、我々が開発した P-NAP が知られるのみである 17)。光制御によって、ONOO–の投与位置
や投与時間を調節すれば、酸化ストレスの原因となる ONOO–の働き方と、細胞情報伝達で産
生する ONOO–の働き方の違いを精査できる可能性も期待できる。
4. 光制御 HNO ドナー
NO と構造は似ているが異なる性質を示す活性酸素の1種に HNO がある。これは、NO が
1電子還元された化学種に相当する。NO とは1電子の違いであるが、化学的性質も生物作用
も大きく異なることが知られている。HNO は、心収縮力増大作用(陽性変力作用)を発揮す
ることが知られており、また、NO と異なる作用機序、すなわち cAMP を介するシグナル伝
達経路で血管弛緩作用を示したりするなど、興味深い作用をもつ。しかし、その詳細につい
ては不明な点が多い 18)。HNO を生細胞で検出できる蛍光性プローブも我々を含む複数のグル
ープにより開発されている 19, 20)。光制御可能な HNO ドナーとして、我々は NiP-DAC-DC を
初めて開発した。光制御可能な HNO ドナーとしては、現在我々が開発した1種類のみが知ら
れている 21)(図 11)。この化合物では、光吸収を引き金として逆 Diels-Alder 型反応によるア
シルニトロソ化合物の生成が起こり、生じたアシルニトロソ化合物が不安定なため容易に加
水分解される事で、HNO を産生すると考えられた。逆 Diels Alder 型反応は本来、光禁制で熱
により進行する反応であり、このことを利用して加熱することにより自発分解し HNO を放出
する HNO ドナーとして同様の化合物が報告されている 22)。我々が開発した光制御可能な化
合物においては、熱安定性を改善し光照射の内部エネルギー上昇による HNO 放出の割合向上
の工夫を行った。効率や特異性は改善の余地があるが、培養細胞系において、HNO 由来の生
物応答である Calcitonin gene-related peptide (CGRP)産生を光照射依存的に誘導することが確
認できた 23)。HNO のように、新しく発見・着目され、機能がまだ十分に解明されていない活
性酸素の場合、生体内で利用可能な検出蛍光プローブと、制御可能なドナー化合物が両方開
発されることで、詳細な解析が進展すると考えられる。我々は、HNO について、この2つを
図12 光制御型 ONOO–産生化合物を用いた細胞内 ONOO–
生成 (左)HCT116 細胞に光制御型 ONOO–産生化合物 P-NAP と ONOO–蛍光プローブを投与し、光照射すると ONOO–産生を示す緑色蛍光の増大が見られた。(右)一方、同様の処理後に光照射しなかった系ではわずかな蛍光しか見られなかった。Adapted withpermission from J. Am. Chem. Soc., 134, 2563–2568 (2012). Copyright (2012) AmericanChemical Society.
9

それぞれ開発した。今後、その機能の解明が進展し、心臓への陽性変力作用などの医療応用
が考えられるようになるだろう。
5 おわりに
光制御 NO ドナーや光制御 HNO、ONOO–ドナーは、取り扱いにくく不安定な物質である
NO 等の生物作用を研究するツールとして有用であると考えられる。しかし、現状では in vivo
実験系に直接適用するのはまだ難しい状況といえる。制御に用いる光の生体透過性が十分と
いえず、生体の極表層でしか有効に反応誘起できないと考えられるからである。今回示した
様に、二光子励起を利用して生体透過性の高い近赤外光を使用する手法も開発したが、特殊
なレーザーが必要であり、簡便に用いることができるとはいいがたい。今後は、生体透過性
が高い近赤外光を一光子励起(すなわち汎用光源)で利用して NO 等を放出できるドナー化
合物の開発を進めたい。これまで用いてきた色素導入による長波長化を発展させ、近赤外光
で制御可能な NO ドナー等の開発に挑戦したい。
謝辞
光制御 NO、ONOO–、および HNO ドナーに関する研究成果の一部は、生理学研究所 鍋倉
淳一教授、江藤圭博士、京都府立医科大学 鈴木孝禎教授、名古屋市立大学 宮田直樹特任教
授、木村和哲教授、堀田祐志博士、家田直弥博士、との共同研究によるものである。
参考文献
1) Moncada, S., Palmer, R.M., Higgs, E.A., Pharmacol. Rev. 1991, 43, 109-142.
2) Ignarro, L.J., Buga, G.M., Wood, K.S., Byrns, R.E., Chaudhuri, G., Proc. Natl. Acad. Sci. U.S.A.
1987, 84, 9265-9269.
3) Hopper, R.A., Garthwaite, J., J. Neurosci. 2006, 26, 11513-11521.
4) Bodgan, C., Nat. Immunol. 2001, 2, 907-916.
5) Kajimura, M., Fukuda, R., Bateman, R.M., Yamamoto, T., Suematsu, M., Antioxid. Redox Signal.
2010, 13, 157-192.
6) Makings, L.P., Tsien, R.Y., J. Biol. Chem. 1994, 269, 6282-6285.
7) Namiki, S., Arai, T., Fujimori, K., J. Am. Chem. Soc. 1997, 119, 3840-3841.
8) Bourassa, J., DeGraff, W., Kudo, S., Wink, D.A., Mitchell, J.B., Ford, P.C., J. Am. Chem. Soc. 1997,
119, 2853-2860.
9) Prakash, R., Czaja, A.U., Heinemann, F.W., Sellmann, D., J. Am. Chem. Soc. 2005, 127,
13758-13759.
10) Rose, M.J., Fry, N.L., Marlow, R., Hinck, L., Mascharak, P.K., J. Am. Chem. Soc. 2008, 130,
8834-8846.
11) Hishikawa, K., Nakagawa, H., Furuta, T., Fukuhara, K., Tsumoto, H., Suzuki, T., Miyata, N., J. Am.
10

Chem. Soc. 2009, 131, 7488-7489.
12) Glenewinkel-Meyer, T., Crim, F.F., J. Mol. Struct. (THEOCHEM) 1995, 337, 209-224.
Soc., 127, 11720-11726.
13) Nakagawa, H., Hishikawa, K., Eto, K., Ieda, N., Namikawa, T., Kamada, K., Suzuki, T., Miyata,
N., Nabekura, J., ACS Chem. Biol. 2013, 8, 2493-2500.
14) Ieda, N., Hotta, Y., Miyata, N., Kimura, K., Nakagawa, H., J. Am. Chem. Soc. 2014, 136,
7085-7091.
15) Kitamura, K., Kawaguchi, M., Ieda, N., Miyata N., Nakagawa, H., ACS Chem. Biol. 2016, 11,
1271—1278.
16) Peng, T., Yang, D., Org. Lett. 2010, 12, 4932—4935.
17) Ieda, N., Nakagawa, H., Peng, T., Yang, D., Suzuki, T., Miyata, N., J. Am. Chem. Soc., 2012, 134,
2563–2568.
18) Fukuto, J. M. et al., Antioxid. Redox Signal. 2011, 14, 1649-1657.
19) Rosenthal, J. et al., J. Am. Chem. Soc., 2010, 132, 5536–5537.
20) Kawai, K., Ieda, N., Aizawa, K., Suzuki, T., Miyata, N., Nakagawa, H., J. Am. Chem. Soc. 2013,
135, 12690-12696.
21) Matsuo, K., Nakagawa, H., Adachi, Y., Kameda, K., Tsumoto, H., Suzuki, T., Miyata, N., Chem.
Commun., 2010, 46, 3788-3790.
22) Zeng, B. B. et al., Bioorg. Med. Chem. Lett.,2004, 14, 5565–5568.
23) Matsuo, K., Nakagawa, H., Adachi, Y., Kameda, E., Aizawa, K., Tsumoto, H., Suzuki, T., Miyata,
N., Chem. Pharm. Bull., 2012, 60, 1055-1062.
11

糖尿病性神経障害の治癒をめざす TNF-αの分子標的療法
滋賀医科大学 生化学・分子生物学講座 再生・修復医学部門
小島 秀人
1.はじめに
糖尿病と慢性合併症は決して自然治癒することなく、進行性の経過を取る。
言い換えれば、高血糖が一旦出現すると「もとに戻れない」恐るべき病態がで
きあがるのである。糖尿病はどんどん増加し、今や壮年期以降の国民の3分の
1に達しようとしている。これまで、血糖コントロールや合併症の症状緩和を
目的とするさまざまな優れた薬物が開発されてきた。残念ながら、糖尿病の治
癒を実現できる治療法はどれひとつとしてない。糖尿病はどうして「もとに戻
れない」のか。理由は明らかである。糖尿病の原因が解明されてないからであ
る。我々はこの「もとに戻れない」原因究明を目的に研究を進めてきた。その
結果、「骨髄幹細胞が異常である」という誰もが予想していなかった結論を導き
得たのである。我々は糖尿病性神経障害に焦点を当て、特に TNF-αを標的とす
る全く新たな治療戦略を立て研究を行った。まだまだ治療法が見えてきたと言
える段階にないが、これまでの結果をまとめる。
2.神経障害の不思議な特徴
1)高血糖と慢性炎症の因果関係が不明
糖尿病神経障害は多発神経障害と単神経障害に分類される。このうち単神経
障害は非糖尿病でも出現し治癒することもあり糖尿病特異的とは言えない。こ
れに対し、多発神経障害は進行性で不可逆性を示す典型的な合併症である。こ
れまで、慢性炎症が持続する原因として、①神経組織の代謝異常、②栄養因子
の欠乏、③血流障害などが成因とされてきた。したがって、これらを取り除く
ことを目的に新規薬物が開発されてきたが、何れも神経障害を治癒させること
はできなかった。この事実は、高血糖により誘導される慢性炎症の標的は全く
異なった視点から考え直す必要性を示唆している。
2)障害は神経の支配領域に無関係
皮膚の知覚障害は糖尿病に特徴的な神経障害である。両側の上下肢末端から
12

生じ、やがて中枢へと広がる知覚鈍麻と不快なしびれ感は、異常を自覚する部
位が手袋や靴下をはいたような独特の分布を示す。糖尿病性神経障害のもっと
も特徴的な所見は、このように障害の範囲が解剖学的な特定の神経支配に従わ
ないところである。また、障害は末梢神経の種類に関係なく、感覚、自律、運
動のどの神経にも出現し、身体のどこにでも生じる。
3)進行性で不可逆性
一般的に、初期には足底部や手の指先の感覚障害のみであるが、糖尿病罹病
期間が長期になるにつれて障害はより強くなり範囲も拡大する。進行すると起
立性低血圧、発汗異常、下痢や便秘などの自律神経症状が出現する。さらに高
度になると下肢の筋力低下や筋萎縮も出現し、患者の QOL は著しく低下してく
る。一方、血糖コントロールや代謝改善は病勢のスピードを抑えるのが精一杯
で、機能改善には全く歯が立たない。つまり、血糖値や栄養因子などを改善さ
せる程度の生やさしい治療では太刀打ちできない最悪の“何か”が神経の生じ
ており、それが「元に戻れない」病態を作りだしていると考えるべきである。
これまでの常識に捕らわれない自由な発想が要求されている。
4)異常な遺伝子発現と染色体数
(1)プロインスリンの発現
筆者は遺伝子治療により肝臓内に膵島を新生させ、1型糖尿病の完治をめざ
す研究をしていた時、全く予想外の発見をすることになった。未治療糖尿病マ
ウスの肝臓において、遺伝子導入したマウスの比較対照としてインスリンタン
パク質を染色したところ、発現するはずのないインスリンタンパク質を偶然見
いだした。この所見は非糖尿病では全く見られず、糖尿病マウスでは肝臓だけ
でなく脂肪組織や骨髄に発現していた 1, 2)。糖尿病を発症していないマウスでは
インスリンタンパク質は膵臓と胸腺のみで発現している。膵臓のインスリンは
血糖値の調節など主として代謝上の役割を持ち、胸腺からのインスリンはイン
スリンに対し自己組織と反応する T 細胞除去のための negative selection に役
割を持つ。しかし、肝臓や脂肪組織などからインスリンが産生され、何かの役
割を持ちうるなどという現象は、どこにもの記載が存在しなかったのである 3)。
しかも、インスリンはインスリンでも産生される蛋白質の主体は未熟なプロイ
ンスリンであり、血糖を下げる働きなど全く持たず、とても合目的であるとは
13

言えないものであった。
(2)TNF-αの発現
様々な臓器内でのプロインス
リンの発現状態を糖尿病と非糖
尿病で比較して調べてみた。そ
の結果、非糖尿病では膵臓と胸
腺以外の臓器では発現が見られ
なかったが、糖尿病では末梢神
経組織 4)、肝臓 5)、脂肪組織 2)、
骨髄 2)、膵外分泌組織 2)で発現し
ていた(図1)。さらに、インリ
ン以外にグルカゴンやソマトス
タチン、PP など他の膵ホルモン
の mRNA も少なからず観察さ
れた 2)。驚いたことに、プロイ
ンスリンを発現している臓器で
は同時に強力な炎症性サイトカ
インである TNF-αの発現が見
られた 4, 5)。TNF-αと糖尿病な
らびに合併症との関連は1型、2型ともに様々な報告がある 6)。膵ホルモンの発
現は、膵以外の臓器の機能に対し何か意味があるものかもしれないが、TNF-α
の発現は糖尿病状態の改善とは真逆に働くものである。インスリン感受性を悪
化させ、炎症反応を作り出す本体である。糖尿病マウスの脊髄後根神経節(dorsal
root ganglia: DRG)においてもプロインスリンの発現と同時に TNF-αの発現を
見いだしたことから、神経障害の標的以外の何物でもないと考えた 4)。
3)染色体数が増加
DRG 神経細胞を分離培養して観察したところ、2核以上の複数の核を持つ細
胞にプロインスリンの発現が観察されたことから、プロインスリンの陽性の有
無と染色体数(ploidy volume)の変化の関連を検討した。非糖尿病マウスから得
られた神経細胞では 99.1%の細胞が 2n で残りの 0.9%はすべて 4n であった。一
14

方、糖尿病マウスの神経
細胞では 2nは 86.6%で、
4n 以上が 13.4%であっ
た。内訳は 4nが 12.5%、
6n が 0.7%、8n が 0.2%
であった。また、4n 以
上を示した細胞の実に
97%がプロインスリン
に陽性を示した(図2)。
さらに、プロインスリンが陽性の細胞はほとんどが TNF-αも陽性であった 4)。
4)神経線維からもプロインスリン
糖尿病マウスではでは DRG 神経細胞と同様に坐骨神経など神経線維内でも
プロインスリンと TNF-αの両者がともに発現していた。さらに、in situ
hybridization による検討から、糖尿病の神経線維内では両者の mRNA 発現も
観察された。また、これらの所見が見られるところでは同時に神経線維の形態
異常も観察された 4)。
糖尿病で見られた ploidy volume の増加の原因として、糖尿病状態では末梢
神経の細胞増殖が亢進したのか、あるいは神経組織に別の細胞が細胞融合した
かのどちらかである。末梢神経細胞がどんどん成長個体で盛んに増殖するとは
考えにくいことから後者の
可能性が高い。実際に骨髄
内にはインスリン遺伝子や
Tnf-α遺伝子を発現する細
胞が存在している。したが
って、この細胞が骨髄から
神経組織内へと遊走し、神
経細胞や神経線維に融合し
た可能性は十分考えられる
(図3)。ただし、正常でも
骨髄由来の細胞が末梢の細
胞と融合することは知られ
15

ている。しかし、その頻度は桁違いに小さく、糖尿病におけるこの様な高い頻
度ではない 4, 7)。糖尿病の細胞融合は明らかに異常である。
3.「元に戻れない」原因は異常な細胞融合
1)異常な細胞融合
非糖尿病マウスでは観察されなかったが、糖尿病ではプロインスリンあるい
は TNF-αが染色される神経細胞は汎骨髄細胞マーカーである CD45 が陽性と
なった 4)。神経細胞自身が自ら CD45 を発現するとは考えにくいことから、神
経細胞と融合したのは骨髄由来の細胞である。これは病態生理学の常識を確実
にひっくり返す現象である。
骨髄移植モデル
を使用してさらに
細胞融合を検討し
た。レシピエント
ならびに骨髄ドナ
ーの両者にお互い
に異なる遺伝マー
カーを組み込んで
おき、両者のマー
カーが同じ神経細
胞内で発現するど
うかを検討したと
ころ、糖尿病では細胞融合が起こることが明らかとなった(図4)。また、融合
した神経細胞内でのみ TNF-αが発現し、癒合していない神経細胞からは発現が
なかった(図4)。Tnf-α遺伝子は骨髄の細胞から持ち込まれたのである。
2)骨髄内にある幹細胞の異常
骨髄内におけるインスリンと Tnf-α遺伝子の発現を糖尿病マウスと非糖尿病
マウスで RT-PCR で比較した。糖尿病でも非糖尿病でもインスリンならびに
Tnf-α遺伝子の発現が認められた。骨髄内における Tnf-α遺伝子の発現は予想
されたが、インスリン遺伝子の発現は驚きであった。しかも非糖尿病マウスで
mRNA が発現しているなどとは考えてもみなかった。胸腺での自己免疫調節機
16

能と関係するものかもしれないが、糖尿病マウスの骨髄では非糖尿病と比較し
て両者とも明らかに発現が増加していた。しかし、実際にプロインスリンと
TNF-αについて骨髄細胞を染色してみると染色されるのは糖尿病マウスのみ
で、非糖尿病では全く染色されず、タンパク質としては発現していなかった 8)。
糖尿病でのみタンパク質発現の異常を認めたことから、非糖尿病と比較しな
がら細胞の系譜をたどってみた。非糖尿病マウスでは、骨髄幹細胞分画である
KSL 分画(c-Kit+/Sca-1+/ Lineage-)において、両者とも mRNA 発現が観察さ
れなかった。しか
し、糖尿病では両
者ともKSL分画で
発現していた(図
5)。糖尿病の幹細
胞は integrityを失
っていたのである
8)。このことは、幹
細胞は進むべき分
化の方向が制限さ
れ、保持した異常
が子孫のすべての
細胞へと引き継が
れることを意味する。すなわちニッチへと逃げ込んだがん幹細胞のように、治
療抵抗性を獲得し「糖尿病幹細胞」が作られたのである。
3)幹細胞内に作られた記憶
インスリンと Tnf-αの遺伝子の異常な発現プログラムが作られていたのは糖
尿病の骨髄幹細胞の中である。もしそれを非糖尿病マウスに移植したらどうな
るだろうか。糖尿病の骨髄幹細胞移植により神経障害が正常マウスで再現でき
ないかと考えた。ドナーである糖尿病マウスの骨髄をレシピエントとなる放射
線照射した非糖尿病マウスに骨髄移植し、およそ3ヶ月たった後に移植された
非糖尿病レシピエントの DRG を観察した。予想どおり、神経細胞における骨髄
細胞との細胞融合が観察され、神経伝導速度の低下が認められた。なんと、骨
髄移植で非糖尿病マウスに糖尿病性神経障害が発症したのである 8)。このことか
17

ら、移植されたマウスの血糖値は正常であり、神経障害はレシピエントの血糖
値とは独立したものであると結論づけられた。これこそが、血糖値コントロー
ルによっても神経障害は決して良くならず、もう「もとには戻れない」原因だ
ったのである。神経障害の犯人はニッチに守られた異常な骨髄幹細胞であった。
4)Stem cell disease という概念
がんでは治療抵抗性の原因としてがん幹細胞の存在が示唆されている。糖尿
病ならびに糖尿病合併症も全く同様であると仮説を立てると、「もとに戻れない」
病態の説明が可能となる。我々の研究以外にも細小血管合併症である糖尿病網
膜症に関して興味深い報告がなされている。糖尿病では酸化ストレスなどによ
り網膜の毛細血管が傷害され脱落し、血管内皮前駆細胞から新たに多くの毛細
血管が作られる。その際、糖尿病では再生血管の内径が著しく細くて赤血球が
通過できないものがある。そのような血管では血流が途絶し網膜の虚血が生じ、
網膜症が進行するというのである 9)。一方、糖尿病では骨髄内に侵入する神経も
糖尿病のために神経障害を発症しており、骨髄内の幹細胞の分化誘導をうまく
調節できなくなっているという。幹細胞から分化し、血管内へと遊離した内皮
前駆細胞も分化異常が生じており、網膜に到達してもそこで正常な毛細血管を
形成することができず、異常に細い毛細血管が出来るのだという 9)。神経障害が、
骨髄幹細胞ニッチでの調節異常を生じている可能性があることから、悪循環の
ループが成立している。このループの正常化こそが治療につながる。
4.TNF-αを標的とするアプローチ
1)抗 TNF-α抗体を用いた神経細胞のリセット
神経障害の発症には融合細胞で発現する TNF-αが重要な役割を持つ可能性
が高い。そこで、TNF-αの抑制を目的に慢性関節リウマチの治療薬として開発
された分子標的薬インフリキシマブを糖尿病マウスに投与した。インフリキシ
マブは TNF-αに特異的に接着し、その働きを抑えるモノクローナル抗体である。
わずか一回の投与で神経伝導速度が正常化した 10)。
TNF-αは膜結合型蛋白質として作られ、TNF-α切断酵素により切断されて
可溶型 TNF が遊離し、離れた細胞の受容体に結合して作用する。従って、イン
フリキシマブの作用はこの遊離 TNF-αを抑えて作用を示したものである。さら
に、膜型 TNF も近くに TNF-α受容体を発現している細胞があるとそこに結合
18

し , TNF- α 発 現 細 胞 内 に
reverse signal が伝達される。
TNF-α抗体はこの膜型 TNF 発
現細胞に結合し、細胞内ドメイ
ンにあるセリン残基のリン酸化
を介してこの細胞に対し細胞の
アポトーシスを誘導したり、細
胞の炎症惹起作用を抑制したり
すると考えられている 11)。実際、
我々の研究で、インフリキシマ
ブは DRG 組織における Tnf-α
をはじめとする様々な炎症性サ
イトカインの mRNA 発現をほ
ぼ抑制した(図6)10)。慢性関
節リウマチやクローン病と同様
に糖尿病神経障害の治療薬とし
て応用できる可能性がある。た
だし、高血糖が持続する限り、
骨髄内の幹細胞から分化した細胞がまた遊走してきて,神経細胞に細胞融合し、
神経障害は再燃する可能性がある。
2)骨髄の TNF-αの発現を抑制し神経障害を抑える
神経内や血液中へと遊走した異常細胞に対しては抗 TNF-α抗体製剤が有用
であるが、骨髄中でニッチ内に隠れ込んだ異常幹細胞に対しては十分な効果を
期待できない。そこで、骨髄内で TNF-αの発現を遺伝的に抑えるモデルを作成
したところ糖尿病にしても神経障害の発症が完全に抑制された 12)。このモデル
では同時に骨髄内のインスリン陽性細胞も消失した。さらに、骨髄内で TNF-
αを発現するプロインスリン陽性細胞を標的として遺伝子改変モデルを用いて
特異的に消失させたところ、高血糖が存在しても神経障害が発症しなかった 13)。
3)神経障害の治癒をめざす戦略
以上の研究結果から、細胞融合を仕掛ける異常な細胞を生み出す骨髄幹細胞
19

をなくすことは、「もとに戻れない」病態をもとに戻すための方法のひとつであ
ると結論づけられる。したがって、この方法を用いて糖尿病性神経障害を治癒
させるには、異常細胞を生み出す高血糖の正常化と同時に、骨髄内のニッチに
隠れ込んだ「糖尿病幹細胞」を根絶しなくてはならない。まさにがん治療と同
じ戦略が必要となる。国民の3分の1にも達しようとしている患者のすべてに、
化学療法と同時に骨髄幹細胞移植をするのは現実離れしている。この講演では
もっと現実的な方法として、標的化ベクターを作成して、異常幹細胞だけを根
絶するためのストラテジー14)について述べて責務を果たしたい。
5.おわりに
糖尿病性神経障害を治癒させる方法は糖尿病そのものに対して、完全な治癒
を導く方法に他ならない。この研究はモデル動物を使った実験で、糖尿病患者
さんにおける臨床研究ではない。今後、糖尿病克服を夢見て、患者さんについ
ての研究で確証を得て、安全で確実な治療法を開発してゆきたい。
謝辞
ベイラー医科大学の Lawrence Chan 教授をはじめとする共同研究者の方々
に深謝いたします。また、本研究の一部は公益財団法人篷庵社の研究助成によ
るものであり、厚く御礼申し上げます。また、御推薦して下さいました宮崎瑞
夫先生、岩尾洋先生、岡村富夫先生に深謝いたします。
参考文献
1) Kojima H, et al: NeuroD-betacellulin gene therapy induces islet
neogenesis in the liver and reverses diabetes in mice. Nat Med 9: 596-603,
2003
2) Kojima H, et al: Extrapancreatic insulin-producing cells in multiple
organs in diabetes. Proc Natl Acad Sci U S A 101: 2458-2463, 2004
3) Kojima H, et al: Extrapancreatic proinsulin/insulin-expressing cells in
diabetes mellitus: is history repeating itself? Endocr J 53: 715-722, 2006
4) Terashima T, et al: The fusion of bone-marrow-derived
proinsulin-expressing cells with nerve cells underlies diabetic
neuropathy. Proc Natl Acad Sci U S A. 2005 Aug 30;102(35):12525-30.
Epub 2005 Aug 22.
20

5) Fujimiya M, et al: Fusion of proinsulin-producing bone marrow-derived
cells with hepatocytes in diabetes. Proc Natl Acad Sci U S A102:
12525-12530, 2005
6) Flyvbjerg A, et al: Diabetic angiopathy, the complement system and the
tumor necrosis factor superfamily. Nat Rev Endocrinol 6: 94-101, 2009
7) Oren-Suissa M and Podbilewicz B: Evolution of Programmed Cell
Fusion: Common Mechanisms and Distinct Functions. Dev Dyn239:
1515-1528, 2010
8) Katagi M et al: Hyperglycemia induces abnormal gene expression in
hematopoietic stem cells and their progeny in diabetic neuropathy. FEBS
Lett 588: 1080-1086, 2014
9) Yellowlees Douglas J, et al: Bone marrow-CNS connections: implications
in the pathogenesis of diabetic retinopathy. Prog Retin Eye Res 31:
481-494, 2012
10) Yamakawa I, et al: Inactivation of TNF-α ameliorates diabetic
neuropathy in mice. Am J Physiol Endocrinol Metab 301: E844-E852,
2011
11) Horiuch T, et al: Transmembrane TNF-a: structure, function and
interaction with anti-TNF agents. Rheumatology 49: 1215–1228, 2010
12) Urabe H, et al: Bone marrow-derived TNF-α causes diabetic neuropathy
in mice. Diabetologia 58: 402-410, 2015
13) Urabe H, et al: Ablation of a small subpopulation of diabetes-specific
bone marrow-derived cells in mice protects against diabetic neuropathy.
Am J Physiol Endocrinol Metab 310: E269-E275, 2015 Dec 22.Marpadga
A, et al: Epigenetic mechanisms in diabetic complications and metabolic
memory. Diabetologia 58: 443-455, 2015
14) Zhao L, et al: Polyglycerol-functionalized nanodiamond as a platform for
gene delivery: Derivatization, characterization, and hybridization with
DNA. Beilstein J Org Chem 10: 707-713, 2014
21

酸化コレステロール secosterol の⽣物活性機構解析 静岡県⽴⼤学 ⾷品栄養科学部
⼤学院薬⾷⽣命科学総合学府 三好規之
はじめに 生体膜や血漿リポタンパク質の外層の必須構成成分であるコレステロールは、ホルモンや胆汁酸など
のステロイド化合物の前駆体としても利用され、様々な生体調節機能を担っている。一方、病理的過程の
コレステロールの主たる役割は、脳、冠動脈および末梢血管の病気を引き起こす重要な動脈硬化発症因
子として疑われている。コレステロールは酵素的酸化反応あるいは自動酸化反応(ラジカル反応・非ラジ
カル反応)によって酸化修飾を受け、現在までに 100 種類以上の同定されている様々な酸化コレステロー
ルを生成する。脂質ペルオキシラジカルによって生成する 5,6-epoxycholesterol や 3O2 によって生成する
7-hydroperoxycholesterol、7-ketocholesterol など自動酸化によって生成する酸化コレステロールのいくつ
かは、糖尿病患者の腎、心、肝や、ヒト動脈硬化プラーク、酸化LDL中で増加することが報告されており、
炎症性疾患への関与が強く示唆されている分子群である。一方、ヒト動脈硬化プラークやアルツハイマー
およびパーキンソン病患者脳剖検等から、非常に強力な酸化力を有する活性酸素種の一つであるオゾ
ンとコレステロールの反応物である 3β-hydroxy-5-oxo-5,6-secocholestane-6-al (secosterol-A) と、それがア
ルドール反応で転換した 3β-hydroxy-5β-hydroxy-B-nor-cholestane-6β-carboxaldehyde (secosterol-B) が
検出された(1)。Secosterol-A および-B は、化学的に特徴的な官能基(アルデヒド基およびケト基)を有し
ており(図 1)、生体成分との相互作用により動脈硬化部位におけるプラーク形成や(1)、アミロイド β や α-
シヌクレインなどタンパク質と反応して凝集、異常折りたたみや線維化を引き起こすことが報告されており
(2, 3)、活性酸素・窒素種が中心的な役割を果たすと考えられている炎症関連病変への関与が強く疑わ
れている。
そこで本研究では、生体内で生成した secosterol 類による疾病への関与およびそのメカニズムを明らか
にする目的で、まず、(1) LC-MS/MS を用いた secosterol 高感度定量分析法の開発を行い、確立した分
析法を用いて (2) 生体試料に含まれる secosterol の定量分析を行った。さらに、この分析法を応用し、
(3) 生体試料から secosterol 構造類似体の新規検出・同定を行い、(4) 生体内での secosterol 生成メカニ
ズムの解析を行った。以上の知見を踏まえ、(5) secosterol の生物活性試験を行い、炎症関連疾患におけ
るの病理的役割について詳細に検討した。
図 1. コレステロールおよび secosterol の化学構造
Secosterol-BCholesterol Secosterol-A
22

1. LC-MS/MS を⽤いた secosterol 定量分析法の開発
生体内で微量に生成するsecosterolを高感度に且つ高精度に定量解析し、secosterol生成機構解析や
生物活性試験へ有益な情報とする目的で、LC-ESI-MS/MSを用いたsecosterol分析法の開発を行った。
まず、検出の高感度化を目的として、誘導体化試薬を検討した。図2が示すように、未標識のsecosterol-A
あるいはsecosterol-BのLC-MS/MS分析での検出限界は、20 fmol、アルデヒド化合物の誘導体化試薬と
し て 汎 用 さ れ て い る dinitrophenylhydrazine (DNPH) で 標 識 し た secosterol-A-DNPH あ る い は
secosterol-B-DNPHの検出限界は10 fmol であった。しかし、蛍光標識試薬の一つであるdansyl
hydrazine (DNSL) で標識したsecosterolの検出限界は、secosterol-A-DNSLあるいはsecosterol-B-DNSL
が1 fmol であり、さらに共同研究者の東(東京理科大学)が開発した2-hydrazino-1-methylpyridine
(HMP) を調製し、secosterol-Aおよびsecosterol-B誘導体のLC-ESI-MS/MS分析へ応用した結果、検出
限界はsecosterol-A-HMPおよびsecosterol-B-HMPでそれぞれ0.05、0.01 fmol であり、これまでのDNSL
誘導体化法に比べ~100倍高感度に分析することが可能となった。このことは、海外の研究グループが
secosterol 高感度分析で採用している誘導体試薬である1-pyrenebutyric hydrazine (PBH; LOD = 10
fmol)、Girard P hydrazine (GP; LOD = 2.7 fmol) と比較してもsecosterol 高感度分析における優位性を
示 し て い る 。 我 々 は さ ら に 、 安 定 同 位 体 標 識 し た 内 部 標 準 物 質 (3,4-13C-secosterol-A お よ び
図 2. 誘導体化法による secosterol ⾼感度分析の典型的なクロマトグラム(4)
Secostero 標準品を未標識あるいは各誘導体化後、LC-MS/MS 分析を⾏った。
23

3,4-13C-secosterol-B)
を調製し内部標準法に
よる高精度、再現性の
高い定量法を確立した
(図3)。本分析法を用
いたマウス血漿分析で
は回収率96.3~104.5%、
変 動 係 数 ( CV 値 ) は
0.6~8.2%であり、ヒト血
漿やマウス臓器(脳、肝
臓 、 肺 ) に 存 在 す る
secosterol-A お よ び
secosterol-Bを同様の感
度、精度で分析できるこ
とを確認した(4)。
2. ⽣体試料に含まれる secosterol の定量分析
確立した以上の分析法を用いて、様々な生体試料中の secosterol について定量解析を行った結果と、
過去の secosterol 分析に関する報告をまとめたものを表 1 に示す。生体試料から secosterol 検出の最初
の 報 告 は 、 HPLC-UV 検 出 器 を 用 い て 、 オ ゾ ン 曝 露 ラ ッ ト 肺 か ら secosterol-A-DNPH お よ び
secosterol-B-DNPH が検出されている(5)。Griffiths らの研究グループは GP 誘導体化法により、正常ラッ
トの脳から secosterol-A(~100 pg/mg)および secosterol-B(~300 pg/mg)が検出されることを報告している
(6)。ヒト脳においても secosterol (secosterol-A + secosterol-B)が、アルツハイマー病患者で 0.44
pmol/mg (n = 4)、対照群で 0.35 pg/mg (n = 7)で検出されている(7)。また、対照群に比べて、高いレベル
の secosterol (secosterol-A + secosterol-B)が、Lewy 小体型認知症患者の大脳皮質で検出されている
(3)。一方で、Wentoworth らは、ヒト動脈硬化プラークから 6.8-61.3 pmol/mg の secosterolを検出しており、
対照群に比べて動脈硬化症患者の血漿で secosterol-B が高値(70-1690 nM)を示すことも報告した(1)。
我々は、上述した安定同位体標識した内部標準物質を用いた高感度定量法により、健常人血漿、マウス
血漿、各主要臓器に存在する secosterol-A および secosterol-B の定量し、secosterol は生体内で非病理
的条件化においても構成的に生成され、検出されることを明らかにした(4)。
3. ⽣体試料から構造類似体の新規検出・同定
生体内においてコレステロールは3位にOH基を有する遊離型と、3位にOH基脂肪酸が結合したエステ
ル型コレステロールが存在しており、特に血中に存在するLDL分子などには多量のエステル型コレステロ
図 3. ⾎漿、脳サンプルを⽤いた secosterol の定量分析(4)
マウス⾎漿および脳サンプルより脂溶性画分を調製し、HMP 誘導体化後、LC-MS/MS 分析を⾏った。
0
100
50
25
75
Re
lati
ve a
bu
nd
an
ce
(%
)
0
100
50
25
75
0
100
50
25
75
100
50
25
75
Plasma Plasma
Brain Brain
Secosterol-A-HMP
Secosterol-B-HMP
Secosterol-A-HMP
Secosterol-B-HMP
3,4-13C-Secosterol-B-HMP
3,4-13C-Secosterol-A-HMP
3,4-13C-Secosterol-B-HMP
3,4-13C-Secosterol-A-HMP
m/z 524.0→109.1
m/z 524.0→109.1
m/z 526.0→109.1
m/z 526.0→109.1
24

表
1.
⽣体
試料
に含
まれ
るse
cost
erol
-Aお
よび
seco
ster
ol-B
の定
量解
析
Tis
sues
/flu
ids
Spec
ies
For
ms
Equ
ipm
ents
C
once
ntra
tion
s N
R
ef.
Lun
g R
at (
SD
) ex
pose
d to
O3
Sec
o-A
-DN
PH
H
PL
C-U
V
ND
5 S
eco-
B-D
NP
H
ND
Ath
eros
cler
otic
pla
que
Hum
an
Sec
o-A
-DN
PH
H
PL
C-U
V, L
C-M
S
6.8
– 61
.3 p
mol
/mg
n=11
1 P
lasm
a H
uman
(at
hero
scle
roti
c pa
tien
ts)
Sec
o-B
-DN
PH
70
– 1
690
nM
n=8
Bra
in
Hum
an (
Alz
heim
er p
atie
nts)
S
eco-
A-D
NP
H+
Sec
o-B
-DN
PH
H
PL
C-U
V, L
C-M
S
0.44
pm
ol/m
g n=
4 7
Hum
an (
cont
rol)
S
eco-
A-D
NP
H+
Sec
o-B
-DN
PH
0.
35 p
mol
/mg
n=7
Bra
in
Hum
an (
Lew
y bo
dy d
emen
tia)
S
eco-
A-D
NS
L+
Sec
o-B
-DN
SL
H
PL
C-f
luor
esce
nce
dete
ctor
0.
21 µ
M
n=15
3 H
uman
‘ag
e-m
atch
ed c
ontr
ol)
Sec
o-A
-DN
SL
+S
eco-
B-D
NS
L
0.09
µM
n=
18
Bra
in
Rat
S
eco-
A-G
P
LC
-MS
~100
pg/
mg
6 S
eco-
B-G
P
~300
pg/
mg
Hum
an
Sec
o-A
-GP
+ S
eco-
B-G
P
150
pg/m
g
Pla
sma
Mou
se (
C57
BL
/6J)
S
eco-
A-D
NS
L
LC
-MS
/MS
wit
h IS
(13
C-s
ec-A
+ 13
C-s
ec-B
)
0.5±
0.2
nM
n=8
10
Sec
o-B
-DN
SL
1.
1±0.
3 nM
n=
8
Mou
se (
C57
BL
/6J
MP
O-K
O)
Sec
o-A
-DN
SL
0.
03±0
.1 n
M
n=7
Sec
o-B
-DN
SL
0.
5±0.
4 nM
n=
7
Liv
er
Mou
se (
C57
BL
/6J)
S
eco-
B-D
NS
L
126.
0±42
.7 p
mol
/g
n=8
Mou
se (
C57
BL
/6J
MP
O-K
O)
Sec
o-B
-DN
SL
62
.2±2
1.6
pmol
/g
n=7
Pla
sma
Hum
an (
heal
thy
volu
ntee
rs)
Sec
o-A
-HM
P
LC
-MS
/MS
wit
h IS
(13
C-s
ec-A
+ 13
C-s
ec-B
)
23.6
±16.
6 nM
n=
10
4
Sec
o-B
-HM
P
27.3
±41.
0 nM
n=
10
Mou
se (
C57
BL
/6J)
Sec
o-A
-HM
P
1.4±
0.7
nM
n=3
Sec
o-B
-HM
P
4.3±
0.8
nM
n=3
Bra
in
Sec
o-A
-HM
P
10.4
±16.
3 nM
n=
3
Sec
o-B
-HM
P
110.
9±10
.6 n
M
n=3
Liv
er
Sec
o-A
-HM
P
34.1
±21.
6 nM
n=
3
Sec
o-B
-HM
P
161.
5±56
.3 n
M
n=3
Lun
g S
eco-
A-H
MP
29
.1±1
.3 n
M
n=3
Sec
o-B
-HM
P
80.4
±1.4
nM
n=
3
25

ールが含まれている。しかしながら、これまでに生体試料からエステル型secosterolを検出した報告は無い。
そこで、まずエステル型コレステロールのin vitroオゾン酸化によるエステル型secosterolの生成について
検討した。飽和脂肪酸であるパルミチン酸が結合したcholesteryl palmitate(C16:0-CE)を試験管内オゾン
酸化させたところ、secosterol-Aにパルミチン酸が結合したsecosterol-A palmitateおよびアルドール化によ
るsecosterol-B palmitateの生成が認められた。一方、不飽和脂肪酸であるオレイン酸あるいはリノール酸
が結合したcholesteryl oleate(C18:1-CE)およびcholesteryl linoleate(C18:2-CE)の試験管内オゾン酸化で
は、9-oxononanoyl cholesterol(9-ONC)が一次生成物として生成され、9-ONCがさらにオゾン酸化され
9-oxononanoyl secosterol-A ( 9-ON-secoA ) お よ び ア ル ド ー ル 化 に よ る 9-oxononanoyl secosterol-B
(9-ON-secoB)の生成が認められた(図4)。これらのオゾン酸化コレステロールエステルの標準品を調製
(精製)し、dansyl hydrazine誘導体化によるLC-ESI-MS/MSを用いた分析法を確立した(図5)。本分析法
を健常人血清から調製したLDLの分析に応用したところ、全てのサンプル(n=6)から9-ONC(182.7±75.8
図 4. エステル型 secosterol の化学構造式
図 5. ヒト LDL 画分に含まれるエステル型 secosterol の検出(8)
ヒト⾎液由来 LDL 画分から脂溶性画分を調製し、DNSL 誘導体化後、LC-MS/MS 分析を⾏った。
9-ON-secoB9-ON-secoA
2x10
1
2
3
4
secosterol-A-DNSL
secosterol-B-DNSL
1x10
5
5.5
6
6.5
7
7.5
9-ONC-DNSL
9-ON-seco-B-bisDNSL9-ON-seco-A
-bisDNSL
1x10
4.55
4.6
4.65
4.7
4.75
(min)21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59
m/z 788.2>369.2
m/z 666.4>630.4
m/z 534.5>630.2
26

pmol/mg LDL protein ) お よ び 9-ON-secoA ( 16.5±5.4 pmol/mg LDL protein ) 、 9-ON-secoB
(11.3±3.9pmol/mg LDL protein)が検出され、生体試料における9-ON-secoA、9-ON-secoBの検出を初め
て報告した(8)。
4. ⽣成メカニズム
既に我々は、コレステロールと一重項酸素との試験管内反応で、secosterol-A と secosterol-B のうち
secosterol-B が優先的に産生されること、またコレステロールを myeroperoxidase (MPO)/CL-/H2O2 システ
ムを用いた緩衝液中の試験管内反応で酸化させることで、secosterol-Aおよび secosterol-Bが同程度の比
率で生成することを見出している(9)。そこで、より生体内に近い反応条件で secosterol 生成メカニズムを
検討するために、調製した secosterol-A あるいは secosterol-B 標準品を RPMI1640 培地あるいは 10%ウ
シ血清(FBS)を含む RPMI1640 培地へ添加し、バイオマトリックス中での化学的安定性を検討した。その
結果、1) secosterol-A は培地添加後数秒のうちに secosterol-B へ変換される、2) またこの変換は血清中
の何らかの成分によって強く促進される、3) 培地中では secosterol-B から secosterol-A への変換は生じな
い、4) secosterol-A および secosterol-B は培地中でそれぞれ 3β-hydroxy-5-oxo-secocholestan-6-oic acid
(secoA-COOH)、3β-hydroxy-5β-hydroxy-B-norcholestane-6-oic acid(secoB-COOH)へと酸化されること
などを明らかにした(図 6)。さらに、好中球様に分化させた HL-60 細胞(nHL-60)を活性化剤で刺激する
ことで活性酸素種が生成し、培地中のコレステロールが酸化され secosterol-A が産生する、さらに FBS の
存 在 下 で は 、 産 生 し た
secosterol-A が 速 や か に
secosterol-B に変換された。
同様に、nHL-60 細胞を用い
た secosterol 産生系で、各種
阻害剤、補足剤を用いた
secosterol 産生メカニズムの
検 討 を 行 っ た と こ ろ 、
NADPH oxidase の活性化
や MPO の関与、一重項酸
素やオゾンの影響などが示
唆 さ れ た 。 さ ら に 、
C57BL/6J_WT マウスへのエ
ンドトキシン(LPS)投与によ
る急性炎症モデルでは、血
中 secosterol-A お よ び
secosterol-B 濃度は LPS 投
与後 22 時間まで時間依存
的に上昇した(図 7)。一方
図 6. 培養液中での secosterol 安定性の検討(10)
標準品 secosterol-A(上段)あるいは secosterol-B(下段)を無⾎清培地(左側)あるいは⾎清いり培地に添加し、⼀定時間インキュベート後の培地に含まれる化合物の分析を⾏った。
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturatedsecosterol‐B
Secosetrols(nM)
Serum Free RPMI
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
10%FBS/RPMI
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosterol‐A
Secosterol‐B
Seco‐A‐COOH
Seco‐B‐COOH
α,β‐unsaturated secosterol‐B
0
20
40
60
80
100
120
0 10s 0.25 0.5 1 2 3
Secosetrols(nM)
Time after incubation (h) Time after incubation (h)
Time after incubation (h) Time after incubation (h)
Serum Free RPMI 10%FBS/RPMI
27

で、C57BL/6J_MPO-KO マ
ウスでは、LPS 投与 0 時間(t
= 0)における secosterol-A は
検出限界以下、secosterol-B
は 0.5 nM と WT の半値であ
り、LPS 投与による血中濃度
の上昇は認められなかった
(10)。これらの結果より、生
体内において好中球活性化
によって生成されるオゾン様
活性酸素種や一重項酸素と
コレステロールの反応よる生体内 secosterol 類生成機構が示唆された(図 8)。
図 8. ⽣体内における secosterol ⽣成の予想スキーム(10)
Cholesterol
Secosterol-A Secosterol-B
5α-OOH cholesterolWentworth P. Jr, et al.,Science (2003)
1O2H2O
Trp, Met, His
NADPH oxidaseXanthine oxidase O2
-· H2O2 HOCl
1O2H2O2, O3IgG
MPO
Seco-A-COOH Seco-B-COOH α,β-UnsaturatedSecosterol-B
図 7. 急性炎症刺激による secosterol ⽣成(10) C57BL/6J WT と MPO-/-マウスへ LPS 投与し、⾎中 secosterol を定量した。
0.0
1.0
2.0
3.0
0 6 12 18 24
WT
MPO‐/‐
0.0
1.0
2.0
3.0
0 6 12 18 24
WT
MPO‐/‐
0.0
1.0
2.0
3.0
0 6 12 18 24
WT
MPO‐/‐
0.0
1.0
2.0
3.0
0 6 12 18 24
WT
MPO‐/‐
Sec
ost
ero
l-A
(n
M)
Sec
ost
ero
l-B
(n
M)
Time after ip LPS injection (h) Time after ip LPS injection (h)
Secosterol-A (nM) Secosterol-B (nM)
Statistically significant: * P < 0.05, ** P < 0.01 compared with the levels detected in untreated mice.
**
***
28

5. ⽣物活性試験 まずsecosterol類の細胞毒性を精査する目的で、secosterol-AおよびB、細胞毒性を有する酸
化 コ レ ス テ ロ ー ル で あ る 5β,6β-epoxycholesterol ( 5β,6β-epoxyCh ) 、 7β-hydroxycholesterol
(7β-OHCh)、7-ketocholesterol(7-KCh)、25-hydroxycholesterol(25-OHCh)さらに未酸化のコ
レステロールをヒト骨髄性白血病由来HL-60細胞に曝露したところ、secosterol-AおよびBが最も
強い細胞毒性を示した(図 9)。HL-60細胞に対するsecosterol類の細胞毒性は曝露後 72時間
まで時間依存的であったが、他の酸化コレステロールによる細胞毒性は曝露 24時間以降の時
間 依 存 性 は認 められなかった。Secosterol-AおよびBの細 胞 毒 性 は、ラット褐 色 種 由 来 細 胞
PC-12、ヒト血管内皮様細胞EA.hy926、ヒト肺がん細胞A549などにおいても認められた。さらに、
secosterol-AおよびBの構造類似体である6位にカルボキシル基を有する secoA-COOHおよび
secoB-COOH や 、 6 位 に ヒ ド ロ キ シ 基 を 有 す る 3β-hydroxy-5-oxo-5,6-secocholestan-6-ol
( secoA-CH2OH ) お よ び 3β-hydroxy-5β-hydroxy-B-norcholestane-6-ol ( secoB-CH2OH ) が
HL-60細胞に対して強い細胞毒性(EC50=数µM)を示すことを初めて見出した(11)。
一方、secosterol類はapolipoprotein C-IIやβ-amyloid、α-synuclein、ミエリン塩基性タンパク
質 などの凝集 や繊維化を引き起こすことが報告 せれており、神経 変性 疾患 や動脈 硬化 発症 ・
進行への関与が強く疑われている。我々の予備的な検討からもsecosterol類はウシアルブミン等
をリン酸緩衝液中で不溶化させることを明らかにしている。そのため、secosterol類によって溶解
性 や構 造 的 に変 化 を受 けやすいタンパク質 をについて解 析 を行 った。ヒト骨 髄 性 白 血 病 由 来
HL-60細胞を超音波処 理し遠心により調製 した細胞抽出液 にsecosterol-AおよびBを添加し、
37ºC で 4 日 間 インキュベート後 遠 心 により可 溶 画 分 を除 去 した。不 溶 化 したペレットに SDS
sample bufferを加え溶解しSDS-PAGEに供した。Secosterol処理群で複数の特異的バンドが認
められ、そのうちの一つを質量分析によりankyrin repeat domain-containing protein 6(diversin)
であると同定した。DiversinはWntシグナル経路に抑制的に働くスイッチであることが報告されて
いることから、secosterol類はdiversinを不活化させることにより酸化ストレスに関連した発がんメカ
ニズムに関与している可能性が示唆された。
図 9. HL-60 細胞に対する酸化コレステロールの細胞毒性(11)
0
100
20
40
60
80
120
140
100101
Concentration (µM)
% of HL‐60 cells viability Cholesterol
25‐OH Chol.
7K Chol.
7β‐OH Chol.
5β6β‐epoxy Chol.Secosterol‐A
Secosterol‐B
24 h incubation
100101
Concentration (µM)
48 h incubation
100101
Concentration (µM)
72 h incubation
29

さらに、代表的な血管病である動脈硬化症のプラークや、アルツハイマー病やパーキンソン病
などの神経変性疾患脳からsecosterol類が高濃度に検出されていることから、secosterol類の炎
症関連疾患発症・進行に関わる分子メカニズムの解析を行う目的で、血管内皮機能調節や神
経伝達において重要な役割を果たす一酸化窒素(NO)の産生阻害効果を検討した。組換え体
NO合成酵素(rNOS)とsecosterol類を試験管内で反応させRI標識基質を用いたNOS活性測定
を行った結果、secosterol-Aは炎症反応などに関連の深い誘導型NOS(iNOS)に対しては顕著
な阻害効果を示さなかったが(IC50>100 µM)、血管内皮型NOS(eNOS、IC50=50±5 µM)およ
び神経型NOS(nNOS、IC50=22±1 µM)に対して強い阻害効果を示した。さらに未酸化のコレス
テロールやsecosterol-B、他の酸化コレステロール(7-ketocholesterol、5β,6β-epoxycholesterol、
25-hydroxycholesterol)には顕著なNOS活性阻害効果は認められなかった(図 10)。今後培養
細胞や病態モデル動物を用いた詳細な解析が必要ではあるが、今回の結果よりsecosterol-Aは、
eNOSやnNOSの酵素活性阻害によるNO産生阻害を介し、炎症関連疾患病態の発症および進
展に関与していることが示唆された(12)。
おわりに 以上の結果より、secosterol-A、Bおよび本研究で初めて生体試料より検出されたエステル型
secosterolを含む構造類似体は生体傷害性など病態を促進させる活性を示すことが強く示唆さ
れた。今後、secosterol類が示す様々な生理活性の詳細な分子機構解析や病理検体における
定量解析を行い、酸化ストレスに関連する慢性炎症疾患の病態診断・予防戦略、新薬開発や
リスク評価の指標としての応用が期待される(13, 14)。
謝辞
以上は、当研究室の伴野勧博士、賴盈伶博士、岩崎希修士を並びに多くの共同研究者の協力により
図 10. Secosterol-A による神経型および⾎管内⽪型⼀酸化窒素合成酵素阻害(12)
Oxysterol concentration (µM)
0 25 50 75 100
Enzy
me
activ
ity (
%of
con
trol
)
20
0
80
100
40
60
0 25 50 75 100 0 25 50 75 100
*
*
*
**
**
** *
*
nNOS eNOS iNOS
× Cholesterol 25-Hydroxycholesterol■ 5β,6β-Epoxycholesterol▲ 7-Ketocholesterol● Secosterol-A○ Secosterol-B
Secosterol‐ASecosterol‐A
30

得られた研究成果です。本研究の一部は、公益財団法人 篷庵社の研究助成によるものであり、ここに
厚く御礼を申し上げます。また、ご推薦を賜りました伊勢村護先生に心より感謝申し上げます。
参考文献
1. Wentworth P Jr, Nieva J, Takeuchi C, Galve R, Wentworth AD, Dilley RB, DeLaria GA, Saven A, Babior BM, Janda KD, Eschenmoser A, Lerner RA. Evidence for ozone formation in human atherosclerotic arteries. Science (2003) 302, 1053-6.
2. Zhang Q, Powers ET, Nieva J, Huff ME, Dendle MA, Bieschke J, Glabe CG, Eschenmoser A, Wentworth P Jr, Lerner RA, Kelly JW. Metabolite-initiated protein misfolding may trigger Alzheimer's disease. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. (2004) 101, 4752-7.
3. Bosco DA, Fowler DM, Zhang Q, Nieva J, Powers ET, Wentworth P Jr, Lerner RA, Kelly JW. Elevated levels of oxidized cholesterol metabolites in Lewy body disease brains accelerate alpha-synuclein fibrilization. Nat. Chem. Biol. (2006) 2, 249-53.
4. Tomono S, Miyoshi N, Ito M, Higashi T, Ohshima H. A highly sensitive LC-ESI-MS/MS method for the quantification of cholesterol ozonolysis products secosterol-A and secosterol-B after derivatization with 2-hydrazino-1-methylpyridine. J. Chromatogr. B, (2011) 879, 2802-8.
5. Pryor WA, Wang K, Bermúdez E. Cholesterol ozonation products as biomarkers for ozone exposure in rats. Biochem. Biophys. Res. Commun. (1992) 188, 618-23.
6. Karu K, Hornshaw M, Woffendin G, Bodin K, Hamberg M, Alvelius G, Sjövall J, Turton J, Wang Y, Griffiths WJ. Liquid chromatography-mass spectrometry utilizing multi-stage fragmentation for the identification of oxysterols. J. Lipid Res. (2007) 48, 976-87
7. Zhang Q, Powers ET, Nieva J, Huff ME, Dendle MA, Bieschke J, Glabe CG, Eschenmoser A, Wentworth P Jr, Lerner RA, Kelly JW. Metabolite-initiated protein misfolding may trigger Alzheimer's disease. Proc. Natl. Acad. Sci. USA. (2004) 101, 4752-7.
8. Miyoshi N, Iwasaki N, Tomono S, Higashi T, Ohshima H. Occurrence of cytotoxic 9-oxononanoyl secosterol aldehydes in human low density lipoprotein. Free Radic. Biol. Med., (2013) 60, 73-9.
9. Tomono S, Miyoshi N, Sato K, Ohba Y, Ohshima H. Formation of cholesterol ozonolysis products through an ozone-free mechanism mediated by the myeloperoxidase-H2O2-chloride system. Biochem. Biophys. Res. Commun. (2009) 383, 222-7.
10. Tomono S, Miyoshi N, Shiokawa H, Iwabuchi T, Aratani Y, Higashi T, Nukaya H, Ohshima H. Formation of cholesterol ozonolysis products in vitro and in vivo through a myeloperoxidase-dependent pathway. J. Lipid Res., (2011) 52, 87-97.
11. Tomono S, Yasue Y, Miyoshi N, Ohshima H. Cytotoxic effects of secosterols and their derivatives on several cultured cells. Biosci. Biotechnol. Biochem., (2013) 77, 651-3.
12. Lai YL, Tomono S, Miyoshi N, Ohshima H. Inhibition of endothelial- and neuronal-type, but not inducible-type, nitric oxide synthase by the oxidized cholesterol metabolite secosterol aldehyde: Implications for vascular and neurodegenerative diseases. J. Clin. Biochem. Nutr., (2012) 50, 84-9.
13. Miyoshi N. Chemical alterations and regulations of biomolecules in lifestyle-related diseases. (Review) Biosci. Biotechnol. Biochem., (2016) in press
14. Miyoshi N, Iuliano L, Tomono S, Ohshima H. Implications of cholesterol autoxidation products in the pathogenesis of inflammatory diseases. (Review) Biochem. Biophys. Res. Commun., (2014) 446, 702-8.
31

新たな薬効評価系の確立に向けて
大阪市立大学大学院医学研究科 分子病態薬理学
泉 康雄
1.はじめに
我が国では心疾患・脳血管疾患による死因が 25%を超えており、循環器系疾患の克服は
国民の健康維持に極めて重要である。レニン・アンジオテンシン・アルドステロン(RAA)
系阻害薬、インスリン抵抗性改善薬、脂質改善薬など画期的な薬剤が登場し、一定の効果
が得られているにもかかわらず、超高齢化や食生活の欧米化に伴い、高血圧・糖尿病・脂
質異常症といった生活習慣病は増加している。すなわち、心疾患・脳血管疾患を減らすた
めには、RAA 系の抑制や炎症性サイトカイン・増殖因子作用の抑制だけでは不十分である。
そこで、心血管病における微小環境ネットワークでの新たなパラダイムを見出すことが重
要となる。
近年、心血管病は慢性炎症の一つと考えられている。慢性炎症は持続的なストレスに対
する防御反応であるが、組織の機能障害とリモデリングを引き起こし、病態を形成する。
我々は、虚血性心疾患を含む心血管疾患を慢性炎症の視点から捉え、異種細胞間連絡を担
う分子に注目し、その中で、「エキソソーム」に焦点を当てて研究を行ってきた。様々な病
態モデル動物が研究に用いられているが、例えば、げっ歯類では動脈硬化が起こりにくく、
動脈硬化巣に線維性被膜も形成されないなど、げっ歯類と非げっ歯類では病態が異なるこ
とも少なくない。我々は非げっ歯類哺乳動物(超小型ミニブタ)を用いて、非侵襲的な病
態モデルの作製に成功し、本モデルからエキソソームの役割についての知見も得られつつ
ある。本発表では、主に心血管病モデルにおけるエキソソームの役割について述べる。
2.エキソソーム
エキソソームは、mRNA、microRNA、タンパク質などを内包している径 30~100 nm 程
度の細胞外膜小胞であり、細胞間の情報伝達を担うと考えられている 1)。エンドサイトー
シスによって形成されたエンドソームから内側へ出芽するようにして作られる多数の膜小
胞でエキソサイトーシスによって細胞外へ分泌されたものがエキソソームとされる。
エキソソームは血液だけでなく、唾液や尿などの様々な体液に含まれている。体液中に
分泌されたエキソソームは、受容細胞上の受容体への結合やエンドサイトーシスおよび直
接的な膜融合により、受容細胞のシグナル因子活性化やタンパク質、mRNA、microRNA
の運搬を介して情報を伝達している 2)(図 1)。
エキソソームの単離方法にはいくつかあるが、できるだけ不純物を除外するため、我々
は、 も一般的な方法として用いられている超遠心法を修正した方法を用いた。エキソソ
ームはその膜表面や内部にテトラスパニン類(CD9、CD63、CD81 など)や熱ショックタ
ンパク質(heat shock protein (HSP) 90、heat shock cognate protein (HSC) 70、HSP70)を有し
32

図 1: エキソソームは細
胞間で情報を伝達する .
様々な”情報”を持つエ
キソソームは細胞から分
泌された後、他の細胞へ
と運ばれ、受容体やエン
ドサイトーシス、膜融合
を介して細胞間で情報を
伝達する。
ていることが知られている。
エキソソームの役割解明については、癌領域での研究が進んでおり、癌の生存や転移、
薬剤耐性に関わっていることが明らかとなっている 3)。一方、心血管病における血中エキ
ソソームの役割については未だ十分には明らかにされていない。本発表では、いくつかの
心血管病モデル(高血圧モデル・心不全モデル・動脈硬化モデル)から得られた、血中エ
キソソームの役割について述べる。
3.高血圧モデルにおけるエキソソームの役割
高血圧は心血管疾患、脳卒中、慢性腎不全等の も重要な危険因子の一つである。また、
高血圧は左の心室肥大を引き起こし、慢性心不全や心室性不整脈の発生率を高める。標的
臓器の損傷は、血圧依存的に、あるいは、いくつかのホルモンや神経伝達物質(特にアン
ジオテンシン II (AII))によって引き起こされる。そこで、高血圧モデルを作製して、高血
圧状態でのエキソソームの役割を調べた 4)。
8 週齢の雄性ウィスターラットに対して、浸透圧ミニポンプを皮下に植え込み、AII (200
ng/kg/min)の持続投与を行うことで、高血圧モデルを作製した。対照群は同様の方法で、生
図 2: AII 投与後のラットの血圧・左室重量 . AII 投与 3 日後および 7 日後ラットの
収縮期血圧(SBP)(A)、左心室重量/体重(LV weight /BW)(B). 値は平均値±標準偏差
(n=5-12). ** P <0.01.
33

理食塩水のみを投与した。対照群に比べて、AII 持続投与 3 日目、および 7 日目に収縮期
血圧は有意に上昇し、投与 7 日目では左室重量も有意に増加した(図 2)。そこで、AII お
よび生理食塩水投与 7 日目のラット血清から超遠心法を用いてエキソソームを精製・回収
し、対象群のエキソソームと比較検討した。
高血圧あるいはコントロールラットの血液から超遠心法にて得られたエキソソームの
数および粒子径を NanoSight®を用いて測定した。AII 投与ラットの血中エキソソーム
(AII-exo) 数は 4.0 x108/uL serum、コントロールラットの血中エキソソーム (Con-exo) は 1.6
x108/uL serum であり、Con-exo と比較して AII-exo の単位血清あたりのエキソソーム数が
2.5 倍に増加した。また、エキソソームの平均径は AII-exo の方が、Con-exo よりも小さか
った(図 3)。
図 3: コントロールラットと
AII 投与ラットの血中エキソ
ソーム数の比較 . Con-exo、
AII-exo の数および平均サイ
ズ (n=4).
高血圧の持続は内皮障害を引き起こすことから、エキソソームの内皮細胞に対する影響
を調べた。超遠心法で単離した沈殿物にはエキソソーム以外にもグロブリンやアルブミン
などの夾雑物が含まれていることから、より純度の高いエキソソームを得るために、超遠
心法で得られたエキソソームをさらに密度勾配超遠心によって精製したエキソソームをヒ
ト冠動脈内皮細胞(HCAEC)に添加した。
AII-exo は添加 5 分後に HCAEC の p38 mitogen-activated protein kinase (p38)活性を亢進し
た。一方、nuclear factor-kappa B (NF-κB)の活性は AII-exo による活性亢進を認めなかった
(図 4A)。
次に、AII-exo を添加して HCAEC の炎症関連タンパク質 intercellular adhesion molecule-1
(ICAM-1)、plasminogen activator inhibitor-1 (PAI-1)発現および endothelial nitric oxide synthase
(eNOS)リン酸化に与える影響を検討した。AII-exo の添加 24 時間後、内皮細胞の ICAM-1
発現は未刺激 ( Exo (-) ) に比べて Con-exo の添加で減少し、AII-exo の添加で増加した。 ま
た、PAI-1 発現は Exo (-) と比べて Con-exo を添加しても発現は変化しなかったが、AII-exo
の添加で増加した。さらに、eNOS リン酸化は Exo (-) または Con-exo と比べて AII-exo を
添加にて減弱した(図 4B)。以上のことより、AII-exo が内皮細胞の炎症を惹起する可能性
が明らかとなった。
AII 投与によって心臓にマクロファージが浸潤していることが知られており、本モデル
34

図 4: 血中エキソソームの内皮細胞に与える影響 . (A) HCAEC に AII-exo を添加
30 分後までの p38 と NF-κB のリン酸化 . (B) Con-exo あるいは AII-exo 添加 24
時間後の HCAEC の ICAM-1、PAI-1 タンパク質発現と eNOS リン酸化 .
においても、AII を 7 日間持続投与したラット心臓標本では左室内に多数の炎症性細胞の
浸潤を認め、抗 ED-1 (CD68)抗体陽性を示したことからマクロファージの存在を確認でき
た。我々は、血中にはマクロファージ由来のエキソソームが存在し、それが内皮細胞の炎
症に関与しているとの仮説を立て、検証を行った。興味深いことに、血液から精製したエ
キソソームのタンパク質でウェスタンブロットを行ったところ、ED-1 抗体によるバンドが
検出され、血中にはマクロファージ由来エキソソームが含まれることが強く示唆された。
そこで、培養マクロファージが分泌するエキソソームの HCAEC に及ぼす影響を検討した。
図 5: マクロファージが分泌するエキソソームは
血管内皮細胞の炎症を惹起する . (A) THP-1 由来
マクロファージから分泌されたエキソソームの
エキソソームマーカー発現およびマクロファー
ジマーカー発現 . (B) AII-Mφ-exo を添加 0-30 分
後の HCAEC の p38MAPK と NF-κB のリン酸化 .
(C) Con-M-exo、Hyp-Mφ-exo、AII-Mφ-exo を添加
24 時間後の HCAEC の ICAM-1、PAI-1 のタンパク
質発現とマクロファージマーカーCD68 発現 .
35

ヒト白血球由来単球 (THP-1) 由来マクロファージに対して、未刺激、AII 刺激(100
μg/mL)、低酸素刺激(1% O2)を 24 時間行った後に、培養上清からエキソソームを精製・回
収した。それぞれのエキソソームを HCAEC に添加した。
未刺激マクロファージ由来エキソソーム (Con-Mφ-exo)、AII 刺激マクロファージ由来エ
キソソーム (AII-Mφ-exo)、低酸素刺激マクロファージ由来エキソソーム (Hyp-Mφ-exo) に
エキソソームマーカーHSP90、 HSC70、マクロファージマーカーの CD68、CD45 を検出し、
Mφ-exo が単離できていることを確認した(図 5A)。血中エキソソームを 24 時間添加した
場合と同様に AII-Mφ-exo を添加後、HCAEC の p38MAPK のリン酸化が早期に増大したが、
NF-κB のリン酸化に変化はなかった(図 5B)。また血中エキソソームを 24 時間添加した場
合と同様に、Con-Mφ-exo、AII-Mφ-exo、Hyp-Mφ-exo を添加 24 時間後、AII-Mφ-exo、
Hyp-Mφ-exo を添加した HCAEC の ICAM-1、PAI-1 が増加した。さらに、マクロファージ
マーカーの CD68 が検出され、Mφ-exo が HCAEC に取り込まれていることが示された (図
5C) 。データではまだお示しできないが、Con-Mφ-exo、AII-Mφ-exo、Hyp-Mφ-exo それぞ
れからタンパク質を抽出し、質量分析計にて解析を行ったところ、刺激によって、エキソ
ソームに含まれるタンパク質の種類も異なっていることが明らかとなった。
本モデルにおいて、(1) 正常血圧ラットの血中エキソソームと比べて AII 投与による高
血圧モデルラットの血中エキソソーム数が増加する、(2) 血中にはマクロファージ由来エ
キソソームが存在する、(3) AII 投与ラットの血中エキソソーム及び AII 刺激マクロファー
ジのエキソソームは内皮細胞の炎症を惹起する、ことが明らかとなった。高血圧ラットの
血中に含まれるマクロファージ由来エキソソームが血管内皮細胞の炎症を惹起することで
高血圧性心疾患の進展に関与している可能性が示唆され、今後は薬剤によるエキソソーム
への関与を明らかにしていく予定である。
4.心不全モデルにおけるエキソソームの役割
虚血性心疾患の増加や人口の高齢化に伴い、心不全患者が増加している。我が国には 250
万人以上の慢性心不全患者がいると推測される。慢性心不全の病態生理として、初期のポ
ンプ失調からはじまり、持続性の様々な代償機構の活性化、特に、交感神経系、RAA 系、
サイトカイン系の活性化が関与していることが基礎研究、臨床研究の両面から証明されて
いる。その是正を目指した β 遮断薬や RAA 系阻害薬が慢性心不全に対して有効だという
多くのエビデンスがある。こうした薬物治療の進歩により患者の生命予後は改善している
ものの、治療を受けながら急性増悪を繰り返して、やがて命を落とす患者は減っていない。
それゆえ、新たな視点からの治療法開発が求められている。
慢性心不全に対する非薬物療法として、心臓再同期療法、運動療法、和温療法、手術療
法、補助循環、心臓移植、が記されている。この中で、 も多くの施設で簡便かつ安価に
行えるものは運動療法である。運動療法が運動耐容能を増加させるだけでなく、心不全患
者の不安や抑うつを軽減し、QOL を改善することはほぼ確立されている。しかしながら、
介助なしには運動療法を行えない患者も多い。我々は、運動療法に代わる受動的運動耐容
能増加療法を行うことで、この問題を解決できると考えた。
36

心筋梗塞や虚血・再還流障害に対して、閉塞前に病変部冠動脈が短時間の虚血状態を繰
り返すことで、心筋障害を抑制されることが明らかになった( Ischemic pre-conditioning:
IPreC 効果)。その後、閉塞後の再還流時に短時間の虚血状態を繰り返すことで心筋障害
が抑制されることも明らかとなった(Ischemic post-conditioning: IPostC 効果)。2007 年、
ブタの冠動脈虚血・再還流モデルにおいて、再還流直後に後肢の虚血を繰り返して行うこ
とで、心筋梗塞サイズを有意に縮小することが報告された 5)。2010 年には、急性心筋梗塞
で搬送中の救急車内で四肢駆血処置を行った患者では、非処置の患者に比べて心筋梗塞サ
イズが減少した、という非常に興味深い臨床研究結果が発表された。すなわち、IPreC 効
果や IPostC 効果は、病変部以外の冠動脈や冠動脈以外の遠隔部位での一過性虚血処置を行
うことでも心保護効果を有することが報告された。我々は、心筋梗塞後慢性期の心機能低
下や慢性心不全に対して、遠隔部位での虚血状態(remote ischemic conditioning: RIC)が心
保護作用を有するとの仮説を立て、慢性心不全モデルを作製して、RIC 療法の慢性心不全
に対する有効性を明らかするとともに、エキソソームの関与について調べた 6)。
ラットの冠動脈を結紮することにより心筋梗塞(MI)を作製し、MI 作製 4 週後に超音
波法による心機能評価を行い、非処置群(UT 群)と RIC 処置群(RIC 群)に分けた。RIC
処置は乳児用止血バンドを用いてラットの両側後肢に対して 5 分の虚血と 5 分の開放を繰
り返し 5 クール、毎日、4 週間行った。また、非 MI 群をコントロール群(CON 群)とし
た。RIC 処置中は下肢への血流が遮断されており、処置後は処置前よりも下肢への血流が
増加することが確認された(図 6)。
図 6: レーザードップラーによる血流測定 . RIC 処
置前(A)に比べ、RIC 中はほとんど血流を認めない
(B). RIC 処置後は処置前よりも血流が増加してい
る(C).
図 7: RIC 処置 4 週間後
の左室機能評価 . 左室
拡張末期容量(A)、左室
収縮末期容量(B)、左室
駆出率 (C)および E/e’
(D). CON; 非心筋梗塞
対照群 , UT; 心筋梗塞
+非処置群 , RIC; 心筋
梗塞+RIC 処置群 . 値
は 平 均 値 ± 標 準 偏 差
(n=11-17). *P< 0.05.
37

UT 群、RIC 処置群で血圧や心拍数、梗塞サイズに差はなかったが、UT 群に比べて RIC
群では左室拡張末期容量および収縮末期容量は有意に減少し、左室駆出率 (LVEF) は非処
置群と比較して RIC 群で有意に改善された(図 7A-C)。さらに、UT 群の LVEF が 4 週間
でより悪化する傾向を示したのに対して、RIC 群の LVEF は治療前より改善傾向を認めた。
慢性心不全では左室の拡張機能の指標の一つである E/e’が増加することが知られているが、
興味深いことに、UT 群に比べて RIC 群では E/e’が有意に改善した(図 7D)。
梗塞周辺領域における左室間質の線維化率も RIC 群で有意に軽減し(図 8A)、心筋梗塞
後に増加(悪化)することが知られている酸化ストレス度の指標の一つである血中活性酸
素代謝産物(d-ROM)値は、RIC 処置により有意に改善した(図 8B)。
図 8: RIC 処置 4 週間後の
左室線維化率 (A)および
酸化ストレス度 (B). 値
は 平 均 値 ± 標 準 偏 差
(n=11-17). *P< 0.05.
図 9: Collagen-3 発現および microRNA 発現 . (A) 左室の梗塞周辺領域における
Collagen-3 発現、(B) 血中エキソソーム中の microRNA (miR-29a, miR-30a, miR-133a) 発
現、(C) 左室の梗塞周辺領域における microRNA 発現、(D) C2C12 細胞の培養上清液か
ら精製したエキソソームの miR-29a 発現 . 値は平均値±標準偏差 . *P< 0.05.
38

MI で亢進した左室の線維化関連分子 Collagen-3 発現は RIC 群で抑制された(図 9A)。
興味深いことに、血中エキソソームの量は UT 群に比べて RIC 群で有意に増加しており、
エキソソーム中の線維化関連 microRNA の miR-29a や miR-133a 発現は RIC 群で有意に増
加していた(図 9B)。左室の心筋梗塞周辺領域における miR-29a、miR-30a 発現も UT 群
に比べて有意に増加していることがわかった(図 9C)。分化させた C2C12 細胞を低酸素
状態(1% O2)にすると、培養上清から精製したエキソソーム中の miR-29a 発現が増加した
(図 9D)。
以上より、(1) 心筋梗塞後の慢性心不全モデルラットに対して RIC 療法は心臓モデリン
グ進展を抑制する、(2) RIC 療法により、血中エキソソーム中には線維化関連遺伝子を抑
制する microRNA が増加する、(3) 骨格筋類似細胞を低酸素にすると放出するエキソソー
ム中の線維化関連遺伝子を抑制する microRNA が増加する、ことが明らかとなった。一過
性に四肢を虚血状態にすることで、エキソソームを介した心保護作用が発揮できる可能性
があり、今後は、臨床検体を用いて解析を行っていく予定である。
5.超小型ミニブタを用いた動脈硬化モデルにおけるエキソソームの役割
医薬品の非臨床安全性試験では、げっ歯類(ラット・マウス)に加えて非げっ歯類哺乳動
物(イヌ・サル・ブタなど)を用いた評価が義務付けられている。しかし、3Rs(苦痛と数
の削減、他の方法への置き換え)の精神遵守や動物愛護の観点から、イヌやサルの使用は
制限されつつある。代替動物としてブタが期待され、実際、様々な研究用のミニブタが開
発されたが、ミニブタの体重は 30~40 kg にも及ぶため、非常に扱いが難しく飼育できる
施設も限られていた。この状況を打破するためには、簡便に扱え、動物愛護の観点からも
許容されうる非げっ歯類哺乳動物の開発が急務となっていた。我々は、近年開発された、
ビーグル犬とほぼ同等の大きさ(性成熟時体重:7 kg 以下、成体時体重 10 kg 以下)で、
性格も温厚な超小型実験用ミニブタ(マイクロミニピッグ®)を用いることでこうした問題
の解決をできると考えた 7)。ヒトに近い哺乳類で非侵襲的な病態モデルを作製し、薬剤の
有効性および毒性・安全性薬理試験の評価系を確立できれば、こうした問題もある程度解消
することができると考えられる。そこで、これまでのげっ歯類では作製が不可能であった
食餌の調整(高脂肪・高コレステロール食)のみで、持続的高コレステロール血症を誘発
し、冠状動脈、脳底動脈を含む全身の動脈に動脈硬化病変が生じる動脈硬化モデル 8)、お
よび内皮機能障害によって引き起こされる高血圧モデル 9)の作製を行い、エキソソームの
関与について調べた。また、マイクロミニピッグに一酸化窒素合成酵素阻害薬
(NG-nitro-L-arginine methyl ester: L-NAME)を投与することで内皮機能を障害して高血
圧を呈するモデルにおけるエキソソームの関与について調べた。
L-NAME 投与で高血圧・心肥大を呈したが、大動脈の動脈硬化は認めなかった。一方、
高脂肪・高コレステロール食投与では血中コレステロールが持続的に高値を示し、大動脈
の動脈硬化を認めた(図 10A, B)。いずれのモデルにおいても、血中のエキソソームのタ
ンパク質濃度は週齢とともに増加したことから、エキソソームが病態形成に関与している
可能性が示唆された。今後、より詳細な検討を進めていく予定である。
39

図 10: Oil-red O 染色による大動脈の動脈硬化(A, B)と血中エキソソームのタンパク
質濃度(C). ND; normal diet, L-NAME; normal diet + L-NAME, HFCD; high-fat and
high-cholesterol diet.
6.おわりに
エキソソームを介した細胞間情報伝達機構は、心血管病の進展に関与している可能性が
高い。一方で、エキソソームは心保護作用にも関与している可能性がある(図 11)。今後、
さらに詳細に解析を行うことで、新たな治療につながることを期待している。
図 11: エキソソームを介した細胞間情報
伝達機構のイメージ
謝辞
以上の研究成果は、岩尾洋先生ならびに多くの共同研究者の協力により得られたもので
す。本研究の一部は、公益財団法人篷庵社の研究助成によるものであり、ここに厚く御礼
申し上げます。また、ご推薦を賜りました宮﨑瑞夫先生に心より感謝申し上げます。
40

参考文献
1) Yellon DM, Davidson SM. Exosomes: nanoparticles involved in cardioprotection?
Circ Res. 2014;114:325-332.
2) Tang MK, Wong AS. Exosomes: Emerging biomarkers and targets for ovarian cancer.
Cancer Lett. 2015;367:26-33.
3) Valadi H, Ekström K, Bossios A, Sjöstrand M, Lee JJ, Lötvall JO. Exosomes in
cancer development, metastasis, and drug resistance: a comprehensive review.
Cancer Metastasis Rev. 2013;32:623-642.
4) Osada-Oka M, Shiota M, Izumi Y, Nishiyama M, Tanaka M, Yamaguchi T, Sakurai E,
Miura K, Iwao H. Macrophage-derived exosomes induce inflammatory factors in
endothelial cells under hypertensive conditions. [in submission]
5) Przyklenk K, Bauer B, Ovize M, Kloner RA, Whittaker P. Regional Ischemic
Preconditioning Protects Remote Virgin Myocardium from Subsequent Sustained
Coronary-Occlusion. Circulation. 1993;87:893-899.
6) Yamaguchi T, Izumi Y, Nakamura Y, Yamazaki T, Shiota M, Sano S, Tanaka M,
Osada-Oka M, Shimada K, Miura K, Yoshiyama M, Iwao H. Repeated remote
ischemic conditioning attenuates left ventricular remodeling via exosome-mediated
intercellular communication on chronic heart failure after myocardial infarction.
Int J Cardiol. 2015;178:239-246.
7) Kaneko N, Itoh K, Sugiyama A, Izumi Y. Microminipig, a non-rodent experimental
animal optimized for life science research-preface. J Pharmacol Sci. 2011;115:112-
114.
8) Miyoshi N, Horiuchi M, Inokuchi Y, Miyamoto Y, Miura N, Tokunaga S, Fujiki M,
Izumi Y, Miyajima H, Nagata R, Misumi K, Takeuchi T, Tanimoto A, Yasuda N,
Yoshida H, Kawaguchi H. Novel microminipig model of atherosclerosis by high fat
and high cholesterol diet, established in Japan. In Vivo. 2010;24:671-680.
9) Yamaguchi T, Yamazaki T, Kawaguchi H, Tawa M, Nakamura Y, Shiota M,
Osada-Oka M, Tanimoto A, Okamura T, Miura K, Iwao H, Yoshiyama M, Izumi Y. A
noninvasive metabolic syndrome model using an extremely small minipig, the
Microminipig. J Pharmacol Sci. 2014;126:168-171.
41

メチル化 DNA 可視化マウスを用いた病態評価法の確立
近畿大学生物理工学部遺伝子工学科発生遺伝子工学研究室
山縣一夫
1:はじめに
DNA のメチル化は、遺伝子刷り込み(ゲノミックインプリンティング)や X
染色体の不活性化、トランスポゾン転移の抑制など正常な発生過程に重要な役
割を果たしているほか、その制御異常が発がんなどの様々な疾患と関連してお
り、DNA メチル化を指標とした抗がん剤の開発も進められている(1)。また、
妊婦の生活習慣が胎児の DNA のメチル化状態に影響を及ぼし、ひいては生まれ
てくる子どもの疾病罹患率に影響を及ぼすとの研究報告もあり、ストレス応答
や環境の変化によってもDNAのメチル化がダイナミックに変化するものとして
認識されるようになってきている。しかし、現在エピジェネティクス研究で広
く用いられている実験手法〔ウェスタンブロット法、クロマチン免疫沈降(ChIP)
法、免疫染色法、バイサルファイトシークエンス法など〕は、サンプルを固定・
変性してしまうことから、ある瞬間のメチル化 DNA の状態しか解析できず、そ
のため単一の細胞や個体レベルでの動態変化を追跡するには必ずしも向いてい
ない。また、免疫染色法以外の手法では多数の細胞の平均を扱うため、マイナ
ーな細胞集団の挙動は見過ごされてしまう。そこで、これらの問題を解決する
新しい解析手法の開発が求められていた。
われわれの研究グループは、後述のような原理に基づいて、メチル化 DNA に
特異的に結合する蛍光プローブを作製し、このプローブをコードする mRNA を
試験管内で合成し、それをマウスの受精卵にインジェクションすることによっ
て、マウス着床前初期胚の発生過程における DNA のメチル化修飾のライブセル
イメージング解析を行ってきた(2、3)。この方法論を用いて体細胞核移植(ク
ローン)胚などを観察することによって、生殖細胞系列のグローバルな DNA の
メチル化状態(主にセントロメア近傍)が体細胞系列のそれに比べて著しく低
いことを明らかにした。しかし、この方法ではプローブを一過的にしか発現さ
せることができないことから、受精卵から桑実胚期の手前までしか観察できな
42

かった。このような背景のもと、DNA のメチル化修飾の変化を長期間かつ安定
的に解析する必要性を感じ、われわれは全身で MBD プローブを発現させたマウ
スを開発することに着想した。全身性の発現を示すプロモーターとして CAG や
CMV プロモーターがよく知られているが、細胞間での遺伝子発現のばらつきが
大きいことからイメージングの定量解析には適していなかった(図 1A、C)。そ
こで、遺伝子発現がユビキタスで、細胞間での発現のばらつきが小さいことが
知られている ROSA26 遺伝子座に着目し、mCherry を融合した MBD プローブを
この領域にノックインすることでレポーターマウスを作製した(4、図 1B、D
-G)。赤色を選択した理由は、自家蛍光が少なく、組織深部の観察に適してい
るからである。樹立したマウスはメジャーリーグで活躍するイチロー選手とか
けて「メチロー(MethylRO:Methylation probe in ROSA26 locus の略)」マウスと
命名した。重要なことは、このメチローマウスが全身で MBD プローブを発現し
ているだけでなく、健康で妊孕性があるということである。このマウスによっ
て様々な細胞種や組織での DNA のメチル化動態解析が可能となった。
2:メチル化 DNA 検出蛍光プローブの原理と正当性
DNA のメチル化修飾を生きたまま可視化するプローブは、当初は熊本大学の
中尾光善博士らのグループによって、MBD1 タンパク質のドメイン解析の過程
で示された(5、図 1B)。その後、核磁気共鳴分光法を用いた構造解析や(6)、
われわれによるメチル化プラスミドへのドットブロット法(3)などによって、
MBD1 の MBD ドメイン単独(以下 MBD プローブ)でメチル化された CpG 配
列に結合できることが示された。また理化学研究所(現、熊本大学)の岡野正
樹博士らは、DNA メチル化酵素(Dnmt1、Dnmt3a、Dnmt3b)のトリプルノック
アウト ES 細胞を用いて、DNA のメチル化修飾がない細胞の核ではこの EGFP
を融合した MBD プローブがドット状の明瞭なシグナルを形成しないことを明
らかにしている(7)。われわれは、この MBD プローブを発現する ES 細胞を
用いて、蛍光分子(RFP)抗体を用いたMeDIP-Seqデータを5mC抗体のMeDIP-Seq
データと比較することで、このプローブが確かにメチル化 DNA を認識している
ことを最近明らかにした(4)。以上のような様々な検討により、本プローブが
細胞内においても確実かつ特異的にメチル化DNAに結合することが明らかとな
った。
43

44

3:メチローマウスの所見
作製したメチローマウスを詳細に観察した。出産直後(図2A、B)と胎齢 12.5
日(図2C)のメチローマウスを観察したところ、全身および胎盤において赤色
蛍光を確認することができた。胎児全体を切片にし、すべての領域を共焦点レ
ーザー顕微鏡で撮影し、画像を合成した(図2E、F)。その結果、観察したすべ
ての細胞で本プローブが核内のヘテロクロマチン領域に集積していることが明
らかとなった。通常、体細胞ではメチル化 DNA は、セントロメアおよびその近
傍領域に代表されるヘテロクロマチンに集積していることが知られているため、
この結果は妥当であると考えられる。次に、生体まで成長したメチローマウス
の各種臓器を取り出し蛍光観察すると、すべての臓器でプローブの発現が見ら
れた(図2D)以上から、メチローマウスは発生過程のすべての細胞系譜や、生
体においてもすべての細胞でメチル化DNAの観察が可能であることを示してお
り、発生過程や病態変化における DNA メチル化変化の解析に使用できると考え
られた。
図1 メチローマウスの作製手順。
(A)CAG プロモーターで GFP を発現するマウス由来の受精卵。割球ごとに発現量が
異なることがわかる。(B)MBD1 タンパク質とメチロープローブの構造。(C)CAG プ
ロモーターで GFP を、CMV プロモーターでメチロープローブを発現する ES 細胞。
CMV プロモーターではサイレンシングを受けてまったく発現しない細胞がある。(D)
ROSA26 遺伝子座へのノックインコンストラクト。(E)PCR による組み換えの確認。
(F)樹立した ES 細胞の各種傾向タンパク質でのウエスタンブロット。(G)ES 細胞
の蛍光写真。赤色でハイライトされたメチル化 DNA がヘテロクロマチンやセントロメ
ア近傍領域に局在していることがわかる。
45

46

4:細胞分化状態の違いによるメチル化 DNA の動態解析
このメチローマウスと低侵襲性ライブセルイメージング技術と組み合わせる
ことによって、マウスの着床前初期胚発生過程及び ES 細胞の樹立過程の長期間
ライブセルイメージングを行った(図3)。初期胚においてはプローブをコード
する mRNA をマイクロインジェクションにより導入していた以前に比べ、胚盤
胞期に至るまで継続して核内に蛍光シグナルを得ることができた(図3A)。4
細胞期胚においてセントロメア集積タンパク質である CENP-C と共イメージン
グしたところ、共局在あるいは非常に隣接していたため、本シグナルはセント
ロメア近傍領域のヘテロクロマチン領域であると結論した(図3B、C)。続いて、
ES 細胞と卵割期胚の核におけるメチル DNA のシグナルを時間軸方向にプロジ
ェクションしたところ、ES 細胞では比較的大きな点状のシグナルの塊が見られ
たのに対して、卵割期胚ではそれが見られなかった(図3D)。このことは、メ
チル化 DNA で観察されるヘテロクロマチンが ES 細胞に比べて卵割期胚で動的
であることを示している。そこで、得られた画像情報をもとにその動態を定量
化する試みを行った(図3E、F)。細胞自体や細胞核の動きをキャンセルするた
め、核内における異なるメチル化 DNA シグナル2点間の距離の時間変化を算出
し(図3E)、その平均値を細胞ごとに示した(図3F)。その結果、図3E で見
られたのと同様に、卵割期胚は ES 細胞や胎児線維芽細胞に比べて、メチル化
DNA の動態がより高いことが明らかとなった。
図2 メチローマウスの全身所見。
(A)作製したメチローマウスは健康であり妊孕性も問題ない。(B)出生直後のメチロ
ー。(C)胎齢 12.5 日のメチロー。胎児だけでなく胎盤にもシグナルが見られる。(D)
メチローより取り出した各種臓器の蛍光写真。(E)胎齢 12.5 日胚の全身切片画像。(F)
全身切片のうち、尾周辺を拡大した画像。核内にヘキストと共局在しメチロープローブ
でラベルされるヘテロクロマチンが見られる。
47

5:細胞分化過程におけるメチル化 DNA 動態の変化
ES 細胞は胚盤胞期胚の内部細胞塊より樹立されることはよく知られている。
上記図3の結果では、卵割期胚に比べて ES 細胞においてより顕著なメチル化
DNA でラベルされるヘテロクロマチンが形成されていることがわかった。つま
り、ES 細胞が樹立されるいずれかの過程においてこのようなヘテロクロマチン
構造の新生過程が見られるはずである。そこで、その過程を捉えるべくメチロ
ーの胚盤胞期胚を ES 細胞誘導培地に入れ、8日間の連続観察を行った(図4)。
その結果、内部細胞塊よりエピブラスト系列が、栄養膜細胞から栄養芽層巨大
図3 初期胚や ES 細胞におけるメチル化 DNA の局在と動態。
(A)メチローマウスの初期胚発生過程。(B、C)メチローマウス初期胚に CENP-C-
EGFP の mRNA をインジェクションして共局在性を観察した画像。(D)メチル化 DNA
のタイムラプス画像を時間軸方向に積算(プロジェクション)した画像。(E)核内にお
けるメチル化 DNA の動態を定量化した図。(F)各細胞における(E)の時間平均。
48

細胞系列が誘導されるに従って、特にセントロメア近傍のメチル化 DNA が上昇
し、かつヘテロクロマチン構造が形成されていく様子を捉えることができた(図
4A、B)。これら動画をもとに、核内のメチル化 DNA の輝度(図4C-E)、ヘ
テロクロマチンインデックス(核内におけるシグナルのばらつきの変動係数、
図4F)、核のサイズ(図4G)を定量化した。その結果、すべての指標について
分化した細胞(ES 細胞や栄養芽層巨大細胞)で高い値を示した。これらの結果
と上記図3の結果から、核内の DNA のメチル化レベルの増減だけでなく核内の
クロマチン構造や配置そのものが細胞分化の指標になり得ることが明らかとな
った。同様の結論は、Torres-Padilla 博士のグループによっても同時期に報告され
た(8)。
49

50

6:おわりに
最近、メチル化 DNA だけでなく、ヒストンの翻訳後修飾のグローバルな変化
を生きたまま観察する試みがなされている。東京工業大学の木村宏博士らのグ
ループはモノクローナル抗体の Fab 断片を蛍光ラベルしたプローブを細胞内に
導入する方法(FabLEM 法)によってヒストンの翻訳後修飾を生きたまま可視化
することに成功している(9)。さらに、同グループはこの Fab 領域を cDNA 化
することに成功して、これによってヒストンの翻訳後修飾を生きた個体(ショ
ウジョウバエやゼブラフィッシュ)で長期間可視化することに成功した(10)。
将来的にはメチローをはじめとするこれらのエピジェネティクス・レポータ
ー・モデル生物を活用することで、発生・分化過程のエピジェネティクスの動
態解析ができるものと考えている。また、現行の光学顕微鏡の解像度では単一
遺伝子座のエピジェネティックな変化を捉えることはできないが(最大でも 1
ボクセルが数十メガ塩基対に相当する程度)、顕微鏡の開発が日進月歩で進んで
いるため、近い将来、超解像顕微鏡などによって単一遺伝子座でのエピジェネ
ティクス・イメージングが実現できるようになる時代が来るかも知れない。
本稿ではメチローマウスを用いた細胞分化過程のライブセルイメージング法
を紹介したが、この他にも組織切片解析でも威力を発揮する。もし 5mC 抗体で
免疫染色しようと思った場合、サンプルを固定した後に抗体の DNA へのアクセ
スを促すため、酸またはアルカリでクロマチンを変性処理する必要があるが、
メチローマウスは固定するだけで良いため簡便に観察できる。以上の方法論は、
がん化などの病態変化におけるメチル化 DNA の変化を観察・定量化できること
を示している。今後はメチローマウスを様々な疾患モデルマウスと掛け合わせ
ることで、病態進行過程でのメチル化 DNA の動態解析という観点から新しい知
見が多数得られると期待している。
図4 胚盤胞期胚期胚から ES 細胞や栄養芽層巨大細胞が誘導されてくる過程における
メチル化 DNA の動態。(A)タイムラプス画像。一部を抜粋して示してある。緑色は
Oct3/4 遺伝子を発現している細胞を示している。(B)栄養膜細胞から栄養芽層巨大細
胞が誘導される過程を拡大したタイムラプス画像。(C-E)各細胞種におけるメチル化
DNA の輝度変化。(F)核内におけるヘテロクロマチンのパターンを定量化した指標、
ヘテロクロマチンインデックス。より輝度の高い凝集したシグナルが多いほど値が高く
なる。(G)細胞核のサイズ。
51

7:謝辞
本研究の一部は公益財団法人蓬庵社の研究助成によりなされたものであり、
そのご厚意に深く感謝申し上げます。また、本助成にご推薦の労をお取りいた
だいた大阪大学微生物病研究所目加田英輔教授に御礼を申し上げます。本研究
は、上田潤博士(現、中部大学)、八尾竜馬研究員(扶桑薬品工業)、前原一満、
大川恭行両博士(九州大学)、佐藤優子、木村宏両博士(現、東京工業大学)に
ご協力をいただき成し得たものであり、ここに深謝いたします。
8:参考文献
1. Bergman Y & Cedar H (2013) DNA methylation dynamics in health and disease.
Nat Struct Mol Biol 20(3):274-281.
2. Yamagata K, et al. (2007) Centromeric DNA hypomethylation as an epigenetic
signature discriminates between germ and somatic cell lineages. Dev Biol
312(1):419-426.
3. Yamazaki T, Yamagata K, & Baba T (2007) Time-lapse and retrospective
analysis of DNA methylation in mouse preimplantation embryos by live cell
imaging. Dev Biol 304(1):409-419.
4。 Ueda J, et al. (2014) Heterochromatin Dynamics during the Differentiation
Process Revealed by the DNA Methylation Reporter Mouse, MethylRO. Stem
Cell Reports 2(6):910-924.
5。 Fujita N, et al. (1999) Methylation-mediated transcriptional silencing in
euchromatin by methyl-CpG binding protein MBD1 isoforms. Mol Cell Biol
19(9):6415-6426.
6. Ohki I, et al. (2001) Solution structure of the methyl-CpG binding domain of
human MBD1 in complex with methylated DNA. Cell 105(4):487-497.
52

7. Tsumura A, et al. (2006) Maintenance of self-renewal ability of mouse
embryonic stem cells in the absence of DNA methyltransferases Dnmt1, Dnmt3a
and Dnmt3b. Genes Cells 11(7):805-814.
8. Boskovic A, et al. (2014) Higher chromatin mobility supports totipotency and
precedes pluripotency in vivo. Genes Dev 28(10):1042-1047.
9. Hayashi-Takanaka Y, Yamagata K, Nozaki N, & Kimura H (2009) Visualizing
histone modifications in living cells: spatiotemporal dynamics of H3
phosphorylation during interphase. J Cell Biol 187(6):781-790.
10. Sato Y, et al. (2013) Genetically encoded system to track histone modification in
vivo. Scientific reports 3:2436.
53