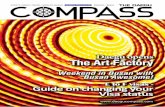研究活動報告 - 大阪女学院(1)“Five Lessons I Learned from my Students—Plenary...
Transcript of 研究活動報告 - 大阪女学院(1)“Five Lessons I Learned from my Students—Plenary...

- 103 -
研究活動報告(アルファベット順)
2010年(1月1日から12月31日)における専任教員の研究活動歴である。ここに掲載されているものは,
大阪女学院大学・短期大学研究活動委員会の依頼に応じて, 各専任教員が自己申請したものに限られていることを付記する。研究活動歴は以下のように分類される。
氏名, (専門領域), Ⅰ.著訳書, Ⅱ.学術論文, Ⅲ.その他の著作(研究ノート, ニュースレター , 報告書,
雑誌, 新聞等), Ⅳ.学会発表, Ⅴ.その他の発表(シンポジウム, 講演, 放送等), Ⅵ.学会および公的な機関の委員, Ⅶ.科学研究費等の公的な研究補助を受けた研究
智原 哲郎(ちはら・てつろう)〔言語テスティング,英語教育〕Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)文部科学省「特色ある大学教育支援プログラム(特色GP)」実施状況調査 主査 2010年3月18日
(2)文部科学省「大学教育推進プログラム」書面審査委員 2010年6月
Cline, William(クライン・ウィリアム)〔English Education〕Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)“Criterion at Osaka Joagkuin College.”CIEE (Council on International Educational Exchange)Criterion Seminar in Osaka, 於:学校法人常翔学園 大阪センター 304教室, 12月4日
Cornwell, Steve(コーンウェル・スティーブ)〔Curriculum Design and Instructional Technology,
English Education, TESOL〕Ⅱ.学術論文
(1)“Becoming an Effective Teacher: Competency Development and Reflective Practice KOTESOL
2010 Conference Proceedings.” 2010年5月, 共著(2)“Writing centers and tutoring in Japan and Asia.” In A. M. Stoke (Ed.), JALT2009 Conference
Proceedings, pp. 692-701. Tokyo: JALT, 2010年9月, 共著Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)“Teaching Strategies for the ESL Classroom: Engage your Students with Five-Minute Activities.”
Learner-centeredness in English Language Classroom in Bangladesh, 2010年12月, 単著Ⅳ.学会発表
(1)“Five Lessons I Learned from my Students—Plenary Presentation.” KOTESOL, 於:Daegu,
Korea, 2010年5月15日(2)“Vocabulary Learning: Theory and Techniques.” Bangladesh English Language Teacher
Association, 於:Dhaka, Bangladesh, 2010年7月2日(3)“Five Minute Activities.” Bangladesh English Language Teacher Association, 於:Dhaka,
Bangladesh, 2010年7月2日(4)“Second Language Acquisition (SLA) for Classroom.” Bangladesh English Language Teacher
Association, 於:Dhaka, Bangladesh, 2010年7月2日(5)“Preparing Students for Exams.” Bangladesh English Language Teacher Association, 於:Dhaka,
Bangladesh, 2010年7月3日(6)“Using the Native Culture to Teach the Target Language.” Bangladesh English Language Teacher
Association, 於:Dhaka, Bangladesh, 2010年7月3日(7)“Grammar Dictation and Other Grammar Fun.” Bangladesh English Language Teacher

- 104 -
Association, 於:Dhaka, Bangladesh, 2010年7月3日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)“Shakespeare's Guide to Reading Skills.” Pecha Kucha Nishinomiya, 於:Konan Univ. Cube,
Nishinomiya, 2010年7月17日(2)“'Tis the Season (Culture and our Students).” Osaka, Kobe, Nara, Kyoto JALT, 於:Konan Univ.
Cube, Nishinomiya, 2010年12月18日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)JALT, Director of Program, 2010年11月~12月(2)JALT Journal, Editorial Advisory Board, 2010年1月~12月(3)The Language Teacher, Editorial Advisory Board, 2010年1月~12月
Ⅶ.科学研究費補助金等の公的研究補助を受けた研究(1)Writing Centers, Grants-in-Aid for Scientific Research grant 19520531, 2007年4月~2010年3月
夫 明美(ふ・あけみ)〔第二言語習得,中間言語語用論〕Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)「授業の玉手箱」, 『教員養成センターニュースレター』第2号, 2010年7月(2)「書籍紹介」, 『教員養成センターニュースレター』第3号, 2010年10月(3)「巻頭エッセイ 絆」, 『教員養成センターニュースレター』第4号, 2011年1月
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「表現力としての音読や発音指導の基本構造」平成22年免許更新講習, 於:大阪女学院大学,
2010年8月7日(2)「表現力を培う語彙学習指導」平成22年免許更新講習, 於:大阪女学院大学, 2010年8月7日
Fujimoto, Donna(フジモト・ドナ)〔Conversation Analysis, Pragmatics, Narrative Analysis, Intercultural
Studies〕Ⅱ.学術論文
(1)“The team alliance in EFL small group discussion.”In T. Greer (Ed.), Observing talk: Conversation
analytic studies of second language interaction, pp.110-132, JALT Pragmatics Special Interest
Group, Tokyo. 2010年11月, 単著(2)“Agreements and disagreements: The small group discussion in a foreign language classroom.”In
G. Kasper, H. Nguyen, D. Yoshimi & J. Yoshioka (Eds.), Pragmatics and language learning, Vol. 12,
pp. 297-326, National Foreign Language Research Center, University of Hawaii, 2010年, 単著Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)“The Contrast Culture Method in Japan: Past, present and future.”SIETAR Japan Newsletter,
Spring, 2010年, 単著(2)“Capitalizing the “P” in pragmatics.”The Intercultural Communication Interest Section Newsletter,
Vol. 7, No. 2, 2010年, 単著Ⅳ.学会発表
(1)“Conversation Analysis and the basics of debate.”36th Annual JALT International Conference, 於:Nagoya, 2010年11月20日
(2)“Tolerance for diversity: No laughing matter.”25th Annual SIETAR Japan Conference, 於:Bunkyo Gakuin University, 2010年10月31日
(3)“That's just not funny: Cultural differences in the use of humor.”25th Annual SIETAR Japan
Conference, 於:Bunkyo Gakuin University, 2010年10月31日(4)“Invited panel: The interactional competence of second language learners.”18th International

- 105 -
Conference on Pragmatics and Language Learning, 於:Kobe University, 2010年7月18日(5)“The Contrast Culture Method: When teachers and students hold divergent views.”9th Annual
Pan SIG Conference, 於:Osaka Gakuin University, Osaka, 2010年5月23日(6)“From Conversation Analysis to language learning.”44th TESOL Annual Convention, 於:Boston,
MA. 2010年3月25日(7)“The cultural competence of non-native English speaking teacher candidates.”44th TESOL
Convention, 於:Boston, MA. 2010年3月25日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)“The Contrast Culture Method for foreign exchange students at Osaka Gakuin University.”International Center, 於:Osaka Gakuin University, 2010年11月27日
(2)“Contrast Culture Method workshop for homestay families.”Study Abroad Program, International
Center, 於:Osaka Gakuin University, 2010年10月9日(3)“Workshop on Contrast Culture Method.”For Rotary Peace Scholars and JICA-sponsored
graduate students, 於:International Christian University, Mitaka, Tokyo, 2010年10月2日(4)“Invited lecture: Conversation Analysis: Practical applications for the classroom.”JALT, 於:Oita
chapter, 2010年9月18日(5)“Special lecture and workshop.”All Osaka English Teachers Association (workshop for 50th
Annual Speech Contest Kinki Region), 2010年7月25日(6)“Invited workshop: Intercultural Training: Exchange students in Japan.”Study Abroad program,
International Center, Osaka Gakuin University, 於:Osaka, 2010年6月15日(7)“Special invited lecture, Comprehensibility and Speaking English.”University of Hyogo,
Gakuentoshi, 於:Kobe, 2010年3月18日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)Society for Intercultural Education Training and Research Co-Program Chair. Apr. 2000-present
(2)Pragmatics Special Interest Group of JALT Program Chair 2010年11月
井上 文彦(いのうえ・ふみひこ)〔カウンセリング,ゲシュタルト療法〕Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)「自家浄化装置の勧め~聴き手の精神衛生のために~」, 『関西いのちの電話広報誌』№137,
2010年12月Ⅳ.学会発表
(1)自主シンポ「ゲシュタルト療法の実践と課題」指定討論者, 日本心理臨床学会, 於:東北大学,
2010年8月4日(2)「ゲシュタルト療法に魅せられて」, 日本臨床ゲシュタルト療法学会, 於:追手門学院大学大
阪城スクエア, 2010年12月5日(3)シンポ「教育に活かしたゲシュタルト療法」座長, 日本臨床ゲシュタルト療法学会, 於:追手
門学院大学大阪城スクエア, 2010年12月5日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)「マイクロ・カウンセリングを取り入れたロールプレイ連続実習」, 於:関西カウンセリングセンター , 2010年5月16日・5月23日
(2)「カウンセリング概論」, 関西いのちの電話, 於:博愛社, 2010年5月20日(3)「ゲシュタルト療法ワークショップ」, 日本ゲシュタルト療法研究所, 於:高野山普賢院, 2010
年8月6~9日(4)「ゲシュタルト療法の理論と実習」, 京都国際福祉センター , 於:同センター , 2010年10月16
日

- 106 -
(5)「グループ・カウンセリング(実習)」, 関西カウンセリングセンター , 於:PLP会館, 2010年12
月6日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)関西いのちの電話 理事 2006年10月~(2)日本臨床ゲシュタルト療法学会 常任理事 2010年12月~
Johnston, Scott(ジョンストン・スコット)〔Culture, International Programs, Writing Centers〕Ⅰ.著訳書
(1)“Handbook on Starting and Running Writing Centers in Japan.”Osaka Jogakuin College, 2010年3月, 共著
Ⅱ.学術論文(1)“Developing Cultural Sensitivity: An Intercultural Simulation Plus.”Asian Conference on the Arts
and Humanities & Social Studies 2010 Proceedings, 2010年6月18日, 単著(2)“Writing Centers and Tutoring in Japan and Asia. (2010).”In A.M. Stoke (Ed.), JALT2009
Conference Proceedings, Tokyo: JALT, 共著Ⅳ.学会発表
(1)“Developing Cultural Sensitivity: An Intercultural Simulation Plus.”Asian Conference on the Arts
and Humanities & Social Studies 2010 Conference, 於:Osaka, 2010年6月19日(2)“Networking among Writing Centers.”2nd Japan Writing Center Symposium, 於:Tokyo, 2010年
2月17日
香川 孝三(かがわ・こうぞう)〔労働法,アジア法〕Ⅰ.著訳書
(1)“2010 Employment Terms and Conditions in Asia Pacific.”Watson Wyatt Worldwide, Singapore
and Hong Kong, 2010年3月, 共著(2)『グローバル化の中のアジアの児童労働』, 明石書店, 2010年4月
Ⅱ.学術論文(1)「中国の児童労働」, 平成19-21年度科研費基盤研究(B)研究成果『子どもの安全保障の国際
学的研究』, 2010年3月(2)「アセアン諸国の労働運動」, 『世界の労働』60巻7号, pp.14-23
(3)「ILOのカンボジア工場改善プログラム-労働基準監督の技術協力」, 『季刊労働法』230号,
pp.167-181
Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)(1)case comment “Obayashi Facilities Ltd. v. X.”Supreme Court (Second Petty Bench) Judgment, 19
October 2007, International Labour Law Reports, vol.28, 2010年1月(2)「2009年のカンボジア・スタディツアーの概要」, アジア・ボランティアセンター編『新しい
国で見つめる社会・歴史・NGO』, 2010年2月(3)「労働と法-アジアに進出した日本企業における労使紛争」, 『労働法律旬報』1717号, 2010年
5月(4)「自著を語る」, 『大阪女学院ハイライト』155号, 2010年6月(5)「ゼミ・コメント」, 『IMF・JC』299号, 2010年8月(6)判例評釈「派遣先の受け入れ拒否に基づく派遣元の雇用継続拒否が解雇権濫用とされた事例」,
名古屋高判平成19・11.16『ジュリスト』1406号, 2010年9月(7)書評「平安朝の父と子――貴族と庶民の家と養育」, 中公新書, 2010年2月『日本ジェンダー研
究』13号, 2010年9月

- 107 -
(8) シンポジウム「東アジアにおける労働紛争処理システムの現状と課題」, 『日本労働法学会誌号』116号, 2010年10月
(9)「国際共生と国益」, 『大阪女学院大学国際共生研究所通信』第2号, 2010年11月Ⅳ.学会発表
(1)「東アジアにおける労働紛争処理システムの現状と課題」, 日本労働法学会, 於:名古屋大学,
2010年5月(2)「アジアにおける非正規労働者」, アジア法学会, 於:青山学院大学, 2010年6月(3) “Legal Remedies to Suicide Caused by Overwork (Karoujisatsu).”Asian Society of Labour Law,
Manila Biennial Conference, 於:University of the Philippines College of Law, 2010年11月
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)講演「労働契約法」, IMF・JC労働リーダーシップコース, 於:関西セミナーハウス, 2010年1月(2)講演「アジアの児童労働」, 京都女子大学公開講座, 2010年6月(3)「ベトナムの戦禍を超えて-竹と詩の国の今は」, 環境と文化・京都会議2010(京都生涯教育
研究所と日本ペンブラブの共催), 於:同志社大学, 2010年10月(4)講演「いくつかの省庁における法整備支援論」, 神戸大学大学院国際協力研究科, 2010年11月
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)日本ジェンダー学会 副代表(2)日本労務学会 理事(3)アジア法学会 理事・学術奨励賞審査委員長(4)兵庫県労働運動史編纂委員会 委員長(5)IMF・JC労働リーダーシップコース 副校長・運営委員(6)NPO法人アジアボランティアセンター 副代表・理事(7)社団法人関西産業関係研究所 理事・主任研究員(8)国際京都学協会 常務理事・事務局長(9)竹文化振興協会 理事(10)京都生涯教育研究所 理事(11)宝ホールディングス株式会社 監査役(12)宝酒造株式会社 監査役(13)Asian Society of Labour Law Member of Executive Board
Ⅶ.科学研究費補助金等の公的研究補助を受けた研究(1)「東アジア諸国における労働法整備と労働契約法制の展開」科研費基盤研究(B)研究分担
者(代表・藤川久昭青山学院大学教授) 平成20~22年度
梶原 直美(かじはら・なおみ)〔古代キリスト教思想史〕Ⅱ.学術論文
(1)「魂についてのオリゲネスの教説に関する一考察」(関西学院大学神学研究会), 『神學研究』57号, pp.55-65, 2010年3月発行, 単著
Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)(1)「学生と大学教育について」, 『キリスト教学校教育』636号, 2010年9月15日, 単著
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「学生と大学教育について」(キリスト教学校教育同盟百周年記念関西地区パネルディスカッ
ション), キリスト教学校教育同盟, 於:頌栄短期大学, 2010年5月15日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)キリスト教学校教育同盟 大学部会関西地区委員 1998年4月より現在まで(2)キリスト教学校教育同盟 中央教育研究委員 2002年4月より現在まで

- 108 -
(3)全国大学チャプレン会 理事 2010年7月より現在まで
加藤 映子(かとう・えいこ)〔言語習得〕Ⅱ.学術論文
(1)「ダイアロジックトレーニング:Before & After」, 『大阪女学院大学紀要』第6号, 2010年3月Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)「プロジェクト3 外国人児童生徒のための言語教育モデルの研究」, 『大阪女学院大学国際共生研究所通信』第2号, 2010年11月
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「専門を英語で教える」, 大阪女学院大学FD, 於:大阪女学院大学, 2010年7月21日(2)“Mother Child Interactions during Book Reading and Maternal Beliefs about Book Reading”, The
Korean Society of Linguistics. Language Acquisition Research Group, 於:ソウル ソガン大学,
2010年9月18日(3)「発音と文法指導を重視した言語スキルの統合教育-TOEICに見る劇的成果-」, 第12回英語
教育総合教育研究会シンポジウム「英語運用力の底上げ」-リメディアルとESPが鍵-, 於:大阪大学大学院言語文化研究科, 2010年12月12日
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)言語科学会 運営委員(2)コンピュータ利用教育学会 国際交流委員会委員
小松 泰信(こまつ・やすのぶ)〔図書館情報学〕Ⅱ.学術論文
(1)「現在の図書館情報学教育に対する要請について考える」, 『桃山学院大学総合研究所紀要』,
2010年6月30日, 共著Ⅳ.学会発表
(1)「大学と大学図書館の近未来」, 桃山学院大学司書課程, 於:桃山学院大学, 2010年10月26日
黒澤 満(くろさわ・みつる)〔国際法,国際関係論〕Ⅰ.著訳書
(1)“The US-India Civil Nuclear Cooperation Agreement: A Japanese Point of View.”Subrata Ghoshroy
and Gotz Neuneck (eds.), South Asia at a Crossroad, Nomos, Germany, pp.280-286, 2010年5月,
単著(2)“Global Nuclear Disarmament: A Japanese Perspective,” Subrata Ghoshroy and Gotz Neuneck
(eds.), South Asia at a Crossroad, Nomos, Germany, pp.316-322, 2010年5月, 単著Ⅱ.学術論文
(1)「プラハ演説からNPT再検討会議へ」, 『Plutonium』No.68, pp.14-21, Winter 2010, 2010年2月, 単著
(2)“Background for President Obama's Nuclear Policy.” 『大阪女学院大学紀要』第6号, pp.17-29,
2010年3月, 単著(3) “From Prague Speech to the NPT Review Conference.” Plutonium, No.68, Winter 2010. pp.13-21,
2010年3月, 単著(4)「2010年NPT再検討会議」, 『阪大法学』第60巻第3号, pp.237-266, 2010年9月, 単著
Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)(1)「開け核なき世界の扉」, 『中国新聞』, 2010年1月1日, 単著(2)「軍縮/平和」, 『imidas e Library(2010)』, 集英社, 2010年2月, 単著

- 109 -
(3)「核兵器のない世界に向けて」, 開発教育協会『DEAR』143号, pp.2-4, 2010年2月, 単著(4)「『核兵器のない世界』求める新たな変化と展望」, 非核の政府を求める会『鳩山政権下、非核
日本の道を探る』, pp.14-21, 2010年2月, 単著(5)「武力行使禁止の国際規範を」, 『長崎新聞』, 2010年2月14日, 単著(6)「核兵器はなくせる」, 『中国新聞』, 2010年2月28日, 単著(7)「NPT再検討会議の成功に向けて」, 『聖教新聞』, 2010年3月25日, 単著(8)「核軍縮に関する国際情勢(16):2010年NPT再検討会議に向けて」, 『平和の風』第16号, pp.10-
13, 2010年4月, 単著(9)「核軍縮の世界:日本は積極的な提言を」, 『佐賀新聞』, 2010年4月17日, 単著(10)「米国が主導する核軍縮」, 『北海道新聞』, 2010年5月1日夕刊, 単著(11)「検証NPT再検討会議:成功だが内容乏しく」, 『毎日新聞』, 2010年6月18日, 単著(12)「核兵器廃絶へ、NPT後の課題は」, 『しんぶん赤旗』, 2010年8月5日, 単著(13) 「2010年NPT再検討会議の成果とその意義(上)」, 『非核の政府を求める会ニュース』第252号,
2010年9月15日, 単著(14) 「日本平和学会部会Ⅰ:核なき世界に向けて:核軍縮の可能性」報告, 『日本平和学会ニュー
ズレター』第19巻2号, pp.2-3, 2010年9月25日, 単著(15) 「『核なき世界』に向けて:NPT再検討会議の成果を踏まえて」, 日本国際問題研究所『国際問
題』No.595, pp.1-3, 2010年10月, 単著(16) “PSAJ Spring Conference/Session I: Toward a World without Nuclear Weapons: Possibility of
Nuclear Disarmament.” Peace Study Bulletin, No.29, pp.5-6, 2010年10月, 単著(17) 「2010年NPT再検討会議の成果とその意義(中)」, 『非核の政府を求める会ニュース』第253号,
2010年10月15日, 単著(18) 書評「吉田文彦『核のアメリカ-トルーマンからオバマまで』岩波書店,2009年」, 日本平和
学会編『核なき世界に向けて』, 早稲田大学出版会, pp.172-175, 2010年10月, 単著(19) 「2010年NPT再検討会議の成果とその意義(下)」, 『非核の政府を求める会ニュース』第254号,
2010年11月15日, 単著(20) 「核軍縮の新たな流れ:好機を逃すな」, 日本原子力学会誌『ATOMOΣ』Vo.52, No.12, pp.2-
3, 2010年12月1日, 単著Ⅳ.学会発表
(1)“Forthcoming NPT Review Conference, 2010.”U.S.-Japan Track II Meeting on Arms Control,
Disarmament, Nonproliferation and Verification, 於:Washington, D. C., U.S., 2010年1月19-20日(2)「核軍縮に関する諸課題」, 日本軍縮学会シンポジウム, 於:東京, 2010年4月25日(3)「2010年NPT再検討会議の審議および最終文書の検討」, 日本国際連合学会, 於:名古屋、南山
大学, 2010年6月26日(4)“Arms Reduction, New START and Pursuit of a World without Nuclear Weapons: Japanese
Perspective.”U.S.-Japan-ROK Trilateral Dialogue on Nuclear Issues, 於:Tokyo, 2010年9月7-8日(5)「オバマの核政策:アメリカはオバマでCHANGEしたか?」, 関西日米フォーラム・関西大学
法学部, 於:大阪, 2010年9月25日(6) “Japan's Nuclear Policy under Democratic Party of Japan.”U.S.-Japan-ROK Trilateral Dialogue on
Nuclear Issues, 於:Seoul, Republic of Korea, 2010年12月6-7日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)「今日の世界:核廃絶の行方」, NHK BS1, 於:東京, 2010年1月4日(2)「核不拡散をめぐる国際情勢」, 平成21年度保証措置セミナー , 核物質管理センター , 於:東京,
2010年1月15日(3)「2010年NPT再検討会議:好機と課題」, 核兵器廃絶-地球市民集会ナガサキ, 於:長崎, 2010

- 110 -
年2月6-8日(4) “Nuclear Disarmament: Possibilities for Progress in 2010.”The University of Auckland, 於:New
Zealand, 2010年3月8日(5) “Japan's Nuclear Policy.”The University of Auckland, 於:New Zealand, 2010年3月10日(6)「核の現状とICNND報告の意義」, 平成21年度長崎市平和推進専門会議, 於:東京, 2010年3月
23日(7)「核不拡散の現状と課題」, NHK報道局国際部勉強会, NHK, 於:東京, 2010年4月9日(8)「我が国の軍縮外交」, 参議院国際・地球温暖化問題調査会, 参議院, 於:東京, 2010年4月21日(9)「核と平和」, 大阪女学院大学アッセンブリープログラム, 於:大阪, 2010年6月16日(10)「NPT再検討会議の成果と限界-核軍縮に関する行動計画を中心に」, IPPNW日本支部講演会,
於:広島, 2010年7月17日(11)「2010年NPT再検討会議の成果とその意義-核軍縮に関する行動計画を中心に」, 非核の政府
を求める会, 於:東京, 2010年7月30日(12)「2010年NPT再検討会議の検証および核兵器廃絶に向けた更なる取組みについて」, 2010ピー
ストークin広島, 於:広島, 2010年8月5日(13)「2010年NPT再検討会議の検証および核兵器廃絶に向けた更なる取組みについて」, 2010ピー
ストークin長崎, 於:長崎, 2010年8月8日(14)「日印原子力協力協定」, TBSテレビ, NEWS23クロス, 於:東京, 2010年9月1日(15)「核軍備管理・軍縮-2010年NPT再検討会議を中心に」, 第9回軍縮・不拡散問題講座, 日本
国際問題研究所, 軍縮・不拡散促進センター , 於:東京, 2010年9月14日(16)「核不拡散をめぐる国際情勢:2010年NPT再検討会議を中心に」, 平成22年度保障措置セミ
ナー , 核物質管理センター , 於:東京, 2010年9月15日(17)「日本のアカデミアにおける平和研究の現状と展望」, 於:長崎大学, 2010年9月18日(18)「核兵器のない世界に向けての国際法の役割-2010年NPT再検討会議の議論を中心に-」, 大
阪弁護士会憲法問題特別委員会学習会, 於:大阪, 2010年10月22日(19)「核兵器のない世界を-NPT再検討会議後の課題」, 2010年国連軍縮週間のつどい, 原水禁大
阪府協議会, 於:大阪, 2010年10月30日(20)「2010年NPT運用検討会議の検証」, 核軍縮・不拡散研究会, 於:東京, 2010年11月24日
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)日本軍縮学会 会長(2)世界法学会 理事(3)核物質管理センター 理事(4)日本国際問題研究所軍縮・不拡散促進センター 客員研究員(5)長崎市平和推進専門会議 委員(6)Editorial Board of the Nonproliferation Review Member
(7)核戦争防止医師会議大阪府支部 特別顧問(8)岡田外務大臣核軍縮・不拡散有識者懇談会 座長
馬渕 仁(まぶち・ひとし)〔教育社会学,国際教育,多文化教育〕Ⅰ.著訳書
(1)『クリティーク 多文化,異文化』, 東信堂, 2010年6月, 単著Ⅱ.学術論文
(1)「多文化共生は可能か? ―公開研究会から大会、そしてその後―」, 『異文化間教育』32号,
2010年7月, 単著

- 111 -
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「多文化教育」部会(司会), 第31回異文化間教育学会, 於:奈良教育大学, 2010年6月12日(2)「異文化と教育」部会(司会), 第62回日本教育社会学会, 於:関西大学, 2010年9月19日(3)「オーストラリアの教育改革」研究推進委員会発表(司会), 第14回オセアニア教育学会, 於:
東京学芸大学, 2010年12月12日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)異文化間教育学会 理事 2003年~(2)日本国際文化学会 常任理事 2008年~
Ⅶ.科学研究費等の公的な研究補助を受けた研究(1)「日本における多文化教育の構築に関する研究―外国人児童生徒と共に学ぶ学校教育の創造」
科学研究費補助金基盤B 2010~2012年度
前田 美子(まえだ・みつこ)〔比較・国際教育,開発教育,理科教育〕Ⅳ.学会発表
(1)「ケニアの教育現場における文化のハイブリッド化」, 日本アフリカ学会第47回学術大会, 於:奈良県文化会館, 2010年5月30日
(2)「カンボジアの教員と不正行為」, 日本比較教育学会第46回大会, 於:神戸大学, 2010年6月27
日(3)“Heightened awareness of a researcher's own culture through carrying out research on
development cooperation.” Symposium on Special Issue of Comparative Education “Conducting
Education Research in Confucian Heritage Cultures”, 於:香港大学, 2010年11月5日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)講演「途上国の教育と日本の支援」, 兵庫県私立中学高等学校副校長・教頭会研修会, 於:兵庫県私学会館, 2010年6月17日
(2)報告「学校教育における不正行為―カンボジアを事例として」, 第15回大阪女学院大学平和・人権研究会, 於:大阪女学院大学, 2010年11月12日
(3)研修講師「授業研究による質の改善」, 平成22年度JICAケニア国別研修「初等理数科指導法改善」, 於:鳴門教育大学, 2010年11月19日
Ⅶ.科学研究費等の公的な研究補助を受けた研究(1)「教員の不正行為に関する研究-カンボジアを事例として」科学研究費補助金 基盤研究C
研究代表者 2009~2012年度(2) 「途上国の授業文化に関する研究:生徒観・教師観・授業観を中心に」科学研究費補助金
挑戦的萌芽研究 研究分担者 2010~2011年度
McCarty, Steve(マッカーティ・スティーブ)〔Bilingualism, e-Learning, Japan〕Ⅰ.著訳書
(1)“Social Media to Motivate Language Learners from Before Admission to After Graduation.”In
Chan W.M., Chin K.N., M. Nagami & T. Suthiwan (Eds.), Media in Foreign Language Teaching and
Learning, National University of Singapore, Centre for Language Studies, pp.87-105, 2010 年12月,
単著Ⅱ.学術論文
(1)“Bilingual Child-Raising Possibilities in Japan.”チャイルド・リサーチ・ネット, 2010年6月, 単著
(2)“Bilingualism Concepts and Viewpoints.”チャイルド・リサーチ・ネット, 2010年4月, 単著

- 112 -
Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)(1)“Japanese People and Society.”General Orientation (JICAの発行したCD-ROMの章), 2010年2月,
単著(2)「日本でできるグローバル体験 ~英語や異文化の取り入れ方~」, 『Worldwide Kids English
Parents’ Website』, 2010年2月, 単著Ⅳ.学会発表
(1)“Video Production for Community Outreach.” International Association of Teachers of English
as a Foreign Language, Learning Technologies SIG, 於:名古屋商科大学大学院, 2010年2月19日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)“Japanese People and Society.”JICA国際協力センター , 於:茨木市, 2010年1月13日他Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)World Association for Online Education 名誉会長&ウェブマスター 2007年―現在に至る(2)Asia-Pacific Association for Computer-Assisted Language Learning 広報委員 2007年―現在に
至る(3)ベネッセ コーポレーション Worldwide Kids English メーン監修 2006年―現在に至る(4)Child Research Net Advisory Board Member 2001年―現在に至る
元 百合子(もと・ゆりこ)〔国際人権法・国際関係学〕Ⅱ.学術論文
(1)“Right of Ethnic Minorities to Education in Japan: Its Realities and International Human Rights
Standards”大阪経済法科大学21世紀社会研究所紀要, 創刊号, 2010年3月, 単著(2)「日本軍性奴隷制と複合差別」, 『女性・戦争・人権学会,学会誌』第10号, 2010年12月, 単著(3)「マイノリティの権利としての母語学習と民族教育:日本の現状と国際人権基準」, 『国際人
権(国際人権法学会,学会誌)』第21号, 2010年10月, 単著Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)「モントリオール国際女性会議」, 『IMADR-JC通信(反差別国際運動日本委員会)』第164号,
2010年11月, 単著Ⅳ.学会発表
(1)“Right of Ethnic Minorities to Education in Japan: Its Realities and International Human Rights Standards”, International Conference on East Asian Studies, 於:ロシア国立極東大学(ウラジオストック), 2010年9月9-10日
(2)「マイノリティの人権としての民族教育権:日本の現状と国際人権基準」, 大阪女学院大学国際共生研究所, 於:大阪女学院大学, 2010年2月2日
(3)「マイノリティ女性に対する複合差別」, 複合差別研究会, 於:大阪女学院大学, 2010年2月20
日(4)「複合差別の視点から見た日本軍性奴隷制」, 東北アジア平和構想研究会, 於:関西学院大学,
2010年4月24日(5)「日本のマイノリティ女性に対する複合差別」, モントリオール国際女性会議, 於:カナダ, モ
ントリオール, 2010年8月13-16日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)「人権の視点から見た多文化共生」, 大阪女学院大学国際共生研究所, (財)アジア・太平洋人権情報センター共催「シンポジウム:若者が語る多文化共生」, 於:大阪女学院大学, 2010年11月27日

- 113 -
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)日本国際人権法学会 企画委員(2)反差別国際運動日本委員会 企画運営委員
Ⅶ.科学研究費等の公的な研究補助を受けた研究(1)マイノリティ女性に対する複合差別に関する政策と制度の比較研究 研究代表者 2008年4
月~2011年3月(2) アジア・太平洋地域の大学院「人権プログラム」の学際的調査・研究 グループ研究 2008
年4月~2011年3月
中垣 芳隆(なかがき・よしたか)〔教職,英語〕Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)「子どもたちの現状と課題」, 大阪府豊能地区青少年問題協議会, 於:箕面市市民会館, 2010年2月27日
中井 弘一(なかい・ひろかず)〔実践英語授業学〕Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)『学びの手引き』, 大阪女学院大学・大阪女学院短期大学, 2010年3月, 共著(主担)(2)「巻頭エッセイ-デザイン力の大切さ」, 『教員養成センター newsletter 創刊号』, 大阪女学院
大学・大阪女学院短期大学, 2010年4月1日(3)「特集教職課程開設記念教員研修報告」, 『教員養成センター newsletter 創刊号』, 大阪女学院
大学・大阪女学院短期大学, 2010年4月1日(4)「授業の玉手箱」, 『教員養成センター newsletter 創刊号』, 大阪女学院大学・大阪女学院短期
大学, 2010年4月1日(5)「英語の教え方教室第1回・2回報告」, 『教員養成センター newsletter 第2号』, 大阪女学院大学・
大阪女学院短期大学, 2010年7月13日(6)「教員免許状更新講習2010報告」, 『教員養成センター newsletter 第3号』, 大阪女学院大学・大
阪女学院短期大学, 2010年10月10日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)「これから求められるディベート能力の育成-論理的に話す力の育成」, 大阪市教育委員会,
事務職員悉皆研修, 2010年7月22日, 8月3, 4日(2)「コミュニケーションのための教室英文法再考」, 門真市教育委員会, 平成22年度門真市中学
校英語「コミュニケーション」研修会, 2010年7月28日(3)「ディベートの基本-論理的に考えるということ」, 兵庫県立三木高等学校, 2010年10月7日(4)「ディベートの基本-論理的に考えるということ」, 兵庫県立姫路飾西高等学校, 2010年7月8
日, 12月14日(5)「日本人教員が『英語の授業は英語で行う』に近づくために考えるべきこと」, 京都産業大学
英語教育研究会, 平成22年度公開講座, 2010年8月(6)「ディベートのおもしろさ」, 兵庫県立西宮西高等学校, 2010年12月1日
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)大阪府立泉陽高等学校 英語教育運営指導委員 2009-2010
西井 正弘(にしい・まさひろ)〔国際法〕Ⅱ.学術論文
(1)「国際法からみた我が国の安全保障法制の特徴」, 『社会システム研究』第13号, pp.1-12, 2010
年3月31日, 単著

- 114 -
Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)(1)「環境と人権問題の関わり」, 『人権口コミ講座』11(京都人権啓発推進会議), pp.17-18, 2010年
3月, 単著(2)書籍紹介「『グローバル化の中のアジアの児童労働―国際競争にさらされる子どもの人権』
香川孝三著」, 『大阪女学院大学国際共生研究所通信』第2号, pp.4, 2010年11月8日, 単著(3)「外交講座開催」, 『大阪女学院ハイライツ』第157号, pp.9, 2010年12月17日, 単著
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「環境と人権と貿易の関わり」, KBS京都放送ラジオ「京都人権情報」, 於:KBS京都, 2010年2月
5日(2)「テロ対策をめぐる世界的動向」, 芦屋市「高齢者大学」, 於:芦屋市市民センター本館, 2010年
9月8日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)(財)国際法学会 評議員 1997年5月~現在(2)世界法学会 理事 1996年5月~現在(3)環境法政策学会 理事 2003年6月~現在(4)Development of International Law in Asia(DILA) 理事・副議長 2006年~2012年(5)(社)京都勤労者学園 学園長 2007年6月~2010年6月
Ⅶ.科学研究費等の公的な研究補助を受けた研究(1)「条約遵守制度に関する包括モデルの探求―地球環境・人権・軍備管理における創造的展開」
住友財団環境研究助成2008年度 2008年10月~2010年5月
奥本 京子(おくもと・きょうこ)〔平和学,紛争転換論,非暴力介入論,文学,演劇論〕Ⅱ.学術論文
(1)「ヒロシマ・ワークショップ実施報告:トランセンド・トレーナー養成講座/ NARPIパイロット・プロジェクト」, 『トランセンド研究:平和的手段による紛争の転換』第8巻第2号, 2010年12月, 共著
Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)(1)「NARPI進捗状況(東北アジア地域平和構築インスティチュート)」, 『非暴力平和隊・日本(NPJ)
ニューズレター』第32号, 2010年1月19日, 単著(2)「NPC代表パク・ソンヨンさんとの交流,非暴力行動トレーニングに関する日韓共同開発,
そして,NARPI進捗状況についての報告」, 『非暴力平和隊・日本(NPJ)ニューズレター』第34号, 2010年6月1日, 単著
(3)「NARPIパイロット・プロジェクト実施報告」, 『非暴力平和隊・日本(NPJ)ニューズレター』第35号, 2010年9月28日, 単著
Ⅳ.学会発表(1)「平和ワークにおける芸術アプローチ(Arts-based Approachs in Peace Work)」, 大阪女学院大
学 研究活動委員会 学内研究会, 於:大阪女学院大学, 2010年3月9日(2)「グローバル・ガバナンスとNGO──成果・課題・展望」, 日本NPO学会第12回年次大会, 於:
立命館大学衣笠キャンパス, 2010年3月14日(3)「『平和的感性』と『批判的精神』について:平和学の視点から<共生>は何を意味するのか」,
大阪女学院大学 第12回平和・人権研究会, 於:大阪女学院大学, 2010年6月16日Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)
(1)「紛争転換ワークショップ」, 東北芸術工科大学 芸術文化論(芸術と平和学)講座, 於:東北芸術工科大学, 2010年1月7日
(2)「外国語を学ぶ=>社会・世界の問題を解決する!」, 高大連携 私立宣真高等学校, 於:宣

- 115 -
真高等学校, 2010年1月18日(3)「平和学ワークショップ 2009年度 地域別研修 『仏語圏アフリカ平和構築』」, 国際協力機
構(JICA), 於:JICA東京, 2010年2月18日(4)「平和学と紛争転換~身近な対立から国際関係まで~」, 西鈴蘭台9条の会, 於:すずらん多目
的ホール, 2010年2月20日(5)「紛争をトランセンドしよう~平和創造の方法を共に考える~」, おおさか社会フォーラム
<もうひとつの世界は可能だ! Another World Is Possible!>, 於:エルおおさか, 2010年3月22
日(6)「トランセンド・メソッド・ワークショップ」, 日本女子大学, 於:日本女子大学目白校キャ
ンパス附属豊明小学校, 2010年6月19日(7) 「紛争転換ワークショップ」, 東北芸術工科大学 芸術文化論(芸術と平和学)講座, 於:東北芸
術工科大学, 2010年7月20日(8)「トランセンド・トレーナー養成講座+NARPIパイロット・プロジェクト」, NARPI日本ネッ
トワーク, トランセンド研究会, 非暴力平和隊・日本, ピースボート, ハーグアピール平和教育地球キャンペーン, ワールドフレンドシップセンター , 大竹財団, 於:広島市国際青年会館,
8月20日~24日(9)「NARPIワークショップ」, NARPI, ピースボート, 於:オセアニア号船上, 2010年10月24日
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)国際トランセンド コンビーナー(東北アジア地域代表) 2006年~現在に至る(2)トランセンド(平和的手段による紛争転換)研究会 会長 2008年11月24日~現在に至る(3)非暴力平和隊・日本 理事 2003年1月31日~現在に至る(4)日本平和学会 平和と芸術分科会 責任者 2005年6月4日~現在に至る(5)財団法人大阪国際平和センター(ピースおおさか) 企画運営委員(展示専門部会) 2007年4
月1日~2011年3月31日(6)同上 運営協力懇談会委員 2007年8月12日~2011年8月11日(7)日本平和学会 第19期企画委員会委員 2010年1月~2011年12月(8)日本平和学会 分科会責任者連絡会議 副世話人 2009年6月~2011年6月(9)NARPI(Northeast Asia Peace Research Institute) 運営委員会委員 2009年~現在に至る(10)日本平和学会 第19期理事 2010年1月~2011年12月(11)ACTION Asia Leader 2010年11月~現在に至る
関根 聴(せきね・あきら)〔社会学・家族社会学・福祉社会学・ジェンダー論〕Ⅱ.学術論文
(1)「高齢社会における世代関係」, 『吉備国際大学大学院社会学研究科論叢11号』, 2010年3月, 単著
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「男女共同参画推進条例制定記念シンポジウム」パネリスト, 八尾市主催, 於:八尾市文化会館,
2010年6月5日(2)「女性が長生きするということ(高齢社会と女性問題)」, 茨木市健康福祉部高齢福祉課主催「い
ばらきシルバーカレッジ:現代社会を読み解くコース」講師(講演), 於:茨木市立生涯学習センターきらめき, 2010年10月17日
(3)「男女がともに分かちあう介護~家族を支えるための準備~」, 綾部市教育委員会主催 人権セミナー 講師(講演), 於:吉美公民館, 2010年10月23日
Ⅵ.学会および公的な機関の委員(1)大阪市男女共同参画審議会 委員, 専門調査部会 副部会長 2009年8月~2011年8月

- 116 -
(2)高槻市男女共同参画審議会 委員 2009年11月~2011年11月(3)八尾市男女共同参画審議会 副会長 2010月9月1日~2012年8月31日(4)八尾市男女共同参画推進にかかる条例検討委員会 副座長 2009年6月~2010年3月(5)高槻市男女共同参画センター 男性セミナー企画運営委員会 委員長 2010年4月~2011年3
月(6)学校法人池田五月山教会学園 評議員 2008年4月~2012年3月(7)東大阪市社会福祉協議会:福祉と人権 推進委員会 オブザーバー 2005年11月~
関根 秀和(せきね・ひでかず)〔高等教育論,社会学〕Ⅱ.学術論文
(1)「シンポジウム「学士課程における教養教育のあり方」をめぐって- 「学士課程教育」以前 -」,
『大学教育学会誌』第32巻1号, 大学教育学会, 2010年5月Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)「短期大学基準協会が新たに目指すところ「認証評価」の漂流を超えて 」, 『News Letter』Vol.52, 短期大学基準協会, 2010年10月
Ⅴ.その他の発表(シンポジウム・講演・放送等)(1)「私立大学の教育・研究充実に関する研究会(短期大学の部)」討議・コーディネーター , 於:
東京 アルカディア市ヶ谷, 2010年11月4日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)大学教育学会 常任理事(2)近畿都市学会 評議員(3)キリスト教文化学会 理事(4)大学評価・学位授与機構 評議員(5)短期大学基準協会 副理事長・第三者評価委員会 委員長(6)日本私立短期大学協会 副会長(7) 大阪私立短期大学協会 会長
Swenson, Tamara(スウェンソン・タマラ)〔Media, Mass communication, Language acquisition,
Japanese society〕Ⅱ.学術論文
(1)“Representations of homelessness: A frame analysis of Japanese newspaper coverage.”
Communication Association of Japan Conference Proceedings, vol. 40, 2010年6月, 共著Ⅳ.学会発表
(1)“Representations of homelessness: A frame analysis of Japanese newspaper coverage.”
Communication Association of Japan(日本コミュニケション研究学会国際大会), 於:Tokyo(明治大学, 東京), 2010年6月20日
(2)“Beyond watchdogs and mouthpieces: Taking the state-owned press seriously.”International
Communication Association (ICA)(国際メディアとコミュニケーション研究学会国際大会),
於:Singapore, 2010年6月26日(3)“Narrative frames to assess overseas experiences.”Japan Association for Language Teaching
International Conference (全日本言語教育学会), 於:Nagoya (名古屋), 2010年11月20日

- 117 -
Teaman, Brian(ティーマン・ブライアン)〔Linguistics, Phonetics, Computer Assisted Language
Learning〕Ⅳ.学会発表
(1)“Leveraging Emerging Technologies for Speaking.” Fourth annual Wireless Ready International
Symposium, 於:Nagoya Japan, 2010年2月19日(2)“Looking at the Amish from a Japanese student's perspective.” JALT PANSIG 2010, 於:Osaka
Gakuin University, Osaka Japan, 2010年5月22日・23日(3)“MASLE (Machine Aided Spoken Langauge Evaluation) for teaching oral language skills.” CELC
Symposium, 於:National University of Singapore, 2010年5月26日~28日(4)“Speaking On-line via MASLE.” Osaka JALT, 於:Hannan University, Osaka, Japan, 2010年6月27
日Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)Japan Association of Language Teachers, Computer Assisted Language Learning interest group,
Program Chair, 2010年1月1日~12月31日(2)Toyonaka City 3rd Foreign Citizen's Council(外国人市民会議)2009年6月より現在まで
東條 加寿子(とうじょう・かずこ)〔英語教育, e-Learning〕Ⅱ.学術論文
(1)「化学系と機械系の口頭発表における基本語彙」, 『工学教育』56巻6号, 2010年11月, 共著Ⅲ.その他の著作(研究ノート・報告書・雑誌・新聞・ニュースレター等)
(1)"JECPRESE (The Japanese-English Corpus of Presentations in Science and Engineering).", (理工系プレゼンテーション検索サイト)の共同開発, http://www.jecprese.sci.waseda.ac.jp
(2)「英語力の構造を考える」, 『大阪女学院大学教員養成センター NEWS LETTER』第2号, 単著Ⅶ.科学研究費等の公的な研究補助を受けた研究
(1)「理工系口頭発表コーパスに基づいた専門日本語・英語の教育法の開発」 文部科学省科学研究費補助金基盤研究C(研究分担者) 2009年4月~2012年3月
Verity, Deryn(ベリティ・デリン)〔English Language Teaching, Teacher Education〕Ⅰ.著訳書
(1)“The reverse move: Enriching informal knowledge in the pedagogical grammar class.”In Johnson, K. & P. Golembek, (Eds.), Research on Second Language Teacher Education: A
Sociocultural Perspective on Teacher Professional Development, ESL & Applied Linguistics
Professional Series, Publisher: Routledge, 2010年12月, 単著Ⅱ.学術論文
(1)“Big questions: A speaking practice exercise.”The Language Teacher, Tokyo: Japan Association
for Language Teaching, 34(4), pp.59-60, 単著Ⅳ.学会発表
(1)“Ruminations and Connections: Posters as Food for Thought." (with Steve Cornwell)Invited
workshop for A Moveable Feast, sponsored by Osaka JALT, and Teacher Education and Learner
Development SIGs, 於:Osaka, 2010年10月, 共著(2)“CALL and online teacher education--an open discussion." (with Steve Cornwell)JALT CALL
annual conference “CALL: What's your motivation?”Kyoto Sangyo University, 於:Kyoto, Japan,
2010年6月, 共著(3)“Creating a reflective community of online learners." (with Steve Cornwell)JALT CALL annual
conference “CALL: What's your motivation?”Kyoto Sangyo University, 於:Kyoto, Japan, 2010年6

- 118 -
月, 共著(4)“The New School MATESOL: 4 keys to effective online learning." Invited panelist TESOL annual
conference, “Re-imagining TESOL,”, 於:Boston, USA, 2010年3月, 共著Ⅵ.学会および公的な機関の委員
(1)Japan Association of Language Teaching, Special Interest Group for Teacher Education Coordinator 2010年11月