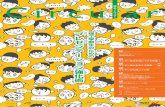電気通信普及財団賞(テレコム自然科学賞)受賞論文´代受賞者...電気通信普及財団賞(テレコム自然科学賞)受賞論文 第1回 入賞 移動体データ伝送におけ
第21回BELCA賞決定 · 2012. 2. 10. ·...
Transcript of 第21回BELCA賞決定 · 2012. 2. 10. ·...
-
平成24年2月10日
公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA)
TEL 03-5408-9830 FAX 03-5408-9840
担当:近藤(コンドウ)
第21回BELCA賞決定
公益社団法人 ロングライフビル推進協会(BELCA、会長:山内 隆司)は、ロングライ
フ部門3件、ベストリフォーム部門7件の合計10件を第21回のBELCA賞に決定いたしました
のでお知らせします。(別紙1)
ロングライフ部門 ザ・プリンス箱根 本館
阪神甲子園球場
早稲田大学 2号館
ベストリフォーム部門 石川県政記念 しいのき迎賓館
国立大学法人 東京工業大学 すずかけ台キャンパスG3棟
芝学園 講堂
鶴岡まちなかキネマ
南海ターミナルビル
福岡パルコ
ローム京都駅前ビル
BELCA賞は、良好な建築ストック、つまり社会の中で生き生きと活用される建築の形成に
寄与することを目的に設けられた、我が国初の既存建築物の総合的表彰制度です。賞を2部門に
分け、周到な長期計画で、安定した維持保全を継続しているものをロングライフ部門、巧みな改
修によって既存建築物を活性化し、現代社会に蘇生させたものをベストリフォーム部門と定め、
第1回(平成3年)から今回まで計21回、表彰件数は206件を数えています。
賞の選考は、建築学界、建物所有、設計、建設、設備、メンテナンスといった多分野からなる
「BELCA賞選考委員会」(委員長:内田 祥哉東京大学名誉教授)(別紙2)により行われ
ました。
表彰式は来る平成24年5月15日(火)16時より、東京都中央区日本橋蛎殻町のロイヤルパーク
ホテルで開催される予定です。表彰式では、ロングライフ部門で建物所有者、設計者、施工者、
維持管理者の4者、ベストリフォーム部門で建物所有者、改修設計者、改修施工者の3者が表彰
されます。
なお、受賞建物には賞牌(文化勲章受章者 帖佐美行氏(故人)作)が贈呈されます。
1-1
-
第21回BELCA賞表彰建物(順不同・受賞者名等は今後変更されることもあります)
ロングライフ部門
建物名 所在地 用途 受賞者所有者 設計者 施工者 維持管理者
1 ザ・プリンス箱根 本館 神奈川県足柄下郡 ホテル ㈱プリンスホテル 村野藤吾 清水建設㈱、高砂熱学工業㈱、 ㈱プリンスホテル箱根町元箱根144 ㈱松田平田設計(改修) ㈱関電工、㈱西原衛生工業所、
日本オーチス・エレベータ㈱、㈱川島織物セルコン
2 阪神甲子園球場 兵庫県西宮市 観覧場(野球場) 阪神電気鉄道㈱ ㈱大林組 ㈱大林組 阪神電気鉄道㈱甲子園町1-82
3 早稲田大学 2号館 東京都新宿区 大学(図書館、博物館) 学校法人 早稲田大学 内藤多仲、今井兼次、桐山均一 上遠組 学校法人 早稲田大学西早稲田1-6-1 西谷章(改修)、古谷誠章(改修)、 大成建設㈱東京支店(改修)
大成建設㈱一級建築士事務所(改修)
ベストリフォーム部門
建物名 所在地 竣工年 改修年 用途 受賞者改修前 改修後 所有者 改修設計者 改修施工者
1 石川県政記念 しいのき迎賓館 石川県金沢市 1924年 2010年 県庁舎 複合文化交流施設 石川県 ㈱山下設計 大成建設㈱、兼六建設㈱、広坂2-1-1 (ギャラリー、セミナー室、 ㈱岡組、成瀬電気工事㈱、立野電気工事㈱、
レストラン、事務所等) ㈱柿本商会、みなみ設備工業㈱、鈴木管工業㈱、ホクレイ㈱、三精輸送機㈱
2 国立大学法人 神奈川県横浜市 1979年 2010年 講義・研究室棟 講義・研究室棟 国立大学法人 東京工業大学 国立大学法人 東京工業大学 ㈱淺沼組東京工業大学 緑区長津田町4259 ㈱綜企画設計 ㈱柿本商会すずかけ台キャンパスG3棟 ㈱テクノ工営 ㈱積田電業社
3 芝学園 講堂 東京都港区 1966年 2010年 学校(講堂) 学校(講堂) 学校法人 芝学園 清水建設㈱一級建築士事務所 清水建設㈱芝公園3-5-37 ㈱関電工
大成温調㈱4 鶴岡まちなかキネマ 山形県鶴岡市 1932年 2010年 絹織物工場 映画館 ㈱まちづくり鶴岡 ㈱設計・計画高谷時彦事務所 ㈱佐藤工務、鶴岡建設㈱、㈱マルゴ
山王町13-36 ~ ㈲安芸構造計画事務所 ㈱渡会電気土木、山形空調㈱1936年
5 南海ターミナルビル 大阪府大阪市中央区 1932年 2009年 複合施設 複合施設 南海電気鉄道㈱ ㈱プランテック総合計画事務所 ㈱竹中工務店、㈱錢高組、難波5-1-60 (駅舎・物販店舗 (駅舎・物販店舗 ㈱髙島屋 ㈱竹中工務店 ㈱大林組、南海辰村建設㈱、
・ホテル 他) ・ホテル 他) ㈱大林組 南海ビルサービス㈱6 福岡パルコ 福岡市中央区 1936年 2010年 百貨店 物販店舗 学校法人 都築学園 ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店
天神2-11-1 ㈱パルコ ㈱パルコ
7 ローム京都駅前ビル 京都府京都市下京区 1977年 2010年 テナントオフィス 自社オフィス ローム㈱ ㈱竹中工務店 ㈱竹中工務店塩小路通烏丸西入ル東塩小路町579-32
竣工年(改修年)
1978年(2007年)
1924年
1925年
別紙1
1-2
-
第21回BELCA賞表彰建物写真一覧
ロングライフ部門
ベストリフォーム部門
石川県政記念 しいのき迎賓館
(石川県金沢市)
早稲田大学 2号館
(東京都新宿区)
ザ・プリンス箱根 本館
(神奈川県足柄下郡)
阪神甲子園球場
(兵庫県西宮市)
(次頁に続く)
参考
2-1
-
ベストリフォーム部門
国立大学法人 東京工業大学
すずかけ台キャンパスG3棟
(神奈川県横浜市)
芝学園 講堂
(東京都港区)
鶴岡まちなかキネマ
(山形県鶴岡市)
南海ターミナルビル
(大阪府大阪市)
福岡パルコ
(福岡県福岡市)
ローム京都駅前ビル
(京都府京都市)
2-2
-
第21回(平成23年度)BELCA賞選考委員会
(順不同・敬称略)
委 員 長 内田 祥哉 (東京大学名誉教授)
副委員長 三井所 清典(㈱アルセッド建築研究所 代表取締役・芝浦工業大学名誉教授)
副委員長 鎌田 元康 (東京大学名誉教授)
委□□員 上田 博司 (㈱東急コミュニティー 取締役専務執行役員)
〃 唐沢 隆男 (㈱日立建設設計 常務取締役)
〃 北 泰幸 (㈱竹中工務店 常務執行役員)
〃 木場 一操 (㈱きんでん 技師長)
〃 杉山 直 (㈱大林組 取締役専務執行役員 東京本店長)
〃 千田 公男 (新菱冷熱工業㈱ 常務取締役 首都圏事業本部副本部長)
〃 村尾 幸彦 (エヌ・ティ・ティ都市開発㈱ ビル事業本部 PM事業部長)
〃 森 暢郎 (㈱山下設計 特別顧問)
別紙2
3
-
第21回BELCA賞選考総評
BELCA賞選考委員会委員長 内田 祥哉
BELCA賞は、良好な建築ストック、つまり社会の中で生き生きと活用される建築の形成に寄与することを目的に
設けられた賞である。賞を2部門に分け、周到な長期計画で、安定した維持保全を継続しているものをロングラ
イフ、活用に翳りの見えてきた建物を、巧みな改修によって現代社会に蘇生させたものをベストリフォームとし、
平成3年から前回まで計20回、表彰件数は196件を数えている。
ロングライフ部門では所有者、設計者、施工者、維持管理者の4者を、ベストリフォーム部門では所有者、改
修の設計者、施工者の3者を表彰している。昨今の地球環境問題にともなう建築物の長期利用の 気運を背景に、
BELCA賞への関心は年々高まりつつあるが、現代社会の中で活躍するためには、ロングライフ部門でも、熱源、照
明、給排水、空調など諸設備の抜本的改造が必要となっている。他方ベストリフォーム部門でも、建物の歴史的
経験を保存する傾向が増しているため、近年は両部門を区別しないで合わせて10件を選考している。その結果、
本年はたまたま、ロングライフ部門3件、ベストリフォーム部門7件を表彰することとなった。
今回表彰されるロングライフ部門には、名作の声高いリゾートホテル、球史にとって欠くことの出来ない野球
場、新築当時の姿を損なわない耐震補強に成功した大学図書館が選に残った。
ベストリフォーム部門では、地域の貴重な歴史遺産として保存されていた煉瓦造の県庁舎、これまでにない耐
震補強の考え方で容姿を一新させた大学研究室、地道で配慮の行き届いた改修で見事に蘇生した講堂、映画館へ
の転用で地域の活性化を担う絹織物工場、逐次増築で非能率化していた交通拠点を現行法規の中で一体化した巨
大な複合施設、中心市街の賑わいを取り戻した商業施設、テナントビルを自社ビルに改造し企業イメージをファ
サードに表現した駅前ビルと、以上選に残った物件を見ると、いずれも名実ともに、建築の寿命を延ばすための
手法が社会に定着しつつあることを実感させる。
選考委員会を顧みると、本年の応募案件は昨年にも増して優れた物件が多く、委員のあいだでは早くから選考
の難しさがいわれていた。応募条件への適合性についても厳密に確認したため、残念ながら選に漏れた物件もあ
ったが、それらについては条件の整備を待って、再度の応募を期待したい。此の分野の技術はますます多角的に
展開されていくので、応募作品の水準も年ごとに高まることが予想される。
回を重ねるにつけ、BELCA賞も周知の範囲を広めつつあるが、今回新たに石川県と山形県からの受賞があった。
建物の維持保全技術の全国的な普及向上を目指す賞の趣旨から、未入選の地域からの応募を切に期待したい。
4-1
別紙3
-
第21回BELCA賞ロングライフ部門選考講評
BELCA賞選考委員会 副委員長 三井所 清典
BELCA賞における建築のロングライフの概念はますます広まってきた。審査会では意識的に明確な規定をせず、
応募者の意図を尊重することにしている。ロングライフを長寿命という言葉に置き換えるなら、その有様は多様
である。建築をできるだけ創建当時の状態で維持することは概念として分かり易い。ただ時間の推移の中で形成
される建築の雰囲気は時々の状態で高い価値を見出すことができるので、風雪を刻み続ける建築の長寿命を計る
ことも意味がある。今回は殆ど全体に亘るリニューアルを行い機能や性能の向上を図った建築が長寿命部門に応
募された。全面的に変化しているものの見る人には全く以前の建築と同じイメージに映るものでイメージの長寿
命化ともいうべき建築である。また近年は耐震診断や必要な耐震補強がなされていない建築は受賞の対象にはな
りにくい。応募は何回も可能なので然るべき検討や改修を済まして再度の挑戦を期待したい。
「ザ・プリンス箱根本館」(1978年竣工)は景勝地箱根芦ノ湖畔の自然環境の中に佇むリゾートホテルである。
このホテルの特質は設計者村野藤吾が目指した設計の考え方とその思想を守った2007年の大改修の方針に裏付け
られる。村野は湖畔の環境と景観の保全に徹する目的から「一木一石たりとも大切に保存し、みだりに変更して
はならない」ことを設計の原則とし、工事中もこれを守らせた。具体的には、ホテルの建築を分割し、巨大化を
避け、2棟の円形客室棟を樹林の中の空地に分散配置し、エントランスやメインロビーのある中央棟も同様に樹
間に建設されている。しかもそれらの建築はすべて周辺の松や杉の樹高を超えないように建てられ、ホテル全体
がそれぞれ樹林に包まれ湖畔の景観に調和する建築となっている。またそのことによって建築の内外が自然と融
合した魅力的な空間が生み出されている。2007年に実施された大改修の方針は内外共に村野の設計思想を受け継
ぎ美しいデザインとディテールを保存し、竣工当時の姿に修復することであった。特に共用部はそれが徹底され
ている。職人の巧みの技を把握するため実測調査をするなどの努力によって改修を実施した成果はロングライフ
部門に価するものと高く評価された。
「阪神甲子園球場」(1924年竣工)は日本で初めての本格的な野球場として西宮に建設され、以来旧制中等学
校、引き続き現在の全国高等学校野球の聖地となっている。またプロ野球チーム阪神タイガースのフランチャイ
ズ球場としても歴史を刻み、国民に深く親しまれている球場である。今回野球場としての現代的魅力と施設の安
全を向上させるため、2007年から2010年にかけて大改修・大改装が実施され、施設の機能的及び物理的長寿命化
が図られた。改修は内野・外野のスタンドの床や客席の改良、内野席上部の銀傘架け替えによる屋根の拡張と中
間支柱の撤去、ツタの絡んでいたRC外周壁の増打による新しいファサードのデザイン、耐震補強や避難計画の総
合的見直し、売店や食堂、甲子園歴史館等、外周のオープンな場に設けられた記念碑を含むアメニティ施設の充
実が図られている。銀傘上の太陽光発電設備など設備上の省エネ対策も施されている。実に立派なリニューアル
であるが、不思議なことに以前からそうであったかの様に見える。見る人にとって「あるべき甲子園の姿」とし
て映るのであろうか、見事なイメージ保存による長寿命化として高く評価される。
「早稲田大学2号館」(1925年竣工)は早稲田大学図書館として建設された建物である。当時建築学科主任教授
内藤多仲が中心となり、意匠は30歳の助教授 今井兼次が担当した。意匠性に富む6本の円柱のあるエントラ
ンスホールと天井の高い500人収容の大閲覧室のある図書館は大正末に東洋一と言われたという。その後1955年に
自習室や事務室の新館ゾーンと書庫ゾーンが増築され、1990年には中央図書館機能が移転した。1997年のキャン
パス整備指針でこの3つのゾーンが一体化した建築は大学の歴史を継承していく軸路に接し、内外部とも最大限
保存すべきという改修方針が定められている。2号館の保存改修は1998年と2010年の2回に亘る改修で見事に応
えたと評価される。1998年の改修で大隈記念室と會津八一記念博物館の新機能が加えられ、1999年東京都歴史的
建造物第1号に選定された。2010年の改修では3ゾーンを一体とした建築の耐震補強が行われたが、補強は新館
ゾーンと書庫ゾーンに限定し、初期の図書館ゾーンは歴史的意匠性が尊重された質の高い空間として保存された。
このような全学からの期待に応えた建築の長寿命化の改修設計と工事が、ロングライフ部門に価すると高く評価
された。
4-2
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門選考講評
BELCA賞選考委員会 副委員長 鎌田 元康
本年度のBELCA賞の応募物件数は、昨年度に比べロングライフ部門で微増、ベストリフォーム部門で微減、全体で微減であっ
た。その中にあって、今回のベストリフォーム部門表彰物件数は、昨年度より1件増え、7件となった。表彰に値すると評価された7
件は、例年通りの激戦を勝ち抜いた物件だけに、それぞれ極めて優れたリフォームであり、改修内容も以下の物件ごとの概要に示す
ように、近年になく多岐にわたったものであった。その詳細を記すのに部門選考講評に許された字数はあまりに少なく、詳細につい
ては、この後に示される物件ごとの選考評をご覧いただきたい。
「石川県政記念 しいのき迎賓館」(1924年竣工、2010年改修)は、旧県庁本館(日本建築学界が保存要望)と「堂形のシイノキ」
(国の天然記念物)の一体保存と県庁跡地利用により中心市街地の活性化を図ることを目的とした事業である。歴史的な価値の高い
旧本館の正面部分は、レトロフィット免震の採用と鉄骨や炭素繊維による構造補強を施して残し、増築部分は保存部分の対比として
ガラス主体の極めて透明性の高い現代建築とし、芝生広場から旧庁舎壁面を透けて見せるなどの工夫がなされている。丁寧な内装保
存がなされた保存部分と、明るく開放的な増築部分が見事に調和していることに、現地審査を行った委員全員が感心させられた物件
であり、かつ、省エネルギー面での工夫、平面計画が適切になされている。
「国立大学法人 東京工業大学すずかけ台キャンパスG3棟」(1979年竣工、2010年改修)は、1970年代後半から実質的運用を開
始したキャンパスにある高層研究棟のうち1棟のリフォームである。当該建物は、オフィス空間相互を、3mセットバックした縦シ
ャフトで連結するという明快な構成となっているが、このセットバックした5m幅の空間前面に、下部ピン接合の非自立型でプレス
トレスを導入された“ロッキング壁柱”を、既存建物に吸収ダンパーを介して寄り添わせ、地震時における変形を特定階に集中させ
ることなくコントロールする手法を開発・採用し、また、壁柱後方にできたボイド状空間に個別空調の室外機を設置し美観を向上さ
せた点、および設備改修なども適切である点が評価された。
「芝学園 講堂」(1966年竣工、2010年改修)は、創建当時より学園の講堂としての利用に留まらず、地域住民に開放され、映画
鑑賞の場として親しまれ愛されてきた建物を、“新しい時代に従前と変わらぬ愛着を持って使い続けてもらうにはどうしたら良いか”
の一点に向かって、学園・コンサルタント・建設会社が一体となり、考え抜き改修に取り組み成功させた物件である。冷房設備の新
設、残響時間に配慮し設置した木質壁内側への空調ダクトの隠蔽と上下温度差を少なくするための工夫、男子校であるため不十分で
あった女子トイレの大幅増設、省エネ・省資源に配慮した設備機器の更新などが、平面・立面的に厳しい条件の中で行われていること、
なによりも、学園関係者の建物への愛着と有効活用への熱意が評価された。
「鶴岡まちなかキネマ」(1936年竣工、2010年改修)は、鶴岡市中心地で昭和初期から続いていた絹織物工場の移転を契機として、
その跡地利用に、鶴岡商工会議所加盟企業の出資による民間資本のまちづくり会社が事業主体となって取り組んだ、中心市街地活性
化プロジェクトによる改修物件である。トップライトからの明かりを得て、絹織物工場の記憶を呼び起こさせる木造トラスが美しく
表現されたエントランスホール、梁下高さを確保するために地盤を掘り下げて階段状スラブを新設し、内装・椅子などの工夫により
温もりと雰囲気のある空間を創出している40席~165席の4つのシネマなどが評価されたが、これらは一次審査資料からは十分読み取
れず、現地審査参加委員すべてが、書類による審査の限界を知らされた物件でもある。
「南海ターミナルビル」(1932年竣工、2009年改修)は、なんばの中枢的役割を担いつつ増改築を繰り返し、機能や動線が複雑に
錯綜する巨大複合施設となっていた当該ビルを、メインテナントである高島屋の“新本館計画(既存改修・新棟建設)”を契機とし
て、全体を再構築・改修することにより街の活性化を指向したものである。“保存・再生・先進”のコンセプトのもと、歴史的景観
としての北面外周部の補修・洗浄と乾式タイルへの貼り替えによる保存、中央に位置した“ロケット広場”の複数の庇の撤去と2本の
マストに支えられたガラスキャノピーの大空間への改修など、多くの工事が適切に行われているが、各種大臣認定の取得や創意工夫
により、快適な一体的適格建築に改修し得た点が特に高く評価された。
「福岡パルコ」(1936年竣工、2010年改修)は、旧岩田屋百貨店本館が全面的に一新された商業施設であり、老舗百貨店の近接地
移転により、福岡の代表的な街角の灯が消えていたものを蘇らせ、新たな商業文化の創生の起爆剤となった物件といえる。今回の大
規模改修の要点は、安全性、事業性、環境の3点であるが、既存構造体を利用した上での巧みな耐震改修、特別避難階段・非常用エ
レベーター新設、店舗構成配置や共用部デザインの一新に加えての既存エスカレーター設置部の改修、既存外壁に新たな外壁を付加
してのデザイン一新と二重外璧を利用した熱負荷低減、隣接建物の設備との一体的利用を前提としたバリアフリー面での改修など、
多様な改修工事が適切、かつ、巧みに行われていることが評価された。
「ローム京都駅前ビル」(1977年竣工、2010年改修)は、京都市内に本社を置く総合半導体メーカーが自社ビルとして取得した中
規模の既存ビルを、“駅前都市景観への貢献”“環境負荷低減”“耐震性・快適性の向上”をテーマに、既存躯体を再利用し、仕上
げと設備を全面更新することで新築同様に再生させたものである。塔屋一層を解体して近隣ビルとスカイラインを合わせ、京都の伝
統である格子形状の太陽光追尾センサー付ブラインド内蔵ダブルスキンカーテンウォールに更新している。さらに屋上緑化・屋上壁
面緑化、各種高効率機器の採用、雨水と空調用ドレイン水の利用、デマンド制御による最大使用電力制御など多様な省エネ・省資源
手法を採用し、耐震補強や不要となった地下機械室の食堂への転用なども適切に行われているなど、ストックの再生に向けた努力が
評価された。
4-3
-
第21回BELCA賞ロングライフ部門受賞建物選考評
ザ・プリンス箱根 本館
所 在 地:神奈川県足柄下郡箱根町元箱根144
竣 工 年:1978年(昭和53年)
用 途:ホテル
建物所有者:㈱プリンスホテル
設 計 者:村野藤吾
㈱松田平田設計(改修)
施 工 者:清水建設㈱、高砂熱学工業㈱、㈱関電工、㈱西原衛生工業所、
日本オーチス・エレベータ㈱、㈱川島織物セルコン
維持管理者:㈱プリンスホテル
ザ・プリンス箱根本館は、日本を代表する景勝地である富士山麓の箱根芦ノ湖畔に建っている。その自然環境
を生かしたリゾートホテルであり、村野藤吾の晩年の代表作である。1978年に竣工した本館がロングライフにな
った理由は、設計の考え方と大規模改修の方針の2点に要約できる。
まず設計において、設計者の村野藤吾は、長寿命のホテルづくりを目指すと共に、国立公園のなかでも厳しい
計画条件が課せられている芦ノ湖地域の建設地にあって、その湖畔特有の景観を守り、敷地内においても「一木
一石たりともみだりに変更してはならない」を設計原則にしたとのことである。
具体的には、円形の客室棟2棟が樹林の中の空地に分散配置され、フロントや管理部門に加えてメインロビー
や宴会場がある中央棟も同様に樹間に建設されている。そして建物はすべて周辺の樹高を超えない計画で、ホテ
ル全体が樹林に包まれて湖畔の景観と調和する設計になっている。またホテル内部では、宿泊者が富士山や芦ノ
湖などの見事な自然景観を満喫できるように随所に空間的な演出が行われ、風景と建築が一体化し、建築の内と
外とが融合したホテル空間が生み出されている。デザインが優美で空間が魅力的なこのホテルは、リゾートホテ
ルの最高峰のひとつとなっている。
次は、2007年に竣工後初めて実施された大規模改修の考え方である。その改修方針は、内外部共に村野藤吾
の設計思想を受け継ぎ、美しいデザインとディテールを保存して竣工当時の姿に修復することであった。そのた
めに村野藤吾のディテールとそれに応えた職人の匠の技を把握するために現地実測調査が行われ、その調査結果
が踏まえられて改修工事が実施されている。
具体的な取り組みとして、インド砂岩割石目地塗込の外壁、客室棟の花弁のような曲面バルコニーなどの特徴
的な外装については、保存修復を目標に清掃・補修が行われた。一方、メインロビーやレストランなどのパブリ
ックエリアも同様で、壁や床については補修あるいは復元材料での張替が行われ、そしてオリジナル家具類も布
地張替などによる原型保存が徹底されている。
ちなみに客室は、「現代和モダニズム」という新しい改修テーマで、ホテル側のニーズを踏まえながら全面的
に改修されたが、パブリックエリアなどの改修方針と異なっていたのはいささか残念である。また耐震補強は外
観やインテリアを損ねないように施工された。日常の維持管理や保全は、設備機器更新などを除いて、ホテルブ
ランド維持のためにホテル直営で実施されている。
最後に、短工期であっても的確な保存修復のために現地実測調査を行った関係者の努力に敬意を表する。ここ
で得られた技術情報が今後の改修に役立つように確実に継承されることを望むものである。これは村野藤吾設計
の価値あるホテル空間を提供するホテルブランド戦略にも合致することであろう。ザ・プリンス箱根本館は、建
物と景観が一緒に大事に維持される長寿命ホテルの優れた事例である。
4-4
-
第21回BELCA賞ロングライフ部門受賞建物選考評
阪神甲子園球場
所 在 地:兵庫県西宮市甲子園町1-82
竣 工 年:1924年(大正13年)
用 途:観覧場(野球場)
建物所有者:阪神電気鉄道㈱
設 計 者:㈱大林組
施 工 者:㈱大林組
維持管理者:阪神電気鉄道㈱
高校野球の開催を主目的として大正13年に建設された、日本で初めての本格的な野球場のリニューアル工事で
ある。既存の構造体の大半を耐震補強し、又、銀傘を高く架け替え、客席、設備も全面入れ替える等、ほとんど
全面改修されており、ベストリフォームと言っても差し支えないほどであるが、これまでと変わらぬ甲子園球場
のイメージを残し、歴史と伝統を継承したいという、建築主の熱い想いを尊重し、ロングライフ部門としての授
賞となった。甲子園球場と言えば、蔦で覆われた外観が印象的であったが、その下の旧外壁は打ち放しコンクリ
ートであった。現地を視察した時の印象では、新たに構築された外壁煉瓦タイルが、旧来からのものが補修され
残されたような錯覚に陥った。このように改修に当たっては、観客が抱く甲子園のイメージを大切にすることを
第一に優先し、随所にそのコンセプトが展開されている。
外観は、連続アーチ、ポツ窓といった旧来の形状を継承しつつ、構造体から切り離された中空煉瓦積み工法で
施工されている。今後、蔦を復活させていくとのことであるが、その際に、構造体への悪影響を無くし、メンテ
ナンスのし易さを良く考慮した工法である。銀傘は、構造躯体の耐震補強に併せて全面的な架け替えが行われた。
高さを一段と高くし、視線の妨げとなる柱を極力後方へ移動させ、視認性を一段と向上させている。又、その高
さを活用してロイヤルスィートを新たに設置しアメニティを高めている。
省エネ対策としては、空調熱源のリバースリターン方式、ポンプ等の台数制御やインバータ制御などを採用し
ている。環境負荷低減対策として、新たに構築した銀傘屋根上を利用して太陽光発電設備(200kW)を新設し、雨
水や井戸水の利用なども新たに考慮されている。特に、施工面においては、シーズンオフにしか工事が出来ない
という制約の中で、足掛け4年に亘った長期工事であったが、避難安全検証法や、計画認定等の法制度を上手く活
用し、各工事段階において、4万7千人もの大観衆の安全性を検証しながら施工を周到に進めていったことが評価
された。
又、新たな施設として、野球文化の振興のために「甲子園歴史館」と「新野球塔」を設ける等、野球に対する
建築主の情熱が感じられた。バリアフリー化やボールの見えやすいカクテル光線を用いる等の試みも図られ、新
しい時代にマッチした球場をつくりだそうとする関係者の意欲が充分に汲み取れた。今後、かつての蔦が覆い茂
り、以前と同じ姿が見られるようになることを期待したい。
4-5
-
第21回BELCA賞ロングライフ部門受賞建物選考評
早稲田大学 2号館
所 在 地:東京都新宿区西早稲田1-6-1
竣 工 年:1925年(大正14年)
用 途:大学(図書館、博物館)
建物所有者:学校法人 早稲田大学
設 計 者:内藤多仲、今井兼次、桐山均一
西谷章(改修)、古谷誠章(改修)、大成建設㈱一級建築士事務所(改修)
施 工 者:上遠組
大成建設㈱東京支店(改修)
維持管理者:学校法人 早稲田大学
この建物は、3つのゾーンから成る。會津八一記念博物館を中心とする保存ゾーンと、その隣に位置する自習
室や事務室で構成される新館ゾーン、そして保存ゾーンの裏に位置する書庫ゾーンである。この3つの異なる用
途のゾーンの機能を如何に維持して全体の耐震補強をするか?というのがテーマであり、これに見事に答えたと
いう点が評価の最大のポイントである。
保存ゾーンは、そもそも1925年「早稲田大学図書館」として竣工した。設計は当時の建築学科主任の内藤多仲
が中心となり、意匠の設計者として今井謙次が参画した。大閲覧室は収容500名、大正末期の図書館としては有数
のもので「東洋一」と言われた。1階のエントランスホールには6本の美しい円柱が配された。このエントラン
スホールから2階へ至る大階段の踊り場には、横山大観、下村観山の合作となる絵画「明暗」が掲げられ、荘厳
な雰囲気を醸し出している。
保存ゾーンは1998年の改修工事で、従来の図書館機能に、大隈記念室・會津八一記念博物館といった新機能が
加えられて、現在では大隈講堂、演劇博物館と共に早稲田大学のシンボルとなっている。また1999年「東京都歴
史的建造物」第1号に選定されて、事実上補強は不可能になった。
したがって隣接する新館ゾーンと書庫ゾーンの二つを、言わば十分強固に補強して、この二つのブロックで保
存ゾーンが負担すべき耐震力をもカバーさせるという発想で耐震補強工事が行われた。
新館ゾーンは自習室や事務室という性格上、出来る限りオープンなスペースを確保するために、炭素繊維巻き
工法や、採光と通風を確保するためのブレース工法が採用された。
また書庫ゾーンは、空間に所狭しと
走る水平材と鉛直材からなる書架の構造を利用して、これに補強材を抱かせる。また、書庫ならではの階高の
低さを上手く使って、効率良く補強材を配置して耐震性能を上げる。さらに外壁面の補強では窓の意匠性あるい
は採光を犠牲にし、つまり窓枠にブレースを入れるなどして、全体として強固な耐震ブロックを作り上げた。
この書庫ゾーンの言わば自己犠牲的な耐震補強の結果かとも思える、狭隘な空間を見た後に、保存ゾーンの會
津八一記念博物館を訪れると、大空間に伸びやかに広がる丸天井の美しさに目を奪われる。現代ではその技の継
承が難しいとされる漆喰塗りが見事である。
4-6
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
石川県政記念 しいのき迎賓館
所 在 地:石川県金沢市広坂2-1-1
竣 工 年:1924年(大正13年)
改 修 年:2010年(平成22年)
用 途:複合文化交流施設(ギャラリー、セミナー室、レストラン、事務所等)(改修後)
県庁舎(改修前)
建物所有者:石川県
改修設計者:㈱山下設計
改修施工者:大成建設㈱、兼六建設㈱、㈱岡組、成瀬電気工事㈱、立野電気工事㈱、
㈱柿本商会、みなみ設備工業㈱、鈴木管工業㈱、ホクレイ㈱、三精輸送機㈱
石川県庁の金沢駅西副都心移転による市街地の活力低下に対し、旧県庁本館(日本建築学界が保存要望)と「堂
形のシイノキ」(国の天然記念物)の一体保存と県庁跡地利用により中心市街地の活性化を図ることを目的とす
る事業である。
歴史的な価値の高い旧本館の正面部分は、保存・再生に向けた綿密な調査と構造耐力試験などを経て、レトロ
フィット免震の採用と鉄骨や炭素繊維による構造補強を施している。構造的な安全性を確保した保存部分外部は、
外装タイルへのピンニングとエポキシ注入、解体部分から採取したタイルでの張替え、人造石洗い出し仕上げの
補修やレリーフの修復も行っているが、工事に際して「堂形のシイノキ」の広がった根を痛めない配慮など、丁
寧な施工は特筆されるべきものといえる。
増築部分は保存部分の対比としてガラス主体の極めて透明性の高い現代建築となっているが、芝生広場からの
景観としても旧庁舎壁面を透けて見せるなど新旧の調和が好ましい。
内部では旧庁舎の意匠を留めた正面玄関、中央階段、旧知事室、旧副知事室は耐震補強や断熱工事の後にオリ
ジナル材再利用を含む丁寧な内装復元がなされているほか、木製バランス窓も原型に復元されている。旧庁舎で
は対応不可能なバリアフリーを増築建物側で処理して、県民や市民を迎える迎賓館としての機能を確保し、セミ
ナー室やギャラリー、国連大学高等研究所さらには著名なレストランを含む「文化交流施設」として再生してい
る。
設備面では、電気室・機械室は増築部分の地下に新設されており、保存部分の屋上には空調機械室や室外機・
非常用発電機を設けている。省エネルギー対策としてはアトリウム空間の居住域空調としての床吹空調・吹抜け
内の温度差を利用した中間期の自然換気・採光のためのトップライト・気密性を確保した木製サッシュなどの採
用により、年間一次エネルギー使用量(2,923MJ/㎡・年)を実現している。一般建築より若干大きめな数値は、
融雪用ヒータが設置されている為と考えられる。
イベントホールやレストラン・カフェからの眺望は、大面積のガラス越しに臨む金沢城公園・兼六園の緑や石
垣の圧倒的なヴォリュームと緩やかな起伏が平面的な広がりを見せる芝生広場との対比的な構成により、時代性
と空間性を感じさせる魅力と迫力がある。
中心市街地活性化という課題に対して、「歴史的蓄積と緑の環境」と「賑わいの広阪・香林坊」との回遊性を
生む動線上に中央公園やいもり堀園地と一体化したイベント対応可能な広場を整備している。文化交流施設とし
て保存再生された「しいのき迎賓館」が活性化の基点として、課せられた継続的貢献を果たして行くものと確信
できる。
4-7
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
国立大学法人 東京工業大学すずかけ台キャンパスG3棟
所 在 地:神奈川県横浜市緑区長津田町4259
竣 工 年:1979年(昭和54年)
改 修 年:2010年(平成22年)
用 途:講義・研究室棟
建物所有者:国立大学法人 東京工業大学
改修設計者:国立大学法人 東京工業大学、㈱綜企画設計、㈱テクノ工営
改修施工者:㈱淺沼組、㈱柿本商会、㈱積田電業社
東工大すずかけ台キャンパスは、学部機能を持たない我が国初の大学院大学創設を目標として、1970年代後半
から実質的な運用を開始した。当G3棟は、初期マスタープランに基づき当時の建築学科の助教授であった谷口
汎邦(現東工大名誉教授)を中心とする長津田研究室により設計された高層研究棟のひとつで、モダニズム建築
の流れを汲むものであった。緑豊かな丘陵地の外部風景を満喫させる横連装の、2つのオフィス空間(メインボデ
ィ)が、3mセットバックした縦シャフトで連結されるという明快な構成であった。耐震改修が喫緊の問題となり、
併せて当初はセントラル空調であったが、次第に個別空調の室外ユニットが窓面に多く取り付けられ美観を損ね
ていた設備面の問題も解決すべく、全面的な改修が行われた。
今回の改修で何よりも特筆されるのは、オフィス空間相互の5mの幅に「ロッキング壁柱」を挿入する耐震補強を
施し、且つ3mのセットバック空間を利用して個別空調設備機能を設置することにより、構造・設備面の問題を
一挙に解決し、デザイン的にもオリジナルデザインの特性を尊重しつつ、時代に対応した発展型の改修を行った
ことにある。耐震性能を向上させるには、建物全体を耐震補強フレームでカバーし、全く新しい建物として建物
として再生させる方法と、既存のデザインに出来るだけ抵触せず耐震性能の向上を目指す方法の大きく二つの方
向が有る。しかし今回は、最小の操作で耐震性能を向上させると共に、なおかつオリジナルデザインの特性を尊
重する第3のレトロフィット手法を試みている。非自立型のプレストレスを導入されたロッキング壁柱を既存建
物に、吸収ダンパーを介して寄り添わせることによって、地震時における変形を特定階に集中させることなくコ
ントロールする手法を開発した。この壁柱脚部は回転自由(ロッキング)でありモーメントを発生しないことか
ら、基礎部の補強を軽減し大幅なコスト低減も図れている。打ち継ぎ目地を眠らせたシャープな壁柱の下部には、
偉人のアフォリズムが刻み込まれ、露出されたピン接合部の緊張感あるディテールとともに、教育空間らしい雰
囲気を醸成している。いかにも耐震補強しましたと言わんばかりの建物が多い中で、あたかも新築で計画された
かのような印象さえ受ける外観である。
外構計画においても、モダニズムの象徴であったピロティ部分を一部復活し、未利用地であった、後背のバン
クとの間の空地にウッドデッキを敷いて、一体利用が出来る空間を作り出し、学生、教員のアクティビティを向
上させていることも評価される。今回の改修をモデルケースとして、この手法を更に展開・発展させ、すずかけ台
キャンパスの新しい風景を順次構築して行かれることを期待したい。
4-8
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
芝学園 講堂
所 在 地:東京都港区芝公園3-5-37
竣 工 年:1966年(昭和41年)
改 修 年:2010年(平成22年)
用 途:学校(講堂)
建物所有者:学校法人 芝学園
改修設計者:清水建設㈱一級建築士事務所
改修施工者:清水建設㈱、㈱関電工、大成温調㈱
1966年に竣工した講堂の外観は、周囲を威圧するような異彩を放つ。しかしながら、ここは創建当時より学園
の講堂としての利用に留まらず、地域住民に開放され、映画鑑賞の場として親しまれ愛されて来た。
半世紀近く経って改装されたが、われわれの胸を打ったのは、学園のこの建物への愛着である。永い間親しま
れて来た建物を、新しい時代に、従前と変わらぬ愛着を持って使い続けてもらうにはどうしたら良いか?その一
点に向かって、学園、コンサルタント、建設会社が一体となり、考え抜き実現させた。
柔らかみのある木質調の壁、創建当時から、講堂という空間の緊張感を引き出す為の演出であったに違いない、
壁面から半円形に突き出た照明用のバルコニーも、木のルーバーで化粧され、周囲に違和感無く溶け込んでいる。
ここでは付属設備である筈のトイレも木のしつらえである。さらに発注者のこだわりは、芝学園の「芝」のイメ
ージを緞帳のデザインに織りこむという手の込みようである。座席もオリジナルの家具だと聞く。
外観は別にして、玄関とそこへのアプローチ、ホワイエなどにも、内部に見られるこだわりと同様のこだわり
が見られれば申し分無かったが、それを補って余りある出来栄えである。
空調設備については冷房設備を新設しているが、残響時間をコントロールするため設置した木質壁の内側に空
調ダクトを隠し、上下の温度差の少ない空間を実現している。
電気設備としては、高天井の照明器具に高効率ダウンライト、LEDライン照明を導入し省エネ化を図るとと
もに、照明器具の交換も、手間暇のかかっていた客席側からではなく新たに天井内にキャットウォークを設置し、
容易にした。
衛生設備面では、男子校であることから不十分であった女子トイレを大幅に増設、保護者や近隣住民への便宜
を図った。節水トイレ、自動水洗、消音装置の設置など大幅な省エネ化を図っている。
また音響映像設備も含め、さまざまな工夫により、大幅な省エネ化を達成し、改修前はCASBEE-Bラン
クであった建物が改修後はAランクとなった。
4-9
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
鶴岡まちなかキネマ
所 在 地:山形県鶴岡市山王町13-36
竣 工 年:1932~1936年(昭和7~11年)
改 修 年:2010年(平成22年)
用 途:映画館(改修後)
絹織物工場(改修前)
建物所有者:㈱まちづくり鶴岡
改修設計者:㈱設計・計画高谷時彦事務所
㈲安芸構造計画事務所
改修施工者:㈱佐藤工務、鶴岡建設㈱、㈱マルゴ
㈱渡会電気土木、山形空調㈱
庄内平野に位置する城下町鶴岡も、郊外の大型商業施設進出や事業主の高齢化などにより、中心市街地の商店
街が衰退するという地方都市共通の構図を描く。
本事業は中心地で昭和初期から続いていた絹織物工場の移転を機に、その跡地を活用する中心市街地活性化プ
ロジェクトであり、事業主体が鶴岡商工会議所加盟企業の出資による民間資本のまちづくり会社であることにも
特徴がある。
当初は解体しての跡地利用が検討されていた産業遺産でもある木造既存工場を、その小屋組みを活かした「街
の回遊の核」となる生活利便施設としての映画館に再生することで、賑わいの起点となり、中心市街地活性化の
シンボルとしている。
用途上は既存不適格の工場を、各種許認可を経て木造で4スクリーンのシネコンに改修し、映画上映の他にも
各種演芸や講演会など広範な活用を図り、一般的なシネコンとは一線を画す、年齢層を越えた地域文化の中核施
設となっている。
エントランスホールではトップライトの明かりを得て、嘗ての絹織物工場の記憶を纏いながら、木造トラスが
美しく力強く表現されているし、40席から165席の4つのシネマでも、小屋組みを見せながら梁下高さ確保
の為に、地盤を掘り下げて階段状スラブを新設し、織物の縦糸横糸を連想する木製ルーバーの壁面と、絹の柔ら
かさを思わせる極めて座り心地の良いオリジナルデザインの客席により、温もりと雰囲気のある空間に仕上がっ
ている。
構造的にも、小屋組み・軸組みの劣化に対する部材の繕いと取替えに加え、構造用合板の耐力壁増設や鉄骨の
外部添え柱による耐震補強が為されている。
元々が古い木造絹織物工場であっただけに、設備面は一新されている。空調設備はEHPパッケージを採用し、
全熱交換器による外気負荷低減を図っている。さらに、駐車場融雪設備は井水散水方式とするなど、省エネルギ
ー上の配慮がなされている。
建物外装には杉の下見板貼りを施し、既存の煙突やオイルタンクを補強し存置することで、嘗ての工場の風景
を継承復元し、ポーチ床の羽二重模様や吟味され抑制されたサイン計画とともに長い歴史に彩られた地域性と懐
古感を醸し出す。
また、維持管理については建築・設備・機械の各地元施工者による保全体制が構築され、長期の維持保全計画
に基づく、きめ細かな管理を行うこととしている。
地元企業に支えられる(株)まちづくり鶴岡を中心に官学・市民を巻き込んだ活動で、市街地活性化を強く指向
し推進するこのプロジェクトは、その主旨と着想と技術が評価されると共に、時を掛けても着実に地域に根付く
土着性を持っている。
4-10
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
南海ターミナルビル
所 在 地:大阪府大阪市中央区難波5-1-60
竣 工 年:1966年(昭和7年)
改 修 年:2010年(平成21年)
用 途:複合施設(駅舎・物販店舗・ホテル 等)
建物所有者:南海電気鉄道㈱
㈱髙島屋
改修設計者:㈱プランテック総合計画事務所
㈱竹中工務店
㈱大林組
改修施工者:㈱竹中工務店、㈱錢高組、㈱大林組、
南海辰村建設㈱、南海ビルサービス㈱
大規模な施設開発が進むキタに対し、ミナミは昔ながらの大阪の風景が残り、御堂筋の南端となる難波地区も
街の機能充実度が低く、治安や環境にネガティブな印象が強かった。
複数の主要施設の集積である南海ターミナルビルは、なんばの中枢的役割を担いつつ増改築を繰り返して、機
能や動線が複雑に錯綜する巨大複合施設となっていた。
本事業は南海ビルメインテナントである高島屋の「新本館計画(既存改修・新棟建設)」を契機として南海タ
ーミナルビル全体の再構築・改修による街の活性化を指向する「再生」であり、コンセプトは「保存・再生・先
進」とされた。
ミナミを象徴する歴史的景観としての南海ビル北面外観は、テラコッタで装飾されて文化的な価値も高く、本
事業ではミナミ再生のシンボルとして補修・洗浄と乾式タイルへの貼り替えにより復元され、正面エントランス
庇の改修や広告掲示場所を限定するガラススクリーンの設置のほか、夜間のライトアップなど施して御堂筋から
の表情を演出している。
巨大複合施設の中央に位置した「ロケット広場」は、複数の庇が架設されて雑然とした閉塞感を伴っていたが、
2本のマストに支えられたガラスキャノピーの大空間に改修され、高島屋・スイスホテル・なんば駅・なんばCI
TY各施設の結節点として「なんばガレリア」と銘打たれ、街のコアを為す気持ちの良い空間として変貌し、「先
進」を体現している。
本プロジェクトの肝は、長年の歴史の中で既存不適格になっていた部分に対して、高島屋の新館増築と既存部
分とを「新本館」として一体の空間を確保するメガプレートを形成させるべく、階段・EVなど縦動線の数や配置
を全館非難安全検証法や防災計画により、国交省・総務省の大臣認定を取得したうえで整理・移動するなど、数
多の工夫や協議により、なんばCITY共々機能的で快適な一体的適格建築に改修し得たことである。
そのことにより設備面でも、排煙設備などの適正化が図られる等の機能確保が為されている。巨大複合施設の
機能・動線が交差する「なんばガレリア」の大アトリウム空間では置換空調方式の採用による快適性確保と1階
ではミスト空調を取り入れた夏季の空調負荷低減を図っているし、大規模な空間と機能の全体を確実に監視・把
握する防災センターの体制も万全に整えられている。
本プロジェクトの様に、稼働中の百貨店を始めとする諸々のテナントと乗降客が多く利用する公共性の高いタ
ーミナル駅での改修工事の難易度の高さは、容易に想像できる。耐震補強も部位的に多くの制約を受ける中で、
位置や補強方法が使い分けられており、その一部は利用者の目にとまり安心感へと繋げる役割も与えられている。
建物所有者とテナント・設計監理者・施工者が一体となって数々の課題を乗り越えて実現したこの労作は、大
阪の一極を為すミナミの活性化に繋がり、街の顔であり続けることでベストリフォーム賞に相応しいと評価する。
4-11
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
福岡パルコ
所 在 地:福岡市中央区天神2-11-1
竣 工 年:1936年(昭和11年)
改 修 年:2010年(平成22年)
用 途:物販店舗(改修後)
百貨店(改修前)
建物所有者:学校法人 都築学園
㈱パルコ
改修設計者:㈱竹中工務店
㈱パルコ
改修施工者:㈱竹中工務店
福岡パルコは、1936年竣工の旧岩田屋百貨店本館が全面的に一新された商業施設である。老舗百貨店の岩田屋
が近接地に移転してから、福岡の代表的な街角の灯が消えていた。このたびパルコが出店したことで街角建築が
蘇り、この天神地区から新たな商業文化の創生が始まっている。
今回の大規模改修の要点は、安全性、事業性、環境の3点である。1つ目の耐震や防災などの安全性向上におい
ては、巧みな改修技術が提案されている。まず耐震改修では、店舗配置の自由度確保のために既存の構造体が利
用された。建物外周部のRC構造躯体の開口部にRC耐震壁が配置されて、内部の柱には鋼板巻き補強が行われ、ま
た耐震ブレースが共用空間に隠蔽されずに設置されてデザイン要素としても取り扱われている。一方の防災改修
では、特別避難階段新設、既存の避難階段に附室増設、既存EVシャフト利用による非常用EV新設などが実施され
た。またバリアフリー対応の面では、隣接建物のバリアフリー設備との一体的利用を前提とした改修が実施され
ている。
次に2つ目の事業性では、集客力ある専門店ビルが目指されている。既存建物は基準柱間が5.9mグリッドで基
準階高が3.35mであるが、この厳しい空間条件が上手く活用されて、空間密度が高く、何かを発見する路地的で
魅力的な空間が生まれている。そのために店舗構成配置や共用部デザインに加えて、既存エスカレーター設置部
の改修も行われている。スリム型エスカレーターを片側に寄せた更新が行なわれて、幅11m奥行1.5mの吹抜が生
み出された。この9層吹抜が下から2層吹抜、3層吹抜、4層吹抜と順々に3つに分割され、動線の要であって開放感
のある心地よい空間になっている。また近隣の商業エリアとの共存も図られて、防災技術の工夫によって隣接施
設との接続が増設されるなど、来街者の回遊性が高められている。そして街区の顔づくりとなる外璧改修デザイ
ンでは、その嗜好においては賛否両論があると思われるが、「イメージ一新」という出店コンセプトに呼応した
インパクトのあるデザインが提案されている。
3つ目の特徴は環境で、設計から維持管理までの全般に亘る環境負荷低減の技術である。具体的には、まず二重
外璧を利用した外皮の熱負荷低減があげられる。これは商業施設が年間を通じて冷房を行うことに着目し、新旧
外壁の間に形成される空気層への外気流入を季節に応じて制御することで負荷低減(日積算熱量4%減)を図るも
のである。次に、外壁や店舗内共用通路へのLED照明の採用、全熱交換器や節水型衛生器具の採用、さらに外壁を
光触媒コーティングすることによる清掃回数の低減など様々な環境上の配慮がなされている。
今回の福岡パルコが成功をおさめているのは、運営者パルコのデザイン陣と本体改修設計者との協働による賜
物である。この福岡パルコは、街の活性化にも貢献するストック型商業施設の好例であり、BELCA賞ベストリフォ
ーム部門にふさわしい建物である。
4-12
-
第21回BELCA賞ベストリフォーム部門受賞建物選考評
ローム京都駅前ビル
所 在 地:京都府京都市下京区塩小路通烏丸西入ル東塩小路町579-32
竣 工 年:1977年(昭和52年)
改 修 年: 2010年(平成22年)
用 途:自社オフィス(改修後)
テナントオフィス(改修前)
建物所有者:ローム㈱
改修設計者:㈱竹中工務店
改修施工者:㈱竹中工務店
この作品は、京都市内に本社を置く総合半導体メーカーが自社ビルとして取得した中規模の既存ビルを、「駅
前都市景観への貢献」「環境負荷低減」「耐震性・快適性の向上」をテーマとして、既存躯体を再利用し、仕上
げと設備を全面更新することで新築同様に再生させた意欲的なリフォームプロジェクトである。
JR京都駅からの視線に配慮したファサードは、塔屋一層を解体し、近隣ビルとスカイラインを合わせた京都伝
統の格子形状のダブルスキンカーテンウォールに更新することで、先進企業の自社ビルらしい端正な佇まいとな
り、夜間のLED照明による「京の光暦」(石井幹子事務所)と名付けられた、多様なパターンで京の四季を表現
したライトアップと併せて、駅前の景観形成に大きく貢献している。又、京都タワーからの見下ろしとヒートア
イランド現象の抑制を意識した屋上緑化・屋上壁面緑化も都市景観に潤いを与えている。
環境負荷低減策として、自社製品でもあるLED照明採用・太陽光追尾センサー付ブラインド内臓のダブルス
キンカーテンウォール・ダブルスキンによる自然換気・自然光センサーによる自動調光制御・雨水と空調ドレイ
ンの再利用・高効率機器(個別空調システム・変圧器)の採用・外気量CO2制御・太陽光発電設備設置などに
より、年間一次エネルギー使用量を改修前比較で41%減の1704MJ/㎡・年に削減し、CASBEE省エネ改修のSランク
相当の環境負荷低減を実現している。また、運用においてはBEMSによる省エネの見える化を行い、デマンド制御
により最大使用電力の制御を図っている。
構造に関しても、既存躯体を全面的に再利用し、耐震壁の増強や鉄骨ブレースを設置することでバランスの良
い耐震補強となり、道路に面して開口を拡大して執務空間の開放感を獲得しながらIS値0.6以上を実現している。
地上階は改修前より天井を高くし、なおかつOAフロアーを敷設するなど建築的な配慮と各種先進設備の導入で
快適な執務空間となり、空調方式の変更などにより生み出された地階の会議室や食堂もLED照明と内装の妙により、
地下の閉塞感は全く感じられない。
宿泊施設や観光施設に近接する京都駅前という立地条件の中で、この様な既存ビルの全面改修を実施するに際
して、安全・騒音・振動・塵埃に対する施工サイドの措置は万に一つの遺漏も許されない厳しいものとなる。そ
れに加えてプロジェクトのテーマにも繋がる環境配慮としての徹底した3R(リデュース・リユース・リサイクル)
活動や綿密な施工計画に基づく資材・廃棄物の搬出入を実施し、更に仮囲いにも都市景観を乱さない配慮が為さ
れるなど、施工者の意思と努力にも敬意を表する。
就業社員に対象者がいないためかバリアフリーの未対応に疑問はあるものの、ストック活用が求められる今、
環境配慮型ビル再生のモデルプロジェクトとして高く評価したい。
4-13
-
前回までのBELCA賞
参考
5