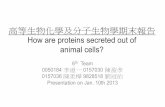生 物 ①(応用生物・生命健康科・現代教育学部) (解答用紙 ...2014/02/05...
Transcript of 生 物 ①(応用生物・生命健康科・現代教育学部) (解答用紙 ...2014/02/05...
-
― 441 ―
生 物
( 解答番号 1 ~ 38 )
次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。
A タマネギの根端は成長が盛んで分裂期の細胞が多い。そのため体細胞分裂の観察にはその根
端がよく用いられる。そこで,発根させたタマネギの根端を固定・染色し,押しつぶし法により
プレパラートを作製し,顕微鏡で観察した。次の図に示すように, のような間期の細胞と,
~ のような分裂期の細胞が見られた。
図 タマネギ根端に見られる細胞分裂像
(注)この問題は,「生物 」の問題である。
解答用紙は,理科のマークシート1枚。
(解答用紙の選択欄に「生物 」を必ず記入・マークすること。)
87AM-No.3
生 物 ①(応用生物・生命健康科・現代教育学部)
-
― 442 ―
前期 中期 後期 終期
ア
イ
ウ
エ
オ
カ
キ
ク
ケ
a b c
ア 染色体 動原体 核小体
イ 染色体 動原体 中心体
ウ 染色体 中心体 核小体
エ 核小体 中心体 動原体
オ 核小体 染色体 中心体
カ 核小体 染色体 動原体
キ 動原体 中心体 核小体
ク 動原体 中心体 染色体
ケ 動原体 染色体 核小体
問1 図の ~ を前期,中期,後期,終期の順に並べた組み合わせとして正しいものを,次の
解答群のア~ケのうちから一つ選べ。 1
1 の解答群
問2 図中の記号a~cで示した名称の組み合わせとして正しいものを,次の解答群のア~ケの
うちから一つ選べ。 2
2 の解答群
88AM-No.3
-
― 443 ―
前期 中期 後期 終期 合計
各期の細胞数 320 40 16 24 400
前期 中期 後期
ア 3.5 8.5 68.0
イ 68.0 8.5 3.5
ウ 64.0 3.2 8.0
エ 64.0 8.0 3.2
オ 3.2 8.0 64.0
カ 8.0 3.2 64.0
問3 細胞分裂に関係する装置のうち,動物細胞にない装置として正しいものを,次の解答群の
ア~キのうちから一つ選べ。 3
3 の解答群
ア 図中の a イ 図中の b ウ 図中の c エ 核膜 オ 細胞板
カ 紡錘糸 キ 紡錘体
問4 タマネギの根端を固定した標本を観察した顕微鏡の視野には,分裂期のそれぞれの時期の
細胞が表のような数で観察された。このようにある時点で固定された標本では,分裂各期の細
胞数の割合は,各期の所要時間の長さに比例している。つまり所要時間の長い時期にある細胞
ほど高い頻度で観察される。他の実験から一分裂期は80分であることが分かった。この分裂期
の長さをもとに分裂前期,中期,後期の長さ(単位 分)を求めることができる。分裂前期,
中期,後期の長さ(単位 分)の組み合わせとして正しいものを,下の解答群のア~カのうち
から一つ選べ。 4
表 分裂各期にある細胞の数
4 の解答群
89AM-No.3
-
― 444 ―
問5 次の記述 ~ のうち,細胞分裂に関する文として正しいものの組み合わせを,下の解答
群のア~コのうちから一つ選べ。 5
体細胞分裂では,まず細胞質分裂がおこり次に核分裂がおこる。
分裂間期には,分裂に必要なDNAやタンパク質が合成される。
動物細胞では,核小体が紡錘体を作るときの起点となる。
体細胞分裂では,分裂前に染色体が複製される。
減数分裂では,分裂前に染色体数が減る。
5 の解答群
ア , イ , ウ , エ , オ ,
カ , キ , ク , ケ , コ ,
問6 次の記述 ~ のうち,動物の染色体に関する文として誤っているものの組み合わせを,
下の解答群のア~コのうちから一つ選べ。 6
染色体の数は生物の種ごとに決まっている。
卵は母由来の染色体を1セット,精子は父由来の染色体を1セットもっているので,受精
卵および体細胞は合計2セットの染色体をもつ。
相同染色体のある対の中の2本は,ともにいずれか一方の親から由来する。
ヒト染色体の1セットは23本であるので,体細胞の染色体数は46本である。
多細胞生物の個体を構成する体細胞は,いろいろ機能が違うと染色体数は異なる。
6 の解答群
ア , イ , ウ , エ , オ ,
カ , キ , ク , ケ , コ ,
90AM-No.3
-
― 445 ―
d e f
ア 溶媒 高張液 低張液
イ 溶媒 等張液 高張液
ウ 溶媒 低張液 等張液
エ 溶質 高張液 低張液
オ 溶質 等張液 高張液
カ 溶質 低張液 等張液
B 細胞は,水を d としていろいろな物質を溶かしているので,その濃度に応じた浸透圧を
もっている。細胞への水の出入りは,細胞と外液の浸透圧の差に応じて生じる。細胞を溶液にひ
たしたとき,細胞内の水が外部に出て細胞が収縮するような溶液を e という。これに対して,
水が細胞内に入って細胞が膨張するような溶液を f という。また細胞を溶液に浸したとき,
見かけ上,水の移動がまったくみられない溶液もある。
問7 文中の空欄 d ~ f に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~カのうちから一つ選べ。 7
7 の解答群
問8 ヒトの細胞にとって下線部の溶液として最も適当なものを,次の解答群のア~エのうちか
ら一つ選べ。 8
8 の解答群
ア 0.7%食塩水 イ 0.9%食塩水 ウ 2%食塩水 エ 5%食塩水
91AM-No.3
-
― 446 ―
a b c
ア 接合 受精 出芽
イ 接合 受精 栄養生殖
ウ 接合 出芽 受精
エ 接合 出芽 栄養生殖
オ 分裂 受精 出芽
カ 分裂 受精 栄養生殖
キ 分裂 出芽 接合
ク 分裂 出芽 栄養生殖
生殖に関する次の文章A~Cを読み,下の問い(問1~8)に答えよ。
A 生殖の方法には,配偶子によらない無性生殖と,配偶子が合体することによって個体がふえ
る有性生殖がある。無性生殖には,親のからだが,ほぼ同じ大きさの個体に分かれることによっ
てふえる a ,母体の一部がふくらみ,それが大きくなって分離することでふえる b ,根
や茎などの器官の一部から新しい個体をつくることでふえる c ,胞子という生殖細胞が母体
に生じ,その生殖細胞によってふえる胞子生殖などがある。
問1 文中の空欄 a ~ c に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~クのうちから一つ選べ。 9
9 の解答群
92AM-No.3
-
― 447 ―
a b c
ア アメーバ 酵母菌 ジャガイモ
イ アメーバ アオカビ 酵母菌
ウ 酵母菌 アメーバ アオカビ
エ 酵母菌 ジャガイモ アメーバ
オ ジャガイモ アメーバ アオカビ
カ ジャガイモ アオカビ アメーバ
キ アオカビ ジャガイモ 酵母菌
ク アオカビ 酵母菌 ジャガイモ
問2 文中の空欄 a ~ c の形式の生殖方法をとる生物の組み合わせとして正しいものを,
次の解答群のア~クのうちから一つ選べ。 10
10 の解答群
93AM-No.3
-
― 448 ―
d e f
ア n n n
イ n n 2n
ウ n 2n n
エ n 2n 2n
オ 2n n n
カ 2n n 2n
キ 2n 2n n
ク 2n 2n 2n
B 次の図は,被子植物の花粉の形成過程を模式的に表したものであり, ~ の順に進行して
いく。図中の黒い部分は核を表し,灰色あるいは薄灰色の部分は細胞質を表している。
図 被子植物の花粉の形成過程
問3 図のd~fの核がもつ核相の組み合わせとして正しいものを,次の解答群のア~クのうち
から一つ選べ。ただし,体細胞の核がもつ核相を2n で表す。 11
11 の解答群
94AM-No.3
-
― 449 ―
g h
ア 精核 精細胞
イ 精核 雄原細胞
ウ 精核 精原細胞
エ 胚乳核 精細胞
オ 胚乳核 雄原細胞
カ 胚乳核 精原細胞
キ 花粉管核 精細胞
ク 花粉管核 雄原細胞
ケ 花粉管核 精原細胞
問4 図のg,hの名称の組み合わせとして正しいものを,次の解答群のア~ケのうちから一つ
選べ。 12
12 の解答群
問5 次の記述 ~ のうち,図の説明として誤っているものの組み合わせを,下の解答群のア
~コのうちから一つ選べ。 13
図の ~ は若い子房の中でおきる。
図の ~ で減数分裂がおきる。
図の の段階を花粉四分子という。
図の gの核相は2n である。
図の hの核相は n である。
13 の解答群
ア , イ , ウ , エ , オ ,
カ , キ , ク , ケ , コ ,
95AM-No.3
-
― 450 ―
i j k
ア 配偶体 胞子のう 胚珠
イ 配偶体 胞子のう 前葉体
ウ 配偶体 前葉体 胚珠
エ 配偶体 前葉体 前葉体
オ 胞子体 胞子のう 胚珠
カ 胞子体 胞子のう 前葉体
キ 胞子体 前葉体 胚珠
ク 胞子体 前葉体 前葉体
C コケ植物やシダ植物では,精子と卵による生殖と,胞子による生殖の両方を行う。
コケ植物では,ふつうに見られる植物体は 配偶体であり,多くは雌雄の区別がある。雄株の
造精器でつくられた精子は,泳いで雌株の造卵器の卵と受精する。受精卵は雌株に付着したまま
発生し, 胞子体を形成する。やがて胞子体に 胞子のうが生じ,その中で減数分裂がおこって
胞子が形成される。胞子が育ち,雄株と雌株になる。
一方,シダ植物では,ふつうにシダとよんでいるのは i である。葉に j が生じ,その
中で減数分裂によって胞子が形成される。胞子は発芽して k となる。 k にある造精器で
つくられた精子は,造卵器の卵と受精し,若いシダとなる。
問6 文中の空欄 i ~ k に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~クのうちから一つ選べ。 14
14 の解答群
96AM-No.3
-
― 451 ―
ア n n n
イ n n 2n
ウ n 2n n
エ n 2n 2n
オ 2n n n
カ 2n n 2n
キ 2n 2n n
ク 2n 2n 2n
i j
ア n n
イ n 2n
ウ n 3n
エ n 4n
オ 2n n
カ 2n 2n
キ 2n 3n
ク 2n 4n
問7 下線部 ~ に示した植物体の核相(n で表す)の組み合わせとして正しいものを,次の
解答群のア~クのうちから一つ選べ。 15
15 の解答群
問8 文中の空欄 i ・ j で示した植物体の核相(n で表す)の組み合わせとして正しい
ものを,次の解答群のア~クのうちから一つ選べ。 16
16 の解答群
97AM-No.3
-
― 452 ―
遺伝情報を担う物質に関する次の文章を読み,下の問い(問1~7)に答えよ。
細胞分裂と生殖の過程を通して染色体の数と大きさがよく保存されていることが知られており,
a とその共同研究者たちによってキイロショウジョウバエの染色体地図の作成が進められ,
b の数と大きさがこの生物の染色体の数と大きさによく対応することが示された。ここから
遺伝情報を担う物質が染色体上にあることが強く支持されるに至っていた。しかしながら,遺伝
情報を担う物質がDNAであることはなかなか受け入れられなかった。これは,DNAがデオキ
シリボースという糖とリン酸,アデニン(A),グアニン(G),チミン(T),シトシン(C)の
たった6種類の小さな化合物が結合したものであり,多彩な機能を担うタンパク質などに比べて
あまりにも単純な物質と思われたからである。これに対して, c は,グリフィスの観察を基
に,病原性をもつ肺炎双球菌から精製したDNAを病原性のない肺炎双球菌に与えると,病原性
をもつ肺炎双球菌に変化することを示し,DNAが病原性という遺伝情報を担うことを明らかに
した。この肺炎双球菌の例のように,細胞外から与えたDNAの遺伝情報によって生物の性質が
変化することを d といい,この研究は外部DNAによる生物の遺伝情報の操作の先駆けとも
なった。
また, e は大腸菌に感染する f の g と h とをそれぞれ区別して検出できるよ
うに標識し,大腸菌に感染させたのち, f の g が大腸菌の外に残り, h のみが大腸
菌の中に入って新しい f を形成させることを示した。彼らの実験は厳密なものではないが,
遺伝情報がDNAによって担われることを新しい方法を用いた実験によって強く印象づけた。
ワトソンとクリックは,DNAが糖とリン酸が交互につながった鎖のような長い分子であるこ
と,A,G,T,Cはそれぞれ糖に結合していること, i が見いだしたDNA中の j の数,
および k の数がそれぞれ生物によらずほぼ一致すること,また, l とフランクリンのX
線回折による研究によって推定されたDNAの立体構造の概要などに基づいて分子モデルを組み,
DNAの m 構造を n 年に発表した。この構造モデルは,DNAの遺伝情報がA,G,T,
Cの配列にあることを明確に示していた。また,対となる j が,あるいは k がそれぞれ
別々の糖とリン酸の鎖に結合して並び, o 性のある配列となっており,遺伝情報の保存のし
くみを説明できる優れたモデルであった。この発表から現在に至る生命科学の大発展が始まった。
98AM-No.3
-
― 453 ―
a b
ア サットン 連鎖群
イ サットン ゲノム
ウ サットン 遺伝子
エ モーガン 連鎖群
オ モーガン ゲノム
カ モーガン 遺伝子
c d
ア アベリー(エイブリー) 形質転換
イ アベリー(エイブリー) 組換え
ウ アベリー(エイブリー) 乗換え
エ ミーシャー 形質転換
オ ミーシャー 組換え
カ ミーシャー 乗換え
問1 文中の空欄 a ・ b に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~カのうちから一つ選べ。 17
17 の解答群
問2 文中の空欄 c ・ d に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~カのうちから一つ選べ。 18
18 の解答群
99AM-No.3
-
― 454 ―
e f g h
ア ドフリース バクテリオファージ タンパク質 DNA
イ ドフリース バクテリオファージ DNA タンパク質
ウ ドフリース S型菌 タンパク質 DNA
エ ドフリース S型菌 DNA タンパク質
オ ハーシーとチェイス バクテリオファージ タンパク質 DNA
カ ハーシーとチェイス バクテリオファージ DNA タンパク質
キ ハーシーとチェイス S型菌 タンパク質 DNA
ク ハーシーとチェイス S型菌 DNA タンパク質
i j k l
ア ラントシュタイナー Aと C Gと T ウィルキンス
イ ラントシュタイナー Aと C Gと T ベーツソン
ウ ラントシュタイナー AとT Gと C ウィルキンス
エ ラントシュタイナー AとT Gと C ベーツソン
オ シャルガフ AとT Gと C ウィルキンス
カ シャルガフ AとT Gと C ベーツソン
キ シャルガフ Aと C Gと T ウィルキンス
ク シャルガフ Aと C Gと T ベーツソン
問3 文中の空欄 e ~ h に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~クのうちから一つ選べ。 19
19 の解答群
問4 文中の空欄 i ~ l に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~クのうちから一つ選べ。 20
20 の解答群
100AM-No.3
-
― 455 ―
m n o
ア はしご 1949 相補
イ はしご 1949 対称
ウ はしご 1953 相補
エ はしご 1953 対称
オ 二重らせん 1949 相補
カ 二重らせん 1949 対称
キ 二重らせん 1953 相補
ク 二重らせん 1953 対称
問5 文中の空欄 m ~ o に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~クのうちから一つ選べ。 21
21 の解答群
問6 遺伝物質の満たすべき条件の記述として誤っているものを,次の解答群のア~オのうちか
ら一つ選べ。 22
22 の解答群
ア 生命活動に必要な情報をもっている。
イ 子孫に遺伝情報が伝達されるように,正確に複製できる。
ウ 生物種間や種内には遺伝的違いがあることから,変化が可能である。
エ 膨大な遺伝情報を担うことができる。
オ 安定な物質であって,体細胞分裂や減数分裂の過程でも切断されない。
101AM-No.3
-
― 456 ―
問7 次の記述 ~ のうち,染色体と遺伝に関する文として正しいものの組み合わせを,下の
解答群のア~クのうちから一つ選べ。 23
ヒトの細胞の核あたりのDNA量は生物の細胞のなかで最大である。
染色体の主要成分はDNAとタンパク質である。
同じ生物でも体細胞の核あたりの平均DNA量は器官によって大きく違う。
体の大きな生物の細胞ほど核あたりのDNAの量が大きい。
細胞増殖のすべての時期を通して細胞あたりのDNAの量は一定である。
連鎖している2つの遺伝子は同じ染色体上にある。
連鎖している2つの遺伝子間の組換え価は,全配偶子の数に対する組換えをおこした配偶
子の数の比率(%)によって示される。
連鎖している2つの遺伝子間の組換え価は,組換えをおこさなかった配偶子の数に対する
組換えを起こした配偶子の数の比率(%)によって示される。
23 の解答群
ア , , イ , , ウ , , エ , ,
オ , , カ , , キ , , ク , ,
102AM-No.3
-
― 457 ―
動物の行動に関する次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~6)に答えよ。
A 動物の生得的行動のうち,外部からの刺激に反応しておこる移動運動などのように方向性が
認められる行動を走性とよぶ。また,クモが巣網を張ったり,鳥が巣づくりをしてひなを育てた
りする行動を本能行動とよぶ。この本能行動を引きおこすには, きっかけとなる刺激が必要で
ある。
問1 次の記述 ~ のうち,走性に関する文として正しいものの組み合わせを,下の解答群の
ア~コのうちから一つ選べ。 24
ミミズが昼間に土のなかで生活するのは,負の光走性によるものである。
小川のメダカがどの個体も頭を流れに向けて泳いでいるのは,負の流れ走性によるもので
ある。
雌のカイコガの分泌するフェロモンによって雄のカイコガが雌に近よっていくのは,正の
化学走性によるものである。
ガが街灯に集まるのは,負の重力走性によるものである。
二酸化炭素濃度が高いところにゾウリムシが移動するのは,負の化学走性によるものであ
る。
24 の解答群
ア , イ , ウ , エ , オ ,
カ , キ , ク , ケ , コ ,
問2 下線部 に関して,本能行動のきっかけとなる刺激を何というか。次の解答群のア~カの
うちから一つ選べ。 25
25 の解答群い き ち かぎ
ア 閾値 イ 触覚刺激 ウ 電気刺激 エ 適刺激 オ 鍵刺激
カ 条件刺激
103AM-No.3
-
― 458 ―
腹部と背部がともに銀白色の
イトヨの形に似せた模型
腹部が赤色で背部が銀白色の
イトヨの形に似せた模型
腹部と背部がともに銀白色の
イトヨの形に似ていない模型
腹部が赤色で背部が銀白色の
イトヨの形に似ていない模型
問3 繁殖期に入ったイトヨの雄は,巣に近づく同種のオスを追い払う本能行動をおこす。次の
図に示すイトヨと大きさがほぼ同じ4つの模型を用いて実験を行った。模型を巣に近づけた場
合,イトヨの雄が攻撃行動をおこす模型の組み合わせとして正しいものを,下の解答群のア~
コのうちから一つ選べ。 26
図 イトヨの模型の形と色
(図では,赤色を濃いグレーで示した。)
26 の解答群
ア のみ イ のみ ウ のみ エ のみ
オ , カ , キ , ク ,
ケ , , コ , , ,
104AM-No.3
-
― 459 ―
B ある種の動物では,生まれてからの経験が記憶として残り,これによって複雑な行動をとる
ことが可能となる。経験によって行動が変化し,その新しい行動が長く続くとき,この行動の変
化を a という。 a には,さまざまなものがある。たとえば,ネズミなどを迷路に入れた
とき,誤りを繰り返しながら正しいやり方を習得していく b や, アヒルなどが卵からかえ
ってまもないときに,最初に見た動くものを親だと思い,後を追う c なども, a のうち
の一つである。
大脳の発達した動物は,記憶として残った経験にもとづく行動のほかに,未経験の出来事に対
しても,これまでの経験にもとづく行動を踏まえて大脳による思考や推理を働かせて目的にかな
った行動をとることができる。このような行動は,知能行動とよばれる。
問4 文中の空欄 a ~ c に入れる語句として最も適当なものを,次の解答群のア~コの
うちから一つずつ選べ。解答番号は a は 27 , b は 28 , c は 29
27 , 28 , 29 の解答群
ア 反射 イ 求愛行動 ウ 試行錯誤 エ 刷込み
オ 慣れ カ 鋭敏化 キ 条件づけ ク 学習
ケ ホメオスタシス コ 洞察学習
問5 下線部 に関して,この事実を発見した研究者として正しい人物を,次の解答群のア~カ
のうちから一つ選べ。 30
30 の解答群
ア ティンバーゲン イ パブロフ ウ フォン フリッシュ
エ ローレンツ オ カハール カ ヘルムホルツ
105AM-No.3
-
― 460 ―
問6 次の記述 ~ のうち,知能行動の例として正しいものの組み合わせを,下の解答群のア
~コのうちから一つ選べ。 31
チンパンジーは草の茎をアリの巣に入れて,茎についてくるアリを食べる。
イヌはえさを与えるとだ液を分泌する。イヌにえさを与えるたびにベルの音を聞かせると,
やがて,イヌはベルの音を聞いただけでだ液を分泌するようになる。
ヒトは目の前にものが飛んでくると,思わず目を閉じる。
金網で作ったおりのなかに入れられたサルは,おりの外にあるえさに気付くと,えさの位
置と反対にある開けられた扉を通って,えさにありつく。
アリはえさをみつけた仲間が分泌した化学物質のあとをたどる。
31 の解答群
ア , イ , ウ , エ , オ ,
カ , キ , ク , ケ , コ ,
106AM-No.3
-
― 461 ―
a b c
ア 根端 師管 気孔
イ 根端 師管 水孔
ウ 根端 道管 気孔
エ 根端 道管 水孔
オ 根毛 師管 気孔
カ 根毛 師管 水孔
キ 根毛 道管 気孔
ク 根毛 道管 水孔
次の文章A・Bを読み,下の問い(問1~4)に答えよ。
A 植物の生命活動に重要な物質である水は,根の表皮細胞が変形した a によっておもに吸
収される。その後,水は茎の中の b を上昇して,葉の c から放出される。 a の細胞
が水を吸収できる理由は,土壌の浸透圧が細胞内の浸透圧より d いためである。 b に入
った水分子は, e 力という力で互いに離れにくい性質をもつため, c から放出されるの
と連動して途切れることなく引き上げられる。葉には多くの c が分散して存在し,水はここ
から水蒸気として大気中に放出される。
問1 文中の空欄 a ~ c に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~クのうちから一つ選べ。 32
32 の解答群
107AM-No.3
-
― 462 ―
d e
ア 高 吸水
イ 高 凝集
ウ 高 浸透
エ 低 吸水
オ 低 凝集
カ 低 浸透
問2 文中の空欄 d ・ e に入れる語句の組み合わせとして正しいものを,次の解答群の
ア~カのうちから一つ選べ。 33
33 の解答群
問3 次の記述 ~ のうち,下線部に説明されているしくみによりおこることとして正しいも
のの組み合わせを,下の解答群のア~コのうちから一つ選べ。 34
ある植物の茎を地面に近い部分で切り取ったところ,切り口から水が出た。
根を除去した切り花も花瓶の水を吸い上げることができる。
サトイモやイチゴなどの植物では,早朝,葉の縁に水滴がついていることがある。
葉の温度上昇を抑える。
34 の解答群
ア , イ , ウ , エ ,
オ , カ , キ , , ク , ,
ケ , , コ , ,
108AM-No.3
-
― 463 ―
図1 CO2濃度と光合成速度 図2 温度と光合成速度
B 図1は二酸化炭素濃度と光合成速度,図2は温度と光合成速度の関係について,同じ植物を
もちいて実験した結果を図示したものである。図1より,光の強さが一定の場合, の部分では
f が限定要因となっているが, の部分では g , h が限定要因となっていると推測
される。図1の実験が35℃でおこなわれたとすると,図2の実験結果と考え合わせた場合, の
部分における限定要因は g と推測される。
図2では,二酸化炭素が十分に与えられている場合,光が弱いと光合成は温度の影響を受けな
いが,光が強いとある一定の温度までは光合成速度が上昇する。図2の結果から,光合成速度の
限定要因は,光が弱い場合には i と考えられる。
問4 文中の空欄 f ~ i に入れる語句として最も適当なものを,次の解答群のア~カの
うちから一つずつ選べ。解答番号は f は 35 , g は 36 , h は 37 ,
i は 38
35 , 36 , 37 , 38 の解答群
ア 酸素濃度 イ 二酸化炭素濃度 ウ 温度 エ 湿度
オ 気圧 カ 光の強さ
109AM-No.3