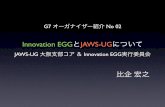知ってほしい 刑罰のこと - 日本弁護士連合会...5 3 3 刑罰について考えてほしいこと 3刑罰について考えてほしいこと ~被告人の改善更生~
第 号 71 - azuchi-museum.or.jpazuchi-museum.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/71.pdf ·...
Transcript of 第 号 71 - azuchi-museum.or.jpazuchi-museum.or.jp/wordpress/wp-content/uploads/2013/03/71.pdf ·...

(松阪市宝塚1号墳:松阪市教育委員会蔵)
(和歌山市井辺八幡山古墳:和歌山市教育委員会蔵)
�
ISSN 0919-0821
平成22年(2010年)3月31日滋賀県立安土城考古博物館
第 号71

(財)滋賀県文化財保護協会 調査整理課通信
�
「金剛般若経」のこけら経
―
全国初の「見せ消ち」もあり
―
近年の調査でわかってきた特徴的な埴輪とし
て、家形埴輪と、それに関わり発見された「導水
施設形埴輪」と「井戸施設形埴輪」があります。
埴輪に表現された「導水施設」や「井戸」が、奈
良県南郷大東遺跡や群馬県三ツ寺Ⅰ遺跡などにお
いて、実際の遺構として発見されており、埴輪に
表現されたまつりが、具体的に各地でなされてい
たことが明らかになってきています。また「埴輪群
像」についても、近年、真の継体天皇の墓とされる
大阪府今城塚古墳の発掘調査により、大規模な埴
輪群像が発見され、古墳時代の王権に関わる祭祀
について再検討を迫ることになってきています。
本展では、こうした埴輪と関連資料を集めて、
それが示す祭祀や思想について考えるとともに、
古代人の祈りや造形についても検討したいと考え
ています。
主な展示資料
南郷大東遺跡出土資料
(奈良県立橿原考古学研究所附属博物館蔵)
神並・西ノ辻遺跡出土資料
(東大阪市教育委員会蔵)
狼塚古墳出土導水施設形埴輪
(藤井寺市教育委員会蔵)
百足塚古墳出土人物埴輪(新富町教育委員会蔵)
保渡田八幡塚古墳出土人物埴輪
(かみつけの里博物館蔵)
山倉一号墳出土人物埴輪(市原市教育委員会蔵)
関連行事等
*特別展記念講演会
「私説埴輪論
―
どうした祭りを表現しているのだろうか―
」
講
師
水野正好氏(奈良大学名誉教授)
開催日
五月五日(火祝)
*博物館講座
「ヤマト王権と水のマツリ―
導水施設と囲形・家
形埴輪からみた王権の権力基盤―
」
講
師
青柳泰介氏(奈良県立橿原考古学研究所)
開催日
五月一六日(日)
「水をまつる王たち―
水利開発と神まつり―
」
講
師
若狭
徹氏(高崎市教育委員会)
開催日
五月三〇日(日)
「宮崎県百足塚古墳の調査」
講
師
有馬
義人氏(新富町教育委員会)
開催日
六月一三日(日)
※�時間はいずれも午後一時三〇分から、会場はい
ずれも当館二階セミナールーム(定員一四〇
名・先着順)
平成二二年度春季特別展�
導水施設と埴輪群像から
見えてくるもの
―
古墳時代の王権とまつり
―
高島市天神畑遺跡の川跡から室町時代のこけ
ら経が一一五点見つかりました。経典は「妙法
蓮華経」が六九点、「金剛般若経」が三八点の
ほかに五種類が確認されました。こけら経の多
くは、先祖供養などのために薄い木の板に写経
したものです。全国の遺跡や寺院、仏像の体内
など一〇〇ヵ所以上で発見されています。川や
池、井戸など水に関係する場所から多く出土し
ています。これまで見つかっている経典のほと
んどは「妙法蓮華経」で、「金剛般若経」の出
土は全国で三例目です。「金剛般若経」は禅宗
で重んじられる経典のため、近江が禅宗文化の
影響を強く受けたことを示す貴重な資料です。
今回見つかったこけら経の中に二点誤字を修
正した「見せ消ち」と呼ばれる「ヒ」の印が見
つかりました。「見せ消ち」の出土例は全国で
初めてです。誤字である「佛」の左側に「ヒ」
を記し、正しい文字「他」を右側に書き入れ
ています。有難い経典を無駄にせず一文字も
塗り消すこと
なく、大切に
扱った様子が
窺えます。
心合寺山古墳出土導水施設形埴輪(八尾市歴史民俗資料館蔵)

滋賀県教育委員会文化財保護課 城郭通信
�
織田信長が発は
っきゅう給した文も
んじょ書の文字は、信長が書い
ていると思われがちですが、基本的には、地位の
ある人は自分で文字を書くことはまずありませ
ん。性格や権力の大きさによって異なりますが、
中でも信長は、自らの文字をほとんど残しません
でした。現存する信長の自筆で確実なものは、
堀ほりひでまさ
秀政が「自じ
ひつ筆之の
御おんしょ書」であるという証明書が添
えられた、細川忠た
だおき興
宛あて
の一通しかありません。
信長の代わりに文字を書いたのが、右ゆ
うひつ筆
と呼ば
れる役を務める家臣でした。戦場で華々しい戦功
を上げる武官とは異なり、文ぶ
んぴつ筆や政治・支配など
で能力を発揮する文官となるため、その名はあま
り知られていません。
写真の楠長諳書状は、信長の右筆の一人である
楠長諳が、自分の名で出した書状です。長諳は楠
正まさしげ成の子孫と称し、最初は松ま
つなが永久ひ
さひで秀に仕えていま
したが、天
てんしょう正元年(一五七三)頃から信長に仕
えるようになります。以後は、もう一人の右筆で
ある武た
けい井
夕せきあん庵
と二人で、ほとんどの信長発給文書
の文字を書くようになりました。
��
もう一枚の写真は信長の黒こ
くいんじょう
印状ですが、文字は
長諳が書いています。少しくずし方の度合いが違
いますが、書面の雰囲気が似ていますし、両方に
共通して見られる「弥」の字の癖も同じです。長
諳の書く「信長」という署名は特徴があるので、
覚えておけば長諳の字を見分けることができるよ
うになります。人に教えるミニ知識として、使っ
てみてはいかがでしょう。
(髙木叙子)
楠くすのき
長ちょうあん諳
書しょじょう状
(元亀三年(
一五七二))
閏正月九日
一二.九㎝×四三.八㎝
史跡観音寺城跡の調査
今年実施した史跡観音寺城跡の調査では、大
きな土塁がそびえている伝本丸跡の虎口を発掘
しました。土塁に付随する門の礎石などが見つ
かると期待したのですが、残念ながらそうした
防御施設はいっさい見つかりませんでした。調
査範囲が狭いので確かなことは言えませんが、
もともとそうした施設はなかったとみられま
す。一般的な中世城郭の防御システムが不明確
な観音寺城の特徴が改めて浮かび上がる結果と
なりました。
さて、発掘調査とともにすすめている石垣調
査では、観音正寺下の伝進藤邸・伝後藤邸と呼
ばれる付近の石垣を調査しました。このあたり
は、伝本丸跡などとともに、もっとも石垣が良
く保存されていることが知られていましたが、
竹林に埋も
れて立ち入
ることが困
難でした。
今回の調査
により、改
めてその威
容をうかが
うことがで
きました。
収蔵資料紹介
▲織田信長黒印状(当館蔵)▲楠長諳書状

�
博物館の主な催し
おおてみち 第 71 号平成22年(2010年)3月31日発行
編集・発行 滋賀県立安土城考古博物館〒521−1311 滋賀県近江八幡市安土町下豊浦6678 TEL0748−46−2424E-mail:[email protected] URL http://www.azuchi-museum.or.jp
4月 〜4日(日)まで 第39回企画展「湖西の風土と遺宝―高島郡を中心に―」〜9日(金)まで テーマ展「近江の城 小川城展」
平成二二年四月二四日(土)〜六月十三日(日)
�
平成二二年度春季特別展�
「導水施設と埴輪群像から見えてくるもの―古墳時代の王権とまつり―」
平成二二年四月二〇日(火)〜六月六日(日)�
テーマ展「摠見寺所蔵名品展」(第二常設展示室)
24日(土)スライド発表会「観音寺城最新情報」� 時間:午後1時30分〜午後5時 参加費:無料� 場所:当館2階セミナールーム
29日(祝・木)春のお茶会 (当日受付、約100名)� 時間:午前10時30分〜午後3時� 場所:当館エントランスホール お茶・お菓子代:300円
5月3日(祝・月)
体験博物館「勾玉をつくろう!!」� 時間:①午前10時〜②午後1時30分〜 参加費:500円� 場所:当館敷地内 定員:各回30名� ※事前申込必要:予約受付開始4月3日(土)先着順
4日(祝・火)�※雨天の場合は 翌5日(祝・水)に 順延
第18回 近江風土記の丘を描こう!!親子写生大会� 時間:午前10時30分〜午後4時 � 場所:「近江風土記の丘」敷地内� 受付:当館玄関前(正午まで) � ※作品展示6月22日(火)〜7月4日(日)
5日(祝・水)
春季特別展記念講演会「私説埴輪論―どうした祭りを表現しているのだろうかー」� 講師:水野正好氏(奈良大学名誉教授) � 時間:午後1時30分〜3時� 会場:当館2階セミナールーム� 定員:140名(当日先着順) 参加費:無料
16日(日)
博物館講座「ヤマト王権と水のマツリ―導水施設と囲形・家形埴輪からみた王権の権力基盤ー」� 講師:青柳泰介氏(奈良県立橿原考古学研究所) � 時間:午後1時30分〜3時 � 会場:当館2階セミナールーム� 定員:140名(当日先着順) 参加費:無料
23日(日)体験博物館「埴輪にふれてみよう!!」� 時間:午後1時30分〜 参加費:500円� 場所:当館内 定員:30名� ※事前申込必要:予約受付開始4月23日(金)先着順
30日(日)
博物館講座「水をまつる王たち―水利開発と神まつりー」� 講師:若狭 徹氏(高崎市教育委員会) � 時間:午後1時30分〜3時� 会場:当館2階セミナールーム� 定員:140名(当日先着順) 参加費:無料
6月
6日(日)
体験博物館「木村古墳群を探検する」� 時間:午後1時30分〜 参加費:300円� 場所:現地 定員:20名� ※事前申込必要:予約受付開始5月6日(木)先着順� 当日集合場所・時間:JR近江八幡駅南口 午後1時(予定)
13日(日)
博物館講座「宮崎県百足塚古墳の調査」� 講師:有馬義人氏(新富町教育委員会) � 時間:午後1時30分〜3時� 会場:当館2階セミナールーム� 定員:140名(当日先着順) 参加費:無料
7月 17日(土)〜9月26日(日) 第40回企画展 滋賀県文化財保護協会調査成果展�「戦国の琵琶湖―近江の城の物語―」