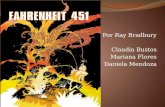第 451 回月例研究会資料 - LINkashikyo.lin.gr.jp/images/05_other/geturei/451.pdf451...
Transcript of 第 451 回月例研究会資料 - LINkashikyo.lin.gr.jp/images/05_other/geturei/451.pdf451...
-
一般社団法人日本科学飼料協会及びその会員は、「私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法
律」等のコンプライアンス(法令順守)の重要性を認識し、これを推進してまいります。
第 451 回月例研究会資料
「家畜の生産性向上と環境負荷低減をはかるルーメン発酵制御」 【講義の概要】 ウシに代表される反芻動物は、上部消化管に複胃を有し、中でも第一胃(ルーメン)
に多様な微生物群を形成することで、摂食した繊維質の分解を微生物にゆだねている。
この嫌気的ルーメン微生物発酵下では代謝性水素の主要処理物としてメタンが生成さ
れる。可燃ガスであるメタンはあい気(ゲップ)として体外へ放出されるため、飼料
エネルギーの損失となる。過去半世紀にわたり、もっぱら「飼料エネルギー利用効率
改善」という視点で反芻家畜からのメタン低減が研究対象になってきた。ルーメン発
酵を低メタン産生が導かれるような様式に変えること、すなわちルーメン微生物相を
調節することの試みが数多くなされてきた。最も成功をおさめたのが抗生物質モネン
シンであった。元来は鶏の抗コクシジウム剤として用いられていたが、牛のルーメン
発酵調節剤として 1970 年代後半から米国を中心に応用展開がなされた。モネンシンはメタン低減とともに、肉牛の飼料要求率改善をもたらすことが実証されたが、EUでの家畜成長促進用抗生剤の撤廃(2006 年)を機に、世界的に代替物質の探索といった潮流が生じている。
その一方で、「反芻家畜からのメタン低減は近年の温暖化論議の中でより大きな注
目を集める」ようになった。その理由は、ルーメン微生物発酵でつくられるメタンが
全世界のメタン生成量の 20%近くを占めること、CO2 換算するとウシ 1 頭がおおよそ自家用車 1 台分の温暖化ガスエミッターであること、総計すると家畜消化管から出るメタンは全地球温暖化ガスの約4 -5%に相当すること、などに要約される。畜産立国であるニュージーランドでは、家畜からのメタンが国全体の温暖化ガス総量の 30%以上を占めるため、その“罪状”は甚大である。このような新たな背景の下で、世界各
国でメタン低減方法の模索が始まった。これまで飼料添加された抗生物質により、約
5-10%程度のメタン低減が可能であったが、抗生物質の永続使用に懸念が示されている今、新たな代替物のニーズが高い。欧州の研究機関では 500 種の収集植物からメタン低減効果を有する数種を培養試験で選抜したものの、動物試験でのメタン低減は明
確にできずに終わっている。メタンを低減させたとしても、代謝性水素が蓄積すると
発酵(飼料消化)そのものが遅滞する。したがってメタン生成以外の水素処理経路を
活性化する必要がある。もっとも現実的なのがプロピオン酸生成経路である。 本研究会では、ルーメン発酵の調節方法を概説し、メタン低減・プロピオン酸増強
効果の意義を説明するとともに、同効果をもつ天然物として注目をあびている素材(カ
シューナッツ殻液、ギンナン果肉)について紹介する。すなわち、本素材に含まれる
希少フェノール類(アナカルド酸ほか)は、その界面活性作用を通してルーメン微生
物を選抜し、発酵様式をプロピオン酸優先型へとシフトさせ、メタン低減を導く。特
に、カシュー素材は動物嗜好性の高いように製剤化され、国内外の給与試験で効果が
実証されつつある。世界的にメタン排出量の多い東南アジアでの研究展開についても
言及する。 平成 29 年 11 月 13 日
北海道大学大学院農学研究院 教授 小林泰男
-
家畜の生産性向上と環境負荷低減をはかるルーメン発酵制御
北海道大学農学部 小林泰男豚
牛
ニワトリ
ルーメン: 牛の第一胃は重要な消化発酵槽であり、メタンガスを活発に生成している
第一胃(ルーメン)70-100L
げっぷ
セルロース ペクチン ヘミセルロース
ウシルーメン(第一胃)での繊維質消化発酵
酢酸 ・ プロピオン酸 ・ 酪酸
ブドウ糖 ピルビン酸
吸収(動物のエネルギーとなる)
水素二酸化炭素
微生物増殖(タンパク源)
セロビオース ガラクツロン酸 キシロース
メタン
ゲップ ルーメン発酵の制御とは?1.繊維質消化の向上2.タンパク質分解(速度と程度)の抑制3.でんぷん分解・発酵(速度)の抑制4.メタン生成の抑制
その戦略は?・家畜の採食速度・量の調節(分割・制限給与)・飼料構成(粗濃比など)の調節・添加物や特殊飼料による調節
ルーメン微生物相の制御
制御の本体 = 微生物の取捨選択
抗生物質 ➡ 家畜への活用
➡ 病気になりにくい = 成長促進 = 飼料節約
➡ 長期使用で生じる問題?
1.これまでの経緯
-
モネンシン投与によりヒトに用いる抗菌性物質に耐性を獲得した食品由来細菌が選択される
モネンシン投与動物からの耐性菌に汚染された食肉を人が摂取する
これらの耐性菌を摂取した人が当該菌による感染症を発症する
抗生物質モネンシンのリスク評価農水省→食品安全委員会へ評価依頼(2003.12)
食品安全委員会の結論 (2006.9)モネンシンはいずれのリスク基準にも該当しない。
↓食用 動物における使用は、ヒトの健康へのリスクになる可能性は無視できる程度と考えられる。
→ 該当せず
→ 該当せず
→ 該当せず
農水省は,モネンシンの継続使用 を正式承認へ
2.海外(主に欧州)の研究動向
二つのプロジェクトが契機。
REPLACE: 全家畜対象(牛、豚、鶏、魚)RUMEN-UP : 牛のみが対象
代謝性水素[2H]
フマル酸還元
プロピオン酸
コハク酸
フマル酸
メタン生成CH4
CO2
グルコース
ピルビン酸
4H2
ギ酸
消化管嫌気発酵での主な水素処理系
飼料の炭水化物
多くの有用物質
ゲップで排出↓
飼料エネルギー損失温暖化貢献
動物が吸収↓
グルコースに転換動物エネルギー源に
× ○
・ 500種類の植物および植物抽出物の収集
・ 試験管レベルでの下記項目への影響検証発酵、メタン産生、タンパク質分解、原生生物、アシドーシス、鼓脹症
・ 見込みがある物質を選抜
・ 下記の項目を再検証投与量反応、化学的特性、毒性、許容性
・ 家畜への給与試験に向けて、候補2物質を選抜
“RUMEN-UP” 研究成果
・ 23種類の有効素材を確認 ⇒ 特許化
・ 8種類は10%以上発酵を遅らせた
・ 複数の効果を持つ素材も確認― 原虫とメタン産生への効果:5種類― タンパク分解と原虫への弱い効果:2種類― 原虫とアシドーシスへの効果:3種類― メタン産生とアシドーシスへの効果:5種類
・ 選抜素材を用いた動物試験において、改善傾向が得られたが、明確な効果でなかった
-
米国を中心とした抗生物質モネンシンの利用
(1970年代後半~現在)
モネンシン添加飼料による、泌乳牛の乾物摂取量、乳量、乳質、メタン産生への影響
反応 (1区あたり12頭の平均値) 対照 モネンシン添加 標準誤差
乾物摂取量(kg/日) 19.7 19.1 0.36
乳量 (kg/日) 26.2 25.9 0.64
乳脂肪 (%) 3.90 3.53 0.098
乳タンパク (%) 3.37 3.23 0.031
メタン産生 (g/日) 458.7 428.7 7.75
メタン産生 (g/kg体重) 0.738 0.675 0.0141
メタン産生 (g/gNDFI※1) 0.069 0.066 0.0016
TMR
a ※2 ba b
a ba b
※1 NDFI:中性デタージェント繊維摂取量 ※2 異文字間に有意差あり (P <0.05)
メタ
ン産
生量
(g/
kg体
重)
時間 (月)
モネンシン給与開始
メタン低減は9%程度
モネンシンの効果要約(肥育牛)
増体量 不変
飼料摂取量 5-12%減少
飼料要求率 5-12%減少 ☺
プロピオン酸 25-33%増加
メタン 9-30%減少
脱アミノ(タンパクの過剰な分解) 抑制 ☺
鼓張症およびアシドーシスの予防
3.国内の研究動向
メタン低減をめざしたプロジェクト
出光興産・北大プロジェクト味の素・帯広畜大プロジェクト横浜バイオ・東京農工大プロジェクトJA愛知西・北大プロジェクト
*メタン低減のみでなく広くルーメン発酵安定化に貢献できることが次第に判明
天然抗菌物質:カシューナッツ殻液
カシューナッツ殻液
①抗菌成分を持つ (食経験あり)
②塗料として安価に輸入
カシューナッツ殻液がメタンとプロピオン酸生成に及ぼす影響を評価
COOHHO R HO R
OH
HO R
アナカルド酸 カルダノール カルドール
グラム陽性菌の生育を抑制
=モネンシンと類似→モネンシン代替物としての可能性
※ R=①C15:0②C15:1③C15:2④C15:3
メタン低減・プロピオン酸増強に及ぼす影響 (閉鎖培養系)
生殻液 加熱殻液
生殻液>加熱殻液有効添加濃度は 250~500μg/ml
(ml)
0
1
2
3
0 200 400 600
メタン生成量
)
(mM)
0
10
20
30
40
50
0 200 400 600
プロピオン酸生成量
カシュー殻液添加濃度(g/ml) カシュー殻液添加濃度(g/ml)
最大98%減
最大50%増
-
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
(log copy / ml)
*
*
**
*
***
*
*
人工ルーメン: ルーメン細菌主要種の変動対照 カシュ-
* P<0.05
水素/ ギ酸生成菌 コハク酸/プロピオン酸生成菌
ウシへの給与試験:メタン排出量 (L/day)
*
ControlCNSL
37.6%減
0
100
200
300
400
無添加 添加
37.6%*
Exp.1
Exp.2
無添加 添加
*19.3%
カシュー殻液を給与することで牛のメタン排出量は減少
菌叢変化
ギ酸、水素生成菌
コハク酸、プロピオン酸
生成菌
モネンシン カシューナッツ殻液
ルーメン発酵
メタンガス
プロピオン酸
粘度
アンモニア
乾物消失率
↓
↑
73%↓
33%↑
46%↓
41%↓
影響なし
16~30%↓
25~32%↑
50~60%↓13~33%↓
影響なし
飼料効率
↓
↑
メタンガス 16~60%↓ 73~98%↓
カシューナッツ殻液は抗生物質モネンシンの代替物として期待大
5~12%↑ ???
プロピオン酸 25~40%↑ 33~75%↑
-
メタン (mL/tube)
添加量依存的にルーメン液培養物からのメタンは低減し,プロピオン酸は増加する
0.0
0.5
1.0
1.5
2.0
2.5
0
10
20
30
40
50
60
プロピオン酸 (モル比 %)0
1
2
3
4
15
20
25
30
35
40
45
藤九郎
久寿
Control
a,b,c: P