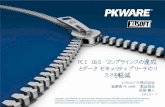Dropboxを活用して 講義資料を配信する方法 · Dropboxログイン方法(P.4~9) . データのアップロード方法(P.10~12) . データの共有方法(P.13~17)
BIM -...
Transcript of BIM -...

施工段階におけるBIM(3次元データ)の活用について
東京第二営繕事務所 保全指導・監督官室 南波 宏志
1.はじめに
国土交通省では、「国土交通省CAL
S/ECアクションプログラム200
8」に基づく具体的な実施項目として、
「3次元データを活用したモデル設
計・施工の実施」を掲げており、営繕
部では平成22年度からBIMの試行
をはじめている。(図1)
1.1 BIMとは?
BIMとは、Building Information
Modeling の略称であり、コンピュータ
上に単に3次元で物体の形が表現できるというだけでなく、コンピュータ上に構成される
空間や各部材・機器等に仕様・性能、コスト等の属性情報を持たせた建物情報モデルを構
築することをいう。つまり、IT技術の向上により、コンピュータの仮想空間上に、実際
の建物と同じモデルを構築(建設)し、設計・建設・運用のシミュレーションを行うこと
が可能となるものである。
図 1 報道発表資料
このBIMモデルを設計から施工、維持管理に至るまでの建築ライフサイクルのあらゆ
る過程で活用することで、建築のライフサイクル全体のプロセスに大きな変化が起こると
考えられている。(図2)
1.2 BIMのメリット
BIMBIMBIMBIM
施主
FM プレゼン
施主
FM プレゼン
意匠整合性
日影解析
環境設計
意匠整合性
日影解析
環境設計
構造
構造解析
整合性
構造解析
構造
構造解析
整合性
構造解析
設備
干渉確認
各種解析
設備
干渉確認
各種解析
施工
数量算出
施工検討
工程計画
施工
数量算出
施工検討
工程計画
図 2 BIM の発展性
営繕部ではBIMのメリットとして、
①設計の説明性が高まること、②建物
情報の入力・整合性確認による品質確
保、③建物情報の統一・一元化による
建築生産、維持管理運営の効率化等を
期待している。今回試行を行った施工
段階でのBIM活用のメリットとして
は、②及び③に関して、設計データを
有効に活用できること、施工図間(伏
図と断面図等)の不整合が無くなるこ
と、納まりの事前検討が効率的に行え
ること、施工者間(建築・電気設備・
機械設備)の取り合い検討が効率的に
行われることなどが考えられた。

1.3 事業概要
試行を行った事業は、海上保安
庁海洋情報部庁舎(仮称)建築工
事で、設計は平成 19~20 年度、工
事は平成 21~23 年度に実施され
るものである。設計者は安井建築
設計事務所、施工者は建築工事が
東亜建設工業、電気設備が九電工、
機械設備工事が日立プラントテク
ノロジーである。
2.施工段階のBIM活用
これまでは大手ゼネコンが設計
施工一貫(デザインビルド、PF
I等)でBIMを利用した事例は
あるが、公共建築工事で通常行わ
れている分離発注方式(設計・施
工及び施工段階では建築・電気・
機械)におけるBIM利用として
は、今回の試行が初の事例となる。
今回のBIM活用は、設計図の一
部がBIMにより作成されていた
ため、分離発注方式におけるBI
M活用を試行・検証し、今後の公
共建築におけるBIM導入に向けた課題整理を行うことを目的に、本省との連携や施工者
の協力のもと実現に至ったものである。
図 3 完成予想図
図 4 BIM連携図
本稿では施工段階のBIM活用の第一段階として、①従来型の発注である設計・施工及
び建築・電気・機械分離発注方式における施工段階でBIMの利用が可能か、②施工段階
でBIMを利用することによるメリット・デメリットについて考察した。なお、試行に当
たってはBIMの作業効率等が不確定なことから、実際の施工に用いる施工図は2次元C
ADで作成し、BIMによる施工図作成と並行して実施した。
2.1 作業環境の構築
BIMデータを施工者間で共用するため、企業間セキュリティを確保しつつデータの共
有ができる特殊なLANを構築した。ハードウェアは高性能の64ビット機、ソフトウエ
アは建築と設備で同一シリーズの設計と同じものと、異なるものの2種類を使用した。
2.2 施工図の作成
施工図作成に先立ち、建物基礎部のRC造部分で構造設計図とBIMモデルの整合性の
確認を行った。その結果、施工上は必要でも、設計段階であまり検討する必要のない小梁
や地中梁・耐圧盤のフカシ等が未入力であり、部材データの新規入力が必要だったものや、

図 5-2 耐圧フカシ部3D図
設計図のデータ入力方法ではスリーブを追加入力できないため、部材データの差し替えが
必要だったもの、部材のサイズ・レベル調整のため数値の修正が必要だったものが大部分
であった。これらの修正に膨大な作業量が必要であったが、この結果、図 5-1、5-2 に示す
ように躯体形状がコンピュータ上で明快に検証できるとともに、従来は部材の位置変更な
どがある度に、関係する複数の図面を修正する必要があったものが、BIMモデルのデー
タ修正を行っている限り、1つのモデルの修正で済み、図面間の食い違いも発生しない。
また、BIMは各部材に寸法等の属性情報を持たせているため、施工に必要な梁符号を表
示させたり(図6)、属性を修正すればBIMモデルが連動して修正されるなどの作業効
率向上が確認された。なお、人通口や一部のフカシについて3次元での入力が困難なもの
については2次元とした施工図段階で書き加えた。作業効率性を考えると、全てのデータ
入力をBIMとするのではなく、2次元CADと使い分けることが有効であることも確認
できた。今回は設計時と同一のソフトウエアを使用したため、データの引き継ぎについて
は問題なく行われた。
2.3 3Dデータの統合
施工図の作図作業は各施工者が行っている
ため、建物の統合データを作成するには各社
の情報を統合させる必要がある。同一シリー
ズのBIMソフトウエアの場合は相互リンク
機能により作業中もそれぞれのデータ参照が
可能であった。次に別メーカーのソフトウエ
アを使用し互換データに変換した後、データ
統合ソフトによりデータ統合を行った。この図 7 干渉チェック
小梁
梁上フカシ部
図 5-1 フカシ部3D図
基礎小梁
耐圧盤勾配に
よるフカシ部
BIMのタグ情報
施工図に必要な符号
図6 属性情報

場合、データ統合後に3Dデータとして干渉部のチェックは行えるものの(図7)データ
を修正する場合は、データ変換前の元々のソフトウエアでデータを修正して再度統合を行
う必要があった。また、属性情報を全て統合することができないため、BIMモデルとし
て完全なものとはならないことが分かった。
図8 躯体図と設備図
3.試行から分かったこと
今回の試行結果から、施工段階でBIM活用をする場合に、
①設計段階で入力されているデータと、施工において必要なデータが異なることなどから、
施工段階でのデータ修正・追加作業に要する作業量が多いため、効率的に施工時の作業を
行うためには設計時に入力する範囲や部材作成方法をルール化することが必要であること。
②分離発注方式においてBIMを試行する場合、企業間のセキュリティを確保しつつ、現
場内ネットワークを構築することが必要である。セキュリティの問題から実施できない可
能性もあるため、発注段階で接続可能な条件を整理する必要があること。
③設計データを施工段階で利用し、また、各社がネットワーク上で作業する場合、他社の
データを変更できてしまうため、部材データ等に間違いがあった場合の責任の所在が明確
になってないこと。
④ソフトウエア上の問題で入力困難な箇所があるため、改良が必要であること。
⑤設計段階と同一のシリーズのソフトウエアの利用がスムースなデータ引き継ぎに繋がる
が、あらかじめソフトウエアの指定をすることが難しいこと。
などが今後、検討・考慮すべき事項として抽出された。
4.まとめ
今回は施工図作成と施工者間の3Dデータの統合を主眼に試行を行ったが、今回の設計
データは意匠図の4割程度のBIM化であったため、追加作業が多かったことや、データ
修正や3Dモデルからの施工図作成に従来より時間を要した。一方で、業者間や図面間の
連携の明快さや属性情報を効率的に利用できることによるメリットも実感できた。今後、
設計段階でのデータ範囲を明確にし、施工を考慮した入力方法のルール化がなされれば、
施工時の各種検討や施工図の作成に要する時間を大幅に短縮できるものと考えられる。
また、今後、施工段階でBIMを用いる場合は、情報共有や使用ソフトウエア等発注条
件の付加が必要なことや、データの管理方法等幾つかの課題も抽出された。これらの課題
が解決されることにより、施工段階でのBIMの活用が一層推進されるものと考える。