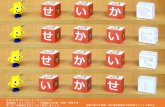‘Best Society’ におけるラーキンの孤独と交際 高 野...
Transcript of ‘Best Society’ におけるラーキンの孤独と交際 高 野...

13
‘Best Society’ におけるラーキンの孤独と交際
高 野 正 夫
(1)
フィリップ・ラーキンという名前を聞けば、詩に関心のあるイギリス人なら
ば誰でも詩人としての姿を思い浮かべる。1945年に若冠23歳で処女詩集 The
North Shipを出版し、最後の詩集 High Windowsを世に送り出し、そして、現
代イギリスの「記念碑」と呼ばれるほどの名声を得た彼の生涯を眺めるとき、
詩人としての存在が真先に思い出される。しかし、The North Shipの翌年に
は Jill、そして 1947年には A Girl in Winterという小説を出版していた。この
事実から推測されるように、若き日のラーキンは、将来は小説家として生きて
いくことを望んでいたようである。
その後も彼は書き続けようとして、第三作目となるべき小説に着手したのは
1947年の8月であった。9月までには50ページほど書き進め、それから1948
年の秋に再び書こうとした。1950年の冬にも書き続けようとしたが、その後、
結婚生活への強い不安を描いたこの作品は中断されていた。ちょうどこの頃
は、ラーキンがベルファーストで図書館員として新たな生活を始めた時期とも
重なり、それが小説の執筆に少なからぬ影響を与えていたのかもしれない。そ
して、1953年に入ると再び彼は小説の完成に向けて続きを書き始めていた。
最初に書き始めてから6年ほどの間、彼は辛抱強く、断続的にではあるが、自
らが書きたいと強く願っていたものを書こうとしてきた。1953年、夏の半ば
まで懸命に努力を続けたが、結局、最終的には小説の完成には至らず、永久に
第三作目の小説は書かれることなく、ラーキンの、偉大な小説家になりたいと
いう野望はついえたのである。
生前ラーキンは、この未完の小説の草稿は誰にも見せなかったようである
が、彼自身は自らの見果てぬ夢は誰にも知られずにそっとそのままにしておき
たかったのであろう。A New World Symphonyという仮の題名もついていたこ
の作品には三冊の草稿があり、それぞれ41ページ、56ページ、そして95ペー
ジの長さであった。「彼が小説家としての経歴を放棄したとき、ラーキンをか

14
すめていったのは悲しみではなく強い怒りであった。彼の知っていた怒りは、
個人的な失敗と同様に芸術的な失敗でもあった。」(1)と、モーションも述べ
ているように、未完の三作目で味わった悲しみは、単なる人間としての悲しみ
ではなく、芸術家としての深い挫折感であった。そして、この時の悲しみは、
それからの生涯にわたって自らに対する強い憤りの気持となって彼の心の奥底
に残り続けたのであろう。
このように第三作目となる作品の執筆に挫折し、ラーキンはそれ以降は詩人
として生きていくことを余儀なくされたのだった。いわば小説家に成りそこね
た詩人というコンプレックスを心に秘めながら、彼は、それを一種の反発力と
して詩人の道を歩むことにしたのであろう。オックスフォード時代以来の親友
であったKingsley Amisのように小説家としての名声を得た友人を羨望の眼差
しで真近に見ながら、彼は、常に小説家としての自分の姿を詩人としての自己
の意識の底におし隠していた。
処女詩集 The North Shipで扱われた主題は、「冷たさ、淋しさ、そして愛の喪
失」(2)が主なものであったが、この時期に書かれた多くの詩と同じように、ラー
キンの二作の小説も、「愛と孤独、成就と失望、選択と偶然」(3)などの主題を中
心に構想を巡らしている。自らの日常生活の様々な経験や出来事を主に詩の題材
としていた初期のラーキンから判断すると、彼の詩や小説の背景には、その当時
彼が味わっていた人生の苦悩や試練が横たわっていることは明白であろう。
つまり、その当時のラーキンの精神状態がどのようなものであったのかが、詩
や小説の中に読み込まれているのである。
1943年にオックスフォードを卒業してシュロップシャーのウェリントンで
図書館員の職につき、1946年にレスターの University Collegeに Assistant
Librarianとして移り、そして 1950年の 10月にベルファーストの Queen’s
UniversityでSub-Librarianになるまでに、ラーキンは、その生涯の中でも最も
苦悩に満ちた時を過ごしていた。小説家になる夢の挫折、父親のガンによる
死、Ruth Bowmanとの出会いと婚約の解消、そしてレスター時代に同居して
いた母親の世話など、人生の中でも最も苦しみに溢れた多難な時期を生きてい
た。そして、この実際の人生において味わっていた様々な不安や苦悩の中で
も、彼の心を強く捉えていたのは孤独というテーマであった。ラーキンの詩に
登場する語り手たちは、自然から孤立した誰もいない部屋で淋しく自らの心象
風景を思い浮かべるとき、孤独は時として多くの悲しみをもたらすと共に、一
方では人生の苦悩をいやしてくれたのであろう。

15
(2)
1950年9月16日、土曜の午後レスターの駅で母親のEvaに見送られてリバ
プール行きの列車に乗り込んだとき、ラーキンにとってまさに新たな人生への
旅立ちが始まったのだった。4年間にわたるレスターのUniversity Collegeでの
Assistant Librarianとしての職を辞して、北アイルランドの主都ベルファースト
にあるQueen’s UniversityでSub-Librarianとなるためであった。ラーキンはベ
ルファースト行きの夜行フェリーの船上で自らの旅立ちの熱い思いをノート
ブックに書き留めていた。未完の詩となった‘Single to Belfast’に記されてい
るように、それは「喪失から未知への旅」(‘I travel/To unknown from lost.’)
であった。悲しみや試練、そして苦悩に満ちたレスターでの生活に句切りをつ
けて、北アイルランドでの見知らぬ土地での暮らしに向かうとき、未知の土地
ベルファーストは、ラーキンにとっては夜の暗い海のように、冷ややかな不安
でその行く手を遮るもののようであった。
しかしながら、それからの4年半にわたるベルファースト時代は、詩人とし
てのラーキンにとっては最も重要な時期であった。それというもの、1955年
に、自らの永住の地となるハルに移ってから出版した The Less Deceivedに収
められたほとんどの作品を、ラーキンはベルファースト時代に書いていたから
だった。イギリスの詩壇に一人前の詩人として認められるきっかけとなったこ
の第二詩集には、ベルファースト時代の彼が、詩人そして人間としてどのよう
に生き、考えたかが記されている。そして、ラーキンの詩にとって重要なテー
マの一つとなっていく孤独や自己と他者とのつながり、個人と社会との関係を
うたった作品としてあげられる、‘Best Society’が書かれたのも彼がベル
ファーストにいた時であった。
最後の詩集、High Windowsに収められた同じテーマの詩である‘Vers de
Société’の前ぶれといわれる‘Best Society’を見れば、ベルファースト時代
のラーキンが、孤独や、社会と個人との関係をどのように捉えていたかが多少
は明らかになるであろう。
一連では語り手の子供時代において、孤独はどのようなものであったかのか
が分かりやすく語られている。
When I was a child, I thought,
Casually, that solitude

16
Never needed to be sought.
Something everybody had,
Like nakedness, it lay at hand,
Not specially right or specially wrong,
A plentiful and obvious thing
Not at all hard to understand.
子供の頃私はふと思った。
孤独は決して求める必要の
ないものだと。
皆んなが持っているもので
裸のように手の届く所にあった。
特に正しい、特にまちがったものでもなく
沢山ある明白なもので、
まったく理解しにくいことはなかった。
「孤独は決して求める必要の/ないものだと。」(‘solitude/Never needed to be
sought.’)思ったという語り手の告白を最初に聞く時、読者はいかに少年時代
の主人公が、普通の子供とは違って、瞑想的で内向的な少年であったことかを
想像してしまう。孤独という抽象的な概念について多少なり分析的に解釈しよ
うという姿勢自体が、きわめて早熟なものであろう。漠然とした心の淋しさぐ
らいと捉えるのが普通の子供の感じる孤独であり、孤独という言葉の持つ意味
を正確に理解する子供など恐らくいないであろう。
もちろん、詩人であるラーキンが語り手と必ずしも一致するとは限らない
が、この詩の語り手の場合にはラーキン自身と重なる部分もあるようである。
厳格な父親のもとで、あまり家庭的な温かみのない雰囲気で育ったラーキン
は、「私たちの家庭では、愛は便所のように必要ではないもののように嫌悪す
べきものだった。」(4)とノートブックに記しているが、家庭的な愛に恵まれ
ることの少なかったラーキン自身の子供時代を振り返ると、孤独というもの
が、いかに少年時代のラーキンには普通の身近なものであったかが容易に推測
される。また、未発表の自叙伝的な断片においてラーキンは、「私の子供時代
にダイアルを合わせようとするとき、私が聞きとる支配的な感情は、圧倒的に
恐怖と退屈です」(5)と記しているが、温かな家庭的な愛に恵まれることのな

17
い子供時代を過ごした少年にとって、悲しいことに孤独は自らを慰めてくれる
心の友であったのかもしれない。
コヴェントリー市の出納係をしていた父のSydneyは、一日中働き、夜は読
書で自らを遠ざけ、さもなければ庭仕事をしていたような家族のことはあまり
顧りみない男であった。家の切り盛りに精を出す母親の Evaは、メイドの手
助けがあったにもかかわらず、自分の惨めな生活や、家事のやりくりの不得意
さにぐちや不満をもらし続け、一度は自殺をすると叫んでテーブルから立ち上
がったこともある神経質な母親であった。そして、年の離れた姉のCatharine
(Kitty)はあまり友達のいない、美術の勉強をMidland Art Schoolで始めるま
では、生彩のない生活に耐えていたような女性であった。父Sydneyは、彼女
をほとんど評価することもなく、またラーキンも姉との年の差ゆえに、自分が
ほとんど「ひとりっ子」の気持ちで育ったと述べていた。
ラーキンの言葉で言えば、「私の父は仕事や庭いじりが好きじゃない、私の
母は家事が好きじゃないし、私の姉も家で暮すのが好きじゃない」(6)という
ように、ラーキンの家族はそれぞれ幸せとは縁のない、まとまりのない存在で
あった。恐らくは普通の子供以上に感受性の強い子供であったであろう少年の
頃の彼にとって、冒頭の語り手の率直な言葉のように、幸せとは言えない家庭
においては、孤独は常に自らの生活の周囲に漂うものであり、また自らの体の
必要不可欠な一部であるように思えたのであろう。
このような退屈で淋しい家庭の息苦しい雰囲気からラーキンを慰めてくれた
のが、学校生活であったというのは、少しばかり皮肉なことかもしれない。「外
で友達がいなかったならば人生は耐えられなかったであろう。」(7)と彼自身が
言っているように、junior school時代の、Colin Gunner や James Sutton、そし
て senior schoolであるKHSの同級生で、同じオックスフォードのSt. John’sに入
学して寮の同じ部屋に住んでいた Noel Hughesなどの友人たちが、少年時代の
ラーキンに熱い友情を育んでくれたのだった。しかし、これとは対照的に、両親
の結婚生活はラーキンに二つの確信を残し、生涯にわたってラーキンに強い影響
を与えていた。「人間は一緒に生活するべきではないし、子供たちも幼い頃に両
親から取り上げられるべきだ」(8)といった、非常に歪曲した家庭や結婚につい
ての考え方を少年時代に植え付けられてしまったラ-キンは、ある意味では不幸
な少年時代を過ごしたと言える。自らの少年時代を‘forgotten boredom’と殊更
なげやりに、そして無関心を装いながら言い放とうとするラーキンにとって、少
年時代の家庭環境や雰囲気が、結婚や共同社会そして孤独に対する彼の見方に、

18
容易に拭いさることのできない暗い影を投げかけていたのであろう。
家庭を温かい愛や安らぎとは無縁の、父親が黙ってじっと耐えなければいけ
ないような場所にしてしまった母親と、愛情や細やかな気遣いを欠いた接し方
しかできなかったために、母親にいつも愚痴をこぼさせていた父親の双方を責
めるラーキンは、自分の育った家庭を「退屈で鉢いっぱいに根が張っていて少
し狂っていた」(9)と多少皮肉を込めて表現しているが、このような家庭の雰
囲気の中で、強い吃音の内向的な子供であったラーキンが、自分だけの孤独の
世界に閉じこもってしまうのも当然のことであったかもしれない。
素直に孤独を淋しいものとは感じることができずに、孤独を常に自分の裸の
ように自然な当たり前のものとして受け入れていたラーキンは、率直に言え
ば、子供らしい無邪気さや純粋さを欠いた妙に大人びた子供であったのかもし
れない。世間一般の家庭の楽しい和やかさに溢れた幸福感を味わわずに子供時
代を過ごしたラーキンは、自らの子供時代の孤独の意味をいつものように観察
的な眼で冷静に分析しているが、2連では成長した主人公の観点から孤独をさ
らに広い視野で捉えている。
Then, after twenty, it became
At once more difficult to get
And more desired- though all the same
More undesirable, for what
You are alone has, to achieve
The rank of fact, to be expressed
In terms of others, or it’s just
A compensating make-believe.
それから 20歳以降、それは、さらに
得がたくもあり、さらに欲される
ものとなった。-もっとも、それでもさらに望ましく
ないものであったが。なぜなら、あなたの
今の孤独は、その事実の地位を
かち取るためには、他人の観点から表現され
なければならないから。さもないとそれはただの
償いの見せかけに過ぎないのです。

19
20歳を過ぎれば誰でも大人としてみなされ、自らに与えられた責任と義務
を果たすべき社会の一員として生きていくのはごく自然なことである。共同社
会の仲間入りを果たした人間にとって、普通は、人との交際を避けて古い伝説
の隠者のように洞窟に一人住みながら、孤独に生きることは許されることでは
ない。晩年の作品である‘To the Sea’において、主人公が、海辺で楽しい時
を過ごしている家族連れから遠く離れて、「『自分一人でいることの』幸せ」(10)
に浸りながら味わう子供の頃の喜びは、大人になった人間にとっては、懐かし
く思い出されるものであるが、一方では、‘More undesirable’(「さらに望まし
くないもの」)ともなるのである。手に入れることが難しくなればなるほどそ
れを自分のものにしたいという欲求が増すのは、人間の心理としてきわめて自
然なことであるが、成人した大人には、子供の頃に経験したものと同じよう
な、他人から分離した孤独を味わうことを不適切だと見なす判断力は当然備
わっているはずである。それ故、孤独は「他人の観点から表現されなければな
らない。」(‘to be expressed/ In terms of others’)という大人の見方が生まれて
くるのである。
社会に生きる人間として、他人との比較によって相対的に物事を捉え理解す
る常識人である主人公は、孤独という概念についても、自分の周囲の共同社会
やそこに生きる人々との人間関係を考慮に入れながら考えなくてはいけないの
であろう。子供の時のように無邪気な空想の世界に一人閉じこもって孤独に生
きていくことは許されないのである。周囲の他人との人間的なつながりを断ち
切って生きることは、それを実行しようと思えば可能かもしれないが、普通の
一般社会においては、それは困難なことであり世間一般の常識や礼儀に欠ける
ものなのである。
良い大人が他人との交際を避けて、一人よがりで自分勝手な、子供じみた孤
独を楽しんでいるという状況を生み出さないためにも、主人公は、「さもない
とそれはただの/償いの見せかけに過ぎないのです。」(‘or it’s just/ A compen-
sating make-believe.’)と言われないようにしなければならないのであろう。こ
の二連の終わりの部分は、多少口先だけの流暢な詭弁と(11)、否定的に見なす
向きもあるようだが、いずれにしても人間の考え方や個性は、その違いや類似
性などすべての点において、他人との比較によって定義されるものだと彼は考
えているようである。
三連に入っても、話し手は、孤独よりも社会における他人との交際を選択す
る方が人間にとってはふさわしいものであることを強調していく。

20
Much better stay in company!
To love you must have someone else,
Giving requires a legatee,
Good neighbours need whole parishfuls
Of folk to do it on- in short,
Our virtues are all social; if,
Deprived of solitude, you chafe,
It’s clear you’re not the virtuous sort.
人との交際は続けた方がずっと良い。
愛するためには誰か他人がいなければならない。
与えるには遺産受取人が必要なのだ。
良き隣人は、仕事を続けてくれる
小教区一体すべての人々が必要なのだ。要するに
私たちの美徳はすべて社交的なのです。もし
孤独を奪われてあなたがいらいらするならば、
あなたが高潔な人でないことは明らかなのです。
人間は決して一人では生きていけない存在であり、誰か愛する人がいて初め
て、愛という概念も成り立つのであると、切々と語りながら、話し手は、人間社
会を構成する、人間が守っていかなければならない、最低限の約束事である人間
関係の大切さを訴えている。まさに他人を愛することが真実の愛であり、自分を
愛するだけでは決して十分な愛とは言えず、すべてにおいて与える側と受け取る
側がいなければ、真の人間関係は成立しないのだと言っているようである。
他人との交際を避けて自己愛のみに頼る生き方は、人間らしい生き方ではな
く、大きな寛大な愛の気持ちで他人を受け入れる生き方こそ、社会に生きる人
間に求められるものなのであろう。そして、「私たちの美徳はすべて社交的な
のです。」(‘Our virtues are all social;’)という言葉によって、共同社会では他
人との交際を基盤にして物事が成立しているのであり、人々が正しい適切なも
のであるとする美徳も人間関係や交際を基本とした、社会一般に共通の普遍的
なものであるべきなのだという強い信念が明言される。そして、三連の最後の
言葉で、孤独を奪われて不愉快な気分になるような人は高潔な、立派な人間で
はないのだと、まるで自分自身が人間として不適格であるかのように断定する

21
とき、話し手の心の中にもう一人の自己が現れて反論を開始する。孤独を求
め、孤独を唯一の精神の拠り所とするような考えを抱く話し手の分身は、ここ
までの「感情の抑制」(12)を快く受け入れる、社会に順応し他人との人間関
係を尊重する考え方に強く反発するのである。
(3)
最後の四連では、孤独を擁護するもう一人の自己が不可思議な自然のイメー
ジと共に登場して、反撃を開始している。
Viciously, then, I lock my door.
The gas-fire breathes. The wind outside
Ushers in evening rain. Once more
Uncontradicting solitude
Supports me on its giant palm;
And like a sea-anemone
Or simple snail, there cautiously
Unfolds, emerges, what I am.
それから、私は乱暴に戸に鍵を掛ける。
ガスの炎は息づく。外の風は
夕辺の雨を告げる。もう一度
反駁しない孤独が
巨大な手の平で私を支えてくれる。
そして、イソギンチャクや
ただのカタツムリのように注意深く
私がすがたを開いて現われる。
3連までの他人との交際を美徳とする考え方とは全く正反対の、もう一人の
自己はまるで自分の本来の姿を取り戻そうとするかのように、孤独の部屋に閉
じこもり外を吹く風の音に耳を澄ませている。雨のさきがけともなる風は主人
公の心の中をすり抜けて、心をさらに不安定な状態にしていく。孤独を奪われ
ていらいらするような人間である話し手にとっては、もはや他人との交際は無

22
意味な虚しいものであり、彼にとっては、自分が高潔な人間であろうとなかろ
うとそれは大きな問題ではなくなっていく。そして、孤独が、交際を良しとす
る心を押しのけて主人公の心を支配するのである。
この最終の四連で話し手は、扉を堅く閉ざして自分の小さな部屋に閉じこも
り、他人との交際を退けて再び孤独を選択するのである。ラーキンの作品のテー
マの一つである選択という行為がここで再び要求される。ラーキンの出世作と
なった The Less Deceivedに収められた‘Reasons for Attendance’では、部屋の
外から熱く踊っているカップルたちを見つめている語り手が、彼らの中に加わっ
て楽しい時間を共に過ごしたいという願望と、それとは反対に、そのまま彼らか
ら離れて一人でいたいという欲望の間で思い悩む姿が描かれていた。結局主人公
は、踊りに興じている若者たちに対して嫉妬を抱きながらも、孤独の方を選択し
ていたのであるが、初期のラーキンにおいては、孤独に対する熱情が、日常生活
の他人との世間的な交際に対する関心を押しのけてしまったようである。そこに
は、「幸福は、普通の社会的、性的な生活の共同社会性に見い出せるのだという
考えを、いかにラーキンが拒絶しているかが示されている。」(13)が、世間一般
の家庭生活や結婚生活を積極的に認めようとしなかったラーキンからすれば、常
に物事の外側にいて、孤独を味わいながら観察者として他の人々をじっと注意深
く見まもるという姿勢は、決して不自然な状態ではなかったのである。
ラーキンは、「私は人生を、孤独によって多様化した交際の事柄というより
はむしろ、交際によって多様化した孤独の事柄として見ている。...私は人々が
とても好きですが、交際しないで人々を捉えることは難しいのです。」(14)と、
孤独についていつものように逆説的に述べているが、孤独は彼にとっては自ら
の人生を構成する非常に重要なものの一つであったのである。人間関係の複雑
さから生まれる様々な軋轢や感情の不一致から生まれる孤独をラーキンは受け
入れてはいるが、一方では、他人との交際の難しさについても言及している。
交際よりも孤独を選択するラーキンの姿勢は、この詩においても明確にされて
いるが、他人との交際を心から楽しみ、味わうことのできない内向的な主人公に
とっては、孤独はまるで神の手の平で包んでくれるかのように、くつろぎと安心
感を与えてくれている。そして、「反駁しない孤独」(‘Uncontradicting solitude’)
に守られながら、ラーキン自身も時には詩的創造力を強く覚えることもあったの
であろう。このような考え方の根底には、孤独は詩人にとって創造力の源であ
り、自らの創造的な行為に不可欠なものであるという詩人としての基本的な概
念があるのであろう。孤独を社会からの否定的な孤立と見なさずに、芸術家の創

23
造力を刺激する、肯定的な芸術家の気質の一つとして捉えているのである。
ラーキンが人生の大半を過ごしたハル出身の、17世紀の詩人Andrew Marvell
が‘Society is all but rude/To this delicious solitude.’と甘美な孤独への熱い思い
を述べた時のように、詩人にとって、社交的な交際は、時には自らの想像力の
平和を乱す粗野なものに映るのである。マーヴェルの場合には、エデンの園の
ような庭園の自然に心を奪われるのであるが、ラーキンにとっても孤独は、自
らの魂をいやして新たな詩の創造へと駆りたててくれるものであった。
孤独を芸術の創作に不可欠なものと考えるとき、ラーキンにとって孤独は非
常に重要なものとなるわけであるが、詩のタイトルである‘Best Society’と
いう言葉の裏にも、孤独を擁護する彼の考え方が潜んでいる。1951年に完成
したと思われるこの詩は、生前には発表されなかった作品で、「自分の『交際』
から離れる行為を自己実現に必要なものとして擁護する『利己的な』ラーキン
を示している」(15)と言われている。表面的に見れば、孤独をマーヴェルの
理想とする「一種の緊張のない唯我論者的な楽園」(16)に類似したものと捉
えようとする時、ラーキンは、多少自己満足的な、利己的な夢想の世界に浸っ
ているように思われるかもしれないが‘Best Society’という語の由来をたど
るとき、ラーキンのしたたかな揺るぎない孤独への信念が明確になる。
Paradise Lostの中でミルトンは‘For solitude is sometimes best society.’(ix.
249)と書いている。(17)この場面は、Adamと Eveが、Eveが一人で庭仕事
に出かけるかどうか議論している所であり、最終的には Eveが一人で出かけ
ることとなり、人間の堕落が始まるのである。Adamが Eveに、彼女の孤独へ
の権利を認め一人で働く許可を与えるときに発する言葉が、「なぜなら孤独は
時には最良の交際であるから」という一行なのである。このようなミルトンの
描いた、Eveの孤独への権利を、まるで自分だけのものとしてほくそ笑んでい
るかのようなラーキンの顔が思わず浮かんでくるようであるが、いずれにして
も、社会における他人との交際を拒絶して孤独を選ぼうとする、詩人ラーキン
の考え方の根底には、ミルトン的な「驚くべきジェンダーの複雑さ」(18)が
示唆されていると共に、孤独を「最良の交際」として擁護しようとする堅い決
意が秘められているのである。
このような聖書的な言及は、詩の最終連に描かれた、孤独の「巨大な手の
平」という表現にも繰り返されているようである。ジョン・ケアリーが、「孤
独の巨大な手の平は神の手のように思われる」(19)と述べ、英国国教会の礼
拝式からの一行、「信心深い人の魂は神の手の中にあり、いかなる苦しみに触

24
れることもない」を、この詩における宗教的な要素として例にあげている。神
の手に抱かれたと感じる時の安らぎや安心感、そして信頼感に似たものを、人
間は、自分一人で孤独になるときに感じることもあるのだろう。
さらに、‘When I was a child’というこの詩の出だしの言葉も、『コリント
前書』(xiii.Ⅱ)の言葉をまねたものであるというケアリーの指摘があるよう
に(20)、ラーキンはこの詩においては意図的に聖書的な要素を活用している。
彼の代表的な宗教をテーマとした詩である、‘Church Going’や‘Aubade’に
見られる懐疑主義的な側面は前面に押し出すことなく、きわめて分かり易い宗
教的な比喩を用いて、社交的な交際よりも居心地の良い孤独を選択する自らの
姿勢を表現しようとしている。
そして、美徳は社交的で、孤独はわがままという主張を押しのけて、孤独の
自己満足的な世界にふける話し手は、最後の非常に個人的な自然のイメージで
ある、自らの「生理的な、心理的な感覚を表した見事な隠喩」(21)によって孤
独を味わうのである。多くの批評家の指摘のように、この最後の三行は、「ハ
ルの隠者」としてのラーキンの名声を完膚なきまでに落としめた悪名高い、彼
のポルノや自慰への強い耽溺ぶりを暗示していると言われている。(22)しか
し、一方では、「微妙に自己性欲的な、自給自足のイメージ」(23)であるイソ
ギンチャクやカタツムリは、ケアリーも述べているように、語り手の「本質的
な自己を表す」(24)ものと解釈することもできるのである。孤独の中において
のみ自己の定義や、自己認識に到達することが可能なのであるとする語り手に
とって、そこはある意味では楽園なのであろう。他人との交際よりも、自分自
身との対話によって自らのアイデンティティーを見い出そうとした主人公に
とって、「本当に自分が自分を知ることができるのは孤独においてのみ」(25)可
能であったに違いない。
(4)
他人との交際を避けて自分だけの利己的な殻に閉じこもる行為を、自己の独
立や自己実現に必要なものであると考えたラーキンは、‘Best Society’におい
ては、孤独を自らの芸術の創作に不可欠なものと擁護していた。同じイング
リッシュ・ラインに分類されるロマン派の詩人ワーズワスが、自らの淋しさを
空高く漂う雲のように例えたときに感じた、「孤独の至福」(‘the bliss of
solitude’)と同じような気分を彼も‘Best Society’において感じているのであ

25
ろうが、この詩が書かれた時の現実生活におけるラーキンの、ベルファースト
での「交際」に目を向けると、彼の暮らしぶりが、‘Vers de Société’の中に描
かれた、孤独な「隠者」とは全く正反対の暮らしぶりであったことが分かる。
1950年の 9月 16日に母親の Evaに見送られてベルファーストへ出発した
ラーキンは、作家になるのだという野望を抱いて新たな人生に旅立っていっ
た。ベルファーストのQueen’s Universityで教職員住宅に住み出したラーキン
は同じ住宅に住む教員たちとの交際を始め、また、Sub-Librarianとして働き始
めた職場の同僚も好意的であったため、彼は新たな大学での仕事を楽しんでい
たのだった。
最初の2、3週間は、新たな友人との出会いに積極的であったが、彼はそれ
までの生活から完全に解き放たれた自由な雰囲気を味わいながら、孤独の価値
と意味を認識していた。一方、Queen’s Universityの知的な雰囲気や生活をレ
スター時代以上に気にいったラーキンは、日記、手紙、新たな小説、そして詩
を書きながら多くの夕方の時間を執筆に傾けるのだった。毎日夕食後、2時間
書くという習慣を再開していた彼は、小説を完成することはできなかったが、
後に、ベルファーストは「それまでで最良の執筆状態を」(26)与えてくれた
と言うほどであった。
ベルファーストでのラーキンは、ある意味では外国人としての感覚で北アイ
ルランドの社会を観察していたわけであるが、彼にしては珍しく、1951年に
はベルファーストの政治にも興味を抱き、‘The March Past’においてはオレ
ンジ党員への共感を示していた。ベルファースト時代に書かれた2、3の詩は、
ラーキンの後年の詩集のきわめて重要なテーマとなっていく、孤独と社会、自
己と社会についての問題を取り上げたものであるが、まったく新たな環境にお
いて自己のアイデンティティーを探ろうとする試みであったのであろう。
第三作目となるべきはずであった小説の予期せぬ停滞はラーキンの詩作にも
大きな影響を与えていたようである。Montherlandを引用しながら、“happiness
‘writes white’”(27)といって嘆いていた彼は、1952年には一篇の詩も書けな
い状態であった。1947年に A Girl in Winterが Faberから出版されてから、出
そうとしていた詩集、In the Grip of Lightは Faberを含めて 6社の出版社に出
版を断られていたのだった。わずかに、親友の Amisに献呈された XX Poems
が、1951年 4月 27日、ベルファーストの Carswellsという印刷屋から私家版
として100冊出されていた。ラーキンは、それをCyril ConnollyやJohn Lehmann
そして、Wendy Hillerなどに送ったが、結果はまったく悲惨なものでほとんど

26
無視されてしまったのだった。
このように、詩人としても、また作家としてもほとんど注目されなかったベ
ルファースト時代でのラーキンではあったが、彼の生活は、社交的な意味にお
いては、孤独な詩人というイメージとはほど遠いものであったようである。
1943年にオックスフォードを出て、シュロップシャーのウェリントンで図書
館員として働いていたときに知り合ったRuth Bowmanとの不幸な破局を再び
繰り返さないためにもラーキンは、ベルファーストに移ってからは、最初は女
性との交際に関してはきわめて慎重であった。
「もし僕が自分が永遠に結婚しない状態を考えると、たえまない疑念、性的
な無関心は、正直にいうなら、マザー・コンプレックスのせいだと思う。何と
いらつくことか、それに何といやなことか。」(28)と、幼ななじみの親友Sutton
に述べていたように、ラーキンの母親 Evaに対する気持ちは、生涯にわたっ
てきわめて強いものであった。他人からすれば退屈と思われるような事柄につ
いて、母親に週に2通の手紙を書き続けていたが、Evaの方も息子の愛に答え
るかのように、彼女の最後の病気の時まで同じ割合で書き続けていた。それは
内容的にはきわめて溺愛するものであったが、ラーキンと母 Evaとの絆の強
さを証明するものであったのであろう。このように母親への愛を維持する一方
で、ラーキンは、1947年以来続いていた恋人Monica Jonesとの関係をベル
ファーストに来ても断つことはなかった。
1947 年の早春の昼食時に、レスターのロンドン・ロードにある‘Tatler
Café’で、レスター大学の英文科の若い講師であったモニカが初めてラーキン
の姿を見かけて以来、生涯の間続いていくことになるモニカとの関係も、ラー
キンがアイルランドに渡ってからも続いていたのであった。彼女へのラーキン
の愛の気持ちは、彼女のために書かれた‘Latest Face’の中にもきわめて濃密
に描かれているが、ルース・ボウマンとの婚約を解消していたラーキンにとっ
ては、モニカが当時規則的につき合っていた唯一の女性であったようである。
しかし、それ以外にもラーキンはベルファースト時代の4年半余りの歳月で、
彼のいくつかの詩のモデルとなったWinifred Arnotや、また、一緒に住むべき
か思案するほどかなり深い関係へと発展していった、人妻Patsy Strangなどと
の出会いもあり、女性関係に関する限り、彼にとって孤独という言葉はほど遠
いものであった。
ベルファーストに移り住むことによって英国から分離した自らの存在をより
冷静に見つめ直し、自己と社会との関係を探ろうとしていたラーキンにとっ

27
て、ベルファーストでの異邦人としての感覚を感じながら異国の地に根づこう
とするとき、それまで続いていた多くの友人関係は遮断されてしまったのだっ
た。もちろんモニカや母親Evaとの絆は断たれることはなかったが、ベルファー
ストでラーキンが感じた強い孤独感は、ベルファースト時代に新たに出会った
女性も含めて、多くの女性との愛によっていやされていったのであろう。
‘Best Society’の最後の場面で、乱暴に部屋の戸に鍵を掛けて孤独を選択し
た主人公に関する限り、まさに孤独こそ「最良の交際」であり、そこには他人
の入り込む余地はまったくないのである。人間関係の無意味さや退屈さを強調
する主人公が望む孤独は、利己的な狭い空間ではあるが、その中で彼は、自分
自身を見つめ直して真の自己実現を図ることができるのであろう。ミルトンの
考える「最良の交際」よりも、ワーズワスが The Preludeの BookⅡで言及し
ていた、「『最良の交際』よりも活動的な幼年時代の孤独の」(29)経験に、よ
り接近した主人公の孤独への願望は、真の自己認識へと通じる選択となるので
あろう。
初期の作品‘Wants’においても、「何よりも先に一人になりたいという願
いがある。」(‘Beyond all this, the wish to be alone:’)と述べられているように、
孤独への願望はラーキンの詩においてはしばしば見られるものである。しか
し、この主人公の孤独への陶酔は、現実の生活でラーキンが感じていた孤独へ
の思いとは必ずしも一致するものではないことに留意する必要があるであろ
う。「美徳は社交的、孤独はわがまま」と、明確に常識的な人間としての判断
や考え方を示していたラーキンにとって‘Best Society’に描写された孤独へ
の陶酔は、ある意味では自らの利己的な願望の一つであったのであろう。現実
的に‘Best Society’を書いたベルファースト時代のラーキンと、詩の主人公
である語り手を比較してみれば、それはまったく一目瞭然であろう。女性への
愛にも増して、美しい庭園を彩る緑の樹木への強い愛を吐露した、ハルの先輩
詩人マーヴェルとはまったく対照的に、女性への愛に溺れることの多かった実
際の人間としてのラーキンは、決して読者やジャーナリズムが神話化して憧れ
ていた「ハルの隠者」などではなかったのである。
ピーター・レヴィも、「彼の人生の神話的な淋しさはただの芸術家の淋しさ
に過ぎず、恐らく彼の伝記の事実ではないと思う」(30)と述べているように、
現実の世界に生きたラーキンは、実際にはイギリスを愛し、そしてそこに生き
たイギリス人の普通の暮らしを描き続けた、孤独と交際の両方を共に愛した人
間であった。そして、‘Best Society’の 20年後に書かれた‘Vers de Société’

28
においてもそうであったように、自己と他者、そして個人と社会との関係は、
ラーキンの生涯を通して重要なテーマの一つであり続けたのである。
[注]テキストはPhilip Larkin, Collected Poems ed. Anthony Thwaite (The Marvell Press and faberand faber, 1988) に拠った。
(1) Andrew Motion, Philip Larkin A Writer’s Life (faber and faber, 1993) p.229.(2) Janice Rossen, Philip Larkin His Life’s Work (Harvester Wheatsheaf, 1989) p.8.(3) Andrew Swarbrick, Out of Reach: The Poetry of Philip Larkin (MACMILLAN, 1995)
p.29.(4) Ibid., p.3.(5) Motion, A Writer’s Life, p.13.(6) Ibid., p.14.(7) Ibid.(8) Ibid., p.15.(9) Ibid., p.14.(10)Janice Rossen, op. cit., p.59.(11)John Carey, ‘The Two Philip Larkins’, New Larkins For Old Critical Essays ed. James
Booth (MACMILLAN, 2000) p.63.(12)James Booth, ‘Philip Larkin: Lyricism, Englishness and Postcoloniality’, Larkin with Poetry
ed. Michael Baron (The English Association, 1997) p.23.(13)Andrew Swarbrick, Master Guides The Whitsun Weddings and The less Deceived By Philip
Larkin (Macmillan, 1986) p.27.(14)Roger Day, Larkin (Open U. P., 1987) p.7.(15)James Booth, Philip Larkin Writer (Harvester Wheatsheaf, 1992) p.163.(16)Ibid.(17)John Carey, op. cit., p.63.(18)James Booth,‘Introduction: New Larkins for Old’, New Larkins for Old Critical Essays ed.
James Booth (MACMILLAN, 2000) p.6.(19)John Carey, op. cit., p.64.(20)Ibid., p.63.(21)James Booth,‘Philip Larkin: Lyricism, Englishness and Postcoloniality’, Larkin with Poetry
ed. Michael Baron (The English Association, 1997) p.23.(22)Ibid., p.19.(23)James Booth,‘Introduction: New Larkins for Old’, New Larkins for Old Critical Essays ed.
James Booth (MACMILLAN, 2000) p.7.(24)John Carey, op. cit., p.64.(25)Andrew Swarbrick, Out of Reach: The Poetry of Philip Larkin (MACMILLAN, 1995)
p.42.(26)Andrew Motion, A Writer’s Life, p.203.(27)Ibid., p.219.(28)Ibid., p.204.(29)Andrew Swarbrick, Out of Reach: The Poety of Philip Larkin (MACMILLAN, 1995) p.41.(30)Peter Levi, The Art of Poety (Yale U. P., 1991) p.282.











![INAX ビジネスユーザー[いいナビ]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/616c531960563f6c56263eae/inax-.jpg)