【行事報告】 アフリカ: 民主主義・開発・統治: 西アフリカ ...db.csri.for.aichi-pu.ac.jp/10-11.pdf【行事報告】 アフリカ: 民主主義・開発・統治:
可視化は社会を変えるか? 関西大学特別講義
-
Upload
atsuhiko-yasuda -
Category
Education
-
view
157 -
download
2
description
Transcript of 可視化は社会を変えるか? 関西大学特別講義

関西大学総合情報学部ヒューマン・インタフェース論 2012.11.22
可視化は社会を変えるか?株式会社ズームス保田充彦

地下室に電球がひとつあります。1階にスイッチが3つあり、そのどれかひとつが地下室の電球のスイッチだとわかっているのですが、どれだかわかりません。1階から地下室の様子は見えません。地下室へ行くのは一度だけで、3つのスイッチのうちどれが電球のスイッチかを知るにはどうすればよいでしょうか。
プレゼンが始まるまで、クイズをお楽しみください。

もんだいのこたえ
ひとつのスイッチ(A)をオンにして、数分間後にオフにする。
別なスイッチ(B)をオンにして、地下室に行く。
電球がついていれば、そのスイッチ(B)が、正しいスイッチ。
電球がついていなければ……… 電球に触ってみる。
電球が暖かければ、最初のスイッチ(A)が、
暖かくなければ、残りのスイッチ(C)が、正しいスイッチ。
★LED電球だと難しいかも………




ハリー・ベックによるロンドン地下鉄路線図 (1933)

Harry Beck以前の路線図は、「地形図」上に路線を描画したものだった。
1889 1905 1908
1914 1919 1924

可視化

可視化
ことが
できるように
する。
見る

理解する見る =

情報の検索から「情報の理解」の時代へ可視化はその有力なツール

可視化とデータ

「ニューヨークタイムズ日曜版一部に掲載されている情報量は、ルネサンス時代に一人の人間が一生かけて出会う情報量より多い。」(R.S.ワーマン「情報選択の時代」)
Googleが把握しているURLリンクの数は1兆個を越えた。(Google公式ブログ 2008/7/25)
2006年に作成もしくは複製されたデジタル情報量は、161エクサ( 1億6100万テラ)バイト。 これは、これまでに書かれた書籍の情報量合計の約300万倍にあたる。(米IDC調査)
2007年から2011年の5年弱でデジタルデータの量は約10倍に増大した(米IBM)
平均的な人が一日に出会う情報は、新聞紙174誌分に相当する (R.Alleyne “Welcome to the information Age”)
2011年に生成されるデータは1.8ゼタ(10の21乗、ペタの100万倍)バイト。これは、米国の全国民が1日3回ツイートして、2万6976年続けるのと同等。(米IDC/米EMC)
YouTubeには毎分48時間分の動画が投稿され、一日30億ビューの視聴がある。(YouTube公式ブログ May, 2011)
Twitterには1日2億件の「つぶやき」が寄せられている。(2011/6/30)
全世界のFacebookのユーザ数が8億人を突破(2011/9/22)
2010年から2020年までの10年間で、データ量は50倍、ファイル数は75倍、必要なサーバー台数は現在の10倍になる。(米IDC/米EMC)
私たちは、データの「洪水」の中にいる。

Flightrader24
世界中を飛行している航空機をリアルタイムで可視化するウェブコンテンツ。アメリカ国内線は「遅れ」の情報も観ることができる。

“Britain from Above”の制作スタッフによる、アメリカの可視化をテーマにした番組が、”America Revealed”。食品、交通、電力、ものづくり等、アメリカの今を様々な視点から切り取るドキュメンタリー番組に挿入されるデータの可視化映像は有益で美しい、インフォグラフィクスになっている。http://www.pbs.org/america-revealed/
社会情報の視覚化 “America Revealed” PBS

“America Revealed” by PBS (2012)

“Locals and Tourists”(地元民と旅行者)
Flickrに投稿された写真データから観光マップを作る試み。 その街の写真を1ヶ月以上にわたって撮影している人は地元民(青色)、1ヶ月位内は旅行者(赤色)と推定。地元民しか知らない「隠れた観光スポット」を可視化している。

「比較エンジン」“FindtheBest”の試み
• 「バイアスのない、データ指向の比較("Unbiased, Data-driven Comparison")」を標榜する、データ比較に特化したビジネスを展開するスタートアップ企業。見た目にわかりやすい比較だけでなく、信頼性を重視する、硬派のデータ比較サイトを展開している。
• 信頼できる比較結果を担保するため、FindTheBestが使うデータは、公共機関、一次情報(製造者など)、専門家情報に限っている。専門家は"Expert Bologger"として同サイトに認定された人に限定。権威や利権といったバイアスを極力排除する姿勢をつらぬいている。

Google Trrend / Google “Flu”
Googleは、特定の検索キーワードでの検索数がインフルエンザ流行の指標となることを発見した。これを使ったGoogleトレンドは、検索の集計データを使用してインフルエンザの流行をリアルタイムに予測している。
◆インフルエンザ患者数(米国)◆Google Fluトレンドの予測

GE/Fathom “Curing” (2012)

オバマ大統領の”Open Government Initiative”施策の一環として、世界中の「公共データの民主化」を目指す活動。様々なデータの公開と、それらを利用したアプリケーション開発・配布を支援している。”Open Government”の流れに乗り、サイト公開から3年で30カ国にネットワークが広がっている。2009年5月開設。(米国版は、現在新規活動停止か?サイトは公開継続されている。)
Data.gov

可視化と社会

「密室(クローズド)」から「公開(オープン)」へ

SPEEDI (緊急時迅速放射能影響予測システム)
「原子力発電所などから大量の放射性物質が放出されたり、そのおそれがあるという緊急事態に、周辺環境における放射性物質の大気中濃度および被ばく線量など環境への影響を、放出源情報、気象条件および地形データを基に迅速に予測するシステム。結果は、ネットワークを介して文部科学省、経済産業省、原子力安全委員会、関係道府県およびオフサイトセンターに迅速に提供され、防災対策を講じるための重要な情報として活用されます。」~SPEEDI HP より

“Debris from Japan Tsunami Travels Across the Pacific”
3.11の大震災で発生したがれきの多くが海に流れ、海流に乗って太平洋を漂流している。その様子をアメリカ海洋大気庁(NOAA)が、コンピュータ・シミュレーションと人工衛星による観測を組み合わせて予想している。がれきは単なる廃棄物として迷惑なだけでなく、トドやアザラシが口にすると生命の危険もあると言う。またサンゴ礁や船のスクリューにもダメージを与える恐れがある。そして今回は、放射能に汚染されたがれきも含まれる。震災がれきは、地球の広い範囲に長期間にわたって影響を与える大きな問題だと言うことが実感できる可視化映像。

スコットランドのエンジニア、政治経済学者。それまでは表でしか示されなかった数値データを、折れ線グラフ、棒グラフ、パイチャート、バーグラフの4種類のグラフで始めて表現した(1786年)。
グラフの発明: William Playfair, 1759 ‒ 1823

ナイチンゲールは統計学者
フローレンス・ナイチンゲールFlorence Nightingale, 1820 -1910
1854年クリミア戦争に従軍し、兵士の死亡の主原因が伝染病であることを訴えるため、独自のカラーチャートを考案し政府に訴えた。ナイチンゲールは、一流の看護師・看護教育者であるとともに、優れた統計学者であり、情報可視化のパイオニアの一人と言える。

“Choloera Map” by John Snow (1854)
1854年英国SOHOで発生したコレラを調査・研究した医師John Snowは、その結果を一枚の「地図」で示した。SOHOの地図上にコレラによる死亡者を図示したのである。当時のロンドンは非常に臭かったため、「臭い」つまり、空気感染説が優勢だった(「ミアズマ」)。しかし、スノウが作成した地図から、死亡者の分布の中心に井戸があることがわかり、コレラは水を介して伝染することが発見された。このしばらく後、コレラの大量発生はなくなり、Snowは疫病学の父の一人と言われる。
ジョン・スノウの「コレラ地図」(1854)

ナイジェル・ホームズ(Nigel Holmes)元タイムマガジンのグラフィック・ディレクター。1994年に独立、”Explanation Graphics”を創業。アップル社、スミソニアン博物館など、様々なクライアントの情報を視覚化している。現在はニューヨークタイムズ紙のイラストなどで活躍。インフォグラフィクスの開拓者と言える。
インフォグラフィクスの実用化 Nigel Holmes/Time誌

情報公開の可視化 Oakland Crimespotting
オークランド市内で発生した犯罪を一目で把握できるサイト。犯罪の発生日、種類、場所でスクリーニングできるインターフェースをもつ。住民の「知る権利」を具現化することを目的としている。Stemen Designがデザインを担当。http://oakland.crimespotting.org/

GOOD Magazine(米)
思想信条に関係なく、クリエイティブ、持続可能、生産的、シェア等をキーワードにした「代替モデル」を支援、展開するサイト。購読料を選ぶことができる上に、購読料は購読者が選んだ非営利団体へ寄付されるというユニークなシステムで運営している雑誌。Information Graphicsが多く使われている。

GOOD Sheet @ Starbucks
“Great Conversations at Starbucks”(スターバックスで素敵な会話を)キャンペーンの一環として、店内で無料配布された。GOOD Magazineのインフォグラフィクスをペーパーナプキンに印刷したもので、二酸化炭素排出、教育、移民、経済、ヘルスケア、ガソリン価格など、客の会話や行動につながるような身近なテーマを扱っている。

GOOD Sheet @ Starbucks
“Great Conversations at Starbucks”(スターバックスで素敵な会話を)キャンペーンの一環として、店内で無料配布された。GOOD Magazineのインフォグラフィクスをペーパーナプキンに印刷したもので、二酸化炭素排出、教育、移民、経済、ヘルスケア、ガソリン価格など、客の会話や行動につながるような身近なテーマを扱っている。

“Arms Globe(兵器の地球)” by Google
各国の小型兵器と銃火器の売買を可視化したインタラクティブ・コンテンツ。毎年450~600億ドル(3兆6千億~4兆8千億)の武器が世界中で売買され、そのうち大半(約75%)は発展途上国への輸出である。国連の常任理事国である米国、ロシア、フランス、英国、中国の5カ国に、ドイツ、イタリアをあわせると、2002年から2009年の武器売買の85%を占める。世界中で増え続ける紛争による死者の8割は民間人で、その9割は小型兵器によるものだと言う。

“Financial Times, Graphic World” @ Grand Central St., N.Y.
ファイナンシャル・タイムズと、インフォグラフィック・ジャーナリスト、デビッド・マカンディスの共同プロジェクト。ニューヨーク、グランドセントラル駅構内に、インタラクティブ映像を投影した。映像のテーマは、グローバル・エコノミーや景気後退、お金の話、など、ファイナンスに関するインフォグラフィック映像になっている。

”Financial Times, Graphic World” @ Grand Central St. (2012)
ファイナンシャル・タイムズと、インフォグラフィック・ジャーナリスト、デビッド・マカンディスの共同プロジェクト。ニューヨーク、グランドセントラル駅構内に、インタラクティブ映像を投影した。映像のテーマは、グローバル・エコノミーや景気後退、お金の話、など、ファイナンスに関するインフォグラフィック映像になっている。

「昔の道頓堀」可視化プロジェクト
大正末頃から昭和初めの道頓堀の街並みを可視化するプロジェクト。歌舞伎の劇場や店舗をCGで再現し、3Dインタラクティブ技術によって「ウォークスルー」できるコンテンツを開発した。

高速道路シミュレータ
高速道路では様々な標識やサインが使われる。そのひとつとして、トンネル内のカーブで運転速度を落とさせるために有効な「壁面サイン」が検討された。このサインの効果を被験者に確認してもらうために、実際の運転を疑似体験できるシミュレータを 3Dゲームエンジン(Unity)を使って 開発した。

可視化とものづくり

オープン&シェアのものづくり~メーカー・ムーブメント(“Maker Movement”)
自分自身の手でモノを作り、その成果を多くの方と共有する「Makerムーブメント」が広がりつるある。
More than just digital quilting(単なるデジタルキルティングではない) -- テクノロジーと社会:「Maker」ムーブメントには、科学の学び方や、科学が革新を促進させる形を変える力がある。それは、新たなる産業革命の前兆かもしれない。止まらない科学離れへの対策や、停滞したものづくり産業を復活させる力としての期待もある。

メーカー・ムーブメント(“Maker Movement”)
“Maker”の定義(Dale Dougherty)1.分野をまたがるプロジェクトを好む人2.物理世界を可視化し、理解したいと思う人3.遊び心を持っている人4.成果をコミュニティと共有する人5.世界をより良くできる、問題は解決できる、全ては変わる、と思う人

Makerムーブメント( JSTサイエンスニュース)
JSTサイエンスニュース 「作る」が変わる!広がるMakerムーブメント(2012.9.19)自分の手でモノを作り、その成果を多くの人と共有しようという「Makerムーブメント」が広がり始めています。この夏開かれた”Make Ogaki Meeting”と「工作カフェ」Fablabつくばを取材。「あらゆる人が消費者から作り手(Maker) になる世界」を目指す、新しいものづくりへの動きをリポートします。

Radiation Watch
「ポケット・ガイガー(スマートフォンに接続する小型ガイガーカウンター)」のユーザーが計測したデータを収集・表示して作成された放射線量マップ。1万人以上のユーザーが計測した放射線量データを、スマートフォン上でリアルタイムに観ることができる。

可視化の新しい流れ

Grassroots Mapping by M.I.T.
インターバル撮影できるデジカメを取り付けた風船付きの凧をあげて、しばらく後に回収すると言う方法で撮影された画像を「つなぎ合わせ」ツールを使って高解像度画像に変換すると言う、市民参加プロジェクト。得られた空撮データは、NASAやNOAA(アメリカ海洋大気圏局)の人工衛星画像よりも解像度が高いと言う。ペルーで土地権利問題に携わったことが開発のきっかけ。その後、メキシコ湾の石油流出事故で活躍した。

街のムードを可視化する Fuehlometer ("Feel-o-meter")「感情計」
Julius von Bismarckらによる2008年のプロジェクト。ドイツ、Lindau島湖畔に設置されたデジタルカメラで、人々の顔を撮影する。そのデータはサーバーへ送られ、うれしい・悲しい・どちらでもないと言った表情が解析、合計される。その結果にもとづいて、湖畔の灯台の頂上にとりつけられた「ニコニコマーク」の顔が変わる。このようなしくみで「街の表情」を可視化した。

マネジメントの可視化 ~GM社の問題追跡可視化システム
「例えば、変速機のケースが耐久試験で壊れたとする。その問題は、文書化されると同時に、LEGOボード上にブロックとして置かれる。ブロックの色は車の部位を、ブロックの大きさは問題の重大さに対応し、それぞれのブロックには、ID番号と問題発生の日付が書かれる。ボード上のブロックの位置で、原因究明から解決策までの進行状況を把握する。

料理を使ったデータ可視化 “Data Cuisine”
"Data Cuisine"のアプローチは、料理によるデータ可視化。"Open Data Cooking(オープンデータ・クッキング)"と言うワークショップを開催している。右:「年齢・言語・レンズ豆」二つの皿はそれぞれ、アメリカとイタリア。英語を使う人の数をヨーグルトで、イタリア語はトマト&バジルが表す。レンズ豆の量は全人口、豆の煮込み量は平均年齢に相当

「サイエンスぬいぐるみ」

可視化と未来

公開 Open共有 Share革新 Innovation
可視化 Visualization

“Locals and Tourists”(地元民と旅行者)
Flickrに投稿された写真データから観光マップを作る試み。 その街の写真を1ヶ月以上にわたって撮影している人は地元民(青色)、1ヶ月位内は旅行者(赤色)と推定。地元民しか知らない「隠れた観光スポット」を可視化している。

Google Trrend / Google “Flu”
Googleは、特定の検索キーワードでの検索数がインフルエンザ流行の指標となることを発見した。これを使ったGoogleトレンドは、検索の集計データを使用してインフルエンザの流行をリアルタイムに予測している。
◆インフルエンザ患者数(米国)◆Google Fluトレンドの予測

Fathom Information Design 社 (Ben Fry)
Processingの開発者、Ben Fry 氏が立ち上げた、情報理解ビジネスを展開するベンチャー企業。会社紹介には、「Fathom Information Design社は、インフォメーション・グラフィクス、インタラクティブ・ツール、ソフトウェア、ウェブ、モバイル端末を使って、顧客が複雑なデータを理解し表現する事を支援します。」とある。

情報の検索から「情報の理解」の時代へ可視化はその有力なツール

情報の「理解」ビジネス
コミュニケーション産業の中には、情報を広めるためになすべきビジネスは三種類しか存在しない。情報の伝達、保存、そして理解、この三つである。
事実上まだ未開拓の分野が、第三の分野、すなわち「理解」ビジネスである。理解とは、データと知識を結ぶ架け橋であり、これこそが情報の本来の目的である。理解に関心を持っている人はいるが、まだ、それを専門にしているビジネスはほとんど存在しない。
私たちには、情報をアクセス可能にし理解可能とする専門の理解ビジネスが必要である。ますます生活を左右するようになったデータを解釈する新しい方法や、そのデータを使用可能、理解可能にし、情報に変えるような新しいモデルが必要である。
R.S.ワーマン「情報選択の時代」(1989)

これからもっとも魅力的な仕事?:「データ・サイエンティスト」
「今から10年後、もっとも魅力的な仕事は、『データ・サイエンティスト』だ。」(ハル・ヴァリアン、Googleチーフ・エコノミスト, 2009 )
データ・サイエンティストとは、次の技術を持っている人。(ベン・フライ、Processing開発者)
コンピュータ・サイエンス
数学、統計学、データ・マイニング
グラフィック・デザイン
情報可視化、ヒューマン=コンピュータ・インタラクション

まとめ(あるいは、希望)
これからは、情報「理解」ビジネスが重要になる
データはたくさんある。でも把握できていない。
情報「理解」ツールとして「可視化」に期待
可視化の可能性
あらゆる分野、様々なアプローチ
データ・サイエンティストは魅力的な仕事になる
可視化が社会を変える...と言うより、情報「理解」を進めるには、可視化は必須
「異分野融合の可視化」「専門深化の可視化」の2つの方向で拡大

課題
身近なことや社会の中で、「これが可視化されるとうれしい(役に立つ、便利、等)」と言うものをあげてください。

さいごに
All life is an Experiment. The more experiments you make the better. - Ralph Waldo Emerson
人生はすべて実験である。実験するほど人生はよくなる。 - ラフル・ワルド・エマーソン

ナポレオンのモスクワ侵攻での兵士の数の変化、気温、移動距離・方向、と言う複数の情報を平面に図示した (1869)。 「史上最高の統計図」「グラフの世界チャンピオン」などと呼ばれる。
「インフォグラフィクス」の創始者: Charles Joseph Minard , 1781-1870

Nonlinear Evolution of the Universe:from 20 million to 14 billion years old (宇宙の非定常的進化~2000万年から140億年前)
ウィルキンソン宇宙背景放射によって求められた非定常的進化のコンピュータ・シミュレーション。銀河クラスターの形成には巨大な空間を扱う必要がある。2005-2006年当時、この分野の計算では最大の解像度を誇る。.
Visualization of an F3 Tornado:storm chaser perspective (F3竜巻の可視化:ストーム・チェイサーの視点)2003年サウス・ダコタで観測されたF4竜巻を初期条件として、強力なスーパーセル型ストームが発生し、強力な竜巻が発生する、約1時間の現象を計算したもの。出力データは数テラバイトにのぼる。データを重視した可視化によって、内部構造が明瞭にわかる。流管は上昇中はオレンジ色に、下降中は青色で示され、ストーム内の経路を見せている。低圧の竜巻の渦中の回転する赤い球は、成長する竜巻を表現している。地表面では、円錐の傾きが風速と風向を表す。温度を表す色によって、竜巻の根元付近の暖気と冷気の境界がわかる。
NCSAの可視化事例
Movie








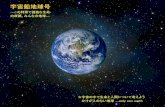






![9年度 講 講義要項 - 西日本短期大学[Nishitan]...西日本短大 講義要項/メディア・プロモーション学科 K 芦塚 背幅4ミリ(決*大島) 2019年度](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/614439f2aa0cd638b460b81e/9-e-ecee-eoecoenishitan-eoec-eceeifffffffffc.jpg)



