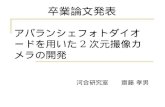立体カムの3次元モデリングの手法 · 単に行える手法を開発した。以降に,その概要を 述べる。 立体カムの3次元モデル化のプロセス
3次元CGによる人体・自然景観の表現 ·...
Transcript of 3次元CGによる人体・自然景観の表現 ·...
-
3次元CGによる人体・自然景観の表現
工学部情報工学科 北嶋研究室
研究概要 北嶋研究室では、3次元モデリングおよびコンピュータグラフィックスに関する独自の技術を開発するとともにそれらを駆使した自然現象のシミュレーションの研究に取り組んでいます。バーチャル(デジタル)ヒューマンと自然景観の表現・シミュレーションの2つの大きな柱があり、それぞれについて、斬新で面白い様々な研究を行うとともに、実用化を目指して頑張っています。
バーチャルヒューマン 自然景観表示 Virtual Human Digital Landscape
樹木形状の生成1
風に揺れるアニメーション2
手書き風の表現3
ヒューマンモデリング1
写真からの顔形状の復元2
表情・発話アニメーション3
http://www.tuat.ac.jp/~kitajima/
「種」の特徴と個体差を同時に表現し、仮想世界で樹木の形状を自動的に生成する研究を行っています。各々の「種」に固有の特徴を統計学や植物学の知識を用いて分析することで、生成される形状を本物に近づけています。具体的には、樹木を「高さ」や「枝の太さ」等の13種類の数値で表現し、この値同士の関係を「階層ベイズモデル」という統計学のモデルで分析することにより、ある種類の樹木は「樹高が1m増えると幹が10cm太くなる」などという関係を求めることができます。
このような関係を求めることで、樹木を自動生成するときに、個体差を表現する一方その「種」らしい形状を作ることができます。
樹木が風に揺れるようすをアニメーション表示するための研究を行っています。コンピュータで生成した樹木に対して、樹木の周囲を流れる風の動きを物理シミュレーションにより計算し、枝や葉にかかる風の力を求めています。それぞれの枝や葉に硬さを設定し、風力による変形を行うことで樹木の動きを作り出します。
物理シミュレーションを用いる方法は、計算量が多く通常の方法ではアニメーションの生成に時間がかかりすぎます。そこで、枝や葉が風を遮る効果をより単純な形式で数式に組み込むことで、計算を高速化する工夫を行っています。
人間が手で描く絵画やアニメの中にも、たくさんの樹木が描かれています。しかし、動きのある作品の中で樹木を詳細に描く作業は、高度な技術と多くの手間がかかります。そこで、この作業をコンピュータで自動化する研究を行っていますが、自動生成した樹木をある作風に模して自動的に表示することができる点に特徴があります。
上図の点線で囲まれた部分がCGにより描かれた樹木です。この研究では、画家が絵筆で樹木を描く際の手順を参考にして、「明るい色で描く領域」「暗い色で描く領域」などを計算により求め、色を塗り重ねていくことで、その画家の作風を再現しています。
デジカメ等の手軽な撮影手段により人体の形状を正確に復元するための研究を行っています。復元した形状データを用いることで、その人にフィットしたオーダーメイドの製品を現在よりも低コストで作成することができます。さらに、自宅に居ながら様々な種類の商品を試着することもできます。
現在は、メガネの試着シミュレーションおよび靴を作成するための足形モデリングについての研究に取り組んでいます。それぞれの部位の特徴的な位置を数十点写真から選択し、研究室で開発した GFFD と名付けた独自の変形手法を用いて個人の形状を取得しています。
人体の中でも特に個性の表れやすい顔形状については、さらに詳しく写真から形状を復元するための研究を行っています。復元の際には、顔を3方向から撮影し、特徴点の指定を行います。顔の場合は、形状を復元するだけではなく、撮影した画像のテクスチャを利用してモデルに合わせて合成することで、より本物らしい表示にすることが可能です。
この仕組みを、インターネット上や携帯電話上で実現できるようにすることで、手軽に自分のCGキャラクターを作成することも可能になります。近々、HP上で公開する予定です。
2で作成した顔形状に対して、自動的に表情付けや口をあけて話している時の様子を表現するための研究を行っています。表情を計算する際には、人間が表情をつくるもとになっている表情筋とよばれる筋肉の動きを仮想的に再現し、それに伴う皮膚の動きをGFFDにより再現しています。 この研究では、無表情の写真を入力するだけで様々な表情が自動的に生成できるので、ゲームや映画に登場するキャラクターの制作にかかる時間を大幅に短縮することもできます。