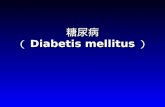1.糖尿病(菅原先生)2019年度 当日映写用 スライド60修正 …...2019-8-27 · 250 食後血糖 空腹時血糖 前糖尿病期 (IFG、IGT) 血 糖尿病と診断
2014年8月7日 広がった糖尿病治療の選択肢 2014年8月7日 特別企画 提供...
Transcript of 2014年8月7日 広がった糖尿病治療の選択肢 2014年8月7日 特別企画 提供...

1
特別企画 提供●ノバルティス ファーマ株式会社2014年8月7日
鈴木 本日は2型糖尿病治療の現状を検証し,今後どのように糖尿病を治療すべきかを検討したいと思います。経口血糖降下薬の歴史を振り返りますと,まずはインスリン分泌促進薬であるスルホニル尿素(SU)薬を中心に開発が進められ,その後,インスリン抵抗性改善薬としてチアゾリジン薬が登場し,また,ビグアナイド薬の臨床的意義が再評価されるようになりました。さらに,糖吸収阻害薬であるα-グルコシダーゼ阻害薬(α-GI),速効型インスリン分泌促進薬であるグリニドが発売されました。 2009年になると,消化管ホルモンであるインクレチンを介した膵β細胞におけるインスリン分泌促進作用と膵α細胞におけるグルカゴン分泌抑制作用を有する薬剤であるDPP-4阻害薬が登場し,当初の予想を上回る勢いで処方が拡大しました。また本年,糖質量調整という新しい作用機序を有するSGLT2阻害薬が登場し,糖尿病治療の選択肢はさらに広がりました。まず,DPP-4阻害薬の登場により,糖尿病治療はどのように変化したのかについてお話しいただきたい
と思います。宮地 当院における過去10年間の2型糖尿病患者のHbA1c値の推移を調べました。その結果,DPP-4阻害薬が発売されて以降,その長期処方が可能となった2011年を境に,HbA1c(NGSP値,以下同)7%未満を達成できる患者さんの割合が大きく増加していました。また,当院の経口血糖降下薬の処方数を調べたところ,DPP-4阻害薬の処方割合は2010年にはわずかに2.7%でしたが,2013年には30.7%に増加し,現在では最も多く処方されている薬剤となりました。一方で,他剤の処方割合は減少傾向にあり,特にSU薬の処方数が減少しました。このことは,低血糖に対するリスクの低下につながっていると推測されます。 しかし,罹病期間が長い患者さんなどでは,DPP-4阻害薬を投与しても,SU薬やインスリン製剤の減量や中止により血糖コントロールが悪化する症例も少なくありません。そのため,今後はより早期からのDPP-4阻害薬の投与が望ましいのではないかと考えています。鈴木 続いて内藤先生に糖尿病治療の質の変化についてご説明いただきたいと思います。内藤 高血糖が糖尿病のリスクということは最も認
2009年にジペプチジルペプチダーゼ(DPP)-4阻害薬が登場し,血糖コントロールの選択肢は大きく広がった。DPP-4阻害薬の中でもビルダグリプチン(エクア®)は,1日2回投与で24時間安定してDPP-4活性を抑制できることから早朝のグルカゴンを抑制できることを特徴としている また,本年より登場した選択的ナトリウム/グルコース共輸送体(SGLT)2阻害薬は,腎における尿糖の再吸収抑制という従来とは異なる機序による経口血糖降下薬であり,血糖依存性の血糖降下作用を有し,低血糖が少ないとされており,糖尿病治療の新たな選択肢として期待されている。 本座談会では,藤田保健衛生大学内分泌・代謝内科准教授の鈴木敦詞氏のご司会の下,順天堂大学特任教授の河盛隆造氏をコメンテーターに迎え,愛知県の糖尿病専門医6氏とともに,これらの薬剤を糖尿病治療にどう活用すべきかをご討議いただいた。
広がった糖尿病治療の選択肢―糖尿病治療を考える―
座談会
愛知
藤田保健衛生大学内分泌・代謝内科 准教授
鈴木 敦詞 氏
司 会
順天堂大学特任教授
河盛 隆造 氏
みやち内科院長
宮地 昇 氏
内藤内科院長
内藤 耕太郎 氏
コメンテーター
高橋ファミリークリニック院長
高橋 信雄 氏
福田内科院長
福田 成俊 氏
わたなべ内科クリニック院長
渡邊 源市 氏
出席者(発言順)
糖尿病治療の選択肢DPP-4阻害薬の処方が拡大
おおこうち内科クリニック院長
大河内 昌弘 氏
EQUA愛知_02.indd 1 2014/07/14 10:02

2
められているエビデンスであり,糖尿病治療では基礎高血糖,食後高血糖,HbA1cを下げることが最大の目標あることはいうまでもありません。また,それらの指標に加えて血糖変動の危険性が指摘されており,急峻な変動のない安定した血糖コントロールが求められています(図1)。最近,血糖の日内変動が心血管イベントの独立した危険因子であることも報告されています1)。 当院において,他のDPP-4阻害薬からビルダグリプチンに切り替えて良好な血糖コントロールが得られた患者さんに対して持続血糖モニター(CGM)を用いて血糖値の変動を測定したところ,空腹時血糖や夜間血糖などを中心に,おおむね良好な結果が得られたという経験をしています。DPP-4阻害薬の登場により,HbA1c低下という「量」の改善から,HbA1cの低下に加えて血糖変動という「質」の改善が得られるようになったと感じています。鈴木 わが国では7種類のDPP-4阻害薬が臨床で使用可能ですが,薬剤間で差はありますか。高橋 ビルダグリプチンの特徴として,まず1日2回投与であることから,他のDPP-4阻害薬と比較して,24時間にわたってDPP-4活性を抑制できるという点が挙げられます。特に早朝のDPP-4活性を抑えられることから,早朝のグルカゴン抑制が他のDPP-4阻害薬よりも強く,強力な血糖降下作用が得られると考えられます。また,ビルダグリプチンはDPP-4と共有結合することから,他のDPP-4阻害薬と比べて強固にDPP-4に結合し,より強いDPP-4抑制効果を示し,GLP-1濃度を高めると考えられています。外国人2型糖尿病患者を対象とした検討においても,プラセボと比較して夜間を通して翌朝までグルカゴン分泌の抑制が維持されていることが示されています(図2)。 私自身,血糖コントロールが不十分な症例に対してビルダグリプチンを投与し,
良好な血糖コントロールを得られたという例を数多く経験しています。
鈴木 続きまして,河盛先生よりこれからの2型糖尿病治療戦略について,お話を伺いたいと思います。河盛 2型糖尿病の理想的な治療は,空腹時のみな
グルカゴンの変化量の推移(臨床薬理,海外データ)図2
(Balas B, et al. J Clin Endocrinol Metab 2007; 92: 1249-1255, 承認時評価資料)
対象:外国人2型糖尿病患者16例 方法:ランダム化,二重盲検,プラセボ対照試験。クロスオーバー法によりビルダグリプチン100mgま
たはプラセボを17時30分に単回投与し,18時に放射標識されたブドウ糖75gが含まれている標準食を摂取させた
【用法および用量】通常,成人には,ビルダグリプチンとして50mgを1日2回朝,夕に経口投与する。なお,患者の状態に応じて50mgを1日1回朝に投与することができる。
時刻
(pg/mL)20
10
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
グルカゴンの投与前からの変化量
**
* *
** * * *
食事ビルダグリプチン100mg(N=16)プラセボ(N=16)
平均値±標準誤差*P<0.05(vs.プラセボ)ANOVA
17:00 08:0005:0002:0023:0020:00
糖尿病合併症発症に影響を与える要素図1
(Del Prato S. Int J Obes Relat Metab Disord 2002; 26 Suppl 3: S9-17)
急峻な血糖変動 食後高血糖 基礎高血糖
高血糖
HbA1c
糖尿病合併症
わずかな血糖上昇がβ細胞機能低下につながる早期の血糖正常化が重要
EQUA愛知_02.indd 2 2014/07/14 10:02

3
らず食後血糖応答をも正常域に維持する,しかも薬剤による低血糖を起こさないことです。しかし,これまでの2型糖尿病治療では,低血糖を危惧して十分量の薬剤を投与できず,高血糖が続き,そのため膵β細胞機能が低下し,後追いで治療を強化してきました。最近,わずかな高血糖持続がβ細胞機能を悪化させるメカニズムが相次いで明らかになり,より早くから血糖値を正常化する必要性が示されています。 私どもは最近,膵β細胞のインスリン顆粒膜上に存在し,顆粒内に亜鉛を流入させてインスリン結晶の形成に寄与する蛋白,Zinc Transporter 8(ZnT8)の活性が高血糖により低下し,亜鉛を中心とした6量体インスリンが減ると,その亜鉛の少ないインスリンは肝臓で分解されやすく,末梢でインスリンが不足して血糖値が上昇する,といった悪循環を形成し,糖尿病が進行することを明らかにしました2, 3)。 また,膵臓の分化,増殖,機能維持に必要な転写因子であるPDX-1は,インスリン,グルコース輸送担体(GLUT2),グルコキナーゼなどの遺伝子の活性化に必須の因子ですが,β細胞内で高血糖により酸化ストレスが生じると,PDX-1の発現が顕著に低下,さらに核外に放出され,インスリン分泌が減少する4)な
ど,「高血糖持続がβ細胞インスリン分泌能を低下させる」ことが実証されています。鈴木 では,2型糖尿病の早期の食後高血糖をどのように改善すべきでしょうか。河盛 糖尿病db/dbマウスにα-GIとビルダグリプチンをそれぞれ単独で投与しても,食後血糖値はコントロールできず,PDX-1の活性が低下し,β細胞マスが減少し,α細胞数が増えました。しかし,両薬の併用により食後血糖を抑えたところ,ZnT8やMafA
(β細胞の機能維持に重要な転写因子)の活性が保たれ,β細胞マスも減少せず,α細胞も増加しないことを最近発表しました5)。ですから,道具はなんであれ,積極的に用いて食後高血糖を正常化することがβ細胞機能を守るために重要なのです。
鈴木 次に,新規の糖尿病治療薬であるSGLT2阻害薬について検討したいと思います。SGLT2は腎近位尿細管に発現し,糖の再吸収の90%を担うトランスポーターです(図3)。SGLT2阻害薬は,SGLT2阻害により尿への糖排泄を増やすことで血糖値を低下させ
ます。これは従来の糖尿病治療薬とは全く異なる作用です。また,血糖値低下による肝脂肪減少を介したインスリン抵抗性の改善,ナトリウム(Na+)の尿排泄による血圧低下,尿酸排泄の増加による尿酸値低下も期待できるとされています。福田 糖の濾過量が血糖値に応じて増減し,また,血糖値が低いときにはSGLT1が活性化して糖再吸収が増加するため(図4),SGLT2阻害薬は低血糖を起こしにくいと考えられています。渡邊 開発試験においてSGLT2阻害薬を投与した症例を数例経験していますが,試験開始時のHbA1cが高い症例でHbA1cが大きく低下し,また,HbA1cの低
腎近位尿細管におけるSGLT1,SGLT2によるグルコース再吸収機構の比較図3
(Chao EC, et al. Nat Rev Drug Discov 2010; 9: 551-559, Lee YJ, et al. Kidney Int 2007; 72: s27-s35, Abdul-Ghani MA, et al. Endocr Pract 2008; 14: 782-790より作図)
SGLT1およびSGLT2の特徴の比較SGLT1
主に小腸に発現。一部腎臓,心臓に発現
ほぼ腎臓に特異的に発現
近位尿細管(S3) 近位尿細管(S1)高(Km=0.4mM) 低(Km=2mM)
低 高
発現部位
腎臓内の発現部位グルコース親和性グルコース輸送能腎臓におけるグルコース再吸収率 ~10% ~90%
SGLT2
グルコース
SGLT2
グルコース再吸収 90%
グルコース再吸収 10%
近位尿細管(S2/S3)
近位尿細管(S1)
集合管SGLT1
尿糖なし
選択的SGLT2阻害薬は尿への糖排泄により血糖依存性の血糖降下が期待される
EQUA愛知_02.indd 3 2014/07/14 10:02

4
2014年8月7日
下が大きい症例では体重,血圧,尿酸値の低下も大きい傾向が示されました。また,HbA1cと並行して食後血糖や空腹時血糖が大きく改善したという印象を持っています。内藤 開発試験において,SGLT2阻害薬を12週間単剤投与して食事負荷試験を行ったところ,用量依存的に食後血糖値を有意に低下させたという報告もあります6)。福田 SGLT2阻害薬には体重減少作用が期待されています。DPP-4阻害薬とSGLT2阻害薬を比較した海外の検討では,DPP-4阻害薬では体重は1年間ほとんど変化しないのに対し,SGLT2阻害薬では体重が2.5%減少したことが報告されています7)。 また,動物実験において,SGLT2の阻害が高血糖毒性の解除を介して膵β細胞を保護することが示唆されています。糖尿病を発症したマウスのSGLT2をノックアウトしたところ,非ノックアウト群と比べ,血糖値が低く,β細胞の体積が大きく,β細胞のアポトーシスが少なく,β細胞機能が維持されていました8)。大河内 SGLT2阻害薬には腎保護作用の可能性も期待されています。糖尿病初期の腎臓では,アンジオテンシンⅡの活性化により腎輸入細動脈が拡張します。また,腎近位尿細管に到達する尿糖が増加してSGLT2が過剰発現し,Na+の再吸収も増加します。結果として,マクラデンサへのNa+の到達が減少し,尿細管から糸球体へのフィードバックシグナルの減少により腎輸出細動脈の収縮も生じます。これらより,糸球体内圧が上昇し過剰濾過が生じます。その後,内皮細胞障害,メサンギウム細胞障害から細胞外基質の線維化,糸球体硬化が生じ,腎症が進展していきます9)。ここで,SGLT2を阻害すると,マクラデンサへのNa+の到達が増加し,フィードバックシグナルが改善するため,糸
球体濾過圧が正常化します10)。このことから,過剰濾過患者に対するSGLT2阻害薬投与により,血糖値にかかわらず糸球体濾過量を改善させることが報告されています。 2型糖尿病性腎症のラットモデルでは,SGLT2阻害薬の投与により,ACE阻害薬と同等に糸球体硬化と腎皮質の線維化が抑制されました。さらに,SGLT2阻害薬とACE阻害薬を併用すると,糸球体硬化と腎皮質線維化はともに相加的に抑制されました11)。以上から,SGLT2阻害薬は,糸球体濾過圧の減少,近位尿細管の高血圧惹起性の細胞障害の抑制,血圧の低下,体重の減少などの機序により,糖尿病初期の腎症の進展を抑制すると考えられます。
鈴木 次に,SGLT2阻害薬を投与する上での注意点を検討したいと思います。大河内 浸透圧利尿により脱水,低血圧,腎機能低下例における腎機能悪化が懸念されます。高齢者ではサルコペニア(骨格筋減少症)により転倒,骨折のリスクや日常生活動作(ADL)の低下につながる可能性
選択的SGLT2阻害薬の作用機序図4
(Nomura S. Curr Top Med Chem 2010; 10: 411-418より作図)
SGLT2阻害薬を単剤で使用した場合,低血糖が少ない理由①グルコースの濾過は血糖依存性であり,血糖が低い場合には濾過量も低下する②血糖が低い場合,SGLT1の活性が増加し,血糖再吸収を増加させる
SGLT2阻害薬投与
グルコース
糖尿病
グルコース
健康人
SGLT2
SGLT1
グルコース
糖尿病(正常血糖時)
グルコース
糖尿病(高血糖時)
グルコース
糖尿病(低血糖時)
選択的SGLT2阻害薬投与時は水分補給を指導する必要が
EQUA愛知_02.indd 4 2014/07/14 10:02

55
2014年8月7日
があります。また,肝での糖産生に伴う脂肪分解により血中ケトンが上昇するため,ケトアシドーシスの懸念もあります。膀胱がん,乳がんの発生率が上昇したという報告もあり,長期的な安全性の確認が必要です。河盛 SGLT2阻害薬により1日100g程度の尿糖が排出される際には,約700mLの尿量が増えます。循環血漿量の低下による血栓症の可能性もあるため,水分補給を強く指導し,かつ投与直後からヘマトクリットの変化を見るべきですね。宮地 開発試験時の経験では,水分補給を指導したところ,脱水による口渇や頻尿は軽度でした。尿路感染症は同一症例で再発を認めましたが,頻度としては高くなかったという印象を持っています。渡邊 私も開発試験時には尿路感染症の経験はありませんでした。ただ,海外のメタアナリシスでは尿路感染症,性器感染症ともに有意にリスクが高いという報告があることから注意は必要です12)。高橋 開発試験において,痩せ型でインスリン分泌能が低下した患者さんにSGLT2阻害薬を投与したところ,食欲が異常に高まり,ドロップアウトした例を経験しています。河盛 痩せ型の患者さんやインスリン分泌が低下した患者さんに用いざるをえない場合は,慎重に頻回の観察で血中ケトン体などをチェックする必要があります。
鈴木 これまでお話しいただいた有用性と安全性を踏まえると,SGLT2阻害薬はどのような症例に使うべきでしょうか。宮地 インスリン分泌が保たれている肥満の患者さんは良い適応になると思います。開発試験に参加した患者さんの中には,体重が減って治療に対する意欲が高くなった方もいました。内藤 BMIが30以上で食事療法を守れないような患者さんに投与したいと考えています。渡邊 ただし,体重減少を過剰に期待して食事療法がおざなりになる可能性もありますので,あらためて食事療法を指導する必要がありますね。大河内 脱水やサルコペニアなどの懸念があるので,
初めは非高齢者で肥満例,脂肪肝があるような例に使いたいと思います。高橋 開発試験の経験では,SGLT2阻害薬はノンレスポンダーが少なく,HbA1cも体重も一定程度は減少するという印象を持っています。河盛 私も比較的若い肥満例で食事・運動療法ができない方に対して単剤で使おうと考えています。高血圧など他疾患がない人に限定しようと考えています。 なお,SGLT2阻害薬は全ての糖尿病治療薬との併用が認められていますが,低血糖を決して起こさないように,SU薬は中止してからSGLT2阻害薬単剤に切り替えるという慎重さが必要でしょう。その後,効果を見ながら他の薬剤を併用すべきと思います。鈴木 SGLT2阻害薬にはどのような薬剤との併用が適しているとお考えですか。河盛 SGLT2阻害薬はすぐに体重,HbA1cを低下させますが,なぜかHbA1c 7%程度で高め安定してしまう例が多いようです。私はインスリン分泌低下のためグルカゴン分泌が亢進し,肝・糖放出率を上げたためと捉えています。すると,グルカゴン分泌を抑制する薬剤,DPP-4阻害薬の併用が理にかなっていると推測しています。SGLT2阻害薬への期待は「高血糖毒性」を取り除くことですから,正常血糖域に持ってくることが必要でしょうね。鈴木 SGLT2阻害薬は血糖値に応じた血糖降下作用を持ち,低血糖を起こしにくく,また,体重減少,インスリン抵抗性改善,血圧低下,β細胞保護,腎保護の作用なども報告されています。SGLT2阻害薬を早期から使うことで,糖尿病の基本病態の1つであるβ細胞機能の低下が抑制されることが期待されます。本日はありがとうございました。
本特別企画はノバルティス ファーマ株式会社の提供です
1)Su G, et al. Diabetes Care 2013; 36: 1026-1032. 2)Tamaki M, et al. Islets 2009; 1: 124-128. 3)Tamaki M, et al. J Clin Invest 2013; 123: 4513-4524. 4)Kawamori D, et al. Diabetes 2003; 52: 2896-2904. 5)Ishibashi K, et al. Biochem Biophys Res Commun 2013; 440:
570-575. 6)Seino Y, et al. Curr Med Res Opin 2014 Mar 19(Epub ahead
of print) 7)Schernthaner G, et al. Diabetes Care 2013; 36: 2508-2515. 8)Jurczak MJ, et al. Diabetes 2011; 60: 890-898. 9)横野博史, 他. 診断と治療 1999; 87: 80-84.10)Cherney DZ, et al. Circulation 2014; 129: 587-597.11)Kojima N, et al. J Pharmacol Exp Ther 2013; 345: 464-472.12)Vasilakou D, et al. Ann Intern Med 2013; 159: 262-274.
選択的SGLT2阻害薬の適応患者像非高齢の肥満例において効果が期待できる
EQUA愛知_02.indd 5 2014/07/14 10:02

EQUA愛知_02.indd 6 2014/07/14 10:02