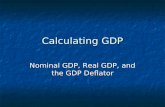はじめにokui/ensyu/koukyo.doc · Web view国 GDP(単位:億ドル)...
Transcript of はじめにokui/ensyu/koukyo.doc · Web view国 GDP(単位:億ドル)...

」 2002/10/23
少子高齢化社会における医療改革追手門学院大学 奥井ゼミ 公共経済論パート
浅野 紘央 上田 祥司 金谷 真伍 佐々木 隆史 廣井 雄一 山本 政光

目次
はじめに
1.少子高齢化社会の現状1-1出生率の低下と晩婚化の進展1-2少子化をもたらした社会背景1-3今後の少子化の進展とその影響
2.政府による医療改革2-1概要2-2問題点
3.現在の医療制度3-1医療保険制度3-2高齢者医療制度3-3介護保険制度3-4医療の国際比較3-5医療制度の問題点
4.これからの医療4-1問題点の修正4-2総合的な改革
おわりに
2

はじめに
近年、日本の高齢者人口は急速に増加している。高齢化率が 7%を超え、高齢化社会と呼ばれ始めたのが、約 30年前だったのが現在では 18%に近い数字になっており、2010年には 20%を上回るであろうと予想されている。 日本を含めた先進国における高齢者の人口の増加は、医療技術や保険制度の飛躍的な進
歩によるものである。しかし、その結果としてそれをもたらした医療や保険制度に新た
な問題を生じさせる結果となった。
そこで、2001年 9月、厚生労働省は医療制度の大幅な改革に向けて、膨張する医療費をまかなう部分、そしてあるべき医療の姿を実現するための諸施策の部分に分かれる試
案を公表した。この試案の副題として「少子高齢社会に対応した医療制度の構築」とある
ように、急増する老人医療費を我々の世代がどのように負担し、持続可能な医療保険制度
とするかが課題とされた。対策の特徴の一つとして「高齢者にも応分の負担」を求めて
いること。二つ目は医療費抑制のため、思い切った総粋管理制度を提唱したことである。
しかし、この試案は具体的には患者には窓口負担の引き上げ、医療保険加入者には保険料
のアップ、医療機関には収入減というすべてにおいて負担が増える内容であり、各方面
から強い批判を集めた。これは、医療改革が一筋縄では行かないことを示している。
そこで、私たちは、この試案は必要なのか、現行の医療制度では、これから先の高齢化
社会では対応していけないのか、こういったところに注目し、試案で提示されている制
度や現行制度の問題点を指摘しながら、三方一両損にならなく、この場しのびにならな
い日本のためになる新しい政策を提言していく。
1 少子高齢化社会の現状近年、主要先進国間で少子高齢化が進展している。特に日本はここ数年で急速に少子高
齢化が進んだ。その主な原因は何か?
1-1 出生率の低下と晩婚化の進展
合計特殊出生率(女性1人が一生の間に産む平均子供数)が戦後、急速に低下した。急速な数値の低下は、結婚した女性の産む子供数が減少したことが原因であり、一家の平均
3

子供数が4~5人から 2~3人に減少した。これに加えて、20代後半~30代前半の未婚率が上昇し、この晩婚化の進展が少子化を進める原因となった 今後、結婚年齢の上昇により、結婚後に産む、子供の数が減ってい。る。
表1-1 先進国における合計特殊出産率の推移
1950年
1980年
1998年 1950年以降の最低合計特殊
出生率
日本 3.65 1.75 1.38 1.38(1998)アメリカ 3.02 1.84 2.06 1.77(1976)イギリス 2.19 1.89 - 1.69(1995)フランス 2.92 1.99 - 1.65(1994)ドイツ 2.05 1.46 - 1.24(1994)イタリア 2.52 1.61 - 1.26(1994)スウェーデ
ン
2.32 1.68 - 1.60(1978)
ノルウェー 2.53 1.73 1.51 1.51(1998)デンマーク 2.58 1.54 - 1.38(1983)
出所「人口動態統計p86」1-2 少子化をもたらした社会的背景
国民の生活水準の向上に伴い、人々の意識やライフスタイルが大きく変わり、結婚・出
産の目的や必然性が変化してきた。経済的な余裕から女性の自立が進み、必ずしも結婚を
人生の目標とは考えない若者が増えるとともに、個々の価値観に基づいて生きていこう
とする人々が多くなってきた。
こういう傾向を反映して 独身でいることに対する社会的プレッシャーが低下し 結婚、 、しないことが周囲にも受け入れられやすくなった。加えて 結婚や出産に対するコストや、負担がこれまで以上に大きくなり、先延ばしにする人が増えてきているのもある。
(1) 家庭における独立 巣立ちの教育の不足・ 近年では、家庭内における人間としての独立・巣立ちの教育が十分ではなくなってき
ている。そのため、子供は就職しても裕福な親の元で同居を続けるケースが多い。
その場合、子供は家事負担もほとんどなく、収入の大半を自分のために使える優雅な独
身生活を謳歌できることから、特に、女性にとって明らかに負担の増える結婚や出産に
は踏み切りにくくなっている。
4

(2) 機会費用の増大
女性の高学歴化と社会進出の増大により、若い女性を中心に所得水準があがってきてい
ることから、女性が仕事をやめることにより失うコスト(機会費用)が増大している。 その結果、女性が結婚や出産 子育てのために仕事をやめようと考えたときに、従前の・生活水準を維持できるような条件を満たす相手を探すのが困難になっている。
(3) 困難な仕事と子育ての両立
最近では、子育て中でも働きたいと考える女性は多い。が、仕事と子育てを両立させよ
うとしても 保育サービスが不足している現状では負担が大きくなりすぎる。、さらに 現在の雇用環境からすればその何れかをやめざるを得ない。、(4)専業主婦の子育て負担
核家族化の進展や子育ての負担増大により、専業主婦の育児不安・ストレス等の問題が
顕在化しつつある。
1-3 今後の少子高齢化の進展とその影響
急速な少子高齢化の進展は総じてみると以下のようなマイナスが考えられる。
(1) 急激な人口減少と高齢者比率の上昇
出生率 出生数の低下を受け、2007年以降、人口が減少に転じるのはほぼ確実であ・り 避けることができない。、 特に問題なのは人口減少のスピードであるが 最も楽観的な見通しである高位推計、 (出生率が2030年にかけて 1.85まで回復する前提)においても、現在の 1億 2600万人から2100年には9千万人まで減少する。さらに 死亡率 出生率が現在から変わらないと仮、 ・定すると、人口は2100年では約4700万人まで減少する。
年齢構成は、平均寿命が延び続けていることから高齢化が急速に進展し、2050年頃
には3人に1人が65歳以上、5人に1人が75歳以上となる。
5

出 所 http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_hoken/
roujin
(2)労働力の減少による経済成長率の低下
人口が減少すると同時に高齢化すれば、経済成長率が急激に低下するのは明らかである。
具体的な理由としては、高齢者が増えれば増えるほど、肉体を使う仕事が制限され、事務
的なものばかりに偏ってしまう。
このように、少子高齢化はその国全体を全て変えてしまう危険性があるので、一刻も
早い対応が必要不可欠である。
2.政府による医療改革治療費のことを心配せずに、誰でも医療を受けることができるようにとつくられたの
が、医療保険制度であり国民すべてが保健で平等な治療が受けられる制度である。しか
し、政府はこの少子高齢化社会を迎え医療保険財政の危機を強調し医療費の自己負担額が
引き上げられる等の内容の改革案を発表した。ここでは、この改革案について詳しく見
ていく。
2-1概要
6

(1)改革の目的
今回の医療制度改革の主眼は、急速な高齢化や保険料収入の伸び悩みで各医療保険財政
が危機的状況に陥る中で、高齢化のピークに入る2025年を視野に、保険料を支払う国
民・事業主と患者、医療機関、行政が負担を分かち合うことで、だれもが一部の負担で必
要な医療を受けられる「国民皆保険制度」を維持・発展させることにある。特に中小企業
のサラリーマンが加入する政府管掌健康保険は、今年度の赤字が7282億円に達する見
込みで、制度改正がなければ、医療費の支払いができなくなる恐れがあった。
また、大企業のサラリーマンが加入する健康保険組合(約1700組合)も、今年度の
赤字は全体で5731億円に達する見込み。自営業者らが加入する国民健康保険も、20
00年度の実質的な赤字は4200億円を超えた。
このように国民の“安心の基盤”である国民皆保険制度は崩壊しかねない状況にあること
から、保険を運営する側の健康保険組合連合会や全国町村会などは法案の早期成立を強く
望んでいた。
来年四月からサラリーマンらの医療費の自己負担率を三割に引き上げることを柱とし
た、改正健康保険法など医療制度改革関連法が2002年7月26日の参院本会議で与党
三党の賛成で可決、成立した。
(2)医療費の引き上げ
これにより、70歳以上の高齢者は今年10月から、サラリーマンは 2002年4月から
医療費の自己負担が重くなる。
サラリーマンの医療自己負担は現在、本人は入院・外来ともに2割、家族は外来が3割、
入院は2割。これが来年4月からすべて3割となり、本人は入院・外来の両方、家族は入
院時の自己負担が現在の1.5倍になる。このことにより、サラリーマンとその家族で
一人当たり年4000円、高齢者で年8000円増えると厚生省は試算している。同時に、
外来窓口で定率負担に上乗せして支払う薬剤費の一部負担は廃止される。
厚生省のモデルケースの試算では、かぜで診療所に月2回通った場合、サラリーマン本
人の自己負担は1530円となり、510円の負担増。虫垂炎の手術で7日間入院した場
合、自己負担は7万2530円、負担増は1万9710円だ。
7

自営業者など国民健康保険の加入者は、すでに3割負担のため、負担増は変わらない。
薬剤費の一部負担が来年4月になくなるのはサラリーマンと同じなので、自己負担は軽
くなる。
サラリーマンも自営業者も、高額の医療費がかかった時の自己負担は現在より増える。
1ヶ月の自己負担額が限度額を超えると超過分の払い戻しを受ける仕組みだが、今年10
月からこの限界額が1割強上がる。
(3)保険料も引き上げ
(a)サラリーマンは患者負担だけでなく、保険料負担も重くなる。現在の保険料は主に
月収の一定比率だが、来年4月から月収とボーナスに同率の保険料がかかる 総報酬制 に「 」変わる。単純な切り替えなら保険料は下がるが、保険財政が悪化しているため総報酬制の
導入時に保険料率を上げる医療保険が多い。
中小企業サラリーマンと家族が加入している政府管掌健康保険は来年4月の保険料引き
上げが決まっている。現在は毎月の給与の8.5%(労使折半)、ボーナスの1%(うち
本人負担は0.3%)の保険料率は「総報酬制」で7.5%に下がるが、0.7%引き上げ8.2%にする。
年収417万円(月収30万、ボーナス1.9ヵ月分)の平均的加入者の場合、 労使合」計の保険料は年3万1000円の自己負担増になる。大企業サラリーマンが加入する健康
組合も保険料上げを検討中のところが多い。
(b)高齢者は定率1割
70歳以上の高齢者の自己負担も重くなる。現在も原則はかかった医療費の1割負担だ
が、診療所の外来には定額負担制が残っている。1割負担でも外来患者の1ヶ月の負担限
度額は約3000円と現役世代に比べ大幅に低い。
今年10月から定額負担制が完全廃止になり、完全な定率1割負担になる。さらに70
歳以上でも高所得者は負担割合が2割に増える。70歳以上の約1割が該当する。
ただし、医療機関の規模により、以下のように支払方法が変わる。
(1)200 床以上の大病院・・・医療費の 10%負担、月上限 5000円(2)200 床未満の中小病院・・・医療費の 10%負担、月上限 3000円(3)診療所・・・(A)か(B)の選択
(A)→医療費の 10%負担、月上限 3000円(B)→一回の診療が 800円、月上限 3200円入院の場合は、医療費の 10%負担で、月上限 37200円
8

69歳以下の患者負担
(1) 月収 56万円以下・・・1 ヶ月にかかった医療費が318000円以下の場合
自己負担限度額の63600円を負担することになる。超えた場合は、超えた分
の 1%を63600円に加算した額を負担することになる。
(2) 月収が 56万円以上の高所得者・・・一ヶ月にかかった医療費が609000円以
下の場合自己負担限度額の121800円を負担することになる。超えた場合は、
超えた分の 1%を121800円に加算した額を負担することになる。
患者が医療機窓口で払う負担は約4800億円、保険料は約1兆円増える。特に中小企業
サラリーマンは患者負担と保険料の両方が上がる。改正保険法が施行されると2003年
度から5年間の平均で患者負担は年4800億円増え、その約6割は69歳以下の現役世
代の負担となる。
健康保険料率の上限
康保険料率の上限見直し 政府管掌健康保険の場合 これまでの健康保険料率と介護保険料、率を合わせて 9.1%以下(健保組合は 9.5%)から 健康保険料率だけで、 9.1%以下(健保組合は 9.5%)にする。
入院時の食事負担
1日 760円から 780円に変更
薬剤費一部負担制度
内服薬 1日分につき 2~3種類まで30円、 4~5種類60円、6種類以上 100円
頓服薬 1 種類につき 10円 外用薬 1種類 50円、2種類 100円、 3種類以上 150円
※ 入院時の薬剤費の一部負担はなし
※ 満六歳未満の者、及び老人医療対象者の薬剤一部負担金は、平成 13年 1月 1日より廃止
改正)
9

平成 12年健康保険法改正法附則に基づき、今般の制度改正全般とあわせ、一般制
度
にかかる外来薬剤一部負担金制度を廃止する。
※1997年の改正で薬剤費一部負担制度を導入したが、制度を廃止するという
ことになる。
改正健康保険法により、当然のこと 70歳以上の患者負担は増加するが、69歳以下の患者も月の負担上限への上乗せ率適用と健康保険料の上限見直しにより、保険料負担は増加す
る可能性がある。
今後も、中長期的に老人医療は増加するので、将来の保険料負担は増加することとなる。
改正健康保険法により、健康保険組合の財政は一時的に潤うことになるが、それもすぐに
悪化することが見えている。
2-2問題点
日本政府が行おうとしている改革の主なものは現役世代からもっと多くの資金を回収
し破綻寸前の社会保障(社会保険、公的扶助、社会福祉、公衆衛生の 4つがある)を持続させようとするものである。
社会保障の中で最も財政が緊迫して今回の改正の原因ともなったのは、社会保険(健康
保険制度、年金制度がある)のうちの年金制度のほうである。
昔は労働人口が多く、しかも、高齢者の寿命が今と比べて短かったので高齢者の負担を
カバーでき、一人当たりの負担が少なくて良かったが、高齢者の寿命が伸び、少子化によ
って少子高齢化が進み年金が上がったために財政は緊迫してきた。
そこで社会保険を現役世代の負担額を上げることによって賄おうとしたものが今回の
改正案である。しかし、図 2-1や表 2-2のとおりこれからも少子高齢化が進んでいくと思われる社会においては、今後さらに一人当たりの負担は多くなっていくと予想され
る。よって、このような政策は短期には多少の効果を挙げるかもしれないが、全く根本
的な解決になっていないので中長期的に見るとまったく意味のないものとなってしまう。
図2-1 労働人口と非労働人口の推移 表2-2
10

出所 http://wwwdbtk.mhlw.go.jp/toukei/youran/data13r/B-04.xls」
年
老人一人当たり
を支える人数
(人)
(1970) 9.70
(1975) 8.57
(1980) 7.40
(1985) 6.62
(1990) 5.79
(1995) 4.79 (2000)
3.92
(2010) 2.85
(2020) 2.16
(2030) 2.00
(2050) 1.50
11

3.現在の医療制度1961年に国民皆保険制度が実現して以来、高齢化が進むにつれさまざまな改革が行われ、現在の医療制度が確立した。しかし、加速度的に高齢化の進む現在においては医療費
の不足、医療の質の低下などさまざまな問題が指摘されている。ここではその現在の医
療について詳しく見ていく。
3-1医療保険制度
医療保険制度とは、病気、けが、出産、死亡などが発生したときに、その治療や休業に
よる所得の中断・減少といった短期的な経済的損失に対して給付を行う制度である。
1.医療保険の種類
医療保険には、一般のサラリーマンを対象とする健康保険、船員を対象とし国(社会保
険庁)が運営する船員保険、各種公務員を対象とし共済組合が運営する国家公務員共済組
合、地方公務員等共済組合、私立学校教職員共済組合がある。健康保険は、主として中小
企業のサラリーマンを対象とし国が運営する政府管掌健康保険と、主として大企業のサラ
リーマンを対象とし企業やグループごとの健康保険組合が運営する組合管掌健康保険から
なる。
地域保険には、自営業者・農業者等が被用者保険の退職者を対象とする「国民健康保
険」がある。なお、75歳以上のものはすべて老人保険制度の対象者となる。 (2002年10月1日以降)
2.医療保険の給付
医療保険の給付には、病気やけがをしたときに医療を受けることのできる療養の給付
(被扶養者に対しては家族療養費)などの医療給付、出産育児一時金(分娩費)、死亡時
の埋葬量、休業中の所得を保障する傷病手当金・出産手当金といった休業給付などがある。
医療給付は自営業者・農業者等を除き、保険の対象となる本人(被保険者)だけでなく、
その扶養する家族(被扶養者)に対しても行われる。また医療給付は、医療機関で一部負
担金を支払うだけで医療サービスが受けられる「現物給付」であり、かかった費用のう
ち一部負担金以外の部分について、保険の運営主体(保険者)が事後的に医療機関に支払
12

うこととなる。一方、出産育児一時金、埋葬料、傷病手当金・出産手当金などは、現金を
支給する「現金給付」である。
療養の給付と家族療養費の一部負担の場合は、職域保険では、本人が二割、その被扶養
者が外来三割・入院二割、地域保険では、自営業者・農業者等(本人)が三割、被用者保
険の退職者本人が二割、その被扶養者が外来三割・入院二割となっている。また、外来で
投薬される薬剤に関して内服薬については投薬ごとに、一日分につき2または3種類の
場合は30円、4または5種類の場合は60円、6種類以上の場合は100円を、外用薬
については、投薬ごとに一種類の場合は50円、2種類の場合は100円、3種類以上の
場合は150円を、頓服薬については、投薬ごとに1種類につき10円を一部負担金とし
て支払うこととされている。
医療保険の給付の財源は、保険料と国庫負担である。保険料は、職域保険では被保険者
本人の月収の一定割合を原則として労使折半しており、また、地域保険では世帯ごとに定
額の応益割と負担能力に応じた応能割を組み合わせて賦課している。
3-2老人医療制度
老人医療制度とは、高齢者が医療機関にかかる際に費用の負担を軽くして、安心して医
療を受けられるようにするための制度である。
老人医療は、75歳(寝たきり等の人は 65歳)以上になった人が対象となり、現在加
入している医療保険の資格のまま、適用を受けることになる。 (2002年10月1日変更)
1.老人医療の対象者
国民健康保険や社会保険等いずれかの医療保険に加入している人で
(1) 75歳以上の人(2002円10月1日以降)ただし、2002年 9月 30日までに 70歳になっている人は引き続き老人保健の対
象である
2002年 10月 1日以降に 75歳になるまで現在の医療保険で医療を受け、75歳になると老人保健で医療を受ける。
(2) 65歳~75歳未満の人で、次の程度の心身の障害がある人で市長の認定を受けた
人
・ 身体障害者手帳 1~3級の人
・ 身体障害者手帳 4 級の一部(音声、言語、下肢の障害)の人
・ 精神障害者保健福祉手帳 1~2 級の人
・ 療養手帳 A(重度)の人
・ 障害者年金受給者(法で定められた人)
2.医療費自己負担額及び高額医療費制度
13

医療機関窓口では、医療費の1割又は2割(入院については限度額がある)を支払い、
その限度額が1ヶ月につき下記の自己負担限度額を超えた場合、それぞれの市町村の
担当窓口に申請すると超えた分が「高額医療費」として支給される。
表 3-1
所得による区分 窓口での負担一ヶ月の負担上限
外来 入院
一定以上の所得のある人 2割40,200円
72,300円+(医療費-
361,500円)×1%
一般の人 1割12,000円
40,200円
市民税非課税世帯の人区分Ⅰ
1割8,000円
15,000円区分Ⅱ 24,600円
表 3-2所得による区分 課税標準額
一定以上の所得のある人 124万円以上
一般の人 124万円未満
市民税非課税世帯の人
世帯の総所得金額 所得の例
区分Ⅰ 全員が0円の世帯
一人世帯
年金収入のみ約65万円以
下
区分Ⅱ 0円でない人がいる世帯
一人世帯
年金収入のみ約267万円
以下
※総所得金額:収入から必要経費等を控除した金額
(公的年金等控除の最低保障金額は 65万円で計算)
※ 「市民税非課税の世帯の人」の区分について
・ 「区分Ⅰ」:世帯主および世帯全員が住民非課税かつ各種所得区分にかかる収入金額等から必要経費、
控除を差し引いた各種所得が 0円となる世帯に属する人
・ 「区分Ⅱ」:世帯主および世帯全員が住民非課税の人
14

出所 「老人保健法による医療制度」
3-3 介護保険法
介護保険の本格的な議論が始まったのは 1994年 12月、厚生省が立ち上げた高齢者介護自立支援システム研究会であるが、ここで掲げられた「介護を必要とする人は、いつ
でも、どこでも、誰でも、必要な介護サービスを利用できるシステムの確立」という創
設目標(直接の表現は「国民誰もが、身近に、必要な介護サービスがスムーズに手に入れ
られるようなシステム」の構築)がどの程度達成されているかが重要なのである。具体
的には、行政が決定をするこれまでのサービス利用システムから利用者が自ら選択する
選択の自由の実現、そして介護の社会化の推進という 2点の到達状況がポイントとなっ
ている。
1.介護保険法の概要
65歳以上の人が要介護状態になった場合には、その原因を問わず介護保険制度を利用
できるが45~64歳までの人の場合は、15種類の特定疾病(表 3-3参照)に該当す
る人に限り介護保険制度上でのサービスを利用することができる。
そしてコンピュータによる判定と訪問調査の結果(特記事項等)、そして主治医の意見
書を踏まえて、介護認定審査会において要介護度が決定される。認定結果(要介護度)に
応じて定められた範囲内で、介護保険のサービスが受けられる。
サービスを受ける際には、ケアマネジャー(個人に合わせて、必要な介護の計画を作
成する人)に依頼して、介護サービス計画(ケアプラン)を作る。
利用したサービスの 1割は自己負担となる。(表 3-3) 特定疫病一覧
1 筋萎縮性側索硬化症(ALS)2 後縦靱帯骨化症
3 骨折を伴う骨粗鬆症
4 シャイ・ドレーガー症候群
5 初老期における痴呆
6 脊髄小脳変性症
7 脊柱管狭窄症
8 早老症(ウェルナー症候群)
9 糖尿病性神経障害、糖尿病性腎症及び糖尿病性網膜症
10 脳血管疾患
15

11 パーキンソン病
12 閉塞性動脈硬化症
13 慢性関節リウマチ
14 慢性閉塞性肺疾患
15 両側の膝関節又は股関節に著しい変形を伴う変形性関節症
出所「http://www.pref.nara.jp/kaigo/sippei.htm」
介護サービスの種類は次のようになっている。
在宅サービス
1.訪問通所サービス
1)訪問介護
ホームヘルパーが訪問し、食事、入
浴、
排泄などの身体介護や、炊事、掃除な
ど
の家事援助を行います。
2)訪問入浴介護
移動入浴車などで訪問し、入浴の介助
を
行います。
3)訪問看護
通院が困難な方に対して、看護婦など
が訪問し、主治医の指示をもとに手当
などを行います。
4)訪問リハビリテーション
通院が困難な方に対して、理学療法士
や
作業療法士が訪問し、リハビリテーシ
ョンを行います。
5)通所介護デイサービスセンターなどに通って、
入浴、食事の提供などの日常生活の世
話や、日常動作訓練を受けられます。
16

6)通所リハビリテーション介護老人保健施設などに通って、リハ
ビリテーションが受けられます。
2.短期入所サービス
1)短期入所生活介護
特別養護老人ホームに短期間入所し
て、入浴、排泄、食事などの、日常生
活上の生活介護を受けられます。
2)短期入所療養介護
介護老人保健施設などに短期間入所し
て、日常生活上の介護のほか、医学的
管理のもとで療養介護を受けられま
す。
3)福祉用具の貸与ベッドや車いすなどの貸与が受けられ
ます。
3.その他の在宅サービス
1)宅療養管理指導
通院が困難な方に対して、医師や歯科
医
師などが療養上の管理や指導を行いま
す。
2)痴呆対応型共同生活介護痴呆の状態にある要介護者が、グルー
プホームで共同生活をしながら、日常
生活上の介護を受けられます。
3)特定施設入所者生活介護有料老人ホームや軽費老人ホーム(ケ
アハウス)などの入所者が、必要な介
護を介護保険で受けられます。
4)福祉用具購入費の支給
ポータブルトイレなどの購入費(支給
限度基準額 10万円)の支給を基準額
の 9割まで受けられます。
5)住宅改修費の支給
手すりの取り付けや段差の解消など、
小規模な住宅改善費(支給限度基準額
20万円)の支給を基準額の9割まで
受けられます。
施設サービス
1)介護老人福祉施設(特別養護老人ホー
ム)
日常生活に介護が必要で、自宅では介
護が困難な要介護者が入所して、食
事、入浴、排泄などの日常生活の介護
17

や健康管理が受けられます。
2)介護老人保健施設(老人保健施設) 病状が安定し、リハビリに重点を置い
たケアが必要な要介護者が入所して、
医学的管理のもとで、日常生活の介護
や、機能訓練が受けられます。
3)介護療養型医療施設(医療施設)長期療養を必要とする要介護者が入院
して、医療、看護、介護が受けられま
す。
出所・在宅介護サービスの種類 http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kaigo/g.html
2.介護保険の利用状況
厚生省は 1999年 12月の段階で、サービスを利用する要介護認定者を 270万人と予想したが、2001年 2月の厚生労働省の最新データでは認定者は 253万人であった。地域的
な偏差はあるものの、全体として当初予定されていた要介護認定者を大幅に下回ってい
るのが特徴である。その要因として、申請に至らないケースや利用をあきらめるケース
が出てきていることに注目しなければならない。
非該当(自立)として対象外になった申請者が平均 7~8%存在しており、それらのケ
ースは各自治体独自の政策でカバーされていることが多いが、通所介護、デイサービス
の利用者のなかには多くの非該当者がおり、彼らは従来どおりのサービスを受けられな
い。
一方、要介護度は、全国的にやや重い方向にシフトしていく傾向が見られる。その中で
実際の利用量は、スタート以前に比べて 2割増というのが各地域の状況で、これまでの
利用者を対象にサービス利用の増減を見てみると、介護保険を契機に増えたケースが 3割、減少したケースが1割、変わっていないケースが5割、その他1割という状況で、特に
サービスを減らした人が1割近く各地で出ているという点は、憂慮すべき点である。
2001年2月の厚生労働省のデータによる各介護度別利用率は、平均で4割、要介護
度1・2では3割台、3・4では4割台、最も重い5でも5割台、限度額の低い要支援が
6割台となっている。概ね限度額の3、4割の水準に利用がとどまっていることが大き
な特徴である。逆に、超過分は基本的に全額自己負担のためそれほど多くないが、限度額
を超えてサービスを利用するケースもでてきている。実際に限度額を超えて利用しなけ
れば介護に対応できない、あるいは家族では対応できないというのがその理由である。
低利用率の要因としては、家族で介護、利用料負担、サービスの不備、地域における基盤
整備の遅れなどが指摘されている。
在宅と施設の利用者比率は在宅7:施設3となっているものの、費用で見ると在宅3:
施設7である。重要なことは、在宅重視を謳ってきた介護保険が施行されたにもかかわ
18

らず、実際には施設へのシフトは大変強まってきていることである。どこの地域でも施
設への入所待機者が著しく増大している。
しかし、介護保険制度全体を見てみると、利用状況は当初予定していたよりも大幅に下
回っているのが現状である。その要因として、実施前から基盤整備のおくれや、保険料、
利用料負担の重さ、医療介護認定の問題などが言われてきた。特に 1割の利用料負担が重
いために必要なサービスが受けられない利用抑制が深刻に広がっている。要介護5なら、
35万8千円までサービスが受けられるのに、1割負担の重みから満額利用できない。
たとえば、30万円分の介護サービスを受けたら、3万円を自己負担しなくてはならな
い。この不景気のときに、家計から3万円を捻出するのは容易ではない。そこで、がん
ばっても2万円が限度ということで、訪問入浴看護や訪問看護など、単価の高いサービス
をやめ、20万円分のサービスしか受けず、ケアマネジャーに至っては必要なサービス
ではなくて、支払い能力に合わせたサービスメニューにせざるを得ない状況である。あ
とは結局家族が介護しているのが実態である。これでは、家族を介護地獄から解放する
という目的は達成できない。
介護保険の利用が伸びない理由の第二は、介護スタッフを家に上げるのに抵抗がある
というものである。他人に自分の家、とりわけ台所を覗かれたくないというのが、実感
だろう。介護となると、老人の部屋のみならず、台所、風呂場、便所など、すべてさら
け出されてしまう。また、大切なものを壊される、盗まれるといった心配をする家族も
いる。逆に、ヘルパーにとっても、変な嫌疑を掛けられるのも嫌なものである。
介護保険利用率が予想以下である第三の理由は、制度や手続きに不慣れというものであ
る。医療保険といえば、保険証があって、それを病院に持っていけば、すぐに診療が受
けられるというシステムに慣れた私たちにとって、介護保険は何ともなじみにくいもの
である。介護認定を受けなければならないこと自体が、利用を抑えているのだろう。介
護保険の仕組みをどれだけの国民が理解しているのだろうか。
3-4医療の国際比較
日本の医療や福祉は現在、ほかの国と比べて高齢化社会にふさわしい量と質を備えたも
のになっているのだろうか?他国の医療制度と比較してみる。
1.スウェーデンの社会制度
スウェーデンモデルとは、生産過程は資本主義的な競争原理、分配過程は社会主義的な
徹底した平等原則を基本としたモデルである。
スウェーデンモデル の特徴は、「 」 全国民を対象にした制度でありすべての市民に基本
的な安心感が保証され、その達成目的は、最低生活水準ではなく、平均生活水準である。
市民に保証される安心感は、ほとんどが税金によって財政運用されている。公的福祉を中
心とするスウェーデンモデルでは、実質税率61%という高負担状況がある。しかも、
19

25%の消費税が課せられる。
スウェーデンには日本とは比較できないほどの選択肢が高齢者に対して準備されてい
る。また、その全てが今まで住んできた地域に密着しているところがノーマライゼーシ
ョンを反映しているし、さらに、どのケア・サービスにおいても、高齢者の今まで通り
の生活をなるべく壊さないようにしているところが日本の施設との大きな違いである。
日本の施設では、その施設に入所者自身の生活をあわせなければならない場合がほとん
どだろう。高齢者にとって、生活のリズムの変化は、大きな環境の変化であり、新しい
環境への適応は困難なことである。
2.イギリス型
イギリスでは医療は、組織的にも財政的にも、圧倒的に政府に依存している。これが、
国民医療保険制度である。英国の国営医療は通常の治療費は歯科治療の一部負担を除いて
無料であり、絶対的な予算不足から運営が難しくなっている。医療予算不足から医師・看
護婦の不足→医師一人当たりの担当患者増大→医師・看護婦の疲弊による医療ミス、と悪
循環を招いている。
2000年の始めに、英国のブレア首相が、国家として医療にもっと支出しなければいけ
ないという英断を下した際に、「英国の医療に市場原理を導入してはどうか」と聞かれ
たブレア首相は。「英国では入院患者の3分の2が高齢者であるという現実があるのに、
市場原理を導入するほどばかげたことはない」とこれを否定したという。高齢者を市場
原理にさらすことがどれだけ恐ろしい結果を招くかを、鋭く認識していたからこその発
言である。
3.アメリカ型
アメリカの医療を支えるものは、第一に市場原理である。医療保険は、私的保障制度で
あり、70%が民間保険会社の医療保険である。患者は病気になったら保険会社に連絡し、
提携している医療機関を受診する事になる。医療費を支払う保険組合、保険会社などが医
療の内容の決定に関わり制限を設ける事により医療の無駄を省き、効率化、営利化を図る
と言うものであり、これはマネジドケアと呼ばれ、アメリカの医療制度の特徴である。
もしも、この市場原理を取り入れるとどうなるのかというのを見てみる。
a) 市場原理で医療の質がよくなり価格が下がるという幻想市場原理を医療に導入することで本当にサービスの質がよくなり,価格が下がるのか
ということを,市場原理医療の先進国,米国を例にとり検証しよう。
米国の営利病院と非営利病院を比較した研究は数多いが,営利(株式会社型)の病院経
営を進めようとしている人々の主張とは反対に,営利病院のほうがコストが高く,医療
の質も劣ったとする結果がほとんどである。 (1)腎透析患者の死亡率は営利医療施設のほ
20

うが高いだけでなく,営利施設の患者は腎移植の待機リストに載せられる率が低い (2)小児喘息で入院した患者を比較すると,営利病院のコストのほうが高い。 (3)メディケアの支出を地域ごとに比較すると,営利病院が経営する地域での支出が,非営利病院が経営す
る地域より高かったといった具合となる。
ただコストが高く,質も劣るだけでなく,営利病院のほうが医療事故に遭う率が高い
ことも報告されている。血液事業を民間の営利企業に委ねた場合に,「効率が悪く,高く
つき,危険」なものになるということは広く知られているが,エビデンスは,病院経営
を営利企業に委ねた場合も同様の結果になることを示しているのである
b) 利潤追求のために営利病院は何をするか
株式会社は,そもそも,出資者(株主)に配当を還元することを主目的とする組織であ
る。ただ,それだけでなく,株価をも維持しなければならないから,経営者は,常に,
高利益率を維持することが要求される。これらの要求を満たすために,株式会社運営の病
院がどのような経営戦略を採用するかということを,90年代中頃に全米一の巨大病院チ
ェーンに成長したコロンビアHCA社(現HCA社)の例で見てみよう。
同社は,低コストを実現するために採算が合わない部門・高賃金の人員(特に看護婦)
を切り捨てたうえで,患者には割高の請求をして利益をあげた。また,巨大な資金力に
物を言わせて,強引な手法で地域でのシェアを拡大したことでも知られている(同チェ
ーンはテキサス州エルパソ市の 2 病院から始まったが,創始者はこの 2 病院の経営を立
て直すために,競合する第 3の病院を買収してこれを閉鎖した)。さらに,同社も含め,
米国の巨大病院チェーンは,「組織的診療報酬不正請求」の前歴を有している企業がほと
んどで,利潤追求のためには違法行為もいとわない商法が世論の指弾を浴びたのである。
c) 医療に市場原理を導入することによる問題点
(1)弱者の排除
市場原理のもとでは,購買力の乏しい人々が医療へのアクセスから排除される。特に,
高齢者は有病率が高く,所得も低いので,市場原理のもとでは容易に排除される。米国政
府は,市場原理からこぼれ落ちた人々に医療保険を提供するために,国家による救済処置
として,メディケア(高齢者)・メディケイド(低所得者)という巨大公的医療保険を運
営している。
(2)負担の逆進性
有病者ほど保険料が高くなるなど,医療が必要な人ほど,医療へのアクセスが閉ざさ
れてしまう。また,企業を通じて保険に加入していれば,大口顧客として割引価格で医療
サービスを購入できるが,無保険者は定価で購入しなければならないなど,弱者ほど負
担が重くなる。
21

(3)バンパイア効果
地域に「サービスの質を落としてでも価格を下げてマージンを追求する」悪質な医療
企業が参入してシェアを獲得した場合,「サービスの質を追求する」良質な企業も,悪質
な企業の経営手法をまねないと生き残れなくなる。吸血鬼にかまれた者が皆吸血鬼にな
るということで,これをバンパイア効果という。
(4)市場原理のもとで価格が下がる保証はない
価格がどちらにふれるかは,売り手と買い手の力関係で決まり,実際,医療を市場原理
に委ねてきた米国では,70~80年代は毎年 10%を超える医療費上昇が続いた(90年代に入り,マネジドケアが興隆してから医療費の伸びにブレーキがかかるが,皮肉なこと
にマネジドケアは,ネットワーク内の医療施設に「統制経済」を強制することで,その
コストを抑制した)。また,米国は政府として薬剤価格を規制していないが,米国の製薬
業界が平均利益率 2割と市場原理の恩恵を享受する一方,米国民は世界一高い薬剤を購入
させられている。
(5)質が損なわれる危険
営利病院のほうが,質が悪く,事故の率も高いという報告が多いことは上述の通りで
ある。
ではなぜ,医療に市場原理を導入するとこうも不都合なことばかり起こるかというと
それは「医療は他の経済活動とは決定的に違う」からに他ならない。医療とは,「人の命
をかたに取ってお金をいただく」という「危ういなりわい」であるからこそ,テレビを
売ったり物を貸したりするのと同じ次元で考えてはならないのである。
他のサービス財については,「お金がないので,あるサービスの購入を諦める」とい
う選択しか消費者に許されないとしても何ら社会の問題とはならないが,医療の場にお
いて消費者にそのような選択しか許されないとすれば,それは成熟した社会として決し
て容認され得ることではない。
また,市場原理を導入して医師や医療機関に競争させることで,医療の質をよくすると
いう主張があるが,医療の質をよくするには,そのための直接の施策を施行し,そのた
めの制度を社会に用意することこそが政策の本筋であるべきであり,市場原理を導入す
ることで医療の質が自動的によくなるなどという主張は本末転倒の発想に基づくものと
言わなければならない
3-5 現在の医療の問題点
日本の医療における問題点は透明性の不足・信頼性の不足・効率性の不足が上げられる。
22

1.透明性の不足-医師の説明が不十分-
医師が自ら行った診療について十分な説明を行わず、患者に対して情報を提供しない、
ということが問題視されている。カルテの開示は法制化されておらず、医師にも治療方
針の決定権を患者にゆだねるなどの姿勢はなく、インフォームド・コンセントというこ
とは日常の診療場面に定着していない。このように情報開示が不十分であることにより
薬づけ、検査づけ等をはじめとする不本意な医療行為が行われ、その極みが悲惨な数多
くの医療事故である。さらに毎年、巨額の医療費不正請求事件が発生している。
これらの不正医療を見破る必要な施策としては、「患者の知る権利」の位置づけを明確
にし、求めがあれば原則としてカルテ、レセプトを開示することをルール化することが
必要である。また、虚像広告等不当表示の禁止を行い、違反に対する罰則を強化しつつ、
広告規制を原則撤廃するべきである。さらに、医療機関の評価項目に関してアウトカム評
価の実施などその充実を図るとともに、病院に対して外部の第三者による評価を受ける
こと及び評価結果の全面開示を義務付けるべきである。
2.信頼性の不足-医師・医療従事者の専門職としての質-
患者軽視としか思えない相次ぐ医療ミスが頻発している。厚生労働省によれば、大学病
院のような高度な医療技術を持つ全国 82カ所の特定機能病院が報告した医療事故件数は、
2000年 4月から今年 2月までの約 2年間で 1万 5003件に上る。その他の小さな医療機
関を含めれば、その数はずっと膨らむに違いない。
まず、医療機関に不信を抱いたことがあるかどうかを尋ねたところ、「ある」と答え
た人が 8割超と圧倒的多数を占めた(82.4%)。医療への信頼が揺らいでいる事実を如
実に物 語る結果となった。その理由では、「治療内容に関する説明が不十分」
(62.5%)というのが最も多く、「医師や看護婦の対応が不親切」(40.3%)という回答が続いた。医療機関の対応のまずさが、患者の不信を招いていると言えるだろう。
その一方で、「治療によって病状がいっそう悪化した」という医療事故を連想させる
ような経験を理由に挙げた人も 1割を超えた(14.2%)。この数字を多いと見るか少ないと見るかは判断が分かれるところだ。しかし、病気を治すという医療の本来の務めか
らすれば、やはり問題視すべきだろう。
治療を受けた際に、医療ミスではないかと思ったことがあるかどうかを尋ねたところ、
「思ったことがある」と答えた人が 4割を占めた(41.7%)。患者が医師の治療に全幅
の信頼を置くといった状態にはほど遠い結果だ。医療機関は、患者の不信を払拭するため
に、十分な説明責任を果たす必要がある。 (アンケート統計の出所 http://nb.nikkeibp.co.jp」)
3.効率性の不足
a) 長い待ち時間と短い診療
「3時間待って3分診療」に代表されるように、日本での待ち時間が長いことは事であ
23

り、問題視されるのも無理はないのだが、その理由はいたって単純である。それは、患
者が質の高いと思う医療機関を自由に訪れることができるからで、実際長い待ち時間は
一般に大病院に限られたことであり、開業医の診療所や、中小病院での待ち時間はずっと
短い。待ち時間を短くする方法として予約制があるが、予約制にすれば1日でみられる
患者の数は制限されてくるため、人気の高い医療機関や医師の場合には何ヶ月も先でない
と予約が取れない、という欧米のようになる。このように、訪れる患者に制限を設けな
い日本の現状で、診療時間が短くなってしまうのは当然のことなのである。
b) 施設面でも人の面でも見劣りする病院
表3-4を見てみると日本の病院の医療提供体制は、病院については、諸外国に比べ人
口あたりの病床数は多いが、全体としてみれば、病床あたりの医療従事者が少なく、平均
在院日数が長い現状にあることがわかる。また、機能分化が進んでいないことから、専
門的な治療について、個々の機関における技術集積が進みにくい現状にある。というも
のの、日本の病院をよくしたいと思うならば、もっとお金をかける必要があることだけ
は確かである。日本の3倍の看護職員数を病床に配置している英国が、「国民に十分な医
療を提供できなかった」と反省し、 看護婦数を増やす ことを大きな目標の1つとして「 」予算を増額している。それと対照的に、日本では「医療費は何がなんでも抑制しなけれ
ばならない」と、医療の質の問題を真剣に改善しようとするどころか、逆に、質のさら
なる悪化を招きかねない施策が点し進められようとしている。日本では,研修医に対し
て最低賃金にも満たない給与しか支払わず,その上,労働基準法に違反する過酷な労働を
強いることが常態化している。2004年に遅まきながら「臨床研修の義務化」を開始する
ことは決まっているが,いまだにその財源をどうするかについての明確な方針は示され
ていない。「医療費を抑制しなければならない」という大合唱が続く中,本当に研修の
義務化を支えるに十分な財源が用意されるのか,不安を抱いている。
医療の質をよくすることに金を使うことを惜しんできたもう 1つの好例が,先進国の
中でも極端に低い「看護職員数」である。厚生労働省発表の数字によると,病床 100 床
当たりの看護職員数は,日本は米国の 5分の 1,英国の 3分の 1にしか過ぎない。日本の
3 倍の看護職員を病床に配置している英国が,「国民に十分な医療を提供できなかった」
と反省し,「看護婦数を増やす」ことを大きな目標の 1つとしての予算を増額している
のと対照的に,日本では「医療費は何がなんでも抑制しなければならない」と,医療の
質の問題を真剣に改善しようとするどころか,逆に,質のさらなる悪化を招きかねない
施策が推し進められようとしている。
表3-4 医療提供体制の各国比較(1998年)国名 人口千人あたり 病床百床当たり 病床百当たりの 平均在院日数
24

の医師数 の医師数 看護職員数
日本 13.1 12.5 43.5 31.8ドイツ 9.3 37.6 99.8 12.0フランス 8.5 35.2 69.7(1997) 10.8(1997)イギリス 4.2 40.7 120 9.8(1996)アメリカ 3.7 71.6 221 7.5(1996)
出 所 「 http://www.mhlw.go.jp/houdou/0109/h0925-
2b.html#sanko1」
・医療費は何がなんでも抑制しなければならないのか?
政府与党は,医療保険制度を維持するためには,医療費は抑制されなければならない
「医療費抑制」を掲げている。しかし,日本の医療費は本当に抑制されなければならな
いほど過剰なものなのだろうか?
先進諸国における医療費支出を日本のそれとを比較してみよう。表3-5の各国におけ
る医療費支出は,医療費支出を対 GDP比で示したが,先進諸国における「国民の命と健康の値段」として,この表を読むことにする。
まず注意すべきところは、GDPの総額が大きい国ほどGDPに対する医療費の割合も大きいという傾向があることである(米国,ドイツ,フランスなど)。つまり,「豊か
な」国ほど,医療に惜しみなく金をかけ,国民の命と健康に高い値段をつけているのが
世界の傾向なのである。先進国の中で,この傾向からはずれ,国民の命と健康の値段を値
切っている国はわずかに 2か国,日本と英国だけである。最下位でなくてよかったと思うが、最下位の座は数年後には、日本のものとなることが約束されている。
2000年の初めに、ブレア首相がこれからは、GDPの 10%まで医療にかかる金を増やすと言明した。なぜ,英国がこのような医療政策の大転換をしたかというと,医療費
を抑制しすぎたがために,アクセスに障害が生じるようになったことが大きな社会問題
となったからである。例えば,「癌と診断されたのに,手術を受けるために何か月も待
たされ,手術を受けた時には転移が進んでいた」というような悲劇的事例が続出したか
らである。
表3-5 先進諸国におけるGDPと医療費支出(1998年、対GDP, OECD調べ)
国GDP(単位:億ド
ル)医療費支出(%GDP)
米国 98,729 13.0ドイツ 17,724 10.6スイス 2,166 10.4
25

フランス 13,311 9.6ノルウェー 1,623 8.9オーストラリア 3,514 8.5イタリア 14,136 8.4
スウェーデン 2,280 8.4日本 39,891 7.6英国 14,156 6.7
出 所 http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2469dir/
n2469_03.htm
・2つまでしか選べない「コスト」「アクセス」「質」
米国オレゴン州の低所得者用医療保険「オレゴン・ヘルス・プラン」の管理部局には,
「Cost, access, quality. Pick any two(コストとアクセスと医療の質。このうち,2つまでなら選んでもよい)」という言葉が額に入れて飾られているが,この言葉ほど医
療保険政策のエッセンスを的確に言い当てた言葉はないだろう。
「コストを抑制してアクセスも保証して質もよくする,3つとも同時に達成することなど夢物語だ」と,言っているのであるが,英国の場合はコストを抑制しすぎたがために,
手術待ちが著しく長くなるなどアクセスが障害されたのである。このオレゴン・ヘル
ス・プランの「2つだけルール」を日本の医療に当てはめたらどうなるだろうか。
日本は世界一医療費の抑制に成功してきたのであるが,それと同時に,これまでは,
「国民皆保険制」を維持しアクセスも保証してきた。コストを抑制し,アクセスを保証
してきた日本の医療が,残りの 1つ,「医療の質」を犠牲にしてきたのは,「2つだけルール」からも明らかなのである。
オレゴン・ヘルス・プラン
オレゴン州が運営する低所得者用の公的医療保険。疾患と医療行為の組み合わせに優先
順位をつけ,優先順位が高いものには保険給付を認めるが,低いものには給付を認めな
い制度。必要度の低い医療サービスについてはアクセスを保証しないことを眼目として
いる。
・日本医療における質の問題
日本の医療の最大の問題は,政府与党が一番気にしているコストにあるのではなく,
その「質」にある。それが表面化したものが頻発する医療事故である。
なぜ質が低下したかと言うと、社会的に医療の質を保証する制度を作ってこなかった
ことに加え,医療の質を高めるための社会資源の投入を惜しんできたことに原因がある
医療の質をよくすることに金を使うことを惜しんできた格好の例が,「医師の卒後研
26

修を保証する財政基盤を社会に用意してこなかった」ことである。その結果,ろくな研
修も受けていない未熟な医師を「一人前」として医療の最前線に立たせることを繰り返
し,多くの患者に犠牲を強いてきた。日本では,研修医に対して最低賃金にも満たない給
与しか支払わず,その上,労働基準法に違反する過酷な労働を強いることが常態化してい
る。2004年に遅まきながら「臨床研修の義務化」を開始することは決まっているが,い
まだにその財源をどうするかについての明確な方針は示されていない。「医療費を抑制
しなければならない」という大合唱が続く中,本当に研修の義務化を支えるに十分な財
源が用意されるのか,不安を抱かざるを得ない。
米国では,メディケア(税金で運営する高齢者医療保険)を通じて,連邦政府が研修医
1人当たり年 10万ドルという巨額のコストを支出しているが,医療の質を保証するためには,質のよい医師を作り出すことこそが肝要との認識があるからこそ,国家として積
極的に莫大な資金を投入し続けてきたのである。
社会的入院
社会的入院とは、高齢者が病気らしい病気はない(あったとしても、服薬程度で済むも
の)のに、ずっと病院に入院して生活していくことである。
原因としては、家族関係の希薄さや住宅問題にある。まず、実の親であっても同居して
面倒を見ることは少なくなった。また、病気ではなくても、食事とかに手をかける必要
性があり、そこまでは手が回らないこともある。
住宅で過ごしているうちは良いが、何かの病気で一端入院となると、上記の問題がク
ローズアップされ、退院が難しくなってそのまま病院で暮らすことになってしまうので
ある。
この社会的入院が老人医療費を増大させる一因となってきた。そこで、社会的入院を減
らす方法として、入院が長期化すると、病院が請求できる医療費を減らす方策がとられ
ることになった。
この方法は、確かに1ヶ月や3ヶ月で退院させる方法へと病院を導いた。しかし、退院
しても帰る場所がないため、どこか別の病院へ移るだけになってしまい、タライ回しと
呼ばれることになった。
入院期間の短期化が医療費削減には結果的に結びつかず、在宅で介護が出来る、または
施設を増やす、といった介護保険の考え方に進んでいった。しかし、作っても作っても
老人ホームは全然足りず、いまだに病院暮らしの人は多い。在宅の方向へ進ませるとい
っても、福祉政策と住宅政策はなかなか噛み合わない。
4.これからの医療現在、政府が行っている改革は 2-2で述べたとおり基本的には当面の財政収支の修復
に終始しているに過ぎず、根本的な解決にはなっていない。これでは少子高齢化が進む
につれ、医療費は増加を続け将来各種社会保険制度の運営が厳しくなっていくのは確実で
あり、近い将来には国家財政が危機に落ち入りシステム自体が崩壊するのは目に見えて
27

いる。
医療制度の抜本改革の必要が言われるようになって久しいが,政府・与党社会保障改革協
議会が 2001年 11月末に策定した『医療制度改革大綱』は,「抜本的」という言葉からはほど遠いだけでなく,「改革」の名にもまったく値しない内容のものとなった。
現在の医療保険財政の危機が長年の失政の結果生じたものであることに対する反省もない
まま,患者の自己負担増と診療報酬の切り下げという当座の「銭勘定」のやりくりでその
帳尻を合わせようとしているに過ぎない噴飯ものの内容となっているからだ。
何が問題なのかというと、政府与党の改革大綱には,どのようにしたら日本の医療をよ
くすることができるのかという理念が完璧に欠如しているからである。
破綻して当然の制度を姑息な手段でしのぐという失政
そもそも,なぜ現在の医療保険財政破綻の危機が招来しているかと言えば,「老健拠出
金制度」という,いずれ破綻することがわかり切っていた制度に闇雲にしがみつき続け
てきたからであることは論を待たない。
日本が世界に類を見ない「少子高齢社会」となり,高齢者の医療に対する「必要」
(「需要」ではない)が増え続けることがわかり切っていたのに,この増え続けるはず
の高齢者の医療費を,被用者保険や国民健康保険から流用して賄うことを続けてきたので
あるから,財政が破綻する健康保険組合が続出したとしても何の不思議もない。不思議な
のは,誰が見ても「もつはずがない」とわかり切っていた「老健拠出金制度」をそのま
まにして,患者自己負担増という姑息な手段でしのぐという失政を繰り返してきたこと
であり,政府・与党が昨(2001)年 11月末にまとめた「医療制度改革大綱」でも,懲りもせずに同じ手段をとり続ける愚を重ねようとしていることである。
※ 老健拠出金制度とは、医療機関の窓口での患者の一部負担を除いた原則70歳以上の
老人医療費を、税金(約30%)と、組合保険、政管健保、国保などからの拠出金
(約 70%)でまかなう制度である。これを老人保健拠出金(老健拠出金)と呼ぶ。
※ 医療制度改革大綱とは、 ①老人保健制度の対象年齢を 70歳から段階的に 75歳に引き上げ、②患者一部負担割合について、被用者本人負担を 3割、70歳から 74歳を 2割、75歳以上を定率 1割(高所得者は 2割)に引き上げ、③老人医療費の伸び率管理制度の導入―というものであった。この伸び率管理制度というのは、医療費の伸びを年率 4%程
度に設定し、それを上回った場合、2年後の診療報酬単価を下げるというものであった。
このような状況を脱するにはシステムそのものの改善も必要ではあるが、まずは、根
本的な部分の改革、つまり医療制度というシステムにとらわれないもっと幅広い視点で
の改革が必要となってくる。
28

4-1問題点の修正
社会的入院の解消
2000年4月から始まった介護保険は社会的入院の解消も大きな柱に掲げたが、医療
保険からの以降は目標の6割程度にとどまった。
それは、医療保険での診療報酬の問題もあったが、在宅介護や特別養護老人ホームなど
の施設介護での「受け皿」がなかったせいもある。退院したくてもできないのである。
厚生労働省の調べによると受け入れ条件が整えば退院可能な人は約5万人いる。実態は
それより相当多いだろう。それを医療保険でカバーする場合、少なくとも入院基本料だ
けで1日1万円以上かかるので、年間1800億円以上かかることになる。切羽詰る医療
保険財政からみても社会的入院の解消は避けて通れない。
厚生労働省は、介護保険で認めている特別養護老人ホームや介護老人保健施設、介護保
険適用の療養型病床群の整備を進めているが、地域によって特別養護老人ホームなどは、
入居待機者があふれているので、施設の建設だけでは、なかなか追いつかない。しかも、
介護保険対応の療養型病床群はどうしても長期入院となりがちである。3ヶ月から半年程
度の入所が原則の介護老人保健施設でさえ、2年以上の長期者が増えている。
これでは、負担する財布が医療保険から介護保険に変わるだけ、ということになりか
ねない。
そこで、ケアハウスや痴呆高齢者向けのグループホームの整備を急ぎたい。自立支援
のケアもでき、建設費も比較的安くすむ。
このように、多様な「受け皿」ができてこそ社会的入院の解消を果たせる。
4-2総合的な改革
1.男女の役割分業の見直しと育児をめぐる国民意識
家庭内においては、男女の固定的な役割分担を見直し、男性が家庭により労力を傾け、
夫婦が協力して家事を含めた家庭の仕事を、父母が協力して子育てを、担うことが望まれ
る。家事・育児への共同参画を進めるためには、夫婦双方が家事や子育てに関して一定の
知識や体験を持っていることが望ましい。
また、幼い子どもに触れ合ったことがないために子育ての負担を実際以上に過重と想
像しているならば、それは、人生の選択の幅を狭める結果をもたらす。
したがって、小中高生の時期やはじめての子どもができた時期における教育・啓発や
体験が重要である。
29

1、家事・育児に関する若い世代への教育
① 親しい人と生活しながら子を産み育てていくことは、人間が生きていく上の基
本的な営みである。その大切さ・楽しさを、次代を担う若い世代が、家庭をはじ
めとする様々な場で実感できることが必要である。なお、成人式をそのための機
会として活用するべきだ。
② 小・中・高校生が保育所・幼稚園で子どもと触れ合う機会を設け、学校の空き
スペースを利用して保育所を学校に併設し、その場で児童・生徒によるボランテ
ィア活動を実施する、といった若い世代が子どもと触れ合う機会を設ける試みを
してはどうか。この場合、高校では保育体験を単位認定できる制度となっている
のでそれを活用し、保育体験を関連する資格取得に結びつけていくべきだ。
③ 若い世代が保育について学び親しむ機会を充実するため、高校生・大学生など
が必要な研修を受けるなどして、働く体験やボランティア体験の一つとしてベビ
ーシッターを行えるような仕組みを考えてみる。
男性の育児・家事参加の推進
男性の育児・家事参加を進めるためには、子育てを男女の問題としてとらえ、男性に
対して子育てや家事の喜びや楽しさを実感できるような環境整備を行うことが必要で
ある。 具体的方策としては、様々なメディアを利用して男性の意識変革を促すととも
に、男性に対する産休や育児休業の取得の義務づけ、男性の意識に関する調査・研究
の実施などが考えられる。 また、現在、妊婦に対しては母子健康手帳が配布されてい
るが、これに対応するような「父子手帳」を配布するとか、母子健康手帳を妊婦手帳
と子育て手帳に分け、後者については夫婦で利用できるような内容にする、といった
工夫を行ってみる。
3、社会全体としての子育て意識
子育ては、次の世代を育てる社会の基本的な営みであり、その社会的責任とともに素晴
しさ・楽しさを改めて社会全体に訴えていくことが必要である。また、今後は環境汚染
や人心の荒廃が進んで世の中は悪くなる一方だというような将来に対する悲観論を強調
する風潮も少子化の一因と言われており、これも改められるべきである。子どもは社会
全体の財産であって、子育ては社会全体で共に担うという国民的合意の確立が必要ではあ
る。例えば、親の職場に子どもを連れていく日を設けるといった取組みによって、子ど
もの存在や家族のきずなの大切さに対する社会の認識が深まるのではないか。少子化が
このまま進んだ場合に将来に及ぼす影響は深刻であり、少子化への対応に取り組む必要性
が高いことについて、政策決定者に対して十分な理解を促すとともに、国・地方のいず
30

れにおいても少子化対策への重点的な配分が行われるよう働き掛けていく必要があるの
ではないか。「少子化問題対策本部(仮称)」を内閣の下に設け、総合的な取組みを進め
ることも検討されるべきである。
2.結婚をめぐる状況への対応
独身の理由として、 適当な相手にめぐり会わない ことを掲げる人が独身者のほぼ半「 」数に上っている。仕事や休暇などに関して多様な選択が可能となっている中、結婚後の生
活スタイルや役割分担において男女が相手に求めるものが食い違っている、と考えられ
る。また、結婚することによって自由や気楽さを失いたくないと考える独身者は女性の
方に多いが、これは、子育てを含む結婚後の生活についての負担が女性に偏りがちと感
じていることの裏返しと思われる。
結婚をめぐるこのような状況に関しては、夫婦双方の仕事と家庭の時間配分や夫婦の子
育ての協力体制など結婚後の生活における男女の役割の見直しを、男女共同参画の視点か
ら進めるこが重要である。
3.地域全体での子育て支援とまちづくり
子育てについて、かつては近隣の人や祖父母の果たす役割は大きかった。現状では、
近隣の役割は相当低下しているし、祖父母の役割も次第に低下してきている。したがっ
て、今後、地域の持つ子育ての力を引き出すような工夫が必要となっている。
また、 住 はやすらぎの場であるとともに家族や知人が触れ合う生活の場であり、「 」街 は多様な人々が交流する場であるはずであるが、高度成長期からの住や街のつくり「 」方は、結局、閉じた空間としての 住 と、遠距離通勤を伴うような 街 を産み出して来た「 」 「 」 。
その転換が図られ始めているが、街づくりにおいては、ハード面でもソフト面でも、多
世代の交流ができ、子どもや子育て世代への配慮も行われることを基本とすべきである。
地域での子育て支援・子育て中の親支援
① 地域で現在行われている親同士の子育てサークルは、子育てに伴う孤立感・不安
感の解消や母親の社会参加の場づくりという点で大きな役割を果たしており、活
動場所を提供するなどにより、その自主性を損なわずに、こうした活動が一層普
及するよう支援していくべきである。
② 子どもが成長して子育てサークルを卒業した母親がその経験を生かして、地域の
子育て支援の担い手として活躍できる仕組みが必要である。
31

③ 地域での子育て支援に関しては、様々な活動を行っているNPOの取組みを生か
すような支援、特に、NPO同士が互いに知り合って情報交換できるような連携
の支援に重点を置く必要がある。
④ 父親が仕事で培った多様な経験を地域の活動に活かせるよう、職場では働き方の
改革を進め、地域では、保育所、幼稚園、PTA、放課後児童クラブなどへの父
親の積極的な参加を可能とするような環境整備が必要である。
⑤ また、子どもの成長に応じて変化する子育ての悩みに対応して乳幼児健診(3か月、1歳6か月、3歳)の際に、子育てに関する学級をそれぞれ開催し、育児不安への
対し方や育児不安に関する相談支援機関に関する情報提供を充実する、といった
ことも必要である。
⑥ 女性センターや公民館などの活動を見直し、子育てのために就業を中断した母親
の起業や再就職を支援する活動内容を充実すべきである。
⑦ 子育て環境の悪化を解消していくためには、地域に誇りの持てる教育が必要であ
る。このため、社会教育の場などで大人や子どもの地域活動を拡充していくこと
が必要であり、その拠点となる関連施設の充実が大切である。
⑧ 仕事に限らず母親の趣味や気晴らしのためにも安心して気軽に利用できるベビー
シッターなどの保育サービスの普及を図ることが必要で、その際、子育ての経験
を持つ女性や高齢者など、子育て支援に意欲と関心のある層を活用する。
⑨ 出産後の母体の回復期に、身の回りの世話や新生児の面倒を見てくれる産褥ヘル
パーの派遣について、支援を行うことが必要である。
⑩ 子育て支援のためには、地域の小児科のネットワークづくりが大切である。
まちづくり
① 地域全体での子育て支援を進めるには、連帯感のある地域社会の形成が必要であ
り、そのためには、職住をできるだけ近接させた生活圏にあったまちづくりが必
要である。
② 安心してベビーカーで外出できるようなまちづくり、妊婦・子ども連れ優先車両
のある電車、おむつ替えのスペースのある公共施設など、安心して子ども連れで
外出できるような配慮の行き届いた子育てに優しいまちづくりを進める必要があ
るのではないか。例えば、おむつ替えのためのスペースを男性トイレにも設け、
バスもベビーカーのまま乗り降りできるようなきめ細かい配慮が必要である。 ま
た、そうするとともに、子連れの外出について、公共の場でどのような行動がふ
さわしいのかを社会全体で議論し、乳幼児連れの親が過度に負担感を持たなくて
済むよう、共通のルールづくりをしていくことが必要である。
32

4.保育等子育てサービスの在り方
保育所は、共働き世帯などの子育てにとって欠かせない拠り所となっている。である
からこそ、都市部に見られる待機の解消は急を要する課題であるし、また、より利用し
やすいものとなることも望まれる。さらに、多様な生活スタイルに対応した様々な保育
サービスが提供されるようになることが望まれる。保育は、子育て期において多くの人
が利用する身近なサービスであるから、地域で、情報が公開され、十分議論が行われ、そ
して需要に対応できる良質なサービスが効率的に提供されるべきである。
また、保育サービスが一層弾力化する中においては、偏に 親の都合 ばかりが優先さ「 」れて保育の質がおろそかにならぬよう、子どもの立場に立って保育の質を確保していく
ための体制の強化が望まれる。
地域における情報公開と整備の計画的実施
① 保育所や、小中学校の状況についても、その経費や費用負担、利用や待機の状況
などに関し、自治体が住民に対して情報公開を行うことが必要である。なお、情
報公開・提供に当たっては、インターネットの活用も含めて誰もがいつでも利用
できるものにする必要がある。このことは、保育所などに限らずすべての情報公
開・提供に共通することである。また、情報提供に際しては、NPOの活動を通
じて築かれた幅広いネットワークを活用するとともに、提供された情報について
NPOがチェックを行うことも重要である。
② 保育所をはじめとする子育て支援サービスの利用手続をより利用しやすいものに
改善していくことが必要である。また、母子健康手帳に保育所の利用手続の仕組
みを掲載するとともに、いつでも、円滑に子育て支援全般に係る相談や情報提供
を受けられるような仕組みを設けるべきである。
待機の解消やサービスの弾力化等への取組みの支援
① 保育サービスの整備は緊急の課題であることから、保育所に対する国の支援の強
化を図る必要がある。
② 都市部での認可保育所における乳児等の低年齢児保育の拡大や延長保育の実施が
必要である。 特に、低年齢児の待機が深刻となっていることから、年齢別定員や
年齢に応じた認可保育所の諸基準の見直しが必要である。
③ 乳児保育、延長保育、病児保育、夜間保育、休日保育など様々な施策の拡充を進
めることが必要である。
④ 保育サービスの整備に際しては、認可保育所を中心とした機能強化を図るべきで
あり、農村・過疎地域はその立地条件から公立保育所で親子を含めた地域共同体
33

の基礎と位置づけるなど、地域ニーズに応じた公営、民間の役割を考えるべきで
ある。
⑤ 公営保育所は、年功序列制、長期雇用の正規職員中心という公務員の雇用制度に
より、利用しやすい弾力的なサービス提供や効率的な運営が困難になっているの
で、公営保育所の業務の全部・一部の委託を含めて民間の認可保育所を活用する
ことによって、認可保育所全体のサービスの向上と効率化を図るべきで、委託に
際し、サービス水準が向上するよう、認可保育所への適正な指導、予算が必要で
ある。
⑥ 保育サービスについては自治体によって大きな格差があることから、市町村格差
の是正が必要である。
⑦ 延長保育や病児保育の受け皿作りの一環として、認可保育所を中心とした地域の
保育者のネットワークづくりが必要である。
5.学歴偏重社会の見直し
学歴偏重の風潮は、子どもにも親にもゆとりを失わせるとともに親の経済的負担を重
くするなどの問題があり、親が産む子どもの数を少なくする方向に働くと考えられる。
学歴偏重の風潮には依然として根強いものがある。教育行政における改革の方向を一層強
めるべきである。
① 学歴偏重社会の原因の一つは、日本の職場における人事制度であり、終身雇用制等の
職場場風土の見直しが必要である。しかし、学歴偏重社会の主な原因を職場の人事制
度にあると特定することは無理である。家庭が多様な価値観を持つことが、学歴偏重
の是正のためにも有効である。このためには、妻も社会で働くことがよいのではな
いか。
② 知育に偏った教育が、人同士の交流の楽しさと難しさを知ったり交流の方法を学ぶ機
会を少なくさせており、これが結婚や子育てという新たな人間関係を築くのを煩わ
しく感じさせているのではないか。したがって、様々な場で様々な世代の人と共に
学び体験し作業していくという機会を増やす必要がある。
③ 子どもが、家事や家族とのコミュニケーションなど家庭生活の在り方を学べるよう、
学校への泊まり込み体験や、地方自治体間の協力による山村留学制度、様々な経験を
持つ外部の社会人による授業などの実施を進める。。
④ 教える側の教員に対しても、年齢や職業経験等多様な人材の登用の推進、自己啓発の
ための研修休業制度の創設とともに、一学級の定員数削減と複数の教師の配置等、教
育への財源投入の拡充が必要である。
34

⑤ 教育費とりわけその大部分を占める大学での教育費負担は重いものとなっており、
それを軽減するため、奨学金を抜本的に拡充するべきではないか。また、大学進学者
に奨学金を貸し付けるだけでなく、進学せずに技能習得等を選択した者に対しても、
技能習得等のための資金を貸し付けることを考えて良いのではないか。
⑥ 学歴偏重社会の原因の一つは、日本の職場における人事制度であり、終身雇用制等の
職場場風土の見直しが必要である。しかし、学歴偏重社会の主な原因を職場の人事制
度にあると特定することは無理である。家庭が多様な価値観を持つことが、学歴偏重
の是正のためにも有効である。このためには、妻も社会で働くことがよいのではな
いか。
⑦ 知育に偏った教育が、人同士の交流の楽しさと難しさを知ったり交流の方法を学ぶ機
会を少なくさせており、これが結婚や子育てという新たな人間関係を築くのを煩わ
しく感じさせているのではないか。したがって、様々な場で様々な世代の人と共に
学び体験し作業していくという機会を増やす必要がある。
⑧ 子どもが、家事や家族とのコミュニケーションなど家庭生活の在り方を学べるよう、
学校への泊まり込み体験や、地方自治体間の協力による山村留学制度、様々な経験を
持つ外部の社会人による授業などの実施を進める。。
⑨ 教える側の教員に対しても、年齢や職業経験等多様な人材の登用の推進、自己啓発の
ための研修休業制度の創設とともに、一学級の定員数削減と複数の教師の配置等、教
育への財源投入の拡充が必要である。
(10)教育費とりわけその大部分を占める大学での教育費負担は重いものとなってお
り、それを軽減するため、奨学金を抜本的に拡充するべきではないか。また、大
学進学者に奨学金を貸し付けるだけでなく、進学せずに技能習得等を選択した者に
対しても、技能習得等のための資金を貸し付けることを考えて良いのではないか。
6.子育てのための経済的負担の軽減
夫婦が理想の子どもの数までは産まない理由として、子育てや子どもの教育に費用が
掛かることをあげる人が多い。これは、特定扶養親族に係る扶養控除額の割増措置、幼稚
園奨励費補助などの様々な施策が十分機能していないという面があるからである。
① 妊娠期から産後の健康診査等の全額公費負担、出産育児一時金の引上げなど出産まで
の経済負担を軽減するとともに、乳幼児医療費の無料化を段階的に図るべきである。
② 育児休業期間中の給付金の割合を引上げるべきではある。このことは、男性が育児休
業を取得しやすくするものともなる。
③ 低所得者対策については別として、基本的には同じサービスを受けているのだから、
保育料負担の均一化を図るべきである。
35

④ 生涯にわたる課税負担において、子どもを育てる家庭が子どもを持たない家庭に比
べて不利にならないようにした上で、前者に対する公的支援を手厚く付与すること
が必要である。
⑤ 二人目の子どもを持つことを躊躇する人が増えていることから、二人目の子どもに
係る税制優遇措置を拡充すべきである。
7、奨学金制度
国が、小・中・高等学校などにおいて経済的に苦しい生徒を援助する奨学金制度は、現
在でもいくつかあるが、これらをさらに充実させていくことにより、最低限必要な教育
を受けさせることができる。これにより、所得の少ない親でも安心して子供を産み育て
ていくことができる。
8、子供の数だけ税金を軽減
人口の減少を防ごうとすれば、一組の夫婦から最低二人は子供が生まれないといけな
いことになる。これより子供が二人としての家庭を平均と考え、子供がいない、もしく
は一人の家庭からは税を徴収し、子供の数が二人以上の家庭に、より充実した公的保障を
与えると、出生率は増加すると考えられる。
そのほかの改革として次のようなものがあげられる。
1.市場原理の導入
競争原理を導入する場合、医療提供側にはどのような競争がもたらされるのだろうか?
① 診療行為(成果)
② 診療スピード
③ 診療コスト
④ 療養環境
⑤ その他サービス
この中で医療保険として評価できるのは①~③までで④と⑤はどちらかといえば付加
価値として評価される項目となる。
また、受益者である患者側にもある意味の競争原理の導入が必要となってくる。この
ある意味とは健康の維持や健康の増進に対するインセンティブを付加するということで、
例えば医療保険にも自動車保険によくある等級制度を導入することによって健康維持に努
力する人の保険料が割り引かれるのであれば、生活習慣病の発生率もある程度下がるの
ではないだろうか。しかし、この原理を導入すると・当然の結果として、発病する確立
の高い人々(有病者、既往症のある人、高齢者等)は保健加入できなくなるか、加入して
も発病の可能性を反映した高い保険料を支払わなければならない。これを解決するには、
36

これらのハイリスク者に対して国が最低ラインを設定し、これを保険会社に義務付ける
ことである程度解決すると考える。
2.市場原理を導入することで起きる問題
①患者自身が必要なサービスを事前に十分判断・選択することが困難である。
②収益性の高い部分に集中し、コストのかかる患者が敬遠される恐れがある。
③救急医療や僻地医療等の不採算部門が切り捨てられる恐れがある。
などがあげられる。
解決案として、①については情報の開示・第三者機関の格付け等で解決できる。②と③
については、国が新しく国営の病院を作り民間で足りない部分を国が補う、ということ
で解決できないだろうか。
3.導入についての条件
①事業を病院経営及び、その周辺事業に特化した企業とする。
②利潤の用途の制限についての適切な努力義務を課すほか、配当について適正な制限を
設ける。
③経営状況・財務状況に関する情報公開を義務付ける。
などの一定の条件を検討する。
2.IT化
医療システムに電子カルテなどを媒体とした、IT化を導入することによって以下のよ
うな効果を生み出すと考えられる。
1.業務の効率化
医事会計/病歴管理/看護支援/検査等の伝票、依頼・報告の業務等の一連の流れを自
動化することが可能となり、業務処理時間の大幅な短縮を図ることができる。
また、ネットワークを利用した画像参照が可能となり、フィルム探しや運搬等にかか
る多くの人件費や保管場所を削減することがでる。
2.情報の共有
空きベッド状況、入院患者の一覧等を院内のどこからでも閲覧・操作することや、患者
の検査データや診療記録等を必要な時に引き出したり、情報の共有化を図ることができ
る。
3.患者へのサービス向上
過去の病歴、検査データ、各診療科目毎に行った診療内容や、投薬情報等の患者データ
を一つのデータベースに集約し、それを参照することで、患者への的確な診察・治療
37

を行うことができる。さらにネットワークを地域病院や診療所へ接続することで診療
データの共有や統合を実現することが可能である。それが患者の医師/病院への信頼度
を高める結果にも繋げることができます。
4.院内外コミュニケーションの活性化
院内外とのメールのやりとりは、コミュニケーションを活性化するのに役立つ。院内
LAN においては、他のセクションの職員とのやりとりや 1度に複数の人間に発信する、不在者への連絡が容易等の効果がある。
5.情報の入手
外部との学術情報のやり取り、遠隔地との情報交換、インターネット上の学術誌の検
索・参照や、電子メールを利用することで取引先や関連病院等の外部との情報交換(業
界情報・臨床データ等)も容易になる等の種々のメリットがある。
6.情報の発信
webサイトを運用することで外部に対し病院の診療時間に関する案内やオーダーエン
トリーシステム(予約システム/処方オーダーシステム)等、情報の発信をすること
ができる。
このように、医療システムのIT化は、医療の質を高め、「見える医療」にもつながる
のである。
3.病院の分業
病院における混雑によって○時間待って、○分間診療といった非効率的(適切でない処
置)な診療が行われるケースが多々ある。そのような診療は望まれるべきものではなく
改善が必要とされる懸案であるといえる。では、どうすれば混雑を解消し効率的な診療
を行うことが出来るのか。混雑の解消のためには、患者の大病院への一極集中を是正しな
ければならない。大病院の受付で大勢の患者が並んでいる光景をよく見かけるが、全て
の患者が大病院の設備、専門技術に合った重病で順番を待っているわけでなく、軽い病気
で並んでいるのが大半であろう。しかし、それではせっかくの設備、技術を欲する患者
に対して適切な医療サービスを提供することが出来ないのではないだろうか。そこで病
状による病院の選択というシステムを提案したい。病状別にすることにより、軽い病気
はそれに合った病院で治療を済ませ、またそこで異常があった場合には、病状別に A 病
院、B 病院というように患者を振り分け、それぞれで治療を受けさせるようにすること
ができる。このことによって、患者ごとに(病状別に)住み分けができ、優先的に必要
な設備、技術を利用することができ、効率的(適切な処置)な治療が受けられるようにな
るのではないだろうか。
38

4.第三者機関の充実と公正化。
すべての人間が自分の信念に従い、行動すればいいのだが中にはそうでない人もいる。
そこで、安定した社会を築くには監査機関を設立する必要がある。現在は各病院が出資し
て管理、運営している。つまり自分で自分を管理、しているのと同じでこれでは自分の
勤めている病院のランクが下がるので、つい、甘えが出てしまい隠ぺい工作をする。
これを政府が各医療機関から資金を集め、まったく医療機関とつながりのない機関を設
立する必要がある。そしてインターネットなどによる情報公開をよりいっそう充実させ
る必要がある。
公開オペ制度
密室であることによって何が起こっても隠す秘密主義の医療を公開オペ制度を導入す
ることによって医療事故が起こったら隠すことのできない制度を作る。基本的には患者
の了解を得てから公開するが、これは患者のプライバシーの問題もある。ひとつ間違っ
て公開してしまうと取り返しがつかない。
5.遺伝子医療
最近のめざましい遺伝子工学の進歩によって,多くの病気が遺伝子レベルの異常によ
って引き起こされていることがわかってきた。病気の原因となっている『異常な遺伝
子』を同定し,代わりに人工的に作った『正常な遺伝子』を外部から細胞内に補充して細
胞本来の機能を回復させることによって病気の治療を行うというのが遺伝子治療の考え
方である。
体に必要な酵素を産生する遺伝子に生まれつき異常があるような病気(先天性代謝異常
症)は正常な遺伝子を投与して酵素を補充するだけで治療効果が得られやすいため,遺伝
子治療の良い適応と考えられている。また高血圧などの生活習慣病や癌、そして神経難病
なども遺伝子の影響を受けることが解明されつつある。
遺伝子治療とは、生命活動の根幹を制御する治療法であり、遺伝子疾患だけでなく、エ
イズや難病など、様々な病気の治療への可能性がある。しかし,遺伝子治療の対象として
現在最も研究が盛んなのは悪性腫瘍(癌)である。なぜならば癌の発生にも遺伝子の異常
が深く関わっていいることが解明されてきたからである。そこで,発癌の原因となって
いる『異常な遺伝子』の代わりに『正常な遺伝子』を癌細胞内に投与して癌の増殖を抑制
することが可能となってきた。
39

おわりに
戦後からの地道な男女平等化運動の努力による女性の地位の向上に伴い、経済的に裕福
になった女性たちが今までのように、男性と結婚しなくても生活していけるようになり、
ライフスタイルや思想の変化も影響して晩婚化が進み、日本国内では少子高齢化が進行し、
数年後には総人口が増加から減少に変わるであろうと予想されている。
日本国内では、長時間待たされて短時間の診療や、あまり説明してくれない医者が多く
いる。しかし、その医者も説明する時間のない患者の数や、看護婦たちは病院のベッド
が空かないので、過労で倒れるまで働かないといけない。別に体は悪くないのに集まる
高齢者たちや国民に痛みを押し付ける信用できない政府など、問題は沢山ある。
このまま少子高齢化が進むと、それに比例して現役労働世代の負担が底なしに膨らんで
いき、少子高齢化がこのまま進むと思われている日本社会においては、根本的な改革に
はならないと思われる。
今現在政府が行おうとしている、改正健康保険法を含む政策は、その場しのぎの政党の
人気取りの政策に終わってしまう。
なので、これから日本の行う政策としては、その場しのぎの増税などではなく国民保険
が行き詰った主な原因のひとつである、少子高齢化の阻止が必要である。そのために行
う政策として次のようなものが上げられる。
1.男女の役割分業の見直しと育児をめぐる国民意識
2.結婚をめぐる状況への対応
3.地域全体での子育て支援とまちづくり
4.保育等子育てサービスの在り方
5.学歴偏重社会の見直し
6.子育てのための経済的負担の軽減
7.奨学金制度
8.こどもの数だけ税金を軽減
しかし、政府が行おうとしている改革も全く無駄ではなく、社会保険の崩壊を遅らせる
40

ことができるので、政府は現在行っている短期的な政策を行いつつ長期的な少子高齢化に
対する政策を行うべきだ。
参考文献
・ 医学書院・週刊医学界新聞 http://www.igaku-shoin.co.jp/nwsppr/n2002dir/n2469dir/n2469_03.htm
・ 医療制度改革試案
http://www.mhlw.go.jp/houdou/0109/h0925-2b.html#sankol
・ 家庭に夢を分科会報告書 http://www.kantei.go.jp/jp/singi/syoshika/981218kateirepo.html
・ 社会保証体制の再構築に関する勧告用語解説
http://www8.cao.go.jp/hoshou/whitepaper/council/kankoku-word/index.html・ 住宅介護サービスの種類
・ http://www.city.tokushima.tokushima.jp/kaigo/g.html ・ 全国介護保険担当課長会議資料
http://www.mhlw.go.jp/topics/kaigo/kaigi/020212/4-2.html・ 老人医療制度
http://www.pref.chiba.jp/syozoku/c_hoken/roujin・ 老人福祉法の施行について
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/~hourei/cgi-bin/t_docframe.cgi?MODE=tsuchi&DMODE=CONTENTS&SMODE=NORMAL&KEYWORD=&EFSNO=8301
・ 「老人保健法による医療制度」
http://www.pref.nara.jp/kaigo/sippei.html・ ICO/Fitness Club On-Line http://icofit.net/old_ico/lecture/health/kokumin2.htm・ NIKKEI4946.com http://www.nikkei4946.com/today/index.html・ 朝日新聞社編(2002)「朝日キーワード 2002」朝日新聞社・ 柄澤昭秀偏(1998)「高齢者の保健と医療」早稲田大学出版部・ 田代菊雄・古川繁子編(1998)「少子高齢化社会の社会福祉」学文社
・ 日本情報教育研究会編(2001)「日本の白書」清文社
・ 三浦文夫編(2001)「高齢者白書」日本社会福祉協議会
・ 人口動態統計p 86
41

42