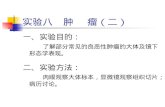一、...
Transcript of 一、...

近世にわけろ山城農民の経済生活
乙
町苛
郡
古市村
(二)
の場合
●
足 立
政 男
一、
二、
三、
四、
五、
古市村の概況
近世における村の貢租状態
村の助郷役及び共の他の負担
其の他の経済生活
む す び
一、古市村の概況
前号の(一)において論述した抑足村が山崎街道に
沿つた半商半職人的性格をもつた農村であつたのに対
し、ここに紹介する古市村はそれとは反対に極めて一
般的な農業生産の農村である。
近世に拍ける山城農民の経済生活(二)
凡そ農艮が村を建設するにあたつて具備せねばなら
ぬ条件が三つあるといわれている。一に口く、水、二
に目く仕事、三に目く、植民者の堅固次る煮志である
と。酉洋の学者は此の三つの条件を称して「三W」岬
ち考暮雪一奉昌ぎ尋巳一といつているが、R本古来の
農氏が新に村を建設する場合にもやはり共の新閑地の
条件として、其処に良い水があるかどうか、そo地に
おいて適当な農業を経営することができるかどうかを
見た上、自ら確乎不抜の精柿をもつて開拓の業に取り
かかつたに相違ない。しかして村の開拓と水の関係が
一〇三(三六三)

立命館経済学(第一巻・第三号)
もつともよく示されていると思われるのがこの古市村
である。古市村は南北に流れる小畑川の東岸にあり、
背後H村落O酉部から北部の堤防に沿つて大きな藪を
背貧い、高い堤防と藪のかげに、全村落が姿を没して
通行人すらユ、こに村藩が展開していることに気付かな
い程である。南北約三百米、東酉約百米の小じんまり
した小聚落には、堤防より僅か二筋の道路が通じてい
るoみで山崎、街逆とは丘陵と小畑川によつて遠くへだ
たり、閉治初年頃迄は約一粁にも及ぶ深い薮地の小径
を通らなければ街遭に出られなかつたようである。村
の束部及び南部は見波す隈り垣六たる一望の田圃が開
けて杜川に達し、出嗣と農家とが接近し、農耕にも収
穫にも実に好都合の地である。村落は一年を通じて東
南の巳光を充分に摂、取することが出来、冬季北酉から
○季節瓜はパい堤甘と籔によって遮断され、地形的に
も実に恐村としてこ○上ない絶好の場所である。
村o中央には小畑川○河床下に深く通ずる洞窟か・リ
マルーノチ
湧出する一つO泉がある。丸淵と呼ばれ、春夏秋冬を
一〇四(三六四)
通じてすき透るような清浄な水が漠友として湧き出で、
如句なる日照りの年にも澗れたことはない.夏は氷の
如く冬は井戸水のように温かである。昔巨の村人はこ
の水をのんで生活していた。近年こン、井戸を堀る家が
ふえて、との清水を汲む家がだんだん滅つて来たがン、
れでも炊事用水として多くの人に利用されている。殊
は水温水質が良好なので、農氏の生命とも言うべき籾
種の発芽用水として大いに利用せられ、毎年苗代田に
籾を下す前約二、三週間の間この泉水に浸しておくの
が慣例である。
下流の水はン、oまま用水路に導入され田圃の灌濁に
利用されている。一度この村を訪ねたものは誰もがこ
の泉水の済浄さに鰐異の眼をみはるであろうし、村が
水によつて成立し、水が聚落を彩成したことに気付く
であろう。実に村全体が俗世界をはなれた桃源境であ
る。
現在水円而積三十一町一股七淋余で耕地o殆んどを
占め、畑は屋敷O周開と小州川のほとりにあるにすぎ

ない。農家戸数四十七戸、人口二百七拾五人(昭和二
十六年度)昭和二十五年度産米割当は供出米六百三十
石七斗三升、保有米三百拾石八斗一升であつて約一千
石の米が収篶され、乙訓郡の穀倉であり、家計豊かな
完全農家のみから成立していて、商店は二戸もない現
況である。荷社寺については現在、寺一、神杜○、
(往古一)である。
二、
近廿における村の貢租状態
小州川に泌概の水源をもち、山崎街道(旧西国街道)
と、ユ、の方向を異にして伎硫するこの古市村は稲作地
帯としての様棚を皇し、前号に揚載した神足村が半商
半農的な概内的商品牛産及びそo流通経済の中に村が
存立しているoに対し、古市村は極めて一般的な農業
生産の上に村の経済が営まれいるのである。
今、市市村が保存する古交書により、近世”延宝七
年及び宝林十三年における村o貢租、状態をみるにお
よン、次Oような村商であるこ
近世における山城農民の経済生活(二)
延宝七紀山城国乙訓郡古市村検地村高(原文のまま)
古検六町弐反六畝拾七歩
上上田、六町三畝三歩
此分米 九拾石四斗六升五合 但壼石五斗代
古検八町五反拾三歩
上田、八町四反五畝拾八歩
此分米百拾八石三斗八升四合 但壷石四斗代
古検七町壷反弐歩
申固七町四反壷畝三歩
此分米八拾八石九斗三升弐合 但壷石弐斗代
古検六反四畝五歩
下田七反拾八歩
此分米七石六升 但壷石代
下々田八畝拾弐歩
此分米七斗五升六合 但九斗代
古検三町四反四畝弐拾七歩
上畑三町六反八畝六歩
此分米四拾七石八斗六升六合 但受石三斗代
古検弐町四反弐拾四歩
中畑弐町四反七畝拾八歩
此分米弐拾七石弐斗三升六合 但壱石壱斗代
古検壱町弐畝七歩
下畑壱町壼反六歩
一〇五(三六五)

立命館経済挙(策一巻・第三号)
此分米九石九斗壷升八合 但九斗代
内四斗四升 無古検
古検三反三畝弐拾歩
下々畑五反五畝拾弐歩 但八斗代
此分米四石四斗三升弐合
内六斗二升四合無古検
古検八反五畝弐拾弐歩
屋敷壱町八畝弐拾四歩
此分米拾四石壼斗四升四合 但壱石三斗代
外三畝弐拾歩 四壁之分除之
反合三拾堂町五反九畝歩
内
古検三拾壼町三反四畝弐歩 内八畝拾五歩永荒、井手、
二
川戊、委細帳之末在之
三拾町六反五畝拾七歩 古祇在畝歩
七反七畝拾五歩 竿先之出目
壱反五畝拾八歩 古検無之分
古検高四百拾四石弐升五合 内拾四石堂斗四升三合永荒地、
井手、川成、無地高委細帳
二
之末有之
分米合四酉九石堂斗九升三合
内三斗壷升弐含御蔵.屋敷
内
四百石三斗八升二合
但御蔵在之内ハ御年貢除之
古検之面在高
一〇六(三六六)
七石四斗五升六合 竿先之出目
壱石三斗五升五合 古検無之分
右者山城国乙訓郡古市村検地依被仰付侯六尺間竿を以壱反
三百歩也町反畝歩員数斗代高下分量委細書記帳面相極置者
也 延宝毒六月
石川主殿頭内
検地惣奉行 石 〃 伊 織固
検地本〆 伴 九郎左衛門O
同 加藤善太夫O
検地奉行 滝見助右衛門○
検地奉行 生田兵左衛門O
古市村庄崖案内の者
同村案内の者
新 助O
汀\
〃
助○
同
助左衛門○
以上o検地村高より、対幕府o農民貨担を考察する
に、水円の総石高は三百五不五斗九升七合、畑地o総
石高は百三丁五斗九升六合であつて、これから他村農
民の入作水円の石高三十一石四斗九升六合と、同じく

他村入作の畠地o石高九斗九升九合を差引くと、水田
残石高二百七拾四石壱斗壱含、畠地残石高百二石五斗
九升七合、合計三百七拾六石六斗九升八含となる。今
五公五民の貢租汽担としてン、の二分の一である百八十
八石三斗四升九合が円畑の正租として上納されると考
えるならば農民の手に残る米は凡そ次の如くなる。
古市農民oみの水円収穫米高二百七拾四石壱斗壱合
から円畑租百八拾八丁三斗九合を差引いた残り八拾五
石七斗五升二合が古市村残ることになる。これを帳附
百姓四十入に分配すると、平均弐石壷斗四升四合弱と
なる。次に二戸あたり平均耕作水田面積を計算すると、
古市村総水旧而積二拾二町六反八秋四歩から他村から
の人作水円面積二町二反四秋四歩■を引いた残り二拾町
四反四似二拾歩o水円が古市村の農民の手によつて耕
作されていることになり、これを四十戸に分けると平
均二戸宛火円而積は約五段一畝歩となる。(古市村畑地-
屋敷を含む総酉積八町九反、他村入作畑面積八畝二十七歩、古
市村農民のみの畠地酉横八町八段一畝三歩、二戸平均二反二
近位に.靭ける山城農氏の経済生活(二)
畝一歩弱、水固と畠地の含計二戸宛平均酉積七反三畝四歩J
この水田の級種が約二斗(一反宛四升)を玄米に換算
して一斗となる。これを前述の作徳米より差引くと残
りは二戸あたり二石四升四合弱で水田一反あたり約四
斗という催少な米が田畠租を上納した後に残る。この
場合検地帳における水田一段あたりの生産高は上、中、
下田平均して約一石三斗四升とたり、或は実際の水田
一段あたりの生産米は余程多かつたのではあるまいか
とも考えられるのであるが、これを生産技術の余程進
歩したと思われる明治七年(一九六年後にあたる)にお
ける同村の水円一段の生産米平均一石四斗四升(後述
参照)に比較してみる時、惟一段あたり一斗の生産兼
顯が見られるにすぎないことから実際におけろ当昨o
収確n亙は検地咲の高と人した相逃は考えられないので
あろ。而してこれを古市村の今巨の供出制度における
一反歩の保有米約一石に比較するとき如何に当峠の農
民魚担が過重であつたかがうかがわれる。しかも今日
供洲すろ米は一石八千円近い代金が農民の懐にかえつ
一〇七(三六七)

立命館経済挙(第一巻・第三晋)
て来て、細女乍らも一年中の生計が可能な状態におか
れているが、当時の農氏の上納米に対しては錨一文の
金もかえらチ、どうかすると欠米だ、先年貢だ、六公
四民だと増加こそすれ滅る事は友かつたのである。更
に宝暦十三年(一七六三年)の古市村の絵図面(註二)に
よつてン、の貢租負担を見るに、古市村の水田は一つ残
らず上納先が明確に決定せられている。
例えば
御蔵入 上々四 壱反を畝弐拾七歩 三右衛門
乙訓寺領 上 田 砿一反壱畝六歩 庄右衛門
般舟院領 上 田 苧反歩 源 助
森日社領 一石二斗六升 九右衛門
しかも上納領地毎に庄崖を置いて責任を取らしめ、
租米収納O先蝶を期している点は今HO比、てはない。
却.ち絵図面奥書によると
一、村高 五竈弐拾石五斗九升八合
新険羽載\
古検禦ルフ
庄墜 勘呉.衛
年寄 助右衛門
般舟院領
春日杜
乙訓寺領
}○八(三六八)
古検年寄 善左衛
百姓懲代 溝左衛
庄屋
年寄
百姓惣代
彌六源左 衝兵
『F弓ド介門範!f
庄屋 庄右 衛門
年寄 半 兵 衛
宝暦十三年末二月 日
とあり、絵図面の石高合計をとると次の如くなる。
古市農氏に所属する水田面積とその石高は
上々田 四町四畝拾三歩
此分米 六拾四石七斗四合 但一石六斗代
上 田 拾弐町三反三畝八歩
此分米 汽八拾四石九斗五升 但一石五斗代
申田六町七反九畝
此分木 八拾八石二斗七升 但一石三斗代
下 凪 五反八畝 此分米 六石三斗八升
反合 弐拾三町七反四畝三歩

分米合 三有四拾四石三斗四合
外春日社 ・七石受斗三升
他村農民の入作水旧砥.磧と石高
上々田 弐反八畝九歩
此分米 四石九斗二升八合
上 田 壱町九畝拾壼歩
此分米 拾六石四斗を升
中田三反五畝八歩
此分米 四石五斗七升五合
申田以下のものはなし。
反合壱町七反弐畝弐拾八歩
分米合 弐拾五石九斗壱升四合
外二春日社領堂石四斗九升五合
以上の水田面積及び石高より古市村農民の上納米と
保有米を算出すると凡そ次のようになる。古市村の高
(村高)五百弐拾石五斗九升八合から他村入作の石高を
控除すると、古市村のみの帳附百姓の持高は四百九拾
六、石八升四合(屋敷畠藪地及他村への出作を含む)となり、
五公五民の租卒で米のみによる貢租とすると二百四
拾八石三斗四升弐合を米で上納しなけれぱならなくな
近世における山城農民の経済隼活(二)
ろ。これを絵図面による古市農異の総収穫米三百五拾
壷石四、廿三升四合から上納すろと、農民の手に残る石
一、同は百三石九升二含と友る。これから更に水田弐拾三
町七反四畝三歩及び春同杜領(水固約四反)の籾種(一
反玄米で弐升の割合)四石八斗二升八合を差引くと九拾
八右弐斗七升四合の米が残る。今農家戸数を四十戸
(延宝時代と変化なし、但し寺庵四を除く)に配分するす
ると平均二戸あたりO作徳米は二石四斗五升七合とな
る。 (一段あたり生産高約一石四斗五升)これは延宝七年
におけろ作徳米二戸あ・/こり乎均商二石四升四合弱に較
べて惟かに四斗多くなっているにすぎない。しかも延
宝より約八拾余年後の農民へ活すなわち、郷倉いれ担
及び元破時代以後の生活の向上等を考えあわすと、農
民の角、担は決して延宝時代より軽くなつていろとは考
えられない。勿論以上の貢租米と作彼米の算出は、検
地帳に記職された旧梧の生産高を基礎にして計算した
ものであり、表面的な収支にすぎないのであつて実際
の生産商は記録なきため正確には算出出来ないのであ
一〇九(三六九)

立命館給済学(第一巻・第三号)
る、が、明治七年三月における文書によると次のような
収穫と支出が見られるのである。
乙訓郡第二区古市村
一、米四百拾五石
内
、肩七拾四石五斗四升五合
弐百石
弐石四斗五升
一年 号 一戸五椛
現
石
右之通相違無御座侯
明治七年三月
一〇(三七〇)
右村戸長
五十凄助右衛門
一 一
、延宝 七 年(西紀一六七九年)呵q
一 一
三年(西紀一七六三年)一四〇一
一 一 、
明治七年ブ西紀一八七四年)■四〇
昭和二十五年(西紀一九五〇年)両七
一 一■
京都府知瑛
長符信篤殴
癸酉租税辻行
これから水田一反あ■たりの生産高を計算すると次の
自家消費
他国輸出 如く比較せられる。
段 宛 汗一 二戸宛平均耕 一村有水田総面積 総 収 獲 米 丈 献
峰-産禍一作水.田面積一 -ト
一石三斗四升~三撃一二十町四振畝一二百七拾四奪斗 .険地帳
毒斗五升六反二歩二扉萬畝一三百奉一煮斗三升一絵図孤
一石四斗四升強 七反一畝二五歩一二八町七反四畝一四百拾五石 戸長川書
三石二升 .六反六畝十歩 ;二町二火七畝一九百岬拾宅石五斗凹升村の統計
有の表によつて水田面積は時代がたっ」にっれて坤加を
示しているが、一反宛の牛産高は検地帳の場合も報皆
書の場合もあまり椚違が認められない。作に宝麻年閉
と明冶初年におけろ生産高は全く同じといってよい状
態である,このことは絵図、両及び検地帳より計〃した
生産高は決して実際の生産高と喰い違っていたいと考
えてよいのであつて、検地帳、而によろ一、反平均生産店
〇一不三斗四升o計ザが明冶七年〇二百年後にたつて
実際収穫一尚が一石四斗四升となつて生産坤加約一斗を
みるのであるが、これは当然生産技術の向上によるo
であり、一、一」り閉○経地年数t考慮に人れる場含はむし
ろ延宝年閉における実際の生産高は検地帳によろ割付

村高より低くかつたのではあるまいかときえ考えられ
るのである。恐らく米を作つた農民達は米を食う日が
一年中で正月か盆で他は雑穀、麦、粟、稗、芋等によつ
てン、の露命をつない,ていたといつて決して遇言でない。
荷一度風水害にあつた場合の農民のみじめな生活は
以上のことより想像に余りあるものがある。彼等の生
きて行く道は幕府に対して、風水害の被害状況を届出
て年貢米の滅免を請うより以外に方法がなかつた。殊
に古市村は地勢上小畑川及び桂川の洪水に見舞われる
や大部分の田畠は冠水のため甚大な被害をうけ、・〆、の
為植付不能、水衡、収穫不能の憂■目にあい、仮米にも
こと欠くという苦難の生活がつづけられている。村の
古文書によるとと
御厭
乙訓郡
二高三百五拾四石五斗八升九合 古市村
此反別 廿八町三反
内
内高弐内十石七斗弐升三合 当干年植付候分
近世における山城農民の経済生活(二)
反別十五町五反弐畝五歩
内
高百五石壱斗を升七合
反別 八町三畝弐歩
残高百五石六斗六合
(?)有之侯分
級種
此反別 七町四反九畝三歩 御願申上候分
右之通無御座侯以上
安政六末年二月
城州乙訓郡古市村
庄屋 彌右衛門
年寄 勘右衛門
、[妹代 助右衛門
小堀勝太郎様
御役所
とある、これは村役人より代官所に安政五年度の枕付
両積を報皆した仰尻書であるが、総水円面積の約五割
四分が枕付られたに逝ぎず、水詐のためか早炊のため
か不明であるが、半分に近い水円が椛付られていない
のである。
更に
一一一(三七一)

立命館経済掌(第一巻・第三号)
乍恐奉御雇上(原文のまま)
一、当田方植付侯内三分通リ無難壱分羊通リ申痛、弐分
半通リ大痛三分通リ水腐乍恐此段御届ケ奉申上侯
以上
慶応元丑六月
城州乙訓郡古市村
庄屋 勘右衛門
.年寄 善右衛門
〃 彌 右 衛門
、丙姓代 清 兵 衛
これは慮応元年丑六月の水害状況を御上に届出てい
るのであるが植付の七十パーセソトが被害、依かに三
十パーセントが無雑というわけで、此の年の秋の苦し
い悲惨な収穫状熊が想像される次第であろ。さらに次
の如き記録によってン、の惨牢は明治初年に及んでいる
事が知られみ
御属ケ書
乙訓郡第三区古市村
田畑反別四拾町三反九畝三拾歩
二(三七二)
内
旧反別 二拾八町七反四畝二拾二歩
内 四町九畝六歩出水二而作物損荒
七町七反拾歩 作物大損
九町六畝拾八歩 作物小損
七町八反八畝拾八歩無難作
本年十月三日大雨二而桂川大洪水二而堤防数ケ所切込右田
地水下二柵戊リ作物損荒仕村申一同難渋仕此段御属ケ奉申
■急以上
胴治六年十一月廿七日 右村一仁ス
京都府七等出仕岡重正文殴
五十凄助右衛門
とあり、桂川の洪爪による被害で村中の者が難渋し
ている事が戸長より報皆されているのであるが、収穫
期を目前に控えての大風水害であつただけに、村氏は
さぞかし失望と悲歎の涙にくれた事と思われる。却ち
古市村を中心とせる籔ケ村の戸長が連署して上司に一〆、
の救済を懇願している文書があるが次の通りである。

奉願口上書
乙訓郡第三区
神
古
馬
勝
一トー
’
足.
市
場龍
寺
植 野
村村村村村
一、本月二日打続帰風簿雨二而三日未明ヨリ桂川筋暴緩致
所三堤防破決仕区内五カ村田畑悉皆水下相成リ侯今日
至漸く然水引落候得共今以七八分斗は水中二有之早郡
者勿論晩稲茂芽を生じ村々難渋仕右者葛野郡第四区下
桂村堤防破決所より桂川大水八九分斗本郡二流落候問
右場所至急止水、御築造御成下侯様村々墾願候 以上
明治元年十月七日
神児村戸長
岩岸荘左衛門
古市村戸長
五↑峻助右衛
馬場村戸長
今堀半兵衛
勝龍寺村戸長
水谷嘉兵、衛
近世における山城農民の経済生活(二)
下植野村戸長
本郡九郎兵衛
右副区長
岡木安堅
京都府七等串仕
個 重 正 丈 殿
とあり、これは上流に位する下桂村の堤防が決壊し、
ン、のため杜川の流水量の八九分までが田畑を抑流し、
早稲は勿論晩稲も冠水したままで滅水しないために発
芽しつつある有様であり、水中にある収¢前○稲は全
く手の施しようもなく、村尖は難渋している故に至急
止水批済策を溝じて貰いたいとの懇願である,(これは
明治初年の記録あり、幕藩時代のものではないが、かかる水
害は其の後も絶えず起り、昭和の今日に-至っている事からし
ても幕藩時代はもっと甚だしい風水害に見舞われたであろう)
又閉接的になるが次o如さ文書によつて、水牢o窮状
が推察されるのである。
口 上 書
乙訓猟古市村
庄 駁 五十棲肋右獅門
一金五拾両
一一三(三七三)
‘

立命館経済学(第一巻・第三晋) 、.
一・私村方之儀者珪削々定水場御座侯付困窮彌増去ル辰
年弐ケ年古今不覚水損仕飯等無御座借金等仕買入凌
來侯ゆへ趣カ難汁致屠今日之融通も難出来侯次第此
度御趣意ニテ私儀半株加入仕此段御属ケ奉申上候
外五人名前も差出候次第前書水損二而極々難渋致居
金子才覚難出来候二付加入之儀幾重にも御断奉申上
候以上
明治五年壬申三月十三日
右 村
岩城勘太郎
掘本善兵衛
鉄道会杜 五十睡三右衛門
坂本長右衛門
岩城醜右衛門
これは妹道会杜の株加入について庁屋五十榛功布衡
門は半株加人す、ガ件〇五-へはニケ年にKろ水害によ
り、困耽も正だしく、∴ても加人企が出木たいから郷
断りすろといういであろが、 「私村ガ∴代々従帖女定
水場郷脈候付困窮彌刷」とか「去.反年弐ヶ年プ午不覚
水損仕」とかによつて炎民が水箏のため十口くから苦し
一一四(三七四)
めれて来た事がわかるのである。更に「飯等無御座借
金等仕買入凌来候ゆえ極六難渋致屠今口]之融通も難出
来候」というに至つては、公べるべき食物もなく、借
金により之を買い求め、今R一日の暮しにも困つて難
渋している姿がありありと目に見えるよう、てある。
.以上の文書、記録によつて、洪水、湛水、水衝等の
大凶作に見舞われたことも数多く、しかもその場合の
窮迫せる悲惨な有様は全く眼を蔽わしめるものがあつ
たように見交けら孔る。ン、して彼等1の生活の窮乏化は
必然的に廿阿利貸資本の浸透を可能ならしめたのであつ
て、やがてン、こ仁は借金のために土地を喪失し、没蒋の
遮命を辿つたものもあつたものと思われる。(後述参照)
術責机の厳格な取り立てを行い、農民から苛酷な訣
求搾取を行った例として引用され至民閉省要Lに目く。
「百杵と、一.口物、午篶にひとし、午さ政に重き賦役を
かけられ、ひど∴-以牢ぺ三てシ?わといへど、更に云
4な・リず、小断鴉↓.□打郷に逢ふて小三逃す、いか様o
非道をしても、竹入とたれば、一侠の米を取ても君風

に誇り、民家へ出ては能く百姓を睨むにかかむのみ也、
其外輩の官人多くは民間の卑賎より出て、民間を攻る。
是豆を煮て豆からをたくがごとく皆爾なり。縦ば牛馬
に重荷を負ふせて打たたき、つまづけば猶怒て大鞭し、
この畜生めと罵るが如し。吉事なく泣く事なし、百姓
相同じ」の文字通りの正租訣求の記録が、古市○「村
の記録」にもみられる。
一、乙訓寺領御坂箇之義宝永年中より御蔵入新検方免ニテ
増加侯分納来リ侯処去ル文政年巾ヨリ安政六未年迄三
十一ケ年之間九分米ニテ増加候分-、」納致居候処御坂調
二相戊右三十一ケ年之算違償金十弐両弐分卜銀五百目
二相成侯処内耳nハ用拾被成下残、リ金弐拾弐両弐分ヲ
為祠堂財寄辿二差上ケ事済仕候右証人者榊足村宇□元
吉也則差上ケ害ノ控、、箏下ケ共一包ニテ村箱布之條尤
二付万延元中秋ヨリ枚見取二相戊候
文久元年酉三月 日
とあり、過去三十一ケ年間の計算違いによる正租○不
足を祠堂寄進o名目により迫徴している。これによつ
て如何に収受の手段が功妙であり、徴収が厳重、てあう
近世に.杉ける山城農民の経済生活(二)
たか、叉ン、れを訴えるにも訴える所がないという有楳
をうかがい知ることが出来るのである。
註一「古市村検地帳」古市村共有財産として「村箱」にー保
存されている。
詫二「古市村絵図酉」棋二米従三米の大地図にして「共有
財産として保存これている。
三、村の助郷役及び其の他の負担
宿駅、駅逓補功のために沿道の農村から馬を課徴す
る事は近世以前より行われていたが徳川幕府も亦此の・
制度を採用した○である。しかして元様二年には宿駅
近傍の郷村を択び、更に七年には令慮に功郷が劃定せ
、りれたの、てあるが、爾来岬冶維新に至るまで企国的助
郷の異酌は享保二年○助柵.配布の班改を除く外は、之
を見たかつたようである。しかし谷病駅の助郷はしぱ
しば異動せしめざるt碍“、仏かつた。次の文書は功郷役
負担免除〇一札である。
差上申一札之事(原文の亥ま)
東海道淀宿助郷御免除被仰付代助郷之儀者摂州佐井村外拾
一一五(三七五)

立命館経済掌(第一巻・第三号)
ヶ村二被仰付旨其御筋より御達有之御仰一渡承知重畏候依
而御請証文差上申候如件
慶応三年卯年十二月九日
大澤御役所
城州綴喜郡内里村年寄
同州久世郡久世村茂平年寄
同州乙訓郡久我村庄屋
1111111111
1111111111
〃 年寄
古市村庄屋
神足村庄屋
奥海印寺村庄屋
友岡村庄慶
善辰安権勘三仙九
兵右右郎右
兵兵衝4/
衛兵衛
衛平衛門門電
不・
門繭
却ち助郷役(淀宿)を免除せられた村が連名で所轄
役所に免除確認の証文を挑出し、この推書た村の泥像
帳に残したもので、雑渋な助郷o訳役を免除せ、りれ。.一
村六の喜びが簡潔な文句の底に流れていて典味深いも
のである。術村の助郷勤高は八拾五不四∴九升二く〕で、
前項で論述した如く、農民達はン、o正租においてすで
に角、担能力の限界に達していたと思われろ上に更に一,一、
一一六(三七六)
の勤高に応ずる助郷人足を送り出さねばならなかつた
の、てあるから、その負担の過重に難渋を極めたことが
想伍される。小壮有為の若者が絶えず徴発せられた。
殊に幕府○助郷入馬○課徴は年中絶間のない有様であ
り、競中東海道の助郷は最も苦痛な重い負担であつた
からして、古市農民も亦その経済牛活に少なからざる
影響をうけて苦んだと思われるコ
維新以後、識者、当路者は「即今天下万民塗炭の苦、
この功郷を以て第一とす。若しこれを廃さば実に万民
の大幸、王政一新の実効ここに顕はると云ふべし」と
までこの制度O存続け非を叫んでいろことからして、
ン、○れ担の苛酪であつて如何に農民を苦しめたもの、て
あるかは想似以上であろ、
雌’ト先《恐宗oみより村が推戊、され、^つ地形上か
らも村の位侃が、山崎街並から小州川と深い薮にて遮
断せられて、貨粋経祈から遠く切り雛された純粋農村
であつ午.事は、一、…述の如寺半農半商的或は半農半職人
的豊村O抑足村豊火に比、へて、功郷役Oれ、担をはたす

上では一層苦痛であつた、てあろう。
共の他の農民貨担としては、小畑川堤防や道路等の
改修、桂川による頻六たる水害の復旧工事等のために
は村自体としても叉他村との共同作業のためにも多く
の氏費や入足の提供が要求されて来た事は間違いある
まい。記録文書として明治初年のものであるが次の如
きもの、がある、
村費明細磧書
乙訓郡第三区
古 市 村
一、諾川之堤防山一舳石垣道賂橋梁昨申十月より当六年九月
中迄之民費左二奉申上僕
一、銭四拾五貫文 小畑川堤防笠重人費
シガラミダケ
一、銭四拾致文 同所側抗符竹入費
一、弐拾弐貰文 同所橋普新入費
〆百拾貰文
右之通入薮柵連無御座候以上
右村戸長
五十薩助宥衛門
明治六年十月廿六日
近世における山域農民の経済生活(二)
京都府七等出仕 国重正文殴
これは一年間の白村内における氏費の明細を上司に
報告したものである。他村との関連におけるものとし
ては次の如き文書が見られる
川之出水之節堤防方組合規則書
乙訓郡第三区
勝寵寺村
神 足 村
古 市 村
右者三ケ村共小畑川筋堤防有之候出水之卸ハ其村二而致来
リ候処今般淀川筋下植野村内之木橋堤防粁で、燃水樋御座候
二付水下勝龍寺始右村三ケ村申倉組合禍定御規則之通村々
二〔一人毎二人夫差出候猟叉臨時出水之節防方相用條杭木、
重俵杵に松明等右村々申合手当致置候問此段速々右奉串上
候 以上
明治元年八月四日
乙訓郡第三区
勝龍寺村
戸 長 印
神足村
一一七(三七七)

立命館経済掌(第一巻・第三号)
京都府
知事
長谷信篤駿
戸
古市村
戸
長長
印印
これは村六が互に防水組合を結成して出水に備えた
規則書であつて人足其の他村六の責任事項が定められ
ている。叉村内の冠婚葬祭費は勿論杜寺や郷倉の修理
並に達立の費用及び杜寺扶養(当時寺庵四、神杜一)等
共同生活費も彼等に取っては無視し得ざるものであつ
たい今「村の記録」よりン、の例を拾えぱ、前述した所
の乙訓寺領における算違いによる三十一ケ年の追徴年
貢の寄進がある、 「・-残り金弐拾弐両弐分ヲ為祠堂財
寄進差上ケ事済仕候、ム〈」とあり、叉前号記載の如く、
「一、安政二卯二月薬師堂破損二付修推屋根募替仕候此儀
何方へも不席拙候入用之段、村方に栢母子坂結仕候
云々」
と寺の修理を行い、費用は村人の頼母子によつてい
る、吏に神杜o修理についても
一一八(三七八)
「一、安政五年已五月若宮様鳥居破損仕侯ゆへ建替仕侯此
儀も何方へも不属出仕候入用銀の儀村方勧化を以仕
侯云々」
とあり、入用銀は村の寄附金によつていることが明
らかである。殊に備荒狩穀のために謀けられた郷倉の
負担を考える時、平均二石余の僅少な作徳米と僅かな
裏作生産物でもつて一年間の生計費を捻出しなければ
ならない彼等にとつて、この郷倉貧担も実に苦痛の種
であつたに梢違たい二収穫米の四分の三に近い正租。
勤高八拾五石四斗の功郷負担、更に郷蔵米の供出、村
の共同負担金の拠出等、三重にも四重にも彼等の経済
生活は縛られていたo、てある。更に明冶六年にお村の
戸数が四拾軒、男肯入、太百N人合計弐百岬人の人口
で、延穴から宝牌を経て維新に至ろ約弐百年の長年月
の閉に少しも増加を示していないという事実(明治七
年五月現在戸狐三拾八戸で減少している)は、彼等がその
経済生活において人〕増殖に対する経済的余力を持つ
て潜らなかったこと’二小すもoとして注目に値すろ点

である。同じ実暦四年の仙蔓藩麗東山の「上言」
に「五六十年以前(元漱頃に当る)御百姓子供生育仕事
には、一夫一緑にても男女五六人も七八人も生育仕候
処、近年不梢続仕る故か、叉世上著り候故にや、一両
人の外は生育不仕、もどす、返すなどと申候て、出生
いなや其父母直きに残害仕候。其の仁と不仁とは愚民
の儀にて不及論奉存候へども、君子より是を観候時に
は、甚だ以て不忍事に可有御座候。乍然畢寛困窮より
■
起り、数人の児子を飢寒せしめんよりは、已れが生を
遂んには不如と申候て、強ひて、両三人の生育に不過
候。此弊風に習ひ候て富民共も多子より少子の労なき
が勝り候とて、是亦三四人に不過候…」とあるが、東
北地方より透かに恵まれた畿内の農民であるにかかわ
らず、戸数がむしろ滅少し、その人口が静止の状態を
呈しているのは、貧窮農民の京都、大阪等の大都市へ
の流入挑避も考えられるのであるが、他面彼等の経済
生活の困窮と生活難の締果牛じた現象であり、その間
の消息を物語つているものとも考えられる。
近世に拍ける山城農民の経済生活(二)
四、共の他の経済生活
「農業全書」、「草木六部耕種」等の記載するように、
休耕することのない我が国農業にとつては、その連年
作付を可能衣らしめる条件としては肥料の施与が不可
欠の重要性をもつている。殊に裏作に麦や菜種を作る
二毛作の此の地方の田嗣では、ン、の地力維持のために
肥料は一層重要性をもつていろわけ、てある。採草地を
持たない古市村の肥料供給源が京都市にあつ4/こため、
百姓達は伏見の下肥問屋から尿肥を購入し、肥料問題
を解決している。肥料も諾物価の騰貴に伴つて次第に
高価になつて幾度も売買値段の変更契約が取りかわさ
れている。 「村の記録」よりその代表的なものを拾え
ば次のようである。
「別紙一札之事」
一、近年諦色高値二付私共暮し方六ケ敬灘渋二付此度城、
摂、河、三ケ同御搬代御柳申上侯而阪、小田子唱荷二
付扮賃五文宛増銭御願申上候所箪一統御隻会の上御承
一一九(三七九)
●

,
立命館経済学(第一巻・第三晋)
知被成下摩仕合奉存候、然ル所本紙一札には五文増丸
三々年御承知被下侯 依乙訓郡之分は此度四文増御願
申上候儀二御座僕間、此段以書付申上置侯宜御承知度
成下候為後日之差入一札価而如件
小廻L
忠 兵
庄
長 次
伏見醍問屋年寄
藤 丘ハ
久 兵
衛七郎衛衛
とあり、小旧子壱椅について五文づつの値上げの所
を乙訓郡は耐に五文璃を丸三ケ年承知して呉れたから
此度は四文の値上げで締構、てある。という興味深い契
約であり、阻料は舟で伏昆から梓川伴の古川に出て、
古川から六間堀o排永跨午辿つて古市村の田圃の南端
ま、てム控さか、一.一、こから胆碗(苓円岡の南端に設けられ
少・しでも逝抄労力を宥こトりと考えられている)に搬入ン、一れ
た これらの外に茉種の搾り糟を前号所載の油崖から
購入している。
「農費目録」
正月三日
一、壱玉
正月十二日
一、五玉
正月廿五日
一、五、玉
二月十二日
一、十王
二月十一日
一二〇(三八○)
(前号参照)
古市
古市
古市
古市
庄 兵 衛
五 左
五 左
彦 兵
衛衛
門門衛
古市
市左衛門
とあり、農民は洲崖から汕糟を晦人して促用した消
息が農質H緑によって幻られる、こO汕糀は当時非常
に、よく効く篶重な肚料〇一つであつたに杣逃ない、
さて以上oように鱗入肥料o存布していること、ン、
して村に探草地をもつていないことは、こO村の農民

が必然的貨幣経済に接近し、すでに貢租及び自給品以
外の商業的農産物を作り出している事を示すものであ
るといつてよい。戸谷敏之氏は肥料として自給肥料が
使われているか、購入肥料が使われているかを規準と
して東北型と近畿型に分け、購入肥料の佼用を生産の
交換経済への入りこみ方の指標とみているのであるが、
全くン、の通りである。かくて徳川幕擦制下の封建的苛
倣訣粂の収納体制の下に農奴化した彼等の生きて行く
道は、白給白足的白然経済の確立が不可能なために商
品的州作農業O経営H菜種、棉、瓜、茄子、牛蓼等、或
は副業H葭賛の製遣、簑作り等、若しくは出稼奉公H
汕以の傭人、海即寺村から京祁へ天燃氷の運搬人足等
にン、O維済生沽〇一部を伏存せざるわけにいかなかつ
たOであろ (かかる貨幣収入のための生活にーっいては次
の機余にゆずることにする)。この点、附号所載の神足村
に比べ交換経済」へo人oこみ方がはるかに浅かつたに
せよ次第にン、O渦中にまさこまれていつたO。てある、
更に古市村における商業資本の侵入にっいては前号所
近杜における山城農民の経済生活(二)
載の「農質R録」によれば次の如くである。
菜種の商品的裁培による商業資本の導入としては、
「農賢目録」
七月四日 夕立 古市村 平 七
勝龍寺村 長左衛門
神批村 喜 左 衛 門
一、壱石弐斗(菜種)
弐斗八合(充換種油)
七月五日晴 古市村 五左衛門
一、壱石弐斗
弐斗壷升三合
七月八日 古市村 五左衛門
一、壱石弐斗
弐斗砥升五合
とあり、古市村百炊平七、五左衛門等が汕屋に人最
の災硫を送り込んで洲と交換しているのがみえる、当
時の百作達は、需災o劣かつたこと、及び近くに人搾
汕菜者が任在するという事、或は稲作に差支え川丁、栽
培収穫が簡単で、貨幣収入を図る上、てもつとも有利で
一二一(三八一)

立命館経済学(第一巻・第三号)
あること等より菜-種を冬作として大量に栽培したの、て
ある。そしてそのためには、搾油業者(神足村浦屋彌兵
衛)の商業資本H前貸を受け入れたのであるが、やが
て彼等はン、の商業資大・の支配下におかれるに至つたの
である。その一例として
借用申金子の事
一、金壱両弐分也
着之金子当御上納差詰縫借用申候処実正也然上返弁之
義者来五月晦日銀元利急度反済可申候万一遅滞仕候ハ
バ私作付置候菜種御坂被下候為後日之一札価而如件
文政十一年十二月十九日
古市村
伊 兵 衛
油屋彌兵衝殿
がある。「万一遅滞仕候ハバ私作付帷候菜種御取被
下候」とあるように搾油商人の前貸を受けているので
ある。このようた証文が百通近くも見られる事は当時
古市に限らず城州の百姓が商薬資本の浸透をうけつつ
あつたことを物語るものである。叉古市村所蔵の古交
一二二(三八二)
書の中に次の如き興味深い証文が見受けら牝る。
年不証文之事(原文のまま)
一、合銀五匁九分五厘也
右者神足村油崖彌兵衛殿機賃銀 此度内倍二相戊リ済
方年不二落合則壷ケ年二銀八分五厘宛来ル巳ヨリ亥迄
七ケ年之尚毎年極月の甘五日限機方へ急度速返可仕候
若相滞ノ儀有之侯はば左之印形人共相弁機方へ少茂難
4
渋相掛ケ申問敷候為後日之一札価而如件
文政三年辰ヤニ月 日
借用主 与 七 郎○
親族請人 彌 助○
右同断 六 源○
御蔵入
御役人巾
とある。機方より内俗になつた借金杉二時に文払い
得ないことから年賦によっ1て支払う亡いうOであろが、
これも機方たる汕崖繭、共衡O甘貨ケうけていた古市村
農民の経済生活の一存在形樵t如らして呉れろもOと
して面白い資料である。

更に頻六たる水害や凶作に襲われ、或は不時の変災
にあつて窮乏化し、上納出来たくなつた百姓達の経済
生活は必然的に高利貸資本の浸透をうけている。例え
ば 借用申銀子之証文
一、合銀三百目也
右之銀子此度蕪拠要■用二付倦圭借用申処実正明白也
則引当左之通
一、家屋締小屋共
宥三ケ所書入置申侯万一相滞之儀有之候ハバ左之請人
共へ引渡売払ひ代銀者兀利相添無相違急度返済可申候
為後日之借用証文価而如件
借用主古市村
親引受
二」
肩年
屋寄
六一伴
五
一助
善九
天保三辰年十月
近杜に拍ける山城農民の経済生活(二)
右左右兵兵兵 一
ユ
h}寸
で、-一
可
灯峠
’イ
’tJ
“阜
1“
衛○
衛○
門O
門○
衛○
門○
神昆
三郎丘ハ衛殴
とある如く、高利貸資本に依存せざるを得なくなつ
た農氏はこの外にも数多くみられるのである。叉上納
に窮したため娘を質奉公に出した例としては
牽公人請状之事
一此よつと申者私娘二御座僚処当御上納二差詰リ来ルニ月
より寅二月迄丸壱ケ年也則給銀百三十六匁被下燵圭受坂御
上納二相立串候処実正也然上其年数之内取逃欠落叉ハ病気
二而不奉公仕ラバ早遠人代相立テ少茂御手支致申間敷侯為
後日之奉公人請状価而如件
文化十年十一月廿九日
古市村 親 利 八○
奉公人 よ っ○
受人 平右衛門○
油崖彌兵衛殿
がある。このようにして古市村の農民がン、の経済生活
の中、受入れていた豪農洲崖の高利貸付資木の額は大
体次の如き貴重な資料(岡本來所蔵棚卸党)によつて明
一二三(三八三)

、立命館経済掌(第一巻・第三号)
らかにされるのである。
. ヨ ー111,’ 一 , ■ 1‘,1 ■31 1,! 1 11 ; 1 - ,1 , ,■ l I’■
年 代
浸透せる高利貸付資本額
天明四年一プ八略一
(米一石九五匁)
銀 三賛二百六拾匁三分六厘
〃 五年
銀 三貫二高六拾六匁九分八厘
〃 六年
銀 三實四百三拾三匁四分一厘
文化九年一戸一項一
銀六質九百五拾匁
金 二分
文化十年喬琶
銀 五貫二百匁 (米一石代四五匁)金拾五両
と云う莫人な額になるのである。
五、むすび
以上私は山城農民の経済生活という研究題目のもと
にン、の具体的実証として前号において乙訓郡神足村の
半商人的、半職人的性格をもつた農民の経済生活な論
じ、ン、の深く流通経済の中に入りこんだ事情を解明し
たつもりであるが、本号において紹介した古市村は前
者とは収対に再編成された近世農村の形熊を比較的維
持している農民の経済生活を代表するもoとして究明
して来た次第であろ ン、れ故前者からは半商人的、半
一二四(三八四)
職人的性格をもつた所の農民の経済生活が説明され得
るであろう、例えば京都市近郊の農村、或は茶園経営
で貨幣経済に入んだ農民の経済生活○如きは之に類似
せる性格をもつていることと思われる 後者からはそ
の他の比較的単純な一般的農村に於ける百姓の経済生
活の大体の実情が汲み取られるように思われる.勿論
漸次研究し実証してこれが発表の機会をもーちたいと考
えている、
さて現在の古市村は長岡町の大字古市部落としてそ
の名をとどめ、乙訓郡O穀倉として、水害に見舞われ
乍らも、ユ、の防禦工事、排水施該の完傭に努力し、そ
の恵まれた村落の立地条件と経営の近代化、機械化に
よつて裕福なる農民としての経済生活を兇ることが川
来るのであるが、一たび近世幕漆休.制下に遡上ろと、
そこには巨夜働き皿して附その日の生活に苦しむ農民
の経済生沽が紋りひろげられているOノしある、封碓領
主の苛酩な詠求と件坂に∴って窮乏化した農民生活は
吏に貨幣経済o壮透に、さo豊村経済o変化によつて益

三不安定な状熊に遣いこまれていつたの、てある。一方、
風水害や早舷に児舞われることもたびたびあつユ.」ため、
余裕の全くない彼等の生活はそのために決定的な打撃
をうけ頻六たる飢鰹に襲われたと考えられる。かくて
明治五年三月の「村の記録」に「私村方之儀義従前六
定水場御座候付困窮彌増去辰年弐ケ年古今不覚水損仕
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 ■ 、 、 、 、
飯等無御座借金等仕貞入凌来候ゆへ極六難渋致旭今R
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、
之融通も難出来候次第」云六とある如く、共の巨の暮
しにも事かき、食うべき食物もなく、借金によつて露
命をつなぐと云うような経済状態がくりかえされて来
たのである。村の古老たちの間にパえられている「背
の古市村の百姓は、麦と粟飯が常食で、飢鰹の年には
稗や竹の実を粉にして之を公べて露命をつないだ」と
か「正月が来ても米の餅をっく百姓は稀であつた」と
いう言葉はかかる雑渋極まる彼等の経済生活の実怖を
物語つているのである。かくて
一片の寸土にン、の生涯を繋締せられ、而も粗衣粗公、
その坐命をすりへらして仰支飼者たる封雄武十閉を扶
近世における山城農民の経済生活(二)
養せねばならない農奴的存在としての彼等の生活は、
二重にも三重にも加えられた搾取と窮乏化への桂桝の
ために身動きもならず、妻子すら充分に扶養出來ず、
人口も停滞し、中には窮乏に堪えかね、訣求の苛酢を
逃れて離村し、比較的白由た都市の空気を求めて京都
或は大阪へと流入し、武家町家の奉公人として、或は
小商人まJ/こは職人として、目雇いとして生活の途を求
め4。こ農民達も少たくはないのである。 「大阪市史」に
閉肉以後「近国近在より火阪に流入する無沽非人甚だ
多」かつたとあるが、離村向都の傾向は彼等の経済生
沽よりすれば必然の緒果であつJ/こともいえるのである。
一二五(三八五)