平成 23 年(2011 - MyDNS.JP · 2018-08-19 ·...
Transcript of 平成 23 年(2011 - MyDNS.JP · 2018-08-19 ·...

平成 23年(2011年)測量士午前問題解答集
法令 No.1 No.2 No.3
4 4 5
多角 No.4 No.5 No.6 No.7 No.8
2 3 3 5 2
水準 No.9 No.10 No.11 No.12
2 3 4 5
地形 No.13 No.14 No.15
1 4 5
写真 No.16 No.17 No.18 No.19 No.20
4 1 3 5 3
編集 No.21 No.22 No.23 No.24
3 1 4 1
応用 No.25 No.26 No.27 No.28
5 4 2 3
正解番号確率
番号 個数 確率(%)
1 4 14
2 4 14
3 7 25
4 7 25
5 6 21
Σ 28 100

[NO. 1]
[NO. 1]
次の a~eの文は、測量法(昭和 24年法律第 188号)に規定された事項について述べたものであ
る。(ア)~(オ)に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか。
次の中から選べ。
解答
a. この法律は、国もしくは公共団体が費用の一部若しくは一部を負担し、若しくは補助して実施
する土地の測量又はこれらの測量の結果を利用する土地の測量について、その実施の基準及び
実施に必要な権能を定め、(ア測量の重複 )を除き、並びに測量の正確さを確保するととも
に、測量業を営む者の登録の実施、業務の規制等により、測量業の適正な運営とその健全な発
達を図り、もって各種測量の調整及び測量制度の改善発達に資することを目的とする。
b.「測量作業機関」とは、(イ 測量計画機関)の指示又は委託を受けて測量作業を実施する者を
言う。
c.「測量標」とは、永久標識、一時標識及び(ウ 仮説標識)をいう。
d. 基本測量の測量成果及び測量記録の謄本又は抄本の交付を受けようとする者は、国土交通省令
で定めるところにより、(エ 国土地理院の長)に申請をしなければならない。
e. 測量業者は、その営業所ごとに(オ 測量士)を一人以上置かなければならない。
ア イ ウ エ オ
1. 測量の重複 測量計画機関 仮設標識 国土交通大臣 測量士
2. 測量の重複 測量業者 仮設標識 国土地理院の長 測量士
3. 測量の障害 測量計画機関 航路標識 国土地理院の長 測量士又は測量士補
4. 測量の重複 測量計画機関 仮設標識 国土地理院の長 測量士
5. 測量の障害 測量業者 航路標識 国土交通大臣 測量士又は測量士補
解答 4
[NO. 2]
次の文は、わが国における地理情報標準について述べたものである。明らかに間違っているものはどれか。
次の中から選べ。
解答

1. 地理情報標準プロファイル(JPGIS)は、地理情報の分野における様々な標準規格をひとまとめにし、データの作
成の際に最低限守るべきルールを整理したものである。〇
2. 製品仕様書は、得ようとする測量成果の種類、内容、構造、品質などについて、地理情報標準に準拠して記
述しなければならない。〇
3. 地理情報標準に準拠して整備されたデータを GIS で利用する場合は、それぞれのシステムの内部形式に変換
して使用することができる。〇
4. 地理情報標準に準拠した製品仕様書は、データ作成時の発注仕様書として使用することはできるが、データ交
換時の説明書としては使用することはできない。×
理由:説明書に使用できる。
5. 地理情報標準の利用が進むことで、データの相互利用がしやすい環境が整備され、異なる整備主体のデータ
共用が可能となる。〇
解答 4
[NO. 3]
次の文は、測量作業機関の作業責任者として、公共測量を行う場合に留意しなければならないことについて述べ
たものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解説
(解答)No.3 安全対策
1. 作業中の緊急事態に備え、社内での救急救命講習開催や連絡体制確立など安全確保のための対策を行った。〇
2. 測量計画機関から個人を特定できる情報を記載した資料が貸与されたことから、測量計画機関及び自社で定める
個人情報保護方針に基づき、厳重な管理体制の下で作業を行うように指示した。〇
3. 国立公園内の特別地域内で止むを得ず樹木伐採の必要が生じたことから、測量計画機関へ報告し、環境大臣の
許可を受けた後に作業を実施させた。〇

4. 数値地形図データ作成の数値編集終了後に、現地調査以降に生じた変化に関する情報を得たため、現地において
補測する測量を行うように指示した。〇
5. 基準点測量において、既知点とする電子基準点の情報を得るため、事前に稼働状況を確認するとともに、日々の座
標値をインターネットを利用して入手し、使用するように指示した。×
理由:公開されている成果を使用しなければならないので、間違い。
解答 5
[NO. 4]
次の文は、わが国における測量の基準について述べたものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解説
1. 地球上の位置を表すための基準として、わが国では平成 14年から世界測地系を採用している。〇
2. 世界測地系で想定した回転楕円体は、その中心が地球の重心と一致し、長軸は地球の自転軸と一致する。
×
理由:長軸はX,Y軸である。
3. 水平位置に関する測量の原点は日本経緯度原点である。日本経緯度原点の地点及び原点数値は政令で
定められている。〇
4. 平面直角座標系(平成 14 年国土交通省告示第 9号)では、回転楕円体の基準面上へ投影された長さ
と、座標系の基準面上へ投影された長さの相対誤差が 1/10,000 を超えないようにするため、座標系原点を通る
子午線(X 軸)上の縮尺係数を 0.9999 とし、全国を 19 の地域に分けている。〇
5. 現在公開されている基本水準点成果は、2000年度成果として、正標高補正を行い算出した成果である。
現在公開されている基本水準点成果は、2000 年度成果として、正標高補正を行い算出した成果である。○
解答 2
[NO. 5]
次の文は、セミ・ダイナミック補正及び関連事項について述べたものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。

解説
1. セミ・ダイナミック補正とは、測量して得た観測結果と、現在公開されている三角点などの基準点の測量成果(1997
年 1 月 1 日 0 時(UTC)を基準)との間に生じる地殻変動に起因する乖離を補正するものである。○
2. 地殻変動によるひずみの影響は、既知点間の距離が長い程大きい。〇
3. 公共測量における 1 級及び 2 級基準点測量を行う際には、セミ・ダイナミック補正を適用しなければならない。×
理由:公共測量では、1級基準点のうち電子基準点のみを既知点として用いる測量が対象なので、間違い。
4. セミ・ダイナミック補正に使用する地殻変動補正パラメータファイルは適用期間が決められている。➭既知点として用い
る複数の電子基準点の元期座標値を、年度間に公表される地殻変動パラメータを用いて既知点の今期座標値に変更
する。○
5. 公共測量において、セミ・ダイナミック補正支援ソフトウェアを使用する際に入力する座標値は、世界測地系に準拠し
ていることが必要である。○
したがって、3 は間違い。
解答 3
[NO. 6]
図 6 に示す測量を行った。既知点 A における方位点 B の方向角 T は 330°0'0”である。新点 C の平面直角座標
系上における座標値を求めるために、既知点 A において水平角αと距離 S を測定し、次の値を得た。
α=150°00’00” αの標準偏差 5”
S=1,200.00m S の標準偏差 4cm
この測定結果を用いて新点 C の座標を求めた。既知点 A の座標に誤差はないものとし、方向角 T の標準偏差を
5”とするとき、新点 C の X座標の標準偏差はいくらか。最も近いものを次の中から選べ。
ただし、距離は平面直角座標系上の距離に補正済であり、角度 1 ラジアンは、2”×105とする。
なお、関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。

1. 3.3cm
2. 3.7cm
3. 4.2cm
4. 4.7cm
5. 5.4cm
(解答)No.6 多角測量「新点 C のx座標の標準偏差(誤差伝播)」
TAC=T+α=330°+150°=120°
cosTAC=-1/2
sinTAC=√3/2
S=1200m
ms=4cm
mT=5″
mα=5″
XC = XA + S ∙ cos(T + α − 360)
YC = YA + S ∙ sin(T + α − 360)
テーラー展開すると
∆XC =∂XC
∂S∆S +
∂XC
∂α∆α +
∂XC
∂T∆T
∆YC =∂YC
∂S∆S +
∂YC
∂α∆α +
∂YC
∂T∆T
∆XC = cos(T + α − 360°) ∆S − Ssin(T + α − 360°)∆α − Ssin(T + α − 360°)∆T
∆YC = sin(T + α − 360°) ∆S + Scos(T + α − 360°)∆α + Scos(T + α − 360°)∆T
両辺を平方して分散に記号に直すと
MX2 = cos2 𝑇𝐴𝐶 mS
2 + S2sin2𝑇𝐴𝐶mα2 + S2sin2𝑇𝐴𝐶mT
2
σX2 = (
−1
2)2(4𝑐𝑚)2 + (1.2 × 105𝑐𝑚)2(
√3
2)2(
5"
2"×105)2 + (1.2 × 105𝑐𝑚)2(
√3
2)2(
5"
2"×105)2
= 4 + 13.5 = 17.5
σX = 4.18cm

(参考)
σY2 = sin2(T + α − 360°) σS
2 + S2cos2(T + α − 360°)σα2 + S2cos2(T + α − 360°)σT
2
σY2 = sin2(120°) 42𝑐𝑚 + 2 × 120,0002𝑐𝑚2𝑐𝑜𝑠2(120°) [
5"
2" × 105]2
=(√3/2)2× 42 + 2 × 122 × 108 × (−1/2)2 × 52/22 × 10−10
=12 + 4.5 = 16.5
σY = 4.06cm
1. 3.3cm
2. 3.7cm
3. 4.2cm
4. 4.7cm
5. 5.4cm
解答 3
[NO. 7]
次の文は、電子基準点を既知点とした公共測量における 1 級基準点測量を行う際の PCV 補正について述べたも
のである。(ア)~(オ)に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか。
次の中から選べ。
解説
GPS アンテナは、(ア 入射)する電波を(イ 位相中心)で測定している。エポックごとに GPS アンテナに(ア 入
射)する電波はその(ア 入射)角によってわずかに位相が変化するため、それに伴って GPS アンテナの物理的な底面
に対する(イ 位相中心)の位置も変動する。この変動を「PCV(Phase Center Variation)」と呼び、(ア 入射)角に
応じて位相のずれを補正することで(イ 位相中心)の変動を補正することを PCV 補正と呼ぶ。
位相のずれは GPS アンテナの機種によって異なるため、それぞれの GPS アンテナに対して理想的な観測状態でのずれを
算出する。こうして求められた位相のずれのモデルを(ウ アンテナ位相特性モデル)という。基線解析の際に(ウ アン
テナ位相特性モデル)を適用して PCV 補正を行うことで、より(エ 高精度な)基線解析が実現される。GPS スタティッ
ク測量において PCV 補正を適用する際の器械高は、(オ アンテナ底面高)を測る。
ア イ ウ エ オ
1. 入射 アンテナ底面 オフセットモデル 高精度な アンテナ底面高

2. 反射 位相中心 オフセットモデル 高精度な アンテナ底面高
3. 反射 アンテナ底面 アンテナ位相特性モデル 迅速な 位相中心高
4. 入射 アンテナ底面 オフセットモデル 迅速な 位相中心高
5. 入射 位相中心 アンテナ位相特性モデル 高精度な アンテナ底面高
解答 5
[NO. 8]
トータルステーションを用いた公共測量における 1 級及び 2 級基準点測量において、図 8 に示すように、標高
48.78mの点 1 と標高 298.63mの点 2 との間の距離及び高低角の観測を行い、表 8 の観測結果を得た。D を斜
め距離、α1を点 1 から点 2方向の高低角、α2を点 2 から点 1 方向の高低角、i1、f1を点 1 の器械高及び目標
高、i2,f2を点 2 の器械高及び目標高とするとき、点 1、2間の基準面上の距離はいくらか。
最も近いものを次の中から選べ。
ただし、地球の平均曲率半径は 6,370km、点 1、2 のジオイド高を平均した値は 35.00mを用いるものとする。
なお、関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。
表 8
D 3,216.06m
α1 5°57’54”
α2 -6°02’06”
i1、f1 1.40m
i2、f2 1.40m
1. 3,198.22m
2. 3,198.33m
3. 3,198.44m
4. 3,198.55m
5. 3,198.66m
(解答)No.8 多角測量=基準面上の距離計算
S = Dcos(α1−α2
2)
R
R+H1+i1+H2+i2
2+N

S = 3,216.06m × cos(5°57′54"+6°02′06"
2)
6,370,000
6,370,000+48.78+1.4+298.63+1.4
2+35.00
S = 3,216.06m × cos(6°)6,370,000
6,370,210.105
S = 3,216.06m × 0.994521895 × 0.999967017
=3,198.337m
1. 3,198.22m
2. 3,198.33m
3. 3,198.44m
4. 3,198.55m
5. 3,198.66m
解答 2
[NO. 9]
次の文は、水準測量の誤差とその消去法について述べたものである。(ア)~(オ)に入る語句の組み合わ
せとして最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
解答
(ア 鉛直)軸の傾きによる誤差は、レベルを整置するとき 2 本の標尺を結ぶ線上にレベルを置き、進行方向に対し
(イ 三脚)の向きを、常に特定の標尺に対向させることにより影響を小さくすることができる。
(ウ 視準)軸誤差は、水準器軸と(ウ 視準)線とが互いに平行でないために生じる誤差で、この誤差を消去す
るには、レベルと前視及び後視の標尺戸の距離を等しくする。
(エ 零点)誤差は、標尺の底面と零目盛とが一致しない誤差であり、これを消去するためには出発点に立てた標尺を
到着点に立てるようにする。すなわち測点数を(オ 偶数)にする。
ア イ ウ エ オ
1. 鉛直 レベル 視準 目盛 偶数
2. 鉛直 三脚 視準 零点 偶数
3. 視準 三脚 鉛直 零点 奇数
4. 視準 レベル 鉛直 目盛 偶数
5. 視準 レベル 鉛直 目盛 奇数

解答 2
[NO.10]
次の a~d の文は、公共測量における水準測量について述べたものである。(ア)~(エ)に入る語句の組
み合わせとして最も適当なものはどれか。
次の中から選べ。
解答
a. 水準測量とは、既知点に基づき、新点である水準点の標高を定める作業をいい、(ア 直接)水準測量方式と渡
海(河)水準測量方式を標準とする。
b. 観測に使用する機器は、適宜、点検及び調整を行う。自動レベル及び電子レベルは、円形水準器及び視準線の点
検調整並びに(イ コンペンセータ)の点検を行う。
c. 2 級水準測量における標尺補正計算は、水準点間の高低差が(ウ 70m)以上の場合に行うものとする。
d. 1 級水準測量の観測において、往復観測値の較差が、許容範囲を超えた場合は再測が必要であり、その許容範囲
は、S を km 単位で表した片道の観測距離としたとき、(エ 2.5mm√S)が標準である。
ア イ ウ エ
1. 直接 鉛直軸 100m 2.5mm√S
2. 間接 気泡管 100m 5mm√S
3. 直接 コンペンセータ 70m 2.5mm√S
4. 直接 コンペンセータ 100m 2.5mm√S
5. 間接 鉛直軸 70m 5mm√S
解答 3
[NO.11]
水準点 A 及び水準点 B を既知点として、新設した水準点 C の標高を求めるため、公共測量における 1 級
水準測量を行い、表 11-1 の観測結果を得た。標尺補正を行った後の水準点 C の標高の最確値はいくら
か。最も近いものを次の中から選べ。

ただし、水準点 A 及び水準点 B の標高は表 11-2 のとおりであり、この観測で使用した標尺の気温 20℃にお
ける標尺改正数は+5μm/m、膨張係数は+1.0×10-6/℃とする。
表 11-1
観測結果
区間 距離 観測高低差 気温の平均値
A→C 2.0km +57.9308m 20℃
C→B 1.0km -24.3725m 15℃
表 11-2
既知点成果
既知点 標高
A 170.5000m
B 204.0600m
1. 228.4314m
2. 228.4316m
3. 228.4318m
4. 228.4320m
5. 228.4322m
(解答)
∆C = {Co + (T − To) ∙ α} ∙ ∆h
Co:基準温度における標尺定数
T:観測時の温度
To:基準温度
α:膨張係数
Δh:高低差
A→C
∆C = {+5μm/m+ (20 − 20) × 1.0μm/m} × 57.9308m = 0.0003m
補正後の比高=57.9308+0.0003=57.9311m
→標高 HC1=170.5000+57.9311=228.4311m
重量 p1=1/S1=1/2

C→B
∆C = {+5μm/m+ (15 − 20) × 1.0μm/m} × (−24.3725m) = −0.0000m
補正後の比高=-24.3725-0.0000=-24.3725m
→標高 HC2=204.0600+24.3725=228.4325m
重量 p2=1/S2=1/1km
重量平均
Hc=(Hc1p1+Hc2p2)/(p1+p2)
=(228.4311×0.5+228.4325×1)/1.5
=228.4320m
1. 228.4314m
2. 228.4316m
3. 228.4318m
4. 228.4320m
5. 228.4322m
解答 4
[NO.12]
次の a~eの文は、公共測量における水準測量について述べたものである。
明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか。
次の中から選べ。
a. 1級水準測量では、気温 20℃における標尺改正数が 50μm/m以下であり、かつ、I号標尺と
II号標尺の標尺改正数の較差が 30μm/m以下である 1級標尺を使用する。〇
b. 1級水準測量の最大視準距離は 50mで、標尺目盛の読定単位は 0.1mmである。〇
c. 2級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用する。×
理由:(準則第 65 条第 2 項)
「2 級水準測量の再測は、同方向の観測値を採用する。」は「1・2 級水準測量の再測は同方向の観測値を
採用しない」ので間違い。
d. 1級水準測量においては、標尺の下方 20cm以下を読定しない。〇

e. 点検計算の許容範囲のうち、既知点から既知点までの閉合差は、Sをkm単位で表した片道の
観測距離としたとき、1~2級水準測量は 15mm√S、3~4級水準測量は 25mm√Sが標準
である。×
理由: 再測(準則第 65条)1・2・3・4級水準測量の水準点・固定点間の往復較差
1 級 2 級 3 級 4 級
較差 2.5mm√S 5mm√S 10mm√S 20mm√S
点検計算の許容範囲のうち、既知点から既知点までの閉合差は、S をkm単位で表した片道の観測距離と
したとき、1~2 級水準測量は 15mm√S、3~4 級水準測量は 25mm√S が標準である。間違い
1. a, b 2. a, c 3. b, d 4. c, d 5. c, e
解答 5
[NO. 13]
次の文は、公共測量におけるトータルステーション(以下「TS」という。)による細部測量につ
いて述べたものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解答
1. TSによる細部測量では、地形、地物などの状況により、基準点から見通しが悪く測定が困難
な場合、基準点から支距法によりTS点を設置し、TS点から測定を行うことができる。×
理由:支距法は使用しない。
(準則第 92 条)
(旧)TS等による地形、地物等の水平位置及び標高の測定は、放射法、支距法等による。
(新)『TS等を用いるTS点の設置は、基準点にTS等を整置し、観測は第37条第2項第一号の
4級基準点測量の規定を準用して放射法又は同等の精度を確保できる方法(以下「放射法等」という)
により行うものとする。』と改正されたので、
『TS による細部測量では、地形、地物などの状況により、基準点から見通しが悪く測定が困難な場合、基準
点から支距法により TS 点を設置し、TS 点から測定を行うことができる。』の文は間違い。(支距法は使用し
ない。)

2. TSによる細部測量において、地形は地性線及び標高値を測定し、図形編集装置によって等高
線描画を行う。〇
3. TSによる細部測量で測定した地形、地物などの位置を表す数値データには、原則として、そ
の属性を表すための分類コードを付与する。〇
4. TSによる細部測量では、地形、地物などの測定を行い、地名、建物などの名称の他、取得し
たデータの結線のための情報などを取得する。〇
5. TSによる細部測量と RTK-GPS法を用いる細部測量とは、併用して実施できる。〇
解答 1
[NO.14]
次の文は、デジタルマッピングによる行政界情報の取得において、まず行政界構成点データを取得
し、その行政界構成点データの識別番号(ID)を、行政界をたどる順番に並べて行政界データを
構成し、さらにその行政界データの識別番号を並べて行政区域データを構成する方法について述べ
たものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
1. 隣り合った行政区域データは、同じ行政界データを共有することができる。〇
2. 行政界データ及び行政区域データには、行政構成点データの座標を保存する必要はない。〇
3. 行政界データ1本のみによって構成される行政区域データがあってもよい。〇
4. 行政区域の名称は、行政界構成点データの中に保存する必要がある。×
5. 行政区域データを描示するためには、行政界データ及び行政界構成点データを用いる必要があ
る。〇
解答 4
[NO.15]
次の文は、地形測量における RTK-GPS測量及びネットワーク型RTK-GPS測量について述べたも
のである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解答
1. RTK-GPS測量は、地形測量における基準点設置のために利用することができる。〇
2. 現地補測にネットワーク型 RTK-GPS測量を利用する場合、電子基準点の観測データを基にした
補正情報及び観測点での上空視界の確保が必要である。〇

3. わが国では電子基準点網が整備されているが、国内でもネットワーク型RTK-GPS測量を
利用できない地域が存在する。〇
4. RTK-GPS法を用いる細部測量では、地形、地物などの水平位置及び標高の測定は、干渉
測位方式により行う。〇
5. ネットワーク型 RTK-GPS測量は、電子基準点から遠いエリアで連続して細部測量を実施する
と、誤差が累積する。×
理由
ネットワーク型 RTK-GPS 測量には、仮想基準点方式(VRS方式)と面補正パラメータ方式(FKP 方式)が
ある。VRS方式は、作業地区を囲んでいる3点以上の電子基準点を利用して、観測点付近の任意地点に
仮想点を作り、仮想点と観測点間の基線ベクトルを求める方式である。この方式は短距離基線の RTK 法と
同等の測位精度を得ることができ、広域を対象とする地形、地物の測定に有効である。
FKP 方式は、作業区域を取り囲む複数の電子基準点データから作業区域内の補正パラメータを面的に算出
する方式である。最寄りの電子基準点と観測点間の基線ベクトルに補正パラメータを加味して求める観測方
式であり、これらも広域を測定する場合は有効な方法である。➭5の文は間違い。
解答 5
[NO.16]
標高が 100mから 700mまでの範囲にある土地の空中写真撮影において、撮影範囲全域にわたって隣接コ
ースの空中写真との重複度が 25%より小さくならないようにしたい。撮影基準面における隣接コースの空中写
真との重複度は最小何%まで許されるか。
最も近いものは次の中から選べ。
ただし、撮影基準面の標高は 100m、航空カメラの画面距離は 15cm、画面の大きさは 23cm×23cm
とする。
また、空中写真は等高度で撮影する鉛直空中写真とし、撮影基準面での縮尺は 1/15,000 とする。
1. 35%
2. 38%
3. 40%
4. 45%
5. 48%
(解答)No.16 サイドラップ

1)撮影基準面h=100mでの撮影高度 H は、縮尺 1/mb=f/H より
H=f×mb=15cm×15,000=2,250m
海抜撮影高度 Ho=H+h=2,250+100=2,350m
2)h’=700mでの撮影高度
H’=Ho-h’=2,350-700=1,650m
1/mb’=f/H’=15cm/1,650m=1/11,000
写真上のコース間隔 w=s(1-q)=23cm×(1-0.25)=17.25cm
コース間隔W=w×mb'=17.25cm×11,000=1,897.5m
3)撮影基準面でのサイドラップ q’=(S-W)/S= 1 −W/S
写真の一辺の地上寸法 S=s×mb=23cm×15,000=3,450m
q'=1 −WS⁄ = 1 − 1,897.5m
3,450m⁄ =0.45(45%)
1. 35%
2. 38%
3. 40%
4. 45%
5. 48%
解答 4
[NO.17]
次の文は、空中三角測量について述べたものである。(ア )~(オ )に入る語句の組み合わせとして最も適
当なものはどれか。次の中から選べ。
解答
(ア パスポイント)は同一撮影コース内の隣接する空中写真の接続に用いる点であり、配置は主点付近及
び主点基線に(イ 直交する)両方向の 3箇所以上を標準とする。(ウ タイポイント)は隣接撮影コース
間の接続に用いる点であり、(エ 1 モデル)に 1点を標準としてほぼ等間隔に配置する。
また、ブロック調整の精度を向上させるため、(ウ タイポイント)は、コース方向に(オ ジグザグ)に配置す
る。(ウ タイポイント)は、(ア パスポイント)で兼ねることができる。
ア イ ウ エ オ
1. パスポイント 直交する タイポイント 1 モデル ジグザグ
2. タイポイント 直交する パスポイント 2 モデル 一直線

3. パスポイント 直交する タイポイント 2 モデル 一直線
4. タイポイント 沿う パスポイント 2 モデル ジグザグ
5. タイポイント 沿う パスポイント 1 モデル ジグザグ
(解答)No.17 空中三角測量
解答 1
[NO.18]
次の a~eの文は、公共測量における地形測量及び空中写真測量の数値編集の点検について述べたも
のである。明らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか。
次の中から選べ。
解答
a. 地形、地物などの取得漏れの点検は、スクリーンモニタ上で行った。〇
b. 出力図による地形及び地物の位置に関する点検の結果が良好であったことから、点検プログラ
ムによる点検を省略した。×
理由
準則第 193条 出力図の点検は、編集済データ及び前条の規定により作成した出力図を用いて行うものとす
る。
2 編集済データの論理的矛盾等の点検は、点検プログラム等により行うものとする。点検プログラムによる点
検を省略しないので間違い。
c. 図郭間の接合で対応するデータ同士の端点座標が一致しているかどうかの点検は、出力図を用
いて行った。×
理由
(接 合)
準則第 191条 接合は、作業単位ごとに行い、同一地物の座標を一致させるものとする。
2 地形、地物等のずれが、第79条に定める製品仕様書の規定値以内の場合は、関係図形データを修
正して接合するものとする。スクリーンモニタ上で座標により点検するので、間違い。
d. 等高線の編集済データにおいて、その種別を表す分類コードと、属性として付与された標高値
との論理的矛盾の点検は、点検プログラムを用いて行った。〇
e. 適切な精度管理を行うため、各工程別の作業における点検の結果を、精度管理表に記載した。
〇

1. a, b 2. a, c 3. b, c 4. b, d 5. d, e
解答 3
[NO.19]
次の a~eの文は、公共測量における GPS/IMUを用いた空中写真撮影について述べたものである。明
らかに間違っているものだけの組み合わせはどれか。
次の中から選べ。
解答
a. GPS/IMU装置を用いた空中写真撮影では、GPS装置により航空カメラの位置を取得し、
IMU装置により航空カメラの傾き及び加速度を取得することができる。〇
b. GPS受信アンテナは航空機の頂部に固定し、IMU装置は航空カメラに取り付ける。〇
c. GPS/IMU装置は、フィルム航空カメラを用いた空中写真撮影では使用できない。×
理由
フィルムカメラにも使用できるので、間違い。
d. GPS/IMU装置のボアサイトキャリブレーション(航空カメラ及びGPS/IMU装置の取
り付け位置の校正)は、航空カメラを取り外した場合のみ行う。×
理由
取り外さない場合にもキャリブレーションするので、間違い。
e. IMU装置はドリフトと呼ばれる時間経過とともに蓄積する誤差が発生するため、撮影前後に
初期化のための飛行を行う必要がある。〇
1. a, c 2. a, e 3. b, d 4. b, e 5. c, d
解答 5

[NO.20]
海面から撮影高度 2,150mで鉛直に撮影した空中写真に、高さ 50mの高塔が先端から付け根までにわたり
1.3mmの像として写り込んでおり、主点から高塔の先端までの距離を計測すると 51.2mmであった。この高塔
が立っている地点の標高はいくらか。
最も近いものを次の中から選べ。
1. 98m
2. 130m
3. 180m
4. 260m
5. 330m
(解答)No.20 写真測量
1)射影変換式は次式の通り表される。 ∆r
r=
∆h
H
この式より撮影高度 H にすると、
H =r
∆r× ∆h =
51.2mm
1.3mm× 50m = 1,969m
2)海抜撮影高度 Ho=2,150mなので、高塔の地点の標高 h は次のとおり求められる。
h=Ho –H=2,150-1,969=181m
写真
海面
hΔh=50
m
Ho=2150m
H
r=51.2mm
Δr=1.3mm

1. 98m
2. 130m
3. 180m
4. 260m
5. 330m
解答 3
[NO.21]
図 21 は、国土地理院発行の 1/25,000 地形図の一部(原寸大、一部を改変)である。図中にある「御
池」の面積の概算値はいくらか。
最も近いものを次の中から選べ。
ただし、表示されているグリッドの大きさは 5mm×5mmとする。
1. 0.007km²
2. 0.1km²
3. 0.7km²
4. 3km²
5. 70km²
(解答)No.21 地図編集

(完全な1マスの個数)=36+(合わせて 1 マスとなるもの 9)=45
(半分のマス)=3 個=1.5
(合計)=45+1.5=46.5(個)
(面積)=46.5×(5mm×25,000)2
=0.727㎢
1. 0.007km²
2. 0.1km²
3. 0.7km²
4. 3km²
5. 70km²
解答 3
[NO.22]
次の文は、地図投影について述べたものである。(ア)~(オ)に入る語句を語群から選び正しい文章にした。(ア)
~(オ)に入る語句の組み合わせとして最も適当なものはどれか。
次の中から選べ。
解答
・地図投影とは、(ア 回転楕円体面上 d)の経緯度を(イ 平面上 e)の座標に変換することである。
・地球上のあらゆる地点間の距離を同一縮尺で(イ 平面上)に表示することは、(ウ 理論上不可能 f)である。
・ユニバーサル横メルカトル図法は、(エ 正角図法 a)の一種である。
・全世界の人口分布を表現する主題図に最も適した図法は(オ 正積図法 b)である。
語群
a. 正角図法 b. 正距図法 c. 正積図法 d. 回転楕円体面上
e. 平面上 f. 理論上可能 g. 理論上不可能
ア イ ウ エ オ
1. d e f a b 2. d e g a c 3. e d f b a 4. e d f b b 5. e d g c c

解答 1
[NO.23]
国土地理院発行の 1/25,000地形図から GIS で利用するためのデータを取得し、属性を付与した。表 23 は
作成したデータの諸元をまとめた一覧表の一部である。表 23 は(ア)~(エ)に入る語句の組み合わせとし
て最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
解答
表 23
取得データ 地図上の地物 データ形式 付与した属性
真幅道路のア道路
中心線 なし 線データ 道路種別、路線番号
博物館建物の外形 イ建物を示す図
形 面データ 建物種別
湖沼の水面域 湖沼の水部領域 ウ面データ 湖沼名
水準点 水準点記号 エ点データ 経緯度原点、標高
ア イ ウ エ
1. 道路縁 博物館記号 点データ 面データ
2. 道路縁 建物を示す図形 面データ 面データ
3. 道路中心線 建物を示す図形 点データ 点データ
4. 道路中心線 建物を示す図形 面データ 点データ
5. 道路中心線 博物館記号 点データ 面データ
解答 4
[NO.24]
次の文は、地理空間情報活用推進基本法(平成 19年法律第 63号)第 2条第 3項に定められた、電
子地図上における地理空間情報の位置を定めるための基準となる基盤地図情報に関する事項につい
て述べたものである。
明らかに間違っているものはどれか。次の中から選べ。
解答
1. 基盤地図情報に係る項目は、①測量の基準点、②海岸線、③公共施設の境界線、④行政区画の
境界線及び代表点並びに⑤河川堤防の表法肩の法線の 5項目である。×
理由

基盤地図情報に係る項目は、①測量の基準点、②海岸線、③公共施設の境界線(道路区域界)、④
公共施設の境界線(河川区域界)、⑤行政区画の境界線及び代表点、⑥道路縁の 6 項目とされるの
で、間違い。
2. 国が保有する基盤地図情報は、原則としてインターネットを利用して無償で提供される。〇
3. 基盤地図情報の平面位置の誤差は、都市計画区域内では 2.5m以内、都市計画区域外では 25m
である。〇
4. 基盤地図情報を利用することにより、地図整備の重複投資の排除が期待できる。〇
5. 基盤地図情報を提供しようとする場合の適合すべき規格には、国際標準化機構(ISO)が定め
た規格が含まれる。〇
解答 1
[NO.25]
次の文は、緩和曲線として用いられるクロソイドについて述べたものである。(ア)~(オ)に入る語句の組み
合わせとして最も適当なものはどれか。
次の中から選べ。
解答
平行しない 2 本の直線道路があり、一方の直線道路から他の直線道路に滑らかに接続する曲線の道路を
考える。一方の直線道路から滑らかな曲線を経て円弧を描き、同様の滑らかな曲線を経て直線道路へ接続
することを考えたとき、この滑らかな曲線を緩和曲線という。
これは、(ア 曲率)の不連続な接続を無くし、自動車の走行を安定させることを目的としている。このような
曲線のうち、(ア 曲率)が(イ 曲線長)に比例する曲線をクロソイドという。このとき、(ウ 曲線半径)
(アの逆数)と(イ 曲線長)の積は一定となる。この定数の正の平方根をクロソイドのパラメータという。一
方の直線道路からクロソイドを経て円弧に接続することを考えたとき、当該クロソイドから当該円弧に接続する
点 P における接線と当該直線道路との成す角を、点 P における(エ 接線角)という。(イ 曲線長)を一
定にしてクロソイドパラメータを大きくすると、点 P における(エ 接線角)は小さくなり、曲がり方は(オ 緩や
か)になる。
ア イ ウ エ オ
1. 曲率 曲線長 曲線半径 極角 緩やか
2. 曲率 法線長 曲線半径 極角 急
3. 曲率半径 法線長 曲率 接線角 緩やか
4. 曲率半径 曲線長 曲率 極角 急

5. 曲率 曲線長 曲線半径 接線角 緩やか
解答 5
[NO.26]
市街地の交通量を緩和するため、図 26 に示すように、現在使用している道路(以下「現道路」という。)を改
良して、新しい道路(以下「新道路」という。)を建設することとなった。
新道路は、基本型クロソイド(対称型)AB から成り、主接線は現道路の中心線と一致し、交点 IPは現道
路交差点の中心にある。円曲線部分の曲線半径 R=220m、交角 I=60°、クロソイドパラメータ A=160m とす
るとき、新道路 AB の路線長はいくらか。
最も近いものを次の中から選べ。
ただし、円周率π=3.142 とする。
なお、関数の数値が必要な場合は、巻末の関数表を使用すること。
1. 175m
2. 232m
3. 289m
4. 347m
5. 403m
(解答)No.26 路線測量「クロソイド(路線長)」
①クロソイド曲線長 L =A2
R=
1602
220= 116.364m
②クロソイド始点(終点)での接線角 τ =L
2R=
116.364
2×220= 0.264463 = 15.1526°
③円曲線部の中心角 α = I − 2τ = 60 − 2 × 15.1526=29.6948o
円曲線部の曲線長
Lc=Rα
=220×29.6948/180×π
=114.035m
∴全曲線長 CL=2L+Lc=2×116.364+114.035=346.763m
1. 175m
2. 232m
3. 289m
4. 347m
5. 403m

解答 4
[NO.27]
表 27 は、境界点 A,B,C,D,E 及び F の 6点で囲まれた土地の面積を算出した際の計算簿である。(ア)~
(カ)に入る数値として最も適当なものはどれか。次の中から選べ。
境界
点
X 座標
(m)
Y 座標
(m)
Yi+1-Yi-1 Xi(Yi+1-Yi-1)
A ア -7.5 -79.5 オ
B 10 イ -12.5 -125
C -19.5 -20 エ カ
D -20 41.5 67.5 -1350
E 5 47.5 -1.5 -7.5
F 15.5 ウ -55 -852.5
倍面積 -5584
面積 -2792
ア イ ウ エ オ カ
1 20 -40 41 81 -1,669.50 -1,579.50
2 21 -39.5 40 81 -1,669.50 -1,579.50
3 20 -40 41 81.5 -1,669.50 -1,578.50
4 20 -39.5 40 81 -1,670.50 -1,579.50
5 21 -39.5 40 81.5 -1,670.50 -1,578.50
(解答)No.27 応用測量「用地測量」
1)まず計算できるのは F の Y 座標であるので、E の Yn+1-Yn-1は YF-YD=-1.500、
つまり YF=-1.500+41.500=40.000 を得る。
2)YBは A における Yn+1-Yn-1から YB-YF=-79.500 より YB=-79.500+40.000=-39.500
3)C における Yn+1-Yn-1は、YD-YB=41.500-(-39.500)=81.000
4)C の Xn(Yn+1-Yn-1)は-19.500×81.000=-1579.500
5)A の Xn(Yn+1-Yn-1)は倍面面積(B~F の合計)+5584.000=-1669.500
6)A の X 座標は XA=Xn(Yn+1-Yn-1)/ (Yn+1-Yn-1)=-1669.500/(-79.500)=21.000
境界
点
X 座標
(m)
Y 座標
(m)
Yi+1-Yi-1 Xi(Yi+1-Yi-1)
A 21 -7.5 -79.5 -1669.5
B 10 -39.5 -12.5 -125
C -19.5 -20 81 -1579.5

D -20 41.5 67.5 -1350
E 5 47.5 -1.5 -7.5
F 15.5 40 -55 -852.5
倍面積 -5584
面積 -2792
解答 2
[NO.28]
次の a~e の文は、公共測量における河川測量について述べたものである。(ア)~(オ)に入る語句の組み
合わせとして最も適当なものはどれか。
次の中から選べ。
解答
a. 定期(ア 横断)測量とは、左右両岸に設置された距離標の視通線上の地形の変化点などについて、
距離標からの距離及び標高を定期的に測定して(ア 横断)面図データファイルを作成する作業である。
b. 定期(イ 縦断)測量において、観測の基準とする点は、原則として水準基標とする。
c. 距離標は、(ウ 河心線)の接線に対して直角方向の両岸の堤防法肩又は法面などに設置する。
d. 水準基標測量は、(エ 2 級)水準測量により行い、水準基標の位置を示すため、点の記を作成する。
e. 深浅測量における水深測定は、指定されたピッチ位置において(オ 2 回)行い、その平均値を採用する。
ただし、河口部などが広大な水域において測定を(オ 2 回)行うことが困難な場合はこの限りでない。
ア イ ウ エ オ
1. 横断 縦断 河心線 3 級 3 回
2. 横断 縦断 堤防中心線 3級 3 回
3. 横断 縦断 河心線 2 級 2 回
4. 縦断 横断 河心線 3 級 3 回
5. 縦断 横断 堤防中心線 2級 2 回
(解答)No.28 河川測量
解答 3








![保管場等における空間線量率の測定地点(週次測 …...保管場における空間線量率のモニタリング結果(週次測定) <空間線量率> [μSv/h]](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/5fd298bbff26707b57725b86/cccececoecie-ccececffffcoeiei.jpg)
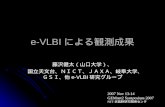







![現地観測地点 [大気質、気象、粉じん等]...※ :観測日毎の値は、1日(24時間)の時間別観測値を平均して算出した値です。 現地観測結果](https://static.fdocuments.net/doc/165x107/60d49fc7414f9978aa35851d/coeeoec-eecc-a-ie124eeec.jpg)

